257 / 396
第四章 絢爛のスクールフェスタ
第257話 エステアとの晩餐
しおりを挟む
タオ・ラン老師に別れを告げ、カナド人街での買い物を済ませて、予定していた時間よりも少しだけ遅く帰宅した。
「夕食の準備の間、一緒に台所を使ってもいい?」
母の作ったエプロンをかけて台所に立った僕の元にエステアがやってくる。
「もちろん。出汁を取るのには時間もかかるだろうからね」
「ありがとう。焜炉魔導器を一口潰してしまうけれど、大丈夫?」
「平気だよ。天火魔導器任せの料理にするつもりだったし」
エステアが鶏で出汁を取ると聞いていたので、丸鶏を仕入れて捌いてもらってある。出汁を取るには当然焜炉魔導器を使うだろうと思っていたので、エステアがそう申し出るのは想定済みだ。
それに、僕としても二人きりで話しておきたいことがあった。
「ありがとう。それにしてもカナド通りはすごいわね。欲しかったものが全部揃っちゃった」
僕が話を切り出す隙を与えまいとしてか、エステアが自分から話題を切り出す。彼女の緊張や警戒が解けるまで、この話題に乗っていた方が話しやすくなるだろうと考え、僕はその話を続けることにした。
「そうだね。新年を迎えるということもあって、普段よりもかなり店も品物も多かったし」
「人も多かったわね。迷子にならなくてよかったわ」
「僕はなりかけたけどね」
エステアの緊張が解けるよう、少し砕けた話題を選ぶ。エステアは少し驚いたように目を瞬いて、それから微かに声を立てて笑った。
「リーフもそんな冗談を言うのね」
「まあね」
ちゃんと冗談として通じたのか、それとも僕の気遣いに気づいたのかはわからないが、エステアの表情が少し和らいだような気がする。
でも、このまま世間話のような当たり障りない話題を続けるのも白々しいかもしれないな。さて、どうやって切り出すのがいいだろう。
タオ・ラン老師に直接指摘されている以上、エステア自身、自分の悩みを自覚していないはずはないのだけど、その悩みの根源が武侠宴舞・カナルフォード杯だと心当たりが僕にはあるだけに、変な誤解は避けたいところだ。単純に心配だ、というのは彼女にとって余計なお世話にならないといいのだけれど。
「…………」
考えがまとまらないまま、ひとまず夕食の仕度を進める。今日は天火魔導器任せの料理にすると決めていたので、カナド通りの市場で購入した根菜類を手頃な大きさに切り、油と塩で和える。大ぶりで肉厚の葉野菜も同じように油と塩で和えて馴染ませた。
肉屋で切り分けてもらった鶏肉は、皮目にフォークで穴をあけて肉叩きで軽く叩き、牛乳とレモンを合わせたマリネ液に浸けておいた。香辛料と塩、少量の油を和えて暫く寝かせたあとに、寮でクッキーを焼くときに使ったクリーパー粉を混ぜた衣をまぶして焼けば、外はパリッと、中は柔らかく仕上がるハズだ。学食で気に入っているミルクチキンのアレンジをずっとやりたいと考えていたので、絶好の機会だ。味を馴染ませておく間に天火魔導器を余熱するのも忘れない。
「……驚いた。すごく手際がいいのね」
隣で長葱という野菜の頭の緑色部分と幾つかの香辛料、鶏の骨と一緒に煮込んでいたエステアが浮いてきた灰汁をレードルで丁寧に取り除きながら感嘆の声を漏らす。
「料理は好きなんだ。錬金術に通じるところがあるし、アレンジの幅も広がる。なにより――」
「ああ! いい匂いがしてきた!」
エステアとの会話に父の明るい声が割り込んできた。
「一年の終わりに娘の手料理が食べられるなんて、パパへのご褒美に違いないな!」
寝室で休んでいた母に付き添ってリビングに出て来た父が、満面の笑みをこちらに向けてくる。僕の手料理といってもまだ完成にはほど遠いので、さすがの僕も苦笑しながらエステアと目を合わせた。
「この匂いはエステアがとっている鶏の出汁の方ですよ、父上」
「ははははっ! それも良い香りで楽しみだが、パパともなれば、リーフの切った野菜の匂いだけでもう一杯やりたくなってしまうんだよ」
「先に飲んでもいいのに」
母がそう言いながら、冷蔵魔導器の脇から用意してあった葡萄酒を一本持ち出す。
「いやいや。最高の料理と一緒に最高の一杯を飲むのが楽しみなんだよ、ナタル」
ごくごく自然な動作でそれを受け取りながら、父は母を支えるように寄り添った。ぱっと見た感じ顔色も良いし、調子は良さそうだが油断は出来ないだろうな。
「……母上、具合はいかがですか?」
「念のため、ルドセフ先生のところに行ってきたし、もう平気よ」
どうやら僕たちが外出している間に通院を済ませてきたらしい。そう語る母の声を聞いた感じでは咳の兆候もなさそうなので、僕は安堵に胸を撫で下ろした。
「良かったです。年末年始は僕に任せてゆっくりしてくださいね」
「そうさせてもらうわ。リーフのお料理を満喫するまたとない機会だものね」
「そうだぞ、ナタル。リーフの料理をいっぱい食べたら元気になれるだろうからな」
父上が手放しで喜んでくれているので、母上の申し訳なさも和らいだ様子だ。
「栄養がつくものをたくさん買ってきましたから、ぜひ召し上がってください」
テーブルクロスを敷いて皿やグラスを並べていたホムが、母を気遣う発言をする。ホムが自主的に話しかけてくれているのを見ると、ちゃんと家族の一員としての自覚をもってくれているのが伝わってくる。
「ホムちゃんもありがとう」
笑顔の母の横顔を見ながら、改めて家族の良さを感じていると、エステアが僕と身体を近づけて囁いた。
「ねえ、リーフ。さっきの話だけど、錬金術に似ているから料理が好きなの?」
「そうだけど? なにか変かい?」
「ううん。普通は逆じゃないのかと思って」
エステアは素朴な疑問のつもりだったらしいが、わざわざそう聞かれたこともあってぎくりとした。言われてみれば錬金術より前に料理に出会うのが普通だ。
「まあ、母上が錬金術師だからね。先に興味を持ったのが錬金術なんだ」
苦し紛れに言い訳をすると、エステアは「そう……」と呟くように相槌を打ち、鍋の火を緩めた。
僕としたことが、少し気が緩んでしまったかもしれないな。まさか前世の記憶を持って転生してきているなんて突拍子もないことに思い至るとは思えないけれど。改めて用心しなければ。
「……そう言えば、メルアは料理がてんでダメだけど錬金術は得意で大好きなのよね。だから不思議に思っちゃったのかも」
どうやらエステアはメルアと僕を比べて不思議に思ったようだ。
「メルアは錬金術でも手間のかかることがあまり得意ではないからね」
「そうなのね」
相槌を打つエステアはメルアの話題が出たこともあり、かなり柔らかな表情だ。それでも結局僕は彼女の悩みについて切り出せないまま、料理を終えてしまった。
* * *
一年の最後の夕食は僕たち家族とエステアの五人で過ごすことになった。
普段研究所での仕事に忙殺されているアルフェのお父さんも、年末のこの一日だけはどうにか家に帰って来ることが出来たので、アルフェは急遽家族水入らずで過ごすことに決めたようだ。
アルフェがいない分、会話を盛り上げようとしたのか、父上がいつになく饒舌に話し、聞き役に回った僕たちをかなり楽しませてくれた。
父上も母上も僕の料理を喜び、たっぷりと用意した料理を囲む食事の時間は、和やかで楽しいひとときになった。
「リーフのかぶのスープは、本当に温まるわね」
目を細めて嬉しそうに語る母は、僕が昔作ったかぶのスープを覚えてくれていたようだ。
「新メニューのミルクチキンも最高だった! これは我が家の定番にしないとな!」
「賛成です!」
驚いたことに賛意を示したのはホムだった。
「わたくしとしては、マスターのアレンジは寮の食堂にも共有されて然るべきかと」
「ありがとう。ホムまでそう言うなら、またぜひ作らないとだね」
食堂を上回っているというニュアンスが含まれているのにも驚いたが、ホムが僕の手料理で喜んでくれるのは単純に嬉しい。
「私もまたご相伴に預かりたいわ」
素直に頷いた僕の隣で、エステアが綺麗に食べ終えた皿に満足げな視線を落として同意を示した。
「ホムが言ったように元々は寮の食堂のメニューをアレンジしたものだけど、貴族寮にはないのかい?」
「貴族寮の料理はもっとかしこまったものが多いのよね。だから息抜きにメルアとのティータイムが欠かせないの」
ああ、要するに貴族が好む前菜からメインデッシュまで続く形式張った料理がメインということなのだろうな。それは厳しいテーブルマナーを要求されるだろうし、周囲の目もあって気軽に食事を楽しむどころではないのかもしれない。僕と恐らく同じことを考えていたらしく、父が同情めいた眼差しをエステアに向けた。
「貴族は貴族でしがらみもあるだろうし、苦労するもんだな」
「ええ……」
エステアは自分が無意識に不平を漏らしたことを気にしたのか、少し歯切れ悪く相槌を打った。
食事の片付けが終わったあとも、僕たちは温かいお茶を飲みながら、久しぶりに火を入れたという暖炉の前で他愛ない話を続けていた。
話題はほとんど僕とアルフェの小さな頃の話だったが、記憶を共有しているはずのホムまで興味深そうに耳を傾けてくれた。もしかすると、ホムには「事実」として記憶が共有されていても、僕が今感じているようなアルフェへの想いのようなものは掴み切れていなかったのかもしれないな。
話が一段落したところで、竜堂の方から新しい年を告げる鐘の音が響く。
「そろそろお開きにしようか」
まだ眠くはないが、明日もあるのであまり夜更かししているのもと考えて立ち上がる。僕と一緒に立ち上がったエステアが、ふと思い詰めたように口を開いた。
「……リーフ」
「どうしたんだい?」
反射的に問いかけたけれど、なにを言い出すのかわからなくて少しだけ緊張した。エステアは僕の表情の変化を感じ取ったのか、笑顔を作ってから切り出した。
「新年のトーチタウンを見て回りたいんだけど」
「じゃあ、今から出ようか」
「一人で大丈夫よ」
一人で、というところを強調したあたり、きっと考えごとをしたいのだろうなと察しがついた。けれど、竜堂をはじめとして街が明るく彩られている新年とはいえ、見知らぬ街の夜にたった一人でエステアを外に出すわけにもいかない。
「慣れない道で迷うようなことがあれば大変だし、ホムを付き添いにつけてもいいかな?」
子ども扱いしているわけではないし、僕なりの心配はこれで伝わるはずだ。
「お供致します」
「……そうね、お願いするわ」
ホムが進み出ると、エステアは素直に僕の提案に従ってくれた。ホムと二人きりにすることを嫌がらなかったことを考えると、もしかするとエステアは一人でじゃなく、ホムと二人きりで話したかったのかもしれないな。
「夕食の準備の間、一緒に台所を使ってもいい?」
母の作ったエプロンをかけて台所に立った僕の元にエステアがやってくる。
「もちろん。出汁を取るのには時間もかかるだろうからね」
「ありがとう。焜炉魔導器を一口潰してしまうけれど、大丈夫?」
「平気だよ。天火魔導器任せの料理にするつもりだったし」
エステアが鶏で出汁を取ると聞いていたので、丸鶏を仕入れて捌いてもらってある。出汁を取るには当然焜炉魔導器を使うだろうと思っていたので、エステアがそう申し出るのは想定済みだ。
それに、僕としても二人きりで話しておきたいことがあった。
「ありがとう。それにしてもカナド通りはすごいわね。欲しかったものが全部揃っちゃった」
僕が話を切り出す隙を与えまいとしてか、エステアが自分から話題を切り出す。彼女の緊張や警戒が解けるまで、この話題に乗っていた方が話しやすくなるだろうと考え、僕はその話を続けることにした。
「そうだね。新年を迎えるということもあって、普段よりもかなり店も品物も多かったし」
「人も多かったわね。迷子にならなくてよかったわ」
「僕はなりかけたけどね」
エステアの緊張が解けるよう、少し砕けた話題を選ぶ。エステアは少し驚いたように目を瞬いて、それから微かに声を立てて笑った。
「リーフもそんな冗談を言うのね」
「まあね」
ちゃんと冗談として通じたのか、それとも僕の気遣いに気づいたのかはわからないが、エステアの表情が少し和らいだような気がする。
でも、このまま世間話のような当たり障りない話題を続けるのも白々しいかもしれないな。さて、どうやって切り出すのがいいだろう。
タオ・ラン老師に直接指摘されている以上、エステア自身、自分の悩みを自覚していないはずはないのだけど、その悩みの根源が武侠宴舞・カナルフォード杯だと心当たりが僕にはあるだけに、変な誤解は避けたいところだ。単純に心配だ、というのは彼女にとって余計なお世話にならないといいのだけれど。
「…………」
考えがまとまらないまま、ひとまず夕食の仕度を進める。今日は天火魔導器任せの料理にすると決めていたので、カナド通りの市場で購入した根菜類を手頃な大きさに切り、油と塩で和える。大ぶりで肉厚の葉野菜も同じように油と塩で和えて馴染ませた。
肉屋で切り分けてもらった鶏肉は、皮目にフォークで穴をあけて肉叩きで軽く叩き、牛乳とレモンを合わせたマリネ液に浸けておいた。香辛料と塩、少量の油を和えて暫く寝かせたあとに、寮でクッキーを焼くときに使ったクリーパー粉を混ぜた衣をまぶして焼けば、外はパリッと、中は柔らかく仕上がるハズだ。学食で気に入っているミルクチキンのアレンジをずっとやりたいと考えていたので、絶好の機会だ。味を馴染ませておく間に天火魔導器を余熱するのも忘れない。
「……驚いた。すごく手際がいいのね」
隣で長葱という野菜の頭の緑色部分と幾つかの香辛料、鶏の骨と一緒に煮込んでいたエステアが浮いてきた灰汁をレードルで丁寧に取り除きながら感嘆の声を漏らす。
「料理は好きなんだ。錬金術に通じるところがあるし、アレンジの幅も広がる。なにより――」
「ああ! いい匂いがしてきた!」
エステアとの会話に父の明るい声が割り込んできた。
「一年の終わりに娘の手料理が食べられるなんて、パパへのご褒美に違いないな!」
寝室で休んでいた母に付き添ってリビングに出て来た父が、満面の笑みをこちらに向けてくる。僕の手料理といってもまだ完成にはほど遠いので、さすがの僕も苦笑しながらエステアと目を合わせた。
「この匂いはエステアがとっている鶏の出汁の方ですよ、父上」
「ははははっ! それも良い香りで楽しみだが、パパともなれば、リーフの切った野菜の匂いだけでもう一杯やりたくなってしまうんだよ」
「先に飲んでもいいのに」
母がそう言いながら、冷蔵魔導器の脇から用意してあった葡萄酒を一本持ち出す。
「いやいや。最高の料理と一緒に最高の一杯を飲むのが楽しみなんだよ、ナタル」
ごくごく自然な動作でそれを受け取りながら、父は母を支えるように寄り添った。ぱっと見た感じ顔色も良いし、調子は良さそうだが油断は出来ないだろうな。
「……母上、具合はいかがですか?」
「念のため、ルドセフ先生のところに行ってきたし、もう平気よ」
どうやら僕たちが外出している間に通院を済ませてきたらしい。そう語る母の声を聞いた感じでは咳の兆候もなさそうなので、僕は安堵に胸を撫で下ろした。
「良かったです。年末年始は僕に任せてゆっくりしてくださいね」
「そうさせてもらうわ。リーフのお料理を満喫するまたとない機会だものね」
「そうだぞ、ナタル。リーフの料理をいっぱい食べたら元気になれるだろうからな」
父上が手放しで喜んでくれているので、母上の申し訳なさも和らいだ様子だ。
「栄養がつくものをたくさん買ってきましたから、ぜひ召し上がってください」
テーブルクロスを敷いて皿やグラスを並べていたホムが、母を気遣う発言をする。ホムが自主的に話しかけてくれているのを見ると、ちゃんと家族の一員としての自覚をもってくれているのが伝わってくる。
「ホムちゃんもありがとう」
笑顔の母の横顔を見ながら、改めて家族の良さを感じていると、エステアが僕と身体を近づけて囁いた。
「ねえ、リーフ。さっきの話だけど、錬金術に似ているから料理が好きなの?」
「そうだけど? なにか変かい?」
「ううん。普通は逆じゃないのかと思って」
エステアは素朴な疑問のつもりだったらしいが、わざわざそう聞かれたこともあってぎくりとした。言われてみれば錬金術より前に料理に出会うのが普通だ。
「まあ、母上が錬金術師だからね。先に興味を持ったのが錬金術なんだ」
苦し紛れに言い訳をすると、エステアは「そう……」と呟くように相槌を打ち、鍋の火を緩めた。
僕としたことが、少し気が緩んでしまったかもしれないな。まさか前世の記憶を持って転生してきているなんて突拍子もないことに思い至るとは思えないけれど。改めて用心しなければ。
「……そう言えば、メルアは料理がてんでダメだけど錬金術は得意で大好きなのよね。だから不思議に思っちゃったのかも」
どうやらエステアはメルアと僕を比べて不思議に思ったようだ。
「メルアは錬金術でも手間のかかることがあまり得意ではないからね」
「そうなのね」
相槌を打つエステアはメルアの話題が出たこともあり、かなり柔らかな表情だ。それでも結局僕は彼女の悩みについて切り出せないまま、料理を終えてしまった。
* * *
一年の最後の夕食は僕たち家族とエステアの五人で過ごすことになった。
普段研究所での仕事に忙殺されているアルフェのお父さんも、年末のこの一日だけはどうにか家に帰って来ることが出来たので、アルフェは急遽家族水入らずで過ごすことに決めたようだ。
アルフェがいない分、会話を盛り上げようとしたのか、父上がいつになく饒舌に話し、聞き役に回った僕たちをかなり楽しませてくれた。
父上も母上も僕の料理を喜び、たっぷりと用意した料理を囲む食事の時間は、和やかで楽しいひとときになった。
「リーフのかぶのスープは、本当に温まるわね」
目を細めて嬉しそうに語る母は、僕が昔作ったかぶのスープを覚えてくれていたようだ。
「新メニューのミルクチキンも最高だった! これは我が家の定番にしないとな!」
「賛成です!」
驚いたことに賛意を示したのはホムだった。
「わたくしとしては、マスターのアレンジは寮の食堂にも共有されて然るべきかと」
「ありがとう。ホムまでそう言うなら、またぜひ作らないとだね」
食堂を上回っているというニュアンスが含まれているのにも驚いたが、ホムが僕の手料理で喜んでくれるのは単純に嬉しい。
「私もまたご相伴に預かりたいわ」
素直に頷いた僕の隣で、エステアが綺麗に食べ終えた皿に満足げな視線を落として同意を示した。
「ホムが言ったように元々は寮の食堂のメニューをアレンジしたものだけど、貴族寮にはないのかい?」
「貴族寮の料理はもっとかしこまったものが多いのよね。だから息抜きにメルアとのティータイムが欠かせないの」
ああ、要するに貴族が好む前菜からメインデッシュまで続く形式張った料理がメインということなのだろうな。それは厳しいテーブルマナーを要求されるだろうし、周囲の目もあって気軽に食事を楽しむどころではないのかもしれない。僕と恐らく同じことを考えていたらしく、父が同情めいた眼差しをエステアに向けた。
「貴族は貴族でしがらみもあるだろうし、苦労するもんだな」
「ええ……」
エステアは自分が無意識に不平を漏らしたことを気にしたのか、少し歯切れ悪く相槌を打った。
食事の片付けが終わったあとも、僕たちは温かいお茶を飲みながら、久しぶりに火を入れたという暖炉の前で他愛ない話を続けていた。
話題はほとんど僕とアルフェの小さな頃の話だったが、記憶を共有しているはずのホムまで興味深そうに耳を傾けてくれた。もしかすると、ホムには「事実」として記憶が共有されていても、僕が今感じているようなアルフェへの想いのようなものは掴み切れていなかったのかもしれないな。
話が一段落したところで、竜堂の方から新しい年を告げる鐘の音が響く。
「そろそろお開きにしようか」
まだ眠くはないが、明日もあるのであまり夜更かししているのもと考えて立ち上がる。僕と一緒に立ち上がったエステアが、ふと思い詰めたように口を開いた。
「……リーフ」
「どうしたんだい?」
反射的に問いかけたけれど、なにを言い出すのかわからなくて少しだけ緊張した。エステアは僕の表情の変化を感じ取ったのか、笑顔を作ってから切り出した。
「新年のトーチタウンを見て回りたいんだけど」
「じゃあ、今から出ようか」
「一人で大丈夫よ」
一人で、というところを強調したあたり、きっと考えごとをしたいのだろうなと察しがついた。けれど、竜堂をはじめとして街が明るく彩られている新年とはいえ、見知らぬ街の夜にたった一人でエステアを外に出すわけにもいかない。
「慣れない道で迷うようなことがあれば大変だし、ホムを付き添いにつけてもいいかな?」
子ども扱いしているわけではないし、僕なりの心配はこれで伝わるはずだ。
「お供致します」
「……そうね、お願いするわ」
ホムが進み出ると、エステアは素直に僕の提案に従ってくれた。ホムと二人きりにすることを嫌がらなかったことを考えると、もしかするとエステアは一人でじゃなく、ホムと二人きりで話したかったのかもしれないな。
0
あなたにおすすめの小説

悪役令息、前世の記憶により悪評が嵩んで死ぬことを悟り教会に出家しに行った結果、最強の聖騎士になり伝説になる
竜頭蛇
ファンタジー
ある日、前世の記憶を思い出したシド・カマッセイはこの世界がギャルゲー「ヒロイックキングダム」の世界であり、自分がギャルゲの悪役令息であると理解する。
評判が悪すぎて破滅する運命にあるが父親が毒親でシドの悪評を広げたり、関係を作ったものには危害を加えるので現状では何をやっても悪評に繋がるを悟り、家との関係を断って出家をすることを決意する。
身を寄せた教会で働くうちに評判が上がりすぎて、聖女や信者から崇められたり、女神から一目置かれ、やがて最強の聖騎士となり、伝説となる物語。

不倫されて離婚した社畜OLが幼女転生して聖女になりましたが、王国が揉めてて大事にしてもらえないので好きに生きます
天田れおぽん
ファンタジー
ブラック企業に勤める社畜OL沙羅(サラ)は、結婚したものの不倫されて離婚した。スッキリした気分で明るい未来に期待を馳せるも、公園から飛び出てきた子どもを助けたことで、弱っていた心臓が止まってしまい死亡。同情した女神が、黒髪黒目中肉中背バツイチの沙羅を、銀髪碧眼3歳児の聖女として異世界へと転生させてくれた。
ところが王国内で聖女の処遇で揉めていて、転生先は草原だった。
サラは女神がくれた山盛りてんこ盛りのスキルを使い、異世界で知り合ったモフモフたちと暮らし始める――――
※第16話 あつまれ聖獣の森 6 が抜けていましたので2025/07/30に追加しました。

異世界でぼっち生活をしてたら幼女×2を拾ったので養うことにした【改稿版】
きたーの(旧名:せんせい)
ファンタジー
【毎週火木土更新】
自身のクラスが勇者召喚として呼ばれたのに乗り遅れてお亡くなりになってしまった主人公。
その瞬間を偶然にも神が見ていたことでほぼ不老不死に近い能力を貰い異世界へ!
約2万年の時を、ぼっちで過ごしていたある日、いつも通り森を闊歩していると2人の子供(幼女)に遭遇し、そこから主人公の物語が始まって行く……。
―――
当作品は過去作品の改稿版です。情景描写等を厚くしております。
なお、投稿規約に基づき既存作品に関しては非公開としておりますためご理解のほどよろしくお願いいたします。

三歳で婚約破棄された貧乏伯爵家の三男坊そのショックで現世の記憶が蘇る
マメシバ
ファンタジー
貧乏伯爵家の三男坊のアラン令息
三歳で婚約破棄され
そのショックで前世の記憶が蘇る
前世でも貧乏だったのなんの問題なし
なによりも魔法の世界
ワクワクが止まらない三歳児の
波瀾万丈
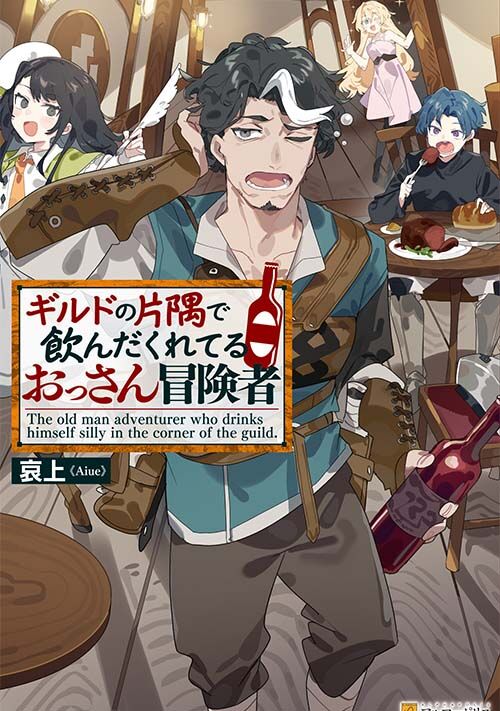
ギルドの片隅で飲んだくれてるおっさん冒険者
哀上
ファンタジー
チートを貰い転生した。
何も成し遂げることなく35年……
ついに前世の年齢を超えた。
※ 第5回次世代ファンタジーカップにて“超個性的キャラクター賞”を受賞。
※この小説は他サイトにも投稿しています。

救世の結界師マールちゃん~無能だと廃棄されましたが、敵国で傭兵のおっさん達に餌付けされてるので、今さら必要と言われても戻りません~
ぽんぽこ@3/28新作発売!!
ファンタジー
「ウチの子、可愛いうえに最強すぎるんだが――!?」
魔の森の隣、辺境伯家。 そこで八歳のメイド・マールは、食事も与えられず“要らない人間”として扱われていた。
――そしてある日ついに、毒と魔獣の禁忌領域《魔の森》へ捨てられてしまう。
「ここ……どこ?」
現れた魔獣に襲われかけたその瞬間。
救いに現れたのは――敵国の”イケオジ”傭兵隊だった。
「ほら、食え」
「……いいの?」
焚き火のそばで差し出された“温かいお粥”は、マールに初めての「安心」と「ごはん」を教えてくれた。
行き場を失った幼女は、強面のおじさん傭兵たちに餌付けされ、守られ、少しずつ笑えるようになる―― そんなシナリオだったはずなのに。
旅の途中、マールは無意識に結界を張り、猛毒の果実を「安全な食べ物」に変えてしまう。
「これもおいしいよ、おじさん!食べて食べて!」
「ウチの子は天才か!?」
ただ食べたいだけ。 だけどその力は、国境も常識もくつがえす。
これは、捨てられた欠食幼女が、敵国でお腹いっぱい幸せになりながら、秘められた力で世界を巻き込んでいく物語。
※若干の百合風味を含みます。


少し冷めた村人少年の冒険記
mizuno sei
ファンタジー
辺境の村に生まれた少年トーマ。実は日本でシステムエンジニアとして働き、過労死した三十前の男の生まれ変わりだった。
トーマの家は貧しい農家で、神から授かった能力も、村の人たちからは「はずれギフト」とさげすまれるわけの分からないものだった。
優しい家族のために、自分の食い扶持を減らそうと家を出る決心をしたトーマは、唯一無二の相棒、「心の声」である〈ナビ〉とともに、未知の世界へと旅立つのであった。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















