お気に入りに追加
0
あなたにおすすめの小説

深川猿江五本松 人情縄のれん
高辻 穣太郎
歴史・時代
十代家治公最晩年の江戸。深川の外れ猿江町は、近くを流れる小名木川にまで迫り出した、大名屋敷の五本の松の木から五本松町とも呼ばれていた。この町に十八歳の娘が独りで切り盛りをする、味噌田楽を売り物にした縄のれんが有った。その名は「でん留」。そこには毎日様々な悩みを抱えた常連達が安い酒で一日の憂さを晴らしにやってくる。持ち前の正義感の為に先祖代々の禄を失ったばかりの上州牢人、三村市兵衛はある夜、慣れない日雇い仕事の帰りにでん留に寄る。挫折した若い牢人が、逆境にも負けず明るく日々を生きるお春を始めとした街の人々との触れ合いを通して、少しづつ己の心を取り戻していく様を描く。しかし、十一代家斉公の治世が始まったあくる年の世相は決して明るくなく、日本は空前の大飢饉に見舞われ江戸中に打ちこわしが発生する騒然とした世相に突入してゆく。お春や市兵衛、でん留の客達、そして公儀御先手弓頭、長谷川平蔵らも、否応なしにその大嵐に巻き込まれていくのであった。
(完結はしておりますが、少々、気になった点などは修正を続けさせていただいております:5月9日追記)

戦国奇人譚 孟嘗ちゃんとおかしな食客
あしき×わろし
歴史・時代
紀元前四世紀末の中国。春秋戦国の乱世に割拠する斉の国。一芸があれば誰でも雇う評判の親分・孟嘗君のもとに、男がひとりやってきた。まったく役にたたないスキルを披露するその男は、意外な素顔をもつ孟嘗君の窮地をとっておきの役にたたないスキルで救うことになる──
さる日本の戦国時代を舞台にしたライトノベルを読んで「もはや実在した男性まで萌やすのか…」と衝撃を受け、あやかって書いた作品となります。かつて『わろし』名義『スキル』のタイトルでBOOKSHORTSに応募し月間優秀作を頂いたのを、改題加筆修正の上でなろうに掲載しましております。

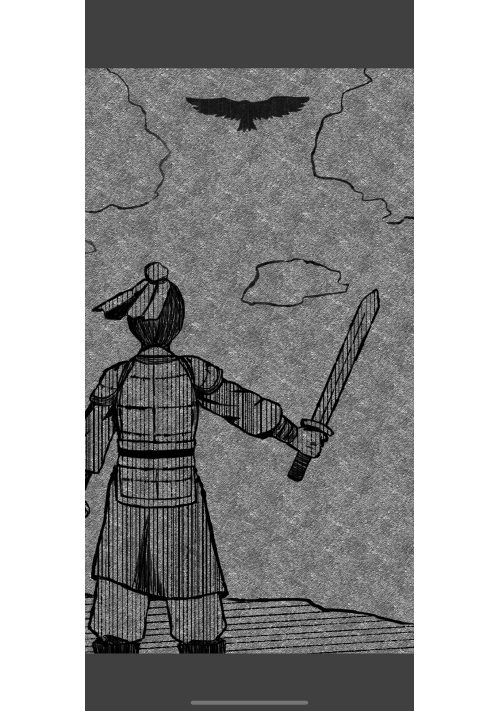
楽毅 大鵬伝
松井暁彦
歴史・時代
舞台は中国戦国時代の最中。
誰よりも高い志を抱き、民衆を愛し、泰平の世の為、戦い続けた男がいる。
名は楽毅《がくき》。
祖国である、中山国を少年時代に、趙によって奪われ、
在野の士となった彼は、燕の昭王《しょうおう》と出逢い、武才を開花させる。
山東の強国、斉を圧倒的な軍略で滅亡寸前まで追い込み、
六か国合従軍の総帥として、斉を攻める楽毅。
そして、母国を守ろうと奔走する、田単《でんたん》の二人の視点から描いた英雄譚。
複雑な群像劇、中国戦国史が好きな方はぜひ!
イラスト提供 祥子様

要塞少女
水城洋臣
歴史・時代
蛮族に包囲され孤立した城を守り抜いた指揮官は、十四歳の少女であった。
三国時代を統一によって終わらせた西晋王朝の末期。
かつて南中と呼ばれた寧州で、蛮族の反乱によって孤立した州城。今は国中が内紛の只中にあり援軍も望めない。絶体絶命と思われた城を救ったのは、名将である父から兵法・武芸を学んだ弱冠十四歳の少女・李秀であった……。
かの『三國志』で、劉備たちが治めた蜀の地。そんな蜀漢が滅びた後、蜀がどんな歴史を辿ったのか。
東晋時代に編纂された史書『華陽國志』(巴蜀の地方史)に記された史実を元にした伝奇フィクションです。



延岑 死中求生
橘誠治
歴史・時代
今から2000年ほど前の中国は、前漢王朝が亡び、群雄割拠の時代に入っていた。
そんな中、最終勝者となる光武帝に最後まで抗い続けた武将がいた。
不屈の将・延岑の事績を正史「後漢書」をなぞる形で描いています。
※この作品は史実を元にしたフィクションです。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















