6 / 112
6話~ストーン・ホルダー~
しおりを挟む
~ストーン・ホルダー~
それから、そう時間はかからなかった。
暫くして、デュボアの部屋の窓の外を長く鋭い影がひとつ、夜気を切り裂くように走った。
四月の夜はまだ肌寒く、塔の石壁には淡い月明かりが薄く滲んでいる。その光の上に、青竹色の鱗が一瞬だけ滑るように映り込み、すぐに消えた。羽音はなく、ただ、閉じた硝子越しに、微かな風のうねりが伝わってきたような気がした。
……あれがジャン・ピエール・カナードの使い魔、風蛇ザイロン。
静かに羽を畳み、寮塔の玄関前、――おそらくは、彼の自室からなるべく近い場所付近に降りたのだろう。
数分後、廊下から軽い足音が響き、扉が二度叩かれた。
「どうぞ」
デュボアの声に応じて入ってきたのは、第二寮『レスポワール』の寮監、ジャン・ピエール・カナード――。
細縁の眼鏡が、室内の灯に一瞬きらりと光る。黒いローブの下、襟元にザイロンがアスコットタイに姿を変えて巻きついていた。
「戻りました」
無駄のない声だった。挨拶すら、細やかに刈り込まれた文章の一節のようだ。
もしも妹のアヤちゃんがここにいたなら、「あの人の爪の垢を煎じて、兄ちゃんに飲ませたいよ」なんて言ったかもしれない。――あの呆れたような笑い声と一緒に。
そんなカナードは後ろ手に戸を閉めると、視線を一度だけゆるやかにこちらへ流した。
そして、その途中、レオの肩にとまっていたネージュを見付けた瞬間、ふっと僅かに眉を上げた。
意外、というよりは、興味深いものを見つけたという反応だったが、静かな眼差しには、冷静な観察者の光が宿っていて、すぐに表情を整えると、何事もなかったかのように微笑みをひとつ浮かべた。
それから、まっすぐデュボアの前へと歩み寄り、ローブの内側からペンダント型のストーン・ホルダーを二つ、静かに取り出す。
「《ノルデュミールの籠》です。これが現段階で最も安定して魔力制御できる構造かと」そう前置きして、カナードは手にした一つを軽く傾けた。「形状は球体を中央で半分に割ったもの。外装は高密度黒鋼。透かし彫りは通気と視認性を兼ねています。内側には振動と熱に対する緩衝魔法を。外側には磁力と結界による多重固定を施しました。開閉には所定の魔力操作が必要です。目立たず、それでいて用途を損なわない。機能と意匠の両立を図ったものとご理解ください。――仕様は以上です。ご確認を」
そう言い添え、カナードは手のひらに並べた二つのペンダントをそのままデュボアに差し出した。
彼の説明は、あまりにも端的で、まるで講義の一節のように、また、こちらの疑問を予測するかのように整えられていて、それでいてどこにも感情の起伏がないのが逆に印象的だった。
デュボアは無言で受け取り、片方を手に取る。
外装に指先を滑らせ、透かし彫りの奥にわずかに覗く空洞を確認すると、留め金の接合部をそっと押して磁力と魔力による固定の具合を丁寧に試した。
「アペリオ」小さく乾いた音を立てて開いた蓋の内側には、緩衝魔法の陣が極めて繊細に刻まれていた。「……問題ないですね。ありがとう。相変わらずお見事。申し分ない仕事だ」
もう一方のペンダントにも目を通し同様の操作を終えると、デュボアは軽く頷き、視線だけでボンシャンに合図を送った。それを受け取ったボンシャンが、箱の中から瓶を取り出す。無色透明なガラスの中に、漆黒の光を宿した球体――奇石ペルル・ノワールがふたつ、静かに沈んでいる。
その瞬間、カナードの瞳が初めて揺れた。
感情というより、正確には「観測」の視線。まるで目の前の現象を理知の奥底で解き明かそうとするような、ごく僅かな間。
だが次の瞬間には、彼の表情はいつも通りの静けさへと戻っていた。
「……これが」
ほんの微かに息を呑む気配。だがそれ以上は何も言わず、再び黙して見守る姿勢に徹している。
デュボアは蓋が開いたペンダントの一つを左手に持ち、右手でボンシャンから奇石を受け取る。奇石は光を吸い込むような漆黒の輝きを放ちながら透かし彫りの奥にゆっくりと収まった。
一瞬、ストーン・ホルダー全体に淡い光が走り、それがぴたりと定まったところで、
「カシェ」
デュボアは留め金を封印するように閉じた。カチ、と小さく音が鳴る。
もう一つの奇石も同様に移し替えられ、二つのノルデュミールの籠が完成した。
デュボアは仕上がったそれらを掌に収めると、くるりと身を転じ、俺の前へと歩み寄って来た。
「ネージュ、コルベール君のところまで飛べますか?」
ボンシャンがやわらかく問いかけると、ネージュは小さく「きゅっ」と鳴いた。
そして、レオの肩を蹴って小さく羽ばたき、ふわりと浮かび上がる。軽やかな弧を描きながら、俺の肩へと降り立った。
「セレスタン・ギレヌ・コルベール、ネージュ、お前たちの奇石だ」
デュボアがそう言って、ペンダントをふたつ、そっと俺の手の中へ乗せた。
伝わる重みと、輝き。
デュボアの言葉に続くように、カナードが一歩前に出て、静かに口を開いた。
「白い君には、まだこのペンダントは大きすぎます。成鳥になり、身に着けられるようになるまでは、コルベール君が預かっていてください」 彼の声音は変わらず淡々としていたが、わずかに目を細めたその表情には、確かに温度があった。「これは、一人と一羽の絆の証です。どうか、大切に――」
言葉の最後は、すっと余韻の中へ溶けていった。
俺は手の中のペンダントを見下ろし、肩に止まったネージュへと視線を移す。小さな翼を揺らしたネージュが、じっとこちらを見返していた。
……ああ、わかってる。
大切にする。必ず。
その後、場の緊張がゆるやかにほどけていき、それぞれが自室へと戻る流れとなった。
俺は改めて、デュボア、ボンシャン、カナードの三人に向き直り、静かに深く一礼をする。
「ありがとうございました」
三人とも穏やかに頷き、あたたかなまなざしを返してくれた。
「礼には及びませんよ」
「協力出来て何よりだ」
ボンシャンとカナードがそう言って、微笑む。その声は穏やかで、なおかつ、芯のある温かさがこもっていた。
デュボアは少し身体を前に傾け、真剣な表情で続けた。
「また何かあったら、すぐに知らせてくれ。俺が不在の時でも、ボンシャン先生かカナード先生のどちらかに頼れば大丈夫だ」
彼の言葉には責任感と信頼がにじみ出ていて、俺の胸にしっかりと響いた。
部屋を出る前、俺は肩にとまっていたネージュをそっと携帯用のゲージに収めて蓋を閉じ、手に提げてから静かにドアをくぐった。
サヴォワール寮の一階廊下を進み、淡い明かりに照らされた階段へと向かう。
二階に着いたところで一度立ち止まり、カゴを持ち直して正面から向き直る。
「レオ。今回は本当に、いろいろと気を配ってくれてありがとう。心から感謝しています」
いきなりかしこまってそう言った俺を見て、レオは少し驚いたように目を瞬かせたが、すぐに柔らかな笑みを浮かべた。そして、どこか照れ隠しのように、軽く眉根のあたりをかきながら口を開く。
「ま、本当は、担当のグラン・フレールとして当然のことだって、そう言うべきなのかもしれないが……、それだけだと、なんだか義務でやってるみたいに聞こえてしまうだろう? ……俺は、セレスにとって『兄』であること以上に、できれば『友人』にもなれたらと思っている。これから、そういうふうに……」言い終える前に、レオは少し恥ずかしそうに視線をそらし、肩をすくめ、言葉を探すように息をついた。「……なんだか、柄にもないことを言ってしまったな」
胸の奥がじんわりと温かくなって、思わず笑みがこぼれる。
「俺も、『友達』って思っていいですか?」
レオは目を細め、口の端をゆるく上げて、穏やかに微笑み頷いた。
「じゃあ――おやすみ、セレス」
「おやすみなさい」
背を向けて去っていくレオの後ろ姿をしばらく見送る。
夜の静寂が胸の奥を優しく撫でるように広がっていく。
その直後。
背後で、ナタンの長い長いため息が静かに漏れた。
「……はあ~~~……」
ふと左右を見やると、リシャールとアルチュールの二人が、揃いも揃って、わずかにうつむいたまま考え込んでいる。片手は額に、もう片方は肘を支えるように添えられ――その姿は、どこか哲学的な苦悩すら滲ませていた。妙に荘厳さを感じる。
……座っていたら、まるでロダンの彫刻だな。
「セレス……、懐に入りすぎだろ……」
「セレス、君はちょっと、天然がすぎる……」
二人の困惑まじりの声が、妙に静けさを帯びて響く。
そんな中、ふとカゴを持つ手に、ブルブルと小さな振動が伝わってきた。
この鳥、今、絶対、両翼の先でくちばしを隠し身を震わせてやがるな……。
カタカタカタカタ……、と小刻みに震えるゲージを手に三階に到着すると、アルチュール、リシャール、ナタンと並んで廊下を進む。
部屋の前で足を止め、それぞれに「おやすみ」と短く言葉を交わした。明日も授業がある。名残惜しくとも、話し込みすぎるわけにはいかない。夜の語らいには限度がある。
扉の前で深呼吸をひとつ。そっとノブを回し、俺は静かに自室の中へと入っていった。
ドアを後ろ手にそっと閉じ、すぐ手に持っていた携帯ゲージを机の上に置く。
留め具を外して蓋を開けると、ネージュは中からフラフラとした足取りで出て来て、そのまま「ちょっと、バスケットをここに持って来てくれ」と言って俺に寝床を運ばせると、「よっこらせ」と両羽で縁を持って乗り越え、中に突っ伏した。
飛べよ……。
「……おい、大丈夫か?」
思わず冷たい視線を向けてそう問うと、くぐもった声が返ってきた。
「……やばい……。今回も尊い。尊い以外の言葉が出て来ない……」
肩をすぼめ、元々小さい身体をもう一回り小さくしながら、ネージュが全身を震わせる。
「は? ……お前、さっきからずっと震えてたよな。カタカタカタカタカタカタカタカタと。俺がどれだけ周囲に気付かれないようゲージを持ってたと思う? お前が具合でも悪いんじゃないかって心配されて、ややこしい空気になるのを避けようと必死だったんだよ……!」
「なあ、セレス。なんだ、あの生き物は。なんで、あんなにも心の琴線を鷲掴みにしてくるんだ? ちょい悪系でありながら、柔らかい笑みと不器用なまでに真剣な眼差し……、ふつくしい。ビジュアル圧が強すぎて、思考が飛ぶ。『兄』である以上に『友人』になりたいなどと……、尊い。尊すぎる。存在が尊い……! 永久保存版だな」
「いや、聞けよ!」
「レオ……、推せる……。推せるというか、もう崇めるレベル……」
「ねえ、聞いて、ネージュさん?」
小刻みに震えながら、ネージュは胸に羽根先を当てて、悶絶している。
「見たろ? 無自覚だぜ、あれ。あの自然体で心に矢を刺してくるレオ・ド・ヴィルヌーヴ、怖ろしい子っ。しかし、正面からあれを受け止めて、あまつさえ『友達って思っていいですか? カッコ、裏声、カッコ閉じる』なんて返したセレス、お前の方もヤバい。なんであんな素直なことさらっと言えるんだ……?」
「いや、そんなこと言われても……、ってか、お前、ちょっと落ち着け。人の言ったことを注釈付き裏声で真似すんな。つーか、とうとう、呼び捨てにしてきたな」
「気にするな」
「しねーけど」
俺は半分呆れながら椅子に腰を下ろし、バスケットの中で打ち震えるネージュを見やる。鳥のくせに情緒が忙しい。
誰に似たんだか。
……俺か……。
「しかし、セレスはアルチュールに傾いてるな……」
「はぁぁぁあ? ち、違ぇし!」
思わず声を上げた俺に、ネージュは片目だけ覗かせて小さく笑った。
「ん? 動揺した」
「してない」
「したな」
「してねぇって!」
「お前ぇさんワンコ系攻めキャラ好きだもんな。しかも、あのルックスだ。見る者の時間を奪う沈黙の美。近づけば壊れてしまうか、あるいは、こちらが壊されてしまうか。そんな危うい魅力が全身の毛穴という毛穴からあふれている」
「なんか、いいこと言いながら、最後は毛穴なんだな」
「間近で見るの、まだ慣れてないだろ? 横に居る時はチラチラチラチラ見てるよな? ……で、時々、お前ぇさんの視線を感じたアルチュールが振り向いて、バチッと目が合って、ちょっとアタフタしてんの。あれがまた……、視線受けぇー振り向く君のーその顔にぃー、動揺の波ー実に良きかなぁー」
「急に詠むな。しかも、なんで朗読調なんだよ」
「いや、これは心の歌……。言葉では収まりきらぬ想いが、五七五七七に姿を変えただけであって……」
「どこの古のオタクだよ。まあ、確かに。毛穴から漏れ出してるなにかが強すぎて、呼吸のリズム崩れるけど。見てるだけで酸素が足りなくなる。推しのすぐそばに居られることは至高の喜びなんだが、たまに視線そらして息継ぎしないと無理。しんどい」
思わず苦笑して首をすくめると、ネージュはふいに少し首を傾げて見せた。
「人、それを恋という」
「だから、違うって言ってるだろう!」
「……そう言い切れるあたり、まだ重症ではないと見える」
「いや、そもそもそういう目で見てねぇって……」
「では、今のところアルチュールもリシャールもナタンもレオも、『特別に気の合う友人』ということで、整理しておいてあげようかね?」
ぐっと羽を伸ばし、バスケットの縁に寄りかかりながらネージュは毛づくろいを始めた。さっきまでの熱狂はどこへやら、あっという間に気ままな調子に戻っている。
窓から差し込む月の光が、白い羽根を銀色に縁取る。
「……話は変わるが。セレス、――さっきのストーン・ホルダーの内部、見たか?」
「ああ。少しだけ」
俺は内ポケットに手を伸ばし、ざくろ色の魔法布に包まれた二つの《ノルデュミールの籠》をそっと取り出すと、デスクの上に並べて置いた。
「アペリオ」
短く呪文を唱えると、カチリと音を立てて蓋が開く。俺は身を乗り出し、中を覗き込んだ。
蓋の裏――そこには、極細の魔力線が蜘蛛の巣のように広がっていた。カナードが描く繊細を極めた魔法陣の編み目は、見る者に静かな威圧感すら与える。
「……これが……、緩衝魔法? 複雑……、どころではないな。もはや、異常の域だ」
「……まったくだ」
思わず呟いた俺の言葉に、ネージュがすぐさま反応した。
彼は、鋭い目を細め、空を仰ぐようにして続けた。
「俺たち鳥の視覚は、人間の数倍――いや、十倍とも言われている。光の波長も幅広く捉えるし、細かな模様や色の違いも、お前ぇさんらよりずっと鮮明に見える」
「そうらしいな」
「そんな目で見ても、これは異常なほど緻密だ。複数の陣が三次元で絡み合い、幾層にも折り重なって、全体でひとつの術式を構成していて単なる図形じゃない。命を持って蠢く構造体みたいだ。線のひとつひとつが迷いなく、淀みなく、正確に引かれている。まるで、生きているみたいなんだ」そこで、ネージュは少し息をのんだ。「これを描いた者は……、まともじゃない。常人の神経で、こんなものを練り上げられるはずがない。けれど、狂気と紙一重の、限界すれすれの知性がなければ、ここまでは届かないだろう。――ジャン・ピエール・カナードは、本当に、魔術の鬼才だ。と、同時に……、この魔法陣は、とんでもなく美しい」
ネージュの目の奥にははっきりとした称賛の色があった。
「美しい?」
「そう。まるで音楽の譜面。旋律を感じる構造。規則と変化の調和」
「……すごいな、そんなふうに見えるのか」
「普通の人間は、訓練しないと目が追いつかない。訓練しても、見えないやつが殆どだろう」ネージュは羽根をわずかに震わせ、バスケットの縁に乗り上げるようにして陣を見下ろした。「これはな、“積み重ね”なんだよ。時間と努力と、勉強と鍛錬。――セレス」
「ん?」
「俺は、卵のときに、デュボアとボンシャンとカナード――三人の寮監たちの魔力の影響をいささか受けている」
――伝書使になるコルネイユの卵ってのは、配られる前、個体の差異が大きく出ないよう、こと細かに性別鑑定に至るまで事前に魔術で均一に管理されている。
レオが言っていたことを思い出す。
「だから三人の使う魔法の“感触”とか、“音色”とか、そういうのが分かるんだが、お前ぇさんみたいに、こっちに来て、光の属性や多大なる加護というチート能力を与えられた特異体質で最初から『できる』人間には、たぶん、こういう積み重ねの末にたどり着く仕事は、逆にキツい……」
「……ああ、うん。ネージュの言うことは分かる。その通りだな……」
「これはさ、きっと何もできなかった頃のカナードが、何年もかけて自分の限界を一つ一つ超えて、やっと辿り着いた精度だと思う」そう言ったネージュの瞳は、真剣だった。「今のお前ぇさんには、どれほど力があろうと、あの三人の誰一人にも敵わない」
「……だろうな」
俺は再びペンダントを見下ろす。そこに収まる漆黒の奇石。
「精進しろよ」
頷いてから、俺は手前のホルダーを手に取った。石が月光を吸い、かすかに光を返す。それを、胸元にそっと着けて下ろし、服の中へと滑り込ませると、しん、と冷たい感触が肌に落ちた。すぐに体温で馴染んで、まるで最初からそこにあったかのように収まる。
「カシェ」
もう一方のホルダーに手を伸ばし、呪文とともに蓋を閉じる。そしてそれを、そっとネージュの前へ差し出した。
ネージュは嬉しそうに羽根をふるわせながら、それを両の羽でそっと抱えバスケットの中へ入れた。まだ身に付けるには、ペンダントは大きすぎる。
「なあ、ネージュ。俺、……頑張らなきゃな」
「推しを救い、友人たちを守るんだろ?」
「ああ」
「俺にも手伝わせてくれ」
「……お前、生まれたてなのに本当にすごいな」
「フッ、まあな。だが――」ネージュは、羽根の先で自分の胸をとんと叩いた。「俺の……、というか、伝書使の基礎を作ったのは、寮監三人によるものだし……、孵化してからは、俺、個人のアイデンティティだ。でもな、俺の大半は、お前ぇさんの記憶と経験で出来ている。そういう意味では、俺の行動や言葉は――お前ぇさんが俺に教えたも同じだ」
俺は息を呑んだ。
ネージュは続ける。
「……誇っていいぞ、セレス。悪くない出来だろ?」
不意に胸の奥が熱くなる。
「……ありがとな。ネージュが俺のところに来てくれたことを心から感謝するよ」
「一晩中、腐談議も出来るしなぁー」
「それは、誇りたくない。授業があるから一晩中は無理。寝たい」
「いや、誇れよ。寝る間も惜しんで腐談議に付き合えよ」
そう言って、ネージュは首をひねりながら、ふっと吐息を漏らすように羽を膨らませた。
その声音には、仲間としての絆と、友としての祈りが、静かに、しかし確かに滲んでいた。
「ところでだな、セレス」
バスケットの中でペンダントを抱えたネージュが、こちらを見て言った。その赤い瞳は、まるでおもちゃを手に入れた子どものようにわくわくと輝いている。
「なんだよ?」
「通信機能があるんだろ? 試してみたい。使ってみないことには、どんな具合かも分からん」
「……授業でやるんじゃないのか? 勝手にやっていいのか?」
「「使うな」とは、言われていない」
得意げにくちばしを鳴らしてそう返してくるネージュに、俺は少しだけ目を細めた。
「……ああ、確かにそれもそうだ。……今なら、距離も近いし、失敗しても大丈夫だな」
「だろ?」
「仕方ないな」
ネージュは嬉しそうに羽根をすぼめて、ちょこんと座り直した。その動きはどこかぎこちなくて、でもその不器用さが、やけに可愛らしい。
「じゃあセレス、ちょっと距離を取ってくれ。そこにいると、声がダダ漏れだ」
「分かった。で、どっちから呼び出す?」
「やっぱり、主、お前ぇさんからで」
「了解」
俺は立ち上がりベッドまでゆっくりと歩いた。マットに腰を下ろし、深呼吸をひとつ。
サリトゥを感じながら掌に意識を集中する。そして、胸元に下げたペンダントをそっと握り、呪文を唱えた。
「……フェルマ・ヴォカ」
その瞬間、ベネンが淡く輝き、細い光の糸が掌からペンダントへと繋がって、やがて目に見えない波となって広がり、消えて行った。
空気がぴんと張り詰める中、声が響く。
「……おっ、こっちの奇石が光った!!」
「ネージュ、レシピオ・ヴォカ、レシピオ・ヴォカ言って」
「おっと、そうだ。レシピオ・ヴォカ!」
直後、ネージュの声が、ノルデュミールの籠に入れられたペルル・ノワールから聞こえて来る。
《そういやぁ、この呪文、既に頭ん中にあったわ。セレスの記憶だな、これは……。えーと、こちらネージュ、聞こえるか?》
どこか緊張を帯びながらも、興奮と期待が入り混じった様子だ。
「ああ、聞こえてる。ばっちりだ、ネージュ。音もすごくクリアだ」
《本当に……? こっちもだ。すげぇ……! 俺の声、ちゃんと届いてるんだなあー》
バスケットの方をちらりと見ると、ネージュが感嘆したようにホルダーに入った石を抱きしめていた。なんだか、彼の喜びが言葉以上に胸に伝わってくる。
「……ああ。まるで……スマホみたいだな」
《おっ、それだっ! それだよセレス! スマホってやつだ! 俺、知ってるぞ、映像とかも送れるやつだろ? あの、ぴっぴってやつ!》
ネージュの声がやけに楽しげで、思わず笑ってしまった。
「ぴっぴって……いやまあ、そんな感じだけどな」
《これ、持ってるだけで文明の利器って感じするわ……。やべぇ……俺、今、一年生の伝書使で最先端だな!》
ぴょこぴょこと羽根を弾ませ、ネージュが言った。
「……あれも、テストしとくか? デュボア先生たちがやってた位置確認」
《あっ、あれな! やろうやろう!》
ノリノリで返ってくる返事に、こちらまで楽しくなる。本気で気に入ったらしい。奇石を手に入れたことが彼にとってどれだけの意味を持っているか、改めて思い知らされる。
「せーの、で行くぞ」
俺は再びペンダントを握り直した。
《よし。せーのっ》
「せーの」
《ローズ・デヴォン》
「ローズ・デヴォン」
一人と一羽の声に呼応するように、ペルル・ノワールがふわりと脈打つ。
直後、目の前の空間に円形の羅針図が浮かび上がった。淡く光る輪郭を持つその図形は、中心から静かに回転しながら周囲を測っていく。まるで、意志を持ったかのようにゆるやかに動き、やがて一点が小さく輝いた。
それは、寮の一室――ネージュの位置を示していた。
《……すげえなこれ。なんか、俺たち本当に“繋がってる”って感じだ……》
「ああ……この奇石、想像以上にすごいな」
ネージュの言葉に、俺も深くうなずいた。
ちなみに、伝書使たちが奇石を使う際には、呪文こそ唱えるが、魔法陣を展開する必要はない。というのも、奇石は彼ら自身の卵の殻から生成されたものであり、自らの起源に由来する素材は魔法回路との親和性がきわめて高い。そのため、余計な媒体を通さずとも、魔力が直接届く。
仕組みについては、『ドメーヌ・ル・ワンジェ王国の薔薇 金の君と黒の騎士』にも記されていた。
そして、先ほどのデュボアと伝書使のノクス、カナードと伝書使のカリュストとのやり取りを見ても、設定はこの世界において、しっかりと踏襲されている。
《なぁセレス、これさえあれば、お前ぇさんが学院に行ってる間も話せるよな?》
「まあな。……ただし、奇石を持ってることはまだ公にできない。それどころか、ネージュが一日で孵化したことも誰かに知られたらマズい」
その言葉を聞いた瞬間、ネージュの羽根がふるりと揺れた。口をへの字に結び、そっとペンダントに視線を落とす。羽根の隙間から覗くその表情は、しょんぼりという言葉そのものだった。
あからさまに落ち込んだ様子が、なんともいじらしい。
「……だからさ。なるべく人目は避けて……、こっそりな。な?」
俺が少しだけ声を和らげて言うと、ネージュはバスケットの中でぱっと顔を上げた。
《こっそり……! そ、それなら……アリだな! よし、作戦名“シークレット通信”、決定!》
しょんぼりしていた表情から一転、ぱたぱたと羽根を弾ませながら、わさわさと動くネージュ。その様子に、思わず口元がほころぶ。
《……ああでも、早く使いたくてうずうずする……!》
ネージュは胸元の石をまた抱きしめていた。
彼はまだ、他の伝書使たちの孵化が始まるまで、しばらくはこの寮の部屋から出られない。だからこそ、こうして通信ができることは、ネージュにとっても大きな意味を持っている。奇石は窓であり、声であり、外と繋がるための小さな翼なのだ。
《セレスが授業を受けている間……、俺、ちゃんと待ってるからな。なるべく騒がずに、大人しくしてる……つもり。でも、窓から見える景色には注目しておくぞ。良い感じの二人連れがいたら、昼休みぐらいを見計らって報告する!》
「……おい」
《もし誰かが、うっかり靴紐がほどけた子にさりげなく結んでやったりしてたら、確実に報告対象だ》
「いや、うちの制服、革靴だから。紐ない」
《……っく、くそぉっ……! 学院内には、“ほどけた靴紐を結んであげる胸板の厚いスパダリ攻め”が存在しないのかっ!?》
ネージュは天を仰ぎ、翼をばっさばっさと動かして悔しがる。声は完全に落ち着いたバリトンボイスなのに、身振りはどこまでも無垢で、なによりも本気で残念そうなのが、妙に可笑しい。
俺は少し笑って、呟く。
「じゃあ……、そろそろ終わりにするぞ、ネージュ」
《おう、仕方ないな。了解。フィネ 》
「じゃあ、フィネ」
その瞬間、淡く光っていた奇石の輝きが、ひとひらの羽根が舞い落ちるように、静かに収まっていった。
通信は、終了した。
けれど、二人の絆は、確かに、そこに在った。
腐男子の絆が――。
༺ ༒ ༻
ネージュが孵化してから十五日が経った昼下がり。
学院の食堂は、いつものように昼食を取る生徒たちの声で賑わっていた。
木漏れ日が差し込む窓際の席に、俺たちはテーブルを挟んで座っている。右斜め前のナタンはパンにバターを塗り、正面のリシャールはスープを一口ごとに吟味しているような表情を浮かべ、右隣のアルチュールはというと、なにやら少しだけ口元に力が入っていた。
「……なあ、相談ってほどじゃないんだが――。ちょっと聞いてくれるか」
その声音はいつになく慎重で、けれど隠しきれない思いが滲んでいる。
俺たちが自然と耳を傾けると、アルチュールはわずかに息を吐いて続けた。
「この学院に来てから、ずっと、まともに身体を動かしてなくて……。授業は想像していた以上に興味深い上に、学ぶことも多いのは理解している。しかし、剣を握る時間が短いと、どうも落ち着かない」そう言ってから、彼は自嘲気味に笑った。「昔から、毎日かかさずやってたんだ。剣を振るのは、俺にとっては、呼吸みたいなものだから」
その一言に、俺は思わず大きく頷いていた。
「……分かる。デュボア先生の剣術の時間だけじゃ、ちょっと物足りないもんな」
気づけば、それは俺自身の実感でもあった。座学も嫌いじゃないが、体を動かすことで整う感覚ってのは、確かにある。
本編でも、アルチュールはちょうどこの頃、学院の生活に慣れ始め、授業の緊張が少しずつほどけてきたタイミングで、こうして自主的に鍛錬を始めていた。
「それならば」バターを塗り終えたナタンが、ふと思いついたように口を開いた。「デュボア先生に頼んで、第一寮の一階ホールを借りられないでしょうか? 先日、カナード先生に教わった簡単な結界で魔法障壁を張って内部を保護しつつ、外に音が漏れないようにすれば、夕食後に鍛錬するにはちょうどいいと思います」少し肩をすくめながら、彼は続ける。「どうせやるなら、この際、四人で集まって交代で手合わせしてみませんか? ひとりで黙々と剣を振るより、刺激になると思いますが。いかがですか、リシャール?」
「殿下と呼べ」
「いーかーがーでーすーか~、りっしゃ~~ルるるる?」
ナタンがわざと巻き舌で語尾を伸ばし呼びかけると、リシャールとアルチュールが思わず吹き出しそうになりながらも、口元に笑みを浮かべた。
その笑みは、曇り空の一瞬の晴れ間のように、二人の端整な顔立ちにふっと柔らかさを増し、まるで磨かれた彫像に温もりの気配が宿ったかのようだった。
――ぬぉぉぉぉおっ! 今の笑い方、ずるいだろ!
無防備に浮かんだアルチュールの笑顔は、普段の無口で不器用な印象を吹き飛ばすくらい自然で、息をのむほど整っていた。本編じゃまずお目にかかれない、『レア・微笑み』だ。尊い!
そしてその隣で微かに笑ったリシャールの横顔ときたら! 金糸の髪が揺れ、まつげの影が頬をかすめる。まるで絵画の中から抜け出した王子様。ふっ、ふつくしい……。
軽く肩を揺らしつつ、アルチュールが頷く。
「室内なら天候にも左右されないし、剣の動きにも集中できそうだ。毎日じゃなくても、時間が合えばぜひ、みんなで……」
ゆったりとスプーンを置いたリシャールが、静かに話に加わる。
「使用する剣道具なんだが――最近、学院には、“特殊な剣”が装備された。まだ通常の授業には取り入れられていないが、以前、王族が視察する魔道軍の剣術試合の場で、それを用いて模擬戦を行うのを見たことがある」
彼の言葉に、アルチュールが目を見開き、ナタンが興味深そうに身を乗り出した。
もちろん、俺は本編を読んでいるので、それの存在を知っていた――そう、模造刀ではあるが、不思議な剣だ。
「“エクラ・ダシエ”――そう呼ばれている剣だ」リシャールは一呼吸置いて、ゆるやかに説明を続けた。「訓練用の模造剣で、形は本物そっくりなんだが、斬撃が人体に触れた瞬間、刃の部分だけが霧のようにふっと消える。だから、怪我をすることはない。斬られた側には痛みはなく軽い衝撃だけが伝わり、斬った側には手応えが残る仕組みになってる。魔法と鍛冶技術の融合で生まれた、高等な訓練用の剣。古代の魔法構造を応用していて、見た目も感触もリアルなのに、決して相手を傷つけないようできている。試合に出ていた者たちは、それを使って見事な技を見せていた」
「エクラ・ダシエ……鋼の閃光、か。理に適ってるな。安全かつ実戦的な訓練ができるとなれば、そりゃ強くなるわけだ」
アルチュールが小さくその名を繰り返すと、ナタンも感心したように頷いた。
「実に格好いい名前ですね。訓練用とはいえ、そういう精巧な道具を使えるなら、本格的に鍛錬する気持ちにもなるというものです。ね、セレスさま」
「そうだな。しかし、王族だけが視察を許されてる魔導軍の試合か。生で観れたら、きっとものすごい迫力なんだろうな……」
俺は思わずそう漏らしながら、リシャールの横顔を見やる。
その視線に気づいたのか、リシャールがわずかに口角を上げて言った。
「今度は、セレスも誘おう。『銀の君』がいると、空気が和らぐ」
ナタンが唐突に、すっと背を正した。
「ありがとうございます。ご配慮、痛み入ります」
「……ナタン、君は誘っていないが?」
そのリシャールの一言に、アルチュールが紅茶のカップを置きながら、穏やかに参戦してきた。
「リシャール、それは少々不公平ではないか。"ぬけがけ"はルール違反だ。セレスを誘うなら、我々にも同じ機会を与えるべきだ」
「必要な人材を勧誘しているだけだ」
リシャールが平然と返すと、アルチュールは少しだけ眉を上げた。
「では、その“必要な人材”というのは、剣術のためか? それとも――心の癒やしのためか?」
一瞬の沈黙。
その間にナタンが満足げにうなずいた。
「まったくもって同感です。セレスさまがいてくださると、場が和みますからね。そもそも侍従として随行するのは当然の……」
「まだ君を連れて行くとは一言も――」
だがナタンは真顔のまま、きっぱりと答えた。
「学院の外であれば、私はセレスさまの侍従です。一緒にうかがうのは当然の義務」
――なにか、「ぬけがけ」とか「ルール違反」いう不穏な単語を耳にしたような気がするけれど……。
俺は少しだけ首をかしげながら、目の前で繰り広げられる静かな攻防を、なんとなく苦笑いしつつ見守った。今日もアルチュールとリシャールの距離は、友人のままで全然縮まらない。進展の兆しなど欠片もなし。もちろん、どこかのタイミングで不意に歯車が噛み合う可能性はあるけど……今はまだ、その時じゃないんだろう。
供給がないなら、待つ。それが、腐の民としてのたしなみだ。
「じゃあ……今度、みんなで行こうな。にぎやかでいいじゃないか」
仕方なく俺がそう言うと、空気がふっと和らいだ気がした。
リシャールは目を伏せて微笑み、アルチュールは肩をすくめながら、「まったく、セレスには敵わないな」と呟く。
ナタンがすぐに、場を仕切り直すように、軽やかに手を振った。
「はいはい。さて、話は戻りますが、具体的な稽古の日時や場所の件、早めに決めておきましょう。今日中にデュボア先生にも相談して、彼の都合も聞いてみませんか?」
「……わかった」
アルチュールがそう返事をして、リシャールも静かに同意した。
「無理なく調整しながら進めよう」
俺は表情だけで賛同を示しながら、その言葉を返した。
そのとき、始業の十分前を告げる予冷のベルが鳴り響いた。
俺たちは顔を見合わせて立ち上がる。それぞれが何かしらの余韻を抱えたような表情だった。特にアルチュールは、どこか高揚したような面持ちで窓の外に目を向けた。
その横顔には、鍛錬のことを思ってか、静かな意欲が宿っている。
それから、こちらへと視線を戻し、彼は短く告げた。
「……行こう。そろそろ始まる」
頷いて、俺たちは教室へと足を向けた。
午後の授業は、淡々と進んだ。
カナードは、迷いなく白墨を手に取る。あえて手で板書するのが彼のやり方だった。黒板には整然とした文字が並び、古代呪文の構文がひとつずつ、簡潔に綴られてゆく。流れるような筆致には、長年積み重ねてきた思考と技術が滲んでいた。
魔法に頼らず、自ら書き記すという一手間に、彼の矜持が宿っている。
線が黒板を滑るその音は、咳払いと混ざりながら、乾いた午後の空気をほんのわずかに震わせていた。
ネージュの言葉を思い出す。
――かつては“何もできなかった”カナードが、積み重ねの末に辿り着いた場所。書くという行為は、今もなお彼にとって、思考と技術を鍛え直すための訓練なのだ。
その手つきに、俺はどこか敬意に近い感情すら覚えていた。リシャールやアルチュールたちの天才的な煌めきとは、また違う光が彼にはある。
俺も、そうありたい――そんなことを、ふと思った。
やがてチャイムが鳴り、授業が終わる。
ざわめきが教室を満たし、椅子の脚が床をこする音が断続的に響いた。誰かの笑い声、誰かの欠伸。外では、風が木の葉を揺らしていた。
生徒たちは思い思いに席を立ち、廊下へと散っていく。
そして、リシャールが静かに立ち上がる。それに続いてアルチュールとナタンも席を離れ、俺もゆっくりと腰を上げた。
まるで決まっていたかのように、自然と足が揃う。
それから、俺たち四人は予定通り、職員寮二階のデュボアの部屋へと向かった――。
回廊を歩きながら、自然と会話が生まれる。
何気ない雑談をしながら、四人で歩く足取りはどこか軽やかだった。
部屋の前に着くと、リシャールが軽くノックした。
三拍ほど間を置いたあと、中からくぐもった声が返ってくる。
「どうぞ、入ってくれたまえ」
扉を開けると、デュボアは窓辺の机に向かって書き物をしていた。分厚い本が何冊も積まれ、その合間には乾きかけたインクと羽根ペン――。
そして、丸テーブルの上には飲み終えたばかりと思われるマグカップがひとつ、無造作に置かれていた。陶器の内側には、濃い茶渋のような跡がわずかに残っている。忙しさの合間に一息ついた痕跡のようだ。部屋の中には、古紙と焙煎豆の混ざったような、落ち着く香りが漂っていた。
「お忙しいところすみません」
リシャールが率先して頭を下げる。俺たちもそれにならった。
「いや、いいんだよ。……どうした? また一風変わった伝書使が孵化したか?」
口元に笑みを浮かべながらも、デュボアの目は冴えていた。
「デュボア先生、寮のホールを、夕方、貸していただけませんか」
リシャールの言葉に、デュボアは少し眉を上げた。意外そうな表情で、「ほう、それはまた……何に使うつもりだ?」と、興味混じりの声を返す。
俺たちはそれぞれうなずき合い、アルチュールが一歩、前に出た。
「剣の練習をしたいんです」
「それから……練習用の《エクラ・ダシエ》の剣も、お借りできないでしょうか」
リシャールが続けると、デュボアは小さく目を細めた。
「……流石、殿下。耳が早いな」
どこか愉快そうに笑って、椅子の背にもたれかかる。
「放課後の、空いている時間だけで構いません」ナタンがひと言、静かに言った。「ホール内部には、我々で魔法障壁を張ります。破損や音の問題も抑えられると思います」
「ほう。なるほど……ただの遊びではなさそうだな。うん。向上心があることはいいことだ」デュボアはふっと鼻を鳴らした。「今夜からか?」
「はい。出来れば」
アルチュールが言うと、デュボアは軽くうなずき、椅子を軋ませて立ち上がった。
「少々待ってくれ」
背後の棚へ向かい、鍵束が入った木箱を開ける。中から真鍮の鍵を一つ選び出すと、手のひらに転がしながら戻ってきた。
「これがホールの鍵だ。鍵穴にこれを入れて『アペリオセザム』、『カシェセザム』で開閉が出来る」
リシャールに手渡しながら、デュボアはもう片方の手で机の引き出しを開ける。そして、細長い紙片を取り出すと羽根ペンを走らせ、さらさらと何事かを書きつけて、インクが乾かぬうちにそのメモを破ってアルチュールに差し出した。
「装備された練習用の《エクラ・ダシエ》の剣だが……本校舎の南倉庫にある。このメモを――」一瞬だけ言葉を切って、目を細める。「倉庫に続く廊下の手前の管理室にいる“ガルディアン・デコール”の誰かに渡せば、すぐに案内してくれるはずだ」
メモを受け取ったアルチュールが、きちんと折って懐にしまう。
「ありがとうございます。助かります」
「礼を言うのは、何か成果が出てからにしてくれ。あと、使っていいのは二本だけだぞ」
デュボアは手をひらひらと振りながら、それでもどこか楽しげに笑った。
そして、立ち去ろうとする俺たちにもうひと言。
「終わったら、剣はホールに置いて、しっかりと扉に鍵をかけること。そのあと、鍵はこの部屋まで返却しに来るように。俺がいないときは、扉のポストに入れておけ。ホールの使用時間は九時までだ。いいな?」
そのポストは、見た目こそ小さな投函口だが、実は魔法で拡張されたアイテムボックスの一種で、容量は見た目以上に広い。学生たちは課題のレポートや書類を入れて提出するのによく使っている。
「はい。気をつけます」
四人揃って頭を下げると、デュボアは軽く手を振って机に戻っていった。
俺たちは鍵を受け取り、静かに部屋をあとにした。
それから、そう時間はかからなかった。
暫くして、デュボアの部屋の窓の外を長く鋭い影がひとつ、夜気を切り裂くように走った。
四月の夜はまだ肌寒く、塔の石壁には淡い月明かりが薄く滲んでいる。その光の上に、青竹色の鱗が一瞬だけ滑るように映り込み、すぐに消えた。羽音はなく、ただ、閉じた硝子越しに、微かな風のうねりが伝わってきたような気がした。
……あれがジャン・ピエール・カナードの使い魔、風蛇ザイロン。
静かに羽を畳み、寮塔の玄関前、――おそらくは、彼の自室からなるべく近い場所付近に降りたのだろう。
数分後、廊下から軽い足音が響き、扉が二度叩かれた。
「どうぞ」
デュボアの声に応じて入ってきたのは、第二寮『レスポワール』の寮監、ジャン・ピエール・カナード――。
細縁の眼鏡が、室内の灯に一瞬きらりと光る。黒いローブの下、襟元にザイロンがアスコットタイに姿を変えて巻きついていた。
「戻りました」
無駄のない声だった。挨拶すら、細やかに刈り込まれた文章の一節のようだ。
もしも妹のアヤちゃんがここにいたなら、「あの人の爪の垢を煎じて、兄ちゃんに飲ませたいよ」なんて言ったかもしれない。――あの呆れたような笑い声と一緒に。
そんなカナードは後ろ手に戸を閉めると、視線を一度だけゆるやかにこちらへ流した。
そして、その途中、レオの肩にとまっていたネージュを見付けた瞬間、ふっと僅かに眉を上げた。
意外、というよりは、興味深いものを見つけたという反応だったが、静かな眼差しには、冷静な観察者の光が宿っていて、すぐに表情を整えると、何事もなかったかのように微笑みをひとつ浮かべた。
それから、まっすぐデュボアの前へと歩み寄り、ローブの内側からペンダント型のストーン・ホルダーを二つ、静かに取り出す。
「《ノルデュミールの籠》です。これが現段階で最も安定して魔力制御できる構造かと」そう前置きして、カナードは手にした一つを軽く傾けた。「形状は球体を中央で半分に割ったもの。外装は高密度黒鋼。透かし彫りは通気と視認性を兼ねています。内側には振動と熱に対する緩衝魔法を。外側には磁力と結界による多重固定を施しました。開閉には所定の魔力操作が必要です。目立たず、それでいて用途を損なわない。機能と意匠の両立を図ったものとご理解ください。――仕様は以上です。ご確認を」
そう言い添え、カナードは手のひらに並べた二つのペンダントをそのままデュボアに差し出した。
彼の説明は、あまりにも端的で、まるで講義の一節のように、また、こちらの疑問を予測するかのように整えられていて、それでいてどこにも感情の起伏がないのが逆に印象的だった。
デュボアは無言で受け取り、片方を手に取る。
外装に指先を滑らせ、透かし彫りの奥にわずかに覗く空洞を確認すると、留め金の接合部をそっと押して磁力と魔力による固定の具合を丁寧に試した。
「アペリオ」小さく乾いた音を立てて開いた蓋の内側には、緩衝魔法の陣が極めて繊細に刻まれていた。「……問題ないですね。ありがとう。相変わらずお見事。申し分ない仕事だ」
もう一方のペンダントにも目を通し同様の操作を終えると、デュボアは軽く頷き、視線だけでボンシャンに合図を送った。それを受け取ったボンシャンが、箱の中から瓶を取り出す。無色透明なガラスの中に、漆黒の光を宿した球体――奇石ペルル・ノワールがふたつ、静かに沈んでいる。
その瞬間、カナードの瞳が初めて揺れた。
感情というより、正確には「観測」の視線。まるで目の前の現象を理知の奥底で解き明かそうとするような、ごく僅かな間。
だが次の瞬間には、彼の表情はいつも通りの静けさへと戻っていた。
「……これが」
ほんの微かに息を呑む気配。だがそれ以上は何も言わず、再び黙して見守る姿勢に徹している。
デュボアは蓋が開いたペンダントの一つを左手に持ち、右手でボンシャンから奇石を受け取る。奇石は光を吸い込むような漆黒の輝きを放ちながら透かし彫りの奥にゆっくりと収まった。
一瞬、ストーン・ホルダー全体に淡い光が走り、それがぴたりと定まったところで、
「カシェ」
デュボアは留め金を封印するように閉じた。カチ、と小さく音が鳴る。
もう一つの奇石も同様に移し替えられ、二つのノルデュミールの籠が完成した。
デュボアは仕上がったそれらを掌に収めると、くるりと身を転じ、俺の前へと歩み寄って来た。
「ネージュ、コルベール君のところまで飛べますか?」
ボンシャンがやわらかく問いかけると、ネージュは小さく「きゅっ」と鳴いた。
そして、レオの肩を蹴って小さく羽ばたき、ふわりと浮かび上がる。軽やかな弧を描きながら、俺の肩へと降り立った。
「セレスタン・ギレヌ・コルベール、ネージュ、お前たちの奇石だ」
デュボアがそう言って、ペンダントをふたつ、そっと俺の手の中へ乗せた。
伝わる重みと、輝き。
デュボアの言葉に続くように、カナードが一歩前に出て、静かに口を開いた。
「白い君には、まだこのペンダントは大きすぎます。成鳥になり、身に着けられるようになるまでは、コルベール君が預かっていてください」 彼の声音は変わらず淡々としていたが、わずかに目を細めたその表情には、確かに温度があった。「これは、一人と一羽の絆の証です。どうか、大切に――」
言葉の最後は、すっと余韻の中へ溶けていった。
俺は手の中のペンダントを見下ろし、肩に止まったネージュへと視線を移す。小さな翼を揺らしたネージュが、じっとこちらを見返していた。
……ああ、わかってる。
大切にする。必ず。
その後、場の緊張がゆるやかにほどけていき、それぞれが自室へと戻る流れとなった。
俺は改めて、デュボア、ボンシャン、カナードの三人に向き直り、静かに深く一礼をする。
「ありがとうございました」
三人とも穏やかに頷き、あたたかなまなざしを返してくれた。
「礼には及びませんよ」
「協力出来て何よりだ」
ボンシャンとカナードがそう言って、微笑む。その声は穏やかで、なおかつ、芯のある温かさがこもっていた。
デュボアは少し身体を前に傾け、真剣な表情で続けた。
「また何かあったら、すぐに知らせてくれ。俺が不在の時でも、ボンシャン先生かカナード先生のどちらかに頼れば大丈夫だ」
彼の言葉には責任感と信頼がにじみ出ていて、俺の胸にしっかりと響いた。
部屋を出る前、俺は肩にとまっていたネージュをそっと携帯用のゲージに収めて蓋を閉じ、手に提げてから静かにドアをくぐった。
サヴォワール寮の一階廊下を進み、淡い明かりに照らされた階段へと向かう。
二階に着いたところで一度立ち止まり、カゴを持ち直して正面から向き直る。
「レオ。今回は本当に、いろいろと気を配ってくれてありがとう。心から感謝しています」
いきなりかしこまってそう言った俺を見て、レオは少し驚いたように目を瞬かせたが、すぐに柔らかな笑みを浮かべた。そして、どこか照れ隠しのように、軽く眉根のあたりをかきながら口を開く。
「ま、本当は、担当のグラン・フレールとして当然のことだって、そう言うべきなのかもしれないが……、それだけだと、なんだか義務でやってるみたいに聞こえてしまうだろう? ……俺は、セレスにとって『兄』であること以上に、できれば『友人』にもなれたらと思っている。これから、そういうふうに……」言い終える前に、レオは少し恥ずかしそうに視線をそらし、肩をすくめ、言葉を探すように息をついた。「……なんだか、柄にもないことを言ってしまったな」
胸の奥がじんわりと温かくなって、思わず笑みがこぼれる。
「俺も、『友達』って思っていいですか?」
レオは目を細め、口の端をゆるく上げて、穏やかに微笑み頷いた。
「じゃあ――おやすみ、セレス」
「おやすみなさい」
背を向けて去っていくレオの後ろ姿をしばらく見送る。
夜の静寂が胸の奥を優しく撫でるように広がっていく。
その直後。
背後で、ナタンの長い長いため息が静かに漏れた。
「……はあ~~~……」
ふと左右を見やると、リシャールとアルチュールの二人が、揃いも揃って、わずかにうつむいたまま考え込んでいる。片手は額に、もう片方は肘を支えるように添えられ――その姿は、どこか哲学的な苦悩すら滲ませていた。妙に荘厳さを感じる。
……座っていたら、まるでロダンの彫刻だな。
「セレス……、懐に入りすぎだろ……」
「セレス、君はちょっと、天然がすぎる……」
二人の困惑まじりの声が、妙に静けさを帯びて響く。
そんな中、ふとカゴを持つ手に、ブルブルと小さな振動が伝わってきた。
この鳥、今、絶対、両翼の先でくちばしを隠し身を震わせてやがるな……。
カタカタカタカタ……、と小刻みに震えるゲージを手に三階に到着すると、アルチュール、リシャール、ナタンと並んで廊下を進む。
部屋の前で足を止め、それぞれに「おやすみ」と短く言葉を交わした。明日も授業がある。名残惜しくとも、話し込みすぎるわけにはいかない。夜の語らいには限度がある。
扉の前で深呼吸をひとつ。そっとノブを回し、俺は静かに自室の中へと入っていった。
ドアを後ろ手にそっと閉じ、すぐ手に持っていた携帯ゲージを机の上に置く。
留め具を外して蓋を開けると、ネージュは中からフラフラとした足取りで出て来て、そのまま「ちょっと、バスケットをここに持って来てくれ」と言って俺に寝床を運ばせると、「よっこらせ」と両羽で縁を持って乗り越え、中に突っ伏した。
飛べよ……。
「……おい、大丈夫か?」
思わず冷たい視線を向けてそう問うと、くぐもった声が返ってきた。
「……やばい……。今回も尊い。尊い以外の言葉が出て来ない……」
肩をすぼめ、元々小さい身体をもう一回り小さくしながら、ネージュが全身を震わせる。
「は? ……お前、さっきからずっと震えてたよな。カタカタカタカタカタカタカタカタと。俺がどれだけ周囲に気付かれないようゲージを持ってたと思う? お前が具合でも悪いんじゃないかって心配されて、ややこしい空気になるのを避けようと必死だったんだよ……!」
「なあ、セレス。なんだ、あの生き物は。なんで、あんなにも心の琴線を鷲掴みにしてくるんだ? ちょい悪系でありながら、柔らかい笑みと不器用なまでに真剣な眼差し……、ふつくしい。ビジュアル圧が強すぎて、思考が飛ぶ。『兄』である以上に『友人』になりたいなどと……、尊い。尊すぎる。存在が尊い……! 永久保存版だな」
「いや、聞けよ!」
「レオ……、推せる……。推せるというか、もう崇めるレベル……」
「ねえ、聞いて、ネージュさん?」
小刻みに震えながら、ネージュは胸に羽根先を当てて、悶絶している。
「見たろ? 無自覚だぜ、あれ。あの自然体で心に矢を刺してくるレオ・ド・ヴィルヌーヴ、怖ろしい子っ。しかし、正面からあれを受け止めて、あまつさえ『友達って思っていいですか? カッコ、裏声、カッコ閉じる』なんて返したセレス、お前の方もヤバい。なんであんな素直なことさらっと言えるんだ……?」
「いや、そんなこと言われても……、ってか、お前、ちょっと落ち着け。人の言ったことを注釈付き裏声で真似すんな。つーか、とうとう、呼び捨てにしてきたな」
「気にするな」
「しねーけど」
俺は半分呆れながら椅子に腰を下ろし、バスケットの中で打ち震えるネージュを見やる。鳥のくせに情緒が忙しい。
誰に似たんだか。
……俺か……。
「しかし、セレスはアルチュールに傾いてるな……」
「はぁぁぁあ? ち、違ぇし!」
思わず声を上げた俺に、ネージュは片目だけ覗かせて小さく笑った。
「ん? 動揺した」
「してない」
「したな」
「してねぇって!」
「お前ぇさんワンコ系攻めキャラ好きだもんな。しかも、あのルックスだ。見る者の時間を奪う沈黙の美。近づけば壊れてしまうか、あるいは、こちらが壊されてしまうか。そんな危うい魅力が全身の毛穴という毛穴からあふれている」
「なんか、いいこと言いながら、最後は毛穴なんだな」
「間近で見るの、まだ慣れてないだろ? 横に居る時はチラチラチラチラ見てるよな? ……で、時々、お前ぇさんの視線を感じたアルチュールが振り向いて、バチッと目が合って、ちょっとアタフタしてんの。あれがまた……、視線受けぇー振り向く君のーその顔にぃー、動揺の波ー実に良きかなぁー」
「急に詠むな。しかも、なんで朗読調なんだよ」
「いや、これは心の歌……。言葉では収まりきらぬ想いが、五七五七七に姿を変えただけであって……」
「どこの古のオタクだよ。まあ、確かに。毛穴から漏れ出してるなにかが強すぎて、呼吸のリズム崩れるけど。見てるだけで酸素が足りなくなる。推しのすぐそばに居られることは至高の喜びなんだが、たまに視線そらして息継ぎしないと無理。しんどい」
思わず苦笑して首をすくめると、ネージュはふいに少し首を傾げて見せた。
「人、それを恋という」
「だから、違うって言ってるだろう!」
「……そう言い切れるあたり、まだ重症ではないと見える」
「いや、そもそもそういう目で見てねぇって……」
「では、今のところアルチュールもリシャールもナタンもレオも、『特別に気の合う友人』ということで、整理しておいてあげようかね?」
ぐっと羽を伸ばし、バスケットの縁に寄りかかりながらネージュは毛づくろいを始めた。さっきまでの熱狂はどこへやら、あっという間に気ままな調子に戻っている。
窓から差し込む月の光が、白い羽根を銀色に縁取る。
「……話は変わるが。セレス、――さっきのストーン・ホルダーの内部、見たか?」
「ああ。少しだけ」
俺は内ポケットに手を伸ばし、ざくろ色の魔法布に包まれた二つの《ノルデュミールの籠》をそっと取り出すと、デスクの上に並べて置いた。
「アペリオ」
短く呪文を唱えると、カチリと音を立てて蓋が開く。俺は身を乗り出し、中を覗き込んだ。
蓋の裏――そこには、極細の魔力線が蜘蛛の巣のように広がっていた。カナードが描く繊細を極めた魔法陣の編み目は、見る者に静かな威圧感すら与える。
「……これが……、緩衝魔法? 複雑……、どころではないな。もはや、異常の域だ」
「……まったくだ」
思わず呟いた俺の言葉に、ネージュがすぐさま反応した。
彼は、鋭い目を細め、空を仰ぐようにして続けた。
「俺たち鳥の視覚は、人間の数倍――いや、十倍とも言われている。光の波長も幅広く捉えるし、細かな模様や色の違いも、お前ぇさんらよりずっと鮮明に見える」
「そうらしいな」
「そんな目で見ても、これは異常なほど緻密だ。複数の陣が三次元で絡み合い、幾層にも折り重なって、全体でひとつの術式を構成していて単なる図形じゃない。命を持って蠢く構造体みたいだ。線のひとつひとつが迷いなく、淀みなく、正確に引かれている。まるで、生きているみたいなんだ」そこで、ネージュは少し息をのんだ。「これを描いた者は……、まともじゃない。常人の神経で、こんなものを練り上げられるはずがない。けれど、狂気と紙一重の、限界すれすれの知性がなければ、ここまでは届かないだろう。――ジャン・ピエール・カナードは、本当に、魔術の鬼才だ。と、同時に……、この魔法陣は、とんでもなく美しい」
ネージュの目の奥にははっきりとした称賛の色があった。
「美しい?」
「そう。まるで音楽の譜面。旋律を感じる構造。規則と変化の調和」
「……すごいな、そんなふうに見えるのか」
「普通の人間は、訓練しないと目が追いつかない。訓練しても、見えないやつが殆どだろう」ネージュは羽根をわずかに震わせ、バスケットの縁に乗り上げるようにして陣を見下ろした。「これはな、“積み重ね”なんだよ。時間と努力と、勉強と鍛錬。――セレス」
「ん?」
「俺は、卵のときに、デュボアとボンシャンとカナード――三人の寮監たちの魔力の影響をいささか受けている」
――伝書使になるコルネイユの卵ってのは、配られる前、個体の差異が大きく出ないよう、こと細かに性別鑑定に至るまで事前に魔術で均一に管理されている。
レオが言っていたことを思い出す。
「だから三人の使う魔法の“感触”とか、“音色”とか、そういうのが分かるんだが、お前ぇさんみたいに、こっちに来て、光の属性や多大なる加護というチート能力を与えられた特異体質で最初から『できる』人間には、たぶん、こういう積み重ねの末にたどり着く仕事は、逆にキツい……」
「……ああ、うん。ネージュの言うことは分かる。その通りだな……」
「これはさ、きっと何もできなかった頃のカナードが、何年もかけて自分の限界を一つ一つ超えて、やっと辿り着いた精度だと思う」そう言ったネージュの瞳は、真剣だった。「今のお前ぇさんには、どれほど力があろうと、あの三人の誰一人にも敵わない」
「……だろうな」
俺は再びペンダントを見下ろす。そこに収まる漆黒の奇石。
「精進しろよ」
頷いてから、俺は手前のホルダーを手に取った。石が月光を吸い、かすかに光を返す。それを、胸元にそっと着けて下ろし、服の中へと滑り込ませると、しん、と冷たい感触が肌に落ちた。すぐに体温で馴染んで、まるで最初からそこにあったかのように収まる。
「カシェ」
もう一方のホルダーに手を伸ばし、呪文とともに蓋を閉じる。そしてそれを、そっとネージュの前へ差し出した。
ネージュは嬉しそうに羽根をふるわせながら、それを両の羽でそっと抱えバスケットの中へ入れた。まだ身に付けるには、ペンダントは大きすぎる。
「なあ、ネージュ。俺、……頑張らなきゃな」
「推しを救い、友人たちを守るんだろ?」
「ああ」
「俺にも手伝わせてくれ」
「……お前、生まれたてなのに本当にすごいな」
「フッ、まあな。だが――」ネージュは、羽根の先で自分の胸をとんと叩いた。「俺の……、というか、伝書使の基礎を作ったのは、寮監三人によるものだし……、孵化してからは、俺、個人のアイデンティティだ。でもな、俺の大半は、お前ぇさんの記憶と経験で出来ている。そういう意味では、俺の行動や言葉は――お前ぇさんが俺に教えたも同じだ」
俺は息を呑んだ。
ネージュは続ける。
「……誇っていいぞ、セレス。悪くない出来だろ?」
不意に胸の奥が熱くなる。
「……ありがとな。ネージュが俺のところに来てくれたことを心から感謝するよ」
「一晩中、腐談議も出来るしなぁー」
「それは、誇りたくない。授業があるから一晩中は無理。寝たい」
「いや、誇れよ。寝る間も惜しんで腐談議に付き合えよ」
そう言って、ネージュは首をひねりながら、ふっと吐息を漏らすように羽を膨らませた。
その声音には、仲間としての絆と、友としての祈りが、静かに、しかし確かに滲んでいた。
「ところでだな、セレス」
バスケットの中でペンダントを抱えたネージュが、こちらを見て言った。その赤い瞳は、まるでおもちゃを手に入れた子どものようにわくわくと輝いている。
「なんだよ?」
「通信機能があるんだろ? 試してみたい。使ってみないことには、どんな具合かも分からん」
「……授業でやるんじゃないのか? 勝手にやっていいのか?」
「「使うな」とは、言われていない」
得意げにくちばしを鳴らしてそう返してくるネージュに、俺は少しだけ目を細めた。
「……ああ、確かにそれもそうだ。……今なら、距離も近いし、失敗しても大丈夫だな」
「だろ?」
「仕方ないな」
ネージュは嬉しそうに羽根をすぼめて、ちょこんと座り直した。その動きはどこかぎこちなくて、でもその不器用さが、やけに可愛らしい。
「じゃあセレス、ちょっと距離を取ってくれ。そこにいると、声がダダ漏れだ」
「分かった。で、どっちから呼び出す?」
「やっぱり、主、お前ぇさんからで」
「了解」
俺は立ち上がりベッドまでゆっくりと歩いた。マットに腰を下ろし、深呼吸をひとつ。
サリトゥを感じながら掌に意識を集中する。そして、胸元に下げたペンダントをそっと握り、呪文を唱えた。
「……フェルマ・ヴォカ」
その瞬間、ベネンが淡く輝き、細い光の糸が掌からペンダントへと繋がって、やがて目に見えない波となって広がり、消えて行った。
空気がぴんと張り詰める中、声が響く。
「……おっ、こっちの奇石が光った!!」
「ネージュ、レシピオ・ヴォカ、レシピオ・ヴォカ言って」
「おっと、そうだ。レシピオ・ヴォカ!」
直後、ネージュの声が、ノルデュミールの籠に入れられたペルル・ノワールから聞こえて来る。
《そういやぁ、この呪文、既に頭ん中にあったわ。セレスの記憶だな、これは……。えーと、こちらネージュ、聞こえるか?》
どこか緊張を帯びながらも、興奮と期待が入り混じった様子だ。
「ああ、聞こえてる。ばっちりだ、ネージュ。音もすごくクリアだ」
《本当に……? こっちもだ。すげぇ……! 俺の声、ちゃんと届いてるんだなあー》
バスケットの方をちらりと見ると、ネージュが感嘆したようにホルダーに入った石を抱きしめていた。なんだか、彼の喜びが言葉以上に胸に伝わってくる。
「……ああ。まるで……スマホみたいだな」
《おっ、それだっ! それだよセレス! スマホってやつだ! 俺、知ってるぞ、映像とかも送れるやつだろ? あの、ぴっぴってやつ!》
ネージュの声がやけに楽しげで、思わず笑ってしまった。
「ぴっぴって……いやまあ、そんな感じだけどな」
《これ、持ってるだけで文明の利器って感じするわ……。やべぇ……俺、今、一年生の伝書使で最先端だな!》
ぴょこぴょこと羽根を弾ませ、ネージュが言った。
「……あれも、テストしとくか? デュボア先生たちがやってた位置確認」
《あっ、あれな! やろうやろう!》
ノリノリで返ってくる返事に、こちらまで楽しくなる。本気で気に入ったらしい。奇石を手に入れたことが彼にとってどれだけの意味を持っているか、改めて思い知らされる。
「せーの、で行くぞ」
俺は再びペンダントを握り直した。
《よし。せーのっ》
「せーの」
《ローズ・デヴォン》
「ローズ・デヴォン」
一人と一羽の声に呼応するように、ペルル・ノワールがふわりと脈打つ。
直後、目の前の空間に円形の羅針図が浮かび上がった。淡く光る輪郭を持つその図形は、中心から静かに回転しながら周囲を測っていく。まるで、意志を持ったかのようにゆるやかに動き、やがて一点が小さく輝いた。
それは、寮の一室――ネージュの位置を示していた。
《……すげえなこれ。なんか、俺たち本当に“繋がってる”って感じだ……》
「ああ……この奇石、想像以上にすごいな」
ネージュの言葉に、俺も深くうなずいた。
ちなみに、伝書使たちが奇石を使う際には、呪文こそ唱えるが、魔法陣を展開する必要はない。というのも、奇石は彼ら自身の卵の殻から生成されたものであり、自らの起源に由来する素材は魔法回路との親和性がきわめて高い。そのため、余計な媒体を通さずとも、魔力が直接届く。
仕組みについては、『ドメーヌ・ル・ワンジェ王国の薔薇 金の君と黒の騎士』にも記されていた。
そして、先ほどのデュボアと伝書使のノクス、カナードと伝書使のカリュストとのやり取りを見ても、設定はこの世界において、しっかりと踏襲されている。
《なぁセレス、これさえあれば、お前ぇさんが学院に行ってる間も話せるよな?》
「まあな。……ただし、奇石を持ってることはまだ公にできない。それどころか、ネージュが一日で孵化したことも誰かに知られたらマズい」
その言葉を聞いた瞬間、ネージュの羽根がふるりと揺れた。口をへの字に結び、そっとペンダントに視線を落とす。羽根の隙間から覗くその表情は、しょんぼりという言葉そのものだった。
あからさまに落ち込んだ様子が、なんともいじらしい。
「……だからさ。なるべく人目は避けて……、こっそりな。な?」
俺が少しだけ声を和らげて言うと、ネージュはバスケットの中でぱっと顔を上げた。
《こっそり……! そ、それなら……アリだな! よし、作戦名“シークレット通信”、決定!》
しょんぼりしていた表情から一転、ぱたぱたと羽根を弾ませながら、わさわさと動くネージュ。その様子に、思わず口元がほころぶ。
《……ああでも、早く使いたくてうずうずする……!》
ネージュは胸元の石をまた抱きしめていた。
彼はまだ、他の伝書使たちの孵化が始まるまで、しばらくはこの寮の部屋から出られない。だからこそ、こうして通信ができることは、ネージュにとっても大きな意味を持っている。奇石は窓であり、声であり、外と繋がるための小さな翼なのだ。
《セレスが授業を受けている間……、俺、ちゃんと待ってるからな。なるべく騒がずに、大人しくしてる……つもり。でも、窓から見える景色には注目しておくぞ。良い感じの二人連れがいたら、昼休みぐらいを見計らって報告する!》
「……おい」
《もし誰かが、うっかり靴紐がほどけた子にさりげなく結んでやったりしてたら、確実に報告対象だ》
「いや、うちの制服、革靴だから。紐ない」
《……っく、くそぉっ……! 学院内には、“ほどけた靴紐を結んであげる胸板の厚いスパダリ攻め”が存在しないのかっ!?》
ネージュは天を仰ぎ、翼をばっさばっさと動かして悔しがる。声は完全に落ち着いたバリトンボイスなのに、身振りはどこまでも無垢で、なによりも本気で残念そうなのが、妙に可笑しい。
俺は少し笑って、呟く。
「じゃあ……、そろそろ終わりにするぞ、ネージュ」
《おう、仕方ないな。了解。フィネ 》
「じゃあ、フィネ」
その瞬間、淡く光っていた奇石の輝きが、ひとひらの羽根が舞い落ちるように、静かに収まっていった。
通信は、終了した。
けれど、二人の絆は、確かに、そこに在った。
腐男子の絆が――。
༺ ༒ ༻
ネージュが孵化してから十五日が経った昼下がり。
学院の食堂は、いつものように昼食を取る生徒たちの声で賑わっていた。
木漏れ日が差し込む窓際の席に、俺たちはテーブルを挟んで座っている。右斜め前のナタンはパンにバターを塗り、正面のリシャールはスープを一口ごとに吟味しているような表情を浮かべ、右隣のアルチュールはというと、なにやら少しだけ口元に力が入っていた。
「……なあ、相談ってほどじゃないんだが――。ちょっと聞いてくれるか」
その声音はいつになく慎重で、けれど隠しきれない思いが滲んでいる。
俺たちが自然と耳を傾けると、アルチュールはわずかに息を吐いて続けた。
「この学院に来てから、ずっと、まともに身体を動かしてなくて……。授業は想像していた以上に興味深い上に、学ぶことも多いのは理解している。しかし、剣を握る時間が短いと、どうも落ち着かない」そう言ってから、彼は自嘲気味に笑った。「昔から、毎日かかさずやってたんだ。剣を振るのは、俺にとっては、呼吸みたいなものだから」
その一言に、俺は思わず大きく頷いていた。
「……分かる。デュボア先生の剣術の時間だけじゃ、ちょっと物足りないもんな」
気づけば、それは俺自身の実感でもあった。座学も嫌いじゃないが、体を動かすことで整う感覚ってのは、確かにある。
本編でも、アルチュールはちょうどこの頃、学院の生活に慣れ始め、授業の緊張が少しずつほどけてきたタイミングで、こうして自主的に鍛錬を始めていた。
「それならば」バターを塗り終えたナタンが、ふと思いついたように口を開いた。「デュボア先生に頼んで、第一寮の一階ホールを借りられないでしょうか? 先日、カナード先生に教わった簡単な結界で魔法障壁を張って内部を保護しつつ、外に音が漏れないようにすれば、夕食後に鍛錬するにはちょうどいいと思います」少し肩をすくめながら、彼は続ける。「どうせやるなら、この際、四人で集まって交代で手合わせしてみませんか? ひとりで黙々と剣を振るより、刺激になると思いますが。いかがですか、リシャール?」
「殿下と呼べ」
「いーかーがーでーすーか~、りっしゃ~~ルるるる?」
ナタンがわざと巻き舌で語尾を伸ばし呼びかけると、リシャールとアルチュールが思わず吹き出しそうになりながらも、口元に笑みを浮かべた。
その笑みは、曇り空の一瞬の晴れ間のように、二人の端整な顔立ちにふっと柔らかさを増し、まるで磨かれた彫像に温もりの気配が宿ったかのようだった。
――ぬぉぉぉぉおっ! 今の笑い方、ずるいだろ!
無防備に浮かんだアルチュールの笑顔は、普段の無口で不器用な印象を吹き飛ばすくらい自然で、息をのむほど整っていた。本編じゃまずお目にかかれない、『レア・微笑み』だ。尊い!
そしてその隣で微かに笑ったリシャールの横顔ときたら! 金糸の髪が揺れ、まつげの影が頬をかすめる。まるで絵画の中から抜け出した王子様。ふっ、ふつくしい……。
軽く肩を揺らしつつ、アルチュールが頷く。
「室内なら天候にも左右されないし、剣の動きにも集中できそうだ。毎日じゃなくても、時間が合えばぜひ、みんなで……」
ゆったりとスプーンを置いたリシャールが、静かに話に加わる。
「使用する剣道具なんだが――最近、学院には、“特殊な剣”が装備された。まだ通常の授業には取り入れられていないが、以前、王族が視察する魔道軍の剣術試合の場で、それを用いて模擬戦を行うのを見たことがある」
彼の言葉に、アルチュールが目を見開き、ナタンが興味深そうに身を乗り出した。
もちろん、俺は本編を読んでいるので、それの存在を知っていた――そう、模造刀ではあるが、不思議な剣だ。
「“エクラ・ダシエ”――そう呼ばれている剣だ」リシャールは一呼吸置いて、ゆるやかに説明を続けた。「訓練用の模造剣で、形は本物そっくりなんだが、斬撃が人体に触れた瞬間、刃の部分だけが霧のようにふっと消える。だから、怪我をすることはない。斬られた側には痛みはなく軽い衝撃だけが伝わり、斬った側には手応えが残る仕組みになってる。魔法と鍛冶技術の融合で生まれた、高等な訓練用の剣。古代の魔法構造を応用していて、見た目も感触もリアルなのに、決して相手を傷つけないようできている。試合に出ていた者たちは、それを使って見事な技を見せていた」
「エクラ・ダシエ……鋼の閃光、か。理に適ってるな。安全かつ実戦的な訓練ができるとなれば、そりゃ強くなるわけだ」
アルチュールが小さくその名を繰り返すと、ナタンも感心したように頷いた。
「実に格好いい名前ですね。訓練用とはいえ、そういう精巧な道具を使えるなら、本格的に鍛錬する気持ちにもなるというものです。ね、セレスさま」
「そうだな。しかし、王族だけが視察を許されてる魔導軍の試合か。生で観れたら、きっとものすごい迫力なんだろうな……」
俺は思わずそう漏らしながら、リシャールの横顔を見やる。
その視線に気づいたのか、リシャールがわずかに口角を上げて言った。
「今度は、セレスも誘おう。『銀の君』がいると、空気が和らぐ」
ナタンが唐突に、すっと背を正した。
「ありがとうございます。ご配慮、痛み入ります」
「……ナタン、君は誘っていないが?」
そのリシャールの一言に、アルチュールが紅茶のカップを置きながら、穏やかに参戦してきた。
「リシャール、それは少々不公平ではないか。"ぬけがけ"はルール違反だ。セレスを誘うなら、我々にも同じ機会を与えるべきだ」
「必要な人材を勧誘しているだけだ」
リシャールが平然と返すと、アルチュールは少しだけ眉を上げた。
「では、その“必要な人材”というのは、剣術のためか? それとも――心の癒やしのためか?」
一瞬の沈黙。
その間にナタンが満足げにうなずいた。
「まったくもって同感です。セレスさまがいてくださると、場が和みますからね。そもそも侍従として随行するのは当然の……」
「まだ君を連れて行くとは一言も――」
だがナタンは真顔のまま、きっぱりと答えた。
「学院の外であれば、私はセレスさまの侍従です。一緒にうかがうのは当然の義務」
――なにか、「ぬけがけ」とか「ルール違反」いう不穏な単語を耳にしたような気がするけれど……。
俺は少しだけ首をかしげながら、目の前で繰り広げられる静かな攻防を、なんとなく苦笑いしつつ見守った。今日もアルチュールとリシャールの距離は、友人のままで全然縮まらない。進展の兆しなど欠片もなし。もちろん、どこかのタイミングで不意に歯車が噛み合う可能性はあるけど……今はまだ、その時じゃないんだろう。
供給がないなら、待つ。それが、腐の民としてのたしなみだ。
「じゃあ……今度、みんなで行こうな。にぎやかでいいじゃないか」
仕方なく俺がそう言うと、空気がふっと和らいだ気がした。
リシャールは目を伏せて微笑み、アルチュールは肩をすくめながら、「まったく、セレスには敵わないな」と呟く。
ナタンがすぐに、場を仕切り直すように、軽やかに手を振った。
「はいはい。さて、話は戻りますが、具体的な稽古の日時や場所の件、早めに決めておきましょう。今日中にデュボア先生にも相談して、彼の都合も聞いてみませんか?」
「……わかった」
アルチュールがそう返事をして、リシャールも静かに同意した。
「無理なく調整しながら進めよう」
俺は表情だけで賛同を示しながら、その言葉を返した。
そのとき、始業の十分前を告げる予冷のベルが鳴り響いた。
俺たちは顔を見合わせて立ち上がる。それぞれが何かしらの余韻を抱えたような表情だった。特にアルチュールは、どこか高揚したような面持ちで窓の外に目を向けた。
その横顔には、鍛錬のことを思ってか、静かな意欲が宿っている。
それから、こちらへと視線を戻し、彼は短く告げた。
「……行こう。そろそろ始まる」
頷いて、俺たちは教室へと足を向けた。
午後の授業は、淡々と進んだ。
カナードは、迷いなく白墨を手に取る。あえて手で板書するのが彼のやり方だった。黒板には整然とした文字が並び、古代呪文の構文がひとつずつ、簡潔に綴られてゆく。流れるような筆致には、長年積み重ねてきた思考と技術が滲んでいた。
魔法に頼らず、自ら書き記すという一手間に、彼の矜持が宿っている。
線が黒板を滑るその音は、咳払いと混ざりながら、乾いた午後の空気をほんのわずかに震わせていた。
ネージュの言葉を思い出す。
――かつては“何もできなかった”カナードが、積み重ねの末に辿り着いた場所。書くという行為は、今もなお彼にとって、思考と技術を鍛え直すための訓練なのだ。
その手つきに、俺はどこか敬意に近い感情すら覚えていた。リシャールやアルチュールたちの天才的な煌めきとは、また違う光が彼にはある。
俺も、そうありたい――そんなことを、ふと思った。
やがてチャイムが鳴り、授業が終わる。
ざわめきが教室を満たし、椅子の脚が床をこする音が断続的に響いた。誰かの笑い声、誰かの欠伸。外では、風が木の葉を揺らしていた。
生徒たちは思い思いに席を立ち、廊下へと散っていく。
そして、リシャールが静かに立ち上がる。それに続いてアルチュールとナタンも席を離れ、俺もゆっくりと腰を上げた。
まるで決まっていたかのように、自然と足が揃う。
それから、俺たち四人は予定通り、職員寮二階のデュボアの部屋へと向かった――。
回廊を歩きながら、自然と会話が生まれる。
何気ない雑談をしながら、四人で歩く足取りはどこか軽やかだった。
部屋の前に着くと、リシャールが軽くノックした。
三拍ほど間を置いたあと、中からくぐもった声が返ってくる。
「どうぞ、入ってくれたまえ」
扉を開けると、デュボアは窓辺の机に向かって書き物をしていた。分厚い本が何冊も積まれ、その合間には乾きかけたインクと羽根ペン――。
そして、丸テーブルの上には飲み終えたばかりと思われるマグカップがひとつ、無造作に置かれていた。陶器の内側には、濃い茶渋のような跡がわずかに残っている。忙しさの合間に一息ついた痕跡のようだ。部屋の中には、古紙と焙煎豆の混ざったような、落ち着く香りが漂っていた。
「お忙しいところすみません」
リシャールが率先して頭を下げる。俺たちもそれにならった。
「いや、いいんだよ。……どうした? また一風変わった伝書使が孵化したか?」
口元に笑みを浮かべながらも、デュボアの目は冴えていた。
「デュボア先生、寮のホールを、夕方、貸していただけませんか」
リシャールの言葉に、デュボアは少し眉を上げた。意外そうな表情で、「ほう、それはまた……何に使うつもりだ?」と、興味混じりの声を返す。
俺たちはそれぞれうなずき合い、アルチュールが一歩、前に出た。
「剣の練習をしたいんです」
「それから……練習用の《エクラ・ダシエ》の剣も、お借りできないでしょうか」
リシャールが続けると、デュボアは小さく目を細めた。
「……流石、殿下。耳が早いな」
どこか愉快そうに笑って、椅子の背にもたれかかる。
「放課後の、空いている時間だけで構いません」ナタンがひと言、静かに言った。「ホール内部には、我々で魔法障壁を張ります。破損や音の問題も抑えられると思います」
「ほう。なるほど……ただの遊びではなさそうだな。うん。向上心があることはいいことだ」デュボアはふっと鼻を鳴らした。「今夜からか?」
「はい。出来れば」
アルチュールが言うと、デュボアは軽くうなずき、椅子を軋ませて立ち上がった。
「少々待ってくれ」
背後の棚へ向かい、鍵束が入った木箱を開ける。中から真鍮の鍵を一つ選び出すと、手のひらに転がしながら戻ってきた。
「これがホールの鍵だ。鍵穴にこれを入れて『アペリオセザム』、『カシェセザム』で開閉が出来る」
リシャールに手渡しながら、デュボアはもう片方の手で机の引き出しを開ける。そして、細長い紙片を取り出すと羽根ペンを走らせ、さらさらと何事かを書きつけて、インクが乾かぬうちにそのメモを破ってアルチュールに差し出した。
「装備された練習用の《エクラ・ダシエ》の剣だが……本校舎の南倉庫にある。このメモを――」一瞬だけ言葉を切って、目を細める。「倉庫に続く廊下の手前の管理室にいる“ガルディアン・デコール”の誰かに渡せば、すぐに案内してくれるはずだ」
メモを受け取ったアルチュールが、きちんと折って懐にしまう。
「ありがとうございます。助かります」
「礼を言うのは、何か成果が出てからにしてくれ。あと、使っていいのは二本だけだぞ」
デュボアは手をひらひらと振りながら、それでもどこか楽しげに笑った。
そして、立ち去ろうとする俺たちにもうひと言。
「終わったら、剣はホールに置いて、しっかりと扉に鍵をかけること。そのあと、鍵はこの部屋まで返却しに来るように。俺がいないときは、扉のポストに入れておけ。ホールの使用時間は九時までだ。いいな?」
そのポストは、見た目こそ小さな投函口だが、実は魔法で拡張されたアイテムボックスの一種で、容量は見た目以上に広い。学生たちは課題のレポートや書類を入れて提出するのによく使っている。
「はい。気をつけます」
四人揃って頭を下げると、デュボアは軽く手を振って机に戻っていった。
俺たちは鍵を受け取り、静かに部屋をあとにした。
83
あなたにおすすめの小説

虚ろな檻と翡翠の魔石
篠雨
BL
「本来の寿命まで、悪役の身体に入ってやり過ごしてよ」
不慮の事故で死んだ僕は、いい加減な神様の身勝手な都合により、異世界の悪役・レリルの器へ転生させられてしまう。
待っていたのは、一生を塔で過ごし、魔力を搾取され続ける孤独な日々。だが、僕を管理する強面の辺境伯・ヨハンが運んでくる薪や食事、そして不器用な優しさが、凍てついた僕の心を次第に溶かしていく。
しかし、穏やかな時間は長くは続かない。魔力を捧げるたびに脳内に流れ込む本物のレリルの記憶と領地を襲う未曾有の魔物の群れ。
「僕が、この場所と彼を守る方法はこれしかない」
記憶に翻弄され頭は混乱する中、魔石化するという残酷な決断を下そうとするが――。
-----------------------------------------
0時,6時,12時,18時に2話ずつ更新

悪役令嬢の兄に転生!破滅フラグ回避でスローライフを目指すはずが、氷の騎士に溺愛されてます
水凪しおん
BL
三十代半ばの平凡な会社員だった俺は、ある日、乙女ゲーム『君と紡ぐ光の協奏曲』の世界に転生した。
しかも、最推しの悪役令嬢リリアナの兄、アシェルとして。
このままでは妹は断罪され、一家は没落、俺は処刑される運命だ。
そんな未来は絶対に回避しなくてはならない。
俺の夢は、穏やかなスローライフを送ること。ゲームの知識を駆使して妹を心優しい少女に育て上げ、次々と破滅フラグをへし折っていく。
順調に進むスローライフ計画だったが、関わると面倒な攻略対象、「氷の騎士」サイラスになぜか興味を持たれてしまった。
家庭菜園にまで現れる彼に困惑する俺。
だがそれはやがて、国を揺るがす陰謀と、甘く激しい恋の始まりを告げる序曲に過ぎなかった――。
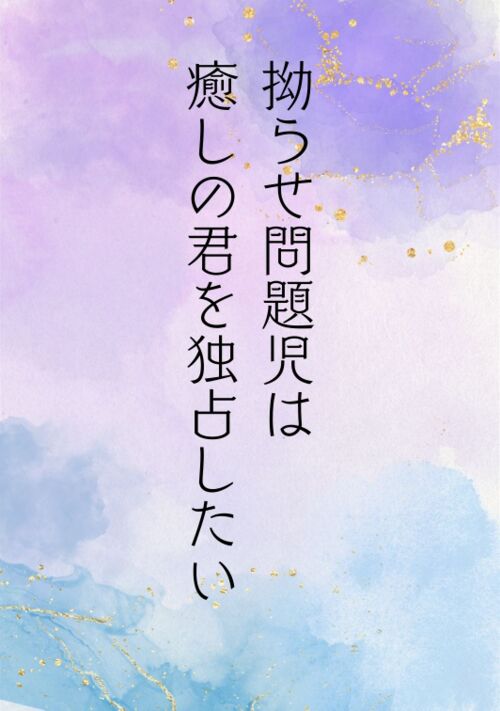
拗らせ問題児は癒しの君を独占したい
結衣可
BL
前世で限界社畜として心をすり減らした青年は、異世界の貧乏子爵家三男・セナとして転生する。王立貴族学院に奨学生として通う彼は、座学で首席の成績を持ちながらも、目立つことを徹底的に避けて生きていた。期待されることは、壊れる前触れだと知っているからだ。
一方、公爵家次男のアレクシスは、魔法も剣術も学年トップの才能を持ちながら、「何も期待されていない」立場に嫌気がさし、問題児として学院で浮いた存在になっていた。
補習課題のペアとして出会った二人。
セナはアレクシスを特別視せず、恐れも媚びも見せない。その静かな態度と、美しい瞳に、アレクシスは強く惹かれていく。放課後を共に過ごすうち、アレクシスはセナを守りたいと思い始める。
身分差と噂、そしてセナが隠す“癒やしの光魔法”。
期待されることを恐れるセナと、期待されないことに傷つくアレクシスは、すれ違いながらも互いを唯一の居場所として見つけていく。
これは、静かに生きたい少年と、選ばれたかった少年が出会った物語。

悪役キャラに転生したので破滅ルートを死ぬ気で回避しようと思っていたのに、何故か勇者に攻略されそうです
菫城 珪
BL
サッカーの練習試合中、雷に打たれて目が覚めたら人気ゲームに出て来る破滅確約悪役ノアの子供時代になっていた…!
苦労して生きてきた勇者に散々嫌がらせをし、魔王軍の手先となって家族を手に掛け、最後は醜い怪物に変えられ退治されるという最悪の未来だけは絶対回避したい。
付き纏う不安と闘い、いずれ魔王と対峙する為に研鑽に励みつつも同級生である勇者アーサーとは距離を置いてをなるべく避ける日々……だった筈なのになんかどんどん距離が近くなってきてない!?
そんな感じのいずれ勇者となる少年と悪役になる筈だった少年によるBLです。
のんびり連載していきますのでよろしくお願いします!
※小説家になろう、アルファポリス、カクヨムエブリスタ各サイトに掲載中です。

異世界で孵化したので全力で推しを守ります
のぶしげ
BL
ある日、聞いていたシチュエーションCDの世界に転生してしまった主人公。推しの幼少期に出会い、魔王化へのルートを回避して健やかな成長をサポートしよう!と奮闘していく異世界転生BL 執着最強×人外美人BL

すべて、お姉様のせいです
シエル
ファンタジー
私の姉は聖女だ。
我が家はごく普通の男爵家で、特に貧乏でも裕福でもない
まったく特筆すべきことがない家である。
そんな我が家の長女であるアイラが、王立貴族学院へ
入学したことで『特別』になった。
お花畑ヒロインの家族もお花畑なの?
そんなヒロイン体質の姉をもつ、セイカの苦労と涙の物語。
※ 中世ヨーロッパがモデルの架空の世界です。
※ ご都合主義なので、ご了承ください。

悪役令息を改めたら皆の様子がおかしいです?
* ゆるゆ
BL
王太子から伴侶(予定)契約を破棄された瞬間、前世の記憶がよみがえって、悪役令息だと気づいたよ! しかし気づいたのが終了した後な件について。
悪役令息で断罪なんて絶対だめだ! 泣いちゃう!
せっかく前世を思い出したんだから、これからは心を入れ替えて、真面目にがんばっていこう! と思ったんだけど……あれ? 皆やさしい? 主人公はあっちだよー?
ユィリと皆の動画をつくりました!
インスタ @yuruyu0 絵も動画もあがります。ほぼ毎日更新!
Youtube @BL小説動画 アカウントがなくても、どなたでもご覧になれます。動画を作ったときに更新!
プロフのWebサイトから、両方に飛べるので、もしよかったら!
名前が * ゆるゆ になりましたー!
中身はいっしょなので(笑)これからもどうぞよろしくお願い致しますー!
ご感想欄 、うれしくてすぐ承認を押してしまい(笑)ネタバレ 配慮できないので、ご覧になる時は、お気をつけください!

ヒロインに婚約破棄された悪役令息
久乃り
BL
ギンデル侯爵子息マルティンは、ウィンステン侯爵令嬢アンテレーゼとの婚約を破棄されて、廃嫡された。ようするに破滅エンドである。
男なのに乙女ゲームの世界に転生したことに気が付いたとき、自分がヒロインに意地悪をしたという理由だけで婚約破棄からの廃嫡平民落ちされ、破滅エンドを迎える悪役令息だと知った。これが悪役令嬢なら、破滅エンドを避けるためにヒロインと仲良くなるか、徹底的にヒロインと関わらないか。本編が始まる前に攻略対象者たちを自分の懐に入れてしまうかして、破滅エンド回避をしたことだろう。だがしかし、困ったことにマルティンは学園編にしか出てこない、当て馬役の悪役令息だったのだ。マルティンがいなくなることでヒロインは自由となり、第2章の社交界編で攻略対象者たちと出会い新たな恋を産むのである。
破滅エンド回避ができないと知ったマルティンは、異世界転生と言ったら冒険者でしょ。ということで、侯爵家の権力を利用して鍛えに鍛えまくり、ついでに侯爵子息として手に入れたお小遣いでチートな装備を用意した。そうして破滅エンドを迎えた途端に国王の前を脱兎のごとく逃げ出して、下町まで走り抜け、冒険者登録をしたのであった。
ソロの冒険者として活動をするマルティンの前になぜだか現れだした攻略対象者たち。特にフィルナンドは伯爵子息であるにも関わらず、なぜだかマルティンに告白してきた。それどころか、マルティンに近づく女を追い払う。さらには攻略対象者たちが冒険者マルティンに指名依頼をしてきたからさあ大変。
方やヒロインであるアンテレーゼは重大なことに気がついた。最短で逆ハールートを攻略するのに重要な攻略対象者フィルナンドが不在なことに。そう、アンテレーゼもマルティンと同じく転生者だったのだ。
慌ててフィルナンドのいる薬師ギルドに押しかけてきたアンテレーゼであったが、マルティン大好きフィルナンドに追い返されてしまう。しかも世間ではマルティンが聖女だと言う噂が飛び交い始めた。
聖女になることが逆ハールートの必須条件なのに、何故男であるマルティンが聖女だと言う噂が流れたのか。不審に思ったアンテレーゼは、今度は教会に乗り込んで行った。
そして教会で、アンテレーゼはとんでもない事実を目の当たりにした。そう、本当にマルティンの周りに攻略対象者たちが群がっていたのだ。しかも、彼らは全員アンテレーゼを敵視してきたのだ。
こんなの乙女ゲームじゃないじゃない!と憤慨するアンテレーゼを置いてきぼりにして、見事マルティンはハーレムエンドを手に入れるのであった。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















