5 / 112
5話~奇石(きせき)の生成~
しおりを挟む
~奇石の生成~
その日、授業と夕食を終えたあと、俺とネージュ、そしてレオは、再び『サヴォワール寮』の寮監、ヴィクター・デュボアの部屋の扉を叩いていた。
尚、リシャール、アルチュール、ナタンがちゃっかり同行しているのは言うまでもない。
「ネージュを連れてるから」、「目立ちたくない」、「これは内密事項」って、あれだけ言ったのに、聞きゃあしねぇよ。
結局、ここに来るまでの道中、センター俺、左右にリシャールとアルチュール、背後にナタン、その隣で携帯ゲージに入ったネージュを抱えたレオ――という五人+一羽のパーティーで、また妙に目立つ行列ができあがっていた。
一人増えてるし……。
元々この世界、というかこの学院、BL小説が原作なだけあってモブに至るまで顔面偏差値が異様に高い。しかし、その中でも俺の周囲はさらに別格だ。
中身はちょっと残念なナタンですら、見た目だけなら英雄譚の主役級、黙って立っていれば、まるで神話から抜け出してきたような造形。
学院の生徒全員が黒毛和牛だとするなら、その中でも最高級のA5ランクだけを選りすぐって盛りつけました~、みたいなチーム編成。
まるで、美術館の特別展にでも迷い込んだかのような光景。
まさに「なんとか教授の総回診」の完成。
余りに緊張し過ぎて奇石生成の前にラップのリリック作成しちまったじゃねえか。
ルネサンス絵画か、貴族肖像画か、どこから見ても見ても完璧な配置と調和がそこにある。品評会ですか? それとも次の王族御用達カレンダーの撮影現場? みたいな? そりゃあ、目を引かないはずがない。
ていうか、前回ですらかなり注目されてたのに、これ以上は本当に勘弁してほしい。
少しの間を置いてデュボアに「入れ」と促され、俺たちは順に中へと足を踏み入れた。
昨夜も見た壁際の小さな丸テーブルが、まず視界に飛び込んでくる。その上には、深い緑色の箱が荘厳な雰囲気をまとって鎮座していた。そして、ソファには悠然と腰を下ろす一人の男――『ソルスティス寮』寮監、ルシアン・ボンシャン。
長い灰色の髪を後ろで一つに束ね、一見、穏やかな微笑みを浮かべる好人物……、だが、その奥底に潜む圧倒的な魔力の気配が、肌を撫でていく。
その横に立つデュボアがこちらに視線を流し、ちらりとリシャール、アルチュール、ナタンの三人に目をやったかと思うと、少しだけ眉をひそめた。
「……コルベール? 随分と人数が多いようだが?」
「デュボア先生、俺は止めたんですけどね。聞かないんですよ、誰も」
肩を竦めながら答えると、ソファに座るボンシャンが片眉を上げ、どこか困ったような顔をしていた。
ちらりと横目をやると、リシャール殿下は悪びれた様子もなく微笑み、アルチュールとナタンは完全にどこ吹く風といった風情。ああ、もう。しかし、こいつらの我の強さには慣れてくるから困る。
デュボアがひとつため息をつき、黒い瞳を細めた。
「君たち三人は、前回の件にも関わっている。……立って見ている分には構わん。ただし、今回も決して口外はしないこと。いいな」
その声は冷たくも突き放すようでもなかった。
完全に追い返すつもりはないらしい。別に王子がいるからという特別扱いでもなく、どうやら単に事情を知る者としての扱いらしい。
重々しい釘刺しに三人が頷くと、ボンシャンが柔らかく微笑んで立ち上がり、静かに口を開いた。
「ようこそ、坊やたち。今夜は、セレスタン・ギレヌ・コルベール君の奇石作りに立ち会わせてもらいますよ。私の役目は、魔力の安定供給の補助と、生成用のガラス瓶の保護」そう言って軽く息を吐くと、視線をリシャールたちへと向け直す。「――コルベール君のグラン・フレールであるレオ・ド・ヴィルヌーヴ君はともかく、ワンジェ君、シルエット君、トレモイユ君。あなたたちの参加には少々首を傾げますが……。まぁ、これもまた“必然の関係”ということなのでしょう。それに、近いうちにあなたたちも奇石作りを控えているのですから、この機会にしっかりと見学なさい」
穏やかではあるが、底に芯のある声だった。
リシャールは、目つきにわずかな決意を宿し軽く頷き、アルチュールとナタンは、緊張を帯びた表情で、「はい」と小さく返事をした。
「さて――緊張しなくて大丈夫です、コルベール君。では、卵殻を用意してください」
「はい」
俺は内ポケットから、しっかりと布に包んで保管していたネージュの卵殻を取り出した。破片も全て揃っている。落とし物と無くし物の常習犯である俺が、散った小さな破片まで必死になって拾い集めた。
「ヴィルヌーヴ君、ゲージの扉を開けて。コルベール君の伝書使にも、ちゃんと見てもらいたいから」
奇石の生成において、伝書使が直接何かをするわけではない。
生成される奇石は、主とその伝書使を繋ぐ専用の魔術通信器であり、魔力を通じて一対一の繋がりが形成され、互いの居場所を感知し、緊急時には即座に連絡を取ることができる魔道具。
その生成を、主と共に伝書使が見届けることが、今後の魔力の共鳴に不可欠とされている。
レオはゆっくりと頷くと、手に持っていた携帯ゲージの扉を静かに開けて言った。
「おいで。セレスがお前に贈る儀式だ」
その穏やかな声に応えるように、ネージュはふわりと羽ばたいてゲージを出ると、レオの肩へと舞い降りた。小さな爪でバランスよく止まりながら、赤い瞳で周囲を見渡している。
その様子を見て、ボンシャンがわずかに目を細めた。
「……聞いてはいましたが、本当に白いのですね」
表情に驚きの気配はない。だが、僅かに見開かれた双眸が、その内心を雄弁に物語っていた。しかし、ボンシャンは、それ以上の感情を見せることなく、再びいつもの落ち着いた微笑を浮かべて俺を見て言った。
「コルベール君。この小さな伝書使は、思っていた以上に特別な存在のようですね。ええ、これは確かに、慎重に見守る必要がありそうです。――それでは、はじめましょうか。奇石の生成儀式を。『絆』をつなぐ魔術です」
緊張で指先が少し震えた。
ボンシャンの言葉とともに、デュボアが丸テーブル上の箱に向け、片手をゆるやかに差し出す。そして、低く短く呟いた。
「アペリオ」
その呪文に呼応するように、深緑の箱がひとりでにカチリと音を立てて開く。姿を現したのは、淡く光る小瓶がひとつ。それと、下に敷かれた煌びやかな文様が印象的な柘榴色の布敷きが一枚。これは、魔力の流れを安定させるための、精緻な術式が織り込まれた特製の魔法布だ。
「コルベール、手の中の卵殻に魔力を込めてみろ」デュボアが低く静かな声で俺に言った。「呪文は、『ヴィータ・リグナム』。命と絆を紡ぐ、古代語の一節。これは、そこの伝書使に名を与えたお前にしかできない」
俺は低く、小さく、言葉を紡ぐ。
「……ヴィータ・リグナム」
すると、ベネンが布越しに淡く光った。直後、呼応するかのようにふわりと浮かび上がった卵殻の破片が、まるで命を吹き込まれたかのように、ひとつ、またひとつと瓶の中へと吸い込まれていく。
「コルベール君、魔力が強い。弱めて! 瓶が割れてしまいます!」
ボンシャンが両掌を小瓶に向け、ガラスの強度を上げながら宙を流れる俺の魔力を整えてくれている。
種類の異なる魔法を同時に操れる魔術師は、この王国でもごく僅か。十本の指で数えられるほどしか存在せず、その中でも実戦で使いこなせるレベルとなると、ほんの一握りだ。
その様子を見ていたリシャールたちも、わずかに表情を引き締めた。
箱の中で白い光が渦を巻き、淡い羽のような輝きが舞い上がる。
静寂の中で、カランと小さく音が鳴った。
「……成功だ」
ネージュを肩に乗せたレオが少しだけ口元を緩めて言った。
「やったな、セレス!」
「凄いな、セレスは」
「流石、セレスさま」
三人が小声で嬉しそうに盛り上がっているのを、デュボアとボンシャンが静かに見守っている。
「これが、俺とネージュを繋ぐ奇石……」
呟くようにそう言いながら、瓶の中をじっと見つめる。底できらりと輝くふたつの小さな珠――。どちらもまるで夜空を閉じ込めたかのような深い黒。
「これは……」
思わず声を漏らすと、すぐさまボンシャンが一歩前に進み、瓶をそっと覗き込んだ。
「――ペルル……?」
彼の微笑は静かに消え、代わりに目元に真剣な色が差す。
「まさか、本当に……」
デュボアが低く呟いたその瞬間、部屋の空気が一段階、冷たく張り詰めたように感じられた。
「何百年ぶり……、でしょう。いや、それすら確かなものではなかった。伝承の中にしか存在しないはず――」ボンシャンが瓶をそっと手に取り、じっと見つめた。「奇石は、その持ち主の命と深く結びついています。主が命を落とすと、奇石もまた役目を終えたかのように砕け散り、跡形もなく消える。まるで、魂の残響すらこの世に留めぬように――石自らがそう望んでいるかのように。だからこそ、遺されることはない。なので、見るのは私もはじめてです……。ペルル・ノワール、『死境の珠』とも呼ばれる特異な奇石。現世と冥界の境界に干渉する力を持つ……。死を越え、再びこの世に舞い戻った魂のしるし。……この珠を身につけた伝書使は、冥界にも行くことができると、古い記録にはあります」
ボンシャンが僅かに息を呑んだように見えた。
――なんで?
なにそれ聞いてない。
……いや、ほんとに聞いてない。
『ドメーヌ・ル・ワンジェ王国の薔薇 金の君と黒の騎士』は、何度も読み返した。けど――「ペルル・ノワール」なんて単語、一度だって出てきた覚えがない……!
それ、ドレッドヘアでやたらとアイラインが似合う色気だだ漏れラム酒大好きな某海賊船の船長の黒い愛艇の名前じゃなかったか?
テンパったまま視線を泳がせると、リシャールもアルチュールもナタンも、三人そろって神妙な面持ちで俺を見守っていた。レオまでが冗談めいた笑みなど微塵も浮かべることなく、その真剣さがかえって胃に来る――。
「黒は、冥界そのものの色。生成者の魂が死の淵の境界に触れ、戻って来た――。でなければ、決して手にできない。いや、生み出せない」ボンシャンの言葉を継いだデュボアの声音もまた、重く低い。「その中でも伝書使の卵殻に主となる魔術師のサリトゥから魔力を分け与えられ、生成された『ペルル・ノワール』は、自然界に存在するものとは本質を異にする。最も特異な『奇石』のひとつだと言っていい。セレスタン・ギレヌ・コルベール……。お前は事故で頭を打ったと聞いている。詳細は分からないが、もしかして、生死の境を越えた経験を持ったのではないか?」
一瞬、心臓が跳ねた。
明確に言い当てられたわけではない。
デュボアもボンシャンも、誰一人として俺が『転生者』だという真実を知らない。知っているのは、ネージュだけ。
あの日、トラックが自宅に突っ込んできた瞬間、甲高いブレーキ音が悲鳴のように響き渡り、耳をつんざく衝突音と共に、俺の魂は何かを突き破った。生と死の境目――その曖昧で、暗く、得体の知れない境界を越えて、気付けば俺はこの異世界にいた。
だけどそれを、誰かに説明できるかといえば……、まず無理だろう。現実味なんてひとかけらもない。何より、自分ですらまだ、その出来事の全容を理解しきれていないのだから。
「セレスさまは、事故のあとに、一度、死亡診断を受けていらっしゃいます」
そう口にしたのは、事情を知る存在、――ナタン。
場の空気が凍りついた。誰もが息を呑み、沈黙が落ちる。
「そう……、らしいです。俺自身は記憶にありませんが……」
口をついて出たのは、『死の向こう側から来た者』であることを曖昧に隠すための都合のいい言葉だった。
それを聞いたアルチュールが、ゆっくりと視線を落とし、静かに言葉を落とす。
「……そうだったのか。セレスが無事で良かった」
上辺の気遣いや、形式的な労りではなかった。その声音には、心からの安堵が混ざっていた。
リシャールが、驚きを隠しきれないまま、目を見開いて言った。
「……そんなことが……」
レオも眉をひそめ、小さく頷いた。
「無事でよかった……。本当に」
言葉少なにそう漏らす声には、二人の率直な感情がにじんでいた。
「しかし……、こんな小さなネージュが、将来、冥界を飛べるようになるんですか?」
俺の問いに、ボンシャンはゆっくりと頷いた。
「ええ。ただし、冥界は、本来、生者が足を踏み入れるべき場所ではありません。伝書使もです。しかし、伝書使の卵殻から生成されたペルル・ノワールには、それを可能にする通路の性質があるなどと伝わっています」ボンシャンがわずかに目を細める。「私たちは、ただ生成に立ち会っただけにすぎません。君と、その白いコルネイユが成し遂げたこの成果は、記録として残すべきでしょう。だが同時に……、君たちを守らねばなりません」
デュボアが無言で頷いた。
ペルル・ノワールがどれほど危うく、貴重な力を持つものか……。そのことを、彼らは理解している。
ボンシャンが続けた。
「未知が多すぎます。……冥界への通路が、いつ、どこへ、どうしたら現れるのか、我々にも断言はできません。……ですからもしもの時、君と伝書使を守る意味でも、まずはその奇石の力を使用者の管理下に置くべきです」
「使用者の管理下に置くとは?」
俺は意味を確かめるように尋ねた。
「――ペンダント型のストーン・ホルダー、『ノルデュミールの籠』に入れるというのは?」
思案の末に、デュボアが提案した。
この世界における『ノルデュミールの籠』とは、本来は、特に脆い奇石や、構造の不安定な魔力結晶を保護する目的で用いられる比較的汎用性の高い魔道具。
衝撃や魔力の揺らぎから対象を隔離し、内部に一定の魔力環境を維持するための特殊な結界処理が施されている。
用途に応じて形状・大きさともに多様であり、小型のペンダント型から腰掛け可能な壺型、さらには据え置き式の大型仕様に至るまで、その加工および調整の自由度が高い点も特徴とされる。
「良い案です、デュボア先生。このペルル・ノワールに対しては、ノルデュミールの籠は本来の用途とは真逆……、破損を防ぐためではなく、力を制限し、秘匿し、暴走を抑えるために使う」
「しかし、一般的なホルダーでは駄目でしょう。特別な魔法を施す必要がある。封印も、結界も、全てにおいて最上級の処置が必須」
「……通信と位置特定以外の力が、持ち主の意思に反して勝手に発動しないように」
「ならば、カナード先生の出番――」デュボアが静かに呟いた。「こんなことなら、はじめから呼んでおけば良かったな」
ジャン・ピエール・カナード――。第二寮『レスポワール』の寮監。結界術と封印魔法の第一人者であり、特に制御系魔法の緻密さと精度は学内随一。その魔法構築は、王都の防衛術式にも採用されている。
「白い伝書使が誕生したという件は、今朝、既に報告済みなんですが……」
そう言ったボンシャンが、苦笑めいた息を吐いた。
「カナード先生は、ロクノール森林の外縁にある『第一研究塔の砦』付近で、綻びの見えた魔力防壁の補修作業に午後から出向いている。ここには俺の判断で呼ばなかった。ボンシャン先生がいるなら万全だと、カナード先生自身も言ってくれていたからな」
「すぐに呼び戻しましょう」
「お願いします」
俺がそう言うと、ボンシャンとデュボアは短く頷き、二人がほぼ同時に胸元へ手を伸ばし、奇石のネックレスを取り出した。
「ここは俺が――」そう言ったデュボアのベネンが、確かな意志を宿すように淡く光る。「フェルマ・ヴォカ」
呪文を唱えると、直ぐに反応が返って来た。
《おうヴィクター、何か用か? 俺の出番か?》
軽快な声は、デュボアの伝書使、ノクス。
「ノクス、ジャンの伝書使は、どこに?」
《カナードの? カリュストならここに居るぞ?》
デュボアは小さく息を吐く。
「ローズ・デヴォン」
その言葉とともに、彼が手に持っていた奇石が、ベネンと共鳴するように淡い光を放った。そして、細い光線が空中に走り、座標を定めるための小さな複数の同心円と幾何線が浮かび上がる――羅針図だ。
円周には古代文字。中心には十字の紋様――。その中に、赤い光点が脈打っている。
「ノクス、お前、今、時計塔の小屋だな?」
《そうだ。カリュストは、さっきからずっと窓際で一羽、『知将の盤』を指している。相手もいねぇのにな。何が楽しいんだか》
ノクスは呆れたように言った。精密な戦術盤の駒を、黙々と動かすだけの孤独な遊戯。彼にはその面白さがさっぱり理解できなかったのだ。
《で、何かあったのか?》
デュボアはわずかに頷き、短く答えた。
「急ぎだ。カリュストをこちらに回してくれ」
《ローズ・デヴォン――ヴィクター、お前は職員寮だな。自室か?》
「そうだ。頼む」
《了解》
「フィネ」
通話が切れ、羅針図が静かに消滅していく。静寂の中に、わずかな緊張感だけが残った。
༺ ༒ ༻
ほどなくして、窓の外から羽ばたきの音が聞こえた。
デュボアが掌を掲げ、魔力の流れを解き放つ。
「アペリオ」
呪文に応じて、窓の錠前が外れ、静かに開く。風が流れ込み、夜の香りと共に、二羽の伝書使が舞い降りてきた。
「待たせたな。ちゃんと連れて来たぞ」
窓枠にとまり、そう口にしたのは、ヴィクター・デュボアの伝書使――ノクス。黒い体躯に青みがかった光沢のある羽根を持つ。首元には、厚手の革で仕立てられた重厚なネックギアが巻かれていて、深い焦げ茶色のそれは、単なる装飾品ではなく、細工された銀の金具と鎖が絡むように配置され、中央に燃えるように赤い奇石がはめ込まれていた。
「ノクス、お前も来たのか」
デュボアがそう言うと、ノクスは軽く羽ばたいて目の前のデスクへ移動した。
「お前が「急ぎ」と口にしただろう? 通信から漂う気配も妙だった。丁度、退屈していたところだ。興味をかきたてられたんだよ」
どこかふてぶてしいその言い草に、デュボアが静かにため息をつく。
「……本当にお前というやつは。自由すぎる」
続けて窓枠にとまったもう一羽の姿に、室内の空気が少しだけ変わった。
ジャン・ピエール・カナードの伝書使――カリュスト。
オニキスのような漆黒の羽根。瞳は鋭く、片目には一風変わった片眼鏡が嵌められている。
それは金属と革で精巧に組まれた極小の工学装置であり、眼窩に合わせて特注された湾曲フレームが、黒く艶のある羽毛にぴたりと寄り添っていた。頭部をぐるりと巻く細い革バンドによって、風を受けても微動だにしない。幅広のつるの部分には、精緻な刻印と装飾があり、深い緑色の奇石と大小の歯車が幾つか埋め込まれ、視線の動きに合わせ、カチリ……、と小さな音を立ててわずかに焦点を調整していた。
「……あの伝書使が、カナード先生の……」ナタンが低く呟いた。「以前から噂を耳にしてはいましたが、直接、見るのは初めてです。実に個性的ですね」
「ああ……」
短くそう応えたアルチュールの声には、わずかに緊張が滲んでいた。何の情報もなく、初見でこの測れない威圧感を帯びたコルネイユを前にすれば、誰だって息をのむ。
尚、俺は会ったことはなかったが、知っているから、驚きはない。寧ろ、厨二病をくすぐる彼の見た目を、二次元ではなく、生で拝見出来たことに、今、深く感動している。……感動しているのだが、周囲が俺とネージュの為に動いてくれているこの場面で、テンションをひとり爆上げしている自分が少しばかり申し訳なくもあり、罪悪感的なモノが、胸の片隅にチクリと刺さった。ほんと、ゴメン。
ナタンの横で、リシャールが一歩前へと出た。
「久しぶりだな、ノクス、カリュストも」
冷静かつ簡潔なその言葉に、カリュストが、片翼を胸に当て深々と頭を垂れる。
「王子殿下。入学、誠におめでとうございます。新たな学びの地に、実り多き時があらんことを」
その仕草は、まるで廷臣のように洗練されていて、風格を帯びていた。
ノクスが羽をふわりと揺らし、にやりと笑うような声色で返す。
「おや、リシャール殿下。入学したんだってな? そりゃまた、おめでとう」
カリュストが一礼を終えるのとほぼ同時に、ノクスの顔がふとレオの肩のあたりに向いた。
「……ん?」黒いクチバシがピクリと動き、瞳が細まる。その背で、わずかに羽が逆立った。「おい、カリュスト。あれ、見えるか……?」
カチリ、と音を立てながら、静かなカリュストの視線がネージュへと向けられる。
「これは、珍しい……」
ネージュが、二羽をじっと見返す。無言のまま、しかし深い関心を宿した赤い眼差しで。
そして――ノクスが叫んだ。
「ヴィクター! 何で教えてくれなかったんだよ!? あれ、伝書使だろ!? お前、どれだけ面白いことを隠してんだ!? 俺たち、仲間だよな?」
デュボアは溜息をついた。
「現在、あの白いコルネイユに関して知る者は、ここに居る顔ぶれと、ジャン、あとは教職員でも上層部のみ。お前たちは、口が軽い。嬉々として学寮中に吹聴しそうだからな」
「ぐ……、そ、それは否定できねぇ……」
ノクスはしゅんと肩をすくめるように項垂れた。
「心外ですね。私は吹聴したりしませんよ」
静かにそう言ったカリュストに、今まで沈黙していたボンシャンが、穏やかな声で言葉を添えた。
「分かっていますよ、君が軽率な真似をしないことも、責任ある判断をすることも。私たちは、よく理解していますし信頼もしています」その一言に、カリュストの片眼鏡が微かに光を反射した。「しかし――」ボンシャンは、慎重に言葉を選ぶように続けた。「あなた達の立場上、特定の個体だけにこのような情報を流せば、他との不均衡が生じます。だからこそ、私は自分の伝書使にも伝えていないのです。今回の件に関しては、必要最低限の者だけが知るべきことでした」
それは配慮と配分の問題であり、偏りを避けるための措置。ボンシャンの瞳は真っ直ぐだった。
「……了解しました」カリュストは深く首肯する。「慎重なご判断、納得いたしました」
その姿はまるで、軍の高官に応じる副官のように、整然としていて静謐だった。
……すごいな、これがジャン・ピエール・カナード寮監の相棒か。
言葉遣い、礼節、振る舞い、姿勢。どれを取っても隙がない。あまりの完成度に、思わず舌を巻く。やはり、真面目な人の伝書使は、格が違う。
俺は、ちらりと、レオの肩に乗っているネージュを見た。
小さな彼の初めて発した言葉、「――うっ……、ん゛ん゛ん゛尊い……」、その一言である。
二次元に溺れ、日々、腐界で魂を昇天させていた俺が、うっかり召喚してしまった心の同類。
……うん、似たんだな、やっぱり、主に……。ってやつか。
遠い目をしながら、改めて窓辺を見やる。
「ところで、デュボア先生、ボンシャン先生、……いかなるご用件で、私がここに呼ばれたのでしょう?」
カリュストが、細く滑らかな声で言葉を発した。
まっすぐに立つその姿は、気負いも媚びもなく、ただ知るべき義務を果たすかのようだ。
その問いに、すぐさま応じたのはボンシャンだった。
「先に、こちらから確認させてください。君の主――ジャン・ピエール・カナード先生は、今どこにいらっしゃるのでしょう?」
「ジャンは、既に帰寮の途にあります」
カリュストは落ち着いた口調で応じた。
「それは好都合です」ボンシャンは頷き、視線をデュボアに向けた。「デュボア先生、ここはコルベール君の担当であるあなたから説明を」
「了解」
そう言って、デュボアは箱から取り出した瓶を掌に乗せ、二羽に見せた。
「……これは?」
カリュストの瞳が鋭く細まる。ノクスもその隣で身を乗り出すようにして瓶の中身を見つめている。
「『ペルル・ノワール』」デュボアは静かに言った。「先ほど、生成されたばかりの『奇石』だ」
「奇石!?」
二羽が同時に叫んだ。
ノクスが、珍しく息を飲むような声音で続ける。
「おいおい……まさか……、これ、そこの白いのの卵殻から……?」
ネージュが、わずかに胸を張り、羽を揺らす。
「ああ。そして、これを創り出したのは、そこに居るセレスタン・ギレヌ・コルベールだ」
デュボアの言葉に、ノクスとカリュストが一斉にこちらを見た。
その視線の圧を受けながら、俺――セレスタンは軽く手を挙げる。
ノクスが「へええ……」と声を漏らした。
──サロンや王宮の催しでは、護衛魔術騎士団に所属する伝書使たちの姿を目にすることは多々あるが、魔法学院教官付きの伝書使と、こうして真正面から向き合うことなど、王族でもない限り流石のコルベール家の者であっても日常では滅多にない。
魔法学院は機密事項に溢れた閉鎖空間だ。
要するに、俺たちにとっては、これが初めての対面ということになる。
一方、カリュストはペルル・ノワールへ視線を戻すと、凝視したまま静かに口を開いた。
「確かに、ジャンに報告すべき事案ですね。急ぎ、本人を呼び出しましょう」そう言って片眼鏡の奥で瞳を細め、首を一度振ると、ゆっくりと呪文を紡いだ。「フェルマ・ヴォカ、ジャン・ピエール・カナード宛て――ローズ・デヴォン。拡張呼出し、緊急」
その声に応じるように、彼の片眼鏡にはめ込まれた奇石が淡く脈打つ。そして、空中に羅針図が展開された。中心の紋様が細かく回転し、位置情報が更新されていく。
そして――、
《……どうした、カリュスト? もう直ぐそちらに着くところだが》
穏やかだが芯のある声。ジャン・ピエール・カナード本人からの応答だった。
「お疲れ様です。寮塔に到着後、至急、第一寮監室までお越しください。報告すべき案件が発生しました。……セレスタン・ギレヌ・コルベール氏による、奇石ペルル・ノワールの生成です」
《……何だと?》
カナードの声の底に、静かな驚愕と鋭い関心が滲んだ。と、同時に、通信に混じる一定の速度で流れていく外気を切る音――。
カナードの使い魔は風蛇で名前はザイロン。青竹色の鱗を持ち、目元を斜めに走る一条の紅い縁取りと、胴体の両脇にはコウモリを思わせる皮膜の羽を備えた異形の蛇だ。
怒れば鱗が音を立てて逆立ち、威圧的な気配を纏う。普段は、彼の喉元に巻かれたアスコットタイ――彼の装いの象徴でもあるそれ――に巧妙に擬態しているが、ひとたびその身を顕せば、主を背に乗せて風を裂き、羽音を立てずに空を駆ける。
今、まさにカナードはそのザイロンの背に騎乗し、上空を滑空しながら通信を行っている。声に混じる風の唸りが、その事実を物語っていた。
「詳細はのちほどお話いたします。すでにデュボア寮監、ボンシャン寮監、リシャール王子以下、関係者が揃っています」
《了解した。すぐに向かう》
カナードがそう応じ、カリュストが通信を切ろうとしたその瞬間、ボンシャンが静かに口を開いた。
「カナード先生――ひとつ、お願いがあります。デュボア先生の部屋へ来る前に、あなたの自室に立ち寄って頂いて、小型のペンダント型『ノルデュミールの籠』を二つお持ちください」
《……なるほど。封印処理の必要があるということですね》
「はい。宜しくお願い致します」
《承知いたしました。――カリュスト、じゃあ、またあとで》
「無事のご帰還、お待ちしています。では。フィネ」
その言葉と共に通信が途絶え、羅針図がふわりと霧散した。
カリュストが一礼し、再び口を開いた。声には、静かな熱意が宿っていた。
「……ノクスと私にとっても、新しい仲間に関する事態です。もはやオブザーバーではいられません。ジャンの到着後、改めて状況を――」
「待ってください、カリュスト」
ボンシャンが軽く右手を挙げて遮った。その目元には、いつもの穏やかな笑みがたたえられていたが、声にはごくわずかに硬さが混じっていた。
「今後の処理については、あくまで学院内の機密として扱います。関係者の数は、必要最小限に絞るべきでしょう。……申し訳ありませんが、今は一度、時計塔へ戻ってください」
その言葉に、ノクスがあからさまに頬を膨らませる。カリュストもわずかに口を引き結んだが、やがて短く頷いた。
「……まさか、帰れと仰るとは思いませんでした」
「ただし――お願いがあります」
ボンシャンはカリュストのほうへ半歩近づき、声をほんの少しだけ低めた。
「あなた方には、この件に関して私の伝書使、オレリアンへ報告を。今、このような状況で、私は彼とは直接連絡を取る時間がありません。そして、寮監付きのあなた方が知ってしまったことを、同じく寮監付きなのに彼だけが知らないとなると……」
ノクスは羽根を一度ぱさりと揺らすと、肩をすくめるような動作をして言った。
「あ~……分かる。分かるわぁ……。やっかいなんだよなぁ、あいつ。あ、あいつって言っちまった。先輩なんだけどな、まあいいか。普段は、滅茶苦茶ニコニコしてて、声も柔らかくて、誰にでも優しくてさ。ちょっとくらいの失敗なら「気にしないでください」なんて笑って流してくれるし、もう神様か何かかと思うじゃねぇか? ……いや、思ってたよ、こっちは。最初はね。でも、怒ると……、いや、「怒る」っていうのとも違うんだよなぁ。オレリアンは、声荒げたりしないし。むしろ、静かになる。静かに、淡々と話し始めるんだよ。それで、一言目から、もうブッ刺さる。抑揚もなく、優しげな口調のまんまで、「それって、つまりこういうことですよね?」とか、「うーん、ちょっとした誤解かな、とは思ったんですけど」って、こっちが一番見られたくなかったとこに、ぐっさりくる。えぐるようにじゃなくて、針でちくっと刺すみたいに。いや、ちくっとじゃないな。じわじわ効いてくる毒針、だな。あとで効くやつ。しかもね、全部こっちの逃げ道、先に潰してくるんだよ。気付いたときには、言い訳の余地どころか、立ってる場所すら無くなってる。言葉にトゲはないのに、「あ、やばい……」って思ったときにはもう遅いんだ。「ごめんなさい」って言う前から、すでに何万字もの反省文書き終わってる気分になる。何が怖いって、こっちはただ詰められてるだけじゃなくて、「理解されてる」って実感があるんだなぁ、これまた。しかも、良くない意味で。あの感じ……、翼竜に睨まれたコルネイユ? みたいな? そんな気持ちになるんだ。完全にフリーズだよ。動いたら食われる。ほんの一言で胃に穴開くし、気がついたら背中の羽が汗びっしょりだ。「なんでこんなに静かなのに怖いんだ……?」って頭抱えたくなる。下手に逆らったら、マジで空飛ぶ気にならん。一週間は巣から出られない。っていうか、自分の巣の場所すら見失う。そんなレベル。あれ食らった日にゃあ、もう夜空見上げて自己反省タイム突入だよ……。凹んじまって、浮上出来ない」
肩の羽根を窄めて延々と語るその姿は、どこか本気で怖がっているように見えた。その横で、カリュストも無言のまま小さくうんうんと頷いている。
それを聞いていたボンシャンが、ふと微笑みを深めた。
「……まるで、私のことを言っているみたいですね?」
その一言に、場の空気がピリッと張り詰めた。
ノクスが瞬時に羽根をぶるっと震わせ、目を見開く。
「ち、ちがうぞ!? いや、似てるけど! でも、お宅のオレリアンはもっとこう、こう……、あー……、うー……!」
言い訳にならない言い訳を必死で並べながらノクスがそろりそろりとカリュストの背に隠れると、カリュストは息を呑んでから、「……ノクス、お前がそれほど慌てるのを、初めて見たかもしれない」と言って、堪えきれずに小さく吹き出した。
と、同時に、ボンシャンが静かに笑いながらも、ほんの少しだけ目を細める。
「でも、カリュスト。今、うんうんと随分と真剣に頷いていましたね?」
カリュストが、僅かに肩を震わせて素早く顔を逸らした。
「それと、背後のデュボア先生」ボンシャンは軽く視線を流し、さらに一言、さりげなく付け加える。「あなたも、ずっと静かに頷いておられましたね?」
「えっ?」と短く息を呑んだのは、ヴィクター・デュボアだった。
集まる一同の視線に、落ち着こうとしているのか片手で胸を軽く叩きながら「あー、うー……」と誤魔化して笑うその姿が、どう見ても陽だまりのゴリラそのもので、喉の奥までせり上がってくる笑いを俺はなんとかして飲み込んだ。
「しかし、面白いですね。全く。うちの子と私と、どこまで通じているのやら。どうか、伝言をよろしくお願いしますよ。彼が拗ねたら、私でも対応に困りますから」
「はいっ! 任せてください」
真剣な顔でそう言って頷くカリュストの隣で、ノクスもようやく落ち着きを取り戻し、小さくくちばしを鳴らした。
「……んじゃあ、とっとと伝えてくるよ。怒られない範囲で……」そう言いつつ羽根をばさりと広げたノクスだったが、その表情にはどこかしら悟りと諦めが混じっていた。「ま、どう言い繕っても、『呼ばれたのはカリュスト君だけなんですよね?』、『何故、ノクス君が一緒に行ったんでしょう?』、『ならば、どうして私も誘わなかったんですか?』って詰められるのは確定なんだけどな……。あーあ、胃が痛ぇ……」
ノクスがそう言うと、二羽は息を合わせるように一礼し、窓際へと歩み出た。
「では、我々はひとまずこれで失礼します。……また後ほど、報告をお待ちしています」
カリュストとノクスが軽やかに飛び立つと、室内には、少しの名残惜しさが滲む静けさだけが残された。
その日、授業と夕食を終えたあと、俺とネージュ、そしてレオは、再び『サヴォワール寮』の寮監、ヴィクター・デュボアの部屋の扉を叩いていた。
尚、リシャール、アルチュール、ナタンがちゃっかり同行しているのは言うまでもない。
「ネージュを連れてるから」、「目立ちたくない」、「これは内密事項」って、あれだけ言ったのに、聞きゃあしねぇよ。
結局、ここに来るまでの道中、センター俺、左右にリシャールとアルチュール、背後にナタン、その隣で携帯ゲージに入ったネージュを抱えたレオ――という五人+一羽のパーティーで、また妙に目立つ行列ができあがっていた。
一人増えてるし……。
元々この世界、というかこの学院、BL小説が原作なだけあってモブに至るまで顔面偏差値が異様に高い。しかし、その中でも俺の周囲はさらに別格だ。
中身はちょっと残念なナタンですら、見た目だけなら英雄譚の主役級、黙って立っていれば、まるで神話から抜け出してきたような造形。
学院の生徒全員が黒毛和牛だとするなら、その中でも最高級のA5ランクだけを選りすぐって盛りつけました~、みたいなチーム編成。
まるで、美術館の特別展にでも迷い込んだかのような光景。
まさに「なんとか教授の総回診」の完成。
余りに緊張し過ぎて奇石生成の前にラップのリリック作成しちまったじゃねえか。
ルネサンス絵画か、貴族肖像画か、どこから見ても見ても完璧な配置と調和がそこにある。品評会ですか? それとも次の王族御用達カレンダーの撮影現場? みたいな? そりゃあ、目を引かないはずがない。
ていうか、前回ですらかなり注目されてたのに、これ以上は本当に勘弁してほしい。
少しの間を置いてデュボアに「入れ」と促され、俺たちは順に中へと足を踏み入れた。
昨夜も見た壁際の小さな丸テーブルが、まず視界に飛び込んでくる。その上には、深い緑色の箱が荘厳な雰囲気をまとって鎮座していた。そして、ソファには悠然と腰を下ろす一人の男――『ソルスティス寮』寮監、ルシアン・ボンシャン。
長い灰色の髪を後ろで一つに束ね、一見、穏やかな微笑みを浮かべる好人物……、だが、その奥底に潜む圧倒的な魔力の気配が、肌を撫でていく。
その横に立つデュボアがこちらに視線を流し、ちらりとリシャール、アルチュール、ナタンの三人に目をやったかと思うと、少しだけ眉をひそめた。
「……コルベール? 随分と人数が多いようだが?」
「デュボア先生、俺は止めたんですけどね。聞かないんですよ、誰も」
肩を竦めながら答えると、ソファに座るボンシャンが片眉を上げ、どこか困ったような顔をしていた。
ちらりと横目をやると、リシャール殿下は悪びれた様子もなく微笑み、アルチュールとナタンは完全にどこ吹く風といった風情。ああ、もう。しかし、こいつらの我の強さには慣れてくるから困る。
デュボアがひとつため息をつき、黒い瞳を細めた。
「君たち三人は、前回の件にも関わっている。……立って見ている分には構わん。ただし、今回も決して口外はしないこと。いいな」
その声は冷たくも突き放すようでもなかった。
完全に追い返すつもりはないらしい。別に王子がいるからという特別扱いでもなく、どうやら単に事情を知る者としての扱いらしい。
重々しい釘刺しに三人が頷くと、ボンシャンが柔らかく微笑んで立ち上がり、静かに口を開いた。
「ようこそ、坊やたち。今夜は、セレスタン・ギレヌ・コルベール君の奇石作りに立ち会わせてもらいますよ。私の役目は、魔力の安定供給の補助と、生成用のガラス瓶の保護」そう言って軽く息を吐くと、視線をリシャールたちへと向け直す。「――コルベール君のグラン・フレールであるレオ・ド・ヴィルヌーヴ君はともかく、ワンジェ君、シルエット君、トレモイユ君。あなたたちの参加には少々首を傾げますが……。まぁ、これもまた“必然の関係”ということなのでしょう。それに、近いうちにあなたたちも奇石作りを控えているのですから、この機会にしっかりと見学なさい」
穏やかではあるが、底に芯のある声だった。
リシャールは、目つきにわずかな決意を宿し軽く頷き、アルチュールとナタンは、緊張を帯びた表情で、「はい」と小さく返事をした。
「さて――緊張しなくて大丈夫です、コルベール君。では、卵殻を用意してください」
「はい」
俺は内ポケットから、しっかりと布に包んで保管していたネージュの卵殻を取り出した。破片も全て揃っている。落とし物と無くし物の常習犯である俺が、散った小さな破片まで必死になって拾い集めた。
「ヴィルヌーヴ君、ゲージの扉を開けて。コルベール君の伝書使にも、ちゃんと見てもらいたいから」
奇石の生成において、伝書使が直接何かをするわけではない。
生成される奇石は、主とその伝書使を繋ぐ専用の魔術通信器であり、魔力を通じて一対一の繋がりが形成され、互いの居場所を感知し、緊急時には即座に連絡を取ることができる魔道具。
その生成を、主と共に伝書使が見届けることが、今後の魔力の共鳴に不可欠とされている。
レオはゆっくりと頷くと、手に持っていた携帯ゲージの扉を静かに開けて言った。
「おいで。セレスがお前に贈る儀式だ」
その穏やかな声に応えるように、ネージュはふわりと羽ばたいてゲージを出ると、レオの肩へと舞い降りた。小さな爪でバランスよく止まりながら、赤い瞳で周囲を見渡している。
その様子を見て、ボンシャンがわずかに目を細めた。
「……聞いてはいましたが、本当に白いのですね」
表情に驚きの気配はない。だが、僅かに見開かれた双眸が、その内心を雄弁に物語っていた。しかし、ボンシャンは、それ以上の感情を見せることなく、再びいつもの落ち着いた微笑を浮かべて俺を見て言った。
「コルベール君。この小さな伝書使は、思っていた以上に特別な存在のようですね。ええ、これは確かに、慎重に見守る必要がありそうです。――それでは、はじめましょうか。奇石の生成儀式を。『絆』をつなぐ魔術です」
緊張で指先が少し震えた。
ボンシャンの言葉とともに、デュボアが丸テーブル上の箱に向け、片手をゆるやかに差し出す。そして、低く短く呟いた。
「アペリオ」
その呪文に呼応するように、深緑の箱がひとりでにカチリと音を立てて開く。姿を現したのは、淡く光る小瓶がひとつ。それと、下に敷かれた煌びやかな文様が印象的な柘榴色の布敷きが一枚。これは、魔力の流れを安定させるための、精緻な術式が織り込まれた特製の魔法布だ。
「コルベール、手の中の卵殻に魔力を込めてみろ」デュボアが低く静かな声で俺に言った。「呪文は、『ヴィータ・リグナム』。命と絆を紡ぐ、古代語の一節。これは、そこの伝書使に名を与えたお前にしかできない」
俺は低く、小さく、言葉を紡ぐ。
「……ヴィータ・リグナム」
すると、ベネンが布越しに淡く光った。直後、呼応するかのようにふわりと浮かび上がった卵殻の破片が、まるで命を吹き込まれたかのように、ひとつ、またひとつと瓶の中へと吸い込まれていく。
「コルベール君、魔力が強い。弱めて! 瓶が割れてしまいます!」
ボンシャンが両掌を小瓶に向け、ガラスの強度を上げながら宙を流れる俺の魔力を整えてくれている。
種類の異なる魔法を同時に操れる魔術師は、この王国でもごく僅か。十本の指で数えられるほどしか存在せず、その中でも実戦で使いこなせるレベルとなると、ほんの一握りだ。
その様子を見ていたリシャールたちも、わずかに表情を引き締めた。
箱の中で白い光が渦を巻き、淡い羽のような輝きが舞い上がる。
静寂の中で、カランと小さく音が鳴った。
「……成功だ」
ネージュを肩に乗せたレオが少しだけ口元を緩めて言った。
「やったな、セレス!」
「凄いな、セレスは」
「流石、セレスさま」
三人が小声で嬉しそうに盛り上がっているのを、デュボアとボンシャンが静かに見守っている。
「これが、俺とネージュを繋ぐ奇石……」
呟くようにそう言いながら、瓶の中をじっと見つめる。底できらりと輝くふたつの小さな珠――。どちらもまるで夜空を閉じ込めたかのような深い黒。
「これは……」
思わず声を漏らすと、すぐさまボンシャンが一歩前に進み、瓶をそっと覗き込んだ。
「――ペルル……?」
彼の微笑は静かに消え、代わりに目元に真剣な色が差す。
「まさか、本当に……」
デュボアが低く呟いたその瞬間、部屋の空気が一段階、冷たく張り詰めたように感じられた。
「何百年ぶり……、でしょう。いや、それすら確かなものではなかった。伝承の中にしか存在しないはず――」ボンシャンが瓶をそっと手に取り、じっと見つめた。「奇石は、その持ち主の命と深く結びついています。主が命を落とすと、奇石もまた役目を終えたかのように砕け散り、跡形もなく消える。まるで、魂の残響すらこの世に留めぬように――石自らがそう望んでいるかのように。だからこそ、遺されることはない。なので、見るのは私もはじめてです……。ペルル・ノワール、『死境の珠』とも呼ばれる特異な奇石。現世と冥界の境界に干渉する力を持つ……。死を越え、再びこの世に舞い戻った魂のしるし。……この珠を身につけた伝書使は、冥界にも行くことができると、古い記録にはあります」
ボンシャンが僅かに息を呑んだように見えた。
――なんで?
なにそれ聞いてない。
……いや、ほんとに聞いてない。
『ドメーヌ・ル・ワンジェ王国の薔薇 金の君と黒の騎士』は、何度も読み返した。けど――「ペルル・ノワール」なんて単語、一度だって出てきた覚えがない……!
それ、ドレッドヘアでやたらとアイラインが似合う色気だだ漏れラム酒大好きな某海賊船の船長の黒い愛艇の名前じゃなかったか?
テンパったまま視線を泳がせると、リシャールもアルチュールもナタンも、三人そろって神妙な面持ちで俺を見守っていた。レオまでが冗談めいた笑みなど微塵も浮かべることなく、その真剣さがかえって胃に来る――。
「黒は、冥界そのものの色。生成者の魂が死の淵の境界に触れ、戻って来た――。でなければ、決して手にできない。いや、生み出せない」ボンシャンの言葉を継いだデュボアの声音もまた、重く低い。「その中でも伝書使の卵殻に主となる魔術師のサリトゥから魔力を分け与えられ、生成された『ペルル・ノワール』は、自然界に存在するものとは本質を異にする。最も特異な『奇石』のひとつだと言っていい。セレスタン・ギレヌ・コルベール……。お前は事故で頭を打ったと聞いている。詳細は分からないが、もしかして、生死の境を越えた経験を持ったのではないか?」
一瞬、心臓が跳ねた。
明確に言い当てられたわけではない。
デュボアもボンシャンも、誰一人として俺が『転生者』だという真実を知らない。知っているのは、ネージュだけ。
あの日、トラックが自宅に突っ込んできた瞬間、甲高いブレーキ音が悲鳴のように響き渡り、耳をつんざく衝突音と共に、俺の魂は何かを突き破った。生と死の境目――その曖昧で、暗く、得体の知れない境界を越えて、気付けば俺はこの異世界にいた。
だけどそれを、誰かに説明できるかといえば……、まず無理だろう。現実味なんてひとかけらもない。何より、自分ですらまだ、その出来事の全容を理解しきれていないのだから。
「セレスさまは、事故のあとに、一度、死亡診断を受けていらっしゃいます」
そう口にしたのは、事情を知る存在、――ナタン。
場の空気が凍りついた。誰もが息を呑み、沈黙が落ちる。
「そう……、らしいです。俺自身は記憶にありませんが……」
口をついて出たのは、『死の向こう側から来た者』であることを曖昧に隠すための都合のいい言葉だった。
それを聞いたアルチュールが、ゆっくりと視線を落とし、静かに言葉を落とす。
「……そうだったのか。セレスが無事で良かった」
上辺の気遣いや、形式的な労りではなかった。その声音には、心からの安堵が混ざっていた。
リシャールが、驚きを隠しきれないまま、目を見開いて言った。
「……そんなことが……」
レオも眉をひそめ、小さく頷いた。
「無事でよかった……。本当に」
言葉少なにそう漏らす声には、二人の率直な感情がにじんでいた。
「しかし……、こんな小さなネージュが、将来、冥界を飛べるようになるんですか?」
俺の問いに、ボンシャンはゆっくりと頷いた。
「ええ。ただし、冥界は、本来、生者が足を踏み入れるべき場所ではありません。伝書使もです。しかし、伝書使の卵殻から生成されたペルル・ノワールには、それを可能にする通路の性質があるなどと伝わっています」ボンシャンがわずかに目を細める。「私たちは、ただ生成に立ち会っただけにすぎません。君と、その白いコルネイユが成し遂げたこの成果は、記録として残すべきでしょう。だが同時に……、君たちを守らねばなりません」
デュボアが無言で頷いた。
ペルル・ノワールがどれほど危うく、貴重な力を持つものか……。そのことを、彼らは理解している。
ボンシャンが続けた。
「未知が多すぎます。……冥界への通路が、いつ、どこへ、どうしたら現れるのか、我々にも断言はできません。……ですからもしもの時、君と伝書使を守る意味でも、まずはその奇石の力を使用者の管理下に置くべきです」
「使用者の管理下に置くとは?」
俺は意味を確かめるように尋ねた。
「――ペンダント型のストーン・ホルダー、『ノルデュミールの籠』に入れるというのは?」
思案の末に、デュボアが提案した。
この世界における『ノルデュミールの籠』とは、本来は、特に脆い奇石や、構造の不安定な魔力結晶を保護する目的で用いられる比較的汎用性の高い魔道具。
衝撃や魔力の揺らぎから対象を隔離し、内部に一定の魔力環境を維持するための特殊な結界処理が施されている。
用途に応じて形状・大きさともに多様であり、小型のペンダント型から腰掛け可能な壺型、さらには据え置き式の大型仕様に至るまで、その加工および調整の自由度が高い点も特徴とされる。
「良い案です、デュボア先生。このペルル・ノワールに対しては、ノルデュミールの籠は本来の用途とは真逆……、破損を防ぐためではなく、力を制限し、秘匿し、暴走を抑えるために使う」
「しかし、一般的なホルダーでは駄目でしょう。特別な魔法を施す必要がある。封印も、結界も、全てにおいて最上級の処置が必須」
「……通信と位置特定以外の力が、持ち主の意思に反して勝手に発動しないように」
「ならば、カナード先生の出番――」デュボアが静かに呟いた。「こんなことなら、はじめから呼んでおけば良かったな」
ジャン・ピエール・カナード――。第二寮『レスポワール』の寮監。結界術と封印魔法の第一人者であり、特に制御系魔法の緻密さと精度は学内随一。その魔法構築は、王都の防衛術式にも採用されている。
「白い伝書使が誕生したという件は、今朝、既に報告済みなんですが……」
そう言ったボンシャンが、苦笑めいた息を吐いた。
「カナード先生は、ロクノール森林の外縁にある『第一研究塔の砦』付近で、綻びの見えた魔力防壁の補修作業に午後から出向いている。ここには俺の判断で呼ばなかった。ボンシャン先生がいるなら万全だと、カナード先生自身も言ってくれていたからな」
「すぐに呼び戻しましょう」
「お願いします」
俺がそう言うと、ボンシャンとデュボアは短く頷き、二人がほぼ同時に胸元へ手を伸ばし、奇石のネックレスを取り出した。
「ここは俺が――」そう言ったデュボアのベネンが、確かな意志を宿すように淡く光る。「フェルマ・ヴォカ」
呪文を唱えると、直ぐに反応が返って来た。
《おうヴィクター、何か用か? 俺の出番か?》
軽快な声は、デュボアの伝書使、ノクス。
「ノクス、ジャンの伝書使は、どこに?」
《カナードの? カリュストならここに居るぞ?》
デュボアは小さく息を吐く。
「ローズ・デヴォン」
その言葉とともに、彼が手に持っていた奇石が、ベネンと共鳴するように淡い光を放った。そして、細い光線が空中に走り、座標を定めるための小さな複数の同心円と幾何線が浮かび上がる――羅針図だ。
円周には古代文字。中心には十字の紋様――。その中に、赤い光点が脈打っている。
「ノクス、お前、今、時計塔の小屋だな?」
《そうだ。カリュストは、さっきからずっと窓際で一羽、『知将の盤』を指している。相手もいねぇのにな。何が楽しいんだか》
ノクスは呆れたように言った。精密な戦術盤の駒を、黙々と動かすだけの孤独な遊戯。彼にはその面白さがさっぱり理解できなかったのだ。
《で、何かあったのか?》
デュボアはわずかに頷き、短く答えた。
「急ぎだ。カリュストをこちらに回してくれ」
《ローズ・デヴォン――ヴィクター、お前は職員寮だな。自室か?》
「そうだ。頼む」
《了解》
「フィネ」
通話が切れ、羅針図が静かに消滅していく。静寂の中に、わずかな緊張感だけが残った。
༺ ༒ ༻
ほどなくして、窓の外から羽ばたきの音が聞こえた。
デュボアが掌を掲げ、魔力の流れを解き放つ。
「アペリオ」
呪文に応じて、窓の錠前が外れ、静かに開く。風が流れ込み、夜の香りと共に、二羽の伝書使が舞い降りてきた。
「待たせたな。ちゃんと連れて来たぞ」
窓枠にとまり、そう口にしたのは、ヴィクター・デュボアの伝書使――ノクス。黒い体躯に青みがかった光沢のある羽根を持つ。首元には、厚手の革で仕立てられた重厚なネックギアが巻かれていて、深い焦げ茶色のそれは、単なる装飾品ではなく、細工された銀の金具と鎖が絡むように配置され、中央に燃えるように赤い奇石がはめ込まれていた。
「ノクス、お前も来たのか」
デュボアがそう言うと、ノクスは軽く羽ばたいて目の前のデスクへ移動した。
「お前が「急ぎ」と口にしただろう? 通信から漂う気配も妙だった。丁度、退屈していたところだ。興味をかきたてられたんだよ」
どこかふてぶてしいその言い草に、デュボアが静かにため息をつく。
「……本当にお前というやつは。自由すぎる」
続けて窓枠にとまったもう一羽の姿に、室内の空気が少しだけ変わった。
ジャン・ピエール・カナードの伝書使――カリュスト。
オニキスのような漆黒の羽根。瞳は鋭く、片目には一風変わった片眼鏡が嵌められている。
それは金属と革で精巧に組まれた極小の工学装置であり、眼窩に合わせて特注された湾曲フレームが、黒く艶のある羽毛にぴたりと寄り添っていた。頭部をぐるりと巻く細い革バンドによって、風を受けても微動だにしない。幅広のつるの部分には、精緻な刻印と装飾があり、深い緑色の奇石と大小の歯車が幾つか埋め込まれ、視線の動きに合わせ、カチリ……、と小さな音を立ててわずかに焦点を調整していた。
「……あの伝書使が、カナード先生の……」ナタンが低く呟いた。「以前から噂を耳にしてはいましたが、直接、見るのは初めてです。実に個性的ですね」
「ああ……」
短くそう応えたアルチュールの声には、わずかに緊張が滲んでいた。何の情報もなく、初見でこの測れない威圧感を帯びたコルネイユを前にすれば、誰だって息をのむ。
尚、俺は会ったことはなかったが、知っているから、驚きはない。寧ろ、厨二病をくすぐる彼の見た目を、二次元ではなく、生で拝見出来たことに、今、深く感動している。……感動しているのだが、周囲が俺とネージュの為に動いてくれているこの場面で、テンションをひとり爆上げしている自分が少しばかり申し訳なくもあり、罪悪感的なモノが、胸の片隅にチクリと刺さった。ほんと、ゴメン。
ナタンの横で、リシャールが一歩前へと出た。
「久しぶりだな、ノクス、カリュストも」
冷静かつ簡潔なその言葉に、カリュストが、片翼を胸に当て深々と頭を垂れる。
「王子殿下。入学、誠におめでとうございます。新たな学びの地に、実り多き時があらんことを」
その仕草は、まるで廷臣のように洗練されていて、風格を帯びていた。
ノクスが羽をふわりと揺らし、にやりと笑うような声色で返す。
「おや、リシャール殿下。入学したんだってな? そりゃまた、おめでとう」
カリュストが一礼を終えるのとほぼ同時に、ノクスの顔がふとレオの肩のあたりに向いた。
「……ん?」黒いクチバシがピクリと動き、瞳が細まる。その背で、わずかに羽が逆立った。「おい、カリュスト。あれ、見えるか……?」
カチリ、と音を立てながら、静かなカリュストの視線がネージュへと向けられる。
「これは、珍しい……」
ネージュが、二羽をじっと見返す。無言のまま、しかし深い関心を宿した赤い眼差しで。
そして――ノクスが叫んだ。
「ヴィクター! 何で教えてくれなかったんだよ!? あれ、伝書使だろ!? お前、どれだけ面白いことを隠してんだ!? 俺たち、仲間だよな?」
デュボアは溜息をついた。
「現在、あの白いコルネイユに関して知る者は、ここに居る顔ぶれと、ジャン、あとは教職員でも上層部のみ。お前たちは、口が軽い。嬉々として学寮中に吹聴しそうだからな」
「ぐ……、そ、それは否定できねぇ……」
ノクスはしゅんと肩をすくめるように項垂れた。
「心外ですね。私は吹聴したりしませんよ」
静かにそう言ったカリュストに、今まで沈黙していたボンシャンが、穏やかな声で言葉を添えた。
「分かっていますよ、君が軽率な真似をしないことも、責任ある判断をすることも。私たちは、よく理解していますし信頼もしています」その一言に、カリュストの片眼鏡が微かに光を反射した。「しかし――」ボンシャンは、慎重に言葉を選ぶように続けた。「あなた達の立場上、特定の個体だけにこのような情報を流せば、他との不均衡が生じます。だからこそ、私は自分の伝書使にも伝えていないのです。今回の件に関しては、必要最低限の者だけが知るべきことでした」
それは配慮と配分の問題であり、偏りを避けるための措置。ボンシャンの瞳は真っ直ぐだった。
「……了解しました」カリュストは深く首肯する。「慎重なご判断、納得いたしました」
その姿はまるで、軍の高官に応じる副官のように、整然としていて静謐だった。
……すごいな、これがジャン・ピエール・カナード寮監の相棒か。
言葉遣い、礼節、振る舞い、姿勢。どれを取っても隙がない。あまりの完成度に、思わず舌を巻く。やはり、真面目な人の伝書使は、格が違う。
俺は、ちらりと、レオの肩に乗っているネージュを見た。
小さな彼の初めて発した言葉、「――うっ……、ん゛ん゛ん゛尊い……」、その一言である。
二次元に溺れ、日々、腐界で魂を昇天させていた俺が、うっかり召喚してしまった心の同類。
……うん、似たんだな、やっぱり、主に……。ってやつか。
遠い目をしながら、改めて窓辺を見やる。
「ところで、デュボア先生、ボンシャン先生、……いかなるご用件で、私がここに呼ばれたのでしょう?」
カリュストが、細く滑らかな声で言葉を発した。
まっすぐに立つその姿は、気負いも媚びもなく、ただ知るべき義務を果たすかのようだ。
その問いに、すぐさま応じたのはボンシャンだった。
「先に、こちらから確認させてください。君の主――ジャン・ピエール・カナード先生は、今どこにいらっしゃるのでしょう?」
「ジャンは、既に帰寮の途にあります」
カリュストは落ち着いた口調で応じた。
「それは好都合です」ボンシャンは頷き、視線をデュボアに向けた。「デュボア先生、ここはコルベール君の担当であるあなたから説明を」
「了解」
そう言って、デュボアは箱から取り出した瓶を掌に乗せ、二羽に見せた。
「……これは?」
カリュストの瞳が鋭く細まる。ノクスもその隣で身を乗り出すようにして瓶の中身を見つめている。
「『ペルル・ノワール』」デュボアは静かに言った。「先ほど、生成されたばかりの『奇石』だ」
「奇石!?」
二羽が同時に叫んだ。
ノクスが、珍しく息を飲むような声音で続ける。
「おいおい……まさか……、これ、そこの白いのの卵殻から……?」
ネージュが、わずかに胸を張り、羽を揺らす。
「ああ。そして、これを創り出したのは、そこに居るセレスタン・ギレヌ・コルベールだ」
デュボアの言葉に、ノクスとカリュストが一斉にこちらを見た。
その視線の圧を受けながら、俺――セレスタンは軽く手を挙げる。
ノクスが「へええ……」と声を漏らした。
──サロンや王宮の催しでは、護衛魔術騎士団に所属する伝書使たちの姿を目にすることは多々あるが、魔法学院教官付きの伝書使と、こうして真正面から向き合うことなど、王族でもない限り流石のコルベール家の者であっても日常では滅多にない。
魔法学院は機密事項に溢れた閉鎖空間だ。
要するに、俺たちにとっては、これが初めての対面ということになる。
一方、カリュストはペルル・ノワールへ視線を戻すと、凝視したまま静かに口を開いた。
「確かに、ジャンに報告すべき事案ですね。急ぎ、本人を呼び出しましょう」そう言って片眼鏡の奥で瞳を細め、首を一度振ると、ゆっくりと呪文を紡いだ。「フェルマ・ヴォカ、ジャン・ピエール・カナード宛て――ローズ・デヴォン。拡張呼出し、緊急」
その声に応じるように、彼の片眼鏡にはめ込まれた奇石が淡く脈打つ。そして、空中に羅針図が展開された。中心の紋様が細かく回転し、位置情報が更新されていく。
そして――、
《……どうした、カリュスト? もう直ぐそちらに着くところだが》
穏やかだが芯のある声。ジャン・ピエール・カナード本人からの応答だった。
「お疲れ様です。寮塔に到着後、至急、第一寮監室までお越しください。報告すべき案件が発生しました。……セレスタン・ギレヌ・コルベール氏による、奇石ペルル・ノワールの生成です」
《……何だと?》
カナードの声の底に、静かな驚愕と鋭い関心が滲んだ。と、同時に、通信に混じる一定の速度で流れていく外気を切る音――。
カナードの使い魔は風蛇で名前はザイロン。青竹色の鱗を持ち、目元を斜めに走る一条の紅い縁取りと、胴体の両脇にはコウモリを思わせる皮膜の羽を備えた異形の蛇だ。
怒れば鱗が音を立てて逆立ち、威圧的な気配を纏う。普段は、彼の喉元に巻かれたアスコットタイ――彼の装いの象徴でもあるそれ――に巧妙に擬態しているが、ひとたびその身を顕せば、主を背に乗せて風を裂き、羽音を立てずに空を駆ける。
今、まさにカナードはそのザイロンの背に騎乗し、上空を滑空しながら通信を行っている。声に混じる風の唸りが、その事実を物語っていた。
「詳細はのちほどお話いたします。すでにデュボア寮監、ボンシャン寮監、リシャール王子以下、関係者が揃っています」
《了解した。すぐに向かう》
カナードがそう応じ、カリュストが通信を切ろうとしたその瞬間、ボンシャンが静かに口を開いた。
「カナード先生――ひとつ、お願いがあります。デュボア先生の部屋へ来る前に、あなたの自室に立ち寄って頂いて、小型のペンダント型『ノルデュミールの籠』を二つお持ちください」
《……なるほど。封印処理の必要があるということですね》
「はい。宜しくお願い致します」
《承知いたしました。――カリュスト、じゃあ、またあとで》
「無事のご帰還、お待ちしています。では。フィネ」
その言葉と共に通信が途絶え、羅針図がふわりと霧散した。
カリュストが一礼し、再び口を開いた。声には、静かな熱意が宿っていた。
「……ノクスと私にとっても、新しい仲間に関する事態です。もはやオブザーバーではいられません。ジャンの到着後、改めて状況を――」
「待ってください、カリュスト」
ボンシャンが軽く右手を挙げて遮った。その目元には、いつもの穏やかな笑みがたたえられていたが、声にはごくわずかに硬さが混じっていた。
「今後の処理については、あくまで学院内の機密として扱います。関係者の数は、必要最小限に絞るべきでしょう。……申し訳ありませんが、今は一度、時計塔へ戻ってください」
その言葉に、ノクスがあからさまに頬を膨らませる。カリュストもわずかに口を引き結んだが、やがて短く頷いた。
「……まさか、帰れと仰るとは思いませんでした」
「ただし――お願いがあります」
ボンシャンはカリュストのほうへ半歩近づき、声をほんの少しだけ低めた。
「あなた方には、この件に関して私の伝書使、オレリアンへ報告を。今、このような状況で、私は彼とは直接連絡を取る時間がありません。そして、寮監付きのあなた方が知ってしまったことを、同じく寮監付きなのに彼だけが知らないとなると……」
ノクスは羽根を一度ぱさりと揺らすと、肩をすくめるような動作をして言った。
「あ~……分かる。分かるわぁ……。やっかいなんだよなぁ、あいつ。あ、あいつって言っちまった。先輩なんだけどな、まあいいか。普段は、滅茶苦茶ニコニコしてて、声も柔らかくて、誰にでも優しくてさ。ちょっとくらいの失敗なら「気にしないでください」なんて笑って流してくれるし、もう神様か何かかと思うじゃねぇか? ……いや、思ってたよ、こっちは。最初はね。でも、怒ると……、いや、「怒る」っていうのとも違うんだよなぁ。オレリアンは、声荒げたりしないし。むしろ、静かになる。静かに、淡々と話し始めるんだよ。それで、一言目から、もうブッ刺さる。抑揚もなく、優しげな口調のまんまで、「それって、つまりこういうことですよね?」とか、「うーん、ちょっとした誤解かな、とは思ったんですけど」って、こっちが一番見られたくなかったとこに、ぐっさりくる。えぐるようにじゃなくて、針でちくっと刺すみたいに。いや、ちくっとじゃないな。じわじわ効いてくる毒針、だな。あとで効くやつ。しかもね、全部こっちの逃げ道、先に潰してくるんだよ。気付いたときには、言い訳の余地どころか、立ってる場所すら無くなってる。言葉にトゲはないのに、「あ、やばい……」って思ったときにはもう遅いんだ。「ごめんなさい」って言う前から、すでに何万字もの反省文書き終わってる気分になる。何が怖いって、こっちはただ詰められてるだけじゃなくて、「理解されてる」って実感があるんだなぁ、これまた。しかも、良くない意味で。あの感じ……、翼竜に睨まれたコルネイユ? みたいな? そんな気持ちになるんだ。完全にフリーズだよ。動いたら食われる。ほんの一言で胃に穴開くし、気がついたら背中の羽が汗びっしょりだ。「なんでこんなに静かなのに怖いんだ……?」って頭抱えたくなる。下手に逆らったら、マジで空飛ぶ気にならん。一週間は巣から出られない。っていうか、自分の巣の場所すら見失う。そんなレベル。あれ食らった日にゃあ、もう夜空見上げて自己反省タイム突入だよ……。凹んじまって、浮上出来ない」
肩の羽根を窄めて延々と語るその姿は、どこか本気で怖がっているように見えた。その横で、カリュストも無言のまま小さくうんうんと頷いている。
それを聞いていたボンシャンが、ふと微笑みを深めた。
「……まるで、私のことを言っているみたいですね?」
その一言に、場の空気がピリッと張り詰めた。
ノクスが瞬時に羽根をぶるっと震わせ、目を見開く。
「ち、ちがうぞ!? いや、似てるけど! でも、お宅のオレリアンはもっとこう、こう……、あー……、うー……!」
言い訳にならない言い訳を必死で並べながらノクスがそろりそろりとカリュストの背に隠れると、カリュストは息を呑んでから、「……ノクス、お前がそれほど慌てるのを、初めて見たかもしれない」と言って、堪えきれずに小さく吹き出した。
と、同時に、ボンシャンが静かに笑いながらも、ほんの少しだけ目を細める。
「でも、カリュスト。今、うんうんと随分と真剣に頷いていましたね?」
カリュストが、僅かに肩を震わせて素早く顔を逸らした。
「それと、背後のデュボア先生」ボンシャンは軽く視線を流し、さらに一言、さりげなく付け加える。「あなたも、ずっと静かに頷いておられましたね?」
「えっ?」と短く息を呑んだのは、ヴィクター・デュボアだった。
集まる一同の視線に、落ち着こうとしているのか片手で胸を軽く叩きながら「あー、うー……」と誤魔化して笑うその姿が、どう見ても陽だまりのゴリラそのもので、喉の奥までせり上がってくる笑いを俺はなんとかして飲み込んだ。
「しかし、面白いですね。全く。うちの子と私と、どこまで通じているのやら。どうか、伝言をよろしくお願いしますよ。彼が拗ねたら、私でも対応に困りますから」
「はいっ! 任せてください」
真剣な顔でそう言って頷くカリュストの隣で、ノクスもようやく落ち着きを取り戻し、小さくくちばしを鳴らした。
「……んじゃあ、とっとと伝えてくるよ。怒られない範囲で……」そう言いつつ羽根をばさりと広げたノクスだったが、その表情にはどこかしら悟りと諦めが混じっていた。「ま、どう言い繕っても、『呼ばれたのはカリュスト君だけなんですよね?』、『何故、ノクス君が一緒に行ったんでしょう?』、『ならば、どうして私も誘わなかったんですか?』って詰められるのは確定なんだけどな……。あーあ、胃が痛ぇ……」
ノクスがそう言うと、二羽は息を合わせるように一礼し、窓際へと歩み出た。
「では、我々はひとまずこれで失礼します。……また後ほど、報告をお待ちしています」
カリュストとノクスが軽やかに飛び立つと、室内には、少しの名残惜しさが滲む静けさだけが残された。
133
あなたにおすすめの小説

虚ろな檻と翡翠の魔石
篠雨
BL
「本来の寿命まで、悪役の身体に入ってやり過ごしてよ」
不慮の事故で死んだ僕は、いい加減な神様の身勝手な都合により、異世界の悪役・レリルの器へ転生させられてしまう。
待っていたのは、一生を塔で過ごし、魔力を搾取され続ける孤独な日々。だが、僕を管理する強面の辺境伯・ヨハンが運んでくる薪や食事、そして不器用な優しさが、凍てついた僕の心を次第に溶かしていく。
しかし、穏やかな時間は長くは続かない。魔力を捧げるたびに脳内に流れ込む本物のレリルの記憶と領地を襲う未曾有の魔物の群れ。
「僕が、この場所と彼を守る方法はこれしかない」
記憶に翻弄され頭は混乱する中、魔石化するという残酷な決断を下そうとするが――。
-----------------------------------------
0時,6時,12時,18時に2話ずつ更新

悪役令嬢の兄に転生!破滅フラグ回避でスローライフを目指すはずが、氷の騎士に溺愛されてます
水凪しおん
BL
三十代半ばの平凡な会社員だった俺は、ある日、乙女ゲーム『君と紡ぐ光の協奏曲』の世界に転生した。
しかも、最推しの悪役令嬢リリアナの兄、アシェルとして。
このままでは妹は断罪され、一家は没落、俺は処刑される運命だ。
そんな未来は絶対に回避しなくてはならない。
俺の夢は、穏やかなスローライフを送ること。ゲームの知識を駆使して妹を心優しい少女に育て上げ、次々と破滅フラグをへし折っていく。
順調に進むスローライフ計画だったが、関わると面倒な攻略対象、「氷の騎士」サイラスになぜか興味を持たれてしまった。
家庭菜園にまで現れる彼に困惑する俺。
だがそれはやがて、国を揺るがす陰謀と、甘く激しい恋の始まりを告げる序曲に過ぎなかった――。

悪役キャラに転生したので破滅ルートを死ぬ気で回避しようと思っていたのに、何故か勇者に攻略されそうです
菫城 珪
BL
サッカーの練習試合中、雷に打たれて目が覚めたら人気ゲームに出て来る破滅確約悪役ノアの子供時代になっていた…!
苦労して生きてきた勇者に散々嫌がらせをし、魔王軍の手先となって家族を手に掛け、最後は醜い怪物に変えられ退治されるという最悪の未来だけは絶対回避したい。
付き纏う不安と闘い、いずれ魔王と対峙する為に研鑽に励みつつも同級生である勇者アーサーとは距離を置いてをなるべく避ける日々……だった筈なのになんかどんどん距離が近くなってきてない!?
そんな感じのいずれ勇者となる少年と悪役になる筈だった少年によるBLです。
のんびり連載していきますのでよろしくお願いします!
※小説家になろう、アルファポリス、カクヨムエブリスタ各サイトに掲載中です。
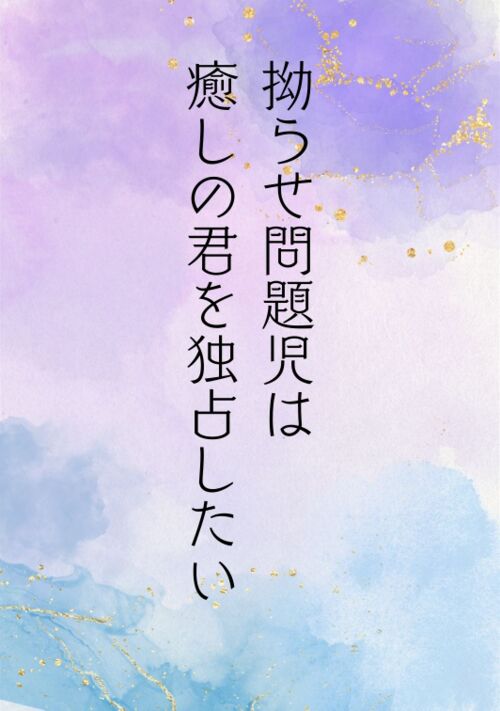
拗らせ問題児は癒しの君を独占したい
結衣可
BL
前世で限界社畜として心をすり減らした青年は、異世界の貧乏子爵家三男・セナとして転生する。王立貴族学院に奨学生として通う彼は、座学で首席の成績を持ちながらも、目立つことを徹底的に避けて生きていた。期待されることは、壊れる前触れだと知っているからだ。
一方、公爵家次男のアレクシスは、魔法も剣術も学年トップの才能を持ちながら、「何も期待されていない」立場に嫌気がさし、問題児として学院で浮いた存在になっていた。
補習課題のペアとして出会った二人。
セナはアレクシスを特別視せず、恐れも媚びも見せない。その静かな態度と、美しい瞳に、アレクシスは強く惹かれていく。放課後を共に過ごすうち、アレクシスはセナを守りたいと思い始める。
身分差と噂、そしてセナが隠す“癒やしの光魔法”。
期待されることを恐れるセナと、期待されないことに傷つくアレクシスは、すれ違いながらも互いを唯一の居場所として見つけていく。
これは、静かに生きたい少年と、選ばれたかった少年が出会った物語。

悪役令息を改めたら皆の様子がおかしいです?
* ゆるゆ
BL
王太子から伴侶(予定)契約を破棄された瞬間、前世の記憶がよみがえって、悪役令息だと気づいたよ! しかし気づいたのが終了した後な件について。
悪役令息で断罪なんて絶対だめだ! 泣いちゃう!
せっかく前世を思い出したんだから、これからは心を入れ替えて、真面目にがんばっていこう! と思ったんだけど……あれ? 皆やさしい? 主人公はあっちだよー?
ユィリと皆の動画をつくりました!
インスタ @yuruyu0 絵も動画もあがります。ほぼ毎日更新!
Youtube @BL小説動画 アカウントがなくても、どなたでもご覧になれます。動画を作ったときに更新!
プロフのWebサイトから、両方に飛べるので、もしよかったら!
名前が * ゆるゆ になりましたー!
中身はいっしょなので(笑)これからもどうぞよろしくお願い致しますー!
ご感想欄 、うれしくてすぐ承認を押してしまい(笑)ネタバレ 配慮できないので、ご覧になる時は、お気をつけください!

異世界で孵化したので全力で推しを守ります
のぶしげ
BL
ある日、聞いていたシチュエーションCDの世界に転生してしまった主人公。推しの幼少期に出会い、魔王化へのルートを回避して健やかな成長をサポートしよう!と奮闘していく異世界転生BL 執着最強×人外美人BL

魔王の息子を育てることになった俺の話
お鮫
BL
俺が18歳の時森で少年を拾った。その子が将来魔王になることを知りながら俺は今日も息子としてこの子を育てる。そう決意してはや数年。
「今なんつった?よっぽど死にたいんだね。そんなに俺と離れたい?」
現在俺はかわいい息子に殺害予告を受けている。あれ、魔王は?旅に出なくていいの?とりあえず放してくれません?
魔王になる予定の男と育て親のヤンデレBL
BLは初めて書きます。見ずらい点多々あるかと思いますが、もしありましたら指摘くださるとありがたいです。
BL大賞エントリー中です。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















