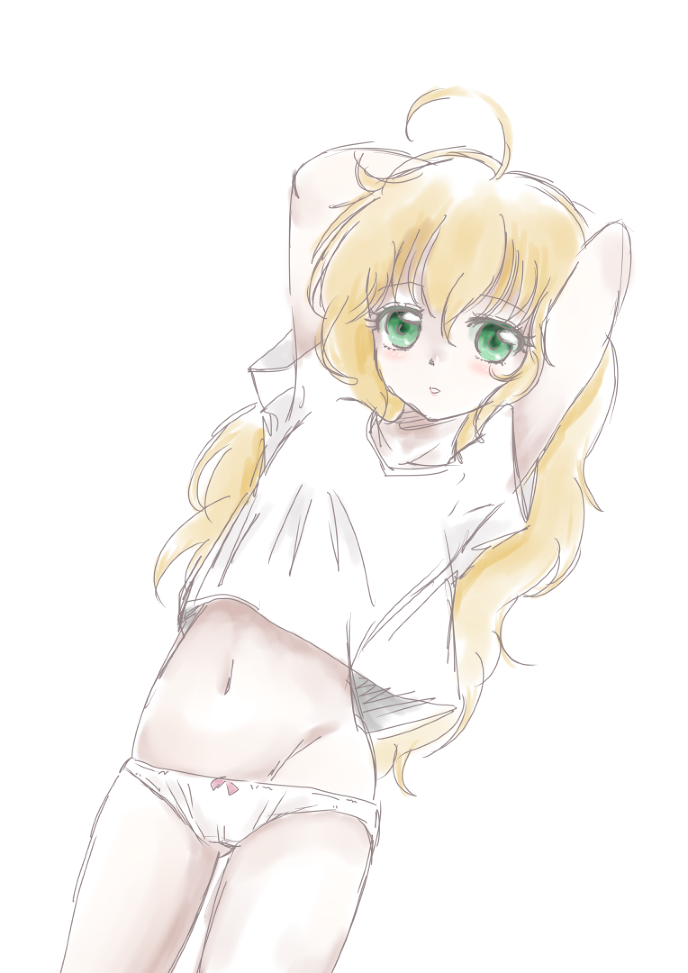4 / 66
第一章 魔法少女大戦
魔弾の射手(デア・フライシュッツ)
しおりを挟む
「あああ~!! 俺はもう頭がパンクしそうだ!!」
イクローは頭を抱えながらそう呻くように言って、キルカの座るベッドに彼女の隣あたりで寝転んだ。
「そうね。 あまり色んなことを話すと大変なの。 ……でもイキロ」
「なんだ?」
「これだけは聞いてなの」
キルカは少し真剣な目つきになった。
「もうわたしはあなたを見つけたの。 だからわたしはあなたを守るの。 どんなことをしても守るの」
イクローはそれを聞いて起き上がると彼女を見つめた。
「守る……って言われてもなぁ。 俺に何か危険な事でもあるってのか?」
彼の言葉に彼女はこくこく、と頷いた。
「わたしがあなたを見つけたということは、他の王家の子たちもそのうちあなたを見つけるの。 そうしたら……」
イクローは目を剥いた。
「俺、攫われちまう……のか?」
キルカは無表情のまま、こくこく、と頷いた。
「マジかよ……。 俺はどうしたらいいんだ!」
イクローがまた頭を抱えるとキルカは彼の頭をぽんぽん、と叩いた。
「大丈夫なの。 わたしたちが守るから、あなたは普通にしていればいいの」
「わたしたち? ああ、そうかバレッタがいたっけな……」
キルカはふるふる、と首を振った。
「あの子だけじゃないのよ」
「まだ仲間がいるのか?」
彼に聞かれてキルカは、こくこく、と頷いた。
「あの子にもそのうち会うの」
キルカが言うのを聞いて、イクローは少し安心した。
そして彼は少し彼女を見つめて言った。
「そういえば……婿探しの儀式ってのは十七歳で来るんだろ?」
その言葉に彼女は目をぱちくりとしてから、頷いた。
「なの」
「お前、どう見ても十七歳には見えないんだけど……?」
イクローは彼女のその幼い外見を見てそう言った。
するとキルカは指を顎に当ててぽつり、と言った。
「今のわたしは本当のわたしじゃないの」
「え? どういう事?」
「わたしは魔力が大きすぎて、自分の体も魔力に侵されてしまうから成長を十二歳で止めて魔力を抑えているのよ」
イクローは驚いて目を見開いた。
「そ、そうなのか? お前……一体どれだけの魔力持ってるんだよ」
彼女はふるふる、と首を振った。
「わからないの。 わたしが全力で魔力を振るったらどのくらいの規模の破壊が起きるか……わたしにもわからないの」
イクローは絶句して目の前の小さな少女を眺めた。
こんな少女がそんな力を持っているなどとにわかには信じられない話である。
「わたしには妹がいるの」
キルカが突然そんな事を言うので彼はなにか話をごまかされたように感じてぽかんとして口を開けた。
「あの子の魔法は……隕石を落とすの」
「い、隕石? ってどれくらいのだ?」
イクローが驚いて聞き返すとキルカは当然のように答えた。
「大きさは自由自在なの。 だからあの子がその気になれば都市のひとつやふたつ簡単に壊せるの。 ううん、その気になればこの星も壊せるかもなの」
「な、なんだって……?」
「でもね」
彼女はそこで言葉を一度切った。
「あの子の、スピカの称号数は一五〇〇〇くらいなの」
彼は彼女の言葉の意味を計りかねて黙って見つめた。
そしてキルカはこう続けた。
「わたしの称号数は三七五六四. あの子の倍以上なの。 だからどのくらいの破壊の規模になるかはやってみないとわからないの」
「や、やってみなくていいぞ! そ、それは!!」
イクローが慌ててそう叫ぶと、彼女は、こくこく、と頷いた。
「なの。 わたしも無益な殺生はしたくないの」
さらりとそんな事を言う小さな少女を見つめて、イクローはなんとなく寒気を覚えた。
キルカはそのまますっと立ち上がった。
彼は何をするのかと彼女を見ていると、ぽん、という音と共に彼女はまた全裸へと戻った。
「待て待て待てぇ!」
イクローが真っ赤になって叫ぶとキルカは不思議そうな顔でふり向いた。
「なんでハダカになるんだ!」
「今日はもう寝ようと思ったの」
彼女はそう言ってベッドの布団をめくった。
「いやいや、いやいやいやいや! せめてなんか着てくれないか? しかもここで俺と一緒に寝るつもりなのか?」
イクローが言うと彼女は首を傾げた。
「ダメなの?」
「ダメだ!」
キルカは少し考えこむ様子になると、彼の部屋の床にぽん、という音とともに小さなベッドを出した。
「これでいいの?」
「それはそれでいいけど、ハダカはやめろぉ!」
すると彼女はまた指を顎に当てて首を傾げてから、またぽん、と小さな音をさせた。
「これでいいの?」
彼女の下半身にはパンツが一枚張り付いていた。
「いやいやいやいやいやいやいや!! それじゃハダカと大差ねえだろ! ああ……もう! とりあえずこれでも着ててくれ!」
イクローはベッドの脇に積んであったしまい忘れた畳まれた洗濯物から自分のTシャツを一枚取り出すと彼女に差し出した。
「わかったの」
彼女はそれを受け取るといそいそと身に着けた。
「うんうん、それならいいだろ……」
イクローが安堵のため息をついたその瞬間、彼女の体にビチャッと言う音とともに右半身に血飛沫が張り付いた。
「うわぁぁ! そ、それは結局なんなんだ?」
彼が驚いて叫ぶと彼女は平然と答えた。
「呪いなの」
「の、呪い?」
彼がオウム返しに聞き返すと、キルカはまたこくこく、と頷いた。
「わたしの一族には呪いがかけられていて、何を着てもこうなるのよ」
「そ、そうなのか? い、妹も?」
「なの。 おかあさんもなの」
「そりゃまた……なんだか厄介な家系だな……」
「もう慣れたの」
彼女は言いながらベッドによじ登ると布団へと潜り込んだ。
「おやすみなさいなの」
「あ、ああ。 おやすみ……」
イクローは彼女の姿を少しの間ぼんやりと見つめていたが、すぐにまた頭を抱えた。
(おいおいおいおい! 母さんに見つかったらどう言い訳すりゃいいんだよ!!)
「おい、キル……」
彼が声をかけようとしたら、すでに彼女は目を閉じてすぅすぅと寝息を立てていた。
「……寝つきいいな」
イクローは小さな声で呟いてベッドに戻って腰かけると、声を殺して笑い出した。
考えてみれば魔法、しかもしまいには地球すら破壊しかねない、なんて想像の遥か斜め上の話を聞いておいて、女の子が部屋にいるのを母親に見つかったらどうしようか、などとものすごくばかばかしい事に思えたのだ。
彼は思う。
もう多少の問題があったら、キルカについて魔法界とやらに逃げてもいい、と。
それも構わない、と思うくらいには彼はもう彼女に好意を抱いていた。
彼は自らもごろり、と自分のベッドに寝転がると枕元のリモコンを手にして電灯を消した。
「おはようっす! センパイ!」
翌朝学校へ行こうと玄関を出ると、馬鈴田まと、いやバレッタがにこにこしながら出迎えてくれた。
「ああ、おはようバレッタ……」
彼はなんとも微妙な顔で挨拶をして仏頂面で学校へと歩き出した。
イクローが朝起きるとなぜかキルカと母親が平然と並んで歯を磨いていて、一緒に朝食をとって、そして送り出してくれたのだ。
おそらく魔法で母親の記憶か何かを書き換えたのだろう。
便利といえば便利だが、なんとも複雑な気分だった。
「どうやら無事姐さんには会えたようで安心したっす!」
彼女はそう言ってまたにこにこと笑顔を浮かべる。。
ふとイクローは思い出して疑問を口にした。
「そういや、なんでキルカが姐さんなんだ?」
すると彼女はでっかいどんぐり眼をくりくりと動かしてから答えた。
「あたしにとって『姐さん』ってのは最高の呼称なんすよ!」
「へぇ……なんかよくわからんが、とにかくお前がキルカを尊敬してるんだって事はわかったよ」
彼がそう返すとバレッタは、にぱ、と笑った。
「その敬愛する姐さんのご命令っすから! あたしはこれから毎日こうしてセンパイの護衛をしながら学校に行くっすよ!」
「ま、毎日?」
「っす!!」
彼女はそう答えてうれしそうに彼の隣をずんずんと歩いていった。
校舎の昇降口でバレッタと別れると、イクローは自分の下駄箱に靴を入れて上履きに履き替えた。
そのまま教室へ向かおうとした所で見事に後ろ頭にアックスボンバーを入れられて彼は蹲った。
「いてえな! なんだよこの野郎!!」
イクローが怒って立ち上がると、そこには悪鬼の如き形相のタイジが腕を組んで仁王立ちしていた。
「どういうことだ!!」
タイジはそう叫んで、イクローの頭に手を回すとそのまま彼の眉間をギュウギュウと締め付けた。
「いてて、いててて、だから何がだ!!」
彼が強引にその手を振りほどくとタイジはイクローの肩を掴んで顔を寄せた。
「お前……いつからまとちゃんと……まとちゃんとあんなに仲良くなった?」
「はぁ?」
イクローは、そこで思い出してため息をついた。
そうだった、バレッタのあの押しの強さに負けてそのまま学校に一緒に来たのをすっかり忘れていたのだ。
「あぁ……。 彼女の家がうちの近くらしくてな。 ばったり会ったんだよ、うん……。 まぁ、一応顔見知りだしな……はは、はははは」
彼はそっと視線を外しながらそう適当な事を口にした。
「なぁ~~~~にぃ~~~??」
タイジはそう言って、その場にしゃがみこんだ。
「うらやましい……うらやましい……うらやましい……」
そのまま座ってブツブツと言いだしたので、イクローは放っておいて教室へと行く事にした。
教室へ入ってその辺にいるクラスメイトに適当にあいさつをしながら窓際の自分の席へと向かうと、その窓の枠にもたれかかって文庫本を読んでいる女子生徒がいた。
「おはよう、蒼鉄さん」
イクローはきさくに彼女にそう声をかけると、彼女は少し笑顔を見せた。
「ああ、おはよう圓道くん。 ごめん、邪魔かしら?」
「いや、大丈夫だよ。 ……今日は何読んでんの?」
彼が聞くと彼女は本の表紙を見せた。
「シェイクスピアのテンペストよ」
「はぁ、またなんか小難しそうなの読んでんだな……。 蒼鉄さんって変なとこ勉強家だよな?」
彼が座ってカバンを机の横に引っかけながら言うと、彼女は口元に手を当ててくすくすと笑った。
「そうかしら? 古典って面白いわよ? なんというか人間の歴史みたいなのを感じて」
「人間の歴史ときたか……」
イクローは思わず笑って答えた。
蒼鉄ちるる、イクローのクラスメイトである。
ちょっとギャルっぽく制服を着崩して、髪は金髪に染めたショートボブ。
それを少しワンレングス風に右側だけ伸ばして半分目が隠れるような髪型をしている。
肌は焼いているのかやや褐色で、見た目だけでいえば完全にギャルそのものである。
ただ恐ろしく美形で、そのもはや巨大と言っていい胸、きゅっとくびれた腰、そこから広がる大き目のお尻と非の打ちどころのない爆裂ボディである。
その見た目で言い寄る男子生徒は星の数ほど、などと言われているが本人は割とクールな性格ですべて適当にあしらっているらしい。
そしてこの見た目にそぐわず、かなり成績は優秀で良くも悪くも変に目立つ女子なのであるが、なぜか二年生になって同じクラスになってからよくイクローに話しかけてくる、どちらかといえばかなり彼とは仲の良い女子であった。
すると始業を告げるチャイムが校内に鳴り響いた。
「じゃあまたな、蒼鉄さん」
「うん、じゃあね圓道くん」
ふたりはそう言い合って手を振ると彼女は自分の席へと戻っていった。
「納得がいか~~~~ん!!」
いきなりイクローの耳元でそう声が聞こえると、また彼の眉間がギリギリと締め上げられた。
「お前はなぜ……あのわが校男子憧れの的! 蒼鉄ちるる様と仲がいいんだぁぁぁ!!」
「いててて、いてぇって!! やめろよ、タイジ!!」
イクローが叫んでなんとかその腕から抜け出すとタイジがじと~っと彼を睨んで いた。
「それは俺も不思議なんだが……。 なんか二年になってから彼女よく話しかけてくれるんだ。 俺にも理由はわからん」
「くぅ~~~~!! うらやましいうらやましいうらやましい……」
タイジがブツブツ言いだすのを眺めてイクローは、また始まった……とため息をついた。
そんな二人を見て、蒼鉄ちるるは、自分の席でくすっと笑った。
すると担任の男性教師が入ってきて、ほらほら席に付け、と怒鳴った。
午前中の授業を終えて、イクローは購買へとパンを買いに走って教室へと戻ってくると、教室の入り口にバレッタが立っていて、にぱ、と笑った。
「なんだよ、お前」
イクローが声をかけると彼女は、同じく手に持った焼きそばパンを見せつけるようにした。
「センパイ! 一緒にご飯を食べましょうっす!」
イクローはため息をついた。
とりあえず教室では目立つので二人は校庭の中庭にあるベンチへと向かった。
「なぁ、バレッタ」
「なんすか?」
彼女は嬉しそうにパンを頬張りながら、そのでっかいどんぐり眼をくりくりと動かして彼を見た。
「さすがに……昼飯はまずいだろ?」
彼がそう言うとバレッタはきょとんとした後で、にぱ、と笑った。
「いえ、おいしいっすよ!!」
「そういう意味じゃねえよ!」
イクローははぁ~、と盛大にため息をついた。
「お前、これからこうして毎日昼飯も俺を誘いにくるつもりなのか?」
「当たり前っす!」
バレッタは、にぱ、と笑って自分の胸を叩いた。
「センパイの護衛はバレッタちゃんにお任せっす!!」
「いや、だからさ……ああもう、なんて説明したらいいんだ……」
イクローが頭を抱えるようにすると、バレッタはきょとん、として首を傾げた。
「あたし、もしかして……なにかやらかしたっすか?」
そして少し落ち込んだような顔になってそう言った。
あまりにもわかりやすく表情がころころ変わるバレッタを見てイクローは思わず少し笑ってしまった。
「いや、お前……基本的にはいいヤツだよな!」
イクローが笑いながらそう言うと、バレッタは照れ臭そうに笑った。
「いやぁ、そんなに褒められると照れるっす!」
「いや、そこまで褒めてねえし……」
そして二人はパンを口に入れ、並んでもぐもぐと咀嚼した。
パンを咀嚼しながら、突然バレッタが立ち上がって周囲を見回す。
「ん? どうしたバレッタ?」
「センパイ……。 なんかおかしいっす」
バレッタはいつものどんぐり眼を鋭い目つきに変えて彼をかばうような体勢になってそう耳元で囁いた。
「ど、どうしたんだ?」
「まずいっすね……。 どうやら結界内に閉じ込められたみたいっす……」
彼女はそう言うと投げキッスのように手の指を唇に当てて、声にならない声で何やら高速で呪文の詠唱をして、その指をイクローの額に当てた。
すると彼の体はなにやら緑色の薄い膜のような物で覆われた。
「防御結界を張ったっす。 あたしが倒されでもしない限りセンパイは安全っす……。 だからここにいてください」
バレッタはそう言いながら胸のあたりで両腕をクロスさせるようにする。
彼女の手の内にオレンジ色の拳銃のような物が現れた。
「て、敵なのか?」
イクローが焦った様子で聞くとバレッタは額に脂汗を浮かせながら答えた。
「わかりませんっすが……。 もしそうならなぜセンパイの事を……いや、どうやって嗅ぎつけたのか……全然わかんないす」
すると校舎の植え込みの陰からマントを着た影がすぅ、と現れた。
「あら? 関係ないのが混じっちゃったわね……まぁ、いいわ。 そこのお嬢ちゃん、怪我をしたくないならおどきなさい」
そいつはそうバレッタに向かって言い放った。
「それは……聞けないっすね。 あたしも任務でここにいるんすから」
バレッタの答えにそいつは少し驚いた様子になった。
「な、何? お前は……魔法少女なの?」
敵のその声と同時に魔導杖を構えたバレッタの髪が徐々に若草のような黄緑色へと変わっていった。
そして瞳は燃える夕焼けのような赤っぽいオレンジ色へ。
さらにぽん、と音がして彼女の衣服がオレンジ色のビスチェとショートパンツになり、順番にさらにその上にショート丈の上着と手足には指無しのグローブとブーツ、黄色いニーハイソックスへと変わった。
一番最後に長い黄色いマフラーが首に巻かれて、風になびいた。
「あ、あんた……あんたは……」
マントの魔法少女らしきそいつは狼狽した様子で口にした。
「ティアマトの『双魔神銃』!!」
「あたしの事を知ってるって事は……あんたも魔法少女っすね?」
バレッタは唸るように言ってその手の魔導杖、魔神銃を構えた。
「で、あんたはどこの魔法少女っすか?」
バレッタは隙を見せず魔神銃を構えたまま尋ねた。
「さぁね……」
相手の魔法少女はそう言うなり着ていたマントを脱ぎ捨てた。
紫色の魔導鎧を身に着けたそいつはその手にボウガンのような魔導杖を発現させ、バレッタと対峙した。
そいつもまた隙を見せる事なくそのボウガンのような魔導杖を構えた。
(こいつ……できるっす!)
バレッタはそいつと睨み合いながら、じりじりと距離を詰めた。
そしていきなり両手も魔神銃を解放した。
軽い発射音を立てながら、彼女の魔神銃は大量の弾丸を吐き出す。
この魔神銃は一分間に六十発の連射が可能である。
そして魔弾の特性を持っているのでバレッタの視界に入っている限り魔法で必ず狙った所へと命中するのだ。
この弾数を避けるのは普通に考えれば不可能である。
だが、あろう事か彼女の弾丸は軌道を逸れて敵魔法少女の背後の植え込みの木をズタズタにした。
なんと弾丸が当たる瞬間にそいつはボウガンのような魔導杖を回転させて弾丸に当て、その軌道を逸らすという離れ業をやってのけたのだ。
今放った三十発ほどの弾丸全てをだ。
「妙っすね……」
バレッタが呟くと、そいつは鼻で笑うように、フン、と言った。
「あんたほどの使い手を……このあたしが知らないわけがないんすが……」
そういくら考えてもバレッタはこの魔法少女を知らなかった。
称号数六〇〇〇あまりという、一般の魔法少女としては破格の強さを持つこのバレッタと互角に渡り合える魔法少女はそうはいないのだ。
ごく普通の魔法少女で大体称号一〇〇〇程度、まぁまぁ強いと言われるそれなりに名の通った魔法少女で一五〇〇~三〇〇〇ほどの称号数である。
そして極稀にいる五〇〇〇を超える者は、エースと呼ばれて敵味方ともに知らぬ者はいない、というレベルなのだ。
つまりバレッタは魔法界ではかなり名の通った誰からも恐れられるほどの強さを持った魔法少女なのである。
だがその彼女と渡り合えるほどの実力者であろうこの魔法少女をバレッタが知らないのはたしかに妙だった。
「あら、あなたほどの魔法少女にそんな風に言ってもらえるなんて光栄だわ。 でもそう簡単にこちらも引くわけにはいかないの。 圓道イクローはもらっていくわ、暴風弾丸娘!!」
そいつはバレッタを別の称号で呼びながら手に持ったボウガンから多数の白い光の矢を放った。
「チッ!」
バレッタは舌打ちをしながら魔神銃の銃身の下に緑色の光の刃を発現させて飛んでくる矢を叩き落とす。
全て落とした、と思った瞬間にバレッタは体勢を崩してがくり、と地に膝をついた。
見れば彼女の左太ももに真っ黒な矢が深々と突き刺さっている。
「……ほんとに、やるもんすね。 白い矢十本の中にタイミングをずらして黒い矢を一本だけ混ぜておくとは……お見それしたっす……」
バレッタは痛みに顔をしかめながら、そう言ってその紫色の魔法少女を睨んだ。
彼女の太ももからぽたぽた、と血が滴った。
そして不思議な事にその血は地面に落ちるその瞬間に白い粉のようになって風に飛ばされて消えていった。
「ば、バレッタ!!」
二人の戦いを固唾を飲んで見守っていたイクローが思わず叫んだ。
「せめて……名前だけでも教えてくれないっすかね? このままじゃ死んでも死にきれないっす」
彼女がそう言うと、紫色は状況は自分に有利と見たのか腰に手を当てて、にやりと口を歪めて笑った。
「いいわ、冥途の土産に教えてあげる! 私の名はチェリアよ!」
そいつがそう名乗るとバレッタは頭を下げて何やら考え込んだ。
「チェリア……チェリア……。 ああ、一人だけ思い当たる魔法少女がいるっす」
「な、なんですって?」
バレッタが呟くように言うとそいつは少し驚いた顔になった。
「あんた……ダムキナの光陰の矢のチェリア、違うっすか?」
彼女が顔を上げてそう言うと、そいつは目を剥いた。
「称号数は少ないのにめったやたらに強い奴がいる、と聞いた事があるっす」
バレッタはそう呟くと、すっくと立ちあがった。
そしていきなり左手の魔神銃のグリップから出ているやたら長いマガジン部分を太ももに刺さった矢に向かって斜め方向に思い切りぶつけた。
彼女の太ももの横あたりからいやな音を立てて鏃が顔を出した。
バレッタは無造作にそれを引っ掴んで思い切りそちら側から引き抜く。
「くっ……」
痛みに顔を歪めて一気に引き抜くとその矢を投げ捨て、また魔神銃を構えた。
矢というものは鏃に返しがあるので矢羽根側から引き抜くとかえってダメージが大きくなるのだ。
わかってはいてもそう簡単にこんな判断ができるものではない。
それこそが普段は呑気に見えてもバレッタという魔法少女が百戦錬磨である事の何よりの証明だった。
「まぁ、この傷は相手をなめてかかってはいけない、という教訓としてありがたく頂いておくっすよ」
バレッタはそう不敵に言って、にやり、と笑ってみせた。
そして彼女は両手を左右に大きく広げて左右真横に向けて魔神銃を放った。
さらに上に向けて魔神銃を放った。
彼女の放つ大量の弾丸はそれぞれ四つの塊として飛んで行き回転しながらそれぞれが小さな竜巻へと変わって大きく弧を描いてバレッタの背後へと戻ってくる。
そして弾丸の竜巻を周囲に従えるような形でバレッタは突進した。
「弾丸の暴風雨!!」
彼女はそう叫んで自らも回転してオレンジ色の竜巻と化すとそのままチェリアへと突き進んでいった。
チェリアは慌ててボウガンから大量の矢を発射するが全て竜巻の渦に飲み込まれて消えていった。
「こ、これが……エースの……実力……?」
彼女は観念したようにそう呟いて、なぜか最後に何もかもが救われた、とでもいうようにやさしい笑顔を浮かべたまま竜巻に飲まれて四散した。
まるでスクリューに巻き込まれていくように。
バレッタが着地して地面に膝をついてはぁはぁ、と肩を揺らしながら大きく息をついた瞬間に、ざぁ、と周りに真っ赤な血の雨が降り注いだ。
「す、すげえ……。 バレッタのヤツ……めちゃくちゃ強いんじゃないか……」
それを見ていたイクローは驚いて思わずそう口にして、あの彼の知る限り呑気そうで気のいい少女だったバレッタが血にまみれて凄惨な姿になっているのを見つめていた。
そしてそのあまりにも凄惨な有様に気づいて思わず口を押えて嘔吐した。
チェリアだったもの、の手や足や内臓やよくわからない肉片がその辺へと無残に散らばっていた。
バレッタは辛そうな顔で片足をひきずるようにしてイクローの元へと戻ってくると、いつものあの、にぱ、という笑顔を見せた。
「大丈夫っすか? センパイ」
「いや、むしろお前が大丈夫なのかよ……?」
イクローはまだ吐き気が止まらない状態でいながらも彼女を気遣ってそう言った。
「すいませんっす……ちょっとカッコ悪いとこを見せちまったっす」
彼女は少ししょんぼりしながらそう言って俯いた。
「そんな事ねえよ……。 お前すげえカッコよかったよ」
イクローはまだ青い顔をしながらそう言って泣きそうな笑顔でバレッタの頭をぽん、と叩いてそのまま撫でた。
「へへ……そんなに褒められたら照れ臭いっす……」
「ああ、今はめちゃくちゃ褒めてる!」
バレッタは頬を赤らめて嬉しそうに笑った。
だがその刹那、バレッタの身体は大きく空中へと打ち上げられた。
「ぐっ……はっ……」
バレッタが苦痛に顔を歪めると彼女はそのまま逆さづりの状態で空中に固定された。
よく見れば蔦のような植物が彼女の体中に巻き付いていた。
「な……?! バレッタ! バレッタぁぁ!!」
イクローは叫んだ。
そして彼の横にマントを着た魔法少女らしい人影が二つ、すぅ、とどこからともなく現れた。
そいつらはイクローの手をつかもうとして、壁のようなものに阻まれて、手を引っ込めた。
「チッ……結界か。 厄介な」
一人がそう言って空中に固定されたバレッタを恨めしそうに眺めた。
「は、離すっす!! 畜生、まだ仲間がいたんすか!」
バレッタは蔦に絡められながら必死にもがいて、そう叫んだ。
ご丁寧に魔神銃のトリガーにかけた指にまで蔦が絡みついていて、それを引く事すらできなかった。
「結界を解くにはあんたを殺すしかないって事ね?」
一人の魔法少女がそう言って空中へ向けて手を伸ばして、そのまま拳を握った。
どうやらこいつが蔦を操っているらしい。
「ぐはぁ……ああああ!!」
蔦に首を絞められてバレッタが呻いた。
ズドン、と何やら低く重い銃声のようなものが遠くで聞こえた、と思った瞬間、そいつの頭は下あごを残して吹き飛んだ。
そいつはそのまま倒れて頭があったあたりに大きな血だまりを作った。
「何? どこから?」
もう一人がそう言って周りを見回した瞬間に、またどこからか銃声が響いて、そいつの頭も弾けた柘榴のように吹き飛んだ。
バレッタは空中からどさり、と地面へと落ちた。
イクローは何が起きたのかわからず、ただ茫然と立ち尽くしていたが、ハッと気づいて慌ててバレッタの元へ駆け寄った。
「お、おい! バレッタ、バレッタ!!」
すると彼を覆っていたほとんど見えない透明の緑色の幕のような結界がだんだんと薄くなって消えていった。
イクローは彼女が自分が死なない限りは結界は消えない、というような事を言っていたのを思い出して顔面を蒼白にして彼女の名を呼び続けた。
「お、おい……まさか……バレッタ! バレッタぁぁ!」
イクローは必死に呼びかけたが彼女はピクリとも動かなかった。
彼が彼女の口元へと耳を近づけると、わずかに呼吸をしているのはわかった。
死んでいるわけではないのだと安心してため息をつきながら彼女をおんぶの形で背負うとイクローは歩き出した。
とりあえず保健室に行こうか、と考えたのだ。
彼には今は他にどうする事もできない。
まだ敵の仲間がいるかも知れない、と用心深く周囲を注意しながらそろそろと中庭を出て校舎へと入ろうとした。
その時、そこから数百メートル離れた校舎の上に立つ者がいた。
手には青く輝く二メートル近くはあろうかという長尺のまるで対戦車ライフルのような、それでいながらあちこちに彫金のような金色の装飾の施されたクラシカルなデザインの不思議な銃を持っている。
その銃口からはうっすらと煙がたなびいていた。
その人物は輝くような水色の髪を風にたなびかせ、それを手でかき上げながら特徴的な水色のルージュに彩られた口元にうっすらと笑みを浮かべた。
「バレッタ……ひとつ貸しよ?」
それはそう言って周囲の結界が消え失せているのを確認し、呪文を詠唱するとその場から、すぅ、と姿を消した。
イクローは保健室へとたどり着くと、失礼します、と声をかけながら戸を開けた。
だが中は無人で、いっそ都合がいい、とバレッタを背負ったまま室内へと入った。
とりあえずベッドに彼女を寝かせてその体を見てみるとそこら中傷だらけではあったが太ももの矢傷以外は大した怪我はしてないようで、ほっと息をついた。
慣れない手つきで傷を消毒して、ガーゼを当て包帯を巻いて、彼女のベッドの傍らで椅子に座って、彼自身も疲れ切っていたのかいつの間にか眠ってしまった。
「センパイ、センパイ……」
そしてそう呼ばれる声でイクローは目を覚ました。
気づけばベッドの布団からでっかいどんぐり眼が覗いていた。
「気が付いたのか、バレッタ。 よかった」
彼がそう言ってため息をつくと、彼女は照れ臭そうに笑った。
「すいませんっす。 すっかりご迷惑をおかけしちまったようっす」
彼女はそう言って体を起こすとぺこり、と頭を下げた。
気づけば彼女の髪と目はいつの間にか茶色に戻っていて、服装も普段の学校の制服へと戻っていた。
「いや、お前は俺を守るために戦ってくれたんだ……俺の方こそごめんな……」
イクローもそう言って頭を下げた。
「いやいやいやいや! これはあたしの任務っすから! センパイが気に病む必要はないんすよ!」
彼女はあわててぶんぶんと手を振った。
イクローはふと壁の時計に目をやって、しまった、という顔をした。
「ヤバイな、下校時間過ぎてる。 今日はタクシーで送ってやるよ。 お前の家はどこだ?」
「ないっす」
「は?」
イクローは目を瞬かせて彼女をじっと見た。
「家はないっすよ? 基本いつもセンパイの家の周囲に結界を張って近くの公園で寝てるっす」
「待て待て待て、それは……大丈夫なのか?」
「任務中っすから」
屈託なく応えるバレッタを見て、イクローは頭を抱えた。
「……わかった。 もういい、お前も俺の家に来い」
「いいんすか?」
「いいもなにも……もう家にはキルカがいるしな」
イクローが言うとバレッタは、ぱぁ、と明るい顔になった。
「ありがとうございますっす!! このご恩は……一生忘れないっす!」
「忘れていいから……ほら、行くぞ。 立てるか?」
「はいっす」
彼はバレッタに肩を貸してやりながら校門を出ると通りがかったタクシーを捕まえて帰宅した。
「絶対おかしいんすよ!!」
家に戻ってキルカに会ったバレッタは眉間にしわを寄せて叫んだ。
今はイクローの部屋でバレッタはキルカによって治癒魔法を受けているところだ。
自分でかければよかったんじゃないのかとイクローが聞いたら自分で自分には治癒魔法はかけられないのだとキルカが教えてくれた。
「おかしいってなにがなの?」
キルカは首を傾げている。
「あたしが戦ったあのチェリアってヤツっす」
「どうおかしいの?」
「あいつの噂は聞いてたっすけど……それにしても強すぎでしたし……それに……」
バレッタはここで一度言葉を切って考え込んだ。
「あいつ、倒しても塩にならなかったんす」
それを聞いてイクローが不思議な顔をした。
「塩ってなんだ?」
するとキルカが説明してくれた。
「わたしたち魔法少女は魔法で殺されると塩の塊になってしまうのよ。 どうしてなのかはわからないのだけど……」
それを聞いてイクローは昨夜会った魔法少女がバレッタの攻撃で白い粉のような物になった事を思い出した。
「あ、あれって……てっきり魔法で動く人形とかだと思ってた……あれが、魔法少女の死……?」
彼はそう言って、また少し吐き気を催したが必死に耐えた。
そういえば今日の戦いでバレッタの流した血も地面に落ちる前に白い粉みたいなものになっていた、と思い出す。
「なのなの」
キルカはこくこくと頷いてバレッタに向き直った。
「塩にならなかったって……それがほんとうならものすごくおかしいの」
「そうなんすよ、姐さん」
そしてバレッタは少し黙った後、こう言った。
「まるで……人間を殺したみたいな……そんな感じっす……」
「どういうことなの……?」
二人が重苦しい雰囲気になっているのを見て、イクローは立ち上がった。
「とりあえず俺コンビニに行ってくるな」
するとバレッタが立ち上がろうとして、痛みに顔をしかめてまた座り込みながら叫んだ。
「あ、あたしもいくっす!」
「お前は休んでろ」
「なの」
イクローとキルカに言われてバレッタはしゅん、と落ち込んだが、すぐに顔を上げてまた叫んだ。
「でも今日も襲われたばっかっすし……一人で出歩くのは危険っすよ!」
「そ、そう言われればそれもそうだな……」
イクローが唸るように言うとキルカがけろりと普通に答えた。
「イキロは大丈夫なの」
「どうして?」
彼が尋ねると、キルカではなくバレッタが何かを思い出したような顔になって声を上げた。
「ああ、あいつがいるんすね?」
バレッタの問いにキルカは頷いた。
「なのなの」
「あいつって?」
「わたしたちのもうひとりの仲間なの」
「ああ、そぅいえばまだ仲間がいるって言ってたっけな……そいつが近くにいるのか?」
イクローは考え込んだ、もしかして今日バレッタを助けてくれたのはそいつなんじゃないのか? と。
「あの子は遠くからずっとイキロの護衛をしていたの」
「そ、そうなのか?」
「なのなの。 だから何かあってもあの子が守ってくれるの。 安心するの」
キルカはそう言ってイクローの頭を触ろうとしたが、届かないので彼の胸あたりをぽふぽふ、と叩いた。
そして彼女は投げキッスのように唇に手を当てると聴こえるか聴こえないかくらいの小さな声で高速で呪文を詠唱してイクローの額に触った。
彼の身体はほとんど見えない透明の赤い膜で包まれた。
「わたしの結界を念のために張っておくの。 これがあれば何があっても大丈夫なの」
「そうか、ありがとよ!」
イクローは明るい顔になると部屋を出て行った。
「あいつの助けを借りなきゃならないとは……このバレッタ、一生の不覚っす……」
バレッタは悔しそうな顔で仰向けに倒れると溜息をついた。
コンビニへの道すがら、イクローはややビクビクしながら周囲を見回して歩いていた。
だが幸いな事にすぐにコンビニにたどり着き、安心しながら店内へと足を踏み入れた。
店内を歩き回っていると、ふとイートインスペースに見知った顔があるのに気づいた。
「あれ? 蒼鉄さんじゃないか」
彼が驚いて声をかけた相手はクラスメイトの蒼鉄ちるるであった。
水色のTシャツに青いショートパンツ、足元は厚底のサンダルというかなりラフな格好で彼女はカフェラテを飲んでいた。
「あら、圓道くん。 こんばんは」
彼女は少し笑顔を見せて挨拶を返した。
「蒼鉄さんって家この辺だっけ?」
「え、ええ……実はそうなの!」
彼女はなぜか少し焦った風に答えた。
「そうか、でもこの辺で会った事ないよね?」
イクローが聞くとちるるは、少し情けない笑顔で言った。
「そういえばそうね! 不思議ね~!」
「まぁ、いいや。 俺ちょっと買い物してくるね」
彼がそう言って一旦そこを立ち去るとちるるは胸を撫でおろして、周囲を見回して、息をついた。
買い物をを終え二人並んで店内を出ると、そのままイクローは危険がないように、といつもの路地ではなく大通りを歩いて帰る事にした。
なぜか普通にそのあとをちるるも付いてくる。
「あれ? 蒼鉄さんの家ってこっち?」
彼が聞くと彼女はにこにこしながらカフェオレのストローを啜りながら頷く。
するとふと八歳~十歳くらいの女の子が二人の元へとぱたぱたと走ってきた。
二人が彼女を不思議そうに見ていると少女は言った。
「おにいさん、わたしと一緒にきて!」
「え? 俺?」
するとちるるが無表情で少女の顔に飲みかけのカフェオレのカップを投げつけた。
びしょ濡れになって唖然とする少女を見てイクローが叫ぶ。
「ちょ、あ、蒼鉄さん?!」
ちるるは背伸びをするように手を上に伸ばして、残念そうに言った。
「あ~あ……同級生、楽しかったのにな……」
イクローと少女がわけがわからず茫然としたまま突っ立っていると、ちるるの伸ばした腕の中にやたら長い対戦車ライフルのような銃がいつの間にか握られていた。
そして彼女の髪はまるで夏の高い空のようなさわやかな水色へ、瞳は深い海のようなコバルトブルーへと変わっていった。
少女がそれを見て目を剥いて叫んだ。
「お、お前は……ティアマトの『魔弾の射手』!!」
「さよなら」
ちるる……だったものは冷たい表情で別れの言葉を言う。
そして素早くその巨大な銃を構えると、いきなりズドン、という低くて重たい音とともに弾丸を発射した。
イクローは頭を抱えながらそう呻くように言って、キルカの座るベッドに彼女の隣あたりで寝転んだ。
「そうね。 あまり色んなことを話すと大変なの。 ……でもイキロ」
「なんだ?」
「これだけは聞いてなの」
キルカは少し真剣な目つきになった。
「もうわたしはあなたを見つけたの。 だからわたしはあなたを守るの。 どんなことをしても守るの」
イクローはそれを聞いて起き上がると彼女を見つめた。
「守る……って言われてもなぁ。 俺に何か危険な事でもあるってのか?」
彼の言葉に彼女はこくこく、と頷いた。
「わたしがあなたを見つけたということは、他の王家の子たちもそのうちあなたを見つけるの。 そうしたら……」
イクローは目を剥いた。
「俺、攫われちまう……のか?」
キルカは無表情のまま、こくこく、と頷いた。
「マジかよ……。 俺はどうしたらいいんだ!」
イクローがまた頭を抱えるとキルカは彼の頭をぽんぽん、と叩いた。
「大丈夫なの。 わたしたちが守るから、あなたは普通にしていればいいの」
「わたしたち? ああ、そうかバレッタがいたっけな……」
キルカはふるふる、と首を振った。
「あの子だけじゃないのよ」
「まだ仲間がいるのか?」
彼に聞かれてキルカは、こくこく、と頷いた。
「あの子にもそのうち会うの」
キルカが言うのを聞いて、イクローは少し安心した。
そして彼は少し彼女を見つめて言った。
「そういえば……婿探しの儀式ってのは十七歳で来るんだろ?」
その言葉に彼女は目をぱちくりとしてから、頷いた。
「なの」
「お前、どう見ても十七歳には見えないんだけど……?」
イクローは彼女のその幼い外見を見てそう言った。
するとキルカは指を顎に当ててぽつり、と言った。
「今のわたしは本当のわたしじゃないの」
「え? どういう事?」
「わたしは魔力が大きすぎて、自分の体も魔力に侵されてしまうから成長を十二歳で止めて魔力を抑えているのよ」
イクローは驚いて目を見開いた。
「そ、そうなのか? お前……一体どれだけの魔力持ってるんだよ」
彼女はふるふる、と首を振った。
「わからないの。 わたしが全力で魔力を振るったらどのくらいの規模の破壊が起きるか……わたしにもわからないの」
イクローは絶句して目の前の小さな少女を眺めた。
こんな少女がそんな力を持っているなどとにわかには信じられない話である。
「わたしには妹がいるの」
キルカが突然そんな事を言うので彼はなにか話をごまかされたように感じてぽかんとして口を開けた。
「あの子の魔法は……隕石を落とすの」
「い、隕石? ってどれくらいのだ?」
イクローが驚いて聞き返すとキルカは当然のように答えた。
「大きさは自由自在なの。 だからあの子がその気になれば都市のひとつやふたつ簡単に壊せるの。 ううん、その気になればこの星も壊せるかもなの」
「な、なんだって……?」
「でもね」
彼女はそこで言葉を一度切った。
「あの子の、スピカの称号数は一五〇〇〇くらいなの」
彼は彼女の言葉の意味を計りかねて黙って見つめた。
そしてキルカはこう続けた。
「わたしの称号数は三七五六四. あの子の倍以上なの。 だからどのくらいの破壊の規模になるかはやってみないとわからないの」
「や、やってみなくていいぞ! そ、それは!!」
イクローが慌ててそう叫ぶと、彼女は、こくこく、と頷いた。
「なの。 わたしも無益な殺生はしたくないの」
さらりとそんな事を言う小さな少女を見つめて、イクローはなんとなく寒気を覚えた。
キルカはそのまますっと立ち上がった。
彼は何をするのかと彼女を見ていると、ぽん、という音と共に彼女はまた全裸へと戻った。
「待て待て待てぇ!」
イクローが真っ赤になって叫ぶとキルカは不思議そうな顔でふり向いた。
「なんでハダカになるんだ!」
「今日はもう寝ようと思ったの」
彼女はそう言ってベッドの布団をめくった。
「いやいや、いやいやいやいや! せめてなんか着てくれないか? しかもここで俺と一緒に寝るつもりなのか?」
イクローが言うと彼女は首を傾げた。
「ダメなの?」
「ダメだ!」
キルカは少し考えこむ様子になると、彼の部屋の床にぽん、という音とともに小さなベッドを出した。
「これでいいの?」
「それはそれでいいけど、ハダカはやめろぉ!」
すると彼女はまた指を顎に当てて首を傾げてから、またぽん、と小さな音をさせた。
「これでいいの?」
彼女の下半身にはパンツが一枚張り付いていた。
「いやいやいやいやいやいやいや!! それじゃハダカと大差ねえだろ! ああ……もう! とりあえずこれでも着ててくれ!」
イクローはベッドの脇に積んであったしまい忘れた畳まれた洗濯物から自分のTシャツを一枚取り出すと彼女に差し出した。
「わかったの」
彼女はそれを受け取るといそいそと身に着けた。
「うんうん、それならいいだろ……」
イクローが安堵のため息をついたその瞬間、彼女の体にビチャッと言う音とともに右半身に血飛沫が張り付いた。
「うわぁぁ! そ、それは結局なんなんだ?」
彼が驚いて叫ぶと彼女は平然と答えた。
「呪いなの」
「の、呪い?」
彼がオウム返しに聞き返すと、キルカはまたこくこく、と頷いた。
「わたしの一族には呪いがかけられていて、何を着てもこうなるのよ」
「そ、そうなのか? い、妹も?」
「なの。 おかあさんもなの」
「そりゃまた……なんだか厄介な家系だな……」
「もう慣れたの」
彼女は言いながらベッドによじ登ると布団へと潜り込んだ。
「おやすみなさいなの」
「あ、ああ。 おやすみ……」
イクローは彼女の姿を少しの間ぼんやりと見つめていたが、すぐにまた頭を抱えた。
(おいおいおいおい! 母さんに見つかったらどう言い訳すりゃいいんだよ!!)
「おい、キル……」
彼が声をかけようとしたら、すでに彼女は目を閉じてすぅすぅと寝息を立てていた。
「……寝つきいいな」
イクローは小さな声で呟いてベッドに戻って腰かけると、声を殺して笑い出した。
考えてみれば魔法、しかもしまいには地球すら破壊しかねない、なんて想像の遥か斜め上の話を聞いておいて、女の子が部屋にいるのを母親に見つかったらどうしようか、などとものすごくばかばかしい事に思えたのだ。
彼は思う。
もう多少の問題があったら、キルカについて魔法界とやらに逃げてもいい、と。
それも構わない、と思うくらいには彼はもう彼女に好意を抱いていた。
彼は自らもごろり、と自分のベッドに寝転がると枕元のリモコンを手にして電灯を消した。
「おはようっす! センパイ!」
翌朝学校へ行こうと玄関を出ると、馬鈴田まと、いやバレッタがにこにこしながら出迎えてくれた。
「ああ、おはようバレッタ……」
彼はなんとも微妙な顔で挨拶をして仏頂面で学校へと歩き出した。
イクローが朝起きるとなぜかキルカと母親が平然と並んで歯を磨いていて、一緒に朝食をとって、そして送り出してくれたのだ。
おそらく魔法で母親の記憶か何かを書き換えたのだろう。
便利といえば便利だが、なんとも複雑な気分だった。
「どうやら無事姐さんには会えたようで安心したっす!」
彼女はそう言ってまたにこにこと笑顔を浮かべる。。
ふとイクローは思い出して疑問を口にした。
「そういや、なんでキルカが姐さんなんだ?」
すると彼女はでっかいどんぐり眼をくりくりと動かしてから答えた。
「あたしにとって『姐さん』ってのは最高の呼称なんすよ!」
「へぇ……なんかよくわからんが、とにかくお前がキルカを尊敬してるんだって事はわかったよ」
彼がそう返すとバレッタは、にぱ、と笑った。
「その敬愛する姐さんのご命令っすから! あたしはこれから毎日こうしてセンパイの護衛をしながら学校に行くっすよ!」
「ま、毎日?」
「っす!!」
彼女はそう答えてうれしそうに彼の隣をずんずんと歩いていった。
校舎の昇降口でバレッタと別れると、イクローは自分の下駄箱に靴を入れて上履きに履き替えた。
そのまま教室へ向かおうとした所で見事に後ろ頭にアックスボンバーを入れられて彼は蹲った。
「いてえな! なんだよこの野郎!!」
イクローが怒って立ち上がると、そこには悪鬼の如き形相のタイジが腕を組んで仁王立ちしていた。
「どういうことだ!!」
タイジはそう叫んで、イクローの頭に手を回すとそのまま彼の眉間をギュウギュウと締め付けた。
「いてて、いててて、だから何がだ!!」
彼が強引にその手を振りほどくとタイジはイクローの肩を掴んで顔を寄せた。
「お前……いつからまとちゃんと……まとちゃんとあんなに仲良くなった?」
「はぁ?」
イクローは、そこで思い出してため息をついた。
そうだった、バレッタのあの押しの強さに負けてそのまま学校に一緒に来たのをすっかり忘れていたのだ。
「あぁ……。 彼女の家がうちの近くらしくてな。 ばったり会ったんだよ、うん……。 まぁ、一応顔見知りだしな……はは、はははは」
彼はそっと視線を外しながらそう適当な事を口にした。
「なぁ~~~~にぃ~~~??」
タイジはそう言って、その場にしゃがみこんだ。
「うらやましい……うらやましい……うらやましい……」
そのまま座ってブツブツと言いだしたので、イクローは放っておいて教室へと行く事にした。
教室へ入ってその辺にいるクラスメイトに適当にあいさつをしながら窓際の自分の席へと向かうと、その窓の枠にもたれかかって文庫本を読んでいる女子生徒がいた。
「おはよう、蒼鉄さん」
イクローはきさくに彼女にそう声をかけると、彼女は少し笑顔を見せた。
「ああ、おはよう圓道くん。 ごめん、邪魔かしら?」
「いや、大丈夫だよ。 ……今日は何読んでんの?」
彼が聞くと彼女は本の表紙を見せた。
「シェイクスピアのテンペストよ」
「はぁ、またなんか小難しそうなの読んでんだな……。 蒼鉄さんって変なとこ勉強家だよな?」
彼が座ってカバンを机の横に引っかけながら言うと、彼女は口元に手を当ててくすくすと笑った。
「そうかしら? 古典って面白いわよ? なんというか人間の歴史みたいなのを感じて」
「人間の歴史ときたか……」
イクローは思わず笑って答えた。
蒼鉄ちるる、イクローのクラスメイトである。
ちょっとギャルっぽく制服を着崩して、髪は金髪に染めたショートボブ。
それを少しワンレングス風に右側だけ伸ばして半分目が隠れるような髪型をしている。
肌は焼いているのかやや褐色で、見た目だけでいえば完全にギャルそのものである。
ただ恐ろしく美形で、そのもはや巨大と言っていい胸、きゅっとくびれた腰、そこから広がる大き目のお尻と非の打ちどころのない爆裂ボディである。
その見た目で言い寄る男子生徒は星の数ほど、などと言われているが本人は割とクールな性格ですべて適当にあしらっているらしい。
そしてこの見た目にそぐわず、かなり成績は優秀で良くも悪くも変に目立つ女子なのであるが、なぜか二年生になって同じクラスになってからよくイクローに話しかけてくる、どちらかといえばかなり彼とは仲の良い女子であった。
すると始業を告げるチャイムが校内に鳴り響いた。
「じゃあまたな、蒼鉄さん」
「うん、じゃあね圓道くん」
ふたりはそう言い合って手を振ると彼女は自分の席へと戻っていった。
「納得がいか~~~~ん!!」
いきなりイクローの耳元でそう声が聞こえると、また彼の眉間がギリギリと締め上げられた。
「お前はなぜ……あのわが校男子憧れの的! 蒼鉄ちるる様と仲がいいんだぁぁぁ!!」
「いててて、いてぇって!! やめろよ、タイジ!!」
イクローが叫んでなんとかその腕から抜け出すとタイジがじと~っと彼を睨んで いた。
「それは俺も不思議なんだが……。 なんか二年になってから彼女よく話しかけてくれるんだ。 俺にも理由はわからん」
「くぅ~~~~!! うらやましいうらやましいうらやましい……」
タイジがブツブツ言いだすのを眺めてイクローは、また始まった……とため息をついた。
そんな二人を見て、蒼鉄ちるるは、自分の席でくすっと笑った。
すると担任の男性教師が入ってきて、ほらほら席に付け、と怒鳴った。
午前中の授業を終えて、イクローは購買へとパンを買いに走って教室へと戻ってくると、教室の入り口にバレッタが立っていて、にぱ、と笑った。
「なんだよ、お前」
イクローが声をかけると彼女は、同じく手に持った焼きそばパンを見せつけるようにした。
「センパイ! 一緒にご飯を食べましょうっす!」
イクローはため息をついた。
とりあえず教室では目立つので二人は校庭の中庭にあるベンチへと向かった。
「なぁ、バレッタ」
「なんすか?」
彼女は嬉しそうにパンを頬張りながら、そのでっかいどんぐり眼をくりくりと動かして彼を見た。
「さすがに……昼飯はまずいだろ?」
彼がそう言うとバレッタはきょとんとした後で、にぱ、と笑った。
「いえ、おいしいっすよ!!」
「そういう意味じゃねえよ!」
イクローははぁ~、と盛大にため息をついた。
「お前、これからこうして毎日昼飯も俺を誘いにくるつもりなのか?」
「当たり前っす!」
バレッタは、にぱ、と笑って自分の胸を叩いた。
「センパイの護衛はバレッタちゃんにお任せっす!!」
「いや、だからさ……ああもう、なんて説明したらいいんだ……」
イクローが頭を抱えるようにすると、バレッタはきょとん、として首を傾げた。
「あたし、もしかして……なにかやらかしたっすか?」
そして少し落ち込んだような顔になってそう言った。
あまりにもわかりやすく表情がころころ変わるバレッタを見てイクローは思わず少し笑ってしまった。
「いや、お前……基本的にはいいヤツだよな!」
イクローが笑いながらそう言うと、バレッタは照れ臭そうに笑った。
「いやぁ、そんなに褒められると照れるっす!」
「いや、そこまで褒めてねえし……」
そして二人はパンを口に入れ、並んでもぐもぐと咀嚼した。
パンを咀嚼しながら、突然バレッタが立ち上がって周囲を見回す。
「ん? どうしたバレッタ?」
「センパイ……。 なんかおかしいっす」
バレッタはいつものどんぐり眼を鋭い目つきに変えて彼をかばうような体勢になってそう耳元で囁いた。
「ど、どうしたんだ?」
「まずいっすね……。 どうやら結界内に閉じ込められたみたいっす……」
彼女はそう言うと投げキッスのように手の指を唇に当てて、声にならない声で何やら高速で呪文の詠唱をして、その指をイクローの額に当てた。
すると彼の体はなにやら緑色の薄い膜のような物で覆われた。
「防御結界を張ったっす。 あたしが倒されでもしない限りセンパイは安全っす……。 だからここにいてください」
バレッタはそう言いながら胸のあたりで両腕をクロスさせるようにする。
彼女の手の内にオレンジ色の拳銃のような物が現れた。
「て、敵なのか?」
イクローが焦った様子で聞くとバレッタは額に脂汗を浮かせながら答えた。
「わかりませんっすが……。 もしそうならなぜセンパイの事を……いや、どうやって嗅ぎつけたのか……全然わかんないす」
すると校舎の植え込みの陰からマントを着た影がすぅ、と現れた。
「あら? 関係ないのが混じっちゃったわね……まぁ、いいわ。 そこのお嬢ちゃん、怪我をしたくないならおどきなさい」
そいつはそうバレッタに向かって言い放った。
「それは……聞けないっすね。 あたしも任務でここにいるんすから」
バレッタの答えにそいつは少し驚いた様子になった。
「な、何? お前は……魔法少女なの?」
敵のその声と同時に魔導杖を構えたバレッタの髪が徐々に若草のような黄緑色へと変わっていった。
そして瞳は燃える夕焼けのような赤っぽいオレンジ色へ。
さらにぽん、と音がして彼女の衣服がオレンジ色のビスチェとショートパンツになり、順番にさらにその上にショート丈の上着と手足には指無しのグローブとブーツ、黄色いニーハイソックスへと変わった。
一番最後に長い黄色いマフラーが首に巻かれて、風になびいた。
「あ、あんた……あんたは……」
マントの魔法少女らしきそいつは狼狽した様子で口にした。
「ティアマトの『双魔神銃』!!」
「あたしの事を知ってるって事は……あんたも魔法少女っすね?」
バレッタは唸るように言ってその手の魔導杖、魔神銃を構えた。
「で、あんたはどこの魔法少女っすか?」
バレッタは隙を見せず魔神銃を構えたまま尋ねた。
「さぁね……」
相手の魔法少女はそう言うなり着ていたマントを脱ぎ捨てた。
紫色の魔導鎧を身に着けたそいつはその手にボウガンのような魔導杖を発現させ、バレッタと対峙した。
そいつもまた隙を見せる事なくそのボウガンのような魔導杖を構えた。
(こいつ……できるっす!)
バレッタはそいつと睨み合いながら、じりじりと距離を詰めた。
そしていきなり両手も魔神銃を解放した。
軽い発射音を立てながら、彼女の魔神銃は大量の弾丸を吐き出す。
この魔神銃は一分間に六十発の連射が可能である。
そして魔弾の特性を持っているのでバレッタの視界に入っている限り魔法で必ず狙った所へと命中するのだ。
この弾数を避けるのは普通に考えれば不可能である。
だが、あろう事か彼女の弾丸は軌道を逸れて敵魔法少女の背後の植え込みの木をズタズタにした。
なんと弾丸が当たる瞬間にそいつはボウガンのような魔導杖を回転させて弾丸に当て、その軌道を逸らすという離れ業をやってのけたのだ。
今放った三十発ほどの弾丸全てをだ。
「妙っすね……」
バレッタが呟くと、そいつは鼻で笑うように、フン、と言った。
「あんたほどの使い手を……このあたしが知らないわけがないんすが……」
そういくら考えてもバレッタはこの魔法少女を知らなかった。
称号数六〇〇〇あまりという、一般の魔法少女としては破格の強さを持つこのバレッタと互角に渡り合える魔法少女はそうはいないのだ。
ごく普通の魔法少女で大体称号一〇〇〇程度、まぁまぁ強いと言われるそれなりに名の通った魔法少女で一五〇〇~三〇〇〇ほどの称号数である。
そして極稀にいる五〇〇〇を超える者は、エースと呼ばれて敵味方ともに知らぬ者はいない、というレベルなのだ。
つまりバレッタは魔法界ではかなり名の通った誰からも恐れられるほどの強さを持った魔法少女なのである。
だがその彼女と渡り合えるほどの実力者であろうこの魔法少女をバレッタが知らないのはたしかに妙だった。
「あら、あなたほどの魔法少女にそんな風に言ってもらえるなんて光栄だわ。 でもそう簡単にこちらも引くわけにはいかないの。 圓道イクローはもらっていくわ、暴風弾丸娘!!」
そいつはバレッタを別の称号で呼びながら手に持ったボウガンから多数の白い光の矢を放った。
「チッ!」
バレッタは舌打ちをしながら魔神銃の銃身の下に緑色の光の刃を発現させて飛んでくる矢を叩き落とす。
全て落とした、と思った瞬間にバレッタは体勢を崩してがくり、と地に膝をついた。
見れば彼女の左太ももに真っ黒な矢が深々と突き刺さっている。
「……ほんとに、やるもんすね。 白い矢十本の中にタイミングをずらして黒い矢を一本だけ混ぜておくとは……お見それしたっす……」
バレッタは痛みに顔をしかめながら、そう言ってその紫色の魔法少女を睨んだ。
彼女の太ももからぽたぽた、と血が滴った。
そして不思議な事にその血は地面に落ちるその瞬間に白い粉のようになって風に飛ばされて消えていった。
「ば、バレッタ!!」
二人の戦いを固唾を飲んで見守っていたイクローが思わず叫んだ。
「せめて……名前だけでも教えてくれないっすかね? このままじゃ死んでも死にきれないっす」
彼女がそう言うと、紫色は状況は自分に有利と見たのか腰に手を当てて、にやりと口を歪めて笑った。
「いいわ、冥途の土産に教えてあげる! 私の名はチェリアよ!」
そいつがそう名乗るとバレッタは頭を下げて何やら考え込んだ。
「チェリア……チェリア……。 ああ、一人だけ思い当たる魔法少女がいるっす」
「な、なんですって?」
バレッタが呟くように言うとそいつは少し驚いた顔になった。
「あんた……ダムキナの光陰の矢のチェリア、違うっすか?」
彼女が顔を上げてそう言うと、そいつは目を剥いた。
「称号数は少ないのにめったやたらに強い奴がいる、と聞いた事があるっす」
バレッタはそう呟くと、すっくと立ちあがった。
そしていきなり左手の魔神銃のグリップから出ているやたら長いマガジン部分を太ももに刺さった矢に向かって斜め方向に思い切りぶつけた。
彼女の太ももの横あたりからいやな音を立てて鏃が顔を出した。
バレッタは無造作にそれを引っ掴んで思い切りそちら側から引き抜く。
「くっ……」
痛みに顔を歪めて一気に引き抜くとその矢を投げ捨て、また魔神銃を構えた。
矢というものは鏃に返しがあるので矢羽根側から引き抜くとかえってダメージが大きくなるのだ。
わかってはいてもそう簡単にこんな判断ができるものではない。
それこそが普段は呑気に見えてもバレッタという魔法少女が百戦錬磨である事の何よりの証明だった。
「まぁ、この傷は相手をなめてかかってはいけない、という教訓としてありがたく頂いておくっすよ」
バレッタはそう不敵に言って、にやり、と笑ってみせた。
そして彼女は両手を左右に大きく広げて左右真横に向けて魔神銃を放った。
さらに上に向けて魔神銃を放った。
彼女の放つ大量の弾丸はそれぞれ四つの塊として飛んで行き回転しながらそれぞれが小さな竜巻へと変わって大きく弧を描いてバレッタの背後へと戻ってくる。
そして弾丸の竜巻を周囲に従えるような形でバレッタは突進した。
「弾丸の暴風雨!!」
彼女はそう叫んで自らも回転してオレンジ色の竜巻と化すとそのままチェリアへと突き進んでいった。
チェリアは慌ててボウガンから大量の矢を発射するが全て竜巻の渦に飲み込まれて消えていった。
「こ、これが……エースの……実力……?」
彼女は観念したようにそう呟いて、なぜか最後に何もかもが救われた、とでもいうようにやさしい笑顔を浮かべたまま竜巻に飲まれて四散した。
まるでスクリューに巻き込まれていくように。
バレッタが着地して地面に膝をついてはぁはぁ、と肩を揺らしながら大きく息をついた瞬間に、ざぁ、と周りに真っ赤な血の雨が降り注いだ。
「す、すげえ……。 バレッタのヤツ……めちゃくちゃ強いんじゃないか……」
それを見ていたイクローは驚いて思わずそう口にして、あの彼の知る限り呑気そうで気のいい少女だったバレッタが血にまみれて凄惨な姿になっているのを見つめていた。
そしてそのあまりにも凄惨な有様に気づいて思わず口を押えて嘔吐した。
チェリアだったもの、の手や足や内臓やよくわからない肉片がその辺へと無残に散らばっていた。
バレッタは辛そうな顔で片足をひきずるようにしてイクローの元へと戻ってくると、いつものあの、にぱ、という笑顔を見せた。
「大丈夫っすか? センパイ」
「いや、むしろお前が大丈夫なのかよ……?」
イクローはまだ吐き気が止まらない状態でいながらも彼女を気遣ってそう言った。
「すいませんっす……ちょっとカッコ悪いとこを見せちまったっす」
彼女は少ししょんぼりしながらそう言って俯いた。
「そんな事ねえよ……。 お前すげえカッコよかったよ」
イクローはまだ青い顔をしながらそう言って泣きそうな笑顔でバレッタの頭をぽん、と叩いてそのまま撫でた。
「へへ……そんなに褒められたら照れ臭いっす……」
「ああ、今はめちゃくちゃ褒めてる!」
バレッタは頬を赤らめて嬉しそうに笑った。
だがその刹那、バレッタの身体は大きく空中へと打ち上げられた。
「ぐっ……はっ……」
バレッタが苦痛に顔を歪めると彼女はそのまま逆さづりの状態で空中に固定された。
よく見れば蔦のような植物が彼女の体中に巻き付いていた。
「な……?! バレッタ! バレッタぁぁ!!」
イクローは叫んだ。
そして彼の横にマントを着た魔法少女らしい人影が二つ、すぅ、とどこからともなく現れた。
そいつらはイクローの手をつかもうとして、壁のようなものに阻まれて、手を引っ込めた。
「チッ……結界か。 厄介な」
一人がそう言って空中に固定されたバレッタを恨めしそうに眺めた。
「は、離すっす!! 畜生、まだ仲間がいたんすか!」
バレッタは蔦に絡められながら必死にもがいて、そう叫んだ。
ご丁寧に魔神銃のトリガーにかけた指にまで蔦が絡みついていて、それを引く事すらできなかった。
「結界を解くにはあんたを殺すしかないって事ね?」
一人の魔法少女がそう言って空中へ向けて手を伸ばして、そのまま拳を握った。
どうやらこいつが蔦を操っているらしい。
「ぐはぁ……ああああ!!」
蔦に首を絞められてバレッタが呻いた。
ズドン、と何やら低く重い銃声のようなものが遠くで聞こえた、と思った瞬間、そいつの頭は下あごを残して吹き飛んだ。
そいつはそのまま倒れて頭があったあたりに大きな血だまりを作った。
「何? どこから?」
もう一人がそう言って周りを見回した瞬間に、またどこからか銃声が響いて、そいつの頭も弾けた柘榴のように吹き飛んだ。
バレッタは空中からどさり、と地面へと落ちた。
イクローは何が起きたのかわからず、ただ茫然と立ち尽くしていたが、ハッと気づいて慌ててバレッタの元へ駆け寄った。
「お、おい! バレッタ、バレッタ!!」
すると彼を覆っていたほとんど見えない透明の緑色の幕のような結界がだんだんと薄くなって消えていった。
イクローは彼女が自分が死なない限りは結界は消えない、というような事を言っていたのを思い出して顔面を蒼白にして彼女の名を呼び続けた。
「お、おい……まさか……バレッタ! バレッタぁぁ!」
イクローは必死に呼びかけたが彼女はピクリとも動かなかった。
彼が彼女の口元へと耳を近づけると、わずかに呼吸をしているのはわかった。
死んでいるわけではないのだと安心してため息をつきながら彼女をおんぶの形で背負うとイクローは歩き出した。
とりあえず保健室に行こうか、と考えたのだ。
彼には今は他にどうする事もできない。
まだ敵の仲間がいるかも知れない、と用心深く周囲を注意しながらそろそろと中庭を出て校舎へと入ろうとした。
その時、そこから数百メートル離れた校舎の上に立つ者がいた。
手には青く輝く二メートル近くはあろうかという長尺のまるで対戦車ライフルのような、それでいながらあちこちに彫金のような金色の装飾の施されたクラシカルなデザインの不思議な銃を持っている。
その銃口からはうっすらと煙がたなびいていた。
その人物は輝くような水色の髪を風にたなびかせ、それを手でかき上げながら特徴的な水色のルージュに彩られた口元にうっすらと笑みを浮かべた。
「バレッタ……ひとつ貸しよ?」
それはそう言って周囲の結界が消え失せているのを確認し、呪文を詠唱するとその場から、すぅ、と姿を消した。
イクローは保健室へとたどり着くと、失礼します、と声をかけながら戸を開けた。
だが中は無人で、いっそ都合がいい、とバレッタを背負ったまま室内へと入った。
とりあえずベッドに彼女を寝かせてその体を見てみるとそこら中傷だらけではあったが太ももの矢傷以外は大した怪我はしてないようで、ほっと息をついた。
慣れない手つきで傷を消毒して、ガーゼを当て包帯を巻いて、彼女のベッドの傍らで椅子に座って、彼自身も疲れ切っていたのかいつの間にか眠ってしまった。
「センパイ、センパイ……」
そしてそう呼ばれる声でイクローは目を覚ました。
気づけばベッドの布団からでっかいどんぐり眼が覗いていた。
「気が付いたのか、バレッタ。 よかった」
彼がそう言ってため息をつくと、彼女は照れ臭そうに笑った。
「すいませんっす。 すっかりご迷惑をおかけしちまったようっす」
彼女はそう言って体を起こすとぺこり、と頭を下げた。
気づけば彼女の髪と目はいつの間にか茶色に戻っていて、服装も普段の学校の制服へと戻っていた。
「いや、お前は俺を守るために戦ってくれたんだ……俺の方こそごめんな……」
イクローもそう言って頭を下げた。
「いやいやいやいや! これはあたしの任務っすから! センパイが気に病む必要はないんすよ!」
彼女はあわててぶんぶんと手を振った。
イクローはふと壁の時計に目をやって、しまった、という顔をした。
「ヤバイな、下校時間過ぎてる。 今日はタクシーで送ってやるよ。 お前の家はどこだ?」
「ないっす」
「は?」
イクローは目を瞬かせて彼女をじっと見た。
「家はないっすよ? 基本いつもセンパイの家の周囲に結界を張って近くの公園で寝てるっす」
「待て待て待て、それは……大丈夫なのか?」
「任務中っすから」
屈託なく応えるバレッタを見て、イクローは頭を抱えた。
「……わかった。 もういい、お前も俺の家に来い」
「いいんすか?」
「いいもなにも……もう家にはキルカがいるしな」
イクローが言うとバレッタは、ぱぁ、と明るい顔になった。
「ありがとうございますっす!! このご恩は……一生忘れないっす!」
「忘れていいから……ほら、行くぞ。 立てるか?」
「はいっす」
彼はバレッタに肩を貸してやりながら校門を出ると通りがかったタクシーを捕まえて帰宅した。
「絶対おかしいんすよ!!」
家に戻ってキルカに会ったバレッタは眉間にしわを寄せて叫んだ。
今はイクローの部屋でバレッタはキルカによって治癒魔法を受けているところだ。
自分でかければよかったんじゃないのかとイクローが聞いたら自分で自分には治癒魔法はかけられないのだとキルカが教えてくれた。
「おかしいってなにがなの?」
キルカは首を傾げている。
「あたしが戦ったあのチェリアってヤツっす」
「どうおかしいの?」
「あいつの噂は聞いてたっすけど……それにしても強すぎでしたし……それに……」
バレッタはここで一度言葉を切って考え込んだ。
「あいつ、倒しても塩にならなかったんす」
それを聞いてイクローが不思議な顔をした。
「塩ってなんだ?」
するとキルカが説明してくれた。
「わたしたち魔法少女は魔法で殺されると塩の塊になってしまうのよ。 どうしてなのかはわからないのだけど……」
それを聞いてイクローは昨夜会った魔法少女がバレッタの攻撃で白い粉のような物になった事を思い出した。
「あ、あれって……てっきり魔法で動く人形とかだと思ってた……あれが、魔法少女の死……?」
彼はそう言って、また少し吐き気を催したが必死に耐えた。
そういえば今日の戦いでバレッタの流した血も地面に落ちる前に白い粉みたいなものになっていた、と思い出す。
「なのなの」
キルカはこくこくと頷いてバレッタに向き直った。
「塩にならなかったって……それがほんとうならものすごくおかしいの」
「そうなんすよ、姐さん」
そしてバレッタは少し黙った後、こう言った。
「まるで……人間を殺したみたいな……そんな感じっす……」
「どういうことなの……?」
二人が重苦しい雰囲気になっているのを見て、イクローは立ち上がった。
「とりあえず俺コンビニに行ってくるな」
するとバレッタが立ち上がろうとして、痛みに顔をしかめてまた座り込みながら叫んだ。
「あ、あたしもいくっす!」
「お前は休んでろ」
「なの」
イクローとキルカに言われてバレッタはしゅん、と落ち込んだが、すぐに顔を上げてまた叫んだ。
「でも今日も襲われたばっかっすし……一人で出歩くのは危険っすよ!」
「そ、そう言われればそれもそうだな……」
イクローが唸るように言うとキルカがけろりと普通に答えた。
「イキロは大丈夫なの」
「どうして?」
彼が尋ねると、キルカではなくバレッタが何かを思い出したような顔になって声を上げた。
「ああ、あいつがいるんすね?」
バレッタの問いにキルカは頷いた。
「なのなの」
「あいつって?」
「わたしたちのもうひとりの仲間なの」
「ああ、そぅいえばまだ仲間がいるって言ってたっけな……そいつが近くにいるのか?」
イクローは考え込んだ、もしかして今日バレッタを助けてくれたのはそいつなんじゃないのか? と。
「あの子は遠くからずっとイキロの護衛をしていたの」
「そ、そうなのか?」
「なのなの。 だから何かあってもあの子が守ってくれるの。 安心するの」
キルカはそう言ってイクローの頭を触ろうとしたが、届かないので彼の胸あたりをぽふぽふ、と叩いた。
そして彼女は投げキッスのように唇に手を当てると聴こえるか聴こえないかくらいの小さな声で高速で呪文を詠唱してイクローの額に触った。
彼の身体はほとんど見えない透明の赤い膜で包まれた。
「わたしの結界を念のために張っておくの。 これがあれば何があっても大丈夫なの」
「そうか、ありがとよ!」
イクローは明るい顔になると部屋を出て行った。
「あいつの助けを借りなきゃならないとは……このバレッタ、一生の不覚っす……」
バレッタは悔しそうな顔で仰向けに倒れると溜息をついた。
コンビニへの道すがら、イクローはややビクビクしながら周囲を見回して歩いていた。
だが幸いな事にすぐにコンビニにたどり着き、安心しながら店内へと足を踏み入れた。
店内を歩き回っていると、ふとイートインスペースに見知った顔があるのに気づいた。
「あれ? 蒼鉄さんじゃないか」
彼が驚いて声をかけた相手はクラスメイトの蒼鉄ちるるであった。
水色のTシャツに青いショートパンツ、足元は厚底のサンダルというかなりラフな格好で彼女はカフェラテを飲んでいた。
「あら、圓道くん。 こんばんは」
彼女は少し笑顔を見せて挨拶を返した。
「蒼鉄さんって家この辺だっけ?」
「え、ええ……実はそうなの!」
彼女はなぜか少し焦った風に答えた。
「そうか、でもこの辺で会った事ないよね?」
イクローが聞くとちるるは、少し情けない笑顔で言った。
「そういえばそうね! 不思議ね~!」
「まぁ、いいや。 俺ちょっと買い物してくるね」
彼がそう言って一旦そこを立ち去るとちるるは胸を撫でおろして、周囲を見回して、息をついた。
買い物をを終え二人並んで店内を出ると、そのままイクローは危険がないように、といつもの路地ではなく大通りを歩いて帰る事にした。
なぜか普通にそのあとをちるるも付いてくる。
「あれ? 蒼鉄さんの家ってこっち?」
彼が聞くと彼女はにこにこしながらカフェオレのストローを啜りながら頷く。
するとふと八歳~十歳くらいの女の子が二人の元へとぱたぱたと走ってきた。
二人が彼女を不思議そうに見ていると少女は言った。
「おにいさん、わたしと一緒にきて!」
「え? 俺?」
するとちるるが無表情で少女の顔に飲みかけのカフェオレのカップを投げつけた。
びしょ濡れになって唖然とする少女を見てイクローが叫ぶ。
「ちょ、あ、蒼鉄さん?!」
ちるるは背伸びをするように手を上に伸ばして、残念そうに言った。
「あ~あ……同級生、楽しかったのにな……」
イクローと少女がわけがわからず茫然としたまま突っ立っていると、ちるるの伸ばした腕の中にやたら長い対戦車ライフルのような銃がいつの間にか握られていた。
そして彼女の髪はまるで夏の高い空のようなさわやかな水色へ、瞳は深い海のようなコバルトブルーへと変わっていった。
少女がそれを見て目を剥いて叫んだ。
「お、お前は……ティアマトの『魔弾の射手』!!」
「さよなら」
ちるる……だったものは冷たい表情で別れの言葉を言う。
そして素早くその巨大な銃を構えると、いきなりズドン、という低くて重たい音とともに弾丸を発射した。
0
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

中1でEカップって巨乳だから熱く甘く生きたいと思う真理(マリー)と小説家を目指す男子、光(みつ)のラブな日常物語
jun( ̄▽ ̄)ノ
大衆娯楽
中1でバスト92cmのブラはEカップというマリーと小説家を目指す男子、光の日常ラブ
★作品はマリーの語り、一人称で進行します。

17歳男子高生と32歳主婦の境界線
MisakiNonagase
恋愛
32歳主婦のカレンはインスタグラムで20歳大学生の晴人と知り合う。親密な関係となった3度目のデートのときに、晴人が実は17歳の高校2年生だと知る。
カレンと晴人はその後、どうなる?

熟女愛好家ユウスケの青春(熟女漁り)
MisakiNonagase
恋愛
高校まで勉強一筋で大学デビューをしたユウスケは家庭教師の教え子の母親と不倫交際するが、彼にとって彼女とが初の男女交際。そこでユウスケは自分が熟女好きだと自覚する。それからユウスケは戦略と実戦を重ねて、清潔感と聞き上手を武器にたくさんの熟女と付き合うことになるストーリーです。

ママはヤンママ女子高生! ラン&ジュリー!!
オズ研究所《横須賀ストーリー紅白へ》
キャラ文芸
神崎ランの父親の再婚相手は幼馴染みで女子高生の高原ジュリーだった。
ジュリーは金髪美少女だが、地元では『ワイルドビーナス』の異名を取る有名なヤンキーだった。
学校ではジュリーは、ランを使いっ走りにしていた。
当然のようにアゴで使われたが、ジュリーは十八歳になったら結婚する事を告白した。
同級生のジュリーが結婚するなんて信じられない。
ランは密かにジュリーの事を憧れていたので、失恋した気分だ。
そう言えば、昨夜、ランの父親も再婚すると言っていた。
まさかとは思ったが、ランはジュリーに結婚相手を聞くと、ランの父親だと判明した。
その夜、改めて父親とジュリーのふたりは結婚すると報告された。
こうしてジュリーとの同居が決まった。
しかもジュリーの母親、エリカも現われ、ランの家は賑やかになった。

私が王子との結婚式の日に、妹に毒を盛られ、公衆の面前で辱められた。でも今、私は時を戻し、運命を変えに来た。
MayonakaTsuki
恋愛
王子との結婚式の日、私は最も信頼していた人物――自分の妹――に裏切られた。毒を盛られ、公開の場で辱められ、未来の王に拒絶され、私の人生は血と侮辱の中でそこで終わったかのように思えた。しかし、死が私を迎えたとき、不可能なことが起きた――私は同じ回廊で、祭壇の前で目を覚まし、あらゆる涙、嘘、そして一撃の記憶をそのまま覚えていた。今、二度目のチャンスを得た私は、ただ一つの使命を持つ――真実を突き止め、奪われたものを取り戻し、私を破滅させた者たちにその代償を払わせる。もはや、何も以前のままではない。何も許されない。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる