13 / 42
第13話 虚弱聖女と証明
しおりを挟む
「セレスティアル! どうしてここにっ!? それに、今の発言は……」
レイ様が初めてご自身の口で言葉を発した。
彼だけじゃない。ローグ公爵も含めた皆の視線が、私に突き刺さる。
相手がオズベルト殿下だったら、決してしない行動だ。罰せられて辛い目に遭うと分かっているから。
だけど……同じように会議の邪魔をしたとして罰せられたとしても、レイ様を守れるなら、それで良かった。
むしろ、私が罰せられることによって、この不穏な空気がなくなり、良い方向に進むなら、願ったり叶ったりだ。
辛い境遇には慣れてるし、実際、追放されて死ぬ思いだってした。
……怖くなんてない。
「何だ、この女は……国王陛下の御前だぞ。護衛たちは一体何をしている!?」
ローグ公爵の鋭い視線と発言が、私に突き刺さった。しかし、ラメンテが前に進み出たことによって、彼は明らかにうろたえた様子を見せた。
「ごめんね、ローグ卿。僕が中に入れるようにお願いしたんだ。彼女も一緒にね」
「ら、ラメンテ様!?」
ラメンテの姿を見た瞬間、レイ様以外の人々が、跪き、頭を垂れた。この光景を見ると、ラメンテが守護獣様として皆に崇められている偉大なる存在だということが伝わってくる。
……いいえ、これが普通の人たちの態度か。
ラメンテは、レイ様の隣に置かれた椅子の上に飛び乗ると、行儀良く座った。そして金色の瞳をこの部屋にいる人々に向けながら、言葉を発する。
「もう争う必要はないよ。聖女が現れたんだから」
「せ、聖女が!? それは誠ですか、ラメンテ様!!」
「うん、ほんとほんと」
もの凄い圧で訊ねるローグ公爵とは正反対に、頷くラメンテの返答がとっても軽い。
ラメンテの瞳が、私に向けられたかと思うと、こちらに来るように指示された。
皆の突き刺さるような視線に心がひりつきながら、ラメンテの横に並ぶ。
特に、ローグ公爵の視線が痛い。
明らかに、私のことをいぶかしんでいるのが伝わってくる。
しかしラメンテは気にした様子なく、話を続ける。
「先日、僕が姿を変えて城に戻ってきた話は、皆知ってるよね? 中には見た人もいるかもしれないけど……」
ラメンテの言葉に、部屋の人たちが口々に当時のことを話し出した。皆、実際に見たか話を聞いたかしていて、知っているみたい。
皆が知っている事実に満足そうに頷きながら、ラメンテが話を続ける。
「あの姿は、僕の本当の姿なんだ。今までは、力が少なくなっていて、本当の姿を維持することが出来なかった。だけど隣の彼女が……セレスティアルが僕に力を与えてくれたことで、本来の姿に戻ることができたんだ」
「我々は、セレスティアルが本物の聖女であると確信している。だから彼女にラメンテの聖女となってもらえるよう、お願いをしていたのだ。そしてたった今、彼女はラメンテの聖女となることを承諾してくれたというわけだ」
ラメンテの言葉を、レイ様ご自身が引き継いだ。
そう語るレイ様は、何故かとても誇らしげだった。先ほどまでの、暗く怖い表情はない。私が目にし続けた明るいレイ様の姿があった。
しかし、
「そ、それならば、彼女が聖女である証拠をお見せください、ラメンテ様!」
ローグ公爵はかたくなだった。
もちろん彼の気持ちだって分かる。いきなり出てきた女が聖女だと言っても、納得できるわけがないだろうし。
ラメンテは余裕そうに、頷いた。
「もちろん。実際に見て貰った方が早いかもね」
嬉しそうに尻尾をぴんっと立てると、皆をバルコニーに呼び出した。
バルコニーからは、王都が一望できた。
大きな街だと思うけれど、クロラヴィア王国よりも、自然が少なく思えた。王都の向こうも薄ら見えるけど、やはり広がっているのは、緑色ではなく砂と思わしき土色。ところどころ、緑がぽつんと立っているのが見える程度だ。
他も同じようであるなら……確かに国民の生活は大変そう。
改めて守護獣様の存在の偉大さを実感した。
気の毒に思っている私に、ラメンテが言う。
「セレスティアル。僕に力を与えてくれる?」
「え、ええ、分かったわ。だけど……」
「大丈夫です、セレスティアル様。万が一倒れたときは、我々がすぐにお助けいたしますから」
傍にいたルヴィスさんが、そっと助け船を出してくれた。
私の体質のことを知ってくれている人がいると、安心できる。
一抹の不安を残しつつも、私はラメンテの身体に触れた。心に集中し、力がラメンテに流れるよう意識する。
力が注がれていく。
私の中から溢れ出た力が、ラメンテの中にしみこんでいく。
ラメンテが力強く吠えた次の瞬間、
「こ、これはっ!」
皆がどよめいた。
なぜなら、王都がみるみる緑色に色づいていったからだ。それだけじゃない。王都の外も同じように、まるで絵の具を塗ったように、茶色が緑に変わっていく。
凄すぎる!
言葉を失っている私の横で、ラメンテが、
「あれ? おかしいなぁ……城内の自然を蘇らせたつもりだったのに……久しぶりだったから力加減間違った?」
とぼやいていたのが気になったけれど。
私たちの傍に影が落ちた。
レイ様だ。
「セレスティアル、ラメンテ! 大丈夫か!?」
身をかがませてラメンテと視線を同じにすると、同じように不調がないかをチェックされ、次は私の両肩を掴むと、私の身体の色んな箇所に視線を飛ばした。
そして、大きく肩を落とす。
「なんとも無いようだな、二人とも」
「うん、僕は全然大丈夫だよ! セレスティアルが力を与えてくれたから、ちっとも疲れてない」
「わ、私も……」
今でも信じられない。
確かに、私から生まれた力をラメンテに与えた。守護獣シィ様と同じなのに、何故私は疲れて倒れてしまわないんだろう。
不思議に思っていると、ローグ公爵がこちらに近づいてきた。心臓が大きく跳ね上がったけれど、彼が私たちに跪いたのを見てさらに心拍が加速した。
な、なに!?
「ラメンテ様、聖女セレスティアル様、先ほどの私の無礼な発言の数々、どうかお許しください」
「うん、分かってくれたならいいんだよ、ローグ卿。顔を上げて」
驚いている私の横で、ラメンテが嬉しそうに彼を許した。
私も戸惑いながら、ラメンテの言葉に同意し、大きく頷く。
良かった。
私のこと、信じてくれたのね。
ホッと胸をなで下ろしていると、レイ様が私の手をそっととった。優しい表情、柔らかな声色が、私の耳と心に吸い込まれていく。
「ありがとう、セレスティアル。ラメンテの聖女になってくれて」
「い、いえ、そんな……」
レイ様が背負っている重責に比べたら、私なんて……と喉元に引っかかったが、外に出ることはなかった。
だってレイ様が悪者になっていることは、秘密なのだから。
私が途中で発言を止めたのを別の理由と捉えたのか、レイ様が微笑む。
「謙遜しなくていい。辛い思いをしたというのに、聖女の役割を引き受けてくれて、本当に感謝している。それに俺も嬉しい」
「そう、ですか。喜んでいただけて良かったです」
「ああ、本当に嬉しい」
レイ様が心の底から嬉しそうにされている。
本当に、私がラメンテの聖女になって嬉しいのね。ずっと国のために必死になっていたから、喜びもひとしおなのかもしれない。
レイ様はラメンテに静かに訊ねた。
「ラメンテ、もうこの国は大丈夫だな?」
「うん! 大丈夫!!」
「そう、か」
尻尾をぶんぶんと振って喜びを表しているラメンテとは正反対に、レイ様は物静かに微笑まれた。
その笑みに、違和感を抱く。
まるで、消えてしまいそうな儚さなように思えた。
次の日、私の嫌な予感が的中する。
『俺は国王の座を降り、城を出る。後はローグ卿に任せる』
こんな書き置きを残し、レイ様は姿を消した。
レイ様が初めてご自身の口で言葉を発した。
彼だけじゃない。ローグ公爵も含めた皆の視線が、私に突き刺さる。
相手がオズベルト殿下だったら、決してしない行動だ。罰せられて辛い目に遭うと分かっているから。
だけど……同じように会議の邪魔をしたとして罰せられたとしても、レイ様を守れるなら、それで良かった。
むしろ、私が罰せられることによって、この不穏な空気がなくなり、良い方向に進むなら、願ったり叶ったりだ。
辛い境遇には慣れてるし、実際、追放されて死ぬ思いだってした。
……怖くなんてない。
「何だ、この女は……国王陛下の御前だぞ。護衛たちは一体何をしている!?」
ローグ公爵の鋭い視線と発言が、私に突き刺さった。しかし、ラメンテが前に進み出たことによって、彼は明らかにうろたえた様子を見せた。
「ごめんね、ローグ卿。僕が中に入れるようにお願いしたんだ。彼女も一緒にね」
「ら、ラメンテ様!?」
ラメンテの姿を見た瞬間、レイ様以外の人々が、跪き、頭を垂れた。この光景を見ると、ラメンテが守護獣様として皆に崇められている偉大なる存在だということが伝わってくる。
……いいえ、これが普通の人たちの態度か。
ラメンテは、レイ様の隣に置かれた椅子の上に飛び乗ると、行儀良く座った。そして金色の瞳をこの部屋にいる人々に向けながら、言葉を発する。
「もう争う必要はないよ。聖女が現れたんだから」
「せ、聖女が!? それは誠ですか、ラメンテ様!!」
「うん、ほんとほんと」
もの凄い圧で訊ねるローグ公爵とは正反対に、頷くラメンテの返答がとっても軽い。
ラメンテの瞳が、私に向けられたかと思うと、こちらに来るように指示された。
皆の突き刺さるような視線に心がひりつきながら、ラメンテの横に並ぶ。
特に、ローグ公爵の視線が痛い。
明らかに、私のことをいぶかしんでいるのが伝わってくる。
しかしラメンテは気にした様子なく、話を続ける。
「先日、僕が姿を変えて城に戻ってきた話は、皆知ってるよね? 中には見た人もいるかもしれないけど……」
ラメンテの言葉に、部屋の人たちが口々に当時のことを話し出した。皆、実際に見たか話を聞いたかしていて、知っているみたい。
皆が知っている事実に満足そうに頷きながら、ラメンテが話を続ける。
「あの姿は、僕の本当の姿なんだ。今までは、力が少なくなっていて、本当の姿を維持することが出来なかった。だけど隣の彼女が……セレスティアルが僕に力を与えてくれたことで、本来の姿に戻ることができたんだ」
「我々は、セレスティアルが本物の聖女であると確信している。だから彼女にラメンテの聖女となってもらえるよう、お願いをしていたのだ。そしてたった今、彼女はラメンテの聖女となることを承諾してくれたというわけだ」
ラメンテの言葉を、レイ様ご自身が引き継いだ。
そう語るレイ様は、何故かとても誇らしげだった。先ほどまでの、暗く怖い表情はない。私が目にし続けた明るいレイ様の姿があった。
しかし、
「そ、それならば、彼女が聖女である証拠をお見せください、ラメンテ様!」
ローグ公爵はかたくなだった。
もちろん彼の気持ちだって分かる。いきなり出てきた女が聖女だと言っても、納得できるわけがないだろうし。
ラメンテは余裕そうに、頷いた。
「もちろん。実際に見て貰った方が早いかもね」
嬉しそうに尻尾をぴんっと立てると、皆をバルコニーに呼び出した。
バルコニーからは、王都が一望できた。
大きな街だと思うけれど、クロラヴィア王国よりも、自然が少なく思えた。王都の向こうも薄ら見えるけど、やはり広がっているのは、緑色ではなく砂と思わしき土色。ところどころ、緑がぽつんと立っているのが見える程度だ。
他も同じようであるなら……確かに国民の生活は大変そう。
改めて守護獣様の存在の偉大さを実感した。
気の毒に思っている私に、ラメンテが言う。
「セレスティアル。僕に力を与えてくれる?」
「え、ええ、分かったわ。だけど……」
「大丈夫です、セレスティアル様。万が一倒れたときは、我々がすぐにお助けいたしますから」
傍にいたルヴィスさんが、そっと助け船を出してくれた。
私の体質のことを知ってくれている人がいると、安心できる。
一抹の不安を残しつつも、私はラメンテの身体に触れた。心に集中し、力がラメンテに流れるよう意識する。
力が注がれていく。
私の中から溢れ出た力が、ラメンテの中にしみこんでいく。
ラメンテが力強く吠えた次の瞬間、
「こ、これはっ!」
皆がどよめいた。
なぜなら、王都がみるみる緑色に色づいていったからだ。それだけじゃない。王都の外も同じように、まるで絵の具を塗ったように、茶色が緑に変わっていく。
凄すぎる!
言葉を失っている私の横で、ラメンテが、
「あれ? おかしいなぁ……城内の自然を蘇らせたつもりだったのに……久しぶりだったから力加減間違った?」
とぼやいていたのが気になったけれど。
私たちの傍に影が落ちた。
レイ様だ。
「セレスティアル、ラメンテ! 大丈夫か!?」
身をかがませてラメンテと視線を同じにすると、同じように不調がないかをチェックされ、次は私の両肩を掴むと、私の身体の色んな箇所に視線を飛ばした。
そして、大きく肩を落とす。
「なんとも無いようだな、二人とも」
「うん、僕は全然大丈夫だよ! セレスティアルが力を与えてくれたから、ちっとも疲れてない」
「わ、私も……」
今でも信じられない。
確かに、私から生まれた力をラメンテに与えた。守護獣シィ様と同じなのに、何故私は疲れて倒れてしまわないんだろう。
不思議に思っていると、ローグ公爵がこちらに近づいてきた。心臓が大きく跳ね上がったけれど、彼が私たちに跪いたのを見てさらに心拍が加速した。
な、なに!?
「ラメンテ様、聖女セレスティアル様、先ほどの私の無礼な発言の数々、どうかお許しください」
「うん、分かってくれたならいいんだよ、ローグ卿。顔を上げて」
驚いている私の横で、ラメンテが嬉しそうに彼を許した。
私も戸惑いながら、ラメンテの言葉に同意し、大きく頷く。
良かった。
私のこと、信じてくれたのね。
ホッと胸をなで下ろしていると、レイ様が私の手をそっととった。優しい表情、柔らかな声色が、私の耳と心に吸い込まれていく。
「ありがとう、セレスティアル。ラメンテの聖女になってくれて」
「い、いえ、そんな……」
レイ様が背負っている重責に比べたら、私なんて……と喉元に引っかかったが、外に出ることはなかった。
だってレイ様が悪者になっていることは、秘密なのだから。
私が途中で発言を止めたのを別の理由と捉えたのか、レイ様が微笑む。
「謙遜しなくていい。辛い思いをしたというのに、聖女の役割を引き受けてくれて、本当に感謝している。それに俺も嬉しい」
「そう、ですか。喜んでいただけて良かったです」
「ああ、本当に嬉しい」
レイ様が心の底から嬉しそうにされている。
本当に、私がラメンテの聖女になって嬉しいのね。ずっと国のために必死になっていたから、喜びもひとしおなのかもしれない。
レイ様はラメンテに静かに訊ねた。
「ラメンテ、もうこの国は大丈夫だな?」
「うん! 大丈夫!!」
「そう、か」
尻尾をぶんぶんと振って喜びを表しているラメンテとは正反対に、レイ様は物静かに微笑まれた。
その笑みに、違和感を抱く。
まるで、消えてしまいそうな儚さなように思えた。
次の日、私の嫌な予感が的中する。
『俺は国王の座を降り、城を出る。後はローグ卿に任せる』
こんな書き置きを残し、レイ様は姿を消した。
31
あなたにおすすめの小説

タダ働きなので待遇改善を求めて抗議したら、精霊達から『破壊神』と怖れられています。
渡里あずま
ファンタジー
出来損ないの聖女・アガタ。
しかし、精霊の加護を持つ新たな聖女が現れて、王子から婚約破棄された時――彼女は、前世(現代)の記憶を取り戻した。
「それなら、今までの報酬を払って貰えますか?」
※※※
虐げられていた子が、モフモフしながらやりたいことを探す旅に出る話です。
※重複投稿作品※
表紙の使用画像は、AdobeStockのものです。

白い結婚のはずでしたが、いつの間にか選ぶ側になっていました
ふわふわ
恋愛
王太子アレクシオンとの婚約を、
「完璧すぎて可愛げがない」という理不尽な理由で破棄された
侯爵令嬢リオネッタ・ラーヴェンシュタイン。
涙を流しながらも、彼女の内心は静かだった。
――これで、ようやく“選ばれる人生”から解放される。
新たに提示されたのは、冷徹無比と名高い公爵アレスト・グラーフとの
白い結婚という契約。
干渉せず、縛られず、期待もしない――
それは、リオネッタにとって理想的な条件だった。
しかし、穏やかな日々の中で、
彼女は少しずつ気づいていく。
誰かに価値を決められる人生ではなく、
自分で選び、立ち、並ぶという生き方に。
一方、彼女を切り捨てた王太子と王城は、
静かに、しかし確実に崩れていく。
これは、派手な復讐ではない。
何も奪わず、すべてを手に入れた令嬢の物語。

聖女業に飽きて喫茶店開いたんだけど、追放を言い渡されたので辺境に移り住みます!【完結】
青緑 ネトロア
ファンタジー
聖女が喫茶店を開くけど、追放されて辺境に移り住んだ物語と、聖女のいない王都。
———————————————
物語内のノーラとデイジーは同一人物です。
王都の小話は追記予定。
修正を入れることがあるかもしれませんが、作品・物語自体は完結です。

【短編】追放された聖女は王都でちゃっかり暮らしてる「新聖女が王子の子を身ごもった?」結界を守るために元聖女たちが立ち上がる
みねバイヤーン
恋愛
「ジョセフィーヌ、聖なる力を失い、新聖女コレットの力を奪おうとした罪で、そなたを辺境の修道院に追放いたす」謁見の間にルーカス第三王子の声が朗々と響き渡る。
「異議あり!」ジョセフィーヌは間髪を入れず意義を唱え、証言を述べる。
「証言一、とある元聖女マデリーン。殿下は十代の聖女しか興味がない。証言二、とある元聖女ノエミ。殿下は背が高く、ほっそりしてるのに出るとこ出てるのが好き。証言三、とある元聖女オードリー。殿下は、手は出さない、見てるだけ」
「ええーい、やめーい。不敬罪で追放」
追放された元聖女ジョセフィーヌはさっさと王都に戻って、魚屋で働いてる。そんな中、聖女コレットがルーカス殿下の子を身ごもったという噂が。王国の結界を守るため、元聖女たちは立ち上がった。

罰として醜い辺境伯との婚約を命じられましたが、むしろ望むところです! ~私が聖女と同じ力があるからと復縁を迫っても、もう遅い~
上下左右
恋愛
「貴様のような疫病神との婚約は破棄させてもらう!」
触れた魔道具を壊す体質のせいで、三度の婚約破棄を経験した公爵令嬢エリス。家族からも見限られ、罰として鬼将軍クラウス辺境伯への嫁入りを命じられてしまう。
しかしエリスは周囲の評価など意にも介さない。
「顔なんて目と鼻と口がついていれば十分」だと縁談を受け入れる。
だが実際に嫁いでみると、鬼将軍の顔は認識阻害の魔術によって醜くなっていただけで、魔術無力化の特性を持つエリスは、彼が本当は美しい青年だと見抜いていた。
一方、エリスの特異な体質に、元婚約者の伯爵が気づく。それは伝説の聖女と同じ力で、領地の繁栄を約束するものだった。
伯爵は自分から婚約を破棄したにも関わらず、その決定を覆すために復縁するための画策を始めるのだが・・・後悔してももう遅いと、ざまぁな展開に発展していくのだった
本作は不遇だった令嬢が、最恐将軍に溺愛されて、幸せになるまでのハッピーエンドの物語である
※※小説家になろうでも連載中※※

白い結婚のはずでしたが、理屈で抗った結果すべて自分で詰ませました
鷹 綾
恋愛
「完璧すぎて可愛げがない」
そう言われて王太子から婚約破棄された公爵令嬢ノエリア・ヴァンローゼ。
――ですが本人は、わざとらしい嘘泣きで
「よ、よ、よ、よ……遊びでしたのね!」
と大騒ぎしつつ、内心は完全に平常運転。
むしろ彼女の目的はただ一つ。
面倒な恋愛も政治的干渉も避け、平穏に生きること。
そのために選んだのは、冷徹で有能な公爵ヴァルデリオとの
「白い結婚」という、完璧に合理的な契約でした。
――のはずが。
純潔アピール(本人は無自覚)、
排他的な“管理”(本人は合理的判断)、
堂々とした立ち振る舞い(本人は通常運転)。
すべてが「戦略」に見えてしまい、
気づけば周囲は完全包囲。
逃げ道は一つずつ消滅していきます。
本人だけが最後まで言い張ります。
「これは恋ではありませんわ。事故ですの!」
理屈で抗い、理屈で自滅し、
最終的に理屈ごと恋に敗北する――
無自覚戦略無双ヒロインの、
白い結婚(予定)ラブコメディ。
婚約破棄ざまぁ × コメディ強め × 溺愛必至。
最後に負けるのは、世界ではなく――ヒロイン自身です。
-
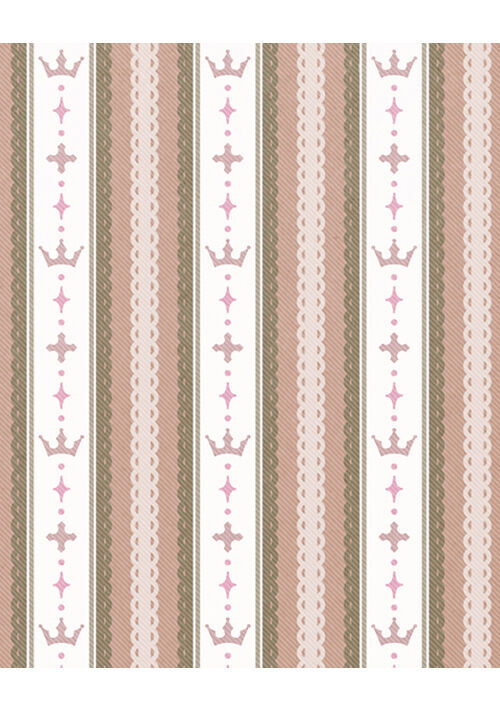
【完結】「神様、辞めました〜竜神の愛し子に冤罪を着せ投獄するような人間なんてもう知らない」
まほりろ
恋愛
王太子アビー・シュトースと聖女カーラ・ノルデン公爵令嬢の結婚式当日。二人が教会での誓いの儀式を終え、教会の扉を開け外に一歩踏み出したとき、国中の壁や窓に不吉な文字が浮かび上がった。
【本日付けで神を辞めることにした】
フラワーシャワーを巻き王太子と王太子妃の結婚を祝おうとしていた参列者は、突然現れた文字に驚きを隠せず固まっている。
国境に壁を築きモンスターの侵入を防ぎ、結界を張り国内にいるモンスターは弱体化させ、雨を降らせ大地を潤し、土地を豊かにし豊作をもたらし、人間の体を強化し、生活が便利になるように魔法の力を授けた、竜神ウィルペアトが消えた。
人々は三カ月前に冤罪を着せ、|罵詈雑言《ばりぞうごん》を浴びせ、石を投げつけ投獄した少女が、本物の【竜の愛し子】だと分かり|戦慄《せんりつ》した。
「Copyright(C)2021-九頭竜坂まほろん」
アルファポリスに先行投稿しています。
表紙素材はあぐりりんこ様よりお借りしております。
2021/12/13、HOTランキング3位、12/14総合ランキング4位、恋愛3位に入りました! ありがとうございます!

「醜い」と婚約破棄された銀鱗の令嬢、氷の悪竜辺境伯に嫁いだら、呪いを癒やす聖女として溺愛されました
黒崎隼人
恋愛
「醜い銀の鱗を持つ呪われた女など、王妃にはふさわしくない!」
衆人環視の夜会で、婚約者の王太子にそう罵られ、アナベルは捨てられた。
実家である公爵家からも疎まれ、孤独に生きてきた彼女に下されたのは、「氷の悪竜」と恐れられる辺境伯・レオニールのもとへ嫁げという非情な王命だった。
彼の体に触れた者は黒い呪いに蝕まれ、死に至るという。それは事実上の死刑宣告。
全てを諦め、死に場所を求めて辺境の地へと赴いたアナベルだったが、そこで待っていたのは冷徹な魔王――ではなく、不器用で誠実な、ひとりの青年だった。
さらに、アナベルが忌み嫌っていた「銀の鱗」には、レオニールの呪いを癒やす聖なる力が秘められていて……?
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















