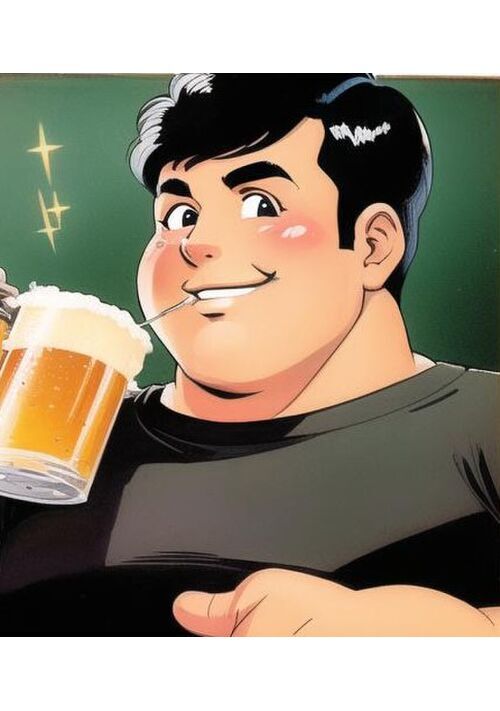19 / 26
3章 最初の僕
19
しおりを挟む
「文字が読めないなら最初からそう言ってくれ!」
「私、下町育ちですよ?庶民なら文字なんて読めないのが普通ですし、知らない方が世間知らずってやつですよ。それなのにあんまりミシェル様が真面目な顔して本を渡してくるもんですから、もうおかしいったらなくて!」
「わかった、もういいから黙って手を動かしてくれ」
文字を読めないと知ってから、僕はレティシアに読み書きを教えていた。自分が本を渡した手前、そのまま放置することもできなかったのだ。
こうなったら徹底的に、色んな教育を施してやる。そして僕への態度が如何に不敬なのかを知れば良いのだ。
マリアは嬉しそうにレティシアをもてなすし、エリックもどこか楽しげだ。
あの少女がこの小屋にいるだけで、不思議と雰囲気が明るいものに変わる。まるで花畑にでもいるかのような錯覚は、どこか本を読んだときの高揚感にも似ていた。
彼女がいると、そこは途端に春になる。まるで彼女がその手で作る花壇のようだ。気が付けば、僕の小屋からは薔薇の花がよく見えるようになっていた。
「……レティシア。どうしてあそこに花壇なんだ」
「え?だってミシェル様、そこの窓際がお好きでしょ?」
確かに、日当たりが良くて程よく風が入る窓際は、僕のお気に入りの読書スペースだ。
「よく知ってるな」
「だっていつもそこにいるもの。だからそこからお花が見えた方がいいかと思って」
「……それだけ?」
「そうですけど?だってここ、ミシェル様のお庭なんでしょ?ミシェル様が見てあげないと、お花が咲く意味がないじゃないですか」
僕ではなく、花をおもんばかっていたらしい。実に彼女らしい理由ではある。
「それにミシェル様も、顔を上げたときの景色は色鮮やかな方がいいでしょう?」
にこりと、レティシアは笑う。花弁のように色鮮やかに、陽だまりのように温かく、レティシアは僕を見つめて頬を緩める。
「……そうだね」
「わぁ、素直だ!」
「一言多いんだよ、君は!いつも!」
レティシアの笑い声が、小屋に響く。自分でも、次第に心が解けている自覚があった。それは長く凍っていた氷を溶かすような、雪解けの陽射しの如く。
穏やかに緩やかに、僕は確かに、彼女に惹かれていた。
一年も経てば、僕の教育の甲斐あって、レティシアは立派な淑女に育っていた。―――― ……見た目だけは。
勝ち気でおてんばな性格がそう簡単に変わるはずもなく、ただ立ち居振る舞いが多少淑やかになっただけのことだ。
しかし本当に、見た目だけは完璧とも言えるだろう。
「ごきげん麗しゅうございます、第三王子殿下」
「………………」
「いかがされました?」
「……いや」
僕に対して傅き、頭を下げるレティシアを見下ろし、不愉快さを感じて眉を顰めた。こうやって正しい礼儀作法で挨拶されるのが、どこか距離があるようで物足りなく感じてしまったのだ。
あの気易い態度の方が、余程心地良い。
「レティシア」
「はい殿下」
「僕に対しての不敬を許す。名前で呼んで良い。敬語も必要ない」
「は……?」
「聞こえなかったか?」
「いや聞こえ……たけど……ミシェル様、頭でも打ったの?」
「そういうところが一言余計なんだ君は!」
そんな気軽さに、息がしやすくなる。
僕と彼女の関係は、このくらい気易くて良いのだ。どうせこんな辺鄙な場所を訪れる人間なんてそう多くないから別に構いやしないだろう。僕以外に彼女を不敬罪と断罪できる貴族はいないのだ。
首を傾げながら僕を見上げるその姿は、羽化したばかりの雛鳥のようだった。
今日もレティシアは花壇に手を入れる。
窓辺から見える一番近い場所に、色とりどりの花を植え、水をやり、甲斐甲斐しく世話を焼く。いつものように本を読み、時折顔を上げれば、花壇とレティシアが色鮮やかにそこに居るのだ。
レティシアはいつの間にか小さな袋を腰に下げるようになった。どうやら、あの日僕が渡した本を持ち歩くための袋らしい。
「それ、ずっとそうしてるつもり?」
「そうよ。だって私の本だもの」
「そうだけど……邪魔だし、汚れない?」
「邪魔だし汚れても私の本だからいいの!大事な物は肌身離さず持つようにしてるのよ」
「……そう」
僕があげた本は、彼女にとって大切な物になったらしい。その事が心をじわじわと温める。心臓が早鐘のように打って落ち着かない。最近は、もう無視できないほど、自分の中でレティシアの存在が大きくなっていた。
「君、15歳になったんだってね」
「そう、多分ね」
「多分って」
「生まれた日がわからないもの。多分15歳ぐらいになったんじゃないかしら」
「……それなら、何か魔法は?」
「当然、何もないわ」
ひらひらと手を振りながらそう答え、レティシアはまた花壇に向き直る。それきり僕も黙って、再び本に目を落とした。
レティシアは魔法を授からなかった。魔法師になることはない。だから、これからも僕らは変わらない。……もう少しぐらいは、この平和を享受していられるだろうか。
レティシアがいない景色は色が足りなくて、物寂しく感じてしまうから。野薔薇のようにしなやかで強い彼女はきっとどこでだって生きていけるだろうけど、僕の方が彼女がいないと駄目になってしまいそうだった。
エリックは、そんな僕たちをなんとも言えない瞳で見つめている。その視線の意味に気が付かないほど鈍感じゃないが、これ以上踏み出す勇気は持ち合わせていなかった。
奇しくも、エリックが望んでいた通りに僕は遅い初恋を知ったのだ。
物語のように劇的じゃない。現実の恋は、緩くじっくりと穏やかに、僕を蝕んで後戻りを許さない。
まるで、遅効性の毒のようだ。気が付けば、僕はレティシアの後ろをついて回るようになっていた。表情がころころと変わる彼女は新しい本のようで、語る声は春風のようで、微笑みは陽だまりだ。その温もりを求めた僕を、レティシアは否定するでもなく受け入れてくれた。
他愛ない雑談も、彼女とするから華やいだものに思えるのだ。
「レティシア、最近街に行ってるんだって?」
「そうよ、お友達が出来たの!」
「へぇ……そうなんだ」
それは初めて知る、嫉妬という感情だった。どす黒く渦巻く己の中の激情に、自分でも驚いたほどだ。
「いつかミシェル様にも紹介してあげる。とっても可愛い子なの。ちょっとミシェル様に似ているかも」
「僕に?」
「そう、すぐ噛みついてくるところとかね!そっくりよ!」
「……犬か何かか?」
「どうかしら?猫かも?」
なんだ、と胸を撫で下ろす。自分の中にこんなに起伏の激しい感情があることが、何故だか酷く人間らしくて嬉しくなった。僕は彼女の側でなら、人らしく息が出来るようだった。
そうして何もない春夏秋冬が、一度巡った。
「レティ、新しい本を買ったんだ。君の感想が聞きたい」
「ねぇミシェル。私って実は庭師なの。仕事させる気はある?」
「手が空いている時でいいんだ。聞かせて」
16歳になったレティシアは、僕に愛称で呼ぶことを許してくれた。それは僕らの距離が縮まったことを表すようで、年甲斐もなく嬉しくなった。
彼女はいつでも僕を柔らかく受け止めてくれる。だから僕も、どうか「ミシェル」と呼んでくれと請うた。
少女の一年は大きく、出会ったばかりの頃はまだ子どもらしくどこかあどけなかったレティシアは、今は咲き誇る薔薇よりもなお美しく咲き誇っていた。身長も伸びたようで、少しだけつむじが近付いたように見える。
彼女の後ろを追ってそのつむじを見下ろすのが、何だかとても楽しかった。
そうして後ろを追いかけてまた季節が一巡り。もう子どもとは呼べなくなった17歳のレティシアは、ある日僕の手を取って艶やかに微笑んだ。
「ねぇミシェル。私、あなたには後ろじゃなくて隣を歩いてもらいたいわ」
「そ……れは、……」
「私の弱虫な王子様は、迎えに行ってあげないと手も繋げないみたいだから」
こんな感情は知らなかった。たくさんの恋を目で追って辿ってきたのに、自分の事になると途端に知らないものになる。僕は本を読んで知ったつもりで、本当は何一つ知らなかったのかもしれない。
「レティシア……僕は、君が好きみたいだ」
「知ってるわ、泣き虫な王子様」
嬉しくて恥ずかしくて、満たされる。落ちた雫は、レティシアの指が掬い上げてくれた。そしてレティシアと繋いだ手から、世界が作り変わるような感覚がする。
「私、下町育ちですよ?庶民なら文字なんて読めないのが普通ですし、知らない方が世間知らずってやつですよ。それなのにあんまりミシェル様が真面目な顔して本を渡してくるもんですから、もうおかしいったらなくて!」
「わかった、もういいから黙って手を動かしてくれ」
文字を読めないと知ってから、僕はレティシアに読み書きを教えていた。自分が本を渡した手前、そのまま放置することもできなかったのだ。
こうなったら徹底的に、色んな教育を施してやる。そして僕への態度が如何に不敬なのかを知れば良いのだ。
マリアは嬉しそうにレティシアをもてなすし、エリックもどこか楽しげだ。
あの少女がこの小屋にいるだけで、不思議と雰囲気が明るいものに変わる。まるで花畑にでもいるかのような錯覚は、どこか本を読んだときの高揚感にも似ていた。
彼女がいると、そこは途端に春になる。まるで彼女がその手で作る花壇のようだ。気が付けば、僕の小屋からは薔薇の花がよく見えるようになっていた。
「……レティシア。どうしてあそこに花壇なんだ」
「え?だってミシェル様、そこの窓際がお好きでしょ?」
確かに、日当たりが良くて程よく風が入る窓際は、僕のお気に入りの読書スペースだ。
「よく知ってるな」
「だっていつもそこにいるもの。だからそこからお花が見えた方がいいかと思って」
「……それだけ?」
「そうですけど?だってここ、ミシェル様のお庭なんでしょ?ミシェル様が見てあげないと、お花が咲く意味がないじゃないですか」
僕ではなく、花をおもんばかっていたらしい。実に彼女らしい理由ではある。
「それにミシェル様も、顔を上げたときの景色は色鮮やかな方がいいでしょう?」
にこりと、レティシアは笑う。花弁のように色鮮やかに、陽だまりのように温かく、レティシアは僕を見つめて頬を緩める。
「……そうだね」
「わぁ、素直だ!」
「一言多いんだよ、君は!いつも!」
レティシアの笑い声が、小屋に響く。自分でも、次第に心が解けている自覚があった。それは長く凍っていた氷を溶かすような、雪解けの陽射しの如く。
穏やかに緩やかに、僕は確かに、彼女に惹かれていた。
一年も経てば、僕の教育の甲斐あって、レティシアは立派な淑女に育っていた。―――― ……見た目だけは。
勝ち気でおてんばな性格がそう簡単に変わるはずもなく、ただ立ち居振る舞いが多少淑やかになっただけのことだ。
しかし本当に、見た目だけは完璧とも言えるだろう。
「ごきげん麗しゅうございます、第三王子殿下」
「………………」
「いかがされました?」
「……いや」
僕に対して傅き、頭を下げるレティシアを見下ろし、不愉快さを感じて眉を顰めた。こうやって正しい礼儀作法で挨拶されるのが、どこか距離があるようで物足りなく感じてしまったのだ。
あの気易い態度の方が、余程心地良い。
「レティシア」
「はい殿下」
「僕に対しての不敬を許す。名前で呼んで良い。敬語も必要ない」
「は……?」
「聞こえなかったか?」
「いや聞こえ……たけど……ミシェル様、頭でも打ったの?」
「そういうところが一言余計なんだ君は!」
そんな気軽さに、息がしやすくなる。
僕と彼女の関係は、このくらい気易くて良いのだ。どうせこんな辺鄙な場所を訪れる人間なんてそう多くないから別に構いやしないだろう。僕以外に彼女を不敬罪と断罪できる貴族はいないのだ。
首を傾げながら僕を見上げるその姿は、羽化したばかりの雛鳥のようだった。
今日もレティシアは花壇に手を入れる。
窓辺から見える一番近い場所に、色とりどりの花を植え、水をやり、甲斐甲斐しく世話を焼く。いつものように本を読み、時折顔を上げれば、花壇とレティシアが色鮮やかにそこに居るのだ。
レティシアはいつの間にか小さな袋を腰に下げるようになった。どうやら、あの日僕が渡した本を持ち歩くための袋らしい。
「それ、ずっとそうしてるつもり?」
「そうよ。だって私の本だもの」
「そうだけど……邪魔だし、汚れない?」
「邪魔だし汚れても私の本だからいいの!大事な物は肌身離さず持つようにしてるのよ」
「……そう」
僕があげた本は、彼女にとって大切な物になったらしい。その事が心をじわじわと温める。心臓が早鐘のように打って落ち着かない。最近は、もう無視できないほど、自分の中でレティシアの存在が大きくなっていた。
「君、15歳になったんだってね」
「そう、多分ね」
「多分って」
「生まれた日がわからないもの。多分15歳ぐらいになったんじゃないかしら」
「……それなら、何か魔法は?」
「当然、何もないわ」
ひらひらと手を振りながらそう答え、レティシアはまた花壇に向き直る。それきり僕も黙って、再び本に目を落とした。
レティシアは魔法を授からなかった。魔法師になることはない。だから、これからも僕らは変わらない。……もう少しぐらいは、この平和を享受していられるだろうか。
レティシアがいない景色は色が足りなくて、物寂しく感じてしまうから。野薔薇のようにしなやかで強い彼女はきっとどこでだって生きていけるだろうけど、僕の方が彼女がいないと駄目になってしまいそうだった。
エリックは、そんな僕たちをなんとも言えない瞳で見つめている。その視線の意味に気が付かないほど鈍感じゃないが、これ以上踏み出す勇気は持ち合わせていなかった。
奇しくも、エリックが望んでいた通りに僕は遅い初恋を知ったのだ。
物語のように劇的じゃない。現実の恋は、緩くじっくりと穏やかに、僕を蝕んで後戻りを許さない。
まるで、遅効性の毒のようだ。気が付けば、僕はレティシアの後ろをついて回るようになっていた。表情がころころと変わる彼女は新しい本のようで、語る声は春風のようで、微笑みは陽だまりだ。その温もりを求めた僕を、レティシアは否定するでもなく受け入れてくれた。
他愛ない雑談も、彼女とするから華やいだものに思えるのだ。
「レティシア、最近街に行ってるんだって?」
「そうよ、お友達が出来たの!」
「へぇ……そうなんだ」
それは初めて知る、嫉妬という感情だった。どす黒く渦巻く己の中の激情に、自分でも驚いたほどだ。
「いつかミシェル様にも紹介してあげる。とっても可愛い子なの。ちょっとミシェル様に似ているかも」
「僕に?」
「そう、すぐ噛みついてくるところとかね!そっくりよ!」
「……犬か何かか?」
「どうかしら?猫かも?」
なんだ、と胸を撫で下ろす。自分の中にこんなに起伏の激しい感情があることが、何故だか酷く人間らしくて嬉しくなった。僕は彼女の側でなら、人らしく息が出来るようだった。
そうして何もない春夏秋冬が、一度巡った。
「レティ、新しい本を買ったんだ。君の感想が聞きたい」
「ねぇミシェル。私って実は庭師なの。仕事させる気はある?」
「手が空いている時でいいんだ。聞かせて」
16歳になったレティシアは、僕に愛称で呼ぶことを許してくれた。それは僕らの距離が縮まったことを表すようで、年甲斐もなく嬉しくなった。
彼女はいつでも僕を柔らかく受け止めてくれる。だから僕も、どうか「ミシェル」と呼んでくれと請うた。
少女の一年は大きく、出会ったばかりの頃はまだ子どもらしくどこかあどけなかったレティシアは、今は咲き誇る薔薇よりもなお美しく咲き誇っていた。身長も伸びたようで、少しだけつむじが近付いたように見える。
彼女の後ろを追ってそのつむじを見下ろすのが、何だかとても楽しかった。
そうして後ろを追いかけてまた季節が一巡り。もう子どもとは呼べなくなった17歳のレティシアは、ある日僕の手を取って艶やかに微笑んだ。
「ねぇミシェル。私、あなたには後ろじゃなくて隣を歩いてもらいたいわ」
「そ……れは、……」
「私の弱虫な王子様は、迎えに行ってあげないと手も繋げないみたいだから」
こんな感情は知らなかった。たくさんの恋を目で追って辿ってきたのに、自分の事になると途端に知らないものになる。僕は本を読んで知ったつもりで、本当は何一つ知らなかったのかもしれない。
「レティシア……僕は、君が好きみたいだ」
「知ってるわ、泣き虫な王子様」
嬉しくて恥ずかしくて、満たされる。落ちた雫は、レティシアの指が掬い上げてくれた。そしてレティシアと繋いだ手から、世界が作り変わるような感覚がする。
応援ありがとうございます!
0
お気に入りに追加
1,023
1 / 5
この作品を読んでいる人はこんな作品も読んでいます!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる