8 / 9
あの日彼女の目には何を映していたのか
しおりを挟む
ほんの些細な変化だった。中里さんと学校内で話すようになったとか、時折メッセージを送り合うようになったとか、そんな些細な変化だった。
ゴールデンウィーク初日の朝、毎日の日課となった朝のニュースを見ていた。母さんは「長い反抗期もこれで終わりなのね」と、呟きながら、出勤していったが、別に反抗期だから朝寝坊だった訳ではない。
重要なのはこれからの予定だ。僕は彼女を知らなすぎる。特に中学時代は。彼女の問題がどこから始まっているか分からない。中学の頃からか? 高校に入ってからか? 過去を調べるのは少し気が引けるが、仕方がない。
ニュースは特に事件はなかった。僕は二階から中学のアルバムを取り出し、階段を駆け降りて、中里さんと同クラスだった友達に片っ端から連絡をかけようとした。スマホの画面上にメッセージが入った。
『おは。今日の補講いくー?』
中里さんだ。彼女のメッセージがイメージと違うことを最近知った。地はこういう子だったと思う。それにしても補講とは。たしかに先生が言っていた気がする。参加は自由。内容は一年、二年の復習だったはずだ。すぐさま、僕は返信した。
『もちろん』
既読はすぐについた。これでいい。僕は急いで二階に戻り、着る予定のなかった制服に着替え、裏口から家を出た。
信号待ちでふと思い立ち、高木も誘ってみたが、断られた。予備校で講習があるとのことだった。
『二人の方がよく話ができるだろう』
締められたメッセージを見て、画面の向こうで笑っている高木をありありと想像でき、少し憎らしくなった。
「あれ? 早いね。補講は午後からなのに」と、彼女は驚いた声で言った。
「あー、間違えた」どうやら、時間を間違えたようだ。
正直に答える。気の利いた言葉を考える余裕はなかった。
「あっ、そうか。明日は午前からだもんね。うん。でも……、うん? そうなんだ……」
初めは納得した様子だったが、途中、違和感を覚えたのか、最後は目を細めながら言った。無言で自分の席に着いた。沈黙。僕はいそいそとカバンから数学の教科書とノートを取り出し、ゴールデンウィークの課題をやり始めた。
数学は一度集中してしまえば、実に没頭しやすい教科である。
どれくらい時間が経っただろうか。隣に気配を感じ、顔を上げると中里さんが立っていた。何か言いたそうな顔で、両手でノートを持っている。
「どうしたの?」
「丹野くん、数学得意だったよね?」
「得意というよりも、性格に合っているんだよね」
「それを得意というのよ」彼女は笑いながら、自分のノートを見せてきた。
「この問題教えてくれない?」
「ああ、なるほど」
渡されたノートを見ると、数学的帰納法の問題のようだ。
「その問題ならちょうど解いたところだ」
「本当? よかったぁ」
中里さんは、ほっとするように手を合わせる。隣の席に座り、椅子を近づける。ふわりと日向のような匂いが僕の鼻を抜けた。
「それで?」と、上目遣いで訊いてくる。
「ここまで出来ているなら、後は式の形を変えるだけだよ。途中式のこの部分をカッコで括れば……ほら、ここと同じになった」
僕が途中式から先を書く。綺麗な字と汚い字が合わさって式が完成する。彼女は食い入るように証明を眺めていた。
「あっ、なるほど。そっかぁ、全然気が付かなかった」
式の変形に納得した彼女に僕は声をかけた。
「あのさ」
「なに? ……っ」
顔を上げた彼女と目が合った。距離は思っていたよりも近く、僕らは少し離れた。彼女は何故か髪を触っていた。
「中里さんはどこか行きたい大学でもあるの?」
「どうして?」
「いつも、朝早くから来て勉強してるから」
片目で彼女を見る。僕の無理矢理出したとぼけた声に、少し止まった後、くすっと笑った。
「……私、看護師になりたくて、理系を選んだんだけど、やっぱり大変ね。かと言って、私大には行けないし、浪人もしたくない。夢が遠のいていく気分よ」
中里さんはため息をつく。私大の看護学部なら文系科目でもいけるが、国公立大は理系科目が必須だ。
「たしか、小学生の頃からの夢だったよね?」
記憶を弄り、僕は言った。カンニングではない。予習だ。
「よく覚えてるね」
「久しぶりに、小学校のアルバムを見たんだ。それでさ」
「あー、それで。恥ずかしいなぁ。ちなみに丹野くんはなんだったの?」
「科学者」早口に言った。
「大雑把ね。まぁ、小学生だから仕方ないか」
「そこなんだよね。具体性がない。そもそもさ、研究で食べていけるのは本当一握りの天才たちだけだよ。大体がサラリーマンに落ち着くわけだ。だとしたら、学部に意味はあるのかなって思うよ。大学名で選んだ方がいい企業に入れるんじゃないかな」
僕の独白に中里さんは虚をつかれたような顔をしていた。
「ふーん、もっと子供っぽいと思っていたけど、結構リアリストなんだね」
僕がリアリストに見えるのは、明らかに夢の影響だった。
「僕はもっと中里さんが大人だと思ってたけどね。メッセージを見ると子供っぽいんだなって思うよ」
「いや、あれはっ! あんまり、メッセージ送ったことないし、顔文字もどうかなーって思ってたからで……」
最後が尻すぼみになる。上目遣いで睨まれるが、僕は可愛いと思ってしまった。僕もまだまだ子供だった。
チャイムが鳴り、中里さんが立ち上がった。
「じゃあ、補講は一階の他目的教室だから気をつけてね」と、ノートを抱えながら言って、自分の席に戻る。
そういえば、昼食を用意していなかった。ため息をついて、僕も立ち上がった。ちらりと見えた彼女のお弁当は、可愛らしいミンク色の箱に似合わず、中身は簡素だったのが印象的だった。
他目的教室は普通の教室の倍の広さだったが、補講には他のクラスの同級生も来ていて、ほぼ満席の状態だった。授業が終わると緊張の糸が切れたように、皆喋り始め、帰る支度をしていた。僕は席に着いたまま中里さんの様子を伺っていた。彼女は新美先生と何やら話をしていた。
「それじゃあ、今年もよろしくね、中里さん」
「分かりました」
新美先生は笑顔のまま、学生の減った教室を出ていった。僕は先生が出ていくのを片目で見送りながら、中里さんに近づいた。
「新美先生となに話してたの?」
「うん? 文化祭のことでちょっとね」
彼女はノートと教科書を閉じ、トントンと机の上で揃えた。人が消えたいなくなった教室に音が響く。
「文化祭? ……もしかして、垂れ幕のこと?」
僕の言葉に彼女はちょっと眉を上げ、目を見開く。
「すごいね、知ってたの?」
「たまたま、だよ。高木から聞いたんだ」
「今年もね、お願いされちゃった」
「三年連続じゃない?」
「新美先生ね、私の字が好きなのよ。だから、テストの時もちょっと点数が甘い時があるの」
悪戯っぽく笑う彼女はどことなく嬉しそうな表情だった。
「僕なんか、五が八に見えるからって減点されたことあるのに」
「それは、わかんなくもないかな」僕の字を思い出したのか彼女は笑って言った。
「今年も書くの?」
「うん。そのつもり」
嬉しそうな彼女を見て「やめた方がいい」とは言えなかった。
少し言葉を詰まらせた僕に勘づいたのか、彼女は「んー?」と唸ってから思い付いたように言った。
「あっ、わかった。あれでしょ? 屋上に行ってみたいんでしょ? 登ったことある?」
「ないよ。 まあ、できるなら登ってみたい」
「じゃあ、飾るときになったら呼ぶね」
「僕はいつでもいいよ」
「本当に気持ちがいいから。ほら、この学校高台にあるでしょ? 夕陽も綺麗なの」
彼女はカバンからスマホを取り出し、写真を見せてきた。そこには、僕が見たことない苅屋市の街並みが広がっていた。ちょうど夕陽の方角には小さく僕らの町が写っている。
「ね? 綺麗でしょ?」
「そうだね」
画面を見つめる彼女。
あの日、彼女はその瞳になにを映していたのだろう。
僕は知らない。
ゴールデンウィーク初日の朝、毎日の日課となった朝のニュースを見ていた。母さんは「長い反抗期もこれで終わりなのね」と、呟きながら、出勤していったが、別に反抗期だから朝寝坊だった訳ではない。
重要なのはこれからの予定だ。僕は彼女を知らなすぎる。特に中学時代は。彼女の問題がどこから始まっているか分からない。中学の頃からか? 高校に入ってからか? 過去を調べるのは少し気が引けるが、仕方がない。
ニュースは特に事件はなかった。僕は二階から中学のアルバムを取り出し、階段を駆け降りて、中里さんと同クラスだった友達に片っ端から連絡をかけようとした。スマホの画面上にメッセージが入った。
『おは。今日の補講いくー?』
中里さんだ。彼女のメッセージがイメージと違うことを最近知った。地はこういう子だったと思う。それにしても補講とは。たしかに先生が言っていた気がする。参加は自由。内容は一年、二年の復習だったはずだ。すぐさま、僕は返信した。
『もちろん』
既読はすぐについた。これでいい。僕は急いで二階に戻り、着る予定のなかった制服に着替え、裏口から家を出た。
信号待ちでふと思い立ち、高木も誘ってみたが、断られた。予備校で講習があるとのことだった。
『二人の方がよく話ができるだろう』
締められたメッセージを見て、画面の向こうで笑っている高木をありありと想像でき、少し憎らしくなった。
「あれ? 早いね。補講は午後からなのに」と、彼女は驚いた声で言った。
「あー、間違えた」どうやら、時間を間違えたようだ。
正直に答える。気の利いた言葉を考える余裕はなかった。
「あっ、そうか。明日は午前からだもんね。うん。でも……、うん? そうなんだ……」
初めは納得した様子だったが、途中、違和感を覚えたのか、最後は目を細めながら言った。無言で自分の席に着いた。沈黙。僕はいそいそとカバンから数学の教科書とノートを取り出し、ゴールデンウィークの課題をやり始めた。
数学は一度集中してしまえば、実に没頭しやすい教科である。
どれくらい時間が経っただろうか。隣に気配を感じ、顔を上げると中里さんが立っていた。何か言いたそうな顔で、両手でノートを持っている。
「どうしたの?」
「丹野くん、数学得意だったよね?」
「得意というよりも、性格に合っているんだよね」
「それを得意というのよ」彼女は笑いながら、自分のノートを見せてきた。
「この問題教えてくれない?」
「ああ、なるほど」
渡されたノートを見ると、数学的帰納法の問題のようだ。
「その問題ならちょうど解いたところだ」
「本当? よかったぁ」
中里さんは、ほっとするように手を合わせる。隣の席に座り、椅子を近づける。ふわりと日向のような匂いが僕の鼻を抜けた。
「それで?」と、上目遣いで訊いてくる。
「ここまで出来ているなら、後は式の形を変えるだけだよ。途中式のこの部分をカッコで括れば……ほら、ここと同じになった」
僕が途中式から先を書く。綺麗な字と汚い字が合わさって式が完成する。彼女は食い入るように証明を眺めていた。
「あっ、なるほど。そっかぁ、全然気が付かなかった」
式の変形に納得した彼女に僕は声をかけた。
「あのさ」
「なに? ……っ」
顔を上げた彼女と目が合った。距離は思っていたよりも近く、僕らは少し離れた。彼女は何故か髪を触っていた。
「中里さんはどこか行きたい大学でもあるの?」
「どうして?」
「いつも、朝早くから来て勉強してるから」
片目で彼女を見る。僕の無理矢理出したとぼけた声に、少し止まった後、くすっと笑った。
「……私、看護師になりたくて、理系を選んだんだけど、やっぱり大変ね。かと言って、私大には行けないし、浪人もしたくない。夢が遠のいていく気分よ」
中里さんはため息をつく。私大の看護学部なら文系科目でもいけるが、国公立大は理系科目が必須だ。
「たしか、小学生の頃からの夢だったよね?」
記憶を弄り、僕は言った。カンニングではない。予習だ。
「よく覚えてるね」
「久しぶりに、小学校のアルバムを見たんだ。それでさ」
「あー、それで。恥ずかしいなぁ。ちなみに丹野くんはなんだったの?」
「科学者」早口に言った。
「大雑把ね。まぁ、小学生だから仕方ないか」
「そこなんだよね。具体性がない。そもそもさ、研究で食べていけるのは本当一握りの天才たちだけだよ。大体がサラリーマンに落ち着くわけだ。だとしたら、学部に意味はあるのかなって思うよ。大学名で選んだ方がいい企業に入れるんじゃないかな」
僕の独白に中里さんは虚をつかれたような顔をしていた。
「ふーん、もっと子供っぽいと思っていたけど、結構リアリストなんだね」
僕がリアリストに見えるのは、明らかに夢の影響だった。
「僕はもっと中里さんが大人だと思ってたけどね。メッセージを見ると子供っぽいんだなって思うよ」
「いや、あれはっ! あんまり、メッセージ送ったことないし、顔文字もどうかなーって思ってたからで……」
最後が尻すぼみになる。上目遣いで睨まれるが、僕は可愛いと思ってしまった。僕もまだまだ子供だった。
チャイムが鳴り、中里さんが立ち上がった。
「じゃあ、補講は一階の他目的教室だから気をつけてね」と、ノートを抱えながら言って、自分の席に戻る。
そういえば、昼食を用意していなかった。ため息をついて、僕も立ち上がった。ちらりと見えた彼女のお弁当は、可愛らしいミンク色の箱に似合わず、中身は簡素だったのが印象的だった。
他目的教室は普通の教室の倍の広さだったが、補講には他のクラスの同級生も来ていて、ほぼ満席の状態だった。授業が終わると緊張の糸が切れたように、皆喋り始め、帰る支度をしていた。僕は席に着いたまま中里さんの様子を伺っていた。彼女は新美先生と何やら話をしていた。
「それじゃあ、今年もよろしくね、中里さん」
「分かりました」
新美先生は笑顔のまま、学生の減った教室を出ていった。僕は先生が出ていくのを片目で見送りながら、中里さんに近づいた。
「新美先生となに話してたの?」
「うん? 文化祭のことでちょっとね」
彼女はノートと教科書を閉じ、トントンと机の上で揃えた。人が消えたいなくなった教室に音が響く。
「文化祭? ……もしかして、垂れ幕のこと?」
僕の言葉に彼女はちょっと眉を上げ、目を見開く。
「すごいね、知ってたの?」
「たまたま、だよ。高木から聞いたんだ」
「今年もね、お願いされちゃった」
「三年連続じゃない?」
「新美先生ね、私の字が好きなのよ。だから、テストの時もちょっと点数が甘い時があるの」
悪戯っぽく笑う彼女はどことなく嬉しそうな表情だった。
「僕なんか、五が八に見えるからって減点されたことあるのに」
「それは、わかんなくもないかな」僕の字を思い出したのか彼女は笑って言った。
「今年も書くの?」
「うん。そのつもり」
嬉しそうな彼女を見て「やめた方がいい」とは言えなかった。
少し言葉を詰まらせた僕に勘づいたのか、彼女は「んー?」と唸ってから思い付いたように言った。
「あっ、わかった。あれでしょ? 屋上に行ってみたいんでしょ? 登ったことある?」
「ないよ。 まあ、できるなら登ってみたい」
「じゃあ、飾るときになったら呼ぶね」
「僕はいつでもいいよ」
「本当に気持ちがいいから。ほら、この学校高台にあるでしょ? 夕陽も綺麗なの」
彼女はカバンからスマホを取り出し、写真を見せてきた。そこには、僕が見たことない苅屋市の街並みが広がっていた。ちょうど夕陽の方角には小さく僕らの町が写っている。
「ね? 綺麗でしょ?」
「そうだね」
画面を見つめる彼女。
あの日、彼女はその瞳になにを映していたのだろう。
僕は知らない。
0
あなたにおすすめの小説

フラレたばかりのダメヒロインを応援したら修羅場が発生してしまった件
遊馬友仁
青春
校内ぼっちの立花宗重は、クラス委員の上坂部葉月が幼馴染にフラれる場面を目撃してしまう。さらに、葉月の恋敵である転校生・名和リッカの思惑を知った宗重は、葉月に想いを諦めるな、と助言し、叔母のワカ姉やクラスメートの大島睦月たちの協力を得ながら、葉月と幼馴染との仲を取りもつべく行動しはじめる。
一方、宗重と葉月の行動に気付いたリッカは、「私から彼を奪えるもの奪ってみれば?」と、挑発してきた!
宗重の前では、態度を豹変させる転校生の真意は、はたして―――!?
※本作は、2024年に投稿した『負けヒロインに花束を』を大幅にリニューアルした作品です。

後日譚追加【完結】冤罪で追放された俺、真実の魔法で無実を証明したら手のひら返しの嵐!! でももう遅い、王都ごと見捨てて自由に生きます
なみゆき
ファンタジー
魔王を討ったはずの俺は、冤罪で追放された。 功績は奪われ、婚約は破棄され、裏切り者の烙印を押された。 信じてくれる者は、誰一人いない——そう思っていた。
だが、辺境で出会った古代魔導と、ただ一人俺を信じてくれた彼女が、すべてを変えた。 婚礼と処刑が重なるその日、真実をつきつけ、俺は、王都に“ざまぁ”を叩きつける。
……でも、もう復讐には興味がない。 俺が欲しかったのは、名誉でも地位でもなく、信じてくれる人だった。
これは、ざまぁの果てに静かな勝利を選んだ、元英雄の物語。

冤罪で辺境に幽閉された第4王子
satomi
ファンタジー
主人公・アンドリュート=ラルラは冤罪で辺境に幽閉されることになったわけだが…。
「辺境に幽閉とは、辺境で生きている人間を何だと思っているんだ!辺境は不要な人間を送る場所じゃない!」と、辺境伯は怒っているし当然のことだろう。元から辺境で暮している方々は決して不要な方ではないし、‘辺境に幽閉’というのはなんとも辺境に暮らしている方々にしてみれば、喧嘩売ってんの?となる。
辺境伯の娘さんと婚約という話だから辺境伯の主人公へのあたりも結構なものだけど、娘さんは美人だから万事OK。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。
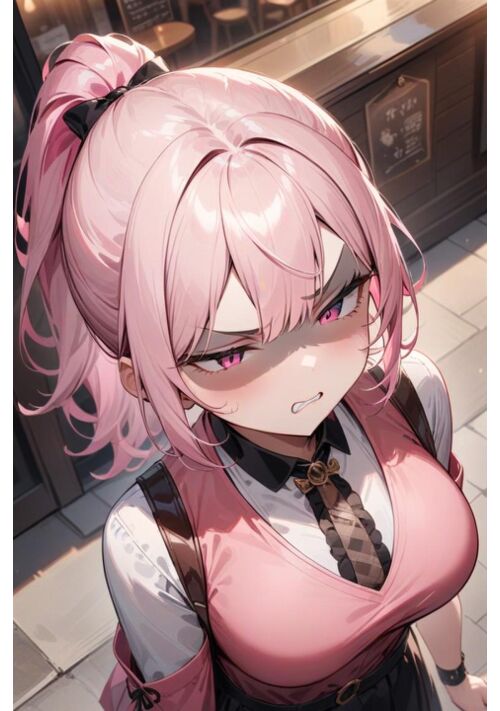
【朗報】俺をこっぴどく振った幼馴染がレンカノしてたので2時間15,000円でレンタルしてみました
田中又雄
恋愛
俺には幼稚園の頃からの幼馴染がいた。
しかし、高校進学にあたり、別々の高校に行くことになったため、中学卒業のタイミングで思い切って告白してみた。
だが、返ってきたのは…「はぁ!?誰があんたみたいなのと付き合うのよ!」という酷い言葉だった。
それからは家は近所だったが、それからは一度も話をすることもなく、高校を卒業して、俺たちは同じ大学に行くことになった。
そんなある日、とある噂を聞いた。
どうやら、あいつがレンタル彼女なるものを始めたとか…。
気持ち悪いと思いながらも俺は予約を入れるのであった。
そうして、デート当日。
待ち合わせ場所に着くと、後ろから彼女がやってきた。
「あ、ごめんね!待たせちゃっ…た…よ…ね」と、どんどんと顔が青ざめる。
「…待ってないよ。マイハニー」
「なっ…!?なんであんたが…!ばっかじゃないの!?」
「あんた…?何を言っているんだい?彼女が彼氏にあんたとか言わないよね?」
「頭おかしいんじゃないの…」
そうして、ドン引きする幼馴染と俺は初デートをするのだった。

戦場帰りの俺が隠居しようとしたら、最強の美少女たちに囲まれて逃げ場がなくなった件
さん
ファンタジー
戦場で命を削り、帝国最強部隊を率いた男――ラル。
数々の激戦を生き抜き、任務を終えた彼は、
今は辺境の地に建てられた静かな屋敷で、
わずかな安寧を求めて暮らしている……はずだった。
彼のそばには、かつて命を懸けて彼を支えた、最強の少女たち。
それぞれの立場で戦い、支え、尽くしてきた――ただ、すべてはラルのために。
今では彼の屋敷に集い、仕え、そして溺愛している。
「ラルさまさえいれば、わたくしは他に何もいりませんわ!」
「ラル様…私だけを見ていてください。誰よりも、ずっとずっと……」
「ねぇラル君、その人の名前……まだ覚えてるの?」
「ラル、そんなに気にしなくていいよ!ミアがいるから大丈夫だよねっ!」
命がけの戦場より、ヒロインたちの“甘くて圧が強い愛情”のほうが数倍キケン!?
順番待ちの寝床争奪戦、過去の恋の追及、圧バトル修羅場――
ラルの平穏な日常は、最強で一途な彼女たちに包囲されて崩壊寸前。
これは――
【過去の傷を背負い静かに生きようとする男】と
【彼を神のように慕う最強少女たち】が織りなす、
“甘くて逃げ場のない生活”の物語。
――戦場よりも生き延びるのが難しいのは、愛されすぎる日常だった。
※表紙のキャラはエリスのイメージ画です。

俺を振ったはずの腐れ縁幼馴染が、俺に告白してきました。
true177
恋愛
一年前、伊藤 健介(いとう けんすけ)は幼馴染の多田 悠奈(ただ ゆうな)に振られた。それも、心無い手紙を下駄箱に入れられて。
それ以来悠奈を避けるようになっていた健介だが、二年生に進級した春になって悠奈がいきなり告白を仕掛けてきた。
これはハニートラップか、一年前の出来事を忘れてしまっているのか……。ともかく、健介は断った。
日常が一変したのは、それからである。やたらと悠奈が絡んでくるようになったのだ。
彼女の狙いは、いったい何なのだろうか……。
※小説家になろう、ハーメルンにも同一作品を投稿しています。
※内部進行完結済みです。毎日連載です。

クラスのマドンナがなぜか俺のメイドになっていた件について
沢田美
恋愛
名家の御曹司として何不自由ない生活を送りながらも、内気で陰気な性格のせいで孤独に生きてきた裕貴真一郎(ゆうき しんいちろう)。
かつてのいじめが原因で、彼は1年間も学校から遠ざかっていた。
しかし、久しぶりに登校したその日――彼は運命の出会いを果たす。
現れたのは、まるで絵から飛び出してきたかのような美少女。
その瞳にはどこかミステリアスな輝きが宿り、真一郎の心をかき乱していく。
「今日から私、あなたのメイドになります!」
なんと彼女は、突然メイドとして彼の家で働くことに!?
謎めいた美少女と陰キャ御曹司の、予測不能な主従ラブコメが幕を開ける!
カクヨム、小説家になろうの方でも連載しています!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















