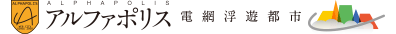この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説


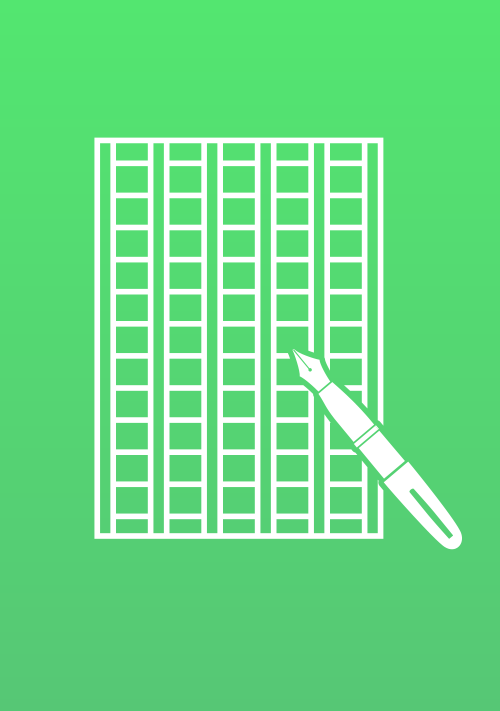
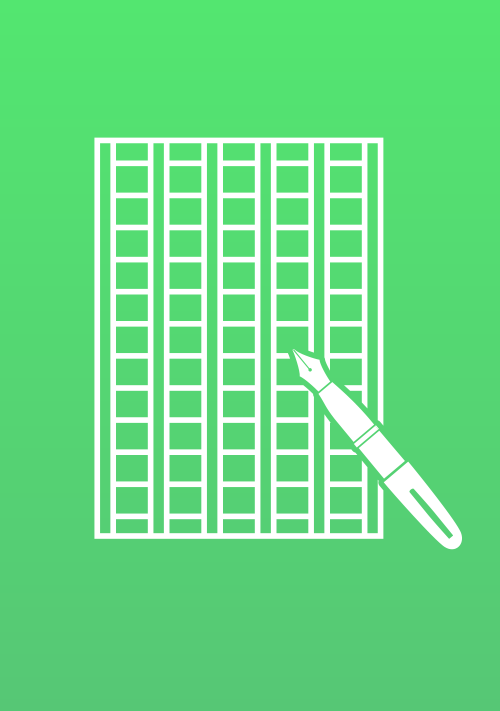
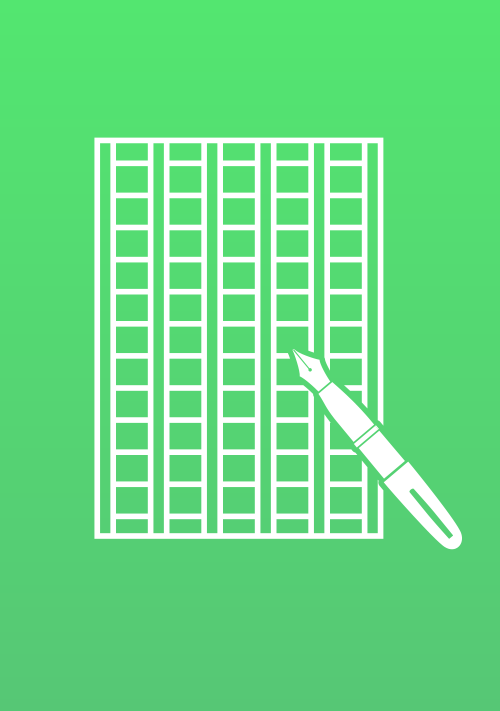



本物の夫は愛人に夢中なので、影武者とだけ愛し合います
こじまき
恋愛
幼い頃から許嫁だった王太子ヴァレリアンと結婚した公爵令嬢ディアーヌ。しかしヴァレリアンは身分の低い男爵令嬢に夢中で、初夜をすっぽかしてしまう。代わりに寝室にいたのは、彼そっくりの影武者…生まれたときに存在を消された双子の弟ルイだった。
※「小説家になろう」にも投稿しています
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる