160 / 336
第二部 四季姫進化の巻
第十三章 秋姫進化 1
しおりを挟む
一
今から六年前。
長月 楸は、生まれて初めて妖怪を見た。
小学一年生の秋。
連休の最終日。長月一家は揃って行楽に出掛けた。
楸の家族は父の柿太郎と母の桔梗。三つ年下の弟、葵の四人だ。
運転好きの父の車でやって来た場所は、四季ヶ丘の南の端にある、広い自然公園だった。
敷地内に大きな湖があり、峠道や原生林が広がる、静かで穏やかな場所だった。
秋めいた季節になると、園内に植えられた銀杏や紅葉が色濃く染まり、一面に彩りを添えた。湖の水面にひらりと落ちて、船みたいに浮かぶ姿もまた、風流だった。
公園の散歩を楽しみ、一家は車で帰路につこうとしていた。
時刻は午後五時を回ったくらい。日の入りがだんだん早くなり、既に夕闇が迫る頃となっていた。
「公園の紅葉、綺麗どしたなぁ」
「春には、桜も満開らしい。次は花見やな」
父は運転席、母は助手席で、今日の散策の感想や次の予定を、楽しそうに語っていた。
「葵。運転中は、立ち上がったらあかんどす」
楸は後ろの席で、まだ幼い弟の葵をあやしていた。四つになったばかりの葵は、まだまだ手のかかる歳だ。楸は率先して、可愛い弟の世話を焼いていた。
急なカーブの多い峠道に差し掛かった頃。突然、柿太郎が「危ない!」と声を張り上げた。同時に急ブレーキが掛けられ、シートベルトに支えられながらも、体が激しく前のめりになった。
楸はびっくりして、頭の中が一瞬、真っ白になる。葵が泣き出す声で我に返った。楸は慌てて葵のシートベルトを外し、抱き上げて桔梗に渡した。
「お父はん、どないしやはったんや?」
葵を抱いて宥めながら、桔梗は不安そうに尋ねる。
「急に、車の前に誰かが……」
柿太郎はドアを開けて頭を突き出し、前方を確認した。楸も、身を乗り出して車の前を見る。ヘッドライトに照らされた道路で、人が尻餅をついて座りこんでいた。
「大丈夫ですか!? お怪我は」
車から飛び出し、柿太郎はその人物の元へ駆け寄った。ハイキング客だろう、小さなリュックを担いだ、壮年の男だった。
「いやぁ、大変、失礼いたしました。急いでいたもので、車に気付かずに飛び出してしまって」
男は己の非を詫びて、頭を下げてきた。柔らかな物腰の、優しそうな人だった。
怪我もなさそうだったし、柿太郎は安心して男と会話を続けた。
「そんなに慌てて、どちらへ?」
「実は今夜、可愛い姪っ子の結婚式がありましてね。祝いの品が決まらなくて。とりあえず麓に行こうと急いでいたのです」
男は山の向こう側に住んでいると説明した。
話が盛り上がり、人の良い柿太郎は、男に笑顔で祝福を送った。
「そら、おめでとうございます。こんな場所で会ったんも、何かの縁です、一緒に乗っていかれませんか? もうじき、日も落ちます。夜道は危ないですよ」
親切心から同乗を勧めたが、男はやんわりと断ってきた。にやりと、目を細めて笑う。その顔を見た途端、楸の背筋に寒気が走った。
「いや、結構です。崖を下れば、麓まで一直線ですし」
直後。突然、車が前進しはじめた。運転席には誰も乗っていないのに、どんどん進んでいく。
柿太郎の慌てる声、桔梗の悲鳴が響く。進行方向の先は、切り立った崖だ。ガードレールがあったはずなのに、なぜかなくなっていた。
柿太郎が車に飛び乗ってブレーキを踏むが、止まる気配がない。
「あかん、みんな、降りるんや!」
諦めてみんなを逃がそうとしたが、手遅れだった。
四人を乗せた車は、崖下へと一直線に落下した。
激しく車が破壊される音。体に走る痛みと衝撃。
車の間に挟まれながらも、楸は辛うじて意識を保ち、朦朧としながら惨状を目の当たりにしていた。
柿太郎は車から投げ出され、鬱蒼と繁る木々の間に倒れ込んでいた。桔梗は、葵を強く抱きしめたまま、助手席で、ぐったりと項垂れていた。葵の泣き声も、聞こえてこない。
ぐしゃぐしゃになった車の側に、誰かが歩いてくる音がした。
さっきの男だ。楸は助けを求めようとしたが、声が出なかった。
誰が見ても、酷い惨劇だ。きっとすぐに、この男が救急車を呼んでくれる。
そう信じていたのに、男の行動は奇妙かつ、非人道的だった。
「ありがたいねぇ。麓まで行かなくても、よい人魂が手に入った」
男は不気味な笑みを浮かべながら、倒れて動かない父の頭を掴んで、揺らしはじめた。やがて、柿太郎の額から、ぼんやりと光る青白い塊が飛び出した。
魚みたいに、ゆらゆらと動く塊を、男は素手でがっしりと掴んで、リュックに詰め込んだ。
続いて、桔梗と葵にも同じ動作を行い、二人の中から出てきた青白いものを捕獲していった。
最後に、男は楸にも近付いてきた。頭に触れようとしたが、楸がまだ意識を保っていると気付き、手を引っ込めた。
「まだ一人、生き残っていたか。すぐに楽にしてやるからね」
男は、楸に向かって妙な力を送りはじめた。だんだんと息苦しくなり、目を開けていられなくなる。
薄れゆく意識の中で、何度も鳴る鐘の音を聞いた。
男の耳にも音が聞こえたらしく、急に慌てだした。
「いかん。宴が始まる。三つで我慢するか」
急いだ様子で、男はその場から立ち去って行った。
楸は茫然と、男の向かった方角を見つめていた。
山の木々の合間に、怪しげな光が、列を成して続いていく。さっきの鐘の音も、行列のある場所から響いてきた。
黒い着物を纏った狐達が、わいわいと騒ぎながら歩いていく。行列の中心では、立派なお籠が運ばれていた。籠の中には、純白の白無垢を着た狐が、慎ましく座っていた。
前に、学校の図書室で読んだ本に、似た情景が描かれていた気がする。楸は無意識に、記憶の糸を手繰り寄せた。
「狐の、嫁入り……」
確か、そう説明書きがあった。思い出すと、急に頭が真っ白になり、意識が完全に途絶えた。
* * *
次に目を覚ますと、楸は病院のベッドの上にいた。
「楸ちゃん! よかった、目ぇ醒ましたんやねぇ。ほんまに、よかった……」
側には、母親の妹にあたる女性――英がいた。涙を流しながら、楸の目覚めを喜んでくれた。
体調が回復してくると、病室に刑事がやってきて、色々と聞かれたし、聞かされた。
一連の出来事は、ハンドル操作を過って峠から転落した事故とされていた。当時の事情を根掘り葉掘り尋ねられ、楸はありのままを話して聞かせた。
カウンセリングを受けながら、家族の死を理解していると判断され、楸は両親と引き合わされた。
みんなは霊安室で並んで横たわり、白い布を顔に被せられていた。
「お父はん、お母はん、葵……」
たった一人、生き残ってしまった。素直には、喜べなかった。一つしかない貴重な命を取り留めたところで、家族を失った身では、絶望と不安しか残されていない。
いっそ、一緒に死ねていれば、どれだけ幸せだったか。現実に思考がついて来ず、涙さえ流す余裕はなかった。
放心状態の楸に、英は優しく接してくれた。
「今日からは、叔母さんと暮らそうな。お母はんの代わりになれるかは分からんけど、努力するから……」
葬式を済ませ、楸は英に引き取られた。母たちも両親を既になくし、まだ大学生で独り身の英もまた、天涯孤独の人だった。たった一人の姉をなくした英の悲しみは、母をなくした楸とも共有できるものがあった。
楸も、いつも優しく気に懸けてくれる英が好きだ。だから、うまくやっていけると思った。
「一緒に、協力して暮らそうね、楸ちゃん」
「よろしゅう、お願いします、お母はん……」
まだ、戸惑いもあったが、受け入れた。受け入れるしか、ないのだから。
「無理に、環境に慣れようとせんでもええんよ。少しずつ、変わっていこう」
英は、楸をとても気遣ってくれた。有り難さを通り越して、申し訳ないほどに。
せめて、迷惑を掛けないようにしなければと、気持ちを引き締めた。
「楸ちゃんの戸籍名は、周なんやね。楸は人名漢字やないから、使えへんのか。二つも名前があると、ややこしいねぇ」
役場への手続きや変更を行いながら、英が不意に呟く。
楸は、柿太郎がどうしても付けたがった名前だが、戸籍に登録できない文字だった。だから戸籍上は別の名前で通し、表向きは楸と呼ばれていた。
楸も、父がくれた名前が好きだ。気に入っている。
だけど、英にお世話になるために邪魔となる名前なら、無理して使おうとは思わない。
「ほんなら、周と呼んでください。学校でも、そう名乗りますさかい。楸の名前は、家族と一緒に墓へ仕舞っておきます」
変わろうと思った。何もかも、一から始めるために。
表向きは、努力で繕っていけた。英との関係も良好で、穏やかな生活を過ごせた。
だが、心の中には大きな蟠りが残ったままだった。時間が経過し、心が休まるのと並行して、枕を涙で濡らす日も増えた。
何度も何度も、事故当時の出来事を夢に見た。その度に脳裏に過ぎる、事故の原因となった、〝あの男〟の存在。
事故を通報してくれた人が車を発見したときには、誰もいなかったそうだ。何の痕跡も残さず、煙みたいに消えてしまった。
警察には、見たままの光景を、しっかりと話して聞かせた。あの男についても、ありのままを。
一応、事情を知っている可能性があるとして、男の行方を捜索はしてくれたが、手がかりも目撃情報もなく、すぐに打ち切られた。最終的には、楸の記憶がショックで錯乱し、幻覚を見たのだと決め付けられ、家族は完璧に事故死として扱われた。
子供の主張なんて、大人は真剣に聞いてくれない。
でも、夢でも幻でもなかった。当時の光景は、ずっと瞼の裏に焼き付いて、離れない。
「あいつ、人間やなかった。変な気配がした……」
本能的に、感じていた。
核心もしていた。みんなは、事故で死んだのではない。意図的に、あの男に殺されたのだと。
でも、見つからなければ、逮捕もできない。存在の証明もできないし、罪を認めさせられない。
そもそも、人でなければ、人の力ではどうにもならないのではないだろうか。
「人の法では、裁けへんかもしれん。せめて私が、何とかせんと……」
ただの事故死で済まされては、みんなが浮かばれない。
楸は心の中で、静かに復讐の炎をたぎらせていた。何ができるかわからなかったが、何かしなければと、心は急いた。
あの男の正体が、人間の皮を被った゛妖怪゛なる存在だと気付くには、まだ時期早尚だった。
* * *
時が流れ、楸は小学六年生になった。
一時期は周囲の目を憚って転校もしたが、名前を変えて再び、馴染みある四季ヶ丘小学校に通っていた。
大学を卒業した英は、実家と縁のある茶道や華道、舞妓の踊りの講師などの職を得て、結婚もせずに楸を養ってくれた。
忙しい英のためにと、楸は弓の習い事や勉学の傍ら、家事を手伝った。
穏やかに過ぎる、平和な時間。
時間が経つとともに、楸の中で燃えていた復讐の憎悪も、少しずつ薄らぎはじめていた。そもそも、あの男を探す手だてが何もないのだから、ろくな行動はできない。今の生活が幸福なら、と考えが改められていった。
家族の命日が近づいた、ある日。学校からの帰り道、楸は急に、妙な気配に足を止めた。
以前にも感じた気配。楸の記憶の奥に忘れ去られていた感覚が、一気に蘇ってきた。
「この気配……間違いないどす、前に感じたものと、同じどす」
楸は精神統一をして、呼吸を整えた。目を閉じて感覚を研ぎ澄まし、気配の出所を探る。
道路脇にある小さな山の登山道から、不思議な気が漂っていた。
何のためらいもなく、楸は山道を駆け登った。
狭い道を上りきった場所には、小さな祠が建てられていた。
気配が濃くなる。楸は物影に潜んで、様子を伺った。
祠の脇に、若い男が一人、立っていた。見知らぬ男だ。
だが、事故現場に居合わせた、壮年の男と同じ気配を放っていた。
何か、あの当時の男の手がかりになるかもしれない。楸は気配を消して、目の前の若い男を観察しつづけた。
男は周囲をきょろきょろと、注意深く見回していた。やがて、誰もいないと察すると、急に体から煙を出し、全身を包んだ。
直後。煙の中から出てきた姿は、人間ではなかった。
「姿が変わった!? 狐……どすか?」
赤みがかった毛並みの、大きな狐だった。尻尾が付け根から何本も生え、時代劇で問屋が着ていそうな、黒っぽい着物を身につけていた。
狐は茂みに飛び込んで、姿を消した。楸は慌てて、後を追い掛けた。
無我夢中で熊笹を掻き分けて進み、広葉樹が鬱蒼と繁る場所へやってきたが、狐の足取りは、ぱったりと分からなくなった。
「しまったどす、見失ってしもうた」
探すべきか、引き返すべきか。
冷静になった途端、楸は山の中で道に迷っていると気付いた。前も後ろも、似た景色。
どの方角に向かえば麓に出られるか、分からない。色づいた山の中は、一気に紅葉の迷宮と化した。
途方に暮れて立ち尽くしていると、周囲を奇妙なものが飛び交っている様子が、視界に入ってきた。ぼんやりと光を放つ、虫みたいなものがフワフワと漂っている。木の上では小さな人の形や動物の形をした何かが、甲高い笑い声を上げて楸を指差していた。
「山の中って、こないに奇妙な生き物が、おるんどすな」
不思議と怖くはなかったが、好奇心をくすぐられた。いままでに見た、どんな図鑑にも載っていない生き物たち。どうして、今まで存在に気づかなかったのだろう。
同時に、楸の心の奥から、熱く強い力が込み上げてきた。初めての感覚に、少し戸惑いもあった。
やがて、その熱が体内に充満すると、樹上の小人たちの言葉が、突然、解るようになった。
「人間だ。人間が迷い込んできた」
「面白い。我々の姿が見える人間か」
「さぞかし、上質な魂を持っておるのだろうな」
「子供の体は、軟らかくて美味いしな」
可愛いげのあった小人たちが、急に邪悪な気配を放ちはじめた。舌なめずりする音、殺気。
命を狙われていると気付き、楸は身を竦めた。
じりじりと、木々や茂みの中から、奇妙な姿の生き物たちが出てきて、詰め寄ってくる。
気づけば、囲まれていた。
逃げられない。どうすればいい?
絶体絶命の窮地に陥った時、心の奥から、言葉が浮かんできた。
和歌みたいな、綺麗な調べだった。
「紅葉降る 暮れの夕焼け 燃ゆる空 富める山々 儚く満る」
全身を、眩しい光と不思議な力に包まれていく。周囲に、真っ赤な紅葉が降り注いだ。
「――秋姫、見参どす!」
気付くと、楸は橙色の十二単を身に纏い、手には長い梓弓を握りしめていた。
「何どすか、この格好は……」
突然の変貌に、楸は動揺する。
頭の中で、声が響いた。
――人に仇なすものを倒せ。使命を果たせ。
「何だ、こいつは! 奇妙な力を持っているぞ」
「我らの敵かもしれん。殺せ!」
楸の変身に驚いた山の住民たちは、殺気を漏らしながら、楸に襲い掛かってきた。恐怖に駆られた楸は、無我夢中で背負った矢を掴み、弓を引いていた。
放った矢は、一匹の小人の顔面を打ち抜いた。悲鳴をあげる暇もなく、小人は光の粒となって消滅した。
「こいつ、強いぞ!」
「我等では、手に負えん! 逃げろ!」
楸の力に恐れを成したものたちは、一目散に山奥へ消えて行った。
脱力し、楸は地面に座りこんだ。薄暗かった山に光が射し、出口もはっきりと見て取れた。
気付けば、楸の格好は元の私服に戻っていた。ランドセルも、側に落ちている。
右手に、綺麗な彼岸花の髪飾りを握りしめていた。今まで存在しなかったものの出現を、楸は茫然と見ていた。
ただ、冷静に、さっきの不思議な力について、思考を巡らせていた。
突然現れた、奇妙な生き物たち。さらに、その生き物たちを一撃で倒せる力を、楸は手に入れた。
山の奥へと姿を消した、人間か狐か、よく分からない存在。家族の死に深く関わるあの生き物も、この力で倒せるのではないか。
復讐を果たす力を手に入れたと、瞬時に察した。まるで、目に見えない誰かが、家族の敵を討てと、後押ししているみたいだ。
だが、同時に恐怖が襲った。
「あかん、無理どす。こんな恐ろしい力、使えへん……!」
得体の知れない力。もし安易に使って、周囲にも悪い影響が起こったら。楸が扱うには、不相応な力に感じられた。
憎しみに駆られたせいで楸自身が自滅しても、自業自得だ。だが、英や、楸を大切に思ってくれる人達にまで被害が及んだら。そう思うと、怖くて怖くて堪らなかった。
楸は髪飾りをポケットの奥に捩込み、家へと逃げ帰った。
部屋の勉強机の一番奥に、ハンカチで包んで突っ込み、隠した。
捨てれば良かったのかもしれない。でも、何をするにも恐さが付き纏い、冷静な思考が働かなかった。
その日の出来事は忘れようと決め、髪飾りにも二度と触れないと心に誓った。
* * *
半年経ち、楸は中学生になった。
何事もなく平和な時間が過ぎた。時々、宙を漂う奇妙なものが視界に入る時はあったが、無視していれば何の干渉もしてこなかった。
たくさん勉強して良い学校へ進学し、英を安心させよう。最近はあまり過去を顧みず、前を向いて勉学に勤しむ姿勢が身についていた。
休日。図書館から帰る途中に、ある人影を見かけた。
背の高い、男の子みたいな風貌の少女。
水無月榎。
中学入学と同時に、名古屋からやってきたクラスメイトだ。
家庭の事情で親御さんの元を離れ、現在は従姉妹の如月椿の家に居候している。
まだ子供なのに親兄弟と別れ、慣れない土地で暮らす。その境遇が楸とも少し似ていて、同情心を抱いた。人懐っこい性格だし、やたらと興味を引かれ、色々と世話を焼きたくなる存在でもあった。
榎は周囲の景色を確かめながら、黙々と山道を上って行った。榎の向かった先には、寂れた廃寺があるだけのはずだが。いったい、何をしに行くのだろう。
気になった楸は、胸騒ぎと誘惑に勝てず、榎の後をこっそりとつけた。
なぜか、追い掛けなければならないと、全身が訴えている感じさえした。
木の影で見張っていると、わけの分からない人間たちが、ゾロゾロと集まってきた。
平安時代の貴族みたいな格好をした、まんまるの男や、怪しい祈祷師みたいな女。
楸は、だんだん心配になってきた。榎は人が善いから、変な詐欺集団に捕まって、騙されているのではないか。金をせびられたり、暴行を受けるのでは。何もかも搾り取られて破滅の道へ落ちる前に、助けなければ。
様子を伺っていると、突然、木の上から大きな烏が現れた。山伏姿をした、三本足の烏。
間違いなく、ただの烏ではない。以前見た、謎の生き物たちと同じ系統の存在か。
さらに、その姿が、榎たちにも見えているのだと気付き、驚いた。
祈祷師の女が果敢に戦いを挑むが、まるで歯が立たない。かなり強い烏だ。
放っておけば、みんなやられる。榎も、無事では済まない。
半年前の力があれば助けられると、一瞬、脳裏を過ぎった。
だが、力を使うために必要だと思われる髪飾りが、手元になかった。
もし、変身できたとしても、本当に戦えるのだろうか。
謎の生き物を矢で射て倒して以来、怖くて弓も握れなくなっているのに。
また、何もできないのか。誰も助けられずに、傍観するだけなのか。
過去の記憶が蘇り、楸の心を痛め付けた。
役に立たなくても、出ていくべきか。覚悟を決め兼ねていると、榎が烏の前に立ちはだかった。
手には、綺麗な百合の髪飾りが握られていた。一瞬、楸の髪飾りと印象が重なり、心臓が大きく高鳴った。
「いと高き 夏の日差しの 力以て 天へ伸びゆく 清き百合花」
草木がざわめき、榎が真っ白な光に包まれていく。楸は瞬きも忘れて、その光景に魅入った。
直後。榎の姿は大きく変貌していた。髪は腰近くまで長く伸び、頭上で纏め上げられていた。格好は、緑を基調とした、十二単。手には白銀の剣を握りしめていた。
「夏姫、ここに見参!」
剣を構え、榎は凛々しく名乗りを挙げる。
楸は榎の姿を目の当たりにして、硬直した。
「夏姫……? 私と同じどす。水無月はんにも、不思議な力が……?」
楸の他にも、同じ力を持つものが存在したとは。かつて手に入れた、恐れていたはずの力に、大きな興味と可能性が振り返してきた。
榎は、この力を使いこなし、楸が知りえない知識も持っている。興奮が勝り、楸は茂みから飛び出していた。
榎――夏姫が妖怪と戦う姿を見て、だんだん、勇気が沸いてきた。
単純に、恐ろしいものと決め付けて、真っ向から向き合ってこなかった。でも、力の扱いや、周りに及ぼす影響は、楸のコントロール次第でいくらでも制御できるのではないか、とも思えた。
妖怪を撃退した榎から、一連の話を説明してもらった。
四季姫。この世に四人存在する、妖怪を倒す使命を帯びて生まれ変わった、千年前の陰陽師。
その内の一人が、楸――秋姫なのだと理解した。
榎は、ともに戦うべき四季姫を探していた。すぐに名乗り出るべきだったのかもしれない。でも、勇気が持てなかった。
何より、榎と楸では、戦う目的が違う。世のため平和のために、と力を使う榎の潔さとは違い、楸は復讐に使う力としか、考えていなかった。陰湿で、嫌な理由だ。
そんな状態で仲間だと申し出たとしても、きっと一緒になんて、戦えない。
四季姫たちが戦うべき敵――妖怪について、楸は何も知らない。どんな連中がいて、どんな生活を送って、人間にどんな影響を及ぼすのか。
家族の命を奪うきっかけを作ったあの男や、同じ気配を有していた狐も、みんな妖怪なのかもしれない。真実を確かめるために、もっと妖怪について調べる必要がある。
その上で、楸の持つ秋姫の力がどう使えるか、見定めたい。
楸自身の気持ちの整理がつくまで、素性は隠しておこうと決めた。
榎たちと別れ、楸は図書館に舞い戻った。妖怪について記された本を、片っ端から読み漁った。
妖怪とは、基本は人の命を奪う災害や疫病などを擬人化させた存在である、とされていた。要するに、単なる迷信や民俗学的な伝説に過ぎない存在だ。
今までなら、その存在も簡単には信じなかったかもしれないが、その姿を視界に捉えてしまった以上、否定はできない。ますます、妖怪に興味が湧いた。
自宅に戻った楸は、半年ぶりに自ら封じた机の引き出しを開いた。
奥に押し込まれた、ハンカチに包まれた髪飾り。再び取り出して、眺める。
光を反射して赤く輝く、硝子細工の彼岸花。内側から、燃えたぎる憎悪を巻き起こしているかに見えた。
「――私の持つ力は、妖怪を倒すための力。私たちを襲った奴は、妖怪」
ようやく、確信が持てた。楸が探し続けた家族の仇は、間違いなく妖怪なのだと。
あの狐の姿をした妖怪を探すためは、妖怪に接触して手掛かりを得る方法が最短だ。榎が敵対している、烏の妖怪たちを標的に選んだ。
危険を伴うかもしれないが、もう楸の勢いは、止められそうになかった。
榎に手傷を追わされた烏を助けに来た、少年の姿をした妖怪を思い出す。かなり強そうだったし、きっと、楸の探す狐の妖怪についても、何か知っているはずだ。好意を持ったふりをして近づき、警戒心を解かせて、利用しよう。
「仲間を探してはる榎はんには申し訳ないどすが、私は、私のやるべき目的を果たさねばならんどす。私の持つ力は、復讐のために、使わせてもらいます」
楸の覚悟は、四季姫の使命とは異なる形で固まった。
* * *
意識が切り替わり、楸は目を覚ました。
布団から飛び起きると、汗だくだった。部屋は明るい。窓の外は、朝日が昇りはじめていた。
「夢、どすか……」
過去の夢を、久しぶりに見ていた。辛い過去から、秋姫として戦いを決意するまで。
現在に至る長い時間を、一晩かけて旅行した気分だ。
「最近は慌しくて、昔の夢も見んかったのに」
結局、倒すべき妖怪の手掛かりは掴めず、秋姫として正体を明かし、四季姫たちと行動を共にし始めた。その後は色々と忙しい出来事が続いて、本来の目的から遠ざかっていた。
今になって、再び夢に出てきた理由は、そろそろ敵討ちの使命を思い出せと、心の中で本心が焦っているからかもしれない。
四季姫としての役目はまだ残っているが、のんびりもしていられなかった。
何より、居心地のよい場所を見つけたせいで、この憎しみが消えてしまうのではないかと思うと、怖かった。
秋姫の力は、復讐のために。
そう、決めたのだから、この気持ちを風化させるわけにはいかなかった。
今から六年前。
長月 楸は、生まれて初めて妖怪を見た。
小学一年生の秋。
連休の最終日。長月一家は揃って行楽に出掛けた。
楸の家族は父の柿太郎と母の桔梗。三つ年下の弟、葵の四人だ。
運転好きの父の車でやって来た場所は、四季ヶ丘の南の端にある、広い自然公園だった。
敷地内に大きな湖があり、峠道や原生林が広がる、静かで穏やかな場所だった。
秋めいた季節になると、園内に植えられた銀杏や紅葉が色濃く染まり、一面に彩りを添えた。湖の水面にひらりと落ちて、船みたいに浮かぶ姿もまた、風流だった。
公園の散歩を楽しみ、一家は車で帰路につこうとしていた。
時刻は午後五時を回ったくらい。日の入りがだんだん早くなり、既に夕闇が迫る頃となっていた。
「公園の紅葉、綺麗どしたなぁ」
「春には、桜も満開らしい。次は花見やな」
父は運転席、母は助手席で、今日の散策の感想や次の予定を、楽しそうに語っていた。
「葵。運転中は、立ち上がったらあかんどす」
楸は後ろの席で、まだ幼い弟の葵をあやしていた。四つになったばかりの葵は、まだまだ手のかかる歳だ。楸は率先して、可愛い弟の世話を焼いていた。
急なカーブの多い峠道に差し掛かった頃。突然、柿太郎が「危ない!」と声を張り上げた。同時に急ブレーキが掛けられ、シートベルトに支えられながらも、体が激しく前のめりになった。
楸はびっくりして、頭の中が一瞬、真っ白になる。葵が泣き出す声で我に返った。楸は慌てて葵のシートベルトを外し、抱き上げて桔梗に渡した。
「お父はん、どないしやはったんや?」
葵を抱いて宥めながら、桔梗は不安そうに尋ねる。
「急に、車の前に誰かが……」
柿太郎はドアを開けて頭を突き出し、前方を確認した。楸も、身を乗り出して車の前を見る。ヘッドライトに照らされた道路で、人が尻餅をついて座りこんでいた。
「大丈夫ですか!? お怪我は」
車から飛び出し、柿太郎はその人物の元へ駆け寄った。ハイキング客だろう、小さなリュックを担いだ、壮年の男だった。
「いやぁ、大変、失礼いたしました。急いでいたもので、車に気付かずに飛び出してしまって」
男は己の非を詫びて、頭を下げてきた。柔らかな物腰の、優しそうな人だった。
怪我もなさそうだったし、柿太郎は安心して男と会話を続けた。
「そんなに慌てて、どちらへ?」
「実は今夜、可愛い姪っ子の結婚式がありましてね。祝いの品が決まらなくて。とりあえず麓に行こうと急いでいたのです」
男は山の向こう側に住んでいると説明した。
話が盛り上がり、人の良い柿太郎は、男に笑顔で祝福を送った。
「そら、おめでとうございます。こんな場所で会ったんも、何かの縁です、一緒に乗っていかれませんか? もうじき、日も落ちます。夜道は危ないですよ」
親切心から同乗を勧めたが、男はやんわりと断ってきた。にやりと、目を細めて笑う。その顔を見た途端、楸の背筋に寒気が走った。
「いや、結構です。崖を下れば、麓まで一直線ですし」
直後。突然、車が前進しはじめた。運転席には誰も乗っていないのに、どんどん進んでいく。
柿太郎の慌てる声、桔梗の悲鳴が響く。進行方向の先は、切り立った崖だ。ガードレールがあったはずなのに、なぜかなくなっていた。
柿太郎が車に飛び乗ってブレーキを踏むが、止まる気配がない。
「あかん、みんな、降りるんや!」
諦めてみんなを逃がそうとしたが、手遅れだった。
四人を乗せた車は、崖下へと一直線に落下した。
激しく車が破壊される音。体に走る痛みと衝撃。
車の間に挟まれながらも、楸は辛うじて意識を保ち、朦朧としながら惨状を目の当たりにしていた。
柿太郎は車から投げ出され、鬱蒼と繁る木々の間に倒れ込んでいた。桔梗は、葵を強く抱きしめたまま、助手席で、ぐったりと項垂れていた。葵の泣き声も、聞こえてこない。
ぐしゃぐしゃになった車の側に、誰かが歩いてくる音がした。
さっきの男だ。楸は助けを求めようとしたが、声が出なかった。
誰が見ても、酷い惨劇だ。きっとすぐに、この男が救急車を呼んでくれる。
そう信じていたのに、男の行動は奇妙かつ、非人道的だった。
「ありがたいねぇ。麓まで行かなくても、よい人魂が手に入った」
男は不気味な笑みを浮かべながら、倒れて動かない父の頭を掴んで、揺らしはじめた。やがて、柿太郎の額から、ぼんやりと光る青白い塊が飛び出した。
魚みたいに、ゆらゆらと動く塊を、男は素手でがっしりと掴んで、リュックに詰め込んだ。
続いて、桔梗と葵にも同じ動作を行い、二人の中から出てきた青白いものを捕獲していった。
最後に、男は楸にも近付いてきた。頭に触れようとしたが、楸がまだ意識を保っていると気付き、手を引っ込めた。
「まだ一人、生き残っていたか。すぐに楽にしてやるからね」
男は、楸に向かって妙な力を送りはじめた。だんだんと息苦しくなり、目を開けていられなくなる。
薄れゆく意識の中で、何度も鳴る鐘の音を聞いた。
男の耳にも音が聞こえたらしく、急に慌てだした。
「いかん。宴が始まる。三つで我慢するか」
急いだ様子で、男はその場から立ち去って行った。
楸は茫然と、男の向かった方角を見つめていた。
山の木々の合間に、怪しげな光が、列を成して続いていく。さっきの鐘の音も、行列のある場所から響いてきた。
黒い着物を纏った狐達が、わいわいと騒ぎながら歩いていく。行列の中心では、立派なお籠が運ばれていた。籠の中には、純白の白無垢を着た狐が、慎ましく座っていた。
前に、学校の図書室で読んだ本に、似た情景が描かれていた気がする。楸は無意識に、記憶の糸を手繰り寄せた。
「狐の、嫁入り……」
確か、そう説明書きがあった。思い出すと、急に頭が真っ白になり、意識が完全に途絶えた。
* * *
次に目を覚ますと、楸は病院のベッドの上にいた。
「楸ちゃん! よかった、目ぇ醒ましたんやねぇ。ほんまに、よかった……」
側には、母親の妹にあたる女性――英がいた。涙を流しながら、楸の目覚めを喜んでくれた。
体調が回復してくると、病室に刑事がやってきて、色々と聞かれたし、聞かされた。
一連の出来事は、ハンドル操作を過って峠から転落した事故とされていた。当時の事情を根掘り葉掘り尋ねられ、楸はありのままを話して聞かせた。
カウンセリングを受けながら、家族の死を理解していると判断され、楸は両親と引き合わされた。
みんなは霊安室で並んで横たわり、白い布を顔に被せられていた。
「お父はん、お母はん、葵……」
たった一人、生き残ってしまった。素直には、喜べなかった。一つしかない貴重な命を取り留めたところで、家族を失った身では、絶望と不安しか残されていない。
いっそ、一緒に死ねていれば、どれだけ幸せだったか。現実に思考がついて来ず、涙さえ流す余裕はなかった。
放心状態の楸に、英は優しく接してくれた。
「今日からは、叔母さんと暮らそうな。お母はんの代わりになれるかは分からんけど、努力するから……」
葬式を済ませ、楸は英に引き取られた。母たちも両親を既になくし、まだ大学生で独り身の英もまた、天涯孤独の人だった。たった一人の姉をなくした英の悲しみは、母をなくした楸とも共有できるものがあった。
楸も、いつも優しく気に懸けてくれる英が好きだ。だから、うまくやっていけると思った。
「一緒に、協力して暮らそうね、楸ちゃん」
「よろしゅう、お願いします、お母はん……」
まだ、戸惑いもあったが、受け入れた。受け入れるしか、ないのだから。
「無理に、環境に慣れようとせんでもええんよ。少しずつ、変わっていこう」
英は、楸をとても気遣ってくれた。有り難さを通り越して、申し訳ないほどに。
せめて、迷惑を掛けないようにしなければと、気持ちを引き締めた。
「楸ちゃんの戸籍名は、周なんやね。楸は人名漢字やないから、使えへんのか。二つも名前があると、ややこしいねぇ」
役場への手続きや変更を行いながら、英が不意に呟く。
楸は、柿太郎がどうしても付けたがった名前だが、戸籍に登録できない文字だった。だから戸籍上は別の名前で通し、表向きは楸と呼ばれていた。
楸も、父がくれた名前が好きだ。気に入っている。
だけど、英にお世話になるために邪魔となる名前なら、無理して使おうとは思わない。
「ほんなら、周と呼んでください。学校でも、そう名乗りますさかい。楸の名前は、家族と一緒に墓へ仕舞っておきます」
変わろうと思った。何もかも、一から始めるために。
表向きは、努力で繕っていけた。英との関係も良好で、穏やかな生活を過ごせた。
だが、心の中には大きな蟠りが残ったままだった。時間が経過し、心が休まるのと並行して、枕を涙で濡らす日も増えた。
何度も何度も、事故当時の出来事を夢に見た。その度に脳裏に過ぎる、事故の原因となった、〝あの男〟の存在。
事故を通報してくれた人が車を発見したときには、誰もいなかったそうだ。何の痕跡も残さず、煙みたいに消えてしまった。
警察には、見たままの光景を、しっかりと話して聞かせた。あの男についても、ありのままを。
一応、事情を知っている可能性があるとして、男の行方を捜索はしてくれたが、手がかりも目撃情報もなく、すぐに打ち切られた。最終的には、楸の記憶がショックで錯乱し、幻覚を見たのだと決め付けられ、家族は完璧に事故死として扱われた。
子供の主張なんて、大人は真剣に聞いてくれない。
でも、夢でも幻でもなかった。当時の光景は、ずっと瞼の裏に焼き付いて、離れない。
「あいつ、人間やなかった。変な気配がした……」
本能的に、感じていた。
核心もしていた。みんなは、事故で死んだのではない。意図的に、あの男に殺されたのだと。
でも、見つからなければ、逮捕もできない。存在の証明もできないし、罪を認めさせられない。
そもそも、人でなければ、人の力ではどうにもならないのではないだろうか。
「人の法では、裁けへんかもしれん。せめて私が、何とかせんと……」
ただの事故死で済まされては、みんなが浮かばれない。
楸は心の中で、静かに復讐の炎をたぎらせていた。何ができるかわからなかったが、何かしなければと、心は急いた。
あの男の正体が、人間の皮を被った゛妖怪゛なる存在だと気付くには、まだ時期早尚だった。
* * *
時が流れ、楸は小学六年生になった。
一時期は周囲の目を憚って転校もしたが、名前を変えて再び、馴染みある四季ヶ丘小学校に通っていた。
大学を卒業した英は、実家と縁のある茶道や華道、舞妓の踊りの講師などの職を得て、結婚もせずに楸を養ってくれた。
忙しい英のためにと、楸は弓の習い事や勉学の傍ら、家事を手伝った。
穏やかに過ぎる、平和な時間。
時間が経つとともに、楸の中で燃えていた復讐の憎悪も、少しずつ薄らぎはじめていた。そもそも、あの男を探す手だてが何もないのだから、ろくな行動はできない。今の生活が幸福なら、と考えが改められていった。
家族の命日が近づいた、ある日。学校からの帰り道、楸は急に、妙な気配に足を止めた。
以前にも感じた気配。楸の記憶の奥に忘れ去られていた感覚が、一気に蘇ってきた。
「この気配……間違いないどす、前に感じたものと、同じどす」
楸は精神統一をして、呼吸を整えた。目を閉じて感覚を研ぎ澄まし、気配の出所を探る。
道路脇にある小さな山の登山道から、不思議な気が漂っていた。
何のためらいもなく、楸は山道を駆け登った。
狭い道を上りきった場所には、小さな祠が建てられていた。
気配が濃くなる。楸は物影に潜んで、様子を伺った。
祠の脇に、若い男が一人、立っていた。見知らぬ男だ。
だが、事故現場に居合わせた、壮年の男と同じ気配を放っていた。
何か、あの当時の男の手がかりになるかもしれない。楸は気配を消して、目の前の若い男を観察しつづけた。
男は周囲をきょろきょろと、注意深く見回していた。やがて、誰もいないと察すると、急に体から煙を出し、全身を包んだ。
直後。煙の中から出てきた姿は、人間ではなかった。
「姿が変わった!? 狐……どすか?」
赤みがかった毛並みの、大きな狐だった。尻尾が付け根から何本も生え、時代劇で問屋が着ていそうな、黒っぽい着物を身につけていた。
狐は茂みに飛び込んで、姿を消した。楸は慌てて、後を追い掛けた。
無我夢中で熊笹を掻き分けて進み、広葉樹が鬱蒼と繁る場所へやってきたが、狐の足取りは、ぱったりと分からなくなった。
「しまったどす、見失ってしもうた」
探すべきか、引き返すべきか。
冷静になった途端、楸は山の中で道に迷っていると気付いた。前も後ろも、似た景色。
どの方角に向かえば麓に出られるか、分からない。色づいた山の中は、一気に紅葉の迷宮と化した。
途方に暮れて立ち尽くしていると、周囲を奇妙なものが飛び交っている様子が、視界に入ってきた。ぼんやりと光を放つ、虫みたいなものがフワフワと漂っている。木の上では小さな人の形や動物の形をした何かが、甲高い笑い声を上げて楸を指差していた。
「山の中って、こないに奇妙な生き物が、おるんどすな」
不思議と怖くはなかったが、好奇心をくすぐられた。いままでに見た、どんな図鑑にも載っていない生き物たち。どうして、今まで存在に気づかなかったのだろう。
同時に、楸の心の奥から、熱く強い力が込み上げてきた。初めての感覚に、少し戸惑いもあった。
やがて、その熱が体内に充満すると、樹上の小人たちの言葉が、突然、解るようになった。
「人間だ。人間が迷い込んできた」
「面白い。我々の姿が見える人間か」
「さぞかし、上質な魂を持っておるのだろうな」
「子供の体は、軟らかくて美味いしな」
可愛いげのあった小人たちが、急に邪悪な気配を放ちはじめた。舌なめずりする音、殺気。
命を狙われていると気付き、楸は身を竦めた。
じりじりと、木々や茂みの中から、奇妙な姿の生き物たちが出てきて、詰め寄ってくる。
気づけば、囲まれていた。
逃げられない。どうすればいい?
絶体絶命の窮地に陥った時、心の奥から、言葉が浮かんできた。
和歌みたいな、綺麗な調べだった。
「紅葉降る 暮れの夕焼け 燃ゆる空 富める山々 儚く満る」
全身を、眩しい光と不思議な力に包まれていく。周囲に、真っ赤な紅葉が降り注いだ。
「――秋姫、見参どす!」
気付くと、楸は橙色の十二単を身に纏い、手には長い梓弓を握りしめていた。
「何どすか、この格好は……」
突然の変貌に、楸は動揺する。
頭の中で、声が響いた。
――人に仇なすものを倒せ。使命を果たせ。
「何だ、こいつは! 奇妙な力を持っているぞ」
「我らの敵かもしれん。殺せ!」
楸の変身に驚いた山の住民たちは、殺気を漏らしながら、楸に襲い掛かってきた。恐怖に駆られた楸は、無我夢中で背負った矢を掴み、弓を引いていた。
放った矢は、一匹の小人の顔面を打ち抜いた。悲鳴をあげる暇もなく、小人は光の粒となって消滅した。
「こいつ、強いぞ!」
「我等では、手に負えん! 逃げろ!」
楸の力に恐れを成したものたちは、一目散に山奥へ消えて行った。
脱力し、楸は地面に座りこんだ。薄暗かった山に光が射し、出口もはっきりと見て取れた。
気付けば、楸の格好は元の私服に戻っていた。ランドセルも、側に落ちている。
右手に、綺麗な彼岸花の髪飾りを握りしめていた。今まで存在しなかったものの出現を、楸は茫然と見ていた。
ただ、冷静に、さっきの不思議な力について、思考を巡らせていた。
突然現れた、奇妙な生き物たち。さらに、その生き物たちを一撃で倒せる力を、楸は手に入れた。
山の奥へと姿を消した、人間か狐か、よく分からない存在。家族の死に深く関わるあの生き物も、この力で倒せるのではないか。
復讐を果たす力を手に入れたと、瞬時に察した。まるで、目に見えない誰かが、家族の敵を討てと、後押ししているみたいだ。
だが、同時に恐怖が襲った。
「あかん、無理どす。こんな恐ろしい力、使えへん……!」
得体の知れない力。もし安易に使って、周囲にも悪い影響が起こったら。楸が扱うには、不相応な力に感じられた。
憎しみに駆られたせいで楸自身が自滅しても、自業自得だ。だが、英や、楸を大切に思ってくれる人達にまで被害が及んだら。そう思うと、怖くて怖くて堪らなかった。
楸は髪飾りをポケットの奥に捩込み、家へと逃げ帰った。
部屋の勉強机の一番奥に、ハンカチで包んで突っ込み、隠した。
捨てれば良かったのかもしれない。でも、何をするにも恐さが付き纏い、冷静な思考が働かなかった。
その日の出来事は忘れようと決め、髪飾りにも二度と触れないと心に誓った。
* * *
半年経ち、楸は中学生になった。
何事もなく平和な時間が過ぎた。時々、宙を漂う奇妙なものが視界に入る時はあったが、無視していれば何の干渉もしてこなかった。
たくさん勉強して良い学校へ進学し、英を安心させよう。最近はあまり過去を顧みず、前を向いて勉学に勤しむ姿勢が身についていた。
休日。図書館から帰る途中に、ある人影を見かけた。
背の高い、男の子みたいな風貌の少女。
水無月榎。
中学入学と同時に、名古屋からやってきたクラスメイトだ。
家庭の事情で親御さんの元を離れ、現在は従姉妹の如月椿の家に居候している。
まだ子供なのに親兄弟と別れ、慣れない土地で暮らす。その境遇が楸とも少し似ていて、同情心を抱いた。人懐っこい性格だし、やたらと興味を引かれ、色々と世話を焼きたくなる存在でもあった。
榎は周囲の景色を確かめながら、黙々と山道を上って行った。榎の向かった先には、寂れた廃寺があるだけのはずだが。いったい、何をしに行くのだろう。
気になった楸は、胸騒ぎと誘惑に勝てず、榎の後をこっそりとつけた。
なぜか、追い掛けなければならないと、全身が訴えている感じさえした。
木の影で見張っていると、わけの分からない人間たちが、ゾロゾロと集まってきた。
平安時代の貴族みたいな格好をした、まんまるの男や、怪しい祈祷師みたいな女。
楸は、だんだん心配になってきた。榎は人が善いから、変な詐欺集団に捕まって、騙されているのではないか。金をせびられたり、暴行を受けるのでは。何もかも搾り取られて破滅の道へ落ちる前に、助けなければ。
様子を伺っていると、突然、木の上から大きな烏が現れた。山伏姿をした、三本足の烏。
間違いなく、ただの烏ではない。以前見た、謎の生き物たちと同じ系統の存在か。
さらに、その姿が、榎たちにも見えているのだと気付き、驚いた。
祈祷師の女が果敢に戦いを挑むが、まるで歯が立たない。かなり強い烏だ。
放っておけば、みんなやられる。榎も、無事では済まない。
半年前の力があれば助けられると、一瞬、脳裏を過ぎった。
だが、力を使うために必要だと思われる髪飾りが、手元になかった。
もし、変身できたとしても、本当に戦えるのだろうか。
謎の生き物を矢で射て倒して以来、怖くて弓も握れなくなっているのに。
また、何もできないのか。誰も助けられずに、傍観するだけなのか。
過去の記憶が蘇り、楸の心を痛め付けた。
役に立たなくても、出ていくべきか。覚悟を決め兼ねていると、榎が烏の前に立ちはだかった。
手には、綺麗な百合の髪飾りが握られていた。一瞬、楸の髪飾りと印象が重なり、心臓が大きく高鳴った。
「いと高き 夏の日差しの 力以て 天へ伸びゆく 清き百合花」
草木がざわめき、榎が真っ白な光に包まれていく。楸は瞬きも忘れて、その光景に魅入った。
直後。榎の姿は大きく変貌していた。髪は腰近くまで長く伸び、頭上で纏め上げられていた。格好は、緑を基調とした、十二単。手には白銀の剣を握りしめていた。
「夏姫、ここに見参!」
剣を構え、榎は凛々しく名乗りを挙げる。
楸は榎の姿を目の当たりにして、硬直した。
「夏姫……? 私と同じどす。水無月はんにも、不思議な力が……?」
楸の他にも、同じ力を持つものが存在したとは。かつて手に入れた、恐れていたはずの力に、大きな興味と可能性が振り返してきた。
榎は、この力を使いこなし、楸が知りえない知識も持っている。興奮が勝り、楸は茂みから飛び出していた。
榎――夏姫が妖怪と戦う姿を見て、だんだん、勇気が沸いてきた。
単純に、恐ろしいものと決め付けて、真っ向から向き合ってこなかった。でも、力の扱いや、周りに及ぼす影響は、楸のコントロール次第でいくらでも制御できるのではないか、とも思えた。
妖怪を撃退した榎から、一連の話を説明してもらった。
四季姫。この世に四人存在する、妖怪を倒す使命を帯びて生まれ変わった、千年前の陰陽師。
その内の一人が、楸――秋姫なのだと理解した。
榎は、ともに戦うべき四季姫を探していた。すぐに名乗り出るべきだったのかもしれない。でも、勇気が持てなかった。
何より、榎と楸では、戦う目的が違う。世のため平和のために、と力を使う榎の潔さとは違い、楸は復讐に使う力としか、考えていなかった。陰湿で、嫌な理由だ。
そんな状態で仲間だと申し出たとしても、きっと一緒になんて、戦えない。
四季姫たちが戦うべき敵――妖怪について、楸は何も知らない。どんな連中がいて、どんな生活を送って、人間にどんな影響を及ぼすのか。
家族の命を奪うきっかけを作ったあの男や、同じ気配を有していた狐も、みんな妖怪なのかもしれない。真実を確かめるために、もっと妖怪について調べる必要がある。
その上で、楸の持つ秋姫の力がどう使えるか、見定めたい。
楸自身の気持ちの整理がつくまで、素性は隠しておこうと決めた。
榎たちと別れ、楸は図書館に舞い戻った。妖怪について記された本を、片っ端から読み漁った。
妖怪とは、基本は人の命を奪う災害や疫病などを擬人化させた存在である、とされていた。要するに、単なる迷信や民俗学的な伝説に過ぎない存在だ。
今までなら、その存在も簡単には信じなかったかもしれないが、その姿を視界に捉えてしまった以上、否定はできない。ますます、妖怪に興味が湧いた。
自宅に戻った楸は、半年ぶりに自ら封じた机の引き出しを開いた。
奥に押し込まれた、ハンカチに包まれた髪飾り。再び取り出して、眺める。
光を反射して赤く輝く、硝子細工の彼岸花。内側から、燃えたぎる憎悪を巻き起こしているかに見えた。
「――私の持つ力は、妖怪を倒すための力。私たちを襲った奴は、妖怪」
ようやく、確信が持てた。楸が探し続けた家族の仇は、間違いなく妖怪なのだと。
あの狐の姿をした妖怪を探すためは、妖怪に接触して手掛かりを得る方法が最短だ。榎が敵対している、烏の妖怪たちを標的に選んだ。
危険を伴うかもしれないが、もう楸の勢いは、止められそうになかった。
榎に手傷を追わされた烏を助けに来た、少年の姿をした妖怪を思い出す。かなり強そうだったし、きっと、楸の探す狐の妖怪についても、何か知っているはずだ。好意を持ったふりをして近づき、警戒心を解かせて、利用しよう。
「仲間を探してはる榎はんには申し訳ないどすが、私は、私のやるべき目的を果たさねばならんどす。私の持つ力は、復讐のために、使わせてもらいます」
楸の覚悟は、四季姫の使命とは異なる形で固まった。
* * *
意識が切り替わり、楸は目を覚ました。
布団から飛び起きると、汗だくだった。部屋は明るい。窓の外は、朝日が昇りはじめていた。
「夢、どすか……」
過去の夢を、久しぶりに見ていた。辛い過去から、秋姫として戦いを決意するまで。
現在に至る長い時間を、一晩かけて旅行した気分だ。
「最近は慌しくて、昔の夢も見んかったのに」
結局、倒すべき妖怪の手掛かりは掴めず、秋姫として正体を明かし、四季姫たちと行動を共にし始めた。その後は色々と忙しい出来事が続いて、本来の目的から遠ざかっていた。
今になって、再び夢に出てきた理由は、そろそろ敵討ちの使命を思い出せと、心の中で本心が焦っているからかもしれない。
四季姫としての役目はまだ残っているが、のんびりもしていられなかった。
何より、居心地のよい場所を見つけたせいで、この憎しみが消えてしまうのではないかと思うと、怖かった。
秋姫の力は、復讐のために。
そう、決めたのだから、この気持ちを風化させるわけにはいかなかった。
0
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

【完結】使えない令嬢として一家から追放されたけど、あまりにも領民からの信頼が厚かったので逆転してざまぁしちゃいます
腕押のれん
ファンタジー
アメリスはマハス公国の八大領主の一つであるロナデシア家の三姉妹の次女として生まれるが、頭脳明晰な長女と愛想の上手い三女と比較されて母親から疎まれており、ついに追放されてしまう。しかしアメリスは取り柄のない自分にもできることをしなければならないという一心で領民たちに対し援助を熱心に行っていたので、領民からは非常に好かれていた。そのため追放された後に他国に置き去りにされてしまうものの、偶然以前助けたマハス公国出身のヨーデルと出会い助けられる。ここから彼女の逆転人生が始まっていくのであった!
私が死ぬまでには完結させます。
追記:最後まで書き終わったので、ここからはペース上げて投稿します。
追記2:ひとまず完結しました!

幻獣保護センター廃棄処理係の私、ボロ雑巾のような「ゴミ幻獣」をこっそり洗ってモフっていたら、実は世界を喰らう「終焉の獣」だった件について
いぬがみとうま🐾
ファンタジー
「魔力なしの穀潰し」――そう蔑まれ、幻獣保護センターの地下で廃棄幻獣の掃除に明け暮れる少女・ミヤコ。
実のところ、その施設は「価値のない命」を無慈悲に殺処分する地獄だった。
ある日、ミヤコの前に運ばれてきたのは、泥と油にまみれた「ボロ雑巾」のような正体不明の幻獣。
誰の目にもゴミとしか映らないその塊を、ミヤコは放っておけなかった。
「こんなに汚れたままなんて、かわいそう」
彼女が生活魔法を込めたブラシで丹念に汚れを落とした瞬間、世界を縛る最凶の封印が汚れと一緒に「流されてしまう。
現れたのは、月光を纏ったような美しい銀狼。
それは世界を喰らうと恐れられる伝説の災厄級幻獣『フェンリル・ヴォイド』だった……。
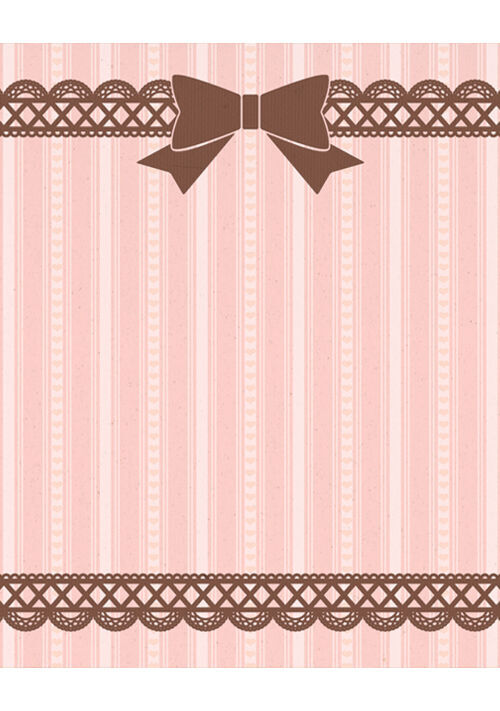
第12回ネット小説大賞コミック部門入賞・コミカライズ企画進行「婚約破棄ですか? それなら昨日成立しましたよ、ご存知ありませんでしたか?」完結
まほりろ
恋愛
第12回ネット小説大賞コミック部門入賞・コミカライズ企画進行中。
コミカライズ化がスタートしましたらこちらの作品は非公開にします。
「アリシア・フィルタ貴様との婚約を破棄する!」
イエーガー公爵家の令息レイモンド様が言い放った。レイモンド様の腕には男爵家の令嬢ミランダ様がいた。ミランダ様はピンクのふわふわした髪に赤い大きな瞳、小柄な体躯で庇護欲をそそる美少女。
対する私は銀色の髪に紫の瞳、表情が表に出にくく能面姫と呼ばれています。
レイモンド様がミランダ様に惹かれても仕方ありませんね……ですが。
「貴様は俺が心優しく美しいミランダに好意を抱いたことに嫉妬し、ミランダの教科書を破いたり、階段から突き落とすなどの狼藉を……」
「あの、ちょっとよろしいですか?」
「なんだ!」
レイモンド様が眉間にしわを寄せ私を睨む。
「婚約破棄ですか? 婚約破棄なら昨日成立しましたが、ご存知ありませんでしたか?」
私の言葉にレイモンド様とミランダ様は顔を見合わせ絶句した。
全31話、約43,000文字、完結済み。
他サイトにもアップしています。
小説家になろう、日間ランキング異世界恋愛2位!総合2位!
pixivウィークリーランキング2位に入った作品です。
アルファポリス、恋愛2位、総合2位、HOTランキング2位に入った作品です。
2021/10/23アルファポリス完結ランキング4位に入ってました。ありがとうございます。
「Copyright(C)2021-九十九沢まほろ」


ネグレクトされていた四歳の末娘は、前世の経理知識で実家の横領を見抜き追放されました。これからはもふもふ聖獣と美食巡りの旅に出ます。
旅する書斎(☆ほしい)
ファンタジー
アークライト子爵家の四歳の末娘リリアは、家族から存在しないものとして扱われていた。食事は厨房の残飯、衣服は兄姉のお下がりを更に継ぎ接ぎしたもの。冷たい床で眠る日々の中、彼女は高熱を出したことをきっかけに前世の記憶を取り戻す。
前世の彼女は、ブラック企業で過労死した経理担当のOLだった。
ある日、父の書斎に忍び込んだリリアは、ずさんな管理の家計簿を発見する。前世の知識でそれを読み解くと、父による悪質な横領と、家の財産がすでに破綻寸前であることが判明した。
「この家は、もうすぐ潰れます」
家族会議の場で、リリアはたった四歳とは思えぬ明瞭な口調で破産の事実を突きつける。激昂した父に「疫病神め!」と罵られ家を追い出されたリリアだったが、それは彼女の望むところだった。
手切れ金代わりの銅貨数枚を握りしめ、自由を手に入れたリリア。これからは誰にも縛られず、前世で夢見た美味しいものをたくさん食べる生活を目指す。

離婚する両親のどちらと暮らすか……娘が選んだのは夫の方だった。
しゃーりん
恋愛
夫の愛人に子供ができた。夫は私と離婚して愛人と再婚したいという。
私たち夫婦には娘が1人。
愛人との再婚に娘は邪魔になるかもしれないと思い、自分と一緒に連れ出すつもりだった。
だけど娘が選んだのは夫の方だった。
失意のまま実家に戻り、再婚した私が数年後に耳にしたのは、娘が冷遇されているのではないかという話。
事実ならば娘を引き取りたいと思い、元夫の家を訪れた。
再び娘が選ぶのは父か母か?というお話です。

俺だけ毎日チュートリアルで報酬無双だけどもしかしたら世界の敵になったかもしれない
宍戸亮
ファンタジー
朝起きたら『チュートリアル 起床』という謎の画面が出現。怪訝に思いながらもチュートリアルをクリアしていき、報酬を貰う。そして近い未来、世界が一新する出来事が起こり、主人公・花房 萌(はなぶさ はじめ)の人生の歯車が狂いだす。
不意に開かれるダンジョンへのゲート。その奥には常人では決して踏破できない存在が待ち受け、萌の体は凶刃によって裂かれた。
そしてチュートリアルが発動し、復活。殺される。復活。殺される。気が狂いそうになる輪廻の果て、萌は光明を見出し、存在を継承する事になった。
帰還した後、急速に馴染んでいく新世界。新しい学園への編入。試験。新たなダンジョン。
そして邂逅する謎の組織。
萌の物語が始まる。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















