12 / 12
最終章 政略結婚の果てに
しおりを挟む
帝国の罠を打ち砕き、死闘を終えたとき、空にはもう夜明けの光が差し込んでいました。
瓦礫と化した廃墟の中で、わたしはレオンハルトさまと、そしてジーナと、三人で強く抱きしめ合いました。
ジーナの小さな手がわたしの背中に回され、レオンハルトさまの腕がわたしを力強く包み込みます。
「……ママ! パパ!」
震える声でそう呼んでくれたジーナは、心細かったのか、わたしたちの胸に顔を埋めて、えぐえぐと声を上げて泣きました。
「ジーナ……。怖かったね。ごめんね、ひとりにさせて」
わたしが髪を撫でてやると、彼女はこくこくと頷きながら、しがみつく力を強めます。
隣でレオンハルトさまが、ぎこちないけれどとても優しい手つきで、ジーナの背中を撫でていました。
「もう大丈夫だ。俺たちが、ちゃんとそばにいる」
彼の低い声が響いて、ジーナはさらに安堵したように、わたしたちの腕の中で静かになりました。
――ああ、この光景こそが、わたしのすべてですわ。
もう、怖いものなんて何もない。 そう思わせてくれる、たった二つの温もりでした。
やがて、ジーナが疲れて眠ってしまったのを確認すると、レオンハルトさまは彼女を抱き上げました。
「屋敷に戻ろう。まずは体を休めるんだ」
その言葉に、わたしは静かに頷きます。
彼の瞳は、疲労の色を隠せないでいましたが、それ以上に、安堵と、わたしへの深い温もりに満たされていました。
家族で並んで歩く道すがら、夜明けの風が、わたしの頬を優しく撫でていきました。
「セレナ」
ふいに、レオンハルトさまがわたしの手を取りました。
彼の大きな、ゴツゴツとした手が、わたしの小さな手を包み込むように握りしめます。
「……ありがとう。おまえがいてくれなければ、俺は……」
彼の言葉に、わたしは微笑んで首を横に振りました。
「いいえ、わたしの方こそ。貴方がいなければ、わたしはジーナを救えませんでしたもの。それに、貴方がわたしを信じてくれたから、この作戦は成功したんです」
彼はわたしの言葉に、ふと立ち止まり、わたしの頬にそっと触れました。
「……初めて会ったとき、まさか君が、こんなにも大切な存在になるとは、思っていなかったよ」
その率直な言葉に、わたしの胸が甘くときめきました。
「ふふ。それはわたしの台詞です。まさか、あんなに不器用な貴方が、これほどまでにわたしを愛してくれるなんてね!」
わたしが茶化すように言うと、彼はまた少し顔を赤くしました。
「……うるさい。でもそれは……」
その続きを待つわたしに、彼はもう一度、わたしの手を強く握りしめました。
「――これは、俺の人生で、最上の幸運だった」
その言葉は、どんな甘い言葉よりも、わたしの心に深く、深く響きました。
屋敷に帰り着くと、レオンハルトさまはわたしとジーナを連れて、暖炉のある部屋へ向かいました。
ジーナはソファに寝かせられ、温かいブランケットがかけられました。
わたしもまた、温かいココアをレオンハルトさまから手渡されました。
「……ありがとう」
わたしがそう言うと、彼はわたしの隣に座り、静かにココアを啜りました。
「……真相はこうだろうと思う」
彼はそう言って、今回の事件について話してくれました。
「帝国の過激派は、替え玉の皇女を使い、偽の誘拐事件を企んだ。そして、わが王国と帝国との間で争いを起こさせ、混乱に乗じてクーデターを起こし、帝国を内部から乗っ取ろうとしていた……」
わたしは、彼の話を聞きながら、静かに頷きました。
「……彼らが、ジーナを狙ったのは?」
わたしが尋ねると、彼は静かに答えました。
「ジーナは、元々替え玉として連れてこられた少女だ。だが、彼女は、クーデター計画の内部情報を、知らず知らずのうちに知っていた。だから、俺たちが計画を阻止した時、証拠を消そうとした」
彼の言葉に、わたしの心は、深く沈みました。
「……そんな……。ジーナは、何も知らずに……」
わたしがそう言うと、彼はわたしの手を再び握りしめました。
「でももう、大丈夫だ。これからは、俺と君が、彼女を守る。どんな危険からも、必ず」
その夜、わたしは、レオンハルトさまの隣で眠りにつきました。
彼の腕の中に抱かれ、彼の胸の音を聞きながら。
翌朝、目覚めたとき、わたしは、彼の温かさに包まれていました。
「……おはよう、セレナ」
彼は、そう言って、わたしの髪を優しく撫でました。
「……おはようございます、レオンハルトさま」
わたしは、そう言って、彼の顔を見つめました。
彼の瞳は、朝の光に照らされ、美しく輝いていました。
「……レオンハルトさま……」
わたしは、そう言って、彼の顔を見つめました。
彼の瞳は、愛おしそうに私を見つめていました。
「……セレナ……愛してる」
彼は、そう言って微笑みました。
わたしは、静かに頷きました。
その瞬間、彼は、わたしを強く抱きしめました。
「……レオンハルトさま……」
わたしは、そう言って、彼の胸に顔を埋めました。
わたしたちは、言葉を交わすことなく、ただ、互いを強く抱きしめ合いました。
「……まさか、こんな日が来るなんて、思っていませんでしたわ」
わたしがそう言うと、彼は静かに頷きました。
「……ああ。俺も、思っていなかった。ただの政略結婚のはずだったのにな」
彼の言葉に、わたしは微笑みました。
「……レオンハルトさま。覚えていらっしゃいますか? 初夜の夜に、貴方が言った言葉を」
わたしがそう言うと、彼は少しだけ顔を赤くしました。
「……うるさい。あんなことは、忘れろ」
彼は、そう言って、わたしの手を取り、強く握りしめました。
「……いえ、忘れませんわ。貴方が、わたしを愛さないと言った、あの言葉を」
わたしがそう茶化して言うと、彼は真剣な眼差しで、わたしの瞳を見つめました。
「……セレナ。俺は、初めて会った時から好きだった。でも、俺には秘密もあったから、君を危険に巻き込むのが怖かったんだ。でも、もう二度と、君を愛さないなんて言わないよ。君は、俺の最高の妻だ。そして、俺たちの子供のジーナの父親だ」
彼の言葉に、わたしの心は温かい気持ちで溢れました。
「……ええ。信じてるわ、レオンハルト。私も、最初からずっとあなたのこと、好きだった」
かつての「愛さない」という初夜の宣言から始まった物語は、今では、わたしたちにとって、最上の愛に満ちています。
【完】
瓦礫と化した廃墟の中で、わたしはレオンハルトさまと、そしてジーナと、三人で強く抱きしめ合いました。
ジーナの小さな手がわたしの背中に回され、レオンハルトさまの腕がわたしを力強く包み込みます。
「……ママ! パパ!」
震える声でそう呼んでくれたジーナは、心細かったのか、わたしたちの胸に顔を埋めて、えぐえぐと声を上げて泣きました。
「ジーナ……。怖かったね。ごめんね、ひとりにさせて」
わたしが髪を撫でてやると、彼女はこくこくと頷きながら、しがみつく力を強めます。
隣でレオンハルトさまが、ぎこちないけれどとても優しい手つきで、ジーナの背中を撫でていました。
「もう大丈夫だ。俺たちが、ちゃんとそばにいる」
彼の低い声が響いて、ジーナはさらに安堵したように、わたしたちの腕の中で静かになりました。
――ああ、この光景こそが、わたしのすべてですわ。
もう、怖いものなんて何もない。 そう思わせてくれる、たった二つの温もりでした。
やがて、ジーナが疲れて眠ってしまったのを確認すると、レオンハルトさまは彼女を抱き上げました。
「屋敷に戻ろう。まずは体を休めるんだ」
その言葉に、わたしは静かに頷きます。
彼の瞳は、疲労の色を隠せないでいましたが、それ以上に、安堵と、わたしへの深い温もりに満たされていました。
家族で並んで歩く道すがら、夜明けの風が、わたしの頬を優しく撫でていきました。
「セレナ」
ふいに、レオンハルトさまがわたしの手を取りました。
彼の大きな、ゴツゴツとした手が、わたしの小さな手を包み込むように握りしめます。
「……ありがとう。おまえがいてくれなければ、俺は……」
彼の言葉に、わたしは微笑んで首を横に振りました。
「いいえ、わたしの方こそ。貴方がいなければ、わたしはジーナを救えませんでしたもの。それに、貴方がわたしを信じてくれたから、この作戦は成功したんです」
彼はわたしの言葉に、ふと立ち止まり、わたしの頬にそっと触れました。
「……初めて会ったとき、まさか君が、こんなにも大切な存在になるとは、思っていなかったよ」
その率直な言葉に、わたしの胸が甘くときめきました。
「ふふ。それはわたしの台詞です。まさか、あんなに不器用な貴方が、これほどまでにわたしを愛してくれるなんてね!」
わたしが茶化すように言うと、彼はまた少し顔を赤くしました。
「……うるさい。でもそれは……」
その続きを待つわたしに、彼はもう一度、わたしの手を強く握りしめました。
「――これは、俺の人生で、最上の幸運だった」
その言葉は、どんな甘い言葉よりも、わたしの心に深く、深く響きました。
屋敷に帰り着くと、レオンハルトさまはわたしとジーナを連れて、暖炉のある部屋へ向かいました。
ジーナはソファに寝かせられ、温かいブランケットがかけられました。
わたしもまた、温かいココアをレオンハルトさまから手渡されました。
「……ありがとう」
わたしがそう言うと、彼はわたしの隣に座り、静かにココアを啜りました。
「……真相はこうだろうと思う」
彼はそう言って、今回の事件について話してくれました。
「帝国の過激派は、替え玉の皇女を使い、偽の誘拐事件を企んだ。そして、わが王国と帝国との間で争いを起こさせ、混乱に乗じてクーデターを起こし、帝国を内部から乗っ取ろうとしていた……」
わたしは、彼の話を聞きながら、静かに頷きました。
「……彼らが、ジーナを狙ったのは?」
わたしが尋ねると、彼は静かに答えました。
「ジーナは、元々替え玉として連れてこられた少女だ。だが、彼女は、クーデター計画の内部情報を、知らず知らずのうちに知っていた。だから、俺たちが計画を阻止した時、証拠を消そうとした」
彼の言葉に、わたしの心は、深く沈みました。
「……そんな……。ジーナは、何も知らずに……」
わたしがそう言うと、彼はわたしの手を再び握りしめました。
「でももう、大丈夫だ。これからは、俺と君が、彼女を守る。どんな危険からも、必ず」
その夜、わたしは、レオンハルトさまの隣で眠りにつきました。
彼の腕の中に抱かれ、彼の胸の音を聞きながら。
翌朝、目覚めたとき、わたしは、彼の温かさに包まれていました。
「……おはよう、セレナ」
彼は、そう言って、わたしの髪を優しく撫でました。
「……おはようございます、レオンハルトさま」
わたしは、そう言って、彼の顔を見つめました。
彼の瞳は、朝の光に照らされ、美しく輝いていました。
「……レオンハルトさま……」
わたしは、そう言って、彼の顔を見つめました。
彼の瞳は、愛おしそうに私を見つめていました。
「……セレナ……愛してる」
彼は、そう言って微笑みました。
わたしは、静かに頷きました。
その瞬間、彼は、わたしを強く抱きしめました。
「……レオンハルトさま……」
わたしは、そう言って、彼の胸に顔を埋めました。
わたしたちは、言葉を交わすことなく、ただ、互いを強く抱きしめ合いました。
「……まさか、こんな日が来るなんて、思っていませんでしたわ」
わたしがそう言うと、彼は静かに頷きました。
「……ああ。俺も、思っていなかった。ただの政略結婚のはずだったのにな」
彼の言葉に、わたしは微笑みました。
「……レオンハルトさま。覚えていらっしゃいますか? 初夜の夜に、貴方が言った言葉を」
わたしがそう言うと、彼は少しだけ顔を赤くしました。
「……うるさい。あんなことは、忘れろ」
彼は、そう言って、わたしの手を取り、強く握りしめました。
「……いえ、忘れませんわ。貴方が、わたしを愛さないと言った、あの言葉を」
わたしがそう茶化して言うと、彼は真剣な眼差しで、わたしの瞳を見つめました。
「……セレナ。俺は、初めて会った時から好きだった。でも、俺には秘密もあったから、君を危険に巻き込むのが怖かったんだ。でも、もう二度と、君を愛さないなんて言わないよ。君は、俺の最高の妻だ。そして、俺たちの子供のジーナの父親だ」
彼の言葉に、わたしの心は温かい気持ちで溢れました。
「……ええ。信じてるわ、レオンハルト。私も、最初からずっとあなたのこと、好きだった」
かつての「愛さない」という初夜の宣言から始まった物語は、今では、わたしたちにとって、最上の愛に満ちています。
【完】
11
この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説

結婚初夜、「何故彼女が死んでお前が生きているんだ」と夫に言われました
ましゅぺちーの
恋愛
侯爵令嬢のアリサは婚約者だった王太子テオドールと結婚した。
ちょうどその半年前、アリサの腹違いの妹のシアは不慮の事故で帰らぬ人となっていた。
王太子が婚約者の妹のシアを愛していたのは周知の事実だった。
そんな彼は、結婚初夜、アリサに冷たく言い放った。
「何故彼女が死んでお前が生きているんだ」と。

【完】出来損ない令嬢は、双子の娘を持つ公爵様と契約結婚する~いつの間にか公爵様と7歳のかわいい双子たちに、めいっぱい溺愛されていました~
夏芽空
恋愛
子爵令嬢のエレナは、常に優秀な妹と比較され家族からひどい扱いを受けてきた。
しかし彼女は7歳の双子の娘を持つ公爵――ジオルトと契約結婚したことで、最低な家族の元を離れることができた。
しかも、条件は最高。公の場で妻を演じる以外は自由に過ごしていい上に、さらには給料までも出してくてれるという。
夢のような生活を手に入れた――と、思ったのもつかの間。
いきなり事件が発生してしまう。
結婚したその翌日に、双子の姉が令嬢教育の教育係をやめさせてしまった。
しかもジオルトは仕事で出かけていて、帰ってくるのはなんと一週間後だ。
(こうなったら、私がなんとかするしかないわ!)
腹をくくったエレナは、おもいきった行動を起こす。
それがきっかけとなり、ちょっと癖のある美少女双子義娘と、彼女たちよりもさらに癖の強いジオルトとの距離が縮まっていくのだった――。


「出て行け!」と言われたのですから、本当に出て行ってあげます!
睡蓮
恋愛
アレス第一王子はイザベラとの婚約関係の中で、彼女の事を激しく束縛していた。それに対してイザベラが言葉を返したところ、アレスは「気に入らないなら出て行ってくれて構わない」と口にしてしまう。イザベラがそんな大それた行動をとることはないだろうと踏んでアレスはその言葉をかけたわけであったが、その日の夜にイザベラは本当に姿を消してしまう…。自分の行いを必死に隠しにかかるアレスであったが、それから間もなくこの一件は国王の耳にまで入ることとなり…。

『婚約者を大好きな自分』を演じてきた侯爵令嬢、自立しろと言われたので、好き勝手に生きていくことにしました
皇 翼
恋愛
「リーシャ、君も俺にかまってばかりいないで、自分の趣味でも見つけて自立したらどうだ?正直、こうやって話しかけられるのはその――やめて欲しいんだ……周りの目もあるし、君なら分かるだろう?」
頭を急に鈍器で殴られたような感覚に陥る一言だった。
彼がチラリと見るのは周囲。2学年上の彼の教室の前であったというのが間違いだったのかもしれない。
この一言で彼女の人生は一変した――。
******
※タイトル少し変えました。
・暫く書いていなかったらかなり文体が変わってしまったので、書き直ししています。
・トラブル回避のため、完結まで感想欄は開きません。

精霊姫の追放
あんど もあ
ファンタジー
栄華を極める国の国王が亡くなり、国王が溺愛していた幼い少女の姿の精霊姫を離宮から追放する事に。だが、その精霊姫の正体は……。
「優しい世界」と「ざまあ」の2バージョン。

悪役令嬢は婚約破棄されてからが本番です~次期宰相殿下の溺愛が重すぎて困っています~
usako
恋愛
侯爵令嬢リリアナは、王太子から公衆の面前で婚約破棄を告げられる。
「あなたのような冷酷な女と結婚できない!」
そう断罪された瞬間――リリアナの人生は終わりを迎えるはずだった。
だが彼女は知っている。この展開が“破滅フラグ”だと。
生まれ変わりの記憶を持つ彼女は、今度こそ幸せを掴むと誓う。
ところが、彼女を拾ったのは冷徹と名高い次期宰相殿下シオン。
「君は俺の庇護下に入る。もう誰にも傷つけさせない」
傲慢な王太子にざまぁされ、愛しすぎる殿下から逃げられない――
運命に抗う令嬢と、彼女を手放せない男の甘く激しい恋の再生譚。
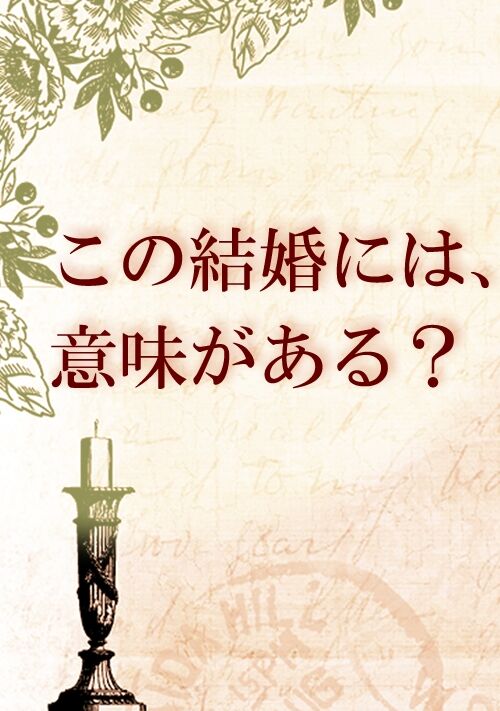
この結婚には、意味がある?
みこと。
恋愛
公爵家に降嫁した王女アリアは、初夜に夫から「オープンマリッジ」を提案される。
婚姻関係を維持しながら、他の異性との遊戯を認めろ、という要求を、アリアはどう解釈するのか?
王宮で冷遇されていた王女アリアの、密かな目的とは。
この結婚は、アリアにとってどんな意味がある?
※他のサイトにも掲載しています。
※他タイトル『沈黙の聖女は、ある日すべてを暴露する』も収録。←まったく別のお話です
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















