4 / 23
第4話 「旅立ちの朝」
しおりを挟む
翌朝、空が白み始める頃に目が覚めた。
いつもなら侍女が起こしに来る時間よりずっと早い。でも、目が冴えて眠れなかった。
今日から、本当に一人で旅に出る。
窓を開けると、冷たい朝の空気が部屋に流れ込んできた。庭園には朝露が降り、草花がキラキラと輝いている。
こんな朝の景色を、じっくり見たのは久しぶりだった。
着替えを済ませ、鏡の前に立つ。
いつもなら華やかなドレスを着るところだが、今日は違う。動きやすい旅装束。濃紺のシンプルなワンピースに、茶色の革のブーツ。マントは深緑色のものを選んだ。
髪は後ろで一つに束ね、帽子を被る。
鏡に映る自分は、今まで見たことのない姿だった。公爵令嬢らしさはどこにもない。でも、不思議と自分らしい気がした。
「お嬢様、朝食の準備ができております」
マルタの声が扉の向こうから聞こえる。
「今行くわ」
食堂に行くと、家族全員が揃っていた。
父、そして三日前に王立騎士学校から急遽戻ってきた弟のフェリックス。
「姉さん!」
十六歳の弟が椅子から立ち上がった。栗色の髪と緑の瞳は、亡き母譲りだ。
「本当に行っちゃうの?」
「ええ。もう決めたことよ」
「でも、危ないよ。一人で旅なんて」
フェリックスの心配そうな顔に、思わず笑みがこぼれる。
「大丈夫。あなたが思うより、お姉ちゃんは強いのよ」
「それは……そうかもしれないけど」
父が咳払いをした。
「フェリックス、座りなさい。エリアナの決断を尊重すると言っただろう」
「はい……」
弟は渋々座り直した。
朝食は、私の好きなものばかりだった。焼きたてのクロワッサン、自家製のジャム、新鮮な果物、温かいスープ。
マルタや料理長が、特別に用意してくれたのだろう。
「美味しい」
一口ずつ、味わって食べる。いつまでもこの温かさを覚えていたかった。
「エリアナ」
父が口を開いた。
「旅費と護身用の短剣は、荷物に入れておいた。それから、これを持っていきなさい」
父が差し出したのは、小さな水晶のペンダントだった。
「これは?」
「母さんが、お前の十歳の誕生日に渡すつもりだったものだ。魔力を込めることができる魔道具でな、危険な時には持ち主を守ってくれる」
ペンダントを手に取る。水晶の中に、虹色の光が閉じ込められているように見えた。
「大事にするわ」
「フェリックス、お前も何かあるんだろう」
父に促され、弟が照れくさそうに小さな包みを差し出した。
「これ、姉さんに。お守りだよ」
開けると、中には手作りの刺繍が施されたハンカチが入っていた。不器用な針目で、小さな花が縫い付けられている。
「自分で作ったの?」
「うん。下手だけど……姉さんの無事を祈って」
胸が熱くなる。
「ありがとう、フェリックス。大切に使うわ」
弟は嬉しそうに笑った。
食事を終え、玄関に向かう。
そこには、セバスチャンと使用人たちが整列して待っていた。
「エリアナお嬢様、どうかご無事で」
セバスチャンが深く頭を下げる。他の使用人たちも、それに続いた。
「みんな、ありがとう。必ず元気に帰ってくるわ」
マルタが目に涙を浮かべながら、大きな包みを手渡してきた。
「お嬢様、お弁当と非常食です。それから、この袋には旅に必要な薬草や包帯も入れておきました」
「マルタ……」
「どうか、お体を大事になさってください」
抱きしめたい衝動を抑えながら、私は笑顔で頷いた。
「行ってきます」
玄関を出ると、馬車が待っていた。御者はいない。今回は、自分で馬車を操縦するつもりだ。
馬車の準備をしているのは、厩舎番のトーマスだった。
「お嬢様、馬の扱いは大丈夫ですか?」
「ええ、小さい頃に教えてもらったもの。大丈夫よ」
「この子はジゼルと言います。おとなしくて賢い馬ですから、きっとお嬢様を守ってくれますよ」
栗毛の美しい馬が、私を見て優しく鼻を鳴らした。
「よろしくね、ジゼル」
馬の首を撫でると、ジゼルは嬉しそうに頭を擦り寄せてきた。
荷物を馬車に積み込み、御者台に座る。
振り返ると、家族と使用人たちが皆、手を振っていた。
この景色を、しっかりと目に焼き付ける。
「行くわよ、ジゼル」
手綱を取り、馬車が動き出す。
門を抜け、大通りに出た。
朝の王都は活気に満ちていた。市場の準備をする商人たち、開店前の掃除をする店主たち、学校へ向かう子供たち。
こんな普通の光景を、私はちゃんと見たことがあっただろうか?
いつも馬車の中から、ちらりと見るだけだった。でも今日は違う。自分で馬車を操り、自分の目で世界を見ている。
北門に差し掛かった時、門番が私を呼び止めた。
「お待ちください。通行証を」
「はい」
父が用意してくれた通行証を見せる。門番はそれを確認すると、驚いた顔で私を見た。
「これは……ヴェルナー公爵家の印が。お嬢様が一人で旅を?」
「ええ。問題ありませんか?」
「いえ、もちろん。ただ、お気をつけて。最近、北の街道で盗賊が出るという噂があります」
「気をつけるわ。ありがとう」
門が開き、私は王都を後にした。
街道に出ると、視界が一気に開けた。
青い空、緑の草原、遠くに見える山々。
こんなに広い世界があったなんて。
馬車を走らせながら、私は思わず笑った。
自由だ。
本当の意味で、自由になれた。
王都から一時間ほど走ると、小さな村が見えてきた。最初の休憩地点、ローゼンブルク村だ。
村の入り口にある井戸で、ジゼルに水を飲ませる。
「よく頑張ったわね」
馬を撫でていると、一人の老婆が近づいてきた。
「お嬢さん、一人旅かい?」
「ええ、そうです」
「珍しいねえ。最近は物騒だから、若い娘が一人で旅するなんて」
「気をつけます」
老婆はじっと私を見つめた。その目は、何かを見透かすような鋭さがあった。
「あんた、不思議な光を纏ってるね」
「え?」
「魔法使いかい?」
驚いて言葉に詰まる。この老婆には、私の魔力が見えているのだろうか?
「いえ、その……」
「隠さなくていいよ。あたしも昔は魔法使いだった。あんたの魔力、珍しい色をしてる。銀色に、全ての色が混ざったような……」
老婆は優しく微笑んだ。
「無属性魔法だね。懐かしいよ、その輝き」
「あなたも……?」
「いや、あたしは違う。でも、昔、無属性魔法使いの友人がいたんだ」
老婆は空を見上げた。
「いい子だったよ。優しくて、誰よりも努力家で。でも、世間はその子を受け入れなかった」
「その人は、今……?」
「北の山に住んでる。魔法の研究をしながら、静かに暮らしてるよ」
もしかして、レオンハルトのことだろうか?
「お嬢さん、あんたもその人に会いに行くのかい?」
「はい。レオンハルトという方を探しています」
老婆の目が大きく見開いた。
「レオンか!まあ、それなら話は早い」
老婆は懐から小さな地図を取り出した。
「これを持っていきな。レオンの家への近道が書いてある。街道を行くより一日早く着けるよ」
「ありがとうございます!でも、こんな大事なものを……」
「いいんだよ。あんたには、レオンが必要だ。そして、レオンにも、あんたみたいな子が必要なんだ」
老婆は私の手を握った。その手は、しわくちゃだけど温かかった。
「頑張りな、お嬢さん。あんたの道は、きっと明るい」
「はい!」
老婆に別れを告げ、私は再び馬車を走らせた。
もらった地図を見ると、確かに近道が記されている。少し険しい山道を通るようだが、それでも一日短縮できるなら価値がある。
午後になり、日差しが強くなってきた。
木陰で休憩を取りながら、マルタが作ってくれたお弁当を食べる。
サンドイッチ、フルーツ、それに冷たいお茶。どれも美味しくて、思わず笑顔になった。
「マルタの料理、やっぱり最高ね」
ジゼルにも餌と水をやり、しばらく休ませる。
木に寄りかかって空を見上げると、雲がゆっくりと流れていた。
こんな風に、何も考えずにぼんやりする時間。
それが、こんなに贅沢なものだったなんて。
しばらく休んで、再び出発する。
地図の近道に入ると、道は次第に狭く、険しくなっていった。木々が鬱蒼と茂り、薄暗い。
少し不安になったが、引き返すわけにはいかない。
「大丈夫、ジゼル。私たちなら進めるわ」
馬に声をかけながら、慎重に進む。
と、その時。
前方の茂みがガサガサと揺れた。
何かいる。
手綱を引き、馬車を止める。
心臓が早鐘を打つ。
茂みから現れたのは——
大きな狼だった。
いや、狼にしては大きすぎる。体長は優に二メートルを超えている。魔獣だ。
灰色の毛並み、鋭い牙、そして獲物を見据える赤い目。
「まずい……」
魔獣は私を睨みつけたまま、じりじりと近づいてくる。
ジゼルが怯え、いななく。
どうする?逃げる?でも、この狭い道では馬車は速度を出せない。すぐに追いつかれる。
戦う?でも、武器は短剣だけだ。魔獣相手に通用するとは思えない。
なら——
魔法を使うしかない。
深呼吸をして、集中する。
手のひらに意識を向けると、銀色の光が浮かび上がった。
魔獣が飛びかかってくる。
私は咄嗟に手を前に突き出した。
「止まって!」
銀色の光が、壁のように広がる。
魔獣はその壁にぶつかり、弾き飛ばされた。
驚いたように立ち上がり、私を睨む。
もう一度飛びかかろうとした、その時。
光の壁が変化した。
炎、水、風、土。全ての属性が混ざり合い、虹色の球体になる。
それは、私の意志に従って魔獣に向かって飛んでいった。
球体が魔獣に触れた瞬間、まばゆい光が辺りを包み込んだ。
光が収まると、魔獣の姿はなくなっていた。
いや、消えたわけじゃない。
そこには、小さな子犬ほどの大きさになった狼が、きょとんとした顔で座っていた。
「え……?」
私も驚いた。
攻撃魔法を使ったつもりだったのに、魔獣を縮小させてしまったらしい。
小さくなった狼は、私を見上げている。さっきまでの凶暴さはどこへやら、まるで子犬のように無邪気な目をしている。
「あなた……大丈夫?」
恐る恐る近づくと、狼はしっぽを振った。
完全に懐いているようだった。
これは、一体どういうこと?
無属性魔法は、予測不能だと聞いていた。でも、まさかこんな風に作用するなんて。
「困ったわね……」
でも、このまま放っておくわけにもいかない。元の大きさに戻ったら、また危険だ。
「ねえ、あなた。もう人を襲ったりしない?」
狼はクンクンと鳴いて、私の手を舐めた。
どうやら、完全に無害化されてしまったらしい。
「わかったわ。一緒に来る?」
狼は嬉しそうに吠えた。
こうして、私は予期せぬ旅の仲間を得た。
馬車に乗せると、狼は私の隣で丸くなって眠ってしまった。
「やれやれ。でも、一人じゃなくなったわね」
ジゼルに声をかけ、再び出発する。
無属性魔法の力を、初めて実戦で使った。
制御はまだ完璧じゃない。でも、確かに力は発動した。
レオンハルトに会えば、もっと正しい使い方を学べるはずだ。
夕日が山の向こうに沈み始めた頃、ようやく開けた場所に出た。
そこから見える景色は、息を呑むほど美しかった。
谷間に、小さな村が見える。フェルトハイム村だ。
「着いたわ」
小さな狼が目を覚まし、私を見上げる。
「さあ、行きましょう。新しい冒険の始まりよ」
馬車は、ゆっくりと村へと下っていった。
私の旅は、まだ始まったばかりだ。
いつもなら侍女が起こしに来る時間よりずっと早い。でも、目が冴えて眠れなかった。
今日から、本当に一人で旅に出る。
窓を開けると、冷たい朝の空気が部屋に流れ込んできた。庭園には朝露が降り、草花がキラキラと輝いている。
こんな朝の景色を、じっくり見たのは久しぶりだった。
着替えを済ませ、鏡の前に立つ。
いつもなら華やかなドレスを着るところだが、今日は違う。動きやすい旅装束。濃紺のシンプルなワンピースに、茶色の革のブーツ。マントは深緑色のものを選んだ。
髪は後ろで一つに束ね、帽子を被る。
鏡に映る自分は、今まで見たことのない姿だった。公爵令嬢らしさはどこにもない。でも、不思議と自分らしい気がした。
「お嬢様、朝食の準備ができております」
マルタの声が扉の向こうから聞こえる。
「今行くわ」
食堂に行くと、家族全員が揃っていた。
父、そして三日前に王立騎士学校から急遽戻ってきた弟のフェリックス。
「姉さん!」
十六歳の弟が椅子から立ち上がった。栗色の髪と緑の瞳は、亡き母譲りだ。
「本当に行っちゃうの?」
「ええ。もう決めたことよ」
「でも、危ないよ。一人で旅なんて」
フェリックスの心配そうな顔に、思わず笑みがこぼれる。
「大丈夫。あなたが思うより、お姉ちゃんは強いのよ」
「それは……そうかもしれないけど」
父が咳払いをした。
「フェリックス、座りなさい。エリアナの決断を尊重すると言っただろう」
「はい……」
弟は渋々座り直した。
朝食は、私の好きなものばかりだった。焼きたてのクロワッサン、自家製のジャム、新鮮な果物、温かいスープ。
マルタや料理長が、特別に用意してくれたのだろう。
「美味しい」
一口ずつ、味わって食べる。いつまでもこの温かさを覚えていたかった。
「エリアナ」
父が口を開いた。
「旅費と護身用の短剣は、荷物に入れておいた。それから、これを持っていきなさい」
父が差し出したのは、小さな水晶のペンダントだった。
「これは?」
「母さんが、お前の十歳の誕生日に渡すつもりだったものだ。魔力を込めることができる魔道具でな、危険な時には持ち主を守ってくれる」
ペンダントを手に取る。水晶の中に、虹色の光が閉じ込められているように見えた。
「大事にするわ」
「フェリックス、お前も何かあるんだろう」
父に促され、弟が照れくさそうに小さな包みを差し出した。
「これ、姉さんに。お守りだよ」
開けると、中には手作りの刺繍が施されたハンカチが入っていた。不器用な針目で、小さな花が縫い付けられている。
「自分で作ったの?」
「うん。下手だけど……姉さんの無事を祈って」
胸が熱くなる。
「ありがとう、フェリックス。大切に使うわ」
弟は嬉しそうに笑った。
食事を終え、玄関に向かう。
そこには、セバスチャンと使用人たちが整列して待っていた。
「エリアナお嬢様、どうかご無事で」
セバスチャンが深く頭を下げる。他の使用人たちも、それに続いた。
「みんな、ありがとう。必ず元気に帰ってくるわ」
マルタが目に涙を浮かべながら、大きな包みを手渡してきた。
「お嬢様、お弁当と非常食です。それから、この袋には旅に必要な薬草や包帯も入れておきました」
「マルタ……」
「どうか、お体を大事になさってください」
抱きしめたい衝動を抑えながら、私は笑顔で頷いた。
「行ってきます」
玄関を出ると、馬車が待っていた。御者はいない。今回は、自分で馬車を操縦するつもりだ。
馬車の準備をしているのは、厩舎番のトーマスだった。
「お嬢様、馬の扱いは大丈夫ですか?」
「ええ、小さい頃に教えてもらったもの。大丈夫よ」
「この子はジゼルと言います。おとなしくて賢い馬ですから、きっとお嬢様を守ってくれますよ」
栗毛の美しい馬が、私を見て優しく鼻を鳴らした。
「よろしくね、ジゼル」
馬の首を撫でると、ジゼルは嬉しそうに頭を擦り寄せてきた。
荷物を馬車に積み込み、御者台に座る。
振り返ると、家族と使用人たちが皆、手を振っていた。
この景色を、しっかりと目に焼き付ける。
「行くわよ、ジゼル」
手綱を取り、馬車が動き出す。
門を抜け、大通りに出た。
朝の王都は活気に満ちていた。市場の準備をする商人たち、開店前の掃除をする店主たち、学校へ向かう子供たち。
こんな普通の光景を、私はちゃんと見たことがあっただろうか?
いつも馬車の中から、ちらりと見るだけだった。でも今日は違う。自分で馬車を操り、自分の目で世界を見ている。
北門に差し掛かった時、門番が私を呼び止めた。
「お待ちください。通行証を」
「はい」
父が用意してくれた通行証を見せる。門番はそれを確認すると、驚いた顔で私を見た。
「これは……ヴェルナー公爵家の印が。お嬢様が一人で旅を?」
「ええ。問題ありませんか?」
「いえ、もちろん。ただ、お気をつけて。最近、北の街道で盗賊が出るという噂があります」
「気をつけるわ。ありがとう」
門が開き、私は王都を後にした。
街道に出ると、視界が一気に開けた。
青い空、緑の草原、遠くに見える山々。
こんなに広い世界があったなんて。
馬車を走らせながら、私は思わず笑った。
自由だ。
本当の意味で、自由になれた。
王都から一時間ほど走ると、小さな村が見えてきた。最初の休憩地点、ローゼンブルク村だ。
村の入り口にある井戸で、ジゼルに水を飲ませる。
「よく頑張ったわね」
馬を撫でていると、一人の老婆が近づいてきた。
「お嬢さん、一人旅かい?」
「ええ、そうです」
「珍しいねえ。最近は物騒だから、若い娘が一人で旅するなんて」
「気をつけます」
老婆はじっと私を見つめた。その目は、何かを見透かすような鋭さがあった。
「あんた、不思議な光を纏ってるね」
「え?」
「魔法使いかい?」
驚いて言葉に詰まる。この老婆には、私の魔力が見えているのだろうか?
「いえ、その……」
「隠さなくていいよ。あたしも昔は魔法使いだった。あんたの魔力、珍しい色をしてる。銀色に、全ての色が混ざったような……」
老婆は優しく微笑んだ。
「無属性魔法だね。懐かしいよ、その輝き」
「あなたも……?」
「いや、あたしは違う。でも、昔、無属性魔法使いの友人がいたんだ」
老婆は空を見上げた。
「いい子だったよ。優しくて、誰よりも努力家で。でも、世間はその子を受け入れなかった」
「その人は、今……?」
「北の山に住んでる。魔法の研究をしながら、静かに暮らしてるよ」
もしかして、レオンハルトのことだろうか?
「お嬢さん、あんたもその人に会いに行くのかい?」
「はい。レオンハルトという方を探しています」
老婆の目が大きく見開いた。
「レオンか!まあ、それなら話は早い」
老婆は懐から小さな地図を取り出した。
「これを持っていきな。レオンの家への近道が書いてある。街道を行くより一日早く着けるよ」
「ありがとうございます!でも、こんな大事なものを……」
「いいんだよ。あんたには、レオンが必要だ。そして、レオンにも、あんたみたいな子が必要なんだ」
老婆は私の手を握った。その手は、しわくちゃだけど温かかった。
「頑張りな、お嬢さん。あんたの道は、きっと明るい」
「はい!」
老婆に別れを告げ、私は再び馬車を走らせた。
もらった地図を見ると、確かに近道が記されている。少し険しい山道を通るようだが、それでも一日短縮できるなら価値がある。
午後になり、日差しが強くなってきた。
木陰で休憩を取りながら、マルタが作ってくれたお弁当を食べる。
サンドイッチ、フルーツ、それに冷たいお茶。どれも美味しくて、思わず笑顔になった。
「マルタの料理、やっぱり最高ね」
ジゼルにも餌と水をやり、しばらく休ませる。
木に寄りかかって空を見上げると、雲がゆっくりと流れていた。
こんな風に、何も考えずにぼんやりする時間。
それが、こんなに贅沢なものだったなんて。
しばらく休んで、再び出発する。
地図の近道に入ると、道は次第に狭く、険しくなっていった。木々が鬱蒼と茂り、薄暗い。
少し不安になったが、引き返すわけにはいかない。
「大丈夫、ジゼル。私たちなら進めるわ」
馬に声をかけながら、慎重に進む。
と、その時。
前方の茂みがガサガサと揺れた。
何かいる。
手綱を引き、馬車を止める。
心臓が早鐘を打つ。
茂みから現れたのは——
大きな狼だった。
いや、狼にしては大きすぎる。体長は優に二メートルを超えている。魔獣だ。
灰色の毛並み、鋭い牙、そして獲物を見据える赤い目。
「まずい……」
魔獣は私を睨みつけたまま、じりじりと近づいてくる。
ジゼルが怯え、いななく。
どうする?逃げる?でも、この狭い道では馬車は速度を出せない。すぐに追いつかれる。
戦う?でも、武器は短剣だけだ。魔獣相手に通用するとは思えない。
なら——
魔法を使うしかない。
深呼吸をして、集中する。
手のひらに意識を向けると、銀色の光が浮かび上がった。
魔獣が飛びかかってくる。
私は咄嗟に手を前に突き出した。
「止まって!」
銀色の光が、壁のように広がる。
魔獣はその壁にぶつかり、弾き飛ばされた。
驚いたように立ち上がり、私を睨む。
もう一度飛びかかろうとした、その時。
光の壁が変化した。
炎、水、風、土。全ての属性が混ざり合い、虹色の球体になる。
それは、私の意志に従って魔獣に向かって飛んでいった。
球体が魔獣に触れた瞬間、まばゆい光が辺りを包み込んだ。
光が収まると、魔獣の姿はなくなっていた。
いや、消えたわけじゃない。
そこには、小さな子犬ほどの大きさになった狼が、きょとんとした顔で座っていた。
「え……?」
私も驚いた。
攻撃魔法を使ったつもりだったのに、魔獣を縮小させてしまったらしい。
小さくなった狼は、私を見上げている。さっきまでの凶暴さはどこへやら、まるで子犬のように無邪気な目をしている。
「あなた……大丈夫?」
恐る恐る近づくと、狼はしっぽを振った。
完全に懐いているようだった。
これは、一体どういうこと?
無属性魔法は、予測不能だと聞いていた。でも、まさかこんな風に作用するなんて。
「困ったわね……」
でも、このまま放っておくわけにもいかない。元の大きさに戻ったら、また危険だ。
「ねえ、あなた。もう人を襲ったりしない?」
狼はクンクンと鳴いて、私の手を舐めた。
どうやら、完全に無害化されてしまったらしい。
「わかったわ。一緒に来る?」
狼は嬉しそうに吠えた。
こうして、私は予期せぬ旅の仲間を得た。
馬車に乗せると、狼は私の隣で丸くなって眠ってしまった。
「やれやれ。でも、一人じゃなくなったわね」
ジゼルに声をかけ、再び出発する。
無属性魔法の力を、初めて実戦で使った。
制御はまだ完璧じゃない。でも、確かに力は発動した。
レオンハルトに会えば、もっと正しい使い方を学べるはずだ。
夕日が山の向こうに沈み始めた頃、ようやく開けた場所に出た。
そこから見える景色は、息を呑むほど美しかった。
谷間に、小さな村が見える。フェルトハイム村だ。
「着いたわ」
小さな狼が目を覚まし、私を見上げる。
「さあ、行きましょう。新しい冒険の始まりよ」
馬車は、ゆっくりと村へと下っていった。
私の旅は、まだ始まったばかりだ。
34
あなたにおすすめの小説


処刑前夜に逃亡した悪役令嬢、五年後に氷の公爵様に捕まる〜冷徹旦那様が溺愛パパに豹変しましたが私の抱いている赤ちゃん実は人生2周目です〜
放浪人
恋愛
「処刑されるなんて真っ平ごめんです!」 無実の罪で投獄された悪役令嬢レティシア(中身は元社畜のアラサー日本人)は、処刑前夜、お腹の子供と共に脱獄し、辺境の田舎村へ逃亡した。 それから五年。薬師として穏やかに暮らしていた彼女のもとに、かつて自分を冷遇し、処刑を命じた夫――「氷の公爵」アレクセイが現れる。 殺される!と震えるレティシアだったが、再会した彼は地面に頭を擦り付け、まさかの溺愛キャラに豹変していて!?
「愛しているレティシア! 二度と離さない!」 「(顔が怖いです公爵様……!)」
不器用すぎて顔が怖い旦那様の暴走する溺愛。 そして、二人の息子であるシオン(1歳)は、実は前世で魔王を倒した「英雄」の生まれ変わりだった! 「パパとママは僕が守る(物理)」 最強の赤ちゃんが裏で暗躍し、聖女(自称)の陰謀も、帝国の侵略も、古代兵器も、ガラガラ一振りで粉砕していく。

なぜ、私に関係あるのかしら?
シエル
ファンタジー
「初めまして、アシュフォード公爵家一女、セシリア・アシュフォードと申します」
彼女は、つい先日までこの国の王太子殿下の婚約者だった。
そして今日、このトレヴァント辺境伯家へと嫁いできた。
「…レオンハルト・トレヴァントだ」
非道にも自らの実妹を長年にわたり虐げ、婚約者以外の男との不適切な関係を理由に、王太子妃に不適格とされ、貴族学院の卒業式で婚約破棄を宣告された。
そして、新たな婚約者として、その妹が王太子本人から指名されたのだった。
「私は君と夫婦になるつもりはないし、辺境伯夫人として扱うこともない」
この判断によって、どうなるかなども考えずに…
※ 中世ヨーロッパ風の世界観です。
※ ご都合主義ですので、ご了承下さい、
※ 画像はAIにて作成しております

『選ばれなかった令嬢は、世界の外で静かに微笑む』
ふわふわ
恋愛
婚約者エステランス・ショウシユウに一方的な婚約破棄を告げられ、
偽ヒロイン・エア・ソフィアの引き立て役として切り捨てられた令嬢
シャウ・エッセン。
「君はもう必要ない」
そう言われた瞬間、彼女は絶望しなかった。
――なぜなら、その言葉は“自由”の始まりだったから。
王宮の表舞台から退き、誰にも選ばれない立場を自ら選んだシャウ。
だが皮肉なことに、彼女が去った後の世界は、少しずつ歪みを正し始める。
奇跡に頼らず、誰かを神格化せず、
一人に負担を押し付けない仕組みへ――
それは、彼女がかつて静かに築き、手放した「考え方」そのものだった。
元婚約者はようやく理解し、
偽ヒロインは役割を降り、
世界は「彼女がいなくても回る場所」へと変わっていく。
復讐も断罪もない。
あるのは、物語の中心から降りるという、最も静かな“ざまぁ”。
これは、
選ばれなかった令嬢が、
誰の期待にも縛られず、
名もなき日々を生きることを選ぶ物語。

【完結】一途すぎる公爵様は眠り姫を溺愛している
月(ユエ)/久瀬まりか
恋愛
リュシエンヌ・ソワイエは16歳の子爵令嬢。皆が憧れるマルセル・クレイン伯爵令息に婚約を申し込まれたばかりで幸せいっぱいだ。
しかしある日を境にリュシエンヌは眠りから覚めなくなった。本人は自覚が無いまま12年の月日が過ぎ、目覚めた時には父母は亡くなり兄は結婚して子供がおり、さらにマルセルはリュシエンヌの親友アラベルと結婚していた。
突然のことに狼狽えるリュシエンヌ。しかも兄嫁はリュシエンヌを厄介者扱いしていて実家にはいられそうもない。
そんな彼女に手を差し伸べたのは、若きヴォルテーヌ公爵レオンだった……。
『残念な顔だとバカにされていた私が隣国の王子様に見初められました』『結婚前日に友人と入れ替わってしまった……!』に出てくる魔法大臣ゼインシリーズです。
表紙は「簡単表紙メーカー2」で作成しました。

婚約破棄されて去ったら、私がいなくても世界は回り始めました
鷹 綾
恋愛
「君との婚約は破棄する。聖女フロンこそが、真に王国を導く存在だ」
王太子アントナン・ドームにそう告げられ、
公爵令嬢エミー・マイセンは、王都を去った。
彼女が担ってきたのは、判断、調整、責任――
国が回るために必要なすべて。
だが、それは「有能」ではなく、「依存」だった。
隣国へ渡ったエミーは、
一人で背負わない仕組みを選び、
名前が残らない判断の在り方を築いていく。
一方、彼女を失った王都は混乱し、
やがて気づく――
必要だったのは彼女ではなく、
彼女が手放そうとしていた“仕組み”だったのだと。
偽聖女フロンの化けの皮が剥がれ、
王太子アントナンは、
「決めた後に立ち続ける重さ」と向き合い始める。
だが、もうエミーは戻らない。
これは、
捨てられた令嬢が復讐する物語ではない。
溺愛で救われる物語でもない。
「いなくても回る世界」を完成させた女性と、
彼女を必要としなくなった国の、
静かで誇り高い別れの物語。
英雄が消えても、世界は続いていく――
アルファポリス女子読者向け
〈静かな婚約破棄ざまぁ〉×〈大人の再生譚〉。

『悪役令嬢は、二度目の人生で無言を貫く。~処刑回避のために黙っていただけなのに、なぜか冷徹宰相様から「君こそ運命の人だ」と溺愛さています~』
放浪人
恋愛
「もう、余計なことは喋りません(処刑されたくないので!)」
王太子の婚約者エリスは、無実の罪を着せられた際、必死に弁解しようと叫び散らした結果「見苦しい」と断罪され、処刑されてしまった。 死に戻った彼女は悟る。「口は災いの元。二度目の人生は、何があっても口を閉ざして生き延びよう」と。
しかし、断罪の場で恐怖のあまり沈黙を貫いた結果、その姿は「弁解せず耐え忍ぶ高潔な令嬢」として称賛されてしまう。 さらに、人間嫌いの冷徹宰相クラウスに「私の静寂を理解する唯一の女性」と盛大な勘違いをされ、求婚されてしまい……!?
「君の沈黙は、愛の肯定だね?」(違います、怖くて固まっているだけです!) 「この国の危機を、一目で見抜くとは」(ただ臭かったから鼻を押さえただけです!)
怯えて黙っているだけの元悪役令嬢と、彼女の沈黙を「深遠な知性」と解釈して溺愛する最強宰相。 転生ヒロインの妨害も、隣国の陰謀も、全て「無言」で解決(?)していく、すれ違いロマンティック・コメディ! 最後はちゃんと言葉で愛を伝えて、最高のハッピーエンドを迎えます。
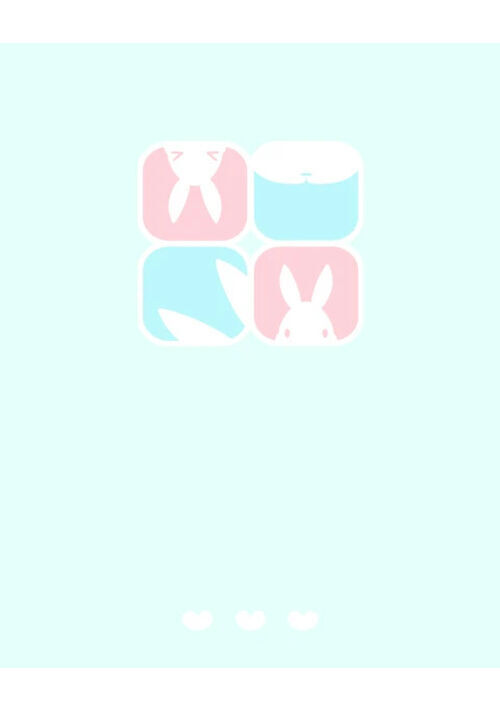
【完結】王太子に婚約破棄され、父親に修道院行きを命じられた公爵令嬢、もふもふ聖獣に溺愛される〜王太子が謝罪したいと思ったときには手遅れでした
まほりろ
恋愛
【完結済み】
公爵令嬢のアリーゼ・バイスは一学年の終わりの進級パーティーで、六年間婚約していた王太子から婚約破棄される。
壇上に立つ王太子の腕の中には桃色の髪と瞳の|庇護《ひご》欲をそそる愛らしい少女、男爵令嬢のレニ・ミュルべがいた。
アリーゼは男爵令嬢をいじめた|冤罪《えんざい》を着せられ、男爵令嬢の取り巻きの令息たちにののしられ、卵やジュースを投げつけられ、屈辱を味わいながらパーティー会場をあとにした。
家に帰ったアリーゼは父親から、貴族社会に向いてないと言われ修道院行きを命じられる。
修道院には人懐っこい仔猫がいて……アリーゼは仔猫の愛らしさにメロメロになる。
しかし仔猫の正体は聖獣で……。
表紙素材はあぐりりんこ様よりお借りしております。
「Copyright(C)2021-九頭竜坂まほろん」
・ざまぁ有り(死ネタ有り)・ざまぁ回には「ざまぁ」と明記します。
・婚約破棄、アホ王子、モフモフ、猫耳、聖獣、溺愛。
2021/11/27HOTランキング3位、28日HOTランキング2位に入りました! 読んで下さった皆様、ありがとうございます!
誤字報告ありがとうございます! 大変助かっております!!
アルファポリスに先行投稿しています。他サイトにもアップしています。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















