13 / 23
第13話 「暗躍する影」
しおりを挟む
シュヴァルツヴァルト村での一件から一週間が経った。
アルトシュタット城の一室で、私は辺境伯に報告書を提出していた。魔獣との戦い、森の異変、そして呪いの存在について、詳細に記したものだ。
「呪いの触媒……ですか」
ルドルフ辺境伯は、報告書を読みながら深刻な表情を浮かべた。
「これは、ただ事ではありませんね」
「はい。おそらく、森の土地を狙っている者がいます」
レオンが、テーブルの上に黒い水晶を置いた。
「この触媒は、かなり高度な呪術で精製されています。素人に扱えるものではない」
「つまり、専門の呪術師を雇える、相当な資産を持った人物ということか」
辺境伯が顎に手を当てて考え込む。
「心当たりは?」
「一つだけ」
辺境伯が立ち上がり、窓の外を見た。
「隣接するグラウベルク子爵領です。彼らは以前から、シュヴァルツヴァルトの森を自領に編入したいと主張していました」
「でも、森は辺境伯領ですよね?」
「ええ。しかし、グラウベルク子爵は宮廷に強い影響力を持っています。もし森が荒廃し、私が管理能力なしと判断されれば……」
「領地を没収される」
レオンが冷たく言い放った。
「よくある手口ですね」
「卑劣だわ」
私は拳を握りしめた。
「森を殺し、魔獣を追い出し、村人を苦しめる。全ては土地が欲しいから?」
「貴族の世界では、よくあることです」
辺境伯が苦々しく笑った。
「だからこそ、あなた方の力が必要なのです。証拠を掴み、彼らの陰謀を暴きたい」
「わかりました」
レオンが頷いた。
「調査します。ただし、時間はかかりますよ」
「構いません。慎重に、確実に進めてください」
部屋を出ると、廊下でカイルが待っていた。
「お疲れ様です。父上から聞きました。グラウベルク子爵のことを調べるんですね」
「ええ。あなたも、何か知ってる?」
「少しだけ。子爵は五十代の男性で、商売に長けています。特に、土地の転売で財を成した」
カイルの声が低くなる。
「噂では、手段を選ばぬ人物だと。過去にも、いくつかの領地で不審な出来事があったそうです」
「不審な出来事?」
「森の枯渇、水源の汚染、魔獣の異常発生……。そして、その度に子爵が土地を手に入れている」
つまりは、今回も同じ手口だということだ。
「許せないわね」
「ええ。でも、証拠がなければ動けません」
カイルが私を見た。
「エリアナ様、危険な調査になるかもしれません。無理はしないでください」
「大丈夫よ。レオンがいるもの」
そう言いながらも、胸の奥に不安が芽生えていた。
相手は、宮廷に影響力を持つ貴族。
下手を打てば、私たちだけでなく、辺境伯家にも累が及ぶ。
慎重に、そして確実に動かなければならない。
翌日、レオンと私はグラウベルク子爵領との境界近くの村を訪れた。
表向きは、魔法使いとしての巡回だ。
村は、アルトシュタット領の村々と比べて、明らかに豊かだった。
整備された道、立派な家屋、よく肥えた家畜。
でも、どこか違和感があった。
村人たちの顔に、笑顔が少ない。
「いらっしゃい」
宿屋の主人が、機械的に挨拶した。
私たちは部屋を取り、情報収集を始めた。
「この村、妙に静かだな」
レオンが窓から外を見ながら呟いた。
「ええ。豊かなのに、活気がない」
「何かを恐れている顔だ」
夕方、私は一人で村を歩いてみた。
市場を覗くと、商人たちが無言で商品を並べている。
子供たちも、静かに遊んでいる。
まるで、誰かに監視されているかのような雰囲気だった。
「すみません」
私は、野菜を売っている老婆に声をかけた。
「この村、いつもこんなに静かなんですか?」
老婆は一瞬、警戒した目で私を見た。
そして、小声で言った。
「旅の方なら、早く出て行った方がいい」
「え?」
「ここは、子爵様の目が光っている。余計なことを聞いたり、話したりすれば……」
老婆が口を閉ざした。
その時、数人の男たちが近づいてきた。
全員、剣を腰に下げている。子爵の私兵だ。
「おい、旅の者。何を聞いている」
リーダー格の男が、威圧的な声で言った。
「いえ、ただ野菜を買おうと思って」
「ならさっさと買って宿に戻れ。日が暮れてからの外出は禁止されている」
「禁止?なぜ?」
「決まりだ。理由を説明する必要はない」
男が一歩近づく。
明らかに、追い払おうとしている。
「わかりました」
私は野菜を買い、その場を離れた。
だが、男たちの視線が背中に突き刺さるのを感じた。
宿に戻ると、レオンが待っていた。
「どうだった?」
「おかしいわ。村全体が、何かに怯えている」
私は、老婆とのやり取りを話した。
「監視社会か。典型的な恐怖支配だな」
レオンが苦い顔をした。
「おそらく、子爵に逆らった者は、何らかの制裁を受けるんだろう」
「ひどいわ」
「貴族の中には、そういう輩もいる。残念ながらな」
その夜、私は眠れずにいた。
窓の外を見ると、村は完全に静まり返っている。
明かりもほとんどなく、まるで死んだ村のようだった。
その時、窓の下で何かが動いた。
黒い影が、建物の間を素早く移動している。
私は、そっと部屋を出た。
廊下は暗く、足音を立てないように歩く。
外に出ると、影はすでに村はずれの森へ向かっていた。
後をつける。
月明かりを頼りに、慎重に進む。
森に入ると、小さな小屋があった。
窓から光が漏れている。
そっと近づき、中を覗くと——
驚くべき光景が広がっていた。
部屋の中央には、大きな魔法陣が描かれている。
その周りに、黒いローブを纏った人物が五人。
彼らは何かを詠唱しながら、魔法陣に魔力を注ぎ込んでいた。
魔法陣の中心には、黒い水晶が置かれている。
あれは——シュヴァルツヴァルトで見つけたものと同じだ。
「呪術師……!」
思わず声が漏れた。
その瞬間、ローブの一人が振り返った。
「誰だ!」
扉が勢いよく開き、私は咄嗟に身を隠した。
「誰かいるぞ!探せ!」
男たちが散開する。
まずい。
私は森の奥へと走った。
枝が顔を引っ掻き、足元の根に何度もつまずきそうになる。
でも、止まれない。
背後から、足音が迫ってくる。
「待て!」
振り返ると、ローブの男が手を伸ばしてきた。
その手が、私の腕を掴もうとした瞬間——
銀色の光が弾けた。
反射的に放った魔法が、男を弾き飛ばす。
「魔法使いか!」
他の男たちも追いついてきた。
五人全員が、私を囲む。
「面倒なことになったな」
リーダー格の男が、禍々しい黒い光を手のひらに集めた。
「見られたからには、消えてもらうしかない」
黒い光が、私に向かって放たれた。
私は咄嗟に防御壁を展開する。
しかし、黒い光は壁を貫通してきた。
呪術だ。通常の魔法とは質が違う。
咄嗟に横に跳び、攻撃をかわす。
だが、すぐに次の攻撃が来た。
五人全員が、魔法を放ってくる。
このままでは避けきれない。
覚悟を決めた、その時。
「エリアナ!」
レオンの声が響く。
彼が、私の前に立ちはだかった。
レオンの周りに、巨大な魔法陣が展開される。
呪術師たちの攻撃を、全て弾き返した。
「レオン!」
「無茶するな、馬鹿弟子!」
彼が手を掲げると、青い炎が呪術師たちを包み込んだ。
「ぐあああ!」
男たちが悲鳴を上げる。
でも、レオンの炎は彼らを傷つけなかった。
ただ、動きを封じただけだ。
「さあ、大人しく話してもらおうか」
レオンが冷たく笑った。
「誰の命令で、呪術を行っている?」
「言うものか……!」
リーダー格の男が歯を食いしばる。
その時、森の奥から複数の足音が聞こえてきた。
現れたのは、フェンリルと黒牙の群れだった。
「エリアナ、大丈夫か」
フェンリルが私の隣に立つ。
「あなた、どうして?」
「お前の匂いを追ってきた。危険を感じてな」
フェンリルが呪術師たちを睨む。
「この者たち、悪い魔力を纏っている」
「ああ。こいつらが、森に呪いをかけた張本人だ」
レオンが、男たちを見下ろした。
「さて、どうする?このまま黙っているか?それとも、魔獣たちに引き渡すか?」
その言葉に、男たちの顔が青ざめた。
「わ、わかった!話す!話すから!」
リーダーが叫んだ。
「俺たちは、グラウベルク子爵に雇われた。森を枯らし、辺境伯領を弱体化させろと……!」
「証拠は?」
「子爵からの書簡を持っている。報酬の約束が書かれた……」
男が震える手で、懐から一通の手紙を取り出した。
レオンがそれを受け取り、目を通す。
「これは……決定的だな」
彼が満足そうに笑った。
「エリアナ、これで証拠は掴めた」
「本当に?」
「ああ。これがあれば、子爵を訴えられる」
私は、ほっと胸を撫で下ろした。
危険な目には遭ったが、目的は達成できた。
「フェンリル、この男たち、アルトシュタット城まで連れて行ってくれる?」
「任せろ。我が群れが、しっかり監視する」
フェンリルが牙を剥いた。
呪術師たちは、恐怖で震えていた。
翌日、私たちは証拠と呪術師たちを連れて城に戻った。
辺境伯は、書簡を読んで深く頷いた。
「これは、動かぬ証拠です。すぐに王宮に報告します」
「グラウベルク子爵は、裁かれますか?」
「ええ。これだけの証拠があれば、宮廷も動かざるを得ないでしょう」
辺境伯が、私とレオンを見た。
「お二人のおかげです。本当にありがとうございました」
「まだ終わっていません」
レオンが厳しい顔で言った。
「子爵は、必ず反撃してきます。気をつけてください」
「わかっています。こちらも、準備を整えます」
私たちは、一旦レオンの家に戻ることにした。
馬車の中で、レオンが言った。
「エリアナ、よく頑張った。でも、無茶はするな」
「ごめんなさい」
「謝らなくていい。お前の行動力は評価する。ただ、もう少し慎重になれ」
彼が私の頭を撫でた。
「お前は、大事な弟子なんだからな」
その言葉が、温かかった。
窓の外では、夕日が沈みかけていた。
長い一日だった。
でも、また一つ、正義を守れた。
これからも、きっと困難は続くだろう。
でも、諦めない。
人々を守り、理不尽と戦い続ける。
それが、私の選んだ道だから。
アルトシュタット城の一室で、私は辺境伯に報告書を提出していた。魔獣との戦い、森の異変、そして呪いの存在について、詳細に記したものだ。
「呪いの触媒……ですか」
ルドルフ辺境伯は、報告書を読みながら深刻な表情を浮かべた。
「これは、ただ事ではありませんね」
「はい。おそらく、森の土地を狙っている者がいます」
レオンが、テーブルの上に黒い水晶を置いた。
「この触媒は、かなり高度な呪術で精製されています。素人に扱えるものではない」
「つまり、専門の呪術師を雇える、相当な資産を持った人物ということか」
辺境伯が顎に手を当てて考え込む。
「心当たりは?」
「一つだけ」
辺境伯が立ち上がり、窓の外を見た。
「隣接するグラウベルク子爵領です。彼らは以前から、シュヴァルツヴァルトの森を自領に編入したいと主張していました」
「でも、森は辺境伯領ですよね?」
「ええ。しかし、グラウベルク子爵は宮廷に強い影響力を持っています。もし森が荒廃し、私が管理能力なしと判断されれば……」
「領地を没収される」
レオンが冷たく言い放った。
「よくある手口ですね」
「卑劣だわ」
私は拳を握りしめた。
「森を殺し、魔獣を追い出し、村人を苦しめる。全ては土地が欲しいから?」
「貴族の世界では、よくあることです」
辺境伯が苦々しく笑った。
「だからこそ、あなた方の力が必要なのです。証拠を掴み、彼らの陰謀を暴きたい」
「わかりました」
レオンが頷いた。
「調査します。ただし、時間はかかりますよ」
「構いません。慎重に、確実に進めてください」
部屋を出ると、廊下でカイルが待っていた。
「お疲れ様です。父上から聞きました。グラウベルク子爵のことを調べるんですね」
「ええ。あなたも、何か知ってる?」
「少しだけ。子爵は五十代の男性で、商売に長けています。特に、土地の転売で財を成した」
カイルの声が低くなる。
「噂では、手段を選ばぬ人物だと。過去にも、いくつかの領地で不審な出来事があったそうです」
「不審な出来事?」
「森の枯渇、水源の汚染、魔獣の異常発生……。そして、その度に子爵が土地を手に入れている」
つまりは、今回も同じ手口だということだ。
「許せないわね」
「ええ。でも、証拠がなければ動けません」
カイルが私を見た。
「エリアナ様、危険な調査になるかもしれません。無理はしないでください」
「大丈夫よ。レオンがいるもの」
そう言いながらも、胸の奥に不安が芽生えていた。
相手は、宮廷に影響力を持つ貴族。
下手を打てば、私たちだけでなく、辺境伯家にも累が及ぶ。
慎重に、そして確実に動かなければならない。
翌日、レオンと私はグラウベルク子爵領との境界近くの村を訪れた。
表向きは、魔法使いとしての巡回だ。
村は、アルトシュタット領の村々と比べて、明らかに豊かだった。
整備された道、立派な家屋、よく肥えた家畜。
でも、どこか違和感があった。
村人たちの顔に、笑顔が少ない。
「いらっしゃい」
宿屋の主人が、機械的に挨拶した。
私たちは部屋を取り、情報収集を始めた。
「この村、妙に静かだな」
レオンが窓から外を見ながら呟いた。
「ええ。豊かなのに、活気がない」
「何かを恐れている顔だ」
夕方、私は一人で村を歩いてみた。
市場を覗くと、商人たちが無言で商品を並べている。
子供たちも、静かに遊んでいる。
まるで、誰かに監視されているかのような雰囲気だった。
「すみません」
私は、野菜を売っている老婆に声をかけた。
「この村、いつもこんなに静かなんですか?」
老婆は一瞬、警戒した目で私を見た。
そして、小声で言った。
「旅の方なら、早く出て行った方がいい」
「え?」
「ここは、子爵様の目が光っている。余計なことを聞いたり、話したりすれば……」
老婆が口を閉ざした。
その時、数人の男たちが近づいてきた。
全員、剣を腰に下げている。子爵の私兵だ。
「おい、旅の者。何を聞いている」
リーダー格の男が、威圧的な声で言った。
「いえ、ただ野菜を買おうと思って」
「ならさっさと買って宿に戻れ。日が暮れてからの外出は禁止されている」
「禁止?なぜ?」
「決まりだ。理由を説明する必要はない」
男が一歩近づく。
明らかに、追い払おうとしている。
「わかりました」
私は野菜を買い、その場を離れた。
だが、男たちの視線が背中に突き刺さるのを感じた。
宿に戻ると、レオンが待っていた。
「どうだった?」
「おかしいわ。村全体が、何かに怯えている」
私は、老婆とのやり取りを話した。
「監視社会か。典型的な恐怖支配だな」
レオンが苦い顔をした。
「おそらく、子爵に逆らった者は、何らかの制裁を受けるんだろう」
「ひどいわ」
「貴族の中には、そういう輩もいる。残念ながらな」
その夜、私は眠れずにいた。
窓の外を見ると、村は完全に静まり返っている。
明かりもほとんどなく、まるで死んだ村のようだった。
その時、窓の下で何かが動いた。
黒い影が、建物の間を素早く移動している。
私は、そっと部屋を出た。
廊下は暗く、足音を立てないように歩く。
外に出ると、影はすでに村はずれの森へ向かっていた。
後をつける。
月明かりを頼りに、慎重に進む。
森に入ると、小さな小屋があった。
窓から光が漏れている。
そっと近づき、中を覗くと——
驚くべき光景が広がっていた。
部屋の中央には、大きな魔法陣が描かれている。
その周りに、黒いローブを纏った人物が五人。
彼らは何かを詠唱しながら、魔法陣に魔力を注ぎ込んでいた。
魔法陣の中心には、黒い水晶が置かれている。
あれは——シュヴァルツヴァルトで見つけたものと同じだ。
「呪術師……!」
思わず声が漏れた。
その瞬間、ローブの一人が振り返った。
「誰だ!」
扉が勢いよく開き、私は咄嗟に身を隠した。
「誰かいるぞ!探せ!」
男たちが散開する。
まずい。
私は森の奥へと走った。
枝が顔を引っ掻き、足元の根に何度もつまずきそうになる。
でも、止まれない。
背後から、足音が迫ってくる。
「待て!」
振り返ると、ローブの男が手を伸ばしてきた。
その手が、私の腕を掴もうとした瞬間——
銀色の光が弾けた。
反射的に放った魔法が、男を弾き飛ばす。
「魔法使いか!」
他の男たちも追いついてきた。
五人全員が、私を囲む。
「面倒なことになったな」
リーダー格の男が、禍々しい黒い光を手のひらに集めた。
「見られたからには、消えてもらうしかない」
黒い光が、私に向かって放たれた。
私は咄嗟に防御壁を展開する。
しかし、黒い光は壁を貫通してきた。
呪術だ。通常の魔法とは質が違う。
咄嗟に横に跳び、攻撃をかわす。
だが、すぐに次の攻撃が来た。
五人全員が、魔法を放ってくる。
このままでは避けきれない。
覚悟を決めた、その時。
「エリアナ!」
レオンの声が響く。
彼が、私の前に立ちはだかった。
レオンの周りに、巨大な魔法陣が展開される。
呪術師たちの攻撃を、全て弾き返した。
「レオン!」
「無茶するな、馬鹿弟子!」
彼が手を掲げると、青い炎が呪術師たちを包み込んだ。
「ぐあああ!」
男たちが悲鳴を上げる。
でも、レオンの炎は彼らを傷つけなかった。
ただ、動きを封じただけだ。
「さあ、大人しく話してもらおうか」
レオンが冷たく笑った。
「誰の命令で、呪術を行っている?」
「言うものか……!」
リーダー格の男が歯を食いしばる。
その時、森の奥から複数の足音が聞こえてきた。
現れたのは、フェンリルと黒牙の群れだった。
「エリアナ、大丈夫か」
フェンリルが私の隣に立つ。
「あなた、どうして?」
「お前の匂いを追ってきた。危険を感じてな」
フェンリルが呪術師たちを睨む。
「この者たち、悪い魔力を纏っている」
「ああ。こいつらが、森に呪いをかけた張本人だ」
レオンが、男たちを見下ろした。
「さて、どうする?このまま黙っているか?それとも、魔獣たちに引き渡すか?」
その言葉に、男たちの顔が青ざめた。
「わ、わかった!話す!話すから!」
リーダーが叫んだ。
「俺たちは、グラウベルク子爵に雇われた。森を枯らし、辺境伯領を弱体化させろと……!」
「証拠は?」
「子爵からの書簡を持っている。報酬の約束が書かれた……」
男が震える手で、懐から一通の手紙を取り出した。
レオンがそれを受け取り、目を通す。
「これは……決定的だな」
彼が満足そうに笑った。
「エリアナ、これで証拠は掴めた」
「本当に?」
「ああ。これがあれば、子爵を訴えられる」
私は、ほっと胸を撫で下ろした。
危険な目には遭ったが、目的は達成できた。
「フェンリル、この男たち、アルトシュタット城まで連れて行ってくれる?」
「任せろ。我が群れが、しっかり監視する」
フェンリルが牙を剥いた。
呪術師たちは、恐怖で震えていた。
翌日、私たちは証拠と呪術師たちを連れて城に戻った。
辺境伯は、書簡を読んで深く頷いた。
「これは、動かぬ証拠です。すぐに王宮に報告します」
「グラウベルク子爵は、裁かれますか?」
「ええ。これだけの証拠があれば、宮廷も動かざるを得ないでしょう」
辺境伯が、私とレオンを見た。
「お二人のおかげです。本当にありがとうございました」
「まだ終わっていません」
レオンが厳しい顔で言った。
「子爵は、必ず反撃してきます。気をつけてください」
「わかっています。こちらも、準備を整えます」
私たちは、一旦レオンの家に戻ることにした。
馬車の中で、レオンが言った。
「エリアナ、よく頑張った。でも、無茶はするな」
「ごめんなさい」
「謝らなくていい。お前の行動力は評価する。ただ、もう少し慎重になれ」
彼が私の頭を撫でた。
「お前は、大事な弟子なんだからな」
その言葉が、温かかった。
窓の外では、夕日が沈みかけていた。
長い一日だった。
でも、また一つ、正義を守れた。
これからも、きっと困難は続くだろう。
でも、諦めない。
人々を守り、理不尽と戦い続ける。
それが、私の選んだ道だから。
13
あなたにおすすめの小説


処刑前夜に逃亡した悪役令嬢、五年後に氷の公爵様に捕まる〜冷徹旦那様が溺愛パパに豹変しましたが私の抱いている赤ちゃん実は人生2周目です〜
放浪人
恋愛
「処刑されるなんて真っ平ごめんです!」 無実の罪で投獄された悪役令嬢レティシア(中身は元社畜のアラサー日本人)は、処刑前夜、お腹の子供と共に脱獄し、辺境の田舎村へ逃亡した。 それから五年。薬師として穏やかに暮らしていた彼女のもとに、かつて自分を冷遇し、処刑を命じた夫――「氷の公爵」アレクセイが現れる。 殺される!と震えるレティシアだったが、再会した彼は地面に頭を擦り付け、まさかの溺愛キャラに豹変していて!?
「愛しているレティシア! 二度と離さない!」 「(顔が怖いです公爵様……!)」
不器用すぎて顔が怖い旦那様の暴走する溺愛。 そして、二人の息子であるシオン(1歳)は、実は前世で魔王を倒した「英雄」の生まれ変わりだった! 「パパとママは僕が守る(物理)」 最強の赤ちゃんが裏で暗躍し、聖女(自称)の陰謀も、帝国の侵略も、古代兵器も、ガラガラ一振りで粉砕していく。

なぜ、私に関係あるのかしら?
シエル
ファンタジー
「初めまして、アシュフォード公爵家一女、セシリア・アシュフォードと申します」
彼女は、つい先日までこの国の王太子殿下の婚約者だった。
そして今日、このトレヴァント辺境伯家へと嫁いできた。
「…レオンハルト・トレヴァントだ」
非道にも自らの実妹を長年にわたり虐げ、婚約者以外の男との不適切な関係を理由に、王太子妃に不適格とされ、貴族学院の卒業式で婚約破棄を宣告された。
そして、新たな婚約者として、その妹が王太子本人から指名されたのだった。
「私は君と夫婦になるつもりはないし、辺境伯夫人として扱うこともない」
この判断によって、どうなるかなども考えずに…
※ 中世ヨーロッパ風の世界観です。
※ ご都合主義ですので、ご了承下さい、
※ 画像はAIにて作成しております

『選ばれなかった令嬢は、世界の外で静かに微笑む』
ふわふわ
恋愛
婚約者エステランス・ショウシユウに一方的な婚約破棄を告げられ、
偽ヒロイン・エア・ソフィアの引き立て役として切り捨てられた令嬢
シャウ・エッセン。
「君はもう必要ない」
そう言われた瞬間、彼女は絶望しなかった。
――なぜなら、その言葉は“自由”の始まりだったから。
王宮の表舞台から退き、誰にも選ばれない立場を自ら選んだシャウ。
だが皮肉なことに、彼女が去った後の世界は、少しずつ歪みを正し始める。
奇跡に頼らず、誰かを神格化せず、
一人に負担を押し付けない仕組みへ――
それは、彼女がかつて静かに築き、手放した「考え方」そのものだった。
元婚約者はようやく理解し、
偽ヒロインは役割を降り、
世界は「彼女がいなくても回る場所」へと変わっていく。
復讐も断罪もない。
あるのは、物語の中心から降りるという、最も静かな“ざまぁ”。
これは、
選ばれなかった令嬢が、
誰の期待にも縛られず、
名もなき日々を生きることを選ぶ物語。

【完結】一途すぎる公爵様は眠り姫を溺愛している
月(ユエ)/久瀬まりか
恋愛
リュシエンヌ・ソワイエは16歳の子爵令嬢。皆が憧れるマルセル・クレイン伯爵令息に婚約を申し込まれたばかりで幸せいっぱいだ。
しかしある日を境にリュシエンヌは眠りから覚めなくなった。本人は自覚が無いまま12年の月日が過ぎ、目覚めた時には父母は亡くなり兄は結婚して子供がおり、さらにマルセルはリュシエンヌの親友アラベルと結婚していた。
突然のことに狼狽えるリュシエンヌ。しかも兄嫁はリュシエンヌを厄介者扱いしていて実家にはいられそうもない。
そんな彼女に手を差し伸べたのは、若きヴォルテーヌ公爵レオンだった……。
『残念な顔だとバカにされていた私が隣国の王子様に見初められました』『結婚前日に友人と入れ替わってしまった……!』に出てくる魔法大臣ゼインシリーズです。
表紙は「簡単表紙メーカー2」で作成しました。

婚約破棄されて去ったら、私がいなくても世界は回り始めました
鷹 綾
恋愛
「君との婚約は破棄する。聖女フロンこそが、真に王国を導く存在だ」
王太子アントナン・ドームにそう告げられ、
公爵令嬢エミー・マイセンは、王都を去った。
彼女が担ってきたのは、判断、調整、責任――
国が回るために必要なすべて。
だが、それは「有能」ではなく、「依存」だった。
隣国へ渡ったエミーは、
一人で背負わない仕組みを選び、
名前が残らない判断の在り方を築いていく。
一方、彼女を失った王都は混乱し、
やがて気づく――
必要だったのは彼女ではなく、
彼女が手放そうとしていた“仕組み”だったのだと。
偽聖女フロンの化けの皮が剥がれ、
王太子アントナンは、
「決めた後に立ち続ける重さ」と向き合い始める。
だが、もうエミーは戻らない。
これは、
捨てられた令嬢が復讐する物語ではない。
溺愛で救われる物語でもない。
「いなくても回る世界」を完成させた女性と、
彼女を必要としなくなった国の、
静かで誇り高い別れの物語。
英雄が消えても、世界は続いていく――
アルファポリス女子読者向け
〈静かな婚約破棄ざまぁ〉×〈大人の再生譚〉。

『悪役令嬢は、二度目の人生で無言を貫く。~処刑回避のために黙っていただけなのに、なぜか冷徹宰相様から「君こそ運命の人だ」と溺愛さています~』
放浪人
恋愛
「もう、余計なことは喋りません(処刑されたくないので!)」
王太子の婚約者エリスは、無実の罪を着せられた際、必死に弁解しようと叫び散らした結果「見苦しい」と断罪され、処刑されてしまった。 死に戻った彼女は悟る。「口は災いの元。二度目の人生は、何があっても口を閉ざして生き延びよう」と。
しかし、断罪の場で恐怖のあまり沈黙を貫いた結果、その姿は「弁解せず耐え忍ぶ高潔な令嬢」として称賛されてしまう。 さらに、人間嫌いの冷徹宰相クラウスに「私の静寂を理解する唯一の女性」と盛大な勘違いをされ、求婚されてしまい……!?
「君の沈黙は、愛の肯定だね?」(違います、怖くて固まっているだけです!) 「この国の危機を、一目で見抜くとは」(ただ臭かったから鼻を押さえただけです!)
怯えて黙っているだけの元悪役令嬢と、彼女の沈黙を「深遠な知性」と解釈して溺愛する最強宰相。 転生ヒロインの妨害も、隣国の陰謀も、全て「無言」で解決(?)していく、すれ違いロマンティック・コメディ! 最後はちゃんと言葉で愛を伝えて、最高のハッピーエンドを迎えます。
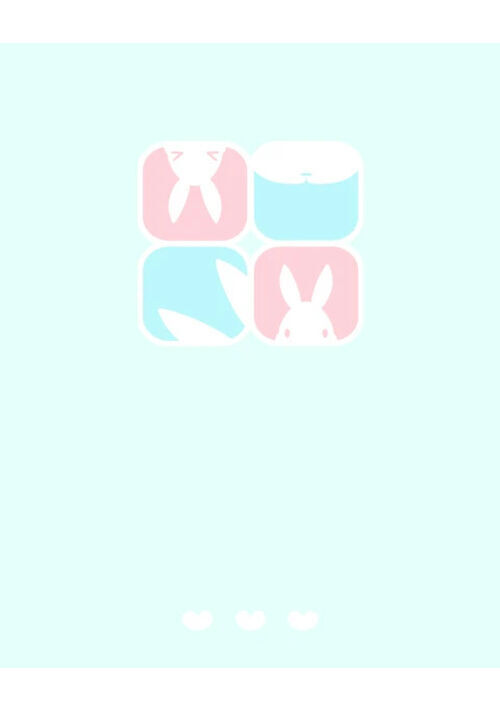
【完結】王太子に婚約破棄され、父親に修道院行きを命じられた公爵令嬢、もふもふ聖獣に溺愛される〜王太子が謝罪したいと思ったときには手遅れでした
まほりろ
恋愛
【完結済み】
公爵令嬢のアリーゼ・バイスは一学年の終わりの進級パーティーで、六年間婚約していた王太子から婚約破棄される。
壇上に立つ王太子の腕の中には桃色の髪と瞳の|庇護《ひご》欲をそそる愛らしい少女、男爵令嬢のレニ・ミュルべがいた。
アリーゼは男爵令嬢をいじめた|冤罪《えんざい》を着せられ、男爵令嬢の取り巻きの令息たちにののしられ、卵やジュースを投げつけられ、屈辱を味わいながらパーティー会場をあとにした。
家に帰ったアリーゼは父親から、貴族社会に向いてないと言われ修道院行きを命じられる。
修道院には人懐っこい仔猫がいて……アリーゼは仔猫の愛らしさにメロメロになる。
しかし仔猫の正体は聖獣で……。
表紙素材はあぐりりんこ様よりお借りしております。
「Copyright(C)2021-九頭竜坂まほろん」
・ざまぁ有り(死ネタ有り)・ざまぁ回には「ざまぁ」と明記します。
・婚約破棄、アホ王子、モフモフ、猫耳、聖獣、溺愛。
2021/11/27HOTランキング3位、28日HOTランキング2位に入りました! 読んで下さった皆様、ありがとうございます!
誤字報告ありがとうございます! 大変助かっております!!
アルファポリスに先行投稿しています。他サイトにもアップしています。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















