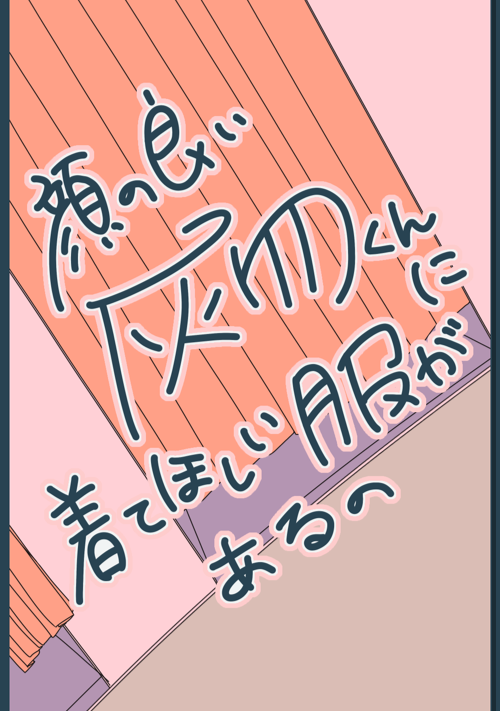21 / 23
子供の頃からの夢
しおりを挟む息を切らした彼の黒い双眸と視線が交差する。
秀ちゃんに対するほんの少しの疑念と不安、でもそれ以上の安堵感で胸がいっぱいになってじわっと目が潤んだ。
「大丈夫か、真白」
うん、という声は広仲さんの悲鳴のような声にかき消された。
「秀一っ、違うの!」
秀ちゃんは「違う?」とほんの少し口角を上げた。
「なにが違うんだ?」
秀ちゃんの鋭い眼差しに広仲さんのトーンが下がる。
「今のは……この子が、私の大切な父親を侮辱するようなことを言ったから、ついカッとなっちゃって……。でも、暴力はいけなかったわね。ここは、お互いさまってことで、許してくれないかしら?」
困ったように、でもどこか慈愛を込めた表情で私に微笑む広仲さん。そのすさまじい切替能力と瞬発力に、呆気にとられてしまった。
彼女は一瞬で勝利条件が切り変わったのを理解したのだ。今、この瞬間からは秀ちゃんの心証が全てだと。その点で広仲さんの取り繕い方は完璧だった。自分の行いを悔いて恥じるような表情や仕草、なにもかもが。
どうしよう、と秀ちゃんの方を見ると、秀ちゃんは私だけを真っ直ぐに見つめていた。その瞳に浮かぶのは、どこまでも純粋なただただ私を心配する感情だけで。広仲さんの言ったことの真偽なんて全く気にしてなんかいないのが伝わってきた。
「怖かっただろ」
すぐ近くまで来ていた秀ちゃんが私を抱き寄せて、広い胸の中に閉じ込められる。その温かさに一気に体から力が抜けた。
「もう大丈夫だ」
「……しゅうちゃん」
何も聞かずに、私のことを丸ごと信じてくれて。無条件で私の味方になってくれて。鼻の奥がツンとした。目頭の奥が熱くなるのを止めていた息を吐き出すことで抑える。
チラリと広仲さんを見ると、秀ちゃんに取り付く島がないのを悟ったのか、顔を強張らせていた。
「家は教えてないはずだけど、どうしてここに?」
「あっ、それは……」
目を泳がす広仲さんを美形が恐ろしいほど冷たい目で見据える。
「たっ、たまたま、仕事、で……秀一の住所を見る機会があって」
「そう、じゃあ何の用でここに?」
「それは、秀一ともう一度ちゃんと話がしたかったから」
「なら用件だけ聞こうか」
「……っどうして断ったの? 私、全然納得いかなくて」
「納得」と小さく秀ちゃんが呟いた。
「だってそうじゃない? 私と結婚した方が秀一はメリットが大きいはずよ? 私たち話も合うし、上手くやっていけると思う。感情も大事だけど、将来を見据えてちゃんと考えて欲しいの」
「将来を見据えて、ね。広仲の言うメリットって親父さんとのこと?」
「そうよ。今後の秀一の大きな力になると思う。それに私、こう見えて尽くすタイプだから。お味噌を手作りしたりするくらい料理は好きだし、掃除も得意なの。お花もお茶も免許を持ってる」
「ああ、確かにそれは魅力的なのかもな」
秀ちゃんの言葉に一気に心臓が凍る。
パッと表情を明るくした広仲さんを見て、さらに心臓が悲鳴をあげた。
「他の誰かにとっては」
え、という声は広仲さんと重なった。
「俺は自分の力で勝ち取ったものが好きなんだよ。だから、広仲の言うコネはいらない。料理もお茶もお花もすごいとは思うけど、俺は家政婦が欲しくて結婚するわけでも無ければ、相手の家の資産が欲しくて結婚するわけでも無い」
彼の顔がこちらを向く。力強い目が私を捉える。
「一緒に手を取り合ってこの先の未来をずっと生きていきたい。そう思える相手と俺は結婚したい」
なんでこっちを見てそんな事を言うの。
恋愛脳のせいで、まるでプロポーズされたみたいに感じてしまって。両頬が熱を持ち、ドキドキと心臓が壊れそうなほど激しく鼓動するのを止められない。
鎮まれ、私! あくまで秀ちゃんは自分の結婚観を語っただけなんだから! まだ付き合ったばかりの私にプロポーズしてるわけじゃ無いから!
「これで、答えになったか?」
あわあわしてる私を他所に秀ちゃんはもう戦闘モードに切り替わっていた。
「……今後不利な立場になっても知らないわよ」
「へえ」と口端を吊り上げた秀ちゃんに広仲さんが眉根を寄せる。
「私は本気よ」
ピンクの紅がひかれた唇を噛み締める広中さんに、秀ちゃんが「それは怖いな」と余裕の笑みを返した。
そのままポケットからスマートフォンを取り出した秀ちゃんが画面を操作し始める。
「お疲れ様です、藤道です。至急で申し訳ないんですけど、総務の誰かが俺の住所を見て個人利用したみたいなんです。誰のIDでどのパソコンからログインしたか社内のアクセスログを調べてくれませんか?」
「はぁ!?」
ありがとうございます、と電話を切ると、美形はその美貌すら武器にして攻撃的に微笑んだ。
「なにその反応、もしかしてIDの不正利用までしてた?」
「……っ」
広仲さんを見据えていた漆黒の瞳が、今度はちらりとアパートの入り口の防犯カメラに流し目を送った。視線一つで彼女の意識をそちらに誘導し終えた彼は、ゆっくりと話し始めた。
「防犯カメラの検挙率って年々上がっているらしいな。録音された音声データとかも裁判での証拠資料で認められてるらしいし、昔と比べて今はそう簡単に悪いことはできないと思わないか?――真白」
録音してあるんだろ、と手を差し出されて、最近秀ちゃんから贈られた小型のボイスレコーダ―を取り出して操作する。先ほどまでのキャットファイトが流れだして、羞恥で悶えた。冷静になった後に好きな人の前で流されるって拷問でしかない。
『……確認なんですけど、私が藤道秀一さんと別れない限り、広仲愛さんはお父様にお願いして彼の人事に手を加えるということですか?』
『そうだって言ってるでしょ?』
チラッと広仲さんをみると表情が凍り付いていた。自分の発言のまずさは分かってるみたいだ。
秀ちゃんも満足したのかピッと録音を切って鼻で笑った。
「いつ二人きりになったって? 熱い夜? 笑わせるなよ、盛り上がるどころか、お前とは目すら合わせてなかったはずだけど」
冷めた声と絶対零度の眼差しに、やっぱり広仲さんの嘘だったんだとほっとする。
「聞くに堪えない妄言も酷かったけど。それ以上に、会社システムへの不正アクセスと不正なID利用、家まで押しかけてくるストーカー行為、セクハラ、そして脅迫行為か。蹴落としあってる役員連中にお知らせしたら、さぞ面白い事になるんだろうな」
決して声を荒げたり、煽るような言い方もしていないのに、微笑み、首を傾ける美形には静かな迫力があった。
「さっきの音声データと防犯カメラ映像は会社で曝してみるのも、ネットで曝してみるのもいいよな」
「っそれだけは……!」
「それとも」
焦りを顔に滲ませた広仲さんの必死の嘆願を、秀ちゃんは冷たい声で遮り、
「今から警察沙汰にしとく?」
無慈悲に切り捨てた。
そして、そのまま漆黒の瞳を細めて、射抜く。
「俺がお前の親父さんの名前を出せば大人しく従うとでも思ってた? 上司に逆らえない従順な人間だと? ましてや、大事な女に目の前で手を出されそうになって、俺がそれを笑って許すとでも?」
ゆっくりと、空気がビリビリと殺気立っていく感覚に全身が粟立った。
秀ちゃんは声の調子や顔に一切感情を出してなんかいない。でも、言葉の後半にいくほどに、激しい感情が燃え上がっていくのが分かった。
「俺は敵対した奴は、二度と歯向かってこられないくらいに徹底的に潰す主義なんだよ」
淡々と話す秀ちゃんから熱を感じる。
その静かな迫力は、怒りの矛先を直接向けられていない私でさえ息を止めるほどで、実際の張本人の広仲さんは顔面蒼白だ。
「ご、ごめんなさい」
こんなにも怒った秀ちゃんを初めて見た。でも、本来の秀ちゃんはたかだかこれくらいの脅しで本気で怒る人なんかじゃなくて。
「謝る相手が違うだろ?」
だから、きっと、全部私のため。私のためだけにこんなにも怒ってくれている。ドキドキと高鳴る胸を抑えて、熱い息をそっと吐き出す。
「役員報酬なんかなくなったって、広仲さんならもう十分貯金してるから大丈夫だよ」
「違う……違うの……ごめんなさい」
「だから、謝る相手は俺じゃないだろ?」
私を映す広仲さんの目に波紋が広がる。一瞬の逡巡の後――眉間にしわを寄せ、ぎゅっと目を唇を噛み締める。ゆっくりと広仲さんの目が私に向いた。
「真白さん、ごめんなさい」
「何を?」と冷たい声が更に続きを促す。
「大変……失礼なことを申しました」
彼女の中の何かが折れていくのが分かった。プライドとか意地とか女としての矜持とか反骨心とか、きっとそんなものが。
その時、秀ちゃんの仕事用の携帯が鳴った。
「はい、藤道です」
短く何かの話を終えた秀ちゃんがスッと広仲さんにスマートフォンを差し出す。ゆるゆると俯いていた顔をあげた広仲さんに「親父さんから」と伝えた。
「……」
緩慢な動作で電話を受け取り、会話のやりとりを終えた広仲さんは、今日会ったばかりの時とは別人のように生気を無くしていた。
「……ありがとう、ございました」
秀ちゃんはスマホを受け取ると、短く会話をしてから電話を切り、ポケットに収めた。
「いくぞ」
「あ、うん」
私の手を引いてアパートに向かって歩き出した秀ちゃんが歩みを止め、少しだけ振り返った。
「よかったな、俺が間に合って。本当に真白に手を上げていたら、マジで社会的に消す所だった」
聞いたこともない声だった。絶対に殺意が乗っていたと思う。実際に、広仲さんはカクン、とへたり込んでしまっていた。
「真白は気にしなくていい。そのうち専務が迎えにくる」
「う、うん」
「誤解されたくないから先に言っておくけど、この前の水曜は確かに専務からアイツを紹介されそうになったけど、俺はアイツと二人っきりになってなんかないし、盛り上がっても無い、むしろ俺は専務としか話をしていない、肉体関係なんて一切無いからな、全部アイツの妄言だ」
一息に言い切った秀ちゃん。私に誤解されたく無いと思っているのが、すごく分かりやすく伝わって来て面映い気持ちになる。ニヤケそうになるのを堪えて、神妙な顔で秀ちゃんを見上げた。
「そうなんだ。でも、あの日、秀ちゃんから女性ものの香水の匂いがしたよ、今日の広仲さんと同じ匂いの」
「香水?」と訝し気な顔をしたあと、宙を見つめ、何かに思い至ったらしい秀ちゃんが眉根を寄せた。
「もしかして、最後にあいつが酔ったフリして俺にしな垂れかかってきた時のやつか……?」
弾かれたように、彼がこちらを向く。
すごく焦った表情の秀ちゃんと目が合って。そこでもう限界だった。くすぐったい様な笑いの衝動が止められなくて口元に手を当てる。私の顔を見た秀ちゃんの顔が焦った表情から一転して、苦虫を噛み潰したような表情になり、悔しそうに唇を噛み締めて視線を逸らすのを見た。
残念だ。笑うのを堪えれられたら、きっと私のために必死で言い訳してくれた秀ちゃんを見れたのに。
「おい、いつまで笑ってんだよ」
不機嫌な声と表情だけど、優しく手を繋いだままでいてくれる秀ちゃんの腕におでこを寄せる。
「ふっ、ごめん。でも、あの日、秀ちゃんから広仲さんの匂いがしたのは本当だよ」
「へえ……って、待て」
突然、玄関を前に立ち止まった美形が眉間に深い皺を刻んで私を見下ろして、小さく嘆息した。
「そうか、それで、あの時、急に態度が変わったのか」
眉間にシワを寄せたまま、秀ちゃんが目をクッと細める。
漆黒の瞳が揺れる。記憶力のいい秀ちゃんのことだ。あの時のことを思い出して、あの時の私の気持ちとか感情とかを察したんだろう。そして、困ったことに、きっとそれはほぼ正確な答えなのだ。
頭を抱き寄せられて、その胸に顔を埋める。優しい声が落ちてくる。
「悪かった……ごめん。嘘を吐くつもりはなかった。あの時の俺には、広仲の存在が本当にどうでもいいことで、自分の中で人数にカウントすらしていなかった」
結構、広仲さんに対して酷いこと言ってる……!
「秀ちゃんは前から広仲さんのこと嫌ってたの?」
「嫌いってほど興味も無かったけど。断っても何度も食事に誘ってくるから面倒くさいとは思ってた。そんなことより……色々と嫌な思いさせてごめんな」
「次からはちゃんと言ってくれなきゃ、やだよ?」
「ああ、分かった、ごめん」
何度も優しく頭を撫でられて、頭にキスされて。くすぐったくなって笑った。
家の中に入ると、どっと疲れがでてきた。
「疲れた?」
「うん、こういう喧嘩は、生まれて初めてだったから」
秀ちゃんは軽々と私を抱き上げると、瞳を覗き込んできた。
「その割になかなか冷静だったな」
「相手が早いうちにボロを出してくれたから。ねえ……私のケンカ姿、引かなかった?」
「全然? カッコよかったよ。惚れ直した」
悪戯っぽく目を細めて口端を吊り上げる秀ちゃんにホッと息を吐く。
「でも、もう二度と無理すんなよ。今日、平手打ちされそうになってたお前見たとき、心臓止まるかと思った」
眉間に皺を寄せた少し怒ったような表情。
揺れる瞳と少し掠れた声音。
すごく、心配してくれてたのが伝わって、ぎゅうっと秀ちゃんの首に抱きついた。
「今度からはできるだけ逃げろよ。必ず俺がなんとかするから」
「うん、ありがと。心配かけてごめんね」
秀ちゃんがクッションに私を下ろす。
「手、冷たくなってるな。温かい紅茶でも飲む?」
うん、と頷くと、優しく頭にポンと手が置かれる。キッチンの方へ向かっていく秀ちゃんの後姿をぼんやりと眺めた。
至れり尽くせりだ。格好良くて、優しくて、頼りになって――こんな素敵な秀ちゃんに見合うような、価値。
『あなたに幸せにできるの?』
胸が、痛い。
秀ちゃんは『真白じゃなきゃダメなんだ』なんて言ってくれたけど、私に価値なんか無い。
さっきは広仲さんを怒らせるために、あんな風に啖呵を切ったけど。立派なご両親も育ちも、私にはない立派な価値だ。むしろ、私の場合は、親戚からあんまり好かれていない両親っていうマイナスポイントすらある。
キッチンから戻ってきた秀ちゃんが温かい紅茶を出してくれた。お礼を伝えると、秀ちゃんが気まずそうに視線を逸らした。
「先に謝っておく、ごめん。たぶん、それ、美味しくないと思う」
「え……?」
ティーカップに入った赤茶色の液体は、いつもより大分色が濃い。口に含むと口中に広がる……苦味。
「しょうがないだろ、小分けになっていない紅茶なんて淹れたことなかったんだから。やっぱりカッコつけずに、缶ビールにしておけばよかった」
不貞腐れた子供みたいで、くす、と笑いが漏れる。一度笑いだしたら止まらなくなって肩を揺らして笑った。
「ビールって」
「苦い紅茶よりマシだろ」
「美味しいよ、秀ちゃんの淹れてくれた苦い紅茶」
「うるさい」
「ほんと。慣れないのに……ありがとう」
ゆっくりともう一度飲む。唇をカップから離すと、秀ちゃんが私の持っていたティーカップを取り上げてテーブルに置いた。
カチャン、という音と共に、唇が奪われる。
ちゅ、ちゅ、と角度を変えて何度か重なる。甘やかな感触に力が抜けたタイミングで舌が私の唇を割って入って来た。
一通り私の口内を貪ると、秀ちゃんが、やっぱ苦いな、と笑った。
「無理して飲むなよ」
頭が抱き寄せられて、頬に感じるシャツ越しの逞しい胸板。オーデコロンと彼の肌の匂いが混ざった落ち着く心地いい香り。とくとくと響く穏やかな心臓の音。力を抜いて身を預けると、髪を梳くように頭を撫でられ始める。
――幸せだ。
「次はちゃんと淹れたいから、今度また淹れ方教えて」
また紅茶を淹れてくれるつもりなんだと口元が緩む。
これから先もこの関係が続くことを前提にした言葉。ずっと、欲しかった幸せ。秀ちゃんと、こんな風に過ごせるのを夢見ていた。でも、秀ちゃんなら、私なんかよりも、もっともっと素敵な女性と付き合える。
顔を上げると、黒い瞳が甘やかに細まる。
ねぇ、本当に私でいいの、なんて。そんな自己満足の質問を聞いて、どうするつもりなんだろう。馬鹿なことを考えるなよって否定してもらって満足するの?
「どうした?」
心配そうに私の顔をぞき込むこの優しい人に、自分の足りなさの責任を、押しつけることなんてしたくない。
「すごく……心地いいなって」
「ならよかった」
微笑み返して顔を伏せようとした瞬間、顎を掴まれグッと上を向かされる。
「なんて、言うわけ無いだろ?」
「え……?」
戸惑う私を、漆黒の瞳が観察するように見下ろす。顎を掴んでいた手が離れて、今度は両手で私の顔をそっと包む。
「自分が今どんな顔してるか分かってんのか?」
「――」
「広仲に言われたことを気にしてんだろ?」
言いたくなくって視線を逸らすと、がぶっと唇に軽く歯を立てられた。びっくりして思わずパチッと目を見開くと、漆黒の瞳が強い光を放って私を見据えた。
「言えよ」
噛まれた所を優しく舐められる。ちゅ、と優しく唇を押しつけられる。
「なあ」
どこまでも優しく頭を撫でられながら、もう一度、労わるように重ねられる。
「言えって」
乱暴な口調なのに、そこに乗せられているのは甘ったるいくらいの愛情と懇願で。きゅうっと胸が震えた。
「……っ私に、秀ちゃんに見合う価値があるのかなって」
瞬間、怒気で彼の瞳の奥がゆらりと揺れたのが間近で見えた。眉間に皺を寄せ、ゆっくりと息を吐く彼を見て、もうダメかもしれない、と思った。
――きっと、もう全部秀ちゃんにバレてしまった。
自分に愛される価値なんか無くっても、秀ちゃんを手放せないエゴも。そのくせ、この不安だけは、拭い去って欲しいと願う甘ったれた根性も。自分の足りなさもエゴも根性も不安も全てを隠して、上辺だけでも取り繕いたかった自分の浅ましさも。
「くだらないな」
イラついた声に肩が跳ねる。私の反応を見た秀ちゃんが「真白に言ったんじゃない」と困った顔をした。
「普通、人を好きになるときに価値とかメリットとか考えないだろ。それとも、真白は俺の価値とか考えてた?」
「――」
「違うよな?」
小さく頷くと、抱き寄せられて、膝の上に座らされた。
「真白はさ。昔から自己評価がすごく低いけど」
「――」
「それを努力で補おうとするところがすごいと俺は思ってるよ」
「――」
「子どもの頃からお前はできるまでずっとコツコツやってて、そういうところずっとすごいと思ってた。できると、すごく嬉しそうに笑うところとか可愛いと思ってたし。大学に入って難関資格を受けるって決めてからは、在学中からダブルスクールして、周りの奴らが遊んでるときもコツコツ勉強してて」
「――」
「俺はそんなお前を尊敬してる」
堪えきれなかった涙が目尻から溢れた。彼の指が優しく拭ってくれる。
「一緒に住み始めてからは、スーパーでお得に買えたって喜んでたり、料理の味付けが上手くいったって喜んでたり、洗濯物の汚れが綺麗に落ちたって喜んでたり」
それって、ほめてなくない? と涙で滲んだ彼を見つめると、濃密に甘いとろりとした眼差しで見つめ返されて、直前の拗ねた気持ちが霧散する。
「そういう小さなことで幸せを感じたり、喜んだりする真白が昔から好きなんだよ。どんな環境でも、どんな状況でも、そうやって幸せであろうとする強い真白を俺が守りたいと思った。そういう小さな幸せをこの先も二人でたくさん見つけて重ねて生きていきたいと思った……お前は最初から十分『いい女』だったよ」
ぶわっと溢れた涙で視界が滲む。瞬きをすると、ぽろぽろと涙が頬を伝って、真剣な顔をした秀ちゃんがはっきりと目に映った。
「真白、俺と結婚してくれるか?」
ちゅ、とおでこに柔らかな感触を落とされる。
「もう十分待ったからさ」
目元をうっすらと染めて、微笑む秀ちゃんは幸せそうで。
「もしかして、覚えてて、くれてたの?」
あの約束とも言えない約束を。
秀ちゃんが心外そうに片眉を上げた。
「お前が『いい女になるまで待ってて』とか言って、泣いてせがんできたんだろ」
何度も何度も小さい頃、秀ちゃんにお願いした。『いい女になるから、すぐ結婚しないで』って。
ちゃんと、覚えててくれたんだ。あんなにおざなりな返事だったのに。
「泣いてはなかったと思う……」
「半泣きだっただろ、ってかそんなに泣くなよ」
もう一度、頭を抱き寄せられて、その首筋に顔を埋める。
「まだ働き始めたばっかりだって分かってるけどさ、籍だけでも入れたい」
どうしよう、嬉しい。嬉しくて、温かくて、涙が止まらない。
秀ちゃんの言葉が、優しく、甘やかに、私を絡めていた呪いのような鎖を溶かしていく。
「秀ちゃん」
ありがとう。約束をしてよかったなんて思えたの、初めてだ。
守られない約束は自分の心を傷つける凶器だった。
自分が果たしていない約束は借金のようだった。
中身を伴わない軽々しく口にされる約束を耳にするたび心がすり減っていった。
分かっていた。自分のこだわりで自分自身を苦しめて傷つけていたことは。それでも、捨てられなかった。
それほどに、重たい鎖だった。
「秀ちゃん」
初めて知った。
約束って破られて悲しいものじゃなくて、守ってもらえて嬉しいものなんだと。
「なんだよ」
「ありがとう。約束、好きになれたかも」
ぎゅっと彼に抱きつく。私は一体何度この人に救われるんだろう。にじむ涙を、彼の肌で拭い取って、顔を上げる。
「私、子供の頃からずっと変わってない夢があるの」
拭ったそばから涙がぽろぽろ溢れていく。仕方がないからそのまま笑った。
「秀ちゃんの、お嫁さんになりたい」
「知ってた。叶ってよかったな」
そう彼は不遜に言って、蕩けるように甘く私を見つめて。私の頭を抱き寄せると、唇に甘い口づけをした。
応援ありがとうございます!
0
お気に入りに追加
65
1 / 5
この作品を読んでいる人はこんな作品も読んでいます!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる