13 / 41
ジャン=ジャック・ルソー
放浪生活の始まり
しおりを挟む
ルソーは親方の元で働きながら、読書が唯一の楽しみになっていた。
貸本屋で本を借りてはむさぶり読んだ。給料は全て本代に消えた。しかし、仕事をサボっては読書をしていたので、親方には読書も悪としてとらえられていた。
見つかると本を破り捨てられた。
そうこうしながら、ルソーは孤独を強めていって、16歳になっていた。
ある日、ルソーは市の門限に遅れてしまった。遅れてしまったと言うより、30分も早く門を閉める門番がいたのだ。
市の門が閉められて親方の家に門限内に帰れなくなったのは、これで3度目なのである。
親方の家に明くる朝帰っても殴られるだけである。
ルソーはいっその事、逃亡しようと決意した。
ルソーにとっては、親方の場所だけが世界ではなかった。
本の中で広い世界を知識としては知っている。
そんな彼がいつまでも孤独で抑圧された親方の場所にとどまり続けることはありえない話だったのかもしれない。
それはそうと、気まぐれで先を読むことも無く、その場限りで行動を起こしてしまうルソーは、市の門が閉まって門限を破ったことがきっかけで逃亡した。
この逃亡が意味することは、恐ろしい。
なんの技術も生きる知恵もない16歳の少年が、親の助けも何もかも捨てて、徒弟奉公を投げ捨て一人生きてゆかねばならないのだ。
親方の元で、様々な事に耐えながら生きている方がよっぽど楽だったに違いない。貧苦に身をゆだねる生活が目に見えていた。
しかし、ルソーの頭の中は違っていた。
鳥籠の中から放たれた鳥のように、自由で素晴らしい世界の始まりのように思っていたのである。
小さな恋人を作り、親しい友人を作り、小さな城を手に入れて近隣の者達にご馳走を振る舞うようなささいな夢を抱いていた。
中二病のようなものだ。
脳内では不可能なことは無い。
しかし、現実は実力が足りない。
それでもルソーは、農村で泊めてもらったり、ご馳走をしてもらったりと分を越えた施しを受けながら過ごし、サヴォワの司祭、ポンヴェール氏を訪ねた。
ポンヴェール氏はルソーを親元に送り返すことよりも、プロテスタントからカトリックへ改宗させることに重きを置いているような人物であった。
ルソーはポンヴェール氏と話していて、自分の方が博識だと感じていたが、議論で打ち負かすようなことはしなかった。
美味しいワインやご馳走を振舞ってくれるポンヴェール氏はいい人で、それを打ち負かすことはルソーには心地よいものではなかった。
ルソーはポンヴェール氏の言うことを素直に聞いているふりをした。まるで、カトリック教へ改宗する事はわけないと思わせぶりな態度をとった。
それは、まるで婦人が口説けそうで口説けないような思わせぶりな態度をとるのに似ていた。
ポンヴェール氏はルソーに
「アヌシーにいるヴァランス婦人を訪ねてみなさい」と勧めた。
ヴァランス婦人はカトリック教へ改宗した熱心なカトリック教徒で、サルジニア王から二千フランの年金を受けている。
その年金は信仰を売り物にしている僧侶達の食いしろにあてがわれていた。
慈悲深いヴァランス婦人なら、きっと養ってくれるというのだ。
ルソーは婦人から施しを受けながら生活をするのは屈辱的で、あまり気が気が進まなかったが、飢えが迫ってくる。
それに、旅行は好きだし、目標がある事は望むところだから、ヴァランス婦人を訪ねることにした。
貸本屋で本を借りてはむさぶり読んだ。給料は全て本代に消えた。しかし、仕事をサボっては読書をしていたので、親方には読書も悪としてとらえられていた。
見つかると本を破り捨てられた。
そうこうしながら、ルソーは孤独を強めていって、16歳になっていた。
ある日、ルソーは市の門限に遅れてしまった。遅れてしまったと言うより、30分も早く門を閉める門番がいたのだ。
市の門が閉められて親方の家に門限内に帰れなくなったのは、これで3度目なのである。
親方の家に明くる朝帰っても殴られるだけである。
ルソーはいっその事、逃亡しようと決意した。
ルソーにとっては、親方の場所だけが世界ではなかった。
本の中で広い世界を知識としては知っている。
そんな彼がいつまでも孤独で抑圧された親方の場所にとどまり続けることはありえない話だったのかもしれない。
それはそうと、気まぐれで先を読むことも無く、その場限りで行動を起こしてしまうルソーは、市の門が閉まって門限を破ったことがきっかけで逃亡した。
この逃亡が意味することは、恐ろしい。
なんの技術も生きる知恵もない16歳の少年が、親の助けも何もかも捨てて、徒弟奉公を投げ捨て一人生きてゆかねばならないのだ。
親方の元で、様々な事に耐えながら生きている方がよっぽど楽だったに違いない。貧苦に身をゆだねる生活が目に見えていた。
しかし、ルソーの頭の中は違っていた。
鳥籠の中から放たれた鳥のように、自由で素晴らしい世界の始まりのように思っていたのである。
小さな恋人を作り、親しい友人を作り、小さな城を手に入れて近隣の者達にご馳走を振る舞うようなささいな夢を抱いていた。
中二病のようなものだ。
脳内では不可能なことは無い。
しかし、現実は実力が足りない。
それでもルソーは、農村で泊めてもらったり、ご馳走をしてもらったりと分を越えた施しを受けながら過ごし、サヴォワの司祭、ポンヴェール氏を訪ねた。
ポンヴェール氏はルソーを親元に送り返すことよりも、プロテスタントからカトリックへ改宗させることに重きを置いているような人物であった。
ルソーはポンヴェール氏と話していて、自分の方が博識だと感じていたが、議論で打ち負かすようなことはしなかった。
美味しいワインやご馳走を振舞ってくれるポンヴェール氏はいい人で、それを打ち負かすことはルソーには心地よいものではなかった。
ルソーはポンヴェール氏の言うことを素直に聞いているふりをした。まるで、カトリック教へ改宗する事はわけないと思わせぶりな態度をとった。
それは、まるで婦人が口説けそうで口説けないような思わせぶりな態度をとるのに似ていた。
ポンヴェール氏はルソーに
「アヌシーにいるヴァランス婦人を訪ねてみなさい」と勧めた。
ヴァランス婦人はカトリック教へ改宗した熱心なカトリック教徒で、サルジニア王から二千フランの年金を受けている。
その年金は信仰を売り物にしている僧侶達の食いしろにあてがわれていた。
慈悲深いヴァランス婦人なら、きっと養ってくれるというのだ。
ルソーは婦人から施しを受けながら生活をするのは屈辱的で、あまり気が気が進まなかったが、飢えが迫ってくる。
それに、旅行は好きだし、目標がある事は望むところだから、ヴァランス婦人を訪ねることにした。
0
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

わたしの下着 母の私をBBA~と呼ぶことのある息子がまさか...
MisakiNonagase
青春
39才の母・真知子は息子が私の下着を持ち出していることに気づいた。
ネットで同様の事象がないか調べると、案外多いようだ。
さて、真知子は息子を問い詰める? それとも気づかないふりを続けてあげるか?
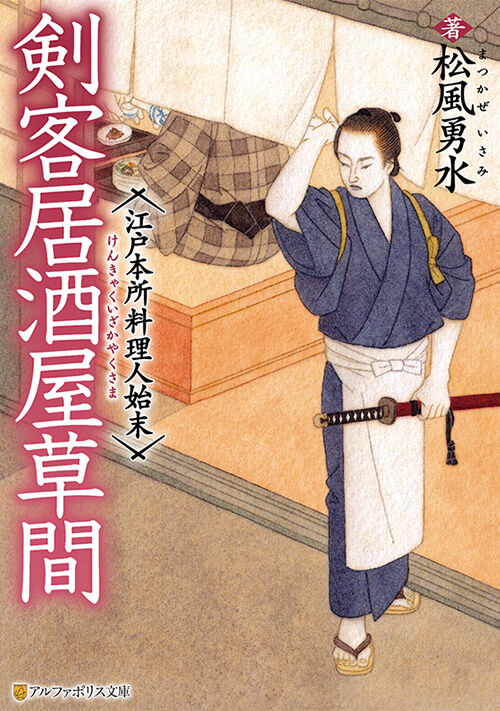
剣客居酒屋草間 江戸本所料理人始末
松風勇水(松 勇)
歴史・時代
旧題:剣客居酒屋 草間の陰
第9回歴史・時代小説大賞「読めばお腹がすく江戸グルメ賞」受賞作。
本作は『剣客居酒屋 草間の陰』から『剣客居酒屋草間 江戸本所料理人始末』と改題いたしました。
2025年11月28書籍刊行。
なお、レンタル部分は修正した書籍と同様のものとなっておりますが、一部の描写が割愛されたため、後続の話とは繋がりが悪くなっております。ご了承ください。
酒と肴と剣と闇
江戸情緒を添えて
江戸は本所にある居酒屋『草間』。
美味い肴が食えるということで有名なこの店の主人は、絶世の色男にして、無双の剣客でもある。
自分のことをほとんど話さないこの男、冬吉には実は隠された壮絶な過去があった。
多くの江戸の人々と関わり、その舌を満足させながら、剣の腕でも人々を救う。
その慌し日々の中で、己の過去と江戸の闇に巣食う者たちとの浅からぬ因縁に気付いていく。
店の奉公人や常連客と共に江戸を救う、包丁人にして剣客、冬吉の物語。

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。

与兵衛長屋つれあい帖 お江戸ふたり暮らし
かずえ
歴史・時代
旧題:ふたり暮らし
長屋シリーズ一作目。
第八回歴史・時代小説大賞で優秀短編賞を頂きました。応援してくださった皆様、ありがとうございます。
十歳のみつは、十日前に一人親の母を亡くしたばかり。幸い、母の蓄えがあり、自分の裁縫の腕の良さもあって、何とか今まで通り長屋で暮らしていけそうだ。
頼まれた繕い物を届けた帰り、くすんだ着物で座り込んでいる男の子を拾う。
一人で寂しかったみつは、拾った男の子と二人で暮らし始めた。
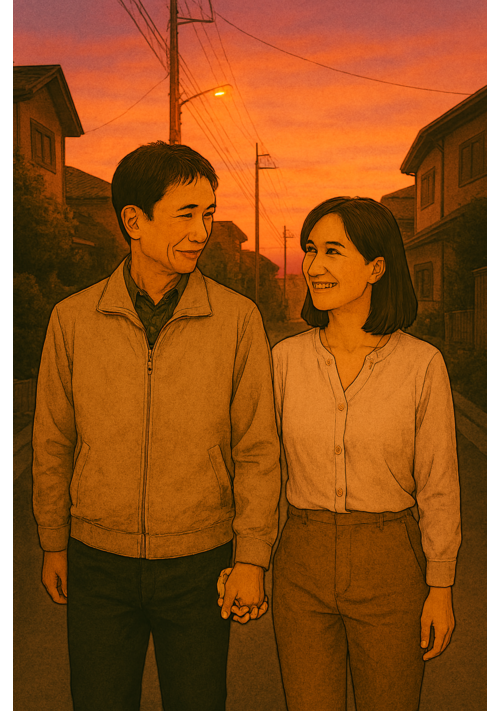

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















