43 / 71
第四章 前を向くとき
07
しおりを挟む
「は、はーい。今行きます!」
ごめんねとありがとうを真宮に残して、藤崎は接客へと向かう。全身が熱くなるこんな感覚は久しぶりだった。ずいぶん忘れていた感覚は、胸の真ん中をじんわりと熱くさせる。懐かしいような切ないようなそれは、いつまでもそこに感覚を残していた。
きっとあの夜のことが引き金になっている。だから少し触られただけでも頬が紅潮する。
奥村を亡くして、もう新しい恋なんてできないと思っていた。あの人以上に好きになれる人なんていないと決めつけていた。だからこんな風に体が反応する自分に驚いている。
(――どうしよう)
藤崎は高揚したような心を必死に押さえながら平静を保った。
「ゆうちゃん、ごめんね。まだ営業時間じゃないのに来ちゃって。あら、今日はどうしたの? 少し顔が赤いわよ?」
花を買いに来たのは近くの常連さんだった。オープンからよく買いに来てくれる年嵩の女性だ。今日は娘夫婦が家に来るからと、室内に飾る花を買いに来たのだという。
「え、そうですか? 風邪引いたかなぁ」
「気をつけないと。最近インフルエンザが流行りだしたってニュースで言ってたから」
「そうなんですか? インフルエンザは困りますね。そうなると休業になりますから」
「でも、優秀なバイトの子がいるから平気だわよ。あ、そうそう。花苗始めたでしょう? 私の近所の奥さんも喜んでたのよ。ゆうちゃんはセンスがいいから。黒板のあれも、かわいらしくていいわよね」
「そう言ってもらえると、やりがいあります。なにかリクエストがあったら言ってくださいね? できるだけご意見に添えるように頑張りたいので」
「あら、そうなの? うれしいわ。じゃあマーガレットなんてどうかしら。切り花も置いてあるけど、苗から育てるのもいいかなって思ってるの」
「そうですね。植えるなら今の時期からですからね。じゃあ少し考えてみます」
藤崎はエプロンのポケットからメモ帳を取りだし、忘れないように書き付ける。こうして話しているうちに、さっきまでの高揚した火照りが落ち着いていくようだった。
お客様が選んだ数本の花を持って奥へと向かい、通常の包装をして袋に入れ、商品を手渡した。
「ありがとうございました」
頭を下げて見送り姿勢を戻すと、クラッと軽く目眩がした。言われた通り体のだるさも感じるし、本当に風邪なのかもしれない。おまけに背中に感じるゾクゾクする悪寒は、時間を追う事に激しくなっていった。
クリスマスが近づくと客足は徐々に増えてくる。いつもなら忙しくない時間帯にも関わらず、バタバタと立て続けに買いに来るお客様があった。店内のリースやクリスマス仕様の様々なアイテムもひと通り作り終え、真宮と一緒に接客をしていた。
オープン前、官能的に塗ってもらったハンドクリームはすでに流れてしまっていた。切るような水の冷たさと、一日ごとに寒くなる冬の風が容赦なくとどめを刺してくる。
ごめんねとありがとうを真宮に残して、藤崎は接客へと向かう。全身が熱くなるこんな感覚は久しぶりだった。ずいぶん忘れていた感覚は、胸の真ん中をじんわりと熱くさせる。懐かしいような切ないようなそれは、いつまでもそこに感覚を残していた。
きっとあの夜のことが引き金になっている。だから少し触られただけでも頬が紅潮する。
奥村を亡くして、もう新しい恋なんてできないと思っていた。あの人以上に好きになれる人なんていないと決めつけていた。だからこんな風に体が反応する自分に驚いている。
(――どうしよう)
藤崎は高揚したような心を必死に押さえながら平静を保った。
「ゆうちゃん、ごめんね。まだ営業時間じゃないのに来ちゃって。あら、今日はどうしたの? 少し顔が赤いわよ?」
花を買いに来たのは近くの常連さんだった。オープンからよく買いに来てくれる年嵩の女性だ。今日は娘夫婦が家に来るからと、室内に飾る花を買いに来たのだという。
「え、そうですか? 風邪引いたかなぁ」
「気をつけないと。最近インフルエンザが流行りだしたってニュースで言ってたから」
「そうなんですか? インフルエンザは困りますね。そうなると休業になりますから」
「でも、優秀なバイトの子がいるから平気だわよ。あ、そうそう。花苗始めたでしょう? 私の近所の奥さんも喜んでたのよ。ゆうちゃんはセンスがいいから。黒板のあれも、かわいらしくていいわよね」
「そう言ってもらえると、やりがいあります。なにかリクエストがあったら言ってくださいね? できるだけご意見に添えるように頑張りたいので」
「あら、そうなの? うれしいわ。じゃあマーガレットなんてどうかしら。切り花も置いてあるけど、苗から育てるのもいいかなって思ってるの」
「そうですね。植えるなら今の時期からですからね。じゃあ少し考えてみます」
藤崎はエプロンのポケットからメモ帳を取りだし、忘れないように書き付ける。こうして話しているうちに、さっきまでの高揚した火照りが落ち着いていくようだった。
お客様が選んだ数本の花を持って奥へと向かい、通常の包装をして袋に入れ、商品を手渡した。
「ありがとうございました」
頭を下げて見送り姿勢を戻すと、クラッと軽く目眩がした。言われた通り体のだるさも感じるし、本当に風邪なのかもしれない。おまけに背中に感じるゾクゾクする悪寒は、時間を追う事に激しくなっていった。
クリスマスが近づくと客足は徐々に増えてくる。いつもなら忙しくない時間帯にも関わらず、バタバタと立て続けに買いに来るお客様があった。店内のリースやクリスマス仕様の様々なアイテムもひと通り作り終え、真宮と一緒に接客をしていた。
オープン前、官能的に塗ってもらったハンドクリームはすでに流れてしまっていた。切るような水の冷たさと、一日ごとに寒くなる冬の風が容赦なくとどめを刺してくる。
0
あなたにおすすめの小説

冷徹勇猛な竜将アルファは純粋無垢な王子オメガに甘えたいのだ! ~だけど殿下は僕に、癒ししか求めてくれないのかな……~
大波小波
BL
フェリックス・エディン・ラヴィゲールは、ネイトステフ王国の第三王子だ。
端正だが、どこか猛禽類の鋭さを思わせる面立ち。
鋭い長剣を振るう、引き締まった体。
第二性がアルファだからというだけではない、自らを鍛え抜いた武人だった。
彼は『竜将』と呼ばれる称号と共に、内戦に苦しむ隣国へと派遣されていた。
軍閥のクーデターにより内戦の起きた、テミスアーリン王国。
そこでは、国王の第二夫人が亡命の準備を急いでいた。
王は戦闘で命を落とし、彼の正妻である王妃は早々と我が子を連れて逃げている。
仮王として指揮をとる第二夫人の長男は、近隣諸国へ支援を求めて欲しいと、彼女に亡命を勧めた。
仮王の弟である、アルネ・エドゥアルド・クラルは、兄の力になれない歯がゆさを感じていた。
瑞々しい、均整の取れた体。
絹のような栗色の髪に、白い肌。
美しい面立ちだが、茶目っ気も覗くつぶらな瞳。
第二性はオメガだが、彼は利発で優しい少年だった。
そんなアルネは兄から聞いた、隣国の支援部隊を指揮する『竜将』の名を呟く。
「フェリックス・エディン・ラヴィゲール殿下……」
不思議と、勇気が湧いてくる。
「長い、お名前。まるで、呪文みたい」
その名が、恋の呪文となる日が近いことを、アルネはまだ知らなかった。

【完結】火を吐く土の国の王子は、塔から来た調査官に灼熱の愛をそそぐ
月田朋
BL
「トウヤ様、長旅お疲れのことでしょう。首尾よくなによりでございます。――とはいえ油断なされるな。決してお声を発してはなりませんぞ!」」
塔からはるばる火吐国(ひはきこく)にやってきた銀髪の美貌の調査官トウヤは、副官のザミドからの小言を背に王宮をさまよう。
塔の加護のせいで無言を貫くトウヤが王宮の浴場に案内され出会ったのは、美しくも対照的な二人の王子だった。
太陽に称される金の髪をもつニト、月に称される漆黒の髪をもつヨミであった。
トウヤは、やがて王家の秘密へと足を踏み入れる。
灼熱の王子に愛され焦がされるのは、理性か欲か。
【ぶっきらぼう王子×銀髪美人調査官】

地味メガネだと思ってた同僚が、眼鏡を外したら国宝級でした~無愛想な美人と、チャラ営業のすれ違い恋愛
中岡 始
BL
誰にも気づかれたくない。
誰の心にも触れたくない。
無表情と無関心を盾に、オフィスの隅で静かに生きる天王寺悠(てんのうじ・ゆう)。
その存在に、誰も興味を持たなかった――彼を除いて。
明るく人懐こい営業マン・梅田隼人(うめだ・はやと)は、
偶然見た「眼鏡を外した天王寺」の姿に、衝撃を受ける。
無機質な顔の奥に隠れていたのは、
誰よりも美しく、誰よりも脆い、ひとりの青年だった。
気づいてしまったから、もう目を逸らせない。
知りたくなったから、もう引き返せない。
すれ違いと無関心、
優しさと孤独、
微かな笑顔と、隠された心。
これは、
触れれば壊れそうな彼に、
それでも手を伸ばしてしまった、
不器用な男たちの恋のはなし。

仮面の王子と優雅な従者
emanon
BL
国土は小さいながらも豊かな国、ライデン王国。
平和なこの国の第一王子は、人前に出る時は必ず仮面を付けている。
おまけに病弱で無能、醜男と専らの噂だ。
しかしそれは世を忍ぶ仮の姿だった──。
これは仮面の王子とその従者が暗躍する物語。
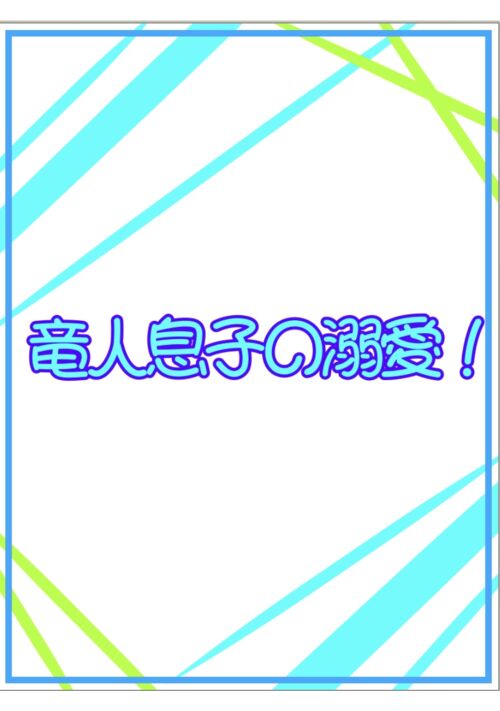
竜人息子の溺愛!
神谷レイン
BL
コールソン書店の店主レイ(三十七歳)は、十八歳になったばかりの育て子である超美形の竜人騎士であるルークに結婚を迫られていた。
勿論レイは必死に断るがルークは全然諦めてくれず……。
だが、そんな中で竜国から使者がやってくる。
そしてルークはある事実を知らされ、レイはそれに巻き込まれてしまうのだが……。
超美形竜人息子×自称おじさん

忘れられない君の香
秋月真鳥
BL
バルテル侯爵家の後継者アレクシスは、オメガなのに成人男性の平均身長より頭一つ大きくて筋骨隆々としてごつくて厳つくてでかい。
両親は政略結婚で、アレクシスは愛というものを信じていない。
母が亡くなり、父が借金を作って出奔した後、アレクシスは借金を返すために大金持ちのハインケス子爵家の三男、ヴォルフラムと契約結婚をする。
アレクシスには十一年前に一度だけ出会った初恋の少女がいたのだが、ヴォルフラムは初恋の少女と同じ香りを漂わせていて、契約、政略結婚なのにアレクシスに誠実に優しくしてくる。
最初は頑なだったアレクシスもヴォルフラムの優しさに心溶かされて……。
政略結婚から始まるオメガバース。
受けがでかくてごついです!
※ムーンライトノベルズ様、エブリスタ様にも掲載しています。

塔の上のカミーユ~幽囚の王子は亜人の国で愛される~【本編完結】
蕾白
BL
国境近くにあるその白い石の塔には一人の美しい姫君が幽閉されている。
けれど、幽閉されていたのはある事情から王女として育てられたカミーユ王子だった。彼は父王の罪によって十三年間を塔の中で過ごしてきた。
そんな彼の前に一人の男、冒険者のアレクが現れる。
自分の世界を変えてくれるアレクにカミーユは心惹かれていくけれど、彼の不安定な立場を危うくする事態が近づいてきていた……というお話になります。
2024/4/22 完結しました。ありがとうございました。

宵にまぎれて兎は回る
宇土為名
BL
高校3年の春、同級生の名取に告白した冬だったが名取にはあっさりと冗談だったことにされてしまう。それを否定することもなく卒業し手以来、冬は親友だった名取とは距離を置こうと一度も連絡を取らなかった。そして8年後、勤めている会社の取引先で転勤してきた名取と8年ぶりに再会を果たす。再会してすぐ名取は自身の結婚式に出席してくれと冬に頼んできた。はじめは断るつもりだった冬だが、名取の願いには弱く結局引き受けてしまう。そして式当日、幸せに溢れた雰囲気に疲れてしまった冬は式場の中庭で避難するように休憩した。いまだに思いを断ち切れていない自分の情けなさを反省していると、そこで別の式に出席している男と出会い…
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















