41 / 109
魔眼の子
41.待てのできる狐
しおりを挟む
はしゃぎ疲れたルーミが眠った頃、ノエルが迎えに来た。
重盛はルーミにとって、今日が悲しいだけの日で終わらなくて良かったと胸を撫で下ろした。
案内されたのはホワイトオーク材のダイニングテーブルがある部屋だった。
数時間前は全身黒い服を纏っていたのに、部屋は目がチカチカするほど白い。
隣で何やら考え込んでいる男も真っ白とくれば、今日一日のコントラストに少し眩暈がした。
テーブルに並ぶのはどれも色鮮やかで美味しそうな惣菜。
事前に聞いていたメニューとはどれも違う。北欧らしい柄が入った青い器に盛られてはいるが、明らかに店で買ってきたというラインナップだ。
「美味しそうですね……?」
「まあ、美味しそうだけど、これ、先生が作った風には見えないぜ」
「申し訳ございません……。祖父が急用で席を外した時に、私がサーモンとミートボールを全焼させました。とてもお出しできる物ではないので、こちらは惣菜屋で購入してきました。マルクス様と奥様は食欲がないので、食事は明日の朝、改めてと仰っております」
目の下のくまを濃くしたノエルは謝罪した。
それもそのはず、ハンナは彼にとっても大事な仕事仲間であり、朝から気を張りつめることが続いていたのだ。気もそぞろなる。さらに食事を作るプロであるシェフも今日はいない。
気持ちだけで十分だと重盛はノエルの肩を叩いた。
「先生、俺達のことはいいよ。食べた後のこともやっておく。皿は綺麗にしてここに置いておくよ。気にしないで休んで」
「こんな日にお邪魔すべきではありませんでした。本当にお構いなく。皆さん、僕達がいては、色々と気が休まらないでしょう……」
いつもと変わらぬ重盛と真紘の様子に安堵したのか、ノエルは大きなため息を吐いた。
「お気遣い感謝します。朝のことだって騎士である私がどうにかすべきだったのに……。情けないばかりです。客室の冷蔵庫にも飲み物などが入っていますので、ご自由にどうぞ。では、お二人もゆっくりお休みください」
「分かりました。食事をいただいたら今日はもう客室からでませんのでお気遣いなく。明日の朝までゆっくり休ませていただきますね」
「おやすみぃ、先生」
忙しなくどこかへと走って行ったノエルを見送る。
隣をふと見ると、真紘は暗くなった窓の外を見ていた。
そのまま夜の闇に攫われてしまいそうな、そんな予感がした。
重盛が咄嗟に真紘の肩を掴むと「食べようか」といつも通りの柔らかな笑みが返ってきた。
部屋の前で別れた時は疲労と眠気が限界だったのか、真紘は目を擦っていた。
「また明日ね、おやすみ」という声が今もこだましている。
それは一人になりたいという、彼の意思表示でもあった。
同じ家に帰り、同じ布団で寝る。
体温を感じながら聞くおやすみに慣れてしまったせいか、重盛はもう真紘に会いたくて堪らなくなった。
冷蔵庫の林檎ジュースを飲んでも、風呂に入っても心が落ち着くことはなかった。
「俺の方が年上だし? いつも強引に布団に潜り込んでる自覚はあるし? 一人になりたい日だってあるよなぁ……」
洗面台に両手をつきながら、鏡の前で自問自答を繰り返す。
白いタイルの床にポタリ、ポタリと水滴が落ちた。
重盛も簡単な生活魔法は会得していたので、今さら尻尾を乾かしてもらう必要はないのだが、やはり真紘のようにはいかなかった。
それに生活魔法を使えるといっても、風呂に入らずとも全身を清められるほどではない。出来ることといえば、泥を落とすとか、ちょろっと水を出すくらいのものだ。
重盛は無心で魔石がセットされたドライヤーのような筒を尻尾に当てた。
乾かすにもコツがあるようで、尻尾はパサパサになった。
あのふわふわとしていて艶のある毛並みは、真紘の思いやりでできていたのだと今頃になって知った。
翌朝、部屋のドアが控えめにノックされた。
日頃から起床時間を決めておかないと自堕落してしまうと心配した真紘が取り決めた時間の少し前だった。
「おはよう、重盛。起きてる?」
「はよ! 起きてる、起きた!」
真紘からのおはようの一言でスイッチが入り、ベッドを飛び降りて勢い良く扉を開けると、既に白シャツと紺のスラックスに着替えた彼がいた。サスペンダーを隠すようにベージュのショールを羽織っている。
今日も自分が選んだ物を愛用してもらえて嬉しい。重盛の尻尾は大きく揺れた。
「わっ、そんな急いで開けなくても。あのさ、朝食までに話しておきたいことがあるんだ。いいかな?」
「ダメって言ったら?」
「いいよって言ってくれるまで帰らない」
「だあッ! なんだよ、それ! もっと色気のある時間に言ってほしい台詞じゃん」
「よく分からないけど、駄目なの? いいの?」
「俺がダメって言ったことなくね?」
真紘を招き入れると途端に気分が上がった。
好きな子を目にするだけで心が躍るなんて乙女かっつーの。
重盛は正直な尻尾を鷲掴み、落ち着けと言い聞かせて深呼吸する。サイドテーブルに置いていた目覚ましをオフにして、そのままベッドに腰かけると、何も言わずとも真紘は隣に座った。
「それで? 昨日からずっと何か言いたげだったけど、教えてくれる感じ?」
「うーん。やっぱりバレてたか。じゃあ白状しようかな。君は昨日の事件、どう思った?」
事件とは白装束の集団が押しかけて来たことだろう。
どう思ったとはまた漠然とした質問だ。
しかし真紘はいきなり結論から話すタイプではないことは分っている。
大事な話は順を追って、自分自身で確認するように記憶を辿っていくのだ。
重盛は正直に答えた。
「人の気持ちを無視した強引なやり方は好きじゃない。特に動物実験は地球でも止めようって取り組みが進んでっし、人体実験だなんて、その人が生きていても死んでいても以ての外だろ。あの集団の理念には賛同できないね」
すると真紘は両手で顔を覆った。
「ちょっ、真紘ちゃん、どうした? 言い方が怖かった?」
顔を覗き込むが、ふるふると首を横に振るだけだ。
「……僕も同じ意見だよ。だからこそ、僕は僕を許せない。やってはいけないことをやってしまった。本当になんてことをしてしまったんだろう……」
真紘が肩を震わせる理由が分からず、重盛は困惑した。
そして昨日、彼がハンナに囁いた言葉を思い出した。
【……なんてことを。ゆっくりお休みください】
「白装束の女がハンナさんに飛び掛かったこと? あれは俺も止められなかったし、真紘ちゃんだけのせいじゃ――」
「違うんだよ重盛……。あの時、君には見えていなかったのかもしれないけど、ハンナさんの瞳は両目とも灰色だったんだ。それを僕が片方だけ赤く染めた」
「ど、どうして……」
「しっかり考えて行動したわけじゃない。ただ先に思っちゃったんだ。どうにかしてハンナさんのご遺体とタルハネイリッカ家をI,mから守らなくちゃいけない。だから、彼女の瞳が赤いと証明されれば、あの場から集団が立ち去るんじゃないかって。そして僕はハンナさんのご遺体を無理矢理変えてしまった。一度想像してしまったことを勢いのまま実行してしまった。いくら傷を治したって、やったことはあの白装束の女性と何も変わらないんだよ……」
己の倫理観に反した自身の行いに真紘は苦しんでいた。きっとそれは他人に許されれば良い問題ではないのだろう。
それを理解した上で、真紘は昨晩、一人になりたいと離れていったのだ。
重盛は真紘の肩をそっと抱いた。
「俺がどうこう言っても、きっとお前は自分を責めるんだろうな。でもあの集団とお前は違う。ハンナさんが守りたかったもんはなんだ? ルーミちゃんだろ。あの狭い空間で剣を抜かれていたら彼女が怪我をしていたかもしれない。もっと怖い思いをしていたかも。それは命を張って彼女を守ったハンナさんが一番悲しむことだ。お前がハンナさんの希望を守ったのは事実だ」
「そうかもしれない……。だけど、それだけじゃないんだ」
顔を上げた真紘は、意外にも涙は流していなかった。覚悟を決めてきたのかもしれないと重盛は思った。
「他には?」
「彼女の願いの根本はタルハネイリッカ家を守ることだ、だからこそ僕はタルハネイリッカ家の秘密を暴く必要がある」
「秘密?」
「言ったでしょ。ハンナさんの両目は灰色だったんだ。魔暴走は起こしていない。じゃあ、誰が魔暴走を起こしたんだと思う……?」
天井からトットット、トットット――と小さな音がした。
上の階のルーミが起きて駆け回っているようだ。お転婆な子だ、ノエルあたりに早く着替えるように追い回されているのかもしれない。
事故に遭って間もないが彼女はハンナに守られて全くの無傷だった。
まさか、と重盛は目を見開いた。
「子供が両親と離れて暮らすのは辛いよね……」
そう呟いた真紘もまた親と離れた子供だった。
重盛も同じだ。死別したとはいえ、寂しさはどうしたって孤独な瞬間に限って心を蝕んだ。
「まあ、そうだな。でも、もうルーミちゃんの瞳はマルクスのおっさんと同じ色だったろ。もう魔暴走は治まったんじゃ? それとも、また同じことが起きるかもしれないから、ちゃんとしたところで治療した方がいいってこと?」
「うーん。多分、治ってないんだと思う。というより治らないんだと思う」
「どゆこと?」
重盛の問いかけに対し、真紘は答えなかった。
「これからやることは全部僕の意志だ。君と意見が割れるかもしれない。そう思うと怖い。でも僕は決めた。君は僕を嫌いになる覚悟、ある?」
「やる内容も教えてくんねぇのにそれ聞く? めちゃくちゃ抽象的な質問じゃん。でも答えは決まってんだよね。俺は初めてお前を知った日から、ずっと好きだよ」
視線が絡み合う。
無言が続き、じわじわと真紘の耳の先が淡く色付いていく。
「そういうこと聞いたんじゃないんだけど……」
「嫌いにならないでぇ~って泣いておねだりするから、安心させてあげようかなって思って」
「泣いてない! ねだってない!」
顔が赤くなっている自覚があるのだろう。真紘は布団をはぎ取り白いタオルケットを頭からかぶった。
「照れるとすぅーぐ怒っちゃうのもきゃわいいね」
「可愛くない!」
「いいや、可愛い。デフォルトで可愛い。いい加減理解した? 真紘ちゃんはさ、目に入れても痛くないほど俺に愛されてるから、安心してお兄さんに話してみ?」
重盛はベッドの上で胡坐をかいて両手を広げる。
真紘はわなわなと肩を震わせたあと、タオルケットを放り投げて勢いよく胸に飛び込んできた。
「一歳差でも同級生だから、誕生日が早い僕の方がお兄さんだよ……。僕は春生まれで君は秋でしょ」
「うははっ! 暴論じゃん! もーそれでいいから教えてよ。何するつもりなんですか、真紘お兄さん?」
ムキッーと威嚇し、顔を梅干しのようにして暴れる真紘を抱いたまま横になる。
乱れて頬に掛かった銀色の束を一房を掬った。
どうしたって好きだよ、だから早く俺の気持ちに追い付いて――。
揺れる翡翠の瞳を見つめながら、重盛はそっと髪に口付けた。
重盛はルーミにとって、今日が悲しいだけの日で終わらなくて良かったと胸を撫で下ろした。
案内されたのはホワイトオーク材のダイニングテーブルがある部屋だった。
数時間前は全身黒い服を纏っていたのに、部屋は目がチカチカするほど白い。
隣で何やら考え込んでいる男も真っ白とくれば、今日一日のコントラストに少し眩暈がした。
テーブルに並ぶのはどれも色鮮やかで美味しそうな惣菜。
事前に聞いていたメニューとはどれも違う。北欧らしい柄が入った青い器に盛られてはいるが、明らかに店で買ってきたというラインナップだ。
「美味しそうですね……?」
「まあ、美味しそうだけど、これ、先生が作った風には見えないぜ」
「申し訳ございません……。祖父が急用で席を外した時に、私がサーモンとミートボールを全焼させました。とてもお出しできる物ではないので、こちらは惣菜屋で購入してきました。マルクス様と奥様は食欲がないので、食事は明日の朝、改めてと仰っております」
目の下のくまを濃くしたノエルは謝罪した。
それもそのはず、ハンナは彼にとっても大事な仕事仲間であり、朝から気を張りつめることが続いていたのだ。気もそぞろなる。さらに食事を作るプロであるシェフも今日はいない。
気持ちだけで十分だと重盛はノエルの肩を叩いた。
「先生、俺達のことはいいよ。食べた後のこともやっておく。皿は綺麗にしてここに置いておくよ。気にしないで休んで」
「こんな日にお邪魔すべきではありませんでした。本当にお構いなく。皆さん、僕達がいては、色々と気が休まらないでしょう……」
いつもと変わらぬ重盛と真紘の様子に安堵したのか、ノエルは大きなため息を吐いた。
「お気遣い感謝します。朝のことだって騎士である私がどうにかすべきだったのに……。情けないばかりです。客室の冷蔵庫にも飲み物などが入っていますので、ご自由にどうぞ。では、お二人もゆっくりお休みください」
「分かりました。食事をいただいたら今日はもう客室からでませんのでお気遣いなく。明日の朝までゆっくり休ませていただきますね」
「おやすみぃ、先生」
忙しなくどこかへと走って行ったノエルを見送る。
隣をふと見ると、真紘は暗くなった窓の外を見ていた。
そのまま夜の闇に攫われてしまいそうな、そんな予感がした。
重盛が咄嗟に真紘の肩を掴むと「食べようか」といつも通りの柔らかな笑みが返ってきた。
部屋の前で別れた時は疲労と眠気が限界だったのか、真紘は目を擦っていた。
「また明日ね、おやすみ」という声が今もこだましている。
それは一人になりたいという、彼の意思表示でもあった。
同じ家に帰り、同じ布団で寝る。
体温を感じながら聞くおやすみに慣れてしまったせいか、重盛はもう真紘に会いたくて堪らなくなった。
冷蔵庫の林檎ジュースを飲んでも、風呂に入っても心が落ち着くことはなかった。
「俺の方が年上だし? いつも強引に布団に潜り込んでる自覚はあるし? 一人になりたい日だってあるよなぁ……」
洗面台に両手をつきながら、鏡の前で自問自答を繰り返す。
白いタイルの床にポタリ、ポタリと水滴が落ちた。
重盛も簡単な生活魔法は会得していたので、今さら尻尾を乾かしてもらう必要はないのだが、やはり真紘のようにはいかなかった。
それに生活魔法を使えるといっても、風呂に入らずとも全身を清められるほどではない。出来ることといえば、泥を落とすとか、ちょろっと水を出すくらいのものだ。
重盛は無心で魔石がセットされたドライヤーのような筒を尻尾に当てた。
乾かすにもコツがあるようで、尻尾はパサパサになった。
あのふわふわとしていて艶のある毛並みは、真紘の思いやりでできていたのだと今頃になって知った。
翌朝、部屋のドアが控えめにノックされた。
日頃から起床時間を決めておかないと自堕落してしまうと心配した真紘が取り決めた時間の少し前だった。
「おはよう、重盛。起きてる?」
「はよ! 起きてる、起きた!」
真紘からのおはようの一言でスイッチが入り、ベッドを飛び降りて勢い良く扉を開けると、既に白シャツと紺のスラックスに着替えた彼がいた。サスペンダーを隠すようにベージュのショールを羽織っている。
今日も自分が選んだ物を愛用してもらえて嬉しい。重盛の尻尾は大きく揺れた。
「わっ、そんな急いで開けなくても。あのさ、朝食までに話しておきたいことがあるんだ。いいかな?」
「ダメって言ったら?」
「いいよって言ってくれるまで帰らない」
「だあッ! なんだよ、それ! もっと色気のある時間に言ってほしい台詞じゃん」
「よく分からないけど、駄目なの? いいの?」
「俺がダメって言ったことなくね?」
真紘を招き入れると途端に気分が上がった。
好きな子を目にするだけで心が躍るなんて乙女かっつーの。
重盛は正直な尻尾を鷲掴み、落ち着けと言い聞かせて深呼吸する。サイドテーブルに置いていた目覚ましをオフにして、そのままベッドに腰かけると、何も言わずとも真紘は隣に座った。
「それで? 昨日からずっと何か言いたげだったけど、教えてくれる感じ?」
「うーん。やっぱりバレてたか。じゃあ白状しようかな。君は昨日の事件、どう思った?」
事件とは白装束の集団が押しかけて来たことだろう。
どう思ったとはまた漠然とした質問だ。
しかし真紘はいきなり結論から話すタイプではないことは分っている。
大事な話は順を追って、自分自身で確認するように記憶を辿っていくのだ。
重盛は正直に答えた。
「人の気持ちを無視した強引なやり方は好きじゃない。特に動物実験は地球でも止めようって取り組みが進んでっし、人体実験だなんて、その人が生きていても死んでいても以ての外だろ。あの集団の理念には賛同できないね」
すると真紘は両手で顔を覆った。
「ちょっ、真紘ちゃん、どうした? 言い方が怖かった?」
顔を覗き込むが、ふるふると首を横に振るだけだ。
「……僕も同じ意見だよ。だからこそ、僕は僕を許せない。やってはいけないことをやってしまった。本当になんてことをしてしまったんだろう……」
真紘が肩を震わせる理由が分からず、重盛は困惑した。
そして昨日、彼がハンナに囁いた言葉を思い出した。
【……なんてことを。ゆっくりお休みください】
「白装束の女がハンナさんに飛び掛かったこと? あれは俺も止められなかったし、真紘ちゃんだけのせいじゃ――」
「違うんだよ重盛……。あの時、君には見えていなかったのかもしれないけど、ハンナさんの瞳は両目とも灰色だったんだ。それを僕が片方だけ赤く染めた」
「ど、どうして……」
「しっかり考えて行動したわけじゃない。ただ先に思っちゃったんだ。どうにかしてハンナさんのご遺体とタルハネイリッカ家をI,mから守らなくちゃいけない。だから、彼女の瞳が赤いと証明されれば、あの場から集団が立ち去るんじゃないかって。そして僕はハンナさんのご遺体を無理矢理変えてしまった。一度想像してしまったことを勢いのまま実行してしまった。いくら傷を治したって、やったことはあの白装束の女性と何も変わらないんだよ……」
己の倫理観に反した自身の行いに真紘は苦しんでいた。きっとそれは他人に許されれば良い問題ではないのだろう。
それを理解した上で、真紘は昨晩、一人になりたいと離れていったのだ。
重盛は真紘の肩をそっと抱いた。
「俺がどうこう言っても、きっとお前は自分を責めるんだろうな。でもあの集団とお前は違う。ハンナさんが守りたかったもんはなんだ? ルーミちゃんだろ。あの狭い空間で剣を抜かれていたら彼女が怪我をしていたかもしれない。もっと怖い思いをしていたかも。それは命を張って彼女を守ったハンナさんが一番悲しむことだ。お前がハンナさんの希望を守ったのは事実だ」
「そうかもしれない……。だけど、それだけじゃないんだ」
顔を上げた真紘は、意外にも涙は流していなかった。覚悟を決めてきたのかもしれないと重盛は思った。
「他には?」
「彼女の願いの根本はタルハネイリッカ家を守ることだ、だからこそ僕はタルハネイリッカ家の秘密を暴く必要がある」
「秘密?」
「言ったでしょ。ハンナさんの両目は灰色だったんだ。魔暴走は起こしていない。じゃあ、誰が魔暴走を起こしたんだと思う……?」
天井からトットット、トットット――と小さな音がした。
上の階のルーミが起きて駆け回っているようだ。お転婆な子だ、ノエルあたりに早く着替えるように追い回されているのかもしれない。
事故に遭って間もないが彼女はハンナに守られて全くの無傷だった。
まさか、と重盛は目を見開いた。
「子供が両親と離れて暮らすのは辛いよね……」
そう呟いた真紘もまた親と離れた子供だった。
重盛も同じだ。死別したとはいえ、寂しさはどうしたって孤独な瞬間に限って心を蝕んだ。
「まあ、そうだな。でも、もうルーミちゃんの瞳はマルクスのおっさんと同じ色だったろ。もう魔暴走は治まったんじゃ? それとも、また同じことが起きるかもしれないから、ちゃんとしたところで治療した方がいいってこと?」
「うーん。多分、治ってないんだと思う。というより治らないんだと思う」
「どゆこと?」
重盛の問いかけに対し、真紘は答えなかった。
「これからやることは全部僕の意志だ。君と意見が割れるかもしれない。そう思うと怖い。でも僕は決めた。君は僕を嫌いになる覚悟、ある?」
「やる内容も教えてくんねぇのにそれ聞く? めちゃくちゃ抽象的な質問じゃん。でも答えは決まってんだよね。俺は初めてお前を知った日から、ずっと好きだよ」
視線が絡み合う。
無言が続き、じわじわと真紘の耳の先が淡く色付いていく。
「そういうこと聞いたんじゃないんだけど……」
「嫌いにならないでぇ~って泣いておねだりするから、安心させてあげようかなって思って」
「泣いてない! ねだってない!」
顔が赤くなっている自覚があるのだろう。真紘は布団をはぎ取り白いタオルケットを頭からかぶった。
「照れるとすぅーぐ怒っちゃうのもきゃわいいね」
「可愛くない!」
「いいや、可愛い。デフォルトで可愛い。いい加減理解した? 真紘ちゃんはさ、目に入れても痛くないほど俺に愛されてるから、安心してお兄さんに話してみ?」
重盛はベッドの上で胡坐をかいて両手を広げる。
真紘はわなわなと肩を震わせたあと、タオルケットを放り投げて勢いよく胸に飛び込んできた。
「一歳差でも同級生だから、誕生日が早い僕の方がお兄さんだよ……。僕は春生まれで君は秋でしょ」
「うははっ! 暴論じゃん! もーそれでいいから教えてよ。何するつもりなんですか、真紘お兄さん?」
ムキッーと威嚇し、顔を梅干しのようにして暴れる真紘を抱いたまま横になる。
乱れて頬に掛かった銀色の束を一房を掬った。
どうしたって好きだよ、だから早く俺の気持ちに追い付いて――。
揺れる翡翠の瞳を見つめながら、重盛はそっと髪に口付けた。
25
あなたにおすすめの小説

公爵家の末っ子に転生しました〜出来損ないなので潔く退場しようとしたらうっかり溺愛されてしまった件について〜
上総啓
BL
公爵家の末っ子に転生したシルビオ。
体が弱く生まれて早々ぶっ倒れ、家族は見事に過保護ルートへと突き進んでしまった。
両親はめちゃくちゃ溺愛してくるし、超強い兄様はブラコンに育ち弟絶対守るマンに……。
せっかくファンタジーの世界に転生したんだから魔法も使えたり?と思ったら、我が家に代々伝わる上位氷魔法が俺にだけ使えない?
しかも俺に使える魔法は氷魔法じゃなく『神聖魔法』?というか『神聖魔法』を操れるのは神に選ばれた愛し子だけ……?
どうせ余命幾ばくもない出来損ないなら仕方ない、お荷物の僕はさっさと今世からも退場しよう……と思ってたのに?
偶然騎士たちを神聖魔法で救って、何故か天使と呼ばれて崇められたり。終いには帝国最強の狂血皇子に溺愛されて囲われちゃったり……いやいやちょっと待て。魔王様、主神様、まさかアンタらも?
……ってあれ、なんかめちゃくちゃ囲われてない??
―――
病弱ならどうせすぐ死ぬかー。ならちょっとばかし遊んでもいいよね?と自由にやってたら無駄に最強な奴らに溺愛されちゃってた受けの話。
※別名義で連載していた作品になります。
(名義を統合しこちらに移動することになりました)

異世界で8歳児になった僕は半獣さん達と仲良くスローライフを目ざします
み馬下諒
BL
志望校に合格した春、桜の樹の下で意識を失った主人公・斗馬 亮介(とうま りょうすけ)は、気がついたとき、異世界で8歳児の姿にもどっていた。
わけもわからず放心していると、いきなり巨大な黒蛇に襲われるが、水の精霊〈ミュオン・リヒテル・リノアース〉と、半獣属の大熊〈ハイロ〉があらわれて……!?
これは、異世界へ転移した8歳児が、しゃべる動物たちとスローライフ?を目ざす、ファンタジーBLです。
おとなサイド(半獣×精霊)のカプありにつき、R15にしておきました。
※ 造語、出産描写あり。前置き長め。第21話に登場人物紹介を載せました。
★お試し読みは第1部(第22〜27話あたり)がオススメです。物語の傾向がわかりやすいかと思います★
★第11回BL小説大賞エントリー作品★最終結果2773作品中/414位★応援ありがとうございました★


裏乙女ゲー?モブですよね? いいえ主人公です。
みーやん
BL
何日の時をこのソファーと過ごしただろう。
愛してやまない我が妹に頼まれた乙女ゲーの攻略は終わりを迎えようとしていた。
「私の青春学園生活⭐︎星蒼山学園」というこのタイトルの通り、女の子の主人公が学園生活を送りながら攻略対象に擦り寄り青春という名の恋愛を繰り広げるゲームだ。ちなみに女子生徒は全校生徒約900人のうち主人公1人というハーレム設定である。
あと1ヶ月後に30歳の誕生日を迎える俺には厳しすぎるゲームではあるが可愛い妹の為、精神と睡眠を削りながらやっとの思いで最後の攻略対象を攻略し見事クリアした。
最後のエンドロールまで見た後に
「裏乙女ゲームを開始しますか?」
という文字が出てきたと思ったら目の視界がだんだんと狭まってくる感覚に襲われた。
あ。俺3日寝てなかったんだ…
そんなことにふと気がついた時には視界は完全に奪われていた。
次に目が覚めると目の前には見覚えのあるゲームならではのウィンドウ。
「星蒼山学園へようこそ!攻略対象を攻略し青春を掴み取ろう!」
何度見たかわからないほど見たこの文字。そして気づく現実味のある体感。そこは3日徹夜してクリアしたゲームの世界でした。
え?意味わかんないけどとりあえず俺はもちろんモブだよね?
これはモブだと勘違いしている男が実は主人公だと気付かないまま学園生活を送る話です。

やっと退場できるはずだったβの悪役令息。ワンナイトしたらΩになりました。
毒島醜女
BL
目が覚めると、妻であるヒロインを虐げた挙句に彼女の運命の番である皇帝に断罪される最低最低なモラハラDV常習犯の悪役夫、イライ・ロザリンドに転生した。
そんな最期は絶対に避けたいイライはヒーローとヒロインの仲を結ばせつつ、ヒロインと円満に別れる為に策を練った。
彼の努力は実り、主人公たちは結ばれ、イライはお役御免となった。
「これでやっと安心して退場できる」
これまでの自分の努力を労うように酒場で飲んでいたイライは、いい薫りを漂わせる男と意気投合し、彼と一夜を共にしてしまう。
目が覚めると罪悪感に襲われ、すぐさま宿を去っていく。
「これじゃあ原作のイライと変わらないじゃん!」
その後体調不良を訴え、医師に診てもらうととんでもない事を言われたのだった。
「あなた……Ωになっていますよ」
「へ?」
そしてワンナイトをした男がまさかの国の英雄で、まさかまさか求愛し公開プロポーズまでして来て――
オメガバースの世界で運命に導かれる、強引な俺様α×頑張り屋な元悪役令息の元βのΩのラブストーリー。

VRMMOで追放された支援職、生贄にされた先で魔王様に拾われ世界一溺愛される
水凪しおん
BL
勇者パーティーに尽くしながらも、生贄として裏切られた支援職の少年ユキ。
絶望の底で出会ったのは、孤独な魔王アシュトだった。
帰る場所を失ったユキが見つけたのは、規格外の生産スキル【慈愛の手】と、魔王からの想定外な溺愛!?
「私の至宝に、指一本触れるな」
荒れた魔王領を豊かな楽園へと変えていく、心優しい青年の成り上がりと、永い孤独を生きた魔王の凍てついた心を溶かす純愛の物語。
裏切り者たちへの華麗なる復讐劇が、今、始まる。

2度目の異世界移転。あの時の少年がいい歳になっていて殺気立って睨んでくるんだけど。
ありま氷炎
BL
高校一年の時、道路陥没の事故に巻き込まれ、三日間記憶がない。
異世界転移した記憶はあるんだけど、夢だと思っていた。
二年後、どうやら異世界転移してしまったらしい。
しかもこれは二度目で、あれは夢ではなかったようだった。
再会した少年はすっかりいい歳になっていて、殺気立って睨んでくるんだけど。
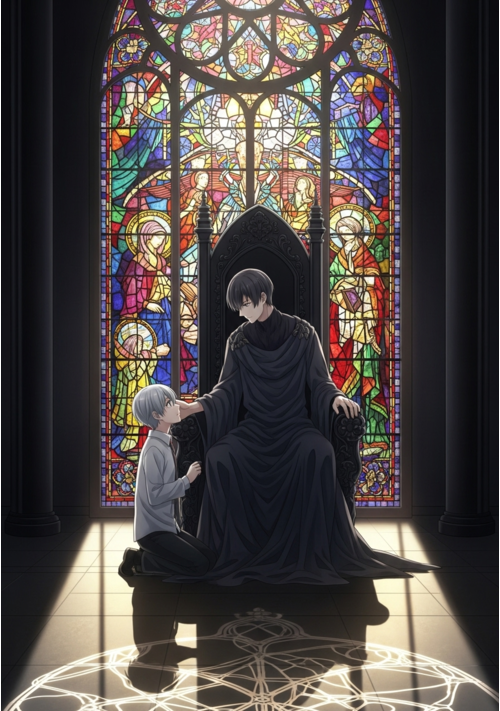
過労死で異世界転生したら、勇者の魂を持つ僕が魔王の城で目覚めた。なぜか「魂の半身」と呼ばれ異常なまでに溺愛されてる件
水凪しおん
BL
ブラック企業で過労死した俺、雪斗(ユキト)が次に目覚めたのは、なんと異世界の魔王の城だった。
赤ん坊の姿で転生した俺は、自分がこの世界を滅ぼす魔王を討つための「勇者の魂」を持つと知る。
目の前にいるのは、冷酷非情と噂の魔王ゼノン。
「ああ、終わった……食べられるんだ」
絶望する俺を前に、しかし魔王はうっとりと目を細め、こう囁いた。
「ようやく会えた、我が魂の半身よ」
それから始まったのは、地獄のような日々――ではなく、至れり尽くせりの甘やかし生活!?
最高級の食事、ふわふわの寝具、傅役(もりやく)までつけられ、魔王自らが甲斐甲斐しくお菓子を食べさせてくる始末。
この溺愛は、俺を油断させて力を奪うための罠に違いない!
そう信じて疑わない俺の勘違いをよそに、魔王の独占欲と愛情はどんどんエスカレートしていき……。
永い孤独を生きてきた最強魔王と、自己肯定感ゼロの元社畜勇者。
敵対するはずの運命が交わる時、世界を揺るがす壮大な愛の物語が始まる。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















