82 / 109
東の国
82.雪小屋
しおりを挟む
ターミナル前の飲食店の主からもらったメモを頼りに真紘と重盛はひたすら歩く。
橙色のぼんやりした光は辛うじて夕陽だと判る。灰色の空からは大きな綿雪がぼたぼたと落ちてきた。
「わっぷ、だあ~風も強すぎ! 今日中に街に辿りつける気がしねーし、もうこの辺に小屋建てない?」
「そうだね、今出すよ」
重盛は風よけになるように風上に立つが、大きな尻尾が流されて懐を漁る真紘の腰にボンボンとぶつかった。
「やべ、逆に邪魔してる」
「待って、動かないで! 今ふわふわを堪能してるから、やぶさかではないので!」
「やぶさかどころかめちゃくちゃ喜んでるじゃん! なんか真紘ちゃん、ちょっと俺に似て来たなぁ……」
溶けた氷の粒は水となり毛がぺしゃりとしているが、真紘は蕩けた表情で尻尾から伝わってくる温もりを堪能している。
「夫婦は似て来るって言うしね……?」
「くぅ……! どうしたって喜んでしまう俺、チョロすぎるぜ……」
重盛は、尻尾を抱き込む真紘からまっぽけを取り上げて、一本道から少し離れた場所にタイニーハウスを設置した。
入口で靴を脱ぎ、上着をバサバサと払う。
「ひゃ~、あったか! ほら、真紘ちゃんもこっちおいでよ」
「靴と洋服を乾かしてからね」
真紘は、ぐっしょり濡れた衣服を魔法で乾かすと、ローブに仕舞っていたメモ紙を取り出して、重盛の隣に腰かけた。
「この森を抜けると近道って書いてあるけど、思っていたより王都は遠いね。リーベ神官と萩野さんに今日中に着くのは難しそうって連絡しないと」
「俺としては、もう少しこのまま二人でもいいんだけど?」
「君の望み通り、吹雪が止むまではもう少しこのままだよ」
「いえーい! てかさ、そもそもこの地図が合ってんのか疑わしいところじゃね? 真紘ちゃんにいきなりプロボーズとか、俺だってそこまでしてないのに!」
「後半はただの私怨じゃないか。ほら、プンプンしないの。連絡するからお静かに。あ、こんばんは。真紘です――」
光る魔石の欠片に話しかける真紘。
連絡に応答したのはリーベだった。フミは宿の女将と一緒に料理をしているらしい。
「リーベ様もお料理得意ですよね?」
「ええ、ですが、フミの周りにはあまり大人の女性がいませんから、良い機会だと思い送り出しました。何より汁物の香りを嗅いで静かに泣き出したので、私では踏み込めないことかと……」
「ああ、なるほど。この国の料理は、元々僕達が暮らしていた場所に近いものだったので、萩野さんも懐かしくなったのではないでしょうか? 彼女は見た目よりも少し幼い、精神的にはまだ十代前半ですから、より家族が恋しいのだと思います……」
「そうでしたか、故郷の……。真紘様も自身の星が恋しいですか?」
「僕ですか? そうですね、家族には今でも会いたいですし、元気でやっているのか心配にもなります。だけど、今は彼が……重盛が隣にいるので、寂しくありません。きっと萩野さんもリーベ神官がいるから、笑って暮らせているのだと思います」
「そうだと良いのですが……。未婚の私には娘どころか妻もおりませんし、未だにフミにとって良き親となれているのか、不安になります。なんて、真紘様に相談すべきことではありませんね、忘れてください、ははっ」
リーベの自信のなさそうな本音は、列車でリーベのために何もできないと思い悩んでいたフミの姿を思い出させた。
互いを思いやり、すれ違う光景は、まるで本物の父と娘のようであった。
「大丈夫ですよ。以前の萩野さんを知っている僕から見ても、彼女は変わりました。リーベ神官との暮らしが楽しいのだと、お茶をした際に聞かせてもらいましたよ。あ……僕から聞いたというのは内緒にしてくださいね。秘密にとは言われていませんが、勝手にお伝えしてしまったので……」
「承知しました。ありがとうございます。真紘様の方が悩みを解決に導く神官らしいですね。いやはやお恥ずかしい」
普段二人きりで話すことのない真紘とリーベは、今まで聞いてみたかったことなど、談義に花を咲かせた。
「真紘様、少々魔石が熱くなってきました。本題に入ってもよろしいでしょうか?」
「それは失礼しました! では、お二人が宿泊されている宿の名前から――」
リーベとフミが泊っている宿の名や、道のりなどを聞いて、事前に用意していた大きな地図に書き込んでいく。
すっかり手持ち無沙汰になった重盛は、真紘の髪を結わえていたリボンを引き抜いた。
真紘は、首元にリボンの裾が当たってビクッと肩を揺らす。
「……ぁっ!」
「真紘様? どうかされましたか?」
「あ、いえ、外の風がちょっと強くておどろ、いた、だけ……です」
やめて、と口をパクパクとさせるも、真紘の声なき訴えは退けられる。さらに人差し指で首筋をつつぅ――っとなぞられ、背中を反らせると、重盛の目は三日月の形になった。
「今夜は大雪になると宿のご主人から伺いました。明日もお気をつけてお越しください。全員がそろって落ち着いたら、王城へご挨拶に参りましょう」
「は、はい……。では、おやすみなさい」
「おやすみなさいませ。真紘様……と、重盛様」
コロンと魔石の欠片が真紘の手から零れ落ちて床に転がる。
「ちょっと! 通話中にいたずらしなっ……っ!」
立ち上がって抗議しようとした瞬間、重盛の腕が腰に回り、真紘は仰向けでベッドに張り付けられていた。
右足首を掴まれて、重盛の肩に乗せられる。
捲れたスラックスの隙間からのぞくふくらはぎに尖った牙が突きたてられた。
「なにしてっ、うぁ……っ!」
ぶるりと震える真紘は、今にも捕食されそうな兎のよう。それがより一層重盛の嗜虐心を煽ることを知らずに瞳を潤ませる。
「や、やめ……」
「ん、どして? 放置されて寂しかったな~」
「それはごめん、だけど、今日お風呂入ってないしっ……あっ、だめ、だめ……っ、舐めないで、きたない、から!」
「ふふん、真紘ちゃんに汚いところなんてなぁい」
「そんなわけなっ、厚着して、汗だってかいてる……」
身を捩ってベッドの奥へと逃げるが、壁につきあたり、返って逃げ場をなくすことになった。
両足を開かれて腰と腰がパズルのようにぴたりと重なる。
期待に満ちた金色の瞳に捕らえられた真紘も興奮を隠せない。全身の血液が一瞬で沸騰したかのように赤くなり、肌が汗ばむと、重盛は舌なめずりをして嬉しそうに目を細めた。
「汗が気になるなら俺のこと綺麗にしてオッケーよ。真紘ちゃんなら一瞬でできるもんな?」
「重盛の汗じゃなくて、自分のが気になるんだよ!」
「俺は嬉しいよ。ほら、いい匂いが濃くなってきた」
「ひっ! 嗅がないで、むり、だってば……。こんな、はうっ! 集中できない、のに、魔法なんて、使えないよ……」
真紘の答えなんてとっくに分かっていた重盛は、真紘の左足も掴んで腰をさらに引き寄せた。
「この体勢恥ずかしいんだけど……」
「真紘ちゃんが逃げるからじゃん」
「逃げないから足首から手離して……」
重盛は真紘の足をそっと下ろして離す。真紘は重盛の太ももに乗ったまま背中に両腕をまわして抱き締めた。
「今日は結構歩いて疲れたから、ちゅ、ちゅーだけなら……」
「ん、じゃあ、続き――」
あと三センチで唇が触れる。真紘が目を閉じたと同時に強い力で扉が外から叩かれた。
ドンドンドン!
二人の鼻先がツンっと触れたところで見つめ合う。
「……いいよね? キスしまーす!」
にゅっと突き出した唇は真紘の両手によって遮られた。
「真紘ちゃぁん!」
「だ、誰か来たみたいだよ! 誰かな~?」
「風じゃね? 風だろ! 風だな!」
「あは、あはは、えへっ、どうかなぁ? それはドア開けてみないと、ね……?」
照れ隠しの早口で言い訳をした真紘は、せかせかとベッドから飛び降りてドアを開ける。
重盛は、真紘が寄りかかっていた壁に頭をゴンっとぶつけた。
ドアを開ける真紘。
猛吹雪の中に立っていたのは、白い大きな塊だった。塊の正体が人のようだとわかったのは「こんばんは」と肌を裂くような強風に負けぬ低く通る声で挨拶をされてからだった。
大男が動くと屋根に積もった雪が落ちるみたいに、ブロック状の雪がぼとぼと地面に落ちる。
「こ、こんばんは……」
「お前は……。久しいな、覚えているか。中央の国で会ったアルマ・スミスだ」
ニット帽とネックウォーマーを取った男は、チャコットを抜けた山中で出会ったアルマ・スミスだった。
出会ったよりも厚手の黒いコートを着ているが、黒に緑を混ぜたような艶々とした長髪は変わらず、凛々しく太い眉毛も健在だった。
「焼き芋の! その節は大変お世話になりました。いただいたお芋は全て美味しくいただきました。特に重盛が作ってくれたスイートポテトが美味しくて!」
復活した重盛が真紘の後ろから顔を出す。
「うおお、アルマ! 久しぶり! 寒いっしょ、真紘ちゃん早く入れてやんな!」
「そうでした! 狭い部屋ですが、どうぞ」
「ああ、悪いな。まさかこんな雪山で再会するとは……」
「わははっ、初めて会った時も森の中だったけどね。はいはい、コートはお預かりしますよーん。真紘ちゃんクリーニングにお任せくださーい」
「はい、乾かしておきますね。お預かりします」
真紘は、アルマから濡れたコートや靴を受け取り、ハンガーにかけ始めた。
重盛はまっぽけから椅子をもう一脚取り出して、アルマに腰かけるよう勧めた。アルマは言われるがままに椅子に腰かけたが、木製の脚はミシリと音を立てた。
「お……。悪い、俺の重みに耐えきれなかったようだ。大事なものだったか?」
椅子の側にしゃがみ込むアルマは、ベッドに座っている重盛に問う。
タルハネイリッカ領の特産品でもある木製の家具は大事ではあるが、そこまで気にすることはない。
「そんな思いつめた顔しなくても大丈夫だって」
「すまない。俺が直してもいいか?」
「うん、全然オッケーだけど……」
「まあ、見ていてくれ」
アルマは自身のリュックから銀色の魔石らしきものを取り出すと、割れてしまった椅子の脚を両手で握り込むようにして魔力を流し始めた。
氷が割れるようなピシピシという音が大きくなり、やがて金色の光がアルマの両手から漏れてスッと消えていく。そして一分もしないうちに椅子の脚は、雪の結晶を模した柄の金属のフレームで覆われた。
「壊してしまった詫びになるだろうか……。気に入らなければ取り外すこともできるが」
「お詫びどころか、とても素敵ですよ!」
洋服を乾かし終えた真紘も会話に戻ってきた。
「すげーよアルマ! 旅しながら修理の仕事してるって言ってたもんな。こんなこともできんのかよ」
「喜んでもらえて何よりだ。今回も修理の仕事の依頼でセンデルに来ていてな。隣の領での仕事を終えて王都に戻る途中だったんだが、雪が想像以上に降って困っていたところだった。そんな時に見つけたのがここだ。こんな山中に小屋があるなんて、驚いた。寒さにやられて幻覚でも見ているのかと疑ったぞ」
アルマは顔を片手で覆った。真顔で冗談をいうようなタイプには見えなかったため、真紘は少しばかり驚いた。
「ふふっ、僕達も王都に向かう途中だったんですよ」
「そうか。結構長いことここに小屋を建てているのか? それとも空間魔法か?」
「はい、空間魔法で、つい二十分前くらいからでしょうか。アルマさんも空間魔法使えるんですね。この世界で使える人に出会ったのは初めてです」
キラキラと目を輝かせて両手を握る真紘に、アルマを渋い顔をして答えた。
「いいか、志水。いくつか訂正しなければならないことがある」
「真紘ちゃんは確かに志水だけど、もう結婚したからこの世界ではタルハネイリッカが名字だよ」
すかさず訂正と牽制を入れる重盛。
「そうか、めでたいな。おめでとう。いや、今はそういうことじゃあない。いいか、タルハネイリッカ」
「タルハネイリッカだとどっちのことかわかんなくね? 真紘ちゃんのことは重盛くんのハニーって呼んで」
「いいか、重盛くんのハニー」
「よくありませんよ! 重盛もてきとうなこと言わないで、アルマさんも真に受けないでください。志水でも真紘でも構いませんので、普通に呼んでください」
重盛は口を尖らせて抗議する。アルマはこれまた素直に頷いた。
「では真紘、まず俺はこの世界の人間ではなく、お前達と同じ地球生まれだ。言うならば、救世主としてお前らの先輩でもある」
真紘と重盛はまた顔を見合わせて目を見開いた。
「お、おっおお、マジか!」
「本当だ。そして二つ目、ただの人間ならば数百年もこうして生きてはいない。俺はこの星に来た時にドワーフになった」
「ドワーフに会ったことあるけど、みんな小さかったよな? アルマは元々デカかったん?」
「そうだ。金属に関する魔法が得意なのもドワーフの特徴だろう。俺は三百年前にこっちに来たからな、ドワーフの中でもかなり有名な方だと思うぞ。保有している魔力量が多いため、魔力量の少ない土地でも普段と変わらず仕事ができるから、自分で言うのもおかしな話だが重宝されている。今ではアテナ王国にいる方が少ないくらいだ」
新たな情報の波に飲み込まれてポカンとしている真紘と重盛。アルマはマイペースに説明を続ける。
「この星で生きている救世主は、俺の恋人である獣人の男と、お前らの一つ前の世代の二人。種族はよくわからんが、どちらも男だな。他の者はみな人間のままで、既に天寿を全うした」
「そうなんですか……。恋人というのは、以前仰っていた控えめで可愛らしい方ですか? あのあと再会して復縁されたんですね!」
「会ってはいない。手紙を出したんだ。会いたいと、今でもあの子を想っていると……。そうしたら自分も同じ気持ちだが、直接会うには心構えが必要だからもう少し待ってくれと返事がきた」
アルマはリュックから手紙の束を取り出す。週に一度は手紙のやり取りをしているようで、初めの手紙を除けば中身はほとんどが近況報告だけだった。
「手紙のために空間魔法を使っているんですね」
「ああ、そうだ。だが、俺はこの小屋みたいに大きなものを出し入れできるほどの高度な魔法は使えないし、戦いにも向いていない。見掛け倒しなんだ」
「人を傷つけるよりも何かを生み出す魔法の方が素敵ですよ。こんなにも綺麗な装飾品、僕には難しいです」
「真紘ちゃんも繊細に見えて意外と大胆なところあるからな。いいじゃん、いいじゃん、みんなギャップがあって! つーかさ、相手からの手紙めちゃくちゃファンシーじゃね? なんか文字も丸っこくて可愛い感じ」
「小鳥の獣人なんだ、あの子はとても可愛いぞ。先週からこっちに来ているようだから、もしかしたらどこかで一目見れるかもしれないと、少し期待している」
淡い色の便箋には押し花が貼ってある。アテナ王国では見ることのできない花で、寒い季節にしか花を咲かせない珍しいものだ。
「見るだけでいいのかよ?」
「声をかけるつもりはないんですか?」
「東の王都も広い。一メートル先にいる、なんて状況にはならないと思う。あの子は照れ屋で見かけてもすぐに逃げてしまうから。今までもそうだったんだ。見つけても目を離したすきにどこか遠くに飛んで行ってしまう……」
「それ付き合ってんだよな……?」
「付き合い始めて三十年近くが経つはずだ」
「……えっと、すれ違い始めて何年?」
「三十年だな……」
「どっ、えっ、なんだ? じゃあ三十年近く触れ合ってないってこと⁉ 話したいとか触りたいとかあるっしょ! 枯れるにはまだ早いって! 三百年も生きていれば早くもないのか⁉ いやいやいやいや、俺は百年経っても、千年経っても真紘ちゃんとお喋りしたいし、抱きしめたいし、キスしてたいけど⁉ アルマとアルマの彼氏は本当に付き合ってんの⁉」
アルマの信じがたいほどの忍耐に、重盛の理解が追い付かずパニックになっている。重盛に触れない日などない生活を顧みると、真紘も重盛と同じような感想を抱いていることに気が付いた。
アルマは大きな背中を丸めてしょんぼりと呟く。
「恋人のままだと……俺は、思っているが……。あの子は、もう、そう思っていない……のか?」
「だだだ、大丈夫です! 手紙からはお相手の気持ちがちゃんと伝わってきますから! この押し花なんかは珍しいものでしょう? 大事な人でなければ、こんな風に贈り物をしませんよ!」
「本当にそう思うか……?」
「思います!」
「そりゃー本人に直接会って聞いてみるしかないっしょ」
真紘は重盛の耳を引っ張って無言で睨む。
「そんな可愛い顔して怒んないで」
「もう、こら! からかわないの!」
「だって、三十年も禁欲してたら俺だったらおかしくなっちゃうよ! 既にもうおかしくなりかけてる、ほら、わかる? さっきだって、もう少しでラブラブタイムだったのにさ、真紘ちゃんだって乗り気だったじゃん! キス待ち顔もすげー可愛かったけど、もっといちゃいちゃしたかった! ちょっとくらいいじわるしたって――いででッ!」
「いっ! いらないことまで言わなくてよろしい!」
二人が押し問答していると、アルマは初めて歯を見せて笑った。
「お前らは本当に仲が良いな。互いに遠慮がないというか、羨ましい。俺もいつか、あの子とそういう関係になれたらいいな」
「アルマ……。からかってごめん。恋愛相談なら長年の片想いを実らせた重盛くんに任せな」
「それは心強いな」
がっしりと握手をする重盛とアルマ。
今でこそ押せ押せの重盛だが、元は相手を見守るだけで十分だ、というタイプだったため、本質的にはアルマと似ているところがあるのかもしれない。
「そういえば、いくつか訂正がある、ということは他にもまだ何か僕達が勘違いしていることがあるのでしょうか?」
真紘の問いに対し、アルマは一拍置いて、これが一番大事だと言った。
「あのな、王都は逆方向だ」
「え?」
「お前達、ここに小屋を建てたのは俺がドアを叩く二十分前だと言ったな。だが俺が通ってきた道には足跡一つなかった。いくら吹雪でも二人が歩いていれば多少の凹みくらい残っているはずだ。途中までは雪も降っていないからな。だから反対側から歩いて来たのだろうと思ったんだが」
「えっと、俺らはドアを出て右側から来た」
「やはりな。俺は左から来たぞ。真紘が持っているメモ紙の地図は、丸々位置関係が逆転している」
真紘は信じられないと手元の地図を見る。
店主のフラれた腹いせだろうか。
「はああああ⁉ あの野郎~っ!」
重盛の叫び声が部屋に響き渡る。
「そんなぁ……」
慣れない雪道を歩いた疲労感が今になってどっと襲い掛かる。真紘は途端に脱力して、ぽてりとベッドに倒れ込んだ。
橙色のぼんやりした光は辛うじて夕陽だと判る。灰色の空からは大きな綿雪がぼたぼたと落ちてきた。
「わっぷ、だあ~風も強すぎ! 今日中に街に辿りつける気がしねーし、もうこの辺に小屋建てない?」
「そうだね、今出すよ」
重盛は風よけになるように風上に立つが、大きな尻尾が流されて懐を漁る真紘の腰にボンボンとぶつかった。
「やべ、逆に邪魔してる」
「待って、動かないで! 今ふわふわを堪能してるから、やぶさかではないので!」
「やぶさかどころかめちゃくちゃ喜んでるじゃん! なんか真紘ちゃん、ちょっと俺に似て来たなぁ……」
溶けた氷の粒は水となり毛がぺしゃりとしているが、真紘は蕩けた表情で尻尾から伝わってくる温もりを堪能している。
「夫婦は似て来るって言うしね……?」
「くぅ……! どうしたって喜んでしまう俺、チョロすぎるぜ……」
重盛は、尻尾を抱き込む真紘からまっぽけを取り上げて、一本道から少し離れた場所にタイニーハウスを設置した。
入口で靴を脱ぎ、上着をバサバサと払う。
「ひゃ~、あったか! ほら、真紘ちゃんもこっちおいでよ」
「靴と洋服を乾かしてからね」
真紘は、ぐっしょり濡れた衣服を魔法で乾かすと、ローブに仕舞っていたメモ紙を取り出して、重盛の隣に腰かけた。
「この森を抜けると近道って書いてあるけど、思っていたより王都は遠いね。リーベ神官と萩野さんに今日中に着くのは難しそうって連絡しないと」
「俺としては、もう少しこのまま二人でもいいんだけど?」
「君の望み通り、吹雪が止むまではもう少しこのままだよ」
「いえーい! てかさ、そもそもこの地図が合ってんのか疑わしいところじゃね? 真紘ちゃんにいきなりプロボーズとか、俺だってそこまでしてないのに!」
「後半はただの私怨じゃないか。ほら、プンプンしないの。連絡するからお静かに。あ、こんばんは。真紘です――」
光る魔石の欠片に話しかける真紘。
連絡に応答したのはリーベだった。フミは宿の女将と一緒に料理をしているらしい。
「リーベ様もお料理得意ですよね?」
「ええ、ですが、フミの周りにはあまり大人の女性がいませんから、良い機会だと思い送り出しました。何より汁物の香りを嗅いで静かに泣き出したので、私では踏み込めないことかと……」
「ああ、なるほど。この国の料理は、元々僕達が暮らしていた場所に近いものだったので、萩野さんも懐かしくなったのではないでしょうか? 彼女は見た目よりも少し幼い、精神的にはまだ十代前半ですから、より家族が恋しいのだと思います……」
「そうでしたか、故郷の……。真紘様も自身の星が恋しいですか?」
「僕ですか? そうですね、家族には今でも会いたいですし、元気でやっているのか心配にもなります。だけど、今は彼が……重盛が隣にいるので、寂しくありません。きっと萩野さんもリーベ神官がいるから、笑って暮らせているのだと思います」
「そうだと良いのですが……。未婚の私には娘どころか妻もおりませんし、未だにフミにとって良き親となれているのか、不安になります。なんて、真紘様に相談すべきことではありませんね、忘れてください、ははっ」
リーベの自信のなさそうな本音は、列車でリーベのために何もできないと思い悩んでいたフミの姿を思い出させた。
互いを思いやり、すれ違う光景は、まるで本物の父と娘のようであった。
「大丈夫ですよ。以前の萩野さんを知っている僕から見ても、彼女は変わりました。リーベ神官との暮らしが楽しいのだと、お茶をした際に聞かせてもらいましたよ。あ……僕から聞いたというのは内緒にしてくださいね。秘密にとは言われていませんが、勝手にお伝えしてしまったので……」
「承知しました。ありがとうございます。真紘様の方が悩みを解決に導く神官らしいですね。いやはやお恥ずかしい」
普段二人きりで話すことのない真紘とリーベは、今まで聞いてみたかったことなど、談義に花を咲かせた。
「真紘様、少々魔石が熱くなってきました。本題に入ってもよろしいでしょうか?」
「それは失礼しました! では、お二人が宿泊されている宿の名前から――」
リーベとフミが泊っている宿の名や、道のりなどを聞いて、事前に用意していた大きな地図に書き込んでいく。
すっかり手持ち無沙汰になった重盛は、真紘の髪を結わえていたリボンを引き抜いた。
真紘は、首元にリボンの裾が当たってビクッと肩を揺らす。
「……ぁっ!」
「真紘様? どうかされましたか?」
「あ、いえ、外の風がちょっと強くておどろ、いた、だけ……です」
やめて、と口をパクパクとさせるも、真紘の声なき訴えは退けられる。さらに人差し指で首筋をつつぅ――っとなぞられ、背中を反らせると、重盛の目は三日月の形になった。
「今夜は大雪になると宿のご主人から伺いました。明日もお気をつけてお越しください。全員がそろって落ち着いたら、王城へご挨拶に参りましょう」
「は、はい……。では、おやすみなさい」
「おやすみなさいませ。真紘様……と、重盛様」
コロンと魔石の欠片が真紘の手から零れ落ちて床に転がる。
「ちょっと! 通話中にいたずらしなっ……っ!」
立ち上がって抗議しようとした瞬間、重盛の腕が腰に回り、真紘は仰向けでベッドに張り付けられていた。
右足首を掴まれて、重盛の肩に乗せられる。
捲れたスラックスの隙間からのぞくふくらはぎに尖った牙が突きたてられた。
「なにしてっ、うぁ……っ!」
ぶるりと震える真紘は、今にも捕食されそうな兎のよう。それがより一層重盛の嗜虐心を煽ることを知らずに瞳を潤ませる。
「や、やめ……」
「ん、どして? 放置されて寂しかったな~」
「それはごめん、だけど、今日お風呂入ってないしっ……あっ、だめ、だめ……っ、舐めないで、きたない、から!」
「ふふん、真紘ちゃんに汚いところなんてなぁい」
「そんなわけなっ、厚着して、汗だってかいてる……」
身を捩ってベッドの奥へと逃げるが、壁につきあたり、返って逃げ場をなくすことになった。
両足を開かれて腰と腰がパズルのようにぴたりと重なる。
期待に満ちた金色の瞳に捕らえられた真紘も興奮を隠せない。全身の血液が一瞬で沸騰したかのように赤くなり、肌が汗ばむと、重盛は舌なめずりをして嬉しそうに目を細めた。
「汗が気になるなら俺のこと綺麗にしてオッケーよ。真紘ちゃんなら一瞬でできるもんな?」
「重盛の汗じゃなくて、自分のが気になるんだよ!」
「俺は嬉しいよ。ほら、いい匂いが濃くなってきた」
「ひっ! 嗅がないで、むり、だってば……。こんな、はうっ! 集中できない、のに、魔法なんて、使えないよ……」
真紘の答えなんてとっくに分かっていた重盛は、真紘の左足も掴んで腰をさらに引き寄せた。
「この体勢恥ずかしいんだけど……」
「真紘ちゃんが逃げるからじゃん」
「逃げないから足首から手離して……」
重盛は真紘の足をそっと下ろして離す。真紘は重盛の太ももに乗ったまま背中に両腕をまわして抱き締めた。
「今日は結構歩いて疲れたから、ちゅ、ちゅーだけなら……」
「ん、じゃあ、続き――」
あと三センチで唇が触れる。真紘が目を閉じたと同時に強い力で扉が外から叩かれた。
ドンドンドン!
二人の鼻先がツンっと触れたところで見つめ合う。
「……いいよね? キスしまーす!」
にゅっと突き出した唇は真紘の両手によって遮られた。
「真紘ちゃぁん!」
「だ、誰か来たみたいだよ! 誰かな~?」
「風じゃね? 風だろ! 風だな!」
「あは、あはは、えへっ、どうかなぁ? それはドア開けてみないと、ね……?」
照れ隠しの早口で言い訳をした真紘は、せかせかとベッドから飛び降りてドアを開ける。
重盛は、真紘が寄りかかっていた壁に頭をゴンっとぶつけた。
ドアを開ける真紘。
猛吹雪の中に立っていたのは、白い大きな塊だった。塊の正体が人のようだとわかったのは「こんばんは」と肌を裂くような強風に負けぬ低く通る声で挨拶をされてからだった。
大男が動くと屋根に積もった雪が落ちるみたいに、ブロック状の雪がぼとぼと地面に落ちる。
「こ、こんばんは……」
「お前は……。久しいな、覚えているか。中央の国で会ったアルマ・スミスだ」
ニット帽とネックウォーマーを取った男は、チャコットを抜けた山中で出会ったアルマ・スミスだった。
出会ったよりも厚手の黒いコートを着ているが、黒に緑を混ぜたような艶々とした長髪は変わらず、凛々しく太い眉毛も健在だった。
「焼き芋の! その節は大変お世話になりました。いただいたお芋は全て美味しくいただきました。特に重盛が作ってくれたスイートポテトが美味しくて!」
復活した重盛が真紘の後ろから顔を出す。
「うおお、アルマ! 久しぶり! 寒いっしょ、真紘ちゃん早く入れてやんな!」
「そうでした! 狭い部屋ですが、どうぞ」
「ああ、悪いな。まさかこんな雪山で再会するとは……」
「わははっ、初めて会った時も森の中だったけどね。はいはい、コートはお預かりしますよーん。真紘ちゃんクリーニングにお任せくださーい」
「はい、乾かしておきますね。お預かりします」
真紘は、アルマから濡れたコートや靴を受け取り、ハンガーにかけ始めた。
重盛はまっぽけから椅子をもう一脚取り出して、アルマに腰かけるよう勧めた。アルマは言われるがままに椅子に腰かけたが、木製の脚はミシリと音を立てた。
「お……。悪い、俺の重みに耐えきれなかったようだ。大事なものだったか?」
椅子の側にしゃがみ込むアルマは、ベッドに座っている重盛に問う。
タルハネイリッカ領の特産品でもある木製の家具は大事ではあるが、そこまで気にすることはない。
「そんな思いつめた顔しなくても大丈夫だって」
「すまない。俺が直してもいいか?」
「うん、全然オッケーだけど……」
「まあ、見ていてくれ」
アルマは自身のリュックから銀色の魔石らしきものを取り出すと、割れてしまった椅子の脚を両手で握り込むようにして魔力を流し始めた。
氷が割れるようなピシピシという音が大きくなり、やがて金色の光がアルマの両手から漏れてスッと消えていく。そして一分もしないうちに椅子の脚は、雪の結晶を模した柄の金属のフレームで覆われた。
「壊してしまった詫びになるだろうか……。気に入らなければ取り外すこともできるが」
「お詫びどころか、とても素敵ですよ!」
洋服を乾かし終えた真紘も会話に戻ってきた。
「すげーよアルマ! 旅しながら修理の仕事してるって言ってたもんな。こんなこともできんのかよ」
「喜んでもらえて何よりだ。今回も修理の仕事の依頼でセンデルに来ていてな。隣の領での仕事を終えて王都に戻る途中だったんだが、雪が想像以上に降って困っていたところだった。そんな時に見つけたのがここだ。こんな山中に小屋があるなんて、驚いた。寒さにやられて幻覚でも見ているのかと疑ったぞ」
アルマは顔を片手で覆った。真顔で冗談をいうようなタイプには見えなかったため、真紘は少しばかり驚いた。
「ふふっ、僕達も王都に向かう途中だったんですよ」
「そうか。結構長いことここに小屋を建てているのか? それとも空間魔法か?」
「はい、空間魔法で、つい二十分前くらいからでしょうか。アルマさんも空間魔法使えるんですね。この世界で使える人に出会ったのは初めてです」
キラキラと目を輝かせて両手を握る真紘に、アルマを渋い顔をして答えた。
「いいか、志水。いくつか訂正しなければならないことがある」
「真紘ちゃんは確かに志水だけど、もう結婚したからこの世界ではタルハネイリッカが名字だよ」
すかさず訂正と牽制を入れる重盛。
「そうか、めでたいな。おめでとう。いや、今はそういうことじゃあない。いいか、タルハネイリッカ」
「タルハネイリッカだとどっちのことかわかんなくね? 真紘ちゃんのことは重盛くんのハニーって呼んで」
「いいか、重盛くんのハニー」
「よくありませんよ! 重盛もてきとうなこと言わないで、アルマさんも真に受けないでください。志水でも真紘でも構いませんので、普通に呼んでください」
重盛は口を尖らせて抗議する。アルマはこれまた素直に頷いた。
「では真紘、まず俺はこの世界の人間ではなく、お前達と同じ地球生まれだ。言うならば、救世主としてお前らの先輩でもある」
真紘と重盛はまた顔を見合わせて目を見開いた。
「お、おっおお、マジか!」
「本当だ。そして二つ目、ただの人間ならば数百年もこうして生きてはいない。俺はこの星に来た時にドワーフになった」
「ドワーフに会ったことあるけど、みんな小さかったよな? アルマは元々デカかったん?」
「そうだ。金属に関する魔法が得意なのもドワーフの特徴だろう。俺は三百年前にこっちに来たからな、ドワーフの中でもかなり有名な方だと思うぞ。保有している魔力量が多いため、魔力量の少ない土地でも普段と変わらず仕事ができるから、自分で言うのもおかしな話だが重宝されている。今ではアテナ王国にいる方が少ないくらいだ」
新たな情報の波に飲み込まれてポカンとしている真紘と重盛。アルマはマイペースに説明を続ける。
「この星で生きている救世主は、俺の恋人である獣人の男と、お前らの一つ前の世代の二人。種族はよくわからんが、どちらも男だな。他の者はみな人間のままで、既に天寿を全うした」
「そうなんですか……。恋人というのは、以前仰っていた控えめで可愛らしい方ですか? あのあと再会して復縁されたんですね!」
「会ってはいない。手紙を出したんだ。会いたいと、今でもあの子を想っていると……。そうしたら自分も同じ気持ちだが、直接会うには心構えが必要だからもう少し待ってくれと返事がきた」
アルマはリュックから手紙の束を取り出す。週に一度は手紙のやり取りをしているようで、初めの手紙を除けば中身はほとんどが近況報告だけだった。
「手紙のために空間魔法を使っているんですね」
「ああ、そうだ。だが、俺はこの小屋みたいに大きなものを出し入れできるほどの高度な魔法は使えないし、戦いにも向いていない。見掛け倒しなんだ」
「人を傷つけるよりも何かを生み出す魔法の方が素敵ですよ。こんなにも綺麗な装飾品、僕には難しいです」
「真紘ちゃんも繊細に見えて意外と大胆なところあるからな。いいじゃん、いいじゃん、みんなギャップがあって! つーかさ、相手からの手紙めちゃくちゃファンシーじゃね? なんか文字も丸っこくて可愛い感じ」
「小鳥の獣人なんだ、あの子はとても可愛いぞ。先週からこっちに来ているようだから、もしかしたらどこかで一目見れるかもしれないと、少し期待している」
淡い色の便箋には押し花が貼ってある。アテナ王国では見ることのできない花で、寒い季節にしか花を咲かせない珍しいものだ。
「見るだけでいいのかよ?」
「声をかけるつもりはないんですか?」
「東の王都も広い。一メートル先にいる、なんて状況にはならないと思う。あの子は照れ屋で見かけてもすぐに逃げてしまうから。今までもそうだったんだ。見つけても目を離したすきにどこか遠くに飛んで行ってしまう……」
「それ付き合ってんだよな……?」
「付き合い始めて三十年近くが経つはずだ」
「……えっと、すれ違い始めて何年?」
「三十年だな……」
「どっ、えっ、なんだ? じゃあ三十年近く触れ合ってないってこと⁉ 話したいとか触りたいとかあるっしょ! 枯れるにはまだ早いって! 三百年も生きていれば早くもないのか⁉ いやいやいやいや、俺は百年経っても、千年経っても真紘ちゃんとお喋りしたいし、抱きしめたいし、キスしてたいけど⁉ アルマとアルマの彼氏は本当に付き合ってんの⁉」
アルマの信じがたいほどの忍耐に、重盛の理解が追い付かずパニックになっている。重盛に触れない日などない生活を顧みると、真紘も重盛と同じような感想を抱いていることに気が付いた。
アルマは大きな背中を丸めてしょんぼりと呟く。
「恋人のままだと……俺は、思っているが……。あの子は、もう、そう思っていない……のか?」
「だだだ、大丈夫です! 手紙からはお相手の気持ちがちゃんと伝わってきますから! この押し花なんかは珍しいものでしょう? 大事な人でなければ、こんな風に贈り物をしませんよ!」
「本当にそう思うか……?」
「思います!」
「そりゃー本人に直接会って聞いてみるしかないっしょ」
真紘は重盛の耳を引っ張って無言で睨む。
「そんな可愛い顔して怒んないで」
「もう、こら! からかわないの!」
「だって、三十年も禁欲してたら俺だったらおかしくなっちゃうよ! 既にもうおかしくなりかけてる、ほら、わかる? さっきだって、もう少しでラブラブタイムだったのにさ、真紘ちゃんだって乗り気だったじゃん! キス待ち顔もすげー可愛かったけど、もっといちゃいちゃしたかった! ちょっとくらいいじわるしたって――いででッ!」
「いっ! いらないことまで言わなくてよろしい!」
二人が押し問答していると、アルマは初めて歯を見せて笑った。
「お前らは本当に仲が良いな。互いに遠慮がないというか、羨ましい。俺もいつか、あの子とそういう関係になれたらいいな」
「アルマ……。からかってごめん。恋愛相談なら長年の片想いを実らせた重盛くんに任せな」
「それは心強いな」
がっしりと握手をする重盛とアルマ。
今でこそ押せ押せの重盛だが、元は相手を見守るだけで十分だ、というタイプだったため、本質的にはアルマと似ているところがあるのかもしれない。
「そういえば、いくつか訂正がある、ということは他にもまだ何か僕達が勘違いしていることがあるのでしょうか?」
真紘の問いに対し、アルマは一拍置いて、これが一番大事だと言った。
「あのな、王都は逆方向だ」
「え?」
「お前達、ここに小屋を建てたのは俺がドアを叩く二十分前だと言ったな。だが俺が通ってきた道には足跡一つなかった。いくら吹雪でも二人が歩いていれば多少の凹みくらい残っているはずだ。途中までは雪も降っていないからな。だから反対側から歩いて来たのだろうと思ったんだが」
「えっと、俺らはドアを出て右側から来た」
「やはりな。俺は左から来たぞ。真紘が持っているメモ紙の地図は、丸々位置関係が逆転している」
真紘は信じられないと手元の地図を見る。
店主のフラれた腹いせだろうか。
「はああああ⁉ あの野郎~っ!」
重盛の叫び声が部屋に響き渡る。
「そんなぁ……」
慣れない雪道を歩いた疲労感が今になってどっと襲い掛かる。真紘は途端に脱力して、ぽてりとベッドに倒れ込んだ。
59
あなたにおすすめの小説

公爵家の末っ子に転生しました〜出来損ないなので潔く退場しようとしたらうっかり溺愛されてしまった件について〜
上総啓
BL
公爵家の末っ子に転生したシルビオ。
体が弱く生まれて早々ぶっ倒れ、家族は見事に過保護ルートへと突き進んでしまった。
両親はめちゃくちゃ溺愛してくるし、超強い兄様はブラコンに育ち弟絶対守るマンに……。
せっかくファンタジーの世界に転生したんだから魔法も使えたり?と思ったら、我が家に代々伝わる上位氷魔法が俺にだけ使えない?
しかも俺に使える魔法は氷魔法じゃなく『神聖魔法』?というか『神聖魔法』を操れるのは神に選ばれた愛し子だけ……?
どうせ余命幾ばくもない出来損ないなら仕方ない、お荷物の僕はさっさと今世からも退場しよう……と思ってたのに?
偶然騎士たちを神聖魔法で救って、何故か天使と呼ばれて崇められたり。終いには帝国最強の狂血皇子に溺愛されて囲われちゃったり……いやいやちょっと待て。魔王様、主神様、まさかアンタらも?
……ってあれ、なんかめちゃくちゃ囲われてない??
―――
病弱ならどうせすぐ死ぬかー。ならちょっとばかし遊んでもいいよね?と自由にやってたら無駄に最強な奴らに溺愛されちゃってた受けの話。
※別名義で連載していた作品になります。
(名義を統合しこちらに移動することになりました)

異世界で8歳児になった僕は半獣さん達と仲良くスローライフを目ざします
み馬下諒
BL
志望校に合格した春、桜の樹の下で意識を失った主人公・斗馬 亮介(とうま りょうすけ)は、気がついたとき、異世界で8歳児の姿にもどっていた。
わけもわからず放心していると、いきなり巨大な黒蛇に襲われるが、水の精霊〈ミュオン・リヒテル・リノアース〉と、半獣属の大熊〈ハイロ〉があらわれて……!?
これは、異世界へ転移した8歳児が、しゃべる動物たちとスローライフ?を目ざす、ファンタジーBLです。
おとなサイド(半獣×精霊)のカプありにつき、R15にしておきました。
※ 造語、出産描写あり。前置き長め。第21話に登場人物紹介を載せました。
★お試し読みは第1部(第22〜27話あたり)がオススメです。物語の傾向がわかりやすいかと思います★
★第11回BL小説大賞エントリー作品★最終結果2773作品中/414位★応援ありがとうございました★

VRMMOで追放された支援職、生贄にされた先で魔王様に拾われ世界一溺愛される
水凪しおん
BL
勇者パーティーに尽くしながらも、生贄として裏切られた支援職の少年ユキ。
絶望の底で出会ったのは、孤独な魔王アシュトだった。
帰る場所を失ったユキが見つけたのは、規格外の生産スキル【慈愛の手】と、魔王からの想定外な溺愛!?
「私の至宝に、指一本触れるな」
荒れた魔王領を豊かな楽園へと変えていく、心優しい青年の成り上がりと、永い孤独を生きた魔王の凍てついた心を溶かす純愛の物語。
裏切り者たちへの華麗なる復讐劇が、今、始まる。


裏乙女ゲー?モブですよね? いいえ主人公です。
みーやん
BL
何日の時をこのソファーと過ごしただろう。
愛してやまない我が妹に頼まれた乙女ゲーの攻略は終わりを迎えようとしていた。
「私の青春学園生活⭐︎星蒼山学園」というこのタイトルの通り、女の子の主人公が学園生活を送りながら攻略対象に擦り寄り青春という名の恋愛を繰り広げるゲームだ。ちなみに女子生徒は全校生徒約900人のうち主人公1人というハーレム設定である。
あと1ヶ月後に30歳の誕生日を迎える俺には厳しすぎるゲームではあるが可愛い妹の為、精神と睡眠を削りながらやっとの思いで最後の攻略対象を攻略し見事クリアした。
最後のエンドロールまで見た後に
「裏乙女ゲームを開始しますか?」
という文字が出てきたと思ったら目の視界がだんだんと狭まってくる感覚に襲われた。
あ。俺3日寝てなかったんだ…
そんなことにふと気がついた時には視界は完全に奪われていた。
次に目が覚めると目の前には見覚えのあるゲームならではのウィンドウ。
「星蒼山学園へようこそ!攻略対象を攻略し青春を掴み取ろう!」
何度見たかわからないほど見たこの文字。そして気づく現実味のある体感。そこは3日徹夜してクリアしたゲームの世界でした。
え?意味わかんないけどとりあえず俺はもちろんモブだよね?
これはモブだと勘違いしている男が実は主人公だと気付かないまま学園生活を送る話です。

2度目の異世界移転。あの時の少年がいい歳になっていて殺気立って睨んでくるんだけど。
ありま氷炎
BL
高校一年の時、道路陥没の事故に巻き込まれ、三日間記憶がない。
異世界転移した記憶はあるんだけど、夢だと思っていた。
二年後、どうやら異世界転移してしまったらしい。
しかもこれは二度目で、あれは夢ではなかったようだった。
再会した少年はすっかりいい歳になっていて、殺気立って睨んでくるんだけど。
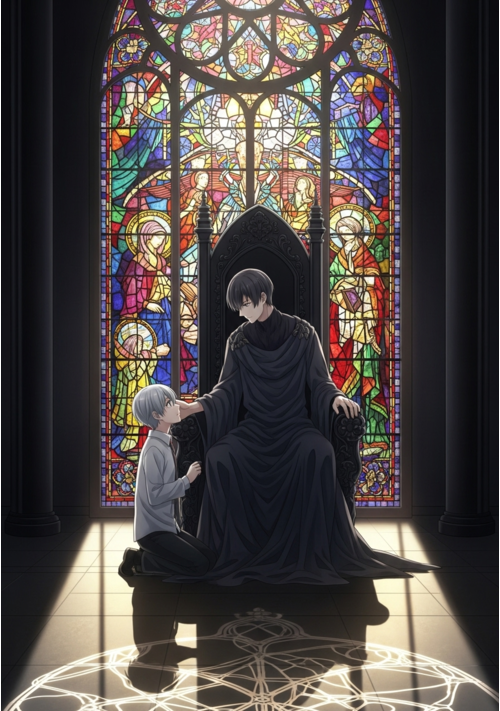
過労死で異世界転生したら、勇者の魂を持つ僕が魔王の城で目覚めた。なぜか「魂の半身」と呼ばれ異常なまでに溺愛されてる件
水凪しおん
BL
ブラック企業で過労死した俺、雪斗(ユキト)が次に目覚めたのは、なんと異世界の魔王の城だった。
赤ん坊の姿で転生した俺は、自分がこの世界を滅ぼす魔王を討つための「勇者の魂」を持つと知る。
目の前にいるのは、冷酷非情と噂の魔王ゼノン。
「ああ、終わった……食べられるんだ」
絶望する俺を前に、しかし魔王はうっとりと目を細め、こう囁いた。
「ようやく会えた、我が魂の半身よ」
それから始まったのは、地獄のような日々――ではなく、至れり尽くせりの甘やかし生活!?
最高級の食事、ふわふわの寝具、傅役(もりやく)までつけられ、魔王自らが甲斐甲斐しくお菓子を食べさせてくる始末。
この溺愛は、俺を油断させて力を奪うための罠に違いない!
そう信じて疑わない俺の勘違いをよそに、魔王の独占欲と愛情はどんどんエスカレートしていき……。
永い孤独を生きてきた最強魔王と、自己肯定感ゼロの元社畜勇者。
敵対するはずの運命が交わる時、世界を揺るがす壮大な愛の物語が始まる。

【完結】テルの異世界転換紀?!転がり落ちたら世界が変わっていた。
カヨワイさつき
BL
小学生の頃両親が蒸発、その後親戚中をたらいまわしにされ住むところも失った田辺輝(たなべ てる)は毎日切り詰めた生活をしていた。複数のバイトしていたある日、コスプレ?した男と出会った。
異世界ファンタジー、そしてちょっぴりすれ違いの恋愛。
ドワーフ族に助けられ家族として過ごす"テル"。本当の両親は……。
そして、コスプレと思っていた男性は……。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















