90 / 109
東の国
90.合流ステーション
しおりを挟む
「リンさん、無理しないで大丈夫ですよ。ミンミン亭で休んでいても……」
探していた教え子がフローラ侯爵襲撃の犯人の可能性が高いと知ってから、リンは明らかに元気をなくしてしまった。
メッシュのように生えている紫色の小さな羽もへたりと下がったままだ。
「ううん……。ボク、こっちに来てから王都から少し外れた場所にある教会で寝泊まりしてたんよ。昨日は酒場を巡ってフェリを探してたから帰ってないけど、今日は夜になったらあっちに一旦戻る。お願い、それまで調査続けよ。だめ?」
「僕は構いませんよ。というか、あの教会で寝泊まりしていたのはリンさんだったんですね。神木の枝に魔力補填をしに行ったのですが、勝手に入ってしまいました。ごめんなさい」
「いいの、いいの。ボクも無断で使こうてる。むしろ森ん中の無人教会やのに使用感あってビックリしたやろ? ごめんなあ」
「そんな……。教会の周りに足跡がなかったのも、リンさんが屋根から出入りしていたからなんですね。謎が解けました」
「天窓から出入りしててん。なら良かった」
小さく笑ったリンは、真紘の肩に頭を乗せた。
主張の強そうな見た目に反して、繊細で自分に自信がない人だ。年下の後輩に寄りかかるのも勇気が必要だっただろう。
そっと肩を抱くと、リンは嬉しそうに笑った。
「人に寄りかかったの久しぶりやわ」
「以前はアルマさんに? 久しぶりなのに、低い位置にある肩ですみません」
「ぶっは! 三十センチ以上身長差あるのにアルマの肩に頭乗せられるわけないやんか! そうじゃなくても難しいかもしれんけど……。昔は寄りかかるより、アルマの脇に手入れて、こうガバっと持ち上げてな、空の散歩したことのが多かったかもしれん」
ケタケタと笑うリンはピョンピョン跳ねて真紘に抱き着く。
身長差はあるものの、体重は真紘の方が軽いため、衝撃に耐えられずふらついた。
「元気が出たみたいで良かったです。お散歩デートいいですね。またきっとできますよ。それに抱えて飛んでしまえばアルマさんは逃げられませんし、こっちのペースじゃないですか」
「きゃははっ! マヒロくんたまに発想が物騒! まっ、それだけ力があればパワーゴリ押しタイプになってもしゃーないか」
「すみません。隣にいる人が何をしても喜ぶもので、この世界に来てからというもの、少しばかり気が大きくなって。力頼りになるのも過信しすぎるのも良くありませんね」
「あ~また旦那の話や! 次、惚気たら刺すで!」
「はっ! 名前は出していないので、セーフではないでしょうか……?」
「ギリアウトやん。ああ、ええなァ~ええなァ~」
「いいですよ? 好きな人を大好きだと言えることは、幸せなことです」
「開き直りよった!」
うな垂れるリンを引きずるようにして進むと公園が見えてきたため、そこで休憩することにした。
ベンチは雪が降ろしてあって、周りにいくつもの足跡が残っている。午前中に誰かが座ったのだろう。
真紘とリンはそこに並んで腰かける。
目の前には水の出ていない丸い噴水。五十センチほど深さのある水受けの中は、小さなスケートリンクのようになっていた。
「あ、来た! こっちや~!」
リンが空に向かって呼び掛けると、白い綿毛のような小さな鳥がベンチの周りに集まってきた。
そして一斉にピッピッピッピッと鳴き始める。
「えっと、ご友人ですか……?」
「ご友人? 友達っちゃ友達だけど、仲間の方が近いなあ。鳥同士の助け合いコミュニティーみたいなもんや。向こうの山にでっかい鷲がおるよとか、王城の中に実がついてる木があったよーとか、情報交換してん」
「リンさんは小鳥さんの話していることも分かるんですね!」
「百パー理解してるわけちゃうけど、鳥相手ならわかる」
「それは素敵ですね」
「せやろ?」
ピューっと口笛を吹いてリンは小鳥達と会話を始める。
重盛も森の中で遭遇した狐に、何やら一言、二言、話しかけていた。何か会話をしていたのかもしれない。
あれもアルマと出会う少し前の記憶だ。
何を話していたのか聞いてみれば良かった。野生のキノコの見分け方には自信がないと言っていたので、食べられる種類でも聞いていたのだろうか。
見つめ合う一人と一匹、互いに尻尾がふりふりと揺れていて、とても可愛らしかったことはよく覚えている。
真紘が物思いにふけっていると、白い小鳥達がバサバサッと飛び立っていった。
「わあっ! お話しはもう大丈夫なんですか?」
「うん。あの子らに、今日の朝、フェリを西門近くで見かけてないか聞いてみたんや……」
随分ストレートな質問をしたものだと真紘は表情に出さず驚く。てっきりモア・センデルあたりで不審者を見かけなかったとか、そういう質問をしているのかと思っていた。
「まだ彼が犯人かは……」
「ボクもさっきまで信じとった。信じとったからこそ、違うっちゅー証拠がほしかった。せやけど、確信に変わってしもた。ボクが王城の周りをうろついとった理由は、そもそも街の西側でフェリを目撃したっちゅー鳥たちからのタレコミやねん。だからモア・センデルの屋根の上も何回か飛んでた。そんで、ついに有力な目撃証言が出て来た」
「それが今の小鳥さんたちの……」
ベンチの背もたれに体を預けて、リンは空を見上げる。
真紘も同じ姿勢を取ると、雲一つない澄みきった冬の青で視界がいっぱいになった。
「王城の西門付近に実がなった木が残っとってな、そこで番の小鳥ちゃんたちが朝ごはん食べてたらしいねん。もう老夫婦で、陽が昇るよりちょっと早く朝食に出発するんやって」
「随分可愛らしいご夫婦ですね」
「なあ~。食欲旺盛なのはええことや。そんでな、西門の屋根に並んで実を食べてた時に、モア・センデルの最上階から人が飛び出してきたらしいねん。初めは大きな鳥かと思うたけど、よお見たら白いコートを着た水色髪した若い男だった言うんよ」
「水色の髪?」
「フェリもこっちの世界に来てから毛色が変わったんや。マヒロくんとはまた違った色白さで、狼の獣人らしいんやけど、耳や尻尾は生えてなくて――」
「牙だけ生えてる……」
「そう! マヒロくん、知っとったん? レヴィ様あたりが王城の書庫にでも記録残してたんやろか?」
センデルの駅前での出会いの記憶はまだ鮮明で、すぐさま点と点が繋がり線になった。
「フェリクスさんって、目元が涼しげで髪は肩について少しはねるくらい。わりと賑やかな方ですか?」
「なんや会ったことあるみたいな言い方するなあ。髪の毛はいつも長めやったけど、三十年も前の記憶や。今はわからん。体はあんまり強なかったけど、テンションはいつも高かったなあ。なんの記録で見たん?」
「記録ではなく僕自身の記憶です。昨日、リンさんのおっしゃるフェリクスさんによく似た方と出会いました。その方は、駅前のセンデル名物の包み握り屋さんで、そこのご主人だと。あれ? でもどうして僕は、彼から狼の獣人だと聞く前に、狼だと思ったんだろう……。彼には牙しか生えていなかったのに……」
頬に当たる風は痛いほど冷たいというのに、嫌な汗が背中を伝う。
リンは血相を変えて真紘の腕を引いて空に舞い上がった。
「り、リンさん⁉」
「あかん、あかんよ! ボクもこっちについてすぐにその店に寄った。店名は【狼と列車】で、そこのマスターは尻尾の大きな狼の……おじいちゃんなんよ……ッ!」
「そんなっ! だけどあの店には若い店主だけで、他の魔力の気配も、重盛の嗅覚にも何も反応がなくて……」
「と、とにかく確かめに行くで!」
猛スピードで進むリンは、今にも泣きそうな顔をしている。
これ以上王都の上空を飛行して目立ちたくないなど言っている場合ではない。
真紘も自身の鈍感さを悔いるばかりだ。
今思えば、あの店に入ってから違和感は数え切れないほどあった。
店主なのにペンやメモの場所が分からず探していたこと。書いてくれた地図が真逆だったこともそうだ。駅前の店主ならば、道案内なんて何度もしているはずだし、間違えるわけがない。
駅前で待ち構えていたのは、魔力の高い貴族が一度に大勢来る機会など今までなかったため、様子見といったところだろう。
救世主が代替わりしていたと知り驚いていたのは、人とあまり交流をせず引き籠っていたせいかもしれない。クルーズトレインの到着セレモニーの周知は街中にポスターが貼ってあったため、生活備品を買いに人里に降りて来た時にでも目にしたのだろう。
だが、突然のプロボーズは、一体、何がきっかけで――。
「まっぽけだ……」
「ぽっけがどうしたん? 何か取り出すにしても、空の上では止めとき。落っことすで」
「そうではなくて、僕は普段から魔力を遮断しているんです。獣人以上にぴったり魔力を止めているので、一切魔力を感じないと思います。でもこのまっぽけは、空間魔法を応用しているので、出し入れする際に魔力が必要になります。誰しも魔法を使う瞬間は魔力がどうしても零れる」
「獣人は魔力を全身に巡らせてなんぼやから、自然体な人が多いし、魔力の多い貴族でも完全に遮断するのは無理やで。そんな神業、できんのマヒロくんくらいとちゃうん?」
「魔力の完全遮断ができる人物は、僕の他にも、もう一人います。怪盗であることが残念なんですが……。そんなレアケースだからこそおかしいんです。僕が会ったフェリクスさんからは、魔力を一切感じられなかった。獣人の身体的特徴が出ていない分、魔力も少ないのかもしれないと思っていましたが、リンさんがおっしゃったように獣人は魔力を内側で循環させているため、自然体な人が多い。どうしたって魔力は零れるものです」
「待って、頭が追いつかん! 」
「つまり、その理論から考えられるのは、フェリクスさんは、そもそも狼の獣人ではないかもしれない、ということです」
「はあ⁉ で、でも本人はそう言って……」
「自己申告でしょう? 小鳥さんたちは空を飛ぶフェリクスさんを目撃しています。どんなに跳躍力があっても足跡は残るし、狼の獣人には無理です。窓枠に残っていた僅かな残滓から、遮断していた魔法を使ったと言われた方が納得できます」
「確かに狼に空を飛ぶんは無理や……。でもボクは、フェリが飛んだ姿を七十年間一度も見たことがない! ずっとボクが抱えて飛んで……。いや、でも飛んだあといつも体が重くなってた。アルマより軽いはずなのに……」
目を背けていた現実がリンを襲う。
真紘だって教え子であるマルクスの息子、ルノが犯罪に関わっていると知れば、落ち着いていられないだろう。数ヶ月一緒にいただけでも、心が痛むというのに、リンはフェリクスと七十年も共にいたのだ。失踪してからずっと探していた教え子が、自身の体調不良の原因であり、フローラ侯爵襲撃を含め、過去三十年に渡る犯罪の犯人かもしれないなんて、相当なショックだろう。
「根拠はもう一つあります。僕、フェリクスさんにまっぽけから取り出したメモ帳を手渡したんです。その時一瞬だけ手元が引きずられた気がしたんですけど、もしかしたら魔力を吸われていたのかも……」
「な、なんやて⁉」
「そのあとすぐに告白されて、プロボーズされました。重盛が怒ってすぐに退店することになったんですけど、フェリクスさんは、僕自身ではなく僕の魔力が気に入って、あんなことを言ったのかもしれません」
真紘の言葉に絶句したリンは、飛びながら暴れるように肢体をはちゃめちゃに動かした。
「ああ~ッ‼ そいつ絶対にフェリや! あの子、ボクにも運命だとか相性が最高だとかプロボーズ紛いなことをよう言うとったんよ! 何も変わっとらん! 魔力でしかボクのことも見とらんかった証拠や! があああッ!」
「なるほど。重盛も火属性持ちだけど、僕に気を遣って魔力の遮断の練習をしていたので、上手なんです。だからフェリクスさんも気づかなかったのかも。もし気付いてたら夫婦そろって求婚されてたんでしょうか? なんだかおかしな話ですね」
「のんびりしてる場合とちゃう! ああ、もう頭きた。振ったこと気にしとった時間も返してほしい。懲らしめたる! 事情聴取はそのあとや!」
「指導に暴力を用いるのはまずいですよ。相手がどんなに悪いことをしていても、教育的指導を謳った暴力は地球でも逮捕されてしまいます」
「知らんもん! ボクは三百年前の人間やし、そもそもなんも覚えとらんけど、三百年前はなんでもありやった気がする!」
「そ、そんなぁ……」
鼻息荒く意気込むリンと、リンをどうやって落ち着かせようか悩む真紘。
「リンさん、あと数分で着きますよ」
大きな駅が見えてきた。その手前には小さな建物がポツポツと散らばっている。
目当ての店の前には先客がいた。
近づくと大きな尻尾が地面の雪を撫でているのが見える。
そして金色の点がキラッと光った。
「重盛!」
急降下する真紘は両手を広げて愛しの夫の名を叫んだ。
「へっ、上か⁉ まっ、真紘ちゃああん‼」
重盛はトン、トンと軽やかに建物の屋根に登り、天から真紘が降って来るのを待っている。
真紘は、屋根の上でさらに飛び上る重盛をキャッチする。推測落下地点よりも早く、隙間が無くなるくらい痛いほどに抱きしめ合うと、くるくると回って、最後は真紘の魔法でふわっと地面に着地した。
「真紘ちゃん‼」
「ただいま、ダーリン……」
「ひゃあ~! やった~! おかえりハニィっ! 王城で仕事してる方が離れてる時間長い日だってあんのに、今日はなんかすっげー寂しかった。今日帰って来る保証もなかったし、心配した……。本当に良かった……。怪我とかない? ちゃんとご飯食べてた?」
ペタペタと真紘の全身を確かめるように触る重盛は、眉が八の字になっており、迷子の子どもを迎えに来た母親のようであった。
真紘は、重盛の背中に両手を回して、胸に頬を寄せて深く息を吸った。
「勝手に離れてごめんね。どこも痛くないよ、元気です。お昼ご飯はリンさんと食べたよ」
「ん、良かった。それならいいよ。リン先輩と話してみてどうだった?」
「こんなこと言ったら失礼かもしれないけど、一緒に調査しながら街中を探索できたし、色々お話しできて楽しかったよ」
「そっか、俺もアルマと腰を据えて話せて良かった。日が暮れる前にこうして合流できたし、あとは犯人を捕まえるだけだな」
「うん。だけど……」
後ろを振り向くと、真紘に続いて降り立ったリンは、俯いたまま震えていた。
アルマもその姿を見て動けずにいる。
重盛の背中をトントンと叩くと抱擁が緩んだため、真紘はリンの隣に移動した。
「すみません、リンさんのペースに合わせないと、とは思っていたのですが……」
リンとアルマのためにとあれこれ計画を立てていたはずが、重盛を見つけて磁石のように引き寄せられてしまった。
ペコペコと頭を下げると、リンは真紘の頭を撫でた。
「ふっ、くくっ、旦那のこと見つけて真っすぐ向かってったなあ。そこまで一途だと感心するわ。それにええよ、年よりの色恋に巻き込んだのはボクらだし。それに強引に誘ってもらわんと、ボク一人では一生動けんかった気するもん。ぎょうさん考えてくれておおきに。でもまだ一対一で話すんは無理やわ、アルマがカッコよすぎて吐きそう……」
「え、えっと、袋あります!」
「今のはそれくらいヤバいってこと」
「それは失礼しました。話し合いも大事ですが、先ずは事件解決に集中しましょう。容疑が晴れても、フェリクスさんを探すお仕事は残っていますし」
「せやった! 恥ずかしがっとる場合ちゃうよな! フェリを探し出して、人を傷つけるようなことは止めさせないと……」
コクコクと頷くリンは両手を握りしめて気合を入れる。
アルマに聞こえないよう小声で会話しているが、重盛の耳はぴくぴく動いているため、恐らく聞いているはずだ。
手招きすると重盛はトコトコと駆けて来る。
「重盛たちは、どうしてここにたどり着いたの?」
「地道に聞き込みしてたんだけど、白いコートの男が水色の髪してたっつー目撃情報をゲットしたからここに来た」
「なんだか説明を端折りすぎでは? 水色の髪だけでここに来たの?」
「だってあいつ、真紘ちゃんにいきなり告った不届き者じゃん? 不審者と変わんねーし。な、アルマ!」
目を細めて拳をもう片方の手のひらに打ち付ける重盛は、店主に対してやはり相当怒っていたらしい。
店主といっても、偽物である可能性が高く、もうフェリクスと呼んでしまった方が良いだろう。
アルマは少し離れたところで腕を組んで咳払いをした。
「何も髪色だけでここに来たわけではない。目撃された男が、昔、リンによく絡んでいた男に似ていたんだ。あいつと会ったあと、リンはいつも具合が悪そうだった。だから俺もあまり良い印象はなくてな」
「はわ、あわわ……」
「あわわ?」
真紘の服を握りしめるリンは、ときめきで今にも呼吸が止まりそうだ。
「フローラ侯爵襲撃と似た事案がないか、教会に魔力不足で倒れた患者が他にもいないか聞きに行ったところ、火属性の獣人や人間が三十年前から運び込まれるようになったことを知ったんだ。リンも火属性だったから、またフェリクスが何か関係があるのではないかと思って――ああ、フェリクスは知っているか?」
「ええ、過去の事件については宿でリーベ神官から、フェリクスさんについてはリンさんから伺いました。なので、僕たちも概ね同じ情報を得たと思います。ね、リンさん」
ぽうっとアルマを見つめるリンは、完全に惚けていた。
こんなに相思相愛なのに、どうしてこうもすれ違っているのか、見ているこちらがやきもきしてしまう。リンのペースに合わせるべきかと考えていたが、待っている間に千年経ってしまいそうだ。
「リンさん?」
「へ、へひ……。聞いとった……。アルマ、ボクの属性覚えてたの。しかも、体調悪そうだったのも心配してくれて……」
「あらー。アルマから見たリン先輩とはちょっと、てか、大分違うな? 避けてんのも思ってたよりポジティブな理由だわ」
重盛は真紘に耳打ちする。
「ポジティブがネガティブに変換されてしまっているんだ」
「どゆこと?」
真紘は口元に手を添えて、重盛の耳元で囁いた。
「僕たちずっと恋バナしてたんだけど、カッコいいアルマさんに自分じゃ釣り合わないって、リンさんは言うんだ。そんなことないのに……。アルマさんのタイプが可愛い子らしいんだけど、それってどう考えてもリンさんのことだよね? 緊張して猫かぶって接してきたから、本当の自分を受け入れてもらえるか不安なんだって……。でも外野の僕たちがいくら大丈夫と言っても、アルマさん本人の言葉には敵わないだろう?」
「すっげー勢いですれ違ってんじゃん! ちなみに俺は真紘ちゃんが世界一、いや、宇宙一可愛いと思ってるよっ」
「でね、あと一押しだと思うんだけど、アルマさんはどうして本気を出してリンさんを追いかけて来ないのかな?」
「嗚呼、痺れるスルースキル! それなぁ、そうなんだけど、アルマの方の悩みの根っこは結構ヘビーで――あ、見た目の話じゃなくて」
「もう、重盛。真剣なんだから茶化さないの」
真紘が重盛の頬を突くと、重盛は満足そうに目を細める。
「へへ……。俺らからすればリン先輩が照れてるだけに見えるんだけど、アルマからすれば、過去にも色々あったせいで、自分に怯えてるようにて見えるらしいんだよ……。まあ、今の二人に必要なのは、お互いが好きだよ、側にいたいよって本音を打ち明けることじゃね?」
「結局どうしたらいいんだろう。リンさん、アルマさんのために盗まれたジルコンの捜索をしてたんだ。話すきっかけにもなるでしょう? ダメだった時のために、ぬいぐるみもあるよ」
「アルマもリン先輩の容疑を晴らしてやれば、対面で話してくれるかもって。目的も気持ちも一緒なんだよな~。あとはタイミングの問題? つか、そのぬいぐるみは今どこにあんの?」
「まっぽけに」
「えーん、まっぽけ使ってたのに、俺のこと思い出さなかったの? ぬいぐるみ入れる前に通話用の魔石戻しておいてよ~。ずっと待ってたんだぞ。フミちゃんに伝言頼んだのに」
「僕たちリーベ様にしか会ってないんだ。すっかり魔石を戻すのを忘れていたよ、ごめんね」
「真紘ちゃんは悪くない。あの二日酔い神官が伝言忘れたのが問題」
「こら、だめだよ。僕が横着してコートのポケットに入れたのが原因なんだから」
「ああ、これよ、これ……。真紘ちゃんから優しくメッてされるのが俺の生き甲斐なのよ」
重盛は真紘に引っ付きながら首筋に鼻を埋める。すると寒さで赤くなった頬がさらに赤くなった。
「あっ、ちょ、ちょっと、人前でちゅーしないで……! 思い出すも何も、ずっと重盛のことばかり考えてるって、リンさんに揶揄われてばかりで――えっ」
肩を上げて目をぎゅっと瞑ると、最後にコートの襟を立てられて鼻と鼻の先が触れる。
「やっ、ば、ばかぁ……」
風が吹けば口がくっついてしまう距離で、金色の瞳が翡翠の奥を覗き込む。
口元が隠れているため、リンとアルマからは口づけしているように見えるのではないだろう。
重盛以外の三人は妙な緊張感に包まれていた。
「ちょっと充電」
「じゅ、じゅうでん……?」
「うん。だから続きは二人きりになったらしよ」
ふっ、と重盛の喉がなったような低い笑い声が張り詰めた糸を断ち切る。
真紘はふらりとよろめく。
「可愛い顔見せんのは俺にだけね」
片腕が背中に回り、もう片方の手で顎をクイっと上げられる。
ぼっと全身を赤くした真紘は激しく抵抗した。
「こ、このスケベ……! チャラい!」
「何もしてないじゃん、まだ!」
「したよ! ひ、人前でこんな、恥ずかしい……!」
リンのじっとりとした視線が辛い。先ほどまで自分も惚けていたというのに。
アルマに至っては遠くの空を見上げて凪いだ表情を浮かべていた。
「お、おお、お見苦しいものを、大変失礼しました! とにかくお店の中を探してみましょう。リンさんは無理せず僕の後ろに着いてきてください」
「もう突然公開キッスせん?」
「しませんし、まだしてません!」
「まだしてないねェ……」
「しません!」
「なるべく善処しまーす」
善処する気のない返事にぎょっとする真紘は、リンの腕に抱き着くと、重盛から逃げるように店の中に飛び込んでいった。
「はあ……。充電完了した……。さあーて、俺らは店の周りぐるっと見て回ってから行くなー。聞こえるー?」
重盛がドア越しに声をかけると、ドアノブにかかっていたCLAUSEの文字がOKに変化した。
室内で真紘が魔法を使ったらしい。
「わははっ、恥ずかしがっちゃって、超かわいい~」
「重盛、流石にあれは目のやり場に困るぞ。真紘もリンと同じくらい真っ赤になっている。可哀相だろう。それを見せられている俺たちも可哀相だ。まだリンと一言も会話していないというのに。やはり避けられている……」
「すいませんでした。でもアルマだって、リン先輩と同じ空間にいるだけで一歩前進じゃん? 事件解決したら落ち着いて話せるって。さっき真紘ちゃんから聞いたけど、あっちもその気っぽいよ」
「本当か!」
物静かなアルマも、こちらの耳がキーンとするほど大きな声を出せるらしい。それほど待ち望んだ対話ということだ。
「声でかあ! マジのマジよ。つか、俺らだって別に見せつけてるわけじゃねーもん。アルマ、昨日から真紘ちゃんの可愛いとこ見すぎじゃね?」
「それは不可抗力だろう。横暴がすぎるぞ」
「ふはっ、ごめん、ごめん。やっぱ生の真紘ちゃん見たら、こうグワーッてたまんなくなっちゃって。アルマもぐわってなる日が来るよ」
「俺にだって、なる日くらいある」
「は? マジで! で、でもずっと会ってなかったのに、いつ?」
「あの子からの手紙を読んでいる時とかだな……」
「むっ、むっつりにも程があるぜ、兄さんよお! 手紙でムラっとするとか平安時代みてえ。最高だな!」
「むらっとするとは言ってないぞ……」
「しないの?」
「……それより平安時代とはなんだ?」
するともしないとも答えないアルマに、重盛はますます笑みを濃くする。
「時代の最先端をゆく、やんごとなき癖じゃな~ってこと。まあ、地球でも大正ロマンとか昭和レトロとか流行ったしな。昔に倣うのもありか。俺も真紘ちゃんに手紙出そうかな。ラブレター読んでドキドキしてくれっかな?」
「いいんじゃないか……」
やっと砕けたトークが始まったのも束の間、先に店内を見て回っていたリンが血相を変えてアルマの胸に飛び込んできた。
探していた教え子がフローラ侯爵襲撃の犯人の可能性が高いと知ってから、リンは明らかに元気をなくしてしまった。
メッシュのように生えている紫色の小さな羽もへたりと下がったままだ。
「ううん……。ボク、こっちに来てから王都から少し外れた場所にある教会で寝泊まりしてたんよ。昨日は酒場を巡ってフェリを探してたから帰ってないけど、今日は夜になったらあっちに一旦戻る。お願い、それまで調査続けよ。だめ?」
「僕は構いませんよ。というか、あの教会で寝泊まりしていたのはリンさんだったんですね。神木の枝に魔力補填をしに行ったのですが、勝手に入ってしまいました。ごめんなさい」
「いいの、いいの。ボクも無断で使こうてる。むしろ森ん中の無人教会やのに使用感あってビックリしたやろ? ごめんなあ」
「そんな……。教会の周りに足跡がなかったのも、リンさんが屋根から出入りしていたからなんですね。謎が解けました」
「天窓から出入りしててん。なら良かった」
小さく笑ったリンは、真紘の肩に頭を乗せた。
主張の強そうな見た目に反して、繊細で自分に自信がない人だ。年下の後輩に寄りかかるのも勇気が必要だっただろう。
そっと肩を抱くと、リンは嬉しそうに笑った。
「人に寄りかかったの久しぶりやわ」
「以前はアルマさんに? 久しぶりなのに、低い位置にある肩ですみません」
「ぶっは! 三十センチ以上身長差あるのにアルマの肩に頭乗せられるわけないやんか! そうじゃなくても難しいかもしれんけど……。昔は寄りかかるより、アルマの脇に手入れて、こうガバっと持ち上げてな、空の散歩したことのが多かったかもしれん」
ケタケタと笑うリンはピョンピョン跳ねて真紘に抱き着く。
身長差はあるものの、体重は真紘の方が軽いため、衝撃に耐えられずふらついた。
「元気が出たみたいで良かったです。お散歩デートいいですね。またきっとできますよ。それに抱えて飛んでしまえばアルマさんは逃げられませんし、こっちのペースじゃないですか」
「きゃははっ! マヒロくんたまに発想が物騒! まっ、それだけ力があればパワーゴリ押しタイプになってもしゃーないか」
「すみません。隣にいる人が何をしても喜ぶもので、この世界に来てからというもの、少しばかり気が大きくなって。力頼りになるのも過信しすぎるのも良くありませんね」
「あ~また旦那の話や! 次、惚気たら刺すで!」
「はっ! 名前は出していないので、セーフではないでしょうか……?」
「ギリアウトやん。ああ、ええなァ~ええなァ~」
「いいですよ? 好きな人を大好きだと言えることは、幸せなことです」
「開き直りよった!」
うな垂れるリンを引きずるようにして進むと公園が見えてきたため、そこで休憩することにした。
ベンチは雪が降ろしてあって、周りにいくつもの足跡が残っている。午前中に誰かが座ったのだろう。
真紘とリンはそこに並んで腰かける。
目の前には水の出ていない丸い噴水。五十センチほど深さのある水受けの中は、小さなスケートリンクのようになっていた。
「あ、来た! こっちや~!」
リンが空に向かって呼び掛けると、白い綿毛のような小さな鳥がベンチの周りに集まってきた。
そして一斉にピッピッピッピッと鳴き始める。
「えっと、ご友人ですか……?」
「ご友人? 友達っちゃ友達だけど、仲間の方が近いなあ。鳥同士の助け合いコミュニティーみたいなもんや。向こうの山にでっかい鷲がおるよとか、王城の中に実がついてる木があったよーとか、情報交換してん」
「リンさんは小鳥さんの話していることも分かるんですね!」
「百パー理解してるわけちゃうけど、鳥相手ならわかる」
「それは素敵ですね」
「せやろ?」
ピューっと口笛を吹いてリンは小鳥達と会話を始める。
重盛も森の中で遭遇した狐に、何やら一言、二言、話しかけていた。何か会話をしていたのかもしれない。
あれもアルマと出会う少し前の記憶だ。
何を話していたのか聞いてみれば良かった。野生のキノコの見分け方には自信がないと言っていたので、食べられる種類でも聞いていたのだろうか。
見つめ合う一人と一匹、互いに尻尾がふりふりと揺れていて、とても可愛らしかったことはよく覚えている。
真紘が物思いにふけっていると、白い小鳥達がバサバサッと飛び立っていった。
「わあっ! お話しはもう大丈夫なんですか?」
「うん。あの子らに、今日の朝、フェリを西門近くで見かけてないか聞いてみたんや……」
随分ストレートな質問をしたものだと真紘は表情に出さず驚く。てっきりモア・センデルあたりで不審者を見かけなかったとか、そういう質問をしているのかと思っていた。
「まだ彼が犯人かは……」
「ボクもさっきまで信じとった。信じとったからこそ、違うっちゅー証拠がほしかった。せやけど、確信に変わってしもた。ボクが王城の周りをうろついとった理由は、そもそも街の西側でフェリを目撃したっちゅー鳥たちからのタレコミやねん。だからモア・センデルの屋根の上も何回か飛んでた。そんで、ついに有力な目撃証言が出て来た」
「それが今の小鳥さんたちの……」
ベンチの背もたれに体を預けて、リンは空を見上げる。
真紘も同じ姿勢を取ると、雲一つない澄みきった冬の青で視界がいっぱいになった。
「王城の西門付近に実がなった木が残っとってな、そこで番の小鳥ちゃんたちが朝ごはん食べてたらしいねん。もう老夫婦で、陽が昇るよりちょっと早く朝食に出発するんやって」
「随分可愛らしいご夫婦ですね」
「なあ~。食欲旺盛なのはええことや。そんでな、西門の屋根に並んで実を食べてた時に、モア・センデルの最上階から人が飛び出してきたらしいねん。初めは大きな鳥かと思うたけど、よお見たら白いコートを着た水色髪した若い男だった言うんよ」
「水色の髪?」
「フェリもこっちの世界に来てから毛色が変わったんや。マヒロくんとはまた違った色白さで、狼の獣人らしいんやけど、耳や尻尾は生えてなくて――」
「牙だけ生えてる……」
「そう! マヒロくん、知っとったん? レヴィ様あたりが王城の書庫にでも記録残してたんやろか?」
センデルの駅前での出会いの記憶はまだ鮮明で、すぐさま点と点が繋がり線になった。
「フェリクスさんって、目元が涼しげで髪は肩について少しはねるくらい。わりと賑やかな方ですか?」
「なんや会ったことあるみたいな言い方するなあ。髪の毛はいつも長めやったけど、三十年も前の記憶や。今はわからん。体はあんまり強なかったけど、テンションはいつも高かったなあ。なんの記録で見たん?」
「記録ではなく僕自身の記憶です。昨日、リンさんのおっしゃるフェリクスさんによく似た方と出会いました。その方は、駅前のセンデル名物の包み握り屋さんで、そこのご主人だと。あれ? でもどうして僕は、彼から狼の獣人だと聞く前に、狼だと思ったんだろう……。彼には牙しか生えていなかったのに……」
頬に当たる風は痛いほど冷たいというのに、嫌な汗が背中を伝う。
リンは血相を変えて真紘の腕を引いて空に舞い上がった。
「り、リンさん⁉」
「あかん、あかんよ! ボクもこっちについてすぐにその店に寄った。店名は【狼と列車】で、そこのマスターは尻尾の大きな狼の……おじいちゃんなんよ……ッ!」
「そんなっ! だけどあの店には若い店主だけで、他の魔力の気配も、重盛の嗅覚にも何も反応がなくて……」
「と、とにかく確かめに行くで!」
猛スピードで進むリンは、今にも泣きそうな顔をしている。
これ以上王都の上空を飛行して目立ちたくないなど言っている場合ではない。
真紘も自身の鈍感さを悔いるばかりだ。
今思えば、あの店に入ってから違和感は数え切れないほどあった。
店主なのにペンやメモの場所が分からず探していたこと。書いてくれた地図が真逆だったこともそうだ。駅前の店主ならば、道案内なんて何度もしているはずだし、間違えるわけがない。
駅前で待ち構えていたのは、魔力の高い貴族が一度に大勢来る機会など今までなかったため、様子見といったところだろう。
救世主が代替わりしていたと知り驚いていたのは、人とあまり交流をせず引き籠っていたせいかもしれない。クルーズトレインの到着セレモニーの周知は街中にポスターが貼ってあったため、生活備品を買いに人里に降りて来た時にでも目にしたのだろう。
だが、突然のプロボーズは、一体、何がきっかけで――。
「まっぽけだ……」
「ぽっけがどうしたん? 何か取り出すにしても、空の上では止めとき。落っことすで」
「そうではなくて、僕は普段から魔力を遮断しているんです。獣人以上にぴったり魔力を止めているので、一切魔力を感じないと思います。でもこのまっぽけは、空間魔法を応用しているので、出し入れする際に魔力が必要になります。誰しも魔法を使う瞬間は魔力がどうしても零れる」
「獣人は魔力を全身に巡らせてなんぼやから、自然体な人が多いし、魔力の多い貴族でも完全に遮断するのは無理やで。そんな神業、できんのマヒロくんくらいとちゃうん?」
「魔力の完全遮断ができる人物は、僕の他にも、もう一人います。怪盗であることが残念なんですが……。そんなレアケースだからこそおかしいんです。僕が会ったフェリクスさんからは、魔力を一切感じられなかった。獣人の身体的特徴が出ていない分、魔力も少ないのかもしれないと思っていましたが、リンさんがおっしゃったように獣人は魔力を内側で循環させているため、自然体な人が多い。どうしたって魔力は零れるものです」
「待って、頭が追いつかん! 」
「つまり、その理論から考えられるのは、フェリクスさんは、そもそも狼の獣人ではないかもしれない、ということです」
「はあ⁉ で、でも本人はそう言って……」
「自己申告でしょう? 小鳥さんたちは空を飛ぶフェリクスさんを目撃しています。どんなに跳躍力があっても足跡は残るし、狼の獣人には無理です。窓枠に残っていた僅かな残滓から、遮断していた魔法を使ったと言われた方が納得できます」
「確かに狼に空を飛ぶんは無理や……。でもボクは、フェリが飛んだ姿を七十年間一度も見たことがない! ずっとボクが抱えて飛んで……。いや、でも飛んだあといつも体が重くなってた。アルマより軽いはずなのに……」
目を背けていた現実がリンを襲う。
真紘だって教え子であるマルクスの息子、ルノが犯罪に関わっていると知れば、落ち着いていられないだろう。数ヶ月一緒にいただけでも、心が痛むというのに、リンはフェリクスと七十年も共にいたのだ。失踪してからずっと探していた教え子が、自身の体調不良の原因であり、フローラ侯爵襲撃を含め、過去三十年に渡る犯罪の犯人かもしれないなんて、相当なショックだろう。
「根拠はもう一つあります。僕、フェリクスさんにまっぽけから取り出したメモ帳を手渡したんです。その時一瞬だけ手元が引きずられた気がしたんですけど、もしかしたら魔力を吸われていたのかも……」
「な、なんやて⁉」
「そのあとすぐに告白されて、プロボーズされました。重盛が怒ってすぐに退店することになったんですけど、フェリクスさんは、僕自身ではなく僕の魔力が気に入って、あんなことを言ったのかもしれません」
真紘の言葉に絶句したリンは、飛びながら暴れるように肢体をはちゃめちゃに動かした。
「ああ~ッ‼ そいつ絶対にフェリや! あの子、ボクにも運命だとか相性が最高だとかプロボーズ紛いなことをよう言うとったんよ! 何も変わっとらん! 魔力でしかボクのことも見とらんかった証拠や! があああッ!」
「なるほど。重盛も火属性持ちだけど、僕に気を遣って魔力の遮断の練習をしていたので、上手なんです。だからフェリクスさんも気づかなかったのかも。もし気付いてたら夫婦そろって求婚されてたんでしょうか? なんだかおかしな話ですね」
「のんびりしてる場合とちゃう! ああ、もう頭きた。振ったこと気にしとった時間も返してほしい。懲らしめたる! 事情聴取はそのあとや!」
「指導に暴力を用いるのはまずいですよ。相手がどんなに悪いことをしていても、教育的指導を謳った暴力は地球でも逮捕されてしまいます」
「知らんもん! ボクは三百年前の人間やし、そもそもなんも覚えとらんけど、三百年前はなんでもありやった気がする!」
「そ、そんなぁ……」
鼻息荒く意気込むリンと、リンをどうやって落ち着かせようか悩む真紘。
「リンさん、あと数分で着きますよ」
大きな駅が見えてきた。その手前には小さな建物がポツポツと散らばっている。
目当ての店の前には先客がいた。
近づくと大きな尻尾が地面の雪を撫でているのが見える。
そして金色の点がキラッと光った。
「重盛!」
急降下する真紘は両手を広げて愛しの夫の名を叫んだ。
「へっ、上か⁉ まっ、真紘ちゃああん‼」
重盛はトン、トンと軽やかに建物の屋根に登り、天から真紘が降って来るのを待っている。
真紘は、屋根の上でさらに飛び上る重盛をキャッチする。推測落下地点よりも早く、隙間が無くなるくらい痛いほどに抱きしめ合うと、くるくると回って、最後は真紘の魔法でふわっと地面に着地した。
「真紘ちゃん‼」
「ただいま、ダーリン……」
「ひゃあ~! やった~! おかえりハニィっ! 王城で仕事してる方が離れてる時間長い日だってあんのに、今日はなんかすっげー寂しかった。今日帰って来る保証もなかったし、心配した……。本当に良かった……。怪我とかない? ちゃんとご飯食べてた?」
ペタペタと真紘の全身を確かめるように触る重盛は、眉が八の字になっており、迷子の子どもを迎えに来た母親のようであった。
真紘は、重盛の背中に両手を回して、胸に頬を寄せて深く息を吸った。
「勝手に離れてごめんね。どこも痛くないよ、元気です。お昼ご飯はリンさんと食べたよ」
「ん、良かった。それならいいよ。リン先輩と話してみてどうだった?」
「こんなこと言ったら失礼かもしれないけど、一緒に調査しながら街中を探索できたし、色々お話しできて楽しかったよ」
「そっか、俺もアルマと腰を据えて話せて良かった。日が暮れる前にこうして合流できたし、あとは犯人を捕まえるだけだな」
「うん。だけど……」
後ろを振り向くと、真紘に続いて降り立ったリンは、俯いたまま震えていた。
アルマもその姿を見て動けずにいる。
重盛の背中をトントンと叩くと抱擁が緩んだため、真紘はリンの隣に移動した。
「すみません、リンさんのペースに合わせないと、とは思っていたのですが……」
リンとアルマのためにとあれこれ計画を立てていたはずが、重盛を見つけて磁石のように引き寄せられてしまった。
ペコペコと頭を下げると、リンは真紘の頭を撫でた。
「ふっ、くくっ、旦那のこと見つけて真っすぐ向かってったなあ。そこまで一途だと感心するわ。それにええよ、年よりの色恋に巻き込んだのはボクらだし。それに強引に誘ってもらわんと、ボク一人では一生動けんかった気するもん。ぎょうさん考えてくれておおきに。でもまだ一対一で話すんは無理やわ、アルマがカッコよすぎて吐きそう……」
「え、えっと、袋あります!」
「今のはそれくらいヤバいってこと」
「それは失礼しました。話し合いも大事ですが、先ずは事件解決に集中しましょう。容疑が晴れても、フェリクスさんを探すお仕事は残っていますし」
「せやった! 恥ずかしがっとる場合ちゃうよな! フェリを探し出して、人を傷つけるようなことは止めさせないと……」
コクコクと頷くリンは両手を握りしめて気合を入れる。
アルマに聞こえないよう小声で会話しているが、重盛の耳はぴくぴく動いているため、恐らく聞いているはずだ。
手招きすると重盛はトコトコと駆けて来る。
「重盛たちは、どうしてここにたどり着いたの?」
「地道に聞き込みしてたんだけど、白いコートの男が水色の髪してたっつー目撃情報をゲットしたからここに来た」
「なんだか説明を端折りすぎでは? 水色の髪だけでここに来たの?」
「だってあいつ、真紘ちゃんにいきなり告った不届き者じゃん? 不審者と変わんねーし。な、アルマ!」
目を細めて拳をもう片方の手のひらに打ち付ける重盛は、店主に対してやはり相当怒っていたらしい。
店主といっても、偽物である可能性が高く、もうフェリクスと呼んでしまった方が良いだろう。
アルマは少し離れたところで腕を組んで咳払いをした。
「何も髪色だけでここに来たわけではない。目撃された男が、昔、リンによく絡んでいた男に似ていたんだ。あいつと会ったあと、リンはいつも具合が悪そうだった。だから俺もあまり良い印象はなくてな」
「はわ、あわわ……」
「あわわ?」
真紘の服を握りしめるリンは、ときめきで今にも呼吸が止まりそうだ。
「フローラ侯爵襲撃と似た事案がないか、教会に魔力不足で倒れた患者が他にもいないか聞きに行ったところ、火属性の獣人や人間が三十年前から運び込まれるようになったことを知ったんだ。リンも火属性だったから、またフェリクスが何か関係があるのではないかと思って――ああ、フェリクスは知っているか?」
「ええ、過去の事件については宿でリーベ神官から、フェリクスさんについてはリンさんから伺いました。なので、僕たちも概ね同じ情報を得たと思います。ね、リンさん」
ぽうっとアルマを見つめるリンは、完全に惚けていた。
こんなに相思相愛なのに、どうしてこうもすれ違っているのか、見ているこちらがやきもきしてしまう。リンのペースに合わせるべきかと考えていたが、待っている間に千年経ってしまいそうだ。
「リンさん?」
「へ、へひ……。聞いとった……。アルマ、ボクの属性覚えてたの。しかも、体調悪そうだったのも心配してくれて……」
「あらー。アルマから見たリン先輩とはちょっと、てか、大分違うな? 避けてんのも思ってたよりポジティブな理由だわ」
重盛は真紘に耳打ちする。
「ポジティブがネガティブに変換されてしまっているんだ」
「どゆこと?」
真紘は口元に手を添えて、重盛の耳元で囁いた。
「僕たちずっと恋バナしてたんだけど、カッコいいアルマさんに自分じゃ釣り合わないって、リンさんは言うんだ。そんなことないのに……。アルマさんのタイプが可愛い子らしいんだけど、それってどう考えてもリンさんのことだよね? 緊張して猫かぶって接してきたから、本当の自分を受け入れてもらえるか不安なんだって……。でも外野の僕たちがいくら大丈夫と言っても、アルマさん本人の言葉には敵わないだろう?」
「すっげー勢いですれ違ってんじゃん! ちなみに俺は真紘ちゃんが世界一、いや、宇宙一可愛いと思ってるよっ」
「でね、あと一押しだと思うんだけど、アルマさんはどうして本気を出してリンさんを追いかけて来ないのかな?」
「嗚呼、痺れるスルースキル! それなぁ、そうなんだけど、アルマの方の悩みの根っこは結構ヘビーで――あ、見た目の話じゃなくて」
「もう、重盛。真剣なんだから茶化さないの」
真紘が重盛の頬を突くと、重盛は満足そうに目を細める。
「へへ……。俺らからすればリン先輩が照れてるだけに見えるんだけど、アルマからすれば、過去にも色々あったせいで、自分に怯えてるようにて見えるらしいんだよ……。まあ、今の二人に必要なのは、お互いが好きだよ、側にいたいよって本音を打ち明けることじゃね?」
「結局どうしたらいいんだろう。リンさん、アルマさんのために盗まれたジルコンの捜索をしてたんだ。話すきっかけにもなるでしょう? ダメだった時のために、ぬいぐるみもあるよ」
「アルマもリン先輩の容疑を晴らしてやれば、対面で話してくれるかもって。目的も気持ちも一緒なんだよな~。あとはタイミングの問題? つか、そのぬいぐるみは今どこにあんの?」
「まっぽけに」
「えーん、まっぽけ使ってたのに、俺のこと思い出さなかったの? ぬいぐるみ入れる前に通話用の魔石戻しておいてよ~。ずっと待ってたんだぞ。フミちゃんに伝言頼んだのに」
「僕たちリーベ様にしか会ってないんだ。すっかり魔石を戻すのを忘れていたよ、ごめんね」
「真紘ちゃんは悪くない。あの二日酔い神官が伝言忘れたのが問題」
「こら、だめだよ。僕が横着してコートのポケットに入れたのが原因なんだから」
「ああ、これよ、これ……。真紘ちゃんから優しくメッてされるのが俺の生き甲斐なのよ」
重盛は真紘に引っ付きながら首筋に鼻を埋める。すると寒さで赤くなった頬がさらに赤くなった。
「あっ、ちょ、ちょっと、人前でちゅーしないで……! 思い出すも何も、ずっと重盛のことばかり考えてるって、リンさんに揶揄われてばかりで――えっ」
肩を上げて目をぎゅっと瞑ると、最後にコートの襟を立てられて鼻と鼻の先が触れる。
「やっ、ば、ばかぁ……」
風が吹けば口がくっついてしまう距離で、金色の瞳が翡翠の奥を覗き込む。
口元が隠れているため、リンとアルマからは口づけしているように見えるのではないだろう。
重盛以外の三人は妙な緊張感に包まれていた。
「ちょっと充電」
「じゅ、じゅうでん……?」
「うん。だから続きは二人きりになったらしよ」
ふっ、と重盛の喉がなったような低い笑い声が張り詰めた糸を断ち切る。
真紘はふらりとよろめく。
「可愛い顔見せんのは俺にだけね」
片腕が背中に回り、もう片方の手で顎をクイっと上げられる。
ぼっと全身を赤くした真紘は激しく抵抗した。
「こ、このスケベ……! チャラい!」
「何もしてないじゃん、まだ!」
「したよ! ひ、人前でこんな、恥ずかしい……!」
リンのじっとりとした視線が辛い。先ほどまで自分も惚けていたというのに。
アルマに至っては遠くの空を見上げて凪いだ表情を浮かべていた。
「お、おお、お見苦しいものを、大変失礼しました! とにかくお店の中を探してみましょう。リンさんは無理せず僕の後ろに着いてきてください」
「もう突然公開キッスせん?」
「しませんし、まだしてません!」
「まだしてないねェ……」
「しません!」
「なるべく善処しまーす」
善処する気のない返事にぎょっとする真紘は、リンの腕に抱き着くと、重盛から逃げるように店の中に飛び込んでいった。
「はあ……。充電完了した……。さあーて、俺らは店の周りぐるっと見て回ってから行くなー。聞こえるー?」
重盛がドア越しに声をかけると、ドアノブにかかっていたCLAUSEの文字がOKに変化した。
室内で真紘が魔法を使ったらしい。
「わははっ、恥ずかしがっちゃって、超かわいい~」
「重盛、流石にあれは目のやり場に困るぞ。真紘もリンと同じくらい真っ赤になっている。可哀相だろう。それを見せられている俺たちも可哀相だ。まだリンと一言も会話していないというのに。やはり避けられている……」
「すいませんでした。でもアルマだって、リン先輩と同じ空間にいるだけで一歩前進じゃん? 事件解決したら落ち着いて話せるって。さっき真紘ちゃんから聞いたけど、あっちもその気っぽいよ」
「本当か!」
物静かなアルマも、こちらの耳がキーンとするほど大きな声を出せるらしい。それほど待ち望んだ対話ということだ。
「声でかあ! マジのマジよ。つか、俺らだって別に見せつけてるわけじゃねーもん。アルマ、昨日から真紘ちゃんの可愛いとこ見すぎじゃね?」
「それは不可抗力だろう。横暴がすぎるぞ」
「ふはっ、ごめん、ごめん。やっぱ生の真紘ちゃん見たら、こうグワーッてたまんなくなっちゃって。アルマもぐわってなる日が来るよ」
「俺にだって、なる日くらいある」
「は? マジで! で、でもずっと会ってなかったのに、いつ?」
「あの子からの手紙を読んでいる時とかだな……」
「むっ、むっつりにも程があるぜ、兄さんよお! 手紙でムラっとするとか平安時代みてえ。最高だな!」
「むらっとするとは言ってないぞ……」
「しないの?」
「……それより平安時代とはなんだ?」
するともしないとも答えないアルマに、重盛はますます笑みを濃くする。
「時代の最先端をゆく、やんごとなき癖じゃな~ってこと。まあ、地球でも大正ロマンとか昭和レトロとか流行ったしな。昔に倣うのもありか。俺も真紘ちゃんに手紙出そうかな。ラブレター読んでドキドキしてくれっかな?」
「いいんじゃないか……」
やっと砕けたトークが始まったのも束の間、先に店内を見て回っていたリンが血相を変えてアルマの胸に飛び込んできた。
39
あなたにおすすめの小説

公爵家の末っ子に転生しました〜出来損ないなので潔く退場しようとしたらうっかり溺愛されてしまった件について〜
上総啓
BL
公爵家の末っ子に転生したシルビオ。
体が弱く生まれて早々ぶっ倒れ、家族は見事に過保護ルートへと突き進んでしまった。
両親はめちゃくちゃ溺愛してくるし、超強い兄様はブラコンに育ち弟絶対守るマンに……。
せっかくファンタジーの世界に転生したんだから魔法も使えたり?と思ったら、我が家に代々伝わる上位氷魔法が俺にだけ使えない?
しかも俺に使える魔法は氷魔法じゃなく『神聖魔法』?というか『神聖魔法』を操れるのは神に選ばれた愛し子だけ……?
どうせ余命幾ばくもない出来損ないなら仕方ない、お荷物の僕はさっさと今世からも退場しよう……と思ってたのに?
偶然騎士たちを神聖魔法で救って、何故か天使と呼ばれて崇められたり。終いには帝国最強の狂血皇子に溺愛されて囲われちゃったり……いやいやちょっと待て。魔王様、主神様、まさかアンタらも?
……ってあれ、なんかめちゃくちゃ囲われてない??
―――
病弱ならどうせすぐ死ぬかー。ならちょっとばかし遊んでもいいよね?と自由にやってたら無駄に最強な奴らに溺愛されちゃってた受けの話。
※別名義で連載していた作品になります。
(名義を統合しこちらに移動することになりました)

異世界で8歳児になった僕は半獣さん達と仲良くスローライフを目ざします
み馬下諒
BL
志望校に合格した春、桜の樹の下で意識を失った主人公・斗馬 亮介(とうま りょうすけ)は、気がついたとき、異世界で8歳児の姿にもどっていた。
わけもわからず放心していると、いきなり巨大な黒蛇に襲われるが、水の精霊〈ミュオン・リヒテル・リノアース〉と、半獣属の大熊〈ハイロ〉があらわれて……!?
これは、異世界へ転移した8歳児が、しゃべる動物たちとスローライフ?を目ざす、ファンタジーBLです。
おとなサイド(半獣×精霊)のカプありにつき、R15にしておきました。
※ 造語、出産描写あり。前置き長め。第21話に登場人物紹介を載せました。
★お試し読みは第1部(第22〜27話あたり)がオススメです。物語の傾向がわかりやすいかと思います★
★第11回BL小説大賞エントリー作品★最終結果2773作品中/414位★応援ありがとうございました★

VRMMOで追放された支援職、生贄にされた先で魔王様に拾われ世界一溺愛される
水凪しおん
BL
勇者パーティーに尽くしながらも、生贄として裏切られた支援職の少年ユキ。
絶望の底で出会ったのは、孤独な魔王アシュトだった。
帰る場所を失ったユキが見つけたのは、規格外の生産スキル【慈愛の手】と、魔王からの想定外な溺愛!?
「私の至宝に、指一本触れるな」
荒れた魔王領を豊かな楽園へと変えていく、心優しい青年の成り上がりと、永い孤独を生きた魔王の凍てついた心を溶かす純愛の物語。
裏切り者たちへの華麗なる復讐劇が、今、始まる。


裏乙女ゲー?モブですよね? いいえ主人公です。
みーやん
BL
何日の時をこのソファーと過ごしただろう。
愛してやまない我が妹に頼まれた乙女ゲーの攻略は終わりを迎えようとしていた。
「私の青春学園生活⭐︎星蒼山学園」というこのタイトルの通り、女の子の主人公が学園生活を送りながら攻略対象に擦り寄り青春という名の恋愛を繰り広げるゲームだ。ちなみに女子生徒は全校生徒約900人のうち主人公1人というハーレム設定である。
あと1ヶ月後に30歳の誕生日を迎える俺には厳しすぎるゲームではあるが可愛い妹の為、精神と睡眠を削りながらやっとの思いで最後の攻略対象を攻略し見事クリアした。
最後のエンドロールまで見た後に
「裏乙女ゲームを開始しますか?」
という文字が出てきたと思ったら目の視界がだんだんと狭まってくる感覚に襲われた。
あ。俺3日寝てなかったんだ…
そんなことにふと気がついた時には視界は完全に奪われていた。
次に目が覚めると目の前には見覚えのあるゲームならではのウィンドウ。
「星蒼山学園へようこそ!攻略対象を攻略し青春を掴み取ろう!」
何度見たかわからないほど見たこの文字。そして気づく現実味のある体感。そこは3日徹夜してクリアしたゲームの世界でした。
え?意味わかんないけどとりあえず俺はもちろんモブだよね?
これはモブだと勘違いしている男が実は主人公だと気付かないまま学園生活を送る話です。

2度目の異世界移転。あの時の少年がいい歳になっていて殺気立って睨んでくるんだけど。
ありま氷炎
BL
高校一年の時、道路陥没の事故に巻き込まれ、三日間記憶がない。
異世界転移した記憶はあるんだけど、夢だと思っていた。
二年後、どうやら異世界転移してしまったらしい。
しかもこれは二度目で、あれは夢ではなかったようだった。
再会した少年はすっかりいい歳になっていて、殺気立って睨んでくるんだけど。
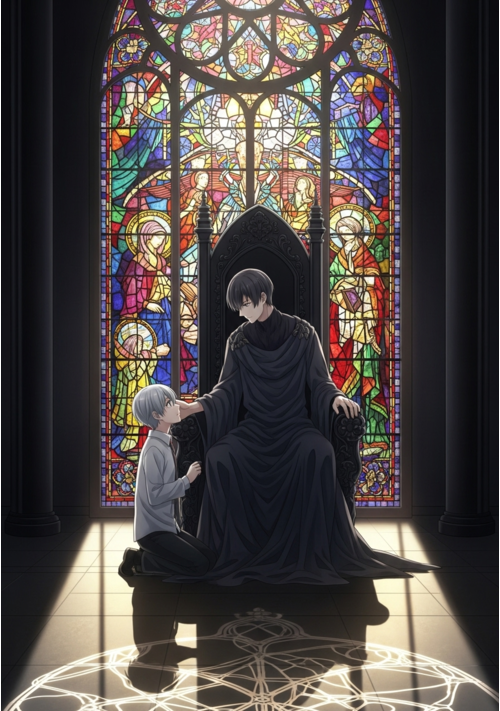
過労死で異世界転生したら、勇者の魂を持つ僕が魔王の城で目覚めた。なぜか「魂の半身」と呼ばれ異常なまでに溺愛されてる件
水凪しおん
BL
ブラック企業で過労死した俺、雪斗(ユキト)が次に目覚めたのは、なんと異世界の魔王の城だった。
赤ん坊の姿で転生した俺は、自分がこの世界を滅ぼす魔王を討つための「勇者の魂」を持つと知る。
目の前にいるのは、冷酷非情と噂の魔王ゼノン。
「ああ、終わった……食べられるんだ」
絶望する俺を前に、しかし魔王はうっとりと目を細め、こう囁いた。
「ようやく会えた、我が魂の半身よ」
それから始まったのは、地獄のような日々――ではなく、至れり尽くせりの甘やかし生活!?
最高級の食事、ふわふわの寝具、傅役(もりやく)までつけられ、魔王自らが甲斐甲斐しくお菓子を食べさせてくる始末。
この溺愛は、俺を油断させて力を奪うための罠に違いない!
そう信じて疑わない俺の勘違いをよそに、魔王の独占欲と愛情はどんどんエスカレートしていき……。
永い孤独を生きてきた最強魔王と、自己肯定感ゼロの元社畜勇者。
敵対するはずの運命が交わる時、世界を揺るがす壮大な愛の物語が始まる。

【完結】テルの異世界転換紀?!転がり落ちたら世界が変わっていた。
カヨワイさつき
BL
小学生の頃両親が蒸発、その後親戚中をたらいまわしにされ住むところも失った田辺輝(たなべ てる)は毎日切り詰めた生活をしていた。複数のバイトしていたある日、コスプレ?した男と出会った。
異世界ファンタジー、そしてちょっぴりすれ違いの恋愛。
ドワーフ族に助けられ家族として過ごす"テル"。本当の両親は……。
そして、コスプレと思っていた男性は……。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















