15 / 28
第十三話・猫の手、お貸しします
しおりを挟む島から帰ったマリンには、ハンターギルドから無期限の休養が言い渡された。
犯人に無理やり接種させられたとはいえ薬物の中毒に陥っていたから、それを克服するまでという条件付きで。
そしてシトリンもまた、マリンの介護という名目でパールからはお休みをいただいている。そして自宅でのマリン、パンツとブラウスというラフというか乙女にあるまじき恰好で室内を徘徊しながら、
「薬……薬、どこに置いたんじゃっけ」
「マリンさん⁉ まさか薬を持って帰ったんですか‼」
驚愕の表情を浮かべて、シトリンが険しい表情でマリンに詰め寄った。
「違う違う! ほら、注射は胸にされたじゃろ? その注射痕に塗る薬のことじゃけん」
「な、な~んだ……」
ヘナヘナと座り込んでしまうシトリン。もちろんシトリンはマリンが定期的にその薬を塗っていることは知っていたが、ナーバスになっているせいでついつい過敏に反応してしまったのだ。
「それならここの引き出しですよ。私が塗ってあげますから、ボタン外してください」
「あ、うん。ごめんね、迷惑ばかりかけて」
しょんぼりと項垂れるマリンに、シトリンは優しく微笑みかける。
「マリンさん、気になさらないでください」
そしてボタンを外そうとするマリンなのだが……。
「あぅ……ボタンもお願いしていいかな?」
「そんなの、いつでも『命令』してくださいってば‼」
実はかの事件で海中に眼鏡を落として以来、マリンは眼鏡を補充していない。スペアが家のどこかにあるはずなのだけど、薬物中毒で朦朧としているために思い出せないでいるのだ。
そして眼鏡がない状態だと、ボタンすら上手くはめられなくて。
「(ゴクリ……)」
マリンの裸は、一緒にお風呂に入るときに何度も見慣れているシトリンだったが……自分がマリンのブラウスのボタンを外すという倒錯的なシチュエーションに、興奮を隠し切れないでいた。
「シトリン、鼻息荒いけ!」
マリンが苦笑いを浮かべてツッコむ。
「あ、はい。すいません」
そしてシトリンの前に顕わになる、マリンの形のいい乳房。だがその片方は、無数の注射痕が黒い点となってその白い乳房に浮き上がっていた。
(痛々しいな……)
太い針が使われたこと、乱暴に注射されたことにくわえて薬物による膿の痕で、なかなか傷は綺麗にならなかった。
「あの、マリンさん」
「何?」
「丹念に塗っておきたいので、乳首引っ張っていいでしょうか?」
「……」
シトリンの真意がわからずに、しばし逡巡するマリン。
(親切で塗ってくれようっちゅうのに、疑ったらダメじゃね)
と思い直して、無言で頷く。
「では」
シトリンは右手の肉球に軟膏を抉り取ると、左手……こちらは人間と同じ手なので、人差し指と親指でマリンの乳首をつまんで軽く引っ張る。
「冷たくないですか?」
「ううん、むしろ暖かくていい気持ちじゃけん」
猫獣人の平熱は四十度近い。マリンはウットリしながら、シトリンにされるがままに身を委ねる。
そしてシトリンがマリンの至近距離にいるとあって、高身長のマリンからはシトリンのデコルテから下、服に隠されている部分が目に入って……。
(……まさか?)
自分は薬物の発作の間の記憶が、ほとんどない。軽い発作のときはかろうじて覚えてはいるのだけど。
軟膏を塗り終えたシトリン、マリンのブラウスのボタンを留め始める。
「というかですね、マリンさん? いくら家の中だからって、ブラくらいしてくださいよ」
そして軟膏の蓋を閉めて、それを元あった場所にしまうべく踵を返すシトリン……の手首を、後ろからガシッとマリンが掴む。
「マリンさん?」
「シトリン。これは『命令』じゃけど」
「はっ、はい! なんでしょうか?」
マリンはシトリンに『命令』をしたがらない。いつも『お願い』ばかりだったから、シトリンはちょっと嬉しそうな表情を浮かべるのだけど。
(何かマリンさん、怒ってる?)
そう、マリンは厳しい表情でシトリンを睨むような目つきなのだ。
「シトリン、服全部脱いで」
「⁉」
ついに‼と何かを期待したシトリンだが、顔には出さず。
「全部……素っ裸になれってことですか?」
「そう」
マリンの真意がわからないシトリン、嬉しさ半分戸惑い半分で複雑そうな表情を浮かべるものの……おずおずと一枚ずつマリンの前で服を脱いでいく。
「脱ぎました」
マリンの前で、全裸になるシトリン。両手の肘から先はレッドタビーの被毛に覆われていて、右手だけ猫の手だ。左手は何故か人間態のままで、手首から先は無毛となっている。
ちなみに両脚はどちらも猫の足となっていて、これは獣人によって生まれつき千差万別である。兎獣人のパールもシトリンと同じく肘と膝から先が兎の毛に覆われているが、両手首から先は人間態であった。
まだ十三歳ゆえに、胸の膨らみはささやかではあった。だがその小さくて白い乳房に、手のひらのような形がウッスラと見えて。
「シトリン、その身体の痣……」
マリンはハッと息を呑む。被毛に覆われていない部分のシトリンの白い肌が、ところどころ赤黒く腫れているのだ。
それはまるで、暴行を受けたかのような……あの事件が解決してからは、マリンとシトリンは四六時中一緒にいる。だからシトリンの身体にそれがあるということは、答えは一つしかなかった。
「シトリン、引き続き『命令』じゃけど」
「はい」
険しいながらも、マリンの目は潤んでいた。このシトリンのこの白い肌を、こんな風にした犯人は一人しかいないから。
「薬物の発作が起きているときの私は、シトリンをいじめちょるんじゃろ?」
普通に訊いただけならば、シトリンは絶対に肯定しないだろう。だからこその、奴隷環の呪によって抗うことのできない『命令』という手段を取ったマリンだ。
だが予想に反して、シトリンはキョトンとした表情を浮かべている。
「違いますよ? マリンさんは私をいじめてないです」
「え?」
今度はマリンもポカーンとしてしまった。
「え、でもでもでも‼ シトリンのその身体の痣は何? 薬物で発作になってる私に乱暴されちょるんじゃろ⁉」
「されてないですね」
「えっと……」
ではその痣はどうしたというのだろうか。状況的にどう考えても、マリン以外にその痣の原因の説明が付かないのだ。
「あの、『命令』じゃけど」
「はい」
「私がシトリンを、理不尽に殴ってるんじゃろ? 乱暴しちょるんじゃろ?」
「心当たりがないですね」
毅然として、断言するシトリン。
「???」
マリンはさっぱりわけがわからない。
「この痣は、私が色々とドジっちゃってついた痣なんです。だから心配しないでください」
「そ、そうなん?」
「はい」
納得できないマリンだったが、もしシトリンが嘘をついていたら奴隷勘の呪が発動するはずだ。それが発動していないということは、少なくともシトリンは嘘をついていないことになる。
「そ、そう……あ、もう服着ていいけ」
「はい、わかりました」
そしていそいそと服を着るシトリンを見ながら、マリンはさっぱりわけがわからないといった風である。
ちなみにシトリンは、いずれマリンにそれを問われることを危惧していた。そこでシトリンは自分の中で、薬物発作で暴れるマリンを止める最中に負った怪我は脳内で『ご褒美』に転換していたのだ。
そして痣が付いた本当の理由についても訊かれるだろうから、『マリンさんを上手く止めることのできなかった自分のドジのせい』という涙ぐましい転換を行っていた。
よってシトリンは『マリンが乱暴したのか』という問いに、これはご褒美だから違うと答えることができ、『じゃあその痣は何なのか』という問いにも(マリンを上手く制御できない)自分のドジのせいだと。
つまりシトリンは『嘘を付いていない』のだ。
もっとも、『マリンが叩いた痣なのか』という問いであったらば嘘は付けなかっただろう。そこらへんはちょっと賭けだったから、シトリンは終始ヒヤヒヤしていたのだけど。
そして服を着ながらシトリン、マリンに見えないように小さくガッツポーズをするのであった。
「シトリンにお願いがあるんじゃけど」
「なんでしょう?」
今度は『お願い』か、と嘆息しつつも風呂上りの二人。ともにバスタオルを巻いただけのあられもない姿だ。
マリンは両手を広げて、
「『構築』」
と呟く。マリンの両手が無数の光の粒に包まれて、そこに顕現したのは一本のロープ。そしてそれを左右にビンッと引っ張って強度を確認すると、
「これで、私を縛ってほしいんよ」
「はい⁉」
今度は何を言い出すのかと、シトリンは仰天だ。
「ま、続きはリビングでするけん。まずは服着んさい」
「あ、はい」
そして二人、服を着ていざリビングへ。ローテーブルをはさんで、シトリンが淹れたお茶をいただく。
そして机上にあるのはミルクの小瓶とシュガーポット、二枚のソーサー……とロープ。
(マリンさんを縛るってどういうことだろう?)
ロープをチラチラと見ながら落ち着きがないシトリンと、それを意にも介さず美味しそうにお茶を飲むマリンだ。そして二人がティーカップを置くのがほぼ同時だった。
「シトリン」
「はい」
「さっき一緒にお風呂に入ったとき、じっくりとシトリンの身体をチェックしてみたんじゃけど」
「あ、はい」
頬が火照って、真っ赤に染まるシトリン。恥ずかしそうに両頬を抑える。だがマリンは真剣な表情で、唇の端が少し震えていた。
「何がどうしてシトリンが嘘つけたのか知らんけど、やっぱりその身体の痣は人が乱暴してつけたもんなんよ。よく見れば、それは誤魔化せんけ」
「……」
どうやら、シトリンの作戦は上手くいかなかったようだ。思わず嘆息するシトリンである。
「シトリンをそんな目に遭わせた犯人は、もちろん私なんじゃろ?」
「……その質問は、『命令』ですか?」
マリンもシトリンも、涙目だ。
「……命令は、もうしたくないけ」
「そうですか。では私から答えることは、何もないです」
それはすなわち、肯定を意味した。マリンの握りしめた拳が、震える。
「じゃけん、私を縛り上げてほしいんよ」
「だからそのじゃけんが、どうして縛ることに繋がるんです⁉」
予想外のマリンの言葉に、シトリンはびっくり仰天である。
「もし私がまた発作で暴れだしたら、困るじゃろ?」
「そっ、それは」
「少なくとも私が困るんよ。シトリンに、酷い目に遭わせたくないけ」
マリンの頬を、涙が伝った。
「マリンさん……」
「じゃから発作が出そうになったら事前に言うけん、そのときは私を縛りあげてどっかに……ほうじゃね、外の木にでも吊るしておいてほしいんよ」
「それ何ていうプレイ……」
「プ……⁉」
呆然としてしまったシトリンだったが、
「お断りします」
と毅然と言ってのける。だがマリンも譲れないので、
「『命令』じゃけ」
マリンは低い声で、たった一言そう告げる。
「さっき、命令したくないって……もう、わかりましたよ‼」
シトリンは、泣きそうな顔ながら半ギレだ。
「でも、そうですね。縛っている間に発作が始まったら意味がないですから……上半身をあらかじめ縛っておくのはどうでしょう?」
「上半身だけ?」
「はい。もちろん、日常生活に支障がないように、手足は自由に動かせるように。それなら、いざというときに縛るのは手足だけで済みますし、上半身部分の縄に繋げるだけで簡単に木に吊るせます」
自分、何言ってるんだろうとシトリンは少し混乱していた。
「ほうじゃね。そういう縛り方あるんなら、お願いしていい?」
「命令ですよね?」
「うん」
シトリンは諦め顔で一つ大きなため息を吐くと、
「かしこまりました。今、よろしいでしょうか?」
「ええよ。お願いね」
「はい」
そしてシトリンの手によって、マリンの上半身にだけ縄を張り巡らせていく。胸の中央を通る縄により、ブラウスにマリンの両胸が浮き上がる。
「シトリン……これは……」
「はい、亀甲縛りですね」
シトリンはヤケクソ気味に、縄をマリンの身体に這わせている。
「くれぐれも、来客の際は玄関に出ないように。私が代わりに出ますから」
「言われんでも、こんな格好人に見られたら死ぬけん……」
真っ赤になった顔を、両手で覆って恥ずかしがるマリン。
「できました」
「あ、ありがとう」
今シトリンの前にいるのは、上半身を服の上から亀甲縛りにされたマリンである。
「凄いビジュアルですね!」
「言わんといて、シトリン……」
そしてマリンは両手の指で左右から縄に手をかけると、
「強度はどんなもんじゃろうね」
そう言って、引っ張ってみせた。
『ブチッブチッブチッ‼』
見事に縄は引きちぎられ、その残骸がマリンの足元にポトリと落ちる。
「……」
「……」
それを、能面のような無表情で無言で見つめる二人。
「シトリン」
「はい」
「別の手を考えるけ」
「わかりました」
とりあえず縄を片付けながら、シトリンは思う。
(やっぱマリンさんを縛るよりは、マリンさんに縛られるほうがいいな)
もちろんマリンには、そんなことは絶対に言えないけれども。そしてマリンもまた、
(シトリンに縛られてるときのあのゾクゾクする感覚、なんじゃったんじゃろ?)
マリンは、未知の世界へと続く門を開きつつあった。
「って何考えちょるん、私⁉」
「はい? 何かおっしゃいました」
「ううん、何も」
顔を真っ赤にして、両手をぶんぶん振って否定するマリン。
「ほうじゃ、ソラ姉のところ行こう!」
「ソラ様のところへですか?」
ソラは、この国では知らぬ者のいない大賢者だ。そしてこの大陸随一の魔導士にして呪術師、そして大商会の会頭という側面も持つ。
「何か、私を制御できる魔導具か治療法があるかもしれんけ」
「なるほど、名案ですね!」
ソラのところでメイドとして働いているコユキにも久しぶりに会えるのもあって、シトリンに異論はなかった。
(それにしても、マリンさんを『制御』か)
シトリンの脳内に、よからぬ妄想だけが膨らむ。
「もし私がマリンさんを制御できたら、まず服を脱がして……」
シトリンは、口角から涎をたらさんばかりのひどい顔である。
「……シトリン、声にでちょるけ。そういうのは、できるだけ脳内でね?」
「あ、声に出てました? すっ、すいません‼」
「困った子じゃね」
なんともいえない、複雑そうな表情を浮かべるマリンだった。
そして翌日、ソラの住まう天璣の塔にて――。
「そう、そんな目に遭ったのね」
ソラが、物憂げな表情でマリンに語りかける。
「はい、それで発作の最中……ひどいときは、シトリンに暴力を振るってるようなのです」
「‼」
「ちょっ、マリンさんはそれは違」
少し驚きの表情を浮かべるソラと、慌てて立ち上がってマリンの言葉を否定しようとするシトリン。
「違わんよ」
「違いますってば‼」
「違わんのんよ、シトリン」
寂しそうにそうつぶやくマリンに、イラつきを隠せないシトリン。両手でバンッとテーブルを叩くと、
「あれはご褒美なんですっ‼」
「何の話よ⁉」
ソラは、さっぱりわけがわからない。
「まぁ、そこらへんの齟齬はともかくとして。要は発作で暴れるマリンを止めようとして、シトリンちゃんが怪我しちゃうこともある。そうよね?」
「はい」
これは本当なので、シトリンは無言だ。
「うーん、ここにティア姉がいたら良かったんだけどな。ちょっと前まで滞在してたんだけどね」
この大陸の西端にあるベネトナシュ王国は揺光の塔に住まいを構える、六賢者が一人・ティア師。大陸随一の治癒魔法の使い手で、シトリンも助けられたことがあった。
「まぁティア姉のように治癒というアプローチはできないけど、そうね……マリンあなた、シトリンちゃんの奴隷になってみる?」
「は?」
「え?」
何を言い出すのかとソラを、そして互いに顔を見合わせるマリンとシトリン。ソラは引き出しの中をごそごそと探りながら金色と銀色の腕輪を二つ取り出した。
「コレなんだけど」
見た目は、女性の手首よりちょっと太い感じの継ぎ目のない腕輪だ。だが人間は手首より手のひらのほうが太いから、装着は不可能だろう。
「と思うでしょ?」
ソラは腕輪の中に手を入れようとするが、指が邪魔になって入らない……と思ったら腕輪がスッポリと手首にハマった。今度は逆に、その腕輪をどうやって外すのかが不可解だ。
「リトルスノウ」
「はい」
猫獣人……シトリンと違い、完全に見た目が猫のメイド・リトルスノウが呼び出される。
「あなたはこっちをハメてちょうだい」
「かしこまりました」
そう言って、銀の腕輪のほうをハメるリトルスノウ。
「じゃお願いね」
ソラがそう言いながら、金の腕輪をハメた手を差し出す。銀の腕輪をハメたリトルスノウがソラの腕輪に指をかけると、腕輪がいとも簡単にスポンと外れてしまった。
「えっ……外れた⁉」
「ソラ様、これはどうなってるのですか⁉」
不思議そうな表情のマリンとシトリンを前に、ソラはドヤ顔である。
「これは私が開発した魔導具なの、即席奴隷環といったところね。銀の腕輪をした『ご主人様』が、金の腕輪をした『奴隷』を使役できるってわけ」
「なるほど、それで『私がシトリンの奴隷』ということですか?」
「うん」
思わず顔を見合わせるマリンとシトリンだったが、
「つまり私がご主人様であると同時に、シトリンの奴隷にもなる……と?」
「そういうことね。もしマリンが暴れだしたら、シトリンちゃんから命令するといいわ。『暴れるな』とでも『私に暴力を振るうな』とでもね」
マリンが光明を見出したとばかりに目を輝かせる一方で、シトリンは少し複雑そうだ。
「買います! おいくらでしょうか?」
「あ、ううん。それは貸してあげるわ。リハビリが終わるまで」
「ありがとうございます、ソラ姉。でも借りるに際して無料というわけにも……」
「うん、だから交換条件」
「交換条件?」
訝し気な表情を浮かべるマリンの前に、ソラは一冊のノートを取り出す。
「まぁ平たくいうと、出荷前の動作テストを行ってほしいの。試してみてほしいことが、そのノートに書かれてるから」
「はぁ……拝見します」
マリンはノートを手に取り、ページをめくる。シトリンが横から身を乗り出し、それを覗き込む。
『①お互いが相反する命令を出し合う』
『②本来の奴隷が嫌がる命令をご主人様が出してみる(任意)』
『③本来のご主人様が嫌がる命令を奴隷が出してみる(必須)』
「これは?」
「うん。さすがに主従が定まってる環境でその真逆にするわけだからね。どういう動作をするのか、ちょっと確かめたいの。まぁその臨床試験みたいなものね」
「何か不穏なルビが……かしこまりました。これらをレポートにまとめればいいんですね?」
「うん、お願いね」
そして帰路の途、馬車の中で二人。
「①はわかるんよ。たとえば私がシトリンに何か『命令』したとして、シトリンが『その命令を取り下げろ』と命令したら……」
「命令がバッティングしますね」
「じゃね。どっちの強制力が勝つのか。まぁソラ姉は大陸一のじゅじゅちゅ師じゃけ、そっちのが勝ちそうな気もするけど……」
「何て」
「いや、だから呪術師」
「……はい」
マリンでも噛むことがあるのかと、シトリンは笑いを噛み殺す。上手く誤魔化せなかったことを察して、マリンは苦笑いだ。
「そして②。これはね……想像できんねぇ。逆に訊くけど、シトリンはどんな命令されたらイヤなん?」
「そうですねぇ……」
顎に手をやってしばし考え込むシトリンだったが、
「たとえば奴隷解放する、とか言われたらショックで寝込みそうです」
「何を言って……」
「真剣ですよ」
「……」
シトリンの奴隷解放は、マリンも考えなかったわけじゃない。シトリンには内緒で、奴隷ギルドに問い合わせてみたことがあったのだ。
だが元々違法奴隷だったシトリンなので、『どういう契約』が交わされたのか不明なのだ。シトリンの奴隷環を調査することによってそれが把握できる可能性もあるのだが、下手にいじると呪が発動する可能性もあるとのこと。
とりあえず現状は、『マリンの死』でしか解放できないとのことだった。
「そして③か……」
「これはどういう意味なのでしょうか?」
マリンはしばし考え込んで。
「私が嫌がることを、シトリンがその銀の腕輪の呪力を使って命令する……ということじゃと思うけど」
「私、そんなことしたくありません」
「じゃろうね。でもしてもらうけん」
「……」
何故だかはマリンにはわからなかったが、③は『必須』となっているためだ。
マリンとしては、もうシトリンに薬物の中毒発作で迷惑をかけない暴力を振るわないというのが最優先事項である。この即席奴隷環があればなんとかなりそうなので、交換条件とあらば従うほかなかった。
「でもマリンさん、よくよく考えると変じゃないですか?」
「何が?」
「①は私もわかるんです。でも②と③はそれぞれの気持ちの持ちようといいますか、つまりは奴隷勘の呪により最終的には命令に従ってしまうわけですよね」
「私も、それがわからんのよ。要は相手がどれだけ嫌がるかが、主人のほうの物差し加減というか胸先三寸というかね」
「ですよね」
実は③は、ソラからシトリンへの悪戯を兼ねた『プレゼント』だった。
シトリンによるマリンへの愛情はリミッターを振り切っていることを知っていたので、これを好機と捉えてマリンを好きにしちゃえ……という。
だがそれをマリンに気取られないため、あえて②を紛れ込ませたのだ。
マリンは知らなかった。ソラは『他人で実験するのが大好き』だという、マッドな一面を持つことを。
「ま、②と③は追々考えるとして、家に帰ったらまず①をやってみんとね」
「はい……ちょっと怖いですね」
そう、何が起こるかわからない。そしてそれは、即席魔導環を作ったソラにもわからないのだ。
「まぁそれ故の、交換条件なんじゃろうけど……」
困惑の表情を浮かべるマリンを前に、シトリンは無言である。
(マリンさんが嫌がる命令、か……)
そしてシトリン、ソラの意図することに気づいたのかどうか……その妄想は、果てしなく『あっちの方向』に膨らむばかりであった。
「じゃ、じゃあまずは①からじゃね」
「は、はい!」
思わず生唾を呑む両者。マリンはまず、水の入ったコップを用意して。
「シトリン、『命令』じゃけ。その水を全部飲みんさい」
「マリンさん、『命令』です。その水を全部飲んでください」
腕に、『ご主人様』としての銀の腕輪をはめているシトリン。どちらもがご主人様であり、奴隷でもある状況である。
「……」
「……」
「何も起こらんね?」
「ですね?」
だが次の瞬間、シトリンの首の奴隷環からマリンの手首の奴隷環から。
『キーン!』
という乾いた金属音がしたかと思うと、二人の身体中を耐え難い苦痛と不快感が血流に乗って駆けめぐる。
「うぐっ⁉」
「いぎっ⁉」
そしてそのまま床に転げ回って七転八倒の二人。
(ど、どうすればいいん?)
大量の脂汗を流しながら、なんとかそれでもアイコンタクトでシトリンに縋るマリン。シトリンは『慣れて』いるだけあって、
「マリンさん、命令は『取り消し』ます!」
となんとか声を絞り上げる。途端に、マリンの身体からスゥーッとそれは引いていき。
「そういうことなん‼」
マリンも素早く察して、
「シトリン‼ 命令は取り下げるけん!」
そしてシトリンも、奴隷環の呪から解放される。床に倒れたまま二人、荒い呼吸が止まらない。
「こ、こんなんじゃったんじゃね……」
初めての経験で、マリンは青白い顔で息も絶え絶えだ。
(パパとママは、この痛みに抗えんで……)
まさに人の心を、情け容赦なくへし折る呪いだ。こんなものが、この世に存在することに……マリンは身の毛のよだつ心地がする。
シトリンは『経験者』だけあって、先にマリンより立ち上がっていた。そしてコップの水をもう一杯用意すると、マリンの手を引いて立ち上がるのを手伝う。
「まずは一息入れましょう、マリンさん」
「ほうじゃね……」
二人とも、身体中が汗でびしょ濡れである。マリンもシトリンも、前髪が汗でベターッとおでこに張り付いていた。
「こんな……こんなんじゃったん……」
マリンは元々、奴隷制度に反対ではなかった。奴隷とならなければ生きていけない者、罪から解放されないものもいるのだ。
(じゃからと言って、これは……)
マリンは初めて、自分の信念が揺らぐのを感じた。そして自分もまた、シトリンの細い首に装着されている奴隷環を制御する立場であることに。
(寒気がするね)
コップを持ったまま固まっているマリンに、シトリンは不思議そうな表情を向ける。
「マリンさん?」
「あ、あぁ……うん。ここに、『任意』て書いてあるけん、②は……やらんけ」
「はい」
マリンが、シトリンの嫌がる命令をするという課題。
命令したら、シトリンはイヤでもやるだろう。だが確固たる信念で抗うと奴隷環の呪がシトリンに襲いかかる。
もし本当にシトリンにとってイヤな命令だったら、シトリンは抗ってしまうだろう。それこそシトリンが言っていたように、『奴隷解放』するという命令であっても。
(でも、これで腹は決まったけん)
今のところ、シトリンを奴隷解放する方法は『マリンの死』という手段しかない。だからと言って、シトリンを解放するために自死するなんて当のシトリンが許してくれないし悲しむだろうから。
「なんとか、ほかの方法を見つけんとね」
「はい?」
「あ、ううん。こっちの話……で、次に③じゃけど」
マリンの嫌がる命令を、ご主人様であるシトリンが下すという課題だ。
「うぅ、どうしてもやらなきゃですか?」
「そう言いなさんな。シトリンだって、私の奴隷をやってて色々鬱憤たまっとるじゃろ? それを晴らせばええんよ。ええ機会じゃし」
「それ、本気で言ってるんだったら怒りますよ?」
珍しくシトリン、マリンに対して本気で不快感を投げかける。
「ええよ。私はシトリンの奴隷なんじゃけ」
「マリンさんが私の……愛の奴隷?」
「どっから『愛の』が出てきたん⁉」
ダメだこの子、そんな感じでマリンは嘆息してしまう。だが、シトリンが本当にそうしたいなら……。
「あっ⁉」
「マリンさん?」
胸の奥から染み出すように涌出てくる不快感……これは、中毒の発作が始まる前触れだ。マリンは敏感にそれを感じ取ると、
「シトリン‼ 発作が来る!」
「え、えぇっ⁉」
「早く! 何か早く命令しんさい‼」
このまま発作が始まってしまえば、自分は再び我を忘れて薬を渇望し暴れだすだろう。そしてそれを止めようとするシトリンに、手をあげてしまうのだ。
「どっ、どど、どうすれば⁉」
「なんでもええけ、早く!」
両者ともに、鬼気迫る表情だ。そしてシトリンは逡巡する。
(暴れたらダメって命じる? それとも私に暴力を振るうなって?)
だがそれは発作中のマリンに対し、無理を強いることにならないか。そして発作の過程で薬を渇望する気持ちが勝ったら、命令に抗うことをマリンの身体が選択するだろう。
(そしたら、奴隷環の呪が……)
ふと思い出すのは、島の診療所での女医との会話。
「房中術……」
性的興奮を与え続け、かつ『絶頂』の寸前の状態を長く保つことによって生命力を高める異国の医術。今回のケースでは、中毒症状による発作の不快感を緩和させることができるかもしれないという可能性。
シトリンは性奴隷としての教育を受ける際にそれを学んではいたけれども、『実地』で試したことはまだなかった。
(うーっ、マリンさんの為‼ 罰は甘んじて受けよう!)
そう決意すると、
「マリンさん、命令です! 服を全部脱いで私に身を委ねてください‼」
「シトリン⁉」
発作寸前のマリン、惑いながらもその手は自らの服を脱がすように勝手に動いてしまう。
「あ……なんで私、服を脱ごうと⁉」
これが奴隷環の呪の……本当の恐ろしさかと、マリンは身震いする。そして全裸になったマリンに、
「そこのソファーに横になってください」
シトリンは静かに、そう言い放った。
「何を期待したか知りませんけど、もう終わりましたから」
「シトリン? 誰に何を説明しちょるん?」
タオルで『何か』に濡れた自分の指を拭い終えたシトリン、ソファーでぐったりとしている全裸のマリンにタオルケットをかけてやる。
「あ、ありがと……」
マリンの顔と身体は、上気して真っ赤に染まっていた。目はうつろで口は半開き、口角からは涎が少したれていた。
「失礼します」
そう言ってシトリンは、その涎をハンカチで拭ってやる。
「マリンさんを……私は犯してしまいました」
そしてがっくりと項垂れて、両膝から崩れ落ちて両手をつく。そしてホロホロと涙を落とすと、
「どうぞ、ご存分に処罰を……」
「あ……ん……?」
マリンは、まだ思考が定まらないようだ。
シトリンを引き取る前、一人で『そういうこと』をしたことはあるけれど……それとは比べ物にならないその快感は、マリンにとっては未知の世界だった。
そしてその間だけは、薬の中毒のことも忘れていられた。
「シトリン、これもしかして……」
「はい、島のお医者さんが言ってた『房中術』です。間違えて、最後はイカせてしまったんですが……」
なるほど、とマリンは納得する。そして何故シトリンがそれを身につけてるかという意味にも気づいて。
「シトリンには、つらいことさせたんよね?」
「……いえ」
シトリンは、床に落ちている先ほど自分の手を拭っていたタオルに目をやる。そこには、若干の……マリンの血が滲んでいた。
「シトリンに、食われちゃったけん」
そう言うマリンは笑顔だったが、まだ体力が回復しないのかそれは少し弱々しい。
「もしかして……初めてでしたか?」
決して自分の爪で傷つけたが故の出血じゃないことは、シトリンも確信していた。自分は大変なことをしてしまったのだと、そのとてつもなく大きな罪悪感でシトリンの小さな胸が悲鳴をあげる。
マリンは慈愛のこもった笑顔で上半身を起こすと、シトリンがかけてくれたタオルケットが外れてその胸と腹が顕になった。
「じゃねぇ。あらかじめ言っておくけど、初めてがシトリンで本当に良かったけん」
そう言って、まだ床に四つん這いになってるシトリンの頭を何度もかいぐり回す。
「じゃけどシトリン」
「はい」
仕方なかったとは言え、その判断が正解だったかどうかわからない。何よりご主人様であるマリンの花を、自らの指で破瓜させてしまった。
(どうか、厳罰を‼)
そう思ってギュッと目を瞑るシトリンのおでこに、マリンは優しくキスをすると。
「私は、シトリンをそういう用途で引き取ったわけじゃないけん。もしイヤじゃったらやらんでええけん、そのときは遠慮なく言いんさい」
「イヤなわけ……ないじゃないですか」
シトリンは顔を上げてそのままソファーに半身を起こしているマリンに静かに抱きつくと、そのお腹に顔を埋めて無言で泣き始めた。
「この即席奴隷環、私の治療が治まるまではずっとこのままにするけん。じゃから何か私に命令したいことあったら、好きにしてええからね?」
シトリンはマリンのお腹に顔を埋めたまま、何度も無言で頷くのみであった。
「なるほど、それでマリンはシトリンちゃんに食べられちゃったと」
「お恥ずかしながら」
天璣の塔で、ソラ。自分が半分焚き付けたようなものではあったが、さすがにここまで行くとは予想外だったようで……そして淡々とそういう会話をかわすソラとマリンを尻目に、シトリンは真っ赤になってうつむいている。
あれから三ヶ月。マリンの中毒症状もすっかり収まり、医師からは寛解のお墨付きが出た。そこで改めて奴隷環を返しにソラ宅を来訪したマリンとシトリンである。
「お借りするという約束でしたけど、これはいつになったら商品化されますか?」
マリンが、凄く真剣な顔で問う。
「うーん、人体実……じゃなかった。ほかにもやってみないといけない臨床試験あるから、当分先になるわね。これ、欲しいの?」
「はい、シトリンだけに奴隷環の呪の忌まわしさを背負わせるわけには……」
「マリンさん……」
困ったようにソラは二人を眺めていたが、
「多分だけど、すでに主従が固まっているご主人様と奴隷のペアには売るわけにはいかなくなると思う」
「⁉ どうしてですか?」
驚いて、思わず立ち上がるマリンだ。
「うん、マリンのこのレポートによるとね……①のほう」
「はい」
ソラは険しい顔で、
「私、本当に申し訳ないことをしたなと思ってるの」
「ソラ姉?」
そしてソラはページをめくりながら、
「まずシトリンちゃんが、マリンに『命令の取り下げ』を行った。次にマリンが、シトリンちゃんに対して。」
「はい」
「マリンもシトリンちゃんも、自分ではわからないでしょうけど……」
ソラはゆっくりと、マリンのレポートが書かれているノートを閉じると、
「奴隷環の呪に侵されている真っ只中で、そこまで頭が回って行動に移せる。言葉は悪いけど、そんなバケモノコンビってあなたたちぐらいのものよ?」
「と言いますと?」
「いや、ソラ様。普通に命令を取り消しただけですよ?」
さっぱりわけがわからないといったマリンとシトリンに、ソラは呆れた表情を隠せない。
「私も自分自身に対して実験してみたことあるからわかるんだけど、あの奴隷環の呪をくらったら『普通の人』はね? 意識が混濁してとてもそんな余裕を保ってられないの」
「え……」
「そう、なんですか?」
「うん」
そしてソラは、テーブルに両手を付いて深々と二人に頭を下げた。
「私、あなたたちを殺してしまってたかもしれない。それは本当にごめんなさい」
ソラ曰く、命令のバッティングによる両者への奴隷環の呪。これにより、常人はただそれに苦しみもがくだけで……その先に待っているのは、共倒れ。
両者ともに、発狂して死んでしまう可能性が高いのだと。それを聴いて、マリンとシトリンは改めてゾッとする。
「だから商品化されても、奴隷を所持している人にはお売りするわけにはいかないのよね。まぁそれがわかっただけでも、マリンたちで人体……臨床試験をした甲斐はあったわ」
「さっきからひどい言い間違いが多いですね?」
思わずジト目のマリンに対し、
「気のせいでしょ」
と意に介してなさそうなソラだった。
中毒症状もほぼ抜けたので、マリンは職場に復帰していた。同時にシトリンもウエイトレス業に復活する傍らで、ハンター業としての活動も開始する。
「マーリーンーさんっ」
うきうきルンルンで、三番カウンターにシトリン。
「お帰りなさい、シトリンさん。ご無事なようで何よりです」
今は職務中、マリンも受付嬢としてシトリンには敬語を使う。シトリン、それは理解しているものの一抹の寂しさを感じ得なくて。
「こちら、討伐結果です‼」
でも今はとりあえず、隣の解体所から発行してもらった受領票を机上に差し出す。
このハンターギルドでは、まず隣にある解体所に討伐対象の魔石を持ち込む。肉・角・牙など、換金してもらう場合はそのままに。
そして受領票と換金してもらう場合は引換証を発行してもらい、それをハンターギルドに提出すれば晴れて依頼完遂となる仕組みだ。
「こっちが討伐結果で、換金してもらうのがこっちで……」
鼻息も荒く、カウンターに置いた受領票と引換証を指さして説明するシトリンに、
「『お客様』、説明していただかなくとも結構です。では拝見しますね」
「あうっ」
マリンの塩対応に、ハイテンションだったシトリンは出鼻をくじかれてしまった。
「ふむ……『毒牙大海蛇』ですか」
マリンは頭を抱えた。
(誰がシトリンに、こんな危ない依頼を許可したん⁉)
一応SランクもしくはAランクパーティー『推奨』の案件である。『必須』ではなくて『推奨』なので、条件を満たさなくても受付嬢の胸先三寸で依頼を受理する場合はあるのだ。
シトリンならそりゃやってのけるだろうが、オカンモードのマリンはそれでも心配でしょうがなかった。
いつもはどんなに列が混んでても、マリンのいる三番カウンターに並ぶシトリン。だけど討伐対象が大物の討伐のときは、マリンに反対されるやら心配されるやらで。
奴隷であるシトリンの評判は、そのままご主人様であるマリンの評判に影響する。できるだけ大物を狩って、マリンの評判をあげたい……その一心のシトリン。
なので討伐対象が大物のときだけ、三番カウンターを避けていたのはマリンに内緒であった。
「おめでとうございます、そしてありがとうございますシトリンさん。かの大蛇の存在は、地元漁師さんたちの悩みの種でしたからね……ところで、あなたから何やら生臭い臭いが?」
「あ、ごめんなさい」
シトリン、赤面しながらポーチの中から一つの包みを取り出した。
「これ、帝王イカなんです」
何やらドヤってるシトリンに、マリンは首をかしげる。
「それは解体所に預け忘れてしまったのですか?」
「いえ、そうではなく……」
シトリン、恥ずかしそうに頭をかきながら少し赤い顔だ。
「マリンさん、お好きだったから……お酒の肴にどうかと思いまして、ついでに討伐して美味しそうなところだけ切り取ってきました」
「……」
マリンは無言で、ちょいちょいとシトリンを手招きする。といっても、マリンとシトリンはカウンターをはさんで向かい合ってるのだ。
「あの、マリンさん?」
マリンの意図することがわからず、それでもシトリンはカウンターに前のめりになって顔をマリンに近づける。
「帰ったら、二人で食べようね」
小声でマリンがそう言って、シトリンの頭をなでなで。
「‼ ハイ! 美味しくいただきましょう!」
「シトリン、声大きいけ‼」
慌ててマリンが、キョロキョロと周囲を確認。シトリンも、やってしまったとばかりに冷や汗だ。
「んっ、んんっ‼ では、ギルドカードをこちらに」
「あ、はい」
シトリンが差し出すそれには、白銀で『A』と刻印されたそれが燦然と輝く。このハンターギルドでは現在はSクラスは不在で、Aクラスが十余名しかいない。
その十余名の中でもシトリンは、限りなくSクラスに近いともっぱらの評判だった。そしてSクラスに昇格するためには、二年間のAクラス経験が必要となる。
(もしそのルールがなかったら、シトリンはSクラス相当なんよね)
九年前、ハンターギルドに初めて登録した当時十二歳のマリンもまたルールの壁に阻まれた。ギルドマスター・パールからSクラスとの評価をもらいながら、Aクラスを二年間務めざるを得なかったのだ。
「はい、結構です。報奨金および換金分は口座に振り込んでおきますね」
「はーい、お願いします」
「それと、本日は『Z』が立て込むので『八』となる見込みです。ですので『G』が限界ならば、先に『イン』して構いませんので」
そう言いながら、マリンがギルドカードをシトリンに返却。
「了解です! お待ちしてますね‼」
「……」
シトリンはギルドカードを受け取り、るんたったしながらギルドを出て行った。
そしてその会話を隣で、ほかのハンターとの手続きを進めながら聞き耳を立てていた二番カウンターのモルガナは苦笑いを禁じ得ない。
(何の話やら……どうせ、二人だけにしかわからない暗号なんだろうなぁ)
実はそのとおりで、『残業で遅くなるから、帰りは午後『八』時ごろになる。もしお腹が空いて我慢できないならば、先に晩御飯を胃に『イン』してて構わないよ』という、二人にしかわからないやり取りなのだ。
もっともマリンは、シトリンが先に食べないだろうことは容易に予想がつくのだけど。シトリンならば、何時までも待ってしまうだろう。
(そのうち、遠慮せずに食べてくれるようになるんかねぇ)
思わずため息をつくマリンだったが、ここのところシトリンによる獅子奮迅の奮闘ぶりは大変目覚ましく。その名声は、国内各都市にまで轟いていた。
特にシトリンは今回のように『魔獣により町の人が困っている』という案件を優先させるので、ハンターギルドには都度シトリンへのお礼状が山ほど届く。
その『自慢のシトリン』は、マリンにとって誇らしくもあった。そしてそのシトリンの原動力がお土産を持って帰って過ごす、マリンと食卓を囲む至福で至高の時間。
シトリンは自分がいかに討伐したかを得意満面に話し、それをマリンに褒めてもらう。それはシトリンにとって何ものにも代えがたい、頑張った自分へのご褒美だったのだ。
(まぁ私も、早く帰れるようにせんといけんね)
そしてチラと時計を見る。
「あと、一分。誰も来ませんように……。
ハンターギルドは十九時が最終受付だ。だが業務は十九時で終了というわけではなく、十九時寸前に来た客の対応は最後までやらなければいけない。
(あと十秒……五秒、四、三……)
だが無常にも、あと一秒と迫ったところで三番カウンターの椅子に一人の女性ハンターが腰をかけた。
「こちら、お願いしまーす!」
そう言って机上に受領票を置くその少女――背中の半ばあたりまで伸びた、ゆるフワの淡いアッシュブラウンの髪がハーフアップにまとめられている。美しくも若干の幼さを残した勝気そうで精悍な表情には、紫水晶を思わせる美しい澄んだ紫の瞳。
だがその美しい容貌に似つかわしくなく、首から下はミスリル製の鎧を身に纏い腰には同じくミスリル銀の長剣を帯刀していた。そして何故か、左肩に蝙蝠が鎮座している。
「……」
「お願いしまーす?」
「……」
八時過ぎてしまうかもしれない、シトリンを待たせてしまう……という絶望もあったが、マリンの表情は別の意味で凍り付いた。
「……こんなところで、何やってるんです?」
その少女を、マリンは知っている。知りすぎるほど知っていた。
「え、ちょっとフェクダに用があって。ついでに、運動も兼ねて討伐依頼を受けたんです」
マリンは胡散臭そうに、提出された受領票に目を通す。
「リヴァイアサンて……そりゃ確かに、依頼票は貼ってましたけど⁉」
マリンの驚愕するその声に、思わず隣のモルガナも振り返った。
「え、あの依頼を受けたの?」
そして驚きの表情を隠さず、その少女を凝視する。
「えぇ、私なら大丈夫かなと思って?」
この依頼は、『Sランクパーティーで臨むこと』というのが『必須』条件だった。現在のフェクダでは、たまたまタイミング的にSランクハンターが不在だ。
なので誰も引き受けることができないものだから、その依頼票は長きに渡り手つかずだった。ただSランクであればいいので、他国のハンターにも門戸は開いていたのだけど。
「でも、お一人ですか? Sランクハンターの『パーティ』が『必須』なのですよ?」
確認するようにモルガナが少女に問う。どう見ても少女は一人で、パーティを組んでいる様子が無かったからだ。
「この方なら、一人でもやってのけるでしょうね」
マリンは、呆れたように嘆息をしてみせる。
「モルガナさん。うちの誰が受け付けたのかは知らないけど、アレを見せられたら断れなかったと思います」
「アレって?」
二人の会話をキョトンとして聞いていたその少女、
「アレってコレです?」
そう言いながら、ハンターギルドカードを机上に置いた。
「え、嘘っ⁉」
それを見て、モルガナが絶句する。何せこのカードは、この大陸にたった二枚しか存在しないのだ。そのうち一枚は、マリンが所持している。
モルガナはマリンがそれを持っているのを見せてもらったことがあるし、何より五年前に発行作業を行ったのは自分だ。
まだ若干十六歳だったマリンに『ソレ』を手渡した当時。まだフェクダ王国どころか大陸に一枚も存在していなかったそれは、王室権限で新たに新設された伝説の――。
「SSランクって……」
ポカーンとして、その少女を見つめるモルガナ。そのハンターギルドカードには、白金で確かに『SS』という刻印が眩しく煌めいていた。
「で、なんでこんなところにいるんです?」
マリンはめんどくさそうに少女に少女を見やると、
「ねぇ、ク・ラ・リ・ス・殿下?」
だがその少女――次期皇帝としてその手腕を目されるクラリス・カリストはマリンのそんな態度を意にも介さず、
「ブルー、お久しぶりです!」
と満面の笑みを浮かべるのであった。
0
あなたにおすすめの小説

わたしの下着 母の私をBBA~と呼ぶことのある息子がまさか...
MisakiNonagase
青春
39才の母・真知子は息子が私の下着を持ち出していることに気づいた。
ネットで同様の事象がないか調べると、案外多いようだ。
さて、真知子は息子を問い詰める? それとも気づかないふりを続けてあげるか?

転落貴族〜千年に1人の逸材と言われた男が最底辺から成り上がる〜
ぽいづん
ファンタジー
ガレオン帝国の名門貴族ノーベル家の長男にして、容姿端麗、眉目秀麗、剣術は向かうところ敵なし。
アレクシア・ノーベル、人は彼のことを千年に1人の逸材と評し、第3皇女クレアとの婚約も決まり、順風満帆な日々だった
騎士学校の最後の剣術大会、彼は賭けに負け、1年間の期限付きで、辺境の国、ザナビル王国の最底辺ギルドのヘブンズワークスに入らざるおえなくなる。
今までの貴族の生活と正反対の日々を過ごし1年が経った。
しかし、この賭けは罠であった。
アレクシアは、生涯をこのギルドで過ごさなければいけないということを知る。
賭けが罠であり、仕組まれたものと知ったアレクシアは黒幕が誰か確信を得る。
アレクシアは最底辺からの成り上がりを決意し、復讐を誓うのであった。
小説家になろうにも投稿しています。
なろう版改稿中です。改稿終了後こちらも改稿します。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

裏切られ続けた負け犬。25年前に戻ったので人生をやり直す。当然、裏切られた礼はするけどね
魚夢ゴールド
ファンタジー
冒険者ギルドの雑用として働く隻腕義足の中年、カーターは裏切られ続ける人生を送っていた。
元々は食堂の息子という人並みの平民だったが、
王族の継承争いに巻き込まれてアドの街の毒茸流布騒動でコックの父親が毒茸の味見で死に。
代わって雇った料理人が裏切って金を持ち逃げ。
父親の親友が融資を持ち掛けるも平然と裏切って借金の返済の為に母親と妹を娼館へと売り。
カーターが冒険者として金を稼ぐも、後輩がカーターの幼馴染に横恋慕してスタンピードの最中に裏切ってカーターは片腕と片足を損失。カーターを持ち上げていたギルマスも裏切り、幼馴染も去って後輩とくっつく。
その後は負け犬人生で冒険者ギルドの雑用として細々と暮らしていたのだが。
ある日、人ならざる存在が話しかけてきた。
「この世界は滅びに進んでいる。是正しなければならない。手を貸すように」
そして気付けは25年前の15歳にカーターは戻っており、二回目の人生をやり直すのだった。
もちろん、裏切ってくれた連中への返礼と共に。

冤罪で辺境に幽閉された第4王子
satomi
ファンタジー
主人公・アンドリュート=ラルラは冤罪で辺境に幽閉されることになったわけだが…。
「辺境に幽閉とは、辺境で生きている人間を何だと思っているんだ!辺境は不要な人間を送る場所じゃない!」と、辺境伯は怒っているし当然のことだろう。元から辺境で暮している方々は決して不要な方ではないし、‘辺境に幽閉’というのはなんとも辺境に暮らしている方々にしてみれば、喧嘩売ってんの?となる。
辺境伯の娘さんと婚約という話だから辺境伯の主人公へのあたりも結構なものだけど、娘さんは美人だから万事OK。
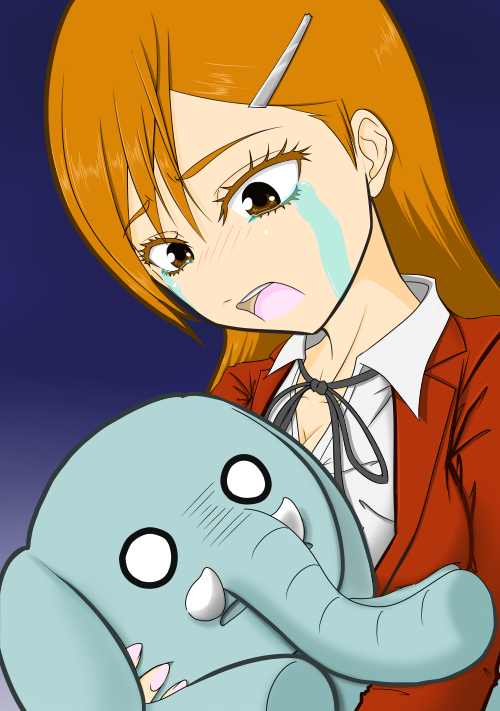
俺は美少女をやめたい!
マライヤ・ムー
ファンタジー
美少女になってしまった俺が男に戻る方法は、100人の女の子のくちびるを奪うこと! けがれなき乙女の園、ささやく魔導書、うなるチェーンソー、そして咲き乱れる百合の花。

クラス転移したけど、皆さん勘違いしてません?
青いウーパーと山椒魚
ファンタジー
加藤あいは高校2年生。
最近ネット小説にハマりまくっているごく普通の高校生である。
普通に過ごしていたら異世界転移に巻き込まれた?
しかも弱いからと森に捨てられた。
いやちょっとまてよ?
皆さん勘違いしてません?
これはあいの不思議な日常を書いた物語である。
本編完結しました!
相変わらず話ごちゃごちゃしていると思いますが、楽しんでいただけると嬉しいです!
1話は1000字くらいなのでササッと読めるはず…

七億円当たったので異世界買ってみた!
コンビニ
ファンタジー
三十四歳、独身、家電量販店勤務の平凡な俺。
ある日、スポーツくじで7億円を当てた──と思ったら、突如現れた“自称・神様”に言われた。
「異世界を買ってみないか?」
そんなわけで購入した異世界は、荒れ果てて疫病まみれ、赤字経営まっしぐら。
でも天使の助けを借りて、街づくり・人材スカウト・ダンジョン建設に挑む日々が始まった。
一方、現実世界でもスローライフと東北の田舎に引っ越してみたが、近所の小学生に絡まれたり、ドタバタに巻き込まれていく。
異世界と現実を往復しながら、癒やされて、ときどき婚活。
チートはないけど、地に足つけたスローライフ(たまに労働)を始めます。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる





















