あなたにおすすめの小説

病弱な彼女は、外科医の先生に静かに愛されています 〜穏やかな執着に、逃げ場はない〜
来栖れいな
恋愛
――穏やかな微笑みの裏に、逃げられない愛があった。
望んでいたわけじゃない。
けれど、逃げられなかった。
生まれつき弱い心臓を抱える彼女に、政略結婚の話が持ち上がった。
親が決めた未来なんて、受け入れられるはずがない。
無表情な彼の穏やかさが、余計に腹立たしかった。
それでも――彼だけは違った。
優しさの奥に、私の知らない熱を隠していた。
形式だけのはずだった関係は、少しずつ形を変えていく。
これは束縛? それとも、本当の愛?
穏やかな外科医に包まれていく、静かで深い恋の物語。
※この物語はフィクションです。
登場する人物・団体・名称・出来事などはすべて架空であり、実在のものとは一切関係ありません。
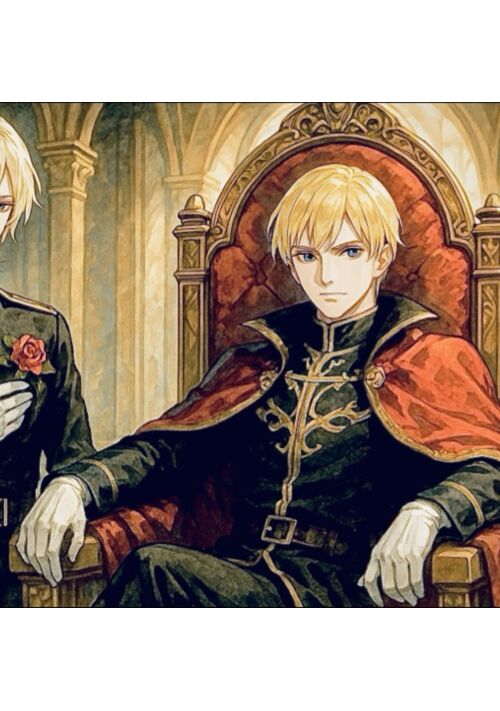
魅了持ちの執事と侯爵令嬢
tii
恋愛
あらすじ
――その執事は、完璧にして美しき存在。
だが、彼が仕えるのは、”魅了の魔”に抗う血を継ぐ、高貴なる侯爵令嬢だった。
舞踏会、陰謀、政略の渦巻く宮廷で、誰もが心を奪われる彼の「美」は、決して無害なものではない。
その美貌に隠された秘密が、ひとりの少女を、ひとりの弟を、そして侯爵家、はたまた国家の運命さえも狂わせていく。
愛とは何か。忠誠とは、自由とは――
これは、決して交わることを許されぬ者たちが、禁忌に触れながらも惹かれ合う、宮廷幻想譚。

冷徹公爵の誤解された花嫁
柴田はつみ
恋愛
片思いしていた冷徹公爵から求婚された令嬢。幸せの絶頂にあった彼女を打ち砕いたのは、舞踏会で耳にした「地味女…」という言葉だった。望まれぬ花嫁としての結婚に、彼女は一年だけ妻を務めた後、離縁する決意を固める。
冷たくも美しい公爵。誤解とすれ違いを繰り返す日々の中、令嬢は揺れる心を抑え込もうとするが――。
一年後、彼女が選ぶのは別れか、それとも永遠の契約か。


愛されないと吹っ切れたら騎士の旦那様が豹変しました
蜂蜜あやね
恋愛
隣国オデッセアから嫁いできたマリーは次期公爵レオンの妻となる。初夜は真っ暗闇の中で。
そしてその初夜以降レオンはマリーを1年半もの長い間抱くこともしなかった。
どんなに求めても無視され続ける日々についにマリーの糸はプツリと切れる。
離縁するならレオンの方から、私の方からは離縁は絶対にしない。負けたくない!
夫を諦めて吹っ切れた妻と妻のもう一つの姿に惹かれていく夫の遠回り恋愛(結婚)ストーリー
※本作には、性的行為やそれに準ずる描写、ならびに一部に性加害的・非合意的と受け取れる表現が含まれます。苦手な方はご注意ください。
※ムーンライトノベルズでも投稿している同一作品です。

今さらやり直しは出来ません
mock
恋愛
3年付き合った斉藤翔平からプロポーズを受けれるかもと心弾ませた小泉彩だったが、当日仕事でどうしても行けないと断りのメールが入り意気消沈してしまう。
落胆しつつ帰る道中、送り主である彼が見知らぬ女性と歩く姿を目撃し、いてもたってもいられず後を追うと二人はさっきまで自身が待っていたホテルへと入っていく。
そんなある日、夢に出てきた高木健人との再会を果たした彩の運命は少しずつ変わっていき……

押しつけられた身代わり婚のはずが、最上級の溺愛生活が待っていました
cheeery
恋愛
名家・御堂家の次女・澪は、一卵性双生の双子の姉・零と常に比較され、冷遇されて育った。社交界で華やかに振る舞う姉とは対照的に、澪は人前に出されることもなく、ひっそりと生きてきた。
そんなある日、姉の零のもとに日本有数の財閥・凰条一真との縁談が舞い込む。しかし凰条一真の悪いウワサを聞きつけた零は、「ブサイクとの結婚なんて嫌」と当日に逃亡。
双子の妹、澪に縁談を押し付ける。
両親はこんな機会を逃すわけにはいかないと、顔が同じ澪に姉の代わりになるよう言って送り出す。
「はじめまして」
そうして出会った凰条一真は、冷徹で金に汚いという噂とは異なり、端正な顔立ちで品位のある落ち着いた物腰の男性だった。
なんてカッコイイ人なの……。
戸惑いながらも、澪は姉の零として振る舞うが……澪は一真を好きになってしまって──。
「澪、キミを探していたんだ」
「キミ以外はいらない」
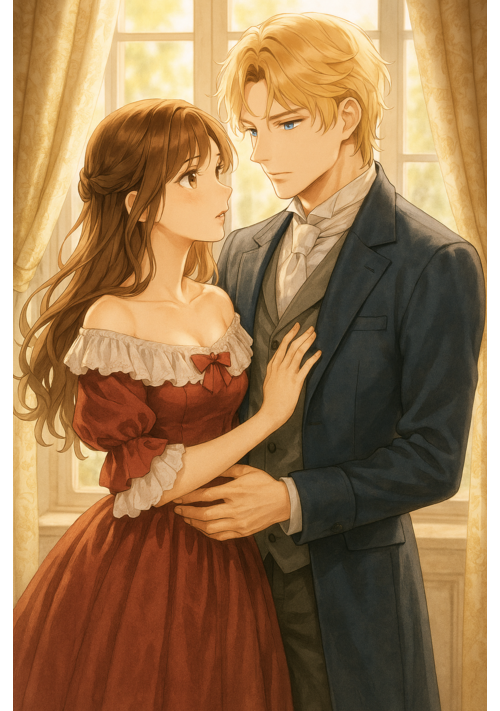
《完結》追放令嬢は氷の将軍に嫁ぐ ―25年の呪いを掘り当てた私―
月輝晃
恋愛
25年前、王国の空を覆った“黒い光”。
その日を境に、豊かな鉱脈は枯れ、
人々は「25年ごとに国が凍る」という不吉な伝承を語り継ぐようになった。
そして、今――再びその年が巡ってきた。
王太子の陰謀により、「呪われた鉱石を研究した罪」で断罪された公爵令嬢リゼル。
彼女は追放され、氷原にある北の砦へと送られる。
そこで出会ったのは、感情を失った“氷の将軍”セドリック。
無愛想な将軍、凍てつく土地、崩れゆく国。
けれど、リゼルの手で再び輝きを取り戻した一つの鉱石が、
25年続いた絶望の輪を、少しずつ断ち切っていく。
それは――愛と希望をも掘り当てる、運命の物語。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















