1 / 3
1
しおりを挟む
その日は、きらきらとした夜会の灯りの下で、始まりました。
王都の中心にある華やかな大広間。あちこちから音楽と笑い声がこぼれていて、ドレスの裾がふわふわと揺れるたびに、香水と花の香りが舞ってきます。
わたし、リーナ・エヴァンストンは、その場の片隅にそっと立っていました。
肩までの栗色の髪をゆるく結い、控えめな水色のドレスを着て。自分でも地味だってわかっています。だけど、わたしはこれしか知らなかったから、仕方なかったのです。
「ねえ見て、あれリーナ子爵令嬢じゃない? また地味~なドレス着てる」
「うそ、ほんとだ。まるで壁みたい。社交界っていうより、お城の装飾品って感じ?」
聞こえないふりをしても、そういう声はどうしても耳に届いてしまいます。
笑ってるのは、エドワルドの取り巻きの女の子たち。彼女たちはいつだって、わたしのことを「つまらない令嬢」って呼んでくるのです。
わたしの婚約者、エドワルド・ベイラント。貴族の中でも有力な家系の若き騎士団長。金髪で背が高くて、ぱっと見は絵に描いたような「素敵な貴族さま」でした。
でも、ほんとの彼は――。
「リーナ、ちょっと話があるんだ」
その声がしたとき、胸の奥がひやりと冷たくなりました。
わたしは彼の顔を見上げました。目が、笑っていませんでした。むしろ、どこかうんざりしているような、冷たい目。
「こんなところで?」
「いいから」
有無を言わせぬ態度で、わたしは人目の少ない庭園の端へと連れていかれました。
夜の風が少しだけ冷たくて、思わず肩をすくめます。だけど、エドワルドはそんなこと、全然気にしていない様子で、まっすぐにわたしを見おろしました。
「リーナ、君とは婚約を解消する」
「――……え?」
声が出ませんでした。
言葉が、頭の中でうまく形にならなくて、ただ、胸の奥がぎゅっと痛んで、息が止まりそうになったのです。
「君ってさ、平凡すぎるんだよ。どこにでもいる令嬢って感じで、正直つまらない。社交界じゃ君の話題なんて誰もしないし、僕の隣に立つなら、もっと華やかで話題になる女性がいい」
何それ。
わたしが何をしたっていうの。
地味なドレスが悪いの? 控えめにしていたことが? おしとやかでいたことが? あなたのお父さまが決めた婚約を、まじめに守ってきただけなのに。
……でも。
わたしは唇を噛んで、必死で涙をこらえました。
「わかりました。エドワルド様がそうおっしゃるのなら」
「え? ……ああ、そう。まあ、そういうとこが“つまらない”って思うんだけどね」
ひとこと、ひとことが、心を削るみたいに痛かった。
でも、泣きたくなかった。
こんな人の前で、涙なんて見せたくなかった。
「じゃ、そういうことで。僕はもう次の相手を決めてるからさ。あ、あとで正式な書類は送るよ」
そう言い残して、彼はさっさと背を向けて行ってしまいました。
わたしのことなんて、最初からいなかったかのように。
……バカみたい。
何年も彼の婚約者として、ちゃんとふるまってきたのに。
信じてたのに。
でも――きっと、これでよかったんだと思う。
だって、あんな人と結婚してたら、わたし、一生「地味でつまらない妻」って言われ続けていたんだもの。
「……ふふ。よかったわね、エドワルド様。これで、もっと“話題になる女性”とやらと、好きに騒げるじゃない?」
ぽつりとつぶやいた声に、誰も気づかない。
満月の下、わたしの影は細く長く伸びていて――その先に、まだ見えない未来があるように感じました。
そのときは、まさか自分が隣国の大将軍に見初められて、全く違う人生を歩むなんて、少しも想像していなかったけれど――。
馬車の車輪が、ガタガタと揺れながら小さな村道を進んでいく。
窓から差しこむ風は、王都よりずっと冷たくて、まるで季節がひとつ早く巡っているようだった。
「ラステリア行きの乗り合い馬車は、こっちだよ、お嬢さん」
そう言って手を差し出してくれたのは、白髪まじりの親切な御者のおじいさんだった。
わたしは、王都の屋敷を出るとき、あまりにあっけないくらいすぐに荷物をまとめた。
小さな鞄に詰められたのは、最小限の着替えと、家族の記念のペンダント。それから――誰にも見せたことのない日記帳。
「……こんなに、簡単に出て行けるんだね」
思わず、ぽつりと声に出していた。
あんなにがんばって、貴族らしくふるまおうとした王都での日々。あれは何だったんだろうって、ひとりで笑えてきた。
わたしの行き先は、隣国ラステリア。
母の遠縁にあたるおばさまが、小さな町で暮らしているという手紙を昔もらったことがあって……それだけが、今のわたしのたより。
「ご無沙汰しております、って、ちゃんと伝えられるかな……」
少し不安で、でも、少し楽しみで。
王都で“地味でつまらない”って言われてきたわたしにとって、ラステリアはまるで別の世界みたいに思えた。
――けれど。
運命って、たまにほんとうに、びっくりするようなことをしてくる。
馬車が深い森を抜けるころ、突然、ガタッと車体が揺れて、御者のおじいさんが慌てた声をあげた。
「なっ、なんだ!? ……あれは……っ!」
「なに?」
わたしも身を乗り出して外をのぞきこむ。
そのとき――道の先に、数人の男たちが立っていた。顔の下半分を布で隠し、手には鈍く光る剣。
……まさか、山賊!? こんな場所で……!
「止まれー! 荷物を全部置いてけぇ!!」
男のひとりが叫びながら、こちらに駆けてくる。
御者のおじいさんが手綱を引いて馬車を止めたけど、わたしの心臓はどくどくと鳴って、手足が冷たくなっていった。
「どうしよう……どうすれば……っ」
逃げ道もない。助けもいない。わたし一人じゃ、きっと――
そのときだった。
ずどんっ!!!
まるで雷みたいな音が響いて、男たちが次々に倒れていった。
……え? なに? いったい何が――
「……下がっていろ、嬢ちゃん」
その声は、低くて、どこかやさしい響きがあった。
現れたのは、馬にまたがったひとりの男の人。長い黒髪を風になびかせ、漆黒の鎧をまとい、背中には……大きな剣。
わたしは、目を奪われた。
ただ、ただ、見とれてしまったのだ。
「よく無事だったな。……怖かったろう」
彼が近づいて、手を差しのべてくれた。
その大きな手に触れた瞬間、心の中の恐怖がすぅっと引いていくのがわかった。
「……あ、あの。ど、どなた……ですか?」
声がうわずってしまって、自分でも恥ずかしかった。
「グレイ・コーディア。ラステリア王国の将軍職を仰せつかっている」
……しょ、将軍……!?
わたし、そんなすごい人に助けられたの!?
「こんな道に、貴族の娘がひとりで旅をしてるなんて……何か、わけがあるんだろう?」
彼はそう言って、わたしの目をまっすぐに見つめた。
その目が、まるで全てを見抜いているようで、わたしは思わず、目をそらしてしまった。
「……事情があって、ラステリアへ向かっていたんです」
「そうか。なら、ラステリアにある俺の屋敷に来い。それに道中は危険だ。ここから先は、護衛が必要だ」
「えっ、でも……そんな、大将軍さまにご迷惑は……!」
「助けたんだから、最後まで責任を持たせてくれ」
彼は、にかっと笑った。
その笑顔は、ちょっと子どもみたいで、でもどこか頼りがいがあって。――胸が、少しだけ温かくなった。
わたしは、その手を、ぎゅっと握り返した。
「……ありがとうございます。よろしくお願いします、グレイ様」
こうして、わたしの旅は、大きく変わっていく。
遠い国で、偶然出会ったひとりの男の人。
――後に、わたしの人生をまるごと変える人になるなんて、このときのわたしは、まだ知らなかった。
ラステリアの都は、思っていたよりもずっと大きくて、そして優しい街でした。
王都ほどキラキラはしていないけれど、道を歩く人たちの表情が明るくて、笑い声が自然で……なにより、空がすごく広くて。
「……うわぁ……」
ぽつりとつぶやいたその声に、となりを歩く彼――グレイ・コーディア将軍が、ちらりとこちらを見ました。
「驚いたか?」
「はい。こんなにのびのびした街、初めてです」
「そうか。……気に入ってもらえたなら、よかった」
その言葉を聞いて、ふっと胸があたたかくなった気がしました。
……こんなふうに、わたしの気持ちをまっすぐ聞いてくれる人。
王都には、いなかったな。
◇ ◇ ◇
グレイ様の屋敷は、都の中心から少し離れた丘の上にありました。
高い石の門と広い庭があるけれど、どこか素朴で、重すぎない雰囲気。
「……おじゃまします……」
扉をくぐった瞬間、緊張でつい背筋がぴんと伸びてしまって。
でも、すぐに出迎えてくれたのは、ふわふわの白い犬と、やさしそうなメイドさんたち。
「まあまあ、なんて可愛らしいお客様でしょう!」
「将軍様がご自分から“屋敷に迎える”なんて、珍しいですねぇ」
「お嬢さん、道中お疲れだったでしょう。すぐにお風呂の準備を――」
「ちょ、ちょっと待ってくださいっ!?」
矢継ぎ早に世話を焼かれて、びっくりしてしまいました。
王都では、誰もこんなふうに、わたしを“歓迎”してくれたことなんてなかったから。
グレイ様は、それを見て、くすっと笑って。
「悪いな。うちの連中、気に入った客がくるとちょっと浮かれすぎるんだ」
「い、いえ……その、うれしいです。とても……」
「そうか。なら、もっと甘えていいんだぞ」
……“甘えていい”なんて。
そんな言葉、わたしの人生で誰かに言われたの、初めてかもしれません。
◇ ◇ ◇
お風呂をいただいて、ふわふわのナイトドレスに着替えて、温かいスープを飲んだころ――
わたしの心も、ほんのすこしだけ、ほどけてきました。
「……なあ、リーナ。ひとつ、聞いてもいいか?」
「はい?」
グレイ様は、湯気の立つ紅茶を持ったまま、まっすぐにわたしを見つめていました。
「王都から、どうして出てきたんだ?」
その声はやさしくて、強くて、でも押しつけがましくなくて。
だから――わたしも、ゆっくりと口をひらきました。
「婚約破棄、されたんです」
「……そうか」
「“君は平凡でつまらない”って言われました。……貴族の令嬢なのに、地味だって。……笑われてました、ずっと」
言ってるうちに、涙が出そうになってきて。
だけど、ぐっとこらえた。
「でも、あんな人に傷つけられて、悲しんでる自分が、もっと嫌で。……それで、出てきたんです」
グレイ様は、何も言わずに、ただ黙って聞いてくれていました。
その沈黙が、なぜだか、わたしにはうれしかった。
やがて、彼は一言だけ、こう言いました。
「……よく来てくれたな、リーナ」
その言葉だけで、涙がぽろりとこぼれてしまった。
グレイ様はあわててティーカップを置いて、わたしに近づいてきました。
「す、すまない! 嫌なこと思い出させたか!? 泣かせるつもりじゃ――」
「ちがうんです……ちがうの……」
わたしは首をふって、袖でぬぐいました。
「うれしかったの、です。……こんなふうに、ちゃんと話を聞いてくれて、信じてくれて……」
そう。
ただ、それだけのことが、わたしには今までなかった。
「君は、何ひとつ“つまらなく”なんかない。むしろ、よくぞ今まで耐えてきた。偉いな」
グレイ様のその言葉が、どれだけ胸に染みたか……言葉にはできません。
その晩。
わたしは初めて、夢も見ずに、ぐっすり眠りました。
心のどこかに、あたたかいものを抱えたまま。
王都の中心にある華やかな大広間。あちこちから音楽と笑い声がこぼれていて、ドレスの裾がふわふわと揺れるたびに、香水と花の香りが舞ってきます。
わたし、リーナ・エヴァンストンは、その場の片隅にそっと立っていました。
肩までの栗色の髪をゆるく結い、控えめな水色のドレスを着て。自分でも地味だってわかっています。だけど、わたしはこれしか知らなかったから、仕方なかったのです。
「ねえ見て、あれリーナ子爵令嬢じゃない? また地味~なドレス着てる」
「うそ、ほんとだ。まるで壁みたい。社交界っていうより、お城の装飾品って感じ?」
聞こえないふりをしても、そういう声はどうしても耳に届いてしまいます。
笑ってるのは、エドワルドの取り巻きの女の子たち。彼女たちはいつだって、わたしのことを「つまらない令嬢」って呼んでくるのです。
わたしの婚約者、エドワルド・ベイラント。貴族の中でも有力な家系の若き騎士団長。金髪で背が高くて、ぱっと見は絵に描いたような「素敵な貴族さま」でした。
でも、ほんとの彼は――。
「リーナ、ちょっと話があるんだ」
その声がしたとき、胸の奥がひやりと冷たくなりました。
わたしは彼の顔を見上げました。目が、笑っていませんでした。むしろ、どこかうんざりしているような、冷たい目。
「こんなところで?」
「いいから」
有無を言わせぬ態度で、わたしは人目の少ない庭園の端へと連れていかれました。
夜の風が少しだけ冷たくて、思わず肩をすくめます。だけど、エドワルドはそんなこと、全然気にしていない様子で、まっすぐにわたしを見おろしました。
「リーナ、君とは婚約を解消する」
「――……え?」
声が出ませんでした。
言葉が、頭の中でうまく形にならなくて、ただ、胸の奥がぎゅっと痛んで、息が止まりそうになったのです。
「君ってさ、平凡すぎるんだよ。どこにでもいる令嬢って感じで、正直つまらない。社交界じゃ君の話題なんて誰もしないし、僕の隣に立つなら、もっと華やかで話題になる女性がいい」
何それ。
わたしが何をしたっていうの。
地味なドレスが悪いの? 控えめにしていたことが? おしとやかでいたことが? あなたのお父さまが決めた婚約を、まじめに守ってきただけなのに。
……でも。
わたしは唇を噛んで、必死で涙をこらえました。
「わかりました。エドワルド様がそうおっしゃるのなら」
「え? ……ああ、そう。まあ、そういうとこが“つまらない”って思うんだけどね」
ひとこと、ひとことが、心を削るみたいに痛かった。
でも、泣きたくなかった。
こんな人の前で、涙なんて見せたくなかった。
「じゃ、そういうことで。僕はもう次の相手を決めてるからさ。あ、あとで正式な書類は送るよ」
そう言い残して、彼はさっさと背を向けて行ってしまいました。
わたしのことなんて、最初からいなかったかのように。
……バカみたい。
何年も彼の婚約者として、ちゃんとふるまってきたのに。
信じてたのに。
でも――きっと、これでよかったんだと思う。
だって、あんな人と結婚してたら、わたし、一生「地味でつまらない妻」って言われ続けていたんだもの。
「……ふふ。よかったわね、エドワルド様。これで、もっと“話題になる女性”とやらと、好きに騒げるじゃない?」
ぽつりとつぶやいた声に、誰も気づかない。
満月の下、わたしの影は細く長く伸びていて――その先に、まだ見えない未来があるように感じました。
そのときは、まさか自分が隣国の大将軍に見初められて、全く違う人生を歩むなんて、少しも想像していなかったけれど――。
馬車の車輪が、ガタガタと揺れながら小さな村道を進んでいく。
窓から差しこむ風は、王都よりずっと冷たくて、まるで季節がひとつ早く巡っているようだった。
「ラステリア行きの乗り合い馬車は、こっちだよ、お嬢さん」
そう言って手を差し出してくれたのは、白髪まじりの親切な御者のおじいさんだった。
わたしは、王都の屋敷を出るとき、あまりにあっけないくらいすぐに荷物をまとめた。
小さな鞄に詰められたのは、最小限の着替えと、家族の記念のペンダント。それから――誰にも見せたことのない日記帳。
「……こんなに、簡単に出て行けるんだね」
思わず、ぽつりと声に出していた。
あんなにがんばって、貴族らしくふるまおうとした王都での日々。あれは何だったんだろうって、ひとりで笑えてきた。
わたしの行き先は、隣国ラステリア。
母の遠縁にあたるおばさまが、小さな町で暮らしているという手紙を昔もらったことがあって……それだけが、今のわたしのたより。
「ご無沙汰しております、って、ちゃんと伝えられるかな……」
少し不安で、でも、少し楽しみで。
王都で“地味でつまらない”って言われてきたわたしにとって、ラステリアはまるで別の世界みたいに思えた。
――けれど。
運命って、たまにほんとうに、びっくりするようなことをしてくる。
馬車が深い森を抜けるころ、突然、ガタッと車体が揺れて、御者のおじいさんが慌てた声をあげた。
「なっ、なんだ!? ……あれは……っ!」
「なに?」
わたしも身を乗り出して外をのぞきこむ。
そのとき――道の先に、数人の男たちが立っていた。顔の下半分を布で隠し、手には鈍く光る剣。
……まさか、山賊!? こんな場所で……!
「止まれー! 荷物を全部置いてけぇ!!」
男のひとりが叫びながら、こちらに駆けてくる。
御者のおじいさんが手綱を引いて馬車を止めたけど、わたしの心臓はどくどくと鳴って、手足が冷たくなっていった。
「どうしよう……どうすれば……っ」
逃げ道もない。助けもいない。わたし一人じゃ、きっと――
そのときだった。
ずどんっ!!!
まるで雷みたいな音が響いて、男たちが次々に倒れていった。
……え? なに? いったい何が――
「……下がっていろ、嬢ちゃん」
その声は、低くて、どこかやさしい響きがあった。
現れたのは、馬にまたがったひとりの男の人。長い黒髪を風になびかせ、漆黒の鎧をまとい、背中には……大きな剣。
わたしは、目を奪われた。
ただ、ただ、見とれてしまったのだ。
「よく無事だったな。……怖かったろう」
彼が近づいて、手を差しのべてくれた。
その大きな手に触れた瞬間、心の中の恐怖がすぅっと引いていくのがわかった。
「……あ、あの。ど、どなた……ですか?」
声がうわずってしまって、自分でも恥ずかしかった。
「グレイ・コーディア。ラステリア王国の将軍職を仰せつかっている」
……しょ、将軍……!?
わたし、そんなすごい人に助けられたの!?
「こんな道に、貴族の娘がひとりで旅をしてるなんて……何か、わけがあるんだろう?」
彼はそう言って、わたしの目をまっすぐに見つめた。
その目が、まるで全てを見抜いているようで、わたしは思わず、目をそらしてしまった。
「……事情があって、ラステリアへ向かっていたんです」
「そうか。なら、ラステリアにある俺の屋敷に来い。それに道中は危険だ。ここから先は、護衛が必要だ」
「えっ、でも……そんな、大将軍さまにご迷惑は……!」
「助けたんだから、最後まで責任を持たせてくれ」
彼は、にかっと笑った。
その笑顔は、ちょっと子どもみたいで、でもどこか頼りがいがあって。――胸が、少しだけ温かくなった。
わたしは、その手を、ぎゅっと握り返した。
「……ありがとうございます。よろしくお願いします、グレイ様」
こうして、わたしの旅は、大きく変わっていく。
遠い国で、偶然出会ったひとりの男の人。
――後に、わたしの人生をまるごと変える人になるなんて、このときのわたしは、まだ知らなかった。
ラステリアの都は、思っていたよりもずっと大きくて、そして優しい街でした。
王都ほどキラキラはしていないけれど、道を歩く人たちの表情が明るくて、笑い声が自然で……なにより、空がすごく広くて。
「……うわぁ……」
ぽつりとつぶやいたその声に、となりを歩く彼――グレイ・コーディア将軍が、ちらりとこちらを見ました。
「驚いたか?」
「はい。こんなにのびのびした街、初めてです」
「そうか。……気に入ってもらえたなら、よかった」
その言葉を聞いて、ふっと胸があたたかくなった気がしました。
……こんなふうに、わたしの気持ちをまっすぐ聞いてくれる人。
王都には、いなかったな。
◇ ◇ ◇
グレイ様の屋敷は、都の中心から少し離れた丘の上にありました。
高い石の門と広い庭があるけれど、どこか素朴で、重すぎない雰囲気。
「……おじゃまします……」
扉をくぐった瞬間、緊張でつい背筋がぴんと伸びてしまって。
でも、すぐに出迎えてくれたのは、ふわふわの白い犬と、やさしそうなメイドさんたち。
「まあまあ、なんて可愛らしいお客様でしょう!」
「将軍様がご自分から“屋敷に迎える”なんて、珍しいですねぇ」
「お嬢さん、道中お疲れだったでしょう。すぐにお風呂の準備を――」
「ちょ、ちょっと待ってくださいっ!?」
矢継ぎ早に世話を焼かれて、びっくりしてしまいました。
王都では、誰もこんなふうに、わたしを“歓迎”してくれたことなんてなかったから。
グレイ様は、それを見て、くすっと笑って。
「悪いな。うちの連中、気に入った客がくるとちょっと浮かれすぎるんだ」
「い、いえ……その、うれしいです。とても……」
「そうか。なら、もっと甘えていいんだぞ」
……“甘えていい”なんて。
そんな言葉、わたしの人生で誰かに言われたの、初めてかもしれません。
◇ ◇ ◇
お風呂をいただいて、ふわふわのナイトドレスに着替えて、温かいスープを飲んだころ――
わたしの心も、ほんのすこしだけ、ほどけてきました。
「……なあ、リーナ。ひとつ、聞いてもいいか?」
「はい?」
グレイ様は、湯気の立つ紅茶を持ったまま、まっすぐにわたしを見つめていました。
「王都から、どうして出てきたんだ?」
その声はやさしくて、強くて、でも押しつけがましくなくて。
だから――わたしも、ゆっくりと口をひらきました。
「婚約破棄、されたんです」
「……そうか」
「“君は平凡でつまらない”って言われました。……貴族の令嬢なのに、地味だって。……笑われてました、ずっと」
言ってるうちに、涙が出そうになってきて。
だけど、ぐっとこらえた。
「でも、あんな人に傷つけられて、悲しんでる自分が、もっと嫌で。……それで、出てきたんです」
グレイ様は、何も言わずに、ただ黙って聞いてくれていました。
その沈黙が、なぜだか、わたしにはうれしかった。
やがて、彼は一言だけ、こう言いました。
「……よく来てくれたな、リーナ」
その言葉だけで、涙がぽろりとこぼれてしまった。
グレイ様はあわててティーカップを置いて、わたしに近づいてきました。
「す、すまない! 嫌なこと思い出させたか!? 泣かせるつもりじゃ――」
「ちがうんです……ちがうの……」
わたしは首をふって、袖でぬぐいました。
「うれしかったの、です。……こんなふうに、ちゃんと話を聞いてくれて、信じてくれて……」
そう。
ただ、それだけのことが、わたしには今までなかった。
「君は、何ひとつ“つまらなく”なんかない。むしろ、よくぞ今まで耐えてきた。偉いな」
グレイ様のその言葉が、どれだけ胸に染みたか……言葉にはできません。
その晩。
わたしは初めて、夢も見ずに、ぐっすり眠りました。
心のどこかに、あたたかいものを抱えたまま。
69
あなたにおすすめの小説

殿下から「華のない女」と婚約破棄されましたが、王国の食糧庫を支えていたのは、実は私です
水上
恋愛
【全11話完結】
見た目重視の王太子に婚約破棄された公爵令嬢ルシア。
だが彼女は、高度な保存食技術で王国の兵站を支える人物だった。
そんな彼女を拾ったのは、強面の辺境伯グレン。
「俺は装飾品より、屋台骨を愛する」と実力を認められたルシアは、泥臭い川魚を売れる商品に変え、害獣を絶品ソーセージへと変えていく!
一方、ルシアを失った王宮は食糧難と火災で破滅の道へ……。

「地味な眼鏡女」と婚約破棄されましたが、この国は私の技術で保たれていたようです
水上
恋愛
【全11話完結】
「君は地味で華がない」と婚約破棄されたリル。
国を追放されるが、実は王国は全て彼女の技術で保たれていた!
「俺の世界を鮮やかにしてくれたのは君だ」
目つき最悪と恐れられた辺境伯(実はド近眼)に特製眼鏡を作ったら、隠れた美貌と過保護な愛が炸裂し始めて!?
そして、王都では灯台は消え、食料は腐り、王太子が不眠症で発狂する中、リルは北の辺境で次々と革命を起こしていた。

「華がない」と婚約破棄されたけど、冷徹宰相の恋人として帰ってきたら……
有賀冬馬
恋愛
「貴族の妻にはもっと華やかさが必要なんだ」
そんな言葉で、あっさり私を捨てたラウル。
涙でくしゃくしゃの毎日……だけど、そんな私に声をかけてくれたのは、誰もが恐れる冷徹宰相ゼノ様だった。
気がつけば、彼の側近として活躍し、やがては恋人に――!
数年後、舞踏会で土下座してきたラウルに、私は静かに言う。
「あなたが捨てたのは、私じゃなくて未来だったのね」

婚約破棄された令嬢、気づけば王族総出で奪い合われています
ゆっこ
恋愛
「――よって、リリアーナ・セレスト嬢との婚約は破棄する!」
王城の大広間に王太子アレクシスの声が響いた瞬間、私は静かにスカートをつまみ上げて一礼した。
「かしこまりました、殿下。どうか末永くお幸せに」
本心ではない。けれど、こう言うしかなかった。
王太子は私を見下ろし、勝ち誇ったように笑った。
「お前のような地味で役に立たない女より、フローラの方が相応しい。彼女は聖女として覚醒したのだ!」

離婚寸前で人生をやり直したら、冷徹だったはずの夫が私を溺愛し始めています
腐ったバナナ
恋愛
侯爵夫人セシルは、冷徹な夫アークライトとの愛のない契約結婚に疲れ果て、離婚を決意した矢先に孤独な死を迎えた。
「もしやり直せるなら、二度と愛のない人生は選ばない」
そう願って目覚めると、そこは結婚直前の18歳の自分だった!
今世こそ平穏な人生を歩もうとするセシルだったが、なぜか夫の「感情の色」が見えるようになった。
冷徹だと思っていた夫の無表情の下に、深い孤独と不器用で一途な愛が隠されていたことを知る。
彼の愛をすべて誤解していたと気づいたセシルは、今度こそ彼の愛を掴むと決意。積極的に寄り添い、感情をぶつけると――
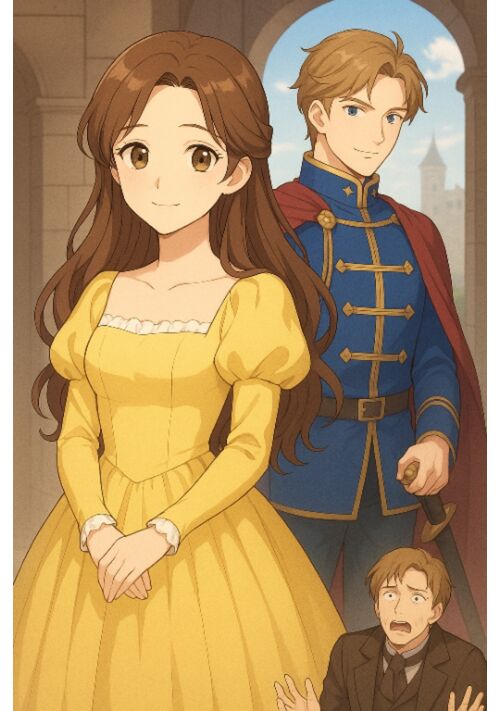
地味令嬢の私ですが、王太子に見初められたので、元婚約者様からの復縁はお断りします
有賀冬馬
恋愛
子爵令嬢の私は、いつだって日陰者。
唯一の光だった公爵子息ヴィルヘルム様の婚約者という立場も、あっけなく捨てられた。「君のようなつまらない娘は、公爵家の妻にふさわしくない」と。
もう二度と恋なんてしない。
そう思っていた私の前に現れたのは、傷を負った一人の青年。
彼を献身的に看病したことから、私の運命は大きく動き出す。
彼は、この国の王太子だったのだ。
「君の優しさに心を奪われた。君を私だけのものにしたい」と、彼は私を強く守ると誓ってくれた。
一方、私を捨てた元婚約者は、新しい婚約者に振り回され、全てを失う。
私に助けを求めてきた彼に、私は……

婚約破棄された夜、最強魔導師に「番」だと告げられました
有賀冬馬
恋愛
学院の祝宴で告げられた、無慈悲な婚約破棄。
魔力が弱い私には、価値がないという現実。
泣きながら逃げた先で、私は古代の遺跡に迷い込む。
そこで目覚めた彼は、私を見て言った。
「やっと見つけた。私の番よ」
彼の前でだけ、私の魔力は輝く。
奪われた尊厳、歪められた運命。
すべてを取り戻した先にあるのは……

地味子と蔑まれた私ですが、公爵様と結ばれることになりましたので、もうあなたに用はありません
有賀冬馬
恋愛
「君は何の役にも立たない」――そう言って、婚約者だった貴族青年アレクは、私を冷酷に切り捨てた。より美しく、華やかな令嬢と結婚するためだ。
絶望の淵に立たされた私を救ってくれたのは、帝国一の名家・レーヴェ家の公爵様。
地味子と蔑まれた私が、公爵様のエスコートで大舞踏会に現れた時、社交界は騒然。
そして、慌てて復縁を申し出るアレクに、私は……
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















