1 / 1
髪に宿る復讐――令嬢ミーアの冷酷なる美
しおりを挟む
ミーアは、その噂を耳にしたとき、初めて自分の髪を他人の言葉で測られたような気がした。屋敷の陽だまりに差し込む午後の光が、彼女の栗色の髪を飾り立てるたび、使用人たちは無意識に目を細め、客人は礼節を忘れて視線を留めた。髪はもはや単なる身体の一部ではなく、彼女の周囲に漂う重さとなり、祝宴では装飾のように、書簡の端では話題のように扱われた。
しかしその美しさが祝福となるどころか、彼女と婚約者の間に溝を作るとは、ミーアは思いも寄らなかった。破談の知らせは冬の朝に届いた。届けに来た使者の顔は陰鬱で、言葉は簡潔だった。「身辺の好奇を避けるため、婚約を解消する」——理由は曖昧に濁され、けれども周囲の囁きは鋭かった。噂は即座に形を取り、彼女の「美しい髪」が原因だと囁かれた。まるで彼女の存在そのものが、贖い難い罪であるかのように。
初めの数日は、ミーアの世界が色を失った。朝夕に通われる館の広間は、以前なら輝いて見えたろう光沢を失い、家具の木目は彼女のため息の重さを吸い取るように寂しげだった。彼女は窓辺に座り、指先でいつもの癖のように髪を梳きながら、過ぎ去った時間を何度も反芻した。婚約者の笑い声、二人で交わした冗談、そして最後に交わした言葉のひとかけら——それらはすべて、今となっては遠い音でしかなかった。胸の奥にぽっかりと空いた穴が、冷たい風と共に響いた。
やがて、悲しみは鈍い疼きとなり、疼きはいつのまにか思考へと姿を変えた。ミーアは自問した。自分は何を失ったのか、何を取り戻したいのか。怒りは最初は幼い火の粉のように小さく、彼女の内側でぱちぱちと音を立てただけだったが、その火は静かに燃え広がっていった。破談のただ中で生じた屈辱、周囲の視線、そしてあの「理由」の不条理さ——すべてが彼女の中で混ざり合い、復讐という形を模索し始める。
復讐の思考は、彼女の理性と感情のあわいで静かに育った。ミーアは復讐そのものを美化するつもりはなかった。だが屈辱に対する応報を望む心は、誰にでも偶発的に芽生えるものだ。彼女はまず冷静に事実を整理した。相手は公爵家の一人息子であり、社交界に顔が広い。彼の関心は外見にも向けられており、自分の体面を保つための習慣を持っていた。人前で見苦しく振る舞うことは、彼にとって何より忌避すべきことである。
ある晩、ミーアは古い舞踏会の写真を見返していて、ふと気づく。婚約者が常に整えていたもの——それは髪だった。彼は外見にほとんど無頓着そうに見えて、実は細やかな手入れを怠らない男だった。貴族の嗜みとしての散髪や整髪は、彼にとって自らの立場を守るための儀礼だったのだろう。ミーアの心に、ある思索が滑り込んだ。人は、自分の誇りと結びついたものに最も敏感であり、それを損なわれることを極端に嫌う——ならば、彼が依拠する日常の痕跡に目をつければ、撃ち得るかもしれない。
記憶の断片が繋がっていく。彼が定期的に通っていたというあのサロンのこと。街角の白い柱、扉脇に置かれた鉄の花器、窓辺に並ぶ香水瓶の軋む音。彼はそこで手入れを受け、鏡の中で自らを整え、社交の場に出て行った。ミーアは想像した。夜の帳が降りた後のサロン、残された椅子と落ちた毛先、そして誰もいない鏡に映る空虚な肩越しの自分——その風景は、彼女の怒りを現実へと誘うように見えた。
だが、復讐を思いつくことと、それを実行することはまったく別の次元だ。ミーアは慎重だった。彼女の内面には、自分が悪に染まることを拒む一線も残っていた。だが同時に、あまりにも理不尽な別離をただ受け入れることもできなかった。感情と道徳の間で揺れる心の中、あのサロンがひとつの軸として立ち上がった。もしも、相手の誇りに傷をつける手段があるとしたら——そしてそれが彼の誇りを形作る“髪”に関係するのなら——それは復讐の餌食として慎重に検討に値するのではないか。
ミーアは窓の外に目をやった。街灯が落ち葉の上に繊細な輪を描き、冬の空気が頬を刺す。ひと呼吸おいて、彼女は自分の手のひらを見つめる。その掌は震えてはいなかった。静かに、しかし確固たる声で彼女は自分に言い聞かせた。「何をしても、私は私だ」と。だが同時に思考の片隅で、ある冷たい可能性が形を取り始めるのを止められなかった――毛根を壊すという薬品の存在を仄めかす噂を、彼が通うそのサロンの空間に用いることができるかもしれない、という考えである。
その考えはまだ漠然としており、実行の輪郭は何も示していなかった。ただ、彼女の胸の中で小さな石が落ち、それが波紋を広げているだけだった。ミーアは深く息を吐き、鏡の前で自分の髪を一度手で撫でた。髪は変わらず柔らかく、光を受けて震えていた。彼女の瞳には、悲しみと復讐心とが混じった不思議な光が宿っていた。ここまで考えが及んだところで、彼女は静かに唇を噛み締めた。復讐の可能性――それは、もはや単なる空想ではなかった。
ミーアの胸の内に芽生えた復讐の影は、静かに、しかし確かな輪郭を帯びていった。彼女はある日、机の上に広げた帳面を閉じ、深く息を吸った。必要なのは——“毛根を破壊する薬”。そんなものがこの世に本当に存在するのか、最初は半信半疑だった。だが人々の間に流れる噂や、古い薬師が残した禁断の文献には、時折その名がぼんやりと記されていることがあった。
ミーアは考えた末、表の世界ではなく裏の街へ足を踏み入れることを決意した。貴族である彼女の姿は目立つ。ゆえに、外套で身を隠し、髪は布で覆い、薄暗い街路地へと溶け込むように歩いた。
夜の空気は汚れた鉄の味を含み、濁ったランタンの光が濡れた石畳に反射していた。闇市へ通じるスラムは、昼でも薄暗いが、夜になると別の息遣いを持ち始める。物乞いが膝を抱え、武器を抱えた男たちが煙草の煙を吐き、誰もが誰かを警戒しながら歩く世界。ミーアは足音を忍ばせるたび、心の奥で微かな震えを覚えたが、それでも前に進んだ。
彼女は、噂を頼りに薬師や密売人、そして黒ずんだ屋台を巡り、少しずつ情報を集めた。「毛根を壊す薬」と言えば皆、眉をひそめたり、背を向けたりした。危険すぎるのだ。人を狂わせ、人生を奪う薬剤——表の世界では存在そのものが否定されている。
しかし、諦めないミーアの耳に、ついにひとつの声が届いた。それは、目の奥に獣じみた光を宿した薬の仲買人だった。
「……あるには、あるさ。お嬢さんのような甘い顔には似合わん代物だがな」
ミーアは唇を結び、薄暗い商談用の小部屋へ通された。机の上には油紙に包まれた小瓶が置かれている。瓶の中身は黒く濁り、底からゆっくりと煙のような靄が立ち上る。
「法外な値段だぜ。普通の薬草屋三軒、まるごと買えるほどの金がいる」
提示された額を聞いた瞬間、ミーアの胸は冷たく沈んだ。貴族の娘であるとはいえ、自由に使える財は限られている。まして破談で実家が世間体に敏感になっている今、莫大な金を持ち出すことなど到底できない。
しかし、ここで引き下がるわけにもいかなかった。
ミーアはそこで、一つの顔を思い出した。
——以前、夜会でしつこいほど彼女に言い寄ってきた伯爵家の三男。金は腐るほど持っており、放蕩と贅沢で知られる男。彼はミーアにぞっこんで、ほんの一言の笑みですら宝石のように受け取る愚かさを持っていた。
「……あの方を、利用するしかありませんわね」
彼女はひそかに呟き、翌日、晴れやかな顔で伯爵家の別邸を訪れた。男は驚くほど簡単に彼女を迎え入れ、彼女のお願いに酔狂なほど喜んだ。
「危険が伴うのだと説明した上で」——いや、説明はほんの一部だけ。
「化粧品の珍しい原料を探しているのですの。どうしても手に入れたいものがあって……」と、わずかに涙を滲ませてみせれば、男はすぐに財布を開いた。
そして二日後、例の小瓶はミーアの手の中にあった。
彼女はそれを静かに見つめた。瓶を傾けると、とろりとした黒い液がゆっくりと揺れ、まるで生き物のように光を吸い込みながら蠢いた。胸の奥に不安が走る。それでも、彼女は手を離さなかった。
「……本当に、大丈夫かしら。いえ、確かめなくては」
薬の真価は試さねばならない。誤って自分が使えば取り返しがつかない。敵に使うにも慎重さがいる。
ミーアは公爵家の古く薄暗い地下牢を思い出した。かつて反逆罪で捕らえられた囚人たちが数名、条件付きで「実験材料」として王家に差し出されていたことを、彼女は幼い頃に聞いたことがあった。世間には隠されたままのその地下施設は、ほとんど誰も存在を知らず、監視する兵も最低限だ。
夜、彼女は外套をまとい、執事の目を欺き、静かに屋敷を抜け出した。風は冷たいが、心は奇妙なほど澄んでいた。
灯りの少ない廊下を歩きながら、ミーアは胸に手を当てた。震えてはいない。
「試す価値はあるはず……。これが使えるかどうか、その判断をしなければ」
地下牢の扉が鈍い音を立てて開き、薄暗い石室の奥、囚人が一人、鉄格子の向こうでうずくまっている。かすれた息と、湿った土の匂い。
ミーアは一歩進み、黒い小瓶を掌に乗せた。
彼女の瞳には冷たい決意が燃えていた。
地下牢の空気は、湿った石と錆びた鉄の匂いが混じり合い、ひどく重かった。ミーアの持つ燭台の灯りがゆらゆらと揺れ、その明かりの端で囚人たちの影が細長く伸びては縮んだ。
彼らは皆、長い拘束生活の中で肌も心も疲れ切っていたが、その中にひときわ異質な男がいた。
——アフロの男。
彼の髪は鉄格子の向こう側で黒い雲のように広がり、その存在だけで空気すら押しのけるほどの圧があった。面持ちは荒んでいるが、あの髪だけはこの暗闇の中で妙な生命力を放っていた。
ミーアは小さな息をつき、手の中の黒い薬瓶を確かめた。彼女の指先は冷たかったが、決意は揺らいでいない。
「失礼いたします……少し、試させていただきますね」
柔らかな声に囚人は怪訝そうに顔を上げた。
「……なんだ、嬢ちゃん。俺に何をするつもりだ」
ミーアは言葉を返す代わりに、瓶の蓋をそっと開いた。中から立ち上る黒い靄は、まるで生き物の吐息のようで、彼女の頬をかすめた瞬間に冷たい痛みを残した。
一滴。
ただそれだけで、どれほどの力を持つのかを確かめればいい。
ミーアは鉄格子に近づき、アフロの房のひとかけをそっと摘んで、薬を一滴だけ落とした。
その瞬間——
「……っ!?」
音がしたわけではなかった。しかしアフロは、まるで電撃を受けたように体を震わせた。
黒い滴は、触れた毛先を食い尽くすかのように広がり、みるみるうちに髪の色が抜け、縮れ、崩れ、そして——消えた。
たった一房。それだけのはずだった。
だが液体は毛先に留まらず、まるで毛根へ向かって潜り込むように広がり、瞬く間に頭皮全体に浸透していく。
アフロの男は顔をしかめ、額を押さえた。
「な、なんだこれ……! 熱い……いや、冷たいっ……!?」
その言葉が終わるよりも早く、彼の髪は——
泡が弾けるような無音の衝撃とともに、すべて抜け落ちた。
一本残らず。
黄金色の燭光に照らし出されたその頭は、驚くほどつるりと滑らかで、影さえ宿さなかった。
そしてそれは頭髪だけに留まらなかった。
腕の毛、顎髭、胸毛、脚の毛——視界に触れるすべての体毛が、次々と儚い煙のように消えていく。
「ひっ……ひぃあああああああああっ!!!」
その悲鳴は、石壁に反響し、鋭く長く伸びて地下全体に響いた。
まるで自分の一部が剥ぎ取られるのを理解した瞬間の絶叫だった。
ミーアは息を呑み、しかし目を逸らさなかった。
残酷ではある。だが、確かに——
確実に効果がある。
一滴でこれほど。彼女が求めていた“確実性”は、想像よりはるかに強力だった。
ミーアは小瓶の蓋をしっかり閉じ、外套の中にしまった。
「……ありがとうございました。これで……わたくし、失敗いたしませんわね」
悲鳴はまだ続いていたが、彼女はその場を静かに後にした。
背後から響く元アフロの嗚咽混じりの叫びは、やがて遠ざかり、階段を上る頃にはただの低い残響となった。
ミーアの足取りは軽くも重くもなかった。
ただ、はっきりとした確信だけが心の中に灯っていた。
——これなら、必ず復讐を遂げられる。
その瞳には、冷たい光が凛と宿っていた。
地下牢を後にした夜から、ミーアの心は静かな炎に包まれていた。
かつての悲嘆はもう微塵も残っていない。代わりにあるのは、たった一つの目的——その瞬間を確実に捉えるための冷徹な集中だった。
まず必要なのは、彼が次にサロンを訪れる日。
ミーアは情報網を使い、小姓たちに贈り物を渡し、時には女主人の噂話に紛れて巧みに聞き込みをした。やがて、一つの確かな情報が耳に届いた。
——チワワ公爵家嫡男、三日後の夕刻。
晩餐会に向けた最終身だしなみとして、サロンに予約を入れている。
ミーアの胸に、ひやりとした高揚が走った。
いよいよだ、と。
当日、表向きのミーアはいつも通り優雅で落ち着いていた。だがその内側には凍てつくような緊張があり、指先がごく僅かに震えていた。
彼女は偽名を用い、別家系の遠縁を装った簡潔な身分証と、それらしい紹介状を準備してサロンに予約を入れた。変装のために薄布のヴェールを被り、普段の髪はきつめにまとめ、あえて貴族らしからぬ落ち着いた色のドレスをまとった。
表から見れば、まったく別の令嬢。人目に触れればすぐに信じられるほどの仕上がりだ。
そして、時刻は訪れた。
サロンの扉が静かに開く。
高い天窓から落ちる白光が、部屋の空気を澄んだ銀の色に染めていた。香油と花弁の香りが混じり合い、音もなく流れる音楽が、緊張を逆に押し広げていく。
そのとき——
扉口に現れたのは、見間違えようのない姿だった。
チワワ。
かつての婚約者であり、ミーアを切り捨てた男。
彼は相変わらず優雅な外套をまとい、整い過ぎた髪を揺らしながら受付へ進む。
光に照らされたその髪は、過去と同じように手入れが行き届き、彼自身がそれを誇りとしているのが遠目にもわかるほどだった。
ミーアはヴェールの隙間から、その姿をじっと見つめた。
胸の鼓動がひどく速い。
けれど怯えてはいない。
ただ、決定の瞬間が近いことを身体が悟ってざわめいていた。
チワワは個室へ案内され、ミーアも別室へ通されたが、予約時間はほとんど同じだ。
やがて、薄い扉の向こうから、軽やかな声が聞こえた。
「ではお客様、深いリラックスのために……こちらの目隠しを。耳栓もご用意しております」
彼はサロンでのケアに絶対的な信頼を置いており、施術中は何も見ず、何も聞かない状態で横になるのが常だった。
その油断こそ、ミーアの求めた“隙”だった。
ミーアは担当の美容師に近づき、懐から小袋をそっと差し出した。
袋は思ったよりも重く、金貨の触れ合う澄んだ音がかすかに響いた。
「……何も、見なかったことにしていただけますかしら」
囁くと、美容師は一瞬だけ目を硬くし、次いで無言で小さく頷いた。
個室の空気は、緊張で張り詰めていた。
ベッドに横たわるチワワの顔は、目隠しに覆われ、耳栓によって外界と遮断されている。
彼は深く呼吸しながら、完全に無防備な姿を晒していた。
サロン特製の香油の香りに包まれ、満ち足りた眠りのような表情さえ浮かべている。
ミーアは外套の内側から、あの黒い小瓶を取り出した。
蓋を開くと、あの日と同じ、冷たい気配が指先を撫でる。
心臓が苦しいほどに高鳴る。
これが——すべての終わりであり、始まりでもある。
美容師は一歩退き、まるで儀式の立会い人のような無表情で沈黙していた。
ミーアはゆっくりとチワワの頭上に立つ。
彼は知らない。
自分を捨てた代償が、今まさに髪に触れようとしていることを。
ミーアは一度だけ深く息を吸い——その瞬間、迷いは霧のように消えた。
そして、
黒い薬を——すべて——彼の頭に、ぶっかけた。
どろりとした液体が髪を呑み込み、黒い染みが一瞬で広がる。
その音なき侵食は、すぐさま彼の毛根へ潜り込んだ。
彼はまだ、何も知らない。
だが、数秒後には——
その男の運命は、二度と元には戻らないものへと変わるのだった。
黒い液が元婚約者チワワの頭を覆い尽くした瞬間、ミーアは身体が勝手に動くほどの速度で部屋を離れた。
美容師は固まったまま何も言わない。
代わりに、チワワの喉から絞り出されるような悲鳴が、壁を震わせて響き渡った。
「なッ……あ゛ああああああああああああッ!!?!?」
その叫びが耳をつんざいた瞬間、ミーアは裏口へと走り抜けた。
長い廊下の先、スタッフ専用の階段を一気に駆け上がり、息をひそめながら上階の細い飾り窓に身を寄せる。
そこは下の施術室を、わずかな隙間から覗き込める位置だった。
指先は冷たく、心臓は痛いほど脈打っていた。
それでもミーアは、しっかりと下を見つめた。
すると——
チワワの髪は、先ほどまでの見事な艶と量を完全に失っていた。
黒い薬は彼の頭皮を容赦なく侵し、毛根はすべて溶け消え、跡形もない。
光を反射するほどつるりと滑らかで、影一つ宿さない。
そして、薬は髪だけではなく……彼の着ていた高級な衣服までもじわじわと溶かしていた。
「や、やめろッ……これは……!? なんだこれはあああッ!!」
彼は慌てふためき体を隠そうとするが、既に隠す布は一切残っていない。
全身が真っ白に、つるりとなり、毛という毛が一切存在せず、まるで殻を失った“卵”のような風貌になっていた。
チワワは息荒く立ち上がり、怒りに全身を震わせた。
「従者だッ!! 従者はどこだ!! 今すぐ来いッ!! このサロンを……このサロンをぶち壊してやる!!!」
彼が怒声を張り上げた瞬間、慌てて数名の従者が駆け込んでくる。
その姿を見た彼らは、一瞬で言葉を失った。
主人が、白い卵のような全裸の男にしか見えないのだから当然だった。
しかしチワワはそんな反応に気づく余裕もなく、怒りの赴くまま全てを破壊しようと踏み出した。
――だが、そのとき。
低く、重く響く声が室内に落ちた。
「何事だ。」
サロンの奥から現れたのは、この街でも名を知られるサロンのオーナー。
優雅な外套を纏い、動じない視線で一歩、また一歩と中へ入ってくる。
彼の胸章は高位貴族の証であり、チワワよりも遥かに爵位が上だった。
「おや……どちら様でしたかな?」
その静かな声音に、チワワは凍りついた。
目隠しのまま薬を浴びたせいで、彼にはまだ相手が誰かわかっていなかったのだ。
「わ、私だ!! チワワ公爵家の……!」
「……その振る舞い、器物破損の現行犯と見なすしかありませんな。」
オーナーの言葉は冷たかった。
従者たちは青ざめ、どう動くべきかわからず硬直する。
「や、やめろ……! 私は被害者だ! これは罠だ!!」
しかし、彼の言葉が届くより早く、衛兵隊が呼ばれた。
高位貴族の施設を破壊しようとした罪は重い。
チワワは取り押さえられ、全裸のまま連れ出されていく。
道中、見た者すべてが驚愕し、そして噂が瞬く間に広まった。
——白くつるつるに輝く“卵のような男”が捕まった、と。
その日を境に、社交界では彼をこう呼ぶようになった。
“卵男(エッグマン)”。
あらゆる毛を失い、誇りも名誉も消え失せた哀れな男として。
ミーアは上階の影からその一部始終を見届け、静かに目を閉じた。
胸の奥の何かが、ゆっくりと冷たく解けていくのを感じた。
「……終わりましたわね。」
復讐は、完璧に終わったのだ。
ミーアの唇には、わずかな微笑が浮かんでいた。
それは安堵とも冷笑ともつかぬ、長い苦しみから解放された者の表情だった。
復讐を終えた日々、ミーアは初めて心から深い安堵を覚えていた。
社交界のざわめきから、嫌な噂から、過去の屈辱から、すべてが遠ざかったように思えた。
屋敷の庭の薔薇は、春の光に柔らかく揺れ、窓辺で光を浴びる髪は、かつての悲しみとは無縁に輝いていた。
彼女は静かに微笑み、静謐な午後の一瞬を、誰にも邪魔されずに味わった。
何度も深く息を吐き、心の奥に巣食っていた怒りが、ついに霧のように消えていくのを感じた。
だが、幸せは長くは続かなかった。
ある日、豪奢な馬車で屋敷を訪れたのは、見たこともない貴族の子息だった。
背筋をまっすぐに伸ばし、目は自信に満ち、口元には得意げな微笑。
彼の名は——高分子ポリマー。
その名の通り、奇妙な存在感を放つ男であった。
彼は自分こそがこの世で最も美しいと信じ、他者の意見など一切耳に入れぬ、偏執的な自己陶酔者だった。
「わたくしの愛を受け入れていただきたい、ミーア殿。あなたこそ、この世で最も魅惑的な女性である」
そう告げられた瞬間、ミーアは静かに笑った。
胸の奥に再び、甘美で冷たい火が灯る。
——愛を手に入れるための手段。
そして、また、彼の驕慢を試す機会。
ミーアは申し出を受け入れることにした。
ただし、条件がひとつだけあった。
「……あなたの髪も、わたくしが整えることにいたしますわね」
ポリマーは一瞬目を見開いたが、すぐに自分の美しさに自信を持つあまり、快諾した。
それは、甘美な契約の始まりだった。
二人の愛は、他人の目には純粋で豪奢な恋のように映った。
庭で微笑み合い、舞踏会では腕を組み、夜の燭光に照らされながら互いの存在を確かめ合う。
しかし、その愛は、かつてミーアが経験した復讐の影なしには成り立たなかった。
やがて、ポリマーもまた、黒い薬の影響を受けることとなる。
初めは微細な変化、次に目に見える崩れ——髪は消え、頭は光を反射する白い球体のようになった。
彼の誇りも尊大な自尊も、すべてが溶けて消えた。
社交界での面目も、崇高な自意識も、ただの幻想となった。
ミーアはそれを、静かに見届けた。
胸の奥で再び冷たい満足が広がり、かつての怒りが形を変えたものの、今度は恐ろしく粛然とした計画の達成感となった。
「愚かなる粋がり屋たち……すべて、この手で終わらせるのですわ」
彼女の瞳は、穏やかな微笑とともに冷徹な光を帯びていた。
庭の薔薇は揺れ、夜の風が髪を撫でる中、彼女は確信していた。
力を持つ者、誇り高き者、他人を見下す者――すべての傲慢は、やがてこの手の中で白く滑らかな形となり、永遠に失われるのだ、と。
社交界の夜は長く、冷たく、そして恐ろしく静かだった。
その中で、ミーアは静かに微笑む。
彼女の手の中で、男たちはただ、卵のように輝き、跡形もなく消えていく。
復讐の渦が静まった後、ミーアの名は密やかに、しかし確実に、社交界の隅々に響き渡った。
人々は噂した――“白い卵のような男たちを跡形もなく消した女”――と。
その名は、彼女が姿を現すたびに、誰もが息を飲み、足を止めるようになった。
そしてやがて、表の世界の華やかさの陰で、ミーアは社交界の影の女王と呼ばれるようになった。
彼女の手の中で、権力者たちは跪き、声を震わせながら微笑みを捧げた。
金も爵位も、外交の駆け引きも、戦争の噂も――すべてはミーアの掌の上で踊った。
その影響力は、単なる恐怖ではなく、秩序となり、人々の心の中に深く刻まれた。
ミーアはその力を、己の欲望だけのために使うことはなかった。
彼女は長年の屈辱を胸に刻み、女性たちの可能性を解き放つ決意をした。
街や都市、国の制度を巧みに操り、女性の権利と地位を飛躍的に拡大させた。
学問、軍事、商業、政治――かつて男性だけのものだった権力の座に、女性たちが次々と立つようになった。
そして、国は変貌した。
もはや誰もが認める女性主導の最強ウーマン国家。
その名を、民は畏敬と畏怖を込めて呼んだ――「ミーア女王の国」。
だが、世界は黙っていなかった。
遠方の大陸、力を誇るブルドッグ将軍率いるプリンアラモード帝国は、女性が支配する国に不満を抱き、戦争を仕掛けてきた。
だが、ミーアは恐れなかった。
彼女の掌には、復讐の冷たくも確実な力があった。
戦場では、帝国軍の誇る兵も将軍の剛勇も、彼女の計略と薬の影響の前に無力となった。
戦争は、瞬く間に彼女の勝利で終わった。
ブルドッグ将軍率いる帝国は、国名をエッグ帝国へと改名させられ、ミーア女王の支配下に置かれた。
男性の傲慢は完全に抑えられ、国境の城塞にも、宮廷の帳簿にも、卵のような無力な象徴が刻まれた。
世界は恐怖と敬意の入り混じった静寂に包まれた。
そしてミーアは、自らを神の如く位置づけた。
王でもなく、女王でもなく、全てを見渡す神の視線で世界を監視する者。
力を誇り、調子に乗る男たちは、彼女の前に跪くか、永遠に消え去るかの二択しかなかった。
庭の薔薇はかつてと変わらず揺れるが、その影の下で、ミーアは微笑んだ。
冷たく、恐ろしく、美しい微笑。
世界を思い通りに動かす女神として、彼女の支配は永遠に続くことを、誰も疑わなかった。
そして、世界は静かに、しかし確実に――女王ミーアの手によって支配され、男たちは駆逐され続けた。
誰もがその影に怯えながら日々を生きる世界となったのだ。
しかしその美しさが祝福となるどころか、彼女と婚約者の間に溝を作るとは、ミーアは思いも寄らなかった。破談の知らせは冬の朝に届いた。届けに来た使者の顔は陰鬱で、言葉は簡潔だった。「身辺の好奇を避けるため、婚約を解消する」——理由は曖昧に濁され、けれども周囲の囁きは鋭かった。噂は即座に形を取り、彼女の「美しい髪」が原因だと囁かれた。まるで彼女の存在そのものが、贖い難い罪であるかのように。
初めの数日は、ミーアの世界が色を失った。朝夕に通われる館の広間は、以前なら輝いて見えたろう光沢を失い、家具の木目は彼女のため息の重さを吸い取るように寂しげだった。彼女は窓辺に座り、指先でいつもの癖のように髪を梳きながら、過ぎ去った時間を何度も反芻した。婚約者の笑い声、二人で交わした冗談、そして最後に交わした言葉のひとかけら——それらはすべて、今となっては遠い音でしかなかった。胸の奥にぽっかりと空いた穴が、冷たい風と共に響いた。
やがて、悲しみは鈍い疼きとなり、疼きはいつのまにか思考へと姿を変えた。ミーアは自問した。自分は何を失ったのか、何を取り戻したいのか。怒りは最初は幼い火の粉のように小さく、彼女の内側でぱちぱちと音を立てただけだったが、その火は静かに燃え広がっていった。破談のただ中で生じた屈辱、周囲の視線、そしてあの「理由」の不条理さ——すべてが彼女の中で混ざり合い、復讐という形を模索し始める。
復讐の思考は、彼女の理性と感情のあわいで静かに育った。ミーアは復讐そのものを美化するつもりはなかった。だが屈辱に対する応報を望む心は、誰にでも偶発的に芽生えるものだ。彼女はまず冷静に事実を整理した。相手は公爵家の一人息子であり、社交界に顔が広い。彼の関心は外見にも向けられており、自分の体面を保つための習慣を持っていた。人前で見苦しく振る舞うことは、彼にとって何より忌避すべきことである。
ある晩、ミーアは古い舞踏会の写真を見返していて、ふと気づく。婚約者が常に整えていたもの——それは髪だった。彼は外見にほとんど無頓着そうに見えて、実は細やかな手入れを怠らない男だった。貴族の嗜みとしての散髪や整髪は、彼にとって自らの立場を守るための儀礼だったのだろう。ミーアの心に、ある思索が滑り込んだ。人は、自分の誇りと結びついたものに最も敏感であり、それを損なわれることを極端に嫌う——ならば、彼が依拠する日常の痕跡に目をつければ、撃ち得るかもしれない。
記憶の断片が繋がっていく。彼が定期的に通っていたというあのサロンのこと。街角の白い柱、扉脇に置かれた鉄の花器、窓辺に並ぶ香水瓶の軋む音。彼はそこで手入れを受け、鏡の中で自らを整え、社交の場に出て行った。ミーアは想像した。夜の帳が降りた後のサロン、残された椅子と落ちた毛先、そして誰もいない鏡に映る空虚な肩越しの自分——その風景は、彼女の怒りを現実へと誘うように見えた。
だが、復讐を思いつくことと、それを実行することはまったく別の次元だ。ミーアは慎重だった。彼女の内面には、自分が悪に染まることを拒む一線も残っていた。だが同時に、あまりにも理不尽な別離をただ受け入れることもできなかった。感情と道徳の間で揺れる心の中、あのサロンがひとつの軸として立ち上がった。もしも、相手の誇りに傷をつける手段があるとしたら——そしてそれが彼の誇りを形作る“髪”に関係するのなら——それは復讐の餌食として慎重に検討に値するのではないか。
ミーアは窓の外に目をやった。街灯が落ち葉の上に繊細な輪を描き、冬の空気が頬を刺す。ひと呼吸おいて、彼女は自分の手のひらを見つめる。その掌は震えてはいなかった。静かに、しかし確固たる声で彼女は自分に言い聞かせた。「何をしても、私は私だ」と。だが同時に思考の片隅で、ある冷たい可能性が形を取り始めるのを止められなかった――毛根を壊すという薬品の存在を仄めかす噂を、彼が通うそのサロンの空間に用いることができるかもしれない、という考えである。
その考えはまだ漠然としており、実行の輪郭は何も示していなかった。ただ、彼女の胸の中で小さな石が落ち、それが波紋を広げているだけだった。ミーアは深く息を吐き、鏡の前で自分の髪を一度手で撫でた。髪は変わらず柔らかく、光を受けて震えていた。彼女の瞳には、悲しみと復讐心とが混じった不思議な光が宿っていた。ここまで考えが及んだところで、彼女は静かに唇を噛み締めた。復讐の可能性――それは、もはや単なる空想ではなかった。
ミーアの胸の内に芽生えた復讐の影は、静かに、しかし確かな輪郭を帯びていった。彼女はある日、机の上に広げた帳面を閉じ、深く息を吸った。必要なのは——“毛根を破壊する薬”。そんなものがこの世に本当に存在するのか、最初は半信半疑だった。だが人々の間に流れる噂や、古い薬師が残した禁断の文献には、時折その名がぼんやりと記されていることがあった。
ミーアは考えた末、表の世界ではなく裏の街へ足を踏み入れることを決意した。貴族である彼女の姿は目立つ。ゆえに、外套で身を隠し、髪は布で覆い、薄暗い街路地へと溶け込むように歩いた。
夜の空気は汚れた鉄の味を含み、濁ったランタンの光が濡れた石畳に反射していた。闇市へ通じるスラムは、昼でも薄暗いが、夜になると別の息遣いを持ち始める。物乞いが膝を抱え、武器を抱えた男たちが煙草の煙を吐き、誰もが誰かを警戒しながら歩く世界。ミーアは足音を忍ばせるたび、心の奥で微かな震えを覚えたが、それでも前に進んだ。
彼女は、噂を頼りに薬師や密売人、そして黒ずんだ屋台を巡り、少しずつ情報を集めた。「毛根を壊す薬」と言えば皆、眉をひそめたり、背を向けたりした。危険すぎるのだ。人を狂わせ、人生を奪う薬剤——表の世界では存在そのものが否定されている。
しかし、諦めないミーアの耳に、ついにひとつの声が届いた。それは、目の奥に獣じみた光を宿した薬の仲買人だった。
「……あるには、あるさ。お嬢さんのような甘い顔には似合わん代物だがな」
ミーアは唇を結び、薄暗い商談用の小部屋へ通された。机の上には油紙に包まれた小瓶が置かれている。瓶の中身は黒く濁り、底からゆっくりと煙のような靄が立ち上る。
「法外な値段だぜ。普通の薬草屋三軒、まるごと買えるほどの金がいる」
提示された額を聞いた瞬間、ミーアの胸は冷たく沈んだ。貴族の娘であるとはいえ、自由に使える財は限られている。まして破談で実家が世間体に敏感になっている今、莫大な金を持ち出すことなど到底できない。
しかし、ここで引き下がるわけにもいかなかった。
ミーアはそこで、一つの顔を思い出した。
——以前、夜会でしつこいほど彼女に言い寄ってきた伯爵家の三男。金は腐るほど持っており、放蕩と贅沢で知られる男。彼はミーアにぞっこんで、ほんの一言の笑みですら宝石のように受け取る愚かさを持っていた。
「……あの方を、利用するしかありませんわね」
彼女はひそかに呟き、翌日、晴れやかな顔で伯爵家の別邸を訪れた。男は驚くほど簡単に彼女を迎え入れ、彼女のお願いに酔狂なほど喜んだ。
「危険が伴うのだと説明した上で」——いや、説明はほんの一部だけ。
「化粧品の珍しい原料を探しているのですの。どうしても手に入れたいものがあって……」と、わずかに涙を滲ませてみせれば、男はすぐに財布を開いた。
そして二日後、例の小瓶はミーアの手の中にあった。
彼女はそれを静かに見つめた。瓶を傾けると、とろりとした黒い液がゆっくりと揺れ、まるで生き物のように光を吸い込みながら蠢いた。胸の奥に不安が走る。それでも、彼女は手を離さなかった。
「……本当に、大丈夫かしら。いえ、確かめなくては」
薬の真価は試さねばならない。誤って自分が使えば取り返しがつかない。敵に使うにも慎重さがいる。
ミーアは公爵家の古く薄暗い地下牢を思い出した。かつて反逆罪で捕らえられた囚人たちが数名、条件付きで「実験材料」として王家に差し出されていたことを、彼女は幼い頃に聞いたことがあった。世間には隠されたままのその地下施設は、ほとんど誰も存在を知らず、監視する兵も最低限だ。
夜、彼女は外套をまとい、執事の目を欺き、静かに屋敷を抜け出した。風は冷たいが、心は奇妙なほど澄んでいた。
灯りの少ない廊下を歩きながら、ミーアは胸に手を当てた。震えてはいない。
「試す価値はあるはず……。これが使えるかどうか、その判断をしなければ」
地下牢の扉が鈍い音を立てて開き、薄暗い石室の奥、囚人が一人、鉄格子の向こうでうずくまっている。かすれた息と、湿った土の匂い。
ミーアは一歩進み、黒い小瓶を掌に乗せた。
彼女の瞳には冷たい決意が燃えていた。
地下牢の空気は、湿った石と錆びた鉄の匂いが混じり合い、ひどく重かった。ミーアの持つ燭台の灯りがゆらゆらと揺れ、その明かりの端で囚人たちの影が細長く伸びては縮んだ。
彼らは皆、長い拘束生活の中で肌も心も疲れ切っていたが、その中にひときわ異質な男がいた。
——アフロの男。
彼の髪は鉄格子の向こう側で黒い雲のように広がり、その存在だけで空気すら押しのけるほどの圧があった。面持ちは荒んでいるが、あの髪だけはこの暗闇の中で妙な生命力を放っていた。
ミーアは小さな息をつき、手の中の黒い薬瓶を確かめた。彼女の指先は冷たかったが、決意は揺らいでいない。
「失礼いたします……少し、試させていただきますね」
柔らかな声に囚人は怪訝そうに顔を上げた。
「……なんだ、嬢ちゃん。俺に何をするつもりだ」
ミーアは言葉を返す代わりに、瓶の蓋をそっと開いた。中から立ち上る黒い靄は、まるで生き物の吐息のようで、彼女の頬をかすめた瞬間に冷たい痛みを残した。
一滴。
ただそれだけで、どれほどの力を持つのかを確かめればいい。
ミーアは鉄格子に近づき、アフロの房のひとかけをそっと摘んで、薬を一滴だけ落とした。
その瞬間——
「……っ!?」
音がしたわけではなかった。しかしアフロは、まるで電撃を受けたように体を震わせた。
黒い滴は、触れた毛先を食い尽くすかのように広がり、みるみるうちに髪の色が抜け、縮れ、崩れ、そして——消えた。
たった一房。それだけのはずだった。
だが液体は毛先に留まらず、まるで毛根へ向かって潜り込むように広がり、瞬く間に頭皮全体に浸透していく。
アフロの男は顔をしかめ、額を押さえた。
「な、なんだこれ……! 熱い……いや、冷たいっ……!?」
その言葉が終わるよりも早く、彼の髪は——
泡が弾けるような無音の衝撃とともに、すべて抜け落ちた。
一本残らず。
黄金色の燭光に照らし出されたその頭は、驚くほどつるりと滑らかで、影さえ宿さなかった。
そしてそれは頭髪だけに留まらなかった。
腕の毛、顎髭、胸毛、脚の毛——視界に触れるすべての体毛が、次々と儚い煙のように消えていく。
「ひっ……ひぃあああああああああっ!!!」
その悲鳴は、石壁に反響し、鋭く長く伸びて地下全体に響いた。
まるで自分の一部が剥ぎ取られるのを理解した瞬間の絶叫だった。
ミーアは息を呑み、しかし目を逸らさなかった。
残酷ではある。だが、確かに——
確実に効果がある。
一滴でこれほど。彼女が求めていた“確実性”は、想像よりはるかに強力だった。
ミーアは小瓶の蓋をしっかり閉じ、外套の中にしまった。
「……ありがとうございました。これで……わたくし、失敗いたしませんわね」
悲鳴はまだ続いていたが、彼女はその場を静かに後にした。
背後から響く元アフロの嗚咽混じりの叫びは、やがて遠ざかり、階段を上る頃にはただの低い残響となった。
ミーアの足取りは軽くも重くもなかった。
ただ、はっきりとした確信だけが心の中に灯っていた。
——これなら、必ず復讐を遂げられる。
その瞳には、冷たい光が凛と宿っていた。
地下牢を後にした夜から、ミーアの心は静かな炎に包まれていた。
かつての悲嘆はもう微塵も残っていない。代わりにあるのは、たった一つの目的——その瞬間を確実に捉えるための冷徹な集中だった。
まず必要なのは、彼が次にサロンを訪れる日。
ミーアは情報網を使い、小姓たちに贈り物を渡し、時には女主人の噂話に紛れて巧みに聞き込みをした。やがて、一つの確かな情報が耳に届いた。
——チワワ公爵家嫡男、三日後の夕刻。
晩餐会に向けた最終身だしなみとして、サロンに予約を入れている。
ミーアの胸に、ひやりとした高揚が走った。
いよいよだ、と。
当日、表向きのミーアはいつも通り優雅で落ち着いていた。だがその内側には凍てつくような緊張があり、指先がごく僅かに震えていた。
彼女は偽名を用い、別家系の遠縁を装った簡潔な身分証と、それらしい紹介状を準備してサロンに予約を入れた。変装のために薄布のヴェールを被り、普段の髪はきつめにまとめ、あえて貴族らしからぬ落ち着いた色のドレスをまとった。
表から見れば、まったく別の令嬢。人目に触れればすぐに信じられるほどの仕上がりだ。
そして、時刻は訪れた。
サロンの扉が静かに開く。
高い天窓から落ちる白光が、部屋の空気を澄んだ銀の色に染めていた。香油と花弁の香りが混じり合い、音もなく流れる音楽が、緊張を逆に押し広げていく。
そのとき——
扉口に現れたのは、見間違えようのない姿だった。
チワワ。
かつての婚約者であり、ミーアを切り捨てた男。
彼は相変わらず優雅な外套をまとい、整い過ぎた髪を揺らしながら受付へ進む。
光に照らされたその髪は、過去と同じように手入れが行き届き、彼自身がそれを誇りとしているのが遠目にもわかるほどだった。
ミーアはヴェールの隙間から、その姿をじっと見つめた。
胸の鼓動がひどく速い。
けれど怯えてはいない。
ただ、決定の瞬間が近いことを身体が悟ってざわめいていた。
チワワは個室へ案内され、ミーアも別室へ通されたが、予約時間はほとんど同じだ。
やがて、薄い扉の向こうから、軽やかな声が聞こえた。
「ではお客様、深いリラックスのために……こちらの目隠しを。耳栓もご用意しております」
彼はサロンでのケアに絶対的な信頼を置いており、施術中は何も見ず、何も聞かない状態で横になるのが常だった。
その油断こそ、ミーアの求めた“隙”だった。
ミーアは担当の美容師に近づき、懐から小袋をそっと差し出した。
袋は思ったよりも重く、金貨の触れ合う澄んだ音がかすかに響いた。
「……何も、見なかったことにしていただけますかしら」
囁くと、美容師は一瞬だけ目を硬くし、次いで無言で小さく頷いた。
個室の空気は、緊張で張り詰めていた。
ベッドに横たわるチワワの顔は、目隠しに覆われ、耳栓によって外界と遮断されている。
彼は深く呼吸しながら、完全に無防備な姿を晒していた。
サロン特製の香油の香りに包まれ、満ち足りた眠りのような表情さえ浮かべている。
ミーアは外套の内側から、あの黒い小瓶を取り出した。
蓋を開くと、あの日と同じ、冷たい気配が指先を撫でる。
心臓が苦しいほどに高鳴る。
これが——すべての終わりであり、始まりでもある。
美容師は一歩退き、まるで儀式の立会い人のような無表情で沈黙していた。
ミーアはゆっくりとチワワの頭上に立つ。
彼は知らない。
自分を捨てた代償が、今まさに髪に触れようとしていることを。
ミーアは一度だけ深く息を吸い——その瞬間、迷いは霧のように消えた。
そして、
黒い薬を——すべて——彼の頭に、ぶっかけた。
どろりとした液体が髪を呑み込み、黒い染みが一瞬で広がる。
その音なき侵食は、すぐさま彼の毛根へ潜り込んだ。
彼はまだ、何も知らない。
だが、数秒後には——
その男の運命は、二度と元には戻らないものへと変わるのだった。
黒い液が元婚約者チワワの頭を覆い尽くした瞬間、ミーアは身体が勝手に動くほどの速度で部屋を離れた。
美容師は固まったまま何も言わない。
代わりに、チワワの喉から絞り出されるような悲鳴が、壁を震わせて響き渡った。
「なッ……あ゛ああああああああああああッ!!?!?」
その叫びが耳をつんざいた瞬間、ミーアは裏口へと走り抜けた。
長い廊下の先、スタッフ専用の階段を一気に駆け上がり、息をひそめながら上階の細い飾り窓に身を寄せる。
そこは下の施術室を、わずかな隙間から覗き込める位置だった。
指先は冷たく、心臓は痛いほど脈打っていた。
それでもミーアは、しっかりと下を見つめた。
すると——
チワワの髪は、先ほどまでの見事な艶と量を完全に失っていた。
黒い薬は彼の頭皮を容赦なく侵し、毛根はすべて溶け消え、跡形もない。
光を反射するほどつるりと滑らかで、影一つ宿さない。
そして、薬は髪だけではなく……彼の着ていた高級な衣服までもじわじわと溶かしていた。
「や、やめろッ……これは……!? なんだこれはあああッ!!」
彼は慌てふためき体を隠そうとするが、既に隠す布は一切残っていない。
全身が真っ白に、つるりとなり、毛という毛が一切存在せず、まるで殻を失った“卵”のような風貌になっていた。
チワワは息荒く立ち上がり、怒りに全身を震わせた。
「従者だッ!! 従者はどこだ!! 今すぐ来いッ!! このサロンを……このサロンをぶち壊してやる!!!」
彼が怒声を張り上げた瞬間、慌てて数名の従者が駆け込んでくる。
その姿を見た彼らは、一瞬で言葉を失った。
主人が、白い卵のような全裸の男にしか見えないのだから当然だった。
しかしチワワはそんな反応に気づく余裕もなく、怒りの赴くまま全てを破壊しようと踏み出した。
――だが、そのとき。
低く、重く響く声が室内に落ちた。
「何事だ。」
サロンの奥から現れたのは、この街でも名を知られるサロンのオーナー。
優雅な外套を纏い、動じない視線で一歩、また一歩と中へ入ってくる。
彼の胸章は高位貴族の証であり、チワワよりも遥かに爵位が上だった。
「おや……どちら様でしたかな?」
その静かな声音に、チワワは凍りついた。
目隠しのまま薬を浴びたせいで、彼にはまだ相手が誰かわかっていなかったのだ。
「わ、私だ!! チワワ公爵家の……!」
「……その振る舞い、器物破損の現行犯と見なすしかありませんな。」
オーナーの言葉は冷たかった。
従者たちは青ざめ、どう動くべきかわからず硬直する。
「や、やめろ……! 私は被害者だ! これは罠だ!!」
しかし、彼の言葉が届くより早く、衛兵隊が呼ばれた。
高位貴族の施設を破壊しようとした罪は重い。
チワワは取り押さえられ、全裸のまま連れ出されていく。
道中、見た者すべてが驚愕し、そして噂が瞬く間に広まった。
——白くつるつるに輝く“卵のような男”が捕まった、と。
その日を境に、社交界では彼をこう呼ぶようになった。
“卵男(エッグマン)”。
あらゆる毛を失い、誇りも名誉も消え失せた哀れな男として。
ミーアは上階の影からその一部始終を見届け、静かに目を閉じた。
胸の奥の何かが、ゆっくりと冷たく解けていくのを感じた。
「……終わりましたわね。」
復讐は、完璧に終わったのだ。
ミーアの唇には、わずかな微笑が浮かんでいた。
それは安堵とも冷笑ともつかぬ、長い苦しみから解放された者の表情だった。
復讐を終えた日々、ミーアは初めて心から深い安堵を覚えていた。
社交界のざわめきから、嫌な噂から、過去の屈辱から、すべてが遠ざかったように思えた。
屋敷の庭の薔薇は、春の光に柔らかく揺れ、窓辺で光を浴びる髪は、かつての悲しみとは無縁に輝いていた。
彼女は静かに微笑み、静謐な午後の一瞬を、誰にも邪魔されずに味わった。
何度も深く息を吐き、心の奥に巣食っていた怒りが、ついに霧のように消えていくのを感じた。
だが、幸せは長くは続かなかった。
ある日、豪奢な馬車で屋敷を訪れたのは、見たこともない貴族の子息だった。
背筋をまっすぐに伸ばし、目は自信に満ち、口元には得意げな微笑。
彼の名は——高分子ポリマー。
その名の通り、奇妙な存在感を放つ男であった。
彼は自分こそがこの世で最も美しいと信じ、他者の意見など一切耳に入れぬ、偏執的な自己陶酔者だった。
「わたくしの愛を受け入れていただきたい、ミーア殿。あなたこそ、この世で最も魅惑的な女性である」
そう告げられた瞬間、ミーアは静かに笑った。
胸の奥に再び、甘美で冷たい火が灯る。
——愛を手に入れるための手段。
そして、また、彼の驕慢を試す機会。
ミーアは申し出を受け入れることにした。
ただし、条件がひとつだけあった。
「……あなたの髪も、わたくしが整えることにいたしますわね」
ポリマーは一瞬目を見開いたが、すぐに自分の美しさに自信を持つあまり、快諾した。
それは、甘美な契約の始まりだった。
二人の愛は、他人の目には純粋で豪奢な恋のように映った。
庭で微笑み合い、舞踏会では腕を組み、夜の燭光に照らされながら互いの存在を確かめ合う。
しかし、その愛は、かつてミーアが経験した復讐の影なしには成り立たなかった。
やがて、ポリマーもまた、黒い薬の影響を受けることとなる。
初めは微細な変化、次に目に見える崩れ——髪は消え、頭は光を反射する白い球体のようになった。
彼の誇りも尊大な自尊も、すべてが溶けて消えた。
社交界での面目も、崇高な自意識も、ただの幻想となった。
ミーアはそれを、静かに見届けた。
胸の奥で再び冷たい満足が広がり、かつての怒りが形を変えたものの、今度は恐ろしく粛然とした計画の達成感となった。
「愚かなる粋がり屋たち……すべて、この手で終わらせるのですわ」
彼女の瞳は、穏やかな微笑とともに冷徹な光を帯びていた。
庭の薔薇は揺れ、夜の風が髪を撫でる中、彼女は確信していた。
力を持つ者、誇り高き者、他人を見下す者――すべての傲慢は、やがてこの手の中で白く滑らかな形となり、永遠に失われるのだ、と。
社交界の夜は長く、冷たく、そして恐ろしく静かだった。
その中で、ミーアは静かに微笑む。
彼女の手の中で、男たちはただ、卵のように輝き、跡形もなく消えていく。
復讐の渦が静まった後、ミーアの名は密やかに、しかし確実に、社交界の隅々に響き渡った。
人々は噂した――“白い卵のような男たちを跡形もなく消した女”――と。
その名は、彼女が姿を現すたびに、誰もが息を飲み、足を止めるようになった。
そしてやがて、表の世界の華やかさの陰で、ミーアは社交界の影の女王と呼ばれるようになった。
彼女の手の中で、権力者たちは跪き、声を震わせながら微笑みを捧げた。
金も爵位も、外交の駆け引きも、戦争の噂も――すべてはミーアの掌の上で踊った。
その影響力は、単なる恐怖ではなく、秩序となり、人々の心の中に深く刻まれた。
ミーアはその力を、己の欲望だけのために使うことはなかった。
彼女は長年の屈辱を胸に刻み、女性たちの可能性を解き放つ決意をした。
街や都市、国の制度を巧みに操り、女性の権利と地位を飛躍的に拡大させた。
学問、軍事、商業、政治――かつて男性だけのものだった権力の座に、女性たちが次々と立つようになった。
そして、国は変貌した。
もはや誰もが認める女性主導の最強ウーマン国家。
その名を、民は畏敬と畏怖を込めて呼んだ――「ミーア女王の国」。
だが、世界は黙っていなかった。
遠方の大陸、力を誇るブルドッグ将軍率いるプリンアラモード帝国は、女性が支配する国に不満を抱き、戦争を仕掛けてきた。
だが、ミーアは恐れなかった。
彼女の掌には、復讐の冷たくも確実な力があった。
戦場では、帝国軍の誇る兵も将軍の剛勇も、彼女の計略と薬の影響の前に無力となった。
戦争は、瞬く間に彼女の勝利で終わった。
ブルドッグ将軍率いる帝国は、国名をエッグ帝国へと改名させられ、ミーア女王の支配下に置かれた。
男性の傲慢は完全に抑えられ、国境の城塞にも、宮廷の帳簿にも、卵のような無力な象徴が刻まれた。
世界は恐怖と敬意の入り混じった静寂に包まれた。
そしてミーアは、自らを神の如く位置づけた。
王でもなく、女王でもなく、全てを見渡す神の視線で世界を監視する者。
力を誇り、調子に乗る男たちは、彼女の前に跪くか、永遠に消え去るかの二択しかなかった。
庭の薔薇はかつてと変わらず揺れるが、その影の下で、ミーアは微笑んだ。
冷たく、恐ろしく、美しい微笑。
世界を思い通りに動かす女神として、彼女の支配は永遠に続くことを、誰も疑わなかった。
そして、世界は静かに、しかし確実に――女王ミーアの手によって支配され、男たちは駆逐され続けた。
誰もがその影に怯えながら日々を生きる世界となったのだ。
16
この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説

処刑前夜に逃亡した悪役令嬢、五年後に氷の公爵様に捕まる〜冷徹旦那様が溺愛パパに豹変しましたが私の抱いている赤ちゃん実は人生2周目です〜
放浪人
恋愛
「処刑されるなんて真っ平ごめんです!」 無実の罪で投獄された悪役令嬢レティシア(中身は元社畜のアラサー日本人)は、処刑前夜、お腹の子供と共に脱獄し、辺境の田舎村へ逃亡した。 それから五年。薬師として穏やかに暮らしていた彼女のもとに、かつて自分を冷遇し、処刑を命じた夫――「氷の公爵」アレクセイが現れる。 殺される!と震えるレティシアだったが、再会した彼は地面に頭を擦り付け、まさかの溺愛キャラに豹変していて!?
「愛しているレティシア! 二度と離さない!」 「(顔が怖いです公爵様……!)」
不器用すぎて顔が怖い旦那様の暴走する溺愛。 そして、二人の息子であるシオン(1歳)は、実は前世で魔王を倒した「英雄」の生まれ変わりだった! 「パパとママは僕が守る(物理)」 最強の赤ちゃんが裏で暗躍し、聖女(自称)の陰謀も、帝国の侵略も、古代兵器も、ガラガラ一振りで粉砕していく。

【完】今流行りの婚約破棄に婚約者が乗っかり破棄してきました!
さこの
恋愛
お前とは婚約を破棄する! と高々と宣言する婚約者様。そうですね。今流行っていますものね。愛のない結婚はしたくない! というやつでわすわね。
笑顔で受けようかしら
……それとも泣いて縋る?
それではでは後者で! 彼は単純で自分に酔っているだけで流行りに乗っただけですもの。
婚約破棄も恐らく破棄する俺カッコいい! くらいの気持ちのはず! なのでか弱いフリしてこちらから振ってあげましょう!
全11話です。執筆済み
ホットランキング入りありがとうございます
2021/09/07(* ᴗ ᴗ)

『お前とは結婚できない』と婚約破棄されたので、隣国の王に嫁ぎます
ほーみ
恋愛
春の宮廷は、いつもより少しだけざわめいていた。
けれどその理由が、わたし——エリシア・リンドールの婚約破棄であることを、わたし自身が一番よく理解していた。
「エリシア、君とは結婚できない」
王太子ユリウス殿下のその一言は、まるで氷の刃のように冷たかった。
——ああ、この人は本当に言ってしまったのね。

婚約破棄された令嬢、なぜか王族全員から求婚されています
ゆっこ
恋愛
婚約破棄の宣言が響いた瞬間、あたりの空気が凍りついた。
「――リリアーナ・フォン・クレメンス。お前との婚約は、ここで破棄する!」
王太子アーロン殿下の声が、舞踏会場に響き渡る。
淡い金髪を後ろでまとめ、誇らしげな顔で私を見下ろしている彼の隣には、黒髪の令嬢――男爵家の娘であるセレナが、哀れみを含んだ目をこちらに向けていた。
……ああ、これ。よくあるやつだ。
舞踏会の場で公開断罪して、庶民出の恋人を正当化するという、古今東西どこにでもある茶番。
「殿下、理由をお伺いしても?」

【完結】転生令嬢が、オレの殿下を"ざまあ"しようなんて百年早い!〜"ざまあ王子"の従者ですが、やり返します〜
海崎凪斗
恋愛
公爵令嬢ロベリアは、聖女への嫌がらせを理由に婚約破棄された――はずだった。だが夜会の席、第二王子が「冤罪だった」と声を上げたことで、空気は一変する。
けれど第一王子の従者・レンは言う。
「いや?冤罪なんかじゃない。本当に嫌がらせはあったんだよ」「オレの殿下を"ざまあ王子"にしようなんて、百年早い!」
※ざまぁ系ではありますが、"ざまぁされそうな王子の従者が、それを阻止して悪役令嬢気取りの転生者をざまぁし返す話"です。主従モノに近いので、ご注意ください。
プロローグ+前後編で完結。
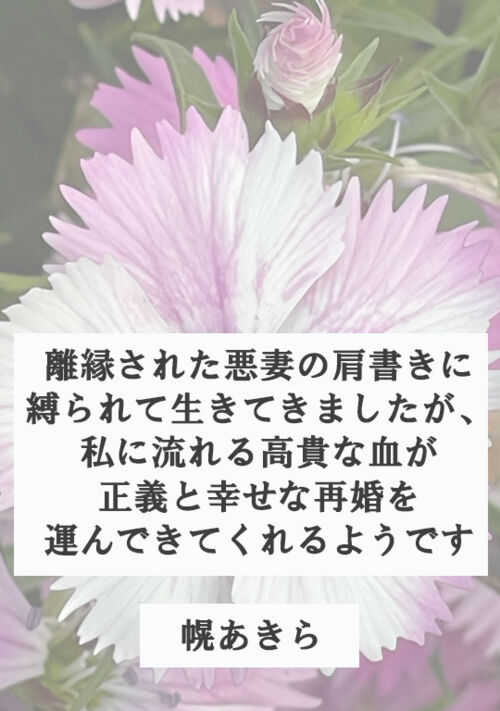
離縁された悪妻の肩書きに縛られて生きてきましたが、私に流れる高貴な血が正義と幸せな再婚を運んできてくれるようです
幌あきら
恋愛
【異世界恋愛・虐げられた嫁・ハピエン・ざまぁモノ・クズな元夫】 (※完結保証)
ハンナは離縁された悪妻のレッテルを貼られていた。理由は嫁ぎ先のマクリーン子爵家の財産に手を付け、政治犯を匿ったからだという。
一部は事実だったが、それにはハンナなりの理由がちゃんとあった。
ハンナにそれでも自分を大切にしてくれた人への感謝を忘れず健気に暮らしていたのだが、今度は元夫が、「新しい妻が欲しがるから」という理由で、ハンナが皇帝殿下から賜った由緒正しい指輪を奪っていってしまった。
しかし、これには皇帝殿下がブチ切れた!
皇帝殿下がこの指輪を私に授けたのには意味があったのだ。
私に流れるかつての偉大な女帝の血。
女帝に敬意を表さない者に、罰が下される――。
短め連載です(3万字程度)。設定ゆるいです。
お気軽に読みに来ていただけたらありがたいです!!
他サイト様にも投稿しております。

婚約破棄されたので、隠していた古代魔法で国を救ったら、元婚約者が土下座してきた。けどもう遅い。
er
恋愛
侯爵令嬢の前で婚約破棄された平凡な男爵令嬢エレナ。
しかし彼女は古代魔法の使い手で、3年間影から婚約者を支えていた恩人だった!
王国を救い侯爵位を得た彼女に、没落した元婚約者が土下座するが「もう遅い」。

【完結】魔力の見えない公爵令嬢は、王国最強の魔術師でした
er
恋愛
「魔力がない」と婚約破棄された公爵令嬢リーナ。だが真実は逆だった――純粋魔力を持つ規格外の天才魔術師! 王立試験で元婚約者を圧倒し首席合格、宮廷魔術師団長すら降参させる。王宮を救う活躍で副団長に昇進、イケメン公爵様からの求愛も!? 一方、元婚約者は没落し後悔の日々……。見る目のなかった男たちへの完全勝利と、新たな恋の物語。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















