258 / 496
第三章 クラス丸ごと異世界転生!? 追放された野獣が進む、復讐の道は怒りのデスロード!
3-58.クトリア議会議長、レイフィアス・ケラー「……頭が痛い……」
しおりを挟む在原秀美。それがアルバの前世における名前だと言う。
「修学旅行の引率をしていた、新任の副担任……。そして同じ飛行機には私が担当していたクラスの生徒たちが乗っていた。多くは、私同様に“辺土の老人”によりこの世界へと生まれ変わりをさせられている」
「あなたが……?」
その飛行機の機内でか、或いは“辺土の老人”のところでか、面識があったのだろうテレンスがそう言う。
「テレンス殿がこの世界で“目覚めた”ばかりの少なくない元生徒たちの手助けをしてくれていたらしいことは既に調べてある。そうなのだろう?」
「ええ、まあ……そうですね。それが本当の意味で彼らの“助け”になれていたのか───今でも疑問です。
ましてその“辺土の老人”とやらの目論見を知った今では、あるいは私の行いは彼らをより混沌とした破滅へと向かわせてしまったのではないかと……その様にも思えます」
彼らが前世の記憶に目覚めたのも、やはり一度この世界での死、または死に瀕する危機を経験した際に……と言うことらしい。その辺は僕やガンボン、またはJBやイベンダー達と変わらない。
そして王国軍によるクトリア王都解放の戦いの場は、まさにそういう「死、または死に瀕する危機」を経験する者が大量に居た場面で、そこでアルバの元生徒たちの多くが“目覚め”た……。
「───元生徒……? いや、まさかそいつらが……」
不意にそうイベンダーが口を挟むと、
「ああ、そうだ。“三悪”───ネフィル、ヴィオレタ、クーク達は私の元生徒であり、そして私の血によって魔人 となった者達だ」
僕を含めた全員に衝撃の走る告白。
僕が“三悪”について知っていることなんて、プレイゼスでやってた歌劇の内容と大差ない。言うなれば“物語化された事実”。
けれども、JBやイベンダーは“三悪”たちと直接相対し戦っている。この告白に対する衝撃度はかなり違っているはずだ。
「……いや、そうだったか。すまん」
「私に謝る必要はないし、彼らの死に対して君らが負うべき責はない。それに……私が今したいのは、そういう“過去の話”ではなく、“これからの話”だ。
つまり、まだ生きている私の元生徒達のうち何人かが、何らかの形で“辺土の老人”の思惑に沿って動いていると思われることだ───当人が望むと望まざると、な」
アルバの前世における元生徒達。
彼らについてのこの世界での情報……ただし六年は前になるのものについてはテレンスが詳しかった。
魔人だった者達の他にも、 犬獣人、猫獣人、犀人、猿獣人、猪人、空人といった獣人種に生まれ変わっていた者達も多いという。
ただし彼の持っている情報では、その後については殆ど分かって居ない。
分かっている僅かな情報には、彼らの中の一部はリカトリジオス軍と合流したらしいと言うことぐらいだ。
「リカトリジオス軍については王国でも警戒はしています。
クトリアの駐屯軍の目的も、その半分はリカトリジオス軍の勢力への牽制の意味合いも強いです。
彼らはこれまでの犬獣人部族と異なり、帝国流の軍編成と運用を取り入れています。
元々集団戦に強く、身体的に我々帝国人を上回る彼らが、完璧な帝国流の軍を動かせるようになれば、それは大きな脅威となりうる───そう主張する者も居ます」
外交特使らしいと言うべきか、慎重に言葉を選んでのその言に、
「ふーんむ……。その言い方だと、お前さんはもう少し違う見解を持ってそうだな」
と、イベンダー。それにさらに返して、
「───私と、一部の者達の見解としては、彼らは“脅威となりうる”勢力ではありません。
既に十分な脅威です」
と断言。
「そいつは……王国にとってか? それともクトリアにとってか?」
身を乗り出しつつそう聞くのは“キング”。その問いへの答えはやはり予想通りに、
「その、どちらにとっても───です」
ここで、テレンスは再び悩ましげに表情を曇らせ、それからある種の覚悟を決めたようにして向き直り、
「───本来なら……これは今の私の立場で言って良いことではありません。特にこのような場では。
しかし……この“前世”のこと。そして“辺土の老人”の思惑のこと……。それらを加味した上で、この事を伝えます」
改めてそう向き直りつつ、僕へと語りかける。
「レイフ。元老院では大きく二つに意見が割れています。
その理由として、やはりリカトリジオス軍への脅威論も含まれています」
……ああ、やはりそこは、そう来るか。
「一つは、クトリア共和国との同盟関係を強化し、リカトリジオス軍に備えると言う論。
もう一つは……」
「再びクトリア王都解放戦を行い、今度こそクトリア全土を実行支配し、王無きクトリアを完全に領土化してリカトリジオス軍へと備える……という強硬論ですね」
「───はい」
テレンスとしては今の告白、下手をすれば地位どころか首すら飛ばされ兼ねない危険なもの。
それを会って間もない僕や、アルバ含めたクトリアの住人の前で口にするのはかなりの賭けだろう。
「───なる程。つまりお前さん……いや、お前さんの後ろにいる者は、同盟派……と言うことか」
「……はい」
イベンダーのその即座の切り返しに、まるで動じもせず返すテレンス。
「んん? おっさん、そりゃどうしてだ?」
「でなきゃ今ここでその話を持ち出す意味がない。
強硬派が居るというカードをちらつかせつつ、そうならぬ為にはとより強固で、王国側に有利な同盟条件を引き出す。まあ単純な駆け引きだ」
右手のナイフをちらつかせつつ、左手で握手の手を差し出す。確かにそれは外交の基本も基本である話。
「ですが、強硬派が少なからず発言力を持っているのも事実です。
何よりその強硬派の論拠には、クトリア脅威論も含まれています。リカトリジオス軍よりも共和制となり国として成立したクトリアの方こそが、まず先に王国への脅威となりうる……と。
彼らは長年のザルコディナス三世の暴政時代とその後の邪術士専横の時代に、クトリアへの強い侮りと差別意識を強化し、それ故に今のクトリアの変化に対してある種の強迫観念めいた恐怖を感じているのです」
「なるほどな。奴隷解放から公民権運動を経てブラックパワーが高まると、そのバックラッシュとしてKKKみたいな白人至上主義者が暴れ出す……てのと同じか」
「……ええ」
JBの的確な例えに、テレンスもまた同意する。
侮っていた相手が力を付けると、その反動で夜郎自大な好戦気分が高まるというのは、確かによくある話。
「思い上がって調子に乗ってる奴らにどっちが上なのかを思い知らせてやれ」というやつだ。
「それと……お前さん、確かフルネームはテレンス・トレディア・レオナルディ……だったか?」
「はい」
「それは、リッカルド・コンティーニ将軍の正妻となったラーナ・レオナルディの縁者……と言うことか?」
これまた、イベンダーが思いもよらぬ名前を出して来る。
さすがのテレンスもこれには面食らったようだが、その驚きの表情はすぐに引っ込めて、
「良くご存じで」
「俺個人……というか、疾風戦団がコンティーニ家とは縁浅からぬ仲だからな。
そしてレオナルディ家となれば、その後ろ盾はフュリオス家……だろう?」
コンティーニ家は言うまでもなく、闇の主討伐軍の総司令官を任じられ大敗を喫したリッカルド・コンティーニ将軍に、現在未だ王国駐屯軍“悪たれ”部隊を率いているニコラウス・コンティーニの家。
レオナルディ家……というのは僕はよく知らないが、フュリオス家は確かに有名だ。というかティフツディル王国五将軍のうち知将として名高い老将、大ニコラウス・フュリオスの家だものね。
つまり……、
「隠す意味はないので明かしますが、コンティーニ家、フュリオス家の二将軍家に、我がレオナルディ家と北方辺境伯のベルモンド家等が、同盟派の主な貴族です」
言い換えれば、その同盟派の肝いりで外交特使となっただろうテレンス氏が、強硬派を納得させられるだけの有利な材料を持って帰らないと、強硬派が勢いづく……と。
なんとも……、
「……頭が痛い……」
深いため息と共に顔を伏せる。
「ふうむ、確かにな。国として舐められるのはマズいが、舐められまいと強気に出過ぎて強硬派を刺激するのもマズい。こりゃもう少し色々、裏工作なんぞもして回らんといかんだろう」
裏工作とか! そんなの僕には無理無理無理のグレ無理ンですよ!?
「その辺は……我々の出番だ」
その僕へと優しい笑み……らしきものを浮かべてそう言うのはアルバ。
「今回の外交特使団の中には、勿論その強硬派側から送り込まれた者達も居るのだよな?」
「もちろん、当然です」
「後でその者達のことを教えてくれ」
そこで、少し嫌な予感がして、
「ちょ、ア、アルバ、まさかだけど……!?」
「おう、ちょっとそのまさかだぜ!?」
慌てる僕とJBに、再び蠱惑的な笑みを浮かべて、
「安心しろ、そう下手なまねなどせんよ。魔術の何のに頼らずとも、特使程度を骨抜きにする手練手管などいくらでもある」
と言う。
本当に!? 本当の本当に、本当ですか!?
「───しかしそういう話になって来ると、俺に出来ることはそう無さそうだな」
「いや、あるぞ“キング”。むしろお前にしか出来ぬ事がある」
頭をかきつつの“キング”に対し、アルバはまたもそう笑みを返す。
「クトリア内部に、“王国との同盟を歓迎するムード”を広めることだ。
今までならパスクーレとか言うお主の右腕を称する男辺りが中心になって、反王国のムードを盛り上げてただろうが、幸いにも今あやつはそれどころじゃ無い様だしな。
お前の子飼いの中でも発言力、影響力のある連中に、お前自身がクトリア共和国とティフツディル王国との同盟を歓迎しているという事をそれとなく伝えるんだ。
そうすればその者達がさらに多くの連中にそれを伝える。それを聞いた者達もまたそれを伝える……。
その世論を感じれば、強硬派側の特使たちもそれを本国の強硬派貴族にその様に伝える。
その影響力は、決して安くはないぞ」
民主主義の政治体制で無くとも、世論というのはそう侮れない。原始的な社会でも、より発展した複雑な政治体制の社会でも、影響力の過多や伝搬の過程経緯に差はあれども、その事は変わらないのだ。
「なるほど。それなら少しは俺らにも出来そうだな」
“キング”同様、直接的にはこの外交問題に関われないJBもまたそう言う。
「何にせよ、現実的な当面の問題はクトリア共和国とティフツディル王国との同盟を無事締結すること。
まずはそこ……と言うことですね」
再びため息をつきそうになるのを堪えて、僕がそうまとめる。
見回す一堂もまたそれに頷き返し、アルバの取り纏めで集まることとなったこの秘密の集いに一つの統一された目標が決まった……かに思われたが、まだ話はそこで終わらない。
「───当面は、それだ。
だがそのことは“辺土の老人”の思惑それ自体とは、そう大きく関係はないだろう」
そう話を戻すのはやはりアルバ。
話の流れとして外交問題に焦点が移ったため忘れかけていたが、確かにそうだ。僕らをアルバが集めた理由は、クトリア共和国とティフツディル王国の同盟のことを話し合うためじゃない。
「ですが、王国とクトリア共和国との同盟関係が破綻すれば、“辺土の老人”の求める破壊と滅びには近付くのではないですか?」
テレンスの疑問に、今度は僕が答える。
「はい、近づきます。ですがそれは、“辺土の老人”にとっては、あくまで些末。いえ、一部でしかないのです」
テレンスのみならず、アルバ、それとイベンダーを除く一堂がそれぞれ「ちょっと何言ってるのか良く分からないんですけど?」という表情。
「“辺土の老人”は、あくまでも特等席で多くの破壊と滅びを眺めることを求めて居ます。
なので特定の勢力に肩入れする事はありませんし、特定の勢力を敵対視することもありません。
例えば王国とクトリア共和国の同盟が破綻し、クトリアが滅び、また王国も大きな損害を被るのも彼にとっては喜びであり成果です。
けれども逆に、王国とクトリア共和国の同盟が強固になり、リカトリジオス軍をはねのけそれを撃退し、リカトリジオス軍が滅びたとしても───それもまた“辺土の老人”にとっては喜びであり成果なのです」
そう、“辺土の老人”というのはそういう、本当に悪質でおぞましい、実に厄介な存在なのだ。
「───人は、過ちを繰り返す……。争いと死と破壊の尽きぬ限り、その“辺土の老人”の手の平の上……て事か」
「胸くそ悪ィ爺だな、そいつは」
イベンダーがやや珍しく嫌悪感を現してそう言うと、JBもまた吐き捨てるようにそう続ける。
「ああ。そして───そこからの“本題”だ。
今回……つまり、私と“キング”、テレンスとをこの世界へと送り込んだ件の中心には、恐らくはやはり、あの忌まわしき武器が関わっている」
アルバがそう言葉を続ける。何よりもまずは僕。そしてイベンダーへと視線を向けて言うその「忌まわしき武器」───。
「まさか……“災厄の美妃”か……?」
0
あなたにおすすめの小説

貧民街の元娼婦に育てられた孤児は前世の記憶が蘇り底辺から成り上がり世界の救世主になる。
黒ハット
ファンタジー
【完結しました】捨て子だった主人公は、元貴族の側室で騙せれて娼婦だった女性に拾われて最下層階級の貧民街で育てられるが、13歳の時に崖から川に突き落とされて意識が無くなり。気が付くと前世の日本で物理学の研究生だった記憶が蘇り、周りの人たちの善意で底辺から抜け出し成り上がって世界の救世主と呼ばれる様になる。
この作品は小説書き始めた初期の作品で内容と書き方をリメイクして再投稿を始めました。感想、応援よろしくお願いいたします。

最低のEランクと追放されたけど、実はEXランクの無限増殖で最強でした。
MP
ファンタジー
高校2年の夏。
高木華音【男】は夏休みに入る前日のホームルーム中にクラスメイトと共に異世界にある帝国【ゼロムス】に魔王討伐の為に集団転移させれた。
地球人が異世界転移すると必ずDランクからAランクの固有スキルという世界に1人しか持てないレアスキルを授かるのだが、華音だけはEランク・【ムゲン】という存在しない最低ランクの固有スキルを授かったと、帝国により死の森へ捨てられる。
しかし、華音の授かった固有スキルはEXランクの無限増殖という最強のスキルだったが、本人は弱いと思い込み、死の森を生き抜く為に無双する。
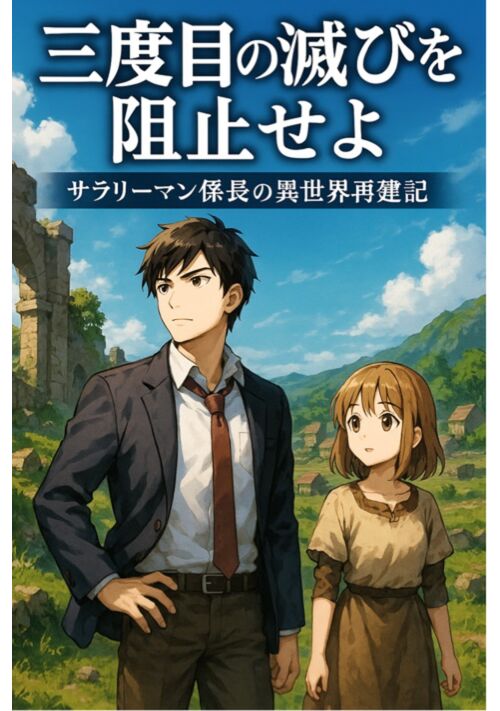
『三度目の滅びを阻止せよ ―サラリーマン係長の異世界再建記―』
KAORUwithAI
ファンタジー
45歳、胃薬が手放せない大手総合商社営業部係長・佐藤悠真。
ある日、横断歩道で子供を助け、トラックに轢かれて死んでしまう。
目を覚ますと、目の前に現れたのは“おじさんっぽい神”。
「この世界を何とかしてほしい」と頼まれるが、悠真は「ただのサラリーマンに何ができる」と拒否。
しかし神は、「ならこの世界は三度目の滅びで終わりだな」と冷徹に突き放す。
結局、悠真は渋々承諾。
与えられたのは“現実知識”と“ワールドサーチ”――地球の知識すら検索できる探索魔法。
さらに肉体は20歳に若返り、滅びかけの異世界に送り込まれた。
衛生観念もなく、食糧も乏しく、二度の滅びで人々は絶望の淵にある。
だが、係長として培った経験と知識を武器に、悠真は人々をまとめ、再び世界を立て直そうと奮闘する。
――これは、“三度目の滅び”を阻止するために挑む、ひとりの中年係長の異世界再建記である。

異世界でぼっち生活をしてたら幼女×2を拾ったので養うことにした【改稿版】
きたーの(旧名:せんせい)
ファンタジー
【毎週火木土更新】
自身のクラスが勇者召喚として呼ばれたのに乗り遅れてお亡くなりになってしまった主人公。
その瞬間を偶然にも神が見ていたことでほぼ不老不死に近い能力を貰い異世界へ!
約2万年の時を、ぼっちで過ごしていたある日、いつも通り森を闊歩していると2人の子供(幼女)に遭遇し、そこから主人公の物語が始まって行く……。
―――
当作品は過去作品の改稿版です。情景描写等を厚くしております。
なお、投稿規約に基づき既存作品に関しては非公開としておりますためご理解のほどよろしくお願いいたします。

転移先で日本語を読めるというだけで最強の男に囚われました
桜あずみ
恋愛
異世界に転移して2年。
言葉も話せなかったこの国で、必死に努力して、やっとこの世界に馴染んできた。
しかし、ただ一つ、抜けなかった癖がある。
──ふとした瞬間に、日本語でメモを取ってしまうこと。
その一行が、彼の目に留まった。
「この文字を書いたのは、あなたですか?」
美しく、完璧で、どこか現実離れした男。
日本語という未知の文字に強い関心を示した彼は、やがて、少しずつ距離を詰めてくる。
最初はただの好奇心だと思っていた。
けれど、気づけば私は彼の手の中にいた。
彼の正体も、本当の目的も知らないまま。すべてを知ったときには、もう逃げられなかった。

借金まみれで高級娼館で働くことになった子爵令嬢、密かに好きだった幼馴染に買われる
しおの
恋愛
乙女ゲームの世界に転生した主人公。しかしゲームにはほぼ登場しないモブだった。
いつの間にか父がこさえた借金を返すため、高級娼館で働くことに……
しかしそこに現れたのは幼馴染で……?

バーンズ伯爵家の内政改革 ~10歳で目覚めた長男、前世知識で領地を最適化します
namisan
ファンタジー
バーンズ伯爵家の長男マイルズは、完璧な容姿と神童と噂される知性を持っていた。だが彼には、誰にも言えない秘密があった。――前世が日本の「医師」だったという記憶だ。
マイルズが10歳となった「洗礼式」の日。
その儀式の最中、領地で謎の疫病が発生したとの凶報が届く。
「呪いだ」「悪霊の仕業だ」と混乱する大人たち。
しかしマイルズだけは、元医師の知識から即座に「病」の正体と、放置すれば領地を崩壊させる「災害」であることを看破していた。
「父上、お待ちください。それは呪いではありませぬ。……対処法がわかります」
公衆衛生の確立を皮切りに、マイルズは領地に潜む様々な「病巣」――非効率な農業、停滞する経済、旧態依然としたインフラ――に気づいていく。
前世の知識を総動員し、10歳の少年が領地を豊かに変えていく。
これは、一人の転生貴族が挑む、本格・異世界領地改革(内政)ファンタジー。

天才女薬学者 聖徳晴子の異世界転生
西洋司
ファンタジー
妙齢の薬学者 聖徳晴子(せいとく・はるこ)は、絶世の美貌の持ち主だ。
彼女は思考の並列化作業を得意とする、いわゆる天才。
精力的にフィールドワークをこなし、ついにエリクサーの開発間際というところで、放火で殺されてしまった。
晴子は、権力者達から、その地位を脅かす存在、「敵」と見做されてしまったのだ。
死後、晴子は天界で女神様からこう提案された。
「あなたは生前7人分の活躍をしましたので、異世界行きのチケットが7枚もあるんですよ。もしよろしければ、一度に使い切ってみては如何ですか?」
晴子はその提案を受け容れ、異世界へと旅立った。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















