265 / 496
第三章 クラス丸ごと異世界転生!? 追放された野獣が進む、復讐の道は怒りのデスロード!
3-65.クトリア議会議長、レイフィアス・ケラー「え、マジで?」
しおりを挟むかつて古代ドワーフが都市を造り、その後彼らが居なくなった後に人間が現れ、その遺跡の上に町を作り都市となりクトリア王朝を築いた。
当初は牧畜、その後には綿花の栽培を主な産業として栄え、大型のガレー船を建造できる様になってからは東方や南方とを繋ぐ交易都市になる。
立地的には“巨神の骨”という大山脈に囲まれ護られていて、また東西南北それぞれの要所として陸路でも交易の中継地となっていた。
第一期クトリア王朝は、その地理的な恩恵に護られた上で、恐らくは僕がクリアした古代ドワーフの王権の試練を成し遂げた者が王朝を開くことで魔力溜まりの力も適切に使えていたのだろう。
しかしその繁栄はひとまず東方人との戦争で崩れ去る。
混乱した政情をティフツデイル帝国貴族達の後ろ盾を得て立て直して開かれた第二期クトリア王朝は、はじめの頃は第一期クトリア王朝の政治や体制を踏襲していたものの、次第に交易や綿花栽培を重視しなくなり、魔力溜まり依存で無理な利用の仕方をし土地の魔力を歪め、疲弊させて国力を減退させる。そして最期にその王権を引き継いだザルコディナス三世は、ご存じの通りの暴政の果てに国を滅ぼした。
母のナナイがヴォルタス家と共に海賊退治をしていたのはそのザルコディナス三世の時代。
彼らヴォルタス家が武装商船団を結成し海賊退治に邁進したのも、そもそもザルコディナス三世が海軍兵力を海賊退治へと差し向けなかったからだ。
その意味で、今のヴォルタス家の有り方は、良かれ悪しかれクトリア海軍と強い関係……因縁がある。
「───それは……」
言葉に詰まる。
ロジウスの主張、いや、問い掛けは大きい。そしてそれにきちんと答えられるだけのものを、今の僕は持っていない。
「……いえ、正直に言います。今の私には、その問いへと返せるだけの計画、案はありません」
駆け引きとか、口先でうまく誑し込むとか、そういうのは僕には真似できないし……少なくともこの場面ではそれを使うべきじゃない。そう思う。
「ほなら───陸の兵力でのみクトリア防衛をしはる言うつもりでっか?」
「決してそういう意味ではありません。しかし……海軍の育成には、陸軍以上に時間がかかります」
「せやたらアレですなぁ。今の所あてらが唯一無二の“海軍兵力”言う事になりますなぁ」
そのロジウスの言葉に僕はハッと気付かされる。
ロジウスはただ単にゴネ得狙いでやいやいと言っていたワケじゃあない。
この一連のやりとりは、「ボーマ城塞及びヴォルタス家がクトリア共和国に参加するかしないか」の交渉じゃなく、「唯一の海軍兵力足りうる武装商船団を抱えるヴォルタス家を、どれくらい厚遇して迎え入れるか?」の交渉だったのだ。
ロジウスの言は完全に当を得ている。彼らの武装商戦団の力がなければ、クトリア共和国には全く海防能力が無い。
東西と北を大山脈の“巨神の骨”に囲まれ、さらにはカロド河に挟まれた形のクトリアにおいて、南のウェスカトリ湾側の海こそが弱点で、それを守る上ではヴォルタス家の武装商戦団の力と、現在は寂れた漁村となっているグッドコーヴの発展と防衛が必須。
また、グッドコーヴは西カロド河の渡河点の防衛にも関わる。
クトリア共和国の防衛、そして海洋交易による経済の発展。どちらに置いてもヴォルタス家の存在はとてつもなく重要だ。
「───貴方のおっしゃる通りです。ヴォルタス家の武装商戦団の力が無ければ、クトリア共和国の海防は成り立ちません」
まるっきりの正直なこととして僕はそう答える。
それに対しロジウスはと言うと、つまらなさそうに目を半眼にしてからこう返す。
「───ほな、その上であてらがクトリア共和国へと帰順することの利点はどないなものになります?」
これはまた、うぅ~……。
「……申し訳ありませんが、現時点で私からこれ以上のことを提示をする事は出来ません」
僕としてはそう答える以外に無い。
と。
そこでパン、と大きく手をたたく音。
「ま、ひとまずそこまでだな。今の所もう詰められる話もないだろ?」
母のナナイがそう場を仕切る。
「……さいですなあ。お互い前向きな話し合いが出来てほんまよろしかったですわ」
皮肉なのか本心なのか、そう言うロジウスに母は、
「そういじめるなよ。お前、やっぱ一番アニチェトに似てるぞ」
と一言。
「はぁ……。そないに言われることはめったにありまへんけどもなぁ。
むしろ似てない似てないとばかり言われとりますわ」
「いやぁ~、似てるな。特にその、一見あけすけにものを言ってるような風を装って、実は本心を巧妙に隠しておくところなんか……よっく似てるぜ?」
ニヤリと笑う母ナナイに、初めてロジウスは今までに見せなかった表情を見せる。
「……さあて、そらまたややこし話ですな」
そのわずかな表情の変化は一瞬。すぐにまた元の顔に戻してそう素知らぬ風に返す。
「日の沈む彼方から昇る雲のことは、お互い気にせざるを得まい」
謎かけのようなその言葉に、今度はただ無表情に首をすくめるのみで返すロジウス。
我ながら思ってた以上に察しの鈍い僕が、そのやりとりの意味を理解するのはもう少し経ってからだ。
□ ■ □
「こりゃまた……たいした獲物だな」
感心すると言うよりやや呆れたようにそう言うのはエヴリンド。
視線の先の荷台には、六体ほどの砂色の鱗に赤黒まだらな腹をもつ巨大なトカゲ……いや、オオヤモリだ。
クトリア近郊及び残り火砂漠を中心に生息するオオヤモリは、幼体は子猫くらいから年経るごとに巨大化し、四、五年かそれくらいで人間を上回る大きさにまで成長する。
そして成長過程での生息域や得た魔力により幾つかの変化をする凶暴で好戦的な魔獣だ……と、ケイル・カプレートの本に書いてあった。
腹の下が赤黒いファイヤーパターンのように見えるのは火炎オオヤモリ。火属性魔力を得て口から火炎を放つ、主に砂漠に住む魔獣だ。
「クトリア近郊にも居たのですね、火炎オオヤモリは」
と、夕方近くになりそれらを荷車に載せてやってきたJB達にそう聞くと、
「いや、どうだかな。俺も初めて見たし、狩人達もここらじゃめったに見ないッて言うぜ」
とのこと。
「ふんふん、そうよなーう。
昔は残り火砂漠でよく見たが、こちらに来てからは初めてよなう」
「うん、そうだね。こっちじゃまず見ないね」
小柄で下腹ぽっちゃりの眉毛猫と、すらりとした長身のブチ猫とがそう補足する。何このブルースブラザーズ的コンビ感。
「では何故この辺に……?」
「んー……、そうねぇ~。何だかまた最近、魔獣が増えてる気がするのよねぇ~。
魔人の賊たちが少なくなった分、魔獣が住処を広げてるのかしらねぇ~」
僕のその疑問に、これまた妙に間延びしたしゃべりで、ひょろりと長身で腕の長い狩人らしき人物が答える。
けど……うーんむ?
生息域の変化、というのは確かにあるだろうとは思う。とは言えそれだけでは、本来クトリア近郊にはめったに居ないという火炎オオヤモリが増えたことには説明がつかない。
というよりも、火属性魔力により変化するというオオヤモリの生態からすれば、火炎オオヤモリがクトリア近郊で増える理由は一つしか有り得ないのだ。
「あ……姐御……、見て下せえや……」
「うぇっへっへ、お、俺っち達の、獲物だぜ~……」
へろへろに疲労困憊という感じのヤマー君ほか数名の衛兵隊候補達がそうエヴリンドに誇るが、それを受けたエヴリンドが衛兵隊候補唯一の女性、ダグマさんへと視線を向けるとうつむき加減で首をふるふると横に振られる。
つまりは彼らの主張することは話半分かそれ以下で、とてもじゃないが「彼ら衛兵隊候補達の獲物」とは言えないのだろう。
話では若手の衛兵隊候補数名と、ブルさんの店と遺跡調査団それぞれの新人数名が、こちらボーマ城塞で一、二週ほどの訓練を受けるという。
ケルアディード郷での若手の訓練教官だったアランディの訓練メニューは、若い頃に僕の母ナナイと旅していたときに学んだ帝国流の兵卒練兵なんかを参考にして闇の森流に改良したものらしいので、きっとあれと同等かそれ以上のハードな訓練になるだろう。
……いやー、大変だわ。
□ ■ □
夜にはまた宴が催される。JB達のため……と言うよりは、JBや僕らの来訪を口実にしたロジータの酒宴……と言うのが実情のようだ。
昼餉の庭園の宴席をさらに大きくし、明日からは死の猛特訓を受けるだろう新人、若手達をももてなす宴の様子からは、接待とか歓待というより、とにかくヴォルタス家の宴会好きっぷりを感じさせられる。
僕は昼間のこともあり、やや気もそぞろで落ち着かない。
自分の考えの甘さに、加えればそこでまたもや母、ナナイに助け船を出されてしまったという事に落ち込みもしている。
ダークエルフ的には40代はまだ未成年。社会的には高校生くらいの扱いだが、人間社会ではもう十分な大人だ。そうやってつい人間に置き換えて考えてしまうのは前世の意識、感覚が蘇っているからではあるだろうけども、それでも自分の不甲斐なさ、未熟さを痛感する。
いつもならうるさいアデリアも、今日は疲れて早めに寝ている。
エヴリンドは僕の横に張り付きつつも、時折羨望のまなざしを向けてくるヤマー君らににらみを利かせてる。
母のナナイは何気にロジータと意気投合し杯を交わし飲み比べなんかをしているし、狩人とJB達は楽器の演奏を始め、何人かは踊り出してもいる。
好青年ぶったデュアンはと言うと、ロジウスとその家族や供の者達に南方諸島の話をせがんで色々と聞いている。
その様子を眺めつつ、それから夜空を仰ぎ見て薄めたヤシ酒を一口。酒はあまり得意ではないし味が分かるほどでもないけども、確かにかなりの上物みたいだ。
ふと、辺りに視線を戻すと、賑やかな喧噪の中ただ一人、やや離れた庭園の木陰で手酌で酒を飲む者が居る。
誰だろうかと目を凝らすと、例のぽっちゃり眉毛猫氏の相方のひょろブチ猫氏だ。
ぽっちゃり猫眉毛氏は未だ厨房で料理をしてるそうで、ここに並ぶいくつかもまた彼の手料理らしい。
なんとはなしに気になってその落ち着いた様子を眺めていると、そう言えばと思い出したことがある。
アルバの前世での教え子の一人で、“辺土の老人”グィビルフオグの齎した武器“災厄の美妃”、又の名を“エルフ殺し”の持ち主であるかもしれないという猫獣人。顔の真ん中に大きな疵痕のあるその人物について、僕らはそれとなく探している。
クトリア周辺には近頃猫獣人が増えてきているが、全体としてはまだまだ少ない。
何かしらの心当たりが彼にもあるかもしれないとそう思い、意を決して話しかけてみようと決める。
「こんばんわ。よろしいですか?」
杖を突きつつ歩み寄り、そう話しかける。
「うん」
肯定かただの応答かよく分からない返しだが、まあよし、とその横の石のベンチへと腰をかける。
「改めまして、レイフと言います。今はクトリア議会の議長を勤めています」
「うん」
……やはり、肯定なのかただの応答なのかいまいち分かり難い。
ブチ猫氏は傍らの容器から手酌で小さなマグへと酒をついで飲んでいる。その器、陶器でも金属でもなくなんとひょうたん。そう、アレです。日本では丸い二つの膨らみを繋げたような形の物として知られる、固い外皮のひょうたん瓜の中身を全部取り出し乾燥させた容器として有名なアレ。
ブチ猫氏のそれは形としては日本でよく知られるくびれのあるあの形というより、強いていうならやや細長いフラスコ型。くびれというよりは丸い膨らみの上に細長い口がついているような形だ。
その下の方に素朴な筆致の花の絵が描かれていて、織部好みとでも言うようなひょうげた風情がある。
物珍しいこともあり、それを半ば凝視するように見ていると、ブチ猫氏は
「飲む?」
とそれを掲げて聞いてくる。
「あ、はい。ありがとうございます」
「うん」
手にしてたマグを差し出すと、トクトクと注がれる透明な液体。ふんわりと香る独特の匂いは……、
「……バナナ?」
甘く香るその果物の独特な匂い。
「うん、バナナ酒。アールマールの」
獣人王国のアールマールは、残り火砂漠を南に向かい縦断した先にあると言う密林の王国。どんなところかは伝え聞く話と僅かな書物でしか分からないが、確か山に囲まれた広い盆地の中にある、主に猿獣人が中心の国だったはず。
ちょうどセンティドゥ廃城塞の奥にある土の迷宮の、それよりさらにさらに広ォ~~~~……い場所、という感じらしい。
ただ、本で読んだ限りだと、猿獣人のバナナ酒は物凄く原始的な、所謂濁酒というようなもので、潰してどろどろにしたバナナをそのまま発酵させ、放っておくと数日後には腐ってしまうようなもののはず。
要は自分たちで飲む分を飲む分だけ作って飲む、というものだ。
けれどもこの器にあるのは澄んだ透明な液体。つまりはおそらく蒸留酒。口にしてみるとなかなか強めのアルコールに、やはりまろやかなバナナの香りにシナモンのようなスパイスの香りも効いていて、かなり個性的な風味がする。
「意外です。バナナ酒は濁酒だけかと思ってました」
「うん。だいたいはね。他にも発泡酒もあるけど、蒸留酒はあんまりない」
やっぱり珍しいもののようだ。
「昔の知り合いが、作ってたんだ。たまにこうして、ちびりと飲む」
そう言うブチ猫氏の顔は、やはり感情の読めないとぼけたもの。
けれどもその声の調子には、やや今までとは異なる何かがあるように思えた。
「───あなたにとって、特別なお酒なのですね」
そう言うとブチ猫氏はやや上を見て少し目を閉じ、それからまたこちらを向いて。
「そうかもしれないし、そうじゃないかもしれない。君がそう思うのなら、多分そうなのかもしれないね。うん」
と、まるで自分に言い聞かせるかのようにそう言った。
暫く、そうして喧騒から離れて静かなときが流れる。ひんやりと乾いた砂漠の夜風が、酒で火照った頬を優しく撫でる。
つかみ所のないブチ猫氏とは、やはり話をするとっかかりもなく、ただお互いに静かなまま夜風を感じて隣り合って座っている。
けれども何故か不思議と、気まずいとも無理にでも話題を探さねばとも思わずに、ごく自然な気持ちで二人そこに居ることが出来た。
あまりにも自然なゆるんだ空気に、僕は暫く、彼に話しかけたそもそもの理由を忘れかけていた。
ややあってその理由を思い出し、僕はその会話の糸口を探す。
「───昔の知り合いと言えば、僕の友人が昔、少し変わった猫獣人と出会ったそうなんです」
「うん」
「その猫獣人は、薄茶色で鬣のある姿で、顔の真ん中、丁度眉間の辺りに大きな爪痕のような傷があって、奇妙な武器を持ていたとかで。何か見聞きしたこととかありませんか?」
「うん」
……うん、この「うん」はどっちだろう?
ここでまた暫くの間。
「───武器のことは分からないけど、疵痕のある奴なら知ってるかもしれないね」
「え、マジで?」
と、思わずエルフ語で間抜けな返しをしてしまう。
いやだって……え? 試しに聞いてみたその最初の相手よ? そら、クトリアに猫獣人は少ないとは言え、色々聞き回って百人目、とかじゃなくて、ファーストクエスチョンよ?
いいの!?
あまりのことにやや呆けてしまいつつも、気を取り直して改めて、
「すみません、あの、それは、どこで、いつ頃のことでしょう?」
「うん。六年くらい前かな。シーリオと、獅子の谷の野営地でね。暫く一緒に訓練してた中に、そんな奴が居たね。その後も会ってる。武器は普通の山刀だったけどもね」
さてこれ、ドンピシャなのか他人の空似か。分からないけどもちと詳しくは聞いてみたい。
「訓練と言うと、狩人のですか?」
「うん。違うね。その時は“砂漠の咆哮”の入団試験の訓練。ふた月くらいかな。うん、忘れたなあ……。
俺は結局やめたけど、アイツは入ってね。うん」
“砂漠の咆哮”!
噂に名高い獣人の戦士団か!
これはまた、かなり有力な情報のようだ。
「その後、どうなされたか……消息は分かりますか?」
「うん、南の方のラアルオーム近くに住んでたけどね。何度かは会ってる。後は知らない。もしかしたらアティックは知ってるかもね。うん」
「アティック?」
「もう一人の、猫獣人だね、うん」
ああ、あの下腹ぽっちゃり眉毛猫氏の方か。
いやー、ビックリした。こんなにも早く、即座に“災厄の美妃”の持ち主かもしれない猫獣人の消息を辿れるとは、恐れ入谷のなんとやら。とにかくビックリですよ、ええ。
そう驚いてふはー、と息を深く吐いていると、その二人の空間へ不躾な空気で入り込む者が居る。
「あー、いたいた、レイフ! 情報、情報ですよ!」
ガッチャガチャと無遠慮にやかましく、なかなか酒臭い息をしながらのご登場はデュアン。
「何です? 声が大きいですよ。
すみません、私の連れが騒がしくて」
おそらくは静かに一人酒を楽しんでいただろうブチ猫氏にそう謝りつつ、僕は立ち上がりデュアンの方へ。
ここまであの調子でやってこられたら、その静かな空気が台無しだ。
「何なの、もう? 静かな空気でまったりしてたのに」
「いやいや、情報です、情報!
あの、眉間に大きな傷のある薄茶褐色の鬣の猫獣人の件なんですけどもね!」
あら、何よ? いやまあ、詳細は伏せつつも一応デュアンにも情報収集は頼んである。勿論、探してる相手は魔力を吸い取る“エルフ殺し”を持っている可能性もあるので、決して深入りせず警戒をするようにとも伝えてある。
しかし───えー? 立て続け? と思い、それから、ああそうか、ぽっちゃり眉毛猫氏のアティックさんと話したのかな? と思いきや……そうじゃなかった。
「いやー、なんとですね。五年くらい前? 南のバールシャムという港町で、ロジウスさん達が川賊退治をしたらしいんですが」
「え、まさかその川賊の中に……?」
「いやいや、逆です、逆。川賊のアジトや街中に潜む川賊の仲間探しを頼んだ者達の中に、それらしき眉間に大きな疵痕の猫獣人が居たらしいんです」
ほほう? ブチ猫氏の話では、“砂漠の咆哮”に入ったと思われるその“疵猫”氏は、その後南のラアルオームへと移住しているという。ラアルオームとバールシャムは……えーと、たしか、結構近い。はず。後で確認しよう。
とにかくその二つの情報が確かなら、残り火砂漠を超えたはるか南の獣人王国にその“疵猫”氏は居る……と言うことになる。
「ただ、ですねえ」
頭の中で情報整理をしているところ、デュアンはさらにそう続ける。
「ロジウス氏によると、恐らくその猫獣人、どうも既に死んでいるらしいのですよ」
───え、マジで?
0
あなたにおすすめの小説

貧民街の元娼婦に育てられた孤児は前世の記憶が蘇り底辺から成り上がり世界の救世主になる。
黒ハット
ファンタジー
【完結しました】捨て子だった主人公は、元貴族の側室で騙せれて娼婦だった女性に拾われて最下層階級の貧民街で育てられるが、13歳の時に崖から川に突き落とされて意識が無くなり。気が付くと前世の日本で物理学の研究生だった記憶が蘇り、周りの人たちの善意で底辺から抜け出し成り上がって世界の救世主と呼ばれる様になる。
この作品は小説書き始めた初期の作品で内容と書き方をリメイクして再投稿を始めました。感想、応援よろしくお願いいたします。

最低のEランクと追放されたけど、実はEXランクの無限増殖で最強でした。
MP
ファンタジー
高校2年の夏。
高木華音【男】は夏休みに入る前日のホームルーム中にクラスメイトと共に異世界にある帝国【ゼロムス】に魔王討伐の為に集団転移させれた。
地球人が異世界転移すると必ずDランクからAランクの固有スキルという世界に1人しか持てないレアスキルを授かるのだが、華音だけはEランク・【ムゲン】という存在しない最低ランクの固有スキルを授かったと、帝国により死の森へ捨てられる。
しかし、華音の授かった固有スキルはEXランクの無限増殖という最強のスキルだったが、本人は弱いと思い込み、死の森を生き抜く為に無双する。

異世界でぼっち生活をしてたら幼女×2を拾ったので養うことにした【改稿版】
きたーの(旧名:せんせい)
ファンタジー
【毎週火木土更新】
自身のクラスが勇者召喚として呼ばれたのに乗り遅れてお亡くなりになってしまった主人公。
その瞬間を偶然にも神が見ていたことでほぼ不老不死に近い能力を貰い異世界へ!
約2万年の時を、ぼっちで過ごしていたある日、いつも通り森を闊歩していると2人の子供(幼女)に遭遇し、そこから主人公の物語が始まって行く……。
―――
当作品は過去作品の改稿版です。情景描写等を厚くしております。
なお、投稿規約に基づき既存作品に関しては非公開としておりますためご理解のほどよろしくお願いいたします。
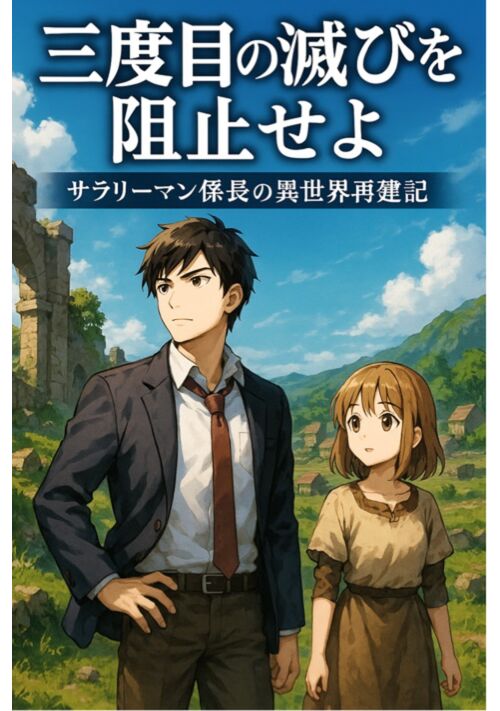
『三度目の滅びを阻止せよ ―サラリーマン係長の異世界再建記―』
KAORUwithAI
ファンタジー
45歳、胃薬が手放せない大手総合商社営業部係長・佐藤悠真。
ある日、横断歩道で子供を助け、トラックに轢かれて死んでしまう。
目を覚ますと、目の前に現れたのは“おじさんっぽい神”。
「この世界を何とかしてほしい」と頼まれるが、悠真は「ただのサラリーマンに何ができる」と拒否。
しかし神は、「ならこの世界は三度目の滅びで終わりだな」と冷徹に突き放す。
結局、悠真は渋々承諾。
与えられたのは“現実知識”と“ワールドサーチ”――地球の知識すら検索できる探索魔法。
さらに肉体は20歳に若返り、滅びかけの異世界に送り込まれた。
衛生観念もなく、食糧も乏しく、二度の滅びで人々は絶望の淵にある。
だが、係長として培った経験と知識を武器に、悠真は人々をまとめ、再び世界を立て直そうと奮闘する。
――これは、“三度目の滅び”を阻止するために挑む、ひとりの中年係長の異世界再建記である。

転移先で日本語を読めるというだけで最強の男に囚われました
桜あずみ
恋愛
異世界に転移して2年。
言葉も話せなかったこの国で、必死に努力して、やっとこの世界に馴染んできた。
しかし、ただ一つ、抜けなかった癖がある。
──ふとした瞬間に、日本語でメモを取ってしまうこと。
その一行が、彼の目に留まった。
「この文字を書いたのは、あなたですか?」
美しく、完璧で、どこか現実離れした男。
日本語という未知の文字に強い関心を示した彼は、やがて、少しずつ距離を詰めてくる。
最初はただの好奇心だと思っていた。
けれど、気づけば私は彼の手の中にいた。
彼の正体も、本当の目的も知らないまま。すべてを知ったときには、もう逃げられなかった。

借金まみれで高級娼館で働くことになった子爵令嬢、密かに好きだった幼馴染に買われる
しおの
恋愛
乙女ゲームの世界に転生した主人公。しかしゲームにはほぼ登場しないモブだった。
いつの間にか父がこさえた借金を返すため、高級娼館で働くことに……
しかしそこに現れたのは幼馴染で……?

バーンズ伯爵家の内政改革 ~10歳で目覚めた長男、前世知識で領地を最適化します
namisan
ファンタジー
バーンズ伯爵家の長男マイルズは、完璧な容姿と神童と噂される知性を持っていた。だが彼には、誰にも言えない秘密があった。――前世が日本の「医師」だったという記憶だ。
マイルズが10歳となった「洗礼式」の日。
その儀式の最中、領地で謎の疫病が発生したとの凶報が届く。
「呪いだ」「悪霊の仕業だ」と混乱する大人たち。
しかしマイルズだけは、元医師の知識から即座に「病」の正体と、放置すれば領地を崩壊させる「災害」であることを看破していた。
「父上、お待ちください。それは呪いではありませぬ。……対処法がわかります」
公衆衛生の確立を皮切りに、マイルズは領地に潜む様々な「病巣」――非効率な農業、停滞する経済、旧態依然としたインフラ――に気づいていく。
前世の知識を総動員し、10歳の少年が領地を豊かに変えていく。
これは、一人の転生貴族が挑む、本格・異世界領地改革(内政)ファンタジー。

天才女薬学者 聖徳晴子の異世界転生
西洋司
ファンタジー
妙齢の薬学者 聖徳晴子(せいとく・はるこ)は、絶世の美貌の持ち主だ。
彼女は思考の並列化作業を得意とする、いわゆる天才。
精力的にフィールドワークをこなし、ついにエリクサーの開発間際というところで、放火で殺されてしまった。
晴子は、権力者達から、その地位を脅かす存在、「敵」と見做されてしまったのだ。
死後、晴子は天界で女神様からこう提案された。
「あなたは生前7人分の活躍をしましたので、異世界行きのチケットが7枚もあるんですよ。もしよろしければ、一度に使い切ってみては如何ですか?」
晴子はその提案を受け容れ、異世界へと旅立った。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















