あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

最愛の番に殺された獣王妃
望月 或
恋愛
目の前には、最愛の人の憎しみと怒りに満ちた黄金色の瞳。
彼のすぐ後ろには、私の姿をした聖女が怯えた表情で口元に両手を当てこちらを見ている。
手で隠しているけれど、その唇が堪え切れず嘲笑っている事を私は知っている。
聖女の姿となった私の左胸を貫いた彼の愛剣が、ゆっくりと引き抜かれる。
哀しみと失意と諦めの中、私の身体は床に崩れ落ちて――
突然彼から放たれた、狂気と絶望が入り混じった慟哭を聞きながら、私の思考は止まり、意識は閉ざされ永遠の眠りについた――はずだったのだけれど……?
「憐れなアンタに“選択”を与える。このままあの世に逝くか、別の“誰か”になって新たな人生を歩むか」
謎の人物の言葉に、私が選択したのは――

私はもう必要ないらしいので、国を護る秘術を解くことにした〜気づいた頃には、もう遅いですよ?〜
AK
ファンタジー
ランドロール公爵家は、数百年前に王国を大地震の脅威から護った『要の巫女』の子孫として王国に名を残している。
そして15歳になったリシア・ランドロールも一族の慣しに従って『要の巫女』の座を受け継ぐこととなる。
さらに王太子がリシアを婚約者に選んだことで二人は婚約を結ぶことが決定した。
しかし本物の巫女としての力を持っていたのは初代のみで、それ以降はただ形式上の祈りを捧げる名ばかりの巫女ばかりであった。
それ故に時代とともにランドロール公爵家を敬う者は減っていき、遂に王太子アストラはリシアとの婚約破棄を宣言すると共にランドロール家の爵位を剥奪する事を決定してしまう。
だが彼らは知らなかった。リシアこそが初代『要の巫女』の生まれ変わりであり、これから王国で発生する大地震を予兆し鎮めていたと言う事実を。
そして「もう私は必要ないんですよね?」と、そっと術を解き、リシアは国を後にする決意をするのだった。
※小説家になろう・カクヨムにも同タイトルで投稿しています。

貧民街の元娼婦に育てられた孤児は前世の記憶が蘇り底辺から成り上がり世界の救世主になる。
黒ハット
ファンタジー
【完結しました】捨て子だった主人公は、元貴族の側室で騙せれて娼婦だった女性に拾われて最下層階級の貧民街で育てられるが、13歳の時に崖から川に突き落とされて意識が無くなり。気が付くと前世の日本で物理学の研究生だった記憶が蘇り、周りの人たちの善意で底辺から抜け出し成り上がって世界の救世主と呼ばれる様になる。
この作品は小説書き始めた初期の作品で内容と書き方をリメイクして再投稿を始めました。感想、応援よろしくお願いいたします。
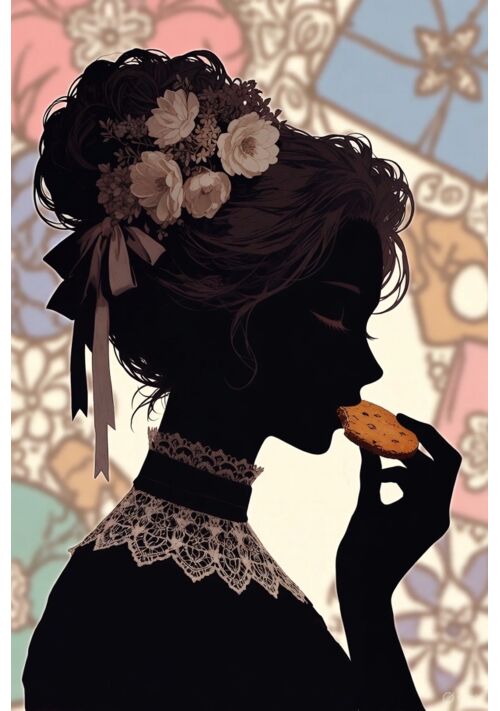
誰からも食べられずに捨てられたおからクッキーは異世界転生して肥満令嬢を幸福へ導く!
ariya
ファンタジー
誰にも食べられずゴミ箱に捨てられた「おからクッキー」は、異世界で150kgの絶望令嬢・ロザリンドと出会う。
転生チートを武器に、88kgの減量を導く!
婚約破棄され「豚令嬢」と罵られたロザリンドは、
クッキーの叱咤と分裂で空腹を乗り越え、
薔薇のように美しく咲き変わる。
舞踏会での王太子へのスカッとする一撃、
父との涙の再会、
そして最後の別れ――
「僕を食べてくれて、ありがとう」
捨てられた一枚が紡いだ、奇跡のダイエット革命!
※カクヨム・小説家になろうでも同時掲載中
※表紙イラストはAIに作成していただきました。

悪役令嬢になるのも面倒なので、冒険にでかけます
綾月百花
ファンタジー
リリーには幼い頃に決められた王子の婚約者がいたが、その婚約者の誕生日パーティーで婚約者はミーネと入場し挨拶して歩きファーストダンスまで踊る始末。国王と王妃に謝られ、贈り物も準備されていると宥められるが、その贈り物のドレスまでミーネが着ていた。リリーは怒ってワインボトルを持ち、美しいドレスをワイン色に染め上げるが、ミーネもリリーのドレスの裾を踏みつけ、ワインボトルからボトボトと頭から濡らされた。相手は子爵令嬢、リリーは伯爵令嬢、位の違いに国王も黙ってはいられない。婚約者はそれでも、リリーの肩を持たず、リリーは国王に婚約破棄をして欲しいと直訴する。それ受け入れられ、リリーは清々した。婚約破棄が完全に決まった後、リリーは深夜に家を飛び出し笛を吹く。会いたかったビエントに会えた。過ごすうちもっと好きになる。必死で練習した飛行魔法とささやかな攻撃魔法を身につけ、リリーは今度は自分からビエントに会いに行こうと家出をして旅を始めた。旅の途中の魔物の森で魔物に襲われ、リリーは自分の未熟さに気付き、国営の騎士団に入り、魔物狩りを始めた。最終目的はダンジョンの攻略。悪役令嬢と魔物退治、ダンジョン攻略等を混ぜてみました。メインはリリーが王妃になるまでのシンデレラストーリーです。

幼女はリペア(修復魔法)で無双……しない
しろこねこ
ファンタジー
田舎の小さな村・セデル村に生まれた貧乏貴族のリナ5歳はある日魔法にめざめる。それは貧乏村にとって最強の魔法、リペア、修復の魔法だった。ちょっと説明がつかないでたらめチートな魔法でリナは覇王を目指……さない。だって平凡が1番だもん。騙され上手な父ヘンリーと脳筋な兄カイル、スーパー執事のゴフじいさんと乙女なおかんマール婆さんとの平和で凹凸な日々の話。

【完結】辺境に飛ばされた子爵令嬢、前世の経営知識で大商会を作ったら王都がひれ伏したし、隣国のハイスペ王子とも結婚できました
いっぺいちゃん
ファンタジー
婚約破棄、そして辺境送り――。
子爵令嬢マリエールの運命は、結婚式直前に無惨にも断ち切られた。
「辺境の館で余生を送れ。もうお前は必要ない」
冷酷に告げた婚約者により、社交界から追放された彼女。
しかし、マリエールには秘密があった。
――前世の彼女は、一流企業で辣腕を振るった経営コンサルタント。
未開拓の農産物、眠る鉱山資源、誠実で働き者の人々。
「必要ない」と切り捨てられた辺境には、未来を切り拓く力があった。
物流網を整え、作物をブランド化し、やがて「大商会」を設立!
数年で辺境は“商業帝国”と呼ばれるまでに発展していく。
さらに隣国の完璧王子から熱烈な求婚を受け、愛も手に入れるマリエール。
一方で、税収激減に苦しむ王都は彼女に救いを求めて――
「必要ないとおっしゃったのは、そちらでしょう?」
これは、追放令嬢が“経営知識”で国を動かし、
ざまぁと恋と繁栄を手に入れる逆転サクセスストーリー!
※表紙のイラストは画像生成AIによって作られたものです。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















