19 / 21
お買い物
しおりを挟む
「よく来たね!サーヤちゃん!折角来たんだから、隅々までよぉく見て行くんだよ?」
奥さんの言葉に、こくりと頷いた。
隣なのにこのお店に来るのは、先月ぶりだ。
ほぼ毎日、奥さんとは顔を会わせているのに。
あの時はまだ寒い時で、お鍋に入れる具材をランと見に来たんだっけ?
「ほら、ここが南の地での特産物だよ?」
奥さんが示した所に、見覚えのある懐かしい風景が広がった。
南の地では、木や畑から直で採って来るのが日常だった。
そのくらい目には馴染みがある。
それが、こうやって籠とか箱とかに入っていたり、紐で束ねられて商品になっているのは何だか変な感じ。
「ピルクはないんだけどね?モモも甘いんじゃないかな?」
奥さんの言葉に、モモも食べていたけれど大きいから食べにくいことを一緒に思い出す。
嫌いじゃない。
だけど、昔は手が汚れても口の周りがベタベタになっても気にしていなかった。
成長したってことかな?
それとも面倒になっただけ?
良いことなのか悪いことなのか分からず、曖昧に首を傾げる。
「うーん、嫌いじゃないけど、手がベタベタになるんだよね…」
「ラン君が全部やってくれるだろ?」
その言葉に苦笑する。
側にいるランの顔は変わらない。
え?当たり前とか思われているのは嫌なんだけど。
でも、事実だから何も言えない。
さっき、反省したばっかりなのに。
メイドみたいなことをさせてって。
「うーん、良いや」
「特に欲しいというわけでもない?」
「…そうだね」
私の様子がそうでもなかったこともあり、ランも無理に進めるという雰囲気ではない。
だから、食べ物コーナーを遠く眺める。
「懐かしいなぁ、と思うくらいかな」
「じゃあ、適当にいくつか買っておこうか?」
調理方法とか知らないランがそんなことを言うのに笑ってしまう。
「いいよ」
「ですが…」
「ランは、お手伝いさんじゃないでしょ?」
「そうだけど…」
そう言いながら、野菜や乾麺、果物なんかを眺める。
こうやって見ても懐かしいけれど、特に何かを欲しいと思うものはなかった。
ピルクほどテンションも上がらないというか…。
それだけ、この北の地での生活に慣れたってことなのかな?
ふと、目に着いた装飾品に意識が向く。
幼馴染が作ったのとは毛色が違う、何かオシャレそうなブレスレットや指輪だ。
「何だい?サーヤちゃん、こういう宝石類気になるのかい?」
「え?うーん、気になるというか…石が見たいと言うか…」
装飾されていない、原石と言うのかそういうものも下の段には並んでいる。
私が気になっているのは、そこだった。
道端に落ちているようなゴツゴツした物から、河原で見かけるつるりとした丸みを帯びた石まで。
多くはないけれど、並んでいるものを眺める。
しゃがみこんでじっと見つめていると『あらぁ』と穏やかな声がした。
何か、聞き覚えあるなぁと思っているとクスクス笑い声が聞こえた。
「あらあら、サーヤちゃんもお年頃になったのかしら?」
クラリスさんだった。
「こんにちは、クラリスさん。何か会うの久しぶりな気がする。…何がお年頃?」
言われた言葉が理解できずに、首を傾げる。
しゃがんでいるから、クラリスさんを見上げる形だ。
クラリスさんは背が高い。
奥さんは私よりは背が高いけど、クラリスさんに比べると低くなる。
「はい、こんにちは。あら?サーヤちゃん、ネックレスとかを見てるんじゃないの?」
クラリスさんの言葉に、ふるふると首を振る。
「ううん、幼馴染がこういう原石?石に興味があってね?もし、変わったのがあったらなぁって…」
「そうだったの?残念ね、ラン君」
何でラン?
ランはにこやかに笑っているだけだ。
「ランは何で残念なの?」
こんなに笑ってて、残念?
「あら?サーヤちゃんが、宝石に興味を持ったら、ラン君が高額商品を買ってくれるんじゃないかって?」
クラリスさんのお茶目なウィンク。
「高額?それはいらないかな?ランには、ほんとに感謝してもしきれないほどお世話になってるし、これ以上迷惑はかけられないよ?」
私の迷いながらの言葉に、ランは「全然、迷惑なんてかかってないから」とはっきり言った。
「それに、分かっちゃいないね?クラリスは。ラン君はサーヤちゃんの好みは、すでに熟知済みだよ」
奥さんの言葉に、ランは得意そうに頷いた。
「仰る通りで」
「あらあら、そうなのね。私もまだまだね」
クスクス笑うクラリスさん。
「ラン?」
さっきのエリザさんの言葉を思い出す。
「ランのお仕事、大変じゃない?」
「何で?」
「だって、さっきエリザさんが…」
ランは優秀だから1人でも出来ている助手だと言った。
本当は、私みたいに何もできない人間にはたくさん手を焼く人が必要なのかも。
落ち込むなぁ。
なのに、ランは何でもない顔をしている。
「あぁ、サーヤは助手10人欲しいの?」
ランの言葉に、今度はぶんぶんと首を振った。
「そんなにいらない!それに、助手の人に迷惑だよ。こんな、何も出来ない紡ぎ司なんて…」
「サーヤ」
ランの優しい声。
「何?」
答える私は少しおどおどしている。
奥さんとクラリスさんに見られているのも、何かなぁ。
こんなとこで、ランに何を言われるのか。
きっとランのことだろうから、嫌なことは言わないだろうけど…。
「サーヤは、紡ぎ司として立派です。それは、誰よりも近くで見ている俺が、絶対に自信を持って言えることです。だから、何も出来ないなんて言わないで?」
「でも、私…パンも上手に焼けない」
「パン?」
ランの言葉にこくりと頷く。
「パン、朝焦がしたでしょ?」
答える私の言葉に、奥さんが吹き出した。
「何だい?サーヤちゃんは、まだそんなこと気にしてんのかい?」
奥さんの言葉に、『そんなこと?』と聞き返す。
「コンロでパン焼くのなんて、主婦だって間違えることもあるさ」
「そうなの?」
「それに焦がしたパンだって、炭になって畑の浄化に役に立った。残りは食べられた、なら良いじゃないか?そうだろう?クラリス?」
クラリスさんは『そうですねぇ』と呑気に頷いた。
「今朝、パンを焦がしちゃったんだ」
恥ずかしそうに言う私にクラリスさんはクスクス笑った。
「あら、私なんてしょっちゅうお鍋を焦がして、旦那様に呆れられていますよ?」
クラリスさんの言葉に、しょっちゅう?と呟く。
「そうなの?パン、焦がしても呆れない?」
「何でそんなに自信がないのかね?サーヤちゃんは、立派な紡ぎ司だろう?」
奥さんの言葉にもコクリと頷く。
「立派、かどうかは分からないけど…。そっか、うん、紡ぎ司はちゃんとしてるつもり、かな?」
「じゃあ、私達の生活を豊かにしてくれているのは、間違いなくサーヤちゃんだわ。毎日、ありがとう」
クラリスさんののんびりとした言葉に、何か元気が湧いてくる。
ありがとう
こうやって言われると、紡ぎ司で良かったと思える。
みんなの励ましで、何だかパンを焦がしたことも『まいっか』と思えるようになる。
「奥さん、クラリスさんありがとう。勿論、ランもいつもありがとう」
3人とも『どういたしまして』と笑ってくれた。
「サーヤちゃん?石に興味があるなら、西の地で探してみると良いと思うわ」
クラリスさんの言葉に、首を傾げる。
「西の地って、古いでしょう?原石も、古い物とか珍しい物が揃っているっていうし」
「何だい?クラリスは、家の店じゃなくて西の地の商店をお勧めするのかい?」
「あら?奥様、私は西の地のフォン商会をお勧めしたつもりなんですけど?」
「…やれやれ、それはそれで」
奥さんが少し困ってる。
何でだろう?
「あー、サーヤちゃん。そのね、西の地の私の店はね、少しだけ格式ばってるっていうか、そう!堅苦しいんだよ。サーヤちゃんはあまり好きじゃないだろ?」
奥さんの言葉にも、こくりと頷く。
確かに。
西の地だけでも、重苦しいのに。
そこに、堅苦しいのが加わったら少し嫌だなぁ。
「でも、石は気になる…」
悩む私に、ランが『そうだ!』と声を出した。
「なぁに?」
「サーヤ、午後に西の地に行きませんか?丁度、報告書を持って行く所だったんですよ?久しぶりに、コルダ様に会いませんか?」
コルダ様とは、西の地の紡ぎ司を指導する先生だ。
私が産まれる前から紡ぎ司をしていて、私が候補生から紡ぎ司になった年に引退した女性だ。
西の地で、私を毎日のようにお茶に誘ってくれた人。
不思議な人で、何も言わないけれど視線はとても問いかけて来るような人だった。
そんな記憶。
嫌われてはいなかった、多分。
「うん」
こくりと頷く。
「どうしたんだい?ラン君、どういう風の吹き回しだね?」
「良い機会じゃないですか?フォンさんも、是非西の地の重鎮に連絡を入れてくださいね?サーヤが原石を見たいんだって、必ず伝えてくださいよ?」
「それはどうだろうね?そんなことを言ったら、個室を用意されるよ?それでも良いのかい?サーヤちゃんは、多分こうやって並んでるのを眺めたいんじゃないのかって思うけどね?私は」
奥さんとランの会話は小さくて、内容までは聞こえなかった。
だけど、不思議と西の地に行く気になっていた。
西の地で、原石を見たい。
そう不思議と思っていた。
「そうだね、じゃあとても高貴な人が行くから、客の出入りだけ制限させておくかね?」
奥さんの言葉に、ハッとした。
「え?奥さんそれは悪いから良いよ。他のお客さんの迷惑になっちゃうから」
私の言葉に、奥さんは少しだけ困った顔をした。
「でもね?大事なサーヤちゃんが、私の店で嫌な思いをしたらと思うと、それが心配なんだよ」
「嫌な思い?」
「ほら、西の地は偏屈な人が多いだろ?それで、紡ぎ司をしてるサーヤちゃんに、何か言いがかりとか文句を言う奴がいても困るし」
奥さんの言葉に、少しだけ迷う。
確かに、怖い人がいたら嫌だなぁ。
「じゃあ、原石だけ見て終わりにする」
他の商品は見ない。
というか、興味がないから。
「ここと同じで、原石って多くないでしょ?装飾品は興味ないし」
「あらあら、ラン君残念ね?」
クラリスさんの言葉に、ランが苦笑を返していた。
何で?
「そうだね、詳しい時間だけでも分かったら教えてほしいね」
奥さんがランにそう言っていた。
「はい、じゃあ14時きっかりにしましょうか?そこから30分、それなら石を見て終わりですよ?」
「うん、分かった」
「コルダ様にも、14時に商店に行くことを伝えれば切り上げも可能ですし」
「うんうん」
「候補生は来るのかい?」
「いいえ?何故連れてくると思われているんですか?」
「なら良いや。分かった14時だね?じゃあ、それで旦那には伝えておくよ」
「ありがとうございます」
急に決まった今日の予定。
ま、いっか。
「じゃあ、お昼は手軽に食べられるようホットサンドでどうです?」
クラリスさんの言葉に、首を傾げる?
「ホットサンド?」
「えぇ、パンに色々な物を挟んで、それをオーブンやコンロで焼くんですよ?とてもおいしいので、お勧めですよ」
「そうなんだ?どんなのか気になる」
私の言葉に、クラリスさんがおっとりと笑った。
「もう、挟んであるものと、中身を選ぶのとどちらが良いかしら?」
「えーと…」
どっちでも良いなぁ。
ちらりとランを見る。
「ランが選んでくれる?」
「仰せの通りに」
「じゃあ、ラン君はこっちに」
クラリスさんとランが食べ物が置いてある方に移動する。
「どれか、気になるのあったかい?」
奥さんの言葉に、また原石を見る。
近くで見ようと、しゃがみ込む。
何か、全部同じに見える。
というか、多分どれでもあの幼馴染は喜びそう。
「時々冒険者が買って行くくらいだからね?そこの下段はほとんど売れたことがないよ」
「売れた方が良い?」
「まぁ、残って邪魔になるよりかはね?」
「じゃあ、奥さんが要らないなって思う石を買うね」
「何でだい?」
「売り上げに貢献するため?あ、でも、ここの石は高くないのか?じゃあ、あんまり貢献できないかな?」
奥さんが声を出して笑っていた。
「充分貢献してるさ?じゃあ、私の選んだ石で購入で良いのかい?」
「うん」
私が選んでも、多分変わらないし。
並んでいる石を、一通り撫でるけれど。
うん、どれも同じに見えるし感じる。
「あ、そうだ。そうしたら、私の実家の近くにある」
「家具工房の親方の所に送るので良いかい?」
「うん」
奥さんの息子さんは、そこで修業をしていたから住所は知っているのだろう。
本当は、幼馴染の工房に送った方が良いのだろう。
だけど彼女の家族は、理由をつけて幼馴染の家に届けてくれるから。
だから、幼馴染の実家で良いだろう。
「じゃあ、代金を」
「分かってないねぇ」
奥さんの言葉に、何がと思う。
「サーヤちゃんは、ツケがあるんだよ?だから、この原石代もいらないよ?」
「えぇ?」
でも、いくらくらいとか教えてくれるかな?
「残りはいくらくらい?」
「銀貨5枚くらいかね?」
奥さんの言葉に、首を傾げる。
「結構曖昧だね」
「駄目かい?」
「奥さんが損しないなら、良いよ」
私の言葉に、奥さんが豪快に笑った。
「毎度あり!」
じゃあ、これで今日の買い物は終了だ。
何か、いっぱい気分転換が出来たなぁ。
奥さんの言葉に、こくりと頷いた。
隣なのにこのお店に来るのは、先月ぶりだ。
ほぼ毎日、奥さんとは顔を会わせているのに。
あの時はまだ寒い時で、お鍋に入れる具材をランと見に来たんだっけ?
「ほら、ここが南の地での特産物だよ?」
奥さんが示した所に、見覚えのある懐かしい風景が広がった。
南の地では、木や畑から直で採って来るのが日常だった。
そのくらい目には馴染みがある。
それが、こうやって籠とか箱とかに入っていたり、紐で束ねられて商品になっているのは何だか変な感じ。
「ピルクはないんだけどね?モモも甘いんじゃないかな?」
奥さんの言葉に、モモも食べていたけれど大きいから食べにくいことを一緒に思い出す。
嫌いじゃない。
だけど、昔は手が汚れても口の周りがベタベタになっても気にしていなかった。
成長したってことかな?
それとも面倒になっただけ?
良いことなのか悪いことなのか分からず、曖昧に首を傾げる。
「うーん、嫌いじゃないけど、手がベタベタになるんだよね…」
「ラン君が全部やってくれるだろ?」
その言葉に苦笑する。
側にいるランの顔は変わらない。
え?当たり前とか思われているのは嫌なんだけど。
でも、事実だから何も言えない。
さっき、反省したばっかりなのに。
メイドみたいなことをさせてって。
「うーん、良いや」
「特に欲しいというわけでもない?」
「…そうだね」
私の様子がそうでもなかったこともあり、ランも無理に進めるという雰囲気ではない。
だから、食べ物コーナーを遠く眺める。
「懐かしいなぁ、と思うくらいかな」
「じゃあ、適当にいくつか買っておこうか?」
調理方法とか知らないランがそんなことを言うのに笑ってしまう。
「いいよ」
「ですが…」
「ランは、お手伝いさんじゃないでしょ?」
「そうだけど…」
そう言いながら、野菜や乾麺、果物なんかを眺める。
こうやって見ても懐かしいけれど、特に何かを欲しいと思うものはなかった。
ピルクほどテンションも上がらないというか…。
それだけ、この北の地での生活に慣れたってことなのかな?
ふと、目に着いた装飾品に意識が向く。
幼馴染が作ったのとは毛色が違う、何かオシャレそうなブレスレットや指輪だ。
「何だい?サーヤちゃん、こういう宝石類気になるのかい?」
「え?うーん、気になるというか…石が見たいと言うか…」
装飾されていない、原石と言うのかそういうものも下の段には並んでいる。
私が気になっているのは、そこだった。
道端に落ちているようなゴツゴツした物から、河原で見かけるつるりとした丸みを帯びた石まで。
多くはないけれど、並んでいるものを眺める。
しゃがみこんでじっと見つめていると『あらぁ』と穏やかな声がした。
何か、聞き覚えあるなぁと思っているとクスクス笑い声が聞こえた。
「あらあら、サーヤちゃんもお年頃になったのかしら?」
クラリスさんだった。
「こんにちは、クラリスさん。何か会うの久しぶりな気がする。…何がお年頃?」
言われた言葉が理解できずに、首を傾げる。
しゃがんでいるから、クラリスさんを見上げる形だ。
クラリスさんは背が高い。
奥さんは私よりは背が高いけど、クラリスさんに比べると低くなる。
「はい、こんにちは。あら?サーヤちゃん、ネックレスとかを見てるんじゃないの?」
クラリスさんの言葉に、ふるふると首を振る。
「ううん、幼馴染がこういう原石?石に興味があってね?もし、変わったのがあったらなぁって…」
「そうだったの?残念ね、ラン君」
何でラン?
ランはにこやかに笑っているだけだ。
「ランは何で残念なの?」
こんなに笑ってて、残念?
「あら?サーヤちゃんが、宝石に興味を持ったら、ラン君が高額商品を買ってくれるんじゃないかって?」
クラリスさんのお茶目なウィンク。
「高額?それはいらないかな?ランには、ほんとに感謝してもしきれないほどお世話になってるし、これ以上迷惑はかけられないよ?」
私の迷いながらの言葉に、ランは「全然、迷惑なんてかかってないから」とはっきり言った。
「それに、分かっちゃいないね?クラリスは。ラン君はサーヤちゃんの好みは、すでに熟知済みだよ」
奥さんの言葉に、ランは得意そうに頷いた。
「仰る通りで」
「あらあら、そうなのね。私もまだまだね」
クスクス笑うクラリスさん。
「ラン?」
さっきのエリザさんの言葉を思い出す。
「ランのお仕事、大変じゃない?」
「何で?」
「だって、さっきエリザさんが…」
ランは優秀だから1人でも出来ている助手だと言った。
本当は、私みたいに何もできない人間にはたくさん手を焼く人が必要なのかも。
落ち込むなぁ。
なのに、ランは何でもない顔をしている。
「あぁ、サーヤは助手10人欲しいの?」
ランの言葉に、今度はぶんぶんと首を振った。
「そんなにいらない!それに、助手の人に迷惑だよ。こんな、何も出来ない紡ぎ司なんて…」
「サーヤ」
ランの優しい声。
「何?」
答える私は少しおどおどしている。
奥さんとクラリスさんに見られているのも、何かなぁ。
こんなとこで、ランに何を言われるのか。
きっとランのことだろうから、嫌なことは言わないだろうけど…。
「サーヤは、紡ぎ司として立派です。それは、誰よりも近くで見ている俺が、絶対に自信を持って言えることです。だから、何も出来ないなんて言わないで?」
「でも、私…パンも上手に焼けない」
「パン?」
ランの言葉にこくりと頷く。
「パン、朝焦がしたでしょ?」
答える私の言葉に、奥さんが吹き出した。
「何だい?サーヤちゃんは、まだそんなこと気にしてんのかい?」
奥さんの言葉に、『そんなこと?』と聞き返す。
「コンロでパン焼くのなんて、主婦だって間違えることもあるさ」
「そうなの?」
「それに焦がしたパンだって、炭になって畑の浄化に役に立った。残りは食べられた、なら良いじゃないか?そうだろう?クラリス?」
クラリスさんは『そうですねぇ』と呑気に頷いた。
「今朝、パンを焦がしちゃったんだ」
恥ずかしそうに言う私にクラリスさんはクスクス笑った。
「あら、私なんてしょっちゅうお鍋を焦がして、旦那様に呆れられていますよ?」
クラリスさんの言葉に、しょっちゅう?と呟く。
「そうなの?パン、焦がしても呆れない?」
「何でそんなに自信がないのかね?サーヤちゃんは、立派な紡ぎ司だろう?」
奥さんの言葉にもコクリと頷く。
「立派、かどうかは分からないけど…。そっか、うん、紡ぎ司はちゃんとしてるつもり、かな?」
「じゃあ、私達の生活を豊かにしてくれているのは、間違いなくサーヤちゃんだわ。毎日、ありがとう」
クラリスさんののんびりとした言葉に、何か元気が湧いてくる。
ありがとう
こうやって言われると、紡ぎ司で良かったと思える。
みんなの励ましで、何だかパンを焦がしたことも『まいっか』と思えるようになる。
「奥さん、クラリスさんありがとう。勿論、ランもいつもありがとう」
3人とも『どういたしまして』と笑ってくれた。
「サーヤちゃん?石に興味があるなら、西の地で探してみると良いと思うわ」
クラリスさんの言葉に、首を傾げる。
「西の地って、古いでしょう?原石も、古い物とか珍しい物が揃っているっていうし」
「何だい?クラリスは、家の店じゃなくて西の地の商店をお勧めするのかい?」
「あら?奥様、私は西の地のフォン商会をお勧めしたつもりなんですけど?」
「…やれやれ、それはそれで」
奥さんが少し困ってる。
何でだろう?
「あー、サーヤちゃん。そのね、西の地の私の店はね、少しだけ格式ばってるっていうか、そう!堅苦しいんだよ。サーヤちゃんはあまり好きじゃないだろ?」
奥さんの言葉にも、こくりと頷く。
確かに。
西の地だけでも、重苦しいのに。
そこに、堅苦しいのが加わったら少し嫌だなぁ。
「でも、石は気になる…」
悩む私に、ランが『そうだ!』と声を出した。
「なぁに?」
「サーヤ、午後に西の地に行きませんか?丁度、報告書を持って行く所だったんですよ?久しぶりに、コルダ様に会いませんか?」
コルダ様とは、西の地の紡ぎ司を指導する先生だ。
私が産まれる前から紡ぎ司をしていて、私が候補生から紡ぎ司になった年に引退した女性だ。
西の地で、私を毎日のようにお茶に誘ってくれた人。
不思議な人で、何も言わないけれど視線はとても問いかけて来るような人だった。
そんな記憶。
嫌われてはいなかった、多分。
「うん」
こくりと頷く。
「どうしたんだい?ラン君、どういう風の吹き回しだね?」
「良い機会じゃないですか?フォンさんも、是非西の地の重鎮に連絡を入れてくださいね?サーヤが原石を見たいんだって、必ず伝えてくださいよ?」
「それはどうだろうね?そんなことを言ったら、個室を用意されるよ?それでも良いのかい?サーヤちゃんは、多分こうやって並んでるのを眺めたいんじゃないのかって思うけどね?私は」
奥さんとランの会話は小さくて、内容までは聞こえなかった。
だけど、不思議と西の地に行く気になっていた。
西の地で、原石を見たい。
そう不思議と思っていた。
「そうだね、じゃあとても高貴な人が行くから、客の出入りだけ制限させておくかね?」
奥さんの言葉に、ハッとした。
「え?奥さんそれは悪いから良いよ。他のお客さんの迷惑になっちゃうから」
私の言葉に、奥さんは少しだけ困った顔をした。
「でもね?大事なサーヤちゃんが、私の店で嫌な思いをしたらと思うと、それが心配なんだよ」
「嫌な思い?」
「ほら、西の地は偏屈な人が多いだろ?それで、紡ぎ司をしてるサーヤちゃんに、何か言いがかりとか文句を言う奴がいても困るし」
奥さんの言葉に、少しだけ迷う。
確かに、怖い人がいたら嫌だなぁ。
「じゃあ、原石だけ見て終わりにする」
他の商品は見ない。
というか、興味がないから。
「ここと同じで、原石って多くないでしょ?装飾品は興味ないし」
「あらあら、ラン君残念ね?」
クラリスさんの言葉に、ランが苦笑を返していた。
何で?
「そうだね、詳しい時間だけでも分かったら教えてほしいね」
奥さんがランにそう言っていた。
「はい、じゃあ14時きっかりにしましょうか?そこから30分、それなら石を見て終わりですよ?」
「うん、分かった」
「コルダ様にも、14時に商店に行くことを伝えれば切り上げも可能ですし」
「うんうん」
「候補生は来るのかい?」
「いいえ?何故連れてくると思われているんですか?」
「なら良いや。分かった14時だね?じゃあ、それで旦那には伝えておくよ」
「ありがとうございます」
急に決まった今日の予定。
ま、いっか。
「じゃあ、お昼は手軽に食べられるようホットサンドでどうです?」
クラリスさんの言葉に、首を傾げる?
「ホットサンド?」
「えぇ、パンに色々な物を挟んで、それをオーブンやコンロで焼くんですよ?とてもおいしいので、お勧めですよ」
「そうなんだ?どんなのか気になる」
私の言葉に、クラリスさんがおっとりと笑った。
「もう、挟んであるものと、中身を選ぶのとどちらが良いかしら?」
「えーと…」
どっちでも良いなぁ。
ちらりとランを見る。
「ランが選んでくれる?」
「仰せの通りに」
「じゃあ、ラン君はこっちに」
クラリスさんとランが食べ物が置いてある方に移動する。
「どれか、気になるのあったかい?」
奥さんの言葉に、また原石を見る。
近くで見ようと、しゃがみ込む。
何か、全部同じに見える。
というか、多分どれでもあの幼馴染は喜びそう。
「時々冒険者が買って行くくらいだからね?そこの下段はほとんど売れたことがないよ」
「売れた方が良い?」
「まぁ、残って邪魔になるよりかはね?」
「じゃあ、奥さんが要らないなって思う石を買うね」
「何でだい?」
「売り上げに貢献するため?あ、でも、ここの石は高くないのか?じゃあ、あんまり貢献できないかな?」
奥さんが声を出して笑っていた。
「充分貢献してるさ?じゃあ、私の選んだ石で購入で良いのかい?」
「うん」
私が選んでも、多分変わらないし。
並んでいる石を、一通り撫でるけれど。
うん、どれも同じに見えるし感じる。
「あ、そうだ。そうしたら、私の実家の近くにある」
「家具工房の親方の所に送るので良いかい?」
「うん」
奥さんの息子さんは、そこで修業をしていたから住所は知っているのだろう。
本当は、幼馴染の工房に送った方が良いのだろう。
だけど彼女の家族は、理由をつけて幼馴染の家に届けてくれるから。
だから、幼馴染の実家で良いだろう。
「じゃあ、代金を」
「分かってないねぇ」
奥さんの言葉に、何がと思う。
「サーヤちゃんは、ツケがあるんだよ?だから、この原石代もいらないよ?」
「えぇ?」
でも、いくらくらいとか教えてくれるかな?
「残りはいくらくらい?」
「銀貨5枚くらいかね?」
奥さんの言葉に、首を傾げる。
「結構曖昧だね」
「駄目かい?」
「奥さんが損しないなら、良いよ」
私の言葉に、奥さんが豪快に笑った。
「毎度あり!」
じゃあ、これで今日の買い物は終了だ。
何か、いっぱい気分転換が出来たなぁ。
0
あなたにおすすめの小説


生贄姫の末路 【完結】
松林ナオ
児童書・童話
水の豊かな国の王様と魔物は、はるか昔にある契約を交わしました。
それは、姫を生贄に捧げる代わりに国へ繁栄をもたらすというものです。
水の豊かな国には双子のお姫様がいます。
ひとりは金色の髪をもつ、活発で愛らしい金のお姫様。
もうひとりは銀色の髪をもつ、表情が乏しく物静かな銀のお姫様。
王様が生贄に選んだのは、銀のお姫様でした。

独占欲強めの最強な不良さん、溺愛は盲目なほど。
猫菜こん
児童書・童話
小さな頃から、巻き込まれで絡まれ体質の私。
中学生になって、もう巻き込まれないようにひっそり暮らそう!
そう意気込んでいたのに……。
「可愛すぎる。もっと抱きしめさせてくれ。」
私、最強の不良さんに見初められちゃったみたいです。
巻き込まれ体質の不憫な中学生
ふわふわしているけど、しっかりした芯の持ち主
咲城和凜(さきしろかりん)
×
圧倒的な力とセンスを持つ、負け知らずの最強不良
和凜以外に容赦がない
天狼絆那(てんろうきずな)
些細な事だったのに、どうしてか私にくっつくイケメンさん。
彼曰く、私に一目惚れしたらしく……?
「おい、俺の和凜に何しやがる。」
「お前が無事なら、もうそれでいい……っ。」
「この世に存在している言葉だけじゃ表せないくらい、愛している。」
王道で溺愛、甘すぎる恋物語。
最強不良さんの溺愛は、独占的で盲目的。

14歳で定年ってマジ!? 世界を変えた少年漫画家、再起のノート
谷川 雅
児童書・童話
この世界、子どもがエリート。
“スーパーチャイルド制度”によって、能力のピークは12歳。
そして14歳で、まさかの《定年》。
6歳の星野幸弘は、将来の夢「世界を笑顔にする漫画家」を目指して全力疾走する。
だけど、定年まで残された時間はわずか8年……!
――そして14歳。夢は叶わぬまま、制度に押し流されるように“退場”を迎える。
だが、そんな幸弘の前に現れたのは、
「まちがえた人間」のノートが集まる、不思議な図書室だった。
これは、間違えたままじゃ終われなかった少年たちの“再スタート”の物語。
描けなかった物語の“つづき”は、きっと君の手の中にある。


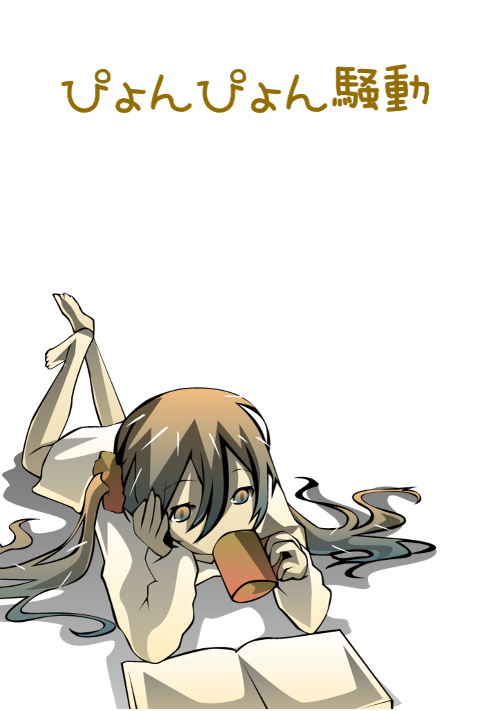
ぴょんぴょん騒動
はまだかよこ
児童書・童話
「ぴょんぴょん」という少女向け漫画雑誌がありました 1988年からわずか5年だけの短い命でした その「ぴょんぴょん」が大好きだった女の子のお話です ちょっと聞いてくださいませ
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















