5 / 21
第二章 執筆
春①
しおりを挟む
1 春
「それじゃあ、お二人は高校のときから同級生なんですか?」
「うん、そうだよ。ま、今は違うけどな」
「おい、余計なことを言うな」
あの日からちょうど一週間後の、通常授業が始まる前日、尊さんに誘われ、大学の駅の近くの居酒屋に三人で訪れている。
尊さんは無理に来なくてもいいよと言ってくれたが、二人のことはまだほとんど知らないし、何よりこういう経験も一度はしてみたいと思っていたので、東京で一番信頼できる人である尊さんの誘いに乗らない理由がなかった。
「高校の頃の奏さんって、どんな感じだったんですか?」
「うーん、まあ今よりは普通な感じだったな」
「まあ、それは否定しない」
「てか、普通に真面目だったよ。勉強も今よりよっぽどやってたし」
「今は真面目じゃないみたいに言うな」
「真面目じゃねえから留年したんだろうが」
奏さんはそれを否定せず、黙々と自分のグラスを手に取る。
「ホント、なんで留年一回で済んでるのかってぐらい、講義出てないよな」
「ふん、それは才能だから仕方ない」
「でも俺知ってるぞ。お前、テストのある科目めっちゃ避けてるだろ? だからこいつ、必修とかほとんど残ってるし、どっちにしろもう一回留年すんじゃね?」
「だから今まで執筆してきたやつを終わらせたら、今年は学業に専念しようと思ってたんだ。なのに、余計な仕事増やしやがって」
「あー、うっさいうっさい。真っ赤な目して泣きそうになりながらよく言うよ」
「これは花粉症だ!」
尊さんは奏さんをあしらいながら、店員を呼び、日本酒のお代わりを注文した。
「そういえば朱美ちゃんって、何学部なんだっけ?」
「文学部です」
「お、じゃあ奏と一緒じゃん」
「ホントですか!?」
そのタイミングで、ちょっと前に頼んだ私のウーロン茶のお代わりが運ばれてきた。
「あの、私、どの講義取ればいいのか全然わからなくて、よろしければ教えていただきたいんですけど……」
「俺もわからん」
「え?」
何食わぬ顔で、湧いた希望を打ち砕く。
「俺はすべて時間割の都合とテストの有無で決めていたから、どれがおすすめだとかは全くわからん。今まで取ってきたやつも、全く覚えてない。お陰で今年度の時間割は最低だ。自分の時間にしようとしていた時間がほとんど潰された」
「……そうなんですね」
「そもそも、学科も違うかもしれないだろう?」
「……確かに」
期待した私がバカだった。
「よかったらさ、朱美ちゃんの学科で知り合いいるかもしれないから、訊いてみようか?」
「え!?」
こっちの希望は相変わらず、正真正銘の希望だった。
「俺、ここ以外にも何個か別のサークル入ってるんだけど、文学部の奴も結構いるから、よかったら訊いてあげるよ」
「本当ですか!? すごく助かります!」
「あ、でも授業って明日から始まるんだっけ?」
「そうです! でも履修登録期間はまだ一週間くらいあるらしいので、大丈夫です!」
「あーそうなんだ。それなら大丈夫だね。それで、何学科なんだっけ?」
「えっとですね──」
学科を伝えると、尊さんはすぐに目を光らせた。
「お、それなら割とすぐ連絡付きそうな奴にいるわ! 今ラインしてみる!」
「え、すごい! ありがとうございます!」
本当にすぐに連絡が取れ、しかも予想以上に詳細に、授業や講義の情報を得られた。
もしかしたら尊さんは、ものすごく顔が広く、なおかつそれが人望と共に浸透している人なのかもしれない。今の私にとって、友人や恋人よりよっぽど価値のある存在だった。
「本当に、伝え切れないくらい、尊さんには感謝の気持ちでいっぱいです! 本当にありがとうございます!」
「やめてや、そんな大袈裟な」
「本当です! 私、そういう情報全く持ってなくて、他の人に置いていかれないかすごく不安だったので、すごく心強いです!」
「ま、一応言っとくと、奏も同じ学科なんだけどね」
「そうなんですか!?」
「だからすぐに知り合い見つかったんだ。そいつとも奏のこと時々話してたから」
「なるほど」
ある程度ではあるが二人のことを知れて、居酒屋デビューも果たし、何より、現時点での大学生活の不安の半分が解消された。今日一日、というかたった二時間くらいだが、とんでもない収獲を得ることができた。昼過ぎに起きた日中には考えられないくらい、充実の夜であった。やはり、外には出てみるべきである。
「奏も朱美ちゃんにおすすめの講義教えてもらえよ」
「な、なんでだ!?」
「お前の方が履修ヤバいだろ? 絶対今の話、お前の方が必要だったろ?」
「どこの世界に一年生におすすめの講義を教えてもらう三年生がいるんだ!? 一部の例外だろう!? そんなもの、俺のプライドが許さん!」
「お前がその例外だって言ってんだよ。ドラゴンボールのキャラみたいなこと言ってねえで素直になれや。ま、こいつのことだからちゃっかり聞き耳立ててそうだけど」
なかなかのパンチを食らった奏さんは、そのまま立ち上がり、おそらくお手洗いに向かった。
「んじゃ、そろそろ帰りますか。朱美ちゃんも明日から授業だしね」
「あ、はい! 今日は色々ありがとうございました!」
「いえいえ。会計済ましとくから先出てていいよ」
「そんな! 私も払います!」
「朱美ちゃん、ここはむしろ遠慮する方が失礼なんだよ?」
「え? そうなんですか……?」
「嘘嘘。まあ、人それぞれだけどね。だけどさすがに今回は先輩が払わないとまずいから、遠慮しないで」
「そう、なんですか。ありがとうございます!」
たぶん、そうなのだろう。
ただ今日に関しては、ここまでの尊さんへの恩が洒落にならないくらいに溜まっていたので、何とか形にしたかった。だが、その隙すら与えてくれない。この人と入学早々に出会えた私は、なんて運が良いのだろう。世の中、捨てたもんじゃない。
さすがに先に一人で店を出るのは気が引けたので、会計を済ます尊さんの後ろにコソコソついていくと、いつの間にか奏さんの荷物が席から消えていた。
「奏さん、どこ行っちゃったんでしょうか?」
「たぶん、もう外出たんだと思うよ」
そのまま二人で店を出ると、尊さんの予想通り、奏さんは既に店の外に出ていた。
「あいつ、前世が忍者だったんじゃないかってくらい、気配消すの上手いんだよね」
「そんな特技もあったんですね」
私たちが出てきたのを確認し、奏さんは前を一人で歩きだした。同時に私と尊さんも、奏さんに追いつかない程度のスピードで歩き出す。
「奏さんって、いつから小説書き始めたんでしょうか?」
「うーん、中学までは知らないけど、高校のときはもう色々書いてたよ。あの小説もそうだし」
「やっぱりそうだったんですね」
「ただ、その当時のものは、たぶんほとんど残ってない」
「え……、なんで、ですか?」
「まあ、色々あったんだよ」
「色々あった」、彼らは口々にその七音を用いる。それは逃げや示唆などではなく、真正面から、彼らの高校時代に起きた何かしらの出来事を鎖にしている。果たして私は、その鎖を解けるほど、彼らの世界に踏み入ることはできるのだろうか。
「ということは逆に、奏さんは大学に入ってからの三年間で、十五個もの作品を執筆したってことですか?」
「そうなるね」
「すごいスピードですよ! それにあれ、内容はともかく、文章量としてはどれも五〇〇ページ近くありますよ! 信じられない……」
「ま、だから留年したんだろうね」
柔らかい尊さんの一言が、二人の笑いを誘う。
だが間違いなく、奏さんの執筆スピードは半端なものではない。
「ちなみに尊さんは、小説は書かれないんですか?」
「うん。小説は書かないかな。目指してるジャンル的には近いとも言えるんだけど」
「えっと、尊さんが目指してるジャンルというのは?」
「放送作家って、わかる?」
「あ、あれですよね! お笑い番組とかの台本書いてる──」
「そうそう! 俺一応、あれ目指しててさ。今もその就活中なんだけど」
どことなく奏さんとのやり取りからも、そのような雰囲気が窺える。
「でもそれって、すごい業界的な仕事じゃん? だから今のうちにいろんなサークル入ったり、いろんなところに顔出したりして、人脈とかコネとか作るようにしてるんだよね」
「な、なるほど」
高校の先生もそうだったが、この世には生きている世界が違う人間がいるということを、改めて実感した。奏さんはともかく、こんなに近くにいることを感じられる尊さんですらそうなのだから、少し、自信がなくなってしまう。
「ここもさ、有名な小説家の人の出身だし、出版業界の人とも知り合いになれるかもと思って入ったんだけど、まあ、今さら言ってもしょうがないよね」
だが彼は、今でもここに籍を置いている。その理由は、やはり、
「やっぱり、奏さんがいるからですか?」
「え?」
脳内と口外がこんがらがり、不要な誤解を与えてしまった。
だが慌てて訂正すると、すぐに理解してくれた。
「まあ、そうだね。あいつとは高校時代、ほぼ一緒に居たし。それに、高校までのあいつの小説は、嫌いじゃない」
不意に見せる真剣な瞳に、思わず見入ってしまう。
この人も私と同様、あの小説の完成を待っている一人なんだ。いくら生きている世界は違っていても、その気持ちは、同じなんだ。
「絶対、完成させます! 尊さんに、恩返しできるように!」
その瞬間、彼はその柔らかな笑顔を、私に独占させてくれた。
「期待、してるよ……!」
すると前方で、奏さんが足を止め、何かを眺めている姿が目に入った。
「あの、尊さん、あれ」
「ああ、あれか」
尊さんは特に驚きもせず、妙な位置で固まっている奏さんを見る。
「よくあるんだよ、あれ」
「何を、見てらっしゃるんでしょうか?」
「たぶん、月だよ」
「月?」
確かによく見ると、奏さんの視線は夜空に向いている。
「なんでかは知らないけど、あいつ、夜に外歩いてると、たまにああやって月をひたすら眺めるんだ。堂々と道で立ち止まって」
「なんか、神秘的ですね……!」
「そうか? ただの迷惑行為だと思うけど」
そう言いながらも尊さんは、固まる奏さんを優しく見つめている。
「ただ、あれをやってるときに大抵アイデアが降りてくるらしい。それっぽく見せてるだけの嘘かもしれないけど」
いや、あれはたぶん、本当にアイデアが生まれているのだと思う。
月夜に照らされる彼を見て、ふと、そう直感した。
「ああなったらしばらくかかるから、先に行く? あのまま放っておいても大丈夫だよ? 別に後で怒ったりしないから」
「いえ、あの、できればでいいんですけど、」
そうやってインスピレーションは開花していくのだと、月の光が教えてくれる。
その瞬間を、見逃すわけにはいかない。
「私も、その、奏さんのことを、見ていてもいいでしょうか?」
そのとき、尊さんは私を見なかった。
まるで、私の言葉がわかっていたかのように。
「やっぱり、とんでもない娘だな」
そうして尊さんは、近くにあったベンチに座った。
「いいよ。俺も付き合う。でも、せめて座りな? 立つことまで付き合わなくてもいいだろ?」
促され、私も座った。奏さんは変わらず、ただそこで立ち止まり、月を眺めている。
だが一瞬、視線をそのままに、身体だけを三六〇度回転させた。
そして、徐に呟く。
「月が、綺麗だ」
そのままゆっくりと、視線を落とし、瞳を閉じる。
そのとき、一瞬だけ、奏さんの佇まいは、現実だとは思えなかった。
あれから約一ヵ月が経ち、新生活は徐々に日常と化してきた。
その頃の私はというと、講義には積極的に出席し、第二外国語で同じクラスになった女の子の友人もでき、バイトも見つかるなど、少しずつではあるが、大学生活に慣れつつあった。
だがそれのどれもが、元はと言えば尊さんの存在のお陰である。どの講義を取ればいいのかも、その情報を今の友人と共有することで仲良くなったのも、尊さんの存在なしではありえない。さらに言えば、バイト先は尊さんの紹介で決まった。尊さんの知り合いに私のアパートの近くに住んでいる二年生の女性の先輩がおり、彼女のバイト先のコンビニで働かせてもらえることとなった。さらに彼女はとても面倒見をよくしてくれて、たまに家に伺ってご飯を作ってくれるなど、様々な面でサポートしてもらっている。先輩も、先輩を紹介してくれた尊さんにも、本当に頭が上がらない。
ただ、最近は直接会えてはいない。部室にも顔を出すことは少なく、その感謝を伝えることができない。いつでも連絡してくれていいよと言ってくれたが、想定される彼の現在の状況を鑑みれば、頼みたいことがあってもなかなか頼みづらい。
その一方で、もう一人のサークルの先輩は、捕まえようと思えばいつでも捕まえられるだろう。なぜならその人は、今私がいるこの大教室内に、堂々と君臨しているのだから。
「あの人、なんかすごくない!? 右手でレジュメ書いて、左手でノートパソコン使ってるよ!? もしかして、なにか起業した人かも!」
相変わらず無駄に器用な彼の姿を見て、一緒に講義を受けている友人は変な勘違いをしている。
しかし、無理もない。確かに今の彼は、ほとんど人がいない大教室の前列に堂々と居座り、彼女の言うように、右手でレジュメに文字を書き、左手でノートパソコンのキーボードを叩いている。おそらくギリギリ良い意味で、只者には見えない挙動であった。
そんな大教室での光景に、今では何かと慣れてしまった。もちろん元々彼を知っているからというのもあるが、尊さんが言っていたように、奏さんは普通一年生で取るような講義を悉くスルーしていたのか、結構な確率で同じ講義を受講していた。だからこそ、今のような光景は、もはや私の中では日常の一欠片に過ぎないのだ。
かと言って、それについて本人と話すわけではない。と言うより、尊さんと会えなくなって以降、奏さんとはほとんど話していない。個人的には執筆の進捗を訊くために話しかけたいのだが、教室内ではそれは憚られるし、部室に行っても、相変わらず何かの作業に熱中し、話しかけにくい雰囲気を醸し出している。もしかしてあの小説の続きを執筆しているのではないかと考えると、変に問い質すわけにもいかない。
そんなこんなで、私は今、順調に運び出した私生活とは裏腹に、微妙なモヤモヤが心から取り除けない。このことを尊さんに相談したいのだが、先ほど言ったようにそういうわけにもいかないため、余計にモヤモヤが募る。
「じゃあ、また来週! 夏目さん!」
今日の最後の講義を終え、友人と別れた。
まだ15時過ぎであるが、この後はバイトもないため、夜までだいぶ時間が空いている。こういうときはとりあえず部室に行ってみるのだが、尊さんは十中八九いないし、ほとんどの確率で自分の作業机に姿を現す奏さんも、もしかしたらまだいないかも、
「失礼しまーす」
と、微かに思って部室に入ると、結局、彼はそこにいた。
確かに私たちより先に半駆け足で教室を飛び出していったが、それにしても、他の場所では体力ゲージが自動的に減っていくのかと思わせるぐらい、彼はいつも部室にいた。ここはワープ機能でも搭載されているのだろうか。
一方で私も、専用になりつつあるいつもの場所で本を読み、時間を潰していた。アニメや漫画でよく出てくる穏やかな文化部の空間のように、それぞれの沈黙が、古いこの部室全体を貫いている。
そんなとき、部室の中央に設置されている机の端っこに、あの小説が書かれた紙の束が置かれていることに気付いた。昨日はなかったはずなので、それをここに置いた人物は一人である。ただ、奥にいるその人物に、そのことを訊くことはできなかった。
とりあえず手に取り、書かれている文言を目に浮かばせる。相変わらず繊細で、大胆で、美しい。ストーリーには粗野な部分も見受けられるが、それでも刻まれている文字の並びに、図らずも釘付けになる。必ずやそれは、釘付けになった人の数だけ、明日を照らす光になる。真っ暗な夜を神秘的に彩る、月の光のように。
「あの、奏さん!」
やはり、なんとしても完成させたい。月の光を、世界中に届かせるために。
そう思った瞬間、沈黙を破る勇気が湧いた。
「ん? ああ、いたのか」
「今、何をやってらっしゃるんですか?」
「お、聞きたいか?」
あ、これ、ダメなやつだ。
「一ヵ月くらい前に、君と尊と三人で居酒屋に行った日があったろう? その日の帰りなんだが、急にアイデアがパッと思いついてね。それで執筆を始めたら、もう止まらなくなってしまって、その内容というのが──」
ああ、尊さん、戻ってきて。私一人でこれを聞かされるのは、さすがに無理がある。
「──というところまで進んだんだが、なかなかその先が思いつかなくてな。ん? そうだ、君、確か俺の執筆に協力するとか言っていたよな? それなら是非してほしいことがあるのだが、どうだろうか?」
なぜこの人は、物事をこんなにも都合良く解釈できるのだろう。これを完全に操っていた尊さんは、天才という類以外では考えられない。
「あの!」
急に大声を出した私に、彼は少しだけたじろいだ。
「私が聞きたいのは、これの話なんです!」
傍らにあるその紙束を掴み、彼に見せつけた。
「これ、書くって約束したでしょう? なのにまた変なもの書き始めて、全然約束守ってくれないじゃないですか! いい加減にしてください!」
普段はおとなしい私の突然の攻勢に、虚を衝かれたのだろう。彼は茫然としている。
「いや、その、忘れていたわけじゃないし、書こうと思う意志はあるんだ。しかし……」
意外なその言葉に、今度は私が虚を衝かれた。
「ストーリーがどうしても、行き詰まってしまって」
確かによく考えれば、この紙束を机に置いたのは彼であり、それはすなわち何かしらのアクションがあったということだろう。そうしてその末に、その行き詰まりに嵌ったのだ。
「どんな風に、ですか?」
「その、主人公が相手の女性を渋谷にデートに誘う展開を考えているんだが……」
思ったよりも定石通りのノーマルな設定に、逆に先が気になった。
「俺はそもそも、渋谷に行ったことがない」
なるほど、そういうことか。そりゃ、展開に行き詰まるわけだ。
ということは、これはつまり、
「行けば、いいんでしょう?」
「え?」
やっと、前に進める。時計の針は、確かに動いている。
「行きましょうよ! 渋谷! 行って、色々体験して、それで先に繋げましょう!」
「随分強引だな……」
「協力するって言ったでしょう? 取材ですよ、取材! それで、いつ行きます? 今週末なんかどうですか? 明日とか、明後日とか」
「日曜なら、一応空いてるが」
「決まりですね! それじゃ、明後日渋谷で会いましょう!」
白状しよう。私は今、心が躍っている。なぜかって? 理由は単純。
単に私は、渋谷に行ってみたかったのだ。
「それじゃあ、お二人は高校のときから同級生なんですか?」
「うん、そうだよ。ま、今は違うけどな」
「おい、余計なことを言うな」
あの日からちょうど一週間後の、通常授業が始まる前日、尊さんに誘われ、大学の駅の近くの居酒屋に三人で訪れている。
尊さんは無理に来なくてもいいよと言ってくれたが、二人のことはまだほとんど知らないし、何よりこういう経験も一度はしてみたいと思っていたので、東京で一番信頼できる人である尊さんの誘いに乗らない理由がなかった。
「高校の頃の奏さんって、どんな感じだったんですか?」
「うーん、まあ今よりは普通な感じだったな」
「まあ、それは否定しない」
「てか、普通に真面目だったよ。勉強も今よりよっぽどやってたし」
「今は真面目じゃないみたいに言うな」
「真面目じゃねえから留年したんだろうが」
奏さんはそれを否定せず、黙々と自分のグラスを手に取る。
「ホント、なんで留年一回で済んでるのかってぐらい、講義出てないよな」
「ふん、それは才能だから仕方ない」
「でも俺知ってるぞ。お前、テストのある科目めっちゃ避けてるだろ? だからこいつ、必修とかほとんど残ってるし、どっちにしろもう一回留年すんじゃね?」
「だから今まで執筆してきたやつを終わらせたら、今年は学業に専念しようと思ってたんだ。なのに、余計な仕事増やしやがって」
「あー、うっさいうっさい。真っ赤な目して泣きそうになりながらよく言うよ」
「これは花粉症だ!」
尊さんは奏さんをあしらいながら、店員を呼び、日本酒のお代わりを注文した。
「そういえば朱美ちゃんって、何学部なんだっけ?」
「文学部です」
「お、じゃあ奏と一緒じゃん」
「ホントですか!?」
そのタイミングで、ちょっと前に頼んだ私のウーロン茶のお代わりが運ばれてきた。
「あの、私、どの講義取ればいいのか全然わからなくて、よろしければ教えていただきたいんですけど……」
「俺もわからん」
「え?」
何食わぬ顔で、湧いた希望を打ち砕く。
「俺はすべて時間割の都合とテストの有無で決めていたから、どれがおすすめだとかは全くわからん。今まで取ってきたやつも、全く覚えてない。お陰で今年度の時間割は最低だ。自分の時間にしようとしていた時間がほとんど潰された」
「……そうなんですね」
「そもそも、学科も違うかもしれないだろう?」
「……確かに」
期待した私がバカだった。
「よかったらさ、朱美ちゃんの学科で知り合いいるかもしれないから、訊いてみようか?」
「え!?」
こっちの希望は相変わらず、正真正銘の希望だった。
「俺、ここ以外にも何個か別のサークル入ってるんだけど、文学部の奴も結構いるから、よかったら訊いてあげるよ」
「本当ですか!? すごく助かります!」
「あ、でも授業って明日から始まるんだっけ?」
「そうです! でも履修登録期間はまだ一週間くらいあるらしいので、大丈夫です!」
「あーそうなんだ。それなら大丈夫だね。それで、何学科なんだっけ?」
「えっとですね──」
学科を伝えると、尊さんはすぐに目を光らせた。
「お、それなら割とすぐ連絡付きそうな奴にいるわ! 今ラインしてみる!」
「え、すごい! ありがとうございます!」
本当にすぐに連絡が取れ、しかも予想以上に詳細に、授業や講義の情報を得られた。
もしかしたら尊さんは、ものすごく顔が広く、なおかつそれが人望と共に浸透している人なのかもしれない。今の私にとって、友人や恋人よりよっぽど価値のある存在だった。
「本当に、伝え切れないくらい、尊さんには感謝の気持ちでいっぱいです! 本当にありがとうございます!」
「やめてや、そんな大袈裟な」
「本当です! 私、そういう情報全く持ってなくて、他の人に置いていかれないかすごく不安だったので、すごく心強いです!」
「ま、一応言っとくと、奏も同じ学科なんだけどね」
「そうなんですか!?」
「だからすぐに知り合い見つかったんだ。そいつとも奏のこと時々話してたから」
「なるほど」
ある程度ではあるが二人のことを知れて、居酒屋デビューも果たし、何より、現時点での大学生活の不安の半分が解消された。今日一日、というかたった二時間くらいだが、とんでもない収獲を得ることができた。昼過ぎに起きた日中には考えられないくらい、充実の夜であった。やはり、外には出てみるべきである。
「奏も朱美ちゃんにおすすめの講義教えてもらえよ」
「な、なんでだ!?」
「お前の方が履修ヤバいだろ? 絶対今の話、お前の方が必要だったろ?」
「どこの世界に一年生におすすめの講義を教えてもらう三年生がいるんだ!? 一部の例外だろう!? そんなもの、俺のプライドが許さん!」
「お前がその例外だって言ってんだよ。ドラゴンボールのキャラみたいなこと言ってねえで素直になれや。ま、こいつのことだからちゃっかり聞き耳立ててそうだけど」
なかなかのパンチを食らった奏さんは、そのまま立ち上がり、おそらくお手洗いに向かった。
「んじゃ、そろそろ帰りますか。朱美ちゃんも明日から授業だしね」
「あ、はい! 今日は色々ありがとうございました!」
「いえいえ。会計済ましとくから先出てていいよ」
「そんな! 私も払います!」
「朱美ちゃん、ここはむしろ遠慮する方が失礼なんだよ?」
「え? そうなんですか……?」
「嘘嘘。まあ、人それぞれだけどね。だけどさすがに今回は先輩が払わないとまずいから、遠慮しないで」
「そう、なんですか。ありがとうございます!」
たぶん、そうなのだろう。
ただ今日に関しては、ここまでの尊さんへの恩が洒落にならないくらいに溜まっていたので、何とか形にしたかった。だが、その隙すら与えてくれない。この人と入学早々に出会えた私は、なんて運が良いのだろう。世の中、捨てたもんじゃない。
さすがに先に一人で店を出るのは気が引けたので、会計を済ます尊さんの後ろにコソコソついていくと、いつの間にか奏さんの荷物が席から消えていた。
「奏さん、どこ行っちゃったんでしょうか?」
「たぶん、もう外出たんだと思うよ」
そのまま二人で店を出ると、尊さんの予想通り、奏さんは既に店の外に出ていた。
「あいつ、前世が忍者だったんじゃないかってくらい、気配消すの上手いんだよね」
「そんな特技もあったんですね」
私たちが出てきたのを確認し、奏さんは前を一人で歩きだした。同時に私と尊さんも、奏さんに追いつかない程度のスピードで歩き出す。
「奏さんって、いつから小説書き始めたんでしょうか?」
「うーん、中学までは知らないけど、高校のときはもう色々書いてたよ。あの小説もそうだし」
「やっぱりそうだったんですね」
「ただ、その当時のものは、たぶんほとんど残ってない」
「え……、なんで、ですか?」
「まあ、色々あったんだよ」
「色々あった」、彼らは口々にその七音を用いる。それは逃げや示唆などではなく、真正面から、彼らの高校時代に起きた何かしらの出来事を鎖にしている。果たして私は、その鎖を解けるほど、彼らの世界に踏み入ることはできるのだろうか。
「ということは逆に、奏さんは大学に入ってからの三年間で、十五個もの作品を執筆したってことですか?」
「そうなるね」
「すごいスピードですよ! それにあれ、内容はともかく、文章量としてはどれも五〇〇ページ近くありますよ! 信じられない……」
「ま、だから留年したんだろうね」
柔らかい尊さんの一言が、二人の笑いを誘う。
だが間違いなく、奏さんの執筆スピードは半端なものではない。
「ちなみに尊さんは、小説は書かれないんですか?」
「うん。小説は書かないかな。目指してるジャンル的には近いとも言えるんだけど」
「えっと、尊さんが目指してるジャンルというのは?」
「放送作家って、わかる?」
「あ、あれですよね! お笑い番組とかの台本書いてる──」
「そうそう! 俺一応、あれ目指しててさ。今もその就活中なんだけど」
どことなく奏さんとのやり取りからも、そのような雰囲気が窺える。
「でもそれって、すごい業界的な仕事じゃん? だから今のうちにいろんなサークル入ったり、いろんなところに顔出したりして、人脈とかコネとか作るようにしてるんだよね」
「な、なるほど」
高校の先生もそうだったが、この世には生きている世界が違う人間がいるということを、改めて実感した。奏さんはともかく、こんなに近くにいることを感じられる尊さんですらそうなのだから、少し、自信がなくなってしまう。
「ここもさ、有名な小説家の人の出身だし、出版業界の人とも知り合いになれるかもと思って入ったんだけど、まあ、今さら言ってもしょうがないよね」
だが彼は、今でもここに籍を置いている。その理由は、やはり、
「やっぱり、奏さんがいるからですか?」
「え?」
脳内と口外がこんがらがり、不要な誤解を与えてしまった。
だが慌てて訂正すると、すぐに理解してくれた。
「まあ、そうだね。あいつとは高校時代、ほぼ一緒に居たし。それに、高校までのあいつの小説は、嫌いじゃない」
不意に見せる真剣な瞳に、思わず見入ってしまう。
この人も私と同様、あの小説の完成を待っている一人なんだ。いくら生きている世界は違っていても、その気持ちは、同じなんだ。
「絶対、完成させます! 尊さんに、恩返しできるように!」
その瞬間、彼はその柔らかな笑顔を、私に独占させてくれた。
「期待、してるよ……!」
すると前方で、奏さんが足を止め、何かを眺めている姿が目に入った。
「あの、尊さん、あれ」
「ああ、あれか」
尊さんは特に驚きもせず、妙な位置で固まっている奏さんを見る。
「よくあるんだよ、あれ」
「何を、見てらっしゃるんでしょうか?」
「たぶん、月だよ」
「月?」
確かによく見ると、奏さんの視線は夜空に向いている。
「なんでかは知らないけど、あいつ、夜に外歩いてると、たまにああやって月をひたすら眺めるんだ。堂々と道で立ち止まって」
「なんか、神秘的ですね……!」
「そうか? ただの迷惑行為だと思うけど」
そう言いながらも尊さんは、固まる奏さんを優しく見つめている。
「ただ、あれをやってるときに大抵アイデアが降りてくるらしい。それっぽく見せてるだけの嘘かもしれないけど」
いや、あれはたぶん、本当にアイデアが生まれているのだと思う。
月夜に照らされる彼を見て、ふと、そう直感した。
「ああなったらしばらくかかるから、先に行く? あのまま放っておいても大丈夫だよ? 別に後で怒ったりしないから」
「いえ、あの、できればでいいんですけど、」
そうやってインスピレーションは開花していくのだと、月の光が教えてくれる。
その瞬間を、見逃すわけにはいかない。
「私も、その、奏さんのことを、見ていてもいいでしょうか?」
そのとき、尊さんは私を見なかった。
まるで、私の言葉がわかっていたかのように。
「やっぱり、とんでもない娘だな」
そうして尊さんは、近くにあったベンチに座った。
「いいよ。俺も付き合う。でも、せめて座りな? 立つことまで付き合わなくてもいいだろ?」
促され、私も座った。奏さんは変わらず、ただそこで立ち止まり、月を眺めている。
だが一瞬、視線をそのままに、身体だけを三六〇度回転させた。
そして、徐に呟く。
「月が、綺麗だ」
そのままゆっくりと、視線を落とし、瞳を閉じる。
そのとき、一瞬だけ、奏さんの佇まいは、現実だとは思えなかった。
あれから約一ヵ月が経ち、新生活は徐々に日常と化してきた。
その頃の私はというと、講義には積極的に出席し、第二外国語で同じクラスになった女の子の友人もでき、バイトも見つかるなど、少しずつではあるが、大学生活に慣れつつあった。
だがそれのどれもが、元はと言えば尊さんの存在のお陰である。どの講義を取ればいいのかも、その情報を今の友人と共有することで仲良くなったのも、尊さんの存在なしではありえない。さらに言えば、バイト先は尊さんの紹介で決まった。尊さんの知り合いに私のアパートの近くに住んでいる二年生の女性の先輩がおり、彼女のバイト先のコンビニで働かせてもらえることとなった。さらに彼女はとても面倒見をよくしてくれて、たまに家に伺ってご飯を作ってくれるなど、様々な面でサポートしてもらっている。先輩も、先輩を紹介してくれた尊さんにも、本当に頭が上がらない。
ただ、最近は直接会えてはいない。部室にも顔を出すことは少なく、その感謝を伝えることができない。いつでも連絡してくれていいよと言ってくれたが、想定される彼の現在の状況を鑑みれば、頼みたいことがあってもなかなか頼みづらい。
その一方で、もう一人のサークルの先輩は、捕まえようと思えばいつでも捕まえられるだろう。なぜならその人は、今私がいるこの大教室内に、堂々と君臨しているのだから。
「あの人、なんかすごくない!? 右手でレジュメ書いて、左手でノートパソコン使ってるよ!? もしかして、なにか起業した人かも!」
相変わらず無駄に器用な彼の姿を見て、一緒に講義を受けている友人は変な勘違いをしている。
しかし、無理もない。確かに今の彼は、ほとんど人がいない大教室の前列に堂々と居座り、彼女の言うように、右手でレジュメに文字を書き、左手でノートパソコンのキーボードを叩いている。おそらくギリギリ良い意味で、只者には見えない挙動であった。
そんな大教室での光景に、今では何かと慣れてしまった。もちろん元々彼を知っているからというのもあるが、尊さんが言っていたように、奏さんは普通一年生で取るような講義を悉くスルーしていたのか、結構な確率で同じ講義を受講していた。だからこそ、今のような光景は、もはや私の中では日常の一欠片に過ぎないのだ。
かと言って、それについて本人と話すわけではない。と言うより、尊さんと会えなくなって以降、奏さんとはほとんど話していない。個人的には執筆の進捗を訊くために話しかけたいのだが、教室内ではそれは憚られるし、部室に行っても、相変わらず何かの作業に熱中し、話しかけにくい雰囲気を醸し出している。もしかしてあの小説の続きを執筆しているのではないかと考えると、変に問い質すわけにもいかない。
そんなこんなで、私は今、順調に運び出した私生活とは裏腹に、微妙なモヤモヤが心から取り除けない。このことを尊さんに相談したいのだが、先ほど言ったようにそういうわけにもいかないため、余計にモヤモヤが募る。
「じゃあ、また来週! 夏目さん!」
今日の最後の講義を終え、友人と別れた。
まだ15時過ぎであるが、この後はバイトもないため、夜までだいぶ時間が空いている。こういうときはとりあえず部室に行ってみるのだが、尊さんは十中八九いないし、ほとんどの確率で自分の作業机に姿を現す奏さんも、もしかしたらまだいないかも、
「失礼しまーす」
と、微かに思って部室に入ると、結局、彼はそこにいた。
確かに私たちより先に半駆け足で教室を飛び出していったが、それにしても、他の場所では体力ゲージが自動的に減っていくのかと思わせるぐらい、彼はいつも部室にいた。ここはワープ機能でも搭載されているのだろうか。
一方で私も、専用になりつつあるいつもの場所で本を読み、時間を潰していた。アニメや漫画でよく出てくる穏やかな文化部の空間のように、それぞれの沈黙が、古いこの部室全体を貫いている。
そんなとき、部室の中央に設置されている机の端っこに、あの小説が書かれた紙の束が置かれていることに気付いた。昨日はなかったはずなので、それをここに置いた人物は一人である。ただ、奥にいるその人物に、そのことを訊くことはできなかった。
とりあえず手に取り、書かれている文言を目に浮かばせる。相変わらず繊細で、大胆で、美しい。ストーリーには粗野な部分も見受けられるが、それでも刻まれている文字の並びに、図らずも釘付けになる。必ずやそれは、釘付けになった人の数だけ、明日を照らす光になる。真っ暗な夜を神秘的に彩る、月の光のように。
「あの、奏さん!」
やはり、なんとしても完成させたい。月の光を、世界中に届かせるために。
そう思った瞬間、沈黙を破る勇気が湧いた。
「ん? ああ、いたのか」
「今、何をやってらっしゃるんですか?」
「お、聞きたいか?」
あ、これ、ダメなやつだ。
「一ヵ月くらい前に、君と尊と三人で居酒屋に行った日があったろう? その日の帰りなんだが、急にアイデアがパッと思いついてね。それで執筆を始めたら、もう止まらなくなってしまって、その内容というのが──」
ああ、尊さん、戻ってきて。私一人でこれを聞かされるのは、さすがに無理がある。
「──というところまで進んだんだが、なかなかその先が思いつかなくてな。ん? そうだ、君、確か俺の執筆に協力するとか言っていたよな? それなら是非してほしいことがあるのだが、どうだろうか?」
なぜこの人は、物事をこんなにも都合良く解釈できるのだろう。これを完全に操っていた尊さんは、天才という類以外では考えられない。
「あの!」
急に大声を出した私に、彼は少しだけたじろいだ。
「私が聞きたいのは、これの話なんです!」
傍らにあるその紙束を掴み、彼に見せつけた。
「これ、書くって約束したでしょう? なのにまた変なもの書き始めて、全然約束守ってくれないじゃないですか! いい加減にしてください!」
普段はおとなしい私の突然の攻勢に、虚を衝かれたのだろう。彼は茫然としている。
「いや、その、忘れていたわけじゃないし、書こうと思う意志はあるんだ。しかし……」
意外なその言葉に、今度は私が虚を衝かれた。
「ストーリーがどうしても、行き詰まってしまって」
確かによく考えれば、この紙束を机に置いたのは彼であり、それはすなわち何かしらのアクションがあったということだろう。そうしてその末に、その行き詰まりに嵌ったのだ。
「どんな風に、ですか?」
「その、主人公が相手の女性を渋谷にデートに誘う展開を考えているんだが……」
思ったよりも定石通りのノーマルな設定に、逆に先が気になった。
「俺はそもそも、渋谷に行ったことがない」
なるほど、そういうことか。そりゃ、展開に行き詰まるわけだ。
ということは、これはつまり、
「行けば、いいんでしょう?」
「え?」
やっと、前に進める。時計の針は、確かに動いている。
「行きましょうよ! 渋谷! 行って、色々体験して、それで先に繋げましょう!」
「随分強引だな……」
「協力するって言ったでしょう? 取材ですよ、取材! それで、いつ行きます? 今週末なんかどうですか? 明日とか、明後日とか」
「日曜なら、一応空いてるが」
「決まりですね! それじゃ、明後日渋谷で会いましょう!」
白状しよう。私は今、心が躍っている。なぜかって? 理由は単純。
単に私は、渋谷に行ってみたかったのだ。
0
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

クラスのマドンナがなぜか俺のメイドになっていた件について
沢田美
恋愛
名家の御曹司として何不自由ない生活を送りながらも、内気で陰気な性格のせいで孤独に生きてきた裕貴真一郎(ゆうき しんいちろう)。
かつてのいじめが原因で、彼は1年間も学校から遠ざかっていた。
しかし、久しぶりに登校したその日――彼は運命の出会いを果たす。
現れたのは、まるで絵から飛び出してきたかのような美少女。
その瞳にはどこかミステリアスな輝きが宿り、真一郎の心をかき乱していく。
「今日から私、あなたのメイドになります!」
なんと彼女は、突然メイドとして彼の家で働くことに!?
謎めいた美少女と陰キャ御曹司の、予測不能な主従ラブコメが幕を開ける!
カクヨム、小説家になろうの方でも連載しています!

迷子を助けたら生徒会長の婚約者兼女の子のパパになったけど別れたはずの彼女もなぜか近づいてくる
九戸政景
恋愛
新年に初詣に来た父川冬矢は、迷子になっていた頼母木茉莉を助け、従姉妹の田母神真夏と知り合う。その後、真夏と再会した冬矢は真夏の婚約者兼茉莉の父親になってほしいと頼まれる。
※こちらは、カクヨムやエブリスタでも公開している作品です。

至れり尽くせり!僕専用メイドの全員が溺愛してくる件
こうたろ
青春
普通の大学生・佐藤健太は目覚めると、自宅が豪華な洋館に変わり10人の美人メイドたちに「お目覚めですか、ご主人様?」と一斉に迎えられる。いつの間にか彼らの“専属主人”になっていた健太は戸惑う間もなく、朝から晩までメイドたちの超至れり尽くせりな奉仕を受け始める。

わたしの下着 母の私をBBA~と呼ぶことのある息子がまさか...
MisakiNonagase
青春
39才の母・真知子は息子が私の下着を持ち出していることに気づいた。
ネットで同様の事象がないか調べると、案外多いようだ。
さて、真知子は息子を問い詰める? それとも気づかないふりを続けてあげるか?
そのほかに外伝も綴りました。

まずはお嫁さんからお願いします。
桜庭かなめ
恋愛
高校3年生の長瀬和真のクラスには、有栖川優奈という女子生徒がいる。優奈は成績優秀で容姿端麗、温厚な性格と誰にでも敬語で話すことから、学年や性別を問わず人気を集めている。和真は優奈とはこの2年間で挨拶や、バイト先のドーナッツ屋で接客する程度の関わりだった。
4月の終わり頃。バイト中に店舗の入口前の掃除をしているとき、和真は老齢の男性のスマホを見つける。その男性は優奈の祖父であり、日本有数の企業グループである有栖川グループの会長・有栖川総一郎だった。
総一郎は自分のスマホを見つけてくれた和真をとても気に入り、孫娘の優奈とクラスメイトであること、優奈も和真も18歳であることから優奈との結婚を申し出る。
いきなりの結婚打診に和真は困惑する。ただ、有栖川家の説得や、優奈が和真の印象が良く「結婚していい」「いつかは両親や祖父母のような好き合える夫婦になりたい」と思っていることを知り、和真は結婚を受け入れる。
デート、学校生活、新居での2人での新婚生活などを経て、和真と優奈の距離が近づいていく。交際なしで結婚した高校生の男女が、好き合える夫婦になるまでの温かくて甘いラブコメディ!
※特別編7が完結しました!(2026.1.29)
※小説家になろうとカクヨムでも公開しています。
※お気に入り登録、感想をお待ちしております。
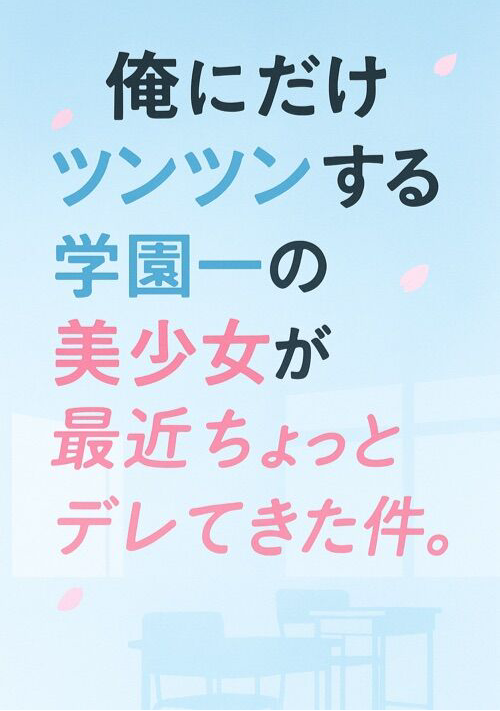
俺にだけツンツンする学園一の美少女が、最近ちょっとデレてきた件。
甘酢ニノ
恋愛
彼女いない歴=年齢の高校生・相沢蓮。
平凡な日々を送る彼の前に立ちはだかるのは──
学園一の美少女・黒瀬葵。
なぜか彼女は、俺にだけやたらとツンツンしてくる。
冷たくて、意地っ張りで、でも時々見せるその“素”が、どうしようもなく気になる。
最初はただの勘違いだったはずの関係。
けれど、小さな出来事の積み重ねが、少しずつ2人の距離を変えていく。
ツンデレな彼女と、不器用な俺がすれ違いながら少しずつ近づく、
焦れったくて甘酸っぱい、青春ラブコメディ。

友達の妹が、入浴してる。
つきのはい
恋愛
「交換してみない?」
冴えない高校生の藤堂夏弥は、親友のオシャレでモテまくり同級生、鈴川洋平にバカげた話を持ちかけられる。
それは、お互い現在同居中の妹達、藤堂秋乃と鈴川美咲を交換して生活しようというものだった。
鈴川美咲は、美男子の洋平に勝るとも劣らない美少女なのだけれど、男子に嫌悪感を示し、夏弥とも形式的な会話しかしなかった。
冴えない男子と冷めがちな女子の距離感が、二人暮らしのなかで徐々に変わっていく。
そんなラブコメディです。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















