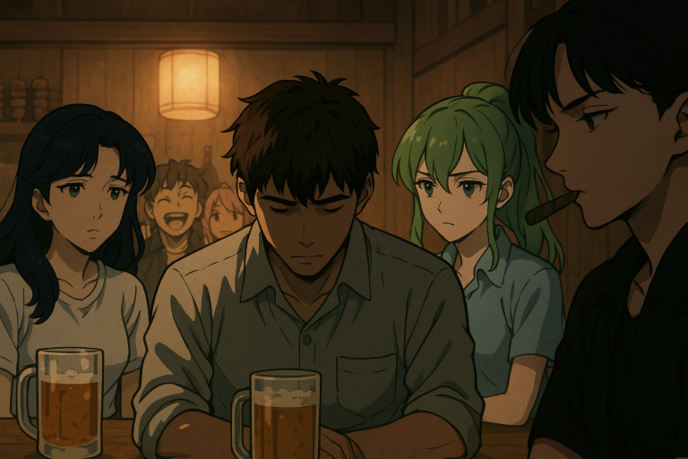47 / 81
第十七章 『特殊な部隊』の『特殊』な飲み会
第46話 『家族は最初の他人』
しおりを挟む
夜の入り口。月島屋の暖簾は、夕立ちの名残りの湿気を吸って重たく、提灯の赤はところどころ薄れている。七輪の火がぱちぱちと脂をはじき、タレの焦げた甘い匂いが路地へ漏れては戻ってくる。
シミュレータの熱がまだ皮膚の奥に残っているせいか、冷房の風がやけに心地いい。氷の入ったグラスにほんのり汗がつき、指の腹に輪じみが移る。
「そんな爺さんの跡を継いだ親父だが……まあ親父はよくやってると思うよ……今の甲武の体制よりは少しはましな身分に関係ない民主主義の実現に向けて頑張ってる……褒めてやってもいいかな」
かなめはそう言うと銃をホルスターに収めた。カウンター下のロッカーの鍵に指を添えていた春子が、そっと手を引く。店の空気が一拍、柔らかくなる。
「ふーん。かなめちゃんはお父さんを尊敬してるんだ……自分さえよければそれで良いっていう『女王様』のかなめちゃんにも尊敬する人がいるなんて……意外かも」
アメリアが冷やかすような調子でそう言った。糸目に光が宿り、ジョッキの取っ手を親指でくるりと回す。
戦闘用人造人間である彼女に両親などいないことは分かっている。誠は少しばかりかなめの答えが気になって視線をかなめに向けた。七輪の火がかすかに強まる。
「尊敬ねえ……確かにたいしたものだとは思ってるのは事実だよ。前の戦争中は民衆を扇動して開戦に導いた軍部を徹底的に批判して勤めていた外務省を出仕禁止になって謹慎処分だった。それが、ひとたび軍部に戦局はもうどうしようもないから何とかしてくれと頭を下げられて一度腰を上げると、軍部の連中には考えもつかない方法で簡単に戦争を止めちまった伝説の外交官として甲武じゃちょっとした英雄だ。そして貴族の最高の位である四大公家筆頭公爵を何の惜しげもなくアタシに譲って名字があるだけの平民の身分になって『平民宰相』と呼ばれるようになると『普通選挙』実現のために頑張ってるのも人気取りと言えばそれまでだが、なかなかできることじゃねえ。でもなあ……尊敬ってのとはちょっと違うんだよな……そもそもアタシみたいに何かといえば反抗してばかりの娘に尊敬されても親父は喜ばねえよ……アイツはそんな単純な男じゃねえんだ……」
かなめはそう言いながら再び葉巻をくわえた。火を点けるライターのチッという乾いた音。吐き出された煙が、カウンター上で薄く層をなし、提灯の赤に溶ける。
どこか釈然としない。どこか父親と微妙な距離を取っている。誠にはかなめの言葉がそんな風に聞こえてならなかった。
「私は何度か西園寺には家族の愚痴を聞かされたことがあるが、母親が……妹が……そして父親も……どれも私の考えている家族像とはあまりにかけ離れすぎていて私の口からは説明する気にすらならない。こいつの家族はどれも個性的過ぎて私には完全に理解不能だ。神前、貴様は家族はどうなんだ?貴様は自分は普通だといつも言ってるのだから普通なんだろうな?私にも理解できるのだろうな?教えてくれ。西園寺の家族はまったく家族を持たない『ラスト・バタリオン』である私の考える『家族』のイメージから壊れるから一般的な家族の話を私は聞きたいん。だ本に載っていた『日曜の食卓』というものが、どんな顔をしているのか、知りたかっただけだ」
それまで静かに話を聞いてきたカウラがそう話を振ってきた。氷の当たる音が、涼しい間をつくる。
「僕の家は……父さんと母さんと僕の三人家族ですよ。普通ですよね?まあ、カウラさんが期待しているような家族と違うところと言えば……父さんが全寮制の私立高の体育教師をしているので、ほとんどうちにいないことくらいですかね、特徴は。まあ、この東和共和国で、結婚理由の1%くらいしかない恋愛結婚は、ほぼ3年以内に100%離婚するって言われてます。だから母子家庭は珍しくないんですけど……。うちは父がほとんど家にいないから、よく『恋愛結婚して離婚したんだろ』って言われて、それが少し恥ずかしかったです」
誠は珍しくまともな話を振ってきたカウラに笑顔でそう答えた。春子が『はーい、盛り合わせ追加』と源さんに声をかけ、香りが一段濃くなる。
「親父が教師で、母ちゃんが主婦か……普通だな。それにこの国だって大企業に勤めている家なら単身赴任だって普通だろうが。うちの整備班にも親父が大企業に勤めてて地方の支店長になったから単身赴任しているなんて話はよく聞くぞ」
かなめがつまらなそうにそう言った。ラムのグラスを軽く親指で弾き、ぴっと音を立てる。
「主婦っていうか……少なくとも専業主婦では無いもので……うちの母は剣道道場を経営していまして、そこの師範なんです。『神前一刀流道場』って言うんですけど……まあ町の子供達を集めて剣道を教えているんです。父と母とどちらを尊敬しているかと言われると……やっぱり母さんかな……父はあまり家にいる印象が無いですし、僕に剣を教えてくれたのも全部母ですし」
誠は得意げに自慢の母の話をした。座敷の方から、道場帰りらしい少年たちの笑い声が一瞬だけ聞こえ、すぐに遠のく。
「あれ?もしかして誠ちゃんはマザコン?」
「男はみなマザコンだと物の本に読んだぞ。まあ、隊長みたいに母親には生まれて一度も会ったこともないし、母親が自分にいるという事を考えた時間がこれまで合計して1時間以下だと公言している人物はそもそも人間の例外なんだ。だから隊長は『駄目人間』なのかもしれない」
両親の居ない『ラスト・バタリオン』コンビであるアメリアとカウラがそうツッコんできた。カウラは淡々と烏龍茶のコースターを端に揃える。
「そう言われると……否定できないような……申し訳ありません。僕はマザコンです」
誠はズバリ『マザコン』かと聞かれると否定することが出来なかった。小夏が笑いつつ、そっと水も置く。
「マザコンねえ……うちのお袋もあれはあれで個性的なんだわ。あの化け物については言いたくねえから言わねえけど。あれか?神前の親父が体育教師って東和は体育は普通の体育と武道があるよな?その科目も剣道か?」
家族の話に感心無さそうにかなめはラムを舐めながらそう言った。葉巻の灰は、折れずに綺麗に伸びている。
「そうですけど……なにか問題でも?結構強いってことになってますよ。一応全国大会に出たこともありますし……剣道も六段ですし」
確かめるように聞いてくるかなめに誠は少し不満そうにそう答えた。
「出会いも剣道。話題も剣道。仕事も剣道……なんだかつまんねえ家だな。他に何か家の特徴とかねえのかよ。神前ってのは遼帝国の帝家の流れと聞くぞ?だったら通常の東和の家族には考えられない奇習があるとか……例えば10月になると家の門柱にヤギを括りつけて月末になるとそれを潰して町内に振舞うとか」
吐き捨てるようにかなめはそう言った。カウンターの端でパーラがむっと眉を寄せ、アメリアが袖をつついてなだめる。
「なんですか!そのなんだかよく分からない奇習は?その奇習にどんな意味があるんですか?そもそもどこでヤギを手に入れるんですか!僕の家は都内ですよ!知り合いにヤギを売っているような人は居ません!そんな奇習があるのも嫌ですけど、テロリストに狙われる家よりよっぽどましじゃないですか!それにうちでは剣道の話題はほとんど出ませんよ!普通に父が居る時はテレビを見て、ご飯食べて、お話をする……それ以上に家族に何が必要なんですか。帝家の流れとかの風習は何一つありません!ご期待に応えられなくて申し訳ありませんね!」
ムキになって誠はそう反論した。
タイミングよく、次の焼鳥の盛り合わせが並ぶ。湯気の向こう、源さんが串の向きをそろえる手が無駄なく早い。誠はまず砂肝を手に取り、ビールを飲み干した。
「まあまあ、いろいろあるのよ、かなめちゃんも。それと10月のかなめちゃんの言う奇習のネタ元は地球圏のハロウィンね。でもアレはカボチャを使うんであってヤギを潰して振舞うようなことはしないわよ。それと、誠ちゃん。島田君には家族の話題は振らない方がいいわよ」
アメリアが誠の空いたグラスにビールを注ぎながらそうささやいた。注ぐ手は、ラベルを上に……月島屋の『内ルール』は、すでに体に染みてきた。そして、サラとパーラに向けて身振り手振りを交えて何やら自慢話をしているらしい島田に目を向けた。
「なんでですか?別に家族の話題くらい振っても良いじゃないですか……島田先輩だって、別にみなしごってわけじゃないですよね?あんまり悲壮感とは無縁そうな顔してますし」
少し妙な言い方をするアメリアに誠はぼんやりと尋ねた。
「まあ、ヤンキーの家庭なんて複雑に決まってんじゃない。アタシが知ってるのは島田君が物心ついた時には両親は家にいなくて、年の離れたお兄さんに育てられたってこと。しかも小学生になる時にそのお兄さんが結婚したお嫁さんとは島田君はかなり相性が悪くて、大学入学以来一度も実家に帰ってないって話くらいかな……今でも一切実家とも連絡は取ってないみたいだし」
アメリアは寂しげにそう言うとサラとパーラを隣に侍らせて大爆笑している島田に目を向けた。サラと笑い合う横顔に、そんな影はどこにも見えない。サラは笑いながらも、ふっと視線だけこちらに寄越す。聞こえている、という合図。
「家族とは……いろいろあるんだな……私は『ラスト・バタリオン』のロールアウト後に行われる社会教育課程で学んだこの国の人間は一生のほとんどを独身で過ごすという現状に対する説明しか覚えていないな。まあ、家族を持つのが少数派である以上西園寺の家や島田の家のようにどこか歪んでいるものしか身近にないというのが普通で、本やテレビCMに出てくるような家族はフィクションだと持っていた。どうやら神前の話を聞くと実際にそう言う家族が存在すると知って少し驚いているのが本音だ」
家族を持たない『ラスト・バタリオン』であるカウラは豚串を食べた後、そうつぶやいた。噛む回数は一定、串の端は皿の同じ位置へ。
「まあな、それぞれ色々あるんだわ。その点、オメエ等『ラスト・バタリオン』は気楽でいいな、そんなめんどくさそうなのと無縁で。親父やお袋なんて家借りるときの保証人くらいの役にしか立ってねえぞ、うちなんか。後は被害ばっか……とくにお袋と妹は最悪だ……しかもあの二人は気が合うから仲良くしていやがる。アタシも親父と仲良く?なんであんな爺さんと仲良くしなきゃいけないんだ?親父は結婚したのが45歳と遅くてアタシが生まれたのが48歳の時だからもう70過ぎてんだぞ?」
かなめは相変わらず悠然と葉巻をくゆらせながらそう言った。春子が目だけで『灰、落ちますよ』と知らせると、かなめは灰皿の縁で静かに落とす。
「でも、一応産んでくれた恩とか、育ててくれたこととか……そう言うのがあるんじゃないですか?それに別に母娘に年齢とかは特に関係ないでしょ?」
そんなことを言う誠も自分の父母の年齢を良く知らない自分に気が付き不思議な気分になっていた。
「別に産んでくれなんてアタシが頼んだわけじゃねえよ。特にこんな身体になってからは特にそうだ。それにアタシは実家の屋敷の見物収入がでかいのと、さっき言った貴族の最高位になると貰える荘園の収入が全部アタシの口座に入るからその金でアタシは好き勝手やれんの。まあ、『無職』になるとそれもパーになるから仕事はしてっけど……両親に育てられたなんて自覚はねえよ」
なんとか取り繕うとする誠の言葉にかなめはつれなくそう答えた。
提灯が小さく揺れて、外の風の向きが変わる。
「私も……家族ってほしいとは思わないわね。まあ、うちの部隊で家族にいい思い出があるのは少数派なんじゃないかしら。運航部の女子は全員『ラスト・バタリオン』で人工的に作られた存在だから家族なんていないけど……技術部の連中も聞いてみるとあんまりいい話は聞かないわよ。家族にいい思い出があるならうちみたいな『特殊な部隊』には来ないんじゃない?第一隊長が……ああ、隊長の家族の話は本人に口止めされてるから言わないわね。かなめちゃんもたぶん隊長とは叔父と姪の関係なのに詳しく知らないんでしょ?親戚にすら言いたくないってことは隊長の家族環境は島田君のそれより複雑ってこと……むしろ悲劇的ともいえるわね。私からはこれくらいしか言えないし言いたくない」
アメリアはそう言いながらビールを飲み干した。泡の縁が、口紅のあとを細い弧に残す。誠は嵯峨がかなめの家に養子に入ったとは聞いていたがそれ以前の事はいつもは全ての出来事を面白おかしく話して見せるアメリアすら『言いたくない』と言わせるものなのだと知って先ほど妻に散々浮気をされた上に先立たれたということを思い出して、なぜ嵯峨が家族の話を一切しないのか分かったような気がした。
「注ぎますよ!」
誠はそんな落ち込んだ気分をごまかすようにそう言ってビールを注ぐ。手首の角度が少しぎこちないのを、小夏がにやりと見逃さない。
いつの間にか島田達が馬鹿話をやめて誠達の方に目をやっていた。サラは肘で島田の脇腹をつつき、パーラは『見ないの』と目で釘を刺す。
「いいんじゃねえの、家族なんていたっていなくたって。『家族は最初の他人』だぜ。世話になったのは事実だが……それに縛られる義理はねえわな」
かなめはそう言って最後のねぎまを食べ終えた。竹串を皿の端に揃えて置く。その整然さだけが、貴族の影をほんの少しだけ連想させた。それでも、かなめが『家族』という言葉にどれだけ蝕まれてきたかは、なんとなく分かる気がした。
サラと島田の馬鹿笑いとパーラのツッコミが店内に響く。テレビは相撲のダイジェストを無音で流し、字幕だけが淡々と進んでいた。
誠は黙って皿に置かれた竹串をいじりながらビールを飲み干していた。炭酸の抜けかけた軽い苦味が、今日の汗をやわらげる。
「そう言えば……話は変わるけど、誠ちゃんはなんで野球をやめたの?かなめちゃんの話じゃ高校時代は『都立の星』って呼ばれるエースだったんでしょ?プロからスカウトされたりしなかったの?」
ビールを飲みながらアメリアは突如何気ない調子で誠に語り掛けた。ジョッキの底から氷をコトリと落とす。
「そんなの投げ過ぎで肩を壊したからに決まってるじゃないか。私も高校野球を野球を趣味の一つとする人間としてよく見るが先発完投が当たり前のあの教育方針ではまだ体格が固まっていない高校生に毎試合100球以上投げさせたら普通は肩が壊れるものだ。珍しい話ではない」
そう言ってカウラは微笑みを浮かべる。いつもの、淡々とした確信の笑みだった。
カウラの視線の先で誠はうなだれつつ話始めた。
その暗い表情に、いつもは明るい面々も誠に何か過去があることくらいは察した。春子はそっと、冷たい水をもう一杯、誠の前に置く。ラベルは上。
「肩をやったのは事実ですけど……それ以前の問題ないんです。実は……僕……後輩のキャッチャーを殴ったんです……試合中に……それで公式の試合には出場できなくなったんです」
誠の突然の告白にカウラとアメリアの表情が曇った。サラが笑いを止め、島田はタバコを灰皿に押しつける。
「うちの高校……都立の進学実験校だったんで……ほとんどの生徒が帰宅部なんですよ」
ビールのグラスを手に誠は話を続ける。グラスの外側を伝う水滴が、輪じみを新しく刻む。
「僕の居た野球部も三年が僕と別のキャッチャーをやっていて主将だった奴と二人っきりだったんです。二年と一年生を合わせても十二人しか部員が居ないんです……しかも一年からほとんどの生徒が予備校に通ってるんでほとんど練習には出られないんです……練習試合もできない有様でしたから」
暗い誠の表情に聞いてきたアメリアさえ少し寂しげな表情を浮かべていた。
七輪の上でつくねが弾け、源さんが手早くタレを重ねる。
「夏の全国大会の東東都予選の3回戦で……相手は……坂東一高って言う学校でして……」
誠は悪夢を振り払うような暗い調子でそう言った。
「坂東一高!その年の全国大会優勝校じゃないの!」
さすがに野球をやっているだけあってアメリアは全国大会出場確実な学校名ぐらいは知っていた。糸目がわずかに見開く。
「うちのキャプテンだったキャッチャーの奴が、その日大学の推薦入試の面接だったんです。そいつなら僕の決め球のフォークを身体で止められるんですけど……補欠の後輩には無理でした……ただそれだけの話です」
誠はそう言って遠い昔のことのようにその光景を思い出していた。夏の空気、白線の匂い、乾いたスパイクの音が誠の耳の中に思い出されて心に突き刺さった。
「ずいぶんと悪趣味な日に面接の予定を入れるわね。それに東和の大学は4月入学でしょ?なんで7がつに入試があるの?」
「そいつは海外留学希望があって夏季入試の日程に合わせて受験したからその日になったそうです。……そのゲルパルトにある医大も9月入学のための入試が7月にあるんです……アメリアさんはゲルパルトの出身だからそれくらい知ってるんじゃないですか?」
あまり話したくない自分のトラウマを語る誠の言葉にはどうしても隠しがたい棘があった。アメリアはそれに気付いて糸目をさらに細めて静かに誠を見守っていた。
「ごめんね、私は知ってて当たり前のことかもしれないわね。そう言えば……4月入学の国って同盟では東和と甲武くらいだものね」
アメリアは納得したというようにシシトウを口に運んだ。今日は当たりを引かない。
「こいつがアマチュア野球の公式戦からは全面出場禁止になってることは知ってるよ。その補欠のキャッチャーのその日のパスボールが8個。他にも内外野のエラーが合わせて22個……5回コールド負けの試合で、240球も投げたら肩も壊れるわな。普通は」
かなめはラムを飲みながらそうつぶやいた。言い方は荒いが、数字は正確だ。
「知ってたんですか?」
少し驚いたような誠の顔を見てかなめはやさしく笑いかけた。
「1回戦は完全試合、2回戦は三安打失点0で、その試合で非公式とは言え左腕で158kmの球速を誇った『都立の星』の最期にしちゃあずいぶん間の抜けた話だってんで調べたんだ。あれだろ?その正キャッチャーの奴はその後、都立の医科大学に進んで今じゃあ母校の監督をしてるって話じゃねえか……うちの野球部にも欲しい人材だ。うちのチームのキャッチャーはあてにならねえからな」
かなめは表情も変えずにラム酒をあおった。パーラが横目で「誰のこと」と睨み、アメリアが肩をすくめて笑う。
「ええ、アイツは……試合の日程が決まった時、自分の大学受験なんてどうでもいいって言ったんです。3回戦さえ超えれば全国大会に出られるようなトーナメント表になってましたから。そのためならゲルパルトの医大は諦めて東和の医大を受けるって。でも僕が止めてアイツはそのままゲルパルトの医大の東都会場での面接を受けたんです。実際、その推薦入試は落ちて、その冬に都立医科大に合格して、そっちに進学しましたから。けど……僕には言えませよ、お前が居ないとゲームにならないなんて……アイツは医者になるつもりで高校に来てたんですから。野球をやりに来てたわけじゃありませんから。僕が殴った後輩も、エラーした後輩もみんな野球をやりに高校に来たわけじゃなくて高校には大学に行くための勉強をしに来てたんですから。アレはただの天狗になってた僕の暴走です」
誠はうつむきながらジョッキに口を近づける。泡が鼻先をくすぐり、目の奥に熱が差した。
そんな仕草の中に少し感傷的になっている自分を感じていた。
「でも殴るなんて……」
さすがに笑いの為には暴力も辞さないアメリアも誠の意外な行動に言葉を詰まらせた。サラが静かに頷く。
「僕も自分で殴るなんて思っていなかったんです。パスボールを詫びに来た後輩を気が付いたら殴ってたんです。正直、天狗になってたんですよ、その時の僕は。マスコミに『都立の星』とか呼ばれて、しかもどのブロックでも東東都大会は番狂わせ続きで坂東一高以外の強豪校はほとんど消えてるという状況で僕の心がおかしくなっていたんです。その試合もプロのスコアラーとかが山と来て……それが試合が始まったらワンサイドゲーム。それもヒット性の当たりが一つも無いのに次々に点を取られて自分のせいじゃないと思ったらなんだか怒りがわいてきちゃって押さえられなかったんです。それまで『もんじゃ焼き製造マシン』とかバカにされて生きてきた反動ですかね……急に注目されたあの時の僕はどうかしてました。生まれて初めて人を殴ったのがそれです。でも、暴力はいけませんよね。即座に僕は退場になり、それ以来、公式試合から永久追放されて……野球はやっていないんです」
アメリアに言われるまでも無い。カウンターの上で小さな沈黙が輪を広げ、やがて吸い込まれていく。
それに誠はそれ以降も人を殴ったことは無かった。
「オメエが来るって聞かされて実は当時の映像を見たが……全国大会優勝チーム相手に外野まで飛んだ当たりがほとんど無かったのは事実だしな……キャッチャーがまともなら勝ちはしねえがいい試合になったろ」
そう言うかなめの慰めの言葉も今の誠にはあまり意味は無かった。だが、数字と映像に裏打ちされたその一言は、どこかで冷めきった自己否定の温度を少しだけ下げる。
「でも三振もほとんど取れませんでしたよ。やっぱり全国レベルの選手は違いますよね。ボールになるスライダーやフォークは見向きもしないし、カウントを取りに行ったストレートはセンター返しで、カーブは……いい勉強になりました。僕にはやっぱり勉強と絵とプラモしかないのかなって……」
そう言って誠はジョッキのビールを飲み干した。泡の消えた輪が底に残り、指先の汗はようやく引いていた。
七輪の火は落ち着きを取り戻し、店の時計の秒針が、次の一拍を刻む。外は完全な夜。暖簾の向こう、路地の風が少し冷たくなっている。
シミュレータの熱がまだ皮膚の奥に残っているせいか、冷房の風がやけに心地いい。氷の入ったグラスにほんのり汗がつき、指の腹に輪じみが移る。
「そんな爺さんの跡を継いだ親父だが……まあ親父はよくやってると思うよ……今の甲武の体制よりは少しはましな身分に関係ない民主主義の実現に向けて頑張ってる……褒めてやってもいいかな」
かなめはそう言うと銃をホルスターに収めた。カウンター下のロッカーの鍵に指を添えていた春子が、そっと手を引く。店の空気が一拍、柔らかくなる。
「ふーん。かなめちゃんはお父さんを尊敬してるんだ……自分さえよければそれで良いっていう『女王様』のかなめちゃんにも尊敬する人がいるなんて……意外かも」
アメリアが冷やかすような調子でそう言った。糸目に光が宿り、ジョッキの取っ手を親指でくるりと回す。
戦闘用人造人間である彼女に両親などいないことは分かっている。誠は少しばかりかなめの答えが気になって視線をかなめに向けた。七輪の火がかすかに強まる。
「尊敬ねえ……確かにたいしたものだとは思ってるのは事実だよ。前の戦争中は民衆を扇動して開戦に導いた軍部を徹底的に批判して勤めていた外務省を出仕禁止になって謹慎処分だった。それが、ひとたび軍部に戦局はもうどうしようもないから何とかしてくれと頭を下げられて一度腰を上げると、軍部の連中には考えもつかない方法で簡単に戦争を止めちまった伝説の外交官として甲武じゃちょっとした英雄だ。そして貴族の最高の位である四大公家筆頭公爵を何の惜しげもなくアタシに譲って名字があるだけの平民の身分になって『平民宰相』と呼ばれるようになると『普通選挙』実現のために頑張ってるのも人気取りと言えばそれまでだが、なかなかできることじゃねえ。でもなあ……尊敬ってのとはちょっと違うんだよな……そもそもアタシみたいに何かといえば反抗してばかりの娘に尊敬されても親父は喜ばねえよ……アイツはそんな単純な男じゃねえんだ……」
かなめはそう言いながら再び葉巻をくわえた。火を点けるライターのチッという乾いた音。吐き出された煙が、カウンター上で薄く層をなし、提灯の赤に溶ける。
どこか釈然としない。どこか父親と微妙な距離を取っている。誠にはかなめの言葉がそんな風に聞こえてならなかった。
「私は何度か西園寺には家族の愚痴を聞かされたことがあるが、母親が……妹が……そして父親も……どれも私の考えている家族像とはあまりにかけ離れすぎていて私の口からは説明する気にすらならない。こいつの家族はどれも個性的過ぎて私には完全に理解不能だ。神前、貴様は家族はどうなんだ?貴様は自分は普通だといつも言ってるのだから普通なんだろうな?私にも理解できるのだろうな?教えてくれ。西園寺の家族はまったく家族を持たない『ラスト・バタリオン』である私の考える『家族』のイメージから壊れるから一般的な家族の話を私は聞きたいん。だ本に載っていた『日曜の食卓』というものが、どんな顔をしているのか、知りたかっただけだ」
それまで静かに話を聞いてきたカウラがそう話を振ってきた。氷の当たる音が、涼しい間をつくる。
「僕の家は……父さんと母さんと僕の三人家族ですよ。普通ですよね?まあ、カウラさんが期待しているような家族と違うところと言えば……父さんが全寮制の私立高の体育教師をしているので、ほとんどうちにいないことくらいですかね、特徴は。まあ、この東和共和国で、結婚理由の1%くらいしかない恋愛結婚は、ほぼ3年以内に100%離婚するって言われてます。だから母子家庭は珍しくないんですけど……。うちは父がほとんど家にいないから、よく『恋愛結婚して離婚したんだろ』って言われて、それが少し恥ずかしかったです」
誠は珍しくまともな話を振ってきたカウラに笑顔でそう答えた。春子が『はーい、盛り合わせ追加』と源さんに声をかけ、香りが一段濃くなる。
「親父が教師で、母ちゃんが主婦か……普通だな。それにこの国だって大企業に勤めている家なら単身赴任だって普通だろうが。うちの整備班にも親父が大企業に勤めてて地方の支店長になったから単身赴任しているなんて話はよく聞くぞ」
かなめがつまらなそうにそう言った。ラムのグラスを軽く親指で弾き、ぴっと音を立てる。
「主婦っていうか……少なくとも専業主婦では無いもので……うちの母は剣道道場を経営していまして、そこの師範なんです。『神前一刀流道場』って言うんですけど……まあ町の子供達を集めて剣道を教えているんです。父と母とどちらを尊敬しているかと言われると……やっぱり母さんかな……父はあまり家にいる印象が無いですし、僕に剣を教えてくれたのも全部母ですし」
誠は得意げに自慢の母の話をした。座敷の方から、道場帰りらしい少年たちの笑い声が一瞬だけ聞こえ、すぐに遠のく。
「あれ?もしかして誠ちゃんはマザコン?」
「男はみなマザコンだと物の本に読んだぞ。まあ、隊長みたいに母親には生まれて一度も会ったこともないし、母親が自分にいるという事を考えた時間がこれまで合計して1時間以下だと公言している人物はそもそも人間の例外なんだ。だから隊長は『駄目人間』なのかもしれない」
両親の居ない『ラスト・バタリオン』コンビであるアメリアとカウラがそうツッコんできた。カウラは淡々と烏龍茶のコースターを端に揃える。
「そう言われると……否定できないような……申し訳ありません。僕はマザコンです」
誠はズバリ『マザコン』かと聞かれると否定することが出来なかった。小夏が笑いつつ、そっと水も置く。
「マザコンねえ……うちのお袋もあれはあれで個性的なんだわ。あの化け物については言いたくねえから言わねえけど。あれか?神前の親父が体育教師って東和は体育は普通の体育と武道があるよな?その科目も剣道か?」
家族の話に感心無さそうにかなめはラムを舐めながらそう言った。葉巻の灰は、折れずに綺麗に伸びている。
「そうですけど……なにか問題でも?結構強いってことになってますよ。一応全国大会に出たこともありますし……剣道も六段ですし」
確かめるように聞いてくるかなめに誠は少し不満そうにそう答えた。
「出会いも剣道。話題も剣道。仕事も剣道……なんだかつまんねえ家だな。他に何か家の特徴とかねえのかよ。神前ってのは遼帝国の帝家の流れと聞くぞ?だったら通常の東和の家族には考えられない奇習があるとか……例えば10月になると家の門柱にヤギを括りつけて月末になるとそれを潰して町内に振舞うとか」
吐き捨てるようにかなめはそう言った。カウンターの端でパーラがむっと眉を寄せ、アメリアが袖をつついてなだめる。
「なんですか!そのなんだかよく分からない奇習は?その奇習にどんな意味があるんですか?そもそもどこでヤギを手に入れるんですか!僕の家は都内ですよ!知り合いにヤギを売っているような人は居ません!そんな奇習があるのも嫌ですけど、テロリストに狙われる家よりよっぽどましじゃないですか!それにうちでは剣道の話題はほとんど出ませんよ!普通に父が居る時はテレビを見て、ご飯食べて、お話をする……それ以上に家族に何が必要なんですか。帝家の流れとかの風習は何一つありません!ご期待に応えられなくて申し訳ありませんね!」
ムキになって誠はそう反論した。
タイミングよく、次の焼鳥の盛り合わせが並ぶ。湯気の向こう、源さんが串の向きをそろえる手が無駄なく早い。誠はまず砂肝を手に取り、ビールを飲み干した。
「まあまあ、いろいろあるのよ、かなめちゃんも。それと10月のかなめちゃんの言う奇習のネタ元は地球圏のハロウィンね。でもアレはカボチャを使うんであってヤギを潰して振舞うようなことはしないわよ。それと、誠ちゃん。島田君には家族の話題は振らない方がいいわよ」
アメリアが誠の空いたグラスにビールを注ぎながらそうささやいた。注ぐ手は、ラベルを上に……月島屋の『内ルール』は、すでに体に染みてきた。そして、サラとパーラに向けて身振り手振りを交えて何やら自慢話をしているらしい島田に目を向けた。
「なんでですか?別に家族の話題くらい振っても良いじゃないですか……島田先輩だって、別にみなしごってわけじゃないですよね?あんまり悲壮感とは無縁そうな顔してますし」
少し妙な言い方をするアメリアに誠はぼんやりと尋ねた。
「まあ、ヤンキーの家庭なんて複雑に決まってんじゃない。アタシが知ってるのは島田君が物心ついた時には両親は家にいなくて、年の離れたお兄さんに育てられたってこと。しかも小学生になる時にそのお兄さんが結婚したお嫁さんとは島田君はかなり相性が悪くて、大学入学以来一度も実家に帰ってないって話くらいかな……今でも一切実家とも連絡は取ってないみたいだし」
アメリアは寂しげにそう言うとサラとパーラを隣に侍らせて大爆笑している島田に目を向けた。サラと笑い合う横顔に、そんな影はどこにも見えない。サラは笑いながらも、ふっと視線だけこちらに寄越す。聞こえている、という合図。
「家族とは……いろいろあるんだな……私は『ラスト・バタリオン』のロールアウト後に行われる社会教育課程で学んだこの国の人間は一生のほとんどを独身で過ごすという現状に対する説明しか覚えていないな。まあ、家族を持つのが少数派である以上西園寺の家や島田の家のようにどこか歪んでいるものしか身近にないというのが普通で、本やテレビCMに出てくるような家族はフィクションだと持っていた。どうやら神前の話を聞くと実際にそう言う家族が存在すると知って少し驚いているのが本音だ」
家族を持たない『ラスト・バタリオン』であるカウラは豚串を食べた後、そうつぶやいた。噛む回数は一定、串の端は皿の同じ位置へ。
「まあな、それぞれ色々あるんだわ。その点、オメエ等『ラスト・バタリオン』は気楽でいいな、そんなめんどくさそうなのと無縁で。親父やお袋なんて家借りるときの保証人くらいの役にしか立ってねえぞ、うちなんか。後は被害ばっか……とくにお袋と妹は最悪だ……しかもあの二人は気が合うから仲良くしていやがる。アタシも親父と仲良く?なんであんな爺さんと仲良くしなきゃいけないんだ?親父は結婚したのが45歳と遅くてアタシが生まれたのが48歳の時だからもう70過ぎてんだぞ?」
かなめは相変わらず悠然と葉巻をくゆらせながらそう言った。春子が目だけで『灰、落ちますよ』と知らせると、かなめは灰皿の縁で静かに落とす。
「でも、一応産んでくれた恩とか、育ててくれたこととか……そう言うのがあるんじゃないですか?それに別に母娘に年齢とかは特に関係ないでしょ?」
そんなことを言う誠も自分の父母の年齢を良く知らない自分に気が付き不思議な気分になっていた。
「別に産んでくれなんてアタシが頼んだわけじゃねえよ。特にこんな身体になってからは特にそうだ。それにアタシは実家の屋敷の見物収入がでかいのと、さっき言った貴族の最高位になると貰える荘園の収入が全部アタシの口座に入るからその金でアタシは好き勝手やれんの。まあ、『無職』になるとそれもパーになるから仕事はしてっけど……両親に育てられたなんて自覚はねえよ」
なんとか取り繕うとする誠の言葉にかなめはつれなくそう答えた。
提灯が小さく揺れて、外の風の向きが変わる。
「私も……家族ってほしいとは思わないわね。まあ、うちの部隊で家族にいい思い出があるのは少数派なんじゃないかしら。運航部の女子は全員『ラスト・バタリオン』で人工的に作られた存在だから家族なんていないけど……技術部の連中も聞いてみるとあんまりいい話は聞かないわよ。家族にいい思い出があるならうちみたいな『特殊な部隊』には来ないんじゃない?第一隊長が……ああ、隊長の家族の話は本人に口止めされてるから言わないわね。かなめちゃんもたぶん隊長とは叔父と姪の関係なのに詳しく知らないんでしょ?親戚にすら言いたくないってことは隊長の家族環境は島田君のそれより複雑ってこと……むしろ悲劇的ともいえるわね。私からはこれくらいしか言えないし言いたくない」
アメリアはそう言いながらビールを飲み干した。泡の縁が、口紅のあとを細い弧に残す。誠は嵯峨がかなめの家に養子に入ったとは聞いていたがそれ以前の事はいつもは全ての出来事を面白おかしく話して見せるアメリアすら『言いたくない』と言わせるものなのだと知って先ほど妻に散々浮気をされた上に先立たれたということを思い出して、なぜ嵯峨が家族の話を一切しないのか分かったような気がした。
「注ぎますよ!」
誠はそんな落ち込んだ気分をごまかすようにそう言ってビールを注ぐ。手首の角度が少しぎこちないのを、小夏がにやりと見逃さない。
いつの間にか島田達が馬鹿話をやめて誠達の方に目をやっていた。サラは肘で島田の脇腹をつつき、パーラは『見ないの』と目で釘を刺す。
「いいんじゃねえの、家族なんていたっていなくたって。『家族は最初の他人』だぜ。世話になったのは事実だが……それに縛られる義理はねえわな」
かなめはそう言って最後のねぎまを食べ終えた。竹串を皿の端に揃えて置く。その整然さだけが、貴族の影をほんの少しだけ連想させた。それでも、かなめが『家族』という言葉にどれだけ蝕まれてきたかは、なんとなく分かる気がした。
サラと島田の馬鹿笑いとパーラのツッコミが店内に響く。テレビは相撲のダイジェストを無音で流し、字幕だけが淡々と進んでいた。
誠は黙って皿に置かれた竹串をいじりながらビールを飲み干していた。炭酸の抜けかけた軽い苦味が、今日の汗をやわらげる。
「そう言えば……話は変わるけど、誠ちゃんはなんで野球をやめたの?かなめちゃんの話じゃ高校時代は『都立の星』って呼ばれるエースだったんでしょ?プロからスカウトされたりしなかったの?」
ビールを飲みながらアメリアは突如何気ない調子で誠に語り掛けた。ジョッキの底から氷をコトリと落とす。
「そんなの投げ過ぎで肩を壊したからに決まってるじゃないか。私も高校野球を野球を趣味の一つとする人間としてよく見るが先発完投が当たり前のあの教育方針ではまだ体格が固まっていない高校生に毎試合100球以上投げさせたら普通は肩が壊れるものだ。珍しい話ではない」
そう言ってカウラは微笑みを浮かべる。いつもの、淡々とした確信の笑みだった。
カウラの視線の先で誠はうなだれつつ話始めた。
その暗い表情に、いつもは明るい面々も誠に何か過去があることくらいは察した。春子はそっと、冷たい水をもう一杯、誠の前に置く。ラベルは上。
「肩をやったのは事実ですけど……それ以前の問題ないんです。実は……僕……後輩のキャッチャーを殴ったんです……試合中に……それで公式の試合には出場できなくなったんです」
誠の突然の告白にカウラとアメリアの表情が曇った。サラが笑いを止め、島田はタバコを灰皿に押しつける。
「うちの高校……都立の進学実験校だったんで……ほとんどの生徒が帰宅部なんですよ」
ビールのグラスを手に誠は話を続ける。グラスの外側を伝う水滴が、輪じみを新しく刻む。
「僕の居た野球部も三年が僕と別のキャッチャーをやっていて主将だった奴と二人っきりだったんです。二年と一年生を合わせても十二人しか部員が居ないんです……しかも一年からほとんどの生徒が予備校に通ってるんでほとんど練習には出られないんです……練習試合もできない有様でしたから」
暗い誠の表情に聞いてきたアメリアさえ少し寂しげな表情を浮かべていた。
七輪の上でつくねが弾け、源さんが手早くタレを重ねる。
「夏の全国大会の東東都予選の3回戦で……相手は……坂東一高って言う学校でして……」
誠は悪夢を振り払うような暗い調子でそう言った。
「坂東一高!その年の全国大会優勝校じゃないの!」
さすがに野球をやっているだけあってアメリアは全国大会出場確実な学校名ぐらいは知っていた。糸目がわずかに見開く。
「うちのキャプテンだったキャッチャーの奴が、その日大学の推薦入試の面接だったんです。そいつなら僕の決め球のフォークを身体で止められるんですけど……補欠の後輩には無理でした……ただそれだけの話です」
誠はそう言って遠い昔のことのようにその光景を思い出していた。夏の空気、白線の匂い、乾いたスパイクの音が誠の耳の中に思い出されて心に突き刺さった。
「ずいぶんと悪趣味な日に面接の予定を入れるわね。それに東和の大学は4月入学でしょ?なんで7がつに入試があるの?」
「そいつは海外留学希望があって夏季入試の日程に合わせて受験したからその日になったそうです。……そのゲルパルトにある医大も9月入学のための入試が7月にあるんです……アメリアさんはゲルパルトの出身だからそれくらい知ってるんじゃないですか?」
あまり話したくない自分のトラウマを語る誠の言葉にはどうしても隠しがたい棘があった。アメリアはそれに気付いて糸目をさらに細めて静かに誠を見守っていた。
「ごめんね、私は知ってて当たり前のことかもしれないわね。そう言えば……4月入学の国って同盟では東和と甲武くらいだものね」
アメリアは納得したというようにシシトウを口に運んだ。今日は当たりを引かない。
「こいつがアマチュア野球の公式戦からは全面出場禁止になってることは知ってるよ。その補欠のキャッチャーのその日のパスボールが8個。他にも内外野のエラーが合わせて22個……5回コールド負けの試合で、240球も投げたら肩も壊れるわな。普通は」
かなめはラムを飲みながらそうつぶやいた。言い方は荒いが、数字は正確だ。
「知ってたんですか?」
少し驚いたような誠の顔を見てかなめはやさしく笑いかけた。
「1回戦は完全試合、2回戦は三安打失点0で、その試合で非公式とは言え左腕で158kmの球速を誇った『都立の星』の最期にしちゃあずいぶん間の抜けた話だってんで調べたんだ。あれだろ?その正キャッチャーの奴はその後、都立の医科大学に進んで今じゃあ母校の監督をしてるって話じゃねえか……うちの野球部にも欲しい人材だ。うちのチームのキャッチャーはあてにならねえからな」
かなめは表情も変えずにラム酒をあおった。パーラが横目で「誰のこと」と睨み、アメリアが肩をすくめて笑う。
「ええ、アイツは……試合の日程が決まった時、自分の大学受験なんてどうでもいいって言ったんです。3回戦さえ超えれば全国大会に出られるようなトーナメント表になってましたから。そのためならゲルパルトの医大は諦めて東和の医大を受けるって。でも僕が止めてアイツはそのままゲルパルトの医大の東都会場での面接を受けたんです。実際、その推薦入試は落ちて、その冬に都立医科大に合格して、そっちに進学しましたから。けど……僕には言えませよ、お前が居ないとゲームにならないなんて……アイツは医者になるつもりで高校に来てたんですから。野球をやりに来てたわけじゃありませんから。僕が殴った後輩も、エラーした後輩もみんな野球をやりに高校に来たわけじゃなくて高校には大学に行くための勉強をしに来てたんですから。アレはただの天狗になってた僕の暴走です」
誠はうつむきながらジョッキに口を近づける。泡が鼻先をくすぐり、目の奥に熱が差した。
そんな仕草の中に少し感傷的になっている自分を感じていた。
「でも殴るなんて……」
さすがに笑いの為には暴力も辞さないアメリアも誠の意外な行動に言葉を詰まらせた。サラが静かに頷く。
「僕も自分で殴るなんて思っていなかったんです。パスボールを詫びに来た後輩を気が付いたら殴ってたんです。正直、天狗になってたんですよ、その時の僕は。マスコミに『都立の星』とか呼ばれて、しかもどのブロックでも東東都大会は番狂わせ続きで坂東一高以外の強豪校はほとんど消えてるという状況で僕の心がおかしくなっていたんです。その試合もプロのスコアラーとかが山と来て……それが試合が始まったらワンサイドゲーム。それもヒット性の当たりが一つも無いのに次々に点を取られて自分のせいじゃないと思ったらなんだか怒りがわいてきちゃって押さえられなかったんです。それまで『もんじゃ焼き製造マシン』とかバカにされて生きてきた反動ですかね……急に注目されたあの時の僕はどうかしてました。生まれて初めて人を殴ったのがそれです。でも、暴力はいけませんよね。即座に僕は退場になり、それ以来、公式試合から永久追放されて……野球はやっていないんです」
アメリアに言われるまでも無い。カウンターの上で小さな沈黙が輪を広げ、やがて吸い込まれていく。
それに誠はそれ以降も人を殴ったことは無かった。
「オメエが来るって聞かされて実は当時の映像を見たが……全国大会優勝チーム相手に外野まで飛んだ当たりがほとんど無かったのは事実だしな……キャッチャーがまともなら勝ちはしねえがいい試合になったろ」
そう言うかなめの慰めの言葉も今の誠にはあまり意味は無かった。だが、数字と映像に裏打ちされたその一言は、どこかで冷めきった自己否定の温度を少しだけ下げる。
「でも三振もほとんど取れませんでしたよ。やっぱり全国レベルの選手は違いますよね。ボールになるスライダーやフォークは見向きもしないし、カウントを取りに行ったストレートはセンター返しで、カーブは……いい勉強になりました。僕にはやっぱり勉強と絵とプラモしかないのかなって……」
そう言って誠はジョッキのビールを飲み干した。泡の消えた輪が底に残り、指先の汗はようやく引いていた。
七輪の火は落ち着きを取り戻し、店の時計の秒針が、次の一拍を刻む。外は完全な夜。暖簾の向こう、路地の風が少し冷たくなっている。
30
あなたにおすすめの小説

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

旧校舎の地下室
守 秀斗
恋愛
高校のクラスでハブられている俺。この高校に友人はいない。そして、俺はクラスの美人女子高生の京野弘美に興味を持っていた。と言うか好きなんだけどな。でも、京野は美人なのに人気が無く、俺と同様ハブられていた。そして、ある日の放課後、京野に俺の恥ずかしい行為を見られてしまった。すると、京野はその事をバラさないかわりに、俺を旧校舎の地下室へ連れて行く。そこで、おかしなことを始めるのだったのだが……。

ちょっと大人な体験談はこちらです
神崎未緒里
恋愛
本当にあった!?かもしれない
ちょっと大人な体験談です。
日常に突然訪れる刺激的な体験。
少し非日常を覗いてみませんか?
あなたにもこんな瞬間が訪れるかもしれませんよ?
※本作品ではGemini PRO、Pixai.artで作成した生成AI画像ならびに
Pixabay並びにUnsplshのロイヤリティフリーの画像を使用しています。
※不定期更新です。
※文章中の人物名・地名・年代・建物名・商品名・設定などはすべて架空のものです。

クラスのマドンナがなぜか俺のメイドになっていた件について
沢田美
恋愛
名家の御曹司として何不自由ない生活を送りながらも、内気で陰気な性格のせいで孤独に生きてきた裕貴真一郎(ゆうき しんいちろう)。
かつてのいじめが原因で、彼は1年間も学校から遠ざかっていた。
しかし、久しぶりに登校したその日――彼は運命の出会いを果たす。
現れたのは、まるで絵から飛び出してきたかのような美少女。
その瞳にはどこかミステリアスな輝きが宿り、真一郎の心をかき乱していく。
「今日から私、あなたのメイドになります!」
なんと彼女は、突然メイドとして彼の家で働くことに!?
謎めいた美少女と陰キャ御曹司の、予測不能な主従ラブコメが幕を開ける!
カクヨム、小説家になろうの方でも連載しています!


中1でEカップって巨乳だから熱く甘く生きたいと思う真理(マリー)と小説家を目指す男子、光(みつ)のラブな日常物語
jun( ̄▽ ̄)ノ
大衆娯楽
中1でバスト92cmのブラはEカップというマリーと小説家を目指す男子、光の日常ラブ
★作品はマリーの語り、一人称で進行します。

ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる