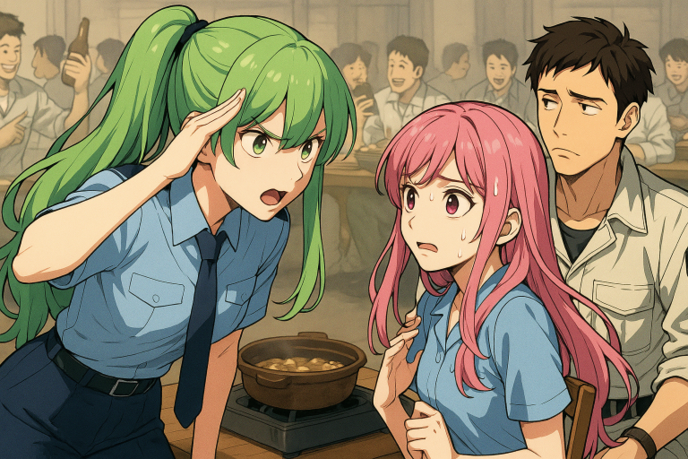77 / 81
第二十九章 『特殊な部隊』の大宴会
第76話 愛を知らない遼州人と、悩めるベルガー大尉
しおりを挟む
日々3万円生活で期限切れのカップ麺以外の物をほとんど食べていないほとんど鍋の具を一人で食べ尽くした嵯峨が、空になりかけた土鍋を名残惜しそうに見下ろしながら、ふと顔を上げた。
クエの白い身と野菜の残骸が沈む汁の向こうで、彼はいやらしい笑みを浮かべる。
「じゃあ聞くわ。ベルガー。この『女王様』とそこの馬鹿がくっつくと、なんかお前さんにとって困る事があるの?俺も納得できるようなカタイで教えて」
誠と同い年ぐらいにしか見えない、その実四十六歳らしい老獪な笑みだった。
薄い唇がにやりと歪み、エメラルドグリーンの瞳を細めたカウラの顔を覗き込む。
誠は助けを求めようと、周囲のテーブルを見回した。
だが、技術部の島田の兵隊達や、アメリアの部下である運航部の面々は……完全にこのまま他者の目を気にしないラブシーンが繰り広げらる事だけを気にしているようだった。
この明らかに『特殊』な状況を『最高の酒の』」としか見ていないようで、誰一人として助け舟を出す気配はない。
視線だけはちょくちょくこちらに飛んでくるが、全員がそろって知らん顔を決め込んでいた。
軍医を探しに行っていたはずのランですら、ランの常識の範囲にあるラブシーンしか想像できないカウラが相手と会って。いつの間にか嵯峨のいる上座の鍋を占拠し、誠達を一瞥することもなく、箸を鍋に突っ込んでクエの身をさらっている。
……完全に、見世物扱いだ。
「それはれすね!西園寺のような『女王様』に苛められると、神前がMに目覚めるのです!そうするとアメリアがその様子を盗撮してネットにながすのれす!困るのはわたしなのです!」
ろれつの怪しい声が、宴会場のざわめきの上にくぐもって響いた。
頬を真っ赤に染めたカウラが、ぐらつく上体を誠の肩に預けながら、力説する。
「神前がMに目覚める?そいつはまずいなあ……うちにはもっと手におえないレベルのドMが来る予定になってるんだよ。ねえ、『偉大なる中佐殿』」
意味不明なカウラの言葉に、嵯峨はわざとらしく肩をすくめて、話題をランに振った。
「違法じゃなきゃいーんじゃねーか?それとそのドM。日野のことだろ?アタシは今はOKしてねー。まーそう言う趣味の人もいるみてーだし。他人に迷惑かけなきゃ、それもアリなんじゃねーか?日野は別だ。アイツは島田以上の問題を起こすのは間違いねー」
ランは無責任にクエの身を頬張りながら、平然とそう言った。
酒の入った一升瓶を片手にぶら下げたまま、まるで他人事である。
「ちっちゃいのに何てこというんですか!」
今のところはMに目覚めたくない誠は、やる気のないランの言葉にそう叫んで反論した。
周りからクスクスと笑いが漏れる。
「なるほどねえ……かなめちゃんが、誠ちゃんに餌をやったり芸を仕込んだりするところを撮影してネットにあげれば……結構儲かるかも」
アメリアは、糸目をさらに細くして満足げな笑みを浮かべる。
手元の缶ビールをくるくる回しながら、すでに頭の中では『アダルトビジネスモデル』が組み立てられているような顔だ。
『誰か止めて!』
心の中で誠は悲鳴を上げたが、誰も止めるつもりは無い。
むしろ技術部の若い兵士が、「それ見たいっすね」と小声で盛り上がっているのが聞こえてきて、余計に絶望的だった。
それでも、まだカウラの演説は続く。
「わたしは!見過ごせないのれす!神前がタレ目女王様として覚醒を迎えるのを見過ごせないのです! ですから隊長!」
急にカウラは、ふらつきながらも直立不動の姿勢をとる。
酒の入った体から、ピシッと軍人としての癖だけは抜けないらしい。
その時、嵯峨は〆のうどん玉を鍋に投入している最中だった。
麺を湯の中でほどきながら、上目遣いでカウラをちらりと見る。
また自分に話題が回ってきたことに、心底『面倒だ』と言いたげな顔をしつつ、嵯峨は仕方なく作業を中断する。
「だからなに?」
さすがに飽きてきたのか、嵯峨の口調は投げやりだった。
「こういう状況で何をするべきか、それを教えていただきたいのです!誠!わらしはなにをしたらいいのら!」
酔っぱらって理性の吹き飛んだカウラに、理屈は通用しなかった。
誠に向けた訴えなのか、隊長への相談なのか、その境界線すらあやふやだ。
「ベルガーが何をしたらいいのかねえ……って、神前支えろ!」
嵯峨の言葉を聞いて、誠は慌てて動き出した。
仰向けにひっくり返りそうになったカウラを、あわてて両腕で支える。
その誠の頭を、カウラはぽかぽかと柔らかいこぶしで殴った。
全然痛くはないのに、妙に胸のあたりがざわざわする。
パーラ、サラ、島田の三人は、呆れ顔をしつつも、次のカウラの絡み酒の標的になる事を恐れて、退散するタイミングを計っていた。
視線だけが、泳ぐようにカウラと嵯峨と出口のあたりを行ったり来たりしている。
一方、アメリアは……。
カウラの壊れっぷりに慌てふためいて誠がぶっ壊れて意味不明なことを言い出さないので、むしろ苛立っているように見えた。
『もっと面白い絵が撮れるはずなのに』とでも言いたげに、唇をとがらせている。
「そりゃあ、愛って奴じゃねーの?カウラは地球人の遺伝子を元に作られた『ラスト・バタリオン』だ。愛とは縁がねー遼州人と考え方が違ってもおかしなことは一つもねーな」
ボソッとランがつぶやいた。
その場にいた誰もが、ぴくりと顔を上げてランの顔を見る。
騒がしいハンガーのざわめきの中で、その一言だけがすっと耳に残った。
ランは、自分でもつまらない事を言ったなあと言う表情を作って、そっぽを向いた。
隣でクエの身を頬張っていた軍医は、彼女にかかわるまいと、露骨に『自分には関係ありません』という顔をする。
そして、また直立不動の姿でかかとを鳴らして敬礼したカウラに、全員の視線が集中した。
「サラ! サラ・グリファン少尉、応答しろ!」
真顔のまま、ものすごい勢いでカウラはサラに迫った。
酔っているはずなのに、その足取りだけやけに素早い。
「ハイ! 大尉殿!」
その場にいた誰もが、カウラに絡まれることが決定したサラに哀れみの視線を投げた。
特に島田は、彼女を助けに行けない自分の非才を嘆いているような顔をしていた。
「愛とはなんなろれす?サラ。おしえれもらうしか、ないのれす?」
カウラは真剣な表情で、困惑するサラに尋ねた。
瞳だけは酔いではなく、別の何かを探しているように見える。
「教えろったって……ねえ……ひよこちゃんに聞けばいいんじゃない……あの子のポエムの題材とかに有りそうだし」
サラの表情は、明らかに危険を感じており、すぐにでも逃げ出したいように見えた。
ただ、誠は彼女と島田の日常を知っていたので、この二人の意見が全く参考にならないということも、よくわかっていた。
だからこそ、誠は椅子から腰を上げた。
酒も入っているのに、妙に頭だけは冷静だった。
「愛か……」
ランが珍しく真剣な目をした。
「答えは簡単じゃねーよ。遼州人のアタシには理解不能だが、地球人の連中ではごく普通らしい。だからこそ、皆んな悩むんだろうな」
ランはそう言って、一人で日本酒を口にした。
彼女の小さな喉が、ごくりと鳴る。
「カウラさん休みましょう!さあこっちに来て」
誠は、サラに絡もうとするカウラを両腕で抱え込んだ。
酔いで重くなった身体が、ずっしりとのしかかる。
「もっとするのら!もっとするのら!わたしはなにもわかってないのら!」
次第にアルコールのめぐりが良くなったのか、カウラは全身の関節をしならせながら叫んだ。
その姿は、冷静沈着な狙撃手の面影もない。
「こりゃ駄目だ。神前、ベルガーを部屋まで送ってやんなよ」
クエのだしの効いた鍋でうどんを茹でながら、嵯峨がそう言った。
あくまで『いつもの仕事を指示する』調子である。
「神前が変な気起こすと面倒だからな……アタシが運ぼうか?」
そう言いながらかなめが自分を見る瞳に、露骨な殺意がこもっていることを、誠は理解していた。
その手は、いつでも拳銃のグリップに伸びそうだ。
「そうよね私も手伝うわ。それとそこの林軍曹!福島伍長!」
巻き込まれたアメリアが、缶ビールをテーブルに置き、ゆっくりと動き出す。
島田の兵隊の中では体格がいい林と福島は、素早く背筋を伸ばし、カウラのそばに立った。
「クラウゼ少佐……本当に自分達でよろしいんでしょうか?」
二人の目が、カウラの細身の身体を舐めまわすように見ているのに気が付いた誠は、この二人を指名したことがアメリアのカウラへの嫌がらせであることを、なんとなく察した。
二人は誠の両脇に走り寄って、自分の『女神』であるカウラに手を伸ばそうとする。
「林!福島!オメー等は菰田と仲が良かったな……道理で目が邪悪すぎる!神前!オメーは体力あんだから一人でなんとかしろ!」
隊を知り尽くす『偉大なる中佐殿』であるランの一言に、二人はひるんで立ち尽くした。
即座に「不採用」と烙印を押されたような顔をする。
「そうなのら!タレ目とつまらない奴はひっこんれるのな!神前!いくろな!」
そう言うと、壊れたようにカウラは笑い始める。
誠の肩にしがみつきながら、くくくと喉を鳴らす。
誠は彼女を背負って、そのまま宴会場であるハンガーを後にした。
格納庫の大扉が遠ざかるにつれ、クエ鍋の匂いと人いきれは薄れ、代わりに金属とオゾンの匂いが戻ってくる。
誰も居ない通路。
床に貼られた黄色い安全ラインだけが、無機質な光に浮かんでいた。
よろけながら歩くカウラを支えつつ、誠はエレベータホールにたどり着いた。
壁面の時計が、宴会が始まってまだ一時間も経っていないことを告げている。
「大丈夫ですか?カウラさん」
心配した誠が声をかける。
カウラは、さっきまでの酔っぱらいぶりが嘘のように、うって変わった調子でシャキッと立つと、乱れた髪を指先で整えた。
「ああ、大丈夫だ」
カウラが落ち着いた静かな口調で話し出した。
瞳の焦点もはっきりと戻っている。
その変化に誠は戸惑う。同時に誠は思った。
『そういえばカウラさん、飲む前から妙に余裕があった気がする……』
誠の戸惑った顔に、照れたような笑みを浮かべると、カウラはネタバラシを始めた。
「半年前はアメリアが、あのような醜態をさらす事が多くてな。それを真似ただけだ」
「じゃあ酒は飲んでなかったのですか?」
あっけに取られて誠が叫んだ。
「飲んだ事は飲んだが、理性が飛ぶほどヤワじゃない。……来たぞ、エレベーター」
カウラを背負ったまま、誠はエレベータに乗り込む。
扉が閉まると同時に、外の喧噪が完全に断ち切られ、密室特有の静けさが降りた。
「それじゃあ何であんな芝居を?なんで僕にそこまでするんです?」
誠の問いかけに、カウラはすぐには答えなかった。
二人だけの空間。時がゆっくりと流れる。
背中越しに伝わる体温。
僅かなカウラの胸のふくらみが、誠の背中にも分かった。
「何でだろうな。私にも分からん。ただ西園寺やアメリアを見るお前を見ていたら、あんな芝居をしてみたくなった……酒を飲んだのは事実だ。それも酒のせいかな」
すねたような調子で、カウラがそう言った。
誠には、その声の奥に、言葉にできない何かが隠れているように感じられた。
エレベータは居住区に到着する。
チン、と軽い音が鳴って扉が開いた。
「しばらく休ませてくれ。やはり酔いが回ってきた」
やはりそれほど酒の強くない人造人間のカウラは、エレベータの隣のソファーを指差して言った。
「そうですね」
誠はそう言うと、カウラをソファーにそっと座らせた。
廊下は静かだった。
この艦の運行はすべて、遼州星系では普通の『アナログ式量子コンピュータ』システムで稼動している。
作戦中で無ければ、ほとんどの運行は人の手の介在無しで可能だ。
だから今この時間帯、運航関係者で業務上飲酒ができない人間は、自室で『釣り』ゲームに興じていることだろう。
彼等はみな、筋金入りの『釣りマニア』なのだから。
誰一人いない廊下。
非常灯の緑の光だけが、静かに床を照らしていた。
「悪いな。私につき合わせてしまって。これで好きなのを飲んでくれ」
カウラはそう言うと、誠に小銭を渡す。
誠はソファーの隣の自販機の前に立った。
「カウラさんはスポーツ飲料か何かでいいですか?」
「任せる」
そう言うとカウラは大きく肩で息をした。
強がっていても、明らかに飲みすぎているのは誠にもわかった。
誠は休憩所のジュースの自販機にカードを入れた。
ガコン、と金属音が響く。
「怒らないんだな。嘘をついたのに……それとも西園寺の下僕の地位が気に入ったのか?」
スポーツ飲料のボタンを押し、缶を機械から取り出す誠を眺めながら、カウラが言った。
「別に怒る理由も無いですから。それと下僕にはなりたくないです。僕は『甲武国』の国民でも無いですし、一応市民なんで」
そう言うと、誠は缶をカウラに手渡す。
「本当にそうなのか? お前のための宴会だ。それに西園寺やアメリアも、お前がいないと寂しいだろう」
コーヒーの缶を取り出している誠に、カウラはそう言った。
振り返ったその先の緑の瞳には、困ったような、悲しいような、感情というものにどう接したらいいのかわからない、そんな気持ちが映っているように誠には見えた。
「カウラさんも放っておけないですから」
「そうか、私は『放っておけない』か……」
カウラは、誠の言葉を繰り返すと、静かに缶に口をつけた。
喉の奥を通る炭酸の音が、かすかに聞こえる。
カウラの肩が揺れる。アルコールは確実にまわっている。
だが誠の前では、何とか毅然として見せようとしているのが感じられた。
その姿が「本当のカウラ」なのか、先程自分で演技だと言った壊れたカウラが本物なのか……誠には図りかねていた。
「やはり、どうも気分が良くない。誠、肩を貸してくれ」
飲み終わった缶を誠に手渡しながら、カウラは誠にそう言った。
「わかりました、大丈夫ですか?」
「大丈夫だ……何をしてるんだろうな……私は。貴様は所詮は愛を知らない遼州人だというのに」
そうは言うものの、かなり足元はおぼつかない。
誠はカウラに肩を貸すと、ゆっくりと廊下をカウラの部屋に向かい歩く。
床板に響く二人分の足音だけが、静かな通路に小さく反響した。
上級士官用の個室が並ぶ区画。
その一角に着くと、カウラはキーを開けた。
「本当に大丈夫ですか?」
「すまない。ベッドまで連れて行ってくれ」
カウラは、いつもは白く透き通る肌を赤く染めながら、誠にそう頼んだ。
カウラの部屋は士官用だけあり、誠のそれより一回り大きい。
だが室内には、パチンコの台が壁一面に並び、誠の部屋よりは大きいはずなのに、どこかしら狭く感じた。
それは……そこに見えるのが彼女にとって唯一の『娯楽』であり、戦場以外の時間のほとんどをここで過ごしてきた証なのだろう、と誠は思った。
「とりあえずここでいい。少し疲れた。もう大丈夫だから帰って良いぞ。西園寺が暴走すると厄介だ」
そう言うと、カウラはそのままベッドに身を沈めた。
誠は静かに立ち上がり、ドアのところで立ち止まった。
「お休みなさい」
「ああ……一緒に海を見られるのを楽しみにしている」
カウラは優しく返した。
それは、前に二人で交わした「約束」を、ちゃんと覚えているという意味でもあった。
誠はそのまま部屋を出た。
廊下が妙に薄暗く感じた。
照明の色は行きと同じはずなのに、心のせいかもしれない。
エレベータがちょうど上がってきていたが、誠は構わず、ハンガーに向かうボタンを押した。
『英雄か……でも、僕自身は何も変わっていないのに……カウラさんをあんな風に変えてしまうなんて……』
誠は自嘲気味に笑った。
背中に残っているはずの体温を、ふと確かめたくなって、それでも拳を握ることで誤魔化した。
……『モテない宇宙人』遼州人のはずの自分が、誰かの「気まぐれ」をここまで揺らしてしまうなんて。誠はエレベータの到着をひたすら待った
クエの白い身と野菜の残骸が沈む汁の向こうで、彼はいやらしい笑みを浮かべる。
「じゃあ聞くわ。ベルガー。この『女王様』とそこの馬鹿がくっつくと、なんかお前さんにとって困る事があるの?俺も納得できるようなカタイで教えて」
誠と同い年ぐらいにしか見えない、その実四十六歳らしい老獪な笑みだった。
薄い唇がにやりと歪み、エメラルドグリーンの瞳を細めたカウラの顔を覗き込む。
誠は助けを求めようと、周囲のテーブルを見回した。
だが、技術部の島田の兵隊達や、アメリアの部下である運航部の面々は……完全にこのまま他者の目を気にしないラブシーンが繰り広げらる事だけを気にしているようだった。
この明らかに『特殊』な状況を『最高の酒の』」としか見ていないようで、誰一人として助け舟を出す気配はない。
視線だけはちょくちょくこちらに飛んでくるが、全員がそろって知らん顔を決め込んでいた。
軍医を探しに行っていたはずのランですら、ランの常識の範囲にあるラブシーンしか想像できないカウラが相手と会って。いつの間にか嵯峨のいる上座の鍋を占拠し、誠達を一瞥することもなく、箸を鍋に突っ込んでクエの身をさらっている。
……完全に、見世物扱いだ。
「それはれすね!西園寺のような『女王様』に苛められると、神前がMに目覚めるのです!そうするとアメリアがその様子を盗撮してネットにながすのれす!困るのはわたしなのです!」
ろれつの怪しい声が、宴会場のざわめきの上にくぐもって響いた。
頬を真っ赤に染めたカウラが、ぐらつく上体を誠の肩に預けながら、力説する。
「神前がMに目覚める?そいつはまずいなあ……うちにはもっと手におえないレベルのドMが来る予定になってるんだよ。ねえ、『偉大なる中佐殿』」
意味不明なカウラの言葉に、嵯峨はわざとらしく肩をすくめて、話題をランに振った。
「違法じゃなきゃいーんじゃねーか?それとそのドM。日野のことだろ?アタシは今はOKしてねー。まーそう言う趣味の人もいるみてーだし。他人に迷惑かけなきゃ、それもアリなんじゃねーか?日野は別だ。アイツは島田以上の問題を起こすのは間違いねー」
ランは無責任にクエの身を頬張りながら、平然とそう言った。
酒の入った一升瓶を片手にぶら下げたまま、まるで他人事である。
「ちっちゃいのに何てこというんですか!」
今のところはMに目覚めたくない誠は、やる気のないランの言葉にそう叫んで反論した。
周りからクスクスと笑いが漏れる。
「なるほどねえ……かなめちゃんが、誠ちゃんに餌をやったり芸を仕込んだりするところを撮影してネットにあげれば……結構儲かるかも」
アメリアは、糸目をさらに細くして満足げな笑みを浮かべる。
手元の缶ビールをくるくる回しながら、すでに頭の中では『アダルトビジネスモデル』が組み立てられているような顔だ。
『誰か止めて!』
心の中で誠は悲鳴を上げたが、誰も止めるつもりは無い。
むしろ技術部の若い兵士が、「それ見たいっすね」と小声で盛り上がっているのが聞こえてきて、余計に絶望的だった。
それでも、まだカウラの演説は続く。
「わたしは!見過ごせないのれす!神前がタレ目女王様として覚醒を迎えるのを見過ごせないのです! ですから隊長!」
急にカウラは、ふらつきながらも直立不動の姿勢をとる。
酒の入った体から、ピシッと軍人としての癖だけは抜けないらしい。
その時、嵯峨は〆のうどん玉を鍋に投入している最中だった。
麺を湯の中でほどきながら、上目遣いでカウラをちらりと見る。
また自分に話題が回ってきたことに、心底『面倒だ』と言いたげな顔をしつつ、嵯峨は仕方なく作業を中断する。
「だからなに?」
さすがに飽きてきたのか、嵯峨の口調は投げやりだった。
「こういう状況で何をするべきか、それを教えていただきたいのです!誠!わらしはなにをしたらいいのら!」
酔っぱらって理性の吹き飛んだカウラに、理屈は通用しなかった。
誠に向けた訴えなのか、隊長への相談なのか、その境界線すらあやふやだ。
「ベルガーが何をしたらいいのかねえ……って、神前支えろ!」
嵯峨の言葉を聞いて、誠は慌てて動き出した。
仰向けにひっくり返りそうになったカウラを、あわてて両腕で支える。
その誠の頭を、カウラはぽかぽかと柔らかいこぶしで殴った。
全然痛くはないのに、妙に胸のあたりがざわざわする。
パーラ、サラ、島田の三人は、呆れ顔をしつつも、次のカウラの絡み酒の標的になる事を恐れて、退散するタイミングを計っていた。
視線だけが、泳ぐようにカウラと嵯峨と出口のあたりを行ったり来たりしている。
一方、アメリアは……。
カウラの壊れっぷりに慌てふためいて誠がぶっ壊れて意味不明なことを言い出さないので、むしろ苛立っているように見えた。
『もっと面白い絵が撮れるはずなのに』とでも言いたげに、唇をとがらせている。
「そりゃあ、愛って奴じゃねーの?カウラは地球人の遺伝子を元に作られた『ラスト・バタリオン』だ。愛とは縁がねー遼州人と考え方が違ってもおかしなことは一つもねーな」
ボソッとランがつぶやいた。
その場にいた誰もが、ぴくりと顔を上げてランの顔を見る。
騒がしいハンガーのざわめきの中で、その一言だけがすっと耳に残った。
ランは、自分でもつまらない事を言ったなあと言う表情を作って、そっぽを向いた。
隣でクエの身を頬張っていた軍医は、彼女にかかわるまいと、露骨に『自分には関係ありません』という顔をする。
そして、また直立不動の姿でかかとを鳴らして敬礼したカウラに、全員の視線が集中した。
「サラ! サラ・グリファン少尉、応答しろ!」
真顔のまま、ものすごい勢いでカウラはサラに迫った。
酔っているはずなのに、その足取りだけやけに素早い。
「ハイ! 大尉殿!」
その場にいた誰もが、カウラに絡まれることが決定したサラに哀れみの視線を投げた。
特に島田は、彼女を助けに行けない自分の非才を嘆いているような顔をしていた。
「愛とはなんなろれす?サラ。おしえれもらうしか、ないのれす?」
カウラは真剣な表情で、困惑するサラに尋ねた。
瞳だけは酔いではなく、別の何かを探しているように見える。
「教えろったって……ねえ……ひよこちゃんに聞けばいいんじゃない……あの子のポエムの題材とかに有りそうだし」
サラの表情は、明らかに危険を感じており、すぐにでも逃げ出したいように見えた。
ただ、誠は彼女と島田の日常を知っていたので、この二人の意見が全く参考にならないということも、よくわかっていた。
だからこそ、誠は椅子から腰を上げた。
酒も入っているのに、妙に頭だけは冷静だった。
「愛か……」
ランが珍しく真剣な目をした。
「答えは簡単じゃねーよ。遼州人のアタシには理解不能だが、地球人の連中ではごく普通らしい。だからこそ、皆んな悩むんだろうな」
ランはそう言って、一人で日本酒を口にした。
彼女の小さな喉が、ごくりと鳴る。
「カウラさん休みましょう!さあこっちに来て」
誠は、サラに絡もうとするカウラを両腕で抱え込んだ。
酔いで重くなった身体が、ずっしりとのしかかる。
「もっとするのら!もっとするのら!わたしはなにもわかってないのら!」
次第にアルコールのめぐりが良くなったのか、カウラは全身の関節をしならせながら叫んだ。
その姿は、冷静沈着な狙撃手の面影もない。
「こりゃ駄目だ。神前、ベルガーを部屋まで送ってやんなよ」
クエのだしの効いた鍋でうどんを茹でながら、嵯峨がそう言った。
あくまで『いつもの仕事を指示する』調子である。
「神前が変な気起こすと面倒だからな……アタシが運ぼうか?」
そう言いながらかなめが自分を見る瞳に、露骨な殺意がこもっていることを、誠は理解していた。
その手は、いつでも拳銃のグリップに伸びそうだ。
「そうよね私も手伝うわ。それとそこの林軍曹!福島伍長!」
巻き込まれたアメリアが、缶ビールをテーブルに置き、ゆっくりと動き出す。
島田の兵隊の中では体格がいい林と福島は、素早く背筋を伸ばし、カウラのそばに立った。
「クラウゼ少佐……本当に自分達でよろしいんでしょうか?」
二人の目が、カウラの細身の身体を舐めまわすように見ているのに気が付いた誠は、この二人を指名したことがアメリアのカウラへの嫌がらせであることを、なんとなく察した。
二人は誠の両脇に走り寄って、自分の『女神』であるカウラに手を伸ばそうとする。
「林!福島!オメー等は菰田と仲が良かったな……道理で目が邪悪すぎる!神前!オメーは体力あんだから一人でなんとかしろ!」
隊を知り尽くす『偉大なる中佐殿』であるランの一言に、二人はひるんで立ち尽くした。
即座に「不採用」と烙印を押されたような顔をする。
「そうなのら!タレ目とつまらない奴はひっこんれるのな!神前!いくろな!」
そう言うと、壊れたようにカウラは笑い始める。
誠の肩にしがみつきながら、くくくと喉を鳴らす。
誠は彼女を背負って、そのまま宴会場であるハンガーを後にした。
格納庫の大扉が遠ざかるにつれ、クエ鍋の匂いと人いきれは薄れ、代わりに金属とオゾンの匂いが戻ってくる。
誰も居ない通路。
床に貼られた黄色い安全ラインだけが、無機質な光に浮かんでいた。
よろけながら歩くカウラを支えつつ、誠はエレベータホールにたどり着いた。
壁面の時計が、宴会が始まってまだ一時間も経っていないことを告げている。
「大丈夫ですか?カウラさん」
心配した誠が声をかける。
カウラは、さっきまでの酔っぱらいぶりが嘘のように、うって変わった調子でシャキッと立つと、乱れた髪を指先で整えた。
「ああ、大丈夫だ」
カウラが落ち着いた静かな口調で話し出した。
瞳の焦点もはっきりと戻っている。
その変化に誠は戸惑う。同時に誠は思った。
『そういえばカウラさん、飲む前から妙に余裕があった気がする……』
誠の戸惑った顔に、照れたような笑みを浮かべると、カウラはネタバラシを始めた。
「半年前はアメリアが、あのような醜態をさらす事が多くてな。それを真似ただけだ」
「じゃあ酒は飲んでなかったのですか?」
あっけに取られて誠が叫んだ。
「飲んだ事は飲んだが、理性が飛ぶほどヤワじゃない。……来たぞ、エレベーター」
カウラを背負ったまま、誠はエレベータに乗り込む。
扉が閉まると同時に、外の喧噪が完全に断ち切られ、密室特有の静けさが降りた。
「それじゃあ何であんな芝居を?なんで僕にそこまでするんです?」
誠の問いかけに、カウラはすぐには答えなかった。
二人だけの空間。時がゆっくりと流れる。
背中越しに伝わる体温。
僅かなカウラの胸のふくらみが、誠の背中にも分かった。
「何でだろうな。私にも分からん。ただ西園寺やアメリアを見るお前を見ていたら、あんな芝居をしてみたくなった……酒を飲んだのは事実だ。それも酒のせいかな」
すねたような調子で、カウラがそう言った。
誠には、その声の奥に、言葉にできない何かが隠れているように感じられた。
エレベータは居住区に到着する。
チン、と軽い音が鳴って扉が開いた。
「しばらく休ませてくれ。やはり酔いが回ってきた」
やはりそれほど酒の強くない人造人間のカウラは、エレベータの隣のソファーを指差して言った。
「そうですね」
誠はそう言うと、カウラをソファーにそっと座らせた。
廊下は静かだった。
この艦の運行はすべて、遼州星系では普通の『アナログ式量子コンピュータ』システムで稼動している。
作戦中で無ければ、ほとんどの運行は人の手の介在無しで可能だ。
だから今この時間帯、運航関係者で業務上飲酒ができない人間は、自室で『釣り』ゲームに興じていることだろう。
彼等はみな、筋金入りの『釣りマニア』なのだから。
誰一人いない廊下。
非常灯の緑の光だけが、静かに床を照らしていた。
「悪いな。私につき合わせてしまって。これで好きなのを飲んでくれ」
カウラはそう言うと、誠に小銭を渡す。
誠はソファーの隣の自販機の前に立った。
「カウラさんはスポーツ飲料か何かでいいですか?」
「任せる」
そう言うとカウラは大きく肩で息をした。
強がっていても、明らかに飲みすぎているのは誠にもわかった。
誠は休憩所のジュースの自販機にカードを入れた。
ガコン、と金属音が響く。
「怒らないんだな。嘘をついたのに……それとも西園寺の下僕の地位が気に入ったのか?」
スポーツ飲料のボタンを押し、缶を機械から取り出す誠を眺めながら、カウラが言った。
「別に怒る理由も無いですから。それと下僕にはなりたくないです。僕は『甲武国』の国民でも無いですし、一応市民なんで」
そう言うと、誠は缶をカウラに手渡す。
「本当にそうなのか? お前のための宴会だ。それに西園寺やアメリアも、お前がいないと寂しいだろう」
コーヒーの缶を取り出している誠に、カウラはそう言った。
振り返ったその先の緑の瞳には、困ったような、悲しいような、感情というものにどう接したらいいのかわからない、そんな気持ちが映っているように誠には見えた。
「カウラさんも放っておけないですから」
「そうか、私は『放っておけない』か……」
カウラは、誠の言葉を繰り返すと、静かに缶に口をつけた。
喉の奥を通る炭酸の音が、かすかに聞こえる。
カウラの肩が揺れる。アルコールは確実にまわっている。
だが誠の前では、何とか毅然として見せようとしているのが感じられた。
その姿が「本当のカウラ」なのか、先程自分で演技だと言った壊れたカウラが本物なのか……誠には図りかねていた。
「やはり、どうも気分が良くない。誠、肩を貸してくれ」
飲み終わった缶を誠に手渡しながら、カウラは誠にそう言った。
「わかりました、大丈夫ですか?」
「大丈夫だ……何をしてるんだろうな……私は。貴様は所詮は愛を知らない遼州人だというのに」
そうは言うものの、かなり足元はおぼつかない。
誠はカウラに肩を貸すと、ゆっくりと廊下をカウラの部屋に向かい歩く。
床板に響く二人分の足音だけが、静かな通路に小さく反響した。
上級士官用の個室が並ぶ区画。
その一角に着くと、カウラはキーを開けた。
「本当に大丈夫ですか?」
「すまない。ベッドまで連れて行ってくれ」
カウラは、いつもは白く透き通る肌を赤く染めながら、誠にそう頼んだ。
カウラの部屋は士官用だけあり、誠のそれより一回り大きい。
だが室内には、パチンコの台が壁一面に並び、誠の部屋よりは大きいはずなのに、どこかしら狭く感じた。
それは……そこに見えるのが彼女にとって唯一の『娯楽』であり、戦場以外の時間のほとんどをここで過ごしてきた証なのだろう、と誠は思った。
「とりあえずここでいい。少し疲れた。もう大丈夫だから帰って良いぞ。西園寺が暴走すると厄介だ」
そう言うと、カウラはそのままベッドに身を沈めた。
誠は静かに立ち上がり、ドアのところで立ち止まった。
「お休みなさい」
「ああ……一緒に海を見られるのを楽しみにしている」
カウラは優しく返した。
それは、前に二人で交わした「約束」を、ちゃんと覚えているという意味でもあった。
誠はそのまま部屋を出た。
廊下が妙に薄暗く感じた。
照明の色は行きと同じはずなのに、心のせいかもしれない。
エレベータがちょうど上がってきていたが、誠は構わず、ハンガーに向かうボタンを押した。
『英雄か……でも、僕自身は何も変わっていないのに……カウラさんをあんな風に変えてしまうなんて……』
誠は自嘲気味に笑った。
背中に残っているはずの体温を、ふと確かめたくなって、それでも拳を握ることで誤魔化した。
……『モテない宇宙人』遼州人のはずの自分が、誰かの「気まぐれ」をここまで揺らしてしまうなんて。誠はエレベータの到着をひたすら待った
20
あなたにおすすめの小説

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

旧校舎の地下室
守 秀斗
恋愛
高校のクラスでハブられている俺。この高校に友人はいない。そして、俺はクラスの美人女子高生の京野弘美に興味を持っていた。と言うか好きなんだけどな。でも、京野は美人なのに人気が無く、俺と同様ハブられていた。そして、ある日の放課後、京野に俺の恥ずかしい行為を見られてしまった。すると、京野はその事をバラさないかわりに、俺を旧校舎の地下室へ連れて行く。そこで、おかしなことを始めるのだったのだが……。

ちょっと大人な体験談はこちらです
神崎未緒里
恋愛
本当にあった!?かもしれない
ちょっと大人な体験談です。
日常に突然訪れる刺激的な体験。
少し非日常を覗いてみませんか?
あなたにもこんな瞬間が訪れるかもしれませんよ?
※本作品ではGemini PRO、Pixai.artで作成した生成AI画像ならびに
Pixabay並びにUnsplshのロイヤリティフリーの画像を使用しています。
※不定期更新です。
※文章中の人物名・地名・年代・建物名・商品名・設定などはすべて架空のものです。


中1でEカップって巨乳だから熱く甘く生きたいと思う真理(マリー)と小説家を目指す男子、光(みつ)のラブな日常物語
jun( ̄▽ ̄)ノ
大衆娯楽
中1でバスト92cmのブラはEカップというマリーと小説家を目指す男子、光の日常ラブ
★作品はマリーの語り、一人称で進行します。

ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。

プール終わり、自分のバッグにクラスメイトのパンツが入っていたらどうする?
九拾七
青春
プールの授業が午前中のときは水着を着こんでいく。
で、パンツを持っていくのを忘れる。
というのはよくある笑い話。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる