あなたにおすすめの小説

魔法使いたちへ
柏木みのり
児童書・童話
十四歳の由は、毎日のように、魔法使いとそうでない人々がごく普通に一緒に暮らす隣の世界を姉の結花と伯母の雅代と共に訪れ、同じく十四歳の親友ジャンと魔法化学の実験に没頭する日々を送っていた。ある晩、秘密の実験中に事故が起き、由の目の前で光の炸裂と共にジャンは忽然と消え去った。
ジャンに何が起きたのか。再会は叶うのか。
「9日間」「はるのものがたり」「春の音が聴こえる」と関連した物語。
(also @なろう)

クールな幼なじみの許嫁になったら、甘い溺愛がはじまりました
藤永ゆいか
児童書・童話
中学2年生になったある日、澄野星奈に許嫁がいることが判明する。
相手は、頭が良くて運動神経抜群のイケメン御曹司で、訳あって現在絶交中の幼なじみ・一之瀬陽向。
さらに、週末限定で星奈は陽向とふたり暮らしをすることになって!?
「俺と許嫁だってこと、絶対誰にも言うなよ」
星奈には、いつも冷たくてそっけない陽向だったが……。
「星奈ちゃんって、ほんと可愛いよね」
「僕、せーちゃんの彼氏に立候補しても良い?」
ある時から星奈は、バスケ部エースの水上虹輝や
帰国子女の秋川想良に甘く迫られるようになり、徐々に陽向にも変化が……?
「星奈は可愛いんだから、もっと自覚しろよ」
「お前のこと、誰にも渡したくない」
クールな幼なじみとの、逆ハーラブストーリー。

生まれたばかりですが、早速赤ちゃんセラピー?始めます!
mabu
児童書・童話
超ラッキーな環境での転生と思っていたのにママさんの体調が危ないんじゃぁないの?
ママさんが大好きそうなパパさんを闇落ちさせない様に赤ちゃんセラピーで頑張ります。
力を使って魔力を増やして大きくなったらチートになる!
ちょっと赤ちゃん系に挑戦してみたくてチャレンジしてみました。
読みにくいかもしれませんが宜しくお願いします。
誤字や意味がわからない時は皆様の感性で受け捉えてもらえると助かります。
流れでどうなるかは未定なので一応R15にしております。
現在投稿中の作品と共に地道にマイペースで進めていきますので宜しくお願いします🙇
此方でも感想やご指摘等への返答は致しませんので宜しくお願いします。

独占欲強めの最強な不良さん、溺愛は盲目なほど。
猫菜こん
児童書・童話
小さな頃から、巻き込まれで絡まれ体質の私。
中学生になって、もう巻き込まれないようにひっそり暮らそう!
そう意気込んでいたのに……。
「可愛すぎる。もっと抱きしめさせてくれ。」
私、最強の不良さんに見初められちゃったみたいです。
巻き込まれ体質の不憫な中学生
ふわふわしているけど、しっかりした芯の持ち主
咲城和凜(さきしろかりん)
×
圧倒的な力とセンスを持つ、負け知らずの最強不良
和凜以外に容赦がない
天狼絆那(てんろうきずな)
些細な事だったのに、どうしてか私にくっつくイケメンさん。
彼曰く、私に一目惚れしたらしく……?
「おい、俺の和凜に何しやがる。」
「お前が無事なら、もうそれでいい……っ。」
「この世に存在している言葉だけじゃ表せないくらい、愛している。」
王道で溺愛、甘すぎる恋物語。
最強不良さんの溺愛は、独占的で盲目的。

笑いの授業
ひろみ透夏
児童書・童話
大好きだった先先が別人のように変わってしまった。
文化祭前夜に突如始まった『笑いの授業』――。
それは身の毛もよだつほどに怖ろしく凄惨な課外授業だった。
伏線となる【神楽坂の章】から急展開する【高城の章】。
追い詰められた《神楽坂先生》が起こした教師としてありえない行動と、その真意とは……。

ノースキャンプの見張り台
こいちろう
児童書・童話
時代劇で見かけるような、古めかしい木づくりの橋。それを渡ると、向こう岸にノースキャンプがある。アーミーグリーンの北門と、その傍の監視塔。まるで映画村のセットだ。
進駐軍のキャンプ跡。周りを鉄さびた有刺鉄線に囲まれた、まるで要塞みたいな町だった。進駐軍が去ってからは住宅地になって、たくさんの子どもが暮らしていた。
赤茶色にさび付いた監視塔。その下に広がる広っぱは、子どもたちの最高の遊び場だ。見張っているのか、見守っているのか、鉄塔の、あのてっぺんから、いつも誰かに見られているんじゃないか?ユーイチはいつもそんな風に感じていた。

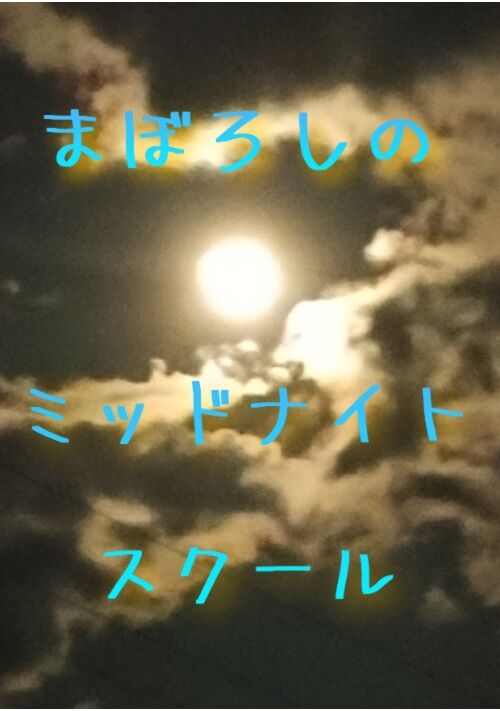
まぼろしのミッドナイトスクール
木野もくば
児童書・童話
深夜0時ちょうどに突然あらわれる不思議な学校。そこには、不思議な先生と生徒たちがいました。飼い猫との最後に後悔がある青年……。深い森の中で道に迷う少女……。人間に恋をした水の神さま……。それぞれの道に迷い、そして誰かと誰かの想いがつながったとき、暗闇の空に光る星くずの方から学校のチャイムが鳴り響いてくるのでした。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















