8 / 20
8
しおりを挟む
優一と初めて交わってから二週間が過ぎた。拓巳は、あの日どのくらいの時間をベッドで過ごしたのか覚えていない。目が覚めたら日が昇っていて、バスローブを着た優一が窓の外を見ていた。バスローブ姿ということはどこかでスーツを脱いだのだろうが、そのことすら思い出せなかった。
初日にたっぷりとαの精を受け入れた拓巳は、Ωとして未熟な体だったせいか三日間熱を出してしまった。熱でぼんやりしながらも「すみません」と謝る拓巳に、優一は「つがいの世話をするのも、わたしにとっては喜びの一つだよ」と優しく笑った。
そんな優一を思い出しながら「早く発情こないかな」と拓巳がつぶやく。最近の拓巳の頭は、ほとんどが発情のことで埋め尽くされていた。次の発情が来たときには優一も発情するだろうと教えられたからだ。
「早くこないかな」
「焦らなくても三カ月ごとに発情はやって来る」
「……優一さん」
ソファに座り庭をぼんやり見ていた拓巳の頭を、優一の冷たい手がポンと優しく撫でる。それだけで腹部の奥がじわりと熱を帯び、後孔がきゅうっと何かを食むように動いた。
「三カ月ってことは、次は二カ月半後か……」
「毎日きちんと食事をして栄養ドリンクも飲んでいる。Ωとしては目覚めたばかりで未熟だが、発情周期にズレは起きないだろう」
(オメガの発情は、三カ月ごとなんだよな)
拓巳はΩというものをよく知らない。そのため優一が教えてくれる知識しか持ち合わせていなかった。優一から、Ωは三カ月ごとに発情を迎えると教えられた。Ωが発情すればαも発情に入る。そこで交われば子を孕みやすくなるとも聞いた。
Ωについて気になることはいろいろあるが、拓巳が一番気になっているのは“つがい”という存在のことだった。次の発情で拓巳が優一の首筋を噛めばつがいの儀式は完了する。拓巳と優一は完全なつがいとなり優一は拓巳だけのものになる。ほかにも知るべきことはたくさんあるはずなのに、つがいとやらになれる日が待ち遠しくて発情のことばかり考えてしまう。
「焦らなくても、わたしのつがいはきみだけだ」
「……でも、優一さんは……」
「わたしが何かな?」
「……イケメンで金持ちだし、男も女も選びたい放題だろうから……俺なんて……」
自分はかっこよくもかわいくもない普通の十九歳の男だ。勉強も運動も適当にしていたから秀でているものは何もない。しかも、一年以上男たちに体を売っていたクズのような存在だ。
拓巳は急にいろんなことが不安になってきた。ソファの上で膝を立てると、顔を隠すように膝頭に額をつける。つがいは絶対的な関係だと優一に教えられたが、拓巳には“絶対的”という関係性がよくわからない。結婚相手と解釈するなら、優一には自分よりもよほどお似合いの人がいるはずだ。そもそも結婚なんて、その先には離婚しかない。母親を思い出し唇を噛み締める。
(オメガっていう人が少ないとしても、ゼロじゃないだろうし)
そう考えると自分が優一に選ばれた理由がますますわからなくなった。だからこそ、つがいが本当に絶対的な関係だとしたら早く完璧なつがいになりたいと焦ってしまう。
「きみがΩだからつがいに選んだわけじゃない。あぁいや、違うな。Ωというのも選んだ要素の一つではあるが、西野拓巳というΩでなければ選ばなかった。ほかのΩでは意味がないからね」
「……」
顔を上げずじっとしている拓巳の隣に優一が座った。
「わたしたちには運命の相手に強烈に惹かれる特性があってね。昔からαとΩにはそういう繋がりがあると言われてきた。互いの数が減ったいま、とくに運命の繋がりを求める傾向が強くなっている。これも種族的本能の一種なのだろう。長い命を共に生きるなら最良の相手がいいと考えるのは当然だ」
俯いたままの拓巳の鼻腔を、かすかな薔薇の甘い香りがくすぐり始める。
「初めてきみの香りを感じたのは、偶然すれ違った夢魔からだ。彼からきみのことを聞き、あのSNSにアクセスした。そうして初めて出会ったあの日、間違いなくわたしのΩだと確信した。きみはまだ目覚めてもいなかったのに、きみしかいないと確信できたのは運命の相手だからだろう」
「……でも、ほかにも俺みたいなオメガがいるかもしれない」
「運命は一人しかいない。人は忘れてしまったかもしれないが、わたしたちはそのことをよく知っている」
断言する優一の言葉と甘く優しい香りに導かれるように、拓巳はゆっくりと顔を上げた。自分を見つめる不思議な色合いの目に視線を囚われながら気になったことを尋ねる。
「運命って……一人、なんですか?」
「一生に一人しか存在し得ない」
「運命しか、つがいにならないんですか?」
拓巳の問いかけに、優一が苦笑のような笑みを浮かべた。
「残念ながら、運命と出会う確率は非常に低くてね。とくに人のΩやαは、人の中にあっては目覚めないことがほとんどだ」
「目覚めない……」
「たとえα因子やΩ因子を持っている人がいたとしても、人同士では関知できない。わたしたちのような強いαと出会ったΩが目覚めるか、もしくは狼や夢魔のΩと性交すれば目覚めるαもいるかもしれないが、そうした人が果たしてどのくらいいるだろうね」
優一の話をすべて理解することはできなかったが、非常に稀な出会いだということは拓巳にもなんとなく理解できる。
「わたしたちは、それだけ確率の低い出会いを果たした。きみは間違いなくわたしだけのΩだ。それはつまり、わたしがきみだけのαだということでもある」
優しく言い切る優一に拓巳の胸が高鳴った。
「八十年近く生きているが、わたしも本当に運命に出会えるとは思っていなかった。人の世に住んで五十年以上経つが、人のΩ自体もあまり見なかったからね」
さらりと話す優一の言葉に拓巳が「え?」と目を見開く。
「あの……八十年、って、」
「わたしの年齢だよ。そろそろ八十年ほどになる」
「ってことは、八十歳……」
「人の世に出てきたのは二十年を少し過ぎたくらいだったから、そういう意味では五十ほどと言ったほうがいいかな」
「……五十歳」
拓巳の背中がブルッと震えた。交わっていたときはどうでもいいと思っていたが、優一がどういう人物なのか改めて考えると不安になってくる。
(長生きってレベルじゃない。それってもしかしなくても、人じゃないってことなんじゃ……)
それとも優一の冗談だろうか。そう思って顔を窺うものの冗談を言っているようには見えない。それに拓巳には心当たりがあった。
初めて交わった日から、そういう雰囲気になると優一は首筋を甘噛みするようになった。そもそも儀式だとか言って噛まれたのも自分が優一を噛むのもおかしな話だ。行為の最中は頭も体も快楽に呑まれて深く考えないままだったが、この先もこのままでいいのだろうか。見惚れていたはずの優一の目を、拓巳は初めて怖いと思った。
「つがいが吸血鬼と呼ばれる存在だというのは、やはり恐ろしいかい?」
「きゅうけつ、き」
「昔から人にはそう呼ばれている。……怖いかい?」
「そんな、ことは……」
最後まで言い切ることはできなかった。
「無理をしなくていい。わたしたちが人からどう思われているかは、よくわかっている。わたしたちのほとんどは強いαで、何者でもない人の上に君臨し続けてきたからね。人に紛れて生きるようになって久しいが、人にはその頃植えつけられた恐怖心が根強く残っているのだろう。もしくは、何者でもない者がαに感じる恐れかもしれないが」
碧色にも灰色にも見える目の奥がわずかに揺れているように感じる。拓巳には、それが優一の悲しみのように思えた。
「怖……くない、とは、言えないですけど……。でも俺、優一さんは優しいと思います。だって……こんなクズみたいな俺を必要だって……。つがいにも、してくれたし……」
徐々に小さな声になっていく拓巳の頭を、優一の大きな手がポンと優しく撫でた。
「自分を卑下する必要はない。きみはわたしのΩだ。つがいになったこれからは新たな命を歩むことになる。まだ年若い見た目は気になるが、そのうち馴染んでいくだろう」
「……年若いって、俺、もう十九……あ、」
「きみが十九歳だということは知っているよ。初対面の夜に、勝手ながら身分証を見せてもらったからね」
「……嘘ついて、すみません」
「謝らなくていい。わたしが二十年ほどで人の世に出てきたから、そのくらいがベストかと思っていただけだ。それに、つがいにしたときのことを考えて念のために確認しただけだから」
「確認って……?」
「長い命で人の世に住むには、あまり若いと目立ってしまう。それでなくともきみは見た目が実年齢より若く見える。それもΩの特徴の一つではあるが、……いや、わかっていて待てなかったのはわたしのほうだ。きみに咎はない」
よくわからないまま優一を見つめていると、小さくフッと笑われる。
「わたしがきみに合わせればいいだけの話だ」
「あわせる?」
「わたしたちは見た目を少しばかり変えることができる。いまはいくつか会社を経営している立場だからこの姿をしているが、人で言うところの十歳ほどは若返ることが可能だ。……ふむ、そうすれば十九歳のきみの隣にいてもおかしくはないな」
「見た目って、え? 十歳って、えぇ?」
「さすがにこのままではよくて親子、中には情夫か何かだと思われかねない。それはわたしとしても本意ではないからね」
一度に多くのことを知らされた拓巳は混乱していた。それでも優しく微笑む優一の表情と甘い香りに、そばにいていいのだとわかりホッとする。そんな拓巳に再び笑いかけた優一はそっと手を伸ばし、まだ少し痩せたままの体を抱きしめた。
「きみはわたしのΩで運命のつがいだ。どうか、わたしのそばにいてほしい」
「……優一さん」
乞うような言葉に、拓巳の背中がふるっと震えた。胸がぎゅっとつかまれるような感覚に目尻が少しだけ濡れる。
たとえ優一が人でなくてもかまわない。生まれて初めてそばにいてほしいと言ってくれた人で、つがいという結婚相手にも選んでくれた。毎日あふれんばかりの気持ちを伝えてくれもする。これまでクズのような人生を送ってきた自分にも価値があるのだと思わせてくれるた。それだけで十分だ。拓巳は思いの丈を込めて優一を抱きしめ返した。
「俺も、そばにいたいです」
「ありがとう……可哀想なわたしだけのΩ」
「え? 優一さん何……、っ」
聞き逃したつぶやきを確認しようと体を離した拓巳だったが、すぐさま口づけられて問いかけることは叶わなかった。そのまま舌を吸われ唇を噛まれ、ジンとした痺れのような快感に体が熱くなる。
そのまま拓巳は、発情を伴わない何度目かの交わりに呑み込まれていった。
初日にたっぷりとαの精を受け入れた拓巳は、Ωとして未熟な体だったせいか三日間熱を出してしまった。熱でぼんやりしながらも「すみません」と謝る拓巳に、優一は「つがいの世話をするのも、わたしにとっては喜びの一つだよ」と優しく笑った。
そんな優一を思い出しながら「早く発情こないかな」と拓巳がつぶやく。最近の拓巳の頭は、ほとんどが発情のことで埋め尽くされていた。次の発情が来たときには優一も発情するだろうと教えられたからだ。
「早くこないかな」
「焦らなくても三カ月ごとに発情はやって来る」
「……優一さん」
ソファに座り庭をぼんやり見ていた拓巳の頭を、優一の冷たい手がポンと優しく撫でる。それだけで腹部の奥がじわりと熱を帯び、後孔がきゅうっと何かを食むように動いた。
「三カ月ってことは、次は二カ月半後か……」
「毎日きちんと食事をして栄養ドリンクも飲んでいる。Ωとしては目覚めたばかりで未熟だが、発情周期にズレは起きないだろう」
(オメガの発情は、三カ月ごとなんだよな)
拓巳はΩというものをよく知らない。そのため優一が教えてくれる知識しか持ち合わせていなかった。優一から、Ωは三カ月ごとに発情を迎えると教えられた。Ωが発情すればαも発情に入る。そこで交われば子を孕みやすくなるとも聞いた。
Ωについて気になることはいろいろあるが、拓巳が一番気になっているのは“つがい”という存在のことだった。次の発情で拓巳が優一の首筋を噛めばつがいの儀式は完了する。拓巳と優一は完全なつがいとなり優一は拓巳だけのものになる。ほかにも知るべきことはたくさんあるはずなのに、つがいとやらになれる日が待ち遠しくて発情のことばかり考えてしまう。
「焦らなくても、わたしのつがいはきみだけだ」
「……でも、優一さんは……」
「わたしが何かな?」
「……イケメンで金持ちだし、男も女も選びたい放題だろうから……俺なんて……」
自分はかっこよくもかわいくもない普通の十九歳の男だ。勉強も運動も適当にしていたから秀でているものは何もない。しかも、一年以上男たちに体を売っていたクズのような存在だ。
拓巳は急にいろんなことが不安になってきた。ソファの上で膝を立てると、顔を隠すように膝頭に額をつける。つがいは絶対的な関係だと優一に教えられたが、拓巳には“絶対的”という関係性がよくわからない。結婚相手と解釈するなら、優一には自分よりもよほどお似合いの人がいるはずだ。そもそも結婚なんて、その先には離婚しかない。母親を思い出し唇を噛み締める。
(オメガっていう人が少ないとしても、ゼロじゃないだろうし)
そう考えると自分が優一に選ばれた理由がますますわからなくなった。だからこそ、つがいが本当に絶対的な関係だとしたら早く完璧なつがいになりたいと焦ってしまう。
「きみがΩだからつがいに選んだわけじゃない。あぁいや、違うな。Ωというのも選んだ要素の一つではあるが、西野拓巳というΩでなければ選ばなかった。ほかのΩでは意味がないからね」
「……」
顔を上げずじっとしている拓巳の隣に優一が座った。
「わたしたちには運命の相手に強烈に惹かれる特性があってね。昔からαとΩにはそういう繋がりがあると言われてきた。互いの数が減ったいま、とくに運命の繋がりを求める傾向が強くなっている。これも種族的本能の一種なのだろう。長い命を共に生きるなら最良の相手がいいと考えるのは当然だ」
俯いたままの拓巳の鼻腔を、かすかな薔薇の甘い香りがくすぐり始める。
「初めてきみの香りを感じたのは、偶然すれ違った夢魔からだ。彼からきみのことを聞き、あのSNSにアクセスした。そうして初めて出会ったあの日、間違いなくわたしのΩだと確信した。きみはまだ目覚めてもいなかったのに、きみしかいないと確信できたのは運命の相手だからだろう」
「……でも、ほかにも俺みたいなオメガがいるかもしれない」
「運命は一人しかいない。人は忘れてしまったかもしれないが、わたしたちはそのことをよく知っている」
断言する優一の言葉と甘く優しい香りに導かれるように、拓巳はゆっくりと顔を上げた。自分を見つめる不思議な色合いの目に視線を囚われながら気になったことを尋ねる。
「運命って……一人、なんですか?」
「一生に一人しか存在し得ない」
「運命しか、つがいにならないんですか?」
拓巳の問いかけに、優一が苦笑のような笑みを浮かべた。
「残念ながら、運命と出会う確率は非常に低くてね。とくに人のΩやαは、人の中にあっては目覚めないことがほとんどだ」
「目覚めない……」
「たとえα因子やΩ因子を持っている人がいたとしても、人同士では関知できない。わたしたちのような強いαと出会ったΩが目覚めるか、もしくは狼や夢魔のΩと性交すれば目覚めるαもいるかもしれないが、そうした人が果たしてどのくらいいるだろうね」
優一の話をすべて理解することはできなかったが、非常に稀な出会いだということは拓巳にもなんとなく理解できる。
「わたしたちは、それだけ確率の低い出会いを果たした。きみは間違いなくわたしだけのΩだ。それはつまり、わたしがきみだけのαだということでもある」
優しく言い切る優一に拓巳の胸が高鳴った。
「八十年近く生きているが、わたしも本当に運命に出会えるとは思っていなかった。人の世に住んで五十年以上経つが、人のΩ自体もあまり見なかったからね」
さらりと話す優一の言葉に拓巳が「え?」と目を見開く。
「あの……八十年、って、」
「わたしの年齢だよ。そろそろ八十年ほどになる」
「ってことは、八十歳……」
「人の世に出てきたのは二十年を少し過ぎたくらいだったから、そういう意味では五十ほどと言ったほうがいいかな」
「……五十歳」
拓巳の背中がブルッと震えた。交わっていたときはどうでもいいと思っていたが、優一がどういう人物なのか改めて考えると不安になってくる。
(長生きってレベルじゃない。それってもしかしなくても、人じゃないってことなんじゃ……)
それとも優一の冗談だろうか。そう思って顔を窺うものの冗談を言っているようには見えない。それに拓巳には心当たりがあった。
初めて交わった日から、そういう雰囲気になると優一は首筋を甘噛みするようになった。そもそも儀式だとか言って噛まれたのも自分が優一を噛むのもおかしな話だ。行為の最中は頭も体も快楽に呑まれて深く考えないままだったが、この先もこのままでいいのだろうか。見惚れていたはずの優一の目を、拓巳は初めて怖いと思った。
「つがいが吸血鬼と呼ばれる存在だというのは、やはり恐ろしいかい?」
「きゅうけつ、き」
「昔から人にはそう呼ばれている。……怖いかい?」
「そんな、ことは……」
最後まで言い切ることはできなかった。
「無理をしなくていい。わたしたちが人からどう思われているかは、よくわかっている。わたしたちのほとんどは強いαで、何者でもない人の上に君臨し続けてきたからね。人に紛れて生きるようになって久しいが、人にはその頃植えつけられた恐怖心が根強く残っているのだろう。もしくは、何者でもない者がαに感じる恐れかもしれないが」
碧色にも灰色にも見える目の奥がわずかに揺れているように感じる。拓巳には、それが優一の悲しみのように思えた。
「怖……くない、とは、言えないですけど……。でも俺、優一さんは優しいと思います。だって……こんなクズみたいな俺を必要だって……。つがいにも、してくれたし……」
徐々に小さな声になっていく拓巳の頭を、優一の大きな手がポンと優しく撫でた。
「自分を卑下する必要はない。きみはわたしのΩだ。つがいになったこれからは新たな命を歩むことになる。まだ年若い見た目は気になるが、そのうち馴染んでいくだろう」
「……年若いって、俺、もう十九……あ、」
「きみが十九歳だということは知っているよ。初対面の夜に、勝手ながら身分証を見せてもらったからね」
「……嘘ついて、すみません」
「謝らなくていい。わたしが二十年ほどで人の世に出てきたから、そのくらいがベストかと思っていただけだ。それに、つがいにしたときのことを考えて念のために確認しただけだから」
「確認って……?」
「長い命で人の世に住むには、あまり若いと目立ってしまう。それでなくともきみは見た目が実年齢より若く見える。それもΩの特徴の一つではあるが、……いや、わかっていて待てなかったのはわたしのほうだ。きみに咎はない」
よくわからないまま優一を見つめていると、小さくフッと笑われる。
「わたしがきみに合わせればいいだけの話だ」
「あわせる?」
「わたしたちは見た目を少しばかり変えることができる。いまはいくつか会社を経営している立場だからこの姿をしているが、人で言うところの十歳ほどは若返ることが可能だ。……ふむ、そうすれば十九歳のきみの隣にいてもおかしくはないな」
「見た目って、え? 十歳って、えぇ?」
「さすがにこのままではよくて親子、中には情夫か何かだと思われかねない。それはわたしとしても本意ではないからね」
一度に多くのことを知らされた拓巳は混乱していた。それでも優しく微笑む優一の表情と甘い香りに、そばにいていいのだとわかりホッとする。そんな拓巳に再び笑いかけた優一はそっと手を伸ばし、まだ少し痩せたままの体を抱きしめた。
「きみはわたしのΩで運命のつがいだ。どうか、わたしのそばにいてほしい」
「……優一さん」
乞うような言葉に、拓巳の背中がふるっと震えた。胸がぎゅっとつかまれるような感覚に目尻が少しだけ濡れる。
たとえ優一が人でなくてもかまわない。生まれて初めてそばにいてほしいと言ってくれた人で、つがいという結婚相手にも選んでくれた。毎日あふれんばかりの気持ちを伝えてくれもする。これまでクズのような人生を送ってきた自分にも価値があるのだと思わせてくれるた。それだけで十分だ。拓巳は思いの丈を込めて優一を抱きしめ返した。
「俺も、そばにいたいです」
「ありがとう……可哀想なわたしだけのΩ」
「え? 優一さん何……、っ」
聞き逃したつぶやきを確認しようと体を離した拓巳だったが、すぐさま口づけられて問いかけることは叶わなかった。そのまま舌を吸われ唇を噛まれ、ジンとした痺れのような快感に体が熱くなる。
そのまま拓巳は、発情を伴わない何度目かの交わりに呑み込まれていった。
94
あなたにおすすめの小説

こわがりオメガは溺愛アルファ様と毎日おいかけっこ♡
なお
BL
政略結婚(?)したアルファの旦那様をこわがってるオメガ。
あまり近付かないようにしようと逃げ回っている。発情期も結婚してから来ないし、番になってない。このままじゃ離婚になるかもしれない…。
♡♡♡
恐いけど、きっと旦那様のことは好いてるのかな?なオメガ受けちゃん。ちゃんとアルファ旦那攻め様に甘々どろどろに溺愛されて、たまに垣間見えるアルファの執着も楽しめるように書きたいところだけ書くみたいになるかもしれないのでストーリーは面白くないかもです!!!ごめんなさい!!!

【完結】愛されたかった僕の人生
Kanade
BL
✯オメガバース
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
お見合いから一年半の交際を経て、結婚(番婚)をして3年。
今日も《夫》は帰らない。
《夫》には僕以外の『番』がいる。
ねぇ、どうしてなの?
一目惚れだって言ったじゃない。
愛してるって言ってくれたじゃないか。
ねぇ、僕はもう要らないの…?
独りで過ごす『発情期』は辛いよ…。

【完結済】極上アルファを嵌めた俺の話
降魔 鬼灯
BL
ピアニスト志望の悠理は子供の頃、仲の良かったアルファの東郷司にコンクールで敗北した。
両親を早くに亡くしその借金の返済が迫っている悠理にとって未成年最後のこのコンクールの賞金を得る事がラストチャンスだった。
しかし、司に敗北した悠理ははオメガ専用の娼館にいくより他なくなってしまう。
コンサート入賞者を招いたパーティーで司に想い人がいることを知った悠理は地味な自分がオメガだとバレていない事を利用して司を嵌めて慰謝料を奪おうと計画するが……。

ウサギ獣人を毛嫌いしているオオカミ獣人後輩に、嘘をついたウサギ獣人オレ。大学で逃げ出して後悔したのに、大人になって再会するなんて!?
灯璃
BL
ごく普通に大学に通う、宇佐木 寧(ねい)には、ひょんな事から懐いてくれる後輩がいた。
オオカミ獣人でアルファの、狼谷 凛旺(りおう)だ。
ーここは、普通に獣人が現代社会で暮らす世界ー
獣人の中でも、肉食と草食で格差があり、さらに男女以外の第二の性別、アルファ、ベータ、オメガがあった。オメガは男でもアルファの子が産めるのだが、そこそこ差別されていたのでベータだと言った方が楽だった。
そんな中で、肉食のオオカミ獣人の狼谷が、草食オメガのオレに懐いているのは、単にオレたちのオタク趣味が合ったからだった。
だが、こいつは、ウサギ獣人を毛嫌いしていて、よりにもよって、オレはウサギ獣人のオメガだった。
話が合うこいつと話をするのは楽しい。だから、学生生活の間だけ、なんとか隠しとおせば大丈夫だろう。
そんな風に簡単に思っていたからか、突然に発情期を迎えたオレは、自業自得の後悔をする羽目になるーー。
みたいな、大学篇と、その後の社会人編。
BL大賞ポイントいれて頂いた方々!ありがとうございました!!
※本編完結しました!お読みいただきありがとうございました!
※短編1本追加しました。これにて完結です!ありがとうございました!
旧題「ウサギ獣人が嫌いな、オオカミ獣人後輩を騙してしまった。ついでにオメガなのにベータと言ってしまったオレの、後悔」

オメガ大学生、溺愛アルファ社長に囲い込まれました
こたま
BL
あっ!脇道から出てきたハイヤーが僕の自転車の前輪にぶつかり、転倒してしまった。ハイヤーの後部座席に乗っていたのは若いアルファの社長である東条秀之だった。大学生の木村千尋は病院の特別室に入院し怪我の治療を受けた。退院の時期になったらなぜか自宅ではなく社長宅でお世話になることに。溺愛アルファ×可愛いオメガのハッピーエンドBLです。読んで頂きありがとうございます。今後随時追加更新するかもしれません。

やっと退場できるはずだったβの悪役令息。ワンナイトしたらΩになりました。
毒島醜女
BL
目が覚めると、妻であるヒロインを虐げた挙句に彼女の運命の番である皇帝に断罪される最低最低なモラハラDV常習犯の悪役夫、イライ・ロザリンドに転生した。
そんな最期は絶対に避けたいイライはヒーローとヒロインの仲を結ばせつつ、ヒロインと円満に別れる為に策を練った。
彼の努力は実り、主人公たちは結ばれ、イライはお役御免となった。
「これでやっと安心して退場できる」
これまでの自分の努力を労うように酒場で飲んでいたイライは、いい薫りを漂わせる男と意気投合し、彼と一夜を共にしてしまう。
目が覚めると罪悪感に襲われ、すぐさま宿を去っていく。
「これじゃあ原作のイライと変わらないじゃん!」
その後体調不良を訴え、医師に診てもらうととんでもない事を言われたのだった。
「あなた……Ωになっていますよ」
「へ?」
そしてワンナイトをした男がまさかの国の英雄で、まさかまさか求愛し公開プロポーズまでして来て――
オメガバースの世界で運命に導かれる、強引な俺様α×頑張り屋な元悪役令息の元βのΩのラブストーリー。

隣国のΩに婚約破棄をされたので、お望み通り侵略して差し上げよう。
下井理佐
BL
救いなし。序盤で受けが死にます。
文章がおかしな所があったので修正しました。
大国の第一王子・αのジスランは、小国の王子・Ωのルシエルと幼い頃から許嫁の関係だった。
ただの政略結婚の相手であるとルシエルに興味を持たないジスランであったが、婚約発表の社交界前夜、ルシエルから婚約破棄するから受け入れてほしいと言われる。
理由を聞くジスランであったが、ルシエルはただ、
「必ず僕の国を滅ぼして」
それだけ言い、去っていった。
社交界当日、ルシエルは約束通り婚約破棄を皆の前で宣言する。
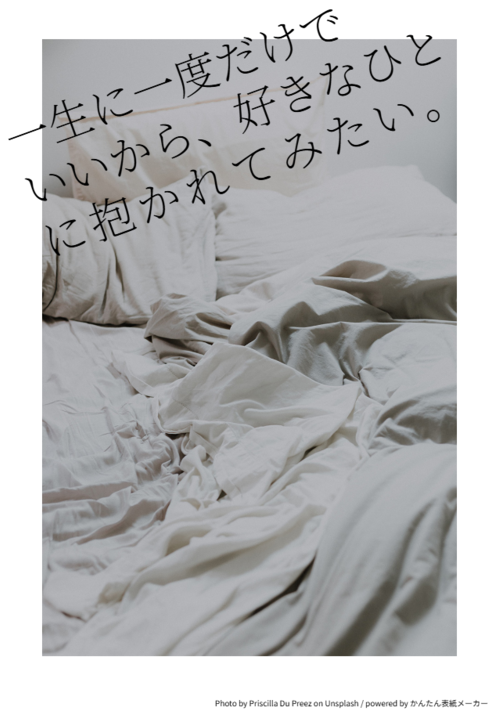
【完結】一生に一度だけでいいから、好きなひとに抱かれてみたい。
抹茶砂糖
BL
いつも不機嫌そうな美形の騎士×特異体質の不憫な騎士見習い
<あらすじ>
魔力欠乏体質者との性行為は、死ぬほど気持ちがいい。そんな噂が流れている「魔力欠乏体質」であるリュカは、父の命令で第二王子を誘惑するために見習い騎士として騎士団に入る。
見習い騎士には、側仕えとして先輩騎士と宿舎で同室となり、身の回りの世話をするという規則があり、リュカは隊長を務めるアレックスの側仕えとなった。
いつも不機嫌そうな態度とちぐはぐなアレックスのやさしさに触れていくにつれて、アレックスに惹かれていくリュカ。
ある日、リュカの前に第二王子のウィルフリッドが現れ、衝撃の事実を告げてきて……。
親のいいなりで生きてきた不憫な青年が、恋をして、しあわせをもらう物語。
第13回BL大賞にエントリーしています。
応援いただけるとうれしいです!
※性描写が多めの作品になっていますのでご注意ください。
└性描写が含まれる話のサブタイトルには※をつけています。
※表紙は「かんたん表紙メーカー」さまで作成しました。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















