16 / 20
16
しおりを挟む
いつも優一が座っている一人掛けのソファで、優一を生んだという美しい人――雪弥が緑茶を飲んでいる。お茶だ茶菓子だと動いていた優一も、拓巳の隣に座り淹れたてのコーヒーを飲んでいた。そんななか、拓巳はどうにも落ち着かず緑茶の入ったコップを持ったままチラチラと二人の様子を窺う。
「それで、どうしてこちらに?」
「この間、たまたまホテルの近くで優一さんを見かけたんです。そうしたら隣に可愛らしい子を連れているじゃないですか。ようやくつがいができたのかと思ったら、いてもたってもいられなくなりましてね」
「先日、顔を見せに行くとあの人に連絡しておいたはずですが」
「おや、聞いていませんよ。……また隠し事でしょうか」
「わたしが絡んでいるからでしょうね」
「まったくあの人は、いくつになっても大人げないことを」
よくわからないが、二人が言う「あの人」というのは、もしかしなくても優一の父親のことだろうか。
それにしても……と拓巳は二人を見た。親子にしてはよそよそしい感じがする。しかし親しくないという雰囲気ではないし、かといって母と息子……には見えない。
(そりゃまぁ男同士だし、年齢も……優一さんのほうが年上に見えるから、かな)
優一よりも雪弥のほうが若く見える。そのせいであべこべに感じてしまうのだろう。そんなことを考えながら二人を見ていた拓巳に、雪弥がにこりと微笑みかけた。
「っ」
美しい人に微笑みかけられただけでも心臓に悪いのに、優一を生んだ人だと思うとどう反応していいのかわからなくなる。かといって無視するわけにはいかないし……と、小さくお辞儀をした拓巳は、気分を落ち着かせようとほんの少し緑茶を口にした。
「それにしても、まさかこんな可愛い子をつがいにするなんて」
「……っ、こほ、ごほっ」
「拓巳くん、大丈夫かい?」
「こほっ。あの、大丈夫、です」
聞き慣れない単語に思わずむせてしまった。先ほども「可愛い子」と言っていた気がするが、これまで拓巳が「可愛い」と言われたことは一度もない。優しく背中を撫でてくれる優一には悪いが、自分が美しいと他人を見る感覚がおかしいのではないかと思ってしまう。
「たしかに拓巳くんは可愛い」
目尻の涙を拭っていると、今度は優一がそんなことを言い始めた。
「ふふっ、優一さんも言いますね」
「本心ですよ」
「わかっています。優一さんのつがいはとても可愛い」
もしかしてからかっているのだろうかと雪弥を見るが、微笑んでいるもののそんなふうには見えない。
「これからあなたはΩとしても変わってもいくでしょう。優一さんに愛され、Ωとして花開いていくことになります」
「あ、い……」
うれしい言葉ではあるが、さすがに親である人に言われるのは恥ずかしかった。
「同時に、人としてのすべてを失っていくことにもなります」
美しい黒い目がつるりと光ったような気がした。見慣れた人の目というよりも、ガラス玉のような無機質な輝きに見える。それはたまに見る優一の目にそっくりで、ゾクリとした寒気が拓巳の背筋を震わせた。
「いえ、必ずしもそうなるとは限りませんか。人でないもののつがいになっても人であり続ける場合もあるでしょうしね。残念ながら、僕はそうはなりませんでしたけれど」
「雪弥さん」
「あぁ、嘆いているのではありませんよ? むしろ人であったときのほうが、よほど人らしくありませんでしたからね。僕はあの人と出会い、優一さんを授かったことで生き返ったのですから」
「……雪弥さん」
二度目の優一の声に、雪弥が静かに微笑み口を閉じた。
(よくわからないけど、なんていうか……)
すごく重たい話だったのかもしれない。二人は静かにお茶やコーヒーを飲んでいるが、拓巳は持ったままのコップに口をつけることができなかった。そうした息苦しさを拓巳が感じ始めていたとき、備え付けのデバイスから来客を知らせる音がした。
「おや、早かったですね」
「雪弥さん、本当に断っていなかったんですか」
「たまにはいいんですよ」
「……はぁ」
大きなため息をついた優一が額に手を当てながら玄関へと向かった。初めて見る優一の様子に、拓巳はわずかな不安を感じつつ背中を見送る。
「拓巳さん」
「は、はい」
声をかけられ、慌てて雪弥を見た。思わず背筋がピンと伸びてしまったのは、相手が優一の親だからだろうか。
「優一さんのつがいになってくれて、ありがとうございます」
「いえ……、あの、」
頭を下げられたが、どう返せばいいのかわからない。それにお礼を言うべきは自分のほうだ。そう思いながら視線をさまよわせる拓巳に雪弥が優しい笑みを向ける。
「優一さんには随分と寂しい思いをさせてきました。αとΩの間に生まれた子としては当然なのかもしれませんが、人であった僕はずっと歯がゆく思っていたのです。どうかその分、拓巳さんが優一さんを愛してあげてください」
拓巳は返事をすることができなかった。もちろん優一のことは好きで、つがいとしてこの先もずっと一緒にいるのだと決めている。それは「愛する」ということになるのだろうが、雪弥の言葉はとても重く聞こえ簡単に頷くことはできなかった。戸惑い固まる拓巳に、雪弥がにこりと微笑みかける。
「まぁ、嫌だと言っても優一さんが離さないでしょうけれど。αのΩに対する執着は病的ですからね。それが運命ともなれば、地の果てまでも追いかけて来るでしょうし」
「運命……って」
「拓巳さんと優一さんは運命なのでしょう? 優一さんは小さい頃から運命を探していましたから。まさか本当に出会えるとは思いませんでしたけど……いえ、優一さんが何十年もかけて探していたのですから、出会うべくして出会ったのでしょう」
そうなのだろうか。いまだにつがいも運命もよくわからない拓巳には実感がないが、「それだけ確率の低い出会いを果たした」と言っていた優一の言葉を思い出すと相当な奇跡なのかもしれない。
「運命であればなおのこと、絶対に手放さないでしょう。強いαというのは、それだけ強い執着を見せるものです。もちろん、そうやって求められるΩのほうも悦びを感じる。拓巳さんもそうでしょう?」
「……あの、……はい」
優一に求められるたびに心も体も歓喜に震えた。自分が必要とされているのだと感じ、たまらない幸福感に包まれる。
「ふふ、よかった。わずかですが、とてもよい香りを感じます。それだけαに愛され、またαを愛しているということなのでしょうから」
「……俺、匂ってますか?」
「つがいになってもΩ同士はわずかに関知し合えますからね。とくに発情前後はなんとなくわかりますよ」
「そうなんですね……」
そういえば、発情後に会ったメイにも「これは最近発情した感じだ」と言われたことを思い出した。
「まぁ、普通はつがいを持つ発情前のΩに会うことはないでしょうけれど」
「そうなんですか?」
「αが外に出すはずがありませんから」
「それがわかっていて外に出たということかね?」
聞こえてきた知らない声に拓巳が振り返ると、眩しいくらいの金髪をした背の高い男が立っていた。
「早かったですね」
「わたしの嗅覚を侮っているのか?」
「まさか」
「それともわたしを試しているのか?」
「あなたが優一さんのことを隠すからですよ」
(まさか、この人が優一さんのお父さん……?)
会話の流れから拓巳はそう判断した。よく見れば整った顔立ちは優一に似ている部分がある。五十代の優一はこんなふうだろうか、そう思わせる雰囲気もあった。ただ、金髪と灰色の目というのがあまりにも外国人っぽくて、優一の父親だと言われてもピンとこない。
「たとえ相手が息子であっても、αを近づけさせたくないと思うのがαだと言っただろう」
「まったく、いつまでも子どものようなことをおっしゃって」
ハァとため息をつく雪弥はあまりに美しく、こういうΩなら閉じ込めておきたくなるのもわかるような気がすると拓巳は思った。
「帰るぞ」
「その前に、息子のつがいにご挨拶してください」
驚いて雪弥を見ると、その目は間違いなく拓巳を見ている。そっと振り返ると金髪の人物も拓巳を見ていた。
「失礼した。わたしはランスロード・ドラクロワ、そこに座る雪弥のつがいだ」
「そして優一さんのお父上でもあります」
「あの、は、初めまして。西野拓巳です」
慌てて立ち上がって頭を下げたものの、こんな挨拶でよかったのだろうか。拓巳は頭を上げ、窺うように金髪の人物を見た。不機嫌そうな表情ではないものの拓巳の言葉に返事や反応はない。何度も視線が上下に動いているということは、息子のつがいとして問題ないか検分しているのだろう。
「ランス、その態度は失礼ですよ」
「あぁいや、気分を害したのなら謝ろう。少し珍しいΩだと思っただけだ」
自分のどこが珍しいかわからない拓巳は、ただ視線を受け止めることしかできなかった。
「どことなく出会った頃の雪弥に似ているな。この国のΩは、皆こういう感じなのか?」
「……?」
ランスロードの眉がわずかに寄ったところで「わたしのΩをジロジロ見ないでください」と優一の声が聞こえた。
「車を手配したので、すぐに到着しますよ。あぁ、Ωに耐性のある運転手ですからご心配なく」
「もしかして香りがしますか?」
「息子でもわたしはαですから関知はできません。ただ、この人の様子からそう感じただけです」
「だから、わたしを試しているのかと問うただろう」
「おやまぁ、それは大変だこと」
大変だと言いながらにこりと笑った雪弥は、ぬるくなったであろう緑茶を飲み干してから立ち上がった。そうして「また会いましょうね」と拓巳に微笑みかけ、「拓巳さんを大事にするのですよ」と優一に声をかける。続けて「帰りましょう」とランスロードの腕を取りリビングを出て行った。拓巳は挨拶をするタイミングを失ったまま二人の背中を見送った。
「それで、どうしてこちらに?」
「この間、たまたまホテルの近くで優一さんを見かけたんです。そうしたら隣に可愛らしい子を連れているじゃないですか。ようやくつがいができたのかと思ったら、いてもたってもいられなくなりましてね」
「先日、顔を見せに行くとあの人に連絡しておいたはずですが」
「おや、聞いていませんよ。……また隠し事でしょうか」
「わたしが絡んでいるからでしょうね」
「まったくあの人は、いくつになっても大人げないことを」
よくわからないが、二人が言う「あの人」というのは、もしかしなくても優一の父親のことだろうか。
それにしても……と拓巳は二人を見た。親子にしてはよそよそしい感じがする。しかし親しくないという雰囲気ではないし、かといって母と息子……には見えない。
(そりゃまぁ男同士だし、年齢も……優一さんのほうが年上に見えるから、かな)
優一よりも雪弥のほうが若く見える。そのせいであべこべに感じてしまうのだろう。そんなことを考えながら二人を見ていた拓巳に、雪弥がにこりと微笑みかけた。
「っ」
美しい人に微笑みかけられただけでも心臓に悪いのに、優一を生んだ人だと思うとどう反応していいのかわからなくなる。かといって無視するわけにはいかないし……と、小さくお辞儀をした拓巳は、気分を落ち着かせようとほんの少し緑茶を口にした。
「それにしても、まさかこんな可愛い子をつがいにするなんて」
「……っ、こほ、ごほっ」
「拓巳くん、大丈夫かい?」
「こほっ。あの、大丈夫、です」
聞き慣れない単語に思わずむせてしまった。先ほども「可愛い子」と言っていた気がするが、これまで拓巳が「可愛い」と言われたことは一度もない。優しく背中を撫でてくれる優一には悪いが、自分が美しいと他人を見る感覚がおかしいのではないかと思ってしまう。
「たしかに拓巳くんは可愛い」
目尻の涙を拭っていると、今度は優一がそんなことを言い始めた。
「ふふっ、優一さんも言いますね」
「本心ですよ」
「わかっています。優一さんのつがいはとても可愛い」
もしかしてからかっているのだろうかと雪弥を見るが、微笑んでいるもののそんなふうには見えない。
「これからあなたはΩとしても変わってもいくでしょう。優一さんに愛され、Ωとして花開いていくことになります」
「あ、い……」
うれしい言葉ではあるが、さすがに親である人に言われるのは恥ずかしかった。
「同時に、人としてのすべてを失っていくことにもなります」
美しい黒い目がつるりと光ったような気がした。見慣れた人の目というよりも、ガラス玉のような無機質な輝きに見える。それはたまに見る優一の目にそっくりで、ゾクリとした寒気が拓巳の背筋を震わせた。
「いえ、必ずしもそうなるとは限りませんか。人でないもののつがいになっても人であり続ける場合もあるでしょうしね。残念ながら、僕はそうはなりませんでしたけれど」
「雪弥さん」
「あぁ、嘆いているのではありませんよ? むしろ人であったときのほうが、よほど人らしくありませんでしたからね。僕はあの人と出会い、優一さんを授かったことで生き返ったのですから」
「……雪弥さん」
二度目の優一の声に、雪弥が静かに微笑み口を閉じた。
(よくわからないけど、なんていうか……)
すごく重たい話だったのかもしれない。二人は静かにお茶やコーヒーを飲んでいるが、拓巳は持ったままのコップに口をつけることができなかった。そうした息苦しさを拓巳が感じ始めていたとき、備え付けのデバイスから来客を知らせる音がした。
「おや、早かったですね」
「雪弥さん、本当に断っていなかったんですか」
「たまにはいいんですよ」
「……はぁ」
大きなため息をついた優一が額に手を当てながら玄関へと向かった。初めて見る優一の様子に、拓巳はわずかな不安を感じつつ背中を見送る。
「拓巳さん」
「は、はい」
声をかけられ、慌てて雪弥を見た。思わず背筋がピンと伸びてしまったのは、相手が優一の親だからだろうか。
「優一さんのつがいになってくれて、ありがとうございます」
「いえ……、あの、」
頭を下げられたが、どう返せばいいのかわからない。それにお礼を言うべきは自分のほうだ。そう思いながら視線をさまよわせる拓巳に雪弥が優しい笑みを向ける。
「優一さんには随分と寂しい思いをさせてきました。αとΩの間に生まれた子としては当然なのかもしれませんが、人であった僕はずっと歯がゆく思っていたのです。どうかその分、拓巳さんが優一さんを愛してあげてください」
拓巳は返事をすることができなかった。もちろん優一のことは好きで、つがいとしてこの先もずっと一緒にいるのだと決めている。それは「愛する」ということになるのだろうが、雪弥の言葉はとても重く聞こえ簡単に頷くことはできなかった。戸惑い固まる拓巳に、雪弥がにこりと微笑みかける。
「まぁ、嫌だと言っても優一さんが離さないでしょうけれど。αのΩに対する執着は病的ですからね。それが運命ともなれば、地の果てまでも追いかけて来るでしょうし」
「運命……って」
「拓巳さんと優一さんは運命なのでしょう? 優一さんは小さい頃から運命を探していましたから。まさか本当に出会えるとは思いませんでしたけど……いえ、優一さんが何十年もかけて探していたのですから、出会うべくして出会ったのでしょう」
そうなのだろうか。いまだにつがいも運命もよくわからない拓巳には実感がないが、「それだけ確率の低い出会いを果たした」と言っていた優一の言葉を思い出すと相当な奇跡なのかもしれない。
「運命であればなおのこと、絶対に手放さないでしょう。強いαというのは、それだけ強い執着を見せるものです。もちろん、そうやって求められるΩのほうも悦びを感じる。拓巳さんもそうでしょう?」
「……あの、……はい」
優一に求められるたびに心も体も歓喜に震えた。自分が必要とされているのだと感じ、たまらない幸福感に包まれる。
「ふふ、よかった。わずかですが、とてもよい香りを感じます。それだけαに愛され、またαを愛しているということなのでしょうから」
「……俺、匂ってますか?」
「つがいになってもΩ同士はわずかに関知し合えますからね。とくに発情前後はなんとなくわかりますよ」
「そうなんですね……」
そういえば、発情後に会ったメイにも「これは最近発情した感じだ」と言われたことを思い出した。
「まぁ、普通はつがいを持つ発情前のΩに会うことはないでしょうけれど」
「そうなんですか?」
「αが外に出すはずがありませんから」
「それがわかっていて外に出たということかね?」
聞こえてきた知らない声に拓巳が振り返ると、眩しいくらいの金髪をした背の高い男が立っていた。
「早かったですね」
「わたしの嗅覚を侮っているのか?」
「まさか」
「それともわたしを試しているのか?」
「あなたが優一さんのことを隠すからですよ」
(まさか、この人が優一さんのお父さん……?)
会話の流れから拓巳はそう判断した。よく見れば整った顔立ちは優一に似ている部分がある。五十代の優一はこんなふうだろうか、そう思わせる雰囲気もあった。ただ、金髪と灰色の目というのがあまりにも外国人っぽくて、優一の父親だと言われてもピンとこない。
「たとえ相手が息子であっても、αを近づけさせたくないと思うのがαだと言っただろう」
「まったく、いつまでも子どものようなことをおっしゃって」
ハァとため息をつく雪弥はあまりに美しく、こういうΩなら閉じ込めておきたくなるのもわかるような気がすると拓巳は思った。
「帰るぞ」
「その前に、息子のつがいにご挨拶してください」
驚いて雪弥を見ると、その目は間違いなく拓巳を見ている。そっと振り返ると金髪の人物も拓巳を見ていた。
「失礼した。わたしはランスロード・ドラクロワ、そこに座る雪弥のつがいだ」
「そして優一さんのお父上でもあります」
「あの、は、初めまして。西野拓巳です」
慌てて立ち上がって頭を下げたものの、こんな挨拶でよかったのだろうか。拓巳は頭を上げ、窺うように金髪の人物を見た。不機嫌そうな表情ではないものの拓巳の言葉に返事や反応はない。何度も視線が上下に動いているということは、息子のつがいとして問題ないか検分しているのだろう。
「ランス、その態度は失礼ですよ」
「あぁいや、気分を害したのなら謝ろう。少し珍しいΩだと思っただけだ」
自分のどこが珍しいかわからない拓巳は、ただ視線を受け止めることしかできなかった。
「どことなく出会った頃の雪弥に似ているな。この国のΩは、皆こういう感じなのか?」
「……?」
ランスロードの眉がわずかに寄ったところで「わたしのΩをジロジロ見ないでください」と優一の声が聞こえた。
「車を手配したので、すぐに到着しますよ。あぁ、Ωに耐性のある運転手ですからご心配なく」
「もしかして香りがしますか?」
「息子でもわたしはαですから関知はできません。ただ、この人の様子からそう感じただけです」
「だから、わたしを試しているのかと問うただろう」
「おやまぁ、それは大変だこと」
大変だと言いながらにこりと笑った雪弥は、ぬるくなったであろう緑茶を飲み干してから立ち上がった。そうして「また会いましょうね」と拓巳に微笑みかけ、「拓巳さんを大事にするのですよ」と優一に声をかける。続けて「帰りましょう」とランスロードの腕を取りリビングを出て行った。拓巳は挨拶をするタイミングを失ったまま二人の背中を見送った。
82
あなたにおすすめの小説

不憫王子に転生したら、獣人王太子の番になりました
織緒こん
BL
日本の大学生だった前世の記憶を持つクラフトクリフは異世界の王子に転生したものの、母親の身分が低く、同母の姉と共に継母である王妃に虐げられていた。そんなある日、父王が獣人族の国へ戦争を仕掛け、あっという間に負けてしまう。戦勝国の代表として乗り込んできたのは、なんと獅子獣人の王太子のリカルデロ! 彼は臣下にクラフトクリフを戦利品として側妃にしたらどうかとすすめられるが、王子があまりに痩せて見すぼらしいせいか、きっぱり「いらない」と断る。それでもクラフトクリフの処遇を決めかねた臣下たちは、彼をリカルデロの後宮に入れた。そこで、しばらく世話をされたクラフトクリフはやがて健康を取り戻し、再び、リカルデロと会う。すると、何故か、リカルデロは突然、クラフトクリフを溺愛し始めた。リカルデロの態度に心当たりのないクラフトクリフは情熱的な彼に戸惑うばかりで――!?
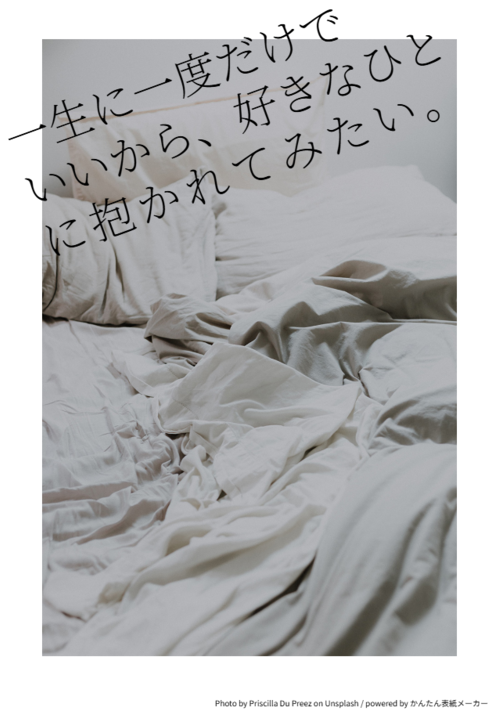
【完結】一生に一度だけでいいから、好きなひとに抱かれてみたい。
村松砂音(抹茶砂糖)
BL
第13回BL大賞で奨励賞をいただきました!
ありがとうございました!!
いつも不機嫌そうな美形の騎士×特異体質の不憫な騎士見習い
<あらすじ>
魔力欠乏体質者との性行為は、死ぬほど気持ちがいい。そんな噂が流れている「魔力欠乏体質」であるリュカは、父の命令で第二王子を誘惑するために見習い騎士として騎士団に入る。
見習い騎士には、側仕えとして先輩騎士と宿舎で同室となり、身の回りの世話をするという規則があり、リュカは隊長を務めるアレックスの側仕えとなった。
いつも不機嫌そうな態度とちぐはぐなアレックスのやさしさに触れていくにつれて、アレックスに惹かれていくリュカ。
ある日、リュカの前に第二王子のウィルフリッドが現れ、衝撃の事実を告げてきて……。
親のいいなりで生きてきた不憫な青年が、恋をして、しあわせをもらう物語。
※性描写が多めの作品になっていますのでご注意ください。
└性描写が含まれる話のサブタイトルには※をつけています。
※表紙は「かんたん表紙メーカー」さまで作成しました。

オメガ大学生、溺愛アルファ社長に囲い込まれました
こたま
BL
あっ!脇道から出てきたハイヤーが僕の自転車の前輪にぶつかり、転倒してしまった。ハイヤーの後部座席に乗っていたのは若いアルファの社長である東条秀之だった。大学生の木村千尋は病院の特別室に入院し怪我の治療を受けた。退院の時期になったらなぜか自宅ではなく社長宅でお世話になることに。溺愛アルファ×可愛いオメガのハッピーエンドBLです。読んで頂きありがとうございます。今後随時追加更新するかもしれません。

のほほんオメガは、同期アルファの執着に気付いていませんでした
こたま
BL
オメガの品川拓海(しながわ たくみ)は、現在祖母宅で祖母と飼い猫とのほほんと暮らしている社会人のオメガだ。雇用機会均等法以来門戸の開かれたオメガ枠で某企業に就職している。同期のアルファで営業の高輪響矢(たかなわ きょうや)とは彼の営業サポートとして共に働いている。同期社会人同士のオメガバース、ハッピーエンドです。両片想い、後両想い。攻の愛が重めです。

【完結】愛されたかった僕の人生
Kanade
BL
✯オメガバース
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
お見合いから一年半の交際を経て、結婚(番婚)をして3年。
今日も《夫》は帰らない。
《夫》には僕以外の『番』がいる。
ねぇ、どうしてなの?
一目惚れだって言ったじゃない。
愛してるって言ってくれたじゃないか。
ねぇ、僕はもう要らないの…?
独りで過ごす『発情期』は辛いよ…。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
✻改稿版を他サイトにて投稿公開中です。

【完結済】極上アルファを嵌めた俺の話
降魔 鬼灯
BL
ピアニスト志望の悠理は子供の頃、仲の良かったアルファの東郷司にコンクールで敗北した。
両親を早くに亡くしその借金の返済が迫っている悠理にとって未成年最後のこのコンクールの賞金を得る事がラストチャンスだった。
しかし、司に敗北した悠理ははオメガ専用の娼館にいくより他なくなってしまう。
コンサート入賞者を招いたパーティーで司に想い人がいることを知った悠理は地味な自分がオメガだとバレていない事を利用して司を嵌めて慰謝料を奪おうと計画するが……。

希少なΩだと隠して生きてきた薬師は、視察に来た冷徹なα騎士団長に一瞬で見抜かれ「お前は俺の番だ」と帝都に連れ去られてしまう
水凪しおん
BL
「君は、今日から俺のものだ」
辺境の村で薬師として静かに暮らす青年カイリ。彼には誰にも言えない秘密があった。それは希少なΩ(オメガ)でありながら、その性を偽りβ(ベータ)として生きていること。
ある日、村を訪れたのは『帝国の氷盾』と畏れられる冷徹な騎士団総長、リアム。彼は最上級のα(アルファ)であり、カイリが必死に隠してきたΩの資質をいとも簡単に見抜いてしまう。
「お前のその特異な力を、帝国のために使え」
強引に帝都へ連れ去られ、リアムの屋敷で“偽りの主従関係”を結ぶことになったカイリ。冷たい命令とは裏腹に、リアムが時折見せる不器用な優しさと孤独を秘めた瞳に、カイリの心は次第に揺らいでいく。
しかし、カイリの持つ特別なフェロモンは帝国の覇権を揺るがす甘美な毒。やがて二人は、宮廷を渦巻く巨大な陰謀に巻き込まれていく――。
運命の番(つがい)に抗う不遇のΩと、愛を知らない最強α騎士。
偽りの関係から始まる、甘く切ない身分差ファンタジー・ラブ!

【WEB版】監視が厳しすぎた嫁入り生活から解放されました~冷徹無慈悲と呼ばれた隻眼の伯爵様と呪いの首輪~【BL・オメガバース】
古森きり
BL
【書籍化決定しました!】
詳細が決まりましたら改めてお知らせにあがります!
たくさんの閲覧、お気に入り、しおり、感想ありがとうございました!
アルファポリス様の規約に従い発売日にURL登録に変更、こちらは引き下げ削除させていただきます。
政略結婚で嫁いだ先は、女狂いの伯爵家。
男のΩである僕には一切興味を示さず、しかし不貞をさせまいと常に監視される生活。
自分ではどうすることもできない生活に疲れ果てて諦めた時、夫の不正が暴かれて失脚した。
行く当てがなくなった僕を保護してくれたのは、元夫が口を開けば罵っていた政敵ヘルムート・カウフマン。
冷徹無慈悲と呼び声高い彼だが、共に食事を摂ってくれたりやりたいことを応援してくれたり、決して冷たいだけの人ではなさそうで――。
カクヨムに書き溜め。
小説家になろう、アルファポリス、BLoveにそのうち掲載します。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















