25 / 26
25 知りたいと思うこと
しおりを挟む
宿泊先に到着したその日の夜、ヴァイルが「一緒に湯を使うか?」と口にした。
「え……?」
湯で体を清めようと布や着替えを用意していたシュエシは、それらを手に持ったまま目を見開く。
(どういう意味だろう……)
いや、意味はわかる。ただ二人でと言われたことがわからなかった。
(まさか体を拭い合うとか……?)
シュエシにとって湯を使うというのは、布を湯に浸し、それで全身を拭うということだ。両親と旅をしていた幼い頃からそれが自分たちの湯浴み方法で、両親を亡くしてからもそれは変わらない。さすがに冬は湯を沸かしていたが、髪の毛を洗うほどの湯を沸かすのは大変だったため昼間に水ですすぐことが多かった。
意味がわからずぽかんとしていると「何をしている?」と声をかけられた。戸惑いながらも「行くぞ」と手を引かれたら断ることはできず、一緒に浴室に入る。「どうしよう」と困惑したまま立ち尽くすシュエシの前でヴァイルが服を脱ぎ始めた。
シュエシは慌てて視線を逸らした。すると視界に優美な形をした湯船が入る。たっぷりの湯が入っているのか湯気が立ち、周囲をほんのり白くしていた。
(ど、どうしたらいいんだろう)
目の端に惜しげもなく裸体をさらすヴァイルの姿が映っている。意識がはっきりしているときに全身裸の姿を見るのは初めてで、慌てて奥の湯船を見た。見てはいけないと思うものの、気になって結局チラチラと視線を向けてしまう。
「なんだ、恥ずかしいのか? 体など何度も見ているだろう」
「そう、ですけど」
「さっさと脱げ、湯が冷めてしまうぞ」
裸のヴァイルが近づいて来る。慌てて視線を逸らしながら胸元のリボンに手をかけた。ところが緊張からか指が震えてうまく解くことができない。
(目の前でドレスを脱ぐなんて……まるで本当の女性になってしまったみたいだ)
旅を始めてからもヴァイルが用意するのはドレスばかりだ。いつの間にかドレスを着るのを当たり前に思っていたが、さすがに目の前で脱ぐのは恥ずかしい。せめて男の服なら気にならないのかもしれないが、服も下着も男物を与えられることはなかった。
もたつくシュエシの背後にヴァイルが近づいた。そっと身を屈め、耳元に顔を寄せる。
「湯浴みのお手伝いをいたしましょうか、奥様?」
突然聞こえてきた艶やかな声に慌てて振り返った。まるで執事だったときのような笑みに、当時のことが蘇る。密かに想いを寄せて悶々としていたことまで思い出してしまい顔が真っ赤になった。
俯きながらもじもじと手を動かす様子に、ヴァイルが小さくため息をついた。
「まさか、いまだに執事のほうがよいなどと思っているわけではないだろうな?」
「そ、そんなことありません」
「その割にはうれしそうに見えるが?」
「ちっ、違います」
「まぁ、いいだろう。それよりさっさと服を脱げ」
「あっ、あのっ」
脱げと言いながら、あっという間にドレスも下着も奪われてしまった。全身真っ赤になったシュエシを軽々と抱き上げたヴァイルは、そのまま湯船に入り膝に座らせるようにしながら体を沈める。
湯船の湯に尻が触れた瞬間、シュエシは「ひぇっ!」と悲鳴を上げた。慌てて身をよじり、湯船の外に飛び出す。
「おい、何をしている」
「だ、だって」
「さっさと中に入れ」
「で、でも」
湯船に沈められるとは思わなかったシュエシは、青ざめた顔で湯船を見た。その様子に「まさか」とつぶやいたヴァイルが眉をひそめる。
「湯に浸かるのは初めてか?」
「は、はい」
返事をするシュエシの目にはうっすらと涙が浮かんでいた。まるで水を怖がる幼子のような反応に端正なヴァイルの顔が険しくなる。
「これまで湯浴みはどうしていた?」
「て、手桶に湯を入れて、布を浸してから体を拭っていました」
「髪は洗っていただろう? なぜ体もそうしなかった?」
「ゆ、湯は大切に使うものですから」
ヴァイルの口から小さなため息がこぼれ落ちる。怒ったのかと思い体を震わせると、「いいから来い」と言われてシュエシが眉尻を下げた。
「湯浴みの仕方を教えてやる」
「で、でも」
「わたしはこうして湯に浸かるのを好む」
「ぼ、僕はいままでどおりで大丈夫です」
「おまえもきっと好きになる」
「そ、そうかもしれませんけど」
「二人で湯に浸かりたいとは思わないのか?」
「え?」
「こういうのは家族になったように感じられていいと思ったんだが」
家族という言葉にシュエシの目がゆらりと揺れた。戸惑いながらもチラチラと湯船を見る。その様子に小さく笑ったヴァイルは、湯船から一旦出るとシュエシを抱きかかえて再び湯に体を沈めた。
「っ」
初めて感じる感覚にシュエシは息を呑んだ。咄嗟にヴァイルの腕を掴み、恐怖に耐えるかのようにぎゅうっと目を閉じる。川で水浴びをしたことはあったが、それとはまったく違い肌がピリピリするのが恐ろしい。段々と顔まで熱くなり、少しだけ息苦しくなる。
「これからは何もかもわたしが教えてやろう」
優しいヴァイルの声に、そっと瞼を開いた。窺うように仰ぎ見ると、黄金色の瞳がじっと自分を見つめていることに気がついて慌てて俯く。
「おまえは化け物としてだけでなく人としても幼子のようなものだとわかった。これからはわたしが手取り足取り教えてやろう」
「だ、大丈夫です。一人で、できます」
「遠慮するな」
濡れた手に髪の毛を掻き上げられ肩がふるっと震えた。顕わになった耳に触れるだけの口づけを落としたヴァイルが「花嫁の世話をしたいだけだ」と囁き、シュエシの耳もうなじも真っ赤になる。
「さて、洗うか」
「え?」
ヴァイルが湯船のそばに置いてあった石鹸を手にした。何をするのだろうと目で追っていると、なぜか湯船にそれを入れて泡立て始める。見る間に湯が泡だらけになるのを驚いて見ていると、湯から石鹸を取り出したヴァイルの手が今度はシュエシの腕を撫で始めた。
「ひっ」
「おとなしくしろ」
「で、でも」
「洗うだけだ」
「あ、あの」
「ほら、次は胸だ」
「っ」
ぬるりとした手に胸を撫でられビクッと震えた。息を詰めていると、今度は太ももや膝を擦られて「んっ」と声が漏れる。もう何度も撫でられたり摘まれたりしてきたというのに、ぬめりがあるからか何ともいえない感覚がした。はじめはくすぐったいような感じだったが、そこに段々と違うものが混じり始める。ぬるっとした指に擦られるだけで背中がゾクッとし肌が粟立った。
「相変わらず敏感だな」
「んぅっ」
「洗っているだけだぞ?」
「わ、かって、ん!」
ヴァイルの手が胸を掠めて高い声が上がった。勝手に淫らな熱を持ってしまう自分が恥ずかしい。それでも感じてしまうからか、それとも熱い湯に浸かっているからか、段々と頭がぼんやりしてきた。
「んふっ」
シュエシの口から漏れたのは明かな嬌声だった。慌てて唇を噛み締めグッと我慢するものの、どうしても吐息が漏れてしまう。体を洗ってもらっているのにいやらしく感じてしまっていることをヴァイルに知られるわけにはいかない。
(我慢、しないと)
何度もそう思ったが、すぐに限界を迎えた。このままでは大変なことになる。シュエシは動き回るヴァイルの手を止めようと両手で手首を掴んだ。
「ヴァ、ヴァイルさまっ」
「おとなしくしていろ」
そう囁かれ掴む力が弱くなる。
「いい子だ」
褒めるように耳元で囁いたヴァイルが、撫でていた手を胸から腹へと動かした。
「んぅっ」
鼻から抜けるような声が漏れた。慌てて唇を噛み締めるが、今度は下生えを撫でられ全身が震えてしまう。そのまま足の付け根や際どい部分を何度も撫でられ、シュエシは茹だったように耳や首を真っ赤にした。
「おまえは本当に敏感だな」
「あっ!」
いつの間にか緩く勃ち上がっていた性器を撫でられ顎が上がった。
「ここもすぐにこうなる」
「ヴァイルさま、だめ、です、っ」
「洗っているだけだ、これ以上のことはしない」
「でもっ」
「それとも、これ以上のことをしてほしいのか?」
囁く低い声に目の前でパチパチと星が瞬いた。薄く開いた黒目は快感の涙に濡れ、血色がよくなった唇から赤い舌先がチロチロと見え隠れする。
「果ててもいいぞ」
そう告げられた瞬間、シュエシの体がビクンと震えた。湯の表面を揺らすように二度、三度と腰が跳ねる。
「おまえは愛いな」
何かを囁いているのはわかるが耳から言葉がすべり落ちてうまく聞き取れない。ヴァイルの腕の中でくたりとしながら「ハァ、ハァ」と何度も荒い息を吐く。そうして落ち着くのを待っていたのかヴァイルがつぶやいた。
「おまえがどのように生きてきたか聞かせてほしい」
「……え……?」
よく聞き取れずに背後をそっと仰ぎ見た。優しい表情にドキッとし、慌てて視線を前に戻す。目の前では大きなヴァイルの手が自分の手を撫でるように洗っている。
「これまでのおまえのことが知りたい」
そう言いながらヴァイルの手が指の股を優しく擦った。まるで指を絡めるような仕草に鼓動がますます速くなる。
「幼い頃旅をしていたときのこと、失った両親のこと、あの土地でどのように生きていたのか、そうしたことを知りたい」
「でも……あまり楽しい話では、ないと思います」
「かまわん。おまえのことが知りたいだけだ」
ヴァイルの指が骨張った自分の指をするりと撫でた。それだけで官能的なものを感じてしまい、肌が粟立つ。同時に両親と手を繋いだ幼い頃の記憶が蘇ったからか、湯の熱とは違うポカポカとしたものを感じた。
「小さいときのことは……あまり覚えていません」
「覚えていることでいい」
「……たぶん、僕がまだ三歳か四歳くらいのときですけど……大きな川があって……」
ポツポツと記憶にあることを言葉にする。それをヴァイルは静かに聞いた。
この日、シュエシはあの土地にたどり着くまでのことをヴァイルに話して聞かせた。おぼろげな記憶をたどる言葉はわかりにくいはずだというのに、ヴァイルは静かに耳を傾け続ける。それは湯から上がった後も続き、ベッドに横になってからもシュエシは言葉を紡ぎ続けた。
「ヴァイルさま……僕の話、おもしろいですか……?」
珍しくたくさん話したからか急激に眠くなってきた。それでも気になってぼんやりした声で尋ねると、「興味深く聞いている」と返ってくる。
「そう、ですか……よかった……」
なんとか耐えていた瞼が少しずつ下りてくる。それでも起きていなくてはと何度か目を瞬かせたものの、結局眠気には逆らえず目を閉じた。
(ヴァイルさまが楽しんでくれたなら、よかった)
それがうれしくて、シュエシの頬が緩む。
「おまえはわたしの花嫁だ。この先はわたしが守ってやろう。だからもう悲しむことも苦しむこともしなくていい」
艶やかな声が聞こえた気がした。半分眠っていたせいか聞き取ることはできなかったものの、低く柔らかな声がすぐそばで聞こえるのがうれしい。シュエシはヴァイルの胸に頬を寄せながらふわりと微笑んだ。
「え……?」
湯で体を清めようと布や着替えを用意していたシュエシは、それらを手に持ったまま目を見開く。
(どういう意味だろう……)
いや、意味はわかる。ただ二人でと言われたことがわからなかった。
(まさか体を拭い合うとか……?)
シュエシにとって湯を使うというのは、布を湯に浸し、それで全身を拭うということだ。両親と旅をしていた幼い頃からそれが自分たちの湯浴み方法で、両親を亡くしてからもそれは変わらない。さすがに冬は湯を沸かしていたが、髪の毛を洗うほどの湯を沸かすのは大変だったため昼間に水ですすぐことが多かった。
意味がわからずぽかんとしていると「何をしている?」と声をかけられた。戸惑いながらも「行くぞ」と手を引かれたら断ることはできず、一緒に浴室に入る。「どうしよう」と困惑したまま立ち尽くすシュエシの前でヴァイルが服を脱ぎ始めた。
シュエシは慌てて視線を逸らした。すると視界に優美な形をした湯船が入る。たっぷりの湯が入っているのか湯気が立ち、周囲をほんのり白くしていた。
(ど、どうしたらいいんだろう)
目の端に惜しげもなく裸体をさらすヴァイルの姿が映っている。意識がはっきりしているときに全身裸の姿を見るのは初めてで、慌てて奥の湯船を見た。見てはいけないと思うものの、気になって結局チラチラと視線を向けてしまう。
「なんだ、恥ずかしいのか? 体など何度も見ているだろう」
「そう、ですけど」
「さっさと脱げ、湯が冷めてしまうぞ」
裸のヴァイルが近づいて来る。慌てて視線を逸らしながら胸元のリボンに手をかけた。ところが緊張からか指が震えてうまく解くことができない。
(目の前でドレスを脱ぐなんて……まるで本当の女性になってしまったみたいだ)
旅を始めてからもヴァイルが用意するのはドレスばかりだ。いつの間にかドレスを着るのを当たり前に思っていたが、さすがに目の前で脱ぐのは恥ずかしい。せめて男の服なら気にならないのかもしれないが、服も下着も男物を与えられることはなかった。
もたつくシュエシの背後にヴァイルが近づいた。そっと身を屈め、耳元に顔を寄せる。
「湯浴みのお手伝いをいたしましょうか、奥様?」
突然聞こえてきた艶やかな声に慌てて振り返った。まるで執事だったときのような笑みに、当時のことが蘇る。密かに想いを寄せて悶々としていたことまで思い出してしまい顔が真っ赤になった。
俯きながらもじもじと手を動かす様子に、ヴァイルが小さくため息をついた。
「まさか、いまだに執事のほうがよいなどと思っているわけではないだろうな?」
「そ、そんなことありません」
「その割にはうれしそうに見えるが?」
「ちっ、違います」
「まぁ、いいだろう。それよりさっさと服を脱げ」
「あっ、あのっ」
脱げと言いながら、あっという間にドレスも下着も奪われてしまった。全身真っ赤になったシュエシを軽々と抱き上げたヴァイルは、そのまま湯船に入り膝に座らせるようにしながら体を沈める。
湯船の湯に尻が触れた瞬間、シュエシは「ひぇっ!」と悲鳴を上げた。慌てて身をよじり、湯船の外に飛び出す。
「おい、何をしている」
「だ、だって」
「さっさと中に入れ」
「で、でも」
湯船に沈められるとは思わなかったシュエシは、青ざめた顔で湯船を見た。その様子に「まさか」とつぶやいたヴァイルが眉をひそめる。
「湯に浸かるのは初めてか?」
「は、はい」
返事をするシュエシの目にはうっすらと涙が浮かんでいた。まるで水を怖がる幼子のような反応に端正なヴァイルの顔が険しくなる。
「これまで湯浴みはどうしていた?」
「て、手桶に湯を入れて、布を浸してから体を拭っていました」
「髪は洗っていただろう? なぜ体もそうしなかった?」
「ゆ、湯は大切に使うものですから」
ヴァイルの口から小さなため息がこぼれ落ちる。怒ったのかと思い体を震わせると、「いいから来い」と言われてシュエシが眉尻を下げた。
「湯浴みの仕方を教えてやる」
「で、でも」
「わたしはこうして湯に浸かるのを好む」
「ぼ、僕はいままでどおりで大丈夫です」
「おまえもきっと好きになる」
「そ、そうかもしれませんけど」
「二人で湯に浸かりたいとは思わないのか?」
「え?」
「こういうのは家族になったように感じられていいと思ったんだが」
家族という言葉にシュエシの目がゆらりと揺れた。戸惑いながらもチラチラと湯船を見る。その様子に小さく笑ったヴァイルは、湯船から一旦出るとシュエシを抱きかかえて再び湯に体を沈めた。
「っ」
初めて感じる感覚にシュエシは息を呑んだ。咄嗟にヴァイルの腕を掴み、恐怖に耐えるかのようにぎゅうっと目を閉じる。川で水浴びをしたことはあったが、それとはまったく違い肌がピリピリするのが恐ろしい。段々と顔まで熱くなり、少しだけ息苦しくなる。
「これからは何もかもわたしが教えてやろう」
優しいヴァイルの声に、そっと瞼を開いた。窺うように仰ぎ見ると、黄金色の瞳がじっと自分を見つめていることに気がついて慌てて俯く。
「おまえは化け物としてだけでなく人としても幼子のようなものだとわかった。これからはわたしが手取り足取り教えてやろう」
「だ、大丈夫です。一人で、できます」
「遠慮するな」
濡れた手に髪の毛を掻き上げられ肩がふるっと震えた。顕わになった耳に触れるだけの口づけを落としたヴァイルが「花嫁の世話をしたいだけだ」と囁き、シュエシの耳もうなじも真っ赤になる。
「さて、洗うか」
「え?」
ヴァイルが湯船のそばに置いてあった石鹸を手にした。何をするのだろうと目で追っていると、なぜか湯船にそれを入れて泡立て始める。見る間に湯が泡だらけになるのを驚いて見ていると、湯から石鹸を取り出したヴァイルの手が今度はシュエシの腕を撫で始めた。
「ひっ」
「おとなしくしろ」
「で、でも」
「洗うだけだ」
「あ、あの」
「ほら、次は胸だ」
「っ」
ぬるりとした手に胸を撫でられビクッと震えた。息を詰めていると、今度は太ももや膝を擦られて「んっ」と声が漏れる。もう何度も撫でられたり摘まれたりしてきたというのに、ぬめりがあるからか何ともいえない感覚がした。はじめはくすぐったいような感じだったが、そこに段々と違うものが混じり始める。ぬるっとした指に擦られるだけで背中がゾクッとし肌が粟立った。
「相変わらず敏感だな」
「んぅっ」
「洗っているだけだぞ?」
「わ、かって、ん!」
ヴァイルの手が胸を掠めて高い声が上がった。勝手に淫らな熱を持ってしまう自分が恥ずかしい。それでも感じてしまうからか、それとも熱い湯に浸かっているからか、段々と頭がぼんやりしてきた。
「んふっ」
シュエシの口から漏れたのは明かな嬌声だった。慌てて唇を噛み締めグッと我慢するものの、どうしても吐息が漏れてしまう。体を洗ってもらっているのにいやらしく感じてしまっていることをヴァイルに知られるわけにはいかない。
(我慢、しないと)
何度もそう思ったが、すぐに限界を迎えた。このままでは大変なことになる。シュエシは動き回るヴァイルの手を止めようと両手で手首を掴んだ。
「ヴァ、ヴァイルさまっ」
「おとなしくしていろ」
そう囁かれ掴む力が弱くなる。
「いい子だ」
褒めるように耳元で囁いたヴァイルが、撫でていた手を胸から腹へと動かした。
「んぅっ」
鼻から抜けるような声が漏れた。慌てて唇を噛み締めるが、今度は下生えを撫でられ全身が震えてしまう。そのまま足の付け根や際どい部分を何度も撫でられ、シュエシは茹だったように耳や首を真っ赤にした。
「おまえは本当に敏感だな」
「あっ!」
いつの間にか緩く勃ち上がっていた性器を撫でられ顎が上がった。
「ここもすぐにこうなる」
「ヴァイルさま、だめ、です、っ」
「洗っているだけだ、これ以上のことはしない」
「でもっ」
「それとも、これ以上のことをしてほしいのか?」
囁く低い声に目の前でパチパチと星が瞬いた。薄く開いた黒目は快感の涙に濡れ、血色がよくなった唇から赤い舌先がチロチロと見え隠れする。
「果ててもいいぞ」
そう告げられた瞬間、シュエシの体がビクンと震えた。湯の表面を揺らすように二度、三度と腰が跳ねる。
「おまえは愛いな」
何かを囁いているのはわかるが耳から言葉がすべり落ちてうまく聞き取れない。ヴァイルの腕の中でくたりとしながら「ハァ、ハァ」と何度も荒い息を吐く。そうして落ち着くのを待っていたのかヴァイルがつぶやいた。
「おまえがどのように生きてきたか聞かせてほしい」
「……え……?」
よく聞き取れずに背後をそっと仰ぎ見た。優しい表情にドキッとし、慌てて視線を前に戻す。目の前では大きなヴァイルの手が自分の手を撫でるように洗っている。
「これまでのおまえのことが知りたい」
そう言いながらヴァイルの手が指の股を優しく擦った。まるで指を絡めるような仕草に鼓動がますます速くなる。
「幼い頃旅をしていたときのこと、失った両親のこと、あの土地でどのように生きていたのか、そうしたことを知りたい」
「でも……あまり楽しい話では、ないと思います」
「かまわん。おまえのことが知りたいだけだ」
ヴァイルの指が骨張った自分の指をするりと撫でた。それだけで官能的なものを感じてしまい、肌が粟立つ。同時に両親と手を繋いだ幼い頃の記憶が蘇ったからか、湯の熱とは違うポカポカとしたものを感じた。
「小さいときのことは……あまり覚えていません」
「覚えていることでいい」
「……たぶん、僕がまだ三歳か四歳くらいのときですけど……大きな川があって……」
ポツポツと記憶にあることを言葉にする。それをヴァイルは静かに聞いた。
この日、シュエシはあの土地にたどり着くまでのことをヴァイルに話して聞かせた。おぼろげな記憶をたどる言葉はわかりにくいはずだというのに、ヴァイルは静かに耳を傾け続ける。それは湯から上がった後も続き、ベッドに横になってからもシュエシは言葉を紡ぎ続けた。
「ヴァイルさま……僕の話、おもしろいですか……?」
珍しくたくさん話したからか急激に眠くなってきた。それでも気になってぼんやりした声で尋ねると、「興味深く聞いている」と返ってくる。
「そう、ですか……よかった……」
なんとか耐えていた瞼が少しずつ下りてくる。それでも起きていなくてはと何度か目を瞬かせたものの、結局眠気には逆らえず目を閉じた。
(ヴァイルさまが楽しんでくれたなら、よかった)
それがうれしくて、シュエシの頬が緩む。
「おまえはわたしの花嫁だ。この先はわたしが守ってやろう。だからもう悲しむことも苦しむこともしなくていい」
艶やかな声が聞こえた気がした。半分眠っていたせいか聞き取ることはできなかったものの、低く柔らかな声がすぐそばで聞こえるのがうれしい。シュエシはヴァイルの胸に頬を寄せながらふわりと微笑んだ。
88
あなたにおすすめの小説

【完結】薄幸文官志望は嘘をつく
七咲陸
BL
サシャ=ジルヴァールは伯爵家の長男として産まれるが、紫の瞳のせいで両親に疎まれ、弟からも蔑まれる日々を送っていた。
忌々しい紫眼と言う両親に幼い頃からサシャに魔道具の眼鏡を強要する。認識阻害がかかったメガネをかけている間は、サシャの顔や瞳、髪色までまるで別人だった。
学園に入学しても、サシャはあらぬ噂をされてどこにも居場所がない毎日。そんな中でもサシャのことを好きだと言ってくれたクラークと言う茶色の瞳を持つ騎士学生に惹かれ、お付き合いをする事に。
しかし、クラークにキスをせがまれ恥ずかしくて逃げ出したサシャは、アーヴィン=イブリックという翠眼を持つ騎士学生にぶつかってしまい、メガネが外れてしまったーーー…
認識阻害魔道具メガネのせいで2人の騎士の間で別人を演じることになった文官学生の恋の話。
全17話
2/28 番外編を更新しました

伝説のS級おじさん、俺の「匂い」がないと発狂して国を滅ぼすらしいい
マンスーン
BL
ギルドの事務職員・三上薫は、ある日、ギルドロビーで発作を起こしかけていた英雄ガルド・ベルンシュタインから抱きしめられ、首筋を猛烈に吸引。「見つけた……俺の酸素……!」と叫び、離れなくなってしまう。
最強おじさん(変態)×ギルドの事務職員(平凡)
世界観が現代日本、異世界ごちゃ混ぜ設定になっております。

【8話完結】魔王討伐より、不機嫌なキミを宥める方が難易度「SSS」なんだが。
キノア9g
BL
世界を救った英雄の帰還先は、不機嫌な伴侶の待つ「絶対零度」の我が家でした。
あらすじ
「……帰りたい。今すぐ、愛する彼のもとへ!」
魔王軍の幹部を討伐し、王都の凱旋パレードで主役を務める聖騎士カイル。
民衆が英雄に熱狂する中、当の本人は生きた心地がしていなかった。
なぜなら、遠征の延長を愛する伴侶・エルヴィンに「事後報告」で済ませてしまったから……。
意を決して帰宅したカイルを迎えたのは、神々しいほどに美しいエルヴィンの、氷のように冷たい微笑。
機嫌を取ろうと必死に奔走するカイルだったが、良かれと思った行動はすべて裏目に出てしまい、家庭内での評価は下がる一方。
「人類最強の男に、家の中まで支配させてあげるもんですか」
毒舌、几帳面、そして誰よりも不器用な愛情。
最強の聖騎士といえど、愛する人の心の機微という名の迷宮には、聖剣一本では太刀打ちできない。
これは、魔王討伐より遥かに困難な「伴侶の機嫌取り」という最高難易度クエストに挑む、一途な騎士の愛と受難の記録。
全8話。

愛しい番の囲い方。 半端者の僕は最強の竜に愛されているようです
飛鷹
BL
獣人の国にあって、神から見放された存在とされている『後天性獣人』のティア。
獣人の特徴を全く持たずに生まれた故に獣人とは認められず、獣人と認められないから獣神を奉る神殿には入れない。神殿に入れないから婚姻も結べない『半端者』のティアだが、孤児院で共に過ごした幼馴染のアデルに大切に守られて成長していった。
しかし長く共にあったアデルは、『半端者』のティアではなく、別の人を伴侶に選んでしまう。
傷付きながらも「当然の結果」と全てを受け入れ、アデルと別れて獣人の国から出ていく事にしたティア。
蔑まれ冷遇される環境で生きるしかなかったティアが、番いと出会い獣人の姿を取り戻し幸せになるお話です。


番に見つからない街で、子供を育てている
はちも
BL
目を覚ますと、腕の中には赤ん坊がいた。
異世界の青年ロアンとして目覚めた「俺」は、希少な男性オメガであり、子を産んだ母親だった。
現世の記憶は失われているが、
この子を守らなければならない、という想いだけははっきりと残っている。
街の人々に助けられ、魔石への魔力注入で生計を立てながら、
ロアンと息子カイルは、番のいない街で慎ましく暮らしていく。
だが、行方不明の番を探す噂が、静かに近づいていた。
再会は望まない。
今はただ、この子との生活を守りたい。
これは、番から逃げたオメガが、
選び直すまでの物語。
*本編完結しました
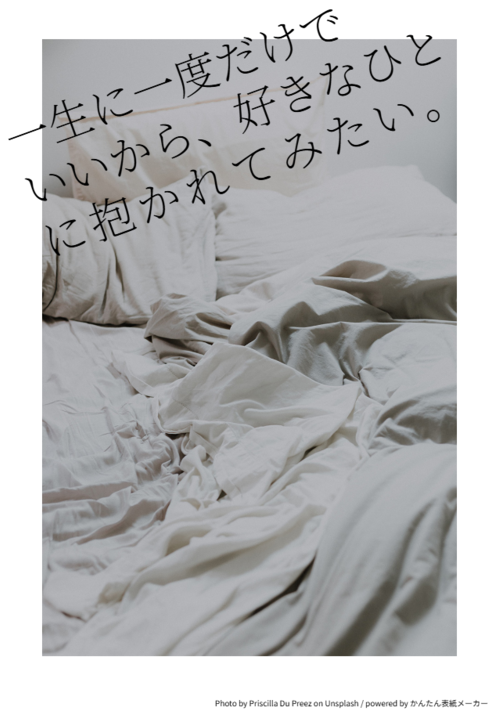
【完結】一生に一度だけでいいから、好きなひとに抱かれてみたい。
村松砂音(抹茶砂糖)
BL
第13回BL大賞で奨励賞をいただきました!
ありがとうございました!!
いつも不機嫌そうな美形の騎士×特異体質の不憫な騎士見習い
<あらすじ>
魔力欠乏体質者との性行為は、死ぬほど気持ちがいい。そんな噂が流れている「魔力欠乏体質」であるリュカは、父の命令で第二王子を誘惑するために見習い騎士として騎士団に入る。
見習い騎士には、側仕えとして先輩騎士と宿舎で同室となり、身の回りの世話をするという規則があり、リュカは隊長を務めるアレックスの側仕えとなった。
いつも不機嫌そうな態度とちぐはぐなアレックスのやさしさに触れていくにつれて、アレックスに惹かれていくリュカ。
ある日、リュカの前に第二王子のウィルフリッドが現れ、衝撃の事実を告げてきて……。
親のいいなりで生きてきた不憫な青年が、恋をして、しあわせをもらう物語。
※性描写が多めの作品になっていますのでご注意ください。
└性描写が含まれる話のサブタイトルには※をつけています。
※表紙は「かんたん表紙メーカー」さまで作成しました。

記憶を失くしたはずの元夫が、どうか自分と結婚してくれと求婚してくるのですが。
鷲井戸リミカ
BL
メルヴィンは夫レスターと結婚し幸せの絶頂にいた。しかしレスターが勇者に選ばれ、魔王討伐の旅に出る。やがて勇者レスターが魔王を討ち取ったものの、メルヴィンは夫が自分と離婚し、聖女との再婚を望んでいると知らされる。
死を望まれたメルヴィンだったが、不思議な魔石の力により脱出に成功する。国境を越え、小さな町で暮らし始めたメルヴィン。ある日、ならず者に絡まれたメルヴィンを助けてくれたのは、元夫だった。なんと彼は記憶を失くしているらしい。
君を幸せにしたいと求婚され、メルヴィンの心は揺れる。しかし、メルヴィンは元夫がとある目的のために自分に近づいたのだと知り、慌てて逃げ出そうとするが……。
ハッピーエンドです。
この作品は他サイトにも投稿しております。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















