1 / 22
一 ありえない死とありがたい生
しおりを挟む
かたよりのない理想的なサイコロを一個振って一の目が出る確率は六分の一である。もう一回振って連続で一の目が出る確率は三十六分の一である。さらに振って三回連続で一の目になるのは二百十六分の一だ。
この調子でえんえんつづけて百回振って百回とも一の確率はどのくらいだろう。計算する気にもなれないが、とても小さい値になるだろう。とうてい起こりえない確率ともいえる。
でも、ゼロではない。
ゼロではない以上、ありうるともいえる。
さて、ここに、学校の帰り道を歩く少年がいる。下校時刻になって降りだした雷雨。小やみになるのを待っていてもよかったのだが、最寄りの駅まで十分ほどだし、さいわいロッカーには置き傘もある。そこで、たたきつけるような雨の中校門を出た。
はねかえる雨で高校の制服のズボンのすそはすぐにびっしょり濡れる。やはり待っていたほうがよかったかなと後悔したが、いまさらもどってもしょうがない。かれは傘のなかで肩をすぼめて歩いた。
ちなみに傘の下はもちろんひとりだ。生まれて十六年、傘下に異性なし。それが、この少年、フルヤダイスケだった。靴下まで濡れてきたのを感じて舌打ちする。
こういうときにかぎって横断歩道で止められる。信号の音楽が雷と雨の音でとぎれとぎれにしかきこえない。光ってから音がするまで間隔があるので怖くはなかったが、光ると遠くの建物が浮かび上がるように見える。
では、ここで視点を宇宙に移そう。
地球はほかの太陽系の天体とおなじく、主星である太陽のまわりをめぐっている。太陽のとてつもなく大きな重力からは逃れられない。それが物理法則だ。
ほかの天体には地球より大きなものあり、小さなものあり、さらにごく小さなものがある。
そのごく小さなものは太陽系が形成された初期にほとんどが地球やほかの惑星に落ちてくっついたり、太陽系の外へ飛び出したりした。
しかし、すべてではない。いまなお少数がそれぞれの軌道を周回している。さらになお少数がほかの天体に引き寄せられるコースをたどる。そのなかでごくまれに地球に来るものがある。さらにごくごくまれに大気圏内で燃え尽きずに地表に到達するものがある。
さらに続けよう。地球の七割は海であり、陸地もほとんどが無人だ。といっても落下する天体に意志はないので、そういうところを選ぶ親切さはない。
いま落下しつつある微小天体も例外ではない。だれかの意志によってではなく、物理法則にしたがってフルヤダイスケの頭部に命中した。
ついでといってはなんだが、宇宙的速度で大気圏を突っ切ってきた微小天体の軌跡がちょうど避雷針のような役割を果たし、そこらにあった雷雲の電気をすべて引き寄せた。
この光景を第三者から見ると、光の矢がフルヤダイスケを貫いたかのようだっただろう。神を敬う心が残っていた時代であれば、なんらかの天罰と記録されたかもしれない。
こうして、この世界におけるフルヤダイスケの一生は終わった。かれの親兄弟は一般的な親兄弟らしく嘆き悲しみ、かれらの社会的身分にふさわしい葬式をあげて弔った。
しかし、それはこの物語の終わりではない。むしろ始まりである。
ダイスケの主観では、目を開けていられないほど明るくなってからうす暗くなったようにしか感じていなかった。目がくらんで頭がふらふらする。ピントの定まらない目を、頭を振ってなんとかしゃんとさせようとするが、自分の周囲に光るもやがただよっていてなにがなんだかわからない。
「まだくらくらする? むりに立とうとしないで。しゃがんで頭を下げて」
若い女性の声だ。子供っぽい感じもする。どこからきこえるのかはっきりしない。返事をしようとするが、口を開きかけたとたん、刺すような頭痛がした。
「無理してしゃべろうとしないで。説明するから。あなた、死んだの」
(なに言ってんだ、こいつ)
「あなたは学校帰りに隕石と雷に打たれて死んだの。めずらしい死に方よ」
(夢か。夢とわかる夢だな。これは)
「そろそろ大丈夫かな。大丈夫だったらゆっくり頭をあげてこっちを見て」
これは理解できる指示だったので言うとおりにする。まだぼやける目をいちどぎゅっと閉じて開くと、もやのただよう草原のようなところにいた。
「こっち」
うしろから声がしたのでふりむくと数メートルはなれたところに女の子がいた。ダイスケの学校の制服を着ているが、知らない子だ。
(だれだ、こいつ?)
「なに、この服。あんたの魂を再構成するついでに最新の記憶から引き出したけど、着心地悪いし、変なデザイン」
だいたいダイスケと同年代くらいだろうか。
「おまえ、なに? ここ、どこ?」
「おまえって……、失礼っていうより無礼ね。あたしは女神よ。まあ、あんたの世界の神じゃないから許してあげる」
「で、ここは?」
「すき間よ。世界と世界の」
(おい、夢ならそろそろ覚めろ。わけがわからん)
ダイスケは女神と自称するちびの女をじっと見た。頭のくらくらはだいぶおさまってきたが、まだ立てない。とっつかまえてやろうかと思ったが、それはまだできそうになかった。
「悪いけど、なにがなんだかわからん。ゆっくりていねいに説明してくれたらありがたいんだが」
「ありがたいんだが」というところはお願いというより皮肉といらだちをまぜて言った。自称女神はため息をつく。
「ああ、しょうがないか。人間だし、ばらばらになった魂をつなぎ合わせたところだし。その態度はものすっごく大目に見てあげる」
(なんでこいつこんなにえらそうなんだ? 体がまともに動くようになったらただはおかない。どうせ夢なんだろ。いや、夢ってことは、おれにはこうされたいって願望でもあんのかな)
ダイスケが頭をひねっている間に、自称女神は説明を始める。
「あんたは、あんたの元いた世界で死んだの。隕石と雷が頭部に命中して即死。お葬式は済んだ。きのう初七日。あんたの世界ではそういうんでしょ」
自称女神はダイスケの顔をのぞきこみ、疑問符だらけの表情を見て怒りだした。
「もう、なにがわかんないの? あんた、生きてるのと死んでるのはわかる?」
「わかる」
ダイスケはいきおいに押されている。あまり女の子と会話した経験がないので、怒る女の子というだけでどう対処していいのか困っている。
「で、あんたは死んでるの。いまは」
「死んでるのに、なんでこうして話ができるの? 体の感覚もあるし」
「それはあたしがやったの。ふつうは肉体が死ぬと魂が飛び散ってばらばらになる。コップがなければ水を入れておけないのとおなじ。でも、あたしが魂を寄せ集めてひとつにまとめなおしたの。感謝しなさい」
(なんか得意げだな。こいつ)
「もちろん、そんなのは世界の法則を乱すから、その中ではできない。世界の外、言ってみれば世界と世界のすき間で作業しなくちゃならない。そういうこと」
(そういうことって、どういうこと?)
「もう説明はいいわね。で、あんたの魂を復元したのは、あたしの世界に投下するためよ」
(またわからないことを言いだしたぞ)
「あんたはあんたの元いた世界では死んだ。これはまちがいないし、いくら神でも死んだ者の復活はできない。ゾンビ映画じゃあるまいし、そんなのできたらめちゃくちゃになるし」
(ゾンビ知ってるんだ……)
「でも、世界がちがうならなんとかなる。魂を新しいコップに入れ直せばいいんだから。あんたの元の姿はわかってるから、それとおなじのを作ったげる。これはサービスよ」
ダイスケはよろよろと立ち上がり、自称女神に近寄ろうとしたが、相手は体を動かしたようすもないのに、かれが近づいた分はなれてしまう。どうしても手の届くところまでいけない。
「おっ、元気になってきたみたいね。でもまだ生まれたての仔馬みたい」
自称女神はよゆうを見せて笑っている。夢が悪夢になってきている。
「ちょっとおとなしくしてて、話がしにくい」
ダイスケは上から押さえつけられる力を感じ、地面にあぐらをかくように座らされた。
「あんた、どうせつまらない人生だったんでしょ。魂をくっつけるときに記憶を流し読みしたけどさ」
腕組みして見下ろしてくる。ばかにしたような眼をしている。ダイスケはにらみ返した。
「ふうん、そのくらいの根性はあるんだ。幼稚園から高校までエスカレーターで上がってきて、大学もそのまま楽して上がるつもりだったんでしょ。それからお父さんの世話で就職してのんびりすごす。そういう人生設計は読んだわよ。気楽なもんね」
「おまえ、おれの心が読めるのか」
「いまは読めない。さっき言ったけど、ばらばらの魂を復旧するときには見なくちゃいけないから。ジグソーパズルの模様を合わせるようなもんね。だからざっとは読んだわよ。くっだらない人生だけど」
「うるさい。おれはのんびり平和に暮らしたいんだ。波風たたせずに静かにな」
「それでSFとかファンタジーとかホラーが好きなんだ。現実でできないことを作り事でまぎらわせてるんだ」
(ほんとに夢か? これ)
「そういうのが好きならちょうどいいかもしれないわよ。パラレルワールドとか異世界冒険ものとか読んだり観たりしてたんだから、こんどはそれが自分に起きたと思いなさいよ」
「なんでおれなんだよ」
「死に方がおもしろかったから」
そいつはあっさり言った。
「あんたの世界じゃ人間はしょっちゅう死んでるけど、あんたは変わってたから目立ったの。それが理由」
「あんたの世界とか、あたしの世界とか、なんだそれは」
自称女神は両手をふわりと動かした。右手側に直径一メートルほどの見慣れた地球が浮かび、左手側に似てはいるが茶色の部分が多い地球が浮かんだ。
右手を動かして言う。バスガイドみたいだ。
「こっちがあんたの世界の地球。まわりの宇宙もふくめて作ったのはあたしの姉さん。あんたが生まれ育って死んだ宇宙よ」
それから左手をひらめかせる。
「こっちがあたしの作った地球。おなじくまわりの宇宙もあたし製作。これからあんたを投下するの」
「なんのために」
「実験すんのよ。あんたもやるでしょ。理科の実験。あたしは自分の世界によその世界の出身者を放り込んでいろいろ実験したいの」
「そんな勝手な」
「じゃあ、あんた死にたい? どうしてもいやならほかの人でもいいし」
言葉に詰まって、ダイスケは下を向いてしまう。夢であろうとなんであろうと、死ねと言われてはいとは答えられない。ふてくされたように口の中でつぶやく。
「神ってなんでもありかよ」
「そうとも言えるし、そうでないとも言えるわね」
「きこえたのか。地獄耳かよ」
百メートルほど向こうに雷が落ちる。
「あたしは女神よ。こんどそんな口きいたらただじゃおかないから」
(うわ、にらんでる。顔真っ赤だ。なんか神に言っちゃいけない言葉だったんだ)
「あ、あんたの話だと、おれのいた世界はあんたのお姉さんが作ったんだろ。なら、その世界の住人のおれをあんたの世界に連れてっていいのか。そんなのはありなのか」
自称女神が口を一文字に結んだ。言い返せないようだ。ダイスケは、攻撃の手がかりを得たと感じてさらに言葉を重ねる。
「あんた、ちがう世界の住人を使う実験だって言ってたけど、なんでちがう世界でないといけないんだ。自分の世界の住人を使えよ」
「おまえはまぬけか。自分の世界を試すのに自分の世界の者をつかってどうする。おまえの世界である組織に問題が起きたら、その組織内部の者に調査させるのか」
「へえ、じゃあ、あんたの世界には問題があるんだ。あんまりたいした女神じゃないな、おまえ」
また雷が落ちる。こんどはもうちょっと近い。
「口のききかたに気をつけなさい。ニンゲン」
「も、もう怖くないぞ。どうせ死んだ身だ。もういっぺん死んでももともとだし。ちゃんと質問に答えろよ」
「ふん、開き直りか。ほんとにいい根性してるな。おまえ」
じろりとダイスケをにらみつけるが、口は笑っているようだ。
「よし、教えてやる。世界に問題があると言うのはその通り。で、それを調べる実験のためにおまえを投下する。それ以上言うと先入観を持たせるから言えない」
「おれになにをさせるつもりだ」
「とくになにかさせるつもりはない。ただおまえの思うとおりに生きてくれればいい。それでこっちの知りたいことはわかるから」
「じゃ、おまえの世界に行ったら、ずっとあんたに見張られてるのか」
「そう。行動をすべて観察する。手出しはしないけどね」
「風呂とトイレもか」
「なに?」
「風呂とトイレものぞくのか」
見る間に真っ赤になる。こんどは怒りではないようだ。
「そ、そうだな……、それは……、か、勘弁してやる。けど、両方合わせて一日に一時間までだぞ、それを超えたら見るからな」
くだらないことを確かめながら、ダイスケは昔読んだSFやファンタジー小説を思い返し、もっときくべきことがあるはずだと考えていた。
「空気とか食べ物はどうだ。窒息したり飢え死にしたりしないだろうな」
「それは心配ない。あたしの世界は基本的にはお前の元いた世界とおなじだから」
「なんで?」
「だって、基礎は姉さんのをコピーしたんだもん。空気や食べ物の組成はいっしょ。ちゃんと呼吸できるし、消化できる。あ、物理定数とかもいっしょね」
ダイスケは拍子抜けした。異世界と言うからには、冒険ものによくあるように重力が弱めで大活躍できるとか、なにかいい思いができないかと考えたのだった。
「じゃ、なにがちがうんだ」
「それは行ってからのお楽しみ」
「ふざけんな。でも、おまえほんとにたいした女神じゃないんだな。世界はコピーだし、問題は起きてるし」
(あ、まずい、口がすべった)
一瞬浮かんだ表情を見てそう思ったが、雷は落ちなかった。自称女神はうなだれてしまった。鼻をすする音がする。
(え、なに、泣かせちゃったのかよ。まずいよ、どうすりゃいい?)
泣いている女性をなぐさめる時はどれだけ場数を踏んでいるかがものを言うが、ダイスケの場数はゼロだった。
「ごめん、ちょっと言い過ぎた。とにかく、いままでの話を整理すると、おれはあんたの世界で新しく生きなおせるっていうんだろ。わかった。やってやる。やってやるからもう泣きやんで」
(どうせ夢だ。これで泣きやんでくれるなら安いもんだ)
自称女神はまだうなだれているが、鼻をすする音はやんだ。まずはよかったとダイスケはほっとする。
しかし、次の瞬間、ダイスケは安請け合いを後悔した。顔をあげた自称女神はにんまりと笑っていた。声に出さなくても顔中にしてやったりと書いてある。ふと、子供のころに見た妖怪図鑑を思い出した。
「それじゃあ、快く了承いただけたので投下しまーす。いってらっしゃーい」
いままで座っていた地面がなくなり、下りエレベーターやすべりはじめたジェットコースターの降下感覚よりはるかにひどい感覚がおそってきた。うたがいもなく落下している。
ダイスケは落ちながら大声で最後の質問をした。耳元で風がうなっている。
「てめえ、名前はー」
「サイ子って呼んでー。お気をつけて―」
かすかになっていく意識に、その返答だけがきこえてきた。
この調子でえんえんつづけて百回振って百回とも一の確率はどのくらいだろう。計算する気にもなれないが、とても小さい値になるだろう。とうてい起こりえない確率ともいえる。
でも、ゼロではない。
ゼロではない以上、ありうるともいえる。
さて、ここに、学校の帰り道を歩く少年がいる。下校時刻になって降りだした雷雨。小やみになるのを待っていてもよかったのだが、最寄りの駅まで十分ほどだし、さいわいロッカーには置き傘もある。そこで、たたきつけるような雨の中校門を出た。
はねかえる雨で高校の制服のズボンのすそはすぐにびっしょり濡れる。やはり待っていたほうがよかったかなと後悔したが、いまさらもどってもしょうがない。かれは傘のなかで肩をすぼめて歩いた。
ちなみに傘の下はもちろんひとりだ。生まれて十六年、傘下に異性なし。それが、この少年、フルヤダイスケだった。靴下まで濡れてきたのを感じて舌打ちする。
こういうときにかぎって横断歩道で止められる。信号の音楽が雷と雨の音でとぎれとぎれにしかきこえない。光ってから音がするまで間隔があるので怖くはなかったが、光ると遠くの建物が浮かび上がるように見える。
では、ここで視点を宇宙に移そう。
地球はほかの太陽系の天体とおなじく、主星である太陽のまわりをめぐっている。太陽のとてつもなく大きな重力からは逃れられない。それが物理法則だ。
ほかの天体には地球より大きなものあり、小さなものあり、さらにごく小さなものがある。
そのごく小さなものは太陽系が形成された初期にほとんどが地球やほかの惑星に落ちてくっついたり、太陽系の外へ飛び出したりした。
しかし、すべてではない。いまなお少数がそれぞれの軌道を周回している。さらになお少数がほかの天体に引き寄せられるコースをたどる。そのなかでごくまれに地球に来るものがある。さらにごくごくまれに大気圏内で燃え尽きずに地表に到達するものがある。
さらに続けよう。地球の七割は海であり、陸地もほとんどが無人だ。といっても落下する天体に意志はないので、そういうところを選ぶ親切さはない。
いま落下しつつある微小天体も例外ではない。だれかの意志によってではなく、物理法則にしたがってフルヤダイスケの頭部に命中した。
ついでといってはなんだが、宇宙的速度で大気圏を突っ切ってきた微小天体の軌跡がちょうど避雷針のような役割を果たし、そこらにあった雷雲の電気をすべて引き寄せた。
この光景を第三者から見ると、光の矢がフルヤダイスケを貫いたかのようだっただろう。神を敬う心が残っていた時代であれば、なんらかの天罰と記録されたかもしれない。
こうして、この世界におけるフルヤダイスケの一生は終わった。かれの親兄弟は一般的な親兄弟らしく嘆き悲しみ、かれらの社会的身分にふさわしい葬式をあげて弔った。
しかし、それはこの物語の終わりではない。むしろ始まりである。
ダイスケの主観では、目を開けていられないほど明るくなってからうす暗くなったようにしか感じていなかった。目がくらんで頭がふらふらする。ピントの定まらない目を、頭を振ってなんとかしゃんとさせようとするが、自分の周囲に光るもやがただよっていてなにがなんだかわからない。
「まだくらくらする? むりに立とうとしないで。しゃがんで頭を下げて」
若い女性の声だ。子供っぽい感じもする。どこからきこえるのかはっきりしない。返事をしようとするが、口を開きかけたとたん、刺すような頭痛がした。
「無理してしゃべろうとしないで。説明するから。あなた、死んだの」
(なに言ってんだ、こいつ)
「あなたは学校帰りに隕石と雷に打たれて死んだの。めずらしい死に方よ」
(夢か。夢とわかる夢だな。これは)
「そろそろ大丈夫かな。大丈夫だったらゆっくり頭をあげてこっちを見て」
これは理解できる指示だったので言うとおりにする。まだぼやける目をいちどぎゅっと閉じて開くと、もやのただよう草原のようなところにいた。
「こっち」
うしろから声がしたのでふりむくと数メートルはなれたところに女の子がいた。ダイスケの学校の制服を着ているが、知らない子だ。
(だれだ、こいつ?)
「なに、この服。あんたの魂を再構成するついでに最新の記憶から引き出したけど、着心地悪いし、変なデザイン」
だいたいダイスケと同年代くらいだろうか。
「おまえ、なに? ここ、どこ?」
「おまえって……、失礼っていうより無礼ね。あたしは女神よ。まあ、あんたの世界の神じゃないから許してあげる」
「で、ここは?」
「すき間よ。世界と世界の」
(おい、夢ならそろそろ覚めろ。わけがわからん)
ダイスケは女神と自称するちびの女をじっと見た。頭のくらくらはだいぶおさまってきたが、まだ立てない。とっつかまえてやろうかと思ったが、それはまだできそうになかった。
「悪いけど、なにがなんだかわからん。ゆっくりていねいに説明してくれたらありがたいんだが」
「ありがたいんだが」というところはお願いというより皮肉といらだちをまぜて言った。自称女神はため息をつく。
「ああ、しょうがないか。人間だし、ばらばらになった魂をつなぎ合わせたところだし。その態度はものすっごく大目に見てあげる」
(なんでこいつこんなにえらそうなんだ? 体がまともに動くようになったらただはおかない。どうせ夢なんだろ。いや、夢ってことは、おれにはこうされたいって願望でもあんのかな)
ダイスケが頭をひねっている間に、自称女神は説明を始める。
「あんたは、あんたの元いた世界で死んだの。隕石と雷が頭部に命中して即死。お葬式は済んだ。きのう初七日。あんたの世界ではそういうんでしょ」
自称女神はダイスケの顔をのぞきこみ、疑問符だらけの表情を見て怒りだした。
「もう、なにがわかんないの? あんた、生きてるのと死んでるのはわかる?」
「わかる」
ダイスケはいきおいに押されている。あまり女の子と会話した経験がないので、怒る女の子というだけでどう対処していいのか困っている。
「で、あんたは死んでるの。いまは」
「死んでるのに、なんでこうして話ができるの? 体の感覚もあるし」
「それはあたしがやったの。ふつうは肉体が死ぬと魂が飛び散ってばらばらになる。コップがなければ水を入れておけないのとおなじ。でも、あたしが魂を寄せ集めてひとつにまとめなおしたの。感謝しなさい」
(なんか得意げだな。こいつ)
「もちろん、そんなのは世界の法則を乱すから、その中ではできない。世界の外、言ってみれば世界と世界のすき間で作業しなくちゃならない。そういうこと」
(そういうことって、どういうこと?)
「もう説明はいいわね。で、あんたの魂を復元したのは、あたしの世界に投下するためよ」
(またわからないことを言いだしたぞ)
「あんたはあんたの元いた世界では死んだ。これはまちがいないし、いくら神でも死んだ者の復活はできない。ゾンビ映画じゃあるまいし、そんなのできたらめちゃくちゃになるし」
(ゾンビ知ってるんだ……)
「でも、世界がちがうならなんとかなる。魂を新しいコップに入れ直せばいいんだから。あんたの元の姿はわかってるから、それとおなじのを作ったげる。これはサービスよ」
ダイスケはよろよろと立ち上がり、自称女神に近寄ろうとしたが、相手は体を動かしたようすもないのに、かれが近づいた分はなれてしまう。どうしても手の届くところまでいけない。
「おっ、元気になってきたみたいね。でもまだ生まれたての仔馬みたい」
自称女神はよゆうを見せて笑っている。夢が悪夢になってきている。
「ちょっとおとなしくしてて、話がしにくい」
ダイスケは上から押さえつけられる力を感じ、地面にあぐらをかくように座らされた。
「あんた、どうせつまらない人生だったんでしょ。魂をくっつけるときに記憶を流し読みしたけどさ」
腕組みして見下ろしてくる。ばかにしたような眼をしている。ダイスケはにらみ返した。
「ふうん、そのくらいの根性はあるんだ。幼稚園から高校までエスカレーターで上がってきて、大学もそのまま楽して上がるつもりだったんでしょ。それからお父さんの世話で就職してのんびりすごす。そういう人生設計は読んだわよ。気楽なもんね」
「おまえ、おれの心が読めるのか」
「いまは読めない。さっき言ったけど、ばらばらの魂を復旧するときには見なくちゃいけないから。ジグソーパズルの模様を合わせるようなもんね。だからざっとは読んだわよ。くっだらない人生だけど」
「うるさい。おれはのんびり平和に暮らしたいんだ。波風たたせずに静かにな」
「それでSFとかファンタジーとかホラーが好きなんだ。現実でできないことを作り事でまぎらわせてるんだ」
(ほんとに夢か? これ)
「そういうのが好きならちょうどいいかもしれないわよ。パラレルワールドとか異世界冒険ものとか読んだり観たりしてたんだから、こんどはそれが自分に起きたと思いなさいよ」
「なんでおれなんだよ」
「死に方がおもしろかったから」
そいつはあっさり言った。
「あんたの世界じゃ人間はしょっちゅう死んでるけど、あんたは変わってたから目立ったの。それが理由」
「あんたの世界とか、あたしの世界とか、なんだそれは」
自称女神は両手をふわりと動かした。右手側に直径一メートルほどの見慣れた地球が浮かび、左手側に似てはいるが茶色の部分が多い地球が浮かんだ。
右手を動かして言う。バスガイドみたいだ。
「こっちがあんたの世界の地球。まわりの宇宙もふくめて作ったのはあたしの姉さん。あんたが生まれ育って死んだ宇宙よ」
それから左手をひらめかせる。
「こっちがあたしの作った地球。おなじくまわりの宇宙もあたし製作。これからあんたを投下するの」
「なんのために」
「実験すんのよ。あんたもやるでしょ。理科の実験。あたしは自分の世界によその世界の出身者を放り込んでいろいろ実験したいの」
「そんな勝手な」
「じゃあ、あんた死にたい? どうしてもいやならほかの人でもいいし」
言葉に詰まって、ダイスケは下を向いてしまう。夢であろうとなんであろうと、死ねと言われてはいとは答えられない。ふてくされたように口の中でつぶやく。
「神ってなんでもありかよ」
「そうとも言えるし、そうでないとも言えるわね」
「きこえたのか。地獄耳かよ」
百メートルほど向こうに雷が落ちる。
「あたしは女神よ。こんどそんな口きいたらただじゃおかないから」
(うわ、にらんでる。顔真っ赤だ。なんか神に言っちゃいけない言葉だったんだ)
「あ、あんたの話だと、おれのいた世界はあんたのお姉さんが作ったんだろ。なら、その世界の住人のおれをあんたの世界に連れてっていいのか。そんなのはありなのか」
自称女神が口を一文字に結んだ。言い返せないようだ。ダイスケは、攻撃の手がかりを得たと感じてさらに言葉を重ねる。
「あんた、ちがう世界の住人を使う実験だって言ってたけど、なんでちがう世界でないといけないんだ。自分の世界の住人を使えよ」
「おまえはまぬけか。自分の世界を試すのに自分の世界の者をつかってどうする。おまえの世界である組織に問題が起きたら、その組織内部の者に調査させるのか」
「へえ、じゃあ、あんたの世界には問題があるんだ。あんまりたいした女神じゃないな、おまえ」
また雷が落ちる。こんどはもうちょっと近い。
「口のききかたに気をつけなさい。ニンゲン」
「も、もう怖くないぞ。どうせ死んだ身だ。もういっぺん死んでももともとだし。ちゃんと質問に答えろよ」
「ふん、開き直りか。ほんとにいい根性してるな。おまえ」
じろりとダイスケをにらみつけるが、口は笑っているようだ。
「よし、教えてやる。世界に問題があると言うのはその通り。で、それを調べる実験のためにおまえを投下する。それ以上言うと先入観を持たせるから言えない」
「おれになにをさせるつもりだ」
「とくになにかさせるつもりはない。ただおまえの思うとおりに生きてくれればいい。それでこっちの知りたいことはわかるから」
「じゃ、おまえの世界に行ったら、ずっとあんたに見張られてるのか」
「そう。行動をすべて観察する。手出しはしないけどね」
「風呂とトイレもか」
「なに?」
「風呂とトイレものぞくのか」
見る間に真っ赤になる。こんどは怒りではないようだ。
「そ、そうだな……、それは……、か、勘弁してやる。けど、両方合わせて一日に一時間までだぞ、それを超えたら見るからな」
くだらないことを確かめながら、ダイスケは昔読んだSFやファンタジー小説を思い返し、もっときくべきことがあるはずだと考えていた。
「空気とか食べ物はどうだ。窒息したり飢え死にしたりしないだろうな」
「それは心配ない。あたしの世界は基本的にはお前の元いた世界とおなじだから」
「なんで?」
「だって、基礎は姉さんのをコピーしたんだもん。空気や食べ物の組成はいっしょ。ちゃんと呼吸できるし、消化できる。あ、物理定数とかもいっしょね」
ダイスケは拍子抜けした。異世界と言うからには、冒険ものによくあるように重力が弱めで大活躍できるとか、なにかいい思いができないかと考えたのだった。
「じゃ、なにがちがうんだ」
「それは行ってからのお楽しみ」
「ふざけんな。でも、おまえほんとにたいした女神じゃないんだな。世界はコピーだし、問題は起きてるし」
(あ、まずい、口がすべった)
一瞬浮かんだ表情を見てそう思ったが、雷は落ちなかった。自称女神はうなだれてしまった。鼻をすする音がする。
(え、なに、泣かせちゃったのかよ。まずいよ、どうすりゃいい?)
泣いている女性をなぐさめる時はどれだけ場数を踏んでいるかがものを言うが、ダイスケの場数はゼロだった。
「ごめん、ちょっと言い過ぎた。とにかく、いままでの話を整理すると、おれはあんたの世界で新しく生きなおせるっていうんだろ。わかった。やってやる。やってやるからもう泣きやんで」
(どうせ夢だ。これで泣きやんでくれるなら安いもんだ)
自称女神はまだうなだれているが、鼻をすする音はやんだ。まずはよかったとダイスケはほっとする。
しかし、次の瞬間、ダイスケは安請け合いを後悔した。顔をあげた自称女神はにんまりと笑っていた。声に出さなくても顔中にしてやったりと書いてある。ふと、子供のころに見た妖怪図鑑を思い出した。
「それじゃあ、快く了承いただけたので投下しまーす。いってらっしゃーい」
いままで座っていた地面がなくなり、下りエレベーターやすべりはじめたジェットコースターの降下感覚よりはるかにひどい感覚がおそってきた。うたがいもなく落下している。
ダイスケは落ちながら大声で最後の質問をした。耳元で風がうなっている。
「てめえ、名前はー」
「サイ子って呼んでー。お気をつけて―」
かすかになっていく意識に、その返答だけがきこえてきた。
0
あなたにおすすめの小説

ジャングリラ~悪魔に屠られ魔王転生。死の森を楽園に変える物語~
とんがり頭のカモノハシ
ファンタジー
「別の世界から勇者を召喚する卑怯な手口」に業を煮やした堕天使・ルシファーにより、異世界へ魔王として転生させられた大学生・左丹龍之介。
先代・魔王が勇者により討伐されて100年――。
龍之介が見たものは、人魔戦争に敗れた魔族が、辺境の森で厳しい生活を余儀なくされている姿だった。
魔族の生活向上を目指し、龍之介は元魔王軍の四天王、悪魔公のリリス、フェンリルのロキア、妖狐の緋魅狐、古代龍のアモンを次々に配下に収めていく。
バラバラだった魔族を再び一つにした龍之介は、転生前の知識と異世界の人間の暮らしを参考に、森の中へ楽園を作るべく奔走するのだが……

異世界転生目立ちたく無いから冒険者を目指します
桂崇
ファンタジー
小さな町で酒場の手伝いをする母親と2人で住む少年イールスに転生覚醒する、チートする方法も無く、母親の死により、実の父親の家に引き取られる。イールスは、冒険者になろうと目指すが、周囲はその才能を惜しんでいる

貧民街の元娼婦に育てられた孤児は前世の記憶が蘇り底辺から成り上がり世界の救世主になる。
黒ハット
ファンタジー
【完結しました】捨て子だった主人公は、元貴族の側室で騙せれて娼婦だった女性に拾われて最下層階級の貧民街で育てられるが、13歳の時に崖から川に突き落とされて意識が無くなり。気が付くと前世の日本で物理学の研究生だった記憶が蘇り、周りの人たちの善意で底辺から抜け出し成り上がって世界の救世主と呼ばれる様になる。
この作品は小説書き始めた初期の作品で内容と書き方をリメイクして再投稿を始めました。感想、応援よろしくお願いいたします。
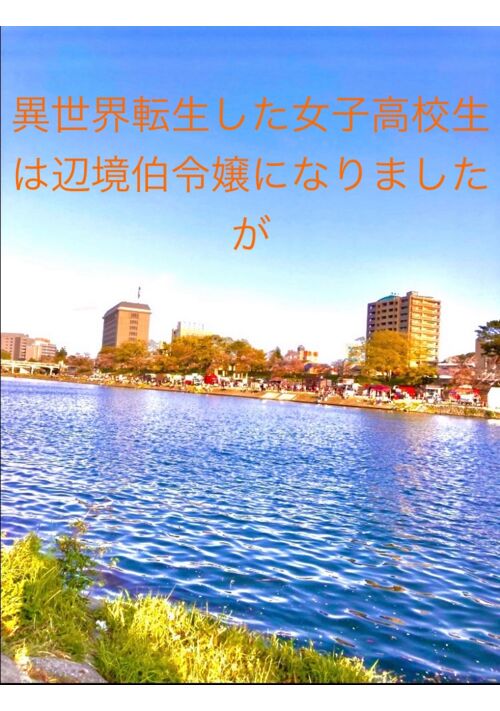
異世界転生した女子高校生は辺境伯令嬢になりましたが
初
ファンタジー
車に轢かれそうだった少女を庇って死んだ女性主人公、優華は異世界の辺境伯の三女、ミュカナとして転生する。ミュカナはこのスキルや魔法、剣のありふれた異世界で多くの仲間と出会う。そんなミュカナの異世界生活はどうなるのか。

転生貴族の領地経営〜現代日本の知識で異世界を豊かにする
初
ファンタジー
ローラシア王国の北のエルラント辺境伯家には天才的な少年、リーゼンしかしその少年は現代日本から転生してきた転生者だった。
リーゼンが洗礼をしたさい、圧倒的な量の加護やスキルが与えられた。その力を見込んだ父の辺境伯は12歳のリーゼンを辺境伯家の領地の北を治める代官とした。
これはそんなリーゼンが異世界の領地を経営し、豊かにしていく物語である。

家ごと異世界転移〜異世界来ちゃったけど快適に暮らします〜
奥野細道
ファンタジー
都内の2LDKマンションで暮らす30代独身の会社員、田中健太はある夜突然家ごと広大な森と異世界の空が広がるファンタジー世界へと転移してしまう。
パニックに陥りながらも、彼は自身の平凡なマンションが異世界においてとんでもないチート能力を発揮することを発見する。冷蔵庫は地球上のあらゆる食材を無限に生成し、最高の鮮度を保つ「無限の食料庫」となり、リビングのテレビは異世界の情報をリアルタイムで受信・翻訳する「異世界情報端末」として機能。さらに、お風呂の湯はどんな傷も癒す「万能治癒の湯」となり、ベランダは瞬時に植物を成長させる「魔力活性化菜園」に。
健太はこれらの能力を駆使して、食料や情報を確保し、異世界の人たちを助けながら安全な拠点を築いていく。

神様の忘れ物
mizuno sei
ファンタジー
仕事中に急死した三十二歳の独身OLが、前世の記憶を持ったまま異世界に転生した。
わりとお気楽で、ポジティブな主人公が、異世界で懸命に生きる中で巻き起こされる、笑いあり、涙あり(?)の珍騒動記。

家族転生 ~父、勇者 母、大魔導師 兄、宰相 姉、公爵夫人 弟、S級暗殺者 妹、宮廷薬師 ……俺、門番~
北条新九郎
ファンタジー
三好家は一家揃って全滅し、そして一家揃って異世界転生を果たしていた。
父は勇者として、母は大魔導師として異世界で名声を博し、現地人の期待に応えて魔王討伐に旅立つ。またその子供たちも兄は宰相、姉は公爵夫人、弟はS級暗殺者、妹は宮廷薬師として異世界を謳歌していた。
ただ、三好家第三子の神太郎だけは異世界において冴えない立場だった。
彼の職業は………………ただの門番である。
そして、そんな彼の目的はスローライフを送りつつ、異世界ハーレムを作ることだった。
二月から週二回更新になります。お気に入り・感想、宜しくお願いします。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















