93 / 100
93:ゼノ・セル・アーベンラインの過去~中編~
しおりを挟む
魔女の名は、クラウディアと言った。
それから、クラウディアは言葉通り、毎日ゼノに会いに来た。そして魔女クラウディアの陽気な性格はあっという間に、ゼノの心を掴んでしまった。そしてクラウディアもゼノに惹かれ、二人は恋人のような関係になっていた。だが、彼女は種族は違えどゼノが侯爵の嫡男という事はちゃんと理解をしていた。
「クラウディア、俺は侯爵になれなくとも、君と一緒にいれれば。」
「ゼノ、あんたの気持ちは嬉しいけど、それはダメよ。初めの約束通り、私は子供を作れればそれでいいの。」
「そんなクラウディア・・・」
「そろそろいい頃合いかもね。ゼノ、子作りしてくれる?」
「・・・君は、そうしたら去ってしまうだろう。」
ゼノはわかっていた、事が終わればクラウディアが、自分の目の前から去っていくであろうと。
「ごめんね。それが魔女の習性なの。魔女は身ごもれば、しばらくは外界と遮断するの。それに、ゼノにも縁談がきているでしょ?だから私はそろそろ去らなければいけないわ。」
「俺が離れたくないといっても?」
「ゼノ、あんたの気持ちは嬉しい。だけどダメなのよ。あんたは侯爵家の嫡男だもの。」
クラウディアも本当は一緒にいたかった。だが、自分がゼノの足を引っ張る訳にはいかないと思っていた。
「俺が・・・俺が平民だったら。」
この時ばかりはゼノは自分の貴族であることを恨めしく思った。
「たらればの話はなしよ。ゼノ、私の一生の思い出になるようにお願いね。」
「クラウディア!!」
魔女は相性を重視するので、あまり恋愛感情を持って子作りをすることはないのだが、ゼノとクラウディアはお互い相思相愛ではあることは理解していた。
そして、離れ離れになることをわかっていた二人は、今この時だけは片時も離れないようにと、熱く抱きしめあっていた。
そして、次の日の朝には、クラウディアはベッドからいなくなっていた。
その後はゼノは結局、貴族であることから政略結婚をした。妻になったシェリ―は伯爵家の令嬢だったが、身体が丈夫な方ではなかった。実は侯爵とはいうものの、アーベンライン家は財政難であった。そこでシェリーの実家で裕福な伯爵家が財政を支援する形での、言わば典型的な政略結婚であった。しかし妻となったシェリ―は、実家の事を鼻にかけるわけでもなく、大人しくも献身的にゼノを支えていた。そしてシェリーとの間には、一人の男児を設けることができた。その子は、コンラートと名付けらられ、その子が4歳になる直前に、またもや唐突にそれは起こったのだった。
寝静まった深夜のこと、ゼノは仕事が立て込んででおり、執務室でまだ仕事をしていた。すると、窓が突然開いたかと思うと、旋風が巻き起こり視界が遮られた。しかし目を開けた次の瞬間、見知らぬ女が立っていた。
「だ、誰だ?!」
ゼノはすぐさま、執務室のデスクに立てかけてあった剣を手に取った。
「あんたがゼノかい?」
「如何にもそうだが・・・何者だ?」
よく見ると女の腕の中には赤ん坊がいた。ゼノは訳が分からず、あぁそういえばクラウディアの時も訳が分からなかったなと、不意に思い出した。
女は質問に答えず、赤ん坊をゼノの前に付きだした。
「この子は、クラウディアの子供、つまりあんたの息子だね。」
「?!クラウディアは?それに息子?え?」
ゼノは訳が分からなかった、目の前の女は誰なのか、魔女は女児しか生まないと聞いていないのに、息子とは一体どういうことなのか。それに期間が合わない。クラウディアと関係したのはもう数年前の話だが、この赤子は間違いなく生まれて間もなかったからだ。そして目の前の女はクラウディアと繋がりを持っているのは間違いなかった。
「前代未聞さね、魔女に男児ができるなんてね。子供に罪がない事はわかっている。だけど、この子を魔女社会で育ててやることはできない。だから、父親であるあんたの所に連れてきた。」
「クラウディアは?クラウディアは一緒じゃないのか?!」
そう何故、この場にクラウディアがいないのか、不思議だったのだ。
それから、クラウディアは言葉通り、毎日ゼノに会いに来た。そして魔女クラウディアの陽気な性格はあっという間に、ゼノの心を掴んでしまった。そしてクラウディアもゼノに惹かれ、二人は恋人のような関係になっていた。だが、彼女は種族は違えどゼノが侯爵の嫡男という事はちゃんと理解をしていた。
「クラウディア、俺は侯爵になれなくとも、君と一緒にいれれば。」
「ゼノ、あんたの気持ちは嬉しいけど、それはダメよ。初めの約束通り、私は子供を作れればそれでいいの。」
「そんなクラウディア・・・」
「そろそろいい頃合いかもね。ゼノ、子作りしてくれる?」
「・・・君は、そうしたら去ってしまうだろう。」
ゼノはわかっていた、事が終わればクラウディアが、自分の目の前から去っていくであろうと。
「ごめんね。それが魔女の習性なの。魔女は身ごもれば、しばらくは外界と遮断するの。それに、ゼノにも縁談がきているでしょ?だから私はそろそろ去らなければいけないわ。」
「俺が離れたくないといっても?」
「ゼノ、あんたの気持ちは嬉しい。だけどダメなのよ。あんたは侯爵家の嫡男だもの。」
クラウディアも本当は一緒にいたかった。だが、自分がゼノの足を引っ張る訳にはいかないと思っていた。
「俺が・・・俺が平民だったら。」
この時ばかりはゼノは自分の貴族であることを恨めしく思った。
「たらればの話はなしよ。ゼノ、私の一生の思い出になるようにお願いね。」
「クラウディア!!」
魔女は相性を重視するので、あまり恋愛感情を持って子作りをすることはないのだが、ゼノとクラウディアはお互い相思相愛ではあることは理解していた。
そして、離れ離れになることをわかっていた二人は、今この時だけは片時も離れないようにと、熱く抱きしめあっていた。
そして、次の日の朝には、クラウディアはベッドからいなくなっていた。
その後はゼノは結局、貴族であることから政略結婚をした。妻になったシェリ―は伯爵家の令嬢だったが、身体が丈夫な方ではなかった。実は侯爵とはいうものの、アーベンライン家は財政難であった。そこでシェリーの実家で裕福な伯爵家が財政を支援する形での、言わば典型的な政略結婚であった。しかし妻となったシェリ―は、実家の事を鼻にかけるわけでもなく、大人しくも献身的にゼノを支えていた。そしてシェリーとの間には、一人の男児を設けることができた。その子は、コンラートと名付けらられ、その子が4歳になる直前に、またもや唐突にそれは起こったのだった。
寝静まった深夜のこと、ゼノは仕事が立て込んででおり、執務室でまだ仕事をしていた。すると、窓が突然開いたかと思うと、旋風が巻き起こり視界が遮られた。しかし目を開けた次の瞬間、見知らぬ女が立っていた。
「だ、誰だ?!」
ゼノはすぐさま、執務室のデスクに立てかけてあった剣を手に取った。
「あんたがゼノかい?」
「如何にもそうだが・・・何者だ?」
よく見ると女の腕の中には赤ん坊がいた。ゼノは訳が分からず、あぁそういえばクラウディアの時も訳が分からなかったなと、不意に思い出した。
女は質問に答えず、赤ん坊をゼノの前に付きだした。
「この子は、クラウディアの子供、つまりあんたの息子だね。」
「?!クラウディアは?それに息子?え?」
ゼノは訳が分からなかった、目の前の女は誰なのか、魔女は女児しか生まないと聞いていないのに、息子とは一体どういうことなのか。それに期間が合わない。クラウディアと関係したのはもう数年前の話だが、この赤子は間違いなく生まれて間もなかったからだ。そして目の前の女はクラウディアと繋がりを持っているのは間違いなかった。
「前代未聞さね、魔女に男児ができるなんてね。子供に罪がない事はわかっている。だけど、この子を魔女社会で育ててやることはできない。だから、父親であるあんたの所に連れてきた。」
「クラウディアは?クラウディアは一緒じゃないのか?!」
そう何故、この場にクラウディアがいないのか、不思議だったのだ。
0
あなたにおすすめの小説

「がっかりです」——その一言で終わる夫婦が、王宮にはある
柴田はつみ
恋愛
妃の席を踏みにじったのは令嬢——けれど妃の心を折ったのは、夫のたった一言だった
王太子妃リディアの唯一の安らぎは、王太子アーヴィンと交わす午後の茶会。だが新しく王宮に出入りする伯爵令嬢ミレーユは、妃の席に先に座り、殿下を私的に呼び、距離感のない振る舞いを重ねる。
リディアは王宮の礼節としてその場で正す——正しいはずだった。けれど夫は「リディア、そこまで言わなくても……」と、妃を止めた。
「わかりました。あなたには、がっかりです」
微笑んで去ったその日から、夫婦の茶会は終わる。沈黙の王宮で、言葉を失った王太子は、初めて“追う”ことを選ぶが——遅すぎた。

さようならの定型文~身勝手なあなたへ
宵森みなと
恋愛
「好きな女がいる。君とは“白い結婚”を——」
――それは、夢にまで見た結婚式の初夜。
額に誓いのキスを受けた“その夜”、彼はそう言った。
涙すら出なかった。
なぜなら私は、その直前に“前世の記憶”を思い出したから。
……よりによって、元・男の人生を。
夫には白い結婚宣言、恋も砕け、初夜で絶望と救済で、目覚めたのは皮肉にも、“現実”と“前世”の自分だった。
「さようなら」
だって、もう誰かに振り回されるなんて嫌。
慰謝料もらって悠々自適なシングルライフ。
別居、自立して、左団扇の人生送ってみせますわ。
だけど元・夫も、従兄も、世間も――私を放ってはくれないみたい?
「……何それ、私の人生、まだ波乱あるの?」
はい、あります。盛りだくさんで。
元・男、今・女。
“白い結婚からの離縁”から始まる、人生劇場ここに開幕。
-----『白い結婚の行方』シリーズ -----
『白い結婚の行方』の物語が始まる、前のお話です。

将来を誓い合った王子様は聖女と結ばれるそうです
きぬがやあきら
恋愛
「聖女になれなかったなりそこない。こんなところまで追って来るとはな。そんなに俺を忘れられないなら、一度くらい抱いてやろうか?」
5歳のオリヴィエは、神殿で出会ったアルディアの皇太子、ルーカスと恋に落ちた。アルディア王国では、皇太子が代々聖女を妻に迎える慣わしだ。しかし、13歳の選別式を迎えたオリヴィエは、聖女を落選してしまった。
その上盲目の知恵者オルガノに、若くして命を落とすと予言されたオリヴィエは、せめてルーカスの傍にいたいと、ルーカスが団長を務める聖騎士への道へと足を踏み入れる。しかし、やっとの思いで再開したルーカスは、昔の約束を忘れてしまったのではと錯覚するほど冷たい対応で――?

世界の現実は、理不尽で残酷だ――平等など存在しない
鷹 綾
恋愛
「学園内は、身分に関係なく平等であるべきです」
その“正義”が、王国を崩しかけた。
王太子ルイスは、貴族学院で平民出身の聖女マリアがいじめられたと信じ、
婚約者である公爵令嬢アリエノール・ダキテーヌを断罪し、婚約破棄を宣言する。
だが――
たとえそれが事実であったとしても、
それは婚約破棄の正当な理由にはならなかった。
貴族社会において、婚約とは恋愛ではない。
それは契約であり、権力であり、国家の均衡そのものだ。
「世界は、残酷で不平等なのです」
その現実を理解しないまま振るわれた“善意の正義”は、
王太子の廃嫡、聖女の幽閉、王家と公爵家の決定的な断絶を招く。
婚約破棄は恋愛劇では終わらない。
それは、国家が牙を剥く瞬間だ。
本作は、
「いじめられたという事実があっても、それは免罪符にはならない」
「平等を信じた者が、最も残酷な結末に辿り着く」
そんな現実を、徹底して描く。
――これは、ざまぁではない。
誰も救われない、残酷な現実の物語である。
※本作は中世ヨーロッパをモデルにしたフィクションです。
学園制度・男女共学などは史実とは異なりますが、
権力構造と政治的判断の冷酷さを重視して描いています。
---

【完結】離縁王妃アデリアは故郷で聖姫と崇められています ~冤罪で捨てられた王妃、地元に戻ったら領民に愛され「聖姫」と呼ばれていました~
猫燕
恋愛
「――そなたとの婚姻を破棄する。即刻、王宮を去れ」
王妃としての5年間、私はただ国を支えていただけだった。
王妃アデリアは、側妃ラウラの嘘と王の独断により、「毒を盛った」という冤罪で突然の離縁を言い渡された。「ただちに城を去れ」と宣告されたアデリアは静かに王宮を去り、生まれ故郷・ターヴァへと向かう。
しかし、領地の国境を越えた彼女を待っていたのは、驚くべき光景だった。
迎えに来たのは何百もの領民、兄、彼女の帰還に歓喜する侍女たち。
かつて王宮で軽んじられ続けたアデリアの政策は、故郷では“奇跡”として受け継がれ、領地を繁栄へ導いていたのだ。実際は薬学・医療・農政・内政の天才で、治癒魔法まで操る超有能王妃だった。
故郷の温かさに癒やされ、彼女の有能さが改めて証明されると、その評判は瞬く間に近隣諸国へ広がり──
“冷徹の皇帝”と恐れられる隣国の若き皇帝・カリオンが現れる。
皇帝は彼女の才覚と優しさに心を奪われ、「私はあなたを守りたい」と静かに誓う。
冷徹と恐れられる彼が、なぜかターヴァ領に何度も通うようになり――「君の価値を、誰よりも私が知っている」「アデリア・ターヴァ。君の全てを、私のものにしたい」
一方その頃――アデリアを失った王国は急速に荒れ、疫病、飢饉、魔物被害が連鎖し、内政は崩壊。国王はようやく“失ったものの価値”を理解し始めるが、もう遅い。
追放された王妃は、故郷で神と崇められ、最強の溺愛皇帝に娶られる!「あなたが望むなら、帝国も全部君のものだ」――これは、誰からも理解されなかった“本物の聖女”が、
ようやく正当に愛され、報われる物語。
※「小説家になろう」にも投稿しています
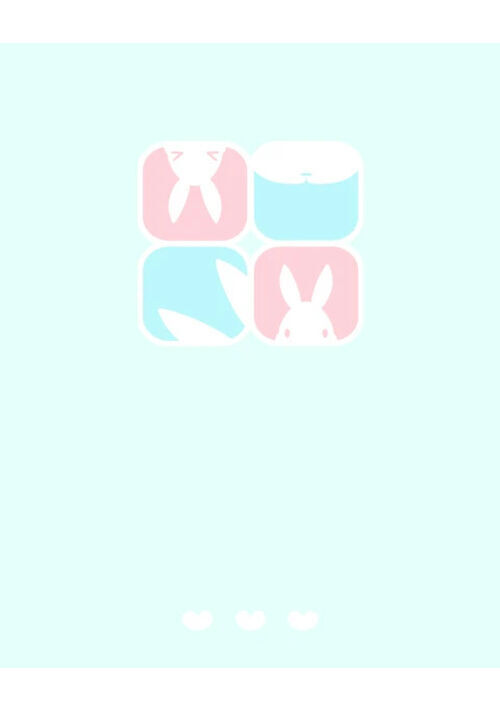
【完結】王太子に婚約破棄され、父親に修道院行きを命じられた公爵令嬢、もふもふ聖獣に溺愛される〜王太子が謝罪したいと思ったときには手遅れでした
まほりろ
恋愛
【完結済み】
公爵令嬢のアリーゼ・バイスは一学年の終わりの進級パーティーで、六年間婚約していた王太子から婚約破棄される。
壇上に立つ王太子の腕の中には桃色の髪と瞳の|庇護《ひご》欲をそそる愛らしい少女、男爵令嬢のレニ・ミュルべがいた。
アリーゼは男爵令嬢をいじめた|冤罪《えんざい》を着せられ、男爵令嬢の取り巻きの令息たちにののしられ、卵やジュースを投げつけられ、屈辱を味わいながらパーティー会場をあとにした。
家に帰ったアリーゼは父親から、貴族社会に向いてないと言われ修道院行きを命じられる。
修道院には人懐っこい仔猫がいて……アリーゼは仔猫の愛らしさにメロメロになる。
しかし仔猫の正体は聖獣で……。
表紙素材はあぐりりんこ様よりお借りしております。
「Copyright(C)2021-九頭竜坂まほろん」
・ざまぁ有り(死ネタ有り)・ざまぁ回には「ざまぁ」と明記します。
・婚約破棄、アホ王子、モフモフ、猫耳、聖獣、溺愛。
2021/11/27HOTランキング3位、28日HOTランキング2位に入りました! 読んで下さった皆様、ありがとうございます!
誤字報告ありがとうございます! 大変助かっております!!
アルファポリスに先行投稿しています。他サイトにもアップしています。

捨てられた聖女、自棄になって誘拐されてみたら、なぜか皇太子に溺愛されています
h.h
恋愛
「偽物の聖女であるお前に用はない!」婚約者である王子は、隣に新しい聖女だという女を侍らせてリゼットを睨みつけた。呆然として何も言えず、着の身着のまま放り出されたリゼットは、その夜、謎の男に誘拐される。
自棄なって自ら誘拐犯の青年についていくことを決めたリゼットだったが。連れて行かれたのは、隣国の帝国だった。
しかもなぜか誘拐犯はやけに慕われていて、そのまま皇帝の元へ連れて行かれ━━?
「おかえりなさいませ、皇太子殿下」
「は? 皇太子? 誰が?」
「俺と婚約してほしいんだが」
「はい?」
なぜか皇太子に溺愛されることなったリゼットの運命は……。

引きこもり聖女は祈らない
鷹 綾
恋愛
内容紹介
聖女ポーラ・スターは、引きこもっていた。
人と話すことができず、部屋から出ることもできず、
彼女の意思表示は、扉に貼られる小さなメモだけだった。
「西の街道でがけ崩れが起きます」
「今日は、クラムチャウダーが食べたいです」
祈らず、姿も見せず、奇跡を誇示することもない聖女。
その存在は次第に「役立たず」と見なされ、
王太子リチャードから一方的に婚約を破棄され、聖女の地位も解かれる。
──だが、その日を境に、王国は壊れ始めた。
天候不順、嵐、洪水、冷害。
新たに任命された聖女は奇跡を演じるが、世界は救われない。
誰もが気づかぬまま、
「何もしない聖女」が、実はすべてを支えていた事実だけが残されていた。
扉の向こうで静かに生きる少女と、
毎日声をかけ続ける精神科医フォージャー。
失われていく王国と、取り戻されていく一人の人生。
これは、
祈らない聖女が選んだ、
誰にも支配されない静かな結末の物語。
『引きこもり聖女は祈らない』
ざまぁは声高でなく、
救いは奇跡ではなく、
その扉の向こうに、確かにあった。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















