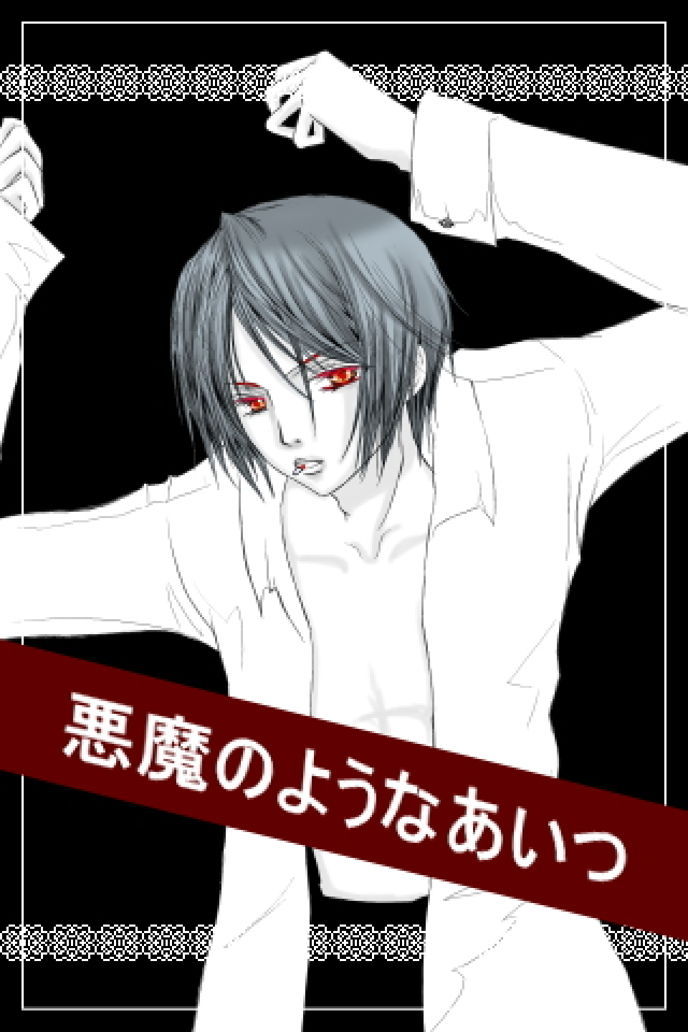1 / 8
第一章 レンズ越しの邂逅
しおりを挟む
脳内物質がもたらす快楽的衝動の相互関係
高城 千鶴(Chiduru Takashiro)
――序論(introduction)
――「快楽」。
所詮、こうした衝動は、脳内に分泌される化学物質のもたらす生理現象に過ぎない。
我々が「気持ち良い」と感じたり、愛だ恋だという感情も、全てこれらの物質に操られているということになるのである。
まさに、愛など脳内物質の作り出したまやかしに過ぎない。
それはひどく理不尽でもあり、同時に愉快でもある。
憐れなエピキュリアンたる我々は、その事実を知りつつもその衝動と悦楽に酔いしれるしかないのである。
これから論じる内容は、まさにそれらに踊らされた憐れなモルモットたちの記録となるであろう。
さて、脳が関知する快楽物質には「脳内麻薬」の別名を持つドーパミンなどがあるが……。
(後略)
華ーー2015年4月5日10時45分 TTV報道局
「暇だな」
俺は、編集の終わったテープの山を横目に見ながら、呟いた。
俺の職業はTTV製作の報道番組『報道ワイドスクープ』のカメラマン。
とは言え、まだ駆け出し。
先輩たちの後塵を拝しつつ、日夜鍛練の日々とか言っとけば、少しは様になるか?
荷物運びやら、カンペ出しやら、ADまがいのことまでやらされる。
ようは体の言い雑用係りだ。
実際、この業界は下積みが長い。
あっという間にメインカメラマンになれるって訳でもないのだ。
わかっちゃいるが、歯がゆい思いを感じることも少なくない。
俺だったらこう撮るのにとか、それは違うんじゃねぇかとか。
そんなことの連続だ。
あーだこーだとフラストレーションは溜まっちまう訳で。
だが、俺はこの仕事が嫌いじゃない。
事件が勃発した際に生じる、あの緊張感。
様々な情報や罵声や怒声や電話のベルが入り乱れ、この場が戦場のようになるあの瞬間が好きだ。
体全身で生きているって感じを痛感できるから。
だが、この待機時間ってのは、好きになれない。
俺は思いっきり欠伸をかました。
「でっかい欠伸やな。見てるこっちまでつられそうやわ」
そのやや甲高い声に椅子ごと振り返ると、芸能デスクの今宮明日香が、女にあるまじき仁王立ちをしていた。
今時絶滅したのではないか?というゴムの二つ結びの髪に、彼女が熱烈にファンだと言う阪神タイガースの野球帽を被っている。
やや赤めのべっ甲ブチのメガネからのぞくくりくりとした目は、いつも好奇心で揺れている。
やや唇がぽってりしているが、そこそこ別嬪系なのは、認める。
Tシャツにジーパンメインの格好がガキくさすぎて萎えるが。
彼女に似ているマンガのキャラがいたはずだったが、なんだったっけ?
ああ、あれだ。「アラレちゃん」だ。
京都府出身らしいが、京都らしいはんなりした感じなんて微塵も感じられないじゃじゃ馬で、おまけにボケには必ず突っ込まないと気が済まない性分らしい。
デスクには、ボケた相手に愛の突っ込みを入れるためのMyハリセンが常備されている。
奴の出身は、本当のところは、絶対大阪府に違いない。
「相変わらず、デスクのこやしになっとるな。遠山颯人」
さりげなく、フルネームで呼び捨てにするなよ。アラレ。
「どっから見ても暇そうやな。うちの取材、手伝って」
「なんだよ。いきなり。俺へのアポは前日の13時までだぜ?」
「あほくさ。何、御笠先輩の猿マネしとるん?あんたがやってもサマにならんわ」
「るっせーよ。で、何の取材だよ」
「お、少しは興味湧いた?これが、総選挙がらみなんよ。
東京駅前で国民改新党が、いきなり街頭演説やるっちゅうことなんやて。
あんまり急な話で、今、みんな他の取材で出払ってもうて、芸能デスクのうちと事件畑のあんたくらいしか人材がおらへんねん。
夕方の放送までにV作らなあかんやて。頼むわ」
「よくお前が動いたな」
「へっへ~ん。この今宮明日香がタダでピンチヒッターなんてやる訳ないやろ。ちゃ~んと交換条件付きや」
「お前らしいな」
「せやけど、ラッキーやで。この取材、交換条件なくてもいただきやわ」
「何がラッキーなんだ?」
「ウマウマやで。今日の選挙演説には、高城一輝が出るもん」
と明日香は顔に似合わない豊満な胸を張った。
「ああん?誰それ」
明日香はおもいっきりコケた。
関西人として、ボケには何が何でも対応しないといけないらしい。
「はあ?あんた、今のギャグ?ぜんぜんウケへん。センスゼロやな」
「冗談じゃねぇよ。なによ。それ。おいしいのか?」
「あんたなあ。それで仮にも報道局に籍を置くカメラマンなん?高城一輝言うたら、今をときめく人気絶大のイケメン若手政治家やないの」
「ま、そいつのことは知っているよ。連日総選挙ったら、そのネタばっかだからな。
だが、俺はね。政治ネタには全く関心ねぇの。俺が追っかけるのは、熱い事件の現場だけだからな」
「それだけが報道やない。政治ネタも芸能ネタもみ~んなひっくるめて報道やないの」
「興味ないね」
俺はそう言って、椅子を回転させて背を向けた。
だが、今日の明日香の気合の入り方は半端なかった。
「あんたが興味あろうがなかろうが、今日の選挙演説の撮りはやってもらうで!!ばっちりカメラ回してや!!」
明日香はそう叫ぶと、椅子ごと俺を報道局の出口へと押し出した。
待てよ!!この怪力!!
「ちょっ!!離せ!!俺はやらねぇぞ!!離せぇええええっ!!」
*
俺は、取材機材の詰まったボックス車に揺られながら、考えていた。
こうして、考えてみると不思議だ。
明日香はどちらかと言えば、芸能専門で、政治ネタなど今まで扱ったことなどない。
そんなこいつが、どうして今回に限って……?
「なあ、明日香。お前、高城一輝とかいう野郎の面、真近で拝みたかっただけじゃねぇの?」
「えっ。まさか~。そんなことあるわけないやないの。てへっ」
図星だな。
演説会場に到着し、俺はボックス車から引っ張り出した相棒=カメラを構えた。
かなりの人ごみだが、TTVの腕章の効果は絶大だ。
バッチリなポジションを見つけ、ズームをかける。
主役の顔がアップだ。
「この国の未来の姿を皆さんは想像できますか?
将来を担う子供達の明るい笑い声を想像できますか?
今の政治は、残念ながら、一部の利権や利害に左右され、正常に機能しているとは言い難い状況です。
我々は、そんな時代はもう終わりにしなければならない」
「アレが今をときめくイケメン政治家か?どうせ、顔だけだろ?」
「何いうてんの。顔だけやない。あの爽やかさ。そこがええやん。一言でいえば、颯人にはない魅力やね」
「うっせーよ」
「それにしても、国民改新党もあんなエエ男を担ぎ出すなんて、反則や。彼にやったら、清き一票どころか、二票でも三票でも百票でも投票したくなるわ」
それはお前だけだろ。
俺はそう心の中で毒づいてみたが、内心、明日香の意見も認めざるおえないだろう。
高城一輝は男の俺から見ても空恐ろしいくらいの美形だし、なんというのだろう。
品の良さとでも言うのか?
俺にはよくわからないが、彼には男の美形によくある嫌味さがまったく感じられないのだ。
今、優しく目を細めて有権者に手を振る姿も、どこかこの世の世俗とは一線を画した感じを受ける。
ああ、童話に出てくる王子様みたいなんだ。
ルックスだけでなく、その全身にまとう雰囲気が。
安易な表現なのは認めるが、それ以外に俺には言葉が見つからない。
大衆から愛される存在を具現化した男。それが政治家・高城一輝か。
公式プロフィールによれば、今、彼は30歳。
俺より6つも年上には見えないな。
選挙ポスターも地味なデザインながら、それが却って彼の美貌を際立たせている。
彼は今回が二期目の当選を賭けた選挙となるらしい。
彼は所謂、「二世議員」だ。
父親は国民改新党の幹事長を務める前官房長官・高城剛三。
彼自身も親父と同じ国民改新党に所属している。
高城一輝は、T大を首席で卒業。
その後、二年間、英国へ留学。
外務省に入省後、政界に打って出るため、退職。
国民改新党の公認を受け、四年前に初当選。
得意の語学を活かし、つい一年前には史上最年少での入閣を果たし、外務副大臣の椅子に座った。
外交では、通訳を間に挟まず直接交渉し、信頼を獲得。
洗練された彼の立ち振る舞いは、外交先のファーストレディたちにもすこぶる評判だった。
というのは、全部さっき読んだ新聞の受け売りだが。
まさに、この男は「清き一票」を集めるに相応しい雰囲気に溢れている。
彼が所属する国民改新党は、この青年の人気で持っているといっても過言ではないだろう。
明らかにこいつのルックス目当ての若い女連中だけでなく、中高年にも絶大な支持を誇る。
恐らくあの実直そうな眼差しと外務副大臣の手腕の賜物だろう。
何せ、政治家のくせに、ファンクラブまであるのだ。
俺は政治家というのは国民から愛されないというのが定説だと勝手に決め付けていたが、ここには、確実に国民から愛されている政治家がいる。
この調子なら、親子そろっての当確は間違いない。
いや、彼の好感度が影響し、国民改新党が大幅に議席を獲得した結果、揺るぎない政権を確保するに違いない。
この爽やかに微笑む青年が、日本を動かす存在になるのか。
その時、ふいに彼と視線がカチ合った。
彼は俺に微笑みかけた。
手慣れた営業スマイルか。
俺はあっかんべーでもしてやろうかと思った。
が、俺の手は止まっていた。
それは今までの微笑みとは違う、どこか寂しげな笑みだったから。
今にも泣き出してしまいそうなそんな儚げな表情だった。
あれでは、泣き笑いだ。
俺はその微笑みに心臓をわしづかみにされたかのような感覚を覚えた。
どう説明したらいいのだろう。
どこか救いを求めるような。
何か苦行に耐えているかのような。
彼は何かを求めている。
この俺に?
見ず知らずのただの有権者であるはずのこの俺に。
はるか年下のこの俺に。
胸が締め付けられるような感覚。
一体なんだ?
なんだったんだ?あの表情は。
地位も名誉も全てを己の手中に収めたはずのあんたが、なぜ苦しむ必要がある?
一体何に?
「皆さん、どうか、私に……力を与えて下さい……!!」
それが、この運命の青年の一人――高城一輝とのファーストコンタクトだった。
月ーー2015年4月5日11時25分 国会議事堂前
「今日の選挙演説も大盛況でしたね。高城先生が立つとギャラリーが3倍増えるそうですよ。
大先生もご子息にそんなに人気を持っていかれて、複雑なんじゃないですか」
「父は素直に喜んでくれていると思いますよ。
それに、有権者の皆さんもわかっていますよ。
私よりも経験豊富な父の方が政治家としては魅力的だと。
私など、まだまだひよっこですから」
そう微笑むと、高城一輝は片手を上げて番記者達と別れた。
高城一輝の第一秘書・楠美香子は、歩き出した一輝の一歩後ろに控えながら、スケジュール帳に目を落とした。
「午後からのご予定をお伝えします。13時からH工業理事・H氏とと会談。
16時からY派の会合、パーティがございます」
ふいに、一輝の歩みが止まった。
美香子に緊張が走った。
「一輝様……。まさか」
「……楠君……」
そう振り返った一輝は悲痛な表情を見せた。
美香子はその瞬間、全てを悟った。
「参りましょう」
美香子は、そっと一輝の背に手を回し、さりげなく彼を支えながら歩き出した。
そして、携帯をある番号にかけた。
*
「事務所に着きましたよ。一輝様」
そう美香子が声を上げると、一輝はそっと微笑んだ。
そして、美香子をいたわるようにぽんと肩を叩いた。
彼は事務所の扉が開くと、倒れこむようにソファに崩れた。
事前に美香子の携帯から知らせを受け、待機していた主治医・御厨が立ちあがった。
次の瞬間には、事務作業を行っていた秘書たちは看護師たちに早変わりする。
3名いる私設秘書は全て医療経験のある者ばかりで構成されていた。
彼の周りを秘書以外の人間がうろうろしていては、妙な疑いを持たれてしまう。
あらゆることがスキャンダルにつながりかねない。
実際、彼の病気のことはもちろん、トップシークレットだった。
このことが公になっては、彼の政治生命は足元から揺らぐ。
高城一輝は、一年ほど前から心臓にある病を患い、闘病生活を行いながら政治活動を行っていたのだ。
この日の発作は、やや強いもののようだった。
実際、事務所へ向かう廊下を進む間にも一輝の額には油汗が浮いていたほどだった。
「御厨先生!!早く!!一輝様、こんなに苦しがっています!!」
美香子は思わず声を上げていた。
「そう慌てるんじゃない。一輝君のことになると、君は冷静さを欠く。君らしくないぞ。楠君。酸素。点滴用意」
ロッカーからあらゆる医療用具が引っ張り出され、事務所の応接室はさながら集中治療室のようになった。
一輝の口元には酸素マスクが装着され、脱がされたスーツの上着が乱暴に床に捨てられる。
美香子は慌ててそれを拾った。
ふとそれを抱き締めると一輝のぬくもりが感じられ、彼女はふっと涙ぐんだ。
乱暴にネクタイが引き抜かれ、ワイシャツのボタンが飛んだ。
引き裂かれるように一輝の胸が露わになる。
これでは、傍目で見ては強姦と変わらない。
ことが一刻を争うため、看護師たちも必死なのだ。
思わず、美香子は顔をそむけた。
見慣れた光景だが、いつも美香子は一輝の半裸の姿を直視できない。
「大丈夫だ。一輝君。やや脈が速いが心配いらないぞ。いつもより多めに注射を打つからちと痛むぞ」
一輝は苦しそうに眼を開けたが、何度か小さく頷いた。
そして、うわごとのように呟いた。
「僕は今……死ぬ訳にはいかない……僕が死んだら……三人の妹たちが……」
*
処置を受け、一輝の息遣いもだいぶ静かになっていた。
美香子は心配だった。
明らかに一輝の発作の回数は増え、重度も増していた。
確かに、今、高城一輝という政治家は、国民改新党にとって、必要不可欠だった。
特にこの総選挙では。
だが、美香子は病気を抱えた状態で政治家という激務をこなして死なれるよりは、ただ一人の人間として、彼に生きていて欲しかった。
党のことなど、もうどうでもよくなっていた。
その思いが自分の職務とは真っ向から対立するものだとしても。
美香子は、一輝を愛しているのだ。
たとえ報われない想いだとしても、構わなかった。
実際、一輝には自分以外に愛している者がいる。
美香子はそれを痛いほど知っていた。
彼が自分に振り向く可能性など、1%もありえない。
ただ、こうしてそばにられるだけでよかった。
そんな愛し方もあるのだと彼女は自分に言い聞かせていた。
「よし。峠は越したぞ。よく頑張ったな一輝君」
美香子は、その御厨の声を聞き、その場に崩れた。
「ありがとうございます。御厨先生。ありがとうございます!!」
美香子はそうまた泣き崩れた。
「楠君。せっかくの美人が台無しじゃないか。私の患者は絶対に死なせんよ。さあ、
涙を拭きたまえ」
「先生……一輝様の発作……最近、回数が増えていますわ。
重度も増しているみたいですし……。私……」
「ああ。本当だったら、政治活動なんて放っておいて、入院を勧めたいところなんだがね。
患者が頑固なもので、承知してくれん。困ったものだ」
「当たり前でしょう……?僕にはまだ、政治家としてやらなければならないことがたくさんあるんだ。
こんなことで……志を曲げる訳にはいかない……」
「だがね。一輝君、命あっての物種じゃないか。君自身が参ってしまったら、志どころではなくなってしまうよ。
それに何より、君を心配する人々の身にもなってみたまえ。ここにいる楠君だって、その一人じゃないか」
「……み、御厨先生……」
「楠君。君には感謝しているよ。いつも僕を助けてくれて」
「か、一輝様……やめて下さい。私は、ただ……自分の職務に忠実にいたいだけです……」
「それでもいいんだ。ありがとう」
「はい……」
「じゃあ、私は行く。いつものように発作止めを処方しておいたから、軽い場合はそれで様子を見るよう伝えておいてくれ」
そう言うと、医師はドアに手をかけた。
その時、御厨の手が握る前にドアノブが回転した。
*
「一輝様。お加減はいかがですか」
そうやや高めのバリトンが響く。
景山蓮。
彼は一輝の父・高城剛三の第一秘書である。
美香子は反射的に身構えた。
蓮は緩やかに波打つ髪に、無機質な銀のメタルフレームのメガネを愛用している。
まず目を引くのが、レンズ越しに垣間見れるどこか作り物めいた整った顔立ち。
驚くほどに長いまつ毛が、紅でも差したかのように濡れた唇がどこか女性的でもある。
その中性的な美しさに惹かれるのか、側近や秘書の中には、景山びいきの者も多かったが、美香子は好きになれなかった。
それというのも、景山という男は、徹底した利己主義者だということを知っていたからだった。
「お倒れになっと伺い、こうしてお見舞いに参りました」
そう言うと、景山は赤い薔薇の花束を差し出した。
「それは、ありがとうございます。景山さん」
美香子は、涙を拭くと、ソファから立ち上がった。
「景山君か。剛三さんにあまり一輝君に無理はさせんように伝えておいてくれ」
「わかりました」
御厨医師はちょっと頭を下げると、事務所を後にした。
「お顔の色も良いようですね。よかった。これならもう大丈夫でしょう」
そう景山は快活に笑った。
「そうだ。高城大先生からご伝言です。
御存じでしょうが、16時から、Y派の会合があります。
もし、難しいようでしたら、そちらは欠席されても構いません。
その後、パーティがあります。
そちらにはどうしてもご出席頂きたいとのことです」
「それはあなたのご意向でしょう?景山さん。
剛三先生がご自分の息子がこんな状況だと言うのに、パーティに出ろなんて言うはずがないわ!!」
美香子は、そう皮肉交じりに鋭い眼光を向けた。
「おやおや。これは心外ですね。私は一介の秘書に過ぎません。
先生に意見するなんて、滅相もないことです」
そう言うと、彼はメタルフレームのメガネを指で押し上げた。
その時、ソファから細い声が響いた。
「いいんだ。楠君。景山君。……わかっているよ。
会合にもパーティにも出席させてもらう。穴は開けない。
僕もせいぜい、客寄せパンダを演じるさ。君たちのために……」
「貴方ならそう答えて下さると信じていましたよ。一輝様」
そう微笑むと、景山はにっこりと微笑んだ。
だが、その視線は一輝のむき出しになった白い胸元に注がれていた。
「早く良くなって下さいね。
今の国民改新党は、あなたなしでは立ち行きません。
お早いご快復をお祈りしております。では、私はこれで」
ドアが閉じると、美香子はまた涙ぐんだ。
言いようのない悔しさが彼女の中に渦巻いた。
その時、秘書の一人が声を上げた。
「高城先生。雪花コーポレーションの雪花様から献金の件でお電話が入っています」
「海杜か。わかった……。今行くよ」
「一輝様……」
「大丈夫。もうだいぶ落ち着いた。心配はいらない」
彼はそう酸素マスクを外していたずらっぽく微笑むと、ぽんと美香子の肩を優しく叩いた。
*
華ーー2015年4月5日18時59分 TTV Aスタジオ
今、冷静になって考えてみると、あの時高城一輝が訴えたのは、俺ではなく、俺の目=カメラに向けてだったのではないだろうか。
彼は俺のカメラを通して、日本中に何かを訴えたのだ。
いや、こうも考えられないだろうか。
彼は不特定多数の人間ではなく、テレビを眼にしているであろう特定の「誰か」に向けて訴えていた。
何かを伝えようとしていた。
いずれにせよ、彼は世間に向けて何か訴えたいことがあったに違いないのだろうが……。
それは一体……?
「本番5秒前!!」
という掛声で、俺は現実に引き戻された。
「4、3、2、1、キュ!!」
「本日のトップニュースです」
そうカメラ目線一直線に凜とした瞳を向けるのは、我らがマドンナ・鏡芙美華。
俺達の番組『報道ワイドスクープ』の看板美人キャスターである。
年齢は28歳らしいが、成熟した知性と色気を同時に発する姿は、見ていて小気味いいくらいだ。
少し茶色かかった緩やかにカールする髪を揺らし、赤く彩られた唇を動かす仕草は、フェミニンというか、フェロモン全開という感じで、デスクからちらりとのぞく細く白い足と併せて世のオッサンたちの清涼剤となっているらしいというのもさっき読んだ週刊誌の受け売りなんだが。
彼女はその容姿だけでなく、自ら綿密な取材を重ね、多くのスクープをものにしてきた。
キャスターになる前は、もともとT新聞社のエース記者だったらしいので、それも頷ける。
こうした面でも、彼女は他の顔だけの美人キャスターたちとは一線を画している。
だが、彼女には黒い噂も絶えない。
彼女につけられた二つ名は、「スクープと寝る女」。
えげつないことこの上ないが、彼女を見ていると、それも真実かもしれないなんて邪推が生まれてくる。
この女のためだったら、禁断の扉を開けてしまうなんて血迷っちまう輩が現れても仕方がないだろう。それもかなりの割合で。
それほど鏡芙美華は、魅惑的な女なのだ。
そして、鏡芙美華自身のスクープ獲得へ見せる姿勢が、その執念が、何を犠牲にしてでも手にしてみせるという意気込みがその噂に真実味を与えている。
俺達のように彼女の間近で共に番組を作る人間ほど、それは強く感じされるのではないだろうか。
スクープのためだったら、本当に自分の身体くらい平気で兵器に使用しそうなほどの。
ま、こんな噂の大半が、真実半分、やっかみ半分といったところだろうが。
本番終了後、彼女は楽屋へ向かう前に俺達の方に歩み寄ってきた。
「みんな、お疲れ様。ちょっといいかしら?」
普段の彼女は、ニュース原稿を読む時の流れるような話し方ではなく、少し甘えたような口調で話す。
あるスタッフによると、そんなところが知的な彼女のイメージとのギャップがあっていいらしいが、どこかつかみどころがなく、そんなところも恐ろしい。
「どうされました?」
チーフディレクターの大河内が、明らかに10センチほど鼻の下を伸ばしながら、彼女に向き直った。
ちなみに、さっきのあるスタッフというのは、まぎれもなく、こいつである。
「あのね。ちょっと、取材に協力して欲しいの」
「何か新しいネタでもあがりましたか」
「まあね。ちょっとね」
「なんですか?そんな嬉しそうな顔して、対象はよほどのいい男なんですか」
「ええ。いい男よ。ウフフ」
「へえ。冗談だったんですが、図星ですか。芙美華さんが目をつけるなんて、よっぽどなんでしょうね」
「もちろん。それに、オイシイ男よ。この男を追えば、必ずスクープに辿り着ける。私の勘は、当たるのよ」
そう言うと、彼女はひとりの男のポートレートをデスクに滑らせた。
それが、二人目の運命の男――芸能プロダクション社長・不動充との出会いだった。
*
月ーー2015年4月5日20時03分 高城一輝選挙事務所
パーティから戻ると、高城一輝は、沈み込むように椅子に腰かけた。
乾杯で飲んだビールが確実に効いていた。
元来、彼はアルコールを受け付けない体質だった。
選挙がらみのパーティも増え、正直、身体がいくつあっても足りない状況だった。
無理をしすぎているのかもしれない。
今更ながら、一輝はそう溜息をついた。
「お疲れ様です。一輝様」
その声に振り返ると、いつの間に部屋に入ってきたのか、景山蓮がメタルフレームのメガネを指で押し上げた。
「君もお疲れ様。こんなところで油を売っていていいのかい?父は赤坂に向かったようだが」
「いいんですよ。大先生は旧友の方々と政治を忘れて羽を伸ばしたいそうで。お伴しようとしたら、追い返されました」
一輝は苦笑した。
「で。僕に何か用かな。僕も少々疲れたのでね。今夜は早く帰ろうと思うんだ」
そう言うと、一輝はカバンに手をかけた。
「今日は楠さんはいらっしゃらないのですか」
「ああ、特に仕事もないからね。パーティ会場から帰した。僕は事務所にこいつを取りに来ただけだから」
一輝は微笑みながら、茶封筒を掲げた。
「そうですか……」
「景山君?どうしたんだい。僕はもう失礼するが」
そう言うと、一輝はポケットから事務所の鍵を取り出した。
「いえ、少し一輝様とお話がしたかったんですよ。
あなたと私は割合近しい場所にいるのに、なかなかゆっくりとお話をする機会もなかったでしょう」
「あ?ああ。そうだね」
「私はね。一輝様。本当にあなたを買っているんです。
あなたはお父様以上の政治家になられる。
そう私は信じているのですよ」
「あ、ああ。それは、ありがとう。だが、それはかいかぶりというものだよ」
「いいえ。私は、あなたを本当に想っているんですよ。
そう。この私だけのものにしてしまいたいくらいに……」
その瞬間、蓮は一輝を背中から抱きしめた。
同時に一輝に別の衝撃が走った。
発作だった。
「うっ……」
「苦しいのですか?もしかして、発作というやつですか?」
察しながらも彼はどこか楽しそうに一輝の身体を撫で回した。
「苦しいのは、この辺り?」
「離してくれ……」
一輝はそう自分の背後から回された蓮の腕を引き剥がすと、立ち上がり、部屋の隅に掛けられたスーツの上着に手をかけた。
内ポケットに手をやる。
だが、それは空っぽだった。
「……!?」
「あなたが欲しいのは、これですか?」
蓮の手にあるもの。それはまぎれもなく、発作止めだった。
いつの間に……!?
「おかわいそうにね。苦しいのでしょう。すぐ、差し上げますよ」
そう言うと蓮は、カプセルを一粒取り出し、それをゆっくりと自分の口に含んだ。
そして次の瞬間には、一輝の唇を奪っていた。
「んっ!!」
一輝は蓮を突き飛ばした。
突き放された蓮は、悪びれる風でもなく、にやりと笑った。
「おや。いけませんね。せっかくカプセルを飲ませてあげようと思っていたのに」
「何の真似だ」
「だから、お薬を。痩せ我慢はあなたのためになりませんよ?」
「君に犯されるくらいなら、死んだ方がマシ……だ……」
「あなたがそれでよくても、こちらはそうはいかないんです。
行ったでしょう?今の国民改新党は、あなたなしでは立ち行かないと……」
蓮はもう一度一輝に口付けた。
もう一度チャンスをやるとでも言うかのように。
一輝の中で、蓮との口付けの屈辱より、胸痛の苦しみから解放されるという思いの方が勝った。
カプセルが喉を通過する確かな感覚があった。
一輝は蓮を再度突き放した。そして、ソファに沈み込んだ。
「薬も飲まれたのですから、発作も時期に収まるでしょう。
でもね、今、あなたにはもうひとつ服用して頂いたんですよ。
薬だけじゃつまらないので、別のものも一緒に」
「別のもの……?」
そう顔を上げ問うた一輝は、自分の身に異変を感じた。
「……!?」
「即効性のようですね。大丈夫ですよ。それも薬ですから。種類は違いますが」
「何を……した?」
「時期にわかりますよ。感じるはずですから、あなたの身体が。ほら、こんな風に」
軽く首筋に指をはわされただけだというのに、今の一輝には数倍の刺激に感じられた。
だが、一輝は残された理性で必死にそれに抵抗した。
「強情な方だ。発作に苦しんでいる上に、媚薬まで服用しながら、それでも屈しないなんて。
でも、時期に楽になりますよ。御厨先生のお薬はよく効きますからね。
それに、もうひとつの薬も効いてくるでしょうから」
一輝は危険を感じ、ドアの方へと歩き出した。
「ダメですよ。これからいいところなんですから。
それに、そんな身体でどこへ行くんです?そんな感じやすい身体で」
蓮はそう言うと、一輝を背中から抱き締めた。
「あっ……!!」
蓮の生暖かい吐息が一輝の首筋にかかる。
一輝はゆっくりと振り向いた。
そこには、いつの間にかメガネを外した蓮の美しい顔があった。
明らかに普段の蓮ではなかった。
本来の魅力が封印を解かれたかのように。
長いまつげに彩られた瞳が妖しく獲物を捕えるように光る。
「欲情には素直に従った方がよいですよ?ねえ。一輝様?」
そう一輝の髪をかきあげると、蓮はその苦痛に震える唇に口付けた。
幾分長い口付けだった。
蓮の舌が絡む感触は、一輝の中でおぞましさから快楽へと変換されつつあった。
そのことに唇を離した蓮は満足そうに微笑むと、
ドアに打ちつけた一輝の身体をまさぐった。
蓮の指先が触れるたび、一輝の吐息が漏れる。
「あっ……いや……」
「いいですね。そうやって悶え苦しむ様子も堪らなくセクシーですよ」
「いやだ……」
一輝のその呟きは、蓮に征服されることに対しても、蓮に屈服せざるおえない今の己自身、両方に向けられたもののようだった。
蓮は一輝のシャツを脱がすと、夢中で愛撫した。
それに一輝が平生、誰も耳にしたことのないような悩ましげな喘ぎ声で答える。
明らかに一輝は理性を失いつつあった。
「いつも思っていました……。
あなたをこうやって私のものにしたいと……。
そう。あなたのすべてをね」
「やめ……て……」
そのままソファに押し倒された時、一輝は完全に己を見失った。
*
月ーー2015年4月5日午後21時14分 地下鉄某駅構内
A生命の保険外交員・由良詩織は、帰路につくため、某地下鉄構内を歩いていた。
学生時代の彼女は、顔立ちも美人ではあったが、華やかなものではなく、引っ込み思案な性格ではあったが、学業の成績はよく、クラス委員なども務め、教員たちの覚えもよかった。
卒業後の進路も、推薦で名門大学へ進むことが決まっていた。
ところがそんな矢先、彼女の父親が事業に失敗し、学費を支払うことができなくなった。
彼女にとっては、まさに青天の霹靂だった。
彼女は、泣く泣く高校中退の道を覚悟した。
卒業まであと三ヶ月というところだった。
その時、学校に掛け合って三ヶ月分の学費納期の延期に尽力してくれたのが、同級生の高城一輝だった。
一輝は当時、一緒にクラス委員を務めた間柄で、どこか押しが弱い彼女をいつも心配してくれていた。
彼女は一輝を同い年の兄のように慕っていた。
それから十数年。
すっかり没交渉となった二人であったが、突然、高城一輝から電話があった。
「君が保険の外交員をしていることを思い出してね」
詩織は、政治家として雲の上の人間となった一輝が自分を覚えていてくれたことが何より嬉しかった。
詩織は、保険のパンフレット一揃えを携え、一輝の事務所を訪れた。
「三億……?」
「ああ」
「三億円って……高城君の……生命保険?」
「うん。僕もいつ何があるかわからないから……備えておきたいんだ」
三億円の生命保険。
それは破格の契約だった。
今まで大口の契約とは無縁の日陰の存在だった彼女の突然の快挙に、一気に周囲の彼女を見る目が変わった。
まして政治家・高城一輝の担当ということで、多くの顧客から詩織への指名が入るようになり、彼女はいつしか、押しも押されもしないトップセールスレディとなっていた。
「ありがとう。高城君のおかげで、私もたくさんのお得意様に恵まれて……感謝しています」
「僕は何もしていないさ。君の努力の賜だろう?君は親身になって顧客と接するから、信頼を持たれるのは当然さ。もっと君は自分に自信を持たなくちゃいけないね」
「そんな……」
「そうやって謙遜する癖もよくないね。君はもっと堂々としていればいいんだよ」
そんなとりとめのない回想に浸る中、詩織は突然、腕を捕まれた。
「えっ!?」
振り返ると、派手な赤シャツに黒い背広(だいぶ草臥れていたが)を纏った長身の男が、ちりちりと細かいウェーブのかかった髪に片手を突っ込みながら、立っていた。
軟派なイメージだが、その目つきだけは、異様に鋭い。
「剛史……」
「よお。詩織。二日ぶりだな。元気にしてたか?」
詩織が何か答える前に、男はガムを咬みながら続ける。
「なあ、聞いてくれよ、詩織。今日はK花賞だったろ。ケンジの奴、何血迷ったんだか、3-4が来るとか言い出してよ、馬鹿野郎だよな。だから俺は2-8にしとけって言ったんだ」
「ねえ、剛史……こないだ渡したお金は?」
「残念ながら、オケラだよ。ケンジの奴のマヌケのせいでな。晩飯喰う金もねぇ。お前見つけて追っかけて、今ここん中に入るために使ったSuicaも残金20円だってんだから、しけてやがる。俺はほとほと運に見放された男だよな」
「そう……じゃあ、チャージしなくちゃ……」
そう言うと、詩織はバッグから財布を取り出した。それを剛史と呼ばれた男は素早くひったくる。
「あっ……」
「なあ、詩織。お前だけは優しくしてくれるんだろう?な?」
そう言うと、剛史は詩織のスーツの胸元から手を差し入れた。
「や……ちょっと……こんなところじゃ……」
「何。かまやしねぇよ。この街じゃ、みんな自分のことしか見ちゃいねぇからよ」
「ダメ……部屋に戻ってから……」という詩織の声も空しく地下道に響いた。
*
媚薬による意識の混濁。
津波のように押し寄せる快楽。
そんな朦朧とした中、高城一輝は、景山蓮のベッドの上で喘いでいた。
舞台は事務所のソファから蓮の寝室に移っていた。
その頃には、一輝の中に明確な意識は残されていなかった。
それは彼にとって幸い以外の何ものでもないだろう。
なぜなら、平生の彼が自らのそんな醜態を目にしたら、その場で舌を噛み切って自殺でもしかねないほどのものだったからに他ならない。
一輝はただ蓮を求め、蓮の要求を蓮自身を全てを飲み込み、蓮の言いなりとなって自らの身体を蓮に捧げた。
ようやく二人が眠りについたのは、既に朝日が昇り始めた頃だった。
「お目覚めですか」
目を開けると、景山蓮が微笑みを浮かべて立っていた。
開け放たれたカーテンから注ぐ陽の光を浴びる姿は、認めたくないが、この上なく美しい。
既に蓮は着替えを済ませていた。
一輝は痛む頭を振りながら、散らばった自分の衣類を引き寄せた。
「おはようございます。一輝様」
そう言うと、蓮は湯気の立つコーヒーカップをベッドサイドに置いた。
「そろそろお目覚めだろうと思い、お持ちしました。どうぞ」
「…………」
「昨日はずいぶん、乱れておいででしたよ」
一輝は蓮の戯言に答えず、衣服をまとうと、玄関に向かった。
「お帰りですか?お送りしましょう」
振り返りもせず、一輝は首を振った。
「困りましたね。一輝様のお車は事務所の駐車場ですよ。タクシーを使っては目立つでしょう」
「………………」
「愉快ですね。あなたは今や籠の中の鳥。私の一存であなたの存在は生かすも殺すこともできる」
そう言うと、蓮は一輝のうなじにキスをした。
「お忘れなのですか?あなたは、昨夜言って下さいましたよ。『私を愛している』と」
――――何です?はっきりおっしゃって下さい。でないとわかりませんよ?
――――……ぁ……あっ……。
――――何です?もう一度。ちゃんと教えて下さい?
――――おねが……い……。景山く……ん。
――――蓮で結構ですよ。一輝様。
――――蓮……。あっ……ああん……。
――――これが欲しいのですか?ふふ……タダでとはいきませんよ。私はちゃんとあなたに愛を告げた。だから、あなたも……ね?
――――あ、あいしてい……る……。蓮……。
「嘘だ……」
「嘘ではありませんよ。一輝様。あなたは確かに言って下さいました。それでもお疑いになるのでしたら、ちゃんと証拠もありますよ」
「証拠……?」
「ええ。私とあなたの愛の証……」
「まさか……君は……」
「言ったでしょう。あなたは『籠の中の鳥』だと。……愛しています。一輝様」
蓮は一輝を背中から抱き締めた。
今度は一輝も拒まなかった。
拒めなかった。
「まあ、そう慌てずに。ちゃんとお送りしますから。せっかく淹れたコーヒーが冷めてしまいますよ。どうぞ、ごゆっくり」
蓮はそのまま一輝の震える唇を奪った。
*
風ーー2015年4月6日10時23分 都内某所
「犯人は、あなたですね?」
探偵の朗々とした自信に満ちた声が広間に響き渡る。
探偵とは、事件という名の混沌とした闇に秩序をもたらす一筋の光明だ。
そして彼らが紡ぐのは、いつ耳にしても思わず聞き惚れずにはいられないその完璧なロジックに裏打ちされた真相。
その全てが語り終えられた時、この事件の真の闇・真犯人へとスポットライトが向けられる。
僕はこの瞬間に立ち会うのが、一番好きだった。
日常とは一線を画した非日常という名の一種のカタルシスを味わうことができるから。
その日も、探偵が指を突きつけた草臥れた中年男性の手に手錠が嵌められた。
その途端、男性の横に座っていた一人の婦人が金切り声を上げ、探偵を指さした。
「この家は、もうおしまいよ!!あんたの……あんたのせいだわ!!」
探偵は特に感情の表れていない端正な顔立ちを彼女に向けた。
「やれやれ、困ったものだ。あなたがこの私に今回の事件をご依頼なさった際に、私は問うたはずですよ?
例え、真相があなたに優しくないものだとしても、あなたに真実を知る覚悟が、おありになりますかと」
彼女――この家の夫人にして、犯人の妻は、悔しげに言葉を失った。
その間にも探偵は、
「私は私の職務を果たしたに過ぎない。失礼」
と身を翻すと、さっさと玄関へと歩を進めた。
僕はその背中を慌てて追いかける。
が、次の瞬間、探偵はふいにその歩みを止めた。
何かが探偵の背中にぶつけられたからだった。
それは、赤いハイヒールだった。
「この、疫病神っ!!」
その言葉とは裏腹に、涙でぐしょぐしょになった弱々しい声の主は、この家の長女、すなわち、今回の事件に真犯人の娘だった。
彼女の、いや、彼女たち家族の生活は、これから180度変遷を迎えることだろう。
セレブと呼ばれたある家族の凋落。
まさに、天国から地獄。
その元凶となったのは、探偵の推理から導き出された真相。
気持ちはわからないでもないが、元はといえば、当主である彼女の父親が自分の会社の金を使い込んだ挙げ句、それを知り、告発しようとした部下を殺害したからに他ならない。
お気の毒だが、自業自得というものだ。
探偵は振り返ることもなく、エントランスへと消えた。
よくテレビドラマでは、事件解決=一件落着、めでたしめでたしとなる訳だが、実際の事件では、そうはならない。
むしろ、暴き出された真相により、新たな悲劇が巻き起こされるのが常だ。
いつかどこかの名探偵が言っていたが、まさに「事件が終結した後からこそ、新たなドラマが生まれる」といったところだろう。
後味が良い事件なんて、三面記事で扱われる珍事以外、この世には存在しないのだ。
そう考えると、探偵という職業は余程、精神的にタフな人間にしか務まらないと思われる。
そういう面で言っても、目の前に対峙しているこの人物は、「名探偵」と言えるかもしれない。
皮肉なことに、屋内の暗雲とは裏腹に、ドアを開けると燦々とした日の光が照っていた。
「いいのか?あのままで」
「良いも悪いもなかろう。私の仕事は終わった。行こう」
「しかし……」
「終わったのだよ。右門君。ここから先は、我々の関知することではない。
我々は神から得た真実という天啓を知らしめているにすぎないのだからね」
探偵は、そう面白くもなさそうに嘯くと長い黒髪をさっと振り払った。
化粧っけはないのに、紅を差したかのようにほんのり紅い唇が目を引く日本人形のように美しい顔立ちに、小柄ながらすらりとしたプロポーションに黒衣がよく似合う。
左近風魔。
彼女は歴とした女流私立探偵である。
正確に言うと、彼女は僕と同じ大学院生なのだが。
「さあ、右門君。帰って暖かい紅茶でも飲もう」
*
月ーー2009年4月6日11時42分 国会議事堂
「一輝様?」
第一秘書・楠美香子の問いかけに、はっとして顔を上げると、そこは議事堂内の赤絨緞の上だった。
今は選挙中だが、外務副大臣のポストにいた一輝は、行政官としての職務引き継ぎのため、国会に出入りすることも
しばしばだった。
「どうされましたか」
美香子の心配気な眼差しが刺さる。
美香子は少しでも異変を感じると、敏感に察知するところがある。
一輝が身体を壊してからはそれが顕著だった。
「いや、何でもないよ。今日のスケジュールを頼む」
そう微笑んだ一輝の背後から声が上がった。
「高城君じゃない、お久しぶり」
そう手を振りながら赤絨緞を軽やかなステップで踏み締め近づいて来るのは、甲賀明美。
一輝と同い年という若さにも関わらず、総選挙での国民改新党の最大のライバル・社会民政党の党首を務める女流政治家である。
ボーイッシュな容姿の明美は、その見た目通りの裏表にない性格で、女性ながら弁が立ち、ハキハキとした物言いをする。
決して二世などではなく、高校時代から新聞配達で学費を稼ぎ、実家は平凡な商店街の精肉店というハングリーさが有権者の支持を集める要因なのだろう。
実は一輝とは同級生で幼馴染みであるということはあまり知られていない。
「ああ、久しぶりだね、君も元気そうで何より」
「本当にお久しぶりよ。あなた、国民改新党の顔だって割にちっとも討論番組に出てくれないんですもの」
「僕かい?僕なんかじゃ君に太刀打ちできないよ。収録前に楽屋から逃げ出すのがオチさ」
「いやあね。人を化け物みたいに。まあね、あなたがリングに上がったら、それこそ容赦しないけど」
「ほら、やっぱり。僕にとって、君は鬼門だね」
「まあ、ひどい。……でも、よかった」
「えっ……?」
「あなた、今、なんだかすごく思いつめたような顔してたから。顔色もあまりよくなかったし。……でも、私の考えすぎだったみたいね」
昔から明美は人の内面を見透かすところがあった。
そして、そうして感じた人の痛みを自分のことのように受け止め、時に一緒に涙し、時に一緒に戦う。
そんな姿勢を持っている少女だった。
彼女の人望は、そうした面がもたらしたものが多い。
だが、明美はいつも一輝の内面には深く入り込もうとはしなかった。
いや、できなかった。
それは、そんな明美から一輝が自らを徹底して閉ざしたからに過ぎない。
二人は大の仲良しだった。昔から二人でよく政治論を戦わせていた、言わば同志だった。
だが、一輝は決して自分の内面を明美に晒そうとはしなかった。
それは、明美を拒むなどという訳ではなく、ただ一輝自身が己の内面を他人に晒すことを潔しとしないから。
そして、明美が自分を友人以上として捉えていることも重々承知していたからに他ならなかった。
一輝はそんな明美の気持ちを察しながら、気がつかないふりをして過ごしてきた。
明美も同じようにただの友人として彼に接してきた。
彼らは互いに怖かったのだろう。
友人という関係がその砂の城のように脆い関係がどちらかの口火によって壊れてしまうことを。
一輝は考える。
特に今は彼女に自分の心のうちを見破られるのは得策ではない。
自分の体調面のことはもちろん、父の秘書に犯されたことなど……。
一輝は笑顔を作った。
政治家となってから、作り笑いは彼の日常に溶け込んでいる。
自分の内面を見透かされないように煙幕を張るのも実に手慣れたものだった。
政治家となって自分が得たのは、そんなものだけ。
時折、一輝はそんな自分をうとましく感じていた。
だが、わかっていてもどうにもできない自分もそこにいる。
「あ、ああ。君はサバサバしている割にどうもそういうことには目敏いね。だが、さすがの君の勘も外れだね。僕は何も思いつめてなんていないさ。確かに少々選挙戦では疲れているがね。それだけさ」
「そう。……それならいいんだけど、あなた、昔から溜め込むとこあるから。適度に肩の力抜いた方がいいわよ」
「ご忠告、ありがたく受け取るよ」
「ああ、引き留めてごめんなさい。お互い正々堂々最後まで頑張りましょう。じゃあね」
事務所に戻り、何気なくつけたテレビの中の先日東京駅で行われた演説のVTRを見て、一輝は愕然とした。
確かにあの時、自分はカメラに向かって訴えた気がする。
それは決して国民改新党への支持でも、自分への支持でもなく、ただ救いを。
そう。そのカメラの向こうにいるであろう一人の少女に向かって。
ある意味、その時の彼にとって、それは完全に無意識の行動だった。
まさか、自分がこの瞬間、こんな表情をしていたなどとは、想像もつかなかった。
だから、愕然とした。
もう自分はそこまで追い詰められているのかと。
彼は確かに求めていた。
ただ、ひとつの救いを。
決壊しそうな自分を救う一筋の光明を。
彼はゆっくりと目を閉じると、小さく呟いた。
在りし日の少女の幻影を瞼の裏に思い描きながら。
その愛しいシルエットに向かって。
「君は今、どこにいる?」
*
華ーー2015年4月6日13時24分 TTV報道局
鏡芙美華の命を受けた大河内チーフディレクターの命令で、今宮明日香が不動充の取材に当たることになった(洒落じゃないぜ?念のため)。
元々明日香は不動を狙っていたらしく、喜んで引き受けたようだった。
が、芸能デスクのカメラマンたちは、某アイドル歌手の突然の結婚会見のため、出払っているらしい。
そうなると必然的に……。
「だから、なんで俺がお前のお供としてカメラ回さなきゃならねぇんだよ?」
不満タラタラな俺に、アラレはさらりと言った。
「そら、遠山颯人。あんたがカメラ回すしか能がないからに決まっとるやないの」
「あんだと!?」
「ほんまのことやないの。あんたにインタビューなんかできるわけあらへんやん。インタビュー言うんは、ほんまに難しいことなんやで。相手の気を引きつつ、こっちが聞きたいことを切り込んでいかなあかんのやから。インタビューは繊細なんや。あんたみたいにおおざっぱな輩には向かん」
「何がインタビューは繊細だ。お前のどこが繊細なんだよ。お前くらいガサツな女みたことないぜ?お前にできることが俺にできないはずがないだろ?」
「ほお~。言うたな?」
「ああ、言ったぜ?」
アラレはにんまりと笑った。
「せやったら、見せてもらおうやないの。あんたの力量って奴を」
「あ?」
「今回のインタビューはあんたに任せたわ」
「な、なんだよ、それ」
「そのままの意味やで。あんた一人で取材に行って来たらええやん」
「なんだと?」
「そんなに自信があるんやったら、うちに遠慮せんと、ちゃっちゃとインタビューして来てみなはれ」
「ああん!?」
「そやな。あんたがあの不動充から晴れてインタビューを取って来れた暁には、一ヶ月間、うちはあんたの召使いにでもなんでもなってやろうやないの。その代わり、あんたがインタビューに失敗した場合は、あんたはこれから一ヶ月、うちの専属カメラマンとして働いてもうらう。どや?おもろい賭けやと思わへん?」
アラレはにんまりと唇の端を上げると、ニャロメのような笑みを俺に向けた。
ここで引いたら男が廃る。
「ああ、いいぜ。やってやろうじゃないか」
「ほっほ~。受けて立ったな。遠山颯人。おもろいことになったなあ。あ、ひとつ忠告しといたるわ。不動充言うたら、うちら芸能関係者では、『眠れる獅子』言う二つ名で呼ばれとるんや」
「は?」
「つまりな。不動充言う男はず~っと取材陣からの攻撃にも全く動じず、口を開いたことがない。ノーコメントを貫き通しとるんよ。動かざること山の如し……語らざること貝の如しってことや。ま、せいぜいおきばりやす~」
聞いてねぇぞ!?いきなりハードル高すぎじゃねぇか!!
ちょっと待てよ?
今回俺が晴れて不動充の取材にこぎ着けた場合、芸能ゴシップとは無縁の報道カメラマンである俺には取材上、何のメリットもない。
なんだかんだと芸能デスクであるこいつの手柄になる訳で……。(それは、一ヶ月間俺の雑用係をやることとは引き替えにならないくらいの手柄だろう)
そして、当然、俺が失敗しても、こいつは痛くも痒くもない。(まして、俺を公然と扱き使えるだろうし)
まして、俺は不動の何を取材すべきなのかさえ、知らない。
「アラレ……てめぇ……図ったな」
「あら~?うちは親切に忠告してやっただけやん。はは~。ま、健闘を祈っとるで~」
*
華ーー2015年4月6日15時03分 都内某ホテル
都内某ホテルの一室で、ひと組の男女が一糸まとわぬ姿で宴を繰り広げていた。
「で?高城大先生は、愛息である一輝氏を使って次はどんな手を打つつもり?」
そう吐息交じりに髪をかきあげると、鏡芙美華は、自分の下になっている男を艶めかしい視線で見降ろした。
「さあ?どうされるのでしょうねぇ」
下になっている男――景山蓮は、汗ばむ芙美華の乳房に愛撫する。
「いじわる。あなたって、どうしていつもそうやってはぐらかすのかしら。他の相手だったら、みんな簡単に口を開いてくれるのに」
「だって、面白くないでしょう?私が簡単に口を割ったら、あなたとこうしていられる時間が少なくなるだけだ」
そう言うと、蓮は芙美華の肌に口付けた。
「時間だわ。残念ながら、お開きね」
そう言うと、芙美華は蓮の身体を押しのけ、ベッドをすり抜けた。
蓮は芙美華の滑らかな裸体の後姿を横目に見ながら、タバコに火をつけた。
「そんなに聞きたいのだったら、私のようにベッドにお誘いして大先生ご本人に聞いてみてはいかがでしょうか。それとも、一輝先生を落としてみますか」
「あなたって、本当にいじわるね。それが無理だってこと、全部承知の上でそんなこと平気な顔して言うんだから」
「次のお相手は誰です?」
芙美華は、ちらりと蓮を振りかえったが、曖昧に笑っただけだった。
「M党のY氏ですか」
その瞬間、ストッキングを足に絡めた芙美華の手が止まった。
蓮が満足げに微笑んだ。
「私の情報網もなかなかでしょう?あなたには及びませんけれど……」
芙美華は、ストッキングを放り投げた。
「来て」
「どうされました?」
「次の相手はキャンセルよ。今は……あなたが欲しい」
そう言うと、芙美華は蓮のタバコを弾き飛ばし、彼に抱きついた。
*
華ーー2009年4月6日16時32分 都内某マンション
ターゲットは都内でも有数の高級住宅街。
その中でひときわ高くそびえる一棟のビルディング。
煉瓦色に染められたそれに愛車のバイクを横付けする。
それにしても、ホテルかと見紛うばかりの豪奢さ。
マンションというよりは、億ションか?
自分の安アパートとの差が無意味に頭を掠める。
だいたい、俺は何しにここに来ているのだろう。
俺は世間で言うところの常識がないから、一体どうして不動充という男が芸能デスクにとって金の成る木なのか、さっぱりわからない。
俺の資料と言えば、ついさっき予備知識を仕入れるために手に入れた週刊誌だけだ。
なんでも、保険金殺人がどうのこうのといった内容だった。
からっきし、興味が沸かない。
俺は報道が特集する事件でも、金銭がらみの殺伐とした奴は嫌いだ。
男女の痴情のもつれって奴もご免被る。
俺が追いかけたいのは、某政治家の汚職だったり、企業の裏にはびこる巨悪だったり……まあ、社会悪なのだ。
今回のネタは、あの我らが鏡芙美華が目を付けるくらいだから、相当な金脈には違いないのだろうとは思うのだが。
いずれにせよ、俺にはどうでもいい話だ。
だた、取り敢えず、明日香との賭けにだけは勝たなければならない。
俺自身のちっぽけなプライドのために。
俺は宅配業者を装って、オートロックという名の第一関門を突破した。
まさか、こんなところでバイト時代のお古のジャンパーが役立つとは思わなかった。
カメラマンというよりは、探偵にでもなった気分だ。
俺は無事に目的のドアの前に着くと、呼び鈴を鳴らした。
反応がない。
俺は再び宅配業者を装い、隣の家に探りを入れることにした。
呼び鈴を鳴らすと、すぐに化粧臭い有閑マダムが顔を出した。
「あら。不動さんだったら、お出かけされたわよ。ついさっき。あなたと入れ違いかしら。残念ねぇ」
マジかよっ!?
俺はいきなり出鼻をくじかれ、つんのめりそうになった。
俺のこの燃えたぎるソウルはどこへ持って行けばいいのよ?
俺は「あ、運送屋さん、実はお願いしたい荷物があるのよ~」という声を遮りドアを閉めると、思わず、不動充の部屋のドアに拳を叩きこんでいた。
「いってえええええっ!!」
鋼鉄のそれに叩きつけた拳からギンギンに痺れる反動が叩き込んだ倍以上の力で返ってきやがった。
踏んだり蹴ったりとは、このことか。
俺は自分のついてなさを呪った。
さて、どうしたものか。
ああしてタンカ切って出てきた手前、何らかの収穫を手にしなければ、帰るに帰れない。
俺にだって、プライドというものはあるんだ。
その時、世にも不思議なことが起こった。
たった今、己の拳を叩きこんだドアがゆっくりと開いたのだ。
俺は、ドアが仕返しにでもしにきたのかと本気で身構えた。
だが、ドアはギィッという耳障りな音だけを響かせて開いた訳ではなかった。
「不動さん、忘れものですか?」
というどこかか細いが可憐な声も引き連れていたのだ。
「えっ……?」
目が合った瞬間、俺たちは、同時に声を上げていたと思う。
次の瞬間、麻痺しかけた俺の鼓膜に響いてきたのは、
「あああああっ!!どうしよう!!」
という猛烈な相手の叫びだった。
どうしようと言われても、俺だってどうしていいのかわからない。
野郎の寂しい独り暮らし、しかも、ご当人は外出中。確実に無人だと思っていた部屋のドアから、いきなりこんなに可愛らしい女の子が現れたのだから。
相当若い。
高校生か?
腰まで届くのではないかというくらいに長い髪を揺らし、人形のようにぱっちりとした瞳をこれでもかというくらいに見開いている。
とにかく、俺はその少女が放つ可憐な不意打ちをくらい、ノックアウト寸前だった。
彼女は俺のそんな動揺にもおかまいなしに、上目遣い(この仕草もなんとも言えず、可愛らしい)で俺を見上げると、消え入りそうな声で言った。
「あ、あのう、私のことは、見なかったことにして頂けないでしょうか」
俺はさすがに面食らった。
「見なかったこと」とは、どういうことだ?
「それはできない相談だ。俺も、君みたいに可愛い子のこと、見なかったことになんてできないからね」
俺は気がついたら、そんな軽口を叩いていた。
*
月ーー2009年4月6日16時43分 国会議事堂前
国民改新党選挙対策委員会からの帰り道。
赤絨毯を踏み締め歩く高城一輝の背後から、秘書・楠美香子の声が響く。
「本日の予定は以上ですわ。一輝様。お車でお送り致しましょうか」
「いいんだ。選挙事務所に用事があるし、少し、一人で歩きたい。車は君が乗って行ってくれてかまわない。自分の車で帰るから」
一輝の選挙事務所は、議事堂から徒歩10分程度のところに構えられていた。
彼の愛車も今はそこで主の帰りを待っている。
美香子は、
「明日は久々のオフですね。ごゆっくりお休みになって下さい」
と寂しげに微笑んだ。
「ああ、選挙戦の真っ最中だからね、心底ゆっくり休めるかわからないが……。
ラストスパートのためにも英気を養ってくるさ」
一輝はそう片手をあげると、議事堂を後にした。
夕暮れの永田町は、人通りが少ない。
警備に当たる警官の姿がちらほら見えるだけだった。
ふと一輝は、歩みを議事堂近くの国立国会図書館に向けた。
久々の休日を共にする書籍を探そうと考えたためだった。
学生時代の自分は、呆れるくらいに本の虫だった。
だが、外務省勤務、こうして国会議員になってからは、呆れるくらいに本と縁遠い生活になっていた。
多くの作家から著作本を贈られることも多いが、その量が多すぎて、どれから手をつけてよいのかわからない。
何より、すべてに目を通す時間がない。
そうなると、必然的にそれらを選別することになる訳だが、せっかく贈られた本をそうして篩いにかけてしまうというのは、なんだか申し訳ない心持ちになる。
結果的にどの本にも手が延ばせなくなっている自分に気づく。
それがなんだかやりきれなくて、本という存在から遠ざかっていた。
だが、その日は無性に書籍に触れたかった。
どんなものでもかまわないから、活字というものに触れたかった。
活字というか、どこか「静的」なものを彼は欲していた。
選挙戦という荒波のような「動的」な日々の中で、彼は安らぎを求めたのかもしれない。
「高城先生ではありませんか」
そう声をかけられたのは、国立国会図書館の門をくぐった時だった。
一輝が振り返ると、そこにはサングラスをかけた一人の男がいた。
「高城一輝先生ですよね?」
相手はサングラスをかけ直しながら、再度問うた。
「はい。そうですが」
一輝は、こうして声をかけられることは特に珍しいことではなかったので、笑顔で答えた。
案の定、相手もにっこりと微笑み、
「私、高城先生を応援しているんですよ。今度の選挙でも、小選挙区は高城先生、比例区は国民改新党に入れようと思っているんです」
「それは、ありがとうございます」
「客」の出現に、一輝は頭を下げた。すると、男は、
「あ、先生、ぜひ、握手をお願いします」
とゆっくりと両手を差し出してきた。
一輝は、その手を握り返そうとしたが、次の瞬間、みぞおちの辺りに鈍痛を感じた。
彼はは声も上げずに崩れた。
*
華ーー2015年4月6日16時55分 都内某マンション
彼女=謎の美少女は、俺を部屋に招き入れると、律儀にお茶を運んできた。
こんな風にされると、逆に恐縮してしまう。
だいたい、何をどう質問したらいいのかわからない。
あの時は、場の流れでつい一人で飛び出してしまったが、冷静になって考えてみると、こうして単身で取材活動などしたことはなかった。
流れるように質問をし、するすると相手の回答を引き出してしまう明日香の才能に、不本意ながら感心せざるおえない。
それにしても、目の前の少女は一体何者なのだろう。
当然、恋人……ということか。
あの野郎。硬派な顔してこんな年下の子と同棲なんてしてやがったのか。
この子が学生だったら、犯罪だぞ?
俺は写真でしか知らない不動の顔を脳裏に描くと、またふつふつと煮えたぎる何かを感じ、拳を固めた。
が、目の前の少女のどこか不安げな視線にぶつかり、俺は慌てて拳を隠した。
「まず……自己紹介しようか。俺は遠山颯人。TTVの報道カメラマンだ。別に怪しいもんじゃないぜ」
怪しい者ではない……という奴ほど怪しいか……。
俺は今更ながらしくじったと感じたが、少女は少し緊張感を和らげたようだった。
俺の言葉を額面通り受け取ったのか。
今時珍しいくらいに素直な子だ。
「あのう、私は雪です」
「雪……?それが君の名前?」
「……はい」
それにしても、この子は何者なのだろう。
考えてみれば、不動は芸能プロダクションの経営者だ。
この子は、奴のとこの新人アイドルか何かかもしれない。
そう言えば、不動は自分のところからデビューさせている新人アイドルを手当たり次第に喰っているって話だった。
デビュー前に「味見」しているなんてとこか。
ああ、さすがに察しがついてるか。そ。これも週刊誌の受け売りだよ。
俺は取材のいろはなんてわからない(知っていてもそんなまどろっこしい駆け引きなんか願い下げだ)から、取り敢えず、そのままストレートに聞いてみた。
「私ですか?そんな……恋人とか、そんなんじゃぜんぜんありませんよ。私、居候なんです」
「居候……?」
「はい。私、いつもお家賃半分払いたいって言っているんですが……不動さんに受け取ってもらえなくて」
一瞬、俺は彼女の回答を冗談だろうと受け取った。だが、彼女の申し訳なさそうな顔は、それが真実だという何よりの証拠な気がした。
「居候って……君、不動さんの親戚かなんかなの?」
「いいえ。私、不動さんとはそういうつながりはないと思います。……たぶん」
「たぶん……?」
「とにかく、私と不動さんがそんな関係なんて、本当にありません。うふふ……。彼、私のことなんて、そんな風に見て下さいません」
彼女はそう微笑んだ。心なしか寂しげな微笑みだった。
「恋人でもないのに、一緒に暮らしているのかい?」
彼女はただ、こくんと頷いた。
不動というのは、どれだけストイックな男なのだろう。
こんな綺麗な子が一つ屋根の下にいるなんて、俺だったら、正直、理性が持ち堪えられるか自信がない。
「あの……さっきのお話なんですけど」
「ん?」
「私のこと、誰にも言わないで頂けませんか?お世話になっている不動さんにご迷惑……おかけしたくないから……」
「それは……まあ、君が困るなら、俺も誰にも言わないが……どうして君はここの厄介になっているんだ?」
「私、帰る場所がないから……」
「ご両親とかは……いないの?」
「わかりません」
彼女はそう悲しげに目を伏せた。
この様子だと、恐らく両親とは死別か生別かしたのだろう。
だが、そのいずれにしても「わかりません」という返答があるだろうか。
さっきの「たぶん」と言い、この子の返答にはどこか釈然としないものがある。
どこかうまく噛み合わないというか、妙な居心地の悪さを感じる。
彼女自身は精一杯俺の質問に誠実答えようとしている。
その気持ちは痛いほど感じるのだが、(彼女の場合、俺が相手だからというのではなく、元来、そういう性格なのだろう)どこか発せらる答えは、俺に響いて来ないのだ。
まるでプログラムされた回答を吐きだすロボットと会話をしているような。
その正体は一体何なのだろう。
俺は嘘のつけない男だ。
腹芸なんてできない。なんでも思ったことが顔に出てしまう。
ガキの頃からそういうとこが不器用で、いろいろなものを失くした気がする。
だが、俺はそんな自分のことを嫌いじゃない。
だから、俺は思ったことを口にしていた。
「君、本当のこと言ってないね」
少しの沈黙が俺たちの間に降りた。
やがて、目の前の少女は、伏し目がちだった瞳を上げた。
「私……記憶がないんです」
「えっ……?」
「だから、不動さんと出会う前のこと、何一つわからないんです」
記憶がない……だと?
それは、所謂、記憶喪失という奴か。
そんなのドラマや小説の中でしかお目にかかったことがないが……。
「じゃあ、君は君自身が誰なのかもわからないのか?」
「はい……。この『雪』という名前も不動さんが付けて下さったんです。……不動さんのお話では、私、一ヶ月くらい前にこのマンションの前に倒れていたらしいんです。不動さんに助けて頂く前のこと、私何も覚えていなくて……私、自分がどこの誰なのかも何もかも……わからないんです」
「そう……だったのか。ごめん。悪いことを言った。嘘つき呼ばわりして……すまない」
「いいえ……いいんです。おかしいって思われるの当然ですよね。それに、今、遠山さんが言ったこと、間違ってないです。だって、この名前だって……『嘘』……なんですから」
彼女はそう言うと、少し微笑んだ。
微笑みというよりは、泣き笑いだった。
自分がどこの何者なのかがわからない。
それくらい心細く、恐ろしいこともないだろう。
彼女はその事実と向き合い……いや、無理矢理向き合わされて、こうして見ず知らずの男の保護を受けて細々と生きている。
俺はもう彼女の顔を見ていられなかった。
言いようのない罪悪感が胸を締め付ける。
「そんな言い方……止せよ。わからないから別の名前を名乗っている……それだけだろう?そういうのは……『嘘』とは言わない」
「ありがとう……ございます……。不動さんがいなかったら、私、きっと生きていなかったと思います。今、こうしてあなたとお話することもできなかったと思います。だから、私、すごく不動さんに感謝しているんです。こんな私の面倒を見て下さって……。それに、あなたに出会えたこともすごく嬉しいです」
「えっ……?」
「私、記憶を無くしてから不動さんしか知り合いがいなくて……新しい人と出会えて、なんだかすごく嬉しいんです。それに、遠山さん、すごく綺麗な目をされてるから。きっと私との約束、守ってくれるって、私、信じています」
俺も不動に感謝しなくてはならないのかもしれない。
奴がいなければ、彼女、『雪』と出会うこともなかっただろうから。
*
月ーー2015年4月6日17時14分 某埠頭
気がつくと、高城一輝は冷たいコンクリートの上にいた。
遠くで海猫の鳴く声が聞こえる。
「お目覚めですか。高城先生」
聞き覚えのある声にゆるゆると首を動かすと、サングラスの男が口元を歪めて立っていた。
男の背後に気配を感じた。
一人や二人ではない。
「彼ら」は一体何人いるのか、薄暗い倉庫の中のため、判別がつかなかった。
一輝は身体を起こしながら、必死に頭を巡らせた。
この男どもは誰の息のかかった者達なのか。
脳裏を過る候補があまりに多すぎて判断がつかなかった。
一輝は自嘲気味に笑った。
考えてみるれば、自分は敵が多すぎると。
とにかく、彼は悟った。
自分は罠にかかったのだと。
「誰に頼まれた?不毛な質問だったかな?そう聞いても君たちは答えてくれないだろうからね」
「まあね。誰かは言えないが、契約内容くらいは教えてやろうか。
あんたをやれば、百万って契約なんだ」
「百万か……随分安く見積もられたものだね。私の命の値段も」
「命?あんた、なんか勘違いしてねぇか?」
「えっ?」
「俺だって、百万ぽっちじゃ殺人まで請け負わないぜ?」
「やる」とは、「殺る」という意味ではないのか?
では、一体……?
「男なんて冗談じゃないって思ったんだけどな。最初は」
「何……?」
「テレビで見るより、ずっと綺麗だね。アンタ」
「何を……考えている?」
「こんな綺麗どころが政治家の先生だってんだから、困るな」
「信じられないな。女でもこんな上玉、なかなかお目にかかれないぜ?」
「まったくだ。たまらんね」
男たちが次々と口を開く。
「何を……する気なんだ?君たちは……?」
「困ったな。先生はとんとおわかりになっていないようだぜ?
まあ、すぐに感じるだろうが。その身体で」
そうせせら笑うと、男は顎を引いた。
その瞬間、いつの間に背後に回っていたのか、別の男が一輝に背後から羽交い締めにした。
「うあっ!!い……いたっ……痛いっ!!」
「手荒な真似はよしな。先生、痛がっているじゃねぇか。
まあ、そういう顔も悪くないがね」
「何の真似だ?君たちの目的は何なんだ?うわっ!?」
瞬く間に背広を奪われ、一輝はつんのめるように体制を崩した。
その身体を受けとめたのは、サングラスの男だった。
「いい背広だね。センセイ。さすがだよ。いい手触りだ。
でも、あんたのその肌の方がいい触り心地なんじゃないのかい?」
「やめろ……!!触るな!!」
一輝がそう身体をひねらせた瞬間、何かが一輝の唇を塞いだ。
それは、サングラスの男の唇だった。
「やめろ!!」
一輝は力いっぱい、その唇を突き離した。
「いい味だ。思った通り。先生、あんた、サイコーだよ」
一輝の脳裏に蓮との秘め事が過った。
悪夢のようなその出来事が。
「や……やめてくれ……」
「俺、ともだち多いからさ。選挙の時の票稼ぎにも悪くないと思うよ。
まあ、あんたの奉仕次第だがね」
「そ。おとなしく観念しようよ。ね?せんせい?」
彼を取り囲む、無数の赤い光。
それは、欲望に目を血走らせた無数の男たち。
一輝にもようやくわかった。
もはや彼は、狼の群れに投げ込まれた憐れな一匹の白兎だということが。
*
既に半裸にむかれた高城一輝は、ウインチで逆さに引き上げられ、その肢体を男どもの好奇の目に晒されていた。
その白い肌には、愛撫による無数の鬱血が見られ、鎖できつく縛りあげられた両手足首からは、鮮血が滴り落ちていた。
逆さにされてもうずいぶん経つ。
頭に全身の血液が降りてくる音が聞こえて来るようだった。
「いいザマだな。先生。どうだい。御気分は?」
一輝は自嘲気味に笑うことしかできなかった。
「さっきの愛撫でだいぶ感じてきたみたいだからな。今度はもっと楽しませてくれるんだろう?」
一輝は答えない。
そんな一輝の唇を男は貪る。
「……んっ……んあっ……」
唇を重ねたまま、一輝の身体はゆっくりと地上に戻された。
サングラスの男はそのまま唇を下降させていく。
その動きに合わせ、一輝の身体がびくんと反応していく。
男はその反応に満足そうに笑うと、一輝の胸の飾りを舐め上げた。
「あっ……!!」
一輝の身体がのけ反ると、男は指先で一輝のもう一方の胸の飾りを弄んだ。
「あっ……!!ああっ!!」
別の男が一輝の両足を取った。鎖が外される。
だが、それは解放を意味してのことではなかった。
引き裂かれるように両足が開かれると、別の男が一輝自身を咥え込んだ。
「ひっ!!あっ!!やっ!!だ、だめ!!」
「何がダメなんだい?先生」
「ああっ!!ああん……!!」
「いいね。先生自身のイイんだろ?こんなに勃ってんだから」
「あっ……あぁ……こんな……」
こんな屈辱を……。
なぜ?
なぜ、自分が?
自分が高城一輝だからか。
政治家・高城一輝だからか。
この時ほど、一輝は自分の職務を恨んだことはなかった。
自分は決して国民改新党の客寄せパンダになりたかった訳でも、こうして複数の男どもに辱められたかった訳でもない。
ただ、この国の未来を少しでも変えていきたい。
自分の手で未来に希望が持てる国を造っていきたかったからだった。
それだけだったのに。
皮肉なことに発作の代わりに自分の身体がびくんびくんと波打つように感じていた。
もし、発作が起きて自分が死んだら、自分はこうして恥辱を晒した状態で発見されるのだろうか。
明らかに男達から性的暴行を受けた痕跡を己の身体中に刻んだまま。
一輝は言いたかった。
『君たち、ことが終わったら、自分の身体は簀巻きにでもして東京湾に沈めてくれないか』
と。
この醜聞が誰かに知られるくらいなら、このまま東京湾の藻屑となった方がどれだけ幸せなのだろう。
だが、空しくそんな訴えも、吐息にしかならなかった。
「いい声じゃねぇか。先生よぉ?もっと鳴けよ」
殺られる。
そう。
殺された方がどれだけマシだというのだろう。
それから一輝は何度も犯された。
何度も何度も。
気がつくと、自分に入り込む男が変わっていた。
これが、何人目なのだろう。
そして、あと何人続くのだろう。
果てしない無間地獄。
いつしか、一輝は積極的に男たちを受け入れていた。
恐らく、彼の脳がこの「屈辱」を「快楽」に変換した方が「幸せ」だと判断した結果なのだろう。
一輝は声を上げた。
「もっと……もっと……激しく……して……」
*
風ーー2015年4月6日18時56分 都内某マンション
その日、午前中だけの講義を終えた僕は、だらだらと研究室で過ごした後、左近風魔の部屋を訪ねていた。
風魔は僕の隣の部屋に住んでいる。
このマンションは、僕が言うのもなんだが、普通の学生だったら、まず手が出ないだろう高級物件だ。
どうして僕がそんないい部屋に住めているかと言えば、答えは簡単で、このマンションのオーナーが叔父だからという一点に尽きる。
僕はこうしたコネクションを持っているからまだわかるのだが、風魔がどうしてここに住むことができているのか、さっぱりわからない。
確かに彼女は私立探偵という職を持っている。
だが、この職は収入とは無縁と考えて間違いない。
なぜなら、風魔は探偵業で金銭を受け取らないからだ。
そう考えると、彼女は僕と同じ、単なる大学院生ということになる。
まして、彼女は他にバイトをしている様子もないから、どこから収入を得ているのか、皆目見当がつかない。
いつか風魔は特待生だという話を聞いたので、学費は支払っていないのかもしれない。
だが、生活費の出所がさっぱりわからない。
親戚の誰かが仕送りでもしているのかもしれないが、今のところ、そういった影は全くちらつかない。
彼女はいかにしてこの生活を維持しているのか……。
僕がそんな取り留めない思考を巡らせていると、待ち人・左近風魔が現れた。
が、僕はその瞬間、口に含んだ紅茶を盛大に噴いていた。
そこには、左近風魔が立っていた。
一糸まとわぬ生まれたままの姿で。
僕は完全に硬直していた。
当たり前だろう。
彼女の、まるで彫刻のように滑らかな肢体が、眼前に惜しげもなく披露されているのだから。
「なんだ。そんなに人間の裸が珍しいのか」
「き、き、き、君はどうしてそんな格好をしているんだっ!?」
「ここは私の家だ。私がどんな格好でいようと何をしていようと、君にとやかく云われるような筋合いはない。だいたい、君が勝手に私のテリトリーを侵しているだけじゃないか」
そう言うと、彼女はうるさそうに長い髪をかき上げた。
その拍子につんと上を向いた形の良い乳房が揺れる。
そんな姿が、目のやり場に困るくらいに悩ましい。
僕は一応、目をそらしつつ、答える。
「そういう問題じゃないだろう?僕は男で君は一応、女じゃないか」
「何を今更わかりきったことを言っている?私はただ自宅でシャワーを浴び、寛いでいたところだ。闖入者は君だぜ?だから、聞いている。『そんなに人間の裸が珍しいのか』と」
そう言うと、彼女はいつの間に現れたのか、彼女の着替えを差し出した「執事」からそれを受け取ると、ブラを身につけた。
だいたい、この「執事」がくせ者なのである。
「執事」と言っても慇懃な老紳士を思い浮かべてもらっては困る。
僕より少し年上か、下手したら同い年か?というくらいに若い青年なのである。
風魔との付き合いももう一年になるが、僕はこの青年の下の名前さえ知らない。
「だいたい、君。そんなことを言い出すなんて、よこしまな精神の現れじゃないか」
そう風魔はにやりと笑うと、僕を見下すように見下ろした。
思わず、「よこしまで何が悪い」と叫びそうになったが、あまりに自分がみじめなのでやめた。
だいたい、風魔みたいに非の打ち所がないほど完璧に整った顔立ちや、体つきを目にすると、かえって気持ちが萎える。
恐れ多いとでもいうのだろうか。
誤解してもらっては困るのだが、僕は決して左近風魔に好意などを寄せてなどいない。
むしろ、嫌っていると言った方が正確だろう。
では、一体なぜ僕が彼女と行動を共にしているのか。
それは、彼女に返さなければならない借りがあるから。
ただ、その一点だ。
僕は一年ほど前、彼女に助けられた。
どんな件だったのかは、少し長くなるので、ここでは語らない。
追々、お知らせしようと思う。
まあ、今の段階では、僕はその件で左近に救われた。とだけ理解してもらえれば十分だ。
その恩をそのままにしておいては、寝覚めが悪いではないか。
彼女と一緒に行動しているのは……ただ、それだけだ。
だいたい、彼女は性格が全くかわいらしさに欠ける。
僕だって、確かに容姿はまあ、可愛い方が嬉しいが、見た目よりも性格が可愛らしい子の方がずっといいと思う。
それに、どういう訳か、彼女は黒衣しか身につけない。
一緒にいると、いつも喪中みたいで気持ちが萎える。
女の子だったら、もっと可愛らしいパステルカラーなんか着こなしてもよさそうなものだと思うのだが。
まあ、僕がそんなこと考えても意味がないことは重々承知しているが、なんとなく考えずにいられない。
僕は自分でも嫌になるくらいにお節介な性格なのだ。
僕がこうして悶々と思い悩んでいる間にも、風魔は着替えを終え(相変わらずの黒衣だ)、僕の向かえに腰を下ろした。
その途端に、「執事」の青年が、湯気の立つティーカップを風魔の前に差し出した。
「ありがとう。黒崎。で、今日は何の用だね。右門君」
「風魔。どうして君はいつもそんな喪服みたいな格好なんだい?君は同じ年代の女性たちが当たり前に持つはずの、オシャレという概念をどこかに置いてきてしまったんじゃないのかな」
僕は幾分、皮肉を込めて言ってみたのだが、あっさりと打ち返された。
ホームランで。
「右門君。愚かだね。君も」
「は……?」
「いいかい、私は探偵だ。探偵というのはね、時に死に遭遇し、死者を哀れみ、死者の声を聞かねばならない。そんな冥界の使者である私がパステルカラーの服装をまとえるとでも思っているのかい?」
「………………」
「私はいつ何時であろうと『探偵』なのだよ。どうかな。君の愚鈍な脳みそでもそろそろ探偵という職業が理解できてきたのではないのかな」
そう言うと、風魔はチャシャ猫のような嫌な笑みを浮かべて悠々と紅茶に口付けた。
こいつ、いつか殺す……。
*
月ーー2015年4月6日19時44分 某埠頭
政治家・高城一輝が連れ込まれた海沿いの倉庫では、歪んだ遊戯が繰り広げられていた。
一輝への愛撫に飽きた男達は、一輝を「玩具」としてゲームを始めた。
順番に一輝の身体スレスレにナイフを突き刺していくというものだった。
ルールはただひとつ。
一輝の素肌を傷つけず、より近くに突き刺したものが勝者。
三度ナイフを振り下ろした合計点で争われる。
丁度、猫が獲物として捕らえた鼠をすぐには殺さず、いたぶるように。
既に一輝の身体には、ナイフを打ち損じた男たちの手による傷が変色しつつある愛撫の痕と共に刻まれていた。
だが、その頃には、高城一輝にも自分を愛玩する男達を冷静に見上げる余裕が出来ていた。
一輝にナイフが振り下ろされる度、男達はやんやと歓声を上げた。
何度目かの閃光が走り、耳元で刃先とコンクリートとかち合う音が響く。
順番は、あの最初に一輝に声をかけたサングラスの男だった。
「ははは……あんた、いい度胸だな。耳元にナイフを振り下ろされて、平然としているなんて」
「褒めてくれているのかい。ちっとも嬉しくないが。それに、君。僕はまだ散髪に行く気もないんだが」
一輝はそう嘯くと、男を見上げた。
今のナイフで一輝の髪が数本切られていた。
「まあ、そう言うなよ。その綺麗な顔に傷がつかなかっただけでもよしとしてくれ。俺は不器用なんでね」
男は次に一輝の肩越しにナイフを放った。
「悪い。手元が狂った」
男がそう笑うと、一輝の白い腕に赤い線が走っていた。
一輝も笑っていた。
「次はどこがいい?」
「もう一度、今のところというのは、どうだい。……失敗したままだと、君も寝覚めが悪いだろう?」
「たいしたタマだな、先生。よし。じゃあ、リクエストにお答えして……」
男はそう口元を歪めると、ナイフを振り下ろした。
が、次の瞬間、はっとして身を固くした。
刃の部分を一輝がしっかりと握っていたから。
「なんっ……!?」
一輝は男の狼狽にふいに笑みを見せると、手首を捻り、ナイフを奪い取った。
その拍子に一輝の手の平から赤い鮮血が滴った。
「許してくれ」
一輝はそう顔を伏せると、逆手でナイフを男の太股に突き刺さった。
「野郎……!!やりやがったな!?」
ひるんだ男の手から逃れると、一輝は駆け出した。
まさかこれだけボロボロになった一輝が反乱を起こすなど思いもよらなかったのか、男達はバラバラと慌てて彼を追いかけた。
一輝は必死に走った。
自分の姿を隠す夜の帳の闇に感謝しながら……。
視界は既に闇にその支配権を明け渡しつつあった。
辺りに響くのは、潮騒と自分の足音、息づかい。
海風が強くなっていた。
ふいに一輝の鼓膜が別の音を捉えた。
一軒の倉庫らしき場所から、ぎぃっという耳障りな音が響いていた。
一輝はその音に誘われるように倉庫に足を踏み入れた。
倉庫内は、廃墟と表現した方がしっくりくるほどに荒れ果てていた。
所々に薬品瓶のようなものが散乱している。
工場というよりは、何かの研究施設の跡地なのかもしれない。
音の正体は、古びたロッカーだった。
ロッカーの扉が風に煽られ開け閉めされる度、軋んだ騒音を響かせている。
その扉は、海風のせいか、ひどく錆び付いているようだった。
一輝の視線は、そのロッカーに釘付けになった。
断続的に開閉するロッカーの中には、今は主を失った白衣がはためいていたのだ。
思いの外、それは汚れていないようだった。
一輝はそれを失敬することにした。
白衣一枚とは言え、何かを身に纏っただけで一輝の精神は微かに落ち着きを取り戻した。
それにしても、どれくらいの時間が経過したのだろう。
秘書の楠美香子と別れたのが午後4時過ぎだった。
この夕闇はその晩のものか?それとも……。
いずれにせよ、この選挙戦の最中に休暇以外の理由で「政治家・高城一輝」が消えるというのは最大のスキャンダルだった。
倉庫を後にし、歩を進めていると、身体の節々に熱さと痛みを感じた。
それでいて、身体の芯は凍えるように寒かった。
自分は今、明らかに発熱している。
全身の重苦しさと強い目眩。
まずい状況だった。
こんなところで意識を失っては、いつ奴らに見つかるかわからないし、何より極上の醜聞だった。
こんな姿を発見でもされたら、それこそ東京湾の藻屑となった方がどれほど幸せかしれない。
遠くでまた海猫の啼く声が聞こえた。
一輝は必死に意識を奮い立たせ、そして、考える。
これからどうするべきなのかを。
だが、その答えは遙かこの埠頭の彼方に広がる海底のように取り留めなく、深く、暗いように思えた。
「おい。誰かいるのか?」
その声に、一輝の身体は硬直した。
顔を上げると、人影があった。
もう終わりだ……!!
一輝はきつく目を閉じた。
そんな彼に降って来たのは息を呑むかのような声。
「あんたは……」
高城 千鶴(Chiduru Takashiro)
――序論(introduction)
――「快楽」。
所詮、こうした衝動は、脳内に分泌される化学物質のもたらす生理現象に過ぎない。
我々が「気持ち良い」と感じたり、愛だ恋だという感情も、全てこれらの物質に操られているということになるのである。
まさに、愛など脳内物質の作り出したまやかしに過ぎない。
それはひどく理不尽でもあり、同時に愉快でもある。
憐れなエピキュリアンたる我々は、その事実を知りつつもその衝動と悦楽に酔いしれるしかないのである。
これから論じる内容は、まさにそれらに踊らされた憐れなモルモットたちの記録となるであろう。
さて、脳が関知する快楽物質には「脳内麻薬」の別名を持つドーパミンなどがあるが……。
(後略)
華ーー2015年4月5日10時45分 TTV報道局
「暇だな」
俺は、編集の終わったテープの山を横目に見ながら、呟いた。
俺の職業はTTV製作の報道番組『報道ワイドスクープ』のカメラマン。
とは言え、まだ駆け出し。
先輩たちの後塵を拝しつつ、日夜鍛練の日々とか言っとけば、少しは様になるか?
荷物運びやら、カンペ出しやら、ADまがいのことまでやらされる。
ようは体の言い雑用係りだ。
実際、この業界は下積みが長い。
あっという間にメインカメラマンになれるって訳でもないのだ。
わかっちゃいるが、歯がゆい思いを感じることも少なくない。
俺だったらこう撮るのにとか、それは違うんじゃねぇかとか。
そんなことの連続だ。
あーだこーだとフラストレーションは溜まっちまう訳で。
だが、俺はこの仕事が嫌いじゃない。
事件が勃発した際に生じる、あの緊張感。
様々な情報や罵声や怒声や電話のベルが入り乱れ、この場が戦場のようになるあの瞬間が好きだ。
体全身で生きているって感じを痛感できるから。
だが、この待機時間ってのは、好きになれない。
俺は思いっきり欠伸をかました。
「でっかい欠伸やな。見てるこっちまでつられそうやわ」
そのやや甲高い声に椅子ごと振り返ると、芸能デスクの今宮明日香が、女にあるまじき仁王立ちをしていた。
今時絶滅したのではないか?というゴムの二つ結びの髪に、彼女が熱烈にファンだと言う阪神タイガースの野球帽を被っている。
やや赤めのべっ甲ブチのメガネからのぞくくりくりとした目は、いつも好奇心で揺れている。
やや唇がぽってりしているが、そこそこ別嬪系なのは、認める。
Tシャツにジーパンメインの格好がガキくさすぎて萎えるが。
彼女に似ているマンガのキャラがいたはずだったが、なんだったっけ?
ああ、あれだ。「アラレちゃん」だ。
京都府出身らしいが、京都らしいはんなりした感じなんて微塵も感じられないじゃじゃ馬で、おまけにボケには必ず突っ込まないと気が済まない性分らしい。
デスクには、ボケた相手に愛の突っ込みを入れるためのMyハリセンが常備されている。
奴の出身は、本当のところは、絶対大阪府に違いない。
「相変わらず、デスクのこやしになっとるな。遠山颯人」
さりげなく、フルネームで呼び捨てにするなよ。アラレ。
「どっから見ても暇そうやな。うちの取材、手伝って」
「なんだよ。いきなり。俺へのアポは前日の13時までだぜ?」
「あほくさ。何、御笠先輩の猿マネしとるん?あんたがやってもサマにならんわ」
「るっせーよ。で、何の取材だよ」
「お、少しは興味湧いた?これが、総選挙がらみなんよ。
東京駅前で国民改新党が、いきなり街頭演説やるっちゅうことなんやて。
あんまり急な話で、今、みんな他の取材で出払ってもうて、芸能デスクのうちと事件畑のあんたくらいしか人材がおらへんねん。
夕方の放送までにV作らなあかんやて。頼むわ」
「よくお前が動いたな」
「へっへ~ん。この今宮明日香がタダでピンチヒッターなんてやる訳ないやろ。ちゃ~んと交換条件付きや」
「お前らしいな」
「せやけど、ラッキーやで。この取材、交換条件なくてもいただきやわ」
「何がラッキーなんだ?」
「ウマウマやで。今日の選挙演説には、高城一輝が出るもん」
と明日香は顔に似合わない豊満な胸を張った。
「ああん?誰それ」
明日香はおもいっきりコケた。
関西人として、ボケには何が何でも対応しないといけないらしい。
「はあ?あんた、今のギャグ?ぜんぜんウケへん。センスゼロやな」
「冗談じゃねぇよ。なによ。それ。おいしいのか?」
「あんたなあ。それで仮にも報道局に籍を置くカメラマンなん?高城一輝言うたら、今をときめく人気絶大のイケメン若手政治家やないの」
「ま、そいつのことは知っているよ。連日総選挙ったら、そのネタばっかだからな。
だが、俺はね。政治ネタには全く関心ねぇの。俺が追っかけるのは、熱い事件の現場だけだからな」
「それだけが報道やない。政治ネタも芸能ネタもみ~んなひっくるめて報道やないの」
「興味ないね」
俺はそう言って、椅子を回転させて背を向けた。
だが、今日の明日香の気合の入り方は半端なかった。
「あんたが興味あろうがなかろうが、今日の選挙演説の撮りはやってもらうで!!ばっちりカメラ回してや!!」
明日香はそう叫ぶと、椅子ごと俺を報道局の出口へと押し出した。
待てよ!!この怪力!!
「ちょっ!!離せ!!俺はやらねぇぞ!!離せぇええええっ!!」
*
俺は、取材機材の詰まったボックス車に揺られながら、考えていた。
こうして、考えてみると不思議だ。
明日香はどちらかと言えば、芸能専門で、政治ネタなど今まで扱ったことなどない。
そんなこいつが、どうして今回に限って……?
「なあ、明日香。お前、高城一輝とかいう野郎の面、真近で拝みたかっただけじゃねぇの?」
「えっ。まさか~。そんなことあるわけないやないの。てへっ」
図星だな。
演説会場に到着し、俺はボックス車から引っ張り出した相棒=カメラを構えた。
かなりの人ごみだが、TTVの腕章の効果は絶大だ。
バッチリなポジションを見つけ、ズームをかける。
主役の顔がアップだ。
「この国の未来の姿を皆さんは想像できますか?
将来を担う子供達の明るい笑い声を想像できますか?
今の政治は、残念ながら、一部の利権や利害に左右され、正常に機能しているとは言い難い状況です。
我々は、そんな時代はもう終わりにしなければならない」
「アレが今をときめくイケメン政治家か?どうせ、顔だけだろ?」
「何いうてんの。顔だけやない。あの爽やかさ。そこがええやん。一言でいえば、颯人にはない魅力やね」
「うっせーよ」
「それにしても、国民改新党もあんなエエ男を担ぎ出すなんて、反則や。彼にやったら、清き一票どころか、二票でも三票でも百票でも投票したくなるわ」
それはお前だけだろ。
俺はそう心の中で毒づいてみたが、内心、明日香の意見も認めざるおえないだろう。
高城一輝は男の俺から見ても空恐ろしいくらいの美形だし、なんというのだろう。
品の良さとでも言うのか?
俺にはよくわからないが、彼には男の美形によくある嫌味さがまったく感じられないのだ。
今、優しく目を細めて有権者に手を振る姿も、どこかこの世の世俗とは一線を画した感じを受ける。
ああ、童話に出てくる王子様みたいなんだ。
ルックスだけでなく、その全身にまとう雰囲気が。
安易な表現なのは認めるが、それ以外に俺には言葉が見つからない。
大衆から愛される存在を具現化した男。それが政治家・高城一輝か。
公式プロフィールによれば、今、彼は30歳。
俺より6つも年上には見えないな。
選挙ポスターも地味なデザインながら、それが却って彼の美貌を際立たせている。
彼は今回が二期目の当選を賭けた選挙となるらしい。
彼は所謂、「二世議員」だ。
父親は国民改新党の幹事長を務める前官房長官・高城剛三。
彼自身も親父と同じ国民改新党に所属している。
高城一輝は、T大を首席で卒業。
その後、二年間、英国へ留学。
外務省に入省後、政界に打って出るため、退職。
国民改新党の公認を受け、四年前に初当選。
得意の語学を活かし、つい一年前には史上最年少での入閣を果たし、外務副大臣の椅子に座った。
外交では、通訳を間に挟まず直接交渉し、信頼を獲得。
洗練された彼の立ち振る舞いは、外交先のファーストレディたちにもすこぶる評判だった。
というのは、全部さっき読んだ新聞の受け売りだが。
まさに、この男は「清き一票」を集めるに相応しい雰囲気に溢れている。
彼が所属する国民改新党は、この青年の人気で持っているといっても過言ではないだろう。
明らかにこいつのルックス目当ての若い女連中だけでなく、中高年にも絶大な支持を誇る。
恐らくあの実直そうな眼差しと外務副大臣の手腕の賜物だろう。
何せ、政治家のくせに、ファンクラブまであるのだ。
俺は政治家というのは国民から愛されないというのが定説だと勝手に決め付けていたが、ここには、確実に国民から愛されている政治家がいる。
この調子なら、親子そろっての当確は間違いない。
いや、彼の好感度が影響し、国民改新党が大幅に議席を獲得した結果、揺るぎない政権を確保するに違いない。
この爽やかに微笑む青年が、日本を動かす存在になるのか。
その時、ふいに彼と視線がカチ合った。
彼は俺に微笑みかけた。
手慣れた営業スマイルか。
俺はあっかんべーでもしてやろうかと思った。
が、俺の手は止まっていた。
それは今までの微笑みとは違う、どこか寂しげな笑みだったから。
今にも泣き出してしまいそうなそんな儚げな表情だった。
あれでは、泣き笑いだ。
俺はその微笑みに心臓をわしづかみにされたかのような感覚を覚えた。
どう説明したらいいのだろう。
どこか救いを求めるような。
何か苦行に耐えているかのような。
彼は何かを求めている。
この俺に?
見ず知らずのただの有権者であるはずのこの俺に。
はるか年下のこの俺に。
胸が締め付けられるような感覚。
一体なんだ?
なんだったんだ?あの表情は。
地位も名誉も全てを己の手中に収めたはずのあんたが、なぜ苦しむ必要がある?
一体何に?
「皆さん、どうか、私に……力を与えて下さい……!!」
それが、この運命の青年の一人――高城一輝とのファーストコンタクトだった。
月ーー2015年4月5日11時25分 国会議事堂前
「今日の選挙演説も大盛況でしたね。高城先生が立つとギャラリーが3倍増えるそうですよ。
大先生もご子息にそんなに人気を持っていかれて、複雑なんじゃないですか」
「父は素直に喜んでくれていると思いますよ。
それに、有権者の皆さんもわかっていますよ。
私よりも経験豊富な父の方が政治家としては魅力的だと。
私など、まだまだひよっこですから」
そう微笑むと、高城一輝は片手を上げて番記者達と別れた。
高城一輝の第一秘書・楠美香子は、歩き出した一輝の一歩後ろに控えながら、スケジュール帳に目を落とした。
「午後からのご予定をお伝えします。13時からH工業理事・H氏とと会談。
16時からY派の会合、パーティがございます」
ふいに、一輝の歩みが止まった。
美香子に緊張が走った。
「一輝様……。まさか」
「……楠君……」
そう振り返った一輝は悲痛な表情を見せた。
美香子はその瞬間、全てを悟った。
「参りましょう」
美香子は、そっと一輝の背に手を回し、さりげなく彼を支えながら歩き出した。
そして、携帯をある番号にかけた。
*
「事務所に着きましたよ。一輝様」
そう美香子が声を上げると、一輝はそっと微笑んだ。
そして、美香子をいたわるようにぽんと肩を叩いた。
彼は事務所の扉が開くと、倒れこむようにソファに崩れた。
事前に美香子の携帯から知らせを受け、待機していた主治医・御厨が立ちあがった。
次の瞬間には、事務作業を行っていた秘書たちは看護師たちに早変わりする。
3名いる私設秘書は全て医療経験のある者ばかりで構成されていた。
彼の周りを秘書以外の人間がうろうろしていては、妙な疑いを持たれてしまう。
あらゆることがスキャンダルにつながりかねない。
実際、彼の病気のことはもちろん、トップシークレットだった。
このことが公になっては、彼の政治生命は足元から揺らぐ。
高城一輝は、一年ほど前から心臓にある病を患い、闘病生活を行いながら政治活動を行っていたのだ。
この日の発作は、やや強いもののようだった。
実際、事務所へ向かう廊下を進む間にも一輝の額には油汗が浮いていたほどだった。
「御厨先生!!早く!!一輝様、こんなに苦しがっています!!」
美香子は思わず声を上げていた。
「そう慌てるんじゃない。一輝君のことになると、君は冷静さを欠く。君らしくないぞ。楠君。酸素。点滴用意」
ロッカーからあらゆる医療用具が引っ張り出され、事務所の応接室はさながら集中治療室のようになった。
一輝の口元には酸素マスクが装着され、脱がされたスーツの上着が乱暴に床に捨てられる。
美香子は慌ててそれを拾った。
ふとそれを抱き締めると一輝のぬくもりが感じられ、彼女はふっと涙ぐんだ。
乱暴にネクタイが引き抜かれ、ワイシャツのボタンが飛んだ。
引き裂かれるように一輝の胸が露わになる。
これでは、傍目で見ては強姦と変わらない。
ことが一刻を争うため、看護師たちも必死なのだ。
思わず、美香子は顔をそむけた。
見慣れた光景だが、いつも美香子は一輝の半裸の姿を直視できない。
「大丈夫だ。一輝君。やや脈が速いが心配いらないぞ。いつもより多めに注射を打つからちと痛むぞ」
一輝は苦しそうに眼を開けたが、何度か小さく頷いた。
そして、うわごとのように呟いた。
「僕は今……死ぬ訳にはいかない……僕が死んだら……三人の妹たちが……」
*
処置を受け、一輝の息遣いもだいぶ静かになっていた。
美香子は心配だった。
明らかに一輝の発作の回数は増え、重度も増していた。
確かに、今、高城一輝という政治家は、国民改新党にとって、必要不可欠だった。
特にこの総選挙では。
だが、美香子は病気を抱えた状態で政治家という激務をこなして死なれるよりは、ただ一人の人間として、彼に生きていて欲しかった。
党のことなど、もうどうでもよくなっていた。
その思いが自分の職務とは真っ向から対立するものだとしても。
美香子は、一輝を愛しているのだ。
たとえ報われない想いだとしても、構わなかった。
実際、一輝には自分以外に愛している者がいる。
美香子はそれを痛いほど知っていた。
彼が自分に振り向く可能性など、1%もありえない。
ただ、こうしてそばにられるだけでよかった。
そんな愛し方もあるのだと彼女は自分に言い聞かせていた。
「よし。峠は越したぞ。よく頑張ったな一輝君」
美香子は、その御厨の声を聞き、その場に崩れた。
「ありがとうございます。御厨先生。ありがとうございます!!」
美香子はそうまた泣き崩れた。
「楠君。せっかくの美人が台無しじゃないか。私の患者は絶対に死なせんよ。さあ、
涙を拭きたまえ」
「先生……一輝様の発作……最近、回数が増えていますわ。
重度も増しているみたいですし……。私……」
「ああ。本当だったら、政治活動なんて放っておいて、入院を勧めたいところなんだがね。
患者が頑固なもので、承知してくれん。困ったものだ」
「当たり前でしょう……?僕にはまだ、政治家としてやらなければならないことがたくさんあるんだ。
こんなことで……志を曲げる訳にはいかない……」
「だがね。一輝君、命あっての物種じゃないか。君自身が参ってしまったら、志どころではなくなってしまうよ。
それに何より、君を心配する人々の身にもなってみたまえ。ここにいる楠君だって、その一人じゃないか」
「……み、御厨先生……」
「楠君。君には感謝しているよ。いつも僕を助けてくれて」
「か、一輝様……やめて下さい。私は、ただ……自分の職務に忠実にいたいだけです……」
「それでもいいんだ。ありがとう」
「はい……」
「じゃあ、私は行く。いつものように発作止めを処方しておいたから、軽い場合はそれで様子を見るよう伝えておいてくれ」
そう言うと、医師はドアに手をかけた。
その時、御厨の手が握る前にドアノブが回転した。
*
「一輝様。お加減はいかがですか」
そうやや高めのバリトンが響く。
景山蓮。
彼は一輝の父・高城剛三の第一秘書である。
美香子は反射的に身構えた。
蓮は緩やかに波打つ髪に、無機質な銀のメタルフレームのメガネを愛用している。
まず目を引くのが、レンズ越しに垣間見れるどこか作り物めいた整った顔立ち。
驚くほどに長いまつ毛が、紅でも差したかのように濡れた唇がどこか女性的でもある。
その中性的な美しさに惹かれるのか、側近や秘書の中には、景山びいきの者も多かったが、美香子は好きになれなかった。
それというのも、景山という男は、徹底した利己主義者だということを知っていたからだった。
「お倒れになっと伺い、こうしてお見舞いに参りました」
そう言うと、景山は赤い薔薇の花束を差し出した。
「それは、ありがとうございます。景山さん」
美香子は、涙を拭くと、ソファから立ち上がった。
「景山君か。剛三さんにあまり一輝君に無理はさせんように伝えておいてくれ」
「わかりました」
御厨医師はちょっと頭を下げると、事務所を後にした。
「お顔の色も良いようですね。よかった。これならもう大丈夫でしょう」
そう景山は快活に笑った。
「そうだ。高城大先生からご伝言です。
御存じでしょうが、16時から、Y派の会合があります。
もし、難しいようでしたら、そちらは欠席されても構いません。
その後、パーティがあります。
そちらにはどうしてもご出席頂きたいとのことです」
「それはあなたのご意向でしょう?景山さん。
剛三先生がご自分の息子がこんな状況だと言うのに、パーティに出ろなんて言うはずがないわ!!」
美香子は、そう皮肉交じりに鋭い眼光を向けた。
「おやおや。これは心外ですね。私は一介の秘書に過ぎません。
先生に意見するなんて、滅相もないことです」
そう言うと、彼はメタルフレームのメガネを指で押し上げた。
その時、ソファから細い声が響いた。
「いいんだ。楠君。景山君。……わかっているよ。
会合にもパーティにも出席させてもらう。穴は開けない。
僕もせいぜい、客寄せパンダを演じるさ。君たちのために……」
「貴方ならそう答えて下さると信じていましたよ。一輝様」
そう微笑むと、景山はにっこりと微笑んだ。
だが、その視線は一輝のむき出しになった白い胸元に注がれていた。
「早く良くなって下さいね。
今の国民改新党は、あなたなしでは立ち行きません。
お早いご快復をお祈りしております。では、私はこれで」
ドアが閉じると、美香子はまた涙ぐんだ。
言いようのない悔しさが彼女の中に渦巻いた。
その時、秘書の一人が声を上げた。
「高城先生。雪花コーポレーションの雪花様から献金の件でお電話が入っています」
「海杜か。わかった……。今行くよ」
「一輝様……」
「大丈夫。もうだいぶ落ち着いた。心配はいらない」
彼はそう酸素マスクを外していたずらっぽく微笑むと、ぽんと美香子の肩を優しく叩いた。
*
華ーー2015年4月5日18時59分 TTV Aスタジオ
今、冷静になって考えてみると、あの時高城一輝が訴えたのは、俺ではなく、俺の目=カメラに向けてだったのではないだろうか。
彼は俺のカメラを通して、日本中に何かを訴えたのだ。
いや、こうも考えられないだろうか。
彼は不特定多数の人間ではなく、テレビを眼にしているであろう特定の「誰か」に向けて訴えていた。
何かを伝えようとしていた。
いずれにせよ、彼は世間に向けて何か訴えたいことがあったに違いないのだろうが……。
それは一体……?
「本番5秒前!!」
という掛声で、俺は現実に引き戻された。
「4、3、2、1、キュ!!」
「本日のトップニュースです」
そうカメラ目線一直線に凜とした瞳を向けるのは、我らがマドンナ・鏡芙美華。
俺達の番組『報道ワイドスクープ』の看板美人キャスターである。
年齢は28歳らしいが、成熟した知性と色気を同時に発する姿は、見ていて小気味いいくらいだ。
少し茶色かかった緩やかにカールする髪を揺らし、赤く彩られた唇を動かす仕草は、フェミニンというか、フェロモン全開という感じで、デスクからちらりとのぞく細く白い足と併せて世のオッサンたちの清涼剤となっているらしいというのもさっき読んだ週刊誌の受け売りなんだが。
彼女はその容姿だけでなく、自ら綿密な取材を重ね、多くのスクープをものにしてきた。
キャスターになる前は、もともとT新聞社のエース記者だったらしいので、それも頷ける。
こうした面でも、彼女は他の顔だけの美人キャスターたちとは一線を画している。
だが、彼女には黒い噂も絶えない。
彼女につけられた二つ名は、「スクープと寝る女」。
えげつないことこの上ないが、彼女を見ていると、それも真実かもしれないなんて邪推が生まれてくる。
この女のためだったら、禁断の扉を開けてしまうなんて血迷っちまう輩が現れても仕方がないだろう。それもかなりの割合で。
それほど鏡芙美華は、魅惑的な女なのだ。
そして、鏡芙美華自身のスクープ獲得へ見せる姿勢が、その執念が、何を犠牲にしてでも手にしてみせるという意気込みがその噂に真実味を与えている。
俺達のように彼女の間近で共に番組を作る人間ほど、それは強く感じされるのではないだろうか。
スクープのためだったら、本当に自分の身体くらい平気で兵器に使用しそうなほどの。
ま、こんな噂の大半が、真実半分、やっかみ半分といったところだろうが。
本番終了後、彼女は楽屋へ向かう前に俺達の方に歩み寄ってきた。
「みんな、お疲れ様。ちょっといいかしら?」
普段の彼女は、ニュース原稿を読む時の流れるような話し方ではなく、少し甘えたような口調で話す。
あるスタッフによると、そんなところが知的な彼女のイメージとのギャップがあっていいらしいが、どこかつかみどころがなく、そんなところも恐ろしい。
「どうされました?」
チーフディレクターの大河内が、明らかに10センチほど鼻の下を伸ばしながら、彼女に向き直った。
ちなみに、さっきのあるスタッフというのは、まぎれもなく、こいつである。
「あのね。ちょっと、取材に協力して欲しいの」
「何か新しいネタでもあがりましたか」
「まあね。ちょっとね」
「なんですか?そんな嬉しそうな顔して、対象はよほどのいい男なんですか」
「ええ。いい男よ。ウフフ」
「へえ。冗談だったんですが、図星ですか。芙美華さんが目をつけるなんて、よっぽどなんでしょうね」
「もちろん。それに、オイシイ男よ。この男を追えば、必ずスクープに辿り着ける。私の勘は、当たるのよ」
そう言うと、彼女はひとりの男のポートレートをデスクに滑らせた。
それが、二人目の運命の男――芸能プロダクション社長・不動充との出会いだった。
*
月ーー2015年4月5日20時03分 高城一輝選挙事務所
パーティから戻ると、高城一輝は、沈み込むように椅子に腰かけた。
乾杯で飲んだビールが確実に効いていた。
元来、彼はアルコールを受け付けない体質だった。
選挙がらみのパーティも増え、正直、身体がいくつあっても足りない状況だった。
無理をしすぎているのかもしれない。
今更ながら、一輝はそう溜息をついた。
「お疲れ様です。一輝様」
その声に振り返ると、いつの間に部屋に入ってきたのか、景山蓮がメタルフレームのメガネを指で押し上げた。
「君もお疲れ様。こんなところで油を売っていていいのかい?父は赤坂に向かったようだが」
「いいんですよ。大先生は旧友の方々と政治を忘れて羽を伸ばしたいそうで。お伴しようとしたら、追い返されました」
一輝は苦笑した。
「で。僕に何か用かな。僕も少々疲れたのでね。今夜は早く帰ろうと思うんだ」
そう言うと、一輝はカバンに手をかけた。
「今日は楠さんはいらっしゃらないのですか」
「ああ、特に仕事もないからね。パーティ会場から帰した。僕は事務所にこいつを取りに来ただけだから」
一輝は微笑みながら、茶封筒を掲げた。
「そうですか……」
「景山君?どうしたんだい。僕はもう失礼するが」
そう言うと、一輝はポケットから事務所の鍵を取り出した。
「いえ、少し一輝様とお話がしたかったんですよ。
あなたと私は割合近しい場所にいるのに、なかなかゆっくりとお話をする機会もなかったでしょう」
「あ?ああ。そうだね」
「私はね。一輝様。本当にあなたを買っているんです。
あなたはお父様以上の政治家になられる。
そう私は信じているのですよ」
「あ、ああ。それは、ありがとう。だが、それはかいかぶりというものだよ」
「いいえ。私は、あなたを本当に想っているんですよ。
そう。この私だけのものにしてしまいたいくらいに……」
その瞬間、蓮は一輝を背中から抱きしめた。
同時に一輝に別の衝撃が走った。
発作だった。
「うっ……」
「苦しいのですか?もしかして、発作というやつですか?」
察しながらも彼はどこか楽しそうに一輝の身体を撫で回した。
「苦しいのは、この辺り?」
「離してくれ……」
一輝はそう自分の背後から回された蓮の腕を引き剥がすと、立ち上がり、部屋の隅に掛けられたスーツの上着に手をかけた。
内ポケットに手をやる。
だが、それは空っぽだった。
「……!?」
「あなたが欲しいのは、これですか?」
蓮の手にあるもの。それはまぎれもなく、発作止めだった。
いつの間に……!?
「おかわいそうにね。苦しいのでしょう。すぐ、差し上げますよ」
そう言うと蓮は、カプセルを一粒取り出し、それをゆっくりと自分の口に含んだ。
そして次の瞬間には、一輝の唇を奪っていた。
「んっ!!」
一輝は蓮を突き飛ばした。
突き放された蓮は、悪びれる風でもなく、にやりと笑った。
「おや。いけませんね。せっかくカプセルを飲ませてあげようと思っていたのに」
「何の真似だ」
「だから、お薬を。痩せ我慢はあなたのためになりませんよ?」
「君に犯されるくらいなら、死んだ方がマシ……だ……」
「あなたがそれでよくても、こちらはそうはいかないんです。
行ったでしょう?今の国民改新党は、あなたなしでは立ち行かないと……」
蓮はもう一度一輝に口付けた。
もう一度チャンスをやるとでも言うかのように。
一輝の中で、蓮との口付けの屈辱より、胸痛の苦しみから解放されるという思いの方が勝った。
カプセルが喉を通過する確かな感覚があった。
一輝は蓮を再度突き放した。そして、ソファに沈み込んだ。
「薬も飲まれたのですから、発作も時期に収まるでしょう。
でもね、今、あなたにはもうひとつ服用して頂いたんですよ。
薬だけじゃつまらないので、別のものも一緒に」
「別のもの……?」
そう顔を上げ問うた一輝は、自分の身に異変を感じた。
「……!?」
「即効性のようですね。大丈夫ですよ。それも薬ですから。種類は違いますが」
「何を……した?」
「時期にわかりますよ。感じるはずですから、あなたの身体が。ほら、こんな風に」
軽く首筋に指をはわされただけだというのに、今の一輝には数倍の刺激に感じられた。
だが、一輝は残された理性で必死にそれに抵抗した。
「強情な方だ。発作に苦しんでいる上に、媚薬まで服用しながら、それでも屈しないなんて。
でも、時期に楽になりますよ。御厨先生のお薬はよく効きますからね。
それに、もうひとつの薬も効いてくるでしょうから」
一輝は危険を感じ、ドアの方へと歩き出した。
「ダメですよ。これからいいところなんですから。
それに、そんな身体でどこへ行くんです?そんな感じやすい身体で」
蓮はそう言うと、一輝を背中から抱き締めた。
「あっ……!!」
蓮の生暖かい吐息が一輝の首筋にかかる。
一輝はゆっくりと振り向いた。
そこには、いつの間にかメガネを外した蓮の美しい顔があった。
明らかに普段の蓮ではなかった。
本来の魅力が封印を解かれたかのように。
長いまつげに彩られた瞳が妖しく獲物を捕えるように光る。
「欲情には素直に従った方がよいですよ?ねえ。一輝様?」
そう一輝の髪をかきあげると、蓮はその苦痛に震える唇に口付けた。
幾分長い口付けだった。
蓮の舌が絡む感触は、一輝の中でおぞましさから快楽へと変換されつつあった。
そのことに唇を離した蓮は満足そうに微笑むと、
ドアに打ちつけた一輝の身体をまさぐった。
蓮の指先が触れるたび、一輝の吐息が漏れる。
「あっ……いや……」
「いいですね。そうやって悶え苦しむ様子も堪らなくセクシーですよ」
「いやだ……」
一輝のその呟きは、蓮に征服されることに対しても、蓮に屈服せざるおえない今の己自身、両方に向けられたもののようだった。
蓮は一輝のシャツを脱がすと、夢中で愛撫した。
それに一輝が平生、誰も耳にしたことのないような悩ましげな喘ぎ声で答える。
明らかに一輝は理性を失いつつあった。
「いつも思っていました……。
あなたをこうやって私のものにしたいと……。
そう。あなたのすべてをね」
「やめ……て……」
そのままソファに押し倒された時、一輝は完全に己を見失った。
*
月ーー2015年4月5日午後21時14分 地下鉄某駅構内
A生命の保険外交員・由良詩織は、帰路につくため、某地下鉄構内を歩いていた。
学生時代の彼女は、顔立ちも美人ではあったが、華やかなものではなく、引っ込み思案な性格ではあったが、学業の成績はよく、クラス委員なども務め、教員たちの覚えもよかった。
卒業後の進路も、推薦で名門大学へ進むことが決まっていた。
ところがそんな矢先、彼女の父親が事業に失敗し、学費を支払うことができなくなった。
彼女にとっては、まさに青天の霹靂だった。
彼女は、泣く泣く高校中退の道を覚悟した。
卒業まであと三ヶ月というところだった。
その時、学校に掛け合って三ヶ月分の学費納期の延期に尽力してくれたのが、同級生の高城一輝だった。
一輝は当時、一緒にクラス委員を務めた間柄で、どこか押しが弱い彼女をいつも心配してくれていた。
彼女は一輝を同い年の兄のように慕っていた。
それから十数年。
すっかり没交渉となった二人であったが、突然、高城一輝から電話があった。
「君が保険の外交員をしていることを思い出してね」
詩織は、政治家として雲の上の人間となった一輝が自分を覚えていてくれたことが何より嬉しかった。
詩織は、保険のパンフレット一揃えを携え、一輝の事務所を訪れた。
「三億……?」
「ああ」
「三億円って……高城君の……生命保険?」
「うん。僕もいつ何があるかわからないから……備えておきたいんだ」
三億円の生命保険。
それは破格の契約だった。
今まで大口の契約とは無縁の日陰の存在だった彼女の突然の快挙に、一気に周囲の彼女を見る目が変わった。
まして政治家・高城一輝の担当ということで、多くの顧客から詩織への指名が入るようになり、彼女はいつしか、押しも押されもしないトップセールスレディとなっていた。
「ありがとう。高城君のおかげで、私もたくさんのお得意様に恵まれて……感謝しています」
「僕は何もしていないさ。君の努力の賜だろう?君は親身になって顧客と接するから、信頼を持たれるのは当然さ。もっと君は自分に自信を持たなくちゃいけないね」
「そんな……」
「そうやって謙遜する癖もよくないね。君はもっと堂々としていればいいんだよ」
そんなとりとめのない回想に浸る中、詩織は突然、腕を捕まれた。
「えっ!?」
振り返ると、派手な赤シャツに黒い背広(だいぶ草臥れていたが)を纏った長身の男が、ちりちりと細かいウェーブのかかった髪に片手を突っ込みながら、立っていた。
軟派なイメージだが、その目つきだけは、異様に鋭い。
「剛史……」
「よお。詩織。二日ぶりだな。元気にしてたか?」
詩織が何か答える前に、男はガムを咬みながら続ける。
「なあ、聞いてくれよ、詩織。今日はK花賞だったろ。ケンジの奴、何血迷ったんだか、3-4が来るとか言い出してよ、馬鹿野郎だよな。だから俺は2-8にしとけって言ったんだ」
「ねえ、剛史……こないだ渡したお金は?」
「残念ながら、オケラだよ。ケンジの奴のマヌケのせいでな。晩飯喰う金もねぇ。お前見つけて追っかけて、今ここん中に入るために使ったSuicaも残金20円だってんだから、しけてやがる。俺はほとほと運に見放された男だよな」
「そう……じゃあ、チャージしなくちゃ……」
そう言うと、詩織はバッグから財布を取り出した。それを剛史と呼ばれた男は素早くひったくる。
「あっ……」
「なあ、詩織。お前だけは優しくしてくれるんだろう?な?」
そう言うと、剛史は詩織のスーツの胸元から手を差し入れた。
「や……ちょっと……こんなところじゃ……」
「何。かまやしねぇよ。この街じゃ、みんな自分のことしか見ちゃいねぇからよ」
「ダメ……部屋に戻ってから……」という詩織の声も空しく地下道に響いた。
*
媚薬による意識の混濁。
津波のように押し寄せる快楽。
そんな朦朧とした中、高城一輝は、景山蓮のベッドの上で喘いでいた。
舞台は事務所のソファから蓮の寝室に移っていた。
その頃には、一輝の中に明確な意識は残されていなかった。
それは彼にとって幸い以外の何ものでもないだろう。
なぜなら、平生の彼が自らのそんな醜態を目にしたら、その場で舌を噛み切って自殺でもしかねないほどのものだったからに他ならない。
一輝はただ蓮を求め、蓮の要求を蓮自身を全てを飲み込み、蓮の言いなりとなって自らの身体を蓮に捧げた。
ようやく二人が眠りについたのは、既に朝日が昇り始めた頃だった。
「お目覚めですか」
目を開けると、景山蓮が微笑みを浮かべて立っていた。
開け放たれたカーテンから注ぐ陽の光を浴びる姿は、認めたくないが、この上なく美しい。
既に蓮は着替えを済ませていた。
一輝は痛む頭を振りながら、散らばった自分の衣類を引き寄せた。
「おはようございます。一輝様」
そう言うと、蓮は湯気の立つコーヒーカップをベッドサイドに置いた。
「そろそろお目覚めだろうと思い、お持ちしました。どうぞ」
「…………」
「昨日はずいぶん、乱れておいででしたよ」
一輝は蓮の戯言に答えず、衣服をまとうと、玄関に向かった。
「お帰りですか?お送りしましょう」
振り返りもせず、一輝は首を振った。
「困りましたね。一輝様のお車は事務所の駐車場ですよ。タクシーを使っては目立つでしょう」
「………………」
「愉快ですね。あなたは今や籠の中の鳥。私の一存であなたの存在は生かすも殺すこともできる」
そう言うと、蓮は一輝のうなじにキスをした。
「お忘れなのですか?あなたは、昨夜言って下さいましたよ。『私を愛している』と」
――――何です?はっきりおっしゃって下さい。でないとわかりませんよ?
――――……ぁ……あっ……。
――――何です?もう一度。ちゃんと教えて下さい?
――――おねが……い……。景山く……ん。
――――蓮で結構ですよ。一輝様。
――――蓮……。あっ……ああん……。
――――これが欲しいのですか?ふふ……タダでとはいきませんよ。私はちゃんとあなたに愛を告げた。だから、あなたも……ね?
――――あ、あいしてい……る……。蓮……。
「嘘だ……」
「嘘ではありませんよ。一輝様。あなたは確かに言って下さいました。それでもお疑いになるのでしたら、ちゃんと証拠もありますよ」
「証拠……?」
「ええ。私とあなたの愛の証……」
「まさか……君は……」
「言ったでしょう。あなたは『籠の中の鳥』だと。……愛しています。一輝様」
蓮は一輝を背中から抱き締めた。
今度は一輝も拒まなかった。
拒めなかった。
「まあ、そう慌てずに。ちゃんとお送りしますから。せっかく淹れたコーヒーが冷めてしまいますよ。どうぞ、ごゆっくり」
蓮はそのまま一輝の震える唇を奪った。
*
風ーー2015年4月6日10時23分 都内某所
「犯人は、あなたですね?」
探偵の朗々とした自信に満ちた声が広間に響き渡る。
探偵とは、事件という名の混沌とした闇に秩序をもたらす一筋の光明だ。
そして彼らが紡ぐのは、いつ耳にしても思わず聞き惚れずにはいられないその完璧なロジックに裏打ちされた真相。
その全てが語り終えられた時、この事件の真の闇・真犯人へとスポットライトが向けられる。
僕はこの瞬間に立ち会うのが、一番好きだった。
日常とは一線を画した非日常という名の一種のカタルシスを味わうことができるから。
その日も、探偵が指を突きつけた草臥れた中年男性の手に手錠が嵌められた。
その途端、男性の横に座っていた一人の婦人が金切り声を上げ、探偵を指さした。
「この家は、もうおしまいよ!!あんたの……あんたのせいだわ!!」
探偵は特に感情の表れていない端正な顔立ちを彼女に向けた。
「やれやれ、困ったものだ。あなたがこの私に今回の事件をご依頼なさった際に、私は問うたはずですよ?
例え、真相があなたに優しくないものだとしても、あなたに真実を知る覚悟が、おありになりますかと」
彼女――この家の夫人にして、犯人の妻は、悔しげに言葉を失った。
その間にも探偵は、
「私は私の職務を果たしたに過ぎない。失礼」
と身を翻すと、さっさと玄関へと歩を進めた。
僕はその背中を慌てて追いかける。
が、次の瞬間、探偵はふいにその歩みを止めた。
何かが探偵の背中にぶつけられたからだった。
それは、赤いハイヒールだった。
「この、疫病神っ!!」
その言葉とは裏腹に、涙でぐしょぐしょになった弱々しい声の主は、この家の長女、すなわち、今回の事件に真犯人の娘だった。
彼女の、いや、彼女たち家族の生活は、これから180度変遷を迎えることだろう。
セレブと呼ばれたある家族の凋落。
まさに、天国から地獄。
その元凶となったのは、探偵の推理から導き出された真相。
気持ちはわからないでもないが、元はといえば、当主である彼女の父親が自分の会社の金を使い込んだ挙げ句、それを知り、告発しようとした部下を殺害したからに他ならない。
お気の毒だが、自業自得というものだ。
探偵は振り返ることもなく、エントランスへと消えた。
よくテレビドラマでは、事件解決=一件落着、めでたしめでたしとなる訳だが、実際の事件では、そうはならない。
むしろ、暴き出された真相により、新たな悲劇が巻き起こされるのが常だ。
いつかどこかの名探偵が言っていたが、まさに「事件が終結した後からこそ、新たなドラマが生まれる」といったところだろう。
後味が良い事件なんて、三面記事で扱われる珍事以外、この世には存在しないのだ。
そう考えると、探偵という職業は余程、精神的にタフな人間にしか務まらないと思われる。
そういう面で言っても、目の前に対峙しているこの人物は、「名探偵」と言えるかもしれない。
皮肉なことに、屋内の暗雲とは裏腹に、ドアを開けると燦々とした日の光が照っていた。
「いいのか?あのままで」
「良いも悪いもなかろう。私の仕事は終わった。行こう」
「しかし……」
「終わったのだよ。右門君。ここから先は、我々の関知することではない。
我々は神から得た真実という天啓を知らしめているにすぎないのだからね」
探偵は、そう面白くもなさそうに嘯くと長い黒髪をさっと振り払った。
化粧っけはないのに、紅を差したかのようにほんのり紅い唇が目を引く日本人形のように美しい顔立ちに、小柄ながらすらりとしたプロポーションに黒衣がよく似合う。
左近風魔。
彼女は歴とした女流私立探偵である。
正確に言うと、彼女は僕と同じ大学院生なのだが。
「さあ、右門君。帰って暖かい紅茶でも飲もう」
*
月ーー2009年4月6日11時42分 国会議事堂
「一輝様?」
第一秘書・楠美香子の問いかけに、はっとして顔を上げると、そこは議事堂内の赤絨緞の上だった。
今は選挙中だが、外務副大臣のポストにいた一輝は、行政官としての職務引き継ぎのため、国会に出入りすることも
しばしばだった。
「どうされましたか」
美香子の心配気な眼差しが刺さる。
美香子は少しでも異変を感じると、敏感に察知するところがある。
一輝が身体を壊してからはそれが顕著だった。
「いや、何でもないよ。今日のスケジュールを頼む」
そう微笑んだ一輝の背後から声が上がった。
「高城君じゃない、お久しぶり」
そう手を振りながら赤絨緞を軽やかなステップで踏み締め近づいて来るのは、甲賀明美。
一輝と同い年という若さにも関わらず、総選挙での国民改新党の最大のライバル・社会民政党の党首を務める女流政治家である。
ボーイッシュな容姿の明美は、その見た目通りの裏表にない性格で、女性ながら弁が立ち、ハキハキとした物言いをする。
決して二世などではなく、高校時代から新聞配達で学費を稼ぎ、実家は平凡な商店街の精肉店というハングリーさが有権者の支持を集める要因なのだろう。
実は一輝とは同級生で幼馴染みであるということはあまり知られていない。
「ああ、久しぶりだね、君も元気そうで何より」
「本当にお久しぶりよ。あなた、国民改新党の顔だって割にちっとも討論番組に出てくれないんですもの」
「僕かい?僕なんかじゃ君に太刀打ちできないよ。収録前に楽屋から逃げ出すのがオチさ」
「いやあね。人を化け物みたいに。まあね、あなたがリングに上がったら、それこそ容赦しないけど」
「ほら、やっぱり。僕にとって、君は鬼門だね」
「まあ、ひどい。……でも、よかった」
「えっ……?」
「あなた、今、なんだかすごく思いつめたような顔してたから。顔色もあまりよくなかったし。……でも、私の考えすぎだったみたいね」
昔から明美は人の内面を見透かすところがあった。
そして、そうして感じた人の痛みを自分のことのように受け止め、時に一緒に涙し、時に一緒に戦う。
そんな姿勢を持っている少女だった。
彼女の人望は、そうした面がもたらしたものが多い。
だが、明美はいつも一輝の内面には深く入り込もうとはしなかった。
いや、できなかった。
それは、そんな明美から一輝が自らを徹底して閉ざしたからに過ぎない。
二人は大の仲良しだった。昔から二人でよく政治論を戦わせていた、言わば同志だった。
だが、一輝は決して自分の内面を明美に晒そうとはしなかった。
それは、明美を拒むなどという訳ではなく、ただ一輝自身が己の内面を他人に晒すことを潔しとしないから。
そして、明美が自分を友人以上として捉えていることも重々承知していたからに他ならなかった。
一輝はそんな明美の気持ちを察しながら、気がつかないふりをして過ごしてきた。
明美も同じようにただの友人として彼に接してきた。
彼らは互いに怖かったのだろう。
友人という関係がその砂の城のように脆い関係がどちらかの口火によって壊れてしまうことを。
一輝は考える。
特に今は彼女に自分の心のうちを見破られるのは得策ではない。
自分の体調面のことはもちろん、父の秘書に犯されたことなど……。
一輝は笑顔を作った。
政治家となってから、作り笑いは彼の日常に溶け込んでいる。
自分の内面を見透かされないように煙幕を張るのも実に手慣れたものだった。
政治家となって自分が得たのは、そんなものだけ。
時折、一輝はそんな自分をうとましく感じていた。
だが、わかっていてもどうにもできない自分もそこにいる。
「あ、ああ。君はサバサバしている割にどうもそういうことには目敏いね。だが、さすがの君の勘も外れだね。僕は何も思いつめてなんていないさ。確かに少々選挙戦では疲れているがね。それだけさ」
「そう。……それならいいんだけど、あなた、昔から溜め込むとこあるから。適度に肩の力抜いた方がいいわよ」
「ご忠告、ありがたく受け取るよ」
「ああ、引き留めてごめんなさい。お互い正々堂々最後まで頑張りましょう。じゃあね」
事務所に戻り、何気なくつけたテレビの中の先日東京駅で行われた演説のVTRを見て、一輝は愕然とした。
確かにあの時、自分はカメラに向かって訴えた気がする。
それは決して国民改新党への支持でも、自分への支持でもなく、ただ救いを。
そう。そのカメラの向こうにいるであろう一人の少女に向かって。
ある意味、その時の彼にとって、それは完全に無意識の行動だった。
まさか、自分がこの瞬間、こんな表情をしていたなどとは、想像もつかなかった。
だから、愕然とした。
もう自分はそこまで追い詰められているのかと。
彼は確かに求めていた。
ただ、ひとつの救いを。
決壊しそうな自分を救う一筋の光明を。
彼はゆっくりと目を閉じると、小さく呟いた。
在りし日の少女の幻影を瞼の裏に思い描きながら。
その愛しいシルエットに向かって。
「君は今、どこにいる?」
*
華ーー2015年4月6日13時24分 TTV報道局
鏡芙美華の命を受けた大河内チーフディレクターの命令で、今宮明日香が不動充の取材に当たることになった(洒落じゃないぜ?念のため)。
元々明日香は不動を狙っていたらしく、喜んで引き受けたようだった。
が、芸能デスクのカメラマンたちは、某アイドル歌手の突然の結婚会見のため、出払っているらしい。
そうなると必然的に……。
「だから、なんで俺がお前のお供としてカメラ回さなきゃならねぇんだよ?」
不満タラタラな俺に、アラレはさらりと言った。
「そら、遠山颯人。あんたがカメラ回すしか能がないからに決まっとるやないの」
「あんだと!?」
「ほんまのことやないの。あんたにインタビューなんかできるわけあらへんやん。インタビュー言うんは、ほんまに難しいことなんやで。相手の気を引きつつ、こっちが聞きたいことを切り込んでいかなあかんのやから。インタビューは繊細なんや。あんたみたいにおおざっぱな輩には向かん」
「何がインタビューは繊細だ。お前のどこが繊細なんだよ。お前くらいガサツな女みたことないぜ?お前にできることが俺にできないはずがないだろ?」
「ほお~。言うたな?」
「ああ、言ったぜ?」
アラレはにんまりと笑った。
「せやったら、見せてもらおうやないの。あんたの力量って奴を」
「あ?」
「今回のインタビューはあんたに任せたわ」
「な、なんだよ、それ」
「そのままの意味やで。あんた一人で取材に行って来たらええやん」
「なんだと?」
「そんなに自信があるんやったら、うちに遠慮せんと、ちゃっちゃとインタビューして来てみなはれ」
「ああん!?」
「そやな。あんたがあの不動充から晴れてインタビューを取って来れた暁には、一ヶ月間、うちはあんたの召使いにでもなんでもなってやろうやないの。その代わり、あんたがインタビューに失敗した場合は、あんたはこれから一ヶ月、うちの専属カメラマンとして働いてもうらう。どや?おもろい賭けやと思わへん?」
アラレはにんまりと唇の端を上げると、ニャロメのような笑みを俺に向けた。
ここで引いたら男が廃る。
「ああ、いいぜ。やってやろうじゃないか」
「ほっほ~。受けて立ったな。遠山颯人。おもろいことになったなあ。あ、ひとつ忠告しといたるわ。不動充言うたら、うちら芸能関係者では、『眠れる獅子』言う二つ名で呼ばれとるんや」
「は?」
「つまりな。不動充言う男はず~っと取材陣からの攻撃にも全く動じず、口を開いたことがない。ノーコメントを貫き通しとるんよ。動かざること山の如し……語らざること貝の如しってことや。ま、せいぜいおきばりやす~」
聞いてねぇぞ!?いきなりハードル高すぎじゃねぇか!!
ちょっと待てよ?
今回俺が晴れて不動充の取材にこぎ着けた場合、芸能ゴシップとは無縁の報道カメラマンである俺には取材上、何のメリットもない。
なんだかんだと芸能デスクであるこいつの手柄になる訳で……。(それは、一ヶ月間俺の雑用係をやることとは引き替えにならないくらいの手柄だろう)
そして、当然、俺が失敗しても、こいつは痛くも痒くもない。(まして、俺を公然と扱き使えるだろうし)
まして、俺は不動の何を取材すべきなのかさえ、知らない。
「アラレ……てめぇ……図ったな」
「あら~?うちは親切に忠告してやっただけやん。はは~。ま、健闘を祈っとるで~」
*
華ーー2015年4月6日15時03分 都内某ホテル
都内某ホテルの一室で、ひと組の男女が一糸まとわぬ姿で宴を繰り広げていた。
「で?高城大先生は、愛息である一輝氏を使って次はどんな手を打つつもり?」
そう吐息交じりに髪をかきあげると、鏡芙美華は、自分の下になっている男を艶めかしい視線で見降ろした。
「さあ?どうされるのでしょうねぇ」
下になっている男――景山蓮は、汗ばむ芙美華の乳房に愛撫する。
「いじわる。あなたって、どうしていつもそうやってはぐらかすのかしら。他の相手だったら、みんな簡単に口を開いてくれるのに」
「だって、面白くないでしょう?私が簡単に口を割ったら、あなたとこうしていられる時間が少なくなるだけだ」
そう言うと、蓮は芙美華の肌に口付けた。
「時間だわ。残念ながら、お開きね」
そう言うと、芙美華は蓮の身体を押しのけ、ベッドをすり抜けた。
蓮は芙美華の滑らかな裸体の後姿を横目に見ながら、タバコに火をつけた。
「そんなに聞きたいのだったら、私のようにベッドにお誘いして大先生ご本人に聞いてみてはいかがでしょうか。それとも、一輝先生を落としてみますか」
「あなたって、本当にいじわるね。それが無理だってこと、全部承知の上でそんなこと平気な顔して言うんだから」
「次のお相手は誰です?」
芙美華は、ちらりと蓮を振りかえったが、曖昧に笑っただけだった。
「M党のY氏ですか」
その瞬間、ストッキングを足に絡めた芙美華の手が止まった。
蓮が満足げに微笑んだ。
「私の情報網もなかなかでしょう?あなたには及びませんけれど……」
芙美華は、ストッキングを放り投げた。
「来て」
「どうされました?」
「次の相手はキャンセルよ。今は……あなたが欲しい」
そう言うと、芙美華は蓮のタバコを弾き飛ばし、彼に抱きついた。
*
華ーー2009年4月6日16時32分 都内某マンション
ターゲットは都内でも有数の高級住宅街。
その中でひときわ高くそびえる一棟のビルディング。
煉瓦色に染められたそれに愛車のバイクを横付けする。
それにしても、ホテルかと見紛うばかりの豪奢さ。
マンションというよりは、億ションか?
自分の安アパートとの差が無意味に頭を掠める。
だいたい、俺は何しにここに来ているのだろう。
俺は世間で言うところの常識がないから、一体どうして不動充という男が芸能デスクにとって金の成る木なのか、さっぱりわからない。
俺の資料と言えば、ついさっき予備知識を仕入れるために手に入れた週刊誌だけだ。
なんでも、保険金殺人がどうのこうのといった内容だった。
からっきし、興味が沸かない。
俺は報道が特集する事件でも、金銭がらみの殺伐とした奴は嫌いだ。
男女の痴情のもつれって奴もご免被る。
俺が追いかけたいのは、某政治家の汚職だったり、企業の裏にはびこる巨悪だったり……まあ、社会悪なのだ。
今回のネタは、あの我らが鏡芙美華が目を付けるくらいだから、相当な金脈には違いないのだろうとは思うのだが。
いずれにせよ、俺にはどうでもいい話だ。
だた、取り敢えず、明日香との賭けにだけは勝たなければならない。
俺自身のちっぽけなプライドのために。
俺は宅配業者を装って、オートロックという名の第一関門を突破した。
まさか、こんなところでバイト時代のお古のジャンパーが役立つとは思わなかった。
カメラマンというよりは、探偵にでもなった気分だ。
俺は無事に目的のドアの前に着くと、呼び鈴を鳴らした。
反応がない。
俺は再び宅配業者を装い、隣の家に探りを入れることにした。
呼び鈴を鳴らすと、すぐに化粧臭い有閑マダムが顔を出した。
「あら。不動さんだったら、お出かけされたわよ。ついさっき。あなたと入れ違いかしら。残念ねぇ」
マジかよっ!?
俺はいきなり出鼻をくじかれ、つんのめりそうになった。
俺のこの燃えたぎるソウルはどこへ持って行けばいいのよ?
俺は「あ、運送屋さん、実はお願いしたい荷物があるのよ~」という声を遮りドアを閉めると、思わず、不動充の部屋のドアに拳を叩きこんでいた。
「いってえええええっ!!」
鋼鉄のそれに叩きつけた拳からギンギンに痺れる反動が叩き込んだ倍以上の力で返ってきやがった。
踏んだり蹴ったりとは、このことか。
俺は自分のついてなさを呪った。
さて、どうしたものか。
ああしてタンカ切って出てきた手前、何らかの収穫を手にしなければ、帰るに帰れない。
俺にだって、プライドというものはあるんだ。
その時、世にも不思議なことが起こった。
たった今、己の拳を叩きこんだドアがゆっくりと開いたのだ。
俺は、ドアが仕返しにでもしにきたのかと本気で身構えた。
だが、ドアはギィッという耳障りな音だけを響かせて開いた訳ではなかった。
「不動さん、忘れものですか?」
というどこかか細いが可憐な声も引き連れていたのだ。
「えっ……?」
目が合った瞬間、俺たちは、同時に声を上げていたと思う。
次の瞬間、麻痺しかけた俺の鼓膜に響いてきたのは、
「あああああっ!!どうしよう!!」
という猛烈な相手の叫びだった。
どうしようと言われても、俺だってどうしていいのかわからない。
野郎の寂しい独り暮らし、しかも、ご当人は外出中。確実に無人だと思っていた部屋のドアから、いきなりこんなに可愛らしい女の子が現れたのだから。
相当若い。
高校生か?
腰まで届くのではないかというくらいに長い髪を揺らし、人形のようにぱっちりとした瞳をこれでもかというくらいに見開いている。
とにかく、俺はその少女が放つ可憐な不意打ちをくらい、ノックアウト寸前だった。
彼女は俺のそんな動揺にもおかまいなしに、上目遣い(この仕草もなんとも言えず、可愛らしい)で俺を見上げると、消え入りそうな声で言った。
「あ、あのう、私のことは、見なかったことにして頂けないでしょうか」
俺はさすがに面食らった。
「見なかったこと」とは、どういうことだ?
「それはできない相談だ。俺も、君みたいに可愛い子のこと、見なかったことになんてできないからね」
俺は気がついたら、そんな軽口を叩いていた。
*
月ーー2009年4月6日16時43分 国会議事堂前
国民改新党選挙対策委員会からの帰り道。
赤絨毯を踏み締め歩く高城一輝の背後から、秘書・楠美香子の声が響く。
「本日の予定は以上ですわ。一輝様。お車でお送り致しましょうか」
「いいんだ。選挙事務所に用事があるし、少し、一人で歩きたい。車は君が乗って行ってくれてかまわない。自分の車で帰るから」
一輝の選挙事務所は、議事堂から徒歩10分程度のところに構えられていた。
彼の愛車も今はそこで主の帰りを待っている。
美香子は、
「明日は久々のオフですね。ごゆっくりお休みになって下さい」
と寂しげに微笑んだ。
「ああ、選挙戦の真っ最中だからね、心底ゆっくり休めるかわからないが……。
ラストスパートのためにも英気を養ってくるさ」
一輝はそう片手をあげると、議事堂を後にした。
夕暮れの永田町は、人通りが少ない。
警備に当たる警官の姿がちらほら見えるだけだった。
ふと一輝は、歩みを議事堂近くの国立国会図書館に向けた。
久々の休日を共にする書籍を探そうと考えたためだった。
学生時代の自分は、呆れるくらいに本の虫だった。
だが、外務省勤務、こうして国会議員になってからは、呆れるくらいに本と縁遠い生活になっていた。
多くの作家から著作本を贈られることも多いが、その量が多すぎて、どれから手をつけてよいのかわからない。
何より、すべてに目を通す時間がない。
そうなると、必然的にそれらを選別することになる訳だが、せっかく贈られた本をそうして篩いにかけてしまうというのは、なんだか申し訳ない心持ちになる。
結果的にどの本にも手が延ばせなくなっている自分に気づく。
それがなんだかやりきれなくて、本という存在から遠ざかっていた。
だが、その日は無性に書籍に触れたかった。
どんなものでもかまわないから、活字というものに触れたかった。
活字というか、どこか「静的」なものを彼は欲していた。
選挙戦という荒波のような「動的」な日々の中で、彼は安らぎを求めたのかもしれない。
「高城先生ではありませんか」
そう声をかけられたのは、国立国会図書館の門をくぐった時だった。
一輝が振り返ると、そこにはサングラスをかけた一人の男がいた。
「高城一輝先生ですよね?」
相手はサングラスをかけ直しながら、再度問うた。
「はい。そうですが」
一輝は、こうして声をかけられることは特に珍しいことではなかったので、笑顔で答えた。
案の定、相手もにっこりと微笑み、
「私、高城先生を応援しているんですよ。今度の選挙でも、小選挙区は高城先生、比例区は国民改新党に入れようと思っているんです」
「それは、ありがとうございます」
「客」の出現に、一輝は頭を下げた。すると、男は、
「あ、先生、ぜひ、握手をお願いします」
とゆっくりと両手を差し出してきた。
一輝は、その手を握り返そうとしたが、次の瞬間、みぞおちの辺りに鈍痛を感じた。
彼はは声も上げずに崩れた。
*
華ーー2015年4月6日16時55分 都内某マンション
彼女=謎の美少女は、俺を部屋に招き入れると、律儀にお茶を運んできた。
こんな風にされると、逆に恐縮してしまう。
だいたい、何をどう質問したらいいのかわからない。
あの時は、場の流れでつい一人で飛び出してしまったが、冷静になって考えてみると、こうして単身で取材活動などしたことはなかった。
流れるように質問をし、するすると相手の回答を引き出してしまう明日香の才能に、不本意ながら感心せざるおえない。
それにしても、目の前の少女は一体何者なのだろう。
当然、恋人……ということか。
あの野郎。硬派な顔してこんな年下の子と同棲なんてしてやがったのか。
この子が学生だったら、犯罪だぞ?
俺は写真でしか知らない不動の顔を脳裏に描くと、またふつふつと煮えたぎる何かを感じ、拳を固めた。
が、目の前の少女のどこか不安げな視線にぶつかり、俺は慌てて拳を隠した。
「まず……自己紹介しようか。俺は遠山颯人。TTVの報道カメラマンだ。別に怪しいもんじゃないぜ」
怪しい者ではない……という奴ほど怪しいか……。
俺は今更ながらしくじったと感じたが、少女は少し緊張感を和らげたようだった。
俺の言葉を額面通り受け取ったのか。
今時珍しいくらいに素直な子だ。
「あのう、私は雪です」
「雪……?それが君の名前?」
「……はい」
それにしても、この子は何者なのだろう。
考えてみれば、不動は芸能プロダクションの経営者だ。
この子は、奴のとこの新人アイドルか何かかもしれない。
そう言えば、不動は自分のところからデビューさせている新人アイドルを手当たり次第に喰っているって話だった。
デビュー前に「味見」しているなんてとこか。
ああ、さすがに察しがついてるか。そ。これも週刊誌の受け売りだよ。
俺は取材のいろはなんてわからない(知っていてもそんなまどろっこしい駆け引きなんか願い下げだ)から、取り敢えず、そのままストレートに聞いてみた。
「私ですか?そんな……恋人とか、そんなんじゃぜんぜんありませんよ。私、居候なんです」
「居候……?」
「はい。私、いつもお家賃半分払いたいって言っているんですが……不動さんに受け取ってもらえなくて」
一瞬、俺は彼女の回答を冗談だろうと受け取った。だが、彼女の申し訳なさそうな顔は、それが真実だという何よりの証拠な気がした。
「居候って……君、不動さんの親戚かなんかなの?」
「いいえ。私、不動さんとはそういうつながりはないと思います。……たぶん」
「たぶん……?」
「とにかく、私と不動さんがそんな関係なんて、本当にありません。うふふ……。彼、私のことなんて、そんな風に見て下さいません」
彼女はそう微笑んだ。心なしか寂しげな微笑みだった。
「恋人でもないのに、一緒に暮らしているのかい?」
彼女はただ、こくんと頷いた。
不動というのは、どれだけストイックな男なのだろう。
こんな綺麗な子が一つ屋根の下にいるなんて、俺だったら、正直、理性が持ち堪えられるか自信がない。
「あの……さっきのお話なんですけど」
「ん?」
「私のこと、誰にも言わないで頂けませんか?お世話になっている不動さんにご迷惑……おかけしたくないから……」
「それは……まあ、君が困るなら、俺も誰にも言わないが……どうして君はここの厄介になっているんだ?」
「私、帰る場所がないから……」
「ご両親とかは……いないの?」
「わかりません」
彼女はそう悲しげに目を伏せた。
この様子だと、恐らく両親とは死別か生別かしたのだろう。
だが、そのいずれにしても「わかりません」という返答があるだろうか。
さっきの「たぶん」と言い、この子の返答にはどこか釈然としないものがある。
どこかうまく噛み合わないというか、妙な居心地の悪さを感じる。
彼女自身は精一杯俺の質問に誠実答えようとしている。
その気持ちは痛いほど感じるのだが、(彼女の場合、俺が相手だからというのではなく、元来、そういう性格なのだろう)どこか発せらる答えは、俺に響いて来ないのだ。
まるでプログラムされた回答を吐きだすロボットと会話をしているような。
その正体は一体何なのだろう。
俺は嘘のつけない男だ。
腹芸なんてできない。なんでも思ったことが顔に出てしまう。
ガキの頃からそういうとこが不器用で、いろいろなものを失くした気がする。
だが、俺はそんな自分のことを嫌いじゃない。
だから、俺は思ったことを口にしていた。
「君、本当のこと言ってないね」
少しの沈黙が俺たちの間に降りた。
やがて、目の前の少女は、伏し目がちだった瞳を上げた。
「私……記憶がないんです」
「えっ……?」
「だから、不動さんと出会う前のこと、何一つわからないんです」
記憶がない……だと?
それは、所謂、記憶喪失という奴か。
そんなのドラマや小説の中でしかお目にかかったことがないが……。
「じゃあ、君は君自身が誰なのかもわからないのか?」
「はい……。この『雪』という名前も不動さんが付けて下さったんです。……不動さんのお話では、私、一ヶ月くらい前にこのマンションの前に倒れていたらしいんです。不動さんに助けて頂く前のこと、私何も覚えていなくて……私、自分がどこの誰なのかも何もかも……わからないんです」
「そう……だったのか。ごめん。悪いことを言った。嘘つき呼ばわりして……すまない」
「いいえ……いいんです。おかしいって思われるの当然ですよね。それに、今、遠山さんが言ったこと、間違ってないです。だって、この名前だって……『嘘』……なんですから」
彼女はそう言うと、少し微笑んだ。
微笑みというよりは、泣き笑いだった。
自分がどこの何者なのかがわからない。
それくらい心細く、恐ろしいこともないだろう。
彼女はその事実と向き合い……いや、無理矢理向き合わされて、こうして見ず知らずの男の保護を受けて細々と生きている。
俺はもう彼女の顔を見ていられなかった。
言いようのない罪悪感が胸を締め付ける。
「そんな言い方……止せよ。わからないから別の名前を名乗っている……それだけだろう?そういうのは……『嘘』とは言わない」
「ありがとう……ございます……。不動さんがいなかったら、私、きっと生きていなかったと思います。今、こうしてあなたとお話することもできなかったと思います。だから、私、すごく不動さんに感謝しているんです。こんな私の面倒を見て下さって……。それに、あなたに出会えたこともすごく嬉しいです」
「えっ……?」
「私、記憶を無くしてから不動さんしか知り合いがいなくて……新しい人と出会えて、なんだかすごく嬉しいんです。それに、遠山さん、すごく綺麗な目をされてるから。きっと私との約束、守ってくれるって、私、信じています」
俺も不動に感謝しなくてはならないのかもしれない。
奴がいなければ、彼女、『雪』と出会うこともなかっただろうから。
*
月ーー2015年4月6日17時14分 某埠頭
気がつくと、高城一輝は冷たいコンクリートの上にいた。
遠くで海猫の鳴く声が聞こえる。
「お目覚めですか。高城先生」
聞き覚えのある声にゆるゆると首を動かすと、サングラスの男が口元を歪めて立っていた。
男の背後に気配を感じた。
一人や二人ではない。
「彼ら」は一体何人いるのか、薄暗い倉庫の中のため、判別がつかなかった。
一輝は身体を起こしながら、必死に頭を巡らせた。
この男どもは誰の息のかかった者達なのか。
脳裏を過る候補があまりに多すぎて判断がつかなかった。
一輝は自嘲気味に笑った。
考えてみるれば、自分は敵が多すぎると。
とにかく、彼は悟った。
自分は罠にかかったのだと。
「誰に頼まれた?不毛な質問だったかな?そう聞いても君たちは答えてくれないだろうからね」
「まあね。誰かは言えないが、契約内容くらいは教えてやろうか。
あんたをやれば、百万って契約なんだ」
「百万か……随分安く見積もられたものだね。私の命の値段も」
「命?あんた、なんか勘違いしてねぇか?」
「えっ?」
「俺だって、百万ぽっちじゃ殺人まで請け負わないぜ?」
「やる」とは、「殺る」という意味ではないのか?
では、一体……?
「男なんて冗談じゃないって思ったんだけどな。最初は」
「何……?」
「テレビで見るより、ずっと綺麗だね。アンタ」
「何を……考えている?」
「こんな綺麗どころが政治家の先生だってんだから、困るな」
「信じられないな。女でもこんな上玉、なかなかお目にかかれないぜ?」
「まったくだ。たまらんね」
男たちが次々と口を開く。
「何を……する気なんだ?君たちは……?」
「困ったな。先生はとんとおわかりになっていないようだぜ?
まあ、すぐに感じるだろうが。その身体で」
そうせせら笑うと、男は顎を引いた。
その瞬間、いつの間に背後に回っていたのか、別の男が一輝に背後から羽交い締めにした。
「うあっ!!い……いたっ……痛いっ!!」
「手荒な真似はよしな。先生、痛がっているじゃねぇか。
まあ、そういう顔も悪くないがね」
「何の真似だ?君たちの目的は何なんだ?うわっ!?」
瞬く間に背広を奪われ、一輝はつんのめるように体制を崩した。
その身体を受けとめたのは、サングラスの男だった。
「いい背広だね。センセイ。さすがだよ。いい手触りだ。
でも、あんたのその肌の方がいい触り心地なんじゃないのかい?」
「やめろ……!!触るな!!」
一輝がそう身体をひねらせた瞬間、何かが一輝の唇を塞いだ。
それは、サングラスの男の唇だった。
「やめろ!!」
一輝は力いっぱい、その唇を突き離した。
「いい味だ。思った通り。先生、あんた、サイコーだよ」
一輝の脳裏に蓮との秘め事が過った。
悪夢のようなその出来事が。
「や……やめてくれ……」
「俺、ともだち多いからさ。選挙の時の票稼ぎにも悪くないと思うよ。
まあ、あんたの奉仕次第だがね」
「そ。おとなしく観念しようよ。ね?せんせい?」
彼を取り囲む、無数の赤い光。
それは、欲望に目を血走らせた無数の男たち。
一輝にもようやくわかった。
もはや彼は、狼の群れに投げ込まれた憐れな一匹の白兎だということが。
*
既に半裸にむかれた高城一輝は、ウインチで逆さに引き上げられ、その肢体を男どもの好奇の目に晒されていた。
その白い肌には、愛撫による無数の鬱血が見られ、鎖できつく縛りあげられた両手足首からは、鮮血が滴り落ちていた。
逆さにされてもうずいぶん経つ。
頭に全身の血液が降りてくる音が聞こえて来るようだった。
「いいザマだな。先生。どうだい。御気分は?」
一輝は自嘲気味に笑うことしかできなかった。
「さっきの愛撫でだいぶ感じてきたみたいだからな。今度はもっと楽しませてくれるんだろう?」
一輝は答えない。
そんな一輝の唇を男は貪る。
「……んっ……んあっ……」
唇を重ねたまま、一輝の身体はゆっくりと地上に戻された。
サングラスの男はそのまま唇を下降させていく。
その動きに合わせ、一輝の身体がびくんと反応していく。
男はその反応に満足そうに笑うと、一輝の胸の飾りを舐め上げた。
「あっ……!!」
一輝の身体がのけ反ると、男は指先で一輝のもう一方の胸の飾りを弄んだ。
「あっ……!!ああっ!!」
別の男が一輝の両足を取った。鎖が外される。
だが、それは解放を意味してのことではなかった。
引き裂かれるように両足が開かれると、別の男が一輝自身を咥え込んだ。
「ひっ!!あっ!!やっ!!だ、だめ!!」
「何がダメなんだい?先生」
「ああっ!!ああん……!!」
「いいね。先生自身のイイんだろ?こんなに勃ってんだから」
「あっ……あぁ……こんな……」
こんな屈辱を……。
なぜ?
なぜ、自分が?
自分が高城一輝だからか。
政治家・高城一輝だからか。
この時ほど、一輝は自分の職務を恨んだことはなかった。
自分は決して国民改新党の客寄せパンダになりたかった訳でも、こうして複数の男どもに辱められたかった訳でもない。
ただ、この国の未来を少しでも変えていきたい。
自分の手で未来に希望が持てる国を造っていきたかったからだった。
それだけだったのに。
皮肉なことに発作の代わりに自分の身体がびくんびくんと波打つように感じていた。
もし、発作が起きて自分が死んだら、自分はこうして恥辱を晒した状態で発見されるのだろうか。
明らかに男達から性的暴行を受けた痕跡を己の身体中に刻んだまま。
一輝は言いたかった。
『君たち、ことが終わったら、自分の身体は簀巻きにでもして東京湾に沈めてくれないか』
と。
この醜聞が誰かに知られるくらいなら、このまま東京湾の藻屑となった方がどれだけ幸せなのだろう。
だが、空しくそんな訴えも、吐息にしかならなかった。
「いい声じゃねぇか。先生よぉ?もっと鳴けよ」
殺られる。
そう。
殺された方がどれだけマシだというのだろう。
それから一輝は何度も犯された。
何度も何度も。
気がつくと、自分に入り込む男が変わっていた。
これが、何人目なのだろう。
そして、あと何人続くのだろう。
果てしない無間地獄。
いつしか、一輝は積極的に男たちを受け入れていた。
恐らく、彼の脳がこの「屈辱」を「快楽」に変換した方が「幸せ」だと判断した結果なのだろう。
一輝は声を上げた。
「もっと……もっと……激しく……して……」
*
風ーー2015年4月6日18時56分 都内某マンション
その日、午前中だけの講義を終えた僕は、だらだらと研究室で過ごした後、左近風魔の部屋を訪ねていた。
風魔は僕の隣の部屋に住んでいる。
このマンションは、僕が言うのもなんだが、普通の学生だったら、まず手が出ないだろう高級物件だ。
どうして僕がそんないい部屋に住めているかと言えば、答えは簡単で、このマンションのオーナーが叔父だからという一点に尽きる。
僕はこうしたコネクションを持っているからまだわかるのだが、風魔がどうしてここに住むことができているのか、さっぱりわからない。
確かに彼女は私立探偵という職を持っている。
だが、この職は収入とは無縁と考えて間違いない。
なぜなら、風魔は探偵業で金銭を受け取らないからだ。
そう考えると、彼女は僕と同じ、単なる大学院生ということになる。
まして、彼女は他にバイトをしている様子もないから、どこから収入を得ているのか、皆目見当がつかない。
いつか風魔は特待生だという話を聞いたので、学費は支払っていないのかもしれない。
だが、生活費の出所がさっぱりわからない。
親戚の誰かが仕送りでもしているのかもしれないが、今のところ、そういった影は全くちらつかない。
彼女はいかにしてこの生活を維持しているのか……。
僕がそんな取り留めない思考を巡らせていると、待ち人・左近風魔が現れた。
が、僕はその瞬間、口に含んだ紅茶を盛大に噴いていた。
そこには、左近風魔が立っていた。
一糸まとわぬ生まれたままの姿で。
僕は完全に硬直していた。
当たり前だろう。
彼女の、まるで彫刻のように滑らかな肢体が、眼前に惜しげもなく披露されているのだから。
「なんだ。そんなに人間の裸が珍しいのか」
「き、き、き、君はどうしてそんな格好をしているんだっ!?」
「ここは私の家だ。私がどんな格好でいようと何をしていようと、君にとやかく云われるような筋合いはない。だいたい、君が勝手に私のテリトリーを侵しているだけじゃないか」
そう言うと、彼女はうるさそうに長い髪をかき上げた。
その拍子につんと上を向いた形の良い乳房が揺れる。
そんな姿が、目のやり場に困るくらいに悩ましい。
僕は一応、目をそらしつつ、答える。
「そういう問題じゃないだろう?僕は男で君は一応、女じゃないか」
「何を今更わかりきったことを言っている?私はただ自宅でシャワーを浴び、寛いでいたところだ。闖入者は君だぜ?だから、聞いている。『そんなに人間の裸が珍しいのか』と」
そう言うと、彼女はいつの間に現れたのか、彼女の着替えを差し出した「執事」からそれを受け取ると、ブラを身につけた。
だいたい、この「執事」がくせ者なのである。
「執事」と言っても慇懃な老紳士を思い浮かべてもらっては困る。
僕より少し年上か、下手したら同い年か?というくらいに若い青年なのである。
風魔との付き合いももう一年になるが、僕はこの青年の下の名前さえ知らない。
「だいたい、君。そんなことを言い出すなんて、よこしまな精神の現れじゃないか」
そう風魔はにやりと笑うと、僕を見下すように見下ろした。
思わず、「よこしまで何が悪い」と叫びそうになったが、あまりに自分がみじめなのでやめた。
だいたい、風魔みたいに非の打ち所がないほど完璧に整った顔立ちや、体つきを目にすると、かえって気持ちが萎える。
恐れ多いとでもいうのだろうか。
誤解してもらっては困るのだが、僕は決して左近風魔に好意などを寄せてなどいない。
むしろ、嫌っていると言った方が正確だろう。
では、一体なぜ僕が彼女と行動を共にしているのか。
それは、彼女に返さなければならない借りがあるから。
ただ、その一点だ。
僕は一年ほど前、彼女に助けられた。
どんな件だったのかは、少し長くなるので、ここでは語らない。
追々、お知らせしようと思う。
まあ、今の段階では、僕はその件で左近に救われた。とだけ理解してもらえれば十分だ。
その恩をそのままにしておいては、寝覚めが悪いではないか。
彼女と一緒に行動しているのは……ただ、それだけだ。
だいたい、彼女は性格が全くかわいらしさに欠ける。
僕だって、確かに容姿はまあ、可愛い方が嬉しいが、見た目よりも性格が可愛らしい子の方がずっといいと思う。
それに、どういう訳か、彼女は黒衣しか身につけない。
一緒にいると、いつも喪中みたいで気持ちが萎える。
女の子だったら、もっと可愛らしいパステルカラーなんか着こなしてもよさそうなものだと思うのだが。
まあ、僕がそんなこと考えても意味がないことは重々承知しているが、なんとなく考えずにいられない。
僕は自分でも嫌になるくらいにお節介な性格なのだ。
僕がこうして悶々と思い悩んでいる間にも、風魔は着替えを終え(相変わらずの黒衣だ)、僕の向かえに腰を下ろした。
その途端に、「執事」の青年が、湯気の立つティーカップを風魔の前に差し出した。
「ありがとう。黒崎。で、今日は何の用だね。右門君」
「風魔。どうして君はいつもそんな喪服みたいな格好なんだい?君は同じ年代の女性たちが当たり前に持つはずの、オシャレという概念をどこかに置いてきてしまったんじゃないのかな」
僕は幾分、皮肉を込めて言ってみたのだが、あっさりと打ち返された。
ホームランで。
「右門君。愚かだね。君も」
「は……?」
「いいかい、私は探偵だ。探偵というのはね、時に死に遭遇し、死者を哀れみ、死者の声を聞かねばならない。そんな冥界の使者である私がパステルカラーの服装をまとえるとでも思っているのかい?」
「………………」
「私はいつ何時であろうと『探偵』なのだよ。どうかな。君の愚鈍な脳みそでもそろそろ探偵という職業が理解できてきたのではないのかな」
そう言うと、風魔はチャシャ猫のような嫌な笑みを浮かべて悠々と紅茶に口付けた。
こいつ、いつか殺す……。
*
月ーー2015年4月6日19時44分 某埠頭
政治家・高城一輝が連れ込まれた海沿いの倉庫では、歪んだ遊戯が繰り広げられていた。
一輝への愛撫に飽きた男達は、一輝を「玩具」としてゲームを始めた。
順番に一輝の身体スレスレにナイフを突き刺していくというものだった。
ルールはただひとつ。
一輝の素肌を傷つけず、より近くに突き刺したものが勝者。
三度ナイフを振り下ろした合計点で争われる。
丁度、猫が獲物として捕らえた鼠をすぐには殺さず、いたぶるように。
既に一輝の身体には、ナイフを打ち損じた男たちの手による傷が変色しつつある愛撫の痕と共に刻まれていた。
だが、その頃には、高城一輝にも自分を愛玩する男達を冷静に見上げる余裕が出来ていた。
一輝にナイフが振り下ろされる度、男達はやんやと歓声を上げた。
何度目かの閃光が走り、耳元で刃先とコンクリートとかち合う音が響く。
順番は、あの最初に一輝に声をかけたサングラスの男だった。
「ははは……あんた、いい度胸だな。耳元にナイフを振り下ろされて、平然としているなんて」
「褒めてくれているのかい。ちっとも嬉しくないが。それに、君。僕はまだ散髪に行く気もないんだが」
一輝はそう嘯くと、男を見上げた。
今のナイフで一輝の髪が数本切られていた。
「まあ、そう言うなよ。その綺麗な顔に傷がつかなかっただけでもよしとしてくれ。俺は不器用なんでね」
男は次に一輝の肩越しにナイフを放った。
「悪い。手元が狂った」
男がそう笑うと、一輝の白い腕に赤い線が走っていた。
一輝も笑っていた。
「次はどこがいい?」
「もう一度、今のところというのは、どうだい。……失敗したままだと、君も寝覚めが悪いだろう?」
「たいしたタマだな、先生。よし。じゃあ、リクエストにお答えして……」
男はそう口元を歪めると、ナイフを振り下ろした。
が、次の瞬間、はっとして身を固くした。
刃の部分を一輝がしっかりと握っていたから。
「なんっ……!?」
一輝は男の狼狽にふいに笑みを見せると、手首を捻り、ナイフを奪い取った。
その拍子に一輝の手の平から赤い鮮血が滴った。
「許してくれ」
一輝はそう顔を伏せると、逆手でナイフを男の太股に突き刺さった。
「野郎……!!やりやがったな!?」
ひるんだ男の手から逃れると、一輝は駆け出した。
まさかこれだけボロボロになった一輝が反乱を起こすなど思いもよらなかったのか、男達はバラバラと慌てて彼を追いかけた。
一輝は必死に走った。
自分の姿を隠す夜の帳の闇に感謝しながら……。
視界は既に闇にその支配権を明け渡しつつあった。
辺りに響くのは、潮騒と自分の足音、息づかい。
海風が強くなっていた。
ふいに一輝の鼓膜が別の音を捉えた。
一軒の倉庫らしき場所から、ぎぃっという耳障りな音が響いていた。
一輝はその音に誘われるように倉庫に足を踏み入れた。
倉庫内は、廃墟と表現した方がしっくりくるほどに荒れ果てていた。
所々に薬品瓶のようなものが散乱している。
工場というよりは、何かの研究施設の跡地なのかもしれない。
音の正体は、古びたロッカーだった。
ロッカーの扉が風に煽られ開け閉めされる度、軋んだ騒音を響かせている。
その扉は、海風のせいか、ひどく錆び付いているようだった。
一輝の視線は、そのロッカーに釘付けになった。
断続的に開閉するロッカーの中には、今は主を失った白衣がはためいていたのだ。
思いの外、それは汚れていないようだった。
一輝はそれを失敬することにした。
白衣一枚とは言え、何かを身に纏っただけで一輝の精神は微かに落ち着きを取り戻した。
それにしても、どれくらいの時間が経過したのだろう。
秘書の楠美香子と別れたのが午後4時過ぎだった。
この夕闇はその晩のものか?それとも……。
いずれにせよ、この選挙戦の最中に休暇以外の理由で「政治家・高城一輝」が消えるというのは最大のスキャンダルだった。
倉庫を後にし、歩を進めていると、身体の節々に熱さと痛みを感じた。
それでいて、身体の芯は凍えるように寒かった。
自分は今、明らかに発熱している。
全身の重苦しさと強い目眩。
まずい状況だった。
こんなところで意識を失っては、いつ奴らに見つかるかわからないし、何より極上の醜聞だった。
こんな姿を発見でもされたら、それこそ東京湾の藻屑となった方がどれほど幸せかしれない。
遠くでまた海猫の啼く声が聞こえた。
一輝は必死に意識を奮い立たせ、そして、考える。
これからどうするべきなのかを。
だが、その答えは遙かこの埠頭の彼方に広がる海底のように取り留めなく、深く、暗いように思えた。
「おい。誰かいるのか?」
その声に、一輝の身体は硬直した。
顔を上げると、人影があった。
もう終わりだ……!!
一輝はきつく目を閉じた。
そんな彼に降って来たのは息を呑むかのような声。
「あんたは……」
0
あなたにおすすめの小説

上司、快楽に沈むまで
赤林檎
BL
完璧な男――それが、営業部課長・**榊(さかき)**の社内での評判だった。
冷静沈着、部下にも厳しい。私生活の噂すら立たないほどの隙のなさ。
だが、その“完璧”が崩れる日がくるとは、誰も想像していなかった。
入社三年目の篠原は、榊の直属の部下。
真面目だが強気で、どこか挑発的な笑みを浮かべる青年。
ある夜、取引先とのトラブル対応で二人だけが残ったオフィスで、
篠原は上司に向かって、いつもの穏やかな口調を崩した。「……そんな顔、部下には見せないんですね」
疲労で僅かに緩んだ榊の表情。
その弱さを見逃さず、篠原はデスク越しに距離を詰める。
「強がらなくていいですよ。俺の前では、もう」
指先が榊のネクタイを掴む。
引き寄せられた瞬間、榊の理性は音を立てて崩れた。
拒むことも、許すこともできないまま、
彼は“部下”の手によって、ひとつずつ乱されていく。
言葉で支配され、触れられるたびに、自分の知らなかった感情と快楽を知る。それは、上司としての誇りを壊すほどに甘く、逃れられないほどに深い。
だが、篠原の視線の奥に宿るのは、ただの欲望ではなかった。
そこには、ずっと榊だけを見つめ続けてきた、静かな執着がある。
「俺、前から思ってたんです。
あなたが誰かに“支配される”ところ、きっと綺麗だろうなって」
支配する側だったはずの男が、
支配されることで初めて“生きている”と感じてしまう――。
上司と部下、立場も理性も、すべてが絡み合うオフィスの夜。
秘密の扉を開けた榊は、もう戻れない。
快楽に溺れるその瞬間まで、彼を待つのは破滅か、それとも救いか。
――これは、ひとりの上司が“愛”という名の支配に沈んでいく物語。


邪神の祭壇へ無垢な筋肉を生贄として捧ぐ
零
BL
鍛えられた肉体、高潔な魂――
それは選ばれし“供物”の条件。
山奥の男子校「平坂学園」で、新任教師・高尾雄一は静かに歪み始める。
見えない視線、執着する生徒、触れられる肉体。
誇り高き男は、何に屈し、何に縋るのか。
心と肉体が削がれていく“儀式”が、いま始まる。

お兄ちゃんができた!!
くものらくえん
BL
ある日お兄ちゃんができた悠は、そのかっこよさに胸を撃ち抜かれた。
お兄ちゃんは律といい、悠を過剰にかわいがる。
「悠くんはえらい子だね。」
「よしよ〜し。悠くん、いい子いい子♡」
「ふふ、かわいいね。」
律のお兄ちゃんな甘さに逃げたり、逃げられなかったりするあまあま義兄弟ラブコメ♡
「お兄ちゃん以外、見ないでね…♡」
ヤンデレ一途兄 律×人見知り純粋弟 悠の純愛ヤンデレラブ。

BL 男達の性事情
蔵屋
BL
漁師の仕事は、海や川で魚介類を獲ることである。
漁獲だけでなく、養殖業に携わる漁師もいる。
漁師の仕事は多岐にわたる。
例えば漁船の操縦や漁具の準備や漁獲物の処理等。
陸上での魚の選別や船や漁具の手入れなど、
多彩だ。
漁師の日常は毎日漁に出て魚介類を獲るのが主な業務だ。
漁獲とは海や川で魚介類を獲ること。
養殖の場合は魚介類を育ててから出荷する養殖業もある。
陸上作業の場合は獲った魚の選別、船や漁具の手入れを行うことだ。
漁業の種類と言われる仕事がある。
漁師の仕事だ。
仕事の内容は漁を行う場所や方法によって多様である。
沿岸漁業と言われる比較的に浜から近い漁場で行われ、日帰りが基本。
日本の漁師の多くがこの形態なのだ。
沖合(近海)漁業という仕事もある。
沿岸漁業よりも遠い漁場で行われる。
遠洋漁業は数ヶ月以上漁船で生活することになる。
内水面漁業というのは川や湖で行われる漁業のことだ。
漁師の働き方は、さまざま。
漁業の種類や狙う魚によって異なるのだ。
出漁時間は早朝や深夜に出漁し、市場が開くまでに港に戻り魚の選別を終えるという仕事が日常である。
休日でも釣りをしたり、漁具の手入れをしたりと、海を愛する男達が多い。
個人事業主になれば漁船や漁具を自分で用意し、漁業権などの資格も必要になってくる。
漁師には、豊富な知識と経験が必要だ。
専門知識は魚類の生態や漁場に関する知識、漁法の技術と言えるだろう。
資格は小型船舶操縦士免許、海上特殊無線技士免許、潜水士免許などの資格があれば役に立つ。
漁師の仕事は、自然を相手にする厳しさもあるが大きなやりがいがある。
食の提供は人々の毎日の食卓に新鮮な海の幸を届ける重要な役割を担っているのだ。
地域との連携も必要である。
沿岸漁業では地域社会との結びつきが強く、地元のイベントにも関わってくる。
この物語の主人公は極楽翔太。18歳。
翔太は来年4月から地元で漁師となり働くことが決まっている。
もう一人の主人公は木下英二。28歳。
地元で料理旅館を経営するオーナー。
翔太がアルバイトしている地元のガソリンスタンドで英二と偶然あったのだ。
この物語の始まりである。
この物語はフィクションです。
この物語に出てくる団体名や個人名など同じであってもまったく関係ありません。

屈辱と愛情
守 秀斗
恋愛
最近、夫の態度がおかしいと思っている妻の名和志穂。25才。仕事で疲れているのかとそっとしておいたのだが、一か月もベッドで抱いてくれない。思い切って、夫に聞いてみると意外な事を言われてしまうのだが……。


どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる