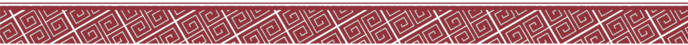19 / 59
13、ゼンジの嗜好
しおりを挟む食欲がわかず、朝食もとれなかったわたしを心配して、クランはこまごまとした世話を焼いてくれた。額の熱冷ましを替えに定期的に来てくれて、そのたび水を飲ませてくれたり、汗を拭いてくれた。
ほんとうに、お世話になりっぱなしだよ……。
昼過ぎには、マシンくんが様子を見に来てくれた。
マシンくんの手には、薬湯の器がのったお盆。
ゼンジさんが煎じてくれたものだろう。
「クラシュン、マシン」
「ゼンジ、マイライキーテイラム」
マイ……キーテイ……、えっと、なんだっけ……。
頭を巡らせていると、クランが訳してくれた。
「ゼンジガ、アヤマッテイタ、ト……。ホントウニ、モウシワケアリマセン、ミナミ・フーシャニ、ヨケイナ、ゴシンパイヲオカケシテ……」
「ううん、わたしが勝手に考えちゃっただけで……」
ぼんやりしながら、薬湯を飲んだ。
うう、暑いのに、熱いのを飲むのは、きついな……。
「アッ、ゼンジ!」
クランが、ぱっと立ち上がった。
同時に、枕の脇にいた旬さんの左手が、まるで臨戦態勢に入ったみたいにこぶしを握った。
部屋の入り口で、ゼンジさんがこちらの様子をうかがっていた。
「マイライアウシュウ、ミナミ・フーシャ……。リシャウシャ?」
黒めがちな大型犬みたいな目が戸の隙間からのぞいている。
「クラシュン、ゼンジさん」
声をかけると、ゼンジさんはどこかうきうきとした様子でやってきて、当たり前のようにクランの隣に椅子を置いて腰を掛けた。
旬さんがぐいっと前に出て、ゼンジさんを威嚇したが、どういうわけか今日のゼンジさんには威嚇が効いていない。
「ムタコークメンターラ。センツヘムカリマンシャ?」
「ネツガ、タカイミタイデスネ。キノウハ、ヨクネムレナカッタノデスカ? トイッテイマス」
旬さんがいつかのように筆を振り上げるようにしてさらに威嚇した。
それにもかかわらず、ゼンジさんは目を見開いて、ぐいぐいと身を乗り出してくる。
「ミナミ・フーシャハ、カラダガヨワイヨウデスガ、イツカラデスカ? コドモノコロカラデスカ? トイッテイマス」
クラン、訳すのはもういいよ。
旬さんとゼンジさんがぶつかりそうだよ……。
「ネツノホカニ、ドノヨウナ、ショウジョウガアリマスカ? タトエバ、ノドノイタミ、カンセツツウ、メマイ……」
「クラン、あの……」
「ムダデス、ミナミ・フーシャ」
「え?……」
クランは隣のゼンジさんを見やった。
その様子はどこかげんなりしているように見える。
一方のゼンジさんは、じっと熱のこもった視線でわたしを見ている。
「コノヒトハ、ビョウキノヒトガ、スキナンデス」
「ん……? どういうこと……?」
「ゼンジハ、ビョウニンヤ、ケガニンガ、スキナンデス。ナオスノガ、スキナンデス……」
ええと……?
薬師だから治療するのは仕事だから、嫌いよりは好きなほうがといいとは思うけど……。
え、なんか、ちがう?
「コウイッテハ、ゴカイヲマネクカモシレマセンガ、ツマリ、ゼンジハ、ミナミ・フーシャガ、キョジャクナノデ、トテモ、コウフンシテイルノデス。コノヒトハ、トニカク、ミナミ・フーシャノ、チリョウシタリ、カンビョウガ、シタイノデス。ガマンスルヨウニ、イイキカセテキタノデスガ、アマリニモ、ミナミ・フーシャノ、オカラダガヨワイノデ、マスマスキョウミヲ、モッテシマッテ……」
興奮……?
興味……??
い、いや、ちょっと待って……、意味がわからない。
熱っぽい頭で必死に考えていると、旬さんがわたしの手に三つの字を書いた。
「フ、ェ、チ……?」
ええ?
つまり、ゼンジさんはなんていうか、看護フェチ? 治療フェチ?
そんな嗜好があるの?
「ゼンジハ、チョット、ヘンナノデス……」
「そう……なんだね……」
「モウスコシ、ゼンジニ、ツキアッテモラエマスカ? カイフクスレバ、コノシツコサカラ、カイホウサレルハズナノデ……」
「あ……、う、うん……」
その後も、繰り返される質問に、おぼろげながら答えた後、わたしの熱はやっぱり下がらなかった。
ああ、一体なんなのもう……。
明日もまたゼンジさんの質問攻めにあうのは、さすがに嫌だ……。
はやく、回復しなくちゃ……。
回復したい……。
幸いにも、翌日熱の下ったわたしは、ゼンジさんの薬湯を飲みながら、自分の虚弱体質について、いろいろと話す羽目になった。
はじめはゼンジさんを警戒していた旬さんなのに、いつのまにか、むしろゼンジさんに診せとけば安心みたいな感じに変わって、自分のことに没頭してしまっている。
むむむむむ……。
ただでさえ、普通にコミュニケーションが取れないのに、それなのに、わたしとは話さないつもりなの?
このままじゃ、気持ちがすれ違っちゃいそうだよ……。
ゼンジさんの看護・治療フェチ、長いので略してKTフェチが幸いしてか、この数日間でわたしの語彙力は一気に上昇した。
借りた辞書とマイ辞書を片手に、自分の体のあれこれや病歴などを説明したのが、短期集中的な会話演習になったからだ。
「だから……、遠い、ところ、行く、難しい。ていりょく、ない」
「体力、です」
「たいりょく、ない」
「うわあ、すごいなあ! 僕至上、一番治療し甲斐があるよ、美波浮者は!」
「こら、ゼンジ! そこは喜ぶところじゃないでしょ! だから、あんたには真剣みが足りないのよ」
「いやあ、僕はいたって真剣そのものだよ!」
クランとゼンジさんのテンポの速いやり取りも、少しずつ聞き取れるようになってきた。
「旬さんと、イスウエーンの、大将軍、会う行く、体力、つけたい思う、まし。たしゅけて、もらい、ましか?」
「もちろんです、美波浮者! 僕が絶対に治してあげますから」
「おしいです美波。助けてもらえますか、ですよ」
「たすけてもりゃえましか」
「たすけて、もらえ、ますか」
「難しいでし……。たすけて、もらえ、ますか」
「そうです!」
ふー……、単語を並べただけでも、なんとか伝わるけど、発音がまだ難しいなあ。
同じ言葉でも中国語みたいに発音が何種類もあるんだもん。
そろそろ発音記号を決めたほうがいいかもしれないな……。
印帳に、今の発音をメモしておく。
印帳越しにクランとゼンジさんを見た。
人のことにかまけて、自分を疎かにしてしまったことは反省しているけれど、こんなに仲のよさそうなふたりを見ていると、一緒になれないなんて、頭でわかってもそう簡単に納得できない。
比べたって仕方ないけど、自分だったらと思うと、切なくてやりきれない。
もしも、旬さんとお互い思いが通じ合っているのに、状況がそれを許さないとしたら。
今のわたしには、とても考えられない。
でも、一番辛いのは本人たちなんだから、脇でいろいろいうのもよくないね……。
「美波浮者、まだまだ聞きたいことがたくさんあります。今度、御不浄にいくときは、ぜひ僕もご一緒させてください。お小水を少々頂戴したく……」
「この変態!」
クランの平手が飛んだ。
「痛ってーっ! なんで殴るんだよ。これはれっきとした治療の一環だぞ」
「あんたってば、頭腐ってるんじゃないの? 女性に対してそんなこというなんて、どうかしてるわよ!」
「だから、治療に役立てるためだっていってるだろ。別に飲むわけじゃないし」
「こんの、ど変態っ! だからあんたに美波の看護をさせたくなかったのよ!」
早口なうえに、わからない言葉が立て続けに出てきたので、クランがなぜゼンジさんをぶったのかよくわからない。
「クラン、へんたーい、は、なんでしか?」
「み、美波は知る必要ありませんから!」
書きつけようとするわたしをクランの手が素早くとどめた。
……なんか、おかしな言葉なんだね。
ゼンジさんのKTフェチは十分変だから、もうあんまりびっくりはしないと思うけど。
そのあと、マシンくんがまた部屋を訪ねてきてくれた。
今日はひとりではなく、年かさの僧侶と二十歳くらいの僧侶の三人だ。
「ご機嫌いかがですか、美波浮者」
「マシンくん、こんにちは」
「熱が下がったと聞いたので、音響治癒法を差し上げようと思い、参りました」
「おうんきょ……?」
三人の僧侶の手には、金物でできた平たく丸いつぶれたボールみたいな形のものがある。
そして、おのおのバチのような棒を持っている。
日本で見たことのあるもので一番近いものでいうと、えーと、パンドラムだ。
「マシン、それはいい案ですね! 美波浮者、これは音楽による癒しをもたらす療法です。きっと気に入ると思いますよ」
「へえ……」
マシンくんたちは準備を整えてその場に座すと、手を合わせて一礼した。
わ、なんか急に厳かな感じに……。
ポワーン、と硬質ながらもふくよかな音が、空気を波のように振るわせていく。
主旋律は若い僧侶で、少し高めの音がするパンドラムからは、ポロンポロンと雨を思わせるようなメロディがする。
中間音域のパンドラムはマシンくんで、多分ギターでいうならコードをならしていて、一番年上の僧侶が低い音でリズムを刻んでいる。
こうして目の前でパンドラムを聞くのは初めてだったけれど、皮膚から音が流れ込んでくるみたいで、うっとりしてしまう。
わあ、すごく心地いい音楽……。
曲が終わると、自然と体が楽になっているのがわかった。
拍手で音の余韻を消してしまうのがおしくて、じっと我慢していたけど、やっぱり最後には拍手した。
「素敵、音でし。マシンくん、ふたりも、素晴らしいを、聞かせてくれて、ありがとうございます」
「美波浮者にお気に召して頂けて幸いです」
マシンくんが誇らしげにほほ笑んでいる。
ちら、と旬さんを見たので、わたしは旬さんにも感想を聞いてみた。
「マシンくん、旬さん、すばらしい、いってまし」
「旬浮者からのお言葉、うれしく存じます」
「おうんきょ治癒ふぉう、とても、好きです。それは、なんといいますか?」
マシンくんが楽器の説明をしてくれた。
パンドラムはこちらの言葉でクワンランというそうだ。
クワンランは、かつては流の力を込めて演奏する流者専用の高価な楽器だったが、新しい術式が広まってからは安価なものもつくられるようになり、一般の人々にも広く親しまれるようになったのだそう。今ではこうした音響治癒療法として利用されるほかに、大人数で合奏したり、領地で一番の演奏家を決めるコンテストのようなものまであるらしい。貴賤に関わらず、とても人気のある楽器なんだそうだ。
話の途中で、若い僧侶が小さく咳払いした。
やにわにマシンくんがはっとして、思い出したようにふたりの先輩僧侶を紹介し始めた。
「向かって左が、クワンランの指導者ターマン師父、中央が兄弟子のカーツです」
ハナムンでは相手の身分が上の場合、見知ったものが紹介をしてくれない限り、口を開くことができないらしい。
マシンくんは、わたしたちの前で演奏することに緊張していて、うっかり紹介を忘れてしまったのだそう。
なんか、年相応な感じがしてほっとしちゃう。
ていうか身分が上、って、旬さんなら確かにそうだろうけど、浮のないわたしにとっては、恐れ多いばかりなんだけど……。
「カーツと申します。ただいま奏上いたしました曲目は、九月の雨でございます」
「九月、の、雨。やさしい、音でし」
「サイシュエンでの夏はまだまだ続きますが、美波浮者には、雨の音楽の処方が必要だと聞きましたので、少し梅雨には早すぎましたが、
この曲を選ばせていただきました」
カーツさんは目眉がきりっとした美僧だ。
おまけに、声もいい。
んん? ひょっとすると、彼もクランのお婿さん候補なのかな?
「つゆ……、梅雨、九月ですか? 日本、六月でし」
今度はターマンさんが口を開いた。
ターマンさんはコルグさんと同じくらいの歳だろうか。
朴訥とした印象は、コルグさんとは違っているけれど、とても僧侶らしい感じがする。
「ハナムンの梅雨は九月ですが、とても短く二週間ほどです。長い雨は秋の収穫に影響が出てしまうので、そのときは雨止めの音楽を奏上します」
「雨止めのおうんがく、ききたいでし」
「美波浮者、それはだめです。僕が処方したのは雨の音楽だけです。雨止めの音楽なんて聴いたら、また体調を崩してしまうかもしれない」
「ああ……。おうんがくの、治療でし。理解しました」
改めて三人にお礼をいい、退出を見送った後、わたしはちらりとクランを見た。
クランとカーツさんの間に醸されたものははっきりとしたなにかではなかったものの、たぶん予想は当たっているように思えた。
「わたしも、いつか、クワンラン、練習、できましか? とても、素敵でし、た」
「それなら、わたしが教えて差し上げますよ」
「だめだめ、クランの教えられる曲は、恋の歌と太陽の曲ばかりじゃないか。今美波浮者に必要なのは、雨や土、あと、ときどき風の曲だけだ」
「か、風の曲なら一曲覚えてるわよ」
「美波浮者、クワンランを学びたいなら、ターマン様に頼むのが一番ですよ。クランはすぐ歌ってごまかしますから」
「ちょっと!」
そっか、クランも、ゼンジさんも、マシンくんも、みんなわたしのために、いろいろ考えてくれているんだな……。
わたし、多分、すごく、ラッキーな気がする。
浮者としてこの世界に運ばれたにもかかわらず、全然浮の力がない。
それにもかかわらず、トラントランの人たちは、みんな礼儀正しいし、とても親切にしてくれる。
こんなにお世話になっているのに、わたしにはなにも返せるものがない。
それどころか、恩返しする暇もなく、イスウエンに発つことになるかもしれない。
「わたし……、行く、いや、でし……」
「え? 美波、なにが嫌なんですか?」
こんなこといったら、旬さんに悪いけど、だって……。
「トラントラン、離れる、不安。行きたく、ない、でし、イスウエン……」
旬さんが驚いたように、わたしの手を強くつかんだ。
「ごめん、旬さん。行かなきゃいけないのはわかってるんだけど、クランたちから離れて行くの、正直不安だよ。わたしは浮のない浮者なのに、イスウエンで受け入れてくれるのかな……」
「みなみ、おれがいる」
旬さんがすばやく指を走らせた。
素直にその言葉を受け止められない。
「でも、旬さんこのところずっと自分のことばっかりじゃん! 旬さんはいいよね、左手だけでもきっといろいろできちゃうんでしょ? よくわかんないけど、どこに誰がいるかもわかって、そのうち喋れるようになって、きっと、翻訳も簡単にできちゃうんでしょ? きっと、イスウエンでも優遇されるよ、旬さんなら。でも、わたしは違う!」
クランとゼンジさんが驚いた顔でわたしを見つめている。
ごめんね、急に火山爆発みたいになって。
でも、一旦火がついたら、とまらない。
今日まで積もり積もってきた、旬さんに放っておかれていた不満。
わたしは、不安なんだよ……!
「旬さんが一生懸命、力の使い方を見つけようとしているのはわかるし、わたしのために頑張ってくれてるのも本当にそうだと思うけど、わたしにはできることがなにも……。この世界でできることなんて、本当にちょっとのことしかなくて、不安なんだよ。クランと、友達と離れることも、親切にしてくれる人たちと離れることも。ゼンジさんやコルグさん、マシンくんたちのこと、少しずつ分かってきたのに、それを全部捨てて、また一からやり直すなんて、わたし嫌だよ……」
気がついたら、目頭が熱くなっていた。
わたしは泣き出してしまう前に、クランとゼンジさんに、旬さんとふたりにして欲しいと告げた。
ふたりが出て行ってから、わたしはもう一度、旬さんと向き合った。
旬さんの手が、そろそろと近寄ってきて、そっとわたしの手を取った。
「ごめん」
「わからない。旬さんの顔がわからない。今、どんな顔してるの? 旬さんと顔を見て話したいよ」
「おれにはみえるよ」
「わたしには見えないの。本当にこっちをみてる? わからないよ……」
我慢していたものが、ほどけてしまった。
ここに来る前なら、わたしは旬さんの胸で泣けた。
今は、すがりたくても頼りない左手があるだけ。
その左手は、見慣れたリングをして、相変わらず薬指は長いけれど、まるで他人の手みたい。
前は、抱きしめていないと不安で眠れなかったけど、今は抱きしめても、本当に旬さんなのかわからなくなるときがある。
「ごめん、みなみ、こんなにふあんにさせてたとは、きがつかなかった」
「ほんとだよ、旬さん、わたしを放ったらかしすぎだよ……」
「おれのほうからは、みなみのすがたが、だいぶはっきりみえるようになったから、あんしんしてた」
「わたしは、さみしかった」
「わるかった、ごめん」
「ずっといっしょにいてくれるっていったのに……」
「それは、たしかに。でも、おれのいしきのとどくところにいたよいつも」
「それは旬さんから見てでしょ。わたしには見えてない」
「そうだな、ごめん」
「もう、あやまってばっかり」
「これからは、ちゃんとそばにいるようにする」
「……」
「クランとでかけるときも、ついていく」
「ううん、それはいいや」
「え、なんで」
指だけなのに、旬さんがうろたえたのがわかった。
なんか、可笑しい……。
本当久々だな。
こんなふうに、ちゃんと旬さんと話をするのは。
「なんで? ついていくって」
「ううん、それはいい」
「なんでだよ、しらないおとことあってるのか?」
「え、なんでそんな話になるの?」
「あってないんだな?」
「会ってないよ。誰なの、知らない男って」
「しらないよ、こっちがききたい」
「なにいってるの?」
「だってきゅうに、ついてこなくていいとかいうから」
ぷっ……、なにそれ。
もしかして、心配してくれたの?
「それは、クランと女子トークしたいから。旬さん、わたしが浮気してると思ったの? ひどいんだけど」
「ひどくないだろべつに」
「え、なにそれ……。傷ついた……」
「ごめん、そうじゃなくて」
「いまさら言い訳とか聞きたくないし……」
「ごめんってば」
「……」
「こっちはみえるっていったて、みなみをまもれる、ちからがあるわけじゃないんだ。ほかのおとこが、みなみをうばおうとしたら、いまのおれには、たちうちできない。はやくふじゅつを、つかえるようにならないかぎり、またぼこぼになぐられて、つちにうめられて、おわりだ」
「そんなの、わたしもやだよ」
「そうだろ、それに」
それにのあと、旬さんはためらっているかのように、わたしの甲の上で止まっている。
なんとなく、なにをいいたいのかわかってしまった。
「旬さんが一日に一回、こうやってちゃんと話す時間を作ってくれたら、わたし大丈夫だから」
「そうだな、おれもひさびさにちゃんとはなせて、よかった」
「でも、今度おろそかにしたら、旬さんのこと忘れちゃうかもしれないからね?」
「そんなことになったら、こんどはおれがなく」
ほんと、話すって大事だね。
すれ違いかけていた気持ちが、ちゃんと元に戻った。
「旬さんは日本でもハナムンでも、世界で一番大切な人だよ」
旬さんの指先に、そっとキスをする。
旬さんは柔らかな手つきで、わたしの頬や唇に触れた。
「おれも、みなみにキスしたい」
そうだね。
早くその日が来るといいな。
8
あなたにおすすめの小説

愛された側妃と、愛されなかった正妃
編端みどり
恋愛
隣国から嫁いだ正妃は、夫に全く相手にされない。
夫が愛しているのは、美人で妖艶な側妃だけ。
連れて来た使用人はいつの間にか入れ替えられ、味方がいなくなり、全てを諦めていた正妃は、ある日側妃に子が産まれたと知った。自分の子として育てろと無茶振りをした国王と違い、産まれたばかりの赤ん坊は可愛らしかった。
正妃は、子育てを通じて強く逞しくなり、夫を切り捨てると決めた。
※カクヨムさんにも掲載中
※ 『※』があるところは、血の流れるシーンがあります
※センシティブな表現があります。血縁を重視している世界観のためです。このような考え方を肯定するものではありません。不快な表現があればご指摘下さい。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

私が王子との結婚式の日に、妹に毒を盛られ、公衆の面前で辱められた。でも今、私は時を戻し、運命を変えに来た。
MayonakaTsuki
恋愛
王子との結婚式の日、私は最も信頼していた人物――自分の妹――に裏切られた。毒を盛られ、公開の場で辱められ、未来の王に拒絶され、私の人生は血と侮辱の中でそこで終わったかのように思えた。しかし、死が私を迎えたとき、不可能なことが起きた――私は同じ回廊で、祭壇の前で目を覚まし、あらゆる涙、嘘、そして一撃の記憶をそのまま覚えていた。今、二度目のチャンスを得た私は、ただ一つの使命を持つ――真実を突き止め、奪われたものを取り戻し、私を破滅させた者たちにその代償を払わせる。もはや、何も以前のままではない。何も許されない。

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

裏切りの代償
中岡 始
キャラ文芸
かつて夫と共に立ち上げたベンチャー企業「ネクサスラボ」。奏は結婚を機に経営の第一線を退き、専業主婦として家庭を支えてきた。しかし、平穏だった生活は夫・尚紀の裏切りによって一変する。彼の部下であり不倫相手の優美が、会社を混乱に陥れつつあったのだ。
尚紀の冷たい態度と優美の挑発に苦しむ中、奏は再び経営者としての力を取り戻す決意をする。裏切りの証拠を集め、かつての仲間や信頼できる協力者たちと連携しながら、会社を立て直すための計画を進める奏。だが、それは尚紀と優美の野望を徹底的に打ち砕く覚悟でもあった。
取締役会での対決、揺れる社内外の信頼、そして壊れた夫婦の絆の果てに待つのは――。
自分の誇りと未来を取り戻すため、すべてを賭けて挑む奏の闘い。復讐の果てに見える新たな希望と、繊細な人間ドラマが交錯する物語がここに。

冤罪で辺境に幽閉された第4王子
satomi
ファンタジー
主人公・アンドリュート=ラルラは冤罪で辺境に幽閉されることになったわけだが…。
「辺境に幽閉とは、辺境で生きている人間を何だと思っているんだ!辺境は不要な人間を送る場所じゃない!」と、辺境伯は怒っているし当然のことだろう。元から辺境で暮している方々は決して不要な方ではないし、‘辺境に幽閉’というのはなんとも辺境に暮らしている方々にしてみれば、喧嘩売ってんの?となる。
辺境伯の娘さんと婚約という話だから辺境伯の主人公へのあたりも結構なものだけど、娘さんは美人だから万事OK。

天才天然天使様こと『三天美女』の汐崎真凜に勝手に婚姻届を出され、いつの間にか天使の旦那になったのだが...。【動画投稿】
田中又雄
恋愛
18の誕生日を迎えたその翌日のこと。
俺は分籍届を出すべく役所に来ていた...のだが。
「えっと...結論から申し上げますと...こちらの手続きは不要ですね」「...え?どういうことですか?」「昨日、婚姻届を出されているので親御様とは別の戸籍が作られていますので...」「...はい?」
そうやら俺は知らないうちに結婚していたようだった。
「あの...相手の人の名前は?」
「...汐崎真凛様...という方ですね」
その名前には心当たりがあった。
天才的な頭脳、マイペースで天然な性格、天使のような見た目から『三天美女』なんて呼ばれているうちの高校のアイドル的存在。
こうして俺は天使との-1日婚がスタートしたのだった。

わたしの下着 母の私をBBA~と呼ぶことのある息子がまさか...
MisakiNonagase
青春
39才の母・真知子は息子が私の下着を持ち出していることに気づいた。
ネットで同様の事象がないか調べると、案外多いようだ。
さて、真知子は息子を問い詰める? それとも気づかないふりを続けてあげるか?
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる