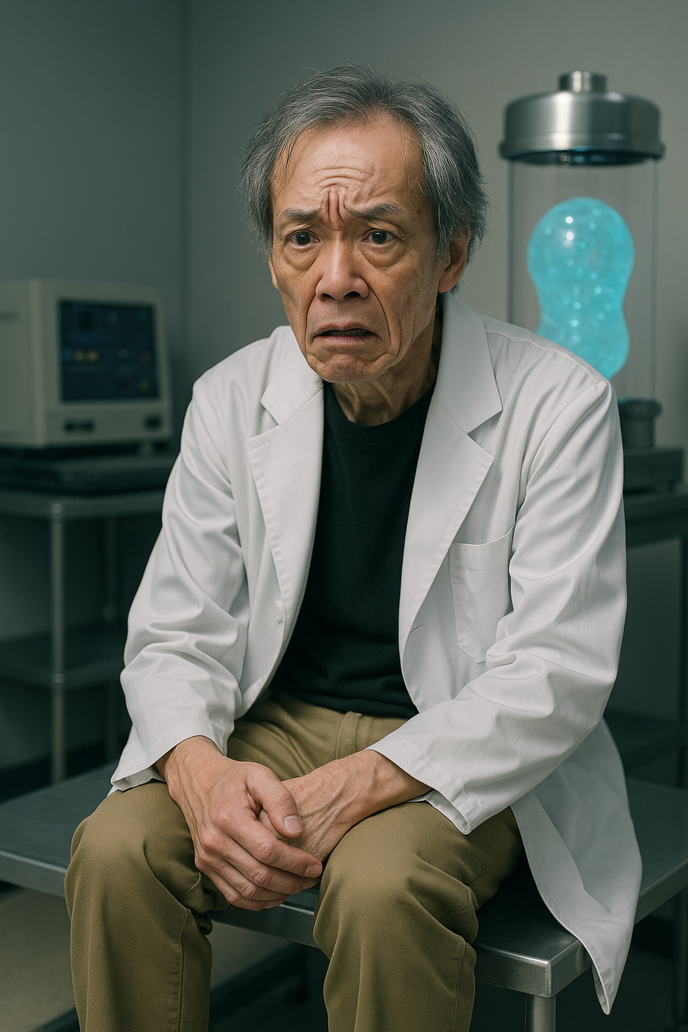1 / 1
博士と美人女子大生の入れ替わり
しおりを挟む
日本科学医療大学、人体実験観察室。
白い光が眩しい無菌室で、一人の女子大生が椅子に座らされていた。彼女の名は綾瀬 美月(あやせ みづき)、医学部四年。スラリとした肢体、知的で涼やかな目元、まさに「才色兼備」を絵に描いたような女性だった。
「…緊張してる?」
目の前の中年の研究者、権田博士がにやりと笑う。
「そりゃしますよ。人類初の“魂分離薬”の被験者なんですから…」
美月は苦笑しながらも、テーブルの上に置かれた琥珀色の液体の入った小瓶を見つめた。
ラベルにはこう書かれていた。
SOUL-FREE β-001
『魂を可視化・可触化する試薬。投与後、ゼリー状に分離される。』
博士は続けた。「この薬は魂と肉体の接合を一時的に解除する。つまり、君の“中身”が目の前に出てくることになる」
「…で、それを誰が観察するんでしたっけ?」
「私と、助手の北村君だ。安心しなさい。魂に対して、我々がどうこうできるわけではない」
美月は深呼吸し、小瓶のキャップを外す。そして、何の味も匂いも感じないその液体を一気に飲み干した。
数秒後──
「っ……!?」
身体に、電流のような痺れが走った。手足の感覚が遠のいていく。
呼吸が乱れ、喉が熱くなる。そして――。
「う…くっ、はぁっ……あ……!!」
美月の口から、ぷるん、と何かがこぼれ落ちた。
それは――淡く光る、ゼリー状の物体。
透明で、虹色にきらめくそれは、ふるふると揺れながら床に落ちず、空中に浮かび上がった。
「成功だ……!!」
権田博士の目が見開かれる。
そのゼリーの中には、確かに美月の“顔”のような形が、ぼんやりと浮かび上がっていた。
閉じられた瞼、やや困惑気味の表情、そして…目が、ゆっくりと開かれる。
ゼリーの中の“美月”が、博士を見て、何かを訴えるように口を動かした。
しかし声は出ない。ただその表情は、確かに“生きている”。
「魂だ……これが、魂……っ!」
美月の体は、今も目を開けたまま椅子に座っていた。呼吸はしているが、意識はない。まるで抜け殻。
魂と肉体――分離は成功したのだ。
「さて、美月君。君自身を、君に見せるとしよう」
博士はゼリーの魂を透明なシリンダーに収め、しっかりと固定する。
その“美月の魂”が、悲しげに震えながら博士を睨んでいるように見えた。
「戻すこともできる。だが…観察には時間が必要だ」
実験は、始まったばかりだった。
「……すまないね、美月君」
実験室に、静かに響く博士の声。
権田博士は、まだ意識のない美月の抜け殻を見下ろしていた。
椅子に腰かけたままの美月の肉体。まるで眠っているようだが、その瞳は虚空を見つめている。
先ほど吐き出された、美月の魂ゼリーは冷却シリンダーに保管されていた。
そして今、博士の手にはもう一つの瓶──改良型・魂分離薬 SOUL-FREE β-002が握られていた。
「この肉体が、あまりにも完璧すぎたんだよ……」
博士は一気に薬を飲み干した。
瞬間、身体が痙攣し、熱がこみあげる。
「ぐぅっ……は、はぁぁっ……!」
そして――
ずるっ…、ぬるん……っ
博士の口から、淡く光る青白いゼリーが這い出してきた。
それはねばついた粘液状の魂であり、博士の顔をそのまま写し取ったような、老いた“意識の塊”。
その魂ゼリーは、まるで意志を持つかのように空中に浮かび上がり、ぷるぷると震える。
やがて、それは美月の肉体の前まで、静かに移動した。
「ふふ……ようやく、私の番だ……」
ゼリーが美月の体の口元へと近づく。
次の瞬間――
ぬるっ、ぬめっ……!
魂ゼリーが、美月の口の中へと、逆流するように侵入していった。
舌の奥を這い、喉を通り、意識の座に到達する。
数秒の沈黙。
すると、美月の体がピクリと動いた。
まばたき。
深い呼吸。
ゆっくりと視線を動かす。
その目は、もう“綾瀬美月”のものではなかった。
若く、整った容姿。しなやかに動く手足。完璧な外見を持つ女子大生の肉体が、中身は権田博士そのものへと変わっていた。
「……こ、これが……ふふ、すばらしい……。若さ、柔らかさ、感覚……! まるで生まれ変わったようだ……!」
鏡を見つめ、博士は陶酔したように自らの顔に触れる。
美しい唇、張りのある肌、弾力ある胸元。
「完璧だ……完璧すぎる……これが、私の新しい人生だ……!」
博士は、もう二度と元の肉体には戻らないつもりだった。
シリンダーの中で揺れる本物の美月の魂が、何かを訴えるように震えていたが――
「大丈夫、安心しなさい。君は安全な場所で保管してあげるよ。永遠にな」
実験は終わった。
だが、博士の人生は今、始まったのだ。
かつて白衣と実験ノートにまみれていた老博士、権田重彦(ごんだしげひこ)。
その魂は、今や美貌の女子大生・綾瀬美月の肉体に宿っていた。
「うふふ……ふふふっ……!」
ショッピングモールの鏡の前で、彼女――いや、“彼”は陶酔した笑みを浮かべる。
ミニスカートにふわふわのブラウス。ピンクのリップに艶のあるウェーブヘア。
ヒールを履きこなすスラリとした脚線美に、通行人の男性たちが視線を奪われる。
「どう? みづき~、それめっちゃ似合ってる~!」
「てか、肌つやつやすぎじゃない? 化粧品なに使ってんの?」
取り囲むのは、美月の“元”の友人たち。
彼女たちは疑うこともなく、“美月”が相変わらず美人でノリが良いことを喜んでいた。
権田博士は、内心ほくそ笑む。
(この肉体には、知性も美も備わっている……学生らしく振る舞うだけで、みんなが笑いかけてくる……!)
ショッピング、カフェ、プリクラ。
女子大生たちと“キャピキャピ”とはしゃぎながら、博士は青春の感覚に浸っていた。
──スイーツ店のテーブルに並ぶ、映えるパフェとコーヒー。
「ほら、“萌えポーズ”しよ~♡」
「きゅんですっ♡」
友人にスマホを向けられ、ピースサインを作る。
博士は一瞬戸惑ったが、すぐに柔らかな笑顔を浮かべた。
「きゅん、です……♡」
(ばかばかしい……いや、いや? ふふふ、これも……悪くないな)
スマホの画面に映ったのは、可愛らしく笑う“美月”。
その瞳の奥に、かつての白髪の老博士の面影は微塵もない。
その日の帰り道、博士は一人で鏡の前に立ち、こう呟いた。
「人は、歳を取るから老いるんじゃない……
望まなくなったとき、老いるのだ。」
鏡の中の美月が、唇を艶かしくなぞり、にやりと笑った。
「だったら私は、これからが青春だよ」
ファッションと遊びで若さを堪能した“美月”――その中身、権田博士は、数日ぶりに大学の地下研究室に戻ってきていた。
「遊びも研究も、若さがあってこそ意味がある。」
そうつぶやきながら、彼女は白衣を身にまとう。
肉体が変わっても、研究者としての誇りは消えていない。
机の上には、新開発の脳波記憶アクセス装置が鎮座していた。
「いよいよだ……この美月の肉体に残された、**記憶の残渣(ざんさ)**を読み解く時が来た」
魂を抜かれた今も、脳細胞の奥底には本人の“感じていたこと”、“考えていたこと”がわずかに残っている。
それを抽出し、再生するという――極めて危険な実験。
彼女は、美月の肉体のこめかみにセンサーを貼り、ゆっくりとスイッチを入れた。
装置が唸りを上げ、視界が眩しくなる。
そして、博士の脳内に“美月の記憶映像”が流れ込んできた――。
大学の講義室。
美月は女子学生たちと談笑している。
「権田先生ってさ、昔はすごかったとか言われてるけど、今はもう老害だよね~」
「マジでそれw プレゼンの時、説明長すぎて寝た~」
美月が笑う。
「私、いつかあの研究室から抜け出してやるって決めてるの。あの人、私の美貌に嫉妬してるだけ。
若い女の可能性を、あの枯れた頭じゃ理解できないのよ」
博士の中で、何かが崩れ落ちた。
目を見開き、装置を外す。
呼吸が荒くなる。手が震えていた。
「嫉妬……? 老害……? この私を、そんなふうに見ていたのか……?」
静かに、しかし確実に怒りの炎が広がっていく。
美月の体を通して感じる鼓動が、怒りと悔しさを倍加させていた。
「この肉体は、私のものだ……だが、その中に宿っていたお前の本心……その侮辱、絶対に許さない……!」
博士は手元の端末を操作し、“保管されていた美月の魂ゼリー”の冷凍シリンダーにアクセスする。
「お前に見せてやる。本当の恐怖と支配を。
自分の体が、どれだけ私に従順になったのかをな……!」
冷たい笑みを浮かべ、彼女は白衣の袖をまくる。
次なる研究テーマは――
**「肉体を通して、魂に罰を与える方法」**だった。
研究室の地下冷却室。
銀色のシリンダーの中で、淡く輝くゼリーが静かに脈動していた。
それが、綾瀬美月の魂。
その魂が発する光は、先ほどの実験以降、わずかに揺れていた。
怒りか、不安か、それとも――恐れか。
その前に立つのは、美月の肉体を持つ博士。
彼女の瞳は冷たく、口元には不敵な笑みが浮かんでいた。
「バカにしてくれたな、美月。老害だの、嫉妬だの。
だが今はどうだ? お前の完璧な体は、私のもの。
なら、お前には――私の“残骸”をくれてやろう」
博士は手元の端末を操作し、隣に設置されたもう一つのシリンダーを開く。
そこには、博士の老いた肉体が保管されていた。
皺の刻まれた皮膚、背の丸まった身体、色あせた髪。
今やただの抜け殻――誰も望まない、役目を終えた器。
「さあ、“お帰りなさい”。だが、居場所は変わったよ。」
博士は、美月の魂ゼリーをシリンダーから慎重に取り出し、装置の注入ポートに接続した。
ボタンを押すと、ゼリーは管を伝って、博士の肉体の口へと流れ込んでいく。
「ぬる……ぬめ……っ、くぅぅ……!」
管の中を這い進む美月の魂は、まるで抵抗するかのように、ゆっくりと進んでいた。
だが、逆らう術はない。
機械は淡々と作動し、やがて――
美月の魂は、博士の老いた体の中へと完全に注入された。
数分後。
ベッドの上で、その体が震え始めた。
まばたき。呼吸。微かな呻き。
やがて、老いた瞳が開かれた。
「……っ!? な、なにこれ……えっ、手が……手がシワシワ……!?」
聞き慣れた高い声ではない。
掠れ、深く、重たい男の声。
それが、美月の声帯でなく、博士の古びた声帯から漏れ出たのだ。
「うそ……いやっ、こんなの、私じゃない……! 戻して……やめてぇ……!」
鏡を見せられた彼女は、自分がかつて見下していた“権田博士”そのものになっていることに気づく。
その様子を、若く美しい自分の元の肉体――つまり博士が乗っ取った美月の体が、笑いながら見下ろす。
「どうだ? “私”になった気分は。
老いて、重く、誰にも相手にされない肉体。
魂だけでは、美貌も若さも手に入らないと理解したか?」
美月は、膝を抱えながら震えた。
もう“可愛い女子大生”でも“憧れの美月”でもない。
彼女は今、その価値を奪った相手の“抜け殻”に閉じ込められたのだった。
――重い身体、鈍い関節。
綾瀬美月の魂が閉じ込められたのは、元・権田博士の肉体だった。
鏡の前には、しわだらけの顔。
かつて自分があざけった老人の姿。
(戻らなきゃ……このまま終わるなんて、絶対に嫌)
美月は、かつて自分のものだった体――今や博士が乗っ取っている姿を思い浮かべるたびに、怒りと屈辱で胸が詰まった。
「でも、なぜ……あの人は私をそこまで憎んだの? ただの小言だけだったのに……」
その疑問を解き明かすため、美月は老いた手で、博士の研究ログにアクセスする。
そして、脳内深層記憶を可視化する実験装置、**「Mnemosyne Extractor(ネモシネ・エクストラクター)」**を起動した。
これは、“本人すら意識していなかった記憶の奥底”を再生する装置。
本来は倫理的に使用禁止に近いが、美月はもうそんなことを気にする余裕などなかった。
記憶投影、開始。
そこに映し出されたのは、かつての研究室の映像。
若い美月がレポートを手渡し、権田博士――つまり、今の自分の肉体が、それを受け取る場面だった。
「ありがとうございますっ、先生。今日の講義もすっごく勉強になりました!」
「……あ、ああ。うむ。……気をつけて帰りたまえ」
表面上はいつも通りの会話――
だが映像はそのまま権田の内心を再現し始めた。
(また来てくれた……今日も笑顔がまぶしい……)
(あの子の目が、声が、私のような老いぼれを見てくれるだけで……)
(いけない、これはただの指導者としての情……いや、違う。……これは――)
(私は、あの子に……恋をしている)
美月は、呼吸を止めた。
椅子に縛られたままのような感覚。
目の前に広がるのは、かつて自分が浴びていた“視線の正体”。
さらに記憶は続いた。
夜の研究室。誰もいない空間で、権田博士が一人、机に伏せながらつぶやく。
「美月くん……君は、私の光だった……」
「もう一度、君の瞳でこの世界を見られたら、どれほど幸せだろうか……」
「……だったら、どうして……!」
美月は震える手で装置を止めた。
「どうして、“私”の体を奪ったのよ……! 恋をしてたなら、どうしてそんなこと……!!」
けれど答えは、すでに美月の胸の中にあった。
(――だから、奪ったんだ)
博士は、美月を手に入れることはできなかった。
愛していたのに、若さも、立場も、何もかもが届かなかった。
だから、せめて――その“器”だけでも手に入れようとしたのだ。
それは恋ではなく、欲望と絶望が混ざり合った支配。
「愛していた? 冗談じゃない……
そんなの、ただの独りよがりの狂気じゃない……!」
美月の心は、怒りと、そして言いようのない恐怖に満ちていった。
彼女は誓う――
(取り戻す……この体も、人生も、全部。絶対に……!)
白衣を脱ぎ捨て、軽やかなワンピースに身を包んだ“美月”。
だがその中身は、かつての老博士――権田重彦である。
鏡の前で口角を上げる。
「綾瀬美月……君の体は、思っていた以上に“魅惑的”だな」
髪をかき上げ、紅をひく。
仕草一つで男たちが振り向くこの体に、博士はすっかり順応していた。
そんな“美月”が向かうのは、研究室のベッドに座る男――博士の体を持つ、美月の魂。
しわだらけの手、力の抜けた腰、乾いた声。
だが、その瞳にはまだ美しき“自分”を取り戻そうとする執念が宿っていた。
「調子はどう? 私の…いや、“お前の”体は」
博士の笑みが含みを帯びる。
「ふふ……今日は、ちょっとだけ“遊び”に付き合ってくれないかしら」
美月の肉体がゆっくりと近づく。
胸元が開いた服、香水の甘い香り、柔らかな太もも、艶やかな唇。
博士の体に入れられた美月(魂)は、目を背ける。
「やめて……気持ち悪い……近づかないで……!」
だが、博士の肉体は反応してしまっていた。
血流が変わる。
呼吸が荒くなる。
かつて“愛した対象”だった肉体を前に、意志とは裏腹に反応してしまう。
「うそ……この体……勝手に……!」
「気づいてる? 君の体は、君よりも私を覚えてるのよ」
博士は、美月の肉体で笑いながら、かつての自分の肩に手を置いた。
「私の吐息、私の瞳、私の肌に――お前はずっと、触れられてきたんだよ」
もはや抗えなかった。
美月の魂が宿った老いた体は、震えながらも“美月”にすがりつく。
その姿を見て、博士は心の中で嗤う。
(ほら……結局は肉体の檻に勝てない。
愛した対象にひざまずき、哀れなほどに欲してしまう。
お前は私の中身を軽蔑していたはずなのに、
今は“私の外見”に、屈している)
博士はそっと囁いた。
「おかえり、わたし。あなたは、ずっと私のものだったのよ」
大学構内にて――
「……本当に申し訳ありません。被害者の方の心のケアを最優先に対応いたします」
学部長の厳しい表情とともに、会議室の扉が閉じられた。
その後ろで震える手を握りしめていたのは、“綾瀬美月”――
だがその中身は、かつての権田博士だった。
「怖かったんです……急に背後から触られて……『私のものだ』なんて……あの人、完全に狂ってる……!」
涙を浮かべながら、そう証言する“美月”の演技は完璧だった。
そう、セクハラをしたとされる加害者は――
今や博士の魂を閉じ込められている、老いた博士の肉体に入った**“もう一人の美月”**。
もちろん、真実は逆だった。
美月の魂は、博士の肉体に入れられ、強制的にその人生を押しつけられた被害者。
だが証拠は一切ない。
魂の入れ替わりなど、誰も信じてはくれなかった。
「接近禁止命令? そ、そんな……! 私は……私は美月なんです! あの子が嘘を……!」
「もうやめなさい」
事務員に腕を掴まれ、連れ出されるその姿は、まるで罪人だった。
後日、大学のカフェテラスにて。
美しいワンピース姿の“綾瀬美月”は、笑顔でスマホを覗いていた。
SNSには、ファッション誌の取材風景、自撮り、ランチ会――
“理想の女子大生”としての人生を、博士は完全に手に入れていた。
「もう“あの人”が私に近づいてくることはない。
過去も、研究も、罪も……すべて“彼”に押しつけたから。」
美月の魂が、かつての肉体の中で孤独に暮らしているなど、誰も知る由もない。
彼女は言った。
「私の名は、綾瀬美月。
未来は、私のものよ」
その笑顔は美しく、そして誰よりも冷たかった。
「美月~! 今度みんなで沖縄行くんだけど、空いてる?」
メッセージアプリの通知に、博士の心が一瞬ざわめいた。
友人たちからの誘い。行き先は沖縄のビーチ。
「(ビーチ……水着……身体を見せる場所……)」
“美月”である今の博士は、鏡に映る完璧なボディラインにいつも陶酔していた。
だが、それと同時に、一つだけ気がかりな点があった。
――胸が、少し控えめなのだ。
「……多少ボリュームがあった方が、男受けも、女子の中でも映える……」
そう呟くと、博士は手元の通販アプリを開き、シリコン製の極厚パッドを注文した。
沖縄、白浜のビーチ。
青い空、透き通る海、若者たちの笑い声。
“美月”は、白のフリル付きビキニに身を包み、友人たちと並んでいた。
「美月~! なんか今日スタイル良すぎじゃない? なにそのバスト、ヤバッ!」
「えっ、ほんと? そうかな~?(※多少の加工はしてある)」
笑いながらピースを決める博士。
だが内心はヒヤヒヤだった。
水に入ったら、バレるかもしれない――。
「泳がないの?」「うん、ちょっと日焼けが心配で……♡」
会話を巧みにかわしながら、博士は“見られるだけ”を楽しんだ。
男たちの視線、女友達の羨望、それらすべてが甘美だった。
(ああ……これが、“美月”として生きるということか……!)
だが、波打ち際で戯れる仲間たちを見つめるうちに、
胸元の不自然なふくらみが少しズレてきていることに気づく。
「……まずい」
すぐにパーカーを羽織り、笑顔で言った。
「ねえ、そろそろカフェ行かない? わたし、スイーツのほうが好き~♡」
誰も博士の秘密には気づかなかった。
少なくともその日は――。
「…うわ~、やっぱり美月ちゃんって可愛いけど、ちょっと胸だけ控えめだよねぇ」
沖縄のビーチで撮った集合写真を見て、友人のさやかが何気なく言った一言。
周囲は「やめなよ~」と笑って流したが、その言葉は、美月の体に入った博士の心に深く突き刺さっていた。
(そうだ……この体に唯一足りないのは、バストの存在感。
美月の魅力を“完璧”にするには、あとほんの少し、ボリュームが必要なんだ)
博士は、すぐに研究に着手した。
テーマは――「局所脂肪移動薬:Adipo-Swap」。
数日後、研究室に呼び出されたさやかが言った。
「えっ、これ飲むとどうなるの? 美月ちゃんの新作ダイエットサプリ?」
「ううん。交換型よ。あなたの“余ってるところ”と、私の“足りないところ”、ちょっとだけ分け合いましょって感じ?」
さやかは笑った。「えー、別にいーよ? たしかに私、でかすぎて困ってるくらいだし」
乾杯のように薬瓶を交わし、二人は同時に服用した。
効果は数分で現れた。
さやかが「ん……? なんか、軽くなってない?」と胸を触るころには、
“美月”は、自分のビキニが張り詰める感覚に目を見開いていた。
「うそ……これ、私の体……なのに……重さが……ある……!」
鏡の前に立つと、そこにはバランスの取れた、豊かな曲線美を備えた“美月”がいた。
ウエストの細さに対して、絶妙なバストの存在感――理想が、今ここにある。
さやかは笑った。「マジで? あたしちょっとスッキリしてラッキーかも♪」
博士は笑顔で返したが、内心ではこう呟いていた。
(これで完成だ。完璧な美月が、ついにここに生まれた――)
沖縄の青い海、白い砂浜、抜けるような空――
美月(中身は博士)は、そのビーチの中心にいた。
白のビキニに身を包み、胸元は以前よりも豊かに、自然な丸みと張りを見せていた。
太陽の光が肌を照らすたび、目を惹く存在感が強調される。
「美月ちゃん、写真撮ってあげる~!」
「え、めっちゃ映えてる! SNSに載せたいくらい♡」
「てか、スタイルやばすぎじゃない?」
まわりには、男も女も自然と集まってくる。
「綾瀬さん、どこから来たの?」「東京の大学生? 連絡先、交換しよっか?」
笑顔で応じる“美月”の中身――博士は、満ち足りていた。
(この反応……やはり“形”が全てを支配する……)
一方、さやかはというと――
「あれ? なんか、さやかちゃん印象変わった?」「前もっと……いや、なんでもない」
「……なんでもないって、なに」
さやかの胸元は以前よりもすっきりしていた。
「バランスいいって感じだね~」と女友達はフォローしてくれるが、明らかに視線の集まり方が違う。
さらに、かつて“巨乳キャラ”として男子からチヤホヤされていた彼女に対し、今は“目立たない子”の扱い。
「…ねぇ、美月。ちょっと話せる?」
夕暮れの砂浜で、さやかが目を伏せて切り出した。
「……やっぱり、戻してほしい」
博士は小さく笑う。「どうして? あんなに“スッキリしてて楽”って言ってたのに」
「……あれは冗談。やっぱり、胸があるって大事だった。あたしの“らしさ”だったんだよ……」
博士は一瞬だけ目を閉じて、答えた。
「じゃあ、“戻す”かどうか、少し考えさせてもらえる?」
さやかが顔を上げると、そこにはニッコリと微笑む美月の姿――
だがその笑顔の奥には、明確な優越感と支配の気配が滲んでいた。
博士は知っていた。
脂肪の量は、単なる体の一部ではない。
それは人間関係、他者からの視線、自分という存在の重みを左右する“武器”なのだ。
「返すかどうかは、わたし次第よ。さやかちゃん」
そう呟きながら、博士は再びビーチの中央へと歩き出した。
砂浜に残されたのは、さやかのかすかな悔しさと、小さな足跡だけだった――。
胸の脂肪量を手に入れて以来、完璧なボディラインを得た“綾瀬美月”――その中身、博士は満ち足りていた。
しかし、日常のふとした瞬間、ある違和感が彼女を苛立たせ始める。
──視線が、わずかに“下から見上げる”角度にある。
同じくモデル体型のさやかと並んだ写真では、やはり微妙な身長差がある。
数センチの差だった。だがそれが、美の完成度において致命的な“ズレ”だと博士は感じていた。
(スタイルとは、相対的な支配でもある。私は、上から見下ろされてはならない)
そうして、博士は新たな薬の研究に着手した。
名を――「GROW-TRANSFER β-01」。
対象者の“骨格成長データ”と“ホルモン値”を一時的に同調させ、身長を強制的に移す薬だった。
ある日、さやかが研究室を訪れる。
「なにこれ? また新しいやつ? 美月ってほんと美容オタクだよね~」
「ちょっとした実験なの。一緒に飲んでみない?」
「ふふ、また“分けっこ”するの? まぁ、いいけど~♪」
さやかが軽く引き受けると、博士は心の中でほくそ笑んだ。
(今度は“上から”君を見る番だよ、さやか)
効果は即効だった。
数時間後、博士の脚は微かに伸び、骨盤位置が上がり、ヒールも履いていないのに“目線が高くなっている”と明確に感じた。
鏡の中の“美月”は、スラッと背筋を伸ばし、全身のシルエットが縦に引き締まって見える。
その横で、さやかが呟いた。
「……え、ちょっと待って。私……なんか縮んでない? てか、え? 美月の方が、背高くない?」
博士はあくまで自然に笑った。
「たぶん気のせいよ? 私、今日スニーカーだけどな~♡」
さやかは鏡を見て、動揺を隠せなかった。
「なんで……?」
だが、薬の効果は徐々に固定化されていく。
後日。
大学の廊下で、二人が並ぶ姿を見た男子学生たちの声が漏れる。
「え、美月ってあんなにスタイル良かったっけ?」
「身長も高く見えるし、脚めっちゃ長くない?」
「隣のさやか、前の方が目立ってたよな…?」
“美月”は微笑んだまま、わざとヒールの音を響かせて歩いた。
すれ違うさやかの頭を、軽く見下ろす高さから。
(やっと、私は完全になった)
沖縄の白い砂浜を歩く、美月とさやか。
照りつける太陽の下、ふたりの姿は一見、仲のいい女子大生同士に見えた。
──しかし、その“立ち位置”は明確に変わっていた。
「うわ……美月ちゃん、脚長っ!」
「え、さやかってこんなに小さかったっけ?」
周囲から聞こえる、心ない感想。
その言葉に、さやかは何も言い返せなかった。
たしかに、美月の身長は以前より明らかに高くなっていた。
脚の付け根の位置が違う。目線が違う。
水着姿になれば、シルエットの差はさらに顕著だった。
ビキニから覗く背筋のライン、ヒップから太ももにかけての伸びやかさ――
視線を奪っていたのは、明らかに“美月”の方だった。
「さやかちゃ~ん、こっちで写真撮ろうよ~」
「え、美月さんも一緒に! はいチーズ!」
スマホに収められた写真を、さやかはそっと確認する。
画面の中の自分は、美月の肩あたりまでしか背がなく、まるで“付き添いの子”のようだった。
「……ねぇ、美月」
帰り道、さやかが沈んだ声で切り出す。
「……身長、返してくれない?」
美月は振り返り、笑顔で首をかしげる。
「え? なんのこと?」
「わかってるでしょ……あの薬。あんたが、私から奪ったんでしょ……」
しばしの沈黙。
美月はゆっくりと背筋を伸ばし、見下ろすようにさやかに向き合った。
「……そうね。確かに、私は“君の高さ”をもらったわ」
さやかの手が震える。悔しさ、屈辱――そして認めたくない敗北感。
「でもね、さやかちゃん。私ね、もうこの高さじゃないと生きていけないの」
その言葉に、さやかは絶句した。
白い光が眩しい無菌室で、一人の女子大生が椅子に座らされていた。彼女の名は綾瀬 美月(あやせ みづき)、医学部四年。スラリとした肢体、知的で涼やかな目元、まさに「才色兼備」を絵に描いたような女性だった。
「…緊張してる?」
目の前の中年の研究者、権田博士がにやりと笑う。
「そりゃしますよ。人類初の“魂分離薬”の被験者なんですから…」
美月は苦笑しながらも、テーブルの上に置かれた琥珀色の液体の入った小瓶を見つめた。
ラベルにはこう書かれていた。
SOUL-FREE β-001
『魂を可視化・可触化する試薬。投与後、ゼリー状に分離される。』
博士は続けた。「この薬は魂と肉体の接合を一時的に解除する。つまり、君の“中身”が目の前に出てくることになる」
「…で、それを誰が観察するんでしたっけ?」
「私と、助手の北村君だ。安心しなさい。魂に対して、我々がどうこうできるわけではない」
美月は深呼吸し、小瓶のキャップを外す。そして、何の味も匂いも感じないその液体を一気に飲み干した。
数秒後──
「っ……!?」
身体に、電流のような痺れが走った。手足の感覚が遠のいていく。
呼吸が乱れ、喉が熱くなる。そして――。
「う…くっ、はぁっ……あ……!!」
美月の口から、ぷるん、と何かがこぼれ落ちた。
それは――淡く光る、ゼリー状の物体。
透明で、虹色にきらめくそれは、ふるふると揺れながら床に落ちず、空中に浮かび上がった。
「成功だ……!!」
権田博士の目が見開かれる。
そのゼリーの中には、確かに美月の“顔”のような形が、ぼんやりと浮かび上がっていた。
閉じられた瞼、やや困惑気味の表情、そして…目が、ゆっくりと開かれる。
ゼリーの中の“美月”が、博士を見て、何かを訴えるように口を動かした。
しかし声は出ない。ただその表情は、確かに“生きている”。
「魂だ……これが、魂……っ!」
美月の体は、今も目を開けたまま椅子に座っていた。呼吸はしているが、意識はない。まるで抜け殻。
魂と肉体――分離は成功したのだ。
「さて、美月君。君自身を、君に見せるとしよう」
博士はゼリーの魂を透明なシリンダーに収め、しっかりと固定する。
その“美月の魂”が、悲しげに震えながら博士を睨んでいるように見えた。
「戻すこともできる。だが…観察には時間が必要だ」
実験は、始まったばかりだった。
「……すまないね、美月君」
実験室に、静かに響く博士の声。
権田博士は、まだ意識のない美月の抜け殻を見下ろしていた。
椅子に腰かけたままの美月の肉体。まるで眠っているようだが、その瞳は虚空を見つめている。
先ほど吐き出された、美月の魂ゼリーは冷却シリンダーに保管されていた。
そして今、博士の手にはもう一つの瓶──改良型・魂分離薬 SOUL-FREE β-002が握られていた。
「この肉体が、あまりにも完璧すぎたんだよ……」
博士は一気に薬を飲み干した。
瞬間、身体が痙攣し、熱がこみあげる。
「ぐぅっ……は、はぁぁっ……!」
そして――
ずるっ…、ぬるん……っ
博士の口から、淡く光る青白いゼリーが這い出してきた。
それはねばついた粘液状の魂であり、博士の顔をそのまま写し取ったような、老いた“意識の塊”。
その魂ゼリーは、まるで意志を持つかのように空中に浮かび上がり、ぷるぷると震える。
やがて、それは美月の肉体の前まで、静かに移動した。
「ふふ……ようやく、私の番だ……」
ゼリーが美月の体の口元へと近づく。
次の瞬間――
ぬるっ、ぬめっ……!
魂ゼリーが、美月の口の中へと、逆流するように侵入していった。
舌の奥を這い、喉を通り、意識の座に到達する。
数秒の沈黙。
すると、美月の体がピクリと動いた。
まばたき。
深い呼吸。
ゆっくりと視線を動かす。
その目は、もう“綾瀬美月”のものではなかった。
若く、整った容姿。しなやかに動く手足。完璧な外見を持つ女子大生の肉体が、中身は権田博士そのものへと変わっていた。
「……こ、これが……ふふ、すばらしい……。若さ、柔らかさ、感覚……! まるで生まれ変わったようだ……!」
鏡を見つめ、博士は陶酔したように自らの顔に触れる。
美しい唇、張りのある肌、弾力ある胸元。
「完璧だ……完璧すぎる……これが、私の新しい人生だ……!」
博士は、もう二度と元の肉体には戻らないつもりだった。
シリンダーの中で揺れる本物の美月の魂が、何かを訴えるように震えていたが――
「大丈夫、安心しなさい。君は安全な場所で保管してあげるよ。永遠にな」
実験は終わった。
だが、博士の人生は今、始まったのだ。
かつて白衣と実験ノートにまみれていた老博士、権田重彦(ごんだしげひこ)。
その魂は、今や美貌の女子大生・綾瀬美月の肉体に宿っていた。
「うふふ……ふふふっ……!」
ショッピングモールの鏡の前で、彼女――いや、“彼”は陶酔した笑みを浮かべる。
ミニスカートにふわふわのブラウス。ピンクのリップに艶のあるウェーブヘア。
ヒールを履きこなすスラリとした脚線美に、通行人の男性たちが視線を奪われる。
「どう? みづき~、それめっちゃ似合ってる~!」
「てか、肌つやつやすぎじゃない? 化粧品なに使ってんの?」
取り囲むのは、美月の“元”の友人たち。
彼女たちは疑うこともなく、“美月”が相変わらず美人でノリが良いことを喜んでいた。
権田博士は、内心ほくそ笑む。
(この肉体には、知性も美も備わっている……学生らしく振る舞うだけで、みんなが笑いかけてくる……!)
ショッピング、カフェ、プリクラ。
女子大生たちと“キャピキャピ”とはしゃぎながら、博士は青春の感覚に浸っていた。
──スイーツ店のテーブルに並ぶ、映えるパフェとコーヒー。
「ほら、“萌えポーズ”しよ~♡」
「きゅんですっ♡」
友人にスマホを向けられ、ピースサインを作る。
博士は一瞬戸惑ったが、すぐに柔らかな笑顔を浮かべた。
「きゅん、です……♡」
(ばかばかしい……いや、いや? ふふふ、これも……悪くないな)
スマホの画面に映ったのは、可愛らしく笑う“美月”。
その瞳の奥に、かつての白髪の老博士の面影は微塵もない。
その日の帰り道、博士は一人で鏡の前に立ち、こう呟いた。
「人は、歳を取るから老いるんじゃない……
望まなくなったとき、老いるのだ。」
鏡の中の美月が、唇を艶かしくなぞり、にやりと笑った。
「だったら私は、これからが青春だよ」
ファッションと遊びで若さを堪能した“美月”――その中身、権田博士は、数日ぶりに大学の地下研究室に戻ってきていた。
「遊びも研究も、若さがあってこそ意味がある。」
そうつぶやきながら、彼女は白衣を身にまとう。
肉体が変わっても、研究者としての誇りは消えていない。
机の上には、新開発の脳波記憶アクセス装置が鎮座していた。
「いよいよだ……この美月の肉体に残された、**記憶の残渣(ざんさ)**を読み解く時が来た」
魂を抜かれた今も、脳細胞の奥底には本人の“感じていたこと”、“考えていたこと”がわずかに残っている。
それを抽出し、再生するという――極めて危険な実験。
彼女は、美月の肉体のこめかみにセンサーを貼り、ゆっくりとスイッチを入れた。
装置が唸りを上げ、視界が眩しくなる。
そして、博士の脳内に“美月の記憶映像”が流れ込んできた――。
大学の講義室。
美月は女子学生たちと談笑している。
「権田先生ってさ、昔はすごかったとか言われてるけど、今はもう老害だよね~」
「マジでそれw プレゼンの時、説明長すぎて寝た~」
美月が笑う。
「私、いつかあの研究室から抜け出してやるって決めてるの。あの人、私の美貌に嫉妬してるだけ。
若い女の可能性を、あの枯れた頭じゃ理解できないのよ」
博士の中で、何かが崩れ落ちた。
目を見開き、装置を外す。
呼吸が荒くなる。手が震えていた。
「嫉妬……? 老害……? この私を、そんなふうに見ていたのか……?」
静かに、しかし確実に怒りの炎が広がっていく。
美月の体を通して感じる鼓動が、怒りと悔しさを倍加させていた。
「この肉体は、私のものだ……だが、その中に宿っていたお前の本心……その侮辱、絶対に許さない……!」
博士は手元の端末を操作し、“保管されていた美月の魂ゼリー”の冷凍シリンダーにアクセスする。
「お前に見せてやる。本当の恐怖と支配を。
自分の体が、どれだけ私に従順になったのかをな……!」
冷たい笑みを浮かべ、彼女は白衣の袖をまくる。
次なる研究テーマは――
**「肉体を通して、魂に罰を与える方法」**だった。
研究室の地下冷却室。
銀色のシリンダーの中で、淡く輝くゼリーが静かに脈動していた。
それが、綾瀬美月の魂。
その魂が発する光は、先ほどの実験以降、わずかに揺れていた。
怒りか、不安か、それとも――恐れか。
その前に立つのは、美月の肉体を持つ博士。
彼女の瞳は冷たく、口元には不敵な笑みが浮かんでいた。
「バカにしてくれたな、美月。老害だの、嫉妬だの。
だが今はどうだ? お前の完璧な体は、私のもの。
なら、お前には――私の“残骸”をくれてやろう」
博士は手元の端末を操作し、隣に設置されたもう一つのシリンダーを開く。
そこには、博士の老いた肉体が保管されていた。
皺の刻まれた皮膚、背の丸まった身体、色あせた髪。
今やただの抜け殻――誰も望まない、役目を終えた器。
「さあ、“お帰りなさい”。だが、居場所は変わったよ。」
博士は、美月の魂ゼリーをシリンダーから慎重に取り出し、装置の注入ポートに接続した。
ボタンを押すと、ゼリーは管を伝って、博士の肉体の口へと流れ込んでいく。
「ぬる……ぬめ……っ、くぅぅ……!」
管の中を這い進む美月の魂は、まるで抵抗するかのように、ゆっくりと進んでいた。
だが、逆らう術はない。
機械は淡々と作動し、やがて――
美月の魂は、博士の老いた体の中へと完全に注入された。
数分後。
ベッドの上で、その体が震え始めた。
まばたき。呼吸。微かな呻き。
やがて、老いた瞳が開かれた。
「……っ!? な、なにこれ……えっ、手が……手がシワシワ……!?」
聞き慣れた高い声ではない。
掠れ、深く、重たい男の声。
それが、美月の声帯でなく、博士の古びた声帯から漏れ出たのだ。
「うそ……いやっ、こんなの、私じゃない……! 戻して……やめてぇ……!」
鏡を見せられた彼女は、自分がかつて見下していた“権田博士”そのものになっていることに気づく。
その様子を、若く美しい自分の元の肉体――つまり博士が乗っ取った美月の体が、笑いながら見下ろす。
「どうだ? “私”になった気分は。
老いて、重く、誰にも相手にされない肉体。
魂だけでは、美貌も若さも手に入らないと理解したか?」
美月は、膝を抱えながら震えた。
もう“可愛い女子大生”でも“憧れの美月”でもない。
彼女は今、その価値を奪った相手の“抜け殻”に閉じ込められたのだった。
――重い身体、鈍い関節。
綾瀬美月の魂が閉じ込められたのは、元・権田博士の肉体だった。
鏡の前には、しわだらけの顔。
かつて自分があざけった老人の姿。
(戻らなきゃ……このまま終わるなんて、絶対に嫌)
美月は、かつて自分のものだった体――今や博士が乗っ取っている姿を思い浮かべるたびに、怒りと屈辱で胸が詰まった。
「でも、なぜ……あの人は私をそこまで憎んだの? ただの小言だけだったのに……」
その疑問を解き明かすため、美月は老いた手で、博士の研究ログにアクセスする。
そして、脳内深層記憶を可視化する実験装置、**「Mnemosyne Extractor(ネモシネ・エクストラクター)」**を起動した。
これは、“本人すら意識していなかった記憶の奥底”を再生する装置。
本来は倫理的に使用禁止に近いが、美月はもうそんなことを気にする余裕などなかった。
記憶投影、開始。
そこに映し出されたのは、かつての研究室の映像。
若い美月がレポートを手渡し、権田博士――つまり、今の自分の肉体が、それを受け取る場面だった。
「ありがとうございますっ、先生。今日の講義もすっごく勉強になりました!」
「……あ、ああ。うむ。……気をつけて帰りたまえ」
表面上はいつも通りの会話――
だが映像はそのまま権田の内心を再現し始めた。
(また来てくれた……今日も笑顔がまぶしい……)
(あの子の目が、声が、私のような老いぼれを見てくれるだけで……)
(いけない、これはただの指導者としての情……いや、違う。……これは――)
(私は、あの子に……恋をしている)
美月は、呼吸を止めた。
椅子に縛られたままのような感覚。
目の前に広がるのは、かつて自分が浴びていた“視線の正体”。
さらに記憶は続いた。
夜の研究室。誰もいない空間で、権田博士が一人、机に伏せながらつぶやく。
「美月くん……君は、私の光だった……」
「もう一度、君の瞳でこの世界を見られたら、どれほど幸せだろうか……」
「……だったら、どうして……!」
美月は震える手で装置を止めた。
「どうして、“私”の体を奪ったのよ……! 恋をしてたなら、どうしてそんなこと……!!」
けれど答えは、すでに美月の胸の中にあった。
(――だから、奪ったんだ)
博士は、美月を手に入れることはできなかった。
愛していたのに、若さも、立場も、何もかもが届かなかった。
だから、せめて――その“器”だけでも手に入れようとしたのだ。
それは恋ではなく、欲望と絶望が混ざり合った支配。
「愛していた? 冗談じゃない……
そんなの、ただの独りよがりの狂気じゃない……!」
美月の心は、怒りと、そして言いようのない恐怖に満ちていった。
彼女は誓う――
(取り戻す……この体も、人生も、全部。絶対に……!)
白衣を脱ぎ捨て、軽やかなワンピースに身を包んだ“美月”。
だがその中身は、かつての老博士――権田重彦である。
鏡の前で口角を上げる。
「綾瀬美月……君の体は、思っていた以上に“魅惑的”だな」
髪をかき上げ、紅をひく。
仕草一つで男たちが振り向くこの体に、博士はすっかり順応していた。
そんな“美月”が向かうのは、研究室のベッドに座る男――博士の体を持つ、美月の魂。
しわだらけの手、力の抜けた腰、乾いた声。
だが、その瞳にはまだ美しき“自分”を取り戻そうとする執念が宿っていた。
「調子はどう? 私の…いや、“お前の”体は」
博士の笑みが含みを帯びる。
「ふふ……今日は、ちょっとだけ“遊び”に付き合ってくれないかしら」
美月の肉体がゆっくりと近づく。
胸元が開いた服、香水の甘い香り、柔らかな太もも、艶やかな唇。
博士の体に入れられた美月(魂)は、目を背ける。
「やめて……気持ち悪い……近づかないで……!」
だが、博士の肉体は反応してしまっていた。
血流が変わる。
呼吸が荒くなる。
かつて“愛した対象”だった肉体を前に、意志とは裏腹に反応してしまう。
「うそ……この体……勝手に……!」
「気づいてる? 君の体は、君よりも私を覚えてるのよ」
博士は、美月の肉体で笑いながら、かつての自分の肩に手を置いた。
「私の吐息、私の瞳、私の肌に――お前はずっと、触れられてきたんだよ」
もはや抗えなかった。
美月の魂が宿った老いた体は、震えながらも“美月”にすがりつく。
その姿を見て、博士は心の中で嗤う。
(ほら……結局は肉体の檻に勝てない。
愛した対象にひざまずき、哀れなほどに欲してしまう。
お前は私の中身を軽蔑していたはずなのに、
今は“私の外見”に、屈している)
博士はそっと囁いた。
「おかえり、わたし。あなたは、ずっと私のものだったのよ」
大学構内にて――
「……本当に申し訳ありません。被害者の方の心のケアを最優先に対応いたします」
学部長の厳しい表情とともに、会議室の扉が閉じられた。
その後ろで震える手を握りしめていたのは、“綾瀬美月”――
だがその中身は、かつての権田博士だった。
「怖かったんです……急に背後から触られて……『私のものだ』なんて……あの人、完全に狂ってる……!」
涙を浮かべながら、そう証言する“美月”の演技は完璧だった。
そう、セクハラをしたとされる加害者は――
今や博士の魂を閉じ込められている、老いた博士の肉体に入った**“もう一人の美月”**。
もちろん、真実は逆だった。
美月の魂は、博士の肉体に入れられ、強制的にその人生を押しつけられた被害者。
だが証拠は一切ない。
魂の入れ替わりなど、誰も信じてはくれなかった。
「接近禁止命令? そ、そんな……! 私は……私は美月なんです! あの子が嘘を……!」
「もうやめなさい」
事務員に腕を掴まれ、連れ出されるその姿は、まるで罪人だった。
後日、大学のカフェテラスにて。
美しいワンピース姿の“綾瀬美月”は、笑顔でスマホを覗いていた。
SNSには、ファッション誌の取材風景、自撮り、ランチ会――
“理想の女子大生”としての人生を、博士は完全に手に入れていた。
「もう“あの人”が私に近づいてくることはない。
過去も、研究も、罪も……すべて“彼”に押しつけたから。」
美月の魂が、かつての肉体の中で孤独に暮らしているなど、誰も知る由もない。
彼女は言った。
「私の名は、綾瀬美月。
未来は、私のものよ」
その笑顔は美しく、そして誰よりも冷たかった。
「美月~! 今度みんなで沖縄行くんだけど、空いてる?」
メッセージアプリの通知に、博士の心が一瞬ざわめいた。
友人たちからの誘い。行き先は沖縄のビーチ。
「(ビーチ……水着……身体を見せる場所……)」
“美月”である今の博士は、鏡に映る完璧なボディラインにいつも陶酔していた。
だが、それと同時に、一つだけ気がかりな点があった。
――胸が、少し控えめなのだ。
「……多少ボリュームがあった方が、男受けも、女子の中でも映える……」
そう呟くと、博士は手元の通販アプリを開き、シリコン製の極厚パッドを注文した。
沖縄、白浜のビーチ。
青い空、透き通る海、若者たちの笑い声。
“美月”は、白のフリル付きビキニに身を包み、友人たちと並んでいた。
「美月~! なんか今日スタイル良すぎじゃない? なにそのバスト、ヤバッ!」
「えっ、ほんと? そうかな~?(※多少の加工はしてある)」
笑いながらピースを決める博士。
だが内心はヒヤヒヤだった。
水に入ったら、バレるかもしれない――。
「泳がないの?」「うん、ちょっと日焼けが心配で……♡」
会話を巧みにかわしながら、博士は“見られるだけ”を楽しんだ。
男たちの視線、女友達の羨望、それらすべてが甘美だった。
(ああ……これが、“美月”として生きるということか……!)
だが、波打ち際で戯れる仲間たちを見つめるうちに、
胸元の不自然なふくらみが少しズレてきていることに気づく。
「……まずい」
すぐにパーカーを羽織り、笑顔で言った。
「ねえ、そろそろカフェ行かない? わたし、スイーツのほうが好き~♡」
誰も博士の秘密には気づかなかった。
少なくともその日は――。
「…うわ~、やっぱり美月ちゃんって可愛いけど、ちょっと胸だけ控えめだよねぇ」
沖縄のビーチで撮った集合写真を見て、友人のさやかが何気なく言った一言。
周囲は「やめなよ~」と笑って流したが、その言葉は、美月の体に入った博士の心に深く突き刺さっていた。
(そうだ……この体に唯一足りないのは、バストの存在感。
美月の魅力を“完璧”にするには、あとほんの少し、ボリュームが必要なんだ)
博士は、すぐに研究に着手した。
テーマは――「局所脂肪移動薬:Adipo-Swap」。
数日後、研究室に呼び出されたさやかが言った。
「えっ、これ飲むとどうなるの? 美月ちゃんの新作ダイエットサプリ?」
「ううん。交換型よ。あなたの“余ってるところ”と、私の“足りないところ”、ちょっとだけ分け合いましょって感じ?」
さやかは笑った。「えー、別にいーよ? たしかに私、でかすぎて困ってるくらいだし」
乾杯のように薬瓶を交わし、二人は同時に服用した。
効果は数分で現れた。
さやかが「ん……? なんか、軽くなってない?」と胸を触るころには、
“美月”は、自分のビキニが張り詰める感覚に目を見開いていた。
「うそ……これ、私の体……なのに……重さが……ある……!」
鏡の前に立つと、そこにはバランスの取れた、豊かな曲線美を備えた“美月”がいた。
ウエストの細さに対して、絶妙なバストの存在感――理想が、今ここにある。
さやかは笑った。「マジで? あたしちょっとスッキリしてラッキーかも♪」
博士は笑顔で返したが、内心ではこう呟いていた。
(これで完成だ。完璧な美月が、ついにここに生まれた――)
沖縄の青い海、白い砂浜、抜けるような空――
美月(中身は博士)は、そのビーチの中心にいた。
白のビキニに身を包み、胸元は以前よりも豊かに、自然な丸みと張りを見せていた。
太陽の光が肌を照らすたび、目を惹く存在感が強調される。
「美月ちゃん、写真撮ってあげる~!」
「え、めっちゃ映えてる! SNSに載せたいくらい♡」
「てか、スタイルやばすぎじゃない?」
まわりには、男も女も自然と集まってくる。
「綾瀬さん、どこから来たの?」「東京の大学生? 連絡先、交換しよっか?」
笑顔で応じる“美月”の中身――博士は、満ち足りていた。
(この反応……やはり“形”が全てを支配する……)
一方、さやかはというと――
「あれ? なんか、さやかちゃん印象変わった?」「前もっと……いや、なんでもない」
「……なんでもないって、なに」
さやかの胸元は以前よりもすっきりしていた。
「バランスいいって感じだね~」と女友達はフォローしてくれるが、明らかに視線の集まり方が違う。
さらに、かつて“巨乳キャラ”として男子からチヤホヤされていた彼女に対し、今は“目立たない子”の扱い。
「…ねぇ、美月。ちょっと話せる?」
夕暮れの砂浜で、さやかが目を伏せて切り出した。
「……やっぱり、戻してほしい」
博士は小さく笑う。「どうして? あんなに“スッキリしてて楽”って言ってたのに」
「……あれは冗談。やっぱり、胸があるって大事だった。あたしの“らしさ”だったんだよ……」
博士は一瞬だけ目を閉じて、答えた。
「じゃあ、“戻す”かどうか、少し考えさせてもらえる?」
さやかが顔を上げると、そこにはニッコリと微笑む美月の姿――
だがその笑顔の奥には、明確な優越感と支配の気配が滲んでいた。
博士は知っていた。
脂肪の量は、単なる体の一部ではない。
それは人間関係、他者からの視線、自分という存在の重みを左右する“武器”なのだ。
「返すかどうかは、わたし次第よ。さやかちゃん」
そう呟きながら、博士は再びビーチの中央へと歩き出した。
砂浜に残されたのは、さやかのかすかな悔しさと、小さな足跡だけだった――。
胸の脂肪量を手に入れて以来、完璧なボディラインを得た“綾瀬美月”――その中身、博士は満ち足りていた。
しかし、日常のふとした瞬間、ある違和感が彼女を苛立たせ始める。
──視線が、わずかに“下から見上げる”角度にある。
同じくモデル体型のさやかと並んだ写真では、やはり微妙な身長差がある。
数センチの差だった。だがそれが、美の完成度において致命的な“ズレ”だと博士は感じていた。
(スタイルとは、相対的な支配でもある。私は、上から見下ろされてはならない)
そうして、博士は新たな薬の研究に着手した。
名を――「GROW-TRANSFER β-01」。
対象者の“骨格成長データ”と“ホルモン値”を一時的に同調させ、身長を強制的に移す薬だった。
ある日、さやかが研究室を訪れる。
「なにこれ? また新しいやつ? 美月ってほんと美容オタクだよね~」
「ちょっとした実験なの。一緒に飲んでみない?」
「ふふ、また“分けっこ”するの? まぁ、いいけど~♪」
さやかが軽く引き受けると、博士は心の中でほくそ笑んだ。
(今度は“上から”君を見る番だよ、さやか)
効果は即効だった。
数時間後、博士の脚は微かに伸び、骨盤位置が上がり、ヒールも履いていないのに“目線が高くなっている”と明確に感じた。
鏡の中の“美月”は、スラッと背筋を伸ばし、全身のシルエットが縦に引き締まって見える。
その横で、さやかが呟いた。
「……え、ちょっと待って。私……なんか縮んでない? てか、え? 美月の方が、背高くない?」
博士はあくまで自然に笑った。
「たぶん気のせいよ? 私、今日スニーカーだけどな~♡」
さやかは鏡を見て、動揺を隠せなかった。
「なんで……?」
だが、薬の効果は徐々に固定化されていく。
後日。
大学の廊下で、二人が並ぶ姿を見た男子学生たちの声が漏れる。
「え、美月ってあんなにスタイル良かったっけ?」
「身長も高く見えるし、脚めっちゃ長くない?」
「隣のさやか、前の方が目立ってたよな…?」
“美月”は微笑んだまま、わざとヒールの音を響かせて歩いた。
すれ違うさやかの頭を、軽く見下ろす高さから。
(やっと、私は完全になった)
沖縄の白い砂浜を歩く、美月とさやか。
照りつける太陽の下、ふたりの姿は一見、仲のいい女子大生同士に見えた。
──しかし、その“立ち位置”は明確に変わっていた。
「うわ……美月ちゃん、脚長っ!」
「え、さやかってこんなに小さかったっけ?」
周囲から聞こえる、心ない感想。
その言葉に、さやかは何も言い返せなかった。
たしかに、美月の身長は以前より明らかに高くなっていた。
脚の付け根の位置が違う。目線が違う。
水着姿になれば、シルエットの差はさらに顕著だった。
ビキニから覗く背筋のライン、ヒップから太ももにかけての伸びやかさ――
視線を奪っていたのは、明らかに“美月”の方だった。
「さやかちゃ~ん、こっちで写真撮ろうよ~」
「え、美月さんも一緒に! はいチーズ!」
スマホに収められた写真を、さやかはそっと確認する。
画面の中の自分は、美月の肩あたりまでしか背がなく、まるで“付き添いの子”のようだった。
「……ねぇ、美月」
帰り道、さやかが沈んだ声で切り出す。
「……身長、返してくれない?」
美月は振り返り、笑顔で首をかしげる。
「え? なんのこと?」
「わかってるでしょ……あの薬。あんたが、私から奪ったんでしょ……」
しばしの沈黙。
美月はゆっくりと背筋を伸ばし、見下ろすようにさやかに向き合った。
「……そうね。確かに、私は“君の高さ”をもらったわ」
さやかの手が震える。悔しさ、屈辱――そして認めたくない敗北感。
「でもね、さやかちゃん。私ね、もうこの高さじゃないと生きていけないの」
その言葉に、さやかは絶句した。
0
この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説








転生先はご近所さん?
フロイライン
ファンタジー
大学受験に失敗し、カノジョにフラれた俺は、ある事故に巻き込まれて死んでしまうが…
そんな俺に同情した神様が俺を転生させ、やり直すチャンスをくれた。
でも、並行世界で人々を救うつもりだった俺が転生した先は、近所に住む新婚の伊藤さんだった。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる