1 / 6
解放軍編
第一話 僕の名前は
しおりを挟む
これは別の次元、別の世界のお話。
この世界には、大きく分けて四つの身分が存在する。
一つ目は、王侯貴族。そして二つ目は平民。
三つ目は、やはり奴隷が来る。
地球が誕生してから数十億年、何度も知的生命体が現れては滅んできた。
しかしこの三つの階級だけは、いつの時代においても、どれだけ繰り返そうとも是正されることはなかった。
支配する側と、される側。
しかしそこにもし、その絶対的な構造から脱した特異種が混じったとしたら。
誰しもが生まれた時から身のうちに持っている、目には見えない力。
それはある時代では精神力と説明され、また別の時代では魔力と表現され。
ある人は、それを運命と呼んだ。
そしてそれらの力を自在に操る人間たちを、誰が呼んだか”宿霊者スカラー”。
そしてこの物語は、そんな不思議な力を従え、己の道を切り開くために戦う人間たちの物語だ。
『新編・ラーマーヤナ』
開幕。
「こらラム、あんたまたサボったね!?ほんとに使えない子だわ!」
表の畑から、おばさんの金切り声が聞こえる。
なんでああも、やかんみたいにカンカンなのかは分からないけれど——要件は、なんとなく察せされる。
心の底から込み上げてくるため息を押し殺しながら、僕は体全体で木製の扉を押し開けた。
ここは、コーサラ国南側のさらに南端、中央からは未発達地帯と揶揄されるど田舎”バシュタット”。
そしてそんなバシュタットでも僕——ラム=アリが住んでいるのは、借地での農業を生業とする小作人、半分奴隷のような扱いを受ける彼らが、すし詰めに住まわされる貧困地域。
大抵の小作人は、この地で一生を過ごす。
中央から派遣された領主から取り立てられる悪辣な年貢と、巡回の官吏から振るわれる不当な暴力。
一度体を壊せば、当然医者にかかる金などあるわけがない。
それでも生きるために働き続け、最期はみんなボロ雑巾のようになって死ぬ。
それが、この国の小作人に定められた運命だ。
こんな悪夢のような運命から逃れるための道は、犯罪に手を染めることを除けば主に二つ。
一つ目が、頭脳や腕っ節を認められて中央に士官することだ。
コーサラ国の内地と僻地の格差は酷いもので、辺境地帯が明日の食べ物にも窮しているのに対し、中央にはその分の揺り戻しとして湯水のように金が溜まっている。
とにかくどんな形であれ、王都圏で手に職を付ければ食いっぱぐれることは無いらしい。
僕は今年で十四歳。
年齢だけで言えば、官吏登用のための試験を受けられるようになる年だ。
しかしこの僕には、ハナからそんな道なんて無い。
なぜなら——。
「ちょっとラム!あんたって子は、拾ってやった恩を仇で返すつもり!?……あら来てたのかい。まったく、腕だけじゃなく耳も聞こえなくなっちまったかと思ったよ!」
おばさんの心ない言葉に項垂れた僕の目に、年相応に未発達な両腕の肘から先、力無くだらりと垂れ下がった両腕が目に入る。
僕には、肘から先の腕の感覚がない。
これは、生まれつきのものではないらしい。
どうやら幼い頃、戦火に巻き込まれた時に付けられた傷で、神経が大きく傷付けられたのだという。
……こんな体では当然、中央の官吏などなれはしない。
それなら、もう一つの道は。
「ほらラム、この大俵を山間の納屋まで運んどくれ。……あんたの力を使えば、これくらいはちょちょいのちょいだろ」
「…うん、ナムリおばさん。……ラム=アリの名の下に命ずる。…”偽りの右腕”」
ナムリおばさんの横に置かれた俵へと視線を移し、精神を集中させる。
イメージするんだ。
この腕が、今まさに動き出す瞬間を。
2、3秒間を置いてから、大人一人分はあろうかという大俵が宙へと浮かび上がった。
底面から支えているのは、青なのか紫なのか、どちらとも言えない不思議な色をした誰かの右腕。
ナムリおばさん曰く、僕からは表面は結晶のようにザラついて見えるその腕が、彼女には見えないらしい。
彼女だけではなく、村人の誰に聞いても答えは同じ。
俵が、ひとりでに動き出したようにしか見えないという。
「……じゃあ、行ってきます。ナムリおばさん」
「…ああ、行っといで。……分かってると思うけどね、ラム。納屋の二階には、絶対に行くんじゃないよ」
僕の育ての親であるナムリおばさんの家は、この付近の小作農地では相談役としてそれなりの待遇を得ている。
しかし、所詮は小作人である。
現在向かっている納屋にしても、家から離れた山中に築かれた、簡素な木造の二階建て。
ただし、おばさんに引き取られてから十数年。
納屋の二階には、一度も立ち入らせてもらえていない。
二階の話をすると、いつも釣り上がっているおばさんの目がいっそう険しくなるのだ。
噂では、おばさんの隠し財産があるのだとか。
まあ、そもそも持って逃げる腕もない僕には関係のないことだけれど。
だらだらと適当な考え事をしながら歩いていると、木々の間に寂れた納屋が見えてきた。
一呼吸おいて空を見上げると、太陽はすでに西の山地へとその身を沈めており、森には夜の匂いが漂いつつある。
鍵のかかっていない扉をどうにか足で開き、いつもの場所に大俵を置いた僕は、ふぅと一つ息をついて”偽りの右腕”を解除した。
宿霊者としての僕の能力、”偽りの右腕”。
どれだけ重い物を持たせても、僕自身に重さは伝わらない優れものだ。
ただ小一時間も出し続けると、高確率で鼻血が出るのがタマにキズと言ったところである。
何はともあれ、やっと帰れる。
そうして納屋の外へと足を進めた、その時だった。
「——マ。……ーマ」
誰かに呼ばれた気がした。
いったい誰が、何のためにこの場所で。
いやそもそも、この納屋の一階には僕一人しかいない。
それに、—声の感じからして大人の男だろう—声の主が隠れることができるようなスペースなんて、一階にはどこにもないのだ。
とすると、残っている可能性は。
「……二階に、誰かいるの…?」
遠慮がちにかけたその言葉に、答えるものはいない。
聞き間違いだろうか。
いや、あれは間違いなく人の声だ。
誰かが納屋の二階にいて、僕のことを呼んだのだ。
ゴクリと息を呑んだ僕は、意を決して階段に足をかけると。
入ってはいけないと言われていた納屋の二階へと、足を踏み入れた。
一歩一歩、踏み締めるたびにギシギシと音のなるような、年季の入った板張りの床を進んでいくと。
奥に見えてきたのは、木製の化粧台の上にぽつんと置かれた銀時計。
こんな田舎にそんなものがあるのにも驚いたが、さらに近づいて手に取ってみるうちに。
その表蓋にあつらえられたとある装飾に気づき、僕は思わずあっと声を上げた。
太陽と獅子の紋章。
コーサラ国王家の家紋、つまりはコーサラ国の紋章である。
単なる模造品かとも考えたが、その考えは僕自身の中にある”この国の常識”によってすぐに打ち消される。
この太陽と獅子の紋章は、コーサラ国王家の顔であり誇りと呼ぶべきもの。
これを彼らの許可無く使用することや、こういった物品に刻印することは、国法により固く禁じられている。
それを破った場合の刑罰は、問答無用で火刑。
この国で、よりによって王族の持ち物を偽造しようなどという愚か者はいないだろう。
それじゃあこれは、本物の王印時計……?
とても信じられないその事実に、夢でも見ているかのようにフワフワした感覚の中。
僕はほぼ無意識のうちに、”偽りの右腕”を呼び出していた。
どういうわけか、そうした方が良いと——そうすべきだと、誰かに言われた気がしたから。
そして、”偽りの右腕”がくるりと銀時計を裏返して見せた、まさにその時。
何か今までとは違う感覚と共に、銀時計がパカリと開いた。
「あっ、開いちゃった……うっ、えっ……!?」
その、瞬間。
閃光。風圧。衝撃。鈍痛。
処理の追いつかない僕の脳みそを置き去りに、さまざまな現象が同時に起こった。
その中でも、衝撃で倒れた戸棚や強打した背中の痛みなど、気にならないほどの”異常事態”が僕の前に現れたんだ。
「……お久しぶりにございます、ご主人様。…おっと。私のことは、たしか忘れているのでしたね。……主よ。私のことは、ルディナとお呼びください」
風圧で立ち込めた埃が晴れた時、僕の前に立っていたのは一人の……というにはあまりにも小さく、1匹と数えるにはあまりに人間らしい、そんな生物。
呆気に取られる僕を前に、その小さな男——ルディナは、サラリととてつもないことを口走った。
そしてこの僕とルディナの出会いは、僕の——それにこの国の運命を、大きく変えていくものとなるんだ。
「我が主——ラーマ皇太子よ。……私が現れたことで、あなた様の力は戻りました!…さあ、国取りを始めようではありませんか!!」
この世界には、大きく分けて四つの身分が存在する。
一つ目は、王侯貴族。そして二つ目は平民。
三つ目は、やはり奴隷が来る。
地球が誕生してから数十億年、何度も知的生命体が現れては滅んできた。
しかしこの三つの階級だけは、いつの時代においても、どれだけ繰り返そうとも是正されることはなかった。
支配する側と、される側。
しかしそこにもし、その絶対的な構造から脱した特異種が混じったとしたら。
誰しもが生まれた時から身のうちに持っている、目には見えない力。
それはある時代では精神力と説明され、また別の時代では魔力と表現され。
ある人は、それを運命と呼んだ。
そしてそれらの力を自在に操る人間たちを、誰が呼んだか”宿霊者スカラー”。
そしてこの物語は、そんな不思議な力を従え、己の道を切り開くために戦う人間たちの物語だ。
『新編・ラーマーヤナ』
開幕。
「こらラム、あんたまたサボったね!?ほんとに使えない子だわ!」
表の畑から、おばさんの金切り声が聞こえる。
なんでああも、やかんみたいにカンカンなのかは分からないけれど——要件は、なんとなく察せされる。
心の底から込み上げてくるため息を押し殺しながら、僕は体全体で木製の扉を押し開けた。
ここは、コーサラ国南側のさらに南端、中央からは未発達地帯と揶揄されるど田舎”バシュタット”。
そしてそんなバシュタットでも僕——ラム=アリが住んでいるのは、借地での農業を生業とする小作人、半分奴隷のような扱いを受ける彼らが、すし詰めに住まわされる貧困地域。
大抵の小作人は、この地で一生を過ごす。
中央から派遣された領主から取り立てられる悪辣な年貢と、巡回の官吏から振るわれる不当な暴力。
一度体を壊せば、当然医者にかかる金などあるわけがない。
それでも生きるために働き続け、最期はみんなボロ雑巾のようになって死ぬ。
それが、この国の小作人に定められた運命だ。
こんな悪夢のような運命から逃れるための道は、犯罪に手を染めることを除けば主に二つ。
一つ目が、頭脳や腕っ節を認められて中央に士官することだ。
コーサラ国の内地と僻地の格差は酷いもので、辺境地帯が明日の食べ物にも窮しているのに対し、中央にはその分の揺り戻しとして湯水のように金が溜まっている。
とにかくどんな形であれ、王都圏で手に職を付ければ食いっぱぐれることは無いらしい。
僕は今年で十四歳。
年齢だけで言えば、官吏登用のための試験を受けられるようになる年だ。
しかしこの僕には、ハナからそんな道なんて無い。
なぜなら——。
「ちょっとラム!あんたって子は、拾ってやった恩を仇で返すつもり!?……あら来てたのかい。まったく、腕だけじゃなく耳も聞こえなくなっちまったかと思ったよ!」
おばさんの心ない言葉に項垂れた僕の目に、年相応に未発達な両腕の肘から先、力無くだらりと垂れ下がった両腕が目に入る。
僕には、肘から先の腕の感覚がない。
これは、生まれつきのものではないらしい。
どうやら幼い頃、戦火に巻き込まれた時に付けられた傷で、神経が大きく傷付けられたのだという。
……こんな体では当然、中央の官吏などなれはしない。
それなら、もう一つの道は。
「ほらラム、この大俵を山間の納屋まで運んどくれ。……あんたの力を使えば、これくらいはちょちょいのちょいだろ」
「…うん、ナムリおばさん。……ラム=アリの名の下に命ずる。…”偽りの右腕”」
ナムリおばさんの横に置かれた俵へと視線を移し、精神を集中させる。
イメージするんだ。
この腕が、今まさに動き出す瞬間を。
2、3秒間を置いてから、大人一人分はあろうかという大俵が宙へと浮かび上がった。
底面から支えているのは、青なのか紫なのか、どちらとも言えない不思議な色をした誰かの右腕。
ナムリおばさん曰く、僕からは表面は結晶のようにザラついて見えるその腕が、彼女には見えないらしい。
彼女だけではなく、村人の誰に聞いても答えは同じ。
俵が、ひとりでに動き出したようにしか見えないという。
「……じゃあ、行ってきます。ナムリおばさん」
「…ああ、行っといで。……分かってると思うけどね、ラム。納屋の二階には、絶対に行くんじゃないよ」
僕の育ての親であるナムリおばさんの家は、この付近の小作農地では相談役としてそれなりの待遇を得ている。
しかし、所詮は小作人である。
現在向かっている納屋にしても、家から離れた山中に築かれた、簡素な木造の二階建て。
ただし、おばさんに引き取られてから十数年。
納屋の二階には、一度も立ち入らせてもらえていない。
二階の話をすると、いつも釣り上がっているおばさんの目がいっそう険しくなるのだ。
噂では、おばさんの隠し財産があるのだとか。
まあ、そもそも持って逃げる腕もない僕には関係のないことだけれど。
だらだらと適当な考え事をしながら歩いていると、木々の間に寂れた納屋が見えてきた。
一呼吸おいて空を見上げると、太陽はすでに西の山地へとその身を沈めており、森には夜の匂いが漂いつつある。
鍵のかかっていない扉をどうにか足で開き、いつもの場所に大俵を置いた僕は、ふぅと一つ息をついて”偽りの右腕”を解除した。
宿霊者としての僕の能力、”偽りの右腕”。
どれだけ重い物を持たせても、僕自身に重さは伝わらない優れものだ。
ただ小一時間も出し続けると、高確率で鼻血が出るのがタマにキズと言ったところである。
何はともあれ、やっと帰れる。
そうして納屋の外へと足を進めた、その時だった。
「——マ。……ーマ」
誰かに呼ばれた気がした。
いったい誰が、何のためにこの場所で。
いやそもそも、この納屋の一階には僕一人しかいない。
それに、—声の感じからして大人の男だろう—声の主が隠れることができるようなスペースなんて、一階にはどこにもないのだ。
とすると、残っている可能性は。
「……二階に、誰かいるの…?」
遠慮がちにかけたその言葉に、答えるものはいない。
聞き間違いだろうか。
いや、あれは間違いなく人の声だ。
誰かが納屋の二階にいて、僕のことを呼んだのだ。
ゴクリと息を呑んだ僕は、意を決して階段に足をかけると。
入ってはいけないと言われていた納屋の二階へと、足を踏み入れた。
一歩一歩、踏み締めるたびにギシギシと音のなるような、年季の入った板張りの床を進んでいくと。
奥に見えてきたのは、木製の化粧台の上にぽつんと置かれた銀時計。
こんな田舎にそんなものがあるのにも驚いたが、さらに近づいて手に取ってみるうちに。
その表蓋にあつらえられたとある装飾に気づき、僕は思わずあっと声を上げた。
太陽と獅子の紋章。
コーサラ国王家の家紋、つまりはコーサラ国の紋章である。
単なる模造品かとも考えたが、その考えは僕自身の中にある”この国の常識”によってすぐに打ち消される。
この太陽と獅子の紋章は、コーサラ国王家の顔であり誇りと呼ぶべきもの。
これを彼らの許可無く使用することや、こういった物品に刻印することは、国法により固く禁じられている。
それを破った場合の刑罰は、問答無用で火刑。
この国で、よりによって王族の持ち物を偽造しようなどという愚か者はいないだろう。
それじゃあこれは、本物の王印時計……?
とても信じられないその事実に、夢でも見ているかのようにフワフワした感覚の中。
僕はほぼ無意識のうちに、”偽りの右腕”を呼び出していた。
どういうわけか、そうした方が良いと——そうすべきだと、誰かに言われた気がしたから。
そして、”偽りの右腕”がくるりと銀時計を裏返して見せた、まさにその時。
何か今までとは違う感覚と共に、銀時計がパカリと開いた。
「あっ、開いちゃった……うっ、えっ……!?」
その、瞬間。
閃光。風圧。衝撃。鈍痛。
処理の追いつかない僕の脳みそを置き去りに、さまざまな現象が同時に起こった。
その中でも、衝撃で倒れた戸棚や強打した背中の痛みなど、気にならないほどの”異常事態”が僕の前に現れたんだ。
「……お久しぶりにございます、ご主人様。…おっと。私のことは、たしか忘れているのでしたね。……主よ。私のことは、ルディナとお呼びください」
風圧で立ち込めた埃が晴れた時、僕の前に立っていたのは一人の……というにはあまりにも小さく、1匹と数えるにはあまりに人間らしい、そんな生物。
呆気に取られる僕を前に、その小さな男——ルディナは、サラリととてつもないことを口走った。
そしてこの僕とルディナの出会いは、僕の——それにこの国の運命を、大きく変えていくものとなるんだ。
「我が主——ラーマ皇太子よ。……私が現れたことで、あなた様の力は戻りました!…さあ、国取りを始めようではありませんか!!」
0
あなたにおすすめの小説
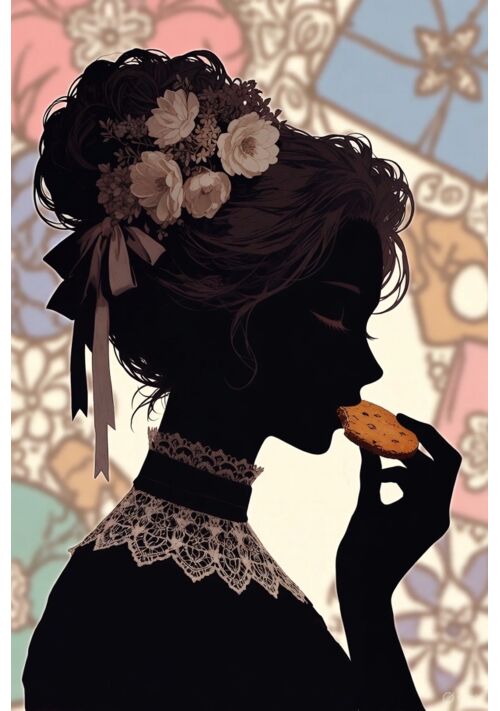
誰からも食べられずに捨てられたおからクッキーは異世界転生して肥満令嬢を幸福へ導く!
ariya
ファンタジー
誰にも食べられずゴミ箱に捨てられた「おからクッキー」は、異世界で150kgの絶望令嬢・ロザリンドと出会う。
転生チートを武器に、88kgの減量を導く!
婚約破棄され「豚令嬢」と罵られたロザリンドは、
クッキーの叱咤と分裂で空腹を乗り越え、
薔薇のように美しく咲き変わる。
舞踏会での王太子へのスカッとする一撃、
父との涙の再会、
そして最後の別れ――
「僕を食べてくれて、ありがとう」
捨てられた一枚が紡いだ、奇跡のダイエット革命!
※カクヨム・小説家になろうでも同時掲載中
※表紙イラストはAIに作成していただきました。

【完結】辺境に飛ばされた子爵令嬢、前世の経営知識で大商会を作ったら王都がひれ伏したし、隣国のハイスペ王子とも結婚できました
いっぺいちゃん
ファンタジー
婚約破棄、そして辺境送り――。
子爵令嬢マリエールの運命は、結婚式直前に無惨にも断ち切られた。
「辺境の館で余生を送れ。もうお前は必要ない」
冷酷に告げた婚約者により、社交界から追放された彼女。
しかし、マリエールには秘密があった。
――前世の彼女は、一流企業で辣腕を振るった経営コンサルタント。
未開拓の農産物、眠る鉱山資源、誠実で働き者の人々。
「必要ない」と切り捨てられた辺境には、未来を切り拓く力があった。
物流網を整え、作物をブランド化し、やがて「大商会」を設立!
数年で辺境は“商業帝国”と呼ばれるまでに発展していく。
さらに隣国の完璧王子から熱烈な求婚を受け、愛も手に入れるマリエール。
一方で、税収激減に苦しむ王都は彼女に救いを求めて――
「必要ないとおっしゃったのは、そちらでしょう?」
これは、追放令嬢が“経営知識”で国を動かし、
ざまぁと恋と繁栄を手に入れる逆転サクセスストーリー!
※表紙のイラストは画像生成AIによって作られたものです。

私はもう必要ないらしいので、国を護る秘術を解くことにした〜気づいた頃には、もう遅いですよ?〜
AK
ファンタジー
ランドロール公爵家は、数百年前に王国を大地震の脅威から護った『要の巫女』の子孫として王国に名を残している。
そして15歳になったリシア・ランドロールも一族の慣しに従って『要の巫女』の座を受け継ぐこととなる。
さらに王太子がリシアを婚約者に選んだことで二人は婚約を結ぶことが決定した。
しかし本物の巫女としての力を持っていたのは初代のみで、それ以降はただ形式上の祈りを捧げる名ばかりの巫女ばかりであった。
それ故に時代とともにランドロール公爵家を敬う者は減っていき、遂に王太子アストラはリシアとの婚約破棄を宣言すると共にランドロール家の爵位を剥奪する事を決定してしまう。
だが彼らは知らなかった。リシアこそが初代『要の巫女』の生まれ変わりであり、これから王国で発生する大地震を予兆し鎮めていたと言う事実を。
そして「もう私は必要ないんですよね?」と、そっと術を解き、リシアは国を後にする決意をするのだった。
※小説家になろう・カクヨムにも同タイトルで投稿しています。

最愛の番に殺された獣王妃
望月 或
恋愛
目の前には、最愛の人の憎しみと怒りに満ちた黄金色の瞳。
彼のすぐ後ろには、私の姿をした聖女が怯えた表情で口元に両手を当てこちらを見ている。
手で隠しているけれど、その唇が堪え切れず嘲笑っている事を私は知っている。
聖女の姿となった私の左胸を貫いた彼の愛剣が、ゆっくりと引き抜かれる。
哀しみと失意と諦めの中、私の身体は床に崩れ落ちて――
突然彼から放たれた、狂気と絶望が入り混じった慟哭を聞きながら、私の思考は止まり、意識は閉ざされ永遠の眠りについた――はずだったのだけれど……?
「憐れなアンタに“選択”を与える。このままあの世に逝くか、別の“誰か”になって新たな人生を歩むか」
謎の人物の言葉に、私が選択したのは――

不倫されて離婚した社畜OLが幼女転生して聖女になりましたが、王国が揉めてて大事にしてもらえないので好きに生きます
天田れおぽん
ファンタジー
ブラック企業に勤める社畜OL沙羅(サラ)は、結婚したものの不倫されて離婚した。スッキリした気分で明るい未来に期待を馳せるも、公園から飛び出てきた子どもを助けたことで、弱っていた心臓が止まってしまい死亡。同情した女神が、黒髪黒目中肉中背バツイチの沙羅を、銀髪碧眼3歳児の聖女として異世界へと転生させてくれた。
ところが王国内で聖女の処遇で揉めていて、転生先は草原だった。
サラは女神がくれた山盛りてんこ盛りのスキルを使い、異世界で知り合ったモフモフたちと暮らし始める――――
※第16話 あつまれ聖獣の森 6 が抜けていましたので2025/07/30に追加しました。

人質5歳の生存戦略! ―悪役王子はなんとか死ぬ気で生き延びたい!冤罪処刑はほんとムリぃ!―
ほしみ
ファンタジー
「え! ぼく、死ぬの!?」
前世、15歳で人生を終えたぼく。
目が覚めたら異世界の、5歳の王子様!
けど、人質として大国に送られた危ない身分。
そして、夢で思い出してしまった最悪な事実。
「ぼく、このお話知ってる!!」
生まれ変わった先は、小説の中の悪役王子様!?
このままだと、10年後に無実の罪であっさり処刑されちゃう!!
「むりむりむりむり、ぜったいにムリ!!」
生き延びるには、なんとか好感度を稼ぐしかない。
とにかく周りに気を使いまくって!
王子様たちは全力尊重!
侍女さんたちには迷惑かけない!
ひたすら頑張れ、ぼく!
――猶予は後10年。
原作のお話は知ってる――でも、5歳の頭と体じゃうまくいかない!
お菓子に惑わされて、勘違いで空回りして、毎回ドタバタのアタフタのアワアワ。
それでも、ぼくは諦めない。
だって、絶対の絶対に死にたくないからっ!
原作とはちょっと違う王子様たち、なんかびっくりな王様。
健気に奮闘する(ポンコツ)王子と、見守る人たち。
どうにか生き延びたい5才の、ほのぼのコミカル可愛いふわふわ物語。
(全年齢/ほのぼの/男性キャラ中心/嫌なキャラなし/1エピソード完結型/ほぼ毎日更新中)

異世界に召喚されて2日目です。クズは要らないと追放され、激レアユニークスキルで危機回避したはずが、トラブル続きで泣きそうです。
もにゃむ
ファンタジー
父親に教師になる人生を強要され、父親が死ぬまで自分の望む人生を歩むことはできないと、人生を諦め淡々とした日々を送る清泉だったが、夏休みの補習中、突然4人の生徒と共に光に包まれ異世界に召喚されてしまう。
異世界召喚という非現実的な状況に、教師1年目の清泉が状況把握に努めていると、ステータスを確認したい召喚者と1人の生徒の間にトラブル発生。
ステータスではなく職業だけを鑑定することで落ち着くも、清泉と女子生徒の1人は職業がクズだから要らないと、王都追放を言い渡されてしまう。
残留組の2人の生徒にはクズな職業だと蔑みの目を向けられ、
同時に追放を言い渡された女子生徒は問題行動が多すぎて退学させるための監視対象で、
追加で追放を言い渡された男子生徒は言動に違和感ありまくりで、
清泉は1人で自由に生きるために、問題児たちからさっさと離れたいと思うのだが……

幼女はリペア(修復魔法)で無双……しない
しろこねこ
ファンタジー
田舎の小さな村・セデル村に生まれた貧乏貴族のリナ5歳はある日魔法にめざめる。それは貧乏村にとって最強の魔法、リペア、修復の魔法だった。ちょっと説明がつかないでたらめチートな魔法でリナは覇王を目指……さない。だって平凡が1番だもん。騙され上手な父ヘンリーと脳筋な兄カイル、スーパー執事のゴフじいさんと乙女なおかんマール婆さんとの平和で凹凸な日々の話。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















