1 / 1
首切り役人と赤い靴
しおりを挟む「いつまでも、お前は踊らなくてはならぬ。」と、天使はいいました。「赤いくつをはいて、踊っておれ。お前が青じろくなって冷たくなるまで、お前のからだがしなびきって、骸骨になってしまうまで踊っておれ。」
――Andersen, Hans Christian,DE RODE SKO,(アンデルセン ハンス・クリスティアン,「赤いくつ」,楠山正雄訳,『新訳アンデルセン童話集 第二巻』同和春秋社,1955)
荒地の上の一軒の寂しい家を、ひとりの若いお役人が訪ねて行きました。
そこはとある首切り役人の家でしたが、もう彼とは何年も連絡が取れないままになっておりました。
お役所の偉いお役人さんは、今になってようやく重い腰を上げ、若いこのお役人さんに、彼の様子を身に行くように命じたのでした。
しぶしぶやってきたお役人さんは荒地の上の寂しい家の、朽ちかけた扉をとんとんと叩きました。しかし返事はありません。
ためしに役人さんがノブを回すと、扉はあっさりと開きました。家の中はしんと静まり返っております。
さして大きくもない一軒家です。寝室はすぐに見つかりました。
役人さんはベッドに横になっている人影を見つけ覗き込み、たいそう肝を冷やしました。
ベッドに横たわっていた首切り役人は、とっくのとうに息をするのを止めていたのです。
死体はそうなってから随分長い時間が経っているようです。
だから腐乱したりひどい臭いがしたりということはありませんでしたが、役人さんは驚いて気が気ではありませんでした。
いったい何があったのかと慌ててあたりを見回すと、ふいにおかしなものが目に入りました。
それはベッドのそばに吊るされた大きな鳥籠なのでしたが、そこに入っているのは鳥ではなくぴかぴか光る赤い靴。さらには靴の中に真っ黒くからからに干からびた、棒切れのようなものが刺さっているのでした。
これはなんだろうと役人さんが首を傾げていると机の上に、一冊の本を見つけました。それは首切り役人の日記でした。
役人さんはそれをそっと開き、彼の身に何が起こったのか読み解くことにしたのでした。
※ ※ ※
ある日突然、首切り役人の家の窓を叩く音がしました。助けて、と悲鳴のような声もします。
ぎょっとして外に出てみますと、そこにいたのは顔も腕も足も傷だらけ、ぼろぼろになった服をまとい、けれど足にだけはぴかぴか光る真っ赤な靴をはいた少女でした。
役人は思わず息を呑みました。
少女は苦しそうに顔をゆがめながら、しかし足取りだけは軽く見事な足拍子(ステップ)を踏み続けています。
「何だお前はっ。おれは悪い奴の首を切り落とす首切り役人だぞ!」
訳が分からず声を張り上げると、少女は悲鳴を上げるように泣きながら言いました。
「お願い! この足を切って、この赤い靴ごと足を切り落としてください。お役人様!」
少女は自分の罪を、すっかりと首切り役人に告白しました。
「あたしはとっても悪い子なのです。教会の洗礼に赤い靴を履いていきました。病気のお婆様の看病をさぼって舞踏会に踊りに行きました。あたしは罰が当たって踊り続けなければならなくなりました。でもあたしは神様に懺悔がしたいんです。だからお願いです。この踊り続ける足を切り落として!」
役人はぎょっとして少女の告白を聞きました。そして少女の足を見ます。
この小さな足に斧を当てる?
こんな握り潰してしまえそうな細い足首に?
しかし足は止まってはくれません。再び赤い靴は少女をどこかに連れ去ろうとします。少女は高い悲鳴を上げました。
首切り役人はとっさに少女を突き倒すと、何十人、何百人もの罪人の首を切り落とした斧で、赤い靴ごとその細い足首を切り落としました。靴は小さい足といっしょに畑を越え、深い森の中へ踊って行ってしまいました。
足を切り落とされた少女は、これまでの疲れもあったのでしょう。高熱を出して倒れてしまいました。
首切り役人は少女のためにたった一つしかないベッドを譲り渡し、懸命に看病をいたしました。
少女は首切り役人の誠意溢れる親切な振る舞いに、涙を流して感謝をいたしました。
「ありがとうございます。お役人様。こんな罪深いあたしに、なんとお優しいことでしょう」
その言葉に首切り役人は、黙って首を振りました。
首切り役人は足を失った少女のために、木を削って義足をつくってやりました。少女はそのことにも大変喜び、――そしてその翌日に姿を消しました。
首切り役人に対する謝罪と、深い感謝を込めた書置き一つを残して。
書置きを見つけた首切り役人は、少女を懸命に探して歩きました。
切り落としたばかりにその足に、なれない義足はさぞや痛いことでしょう。何よりも少女の熱は、いまだに下がりきってはおりませんでした。
首切り役人は必死になって少女を探しましたが、とうとう少女は見つかりませんでした。
そして数ヵ月後、たまたま町に出た首切り役人は風の噂に少女の噂を聞きました。
それは義足の少女が教会で天に召された、と言うものでした。
人々は口々に少女が神に赦され、その御許へ旅立ったことを祝福しましたが、しかし首切り役人だけは何も言わずに自分の住処へ戻りました。
扉をしっかりと閉め、鍵を掛け、そしてそこでようやく叫んだのです。
「なぜ、あの少女が死ななければならなかった!」
少女は己は罪を犯したのだと言いました。
しかし少女が望んだことは、ただ若者らしく美しい靴を欲し、そして養い親の看病ばかりの毎日の中で、たった一度の気晴らしを求めただけ。
それをどうして罪と呼べるのでしょう。
「それならば、あの少女の足を切り落とし、罪人とは言え何百人もの人間の首を切り落とした俺のほうがよっぽどの咎人では無いか!」
首切り役人は力任せに、テーブルに拳を叩き付けます。
テーブルは軋み、足の一本が折れ曲がりました。
首切り役人はそのまましばらく天板に顔を伏せ、押し黙っていました。しかし、やがてのっそりと立ち上がると、いつものように日々の雑務をこなし始めました。
例え彼がどれだけ憤ろうと、少女はすでに天に召されているのです。どんな感傷も後悔も、もはや意味がありません。
そう結論付けた彼は再び、少女が訪れる前と何も変わらない毎日に戻りました。いえ、戻るつもりでした。
しかしそんな彼の気持ちとは裏腹に、怒りと絶望感はいつまでも彼の中でちくちくと、時折身を打つ鈍痛と共に、その存在を主張し続けていました。
幾日ほど経ったころでしょうか。
家の裏で薪を切っていた首切り役人は、ふと気配を感じて振り返りました。
そこには誰の姿もありませんでしたが、首切り役人は誰かが自分を覗いていたことを確信しておりました。
何故なら彼はこのところ、何度も窓から視線を感じたり、姿を見せない何者かが扉の外を伺うように歩く足音を聞いていたからです。
そうでなくともこれまでずっと彼は、いつまでも治まらない不快な心身に悩まされていたのです。
我慢できなくなった首切り役人は、斧を思い切り地面に叩き付けて怒鳴りました。
「いったい誰がこそこそ覗いている! いい加減出て来ないと、この斧でお前を切り刻むぞ!」
びりびりと森の草木が震えるような大声でした。
首切り役人は苛々と怒りを抱いたまま、しばし待ちました。このまま正体を現さないようなら、こちらから向かって本当に切り刻んでやる、とすら考えていました。
数刻、いえ、ほんの数秒あとのことでしょう。やがて、がさりと藪が音を立ててました。
そして表れたその正体を見て、首切り役人は唖然と目を見開いてしまいました。
藪を掻き分けて表れたのは、下はピカピカと光る美しい赤い靴。
その靴を履いた、白くて細い、華奢な足首。
そして――、それだけでした。
赤い靴を履いた白い足は、その足首だけでしずしずと首切り役人の元に歩いてきました。
足首は彼の目の前でちょこんと足を止めます。
首切り役人はぽかんと口を開いたまま立ち尽くしておりました。しかし、やがてその肩は小刻みに震え出します。
ふつふつと煮えたぎるような激しい憤怒の感情が、腹の底から一気に噴出してきたのです。
首切り役人はその手に持っていた薪割り用の斧を、赤い靴に向かって力任せに振り下ろしました。
赤い靴は驚いたように跳びはね、再び藪の中に逃げて行きます。
首切り役人は、喉も枯らさんばかりの声で怒鳴りました。
「よくも俺の前に姿を現せたものだ! もう一度戻ってきて、俺にそのピカピカの赤い色を見せてみろ。斧で千にも万にも刻んでやる!」
がさがさと音を立てて逃げる、それ――自分が切り落とした少女の足首を、射殺さんばかりの目で睨み付けていた首切り役人でしたが、やがて彼は、そのままへなへなと座り込みたい気持ちに駆られました。
あの少女はとっくに天に召されてしまったというのに、何であの足首が、赤い靴だけが歩き回っているんだ。
まるで酷い悪夢でも見たような気持ちでした。
いや、きっと悪夢に違いない。あれは自分の感傷が見せた幻なのだ。
首切り役人はそう思いこんで、いま見たものを忘れようと努めました。
しかしそれ以降、あの赤い靴を履いた足首は、堂々と悪びれることなく首切り役人の前に姿を現すようになったのです。
楽しげに、踊るような見事な足拍子を踏みながら、赤い靴は彼の家にやってきます。
そして彼の家の周りを伺うようにくるくる回ったり、あるいは畑仕事や薪割りをしている彼の元に近寄って来たり。
その度に首切り役人は大声を出して怒鳴りつけ、斧や包丁を持って追い回したりしましたが、むしろそうするたびに赤い靴は、実に嬉しそうに跳ね回りながら逃げていくのでした。
羽根のように軽やかに、踊るような足運びで畑を走り回る赤い靴は実にすばしっこくて、首切り役人はいつもいつも取り逃がし、息をするのも苦しい身体で、悔しげに地団駄を踏む羽目になりました。
それが一週間、二週間。そして、それ以上の間繰り返された頃でした。
再び当たり前のように畑にやってきた赤い靴を、首切り役人はいつものように怒鳴りつけます。
そして素早く踵を返して逃げ出す赤い靴を追いかけようとしたのですが、そこでおやと足を止めました。
いつもならそのまま踊るように跳ね回りながら逃げていく赤い靴なのですが、今日はどういうわけか途中でぴたりと動きを止めてしまったのです。
訝しく思いながら慎重に近付いていく首切り役人でしたが、その理由を知ってぽかんと口を半開きにしました。
どうやら赤い靴は、あまりに元気良く飛び跳ねるあまり、昨夜遅くに降った雨でできた水溜りに、勢い良く飛び込んでしまったようなのでした。
水溜りの中にぽちゃんと嵌まり込んだ赤い靴は、せっかくのピカピカした赤い色も染み一つない白い足もすっかり泥だらけになってしまっています。
それがあまりに衝撃的だったようで、赤い靴は泥水の中で身動きもとれずふるふると震えているのでした。
そんな様子を目に留め唖然としていた首切り役人は、――やがて大きな声で笑い出しました。
尻餅をついたように座り込み、臓腑が痛み、呼吸すら危うくなるほどげらげらと笑い続ける首切り役人を心配するように、泥まみれになった赤い靴はそろそろと近寄ってきました。
首切り役人はそんな赤い靴に手を伸ばし、赤い靴はびくりと一瞬震えましたが、大人しく首切り役人の手の中に納まりました。
「もう降参だ。分かったよ」
首切り役人は眦に浮かんだ笑いの残滓を拭いながら、言いました。
「お前もまた、カーレンなんだな」
それは、書置きの署名でしか知ることができなかった、あの少女の名前でした。
首切り役人は気付いていました。
この、狂ったように踊り続ける赤い靴は、驚くほどに無邪気であどけない存在であること。
どうして首切り役人に纏わり付いているのかは分かりませんが、それだって決して悪意があってのことではないということ。
「お前にはきっと、あの娘が切り離してしまった全てが詰まっているんだな」
あの娘が後悔して、捨て去ってしまったもの。
それは、享楽的な喜びを求める気持ち、お洒落がしたいと望む心、楽しいことや嬉しいことを欲する感情、子供のような悪戯心や奔放さ、年頃の娘らしい矜持の高さ。
そういったものが全て、この赤い靴の中に移ったのだ。
首切り役人は、そう理解していました。
首切り役人は慈しむように、赤い靴や足首に飛び散った泥を自分の服の袖で拭ってやりました。
そうするうちに、首切り役人は自身の手の中に納まっているその細い足首に、触れてみたい欲求に駆られました。
滑らかでみずみずしく、華奢な白い足首。
しかし首切り役人の指はその反対で、重い斧を振り回す故にごつごつと節くれだち、豆だらけでざらついています。
こんな指で触ったら、逆に汚して傷つけてしまいそうだ。
そう彼は躊躇していたのですが、ふいに足首は甘えるように、その肌を首切り役人の手に擦り付けました。
白い肌は、看病のときに触れてしまったあの少女と同じように、すべらかで暖かいものでした。
首切り役人の心臓はまるで、その熱が移ったかのように、ほんのりと暖まります。
「――お前、俺の家に来るか?」
首切り役人が尋ねると、赤い靴は頷くようにふるりとその身を震わせました。
首切り役人は、赤い靴をそのまま自分の家に連れて帰ったのでした。
それから、赤い靴と首切り役人は一緒に暮らし始めました。
口がないなら、喋ることもなくて静かでいいだろう。
食べることがなければ、食費も余計にかかりはしないだろう。
小さな赤い靴は場所を取らず、邪魔になることはないだろう。
そう考えた首切り役人は、きっと赤い靴がそばにあっても、自分の生活はこれまでと変わることはないだろうと、そう思っておりました。
しかしこの同居人。構って欲しいことがあると、歩く彼の足を引っ掛けたり、足の小指を踵で踏んで主張します。
無視して家事仕事をしていると、さらにちょっかいを出して邪魔をしてくるし、ついには仕事道具に悪戯を仕掛けたりするので、それまで同様何度も彼は、赤い靴を怒鳴り、追い掛け回す羽目になりましたました。
あるいはある日を境にふっつりと姿を消してしまったかと思えば、数日後に茨に突っ込んだのか野犬に噛まれたのか、血まみれになって戻ってくることもしばしばありました。
お陰で、首切り役人の静かで淡々とした暮らしは、日ごろの憂いを忘れるほどに、賑やかで一向に気の休まる暇のないものになったのでした。
「お前は、少しは大人しくしていてくれ」
お湯で湿らせた布でその白い足首を拭ってやりながら、首切り役人は嘆息します。
外を駆け回り、砂埃で汚れていた足首は元の白さと滑らかさを取り戻します。先日薮に飛び込んでついた傷も、すっかり治ったようです。
ついでに赤い靴も拭ってやると、靴はピカピカとまるで宝石のように輝きました。
「ここまでじゃじゃ馬だとは、思ってもみなかった。あんまり俺に心配を掛けさせるな」
首切り役人はそう語りかけますが、赤い靴はぴょんと彼の膝の上から飛び降りました。
そして、そんなこと知らないよとばかりに、楽しげに足拍子を踏み、踊ります。
その様子に首切り役人は、仕方がないとばかりに優しい苦笑を浮かべるのでした。
そんな暮らしがしばらく続いたある日、首切り役人は町に出ることにしました。
罪人の首を切る仕事をしている首切り役人が町に出ると、町の人々はみんな嫌な顔をします。
だから彼は町に出るのがあまり好きではなかったのですが、日用品を買う必要があったので仕方がありません。
またここ何年か続いている体の不調も、最近どうにも酷くなってきたのでそれもまた医者に診てもらうつもりでした。
彼に心配そうに寄り添ってくれる赤い靴を家に残し、首切り役人は町で出向きました。
そしていくつか必要な品を購入した後、医者のところへ行きました。
しかしそこで聞いたのは、首切り役人にとってあまりに酷な事実でした。
首切り役人が家に戻ると、いつものように赤い靴が踊るように飛び跳ねながら出迎えてくれました。
しかし、彼の手に大きな鳥籠があることに気付くと、不思議そうな様子でその周りをくるくると回ります。
「頼みがある」
首切り役人は赤い靴を膝に乗せると、真剣な眼差しでそう切り出しました。
「どうやら俺は、治る見込みのない重い病を患っているらしい」
これまでも時折の鈍痛に苦しんでいた彼の身体は、この所、夜に眠れないほどの痛みを訴えておりました。そんな彼の体を詳しく調べた医者は気の毒そうに、首切り役人の命がもうそれほど長くはないことを告げました。
長い間医者に診せることをしていなかったために、ただでさえ治る見込みの薄かった彼の病はすっかり進行して、もはや手の施しようがなくなってしまっているというのです。
「俺が死ぬのは仕方がない。仕事とはいえ、何人もの首をはねた首切り役人だ。それも報いだと思って諦めることにする。だがな、心配なのはただ一つ。お前のことだ」
首切り役人は、そっと赤い靴をその指で撫でました。
「俺はやがて動くこともままならなくなるらしい。そんな時、お前がまたふらりと姿を消して戻ってこなくなったら、俺はきっと気が狂う。誰か心無い人間に捕まって見世物にされてしまっていないかと、野犬に噛まれたり穴に落ちたりして動けなくなってしまってはいないかと。だが、そう思っても俺はお前を探しに行くことができないんだ」
首切り役人は、町で買ってきた大きな鳥籠を指差してこう言いいました。
「俺が死ぬまでには、必ず出すと約束する。だからどうか、それまでこの中に、俺の傍にいてくれないか?」
赤い靴は、嫌だと言うようにふるふると震えます。そしてそのままどこかに行ってしまおうとする足首を、首切り役人は慌てて両手で捕まえました。
「頼む。どうか頼むっ。お願いだ!」
首切り役人は頭を下げ、必死に頼み込みます。
赤い靴は彼の手の中でじたばたと暴れていましたが、やがて大人しくなりました。
首切り役人は赤い靴を、そっと鳥籠の中に入れ、自分のベッドの脇に吊るしました。鳥とは違い、歌うことのない赤い靴は、そうしているとまるで置物のように静かです。
しばらく赤い靴は、拗ねたように彼に踵を向けておりました。
しかしやがて彼が、毎晩体の痛みで苦しむようになると、気遣うように首切り役人側の鳥籠の端ぎりぎりまで近付き、寄り添うようになりました。
昼間、首切り役人が起きているときには、元気付けるように楽しげに鳥籠の中で足拍子を踏みました。
彼も毎日という訳には行かなくなりましたが、それでも動く気力がある限りは、赤い靴を磨き、白い足を布で清めました。
それは、以前の騒々しい賑やかさとは到底比べ物になりませんが、それでも静かで穏やかな、暖かい日々でした。
けれどやはり、そんな毎日は長くは続きませんでした。
病ですっかり体の弱った首切り役人は、もはやベッドから身体を起こすことすらままならなくなってしまっておりました。
時折彼の様子を診に来てくれた町の医者は、何度も町へ移って療養するように勧めましたが、彼はそれを頑なに断り続けていました。そのため、医者もやがて、痛みを抑えるための薬だけをたっぷり渡して、それきり彼の元へやってくることを止めてしまいました。
たった一人でベッドに横になっていた首切り役人は、最後の力を振り絞ると、薬を飲んでもなお苦しいほどに痛む身体を押して、起き上がりました。
扉を開き、そして彼のベッドの横に吊るされていた鳥籠の鍵を外します。
彼は倒れるようにベッドに戻り、横になると、鳥籠を見上げて言いました。
「どうやら俺はここまでのようだ。もう鳥籠にいる必要はない。どこでも、好きな所に行くといい」
彼はどうにかそう言い切ると、目を閉じます。
目を閉じた彼の耳に、こつんと靴底が床を叩く音が聞こえました。赤い靴が鳥籠から飛び降りた音でした。
目を瞑ったまま、遠ざかる足音に耳を澄まそうと思っていた首切り役人でしたが、いつまでたってもその音は聞こえてきません。それどころか、彼の枕元で何かが動く気配があります。
首切り役人は重い瞼を開き、そしてそれに目を留めると、ぼろぼろと涙を溢れさせました。
「そうか……。お前は最後まで、こんな罪深い俺と……一緒に居てくれるのか」
赤い靴は彼の枕元で、爪先を揃えて佇んでいます。
彼は弱々しい手で、赤い靴を引き寄せるとかさかさに乾いてひび割れた唇を、白くて細い華奢な足首に押し付けました。
「――している、カーレン。美しい、…俺の……赤い……」
暖かく、すべらかな足首に唇を触れさせたまま、首切り役人は途切れがちな掠れる声で囁きます。
首切り役人は、視界が霞み、暗くなり、そして何も分からなくなってしまうまでずっと、赤い靴を見つめ続けておりました。
※ ※ ※
お役所から遣わされた若いお役人さんが、日記のページを捲ろうとした時、背後でかたんと音がしました。
驚いて振り返った若いお役人さんは、驚きのあまり大きな悲鳴を上げてしまいました。鳥籠の中から飛び出した赤い靴が、踊るような足取りで自分に向かってくるのです。
それはあまりに恐ろしく、矢も盾も堪らなくなったお役人さんは日記を放り出すと一目散に逃げ出し、それっきり戻ってきませんでした。
赤い靴もまた、そのまま羽根のような軽やかな足捌きで家を出て行き、踊りながらどこかへ消えていきました。
残された家の中で、床に落ちた日記のページが一枚外れ、ひらりと床を滑っていきます。
しかし、それを読む人はもはやどこにもおりません。
それからさらに数年が経ち、廃墟になった首切り役人の家は、ある激しい嵐の晩に崩れて、荒野の一部になりました。
赤い靴がはたしてどこへ行ったのか。それは誰も知りません。
・
・
・
『――日用品を買いに街に出た。
俺は不吉な首切り役人だから、街に出ると道行く人はいつだって嫌な顔をする。
俺もそれを見るのはいい気分では無いので、必要なものを手に入れたらすぐに町を出るつもりだった。
だけど今日は我知らず足を止めてしまうことがあった。
それは靴屋の前。老婆に連れられた一人の少女が靴を選んでいた。
真っ赤に光る綺麗な靴を手にしたときの少女の顔。
憧れと嬉しさできらきらと輝いていた顔をふいに覗き見てしまった時に走った衝撃を、なんと言えばいいのだろう。
だけど俺は不吉な首切り役人だ。
少女が自分と知り合える可能性など、万に一つも無い。
この胸に抱いた感情など、きっと単なる気の迷いに過ぎないのだ。』
――誰にも読まれることのなかった、とある首切り役人の日記より。
<終>
0
この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説

ぼくのだいじなヒーラー
もちっぱち
絵本
台所でお母さんと喧嘩した。
遊んでほしくて駄々をこねただけなのに
怖い顔で怒っていたお母さん。
そんな時、不思議な空間に包まれてふわりと気持ちが軽くなった。
癒される謎の生き物に会えたゆうくんは楽しくなった。
お子様向けの作品です
ひらがな表記です。
ぜひ読んでみてください。
イラスト:ChatGPT(OpenAI)生成

緑色の友達
石河 翠
児童書・童話
むかしむかしあるところに、大きな森に囲まれた小さな村がありました。そこに住む女の子ララは、祭りの前日に不思議な男の子に出会います。ところが男の子にはある秘密があったのです……。
こちらは小説家になろうにも投稿しております。
表紙は、貴様 二太郎様に描いて頂きました。

青色のマグカップ
紅夢
児童書・童話
毎月の第一日曜日に開かれる蚤の市――“カーブーツセール”を練り歩くのが趣味の『私』は毎月必ずマグカップだけを見て歩く老人と知り合う。
彼はある思い出のマグカップを探していると話すが……
薄れていく“思い出”という宝物のお話。

童話絵本版 アリとキリギリス∞(インフィニティ)
カワカツ
絵本
その夜……僕は死んだ……
誰もいない野原のステージの上で……
アリの子「アントン」とキリギリスの「ギリィ」が奏でる 少し切ない ある野原の物語 ———
全16話+エピローグで紡ぐ「小さないのちの世界」を、どうぞお楽しみ下さい。
※高学年〜大人向き

不幸でしあわせな子どもたち 「しあわせのふうせん」
山口かずなり
絵本
小説 不幸でしあわせな子どもたち
スピンオフ作品
・
ウルが友だちのメロウからもらったのは、
緑色のふうせん
だけどウルにとっては、いらないもの
いらないものは、誰かにとっては、
ほしいもの。
だけど、気づいて
ふうせんの正体に‥。

ナナの初めてのお料理
いぬぬっこ
児童書・童話
ナナは七歳の女の子。
ある日、ナナはお母さんが仕事から帰ってくるのを待っていました。
けれど、お母さんが帰ってくる前に、ナナのお腹はペコペコになってしまいました。
もう我慢できそうにありません。
だというのに、冷蔵庫の中には、すぐ食べれるものがありません。
ーーそうだ、お母さんのマネをして、自分で作ろう!
ナナは、初めて自分一人で料理をすることを決めたのでした。
これは、ある日のナナのお留守番の様子です。
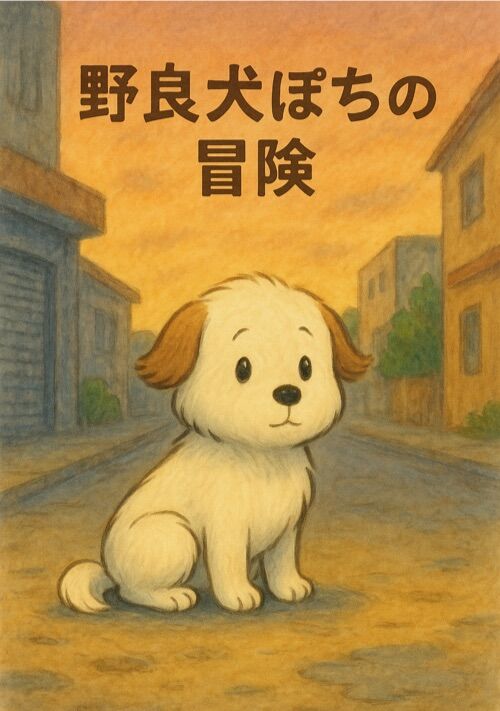
野良犬ぽちの冒険
KAORUwithAI
児童書・童話
――ぼくの名前、まだおぼえてる?
ぽちは、むかし だれかに かわいがられていた犬。
だけど、ひっこしの日に うっかり わすれられてしまって、
気がついたら、ひとりぼっちの「のらいぬ」に なっていた。
やさしい人もいれば、こわい人もいる。
あめの日も、さむい夜も、ぽちは がんばって生きていく。
それでも、ぽちは 思っている。
──また だれかが「ぽち」ってよんでくれる日が、くるんじゃないかって。
すこし さみしくて、すこし あたたかい、
のらいぬ・ぽちの ぼうけんが はじまります。

ノースキャンプの見張り台
こいちろう
児童書・童話
時代劇で見かけるような、古めかしい木づくりの橋。それを渡ると、向こう岸にノースキャンプがある。アーミーグリーンの北門と、その傍の監視塔。まるで映画村のセットだ。
進駐軍のキャンプ跡。周りを鉄さびた有刺鉄線に囲まれた、まるで要塞みたいな町だった。進駐軍が去ってからは住宅地になって、たくさんの子どもが暮らしていた。
赤茶色にさび付いた監視塔。その下に広がる広っぱは、子どもたちの最高の遊び場だ。見張っているのか、見守っているのか、鉄塔の、あのてっぺんから、いつも誰かに見られているんじゃないか?ユーイチはいつもそんな風に感じていた。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















