44 / 71
44【亜楼+海斗Diary】まちがい
しおりを挟む
終業時間を過ぎてすっかり静けさに包まれている『Studio Coolish』のガラス張りのドアの前で、海斗は大きく深呼吸していた。学校から直接ここにやって来た制服のままの海斗は、部で揃えたいつものバッグをしっかりと脇に抱え込むと、また戦地にでも赴くような緊張した面持ちで例のごとく身を潜めながら息を整えている。ここをこっそりと訪れるのも、なんだか慣れてきてしまった。
亜楼の真意を、もう今日で確かめようと思っていた。眞空と冬夜に背中を押されたのもあるが、否定を恐れて逃げ回ってばかりでは本当にどこにも進めずに終わってしまう気がして、なんとか心を持ち直した。どんなことでも乗り越えてみせると誓った恋のはじまりをしっかりと胸に戻し、自分はただまっすぐに突き進むことだけが取り柄なのだと自覚し直す。元々、恋愛対象として見ることは100%ないと言われていた恋だ。否定されてしまったら一旦は最高に落ち込んで、そのあとまた何度だって起き上がればいい。この際だからものわかりがいいのか悪いのかわからない涼にも立ち会ってもらおうと、今日はわざと平日を選んで事務所を訪れていた。
こうなったら亜楼が言い逃れできねぇように問い詰めて、あの人の前でほんとのこと吐かせてやる! この前の嘘だったって言われても、二人の前で亜楼が好きだって目一杯わめき散らしてやる! それがきっと、オレらしいやり方なんだろ?
息を整えて覚悟を決めた海斗は、まずは二人以外の他の社員がいないかを確認するために、前回同様数センチだけガラス戸を開けて中の様子をうかがった。気づかれないようにしゃがみ込み、扉の横に置いてある背の高い観葉植物に低くした身を隠す。静かにのぞき込むと他の社員は見当たらず、予定通り亜楼と涼しかいなかった。社長のデスクの前で、ぼんやりと立ち尽くしている亜楼が見える。
「……淋しいの?」
自分のデスクの前から動こうとしない亜楼に、座ってパソコンを見つめたままの涼が問いかける。
「キミの家、大家族で賑やかでしょう? 絶対淋しくないよ、早く帰ったら?」
「帰るのが、……怖ぇんだ」
また今夜も弟に避けられて、それでもどこかで海斗が部屋のドアをノックするのを期待してしまうのかと思ったら、帰るための足は信じられないほど重くなった。都合が良すぎて反吐が出る。今までの最低な行為のツケが回ってきたのだと、亜楼にもそれはわかっていた。
「またそれ? いつからボクは迷子のお守り係になったのかな」
やれやれと、涼がゆっくりとディスプレイから視線を上げた。どこにも帰れずに彷徨っている大きな子供を、あやすように。
「どうしてほしいの? 慰めればいい?」
「……」
その無言を肯定と受け取った涼が、仕方ないなぁと、ゆっくりと席を立つ。
「慰め方、これしか知らないんだけど、いいの?」
涼はデスク越しに亜楼の頬へと手を伸ばし、そっと触れた。そのまま自身の顔を近づけていき、直前で傾け、口唇に口唇をつけようとする。
──っ。
また目の当たりにしてしまったと、その様子を海斗は物陰で縮こまりながら眺めていた。どういう感情を持つのが正解なのか、今はわからない。怒り、嫉妬、哀しみ、絶望、すべて正解の気もしてくるし、そのどれにも属さない気もしてくる。
『……海斗、顔見たい、見せて……』
『好きだ……』
あれは幻だったんだよと、とうとう答えを言い渡された気がした。しばらく兄と向き合わず、逃げてきた罰だ。真実を吐かせに来たのに。好きだとわめき散らしに来たのに。……何度打ちのめされたって起き上がれる気はしていたのに、こんなのを見せられたら、やはりもう無理だと思った。
見ていられないと、この場から離れようと立ち上がった海斗がよろめいて、脇に抱えていた重たい部活のバッグが横の観葉植物に当たった。大きな音を立てて、背の高い植物の鉢が動く。
「!?」
するはずのない物音に敏感に反応した亜楼が、キスの寸前でガラス戸の方に顔を向けた。
「……忘れ物か?」
社員が忘れ物でも取りに戻ってきたのかと思ったが、中に入ってくる気配がない。不審に思った亜楼は自分の頬に添えられていた涼の手をそっと剥がすと、ドアの方へと慎重に足を運んだ。
海斗が、やば……と思ってもう一度しゃがんで隠れようとしたときにはもう遅く、ガラス戸は亜楼によって無情にも大きく開かれてしまった。
「──!」
「──!」
観葉植物の横でしゃがんでいる海斗を亜楼が見下ろし、ガラス戸の取っ手に手を置いたまま硬直している亜楼を海斗が見上げる。互いに、凍る。
「!? なんで、おまえ、こんなとこにいんだよ……何しに来やがった……」
声はわかりやすく震えた。亜楼は血の気を一瞬にしてなくし、何が起こったかよくわからないと、頭の中が真っ白になる感覚に苦しむ。理解が追いつかない。
……待ってるときは全然来ねぇくせに、こんなときだけタイミングよく現れやがって……まじで、なんで……クソッ……。
「……今の、……見た、のか……?」
涼と、しようとしていたことを。この期に及んで涼に甘えてしまった、情けない自分を。海斗は見たというのか。
「……っ」
海斗が無言で、口唇を固く引き結んだ。悪いのは盗み見をしていた自分の方なのに、兄の恐ろしく冷たい眼に怯え、思わず涙が落ちそうになる。
亜楼もどんな顔をしたらいいのかわからずに、苛立ちを彷徨わせながら、しゃがんでいる海斗をただ見下ろした。
「だから言っただろ、俺にヘンな夢見んじゃねぇって」
いつか吐き捨てるように言ってしまった言葉を、まったくその通りじゃねぇかと亜楼が皮肉として呼び戻す。
「俺は、こういうやつなんだよ」
だらしなくて、淋しがりで、大切なものが何かもわからない最低な、兄。それなのに変わらず澄んだ目をまっすぐに向けてくる海斗の視線に耐えられなくなり、亜楼がつい心にもないことを口走る。
「……えろいことしてぇだけなら、……おまえも混ざるか?」
「──っ!?」
亜楼としてはこの緊迫した空気を崩すための軽い冗談のつもりで、ふざけんなと海斗がいつものようにわぁわぁ騒ぎ出すかと思っていた。情けない姿をなかったことにしたくて、それ以上の下劣な言葉で塗り潰そうとした。
「……なんだよそれ……バカにしてんの……」
海斗の声も震えていた。騒ぎ出すどころか、みるみる顔を赤くさせて目のふちに涙を溜めたのを見てはっとし、最低なことを言ってしまったと亜楼が慌てて口元を手で押さえる。
「いや、海斗、今のは……」
「……んなこと言うおまえ、……まじで……まじでサイテーだよ!」
亜楼と涼が触れ合っている場面を目にしたときよりもその心ないひと言にひどく傷つけられた海斗は、これ以上は本当にこの場にいられなくなって、ぼろぼろと泣き出しそうに歪んだ顔だけを見せて立ち上がった。そのまま兄に背を向けて走り出す。バタバタと豪快に階段を駆け下りる海斗の足音が、静まり返った事務所に冷たく響き渡った。
亜楼は自分が配慮ない言葉を発してしまったことにも、海斗が去り際に残した悲痛に揺れる顔にもひどく衝撃を受けて、呆然と立ち尽くすことしかできなかった。あんなに待っていたのに。やっと来てくれたのに。海斗の前では、いつも何ひとつうまくいかない。
「キミは本当におバカさんだねぇ」
凍っている亜楼の背中に、涼が大きなため息とともに声を掛けた。おそるおそる振り返った部下にやれやれと大袈裟な手振りを見せるが、いつものように物事を愉快そうに捉えているような涼ではなく、本気で亜楼に幻滅しているような冷酷な口調だった。
「ボクはね、そういうおバカさんは大キライなんだよ」
「……」
「だから、そんなバカはボクの方から願い下げだ。ボクの方から振ってあげる。もう亜楼とは寝ないよ。もう、おしまい」
「……りょ、う……さん?」
なんだそれ……と、亜楼はただ唖然と上司の名を弱々しく口にするしかない。
「ボクはね、賢い人がスキなの。キミみたいに、正しいものを正しいと認めてその手に選び取れないようなバカは、寝る価値もないってこと」
「……っ」
「六年? 七年くらい? 楽しかったよ、ありがとう」
淡々と終わりを独断する涼に、けれども亜楼は必死になってそれに抗うことをしなかった。それは多分、すべての答え。
「っていうか、彼、追いかけないの?」
「……」
目を伏せて未だ情けなく固まっている亜楼に、
「追いかけろよバカが!」
と、涼の怒声が浴びせられた。はっとして亜楼が顔を上げると、そこには端正な鋭い猫目をキッと吊り上げて本気で怒っている涼がいた。大丈夫、という魔法の言葉でいつもやさしく自分を導いてくれた涼にこんな風に叱られるのは初めてのことで、亜楼はしばらく呆気に取られていた。仕事で大きなミスをしたときも、上手に抱けなかったときも、叱られたことはなかったのに。
……そうか、叱られるってことは、まちがってるってことか。正しいものを正しいと認めて、その手に選び取る……。俺が正しいと認めなきゃなんねぇもの。この手で選び取りてぇもの。……そっか……そういうことか……。
亜楼はてのひらを見つめ、そしてぎゅっと握りしめて拳を作った。八年前に弟の手をつかんだこの手で、もう一度、まちがうことなく選び取るために。
亜楼は電池交換を終えたように突然俊敏に動き出すと、バタバタとかばんやノートパソコンや書類を引っつかんで帰り支度を始めた。その背中を、涼がいつもの慈愛に満ちた顔に戻って見守っている。
「……涼さんごめんありがとうあいしてる!」
早口にそう告げ、亜楼は海斗を追いかけるために駆け出した。大きな音を立てて豪快に階段を駆け下りる音が海斗のそれとそっくりで、さすがは兄弟と涼は感心してくすっと笑う。
「うまくいくといいね」
鼻歌なんかを口ずさみながら、涼は社長のデスクに戻って優雅に仕事を再開した。
亜楼の真意を、もう今日で確かめようと思っていた。眞空と冬夜に背中を押されたのもあるが、否定を恐れて逃げ回ってばかりでは本当にどこにも進めずに終わってしまう気がして、なんとか心を持ち直した。どんなことでも乗り越えてみせると誓った恋のはじまりをしっかりと胸に戻し、自分はただまっすぐに突き進むことだけが取り柄なのだと自覚し直す。元々、恋愛対象として見ることは100%ないと言われていた恋だ。否定されてしまったら一旦は最高に落ち込んで、そのあとまた何度だって起き上がればいい。この際だからものわかりがいいのか悪いのかわからない涼にも立ち会ってもらおうと、今日はわざと平日を選んで事務所を訪れていた。
こうなったら亜楼が言い逃れできねぇように問い詰めて、あの人の前でほんとのこと吐かせてやる! この前の嘘だったって言われても、二人の前で亜楼が好きだって目一杯わめき散らしてやる! それがきっと、オレらしいやり方なんだろ?
息を整えて覚悟を決めた海斗は、まずは二人以外の他の社員がいないかを確認するために、前回同様数センチだけガラス戸を開けて中の様子をうかがった。気づかれないようにしゃがみ込み、扉の横に置いてある背の高い観葉植物に低くした身を隠す。静かにのぞき込むと他の社員は見当たらず、予定通り亜楼と涼しかいなかった。社長のデスクの前で、ぼんやりと立ち尽くしている亜楼が見える。
「……淋しいの?」
自分のデスクの前から動こうとしない亜楼に、座ってパソコンを見つめたままの涼が問いかける。
「キミの家、大家族で賑やかでしょう? 絶対淋しくないよ、早く帰ったら?」
「帰るのが、……怖ぇんだ」
また今夜も弟に避けられて、それでもどこかで海斗が部屋のドアをノックするのを期待してしまうのかと思ったら、帰るための足は信じられないほど重くなった。都合が良すぎて反吐が出る。今までの最低な行為のツケが回ってきたのだと、亜楼にもそれはわかっていた。
「またそれ? いつからボクは迷子のお守り係になったのかな」
やれやれと、涼がゆっくりとディスプレイから視線を上げた。どこにも帰れずに彷徨っている大きな子供を、あやすように。
「どうしてほしいの? 慰めればいい?」
「……」
その無言を肯定と受け取った涼が、仕方ないなぁと、ゆっくりと席を立つ。
「慰め方、これしか知らないんだけど、いいの?」
涼はデスク越しに亜楼の頬へと手を伸ばし、そっと触れた。そのまま自身の顔を近づけていき、直前で傾け、口唇に口唇をつけようとする。
──っ。
また目の当たりにしてしまったと、その様子を海斗は物陰で縮こまりながら眺めていた。どういう感情を持つのが正解なのか、今はわからない。怒り、嫉妬、哀しみ、絶望、すべて正解の気もしてくるし、そのどれにも属さない気もしてくる。
『……海斗、顔見たい、見せて……』
『好きだ……』
あれは幻だったんだよと、とうとう答えを言い渡された気がした。しばらく兄と向き合わず、逃げてきた罰だ。真実を吐かせに来たのに。好きだとわめき散らしに来たのに。……何度打ちのめされたって起き上がれる気はしていたのに、こんなのを見せられたら、やはりもう無理だと思った。
見ていられないと、この場から離れようと立ち上がった海斗がよろめいて、脇に抱えていた重たい部活のバッグが横の観葉植物に当たった。大きな音を立てて、背の高い植物の鉢が動く。
「!?」
するはずのない物音に敏感に反応した亜楼が、キスの寸前でガラス戸の方に顔を向けた。
「……忘れ物か?」
社員が忘れ物でも取りに戻ってきたのかと思ったが、中に入ってくる気配がない。不審に思った亜楼は自分の頬に添えられていた涼の手をそっと剥がすと、ドアの方へと慎重に足を運んだ。
海斗が、やば……と思ってもう一度しゃがんで隠れようとしたときにはもう遅く、ガラス戸は亜楼によって無情にも大きく開かれてしまった。
「──!」
「──!」
観葉植物の横でしゃがんでいる海斗を亜楼が見下ろし、ガラス戸の取っ手に手を置いたまま硬直している亜楼を海斗が見上げる。互いに、凍る。
「!? なんで、おまえ、こんなとこにいんだよ……何しに来やがった……」
声はわかりやすく震えた。亜楼は血の気を一瞬にしてなくし、何が起こったかよくわからないと、頭の中が真っ白になる感覚に苦しむ。理解が追いつかない。
……待ってるときは全然来ねぇくせに、こんなときだけタイミングよく現れやがって……まじで、なんで……クソッ……。
「……今の、……見た、のか……?」
涼と、しようとしていたことを。この期に及んで涼に甘えてしまった、情けない自分を。海斗は見たというのか。
「……っ」
海斗が無言で、口唇を固く引き結んだ。悪いのは盗み見をしていた自分の方なのに、兄の恐ろしく冷たい眼に怯え、思わず涙が落ちそうになる。
亜楼もどんな顔をしたらいいのかわからずに、苛立ちを彷徨わせながら、しゃがんでいる海斗をただ見下ろした。
「だから言っただろ、俺にヘンな夢見んじゃねぇって」
いつか吐き捨てるように言ってしまった言葉を、まったくその通りじゃねぇかと亜楼が皮肉として呼び戻す。
「俺は、こういうやつなんだよ」
だらしなくて、淋しがりで、大切なものが何かもわからない最低な、兄。それなのに変わらず澄んだ目をまっすぐに向けてくる海斗の視線に耐えられなくなり、亜楼がつい心にもないことを口走る。
「……えろいことしてぇだけなら、……おまえも混ざるか?」
「──っ!?」
亜楼としてはこの緊迫した空気を崩すための軽い冗談のつもりで、ふざけんなと海斗がいつものようにわぁわぁ騒ぎ出すかと思っていた。情けない姿をなかったことにしたくて、それ以上の下劣な言葉で塗り潰そうとした。
「……なんだよそれ……バカにしてんの……」
海斗の声も震えていた。騒ぎ出すどころか、みるみる顔を赤くさせて目のふちに涙を溜めたのを見てはっとし、最低なことを言ってしまったと亜楼が慌てて口元を手で押さえる。
「いや、海斗、今のは……」
「……んなこと言うおまえ、……まじで……まじでサイテーだよ!」
亜楼と涼が触れ合っている場面を目にしたときよりもその心ないひと言にひどく傷つけられた海斗は、これ以上は本当にこの場にいられなくなって、ぼろぼろと泣き出しそうに歪んだ顔だけを見せて立ち上がった。そのまま兄に背を向けて走り出す。バタバタと豪快に階段を駆け下りる海斗の足音が、静まり返った事務所に冷たく響き渡った。
亜楼は自分が配慮ない言葉を発してしまったことにも、海斗が去り際に残した悲痛に揺れる顔にもひどく衝撃を受けて、呆然と立ち尽くすことしかできなかった。あんなに待っていたのに。やっと来てくれたのに。海斗の前では、いつも何ひとつうまくいかない。
「キミは本当におバカさんだねぇ」
凍っている亜楼の背中に、涼が大きなため息とともに声を掛けた。おそるおそる振り返った部下にやれやれと大袈裟な手振りを見せるが、いつものように物事を愉快そうに捉えているような涼ではなく、本気で亜楼に幻滅しているような冷酷な口調だった。
「ボクはね、そういうおバカさんは大キライなんだよ」
「……」
「だから、そんなバカはボクの方から願い下げだ。ボクの方から振ってあげる。もう亜楼とは寝ないよ。もう、おしまい」
「……りょ、う……さん?」
なんだそれ……と、亜楼はただ唖然と上司の名を弱々しく口にするしかない。
「ボクはね、賢い人がスキなの。キミみたいに、正しいものを正しいと認めてその手に選び取れないようなバカは、寝る価値もないってこと」
「……っ」
「六年? 七年くらい? 楽しかったよ、ありがとう」
淡々と終わりを独断する涼に、けれども亜楼は必死になってそれに抗うことをしなかった。それは多分、すべての答え。
「っていうか、彼、追いかけないの?」
「……」
目を伏せて未だ情けなく固まっている亜楼に、
「追いかけろよバカが!」
と、涼の怒声が浴びせられた。はっとして亜楼が顔を上げると、そこには端正な鋭い猫目をキッと吊り上げて本気で怒っている涼がいた。大丈夫、という魔法の言葉でいつもやさしく自分を導いてくれた涼にこんな風に叱られるのは初めてのことで、亜楼はしばらく呆気に取られていた。仕事で大きなミスをしたときも、上手に抱けなかったときも、叱られたことはなかったのに。
……そうか、叱られるってことは、まちがってるってことか。正しいものを正しいと認めて、その手に選び取る……。俺が正しいと認めなきゃなんねぇもの。この手で選び取りてぇもの。……そっか……そういうことか……。
亜楼はてのひらを見つめ、そしてぎゅっと握りしめて拳を作った。八年前に弟の手をつかんだこの手で、もう一度、まちがうことなく選び取るために。
亜楼は電池交換を終えたように突然俊敏に動き出すと、バタバタとかばんやノートパソコンや書類を引っつかんで帰り支度を始めた。その背中を、涼がいつもの慈愛に満ちた顔に戻って見守っている。
「……涼さんごめんありがとうあいしてる!」
早口にそう告げ、亜楼は海斗を追いかけるために駆け出した。大きな音を立てて豪快に階段を駆け下りる音が海斗のそれとそっくりで、さすがは兄弟と涼は感心してくすっと笑う。
「うまくいくといいね」
鼻歌なんかを口ずさみながら、涼は社長のデスクに戻って優雅に仕事を再開した。
12
あなたにおすすめの小説
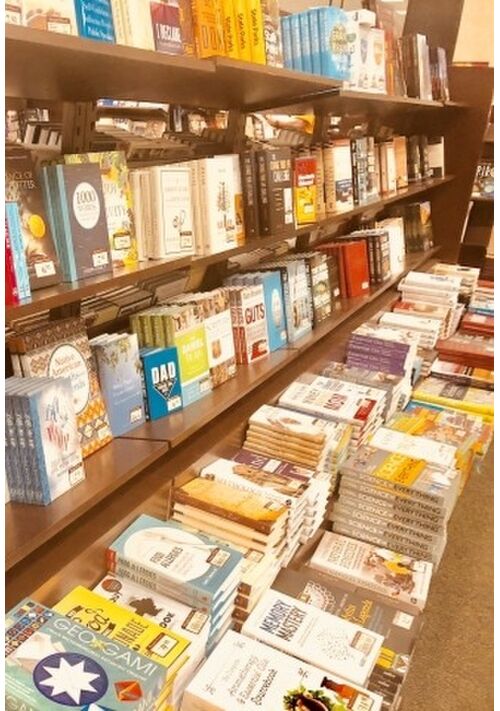
【完結】言えない言葉
未希かずは(Miki)
BL
双子の弟・水瀬碧依は、明るい兄・翼と比べられ、自信がない引っ込み思案な大学生。
同じゼミの気さくで眩しい如月大和に密かに恋するが、話しかける勇気はない。
ある日、碧依は兄になりすまし、本屋のバイトで大和に近づく大胆な計画を立てる。
兄の笑顔で大和と心を通わせる碧依だが、嘘の自分に葛藤し……。
すれ違いを経て本当の想いを伝える、切なく甘い青春BLストーリー。
第1回青春BLカップ参加作品です。
1章 「出会い」が長くなってしまったので、前後編に分けました。
2章、3章も長くなってしまって、分けました。碧依の恋心を丁寧に書き直しました。(2025/9/2 18:40)

夢の続きの話をしよう
木原あざみ
BL
歯止めのきかなくなる前に離れようと思った。
隣になんていたくないと思った。
**
サッカー選手×大学生。すれ違い過多の両方向片思いなお話です。他サイトにて完結済みの作品を転載しています。本編総文字数25万字強。
表紙は同人誌にした際に木久劇美和さまに描いていただいたものを使用しています(※こちらに載せている本文は同人誌用に改稿する前のものになります)。

【完】君に届かない声
未希かずは(Miki)
BL
内気で友達の少ない高校生・花森眞琴は、優しくて完璧な幼なじみの長谷川匠海に密かな恋心を抱いていた。
ある日、匠海が誰かを「そばで守りたい」と話すのを耳にした眞琴。匠海の幸せのために身を引こうと、クラスの人気者・和馬に偽の恋人役を頼むが…。
すれ違う高校生二人の不器用な恋のお話です。
執着囲い込み☓健気。ハピエンです。

告白ごっこ
みなみ ゆうき
BL
ある事情から極力目立たず地味にひっそりと学園生活を送っていた瑠衣(るい)。
ある日偶然に自分をターゲットに告白という名の罰ゲームが行われることを知ってしまう。それを実行することになったのは学園の人気者で同級生の昴流(すばる)。
更に1ヶ月以内に昴流が瑠衣を口説き落とし好きだと言わせることが出来るかということを新しい賭けにしようとしている事に憤りを覚えた瑠衣は一計を案じ、自分の方から先に告白をし、その直後に全てを知っていると種明かしをすることで、早々に馬鹿げたゲームに決着をつけてやろうと考える。しかし、この告白が原因で事態は瑠衣の想定とは違った方向に動きだし……。
テンプレの罰ゲーム告白ものです。
表紙イラストは、かさしま様より描いていただきました!
ムーンライトノベルズでも同時公開。


男子寮のベットの軋む音
なる
BL
ある大学に男子寮が存在した。
そこでは、思春期の男達が住んでおり先輩と後輩からなる相部屋制度。
ある一室からは夜な夜なベットの軋む音が聞こえる。
女子禁制の禁断の場所。

シスルの花束を
碧月 晶
BL
年下俺様モデル×年上訳あり青年
~人物紹介~
○氷室 三門(ひむろ みかど)
・攻め(主人公)
・23歳、身長178cm
・モデル
・俺様な性格、短気
・訳あって、雨月の所に転がり込んだ
○寒河江 雨月(さがえ うげつ)
・受け
・26歳、身長170cm
・常に無表情で、人形のように顔が整っている
・童顔
※作中に英会話が出てきますが、翻訳アプリで訳したため正しいとは限りません。
※濡れ場があるシーンはタイトルに*マークが付きます。
※基本、三門視点で進みます。
※表紙絵は作者が生成AIで試しに作ってみたものです。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















