2 / 15
2.出会いⅡ
しおりを挟む
今年十一歳になるアルバートは、同年代の子どもに比べて随分と小柄だ。食事量が少ないことも原因だが、なにより血を摂取していないことで、成長が九歳の頃で止まっているからだろう。
幼少期は乳児の頃に摂取していた母乳が糧となり、成長することが可能らしいが、乳歯が生え変わる頃合いで、蓄えていた栄養素が底を尽きる。そのため、歯が生え変わったタイミングで、自力で血を摂取する術を学ぶのだそうだ。
いっそグラスにでも血を注いでもらい、それを飲めばいいのではと思うのだが、吸血行為は伴侶となる相手への求愛行動でもあり、ある条件の元で噛みつくことで、他種族の者でも吸血鬼の子を身籠ることができるのだという。
人間族である侯爵夫人が吸血鬼の子を産めたのは、吸血行為という求愛行動があったからだ。
そのため、吸血鬼の子は幼い頃から自力で血を飲む行為を学び、繁殖行為の瞬間に、本能が剥き出しになるよう、訓練するのだというが──本当かどうかは知らない。
「……アルバート様」
「なに?」
「その、不躾なご質問で恐縮ですが、アルバート様は、血を飲むのがお嫌いなのですか?」
本当に不躾な質問だと思う。だが、今のままではアルバートは成長できない。
血自体を嫌っているのだとしたら、今の幼い姿のまま、生きていくことになる。いや、そもそも生きていけるのかすら疑問だ。
ましてやこの家庭環境では、この先どうなることか……考えただけでもゾッとする未来に、聞かずにはいられなかった。
「……嫌いじゃないよ」
どんな答えが返ってくるだろうとドキドキしたが、アルバートは素直に返事をしてくれた。
「そうなのですか?」
「うん……」
「それならば、なぜ血をお飲みにならないのでしょう? あ、好奇心から尋ねた訳ではございません。ただ、その、お体のためにもお飲みになられたほうがよろしいかと……」
踏み込んだ質問に、アルバートは黙り込んでしまった。流石に失礼が過ぎただろうかと慌てるも、余計に言い訳がましくなってしまい、言葉が続かない。
どうしたものかと考えを巡らせていると、紅い瞳がじっとこちらを見つめた。
「……あなたは、優しいね」
「いえ、ご無礼を申し上げました。申し訳ございません」
「謝らないでいいよ。……僕が血を飲めないのは、噛むのが怖いからだ」
「怖い……ですか?」
復唱するように同じ言葉を重ねれば、小さな頷きが返ってきた。
「それは、その……」
「……噛む時ってね、すごく強く噛まなきゃいけないの」
零れた一言が呼び水となったように、アルバートがポツリ、ポツリと胸の内を語った。
「本当に目一杯噛まないと、歯なんて刺さらない。思いっきり噛まないと、血なんて出ない……それが怖いんだ」
「……」
「それに、噛まれた人はきっとすごく痛い。痛いし、噛まれるのだって、すごく怖いと思う……僕は、痛いことも、怖いことも、したくない……」
「ですが、血が飲めないと叩かれるのは、アルバート様ですよ? アルバート様も、痛いのはお嫌でしょう?」
「……叩かれるのは、そんなに痛くないから平気だよ。人間と違って、僕の体は、頑丈だから……」
膝を抱え、縮こまるように身を小さくした少年が、合わせた膝の間に小さな本音を零していく。
「そんなに痛くない」と言っても、痛くない訳じゃない。平気な訳がない。
まして、以前は愛情を注いでくれていた両親に蔑まれ、罵られ、弟妹に嘲笑されることに、心が傷つかない訳がないではないか。
「……アルバート様のお気持ちは分かりました。ですが、今のままではアルバート様のお心が病んでしまいます。血を提供してくれる者も、痛みに対して相応の覚悟を持っているはずです。怖くなってしまうお気持ちは分かりますが、どうかご自身のためにも……どうされました?」
伏せてしまった顔を覗き込むように話し掛ければ、顔を上げたアルバートが、真ん丸な瞳でこちらを見つめた。
「あなたは、怒ったり、笑ったりしないんだね……」
「何にでしょう?」
「僕が、人を噛むのが、怖いってこと……」
「当然です。人を傷つけることを恐れるのも、相手の痛みに寄り添えるのも、アルバート様がお優しい方だからです。笑う者こそ、愚か者でしょう」
そう告げれば、大きく目を見開いたアルバートが、くしゃりと顔を歪めた。
「……やっぱり、あなたは優しいね。……でも、お外でそんなこと言ったらダメだよ? あなたが怒られちゃう」
ああ、本当にどうしてこんなに優しい子が、このように辛い目に遭わなければいけないのだろう。
彼を嘲笑い、吐き捨てるように怒りをぶつけているのは、他でもない彼の家族だ。
そしてその家族が高位貴族だからこそ、不用意な発言をしてはいけないと案じてくれる優しさに、また胸が締め付けられた。
だからだろうか。なんとかして、今の状況から、この優しい子を救えないかと思ってしまった。
ただの自己満足だと分かっている。善人ぶるつもりもない。それでも、この痛々しい少年を放っておけなかった。
「アルバート様、よろしければ、私の血をお飲みになりませんか?」
「え……?」
「これでも騎士ですから、多少の痛みには慣れております。アルバート様に噛みつかれることも、怖くありません。質の良い血かどうかという自信はありませんが……」
「まっ、まって! どうして、そんな、急に……」
「アルバート様に、これ以上傷ついてほしくないからです」
「……僕とお話しするの、初めてだよね?」
「そうですね」
「……なんで、そんなに優しくしてくれるの?」
「私がそうしたいからです」
本心だった。“ただそうしたかったから”、それ以上でも、それ以下でもなかった。
「……ありがとう。でも、もういいんだ。今更もう……」
その続きを、アルバートは口にしなかった。
ただ伏せられた瞳には、両親の愛情を求めることへの諦念がまざまざと浮かんでいて、なんともやるせない気持ちになった。
(でも……)
どちらにせよ、血を摂取しなければアルバートは成長できない。この際、噛むことができないという問題は二の次だ。
「アルバート様は、血がお嫌いな訳ではないのですよね」
「うん……」
「お飲みになられたことが?」
「ない、けど……でも、嫌いじゃ──何してるの!?」
上擦ったアルバートの声が耳に届く。それもそのはずだ。
おもむろに取り出した小型のナイフ。テオドールはその刃を自身の手の平の側面に当てると、滑らせるように刃を引いた。
直後、スッパリと切れたそこから鮮血が滲み、血の雫がポタリと地に垂れた。
「な、何して……」
「これならアルバート様が噛まなくとも、血をお飲みになられ──」
「そうじゃなくて! どうしてそんな痛いことするの!」
痛みを我がことのように嘆き、泣きそうな顔をするアルバートに、己の浅はかな行動を猛省する。
「……申し訳ございません。噛む必要がなければ、怖くないかと思ったのですが……」
「……どうして? どうして、僕のために、そこまでしてくれるの?」
「私が、そうしたかったからです」
声を震わせるアルバートに、先ほどと同じセリフを返せば、ルビーのような瞳が潤みを帯びて煌めいた。
「あ、その、勢いで切ってしまいましたが、これは私の勝手なお節介です。見知らぬ男の血を飲めと言われても怖いでしょうし、手段の一つとして、お心に留めていただければ……!」
気持ちが先走ってしまった行動に、また怖がらせてしまっただろうかと焦りが募る。
よくよく考えなくとも、初めて言葉を交わした男に「私の血を飲んでください」と言われるのも恐怖だろう。
鍛えた肉体と長身の体は、それだけで怖がられることもある。強面ではないと思うが……とそこまで考え、アルバートの整った顔立ちを思い出し、なんとも言えない罪悪感が生まれた。
今でこそ長い前髪で顔を隠しているアルバートだが、その下の顔は天使のように愛らしい美少年だ。そんな幼な子に対し、自身で切りつけた血の滴る左手を差し出し、「血を飲んでください」と強要する大男……
(……犯罪だ!!)
冷静になり、自身の行動のまずさを瞬時に理解する。
「申し訳ございません! お見苦しいものを──」
血の気が引くとはこういうことだろうか。
アルバートの前に差し出していた左手を隠すように腕を引こうとしたその瞬間、真っ白な細い手が伸びてきて、自身の無骨な手を痛いほど強く掴んだ。
突然のことに、驚愕から体を硬直させれば、血の滴る手の側面に柔らかな唇が触れ、濡れた舌先が傷口を舐め上げた。
「アルバート様!?」
アルバートの予想外の行動に、声が裏返る。だが、チュウッと可愛らしい音を立てて己の手に吸い付くアルバートはどこか必死で、掴まれた手を引くこともできなかった。
小さく柔らかな手に握り締められた指先はビクともせず、これが吸血鬼の力か……とおかしなところに感心しながら、遅れてハッとする。
「ア、アルバート様! ご無理をなさらないでくださいませ!」
「うぅんっ」
「っ……」
手に吸い付いたまま、ふるふると首を横に振るアルバート。その間も、小さな舌が傷口を開くように肉を舐め、溢れた血がアルバートの喉奥に消えていく。
時たま痛みが走るも、それを悟られぬよう、じっと耐えながら、懸命に血を求める子の邪魔をしないように、黙って彼の食事が終わるのを待った。
数分にも満たない短い時間が、途方もなく長く感じ始めた頃、チュッという小さなリップ音と共に、アルバートの唇が左手からゆっくりと離れていった。
薄い緊張から解放され、ホッと息を吐く。が、自身の手を掴んだままの小さな手は離れる気配もなく、黙り込んでしまったアルバートに不安が募った。
「アルバート様、大丈夫ですか? 具合を悪くされていませんか?」
今更ながらに、自身の血を飲ませてしまったことへの羞恥が押し寄せる。
それほど不健康な生活は送っている訳ではないが、自分の血が美味いとも到底思えない。
口に合わなかったらどうしよう、と動揺からおかしな心配をしていると、ゆっくりと顔を上げたアルバートの瞳が、真っ直ぐテオドールを見つめた。
「……大丈夫だよ。ありがとう、テオドール」
名を呼んでくれた──それが妙に嬉しくて、羞恥は気恥ずかしさに変わった。
「お体は、大丈夫ですか?」
「うん。……少しだけ、元気になった気がする」
「それは良うございました」
あのように少量の血で、変化など起きるはずがない。でも今は、アルバートの言葉を素直に受け止めた。
「あの、血は止まってるけど、傷口はそのままだから……」
「ええ、後ほど布を当てておきますね」
見れば、切れた傷口はそのままなのに、血は一滴も滲んでいなかった。すべて彼が飲んだのかと思うと不思議な感じだ。
そんなことを考えながら傷口を見つめていると、アルバートがそろそろと顔を上げた。
「あの……本当に、ありがとう」
「いえ、押し付けがましくなってしまい……」
「そっちじゃなくて……! そっちもだけど……その、心配してくれて、ありがとう」
白い頬を淡く染め、もじもじと言葉を紡ぐアルバートは本当に可愛らしく、父性がこれ以上ないほど擽られた。
「お元気になられたのであれば、なによりです」
「……あの、テオドール」
「はい。なんでしょう」
「……また、お話ししてくれる?」
「! ええ、喜んで」
「……ありがとう」
遠慮がちに、それでも繋がりを求めてくれるアルバートに、本心から言葉を返せば、花が綻ぶような可憐な笑みが返ってきた。
この愛らしい子が、もっと笑って過ごせるようになればいいのに──心から願った祈りは、数日後、思わぬ形で叶うことになった。
幼少期は乳児の頃に摂取していた母乳が糧となり、成長することが可能らしいが、乳歯が生え変わる頃合いで、蓄えていた栄養素が底を尽きる。そのため、歯が生え変わったタイミングで、自力で血を摂取する術を学ぶのだそうだ。
いっそグラスにでも血を注いでもらい、それを飲めばいいのではと思うのだが、吸血行為は伴侶となる相手への求愛行動でもあり、ある条件の元で噛みつくことで、他種族の者でも吸血鬼の子を身籠ることができるのだという。
人間族である侯爵夫人が吸血鬼の子を産めたのは、吸血行為という求愛行動があったからだ。
そのため、吸血鬼の子は幼い頃から自力で血を飲む行為を学び、繁殖行為の瞬間に、本能が剥き出しになるよう、訓練するのだというが──本当かどうかは知らない。
「……アルバート様」
「なに?」
「その、不躾なご質問で恐縮ですが、アルバート様は、血を飲むのがお嫌いなのですか?」
本当に不躾な質問だと思う。だが、今のままではアルバートは成長できない。
血自体を嫌っているのだとしたら、今の幼い姿のまま、生きていくことになる。いや、そもそも生きていけるのかすら疑問だ。
ましてやこの家庭環境では、この先どうなることか……考えただけでもゾッとする未来に、聞かずにはいられなかった。
「……嫌いじゃないよ」
どんな答えが返ってくるだろうとドキドキしたが、アルバートは素直に返事をしてくれた。
「そうなのですか?」
「うん……」
「それならば、なぜ血をお飲みにならないのでしょう? あ、好奇心から尋ねた訳ではございません。ただ、その、お体のためにもお飲みになられたほうがよろしいかと……」
踏み込んだ質問に、アルバートは黙り込んでしまった。流石に失礼が過ぎただろうかと慌てるも、余計に言い訳がましくなってしまい、言葉が続かない。
どうしたものかと考えを巡らせていると、紅い瞳がじっとこちらを見つめた。
「……あなたは、優しいね」
「いえ、ご無礼を申し上げました。申し訳ございません」
「謝らないでいいよ。……僕が血を飲めないのは、噛むのが怖いからだ」
「怖い……ですか?」
復唱するように同じ言葉を重ねれば、小さな頷きが返ってきた。
「それは、その……」
「……噛む時ってね、すごく強く噛まなきゃいけないの」
零れた一言が呼び水となったように、アルバートがポツリ、ポツリと胸の内を語った。
「本当に目一杯噛まないと、歯なんて刺さらない。思いっきり噛まないと、血なんて出ない……それが怖いんだ」
「……」
「それに、噛まれた人はきっとすごく痛い。痛いし、噛まれるのだって、すごく怖いと思う……僕は、痛いことも、怖いことも、したくない……」
「ですが、血が飲めないと叩かれるのは、アルバート様ですよ? アルバート様も、痛いのはお嫌でしょう?」
「……叩かれるのは、そんなに痛くないから平気だよ。人間と違って、僕の体は、頑丈だから……」
膝を抱え、縮こまるように身を小さくした少年が、合わせた膝の間に小さな本音を零していく。
「そんなに痛くない」と言っても、痛くない訳じゃない。平気な訳がない。
まして、以前は愛情を注いでくれていた両親に蔑まれ、罵られ、弟妹に嘲笑されることに、心が傷つかない訳がないではないか。
「……アルバート様のお気持ちは分かりました。ですが、今のままではアルバート様のお心が病んでしまいます。血を提供してくれる者も、痛みに対して相応の覚悟を持っているはずです。怖くなってしまうお気持ちは分かりますが、どうかご自身のためにも……どうされました?」
伏せてしまった顔を覗き込むように話し掛ければ、顔を上げたアルバートが、真ん丸な瞳でこちらを見つめた。
「あなたは、怒ったり、笑ったりしないんだね……」
「何にでしょう?」
「僕が、人を噛むのが、怖いってこと……」
「当然です。人を傷つけることを恐れるのも、相手の痛みに寄り添えるのも、アルバート様がお優しい方だからです。笑う者こそ、愚か者でしょう」
そう告げれば、大きく目を見開いたアルバートが、くしゃりと顔を歪めた。
「……やっぱり、あなたは優しいね。……でも、お外でそんなこと言ったらダメだよ? あなたが怒られちゃう」
ああ、本当にどうしてこんなに優しい子が、このように辛い目に遭わなければいけないのだろう。
彼を嘲笑い、吐き捨てるように怒りをぶつけているのは、他でもない彼の家族だ。
そしてその家族が高位貴族だからこそ、不用意な発言をしてはいけないと案じてくれる優しさに、また胸が締め付けられた。
だからだろうか。なんとかして、今の状況から、この優しい子を救えないかと思ってしまった。
ただの自己満足だと分かっている。善人ぶるつもりもない。それでも、この痛々しい少年を放っておけなかった。
「アルバート様、よろしければ、私の血をお飲みになりませんか?」
「え……?」
「これでも騎士ですから、多少の痛みには慣れております。アルバート様に噛みつかれることも、怖くありません。質の良い血かどうかという自信はありませんが……」
「まっ、まって! どうして、そんな、急に……」
「アルバート様に、これ以上傷ついてほしくないからです」
「……僕とお話しするの、初めてだよね?」
「そうですね」
「……なんで、そんなに優しくしてくれるの?」
「私がそうしたいからです」
本心だった。“ただそうしたかったから”、それ以上でも、それ以下でもなかった。
「……ありがとう。でも、もういいんだ。今更もう……」
その続きを、アルバートは口にしなかった。
ただ伏せられた瞳には、両親の愛情を求めることへの諦念がまざまざと浮かんでいて、なんともやるせない気持ちになった。
(でも……)
どちらにせよ、血を摂取しなければアルバートは成長できない。この際、噛むことができないという問題は二の次だ。
「アルバート様は、血がお嫌いな訳ではないのですよね」
「うん……」
「お飲みになられたことが?」
「ない、けど……でも、嫌いじゃ──何してるの!?」
上擦ったアルバートの声が耳に届く。それもそのはずだ。
おもむろに取り出した小型のナイフ。テオドールはその刃を自身の手の平の側面に当てると、滑らせるように刃を引いた。
直後、スッパリと切れたそこから鮮血が滲み、血の雫がポタリと地に垂れた。
「な、何して……」
「これならアルバート様が噛まなくとも、血をお飲みになられ──」
「そうじゃなくて! どうしてそんな痛いことするの!」
痛みを我がことのように嘆き、泣きそうな顔をするアルバートに、己の浅はかな行動を猛省する。
「……申し訳ございません。噛む必要がなければ、怖くないかと思ったのですが……」
「……どうして? どうして、僕のために、そこまでしてくれるの?」
「私が、そうしたかったからです」
声を震わせるアルバートに、先ほどと同じセリフを返せば、ルビーのような瞳が潤みを帯びて煌めいた。
「あ、その、勢いで切ってしまいましたが、これは私の勝手なお節介です。見知らぬ男の血を飲めと言われても怖いでしょうし、手段の一つとして、お心に留めていただければ……!」
気持ちが先走ってしまった行動に、また怖がらせてしまっただろうかと焦りが募る。
よくよく考えなくとも、初めて言葉を交わした男に「私の血を飲んでください」と言われるのも恐怖だろう。
鍛えた肉体と長身の体は、それだけで怖がられることもある。強面ではないと思うが……とそこまで考え、アルバートの整った顔立ちを思い出し、なんとも言えない罪悪感が生まれた。
今でこそ長い前髪で顔を隠しているアルバートだが、その下の顔は天使のように愛らしい美少年だ。そんな幼な子に対し、自身で切りつけた血の滴る左手を差し出し、「血を飲んでください」と強要する大男……
(……犯罪だ!!)
冷静になり、自身の行動のまずさを瞬時に理解する。
「申し訳ございません! お見苦しいものを──」
血の気が引くとはこういうことだろうか。
アルバートの前に差し出していた左手を隠すように腕を引こうとしたその瞬間、真っ白な細い手が伸びてきて、自身の無骨な手を痛いほど強く掴んだ。
突然のことに、驚愕から体を硬直させれば、血の滴る手の側面に柔らかな唇が触れ、濡れた舌先が傷口を舐め上げた。
「アルバート様!?」
アルバートの予想外の行動に、声が裏返る。だが、チュウッと可愛らしい音を立てて己の手に吸い付くアルバートはどこか必死で、掴まれた手を引くこともできなかった。
小さく柔らかな手に握り締められた指先はビクともせず、これが吸血鬼の力か……とおかしなところに感心しながら、遅れてハッとする。
「ア、アルバート様! ご無理をなさらないでくださいませ!」
「うぅんっ」
「っ……」
手に吸い付いたまま、ふるふると首を横に振るアルバート。その間も、小さな舌が傷口を開くように肉を舐め、溢れた血がアルバートの喉奥に消えていく。
時たま痛みが走るも、それを悟られぬよう、じっと耐えながら、懸命に血を求める子の邪魔をしないように、黙って彼の食事が終わるのを待った。
数分にも満たない短い時間が、途方もなく長く感じ始めた頃、チュッという小さなリップ音と共に、アルバートの唇が左手からゆっくりと離れていった。
薄い緊張から解放され、ホッと息を吐く。が、自身の手を掴んだままの小さな手は離れる気配もなく、黙り込んでしまったアルバートに不安が募った。
「アルバート様、大丈夫ですか? 具合を悪くされていませんか?」
今更ながらに、自身の血を飲ませてしまったことへの羞恥が押し寄せる。
それほど不健康な生活は送っている訳ではないが、自分の血が美味いとも到底思えない。
口に合わなかったらどうしよう、と動揺からおかしな心配をしていると、ゆっくりと顔を上げたアルバートの瞳が、真っ直ぐテオドールを見つめた。
「……大丈夫だよ。ありがとう、テオドール」
名を呼んでくれた──それが妙に嬉しくて、羞恥は気恥ずかしさに変わった。
「お体は、大丈夫ですか?」
「うん。……少しだけ、元気になった気がする」
「それは良うございました」
あのように少量の血で、変化など起きるはずがない。でも今は、アルバートの言葉を素直に受け止めた。
「あの、血は止まってるけど、傷口はそのままだから……」
「ええ、後ほど布を当てておきますね」
見れば、切れた傷口はそのままなのに、血は一滴も滲んでいなかった。すべて彼が飲んだのかと思うと不思議な感じだ。
そんなことを考えながら傷口を見つめていると、アルバートがそろそろと顔を上げた。
「あの……本当に、ありがとう」
「いえ、押し付けがましくなってしまい……」
「そっちじゃなくて……! そっちもだけど……その、心配してくれて、ありがとう」
白い頬を淡く染め、もじもじと言葉を紡ぐアルバートは本当に可愛らしく、父性がこれ以上ないほど擽られた。
「お元気になられたのであれば、なによりです」
「……あの、テオドール」
「はい。なんでしょう」
「……また、お話ししてくれる?」
「! ええ、喜んで」
「……ありがとう」
遠慮がちに、それでも繋がりを求めてくれるアルバートに、本心から言葉を返せば、花が綻ぶような可憐な笑みが返ってきた。
この愛らしい子が、もっと笑って過ごせるようになればいいのに──心から願った祈りは、数日後、思わぬ形で叶うことになった。
73
あなたにおすすめの小説


またのご利用をお待ちしています。
あらき奏多
BL
職場の同僚にすすめられた、とあるマッサージ店。
緊張しつつもゴッドハンドで全身とろとろに癒され、初めての感覚に下半身が誤作動してしまい……?!
・マッサージ師×客
・年下敬語攻め
・男前土木作業員受け
・ノリ軽め
※年齢順イメージ
九重≒達也>坂田(店長)≫四ノ宮
【登場人物】
▼坂田 祐介(さかた ゆうすけ) 攻
・マッサージ店の店長
・爽やかイケメン
・優しくて低めのセクシーボイス
・良識はある人
▼杉村 達也(すぎむら たつや) 受
・土木作業員
・敏感体質
・快楽に流されやすい。すぐ喘ぐ
・性格も見た目も男前
【登場人物(第二弾の人たち)】
▼四ノ宮 葵(しのみや あおい) 攻
・マッサージ店の施術者のひとり。
・店では年齢は下から二番目。経歴は店長の次に長い。敏腕。
・顔と名前だけ中性的。愛想は人並み。
・自覚済隠れS。仕事とプライベートは区別してる。はずだった。
▼九重 柚葉(ここのえ ゆずは) 受
・愛称『ココ』『ココさん』『ココちゃん』
・名前だけ可愛い。性格は可愛くない。見た目も別に可愛くない。
・理性が強め。隠れコミュ障。
・無自覚ドM。乱れるときは乱れる
作品はすべて個人サイト(http://lyze.jp/nyanko03/)からの転載です。
徐々に移動していきたいと思いますが、作品数は個人サイトが一番多いです。
よろしくお願いいたします。


オッサン課長のくせに、無自覚に色気がありすぎる~ヨレヨレ上司とエリート部下、恋は仕事の延長ですか?
中岡 始
BL
「新しい営業課長は、超敏腕らしい」
そんな噂を聞いて、期待していた橘陽翔(28)。
しかし、本社に異動してきた榊圭吾(42)は――
ヨレヨレのスーツ、だるそうな関西弁、ネクタイはゆるゆる。
(……いやいや、これがウワサの敏腕課長⁉ 絶対ハズレ上司だろ)
ところが、初めての商談でその評価は一変する。
榊は巧みな話術と冷静な判断で、取引先をあっさり落としにかかる。
(仕事できる……! でも、普段がズボラすぎるんだよな)
ネクタイを締め直したり、書類のコーヒー染みを指摘したり――
なぜか陽翔は、榊の世話を焼くようになっていく。
そして気づく。
「この人、仕事中はめちゃくちゃデキるのに……なんでこんなに色気ダダ漏れなんだ?」
煙草をくゆらせる仕草。
ネクタイを緩める無防備な姿。
そのたびに、陽翔の理性は削られていく。
「俺、もう待てないんで……」
ついに陽翔は榊を追い詰めるが――
「……お前、ほんまに俺のこと好きなんか?」
攻めるエリート部下 × 無自覚な色気ダダ漏れのオッサン上司。
じわじわ迫る恋の攻防戦、始まります。
【最新話:主任補佐のくせに、年下部下に見透かされている(気がする)ー関西弁とミルクティーと、春のすこし前に恋が始まった話】
主任補佐として、ちゃんとせなあかん──
そう思っていたのに、君はなぜか、俺の“弱いとこ”ばっかり見抜いてくる。
春のすこし手前、まだ肌寒い季節。
新卒配属された年下部下・瀬戸 悠貴は、無表情で口数も少ないけれど、妙に人の感情に鋭い。
風邪気味で声がかすれた朝、佐倉 奏太は、彼にそっと差し出された「ミルクティー」に言葉を失う。
何も言わないのに、なぜか伝わってしまう。
拒むでも、求めるでもなく、ただそばにいようとするその距離感に──佐倉の心は少しずつ、ほどけていく。
年上なのに、守られるみたいで、悔しいけどうれしい。
これはまだ、恋になる“少し前”の物語。
関西弁とミルクティーに包まれた、ふたりだけの静かな始まり。
(5月14日より連載開始)
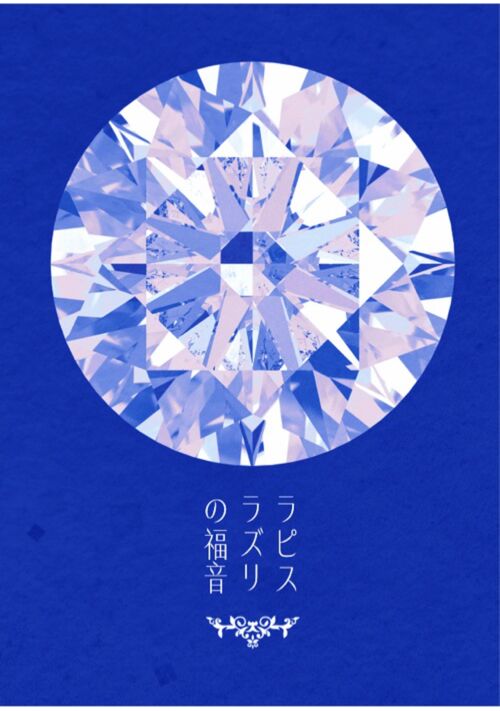
ラピスラズリの福音
東雲
BL
*異世界ファンタジーBL*
特別な世界観も、特殊な設定も、壮大な何かもありません。
幼馴染みの二人が遠回りをしながら、相思相愛の果てに結ばれるお話です。
金髪碧眼美形攻め×純朴一途筋肉受け
息をするように体の大きい子受けです。
珍しく年齢制限のないお話ですが、いつもの如く己の『好き』と性癖をたんと詰め込みました!

壁乳
リリーブルー
BL
ご来店ありがとうございます。ここは、壁越しに、触れ合える店。
最初は乳首から。指名を繰り返すと、徐々に、エリアが拡大していきます。
俺は後輩に「壁乳」に行こうと誘われた。
じれじれラブコメディー。
4年ぶりに続きを書きました!更新していくのでよろしくお願いします。
(挿絵byリリーブルー)

おすすめのマッサージ屋を紹介したら後輩の様子がおかしい件
ひきこ
BL
名ばかり管理職で疲労困憊の山口は、偶然見つけたマッサージ店で、長年諦めていたどうやっても改善しない体調不良が改善した。
せっかくなので後輩を連れて行ったらどうやら様子がおかしくて、もう行くなって言ってくる。
クールだったはずがいつのまにか世話焼いてしまう年下敬語後輩Dom ×
(自分が世話を焼いてるつもりの)脳筋系天然先輩Sub がわちゃわちゃする話。
『加減を知らない初心者Domがグイグイ懐いてくる』と同じ世界で地続きのお話です。
(全く別の話なのでどちらも単体で読んでいただけます)
https://www.alphapolis.co.jp/novel/21582922/922916390
サブタイトルに◆がついているものは後輩視点です。
同人誌版と同じ表紙に差し替えました。
表紙イラスト:浴槽つぼカルビ様(X@shabuuma11 )ありがとうございます!

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















