15 / 44
第2章 「帰らぬ夫と、周囲の誤解」
15話
しおりを挟む
6.揺れる心と、“妻”の役目
ルイーゼと再会したことで、私の中の迷いはさらに深まった。
以前は「どうせ離婚するのだから、仮面夫婦でいるほうが楽」という思考だったのに、今は“仮面の下”で何かが形を成し始めている。
彼のことを気にかけて、傷の回復を願って、少しでも笑顔でいてほしいと思っている自分がいるのだ。
夜の寝室を訪れると、ベガは薄暗がりの中で手紙を読んでいた。リハビリが進み、肩の痛みもだいぶ和らいだようで、少しの時間なら姿勢を保って机に向かえるようになったらしい。
「……どなたからの手紙ですか?」
私は遠慮がちに声をかける。すると、ベガは少し驚いたように顔を上げ、手紙をたたむ。
「北方の領地からだ。残党狩りがまだ続いているらしく、俺が戻るのはいつ頃か、と聞いてきている。王宮からの正式な許可が出れば、近いうちに向かうことになるだろう」
「……そうなんですね」
心の奥で微かな痛みが走る。
そうだ、彼は辺境伯として本来の領地へ戻るのが当たり前だ。王都での治療は一時的なものに過ぎない。彼の傷が回復すれば、彼は再び北方へ帰ることになるのだ。
そうなれば、私たちはどうするのか。このまま離婚して別れるのか、あるいは私も北方へ同行するのか――いや、そんな話は今まで一度もしていない。
「アルタイ、お前こそ珍しいな。こんな時間に俺の部屋へ来るなんて。何かあったのか?」
ベガが怪訝そうに尋ねる。私は少しだけ躊躇してから、椅子に腰を下ろし、正面から彼を見つめた。
「……私、貴方に聞きたいことがあるのです」
「何だ?」
「たとえば、もし貴方が北方へ戻ったら……貴方の“妻”として、私も一緒に行ったほうがいいのでしょうか?」
一瞬、沈黙が落ちる。
彼は息を呑んだようだった。それもそうだろう、こんなことを口にするのは、私にしては珍しいことだから。
「どういう意味だ? お前は最初から、俺とは離婚するつもりだったんじゃないのか?」
「……ええ、そうでした。でも、いざ貴方が戻ってきたら、自分でもわからなくなって……。私は公爵家の当主である父を補佐する立場でもあるし、王都にいたほうが動きやすいのも事実です。それでも、夫婦として考えるなら、一緒に暮らすべきなのかなと思ったりもして……」
言葉を切りながら、私は本音を絞り出すように話す。
これまでずっと仮面夫婦を演じてきた私が、今さら本心を垣間見せるのは、正直気恥ずかしい。
ベガは少し言葉を探るようにして、ゆっくりと口を開いた。
「アルタイ、俺も本音を言おう。……お前がいなければ、俺は最初の戦傷で死んでいたかもしれない。看病してもらったことだけじゃない。俺が帰ってきてからというもの、いつもお前は気丈にふるまって、この邸をまとめてくれている。『公爵令嬢だから当然』と言われるかもしれんが、俺から見ればそれは立派な才能だし、尊敬にも値する」
「……ありがとうございます」
「だから、もしお前が王都での生活を優先したいのなら、それは止めない。公爵家にも色々あるだろうしな。……だが、正直を言えば、北方へ来てくれたら嬉しいとも思う」
そこで一呼吸置き、彼は目を伏せる。
「もっとも、これは俺の“わがまま”だ。お前が何かを犠牲にしてまでついてくる必要はない。お前が自由に選べばいいんだ。最初に言ったように、俺はお前を無理やり縛るつもりは……なかった」
「……なかった、ということは?」
つい問い返してしまうと、ベガは困惑したように唇を引き結んだ。
「それは……その、戦地から戻ってきてお前に世話してもらううちに、離婚なんてしなくてもいいんじゃないかと思うようになった。だが、そう思った途端に“お前を好きなように縛る権利は俺にはない”っていう気持ちも湧いてきて……うまく言えんが、要するに矛盾しているんだよ」
その言葉は、まるで私自身の感情と重なるようでもあった。
離婚したほうがお互いに楽になれるのかもしれない。しかし、それでも一緒にいたい気持ちも、確かに存在する。
そんな曖昧な情が、私たちの関係を複雑にしているのだろう。
「……わかりました。もう少し、考えさせていただけますか?」
私がそう言うと、ベガはほっとしたようにうなずいた。
「もちろんだ。焦らなくていい。俺も急に領地へ戻るわけではないし、あと数週間は治療師の許可が出ないんだから」
「そうですね。では、おやすみなさいませ」
私は足早に部屋を出る。背中に彼の視線を感じつつも、何も言わずに扉を閉めた。
廊下を歩くうちに、心臓がドキドキとうるさく鳴っているのを自覚する。
(私はどうしたいの? 本当に離婚したいわけではないのかもしれない。じゃあ、私は彼とこの先ずっと一緒にいたいの? それとも……)
答えはまだ出ない。
ただ、今はお互いに迷っている――それだけは、はっきりしていた。
ルイーゼと再会したことで、私の中の迷いはさらに深まった。
以前は「どうせ離婚するのだから、仮面夫婦でいるほうが楽」という思考だったのに、今は“仮面の下”で何かが形を成し始めている。
彼のことを気にかけて、傷の回復を願って、少しでも笑顔でいてほしいと思っている自分がいるのだ。
夜の寝室を訪れると、ベガは薄暗がりの中で手紙を読んでいた。リハビリが進み、肩の痛みもだいぶ和らいだようで、少しの時間なら姿勢を保って机に向かえるようになったらしい。
「……どなたからの手紙ですか?」
私は遠慮がちに声をかける。すると、ベガは少し驚いたように顔を上げ、手紙をたたむ。
「北方の領地からだ。残党狩りがまだ続いているらしく、俺が戻るのはいつ頃か、と聞いてきている。王宮からの正式な許可が出れば、近いうちに向かうことになるだろう」
「……そうなんですね」
心の奥で微かな痛みが走る。
そうだ、彼は辺境伯として本来の領地へ戻るのが当たり前だ。王都での治療は一時的なものに過ぎない。彼の傷が回復すれば、彼は再び北方へ帰ることになるのだ。
そうなれば、私たちはどうするのか。このまま離婚して別れるのか、あるいは私も北方へ同行するのか――いや、そんな話は今まで一度もしていない。
「アルタイ、お前こそ珍しいな。こんな時間に俺の部屋へ来るなんて。何かあったのか?」
ベガが怪訝そうに尋ねる。私は少しだけ躊躇してから、椅子に腰を下ろし、正面から彼を見つめた。
「……私、貴方に聞きたいことがあるのです」
「何だ?」
「たとえば、もし貴方が北方へ戻ったら……貴方の“妻”として、私も一緒に行ったほうがいいのでしょうか?」
一瞬、沈黙が落ちる。
彼は息を呑んだようだった。それもそうだろう、こんなことを口にするのは、私にしては珍しいことだから。
「どういう意味だ? お前は最初から、俺とは離婚するつもりだったんじゃないのか?」
「……ええ、そうでした。でも、いざ貴方が戻ってきたら、自分でもわからなくなって……。私は公爵家の当主である父を補佐する立場でもあるし、王都にいたほうが動きやすいのも事実です。それでも、夫婦として考えるなら、一緒に暮らすべきなのかなと思ったりもして……」
言葉を切りながら、私は本音を絞り出すように話す。
これまでずっと仮面夫婦を演じてきた私が、今さら本心を垣間見せるのは、正直気恥ずかしい。
ベガは少し言葉を探るようにして、ゆっくりと口を開いた。
「アルタイ、俺も本音を言おう。……お前がいなければ、俺は最初の戦傷で死んでいたかもしれない。看病してもらったことだけじゃない。俺が帰ってきてからというもの、いつもお前は気丈にふるまって、この邸をまとめてくれている。『公爵令嬢だから当然』と言われるかもしれんが、俺から見ればそれは立派な才能だし、尊敬にも値する」
「……ありがとうございます」
「だから、もしお前が王都での生活を優先したいのなら、それは止めない。公爵家にも色々あるだろうしな。……だが、正直を言えば、北方へ来てくれたら嬉しいとも思う」
そこで一呼吸置き、彼は目を伏せる。
「もっとも、これは俺の“わがまま”だ。お前が何かを犠牲にしてまでついてくる必要はない。お前が自由に選べばいいんだ。最初に言ったように、俺はお前を無理やり縛るつもりは……なかった」
「……なかった、ということは?」
つい問い返してしまうと、ベガは困惑したように唇を引き結んだ。
「それは……その、戦地から戻ってきてお前に世話してもらううちに、離婚なんてしなくてもいいんじゃないかと思うようになった。だが、そう思った途端に“お前を好きなように縛る権利は俺にはない”っていう気持ちも湧いてきて……うまく言えんが、要するに矛盾しているんだよ」
その言葉は、まるで私自身の感情と重なるようでもあった。
離婚したほうがお互いに楽になれるのかもしれない。しかし、それでも一緒にいたい気持ちも、確かに存在する。
そんな曖昧な情が、私たちの関係を複雑にしているのだろう。
「……わかりました。もう少し、考えさせていただけますか?」
私がそう言うと、ベガはほっとしたようにうなずいた。
「もちろんだ。焦らなくていい。俺も急に領地へ戻るわけではないし、あと数週間は治療師の許可が出ないんだから」
「そうですね。では、おやすみなさいませ」
私は足早に部屋を出る。背中に彼の視線を感じつつも、何も言わずに扉を閉めた。
廊下を歩くうちに、心臓がドキドキとうるさく鳴っているのを自覚する。
(私はどうしたいの? 本当に離婚したいわけではないのかもしれない。じゃあ、私は彼とこの先ずっと一緒にいたいの? それとも……)
答えはまだ出ない。
ただ、今はお互いに迷っている――それだけは、はっきりしていた。
5
あなたにおすすめの小説
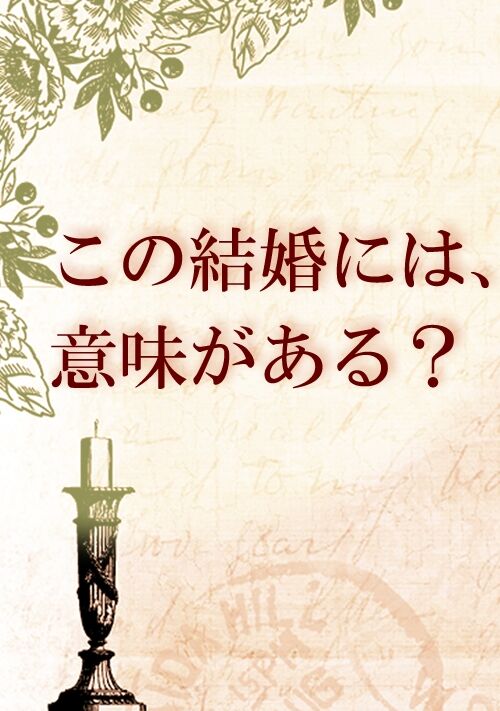
この結婚には、意味がある?
みこと。
恋愛
公爵家に降嫁した王女アリアは、初夜に夫から「オープンマリッジ」を提案される。
婚姻関係を維持しながら、他の異性との遊戯を認めろ、という要求を、アリアはどう解釈するのか?
王宮で冷遇されていた王女アリアの、密かな目的とは。
この結婚は、アリアにとってどんな意味がある?
※他のサイトにも掲載しています。
※他タイトル『沈黙の聖女は、ある日すべてを暴露する』も収録。←まったく別のお話です

「では、ごきげんよう」と去った悪役令嬢は破滅すら置き去りにして
東雲れいな
恋愛
「悪役令嬢」と噂される伯爵令嬢・ローズ。王太子殿下の婚約者候補だというのに、ヒロインから王子を奪おうなんて野心はまるでありません。むしろ彼女は、“わたくしはわたくしらしく”と胸を張り、周囲の冷たい視線にも毅然と立ち向かいます。
破滅を甘受する覚悟すらあった彼女が、誇り高く戦い抜くとき、運命は大きく動きだす。

お姫様は死に、魔女様は目覚めた
悠十
恋愛
とある大国に、小さいけれど豊かな国の姫君が側妃として嫁いだ。
しかし、離宮に案内されるも、離宮には侍女も衛兵も居ない。ベルを鳴らしても、人を呼んでも誰も来ず、姫君は長旅の疲れから眠り込んでしまう。
そして、深夜、姫君は目覚め、体の不調を感じた。そのまま気を失い、三度目覚め、三度気を失い、そして……
「あ、あれ? えっ、なんで私、前の体に戻ってるわけ?」
姫君だった少女は、前世の魔女の体に魂が戻ってきていた。
「えっ、まさか、あのまま死んだ⁉」
魔女は慌てて遠見の水晶を覗き込む。自分の――姫君の体は、嫁いだ大国はいったいどうなっているのか知るために……

初恋にケリをつけたい
志熊みゅう
恋愛
「初恋にケリをつけたかっただけなんだ」
そう言って、夫・クライブは、初恋だという未亡人と不倫した。そして彼女はクライブの子を身ごもったという。私グレースとクライブの結婚は確かに政略結婚だった。そこに燃えるような恋や愛はなくとも、20年の信頼と情はあると信じていた。だがそれは一瞬で崩れ去った。
「分かりました。私たち離婚しましょう、クライブ」
初恋とケリをつけたい男女の話。
☆小説家になろうの日間異世界(恋愛)ランキング (すべて)で1位獲得しました。(2025/9/18)
☆小説家になろうの日間総合ランキング (すべて)で1位獲得しました。(2025/9/18)
☆小説家になろうの週間総合ランキング (すべて)で1位獲得しました。(2025/9/22)

今さら遅いと言われる側になったのは、あなたです
有賀冬馬
恋愛
夜会で婚約破棄された私は、すべてを失った――はずだった。
けれど、人生は思いもよらない方向へ転がる。
助けた騎士は、王の右腕。
見下されてきた私の中にある価値を、彼だけが見抜いた。
王城で評価され、居場所を得ていく私。
その頃、私を捨てた元婚約者は、転落の一途をたどる。
「間違いだった」と言われても、もう心は揺れない。
選ばれるのを待つ時代は、終わった。

結婚初夜、「何故彼女が死んでお前が生きているんだ」と夫に言われました
ましゅぺちーの
恋愛
侯爵令嬢のアリサは婚約者だった王太子テオドールと結婚した。
ちょうどその半年前、アリサの腹違いの妹のシアは不慮の事故で帰らぬ人となっていた。
王太子が婚約者の妹のシアを愛していたのは周知の事実だった。
そんな彼は、結婚初夜、アリサに冷たく言い放った。
「何故彼女が死んでお前が生きているんだ」と。

虐げられた皇女は父の愛人とその娘に復讐する
ましゅぺちーの
恋愛
大陸一の大国ライドーン帝国の皇帝が崩御した。
その皇帝の子供である第一皇女シャーロットはこの時をずっと待っていた。
シャーロットの母親は今は亡き皇后陛下で皇帝とは政略結婚だった。
皇帝は皇后を蔑ろにし身分の低い女を愛妾として囲った。
やがてその愛妾には子供が生まれた。それが第二皇女プリシラである。
愛妾は皇帝の寵愛を笠に着てやりたい放題でプリシラも両親に甘やかされて我儘に育った。
今までは皇帝の寵愛があったからこそ好きにさせていたが、これからはそうもいかない。
シャーロットは愛妾とプリシラに対する復讐を実行に移す―
一部タイトルを変更しました。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















