4 / 24
三話 協力
しおりを挟む
ヴィクターが押しかけてきた翌日から、早速調査が始まった。
と言っても手がかりはないに等しい。
シティ公認の行商人に、獣耳の人影に見覚えはないか当たってみたが、正規ルートを使う人間が違法物に手を出すはずもなく、早くも捜査は暗礁に乗り上げていた。
そこで、リアムがバニシャの匂いを探し出す作戦が立てられたのである。
「麻袋から変わった匂いはしていませんでしたよ……?」
微かに青々とした植物の香りはしていたが、特段怪しいものではなかった。
「気づかないのも無理はない。ご丁寧に、違う薬草の臭いを染み込ませた布で包まれていたからな。……これがバニシャだ。嗅いでみろ」
ロドルナ警察本部の一室で、ヴィクターが差し出した小瓶には、茶色の粉末が入っていた。恐る恐る鼻を近づけると、甘い香りが鼻孔を通り抜ける。
その瞬間、リアムの視界はぐるんとひっくり返った。真下には、ヴィクターがいて、こちらを見上げている。
――え! 何、これ!
手足をジタバタさせても、身体は言うことを聞かない。近づいてくる天井にぶつかりそうになり、リアムは力の限り絶叫した。
「う、うわわわあ!」
「おい!」
肩を揺さぶられ、リアムは「あへぇ?」と気の抜けた声を吐き出す。
――え、僕、ちゃんと立ってる……?
両足はしっかりと地面を踏みしめていた。
「あ、あれ……?」
きょろきょろと辺りを見回すリアムにヴィクターは、小瓶を弄びながら、
「『バニシャ』は幻覚症状も引き起こすからな、嗅ぎすぎるなよ」
遅すぎる忠告をした。
――先に言ってください……。
悪びれることのないヴィクターに、リアムは言い返せず、深呼吸をするしかない。
「臭いは覚えたか?」
「は、はい」
鼻の奥に甘く絡みつく臭いに、リアムはげんなりするも、表情には出さず必死に頷いた。
幻覚、興奮作用に依存性まで併せ持つ、薬草『バニシャ』。
「あの、バニシャを使うのって、危ないんじゃないですか。僕、死ぬかと思いました」
「全面的に禁止すると、さらに高値で取引されるのは目に見えている。そうなったら元も子もないぞ」
――頭ごなしに叱っても、お酒を止めない常連さんたちと同じってことかな。
覗いてはいけない。
手を出してはいけない。
むやみに諫めれば、逆に興味を引いてしまう。
リアムは、ヴィクターの推測に感心し、自らは手を出すまいと心に誓った。
「人間が正気を失うだけなら、ここまで取り締まりは厳しくないんだがな」
「え、すでに大事では……」
バニシャの扱いに慎重にならざるを得ない、もうひとつの理由、それは人間の身体機能を高める効果があるというものだ。幻覚症状などのほうが危険度は高いのではと、リアムは内心首を傾げた。
「特に【人狼】が摂取すると爆発的に身体能力が向上するから、取扱いに注意が必要になる」
「ぐ、具体的にどうなるんですか……?」
ヴィクターの深刻な表情を見る限り、悪い知らせのようだ。
「さあな。バニシャを取り込んだ個体に遭遇した者は、正気を失っていることが多くてな。まともな情報がない。……そんなモノを【人狼】が売り捌いている時点で、状況は最悪だ」
「ど、どういうことですか?」
「……奴らは自分たちで口にする以上のバニシャを抱えてるはずだ。余剰分をシティに流してんだろ、胸糞悪い」
それはつまり。
「お前をひと呑みできる【人狼】が、シティに潜んでいる可能性が高いってことだ」
同族だとしても、人狼は凶暴さを増せば、見境なく襲ってくる。
震えるリアムに、「せいぜい、お仲間に喰われないようにな」とシティを守る捜査官は冷たく言い放った。
捜査開始二日目。
リアムはシティの町中で鼻を引くつかせる。食べ物の匂いや体臭、埃や馬の汚物の臭いで大通りは溢れていた。いくらバニシャが強烈な臭いを放っているからといって、この中から目当ての匂いを見つけ出すのは至難の業だ。
もう一度臭いを確かめさせてくれとヴィクターに頼んだが、持ち出しはできないと却下された。リアムも極力警察本部に近づきたくはないので、諦めざるを得ない。
――僕を信用してないんだなあ。
リアムはがっかりしたが、頼まれたことを投げ出すわけにもいかない。
匂いの選別は想像以上の体力を消耗する。雑多な刺激が脳に響き、リアムは休憩時にはぐったりしていた。
――ヴィクターさん、うんざりしてるかな。
「あの、すみません……」
「捜査に手間はつきものだ。今のところお前の鼻だけに頼ってる俺が、とやかく言う資格はない」
三度目の休憩時。
リアムは川岸のベンチで項垂れた。川向う、三角州には四角い建物が、かすんで見える。まるで巨人が蹲っているようだ。ロドルナ警察が管轄する『中央監獄』である。
――このままなんの手がかりも掴めなかったら、あそこに放り込まれるんじゃ……。
リアムは両手を忙しなく動かし、ヴィクターを盗み見た。
どんよりと厚い雲が広がる空に向かって、ヴィクターは煙草の煙を吐きだす。
先日の激昂が嘘のように、ヴィクターは依然と変わらずリアムに接している。事件解決を優先して気持ちを切り替えているのか。リアムはとりあえず、避けられていないことに安堵した。
休憩の合間にリアムが問えば、ヴィクターは端的だが答えてくれる。
彼が所属している部署は【人狼対策課】で、主にシティ内で発生する人狼絡みの事件を取り扱う。『バニシャ』を確認するため訪れた、警察本部内の人狼対策課のオフィスには、大勢の捜査官が忙しそうに出入りしていたのを思い出す。
――人狼が犯人なんて大ニュース、聞いたことがない。僕が知らないだけで、たくさん事件が起きているのかな。
リアムは世事に疎いが、ゴシップ好きの酔客たちから、シティ•ロドルナを知ることができていた。
彼らならすぐに噂話を広げるはずである。
「そうそう今回のような事件は発生しない。雑務がほとんどだ。……【人狼】には戸籍がない。事件が起きなくともしらみつぶしに個体調査は必要で、それで一日の大半は潰れる」
ヴィクターがリアムを【人狼】だと疑ったのも、戸籍からだった。
「ロドルナでは浮浪児にも管理番号が振られる。お前の名や容姿で照会しても、かすりもしなかった。異国人は母国の証明書がないと、シティに滞在できない。となると残るは……」
あえて制度から除外されているのは、異形だけだ。ここ、ユフラスコ王国を含む大陸で確認されている異形は、【淫魔】【吸血鬼】【人狼】の三種である。
ただ【淫魔】【吸血鬼】は絶滅したと言われて久しい。
残されたのは【人狼】だ。
シティ・ロドルナ内で確認されている人狼のほとんどは、百年前に大森林から移住した者たちの末裔である。
「移住?」
【人狼】たちは進んで迫害される都市に住もうとしたのだろうか。
理解できない。
「……お前たちの祖先はシティ・ロドルナで開拓作業に従事していた。すでにシティの周囲では、家畜の量産が進んでいて、俺たちは豊かな食料を、【人狼】は労働力を提供する、共存関係にあったわけだ。……まあ、それも【人狼】たちの暴動で崩れたがな」
吸殻を携帯灰皿でもみ消したヴィクターは「そろそろ行くぞ」とリアムを促した。
――昔は人と人狼は仲良く暮らしていたのかな。
調査に戻りながら、想像できない理想郷にリアムは想いを馳せる。同時に、幼い頃の記憶が蘇り、気持ちは沈んでいった。
と言っても手がかりはないに等しい。
シティ公認の行商人に、獣耳の人影に見覚えはないか当たってみたが、正規ルートを使う人間が違法物に手を出すはずもなく、早くも捜査は暗礁に乗り上げていた。
そこで、リアムがバニシャの匂いを探し出す作戦が立てられたのである。
「麻袋から変わった匂いはしていませんでしたよ……?」
微かに青々とした植物の香りはしていたが、特段怪しいものではなかった。
「気づかないのも無理はない。ご丁寧に、違う薬草の臭いを染み込ませた布で包まれていたからな。……これがバニシャだ。嗅いでみろ」
ロドルナ警察本部の一室で、ヴィクターが差し出した小瓶には、茶色の粉末が入っていた。恐る恐る鼻を近づけると、甘い香りが鼻孔を通り抜ける。
その瞬間、リアムの視界はぐるんとひっくり返った。真下には、ヴィクターがいて、こちらを見上げている。
――え! 何、これ!
手足をジタバタさせても、身体は言うことを聞かない。近づいてくる天井にぶつかりそうになり、リアムは力の限り絶叫した。
「う、うわわわあ!」
「おい!」
肩を揺さぶられ、リアムは「あへぇ?」と気の抜けた声を吐き出す。
――え、僕、ちゃんと立ってる……?
両足はしっかりと地面を踏みしめていた。
「あ、あれ……?」
きょろきょろと辺りを見回すリアムにヴィクターは、小瓶を弄びながら、
「『バニシャ』は幻覚症状も引き起こすからな、嗅ぎすぎるなよ」
遅すぎる忠告をした。
――先に言ってください……。
悪びれることのないヴィクターに、リアムは言い返せず、深呼吸をするしかない。
「臭いは覚えたか?」
「は、はい」
鼻の奥に甘く絡みつく臭いに、リアムはげんなりするも、表情には出さず必死に頷いた。
幻覚、興奮作用に依存性まで併せ持つ、薬草『バニシャ』。
「あの、バニシャを使うのって、危ないんじゃないですか。僕、死ぬかと思いました」
「全面的に禁止すると、さらに高値で取引されるのは目に見えている。そうなったら元も子もないぞ」
――頭ごなしに叱っても、お酒を止めない常連さんたちと同じってことかな。
覗いてはいけない。
手を出してはいけない。
むやみに諫めれば、逆に興味を引いてしまう。
リアムは、ヴィクターの推測に感心し、自らは手を出すまいと心に誓った。
「人間が正気を失うだけなら、ここまで取り締まりは厳しくないんだがな」
「え、すでに大事では……」
バニシャの扱いに慎重にならざるを得ない、もうひとつの理由、それは人間の身体機能を高める効果があるというものだ。幻覚症状などのほうが危険度は高いのではと、リアムは内心首を傾げた。
「特に【人狼】が摂取すると爆発的に身体能力が向上するから、取扱いに注意が必要になる」
「ぐ、具体的にどうなるんですか……?」
ヴィクターの深刻な表情を見る限り、悪い知らせのようだ。
「さあな。バニシャを取り込んだ個体に遭遇した者は、正気を失っていることが多くてな。まともな情報がない。……そんなモノを【人狼】が売り捌いている時点で、状況は最悪だ」
「ど、どういうことですか?」
「……奴らは自分たちで口にする以上のバニシャを抱えてるはずだ。余剰分をシティに流してんだろ、胸糞悪い」
それはつまり。
「お前をひと呑みできる【人狼】が、シティに潜んでいる可能性が高いってことだ」
同族だとしても、人狼は凶暴さを増せば、見境なく襲ってくる。
震えるリアムに、「せいぜい、お仲間に喰われないようにな」とシティを守る捜査官は冷たく言い放った。
捜査開始二日目。
リアムはシティの町中で鼻を引くつかせる。食べ物の匂いや体臭、埃や馬の汚物の臭いで大通りは溢れていた。いくらバニシャが強烈な臭いを放っているからといって、この中から目当ての匂いを見つけ出すのは至難の業だ。
もう一度臭いを確かめさせてくれとヴィクターに頼んだが、持ち出しはできないと却下された。リアムも極力警察本部に近づきたくはないので、諦めざるを得ない。
――僕を信用してないんだなあ。
リアムはがっかりしたが、頼まれたことを投げ出すわけにもいかない。
匂いの選別は想像以上の体力を消耗する。雑多な刺激が脳に響き、リアムは休憩時にはぐったりしていた。
――ヴィクターさん、うんざりしてるかな。
「あの、すみません……」
「捜査に手間はつきものだ。今のところお前の鼻だけに頼ってる俺が、とやかく言う資格はない」
三度目の休憩時。
リアムは川岸のベンチで項垂れた。川向う、三角州には四角い建物が、かすんで見える。まるで巨人が蹲っているようだ。ロドルナ警察が管轄する『中央監獄』である。
――このままなんの手がかりも掴めなかったら、あそこに放り込まれるんじゃ……。
リアムは両手を忙しなく動かし、ヴィクターを盗み見た。
どんよりと厚い雲が広がる空に向かって、ヴィクターは煙草の煙を吐きだす。
先日の激昂が嘘のように、ヴィクターは依然と変わらずリアムに接している。事件解決を優先して気持ちを切り替えているのか。リアムはとりあえず、避けられていないことに安堵した。
休憩の合間にリアムが問えば、ヴィクターは端的だが答えてくれる。
彼が所属している部署は【人狼対策課】で、主にシティ内で発生する人狼絡みの事件を取り扱う。『バニシャ』を確認するため訪れた、警察本部内の人狼対策課のオフィスには、大勢の捜査官が忙しそうに出入りしていたのを思い出す。
――人狼が犯人なんて大ニュース、聞いたことがない。僕が知らないだけで、たくさん事件が起きているのかな。
リアムは世事に疎いが、ゴシップ好きの酔客たちから、シティ•ロドルナを知ることができていた。
彼らならすぐに噂話を広げるはずである。
「そうそう今回のような事件は発生しない。雑務がほとんどだ。……【人狼】には戸籍がない。事件が起きなくともしらみつぶしに個体調査は必要で、それで一日の大半は潰れる」
ヴィクターがリアムを【人狼】だと疑ったのも、戸籍からだった。
「ロドルナでは浮浪児にも管理番号が振られる。お前の名や容姿で照会しても、かすりもしなかった。異国人は母国の証明書がないと、シティに滞在できない。となると残るは……」
あえて制度から除外されているのは、異形だけだ。ここ、ユフラスコ王国を含む大陸で確認されている異形は、【淫魔】【吸血鬼】【人狼】の三種である。
ただ【淫魔】【吸血鬼】は絶滅したと言われて久しい。
残されたのは【人狼】だ。
シティ・ロドルナ内で確認されている人狼のほとんどは、百年前に大森林から移住した者たちの末裔である。
「移住?」
【人狼】たちは進んで迫害される都市に住もうとしたのだろうか。
理解できない。
「……お前たちの祖先はシティ・ロドルナで開拓作業に従事していた。すでにシティの周囲では、家畜の量産が進んでいて、俺たちは豊かな食料を、【人狼】は労働力を提供する、共存関係にあったわけだ。……まあ、それも【人狼】たちの暴動で崩れたがな」
吸殻を携帯灰皿でもみ消したヴィクターは「そろそろ行くぞ」とリアムを促した。
――昔は人と人狼は仲良く暮らしていたのかな。
調査に戻りながら、想像できない理想郷にリアムは想いを馳せる。同時に、幼い頃の記憶が蘇り、気持ちは沈んでいった。
0
あなたにおすすめの小説

拝啓、目が覚めたらBLゲームの主人公だった件
碧月 晶
BL
さっきまでコンビニに向かっていたはずだったのに、何故か目が覚めたら病院にいた『俺』。
状況が分からず戸惑う『俺』は窓に映った自分の顔を見て驚いた。
「これ…俺、なのか?」
何故ならそこには、恐ろしく整った顔立ちの男が映っていたのだから。
《これは、現代魔法社会系BLゲームの主人公『石留 椿【いしどめ つばき】(16)』に転生しちゃった元平凡男子(享年18)が攻略対象たちと出会い、様々なイベントを経て『運命の相手』を見つけるまでの物語である──。》
────────────
~お知らせ~
※第3話を少し修正しました。
※第5話を少し修正しました。
※第6話を少し修正しました。
※第11話を少し修正しました。
※第19話を少し修正しました。
※第22話を少し修正しました。
※第24話を少し修正しました。
※第25話を少し修正しました。
※第26話を少し修正しました。
※第31話を少し修正しました。
※第32話を少し修正しました。
────────────
※感想(一言だけでも構いません!)、いいね、お気に入り、近況ボードへのコメント、大歓迎です!!
※表紙絵は作者が生成AIで試しに作ってみたものです。

呪われた辺境伯は、異世界転生者を手放さない
波崎 亨璃
BL
ーーー呪われた辺境伯に捕まったのは、俺の方だった。
異世界に迷い込んだ駆真は「呪われた辺境伯」と呼ばれるレオニスの領地に落ちてしまう。
強すぎる魔力のせいで、人を近づけることができないレオニス。
彼に触れれば衰弱し、最悪の場合、命を落とす。
しかしカルマだけはなぜかその影響を一切受けなかった。その事実に気づいたレオニスは次第にカルマを手放さなくなっていく。
「俺に触れられるのは、お前だけだ」
呪いよりも重い執着と孤独から始まる、救済BL。
となります。

劣等アルファは最強王子から逃げられない
東
BL
リュシアン・ティレルはアルファだが、オメガのフェロモンに気持ち悪くなる欠陥品のアルファ。そのことを周囲に隠しながら生活しているため、異母弟のオメガであるライモントに手ひどい態度をとってしまい、世間からの評判は悪い。
ある日、気分の悪さに逃げ込んだ先で、ひとりの王子につかまる・・・という話です。

禁書庫の管理人は次期宰相様のお気に入り
結衣可
BL
オルフェリス王国の王立図書館で、禁書庫を預かる司書カミル・ローレンは、過去の傷を抱え、静かな孤独の中で生きていた。
そこへ次期宰相と目される若き貴族、セドリック・ヴァレンティスが訪れ、知識を求める名目で彼のもとに通い始める。
冷静で無表情なカミルに興味を惹かれたセドリックは、やがて彼の心の奥にある痛みに気づいていく。
愛されることへの恐れに縛られていたカミルは、彼の真っ直ぐな想いに少しずつ心を開き、初めて“痛みではない愛”を知る。
禁書庫という静寂の中で、カミルの孤独を、過去を癒し、共に歩む未来を誓う。

【8話完結】ざまぁされて廃嫡されたバカ王子とは俺のことです。
キノア9g
BL
廃嫡され全てを失った元王子。地道に生きたいのにハイスペ幼馴染が逃がしてくれません。
あらすじ
「第二王子カイル、お前を廃嫡する」
傲慢な振る舞いを理由に、王位継承権も婚約者も失い、国外追放されたカイル。
絶望の最中、彼に蘇ったのは「ブラック企業で使い潰された前世の記憶」だった。
「もう二度と、他人任せにはしない」
前世の反省を活かし、隣国の冒険者ギルドで雑用係(清掃員)として地道にやり直そうとするカイル。しかし、そんな彼を追いかけてきたのは、隣国の貴族であり幼馴染のレオナードだった。
「君がどんな立場になろうと、僕にとっては君は君だ」
落ちぶれたカイルに変わらぬ愛を注ぎ、元婚約者の悪意ある噂からも守り抜くレオナード。
すべてを失った元バカ王子が、社畜根性と幼馴染の溺愛によって幸せを掴むまでの、再起と愛の物語。
全8話。

龍の寵愛を受けし者達
樹木緑
BL
サンクホルム国の王子のジェイドは、
父王の護衛騎士であるダリルに憧れていたけど、
ある日偶然に自分の護衛にと推す父王に反する声を聞いてしまう。
それ以来ずっと嫌われていると思っていた王子だったが少しずつ打ち解けて
いつかはそれが愛に変わっていることに気付いた。
それと同時に何故父王が最強の自身の護衛を自分につけたのか理解す時が来る。
王家はある者に裏切りにより、
無惨にもその策に敗れてしまう。
剣が苦手でずっと魔法の研究をしていた王子は、
責めて騎士だけは助けようと、
刃にかかる寸前の所でとうの昔に失ったとされる
時戻しの術をかけるが…

【完結】君を知らないまま、恋をした
一ノ瀬麻紀
BL
体調を崩し入院した篠宮真白(しのみやましろ)は、制限のある生活を送ることになった。
そんな中、真白は自由に走り回れるもう一つの世界を知る。
そこで過ごす時間は、思うように動けなかった真白にとって、大切なものだった。
仮想空間での出会いや経験を通して、真白の世界は少しずつ広がっていく。
そして真白が本当の気持ちに気づいた時、すべてが繋がり始める――。
※
タイトル及びあらすじ変更しました。(2/10)
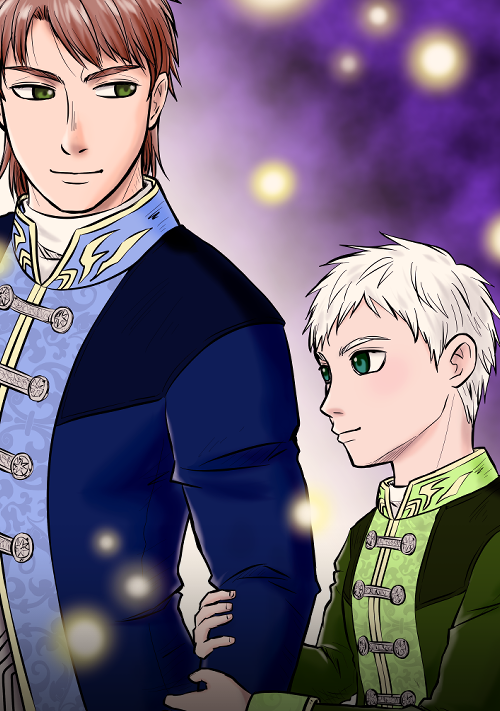
天涯孤独になった少年は、元軍人の優しいオジサンと幸せに生きる
ir(いる)
BL
※2025/11 プロローグを追加しました
ファンタジー。最愛の父を亡くした後、恋人(不倫相手)と再婚したい母に騙されて捨てられた12歳の少年。30歳の元軍人の男性との出会いで傷付いた心を癒してもらい、恋(主人公からの片思い)をする物語。
※序盤は主人公が悲しむシーンが多いです。
※主人公と相手が出会うまで、少しかかります(28話)
※BL的展開になるまでに、結構かかる予定です。主人公が恋心を自覚するようでしないのは51話くらい?
※女性は普通に登場しますが、他に明確な相手がいたり、恋愛目線で主人公たちを見ていない人ばかりです。
※同性愛者もいますが、異性愛が主流の世界です。なので主人公は、男なのに男を好きになる自分はおかしいのでは?と悩みます。
※主人公のお相手は、保護者として主人公を温かく見守り、支えたいと思っています。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















