9 / 35
第8章 妖精の騎士
しおりを挟む
馬の背越しに見えていた海岸線が視界から消えて久しくなった頃、エレンは後ろの方が明るくなってきたのを感じました。西に向かって進んでいるので、太陽が背後から昇ってくるのです。
「ロロ! もうすぐ日の出だよ。僕たち、夜通し馬を走らせたんだ」
エレンは嬉しくなって、前に跨がっているロロの背中をつつきました。しかしロロは反応しないどころか、触った衝撃で前に突っ伏しました。幼いロロは手綱を握ったまま眠ってしまったのです。エレンは慌ててロロを抱きかかえると、手綱をたぐり寄せて、並走していたオレグに呼びかけました。
「おーい、オレグ! ロロが寝ちゃったんだ。どこかで馬をとめよう」
「僕もそうしたいって思っていたところ。馬ってゆりかごみたいに揺れるんだもの」
お兄さんたち二人はそのまま馬を走らせて、木々のこんもりした場所で止めました。そして眠い目を擦りつつ、なんとかロロを地面に降ろすと、エレンもオレグも草のベッドに倒れ込みました。いろんなところが絞られ、不要と思われる飾りのついた女の子の服は窮屈でしたが、それを脱ぐ気力もありません。実際エレンが気を失う直前に見たのは、スカートがかなり捲れたまま鼾をかきはじめたオレグでした。
あまりに深い眠りについていたので、エレンは最初それが夢かと思いました。しかし寝ぼけ眼のピントが合ってくると、モスグリーンの二つの目がじっと自分を見つめていることが分かってきました。
「ぎゃ!」
エレンは覗き込んでいた相手を突き飛ばしました。いえ、正確には突き飛ばそうとしました。モスグリーンの目、もといその人物がひらりとかわしたので。
「ははは! 女の子なのに随分荒っぽいんだねぇ。嫌いじゃないけど」
モスグリーンの目の持ち主はきゃらきゃら笑い声を立てました。いかにも若者らしい屈託のない人物で、痩せているのにひょろりと背は高く、好奇心旺盛な目がくるくる動きます。さらさらとした髪は光を受けて、自ずから光っているよう。エレンはこの若者がリン王子に違いないと直感的に思いました。ガタイが良くて、もじゃもじゃの毛のヴァイキングとは正反対ですが、だからこそ疎外感を感じて家出したのも頷けます。
エレンはこんなに早く王子に出くわすとは思っていなかったので、どう接するか考えていませんでした。だから自分たちが本当は男の子だということを話していいか、さんざん迷いましたが、結局こう答えることにしました。
「お、男らしいとか、女らしいとか、いまどき流行らないよ」
すると青年は少し目の色を変えました。
「そうだね。悪かったよ。謝る」
気まずい沈黙が一瞬ありましたが、また口を開いたのは青年でした。
「あの子たちは君の連れかい」
青年が指した方を見ると、寝相が悪くて移動するには遠すぎる場所にオレグとロロが寝転んでいます。しかも各々は離れて。
「あれ! あんなに遠くに・・・」
「子どもは寝相が悪いものさ。それより君たち、どうしてここに来たの」
「え、あ、そのぉ・・・道に迷っちゃったんだ」
エレンはオーロフじいさんに聞いた話を頭の中で手繰り寄せました。たしか困っている人には助け船を出すはずです。交換条件がありますが。
「そう。それなら森の出口まで案内しよう。友達をもう起こしてもいいかい」
「ちょっと待って。案内する代わりに何か出せって言うんじゃないの」
エレンは口走ってしまってから、しまった! と思いました。
「え? どうして」
青年は目を細めました。
「み、みんな噂しているだ。森の騎士は乙女の心臓を食べるんだって。あなたがその騎士なんでしょう」
エレンが慌てて取り繕うと、青年はぷっと吹き出しました。
「まさか僕が心臓を食べると本気で思っているの!? ご指摘の通り、片方の森の騎士とは僕のことさ。でも騎士は騎士道を重んじる。助けはしても心臓を食べたりはしないよ」
「でも森の騎士は妖精の女王の弟子なんでしょう。女王に心臓を取ってこいって言われたら断れないんじゃないの」
この青年が話しやすいのでエレンは大胆に聞いてしまいました。なんだかぽろっと重要なことを言いそうです。
「弟子といえば弟子だし、そうでないとも言える。でも誓って僕は何もしてないよ」
「じゃあどうしてそういう噂が立つの」
「うーむ。もしかしたら彼女たちは本気にしちゃったのかもしれないなぁ」
そう言ったきり、青年は考え込んでしまいました。
「本気にするってどういうこと。お兄さんが魔法でひどいことをしてやるって脅したの」
「魔法は使えないよ。でもことばっていうのは、魔法が使えなくても一種の効力を持つものさ。特に相手が気を張っていないときには」
「子どもだから分からないよ」
この感傷的な青年の話し方がエレンは苦手でした。
「退屈だったからちょっとからかったんだ。髪がきれいだねとか、吸い込まれそうな瞳だとか。でも別に本気でいったわけじゃないんだ。本当に」
自分は一生縁がなさそうなクサいセリフばかりだったので、エレンは思わず苦笑しました。
「じゃあ女の子たちが変になったのは、お兄さんに恋したからだって言うんだ?」
「無骨な男たちしか知らないからぼーっとしちゃったのかな」
青年は事も無げに肩をすくめました。
「分かったよ。お兄さんは何もしなかったんだ。でもこんな辺鄙な森になぜいるの。妖精の女王が魔法を教えてくれるわけでもないんでしょう。まさか女の子を泣かせるため?」
「君はなんだか僕を非難しているみたいだけど、僕だってこんな悲しいこと、したくてしているわけじゃないんだ」
「そうなの。でもお兄さんが女の子たちを泣かせていることしか知らないもの」
エレンは敢えて聞きたくないっぽい素振りをしました。こういう面倒くさい人には興味がないふりをするのが近道ですから。すると青年はまんまと罠に嵌って話し始めました。
当時青年は色々と悩みがあって家を飛び出しました。しかし突然思い立ったので行く当てもなく、人のいないこの森でぼんやり過ごすだけの日々が何日か続きました。しかし一人でいるというのは恐ろしいもので、青年はどんどん悪い方に考えるようになりました。そしてついに死ぬことが一番だと考えるようになってしまいました。
そこで青年はある日の夕方、蔦を首に巻いて死んでしまおうとしました。しかし本当は覚悟がなかったので、何度やってもうまくいきません。青年は生きることも死ぬこともできない自分に腹が立ちました。そして目に入った一輪の薔薇を思わず摘み取りました。それは本当に美しい薔薇で、生きることそのものを謳歌している様が憎らしく思えたのです。
しかし薔薇をむしりとってすぐ、どこからともなくただならぬ女の人が現れて、大切な薔薇を手折ったのはあなたか、と聞きました。青年は必死に謝りました。あなたの薔薇とは知らなかった、穴埋めは必ずするから許してほしいと。するとその女は、これはあなたの薔薇で、あなたは自分の命を摘み取ってしまっただけだから、許しを請う必要はないのだ、と言いました。青年は驚いて、自分が死んでしまったのか聞きました。すると女王は意地悪く笑って、お前は死にたいと思っていたのではないのかと言いました。その人はなんでも分かってしまう妖精の女王だったのです。
そこで青年は自分がみんなと違って馴染めないこと、来たるべき責務やドラゴンの試練が怖いのだと告白しました。すると女王は自分がドラゴンから領地を奪ったことを話し、良きに取りはからおうと言いました。もちろん青年は手放しで喜びました。しかし相手は妖精の女王ですから、ただという訳にはいきません。女王は交換条件として、折れてしまった青年の薔薇を欲しいと言いました。そして青年はとっとと薔薇を渡してしまいました。
「あのとき薔薇を渡してしまったのが間違いだったんだ」
青年は両手で顔を覆いました。
「どうして? 薔薇にはもう意味がないんでしょ」
青年の話を聞くために起こされていたオレグが聞きました。
「いや。あれには種があったんだよ」
「種?」
少年たちが顔を見合わせると、青年は話を続けました。それによると、青年の摘んだ薔薇には若い実がなっていました。しかしその実は大地から切り離されてしまったので、中の種は死んではいないけれど成長することができなくなってしまいました。そしてそのせいで青年は年をとらなくなりました。青年は女王に種を返してくれと頼みましたが、もちろん返してはくれませんし、ドラゴンの倒し方を教えてくれる気配も一向にありません。
「ある日妖精たちの歌が聞こえてきたんだ。可哀想な女王の新しい獲物は、命を女王に握られておめおめ逃げることもできぬ、と。僕は大変なことをしてしまった」
「でもいじめられているわけじゃないんでしょ。ここにいれば嫌なこともないし、女王と仲良くやればいいじゃない」
ロロは無邪気に言いました。すると青年は絶望の表情を浮かべていいました。
「君はあの女王の恐ろしさを知らないんだ。あの女王ときたら美への執着がすさまじくて、毎晩水鏡を覗いては世界中の美女を見つけて呪いをかけたり、その恋人をたぶらかしたりして喜んでいる。それに女王は顔こそ綺麗だけど、何百年、いや何千年と生きているから―なにせマグマが冷えてこの島ができる頃にドラゴンからこの地をぶんどったんだぜ―本当はどんな姿かたちをしているのか分かったもんじゃない。実際僕は女王の抱いている子鹿がみるみる老いてしまうのを見たことがある。あの美貌は他の生き物の美しさを吸い取って維持されているんだ。だから女王の歌を聞いたとき、冷や汗が止まらなかった。そろそろ若い人間の血が飲みたい、と彼女は歌っていた」
「ってことは、お兄さんはおじいさんになるの。年をとれるならよかったじゃん・・・かしらん」
オレグは女の子のふりをするのを危うく忘れそうになりましたが、青年はそれに気がつくどころか、ひどく狼狽えて目に涙を浮かばせました。エレンは青年がとても傷つきやすいので、オレグに手加減してほしいなと思いました。
「いきなり老人にされて嬉しいもんか。それに下手をすると、命をすべて吸い取られて死んでしまうかもしれない」
青年は本当に怯えた表情をしました。女の子たちがこの顔にやられたのがなんとなく理解できます。
「だったら種を取り戻せばいいよ。そうしたら元のように年をとることができるんでしょう」
「そうだよ。土に埋めて育てればいいんだ。簡単、簡単!」
オレグとロロはとてもいいことを言ったと満足げです。
「問題はそう簡単じゃない。そもそも種は女王がどこかに隠してしまっているし、仮に見つかったとしてもまた時をすすめるのはほとんど不可能だ」
「でも方法はあるんでしょう。どうすればいいんです、リン王子?」
エレンが思い切って名前で呼びかけると、王子は一瞬モスグリーンの目をくっと見開きました。
「僕たち、あなたを連れ戻すとオーロフじいさんと約束したんです。薔薇の種を取り戻したら一緒に王国へ帰ってくれますね」
王子はガラス玉みたいな目でエレンを見つめると、神経質そうに眉根を寄せて、口を閉ざしてしまいました。しかしやがて覚悟を決めてこう言いました。
「真実の愛と英雄的死。芽を出させるにはこの二つが必要だ」
「真実の愛? それってことはやっぱり・・・恋人にキスしてもらうあれなの」
おませなロロは少し興奮気味に言いました。
「そう思って、この近くを通る女の子にはみんな確認しているけど、まだ見つかってないんだ」
「でもその恋人が見つかったとして、英雄的死っていうのは? もしかしてその人はリンさんのために死なないといけないとか。そんなのってあるかしら?」
オレグは腑に落ちないあまり、もう男の子に戻ったことを忘れてうっかり女の子ことばを使いました。
「本当に僕を愛しているのならそれも厭わないんじゃないかな」
「でもリンさんは、そういう自分の都合というか、下心があってその人を探すわけだよね。それって真実の愛なの」
エレンはこの若者の身勝手さにカチンときました。
「僕を心から愛してくれる人を、僕は愛するさ。でもそんな女の子には会ったことないね。みんな口先では愛してるだの、命を捨ててもいいだの言うけど、事情を話した途端、気の間違いだったとか、あなたには他に運命の相手がいるわとか言って、連絡がつかなくなる。まったく世の中欺瞞に満ちているよ」
「でもリンさんが逆の立場だったら、その人のために命を投げ出せるの。できないでしょ」
リンの発言にはいちいち引っかかるところがあるので、エレンはことあるごとに釘を刺すようになっていました。
「まさか。もちろんお断りさ。だってそんな理由で僕に近づくなんて真実の愛じゃないだろ」
それでは女性たちも同じ理由でお断りですよ、ということばが出かけましたが、エレンはぐっと我慢して話題を変えました。
「それより薔薇の種の在処に心当たりはないの。妖精の女王の隠しそうなところとか」
「実は僕も何度か探してみたんだけど、探すところが多すぎて。なにしろこの片方の森すべてが妖精の女王の住処だからね。なにかヒントがないと、とても見つからないよ」
リンによれば、妖精の女王は、昼は小川のそばの妖精岩の陰で眠り、日が暮れるとそのとき森で一番美しい場所に現れて宴をひらきます。そこには妖精たちとリンが集って、豪華な食事や甘美な酒を楽しんだり、歌ったり踊ったりします。しかし月がその夜の一番高いところまで昇ると、響宴のさなか妖精の女王はひとりどこかに消えてしまいます。リンは女王がどこへ行くのか知りたいのですが、そう思ったときには身体がだるくなっていて、やがて眠りに落ちてしまいます。そして目が覚めたときには朝日が昇り、妖精たちも豪華な宴も跡形もなく消えている―それが毎日続くそうなのです。だから女王が薔薇の種をどこに隠したのか、リンにはまったく分かりませんでした。けれどもこのまま手をこまねいているわけにもいきません。エレンたちはひとまず森の中を探すことにしました。
「ロロ! もうすぐ日の出だよ。僕たち、夜通し馬を走らせたんだ」
エレンは嬉しくなって、前に跨がっているロロの背中をつつきました。しかしロロは反応しないどころか、触った衝撃で前に突っ伏しました。幼いロロは手綱を握ったまま眠ってしまったのです。エレンは慌ててロロを抱きかかえると、手綱をたぐり寄せて、並走していたオレグに呼びかけました。
「おーい、オレグ! ロロが寝ちゃったんだ。どこかで馬をとめよう」
「僕もそうしたいって思っていたところ。馬ってゆりかごみたいに揺れるんだもの」
お兄さんたち二人はそのまま馬を走らせて、木々のこんもりした場所で止めました。そして眠い目を擦りつつ、なんとかロロを地面に降ろすと、エレンもオレグも草のベッドに倒れ込みました。いろんなところが絞られ、不要と思われる飾りのついた女の子の服は窮屈でしたが、それを脱ぐ気力もありません。実際エレンが気を失う直前に見たのは、スカートがかなり捲れたまま鼾をかきはじめたオレグでした。
あまりに深い眠りについていたので、エレンは最初それが夢かと思いました。しかし寝ぼけ眼のピントが合ってくると、モスグリーンの二つの目がじっと自分を見つめていることが分かってきました。
「ぎゃ!」
エレンは覗き込んでいた相手を突き飛ばしました。いえ、正確には突き飛ばそうとしました。モスグリーンの目、もといその人物がひらりとかわしたので。
「ははは! 女の子なのに随分荒っぽいんだねぇ。嫌いじゃないけど」
モスグリーンの目の持ち主はきゃらきゃら笑い声を立てました。いかにも若者らしい屈託のない人物で、痩せているのにひょろりと背は高く、好奇心旺盛な目がくるくる動きます。さらさらとした髪は光を受けて、自ずから光っているよう。エレンはこの若者がリン王子に違いないと直感的に思いました。ガタイが良くて、もじゃもじゃの毛のヴァイキングとは正反対ですが、だからこそ疎外感を感じて家出したのも頷けます。
エレンはこんなに早く王子に出くわすとは思っていなかったので、どう接するか考えていませんでした。だから自分たちが本当は男の子だということを話していいか、さんざん迷いましたが、結局こう答えることにしました。
「お、男らしいとか、女らしいとか、いまどき流行らないよ」
すると青年は少し目の色を変えました。
「そうだね。悪かったよ。謝る」
気まずい沈黙が一瞬ありましたが、また口を開いたのは青年でした。
「あの子たちは君の連れかい」
青年が指した方を見ると、寝相が悪くて移動するには遠すぎる場所にオレグとロロが寝転んでいます。しかも各々は離れて。
「あれ! あんなに遠くに・・・」
「子どもは寝相が悪いものさ。それより君たち、どうしてここに来たの」
「え、あ、そのぉ・・・道に迷っちゃったんだ」
エレンはオーロフじいさんに聞いた話を頭の中で手繰り寄せました。たしか困っている人には助け船を出すはずです。交換条件がありますが。
「そう。それなら森の出口まで案内しよう。友達をもう起こしてもいいかい」
「ちょっと待って。案内する代わりに何か出せって言うんじゃないの」
エレンは口走ってしまってから、しまった! と思いました。
「え? どうして」
青年は目を細めました。
「み、みんな噂しているだ。森の騎士は乙女の心臓を食べるんだって。あなたがその騎士なんでしょう」
エレンが慌てて取り繕うと、青年はぷっと吹き出しました。
「まさか僕が心臓を食べると本気で思っているの!? ご指摘の通り、片方の森の騎士とは僕のことさ。でも騎士は騎士道を重んじる。助けはしても心臓を食べたりはしないよ」
「でも森の騎士は妖精の女王の弟子なんでしょう。女王に心臓を取ってこいって言われたら断れないんじゃないの」
この青年が話しやすいのでエレンは大胆に聞いてしまいました。なんだかぽろっと重要なことを言いそうです。
「弟子といえば弟子だし、そうでないとも言える。でも誓って僕は何もしてないよ」
「じゃあどうしてそういう噂が立つの」
「うーむ。もしかしたら彼女たちは本気にしちゃったのかもしれないなぁ」
そう言ったきり、青年は考え込んでしまいました。
「本気にするってどういうこと。お兄さんが魔法でひどいことをしてやるって脅したの」
「魔法は使えないよ。でもことばっていうのは、魔法が使えなくても一種の効力を持つものさ。特に相手が気を張っていないときには」
「子どもだから分からないよ」
この感傷的な青年の話し方がエレンは苦手でした。
「退屈だったからちょっとからかったんだ。髪がきれいだねとか、吸い込まれそうな瞳だとか。でも別に本気でいったわけじゃないんだ。本当に」
自分は一生縁がなさそうなクサいセリフばかりだったので、エレンは思わず苦笑しました。
「じゃあ女の子たちが変になったのは、お兄さんに恋したからだって言うんだ?」
「無骨な男たちしか知らないからぼーっとしちゃったのかな」
青年は事も無げに肩をすくめました。
「分かったよ。お兄さんは何もしなかったんだ。でもこんな辺鄙な森になぜいるの。妖精の女王が魔法を教えてくれるわけでもないんでしょう。まさか女の子を泣かせるため?」
「君はなんだか僕を非難しているみたいだけど、僕だってこんな悲しいこと、したくてしているわけじゃないんだ」
「そうなの。でもお兄さんが女の子たちを泣かせていることしか知らないもの」
エレンは敢えて聞きたくないっぽい素振りをしました。こういう面倒くさい人には興味がないふりをするのが近道ですから。すると青年はまんまと罠に嵌って話し始めました。
当時青年は色々と悩みがあって家を飛び出しました。しかし突然思い立ったので行く当てもなく、人のいないこの森でぼんやり過ごすだけの日々が何日か続きました。しかし一人でいるというのは恐ろしいもので、青年はどんどん悪い方に考えるようになりました。そしてついに死ぬことが一番だと考えるようになってしまいました。
そこで青年はある日の夕方、蔦を首に巻いて死んでしまおうとしました。しかし本当は覚悟がなかったので、何度やってもうまくいきません。青年は生きることも死ぬこともできない自分に腹が立ちました。そして目に入った一輪の薔薇を思わず摘み取りました。それは本当に美しい薔薇で、生きることそのものを謳歌している様が憎らしく思えたのです。
しかし薔薇をむしりとってすぐ、どこからともなくただならぬ女の人が現れて、大切な薔薇を手折ったのはあなたか、と聞きました。青年は必死に謝りました。あなたの薔薇とは知らなかった、穴埋めは必ずするから許してほしいと。するとその女は、これはあなたの薔薇で、あなたは自分の命を摘み取ってしまっただけだから、許しを請う必要はないのだ、と言いました。青年は驚いて、自分が死んでしまったのか聞きました。すると女王は意地悪く笑って、お前は死にたいと思っていたのではないのかと言いました。その人はなんでも分かってしまう妖精の女王だったのです。
そこで青年は自分がみんなと違って馴染めないこと、来たるべき責務やドラゴンの試練が怖いのだと告白しました。すると女王は自分がドラゴンから領地を奪ったことを話し、良きに取りはからおうと言いました。もちろん青年は手放しで喜びました。しかし相手は妖精の女王ですから、ただという訳にはいきません。女王は交換条件として、折れてしまった青年の薔薇を欲しいと言いました。そして青年はとっとと薔薇を渡してしまいました。
「あのとき薔薇を渡してしまったのが間違いだったんだ」
青年は両手で顔を覆いました。
「どうして? 薔薇にはもう意味がないんでしょ」
青年の話を聞くために起こされていたオレグが聞きました。
「いや。あれには種があったんだよ」
「種?」
少年たちが顔を見合わせると、青年は話を続けました。それによると、青年の摘んだ薔薇には若い実がなっていました。しかしその実は大地から切り離されてしまったので、中の種は死んではいないけれど成長することができなくなってしまいました。そしてそのせいで青年は年をとらなくなりました。青年は女王に種を返してくれと頼みましたが、もちろん返してはくれませんし、ドラゴンの倒し方を教えてくれる気配も一向にありません。
「ある日妖精たちの歌が聞こえてきたんだ。可哀想な女王の新しい獲物は、命を女王に握られておめおめ逃げることもできぬ、と。僕は大変なことをしてしまった」
「でもいじめられているわけじゃないんでしょ。ここにいれば嫌なこともないし、女王と仲良くやればいいじゃない」
ロロは無邪気に言いました。すると青年は絶望の表情を浮かべていいました。
「君はあの女王の恐ろしさを知らないんだ。あの女王ときたら美への執着がすさまじくて、毎晩水鏡を覗いては世界中の美女を見つけて呪いをかけたり、その恋人をたぶらかしたりして喜んでいる。それに女王は顔こそ綺麗だけど、何百年、いや何千年と生きているから―なにせマグマが冷えてこの島ができる頃にドラゴンからこの地をぶんどったんだぜ―本当はどんな姿かたちをしているのか分かったもんじゃない。実際僕は女王の抱いている子鹿がみるみる老いてしまうのを見たことがある。あの美貌は他の生き物の美しさを吸い取って維持されているんだ。だから女王の歌を聞いたとき、冷や汗が止まらなかった。そろそろ若い人間の血が飲みたい、と彼女は歌っていた」
「ってことは、お兄さんはおじいさんになるの。年をとれるならよかったじゃん・・・かしらん」
オレグは女の子のふりをするのを危うく忘れそうになりましたが、青年はそれに気がつくどころか、ひどく狼狽えて目に涙を浮かばせました。エレンは青年がとても傷つきやすいので、オレグに手加減してほしいなと思いました。
「いきなり老人にされて嬉しいもんか。それに下手をすると、命をすべて吸い取られて死んでしまうかもしれない」
青年は本当に怯えた表情をしました。女の子たちがこの顔にやられたのがなんとなく理解できます。
「だったら種を取り戻せばいいよ。そうしたら元のように年をとることができるんでしょう」
「そうだよ。土に埋めて育てればいいんだ。簡単、簡単!」
オレグとロロはとてもいいことを言ったと満足げです。
「問題はそう簡単じゃない。そもそも種は女王がどこかに隠してしまっているし、仮に見つかったとしてもまた時をすすめるのはほとんど不可能だ」
「でも方法はあるんでしょう。どうすればいいんです、リン王子?」
エレンが思い切って名前で呼びかけると、王子は一瞬モスグリーンの目をくっと見開きました。
「僕たち、あなたを連れ戻すとオーロフじいさんと約束したんです。薔薇の種を取り戻したら一緒に王国へ帰ってくれますね」
王子はガラス玉みたいな目でエレンを見つめると、神経質そうに眉根を寄せて、口を閉ざしてしまいました。しかしやがて覚悟を決めてこう言いました。
「真実の愛と英雄的死。芽を出させるにはこの二つが必要だ」
「真実の愛? それってことはやっぱり・・・恋人にキスしてもらうあれなの」
おませなロロは少し興奮気味に言いました。
「そう思って、この近くを通る女の子にはみんな確認しているけど、まだ見つかってないんだ」
「でもその恋人が見つかったとして、英雄的死っていうのは? もしかしてその人はリンさんのために死なないといけないとか。そんなのってあるかしら?」
オレグは腑に落ちないあまり、もう男の子に戻ったことを忘れてうっかり女の子ことばを使いました。
「本当に僕を愛しているのならそれも厭わないんじゃないかな」
「でもリンさんは、そういう自分の都合というか、下心があってその人を探すわけだよね。それって真実の愛なの」
エレンはこの若者の身勝手さにカチンときました。
「僕を心から愛してくれる人を、僕は愛するさ。でもそんな女の子には会ったことないね。みんな口先では愛してるだの、命を捨ててもいいだの言うけど、事情を話した途端、気の間違いだったとか、あなたには他に運命の相手がいるわとか言って、連絡がつかなくなる。まったく世の中欺瞞に満ちているよ」
「でもリンさんが逆の立場だったら、その人のために命を投げ出せるの。できないでしょ」
リンの発言にはいちいち引っかかるところがあるので、エレンはことあるごとに釘を刺すようになっていました。
「まさか。もちろんお断りさ。だってそんな理由で僕に近づくなんて真実の愛じゃないだろ」
それでは女性たちも同じ理由でお断りですよ、ということばが出かけましたが、エレンはぐっと我慢して話題を変えました。
「それより薔薇の種の在処に心当たりはないの。妖精の女王の隠しそうなところとか」
「実は僕も何度か探してみたんだけど、探すところが多すぎて。なにしろこの片方の森すべてが妖精の女王の住処だからね。なにかヒントがないと、とても見つからないよ」
リンによれば、妖精の女王は、昼は小川のそばの妖精岩の陰で眠り、日が暮れるとそのとき森で一番美しい場所に現れて宴をひらきます。そこには妖精たちとリンが集って、豪華な食事や甘美な酒を楽しんだり、歌ったり踊ったりします。しかし月がその夜の一番高いところまで昇ると、響宴のさなか妖精の女王はひとりどこかに消えてしまいます。リンは女王がどこへ行くのか知りたいのですが、そう思ったときには身体がだるくなっていて、やがて眠りに落ちてしまいます。そして目が覚めたときには朝日が昇り、妖精たちも豪華な宴も跡形もなく消えている―それが毎日続くそうなのです。だから女王が薔薇の種をどこに隠したのか、リンにはまったく分かりませんでした。けれどもこのまま手をこまねいているわけにもいきません。エレンたちはひとまず森の中を探すことにしました。
0
あなたにおすすめの小説

独占欲強めの最強な不良さん、溺愛は盲目なほど。
猫菜こん
児童書・童話
小さな頃から、巻き込まれで絡まれ体質の私。
中学生になって、もう巻き込まれないようにひっそり暮らそう!
そう意気込んでいたのに……。
「可愛すぎる。もっと抱きしめさせてくれ。」
私、最強の不良さんに見初められちゃったみたいです。
巻き込まれ体質の不憫な中学生
ふわふわしているけど、しっかりした芯の持ち主
咲城和凜(さきしろかりん)
×
圧倒的な力とセンスを持つ、負け知らずの最強不良
和凜以外に容赦がない
天狼絆那(てんろうきずな)
些細な事だったのに、どうしてか私にくっつくイケメンさん。
彼曰く、私に一目惚れしたらしく……?
「おい、俺の和凜に何しやがる。」
「お前が無事なら、もうそれでいい……っ。」
「この世に存在している言葉だけじゃ表せないくらい、愛している。」
王道で溺愛、甘すぎる恋物語。
最強不良さんの溺愛は、独占的で盲目的。

笑いの授業
ひろみ透夏
児童書・童話
大好きだった先先が別人のように変わってしまった。
文化祭前夜に突如始まった『笑いの授業』――。
それは身の毛もよだつほどに怖ろしく凄惨な課外授業だった。
伏線となる【神楽坂の章】から急展開する【高城の章】。
追い詰められた《神楽坂先生》が起こした教師としてありえない行動と、その真意とは……。

あだ名が242個ある男(実はこれ実話なんですよ25)
tomoharu
児童書・童話
え?こんな話絶対ありえない!作り話でしょと思うような話からあるある話まで幅広い範囲で物語を考えました!ぜひ読んでみてください!数年後には大ヒット間違いなし!!
作品情報【伝説の物語(都道府県問題)】【伝説の話題(あだ名とコミュニケーションアプリ)】【マーライオン】【愛学両道】【やりすぎヒーロー伝説&ドリームストーリー】【トモレオ突破椿】など
・【やりすぎヒーロー伝説&ドリームストーリー】とは、その話はさすがに言いすぎでしょと言われているほぼ実話ストーリーです。
小さい頃から今まで主人公である【紘】はどのような体験をしたのかがわかります。ぜひよんでくださいね!
・【トモレオ突破椿】は、公務員試験合格なおかつ様々な問題を解決させる話です。
頭の悪かった人でも公務員になれることを証明させる話でもあるので、ぜひ読んでみてください!
特別記念として実話を元に作った【呪われし◯◯シリーズ】も公開します!
トランプ男と呼ばれている切札勝が、トランプゲームに例えて次々と問題を解決していく【トランプ男】シリーズも大人気!
人気者になるために、ウソばかりついて周りの人を誘導し、すべて自分のものにしようとするウソヒコをガチヒコが止める【嘘つきは、嘘治の始まり】というホラーサスペンスミステリー小説

かつて聖女は悪女と呼ばれていた
朔雲みう (さくもみう)
児童書・童話
「別に計算していたわけではないのよ」
この聖女、悪女よりもタチが悪い!?
悪魔の力で聖女に成り代わった悪女は、思い知ることになる。聖女がいかに優秀であったのかを――!!
聖女が華麗にざまぁします♪
※ エブリスタさんの妄コン『変身』にて、大賞をいただきました……!!✨
※ 悪女視点と聖女視点があります。
※ 表紙絵は親友の朝美智晴さまに描いていただきました♪

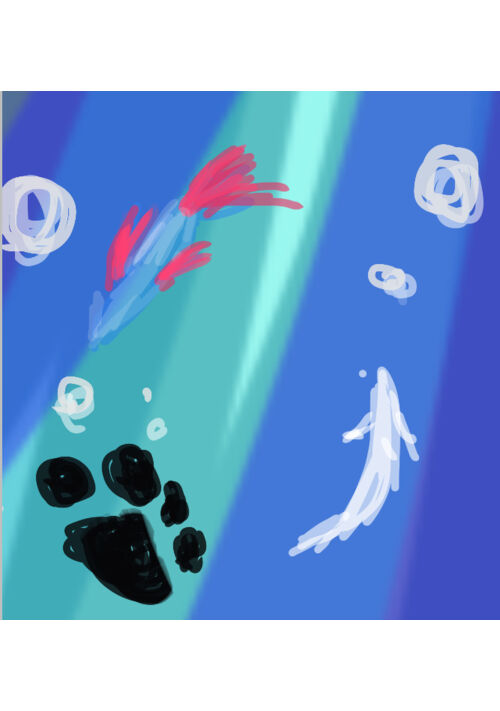
25匹の魚と猫と
ねこ沢ふたよ
児童書・童話
コメディです。
短編です。
暴虐無人の猫に一泡吹かせようと、水槽のメダカとグッピーが考えます。
何も考えずに笑って下さい
※クラムボンは笑いません
25周年おめでとうございます。
Copyright©︎

生贄姫の末路 【完結】
松林ナオ
児童書・童話
水の豊かな国の王様と魔物は、はるか昔にある契約を交わしました。
それは、姫を生贄に捧げる代わりに国へ繁栄をもたらすというものです。
水の豊かな国には双子のお姫様がいます。
ひとりは金色の髪をもつ、活発で愛らしい金のお姫様。
もうひとりは銀色の髪をもつ、表情が乏しく物静かな銀のお姫様。
王様が生贄に選んだのは、銀のお姫様でした。

14歳で定年ってマジ!? 世界を変えた少年漫画家、再起のノート
谷川 雅
児童書・童話
この世界、子どもがエリート。
“スーパーチャイルド制度”によって、能力のピークは12歳。
そして14歳で、まさかの《定年》。
6歳の星野幸弘は、将来の夢「世界を笑顔にする漫画家」を目指して全力疾走する。
だけど、定年まで残された時間はわずか8年……!
――そして14歳。夢は叶わぬまま、制度に押し流されるように“退場”を迎える。
だが、そんな幸弘の前に現れたのは、
「まちがえた人間」のノートが集まる、不思議な図書室だった。
これは、間違えたままじゃ終われなかった少年たちの“再スタート”の物語。
描けなかった物語の“つづき”は、きっと君の手の中にある。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















