10 / 73
第一章 目覚めたら吸血鬼……!?
10、私を召し上がって下さい
しおりを挟む
「目が覚めたか?」
「すみません、フォルネウス様……私……とんだご無礼を……」
「気にするな。俺が急かしすぎたせいだ。無理をさせて悪かった。ほら、すぐに用意しよう」
「待ってください」
袖口をまくりあげ、自身の腕を傷付けようとしたフォルネウス様を、私は慌てて止めた。
「何故、私にそこまで優しくして下さるのですか?」
いくら責任からとはいえ、皇太子であるフォルネウス様が毎晩私の元へ自ら赴き、血を分け与える必要はないはずだ。
「栄養を取るだけなら、あの錠剤を頂ければ十分です。フォルネウス様は、そうされているのですよね?」
「俺は血が苦手なのだ。だからそうしている」
血が苦手な者でも飲める薬があるのなら、それを私に与えていれば済むだけの話なのだ。しかしそれを止めさせて、フォルネウス様は毎晩血を分け与えてくれる。
その理由を、私は知りたかった。それを知れば、自分にもできる事があるのではないかと思ったから。
「でもあの時、『わかさま』は私の血を美味しいと仰って下さいました」
「……っ、俺のことを、覚えていたのか?」
「最初は気付きませんでした。でも皆さんがフォルネウス様の事を『若様』と呼んでいらっしゃるのを聞いて、もしかしたらと思ったんです」
昔、森で迷子になっていた吸血鬼の事を思い出した。綺麗な顔立ちをしたその少年は、確かに自分の血を美味しいと飲んでくれた。
「あの時、アリシアに助けられていなかったら俺はきっと、今ここには居なかっただろう。君は俺の命の恩人なんだ。だから今度は俺が君を助けたい。そんな理由では、だめか?」
「だめじゃないです。ですがフォルネウス様だって、私を助けて下さいました。貴方は私の命の恩人です。だからこそ、私ばかり与えてもらうばかりなのは心苦しいのです」
「アリシア……」
「そこで一つ提案があります。フォルネウス様。お腹が空いたらこれからは、私の血も飲んで頂けませんか?」
今の私が出来る事と言えば、それくらいしか思い付かなかった。もしあの時の言葉がお世辞だったとしたら、その願いはすぐさま取り消そうと思っていた。
「よ、良いのか?!」
しかしまるで少年のように瞳をキラキラと輝かせてそう言われてしまえば、お世辞ではなかったのだと容易に想像はつく。
「はい、勿論です」
その時、きゅーっとしまりない音がフォルネウス様のお腹から鳴った。恥ずかしそうに、フォルネウス様は頬をポリポリと掻いておられる。
「よかったら、いまお召し上がりください」
自身の来ているドレスの襟元を緩めて、フォルネウス様に食すよう促す。
「本当に、良いのか?」
「はい。お手本を見せて頂けると、参考になりますので」
「そうか。なら、頂くぞ」
ベッドの上で私を抱き寄せたフォルネウス様は、首筋にそっと口付けた。
不思議なことに、牙を突き立てられ血を吸われているにも関わらず、少しも痛みを感じなかった。それどころか、心地のよい夢の中に居るような錯覚を感じていた。
あの時吸血鬼襲われた時は、恐怖と気持ち悪さで震える事しか出来なかった。
けれど今は、ふわふわして温かい。
フォルネウス様の吐息が肌に触れる度に、くすぐったいのに嫌な感じは全然しなくて、むしろ心地良い
耳元で聞こえる嚥下音を聞く度に、何故か胸がドキドキする。
血を吸い終ったフォルネウス様が、噛みついた傷口をなめると綺麗にその傷が塞がった。
「アリシア?」
ボーッとして夢見心地な私を、フォルネウス様が心配そうに見ていらっしゃった。
「はっ、もう終ったのですか?」
「ああ。とても美味かった」
「フォルネウス様。全然、痛くなかったんです!」
「吸血鬼の牙には、痛みを感じさせないよう催眠効果があるのだ。そして唾液には、傷口を素早く治す効果がある。きっとそのおかげであろう」
「それでしたら、私がフォルネウス様の血を直接頂いても、痛くはないのですか?」
「ああ、もちろんだ。試してみるか?」
「はい!」
噛んで傷付けると、相手は痛いのだと思っていた。しかし、実際に噛まれて感じたのは心地の良い刺激だった。
フォルネウス様の白い首筋に、さっきより強めに牙を突き立てる。
ドキドキと高鳴る心臓の音が、フォルネウス様に聞こえてしまいそうで恥ずかしい。でも我慢だ。これが正しい食事のマナーなんだからと自分に言い聞かせる。
牙を抜いてそっと血を啜る。
口の中いっぱいに広がった芳醇で濃厚なその味は、今まで腕から頂いていたものより何倍も美味しく感じた。
甘美な血の味を堪能した後、そっと傷口を舐める。すると小さく空いていた二つの穴は綺麗に塞がった。
「ご馳走さまでした。とても美味しかったです」
最上級のご馳走を堪能した私は、お礼を言ってフォルネウス様から離れた。
「何だか、照れますね」
「そ、そうだな」
改めてさっきの行動を思い出すと、顔から火が出そうなくらい恥ずかしくなった。
でも、これが吸血鬼としての食事のマナーなのだ。慣れるしかない、慣れるしか!
「ありがとう、アリシア。久しぶりに、こんなに美味い食事をとった」
フォルネウス様はずっと、あの錠剤しか摂取されていなかったのよね。不味い血を飲み続けるよりは、味のしない錠剤の方がよかった。けれど美味しいものを食べた時の幸せを感じられないのは、寂しいし辛いものがある。
「お役に立てたのなら光栄です。フォルネウス様、これからは遠慮なく私を召し上がって下さいね!」
「本当に、良いのか?」
「フォルネウス様が私の血を美味しく感じてくださる限り、構いませんよ。でももし不味いと感じたら、すぐに教えて下さいね? 我慢して飲んでいただくのは嫌です……」
恩義のせいで変に遠慮されて言い出しづらいなんて事になったら申し訳ないから、そこはきちんと伝えておかないと!
「むしろその逆で、俺はいつも君を食べたい欲求を我慢してたくらいだ。だからあまり、可愛い事を言ってくれるな。一生手放せなくなってしまいそうだ」
フォルネウス様はそう言って、照れたみたいに顔を背けてしまわれた。
「美味しい食事をとると、幸せな気分になれます。フォルネウス様は今までたくさん我慢されてきた分、少しくらい欲張ってもいいと思うんです。だからフォルネウス様がお腹いっぱい味わえるように、私頑張って大きくなります!」
「大きく?」
「だって体を大きくすれば、もっと遠慮なく飲めるようになりますよね? 今から身長は伸びないかもしれませんが、体を鍛えて筋肉をつけます!」
「くっ、ははは! アリシア……その気持ちだけで、俺は嬉しいよ。ありがとう」
何故か物凄く優しい顔をしたフォルネウス様に、頭をよしよしと撫でられてしまった。
私、本気ですよ? 冗談じゃありませんからね?!
「すみません、フォルネウス様……私……とんだご無礼を……」
「気にするな。俺が急かしすぎたせいだ。無理をさせて悪かった。ほら、すぐに用意しよう」
「待ってください」
袖口をまくりあげ、自身の腕を傷付けようとしたフォルネウス様を、私は慌てて止めた。
「何故、私にそこまで優しくして下さるのですか?」
いくら責任からとはいえ、皇太子であるフォルネウス様が毎晩私の元へ自ら赴き、血を分け与える必要はないはずだ。
「栄養を取るだけなら、あの錠剤を頂ければ十分です。フォルネウス様は、そうされているのですよね?」
「俺は血が苦手なのだ。だからそうしている」
血が苦手な者でも飲める薬があるのなら、それを私に与えていれば済むだけの話なのだ。しかしそれを止めさせて、フォルネウス様は毎晩血を分け与えてくれる。
その理由を、私は知りたかった。それを知れば、自分にもできる事があるのではないかと思ったから。
「でもあの時、『わかさま』は私の血を美味しいと仰って下さいました」
「……っ、俺のことを、覚えていたのか?」
「最初は気付きませんでした。でも皆さんがフォルネウス様の事を『若様』と呼んでいらっしゃるのを聞いて、もしかしたらと思ったんです」
昔、森で迷子になっていた吸血鬼の事を思い出した。綺麗な顔立ちをしたその少年は、確かに自分の血を美味しいと飲んでくれた。
「あの時、アリシアに助けられていなかったら俺はきっと、今ここには居なかっただろう。君は俺の命の恩人なんだ。だから今度は俺が君を助けたい。そんな理由では、だめか?」
「だめじゃないです。ですがフォルネウス様だって、私を助けて下さいました。貴方は私の命の恩人です。だからこそ、私ばかり与えてもらうばかりなのは心苦しいのです」
「アリシア……」
「そこで一つ提案があります。フォルネウス様。お腹が空いたらこれからは、私の血も飲んで頂けませんか?」
今の私が出来る事と言えば、それくらいしか思い付かなかった。もしあの時の言葉がお世辞だったとしたら、その願いはすぐさま取り消そうと思っていた。
「よ、良いのか?!」
しかしまるで少年のように瞳をキラキラと輝かせてそう言われてしまえば、お世辞ではなかったのだと容易に想像はつく。
「はい、勿論です」
その時、きゅーっとしまりない音がフォルネウス様のお腹から鳴った。恥ずかしそうに、フォルネウス様は頬をポリポリと掻いておられる。
「よかったら、いまお召し上がりください」
自身の来ているドレスの襟元を緩めて、フォルネウス様に食すよう促す。
「本当に、良いのか?」
「はい。お手本を見せて頂けると、参考になりますので」
「そうか。なら、頂くぞ」
ベッドの上で私を抱き寄せたフォルネウス様は、首筋にそっと口付けた。
不思議なことに、牙を突き立てられ血を吸われているにも関わらず、少しも痛みを感じなかった。それどころか、心地のよい夢の中に居るような錯覚を感じていた。
あの時吸血鬼襲われた時は、恐怖と気持ち悪さで震える事しか出来なかった。
けれど今は、ふわふわして温かい。
フォルネウス様の吐息が肌に触れる度に、くすぐったいのに嫌な感じは全然しなくて、むしろ心地良い
耳元で聞こえる嚥下音を聞く度に、何故か胸がドキドキする。
血を吸い終ったフォルネウス様が、噛みついた傷口をなめると綺麗にその傷が塞がった。
「アリシア?」
ボーッとして夢見心地な私を、フォルネウス様が心配そうに見ていらっしゃった。
「はっ、もう終ったのですか?」
「ああ。とても美味かった」
「フォルネウス様。全然、痛くなかったんです!」
「吸血鬼の牙には、痛みを感じさせないよう催眠効果があるのだ。そして唾液には、傷口を素早く治す効果がある。きっとそのおかげであろう」
「それでしたら、私がフォルネウス様の血を直接頂いても、痛くはないのですか?」
「ああ、もちろんだ。試してみるか?」
「はい!」
噛んで傷付けると、相手は痛いのだと思っていた。しかし、実際に噛まれて感じたのは心地の良い刺激だった。
フォルネウス様の白い首筋に、さっきより強めに牙を突き立てる。
ドキドキと高鳴る心臓の音が、フォルネウス様に聞こえてしまいそうで恥ずかしい。でも我慢だ。これが正しい食事のマナーなんだからと自分に言い聞かせる。
牙を抜いてそっと血を啜る。
口の中いっぱいに広がった芳醇で濃厚なその味は、今まで腕から頂いていたものより何倍も美味しく感じた。
甘美な血の味を堪能した後、そっと傷口を舐める。すると小さく空いていた二つの穴は綺麗に塞がった。
「ご馳走さまでした。とても美味しかったです」
最上級のご馳走を堪能した私は、お礼を言ってフォルネウス様から離れた。
「何だか、照れますね」
「そ、そうだな」
改めてさっきの行動を思い出すと、顔から火が出そうなくらい恥ずかしくなった。
でも、これが吸血鬼としての食事のマナーなのだ。慣れるしかない、慣れるしか!
「ありがとう、アリシア。久しぶりに、こんなに美味い食事をとった」
フォルネウス様はずっと、あの錠剤しか摂取されていなかったのよね。不味い血を飲み続けるよりは、味のしない錠剤の方がよかった。けれど美味しいものを食べた時の幸せを感じられないのは、寂しいし辛いものがある。
「お役に立てたのなら光栄です。フォルネウス様、これからは遠慮なく私を召し上がって下さいね!」
「本当に、良いのか?」
「フォルネウス様が私の血を美味しく感じてくださる限り、構いませんよ。でももし不味いと感じたら、すぐに教えて下さいね? 我慢して飲んでいただくのは嫌です……」
恩義のせいで変に遠慮されて言い出しづらいなんて事になったら申し訳ないから、そこはきちんと伝えておかないと!
「むしろその逆で、俺はいつも君を食べたい欲求を我慢してたくらいだ。だからあまり、可愛い事を言ってくれるな。一生手放せなくなってしまいそうだ」
フォルネウス様はそう言って、照れたみたいに顔を背けてしまわれた。
「美味しい食事をとると、幸せな気分になれます。フォルネウス様は今までたくさん我慢されてきた分、少しくらい欲張ってもいいと思うんです。だからフォルネウス様がお腹いっぱい味わえるように、私頑張って大きくなります!」
「大きく?」
「だって体を大きくすれば、もっと遠慮なく飲めるようになりますよね? 今から身長は伸びないかもしれませんが、体を鍛えて筋肉をつけます!」
「くっ、ははは! アリシア……その気持ちだけで、俺は嬉しいよ。ありがとう」
何故か物凄く優しい顔をしたフォルネウス様に、頭をよしよしと撫でられてしまった。
私、本気ですよ? 冗談じゃありませんからね?!
7
あなたにおすすめの小説

【完結】赤ちゃんが生まれたら殺されるようです
白崎りか
恋愛
もうすぐ赤ちゃんが生まれる。
ドレスの上から、ふくらんだお腹をなでる。
「はやく出ておいで。私の赤ちゃん」
ある日、アリシアは見てしまう。
夫が、ベッドの上で、メイドと口づけをしているのを!
「どうして、メイドのお腹にも、赤ちゃんがいるの?!」
「赤ちゃんが生まれたら、私は殺されるの?」
夫とメイドは、アリシアの殺害を計画していた。
自分たちの子供を跡継ぎにして、辺境伯家を乗っ取ろうとしているのだ。
ドラゴンの力で、前世の記憶を取り戻したアリシアは、自由を手に入れるために裁判で戦う。
※1話と2話は短編版と内容は同じですが、設定を少し変えています。

存在感のない聖女が姿を消した後 [完]
風龍佳乃
恋愛
聖女であるディアターナは
永く仕えた国を捨てた。
何故って?
それは新たに現れた聖女が
ヒロインだったから。
ディアターナは
いつの日からか新聖女と比べられ
人々の心が離れていった事を悟った。
もう私の役目は終わったわ…
神託を受けたディアターナは
手紙を残して消えた。
残された国は天災に見舞われ
てしまった。
しかし聖女は戻る事はなかった。
ディアターナは西帝国にて
初代聖女のコリーアンナに出会い
運命を切り開いて
自分自身の幸せをみつけるのだった。

「がっかりです」——その一言で終わる夫婦が、王宮にはある
柴田はつみ
恋愛
妃の席を踏みにじったのは令嬢——けれど妃の心を折ったのは、夫のたった一言だった
王太子妃リディアの唯一の安らぎは、王太子アーヴィンと交わす午後の茶会。だが新しく王宮に出入りする伯爵令嬢ミレーユは、妃の席に先に座り、殿下を私的に呼び、距離感のない振る舞いを重ねる。
リディアは王宮の礼節としてその場で正す——正しいはずだった。けれど夫は「リディア、そこまで言わなくても……」と、妃を止めた。
「わかりました。あなたには、がっかりです」
微笑んで去ったその日から、夫婦の茶会は終わる。沈黙の王宮で、言葉を失った王太子は、初めて“追う”ことを選ぶが——遅すぎた。
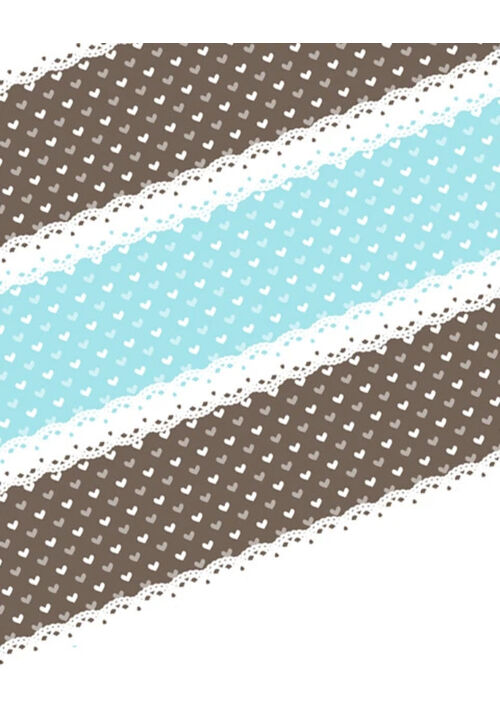
【完結】「私は善意に殺された」
まほりろ
恋愛
筆頭公爵家の娘である私が、母親は身分が低い王太子殿下の後ろ盾になるため、彼の婚約者になるのは自然な流れだった。
誰もが私が王太子妃になると信じて疑わなかった。
私も殿下と婚約してから一度も、彼との結婚を疑ったことはない。
だが殿下が病に倒れ、その治療のため異世界から聖女が召喚され二人が愛し合ったことで……全ての運命が狂い出す。
どなたにも悪意はなかった……私が不運な星の下に生まれた……ただそれだけ。
※無断転載を禁止します。
※朗読動画の無断配信も禁止します。
※他サイトにも投稿中。
※表紙素材はあぐりりんこ様よりお借りしております。
「Copyright(C)2022-九頭竜坂まほろん」
※小説家になろうにて2022年11月19日昼、日間異世界恋愛ランキング38位、総合59位まで上がった作品です!

五年後、元夫の後悔が遅すぎる。~娘が「パパ」と呼びそうで困ってます~
放浪人
恋愛
「君との婚姻は無効だ。実家へ帰るがいい」
大聖堂の冷たい石畳の上で、辺境伯ロルフから突然「婚姻は最初から無かった」と宣告された子爵家次女のエリシア。実家にも見放され、身重の体で王都の旧市街へ追放された彼女は、絶望のどん底で愛娘クララを出産する。
生き抜くために針と糸を握ったエリシアは、持ち前の技術で不思議な力を持つ「祝布(しゅくふ)」を織り上げる職人として立ち上がる。施しではなく「仕事」として正当な対価を払い、決して土足で踏み込んでこない救恤院の監督官リュシアンの温かい優しさに触れエリシアは少しずつ人間らしい心と笑顔を取り戻していった。
しかし五年後。辺境を襲った疫病を救うための緊急要請を通じ、エリシアは冷酷だった元夫ロルフと再会してしまう。しかも隣にいる娘の青い瞳は彼と瓜二つだった。
「すまない。私は父としての責任を果たす」
かつての合理主義の塊だった元夫は、自らの過ちを深く悔い、家の権益を捨ててでも母子を守る「強固な盾」になろうとする。娘のクララもまた、危機から救ってくれた彼を「パパ」と呼び始めてしまい……。
だが、どんなに後悔されても、どんなに身を挺して守られても、一度完全に壊された関係が元に戻ることは絶対にない。エリシアが真の伴侶として選ぶのは、凍えた心を溶かし、温かい日常を共に歩んでくれたリュシアンただ一人だった。
これは、全てを奪われた一人の女性が母として力強く成長し誰にも脅かされることのない「本物の家族」と「静かで確かな幸福」を自分の手で選び取るまでの物語。

将来を誓い合った王子様は聖女と結ばれるそうです
きぬがやあきら
恋愛
「聖女になれなかったなりそこない。こんなところまで追って来るとはな。そんなに俺を忘れられないなら、一度くらい抱いてやろうか?」
5歳のオリヴィエは、神殿で出会ったアルディアの皇太子、ルーカスと恋に落ちた。アルディア王国では、皇太子が代々聖女を妻に迎える慣わしだ。しかし、13歳の選別式を迎えたオリヴィエは、聖女を落選してしまった。
その上盲目の知恵者オルガノに、若くして命を落とすと予言されたオリヴィエは、せめてルーカスの傍にいたいと、ルーカスが団長を務める聖騎士への道へと足を踏み入れる。しかし、やっとの思いで再開したルーカスは、昔の約束を忘れてしまったのではと錯覚するほど冷たい対応で――?


ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















