10 / 17
第三章
1
しおりを挟む
そんなふうに、ときにどきどきと、ときにとろけるような幸福を味わいながら、ヒツジの日々は過ぎていきました。
農場にネコが来てから最初の冬が来ると、ネコはずっと長く夜の時間をヒツジ小屋で過ごしました。ネコはどうやら寒いのが苦手らしく、ヒツジ小屋はとてもあたたかかったからです。
凍てつくように寒い冬の夜は、とくべつ星がきれいだということをなつかしく思い返しながらも、ヒツジはネコというあたらしい星を見つけたおかげで、長い冬の夜をどこかふわふわとした気持ちで過ごすことができました。
しかしそんな折にも、ネコは思い出したように自分がいかに死にたいと思っているのかを話して聞かせ、ヒツジの心に黒い雪を積もらせました。
やがて長い冬を越し、短い春を見送ると、農場には訪れた初夏の景色が広がっていました。そのころになるとヒツジの毛はすっかりのびて、重くなっていました。
おじいさんはもっと早いうちに、ヒツジたちの毛を刈ってくれていましたが、新しい農場主の男は、イライラとヒツジたちを怒鳴りつけるだけで、一向に毛を刈ってくれる素振りも見せません。仲間のヒツジたちも、毛の重さで息苦しそうにしていて、いっそうのろのろと動きました。それでよけいに農場主を怒らせて、犬をけしかけられる有り様でした。
その晩も、いつものようにヒツジ小屋にやってきたネコは、どこか苦しげな寝息を立てて眠る仲間たちの毛に、なかばうもれるようにして立っているヒツジを見るなり、
「なんだか重そうねぇ。ずいぶんとしんどそうに見えるけど?」
と、あいさつもそこそこに言いました。
「そうだねぇ。いつもなら、たんぽぽが咲くころには毛を刈ってもらえたんだけどねぇ」
「たんぽぽなんか、とっくに咲いちゃっているわよ」
「あたらしい農場主さんは、毛の刈り方を知らないのかなぁ」
「さぁねぇ。それにしてもほんとうにすごい毛ねぇ。そんなに立派な毛は、街でもなかなかお目にかかったことがないわ」
「え? それはいいことなの?」
「そうね、好みってものはあるでしょうけど、わたしは好きよ」
ヒツジは舞い上がったようになりました。
「だいいち、そんなにすごい毛があれば、お昼寝のときにシーツなんかいらないじゃない」
ネコはまだ、犬がだめにしてしまったシーツのことを惜しがっていました。そのとき、ネコの目の前をなにか小さな虫が横切り、ネコはグレーがかったピンクの肉球を、すばやく虫にふりおろしました。しかし虫はそれより早く逃げてしまったので、ネコは何気ないふうをよそおいながら肉球を舐めはじめました。
「ほんとうにこの頃じゃ、つまらなくて仕方がないわ。あぁ、わたしもそんなふかふかのシーツでぐっすり眠れたら、この嫌な気分も癒されるでしょうに」
ネコは何気なく言いましたが、ヒツジはそのことばにハッとして、ネコを食い入るように見つめました。
「それじゃ、もしそうすることができれば、きみは憂鬱じゃなくなるのかい?」
「きっとそうなるにちがいないわね」
ネコは肉球の手入れを終えると、そのまま器用に体をねじり、自分の背中を小さな舌で舐めはじめました。
ヒツジは自分の心臓が期待でどきどきと高鳴るのを感じながら、注意深く、重ねてネコにたずねました。
「それじぁ、きみはもう死ななくて済むんだね?」
「え? あぁ、そうね」
ネコは毛繕いに忙しく、面倒くさそうな調子で、ヒツジをあしらうように言いました。
農場にネコが来てから最初の冬が来ると、ネコはずっと長く夜の時間をヒツジ小屋で過ごしました。ネコはどうやら寒いのが苦手らしく、ヒツジ小屋はとてもあたたかかったからです。
凍てつくように寒い冬の夜は、とくべつ星がきれいだということをなつかしく思い返しながらも、ヒツジはネコというあたらしい星を見つけたおかげで、長い冬の夜をどこかふわふわとした気持ちで過ごすことができました。
しかしそんな折にも、ネコは思い出したように自分がいかに死にたいと思っているのかを話して聞かせ、ヒツジの心に黒い雪を積もらせました。
やがて長い冬を越し、短い春を見送ると、農場には訪れた初夏の景色が広がっていました。そのころになるとヒツジの毛はすっかりのびて、重くなっていました。
おじいさんはもっと早いうちに、ヒツジたちの毛を刈ってくれていましたが、新しい農場主の男は、イライラとヒツジたちを怒鳴りつけるだけで、一向に毛を刈ってくれる素振りも見せません。仲間のヒツジたちも、毛の重さで息苦しそうにしていて、いっそうのろのろと動きました。それでよけいに農場主を怒らせて、犬をけしかけられる有り様でした。
その晩も、いつものようにヒツジ小屋にやってきたネコは、どこか苦しげな寝息を立てて眠る仲間たちの毛に、なかばうもれるようにして立っているヒツジを見るなり、
「なんだか重そうねぇ。ずいぶんとしんどそうに見えるけど?」
と、あいさつもそこそこに言いました。
「そうだねぇ。いつもなら、たんぽぽが咲くころには毛を刈ってもらえたんだけどねぇ」
「たんぽぽなんか、とっくに咲いちゃっているわよ」
「あたらしい農場主さんは、毛の刈り方を知らないのかなぁ」
「さぁねぇ。それにしてもほんとうにすごい毛ねぇ。そんなに立派な毛は、街でもなかなかお目にかかったことがないわ」
「え? それはいいことなの?」
「そうね、好みってものはあるでしょうけど、わたしは好きよ」
ヒツジは舞い上がったようになりました。
「だいいち、そんなにすごい毛があれば、お昼寝のときにシーツなんかいらないじゃない」
ネコはまだ、犬がだめにしてしまったシーツのことを惜しがっていました。そのとき、ネコの目の前をなにか小さな虫が横切り、ネコはグレーがかったピンクの肉球を、すばやく虫にふりおろしました。しかし虫はそれより早く逃げてしまったので、ネコは何気ないふうをよそおいながら肉球を舐めはじめました。
「ほんとうにこの頃じゃ、つまらなくて仕方がないわ。あぁ、わたしもそんなふかふかのシーツでぐっすり眠れたら、この嫌な気分も癒されるでしょうに」
ネコは何気なく言いましたが、ヒツジはそのことばにハッとして、ネコを食い入るように見つめました。
「それじゃ、もしそうすることができれば、きみは憂鬱じゃなくなるのかい?」
「きっとそうなるにちがいないわね」
ネコは肉球の手入れを終えると、そのまま器用に体をねじり、自分の背中を小さな舌で舐めはじめました。
ヒツジは自分の心臓が期待でどきどきと高鳴るのを感じながら、注意深く、重ねてネコにたずねました。
「それじぁ、きみはもう死ななくて済むんだね?」
「え? あぁ、そうね」
ネコは毛繕いに忙しく、面倒くさそうな調子で、ヒツジをあしらうように言いました。
0
あなたにおすすめの小説
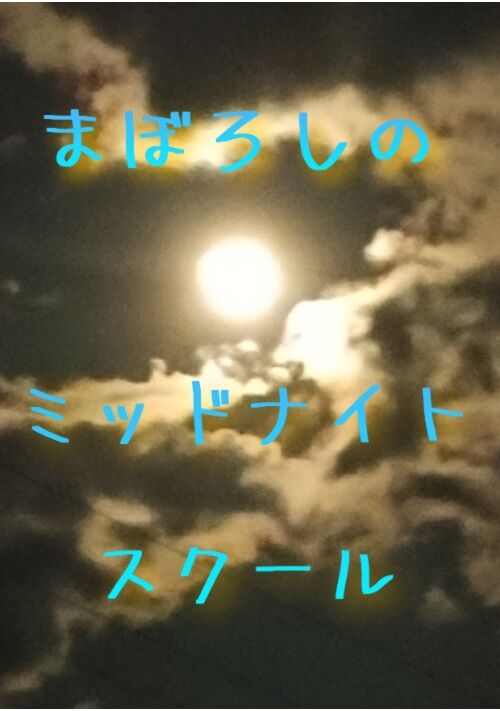
まぼろしのミッドナイトスクール
木野もくば
児童書・童話
深夜0時ちょうどに突然あらわれる不思議な学校。そこには、不思議な先生と生徒たちがいました。飼い猫との最後に後悔がある青年……。深い森の中で道に迷う少女……。人間に恋をした水の神さま……。それぞれの道に迷い、そして誰かと誰かの想いがつながったとき、暗闇の空に光る星くずの方から学校のチャイムが鳴り響いてくるのでした。
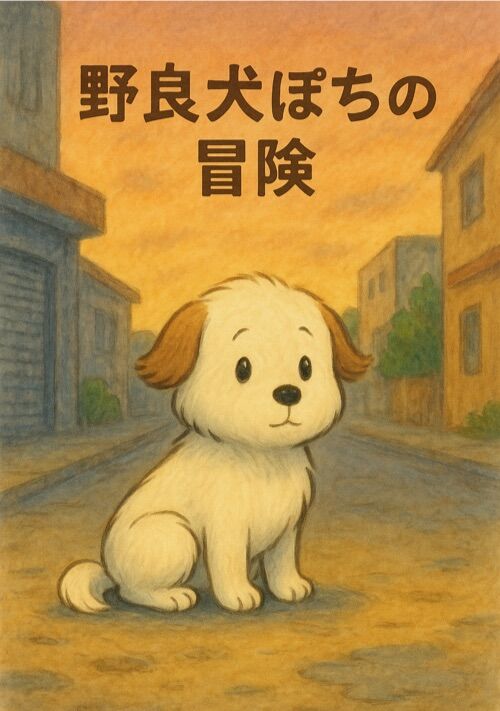
野良犬ぽちの冒険
KAORUwithAI
児童書・童話
――ぼくの名前、まだおぼえてる?
ぽちは、むかし だれかに かわいがられていた犬。
だけど、ひっこしの日に うっかり わすれられてしまって、
気がついたら、ひとりぼっちの「のらいぬ」に なっていた。
やさしい人もいれば、こわい人もいる。
あめの日も、さむい夜も、ぽちは がんばって生きていく。
それでも、ぽちは 思っている。
──また だれかが「ぽち」ってよんでくれる日が、くるんじゃないかって。
すこし さみしくて、すこし あたたかい、
のらいぬ・ぽちの ぼうけんが はじまります。

パンティージャムジャムおじさん
KOU/Vami
児童書・童話
夜の街に、歌いながら歩く奇妙なおじさんが現れる。
口癖は「パラダイス~☆♪♡」――名乗る名は「パンティージャムジャムおじさん」。
子供たちは笑いながら彼の後についていき、歌を真似し、踊り、列は少しずつ長くなる。
そして翌朝、街は初めて気づく。昨夜の歌が、ただの遊びではなかったことに。

ローズお姉さまのドレス
有沢真尋
児童書・童話
*「第3回きずな児童書大賞」エントリー中です*
最近のルイーゼは少しおかしい。
いつも丈の合わない、ローズお姉さまのドレスを着ている。
話し方もお姉さまそっくり。
わたしと同じ年なのに、ずいぶん年上のように振舞う。
表紙はかんたん表紙メーカーさまで作成

ぼくのだいじなヒーラー
もちっぱち
絵本
台所でお母さんと喧嘩した。
遊んでほしくて駄々をこねただけなのに
怖い顔で怒っていたお母さん。
そんな時、不思議な空間に包まれてふわりと気持ちが軽くなった。
癒される謎の生き物に会えたゆうくんは楽しくなった。
お子様向けの作品です
ひらがな表記です。
ぜひ読んでみてください。
イラスト:ChatGPT(OpenAI)生成


瑠璃の姫君と鉄黒の騎士
石河 翠
児童書・童話
可愛いフェリシアはひとりぼっち。部屋の中に閉じ込められ、放置されています。彼女の楽しみは、窓の隙間から空を眺めながら歌うことだけ。
そんなある日フェリシアは、貧しい身なりの男の子にさらわれてしまいました。彼は本来自分が受け取るべきだった幸せを、フェリシアが台無しにしたのだと責め立てます。
突然のことに困惑しつつも、男の子のためにできることはないかと悩んだあげく、彼女は一本の羽を渡すことに決めました。
大好きな友達に似た男の子に笑ってほしい、ただその一心で。けれどそれは、彼女の命を削る行為で……。
記憶を失くしたヒロインと、幸せになりたいヒーローの物語。ハッピーエンドです。
この作品は、他サイトにも投稿しております。
表紙絵は写真ACよりチョコラテさまの作品(写真ID:249286)をお借りしています。

少年騎士
克全
児童書・童話
「第1回きずな児童書大賞参加作」ポーウィス王国という辺境の小国には、12歳になるとダンジョンか魔境で一定の強さになるまで自分を鍛えなければいけないと言う全国民に対する法律があった。周囲の小国群の中で生き残るため、小国を狙う大国から自国を守るために作られた法律、義務だった。領地持ち騎士家の嫡男ハリー・グリフィスも、その義務に従い1人王都にあるダンジョンに向かって村をでた。だが、両親祖父母の計らいで平民の幼馴染2人も一緒に12歳の義務に同行する事になった。将来救国の英雄となるハリーの物語が始まった。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる





















