17 / 17
第1章
第16話 霊剣抜刀。復讐と安寧の力
しおりを挟む
雲一つない快晴で、小鳥達の囀りが上空を奏でるすぐ下には、俺とユメルが毎日交互に掃除をしている広場がある。そして、そこに並び立つ、ファルネスさんとミラさん、その二人を遠巻きから眺めている生徒達。
「よーし、皆んな集まったなー」
散り散りに固まる生徒達を一瞥し、小刻みに頷くファルネスさん。
「今から見せるのは、普通のヒューマンとエルフが、妖精剣士として魔術体系の融合を果たす——つまり、霊剣抜刀するやり方と、その能力の一端だ」
話しながら、ファルネスさんが握っている、どこから持ってきたのか定かではない鉄製の剣を鞘から抜く。
「これは、ごくごく一般的な金属の剣。今からこれで、あの太い木に全力で斬りかかる。その後、霊剣抜刀した状態で木には触れずに一振りする。君達には、その比較を見てもらう」
剣先で指した先には、幹が太く背丈も高い立派と賞賛に値する、植えられた一本の木が生えている。どうやら、ファルネスさんはあの木に向けて一太刀入れるらしい。
俺は、現代最強と謳われる人間の剣捌きと踏み込みを、死んでも見逃すまいと目を見開くが、当のファルネスさんは斬りかかる構えのまま一向に動く素振りを見せない。
それでも尚、目を見開いたままにしているが、次第に外界に晒された眼球が乾いてくるわけで。開かれたままの眼球を、無情な空気は何の罪悪感もなくさすってくる。普通に痛い。
俺はこのままだと、静止したファルネスさんを眺めながら急に涙を流し始める変な奴、の烙印を押されかねないため、本当に一瞬——時間にしたら、一秒にも満たない瞬きをした。
しかし、この一瞬が命取り。
俺の視界が暗転しもう一度明かりを認識した時には、ファルネスさんが踏み込んだ地は削れ、木の幹が抉り取られていた。
砕けた鉄剣を握ったファルネスさんは、「あ、壊しちゃった……どうしよ」とぼやいているが、この人が踏み込んだ際に生じた風によって前髪が崩れた生徒達は、そんなことには全く関心を示さず、ただただ呆然としている。
「あ、あの……先生は、今どこかのタイミングで妖精剣士の力を使いました……?」
ぽかんと口を開けたユメルは、目の前で起こった現象に唖然としながらも、ファルネスさんに対し質問を投げかける。
そんな誰もが思っているだろう質問に対し、笑いながら、まるでユメルがおかしなことを言っているかのようにファルネスさんは答えた。
「もちろん霊剣抜刀はしていないよ。ほら、証拠にミラはそこにいるだろう?」
指さした先には、平然といつも通りの凛とした表情で立っているミラさんの姿が。
「これは、私の純粋な身体能力によるものだし、皆もその内この位には動けるようになるぞ。次に見せるのが、妖精剣士としての能力さ」
そう言うと、元々立っていたミラさんの横に戻りながら、砕けた鉄剣の持ち手を投げ捨てる。
「ミラ、いける?」
「……えぇ、待ちくたびれました。それと、剣壊したのと木に対して斬りかかったの、アタシ絶対に一緒に謝りに行きませんからね?」
「えー……そんな冷たいこと言うなって!」
「当たり前でしょう!資料を作成していたアタシを、急に掴んで外に連れてきたと思ったらこれですよ?あなたのせいで減給されたくありません!」
ふんっと首を捻りそっぽを向くミラさんを、宥めようとするファルネスさん。
「まぁ、その面倒くさそうな事案は置いといて、待ちに待ったであろう霊剣抜刀の、その瞬間を見せるぞ!しっかりと脳裏に張り付けるように!」
言い終わったと同時に、腕を肩の高さに上げ、手の平を目一杯に開くファルネスさん。そして、
「霊剣抜刀」
ファルネスさんが、詠唱のような文言を唱えたその直後、ミラさんの体が白い発光を帯びだし、光の粉々となって空気中へと飛散する。
「神剣……ミラファルア」
ぽつんとそう言った瞬間、ファルネスさんの周囲に、近寄る者を全て焼き払うかの如く灼熱の業火が渦を巻き、徐々に収縮していく業火の中立っている妖精剣士の手には、美しい一本の剣《つるぎ》が収まっていた。
その剣には見たことのない紋様が刻まれており、紅く染まったその刀身は、先程現界した灼熱を脳裏に浮かび上がらせるのには充分すぎる紅い煌めきを放っている。
「はい、これが霊剣抜刀ね。さっきまで、そこで喋ってたミラがこの剣に変わって俺は今、妖精剣士。それっ」
ファルネスさんは、腑抜けた声を出しながら、持っている紅い剣をその場で軽く振ってみせた。
刹那、轟音が鳴り響く。最初は誰もが、どこが音の振動の発信地なのか理解できていなかった。
立ち尽くしていると、男女どちらの声なのか、悲鳴にも似た「え……ッ!?」という叫声を、さっき抉られた太い木に向けた者が。
そこに視線を向けると、綺麗に一閃され地面へと切り倒された無惨な木材の姿を確認でき、切り口には確かに鋭利な刃物の後が残されていた。
「こんな感じで、並の人間には出来ない芸当が可能になる。ちなみに、こんなのは序の序の技で、剣から魔力の斬撃を放っただけ。見て分かると思うけど、はっきり言って威力も殺傷能力も比べ物にならない」
生徒達は唖然とするだけで、誰も言葉を発さない。まぁ当然だろう。これは、もはや驚きや畏怖の段階を通り過ぎているのだ。
「私が持てる全てを、この一年君達に教えよう。この学園に来る者は、妖精紋に選ばれたのはもちろん、魔族によって家族や大切な人を殺されたり、帰る場所を壊された者が大半だ。今見た通り、この力は魔族と対等以上に渡り合う術《すべ》を与えてくれる唯一無二の神秘」
ほんの少し扇状的な表情をしたファルネスさんは、この場にいる全ての生徒と目を合わせていくように、それぞれの顔を、表情を、憎悪を眺めていく。
「この力と、最強の妖精剣士による直々の指導を受けたかったら死ぬ気で契約を交わせ。それが君達の、最初の復讐となるのだから」
俺は話を聞きながら、口の中で血液特有の鉄の味を感じた。どうやら、知らずの内に奥歯を強く噛み過ぎていたらしい。
もう二度と、大切な人が目の前で死んでいくのは見たくない。もう二度と、自分の無力さに後悔をしたくない。
皆の重い意識を遮るかのように、授業の終わりを告げる低い鐘の音が鳴った。
「午前の授業はここまで。午後は、基礎体力を上げる結構キツいメニューがあるから、昼食はしっかりと摂るように!後、タイミング的に今だと思うから伝えておくけど……」
心なしか俺の方に視線を向けたファルネスさんは淡々と続けた。
「フィルニア学園を含む全五校に、それぞれ入学した一年の中から五人、今年対魔本部が総力を挙げて行う、『ローネア奪還戦争』に参加する権利が与えられるから、そのつもりで。まぁ、ここで戦果を出せば、卒業後すぐに、私や他の有名な妖精剣士と肩を並べて、第一線に駆り出されるだろうな。その選抜、半年後に実施するって話が出てるから、興味がある人は腕試しに目指してみるといい」
それだけ言い終わると、踵を返し足早に校舎へと去っていくファルネスさん。
他の生徒達も、最初こそ立ち止まって何かを考えてはいたが、すぐに散り散りとなる。
そんな中、俺だけはその場を動くことはできなかった。
さっきのファルネスさんの話、別に有名な妖精剣士と肩を並べるとか、戦果を出すとか
そこら辺ははっきり言ってどうでも良かった。
ただ、何故どうして、あの街の名前が。俺の故郷の名前が出てくるのだろうか。
……ローネア、奪還。
「よーし、皆んな集まったなー」
散り散りに固まる生徒達を一瞥し、小刻みに頷くファルネスさん。
「今から見せるのは、普通のヒューマンとエルフが、妖精剣士として魔術体系の融合を果たす——つまり、霊剣抜刀するやり方と、その能力の一端だ」
話しながら、ファルネスさんが握っている、どこから持ってきたのか定かではない鉄製の剣を鞘から抜く。
「これは、ごくごく一般的な金属の剣。今からこれで、あの太い木に全力で斬りかかる。その後、霊剣抜刀した状態で木には触れずに一振りする。君達には、その比較を見てもらう」
剣先で指した先には、幹が太く背丈も高い立派と賞賛に値する、植えられた一本の木が生えている。どうやら、ファルネスさんはあの木に向けて一太刀入れるらしい。
俺は、現代最強と謳われる人間の剣捌きと踏み込みを、死んでも見逃すまいと目を見開くが、当のファルネスさんは斬りかかる構えのまま一向に動く素振りを見せない。
それでも尚、目を見開いたままにしているが、次第に外界に晒された眼球が乾いてくるわけで。開かれたままの眼球を、無情な空気は何の罪悪感もなくさすってくる。普通に痛い。
俺はこのままだと、静止したファルネスさんを眺めながら急に涙を流し始める変な奴、の烙印を押されかねないため、本当に一瞬——時間にしたら、一秒にも満たない瞬きをした。
しかし、この一瞬が命取り。
俺の視界が暗転しもう一度明かりを認識した時には、ファルネスさんが踏み込んだ地は削れ、木の幹が抉り取られていた。
砕けた鉄剣を握ったファルネスさんは、「あ、壊しちゃった……どうしよ」とぼやいているが、この人が踏み込んだ際に生じた風によって前髪が崩れた生徒達は、そんなことには全く関心を示さず、ただただ呆然としている。
「あ、あの……先生は、今どこかのタイミングで妖精剣士の力を使いました……?」
ぽかんと口を開けたユメルは、目の前で起こった現象に唖然としながらも、ファルネスさんに対し質問を投げかける。
そんな誰もが思っているだろう質問に対し、笑いながら、まるでユメルがおかしなことを言っているかのようにファルネスさんは答えた。
「もちろん霊剣抜刀はしていないよ。ほら、証拠にミラはそこにいるだろう?」
指さした先には、平然といつも通りの凛とした表情で立っているミラさんの姿が。
「これは、私の純粋な身体能力によるものだし、皆もその内この位には動けるようになるぞ。次に見せるのが、妖精剣士としての能力さ」
そう言うと、元々立っていたミラさんの横に戻りながら、砕けた鉄剣の持ち手を投げ捨てる。
「ミラ、いける?」
「……えぇ、待ちくたびれました。それと、剣壊したのと木に対して斬りかかったの、アタシ絶対に一緒に謝りに行きませんからね?」
「えー……そんな冷たいこと言うなって!」
「当たり前でしょう!資料を作成していたアタシを、急に掴んで外に連れてきたと思ったらこれですよ?あなたのせいで減給されたくありません!」
ふんっと首を捻りそっぽを向くミラさんを、宥めようとするファルネスさん。
「まぁ、その面倒くさそうな事案は置いといて、待ちに待ったであろう霊剣抜刀の、その瞬間を見せるぞ!しっかりと脳裏に張り付けるように!」
言い終わったと同時に、腕を肩の高さに上げ、手の平を目一杯に開くファルネスさん。そして、
「霊剣抜刀」
ファルネスさんが、詠唱のような文言を唱えたその直後、ミラさんの体が白い発光を帯びだし、光の粉々となって空気中へと飛散する。
「神剣……ミラファルア」
ぽつんとそう言った瞬間、ファルネスさんの周囲に、近寄る者を全て焼き払うかの如く灼熱の業火が渦を巻き、徐々に収縮していく業火の中立っている妖精剣士の手には、美しい一本の剣《つるぎ》が収まっていた。
その剣には見たことのない紋様が刻まれており、紅く染まったその刀身は、先程現界した灼熱を脳裏に浮かび上がらせるのには充分すぎる紅い煌めきを放っている。
「はい、これが霊剣抜刀ね。さっきまで、そこで喋ってたミラがこの剣に変わって俺は今、妖精剣士。それっ」
ファルネスさんは、腑抜けた声を出しながら、持っている紅い剣をその場で軽く振ってみせた。
刹那、轟音が鳴り響く。最初は誰もが、どこが音の振動の発信地なのか理解できていなかった。
立ち尽くしていると、男女どちらの声なのか、悲鳴にも似た「え……ッ!?」という叫声を、さっき抉られた太い木に向けた者が。
そこに視線を向けると、綺麗に一閃され地面へと切り倒された無惨な木材の姿を確認でき、切り口には確かに鋭利な刃物の後が残されていた。
「こんな感じで、並の人間には出来ない芸当が可能になる。ちなみに、こんなのは序の序の技で、剣から魔力の斬撃を放っただけ。見て分かると思うけど、はっきり言って威力も殺傷能力も比べ物にならない」
生徒達は唖然とするだけで、誰も言葉を発さない。まぁ当然だろう。これは、もはや驚きや畏怖の段階を通り過ぎているのだ。
「私が持てる全てを、この一年君達に教えよう。この学園に来る者は、妖精紋に選ばれたのはもちろん、魔族によって家族や大切な人を殺されたり、帰る場所を壊された者が大半だ。今見た通り、この力は魔族と対等以上に渡り合う術《すべ》を与えてくれる唯一無二の神秘」
ほんの少し扇状的な表情をしたファルネスさんは、この場にいる全ての生徒と目を合わせていくように、それぞれの顔を、表情を、憎悪を眺めていく。
「この力と、最強の妖精剣士による直々の指導を受けたかったら死ぬ気で契約を交わせ。それが君達の、最初の復讐となるのだから」
俺は話を聞きながら、口の中で血液特有の鉄の味を感じた。どうやら、知らずの内に奥歯を強く噛み過ぎていたらしい。
もう二度と、大切な人が目の前で死んでいくのは見たくない。もう二度と、自分の無力さに後悔をしたくない。
皆の重い意識を遮るかのように、授業の終わりを告げる低い鐘の音が鳴った。
「午前の授業はここまで。午後は、基礎体力を上げる結構キツいメニューがあるから、昼食はしっかりと摂るように!後、タイミング的に今だと思うから伝えておくけど……」
心なしか俺の方に視線を向けたファルネスさんは淡々と続けた。
「フィルニア学園を含む全五校に、それぞれ入学した一年の中から五人、今年対魔本部が総力を挙げて行う、『ローネア奪還戦争』に参加する権利が与えられるから、そのつもりで。まぁ、ここで戦果を出せば、卒業後すぐに、私や他の有名な妖精剣士と肩を並べて、第一線に駆り出されるだろうな。その選抜、半年後に実施するって話が出てるから、興味がある人は腕試しに目指してみるといい」
それだけ言い終わると、踵を返し足早に校舎へと去っていくファルネスさん。
他の生徒達も、最初こそ立ち止まって何かを考えてはいたが、すぐに散り散りとなる。
そんな中、俺だけはその場を動くことはできなかった。
さっきのファルネスさんの話、別に有名な妖精剣士と肩を並べるとか、戦果を出すとか
そこら辺ははっきり言ってどうでも良かった。
ただ、何故どうして、あの街の名前が。俺の故郷の名前が出てくるのだろうか。
……ローネア、奪還。
0
この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説

勇者パーティーを追放されたので、張り切ってスローライフをしたら魔王に世界が滅ぼされてました
まりあんぬさま
ファンタジー
かつて、世界を救う希望と称えられた“勇者パーティー”。
その中で地味に、黙々と補助・回復・結界を張り続けていたおっさん――バニッシュ=クラウゼン(38歳)は、ある日、突然追放を言い渡された。
理由は「お荷物」「地味すぎる」「若返くないから」。
……笑えない。
人付き合いに疲れ果てたバニッシュは、「もう人とは関わらん」と北西の“魔の森”に引きこもり、誰も入って来られない結界を張って一人スローライフを開始……したはずだった。
だがその結界、なぜか“迷える者”だけは入れてしまう仕様だった!?
気づけば――
記憶喪失の魔王の娘
迫害された獣人一家
古代魔法を使うエルフの美少女
天然ドジな女神
理想を追いすぎて仲間を失った情熱ドワーフ
などなど、“迷える者たち”がどんどん集まってくる異種族スローライフ村が爆誕!
ところが世界では、バニッシュの支援を失った勇者たちがボロボロに……
魔王軍の侵攻は止まらず、世界滅亡のカウントダウンが始まっていた。
「もう面倒ごとはごめんだ。でも、目の前の誰かを見捨てるのも――もっとごめんだ」
これは、追放された“地味なおっさん”が、
異種族たちとスローライフしながら、
世界を救ってしまう(予定)のお話である。

転生貴族の領地経営〜現代日本の知識で異世界を豊かにする
初
ファンタジー
ローラシア王国の北のエルラント辺境伯家には天才的な少年、リーゼンしかしその少年は現代日本から転生してきた転生者だった。
リーゼンが洗礼をしたさい、圧倒的な量の加護やスキルが与えられた。その力を見込んだ父の辺境伯は12歳のリーゼンを辺境伯家の領地の北を治める代官とした。
これはそんなリーゼンが異世界の領地を経営し、豊かにしていく物語である。
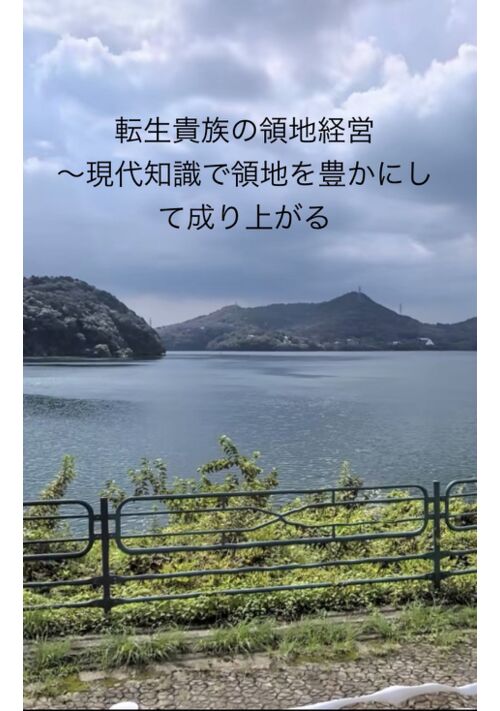
転生貴族の領地経営〜現代知識で領地を豊かにして成り上がる
初
ファンタジー
ネーデル王国の北のリーディア辺境伯家には天才的な少年レイトがいた。しかしその少年の正体は現代日本から転生してきた転生者だった。
レイトが洗礼を受けた際、圧倒的な量の魔力やスキルが与えられた。その力を見込んだ父の辺境伯は12歳のレイトを辺境伯領の北の異種族の住むハーデミア領を治める領主とした。しかしハーデミア領は貧困に喘いだ貧乏領地だった。
これはそんなレイトが異世界の領地を経営し、領地を豊かにして成り上がる物語である。

異世界に転生!? だけどお気楽に暮らします。
辰巳 蓮
ファンタジー
「転生して好きに暮らしてください。ただ、不便なところをちょっとだけ、改善していってください」
とゆうことで、多少の便宜を図ってもらった「ナッキート」が転生したのは、剣と魔法の世界でした。
すいません。年表書いてたら分かりにくいところがあったので、ちょっと加えたところがあります。

クラス転移したら種族が変化してたけどとりあえず生きる
アルカス
ファンタジー
16歳になったばかりの高校2年の主人公。
でも、主人公は昔から体が弱くなかなか学校に通えなかった。
でも学校には、行っても俺に声をかけてくれる親友はいた。
その日も体の調子が良くなり、親友と久しぶりの学校に行きHRが終わり先生が出ていったとき、クラスが眩しい光に包まれた。
そして僕は一人、違う場所に飛ばされいた。

異世界に召喚されて2日目です。クズは要らないと追放され、激レアユニークスキルで危機回避したはずが、トラブル続きで泣きそうです。
もにゃむ
ファンタジー
父親に教師になる人生を強要され、父親が死ぬまで自分の望む人生を歩むことはできないと、人生を諦め淡々とした日々を送る清泉だったが、夏休みの補習中、突然4人の生徒と共に光に包まれ異世界に召喚されてしまう。
異世界召喚という非現実的な状況に、教師1年目の清泉が状況把握に努めていると、ステータスを確認したい召喚者と1人の生徒の間にトラブル発生。
ステータスではなく職業だけを鑑定することで落ち着くも、清泉と女子生徒の1人は職業がクズだから要らないと、王都追放を言い渡されてしまう。
残留組の2人の生徒にはクズな職業だと蔑みの目を向けられ、
同時に追放を言い渡された女子生徒は問題行動が多すぎて退学させるための監視対象で、
追加で追放を言い渡された男子生徒は言動に違和感ありまくりで、
清泉は1人で自由に生きるために、問題児たちからさっさと離れたいと思うのだが……

悪役令息、前世の記憶により悪評が嵩んで死ぬことを悟り教会に出家しに行った結果、最強の聖騎士になり伝説になる
竜頭蛇
ファンタジー
ある日、前世の記憶を思い出したシド・カマッセイはこの世界がギャルゲー「ヒロイックキングダム」の世界であり、自分がギャルゲの悪役令息であると理解する。
評判が悪すぎて破滅する運命にあるが父親が毒親でシドの悪評を広げたり、関係を作ったものには危害を加えるので現状では何をやっても悪評に繋がるを悟り、家との関係を断って出家をすることを決意する。
身を寄せた教会で働くうちに評判が上がりすぎて、聖女や信者から崇められたり、女神から一目置かれ、やがて最強の聖騎士となり、伝説となる物語。

ゲーム転生『魔女♡勇者』〜12人の魔女が世界を統べるファンタジーゲーム世界に転生し、ゲーム知識と最強職『勇者』で魔女ハーレムを目指す〜
空色凪
ファンタジー
ゲームでは攻略対象は一人。現実の今ならハーレム目指せるのでは?
◇
その17歳の少年は2050年の夏休みに、ゲームのし過ぎで食べるのを忘れて餓死した。否、それは釈迦の苦行そのものだった。真理を悟った彼は世界を創った。とある理由で12個も買って、その全てをクリアした程に大好きなファンタジーゲーム『魔女♡勇者』の世界を創ったのだ。彼はその世界にただ一人『勇者』の天職を有して転生する。
『魔女♡勇者』の世界には12人の魔女(理)と呼ばれる存在がいて、世界を統治している。ゲームでは、仕様で一人しか攻略することができない。
だが、ここは現実世界。機械の中ではない。
その17歳の少年アデルはこう考えた。
「なら、12人の魔女全クリルート目指すしかないだろ」
こうしてゲーム知識で無双しつつ、アデルは魔女ハーレムを作る旅に出る。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















