2 / 21
再会と裏切り
第二話
しおりを挟む
春先のキャンパスは、どこもそわそわと浮ついた空気が漂っている。
まだ慣れない様子でうろつく新入生と、サークル勧誘に勤しむ在学生。約一ヶ月ほどは続くそれを見るともなしに眺めながら、陸は昼どきの校内をコンビニ袋を片手に歩いていた。
「兄貴ッ」
いつものように研究室へ向かおうとしていた足が、大きく呼ぶ声に止められる。仕方なく声のした方に顔を向けると、勧誘を受けていたらしい佳が学生に断りを入れてからこちらに駆け寄ってくる。
「こんな所にいたのかよ。相変わらず既読スルーだし電話にも出ねぇから、あちこち走り回ったじゃん。しっかし、ほんと広いよなぁ。迷子になっちまう」
「何のようだ」
「昼飯一緒に食おうぜ。ついでに色々と案内してくれよ」
屈託なく笑う佳に言葉に詰まる。忙しいと断ることは簡単だ。それなのに、端末越しではいくらでも切り捨てることのできる弟の手が、面と向かうと振り払えない。チラつく母の面影を隅に追いやると、仕方なくはしゃぐ佳と食堂へ向かうことを選択する。
こんなにも広大なキャンパスで、自分の選んだ学部と弟の選んだ学部が隣接しているのは何の冗談だろう。不義理な兄など放って大学生活を満喫すれば良いものを、交友関係にそつがない故に構ってくる弟が煩わしい。
「暁人とはキャンパス離れてるんだな。医学部とか、彼奴めちゃくちゃ頭良いじゃん。地元で就職したら先生様になる訳だし、気をつけよ」
「梶のお坊ちゃんが医学部以外の何処に行くんだ」
「そりゃそうなんだけどさ、噂は聞いても顔見て即わかるほどお坊ちゃんのことなんて知らねぇって。なあ、いつから付き合ってたの?」
「俺が大学に入ってから」
「じゃあ暁人が高校の頃からじゃん。それより前から知り合いだったてことだろ。うわ、全然気がつかなかった。お袋たちは知って……るわけねぇか」
気まずそうに笑う佳に、罪がないのは本当だ。教師の父と専業主婦の母。子どもは大人しい長男の陸と、二つ違いのやんちゃな次男佳。珍しくもない、どこにでも居る平凡な家族。
そう、例えば父親が何処か冷めた目で兄を見ていることも、母親の愛情が弟に多く注がれていることも、ありふれた家族のひとつの姿に過ぎない。偏った両親の愛に苦しむのは、どちらか一人だけというものでもない。
「母さんには、ちゃんと連絡しておいたか」
「うん。兄貴が先に知らせておいてくれたから、渋々っぽかったけど許してくれた。サンキューな。あ、今日はそのお礼。好きなもの頼んでくれて良いんだぜ」
「居候しないとやっていけない奴に奢られてもな」
「そ、そこを突かれると辛ぇ。いや、さすがに学食メニューくらいは奢れるって」
久しぶりに交わした兄弟らしい会話に、陸の口元も自然と緩む。それを目ざとく見つけた佳が、嬉しいと全身で訴えるような笑顔を見せた。
親の扱いを否定するように、佳は兄を過剰なまでに慕ってくれている。そして彼のそうした態度が、結果的に両親から陸を遠ざける。
小さな弟が生まれてからずっと繰り返されてきた日常。二人の兄弟の絆は、ひどく歪で捻れていた。
「せっかく奢るって言ってんのに、なんでカレー」
「美味いぞ、ここのカレー。お前も同じじゃないか」
「その店の味を知るには、まずはカレーだよ」
一般人にも人気のある食堂は、ちょうど昼時とあって混み合っていた。タイミングよく空いた席に向かい合って座ると、いただきますと揃って挨拶をしてから手をつける。お喋りな佳は、尋ねてもいないのに午前にあったことを逐一話して聞かせてくれる。
「そうだ。兄貴の泊まり込み日の予定とか、LINEで送ってよ。俺のも送るからさ」
「必要ないだろう。俺の予定がお前になんの関係がある」
「つれないこと言うなって。把握しておいた方が色々と便利じゃん。暁人はちゃんと教えてくれたぜ」
何気ない口調で言われた内容に、ほんの僅かな動揺が走りスプーンと食器が音を立てた。二人で暮らすようになってからもそれ以前も、陸は暁人のプライベートなど把握していない。
そんなことをしなくても、暁人はいつも帰ってきてくれたから。ごめんね、やっぱり陸が一番好き、そう言って仲直りのキスをしてくれたから。
「今度さ、歓迎会のカレーパーティーしようぜ。兄貴の予定に合わせるから、帰りに買い物して一緒にカレー作ろう」
「歓迎会って、誰の?」
「そりゃもちろん、俺のに決まってるじゃん」
「図々しい」
ふざけた調子でテーブルの下の足を蹴ってやると、痛いと大袈裟に顔をしかめられる。なんの含みも感じられない佳に、なんでも悪い方に見ようとしてしまう自分が嫌になる。それでも確かに、佳の存在は静かだった水面に投げ入れられた小石だった。
「俺たちで作って暁人をびっくりさせてやろうぜ。彼奴まだ、兄貴の手料理食ったことないんだろう。昔はよく作ってくれたじゃん。兄貴のコロッケ好きだったよ。高校のダチに話したらさ、コロッケの手作りとかすげぇって感動されたんだぜ」
「人様に食べさせられる出来じゃない」
「頑張ってくれたのは事実じゃん。兄貴が大学入ってから、たまに自分でも作ってるんだ。今度食わせてやるよ。あ、コロッケカレーにする手もあるな」
暁人も喜ぶよとまた言われ、返事をするのも億劫で残っていたカレーを片付けることに集中する。
料理など好きではない。ただ頭が痛いと伏せりがちな母親の負担を減らそうと、彼女に少しでも気に入られたいと願って作っていただけだ。一人でレシピと格闘した料理に親からの称賛への期待はあっても、弟への愛情など欠片も含まれてはいなかった。
「そうだな、たまには作ってみるか。それじゃあ、俺はもう研究室に戻らないといけないから」
「ん、ああ、食器は俺が下げておくよ。付き合ってくれてサンキューな」
忙しいのを言い訳にして、居心地の悪い空間から逃げるように足を早める。食堂を出てしばらく歩くと、ようやく新鮮な空気を深く吸うことができた。佳の存在を感じることが苦痛だった。
『俺も陸が好きだよ』
あの夏の離れで聞いた蝉の声が、頭の奥に染み付いている。そうだ、暫くすればまた夏が来る。生まれて初めて好きだと誰かに言われた、求められたと思えたあのむせ返るような季節がやって来る。
静かなはずの屋内から聞こえてきた甲高い罵声に、陸は鍵を開けかけていた手を慌てて止めた。
山荘のような雰囲気を持つ梶家の離れは、母屋とはかなりの距離を取った独立した建物だ。戦前に建てられたときく家屋は一部が洋館になっており、そこが聡介の書斎になっている。
小さな公立中学に大学教授が訪れてくれたのは、地元の古生物好きを増やすことに貢献したいという聡介自身の活動によるものだ。昔から化石が好きで地学部に入っていた陸は、すぐに変わり者と言われる坊ちゃん先生と意気投合した。
中学二年になる前の春休み、聡介は何度か連れてきてくれていた離れの鍵を陸に渡してくれた。自分が不在の時も好きに使いなさいと言われ、甘えるまま放課後を静かな離れで過ごすようになって数ヶ月経った頃、陸は彼と初めて出会うことになった。
「なにこれ。どうやったら取れるんだよ、くそッ」
鍵をポケットに戻し、庭という名の雑木の林から裏手にこっそりと回る。声の主が居るのは、井戸の近くにある台所のようだ。開いたままになっていた木戸から中を覗くと、まだ小学生くらいの細身の少年が、手に持ったガラス瓶を土間の床で叩き割ろうと振りかぶっていた。
「お、おい、危ないだろう」
「わっ、何するんだよ」
思わず止めに入った陸が瓶を取り上げると、返せと少年が睨みつけてきた。古い家屋特有の薄暗く湿った空間で、明るい茶色の目が陽の光を吸い込んで橙色に輝いてみえる。
「君、どこの子?」
「アンタこそ誰。ここ、俺ん家の敷地だよ」
「え、てことは、もしかして梶先生の息子さん。ええと、先生に古生物学を教えていただいているM中学地学部の学生で、鹿嶋陸と言います。先生にはいつもお世話になっていて」
「そんな話どうでもいい。ね、中学生ならさ、その瓶割ってビー玉を取ってよ」
「ビー、玉」
せっつく少年が指差すガラス瓶を改めて見ると、それは聡介が好んで冷蔵庫にストックしているラムネの瓶だった。
ペットボトルタイプではなく、今では入手困難なオールガラスボトル。瓶でなければ美味しくないと、聡介がわざわざ東京の知人に購入してもらっている品物だ。割るだなんてとんでもないと、慌てて空になっている瓶を背中の後ろに隠す。
「この瓶はメーカーに返さないといけないものだから、割ったら駄目なんだ」
「何それ、それじゃあビー玉取れないじゃん」
「ビー玉が欲しいなら、そこら辺のスーパーでプラスチックボトルのを買え。オールガラスの瓶はもう国内でも作れない貴重品だぞ」
「え、そうなの。ガラス瓶なんていくらでも作れるんじゃないの」
「この瓶を作る機械そのものが無いんだ。今ある瓶がなくなったら、もうこのラムネは作れない」
聡介からの受け売りを彼の息子に向かって訴えると、ふうんと言ってから少年は素直に引き下がった。改めて見ると、明るい茶色のくせ髪が聡介とよく似ている。
「じゃあいいや、別にビー玉とかいらないし。あ、陸も飲む?」
「り、陸って」
「間違えてたかな、それならゴメン。はい、どうぞ」
「いや、合ってるけど」
「俺は梶暁人、小五。父がお世話になってます」
差し出された青いガラス瓶はよく冷えていて、すでに薄っすらと汗をかいていた。濡れた感触のそれを受け取りながら、三歳年上の相手を呼び捨てにする少年に呆気にとられる。
「ちぇ、取れないとなると、すっごく良いものに見えるんだよなぁ」
とっくにこちらに興味をなくしたらしい子どもは、交換と言って取り戻した瓶をひっくり返したり覗き込んだりしている。閉じ込められたビー玉がカラコロと涼しげな音を立ててる中、少年は飽きることなく空っぽの中身を眺めていた。
まだ慣れない様子でうろつく新入生と、サークル勧誘に勤しむ在学生。約一ヶ月ほどは続くそれを見るともなしに眺めながら、陸は昼どきの校内をコンビニ袋を片手に歩いていた。
「兄貴ッ」
いつものように研究室へ向かおうとしていた足が、大きく呼ぶ声に止められる。仕方なく声のした方に顔を向けると、勧誘を受けていたらしい佳が学生に断りを入れてからこちらに駆け寄ってくる。
「こんな所にいたのかよ。相変わらず既読スルーだし電話にも出ねぇから、あちこち走り回ったじゃん。しっかし、ほんと広いよなぁ。迷子になっちまう」
「何のようだ」
「昼飯一緒に食おうぜ。ついでに色々と案内してくれよ」
屈託なく笑う佳に言葉に詰まる。忙しいと断ることは簡単だ。それなのに、端末越しではいくらでも切り捨てることのできる弟の手が、面と向かうと振り払えない。チラつく母の面影を隅に追いやると、仕方なくはしゃぐ佳と食堂へ向かうことを選択する。
こんなにも広大なキャンパスで、自分の選んだ学部と弟の選んだ学部が隣接しているのは何の冗談だろう。不義理な兄など放って大学生活を満喫すれば良いものを、交友関係にそつがない故に構ってくる弟が煩わしい。
「暁人とはキャンパス離れてるんだな。医学部とか、彼奴めちゃくちゃ頭良いじゃん。地元で就職したら先生様になる訳だし、気をつけよ」
「梶のお坊ちゃんが医学部以外の何処に行くんだ」
「そりゃそうなんだけどさ、噂は聞いても顔見て即わかるほどお坊ちゃんのことなんて知らねぇって。なあ、いつから付き合ってたの?」
「俺が大学に入ってから」
「じゃあ暁人が高校の頃からじゃん。それより前から知り合いだったてことだろ。うわ、全然気がつかなかった。お袋たちは知って……るわけねぇか」
気まずそうに笑う佳に、罪がないのは本当だ。教師の父と専業主婦の母。子どもは大人しい長男の陸と、二つ違いのやんちゃな次男佳。珍しくもない、どこにでも居る平凡な家族。
そう、例えば父親が何処か冷めた目で兄を見ていることも、母親の愛情が弟に多く注がれていることも、ありふれた家族のひとつの姿に過ぎない。偏った両親の愛に苦しむのは、どちらか一人だけというものでもない。
「母さんには、ちゃんと連絡しておいたか」
「うん。兄貴が先に知らせておいてくれたから、渋々っぽかったけど許してくれた。サンキューな。あ、今日はそのお礼。好きなもの頼んでくれて良いんだぜ」
「居候しないとやっていけない奴に奢られてもな」
「そ、そこを突かれると辛ぇ。いや、さすがに学食メニューくらいは奢れるって」
久しぶりに交わした兄弟らしい会話に、陸の口元も自然と緩む。それを目ざとく見つけた佳が、嬉しいと全身で訴えるような笑顔を見せた。
親の扱いを否定するように、佳は兄を過剰なまでに慕ってくれている。そして彼のそうした態度が、結果的に両親から陸を遠ざける。
小さな弟が生まれてからずっと繰り返されてきた日常。二人の兄弟の絆は、ひどく歪で捻れていた。
「せっかく奢るって言ってんのに、なんでカレー」
「美味いぞ、ここのカレー。お前も同じじゃないか」
「その店の味を知るには、まずはカレーだよ」
一般人にも人気のある食堂は、ちょうど昼時とあって混み合っていた。タイミングよく空いた席に向かい合って座ると、いただきますと揃って挨拶をしてから手をつける。お喋りな佳は、尋ねてもいないのに午前にあったことを逐一話して聞かせてくれる。
「そうだ。兄貴の泊まり込み日の予定とか、LINEで送ってよ。俺のも送るからさ」
「必要ないだろう。俺の予定がお前になんの関係がある」
「つれないこと言うなって。把握しておいた方が色々と便利じゃん。暁人はちゃんと教えてくれたぜ」
何気ない口調で言われた内容に、ほんの僅かな動揺が走りスプーンと食器が音を立てた。二人で暮らすようになってからもそれ以前も、陸は暁人のプライベートなど把握していない。
そんなことをしなくても、暁人はいつも帰ってきてくれたから。ごめんね、やっぱり陸が一番好き、そう言って仲直りのキスをしてくれたから。
「今度さ、歓迎会のカレーパーティーしようぜ。兄貴の予定に合わせるから、帰りに買い物して一緒にカレー作ろう」
「歓迎会って、誰の?」
「そりゃもちろん、俺のに決まってるじゃん」
「図々しい」
ふざけた調子でテーブルの下の足を蹴ってやると、痛いと大袈裟に顔をしかめられる。なんの含みも感じられない佳に、なんでも悪い方に見ようとしてしまう自分が嫌になる。それでも確かに、佳の存在は静かだった水面に投げ入れられた小石だった。
「俺たちで作って暁人をびっくりさせてやろうぜ。彼奴まだ、兄貴の手料理食ったことないんだろう。昔はよく作ってくれたじゃん。兄貴のコロッケ好きだったよ。高校のダチに話したらさ、コロッケの手作りとかすげぇって感動されたんだぜ」
「人様に食べさせられる出来じゃない」
「頑張ってくれたのは事実じゃん。兄貴が大学入ってから、たまに自分でも作ってるんだ。今度食わせてやるよ。あ、コロッケカレーにする手もあるな」
暁人も喜ぶよとまた言われ、返事をするのも億劫で残っていたカレーを片付けることに集中する。
料理など好きではない。ただ頭が痛いと伏せりがちな母親の負担を減らそうと、彼女に少しでも気に入られたいと願って作っていただけだ。一人でレシピと格闘した料理に親からの称賛への期待はあっても、弟への愛情など欠片も含まれてはいなかった。
「そうだな、たまには作ってみるか。それじゃあ、俺はもう研究室に戻らないといけないから」
「ん、ああ、食器は俺が下げておくよ。付き合ってくれてサンキューな」
忙しいのを言い訳にして、居心地の悪い空間から逃げるように足を早める。食堂を出てしばらく歩くと、ようやく新鮮な空気を深く吸うことができた。佳の存在を感じることが苦痛だった。
『俺も陸が好きだよ』
あの夏の離れで聞いた蝉の声が、頭の奥に染み付いている。そうだ、暫くすればまた夏が来る。生まれて初めて好きだと誰かに言われた、求められたと思えたあのむせ返るような季節がやって来る。
静かなはずの屋内から聞こえてきた甲高い罵声に、陸は鍵を開けかけていた手を慌てて止めた。
山荘のような雰囲気を持つ梶家の離れは、母屋とはかなりの距離を取った独立した建物だ。戦前に建てられたときく家屋は一部が洋館になっており、そこが聡介の書斎になっている。
小さな公立中学に大学教授が訪れてくれたのは、地元の古生物好きを増やすことに貢献したいという聡介自身の活動によるものだ。昔から化石が好きで地学部に入っていた陸は、すぐに変わり者と言われる坊ちゃん先生と意気投合した。
中学二年になる前の春休み、聡介は何度か連れてきてくれていた離れの鍵を陸に渡してくれた。自分が不在の時も好きに使いなさいと言われ、甘えるまま放課後を静かな離れで過ごすようになって数ヶ月経った頃、陸は彼と初めて出会うことになった。
「なにこれ。どうやったら取れるんだよ、くそッ」
鍵をポケットに戻し、庭という名の雑木の林から裏手にこっそりと回る。声の主が居るのは、井戸の近くにある台所のようだ。開いたままになっていた木戸から中を覗くと、まだ小学生くらいの細身の少年が、手に持ったガラス瓶を土間の床で叩き割ろうと振りかぶっていた。
「お、おい、危ないだろう」
「わっ、何するんだよ」
思わず止めに入った陸が瓶を取り上げると、返せと少年が睨みつけてきた。古い家屋特有の薄暗く湿った空間で、明るい茶色の目が陽の光を吸い込んで橙色に輝いてみえる。
「君、どこの子?」
「アンタこそ誰。ここ、俺ん家の敷地だよ」
「え、てことは、もしかして梶先生の息子さん。ええと、先生に古生物学を教えていただいているM中学地学部の学生で、鹿嶋陸と言います。先生にはいつもお世話になっていて」
「そんな話どうでもいい。ね、中学生ならさ、その瓶割ってビー玉を取ってよ」
「ビー、玉」
せっつく少年が指差すガラス瓶を改めて見ると、それは聡介が好んで冷蔵庫にストックしているラムネの瓶だった。
ペットボトルタイプではなく、今では入手困難なオールガラスボトル。瓶でなければ美味しくないと、聡介がわざわざ東京の知人に購入してもらっている品物だ。割るだなんてとんでもないと、慌てて空になっている瓶を背中の後ろに隠す。
「この瓶はメーカーに返さないといけないものだから、割ったら駄目なんだ」
「何それ、それじゃあビー玉取れないじゃん」
「ビー玉が欲しいなら、そこら辺のスーパーでプラスチックボトルのを買え。オールガラスの瓶はもう国内でも作れない貴重品だぞ」
「え、そうなの。ガラス瓶なんていくらでも作れるんじゃないの」
「この瓶を作る機械そのものが無いんだ。今ある瓶がなくなったら、もうこのラムネは作れない」
聡介からの受け売りを彼の息子に向かって訴えると、ふうんと言ってから少年は素直に引き下がった。改めて見ると、明るい茶色のくせ髪が聡介とよく似ている。
「じゃあいいや、別にビー玉とかいらないし。あ、陸も飲む?」
「り、陸って」
「間違えてたかな、それならゴメン。はい、どうぞ」
「いや、合ってるけど」
「俺は梶暁人、小五。父がお世話になってます」
差し出された青いガラス瓶はよく冷えていて、すでに薄っすらと汗をかいていた。濡れた感触のそれを受け取りながら、三歳年上の相手を呼び捨てにする少年に呆気にとられる。
「ちぇ、取れないとなると、すっごく良いものに見えるんだよなぁ」
とっくにこちらに興味をなくしたらしい子どもは、交換と言って取り戻した瓶をひっくり返したり覗き込んだりしている。閉じ込められたビー玉がカラコロと涼しげな音を立ててる中、少年は飽きることなく空っぽの中身を眺めていた。
10
あなたにおすすめの小説

夢の続きの話をしよう
木原あざみ
BL
歯止めのきかなくなる前に離れようと思った。
隣になんていたくないと思った。
**
サッカー選手×大学生。すれ違い過多の両方向片思いなお話です。他サイトにて完結済みの作品を転載しています。本編総文字数25万字強。
表紙は同人誌にした際に木久劇美和さまに描いていただいたものを使用しています(※こちらに載せている本文は同人誌用に改稿する前のものになります)。

シスルの花束を
碧月 晶
BL
年下俺様モデル×年上訳あり青年
~人物紹介~
○氷室 三門(ひむろ みかど)
・攻め(主人公)
・23歳、身長178cm
・モデル
・俺様な性格、短気
・訳あって、雨月の所に転がり込んだ
○寒河江 雨月(さがえ うげつ)
・受け
・26歳、身長170cm
・常に無表情で、人形のように顔が整っている
・童顔
※作中に英会話が出てきますが、翻訳アプリで訳したため正しいとは限りません。
※濡れ場があるシーンはタイトルに*マークが付きます。
※基本、三門視点で進みます。
※表紙絵は作者が生成AIで試しに作ってみたものです。

【第一部完結】カフェと雪の女王と、多分、恋の話
凍星
BL
親の店を継ぎ、運河沿いのカフェで見習店長をつとめる高槻泉水には、人に言えない悩みがあった。
誰かを好きになっても、踏み込んだ関係になれない。つまり、SEXが苦手で体の関係にまで進めないこと。
それは過去の手酷い失恋によるものなのだが、それをどうしたら解消できるのか分からなくて……
呪いのような心の傷と、二人の男性との出会い。自分を変えたい泉水の葛藤と、彼を好きになった年下ホスト蓮のもだもだした両片想いの物語。BLです。
「*」マーク付きの話は、性的描写ありです。閲覧にご注意ください。
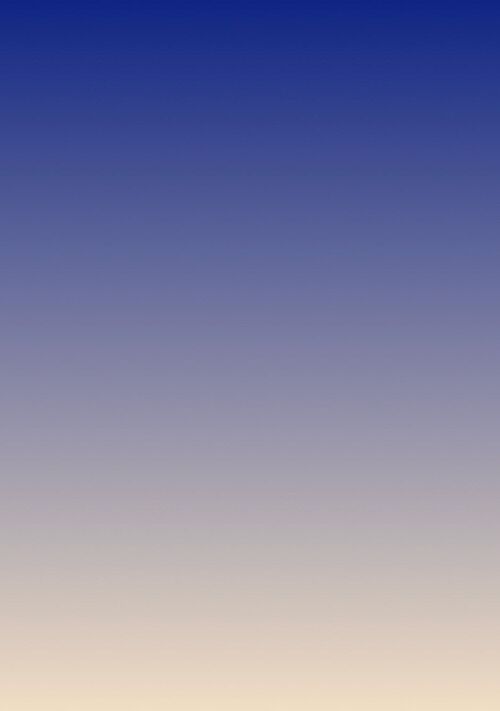
あの部屋でまだ待ってる
名雪
BL
アパートの一室。
どんなに遅くなっても、帰りを待つ習慣だけが残っている。
始まりは、ほんの気まぐれ。
終わる理由もないまま、十年が過ぎた。
与え続けることも、受け取るだけでいることも、いつしか当たり前になっていく。
――あの部屋で、まだ待ってる。

ヤンキーDKの献身
ナムラケイ
BL
スパダリ高校生×こじらせ公務員のBLです。
ケンカ上等、金髪ヤンキー高校生の三沢空乃は、築51年のオンボロアパートで一人暮らしを始めることに。隣人の近間行人は、お堅い公務員かと思いきや、夜な夜な違う男と寝ているビッチ系ネコで…。
性描写があるものには、タイトルに★をつけています。
行人の兄が主人公の「戦闘機乗りの劣情」(完結済み)も掲載しています。

この胸の高鳴りは・・・
暁エネル
BL
電車に乗りいつも通り大学へと向かう途中 気になる人と出会う男性なのか女性なのかわからないまま 電車を降りその人をなぜか追いかけてしまった 初めての出来事に驚き その人に声をかけ自分のした事に 優しく笑うその人に今まで経験した事のない感情が・・・

Take On Me
マン太
BL
親父の借金を返済するため、ヤクザの若頭、岳(たける)の元でハウスキーパーとして働く事になった大和(やまと)。
初めは乗り気でなかったが、持ち前の前向きな性格により、次第に力を発揮していく。
岳とも次第に打ち解ける様になり…。
軽いノリのお話しを目指しています。
※BLに分類していますが軽めです。
※他サイトへも掲載しています。

箱入りオメガの受難
おもちDX
BL
社会人の瑠璃は突然の発情期を知らないアルファの男と過ごしてしまう。記憶にないが瑠璃は大学生の地味系男子、琥珀と致してしまったらしい。
元の生活に戻ろうとするも、琥珀はストーカーのように付きまといだし、なぜか瑠璃はだんだん絆されていってしまう。
ある日瑠璃は、発情期を見知らぬイケメンと過ごす夢を見て混乱に陥る。これはあの日の記憶?知らない相手は誰?
不器用なアルファとオメガのドタバタ勘違いラブストーリー。
現代オメガバース ※R要素は限りなく薄いです。
この作品は『KADOKAWA×pixiv ノベル大賞2024』の「BL部門」お題イラストから着想し、創作したものです。ありがたいことに、グローバルコミック賞をいただきました。
https://www.pixiv.net/novel/contest/kadokawapixivnovel24
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















